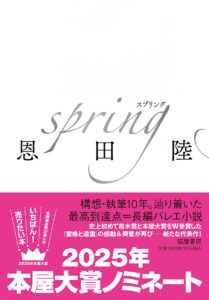 小説「spring」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「spring」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
恩田陸さんの新作『spring』、発売を心待ちにしていた方も多いのではないでしょうか。表紙のデザインも印象的で、手に取らずにはいられませんでした。帯の言葉にも心を掴まれますよね。
本作は、バレエという芸術の世界を舞台に、一人の天才ダンサー・振付家である萬春(よろず はる)の人生を描いた物語です。恩田さんといえば『蜜蜂と遠雷』で音楽コンクールを舞台に才能のぶつかり合いを描き切りましたが、今作ではバレエの世界でどのようなドラマが繰り広げられるのか、期待が高まります。
この記事では、まず『spring』がどのような物語なのか、そのあらすじをご紹介します。そして、物語の核心に触れるネタバレを含みつつ、私がこの作品を読んで何を感じ、考えたのか、詳しくお話ししていきたいと思います。バレエに詳しい方もそうでない方も、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。
小説「spring」のあらすじ
物語の中心人物は、萬春(よろず はる)。彼は幼少期に偶然バレエと出会い、その世界に魅了されます。天賦の才を持つ春は、瞬く間に頭角を現し、周囲を驚かせます。彼の踊りは、技術的な巧みさを超えて、観る者の心を直接揺さぶる何かを持っていました。
八歳でバレエを始めた春は、周囲の大人たち、特に叔父である大学教員の稔(みのる)から与えられた本や映画からも多大な影響を受け、独自の感性を育んでいきます。彼の才能は国内にとどまらず、十五歳にして単身ドイツへと渡り、名門バレエ学校でさらなる研鑽を積むことになります。
物語は、春自身の視点だけでなく、彼を取り巻く様々な人物たちの視点を通して語られます。共に踊ったダンサー仲間、彼の才能を見出し導いた指導者、幼馴染で後に音楽家となる女性、彼の舞台を熱狂的に支持する観客、そして彼の創作活動を支える人々。それぞれの視点から、萬春という人間の多面的な肖像が少しずつ浮かび上がってきます。
彼らは皆、春の圧倒的な才能と、どこか人間離れしたような不思議な存在感に惹きつけられ、時に畏怖の念すら抱きます。春はダンサーとしてだけでなく、振付家としても非凡な才能を発揮し、革新的な作品を生み出していきます。その過程で、様々な人々との出会い、協力、そして衝突が描かれます。
春は常に「舞台の神」とも呼ぶべき、究極の表現を求め続けます。その探求は、時に憎しみと見紛うほどの激しい情熱を伴い、彼自身をも、そして周囲の人々をも巻き込みながら、芸術の高みへと突き進んでいきます。
物語は、春の少年時代から始まり、彼が世界的ダンサー、そして振付家として確固たる地位を築くまでを描き切ります。一人の天才芸術家が、どのようにしてその才能を開花させ、周囲と関わり、時代を駆け抜けていったのか。その軌跡を辿る壮大な物語となっています。
小説「spring」の長文感想(ネタバレあり)
読み終えて、まず心に残ったのは、萬春という存在の圧倒的な引力でした。恩田陸さんが描く「天才」には、『チョコレートコスモス』や『蜜蜂と遠雷』でも心を鷲掴みにされましたが、今回の『spring』における萬春もまた、抗いがたい魅力を持った人物として立ち現れていました。
物語の前半、特に第一部から第三部にかけては、春を取り巻く人々の視点から彼が語られます。ダンサー仲間、叔父の稔、幼馴染の音楽家など、それぞれの語り手が見る春は、まさに「異質」な存在。常人には理解しがたい才能を持ち、時に神懸かり的ですらある。その踊りは人々を熱狂させ、畏怖させます。この、周囲の視点を通して徐々に輪郭が明らかになっていく春の姿は、どこか神秘的で、読んでいるこちらも彼の底知れなさに引き込まれていきました。
特に印象的だったのは、語り手によって春の呼び方が異なる点です。「ハル」「春」「萬」… 呼び方の違いが、それぞれの人物と春との距離感や関係性を如実に示していて、非常に巧みだと感じました。視点が変わるごとに、少しずつ春という人物の内面に近づいていくような、そんなもどかしさと期待感が入り混じった読書体験でした。
しかし、この物語の構成の妙は、第四部で春自身の視点に切り替わる点にあります。それまで周囲から「天才」「異物」として語られてきた春が、自らの言葉で語り始める。そこで明らかになるのは、彼もまた、私たちと同じように悩み、迷い、喜び、そして傷つく一人の人間であるという事実です。
才能への自覚と、それに伴う傲慢さ。純粋さゆえの危うさ。そして、心の拠り所を求める弱さ。恋人に翻弄され、愛人に夢中になり、師の死に動揺し、本番前に焦りを感じる。そうした人間らしい感情や行動が描かれることで、それまで神格化されつつあった春のイメージは覆されます。正直、最初は「なんだ、ただの人間だったのか」と少し拍子抜けした部分もありました。もっと人間離れした、超越的な存在であってほしかったような気もしたのです。
ですが、読み進めるうちに、その人間らしさこそが、彼の表現の源泉であり、魅力なのだと気づかされました。特に、叔父の稔に対して「俺のバレエの何パーセントかには、稔さんも入ってるよ」と言う場面。第二部の稔の視点では、春がいとも簡単に他者の影響を吸収し昇華させているように描かれていましたが、第四部で春自身の口から、それが「稔さんにとっては大したことではないだろう」という遠慮からの過少申告だったと明かされる。この平凡とも言える感情の機微に、私は強く共感し、春という存在がぐっと身近に感じられました。
悲しみ、恥、執着、嫉妬といった負の感情も含めて、あらゆる経験や感情が、彼の踊りとなり、振り付けとなって昇華されていく。そう考えると、第四部で描かれた人間・萬春の姿は、彼の芸術を理解する上で不可欠な要素だったのだと思えます。むき出しの感情が、あの圧倒的なバレエを生み出していたのかもしれません。
ただ、正直に言うと、バレエに関する知識が乏しい私にとって、作中のバレエシーンの描写を十分に味わいきれたかというと、自信がありません。春や他のダンサーたちの踊りの凄さ、革新性が言葉で語られても、具体的なイメージとして立ち上げるのが難しい場面もありました。特に専門的な技術やバレエ史に関する言及は、「はぁ、そうですか」と流してしまう部分も。これは、私の側の問題であり、非常にもどかしく、悔しく感じました。
バレエやクラシック音楽、舞台芸術に関する知識があれば、この物語はさらに何倍も面白く、深く響くものになるのだろうと思います。作中で言及される様々な演目や楽曲(例えば「火の鳥」やストラヴィンスキーの「春の祭典」の使い方など)、そして安部公房の『砂の女』といった文学作品。これらを知っていれば、春の芸術や内面をより深く理解できたはずです。この点は、『蜜蜂と遠雷』を読んだ時にも感じたことですが、芸術を題材にした作品を読む際の、ある種の「壁」なのかもしれません。
とはいえ、知識がないから楽しめない、というわけでは決してありません。むしろ、この作品をきっかけに、今まで知らなかった世界への扉が開かれた感覚があります。作中に登場した架空のバレエ演目「アネクメネ」(非居住地域、という意味だそうです)。自然の厳しさや人間の踏み入れない領域を表現するというコンセプトに強く惹かれました。春が自身の人間らしい部分もさらけ出した上で、なお根源的な自然やエネルギーを表現しようとする。その試みを、ぜひ実際の舞台で観てみたい、音楽を聴いてみたいと強く思いました。
恩田さんが春について「今まで書いた主人公の中でこれほど萌えたのは初めてです」とコメントされているそうですが、私が感じたのは「萌え」とは少し違う、「圧倒」でした。彼は人間でありながら、どこか人間を超えた「エネルギーの塊」のようにも感じられました。そのエネルギーが時に人間らしい感情を伴って発露する。その両義性こそが、萬春というキャラクターの核心なのかもしれません。
この作品は、読む人を選ぶかもしれません。バレエや芸術への関心の度合いによって、受け取り方が大きく変わる可能性があります。ただ、たとえ知識がなくても、一人の人間が才能と向き合い、苦悩し、周囲と関わりながら成長していく普遍的な物語として読むこともできます。そして、読み終えた後には、きっと新しい世界への興味がかき立てられるはずです。
個人的には、『蜜蜂と遠雷』ほどの熱狂的な没入感は得られなかった、というのが正直なところです。あちらはコンクールという明確なゴールと競争があり、感情移入しやすかったのかもしれません。『spring』は、より一人の芸術家の内面と生涯を深く静かに掘り下げていくような印象でした。
それでも、萬春という稀有なキャラクター、彼を取り巻く人々との関係性、そして芸術が生まれる瞬間のきらめきは、確かに心に残りました。特に、第四部で人間としての春を知った上で、改めて第一部から第三部を読み返すと、また違った感慨があるかもしれません。知識を蓄えて、いつか再読してみたい、そう思わせるだけの力を持った作品であることは間違いありません。
この物語は、単なるバレエ小説ではなく、才能とは何か、表現とは何か、そして人間とは何か、という根源的な問いを投げかけてきます。読み終えてすぐには答えが出ない、深く長い余韻を残す一冊でした。
まとめ
この記事では、恩田陸さんの小説『spring』について、その物語の筋道と、ネタバレを含む私の個人的な読み解きをお届けしました。天才バレエダンサーであり振付家でもある萬春の、輝かしくも複雑な人生が、多角的な視点から描かれています。
周囲から見た神秘的な天才としての姿と、彼自身の内面から語られる人間らしい葛藤や感情。その両面を知ることで、萬春という人物像、そして彼の生み出す芸術への理解が深まります。バレエという世界の描写は、知識があればより深く楽しめますが、詳しくない読者にとっても、普遍的な人間ドラマや才能との向き合い方について考えさせられる、読み応えのある作品だと思います。
私自身、バレエの知識不足から完全に没入しきれない部分もありましたが、それでも萬春というキャラクターの圧倒的な存在感や、物語の構成の巧みさには引き込まれました。そして何より、未知の世界への興味という、新たな「芽吹き」を与えてくれた一冊です。
読む人によって様々な受け止め方ができる作品だと思います。この記事が、『spring』という物語への興味を持つきっかけとなれば幸いです。ぜひ一度手に取って、萬春の世界に触れてみてください。



































































