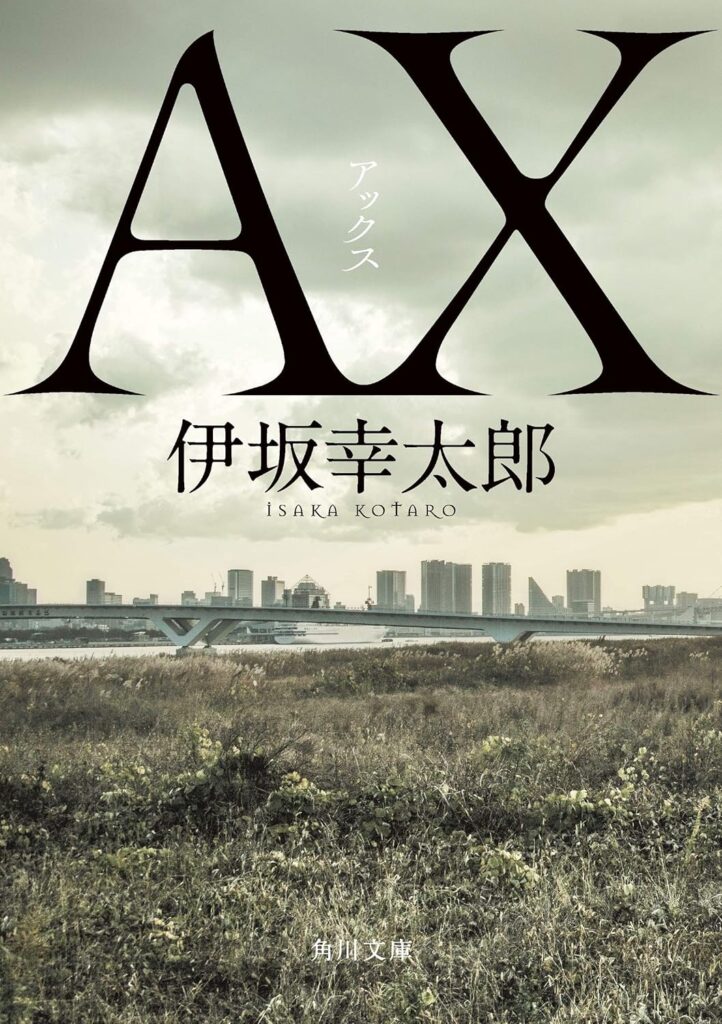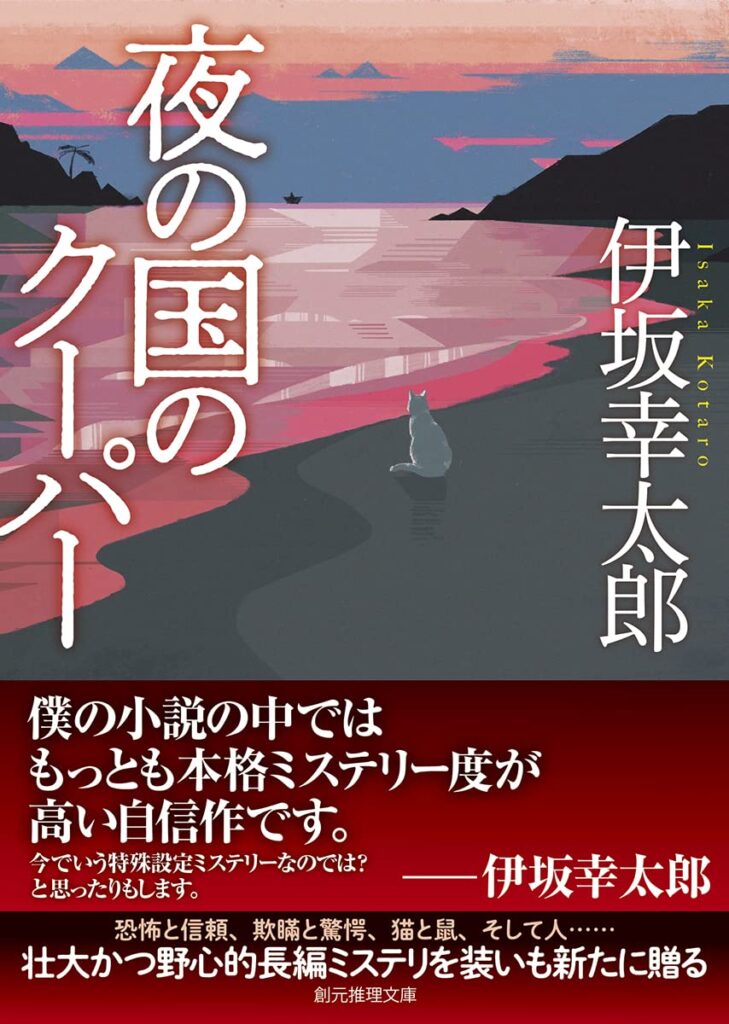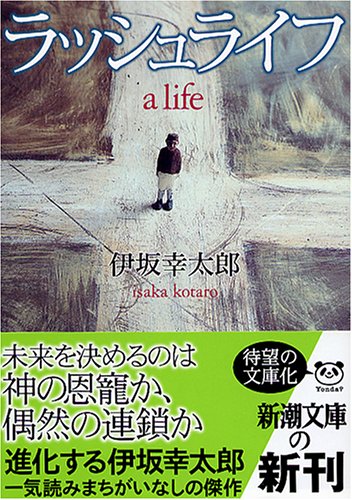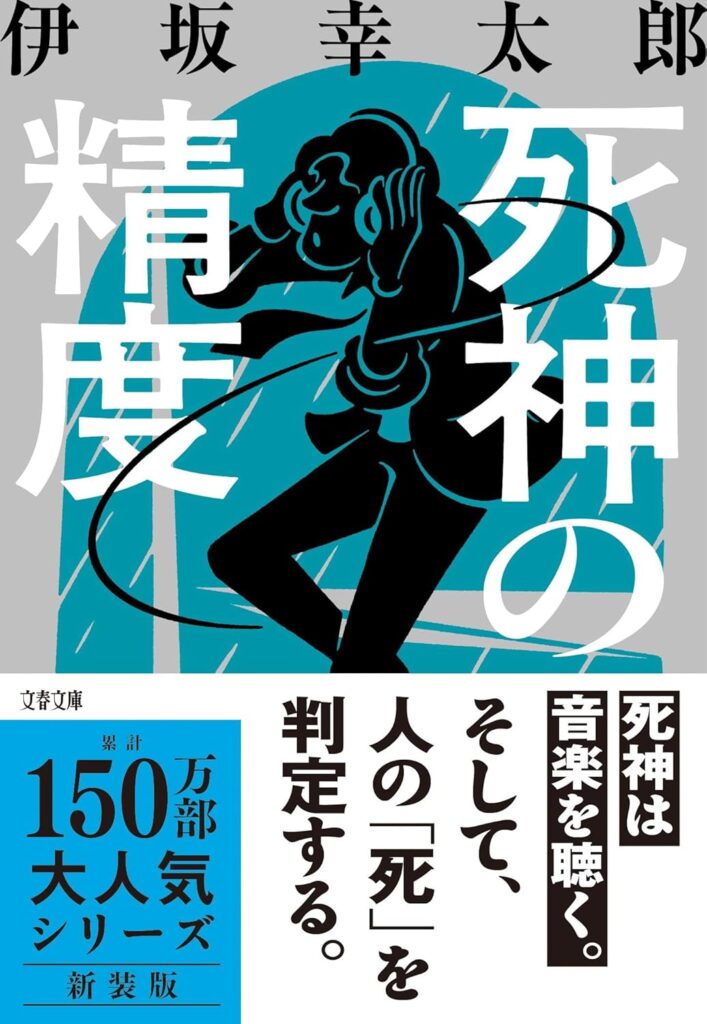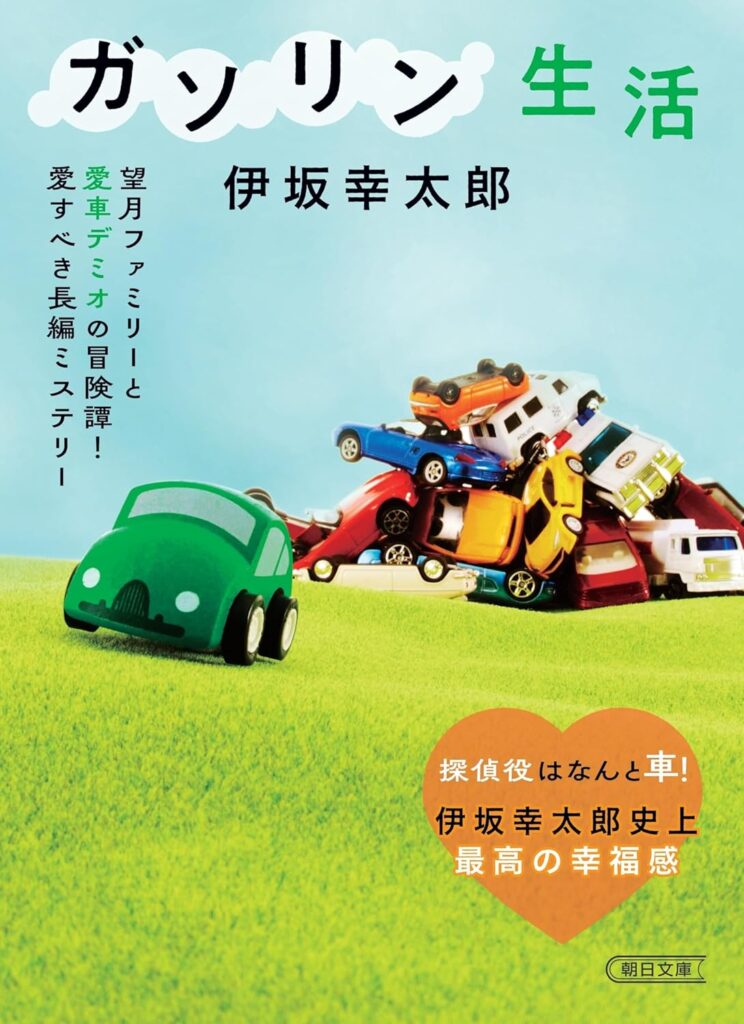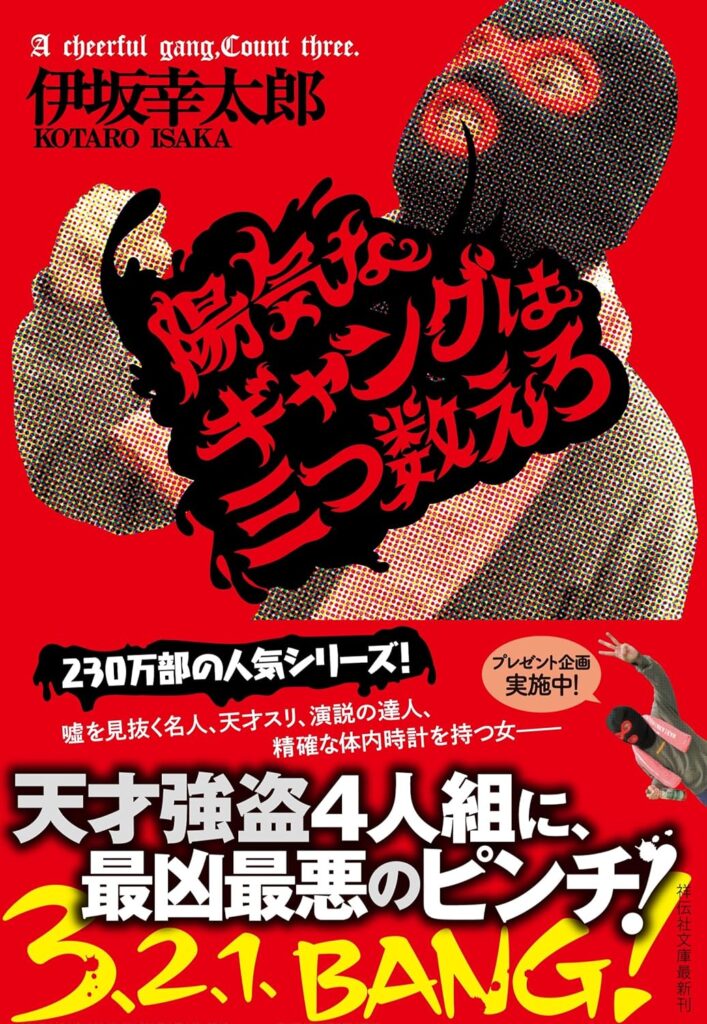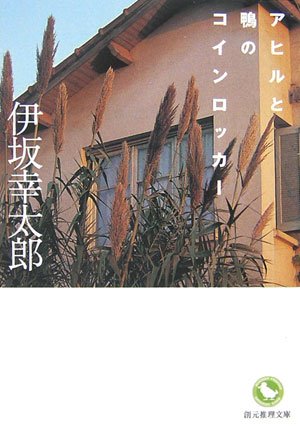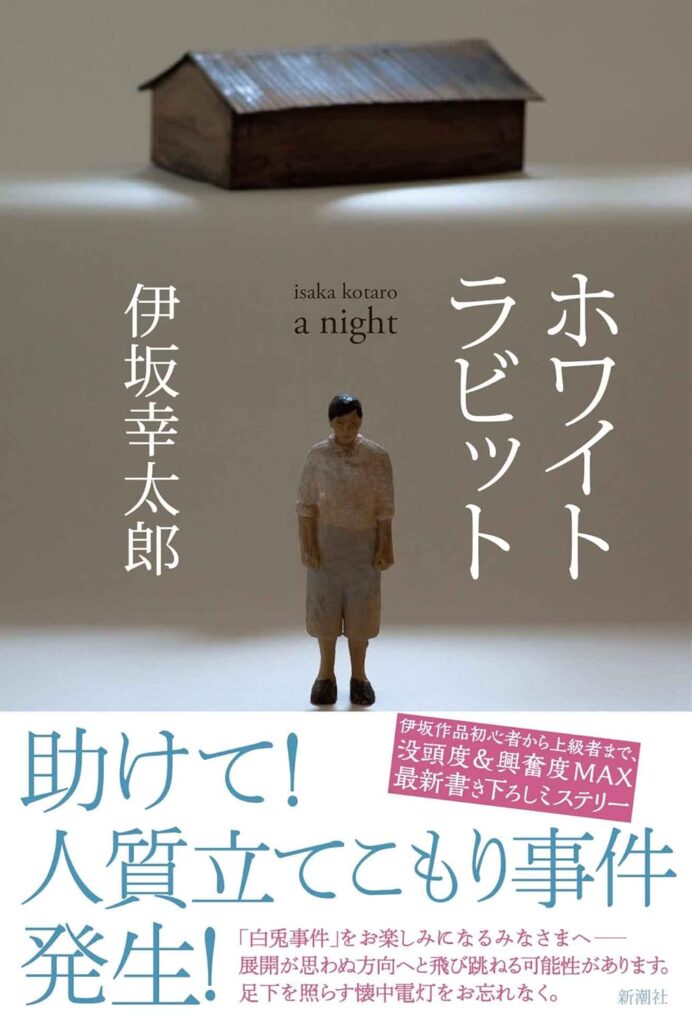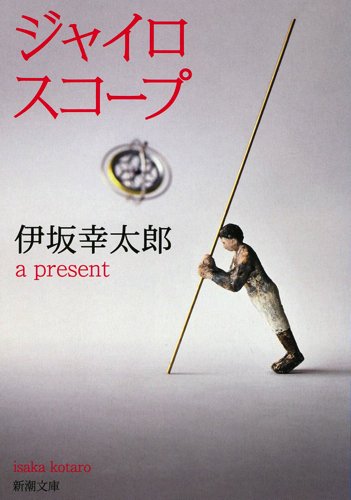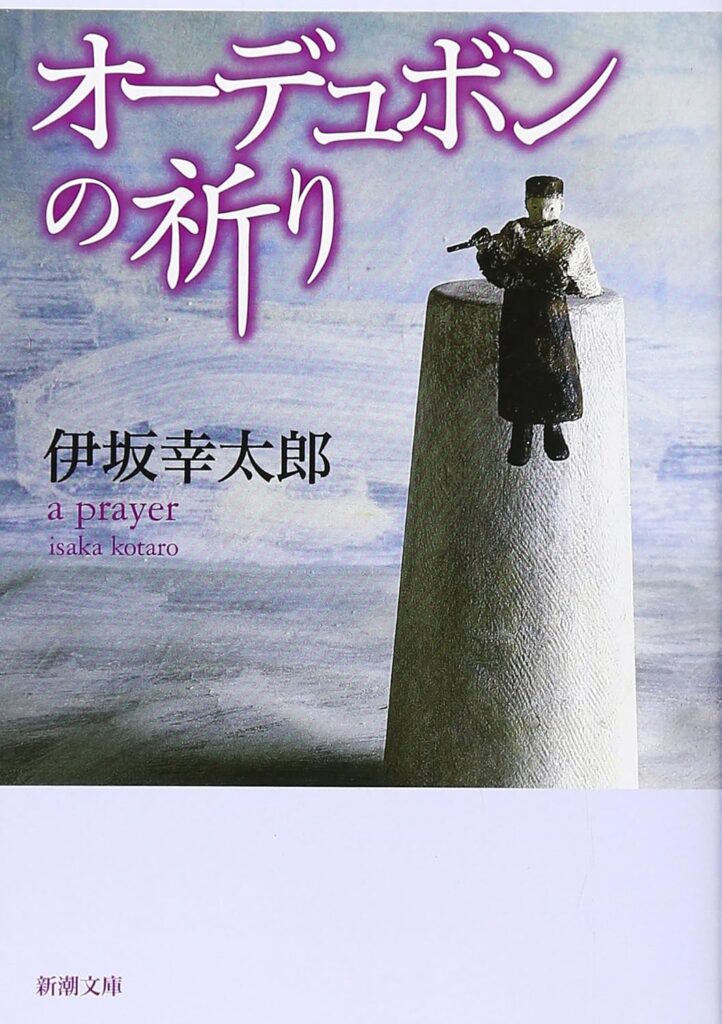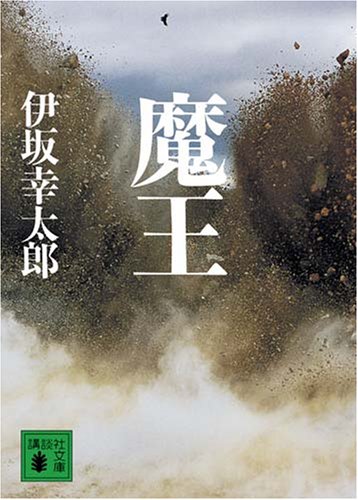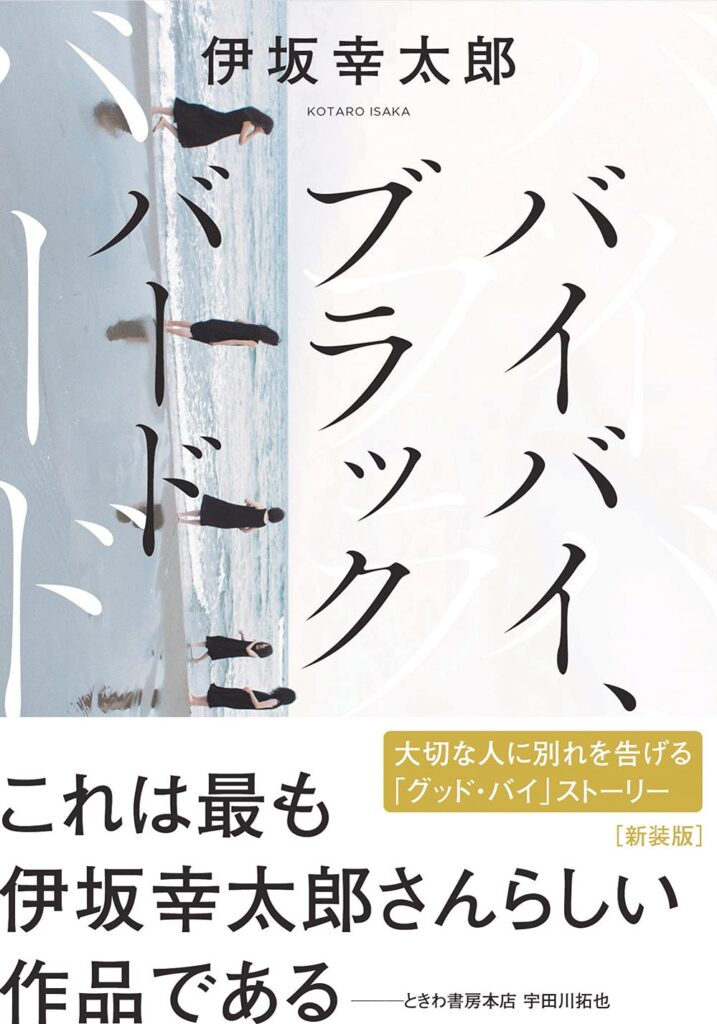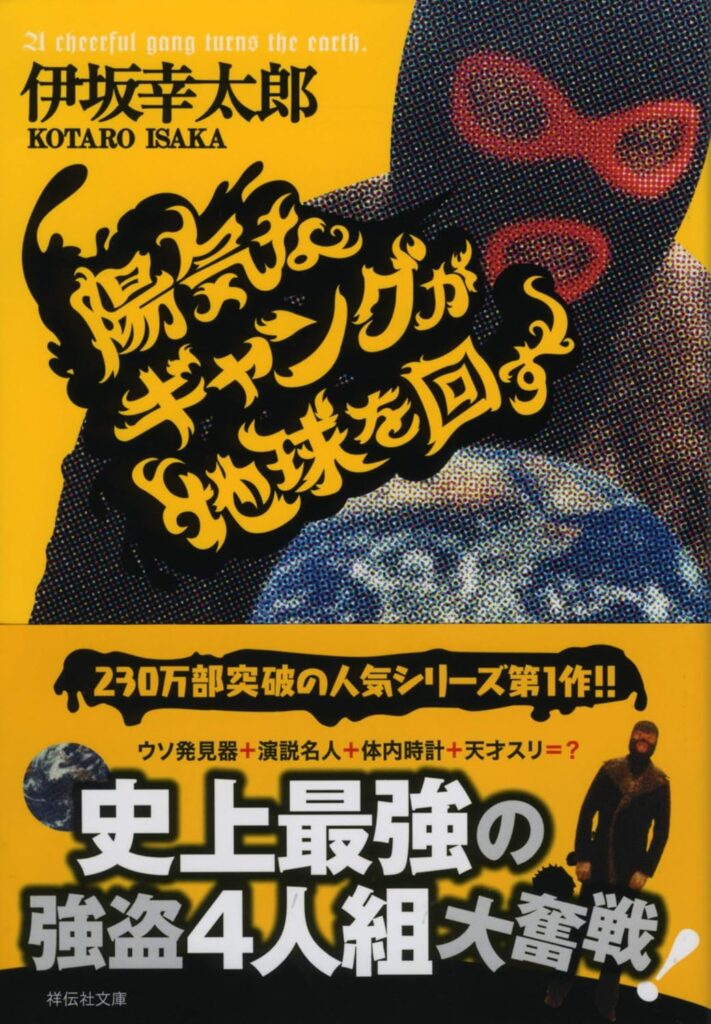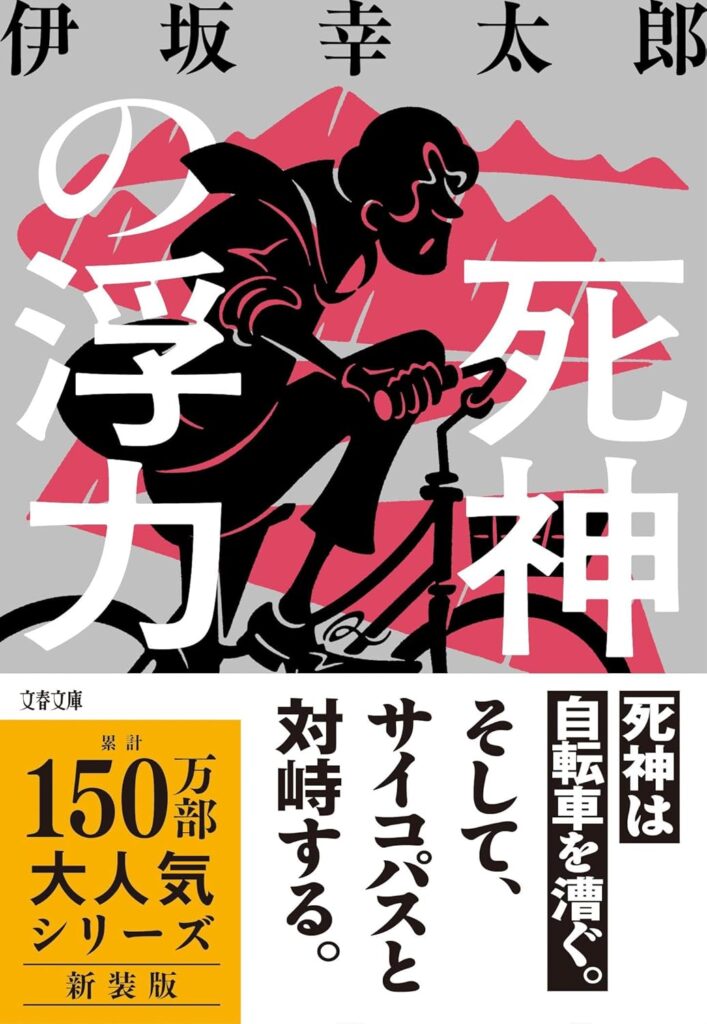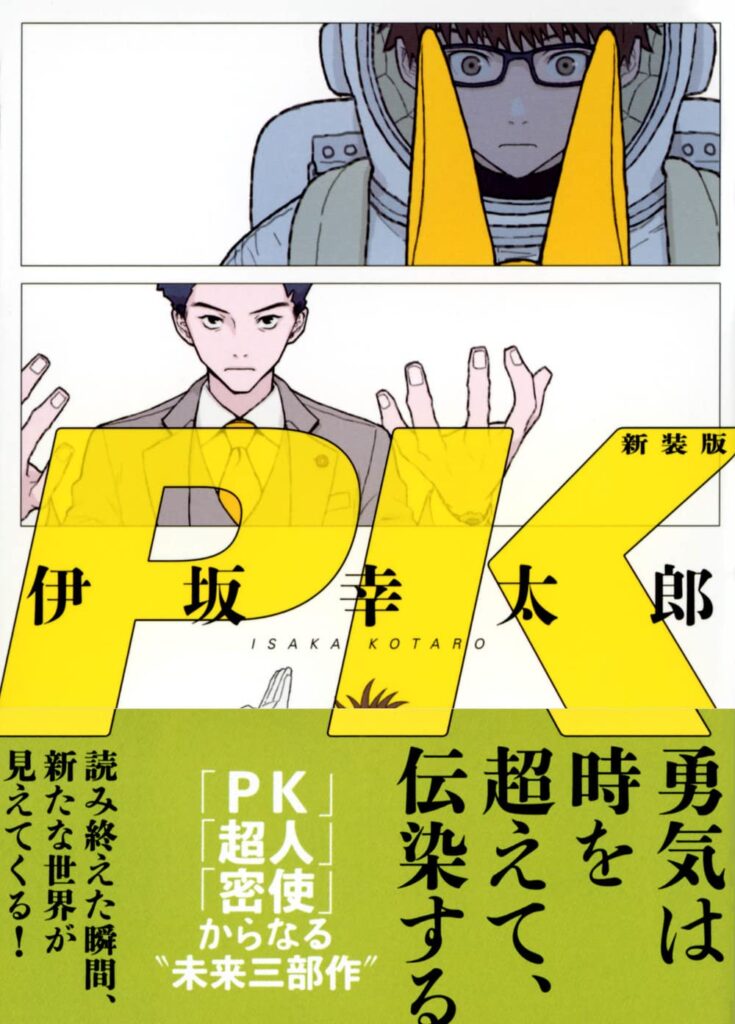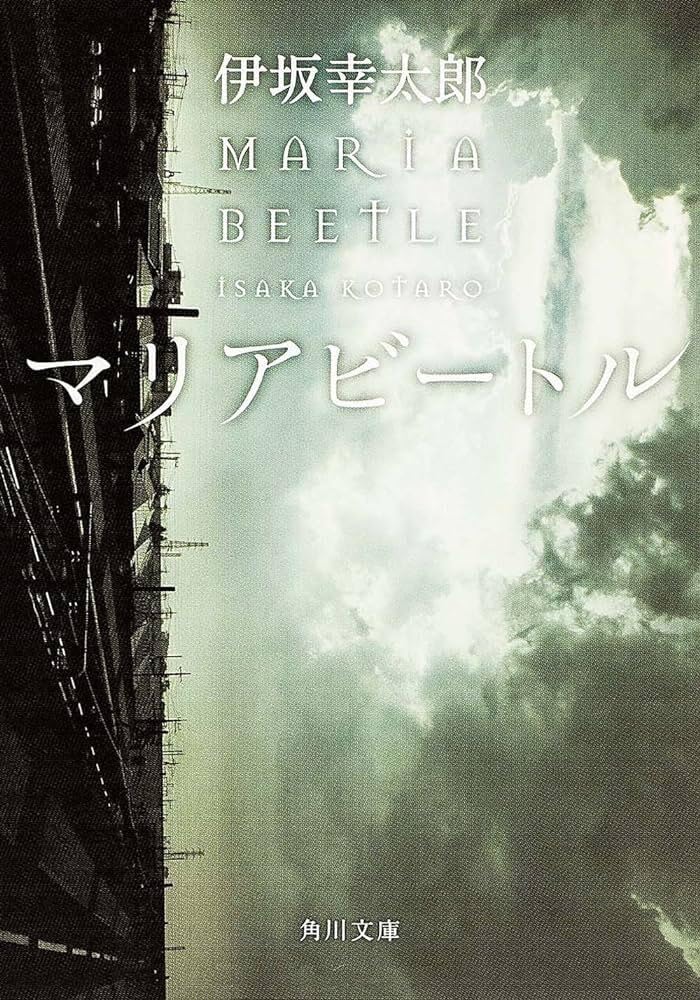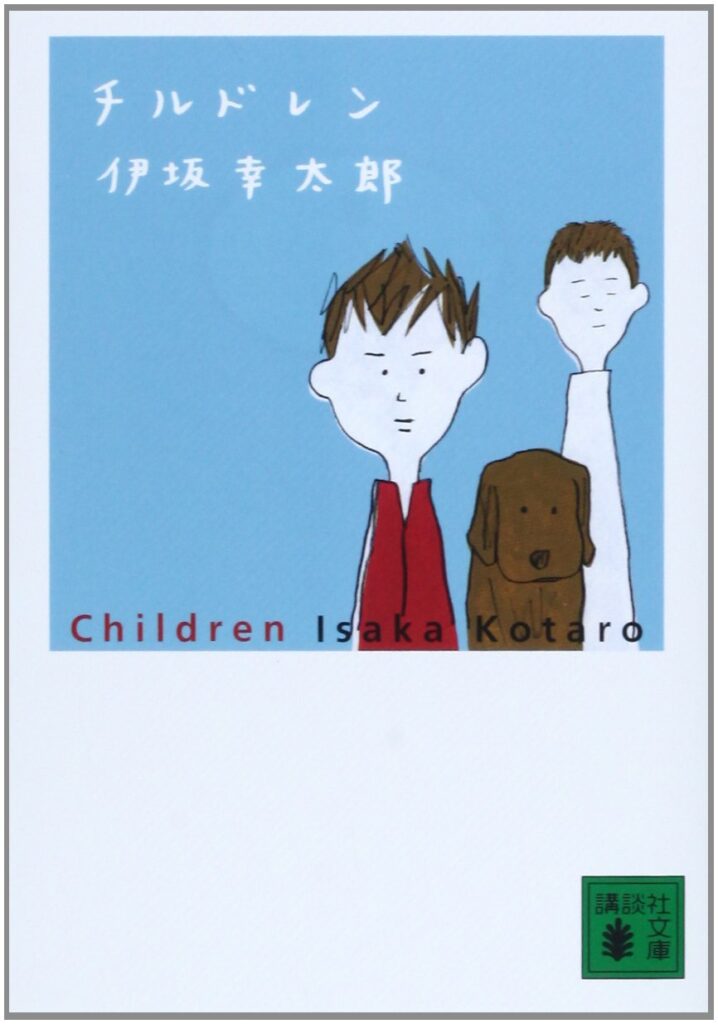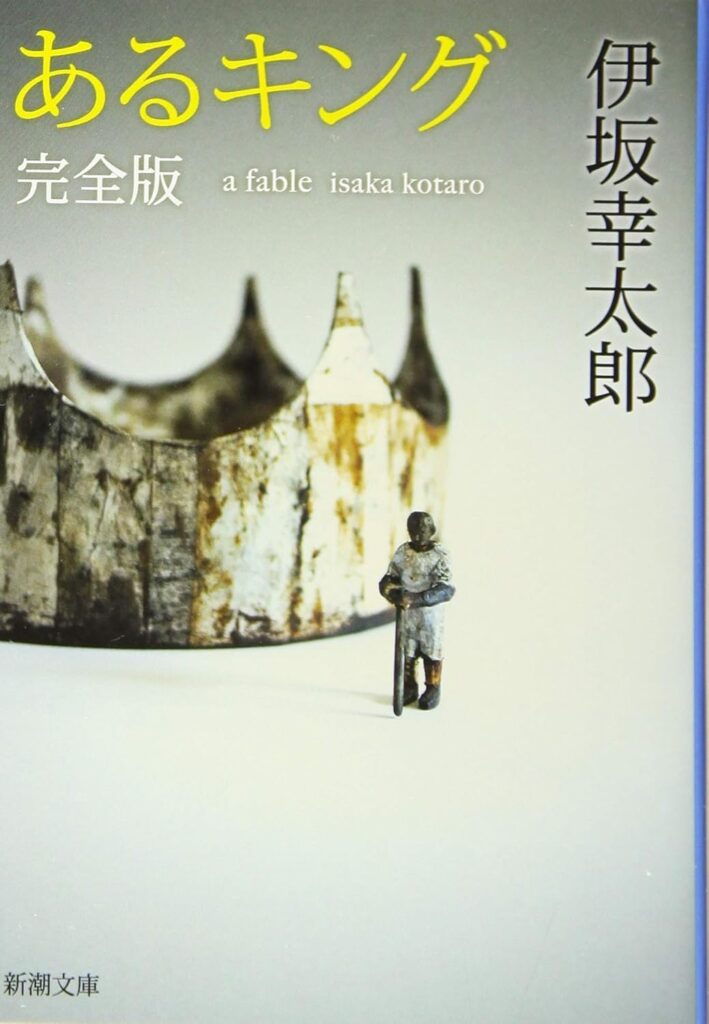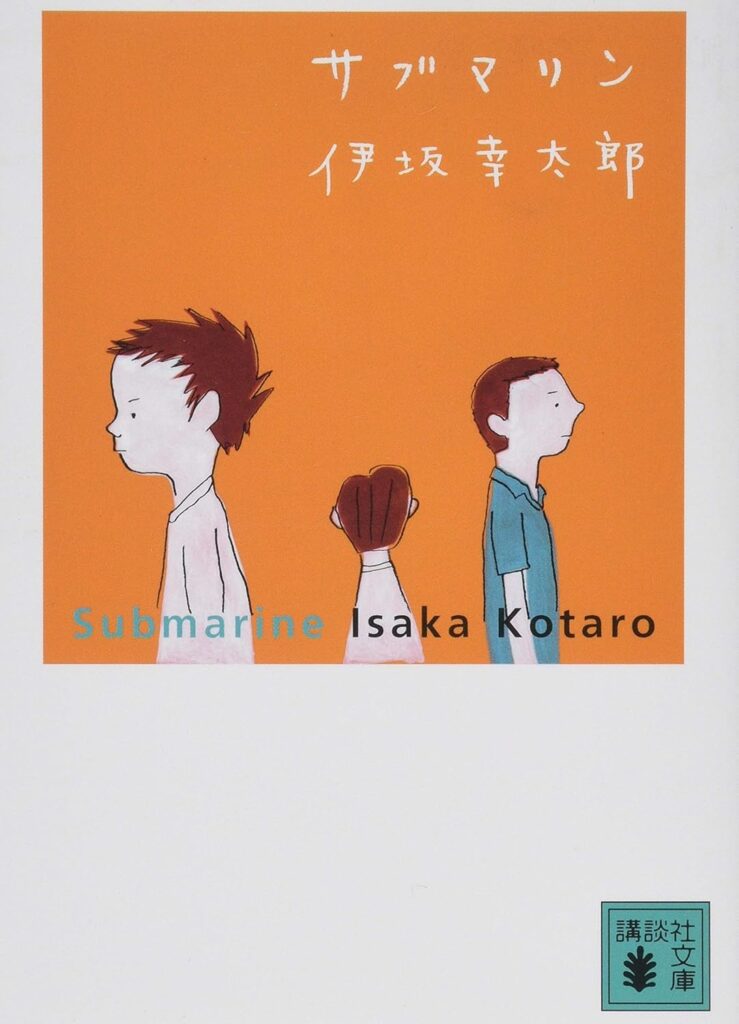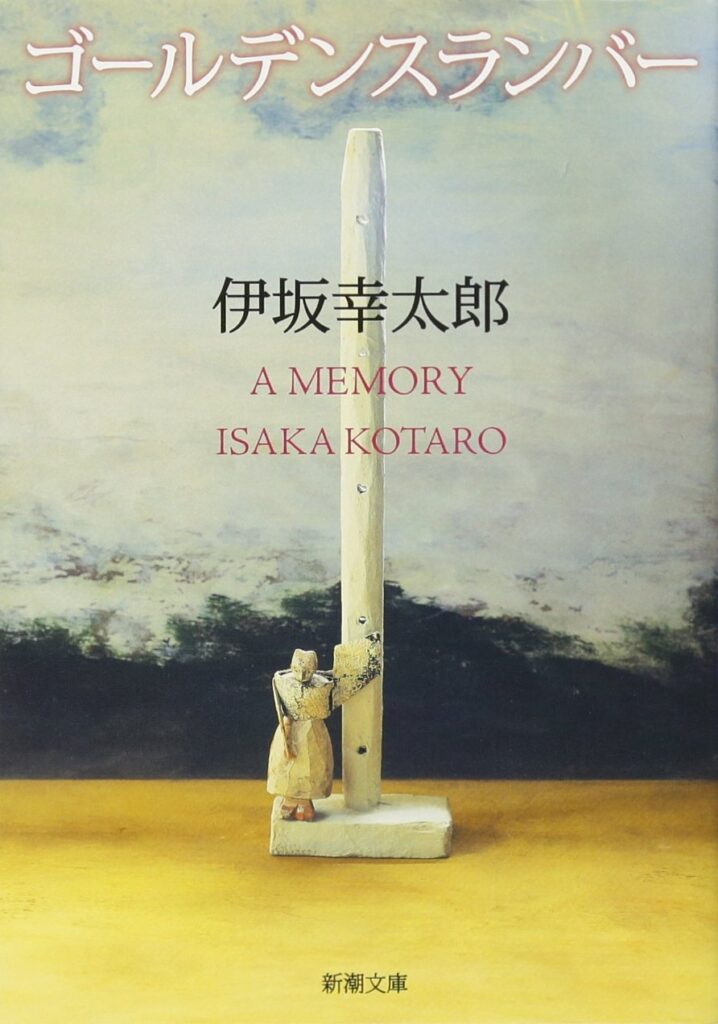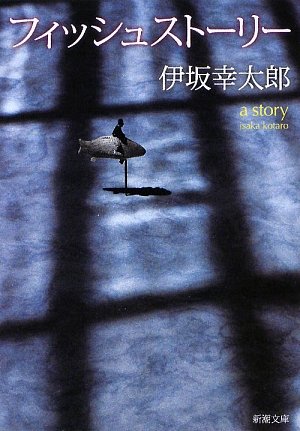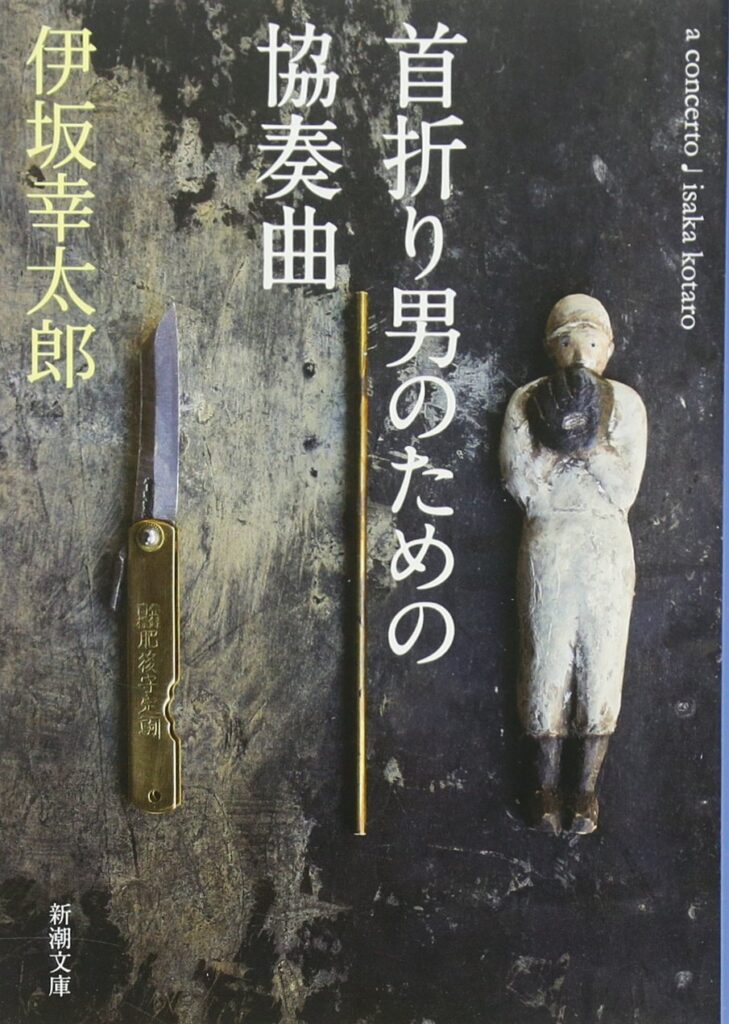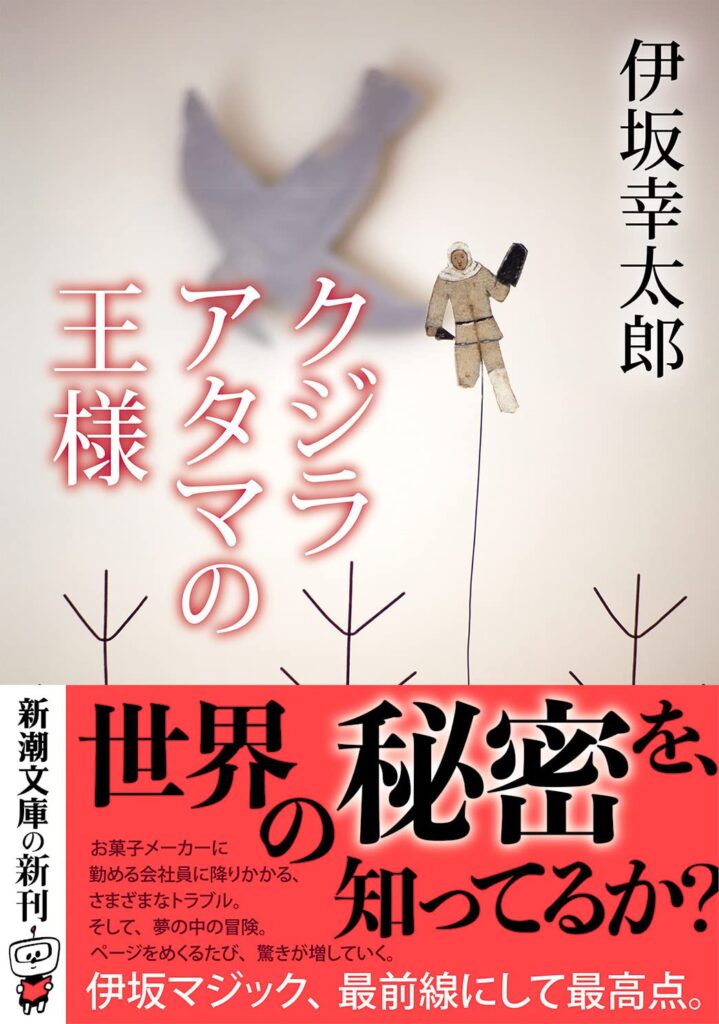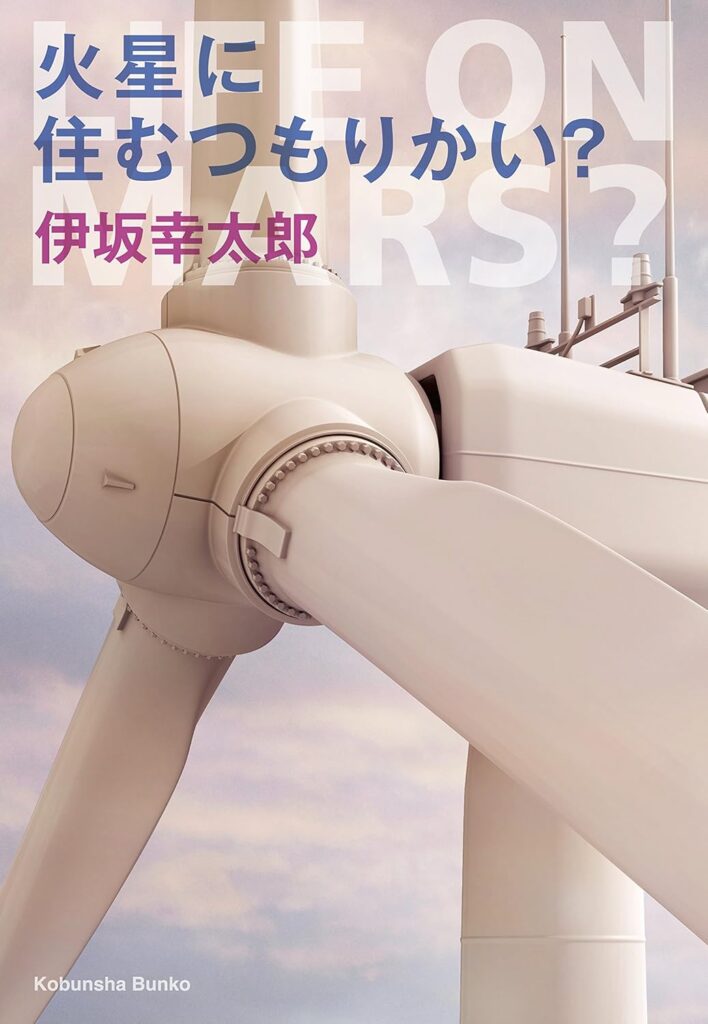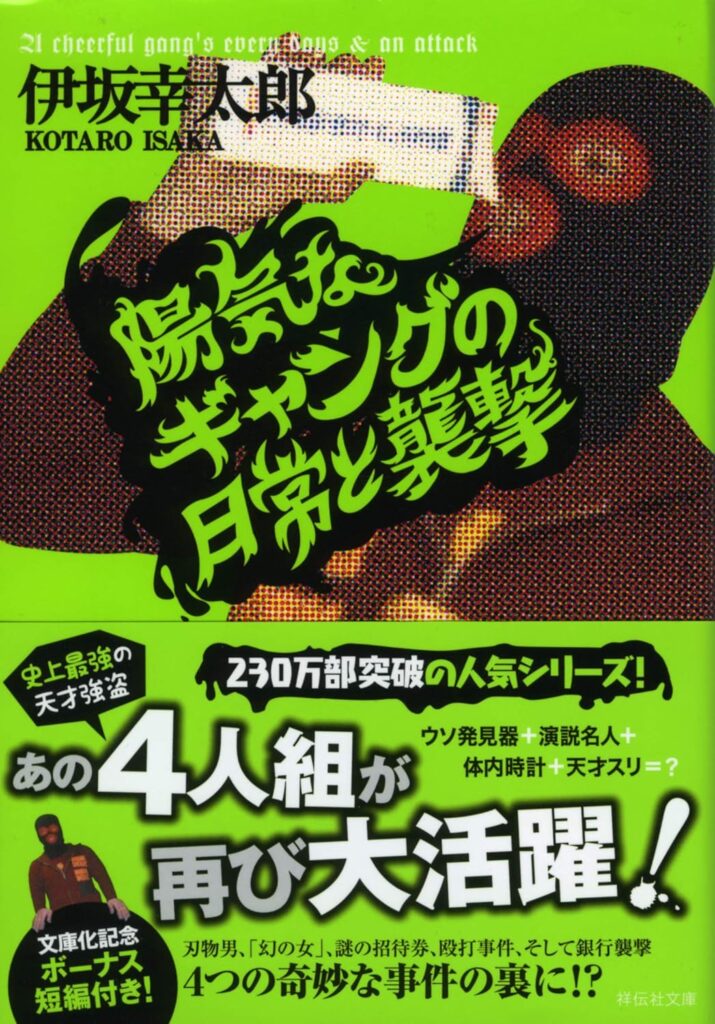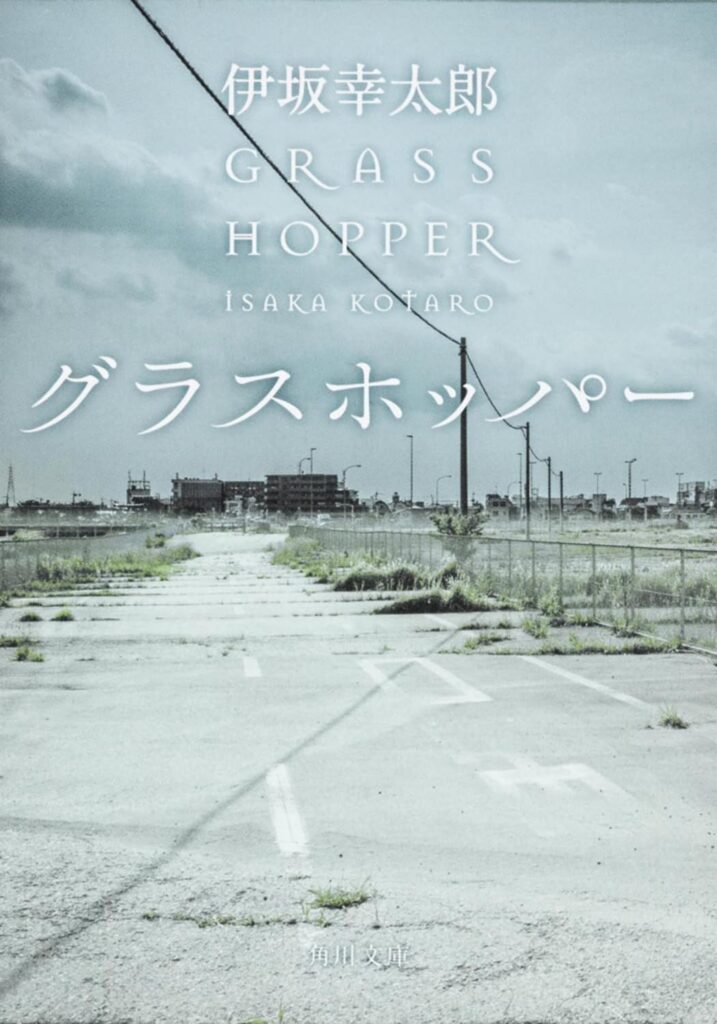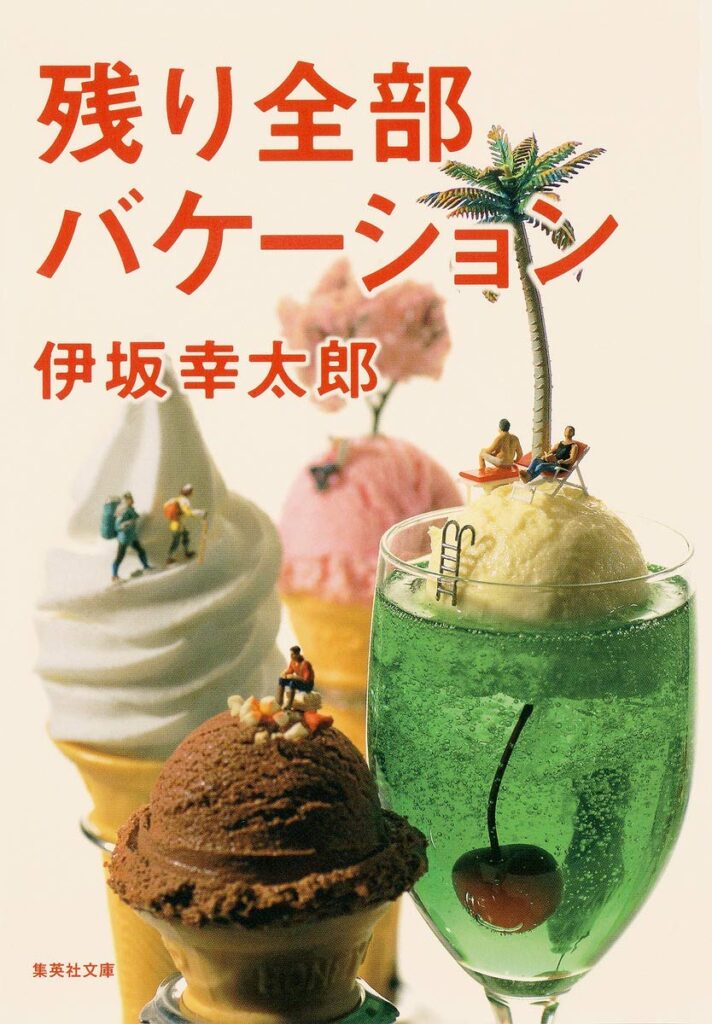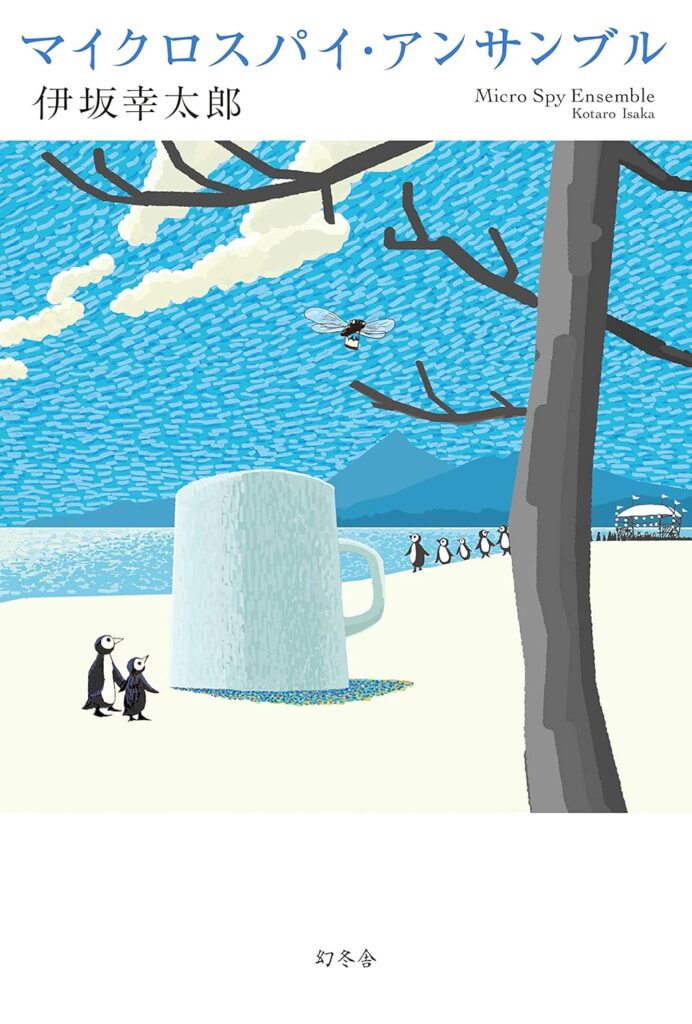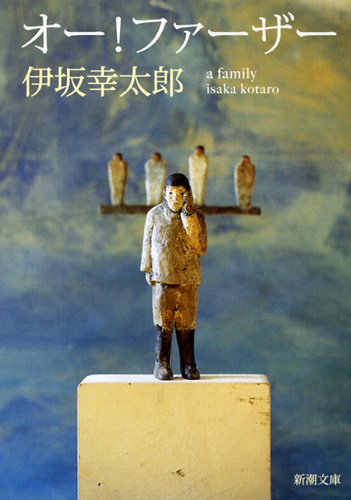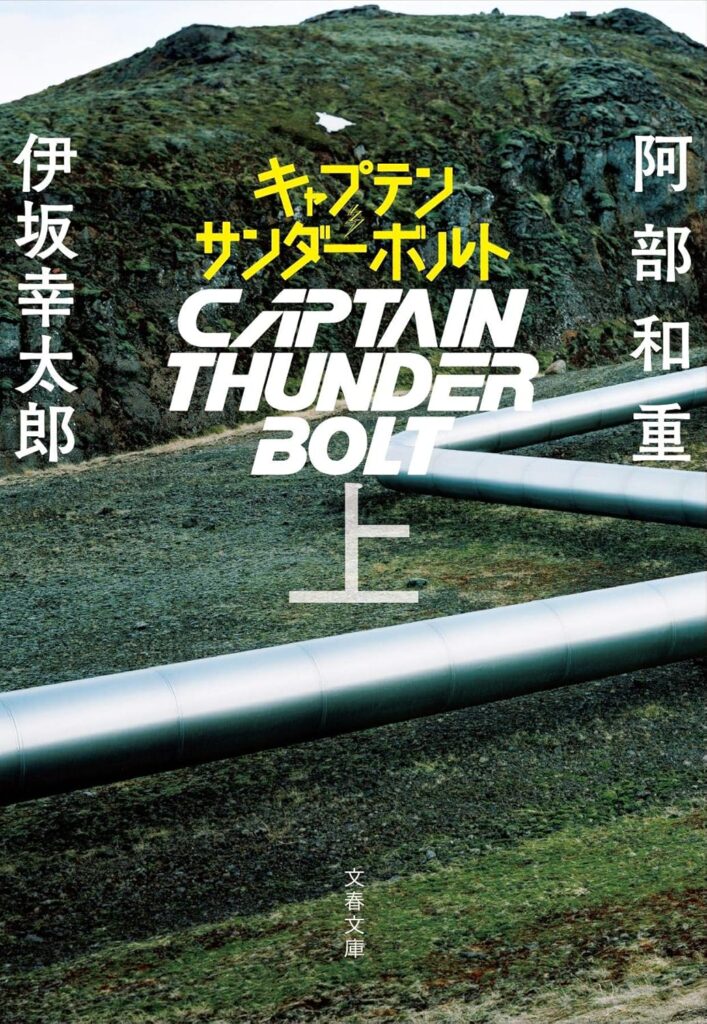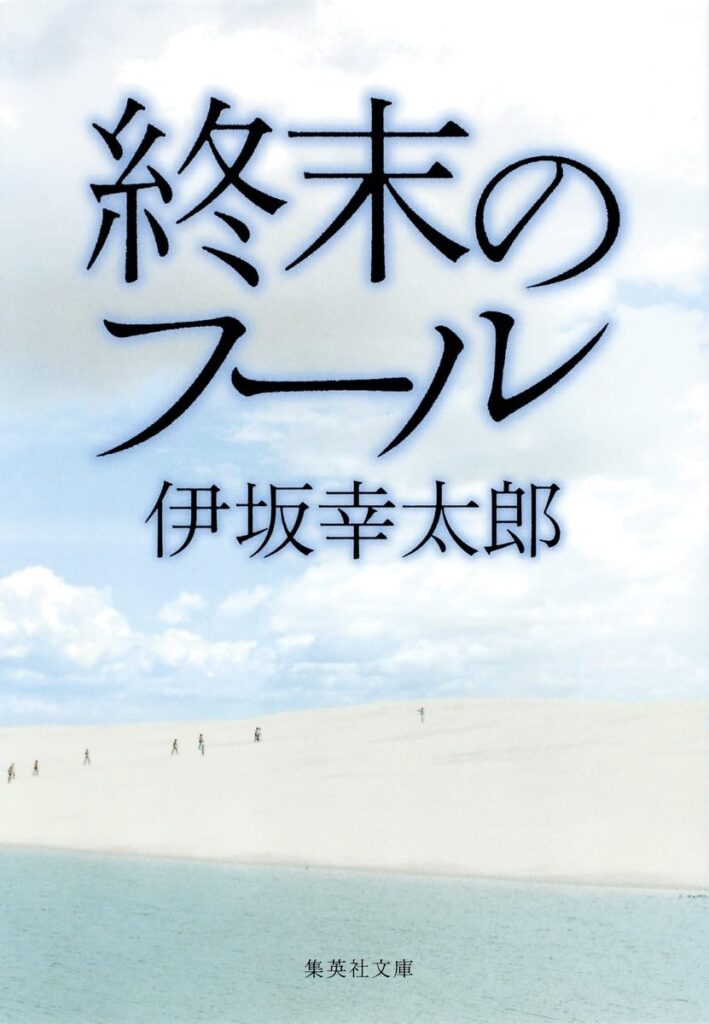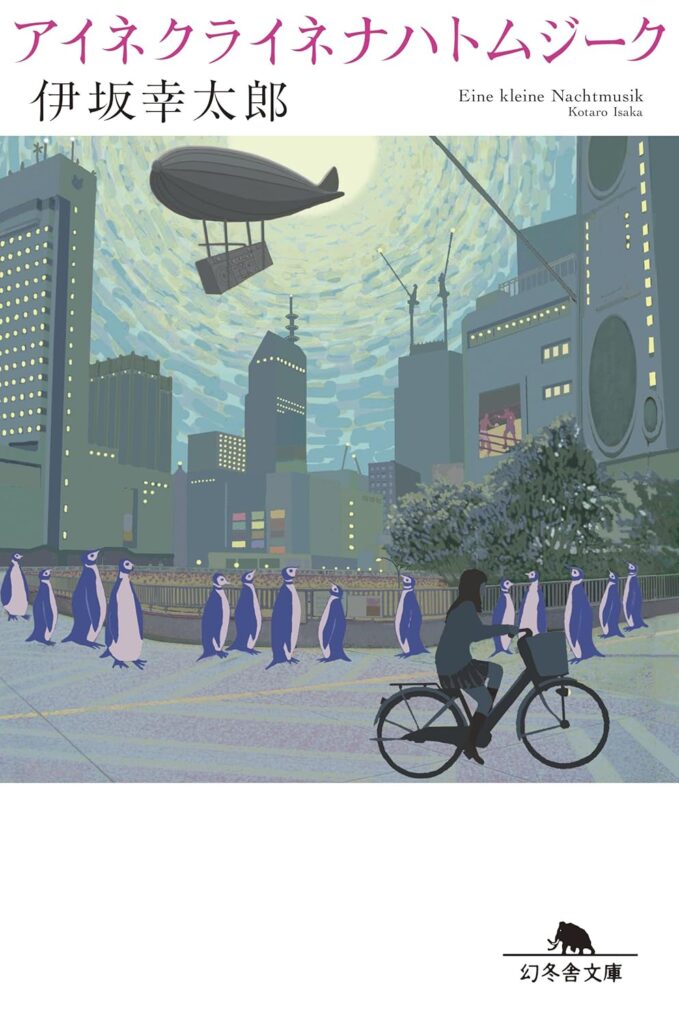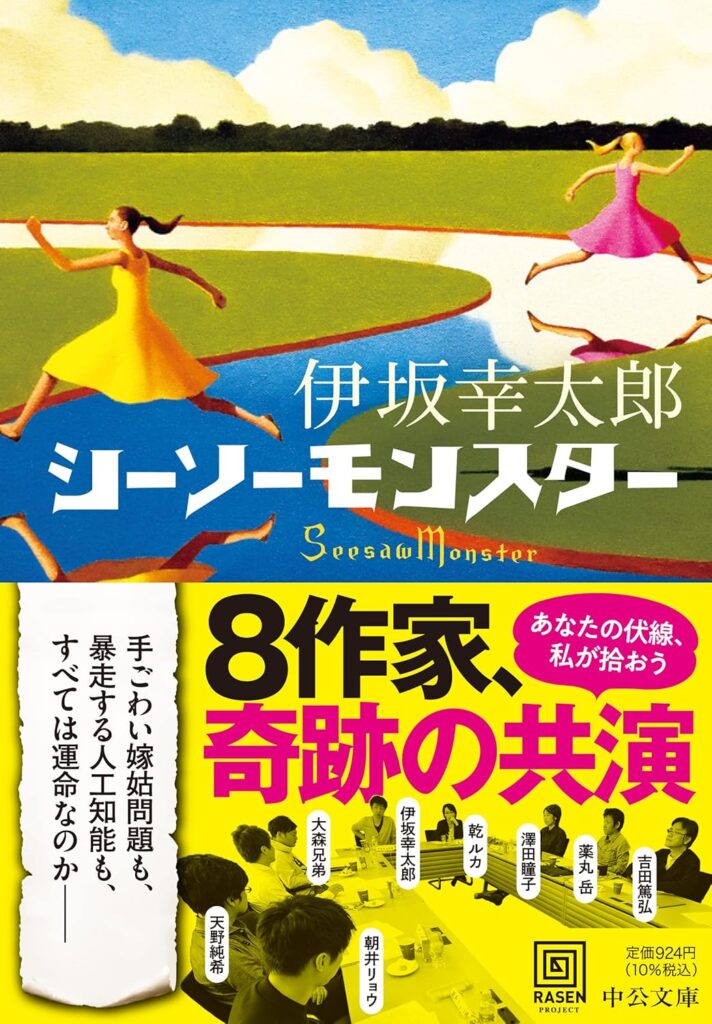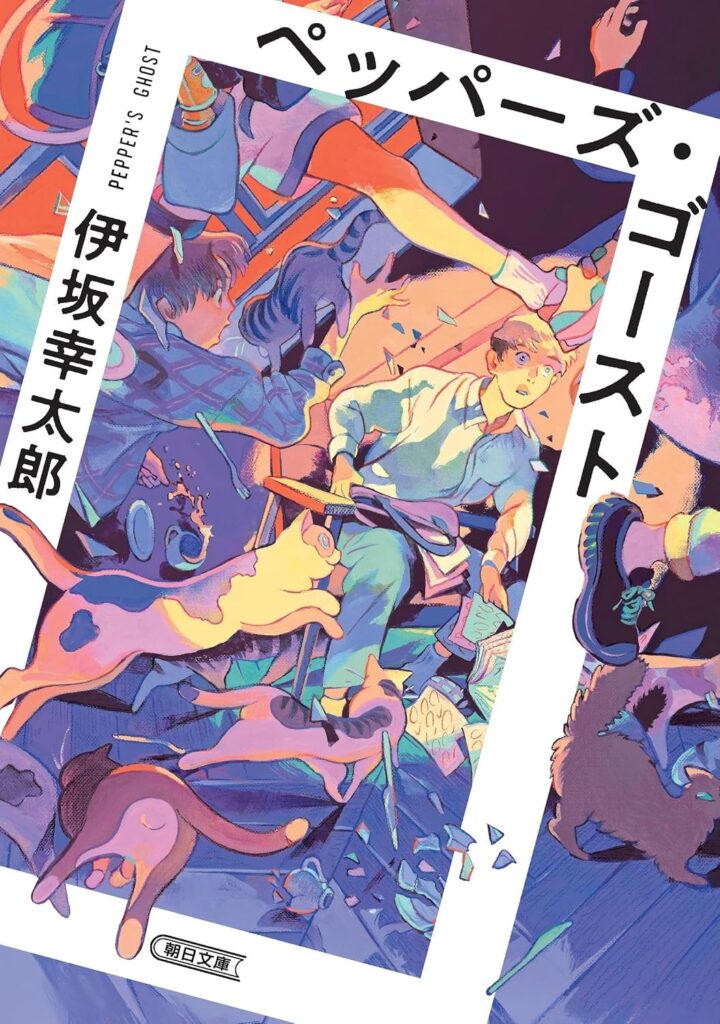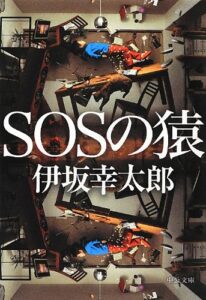 小説「SOSの猿」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。伊坂幸太郎さんの作品の中でも、少し不思議な読後感を残すと言われることもあるこの物語。エクソシストの副業を持つ家電量販店員・二郎と、システムエンジニア・五十嵐という、全く異なる世界の二人の視点が交錯しながら進んでいきます。
小説「SOSの猿」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。伊坂幸太郎さんの作品の中でも、少し不思議な読後感を残すと言われることもあるこの物語。エクソシストの副業を持つ家電量販店員・二郎と、システムエンジニア・五十嵐という、全く異なる世界の二人の視点が交錯しながら進んでいきます。
物語は、二郎が旧知の女性から引きこもりの息子の相談を受ける場面と、五十嵐が株の誤発注事件の原因調査に奔走する場面が交互に描かれます。一見無関係に見える二つの出来事が、やがて奇妙な繋がりを見せ始め、読者を伊坂さん独特の世界へと引き込んでいきます。この記事では、その複雑な物語の概要と、隠された仕掛け、そして読後に残る深い余韻について、詳しく触れていきたいと思います。
読み進めるうちに明らかになる登場人物たちの意外な関係性や、物語の背後に潜むテーマ、そして少しばかり「肩すかし」とも評される結末の解釈まで、じっくりと語っていきます。これから「SOSの猿」を読もうと思っている方、すでに読まれて他の人の見解を知りたい方、どちらにも楽しんでいただける内容を目指しました。
小説「SOSの猿」のあらすじ
家電量販店で働く遠藤二郎には、エクソシスト(悪魔祓い師)というもう一つの顔がありました。ある日、彼は昔憧れていた「辺見のお姉さん」こと奈々から、引きこもりになってしまった息子・眞人の様子を見てほしいと頼まれます。奈々は、眞人が悪魔に取り憑かれているのではないかと心配しているのでした。困っている人を見過ごせない二郎は、この依頼を引き受けることにします。初めて眞人の部屋を訪れた際、二郎は彼と少し話しますが、突然書棚が倒れ、眞人は気を失ってしまいます。その中には「西遊記」の本もありました。
一方、桑原システムという会社で品質管理部に勤める五十嵐真は、取引先である菩薩証券で起きた、短時間で巨額の損失を出した株の誤発注事件の調査に追われていました。自社が納入したシステムに原因があるのではないかと疑われ、五十嵐は同僚と共に原因究明にあたります。調査を進める中で、五十嵐は同僚の女性がまるで『西遊記』に出てくるサソリの精のように見える、という奇妙な体験もします。彼は論理的に原因を突き止めようと奔走します。
二郎は再び眞人の元を訪れます。すると眞人は突然「自分は孫悟空の分身の術で取り憑いている」と名乗り、「未来が見える」と言い出します。そして、窓の外を歩いていた五十嵐真を指差し、彼に半年後に起こる出来事を予言してみせました。その後、二郎は偶然にも五十嵐と出会い、眞人の予言について話します。二人は眞人の予言の真偽や、誤発注事件の真相を探るため協力することになります。コンビニ店長の金子や、そこでゲリラ合唱をする雁子といった人物たちも関わり、物語は核心へと近づいていきます。
調査の過程で、眞人が引きこもるきっかけとなった出来事や、彼が予言の力を使って人知れず他人を助けていたこと、そして誤発注事件に関わる人物の裏の顔などが明らかになっていきます。眞人に憑いていた(あるいは眞人自身が生み出した)「孫悟空」が見せる過去の映像や予言を手がかりに、二郎と五十嵐たちは事件の真相に迫りますが、そこには単純な勧善懲悪では割り切れない現実と、少し不思議な結末が待っているのでした。最終的に、眞人の状態は快方に向かい、二郎や五十嵐もそれぞれの日常の中で新たな一歩を踏み出します。
小説「SOSの猿」の長文感想(ネタバレあり)
伊坂幸太郎さんの『SOSの猿』、読み終えた後に、なんとも言えない不思議な感覚に包まれました。すっきり解決!という爽快感とは少し違う、けれど心にじんわりと何かが残る、そんな作品です。よく「モヤモヤシリーズ」なんて言われることもあるようですが、まさにその言葉がしっくりくるかもしれません。でも、それは決してつまらないという意味ではなくて、物語の構造やテーマ性が一筋縄ではいかない、奥深さを持っているからなのだと感じています。
まず、この物語の大きな特徴は、「私の話」と「猿の話」という二つのパートが交互に語られる構成ですよね。「私の話」は、家電量販店員でありながら副業でエクソシストをしている遠藤二郎の一人称視点で進みます。困っている人を放っておけない、お人好しで少し頼りないけれど、根は真面目な二郎の視点は、読者にとって感情移入しやすい入口になっていると思います。彼が辺見のお姉さんに頼まれて、引きこもりの息子・眞人の「悪魔祓い」に挑む過程は、どこかユーモラスでありながらも、現代社会の抱える問題(引きこもり、コミュニケーション不全など)にも触れていて、考えさせられます。
一方、「猿の話」は、システムエンジニアの五十嵐真を軸に、第三者の視点から語られます。こちらは「因果関係の物語」と作中でも語られるように、論理や事実を重んじる五十嵐が、株の誤発注という大きなトラブルの原因を突き止めていく、ミステリー仕立ての展開です。五十嵐が見る奇妙な幻覚(同僚がサソリの精に見えるなど)は、彼の理性的な世界に不穏な亀裂を入れるようで、物語に独特の緊張感を与えています。そして、読み進めていくうちに、この「猿の話」の語り手が、実は眞人に憑いている(あるいは眞人自身が同一化している)「孫悟空」の分身であることが示唆されます。この仕掛けには驚かされました。
さらに、「猿の話」は、「私の話」から半年後の出来事を「予言」として語っている、という時間的なトリックも仕掛けられています。だから、語られる内容には微妙なズレがあるんですね。五十嵐の勤務先が実際とは違っていたり、誤発注の金額や関わった人物の名前が少し違っていたり。この「予言のズレ」は、未来は確定していない、人の行動によって変わりうるものだ、というメッセージのようにも受け取れました。
物語の中心人物である眞人は、非常にミステリアスな存在です。彼はほとんど直接的には語らず、二郎や孫悟空(語り手)を通してその内面や行動が推測されるばかり。彼がなぜ引きこもるようになったのか、なぜ孫悟空を名乗るのか、そしてなぜ未来を予言できるのか。その明確な答えは示されません。ただ、彼がコンビニで起きた交通事故を目撃し、その加害者への怒りや、被害者への同情といった強い感情を抱えていたこと、そしてその感情をうまく処理できずに苦しんでいたであろうことは伝わってきます。彼が見る「夢」(孫悟空の視点や予言)は、彼自身の願望や、彼が接した人々の情報、そして『西遊記』の物語などが混ざり合った、一種の防衛機制あるいは現実逃避の形だったのかもしれません。
この作品のテーマとして強く感じられたのは、やはりタイトルにもなっている「SOS」です。辺見のお姉さんの眞人に対するSOS、金融屋に追われる老婆のSOS、虐待される子供のSOS、そして眞人自身の声なきSOS。二郎は、そんな他人のSOSを見過ごせない人物として描かれます。彼は決して特別な力を持っているわけではない(悪魔祓いの力も、どこか頼りない感じです)けれど、それでも誰かのために行動しようとします。彼の存在は、「ヒーローじゃなくても、できることはある」という、ささやかだけれど大切なメッセージを伝えているように感じました。
そしてもう一つのテーマは「因果関係」。五十嵐が徹底的に追求するこのテーマは、物語全体を貫いています。株の誤発注の原因、眞人が引きこもった原因、コンビニでの事故と虐待事件の繋がり。全ての出来事は複雑に絡み合い、影響し合っています。しかし、その因果関係を完全に解き明かすことが、必ずしも真の解決に繋がるとは限らない、という点も示唆されています。例えば、誤発注事件の犯人とされる中野(中田)徹や、虐待を行っていた男の動機や背景は深く掘り下げられません。彼らはある種、物語を動かすための装置のようにも見えます。重要なのは、事件の連鎖の中で、登場人物たちがどう考え、どう行動し、どう変化していくか、ということなのかもしれません。
伊坂作品らしい魅力的なキャラクターたちも健在です。二郎や五十嵐はもちろん、コンビニでゲリラ合唱をする雁子や店長の金子など、脇を固める人物たちも個性的で、物語に彩りを与えています。彼らの軽妙な会話は、シリアスになりがちな物語に、ふっと息をつける瞬間をもたらしてくれます。
ただ、参考資料の感想にもあったように、「肩すかし」と感じる部分があるのも事実です。特に終盤、二郎と五十嵐が協力して中野徹の隣の部屋(虐待が行われていた部屋)に乗り込む場面。ここで何か決定的な出来事が起こるかと思いきや、猿の化身が現れて過去の映像を見せる、という展開になります。そして、本当に悪い男はすでに別の場所で逮捕されている。読者が期待するような直接対決や、劇的な解決は訪れません。伏線が回収されないわけではないけれど、カタルシスという点では物足りなさを感じる人もいるでしょう。物語の真相は、幾重にも重なるベールの向こうにあるようで、一枚めくるごとに新たな疑問が顔を出す、まるで迷宮のような構造でした。
また、眞人の「孫悟空」設定や予言能力といったファンタジー要素も、もっと前面に出て活躍するのかと期待していると、少し拍子抜けするかもしれません。孫悟空はあくまで語り手であり、眞人の内面を反映する鏡のような存在であって、派手なアクションを繰り広げるわけではありません。このあたりも、「モヤモヤ」や「肩すかし」感に繋がる一因かもしれません。
しかし、この「肩すかし」や「モヤモヤ」こそが、『SOSの猿』という作品の狙いであり、魅力なのかもしれない、とも思うのです。現実は、物語のように常に明確な解決やカタルシスがあるわけではありません。原因が分かっても、全てが元通りになるわけではない。それでも、人々はそれぞれの場所で、できることを見つけ、少しずつ前に進んでいく。二郎が、自分が売ったエアコンが誰かの役に立っているかもしれないと思えるようになるラストシーンや、五十嵐が新たな趣味を見つけて生き生きとする姿は、派手さはないけれど、確かな希望を感じさせてくれます。眞人もまた、自分の抱える力(あるいは問題)と向き合いながら、少しずつ快方に向かっている。
『SOSの猿』は、単純なエンターテイメントとして消費されることを拒むような、少しひねくれた、けれど誠実な作品だと感じました。読み手を選ぶかもしれませんが、二郎や五十嵐のように、日常の中でふと無力感を感じたり、物事の複雑さに戸惑ったりした経験のある人には、深く響くものがあるのではないでしょうか。読み終わった後、すぐに答えが出るわけではないけれど、じっくりと反芻したくなる。そんな、味わい深い一冊でした。伊坂幸太郎さんの作品の中でも、特に考えさせられる、記憶に残る物語です。
まとめ
この記事では、伊坂幸太郎さんの小説『SOSの猿』について、物語の概要から、ネタバレを含む詳細な考察、そして個人的な感想を述べてきました。エクソシストの二郎とシステムエンジニアの五十嵐、二人の主人公の視点が交錯しながら、引きこもりの少年・眞人を巡る謎や、株の誤発注事件の真相が解き明かされていく過程を描いています。
物語は、「私の話」と「猿の話」という二部構成と、語り手や時系列に関する仕掛けが特徴的です。「SOS」や「因果関係」といったテーマが深く掘り下げられており、登場人物たちの悩みや葛藤、そしてささやかな成長が丁寧に描かれています。読後には爽快感とは少し異なる、考えさせられるような余韻が残るかもしれません。
「肩すかし」や「モヤモヤする」といった評価もある一方で、その複雑さや一筋縄ではいかない展開こそが、この作品の持つ独特の魅力とも言えます。現実と非現実が入り混じる世界観の中で、登場人物たちが悩みながらも前を向こうとする姿は、読者に静かな共感と希望を与えてくれるでしょう。伊坂幸太郎さんのファンはもちろん、少し変わった読書体験を求めている方にも手に取っていただきたい一冊です。