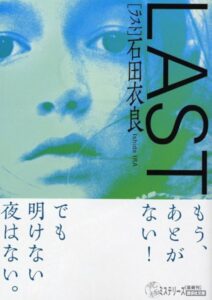 小説「LAST」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「LAST」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
本作は、2003年に直木賞を受賞した石田衣良さんが、その翌年に発表した連作短編集です。多くの人が石田作品に抱くであろう、『池袋ウエストゲートパーク』シリーズのような、若さあふれるエネルギッシュなイメージとは一線を画す、非常に重く、暗い物語が収録されています。希望の光がほとんど見えない、どん底の世界が描かれているのです。
物語のテーマは「もう、あとがない」人々。借金、孤独、抗えない欲望によって社会の崖っぷちに立たされた者たちが、最後にどのような選択をするのか。その一瞬の閃光、あるいは絶望的な結末を、冷徹なまでにリアルな筆致で描き出しています。読んでいると胸が苦しくなるような話ばかりですが、だからこそ現代社会の歪みが鋭く浮かび上がってきます。
この記事では、そんな『LAST』に収められた七つの物語の概要と、物語の核心に触れる詳しい結末、そして私がこの作品から何を感じたのかを、詳しくお話ししていこうと思います。読後感が良い作品を求めている方には、少し厳しい内容かもしれません。ですが、人間の極限状態や社会の暗部に目を向けたい方にとっては、忘れられない一冊になるはずです。
「LAST」のあらすじ
物語の舞台は、2000年代初頭の日本。長く続く不況のなか、社会のセーフティネットからこぼれ落ちてしまった人々が、この物語の主人公たちです。彼らは、真面目に生きてきたはずなのに、あるいはほんの少し道を踏み外しただけなのに、気づけば後戻りできない場所まで追い詰められています。
例えば、父親から継いだ会社を立て直そうと闇金に手を出してしまった男。夫の失業で住宅ローンが払えなくなり、高収入の怪しげな仕事に応募する主婦。暴力団が絡む詐欺の片棒を担がされ、命の危険を感じながら大金を引き出す役目を負った男。彼らは皆、普通の日常から転落し、もはやまともな選択肢が残されていない状況にいます。
そんな彼らの前に、文字通り「最後」の選択が突きつけられます。家族のために自らの命を差し出すのか。人間としての尊厳を捨ててでも、金を得るのか。あるいは、一発逆転を狙って危険な賭けに出るのか。どの物語も、息をのむような緊迫した状況で、主人公の決断が描かれていきます。
しかし、この物語集は、その選択の結果、彼らがどうなったのかを親切には教えてくれません。決断の瞬間、まさにその一点に焦点を当て、物語はぷつりと終わるのです。だからこそ、読者はその選択の重みを突きつけられ、登場人物たちの運命に思いを馳せることになります。希望の見えない世界で、彼らが見せる最後の抵抗、あるいは諦観とはどのようなものなのでしょうか。
「LAST」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、各物語の結末にも触れながら、この作品が持つテーマについて、私の考えを詳しく述べていきたいと思います。七つの物語はそれぞれ独立していますが、根底には共通する現代社会の病理が横たわっています。
貨幣経済という名の暴力
まず、この作品全体を覆っているのは、「金」というものの圧倒的な暴力性です。登場人物の多くは、金によって人生を破壊されます。「ラストライド」の主人公・修二は、会社の運転資金のために借りた金が原因で、闇金から「自分の命で支払うか、妻と娘を風俗に売るか」という究極の選択を迫られます。彼の選択は、もちろん後者ではありません。家族との最後の朝食を終え、死に向かうためのドライブに出る場面で、物語は終わります。ここには救いのかけらもありません。
「ラストジョブ」の主婦・真弓も同様です。夫の会社の倒産と住宅ローンという、誰にでも起こりうるきっかけから、彼女は「セックスボランティア」という仕事に足を踏み入れます。経済的な困窮が、いかにたやすく人間の尊厳を奪い去るか。彼女がその仕事を「最後の仕事」として受け入れる姿は、金が倫理観さえも麻痺させる現実を突きつけてきます。
「ラストドロー」の出村は、暴力団への借金返済のため、振り込め詐欺の「出し子」という犯罪に手を染めます。最後の仕事として二千万円の引き出しを命じられた彼は、土壇場で心臓発作を装って倒れ、救急車で逃走するという奇策で窮地を脱します。これは作中では珍しく、ささやかながらも痛快さを感じる結末ですが、彼がそこに至るまでの恐怖と絶望を思うと、素直に喜べるものでもありません。
そして「ラストバトル」の都築。彼は借金のかたに、日給千円で街金業者の「人間看板」として路上に立たされています。そんな彼に、債権者の中藤はロシアンルーレットでの決着を持ちかけます。勝てば借金は帳消し、負ければ死。彼が自らのこめかみに銃口を当て、引き金を引く直前で物語は終わります。金が人間の命を弄ぶゲームの駒にしてしまう、その非情さが際立つ一編です。
社会の片隅から見つめる視線
石田さんの作品には、社会の中心から外れた人々への温かい視線を感じることが多いですが、本作ではその視線がより冷徹で、鋭くなっているように感じます。「ラストハウス」では、事故で仕事を失い、ホームレスとなった聡が主人公です。上野公園のブルーシート村を「最後の家」と定めた彼の日常が、淡々と描かれます。
そこには、私たちが想像するような悲惨さだけではなく、彼らなりのコミュニティやルールが存在します。聡は、自分の血液を売って日銭を稼ぐミチヨという女性と出会い、静かな共感を寄せます。劇的な展開はなく、ただ社会の底辺で生き続けるしかない人間の姿が、静かに肯定されていく。このリアルな描写は、私たちの日常がいかに脆い土台の上にあるかを気づかせてくれます。
また、「ラストジョブ」で扱われる「障害者の性」というテーマも、社会が普段見ようとしない現実に光を当てています。著者は、彼らを単なる「弱者」として描くのではなく、一人の人間として、その欲望や現実をありのままに描き出そうとしています。この姿勢こそが、物語に深みと説得力を与えているのだと感じます。
救いのない世界と『IWGP』との決別
この『LAST』という作品を語る上で、代表作である『池袋ウエストゲートパーク』シリーズとの比較は避けられません。IWGPでは、主人公のマコトが様々なトラブルを解決し、物語は一種のカタルシスと共に幕を閉じます。そこには、困難な状況を打開してくれるヒーローの存在がありました。
しかし、『LAST』の世界に、マコトのようなヒーローは存在しません。問題は解決されず、登場人物は破滅するか、過酷な現実を生き続けることを強いられるだけです。唯一の例外と言える「ラストドロー」の出村でさえ、彼が手にしたのは束の間の自由であり、その先に平穏な生活が待っている保証はどこにもありません。
なぜ直木賞を受賞した直後に、石田さんはこれほどまでに救いのない物語を書いたのでしょうか。それは、IWGPの光が届かない、社会の構造的な闇を直視しようとする、作家としての強い意志の表れだったのではないでしょうか。『LAST』は、ヒーロー不在の現実世界を映し出す、社会派のノワール小説として読むことができるのです。IWGPの明るさとは正反対の、この徹底した暗さこそが、本作の最大の魅力であり、メッセージなのだと思います。
「選択」という最後の主体性
この物語集を貫くもう一つの重要なテーマは、「選択」です。登場人物たちは、物語のほとんどで、社会や経済という大きな力に翻弄される無力な存在です。しかし、崖っぷちに立たされ、すべての逃げ道を失ったとき、彼らは最後の最後に、自らの意志で「終わり方」を選び取ります。
「ラストライド」の修二が家族のために死を選ぶこと。「ラストジョブ」の真弓が尊厳と引き換えに金を得る仕事を選ぶこと。「ラストバトル」の都築が生死を賭けた引き金を引くこと。その選択は、社会的な正しさや合理性とは無縁かもしれません。しかし、その瞬間に、彼らはただ流されるだけの客体から、自らの運命を決定する主体へと変わるのです。
この「ラスト」の一瞬に、彼らの人生が凝縮され、悲劇的でありながらも強烈な光を放ちます。著者は、この極限状態で見せる人間の最後の抵抗、最後の意志の発露にこそ、生の根源的な何かを見出しているのではないでしょうか。
忘れがたい二つの物語
最後に、特に私の心に深く刻まれた二つの物語について触れたいと思います。それは「ラストコール」と「ラストシュート」です。これらは金銭問題が直接の原因ではないものの、現代社会の心の闇をえぐり出す、強烈な作品でした。
「ラストコール」の主人公は、孤独なサラリーマンです。テレフォンクラブで知り合ったメグミという女性との電話だけが、彼の日々の癒やしでした。しかし、初めてテレビ電話で顔を合わせた彼女は、自らの壮絶な過去を告白した後、彼の目の前で自ら命を絶ってしまいます。バーチャルな繋がりがもたらした、あまりにもリアルで残酷な結末。手の届かない場所で起きた死を前にした主人公の無力感は、読んでいるこちらの胸にも突き刺さります。
そして、本作で最も物議を醸すであろう問題作が「ラストシュート」です。語り手は、エリート心臓外科医の奈良原。しかし彼には、少年に対して性的な欲望を抱くという、誰にも言えない秘密がありました。彼は自らの立場を利用し、手術をした少年を新たな標的に定めます。加害者の視点から、その倒錯した心理が克明に描かれていく様は、まさしく吐き気を催すほどの不快感を伴います。
しかし、この物語は単に胸の悪さだけで終わりません。最終的に、彼の歪んだ欲望は、ターゲットであった少年自身の、痛烈で鮮やかな逆襲によって完膚なきまでに打ち砕かれるのです。加害者が完全な破滅を迎えるこの結末は、他の物語にはない、ある種の裁きが下される瞬間でもあります。人間の最も暗い部分を直視させながらも、そこに一条の光を当てる、忘れがたい一編でした。
まとめ
石田衣良さんの『LAST』は、2000年代初頭の日本社会が抱えていた、経済格差や貧困、そして人間の孤立といった問題を、七つの物語を通して鋭く描き出した作品です。どの物語も救いがなく、読後には重たい感情が残ります。しかし、それはこの作品が、目を背けたくなるような現実から逃げずに、まっすぐに向き合っている証拠でもあります。
本作で描かれる世界は、刊行から時間が経った今も、決して過去のものではありません。むしろ、格差が固定化し、「自己責任」という言葉が安易に使われる現代において、その切実さは増しているとさえ言えるでしょう。私たちは、この物語の登場人物たちと地続きの世界に生きているのです。
この本は、社会から見捨てられた人間が、その生の最後に何を選び取るのかを、私たちに容赦なく問いかけてきます。その問いは、私たちが生きるこの社会のあり方、そして「生きること」や「死ぬこと」の意味を、根源から見つめ直すきっかけを与えてくれます。
絶望的な物語の中に、それでも人間の尊厳や、一瞬の生の輝きを描ききった『LAST』。石田衣良さんの作品の中でも、ひときわ暗く、しかしだからこそ強い光を放つ傑作だと思います。手放しでおすすめできる作品ではありませんが、心してページをめくる価値のある一冊です。






















































