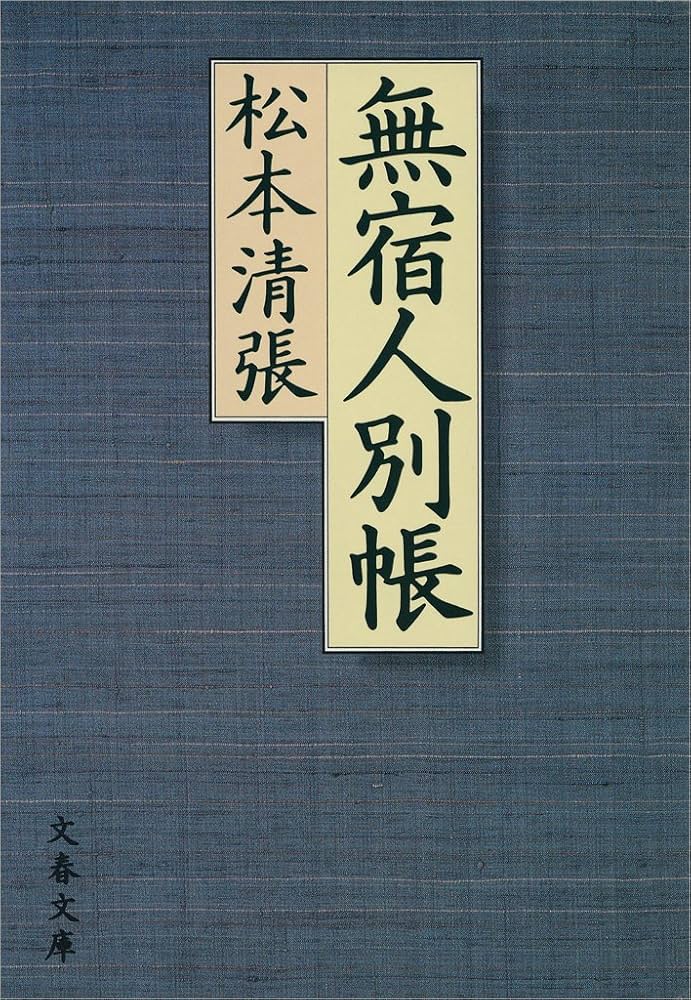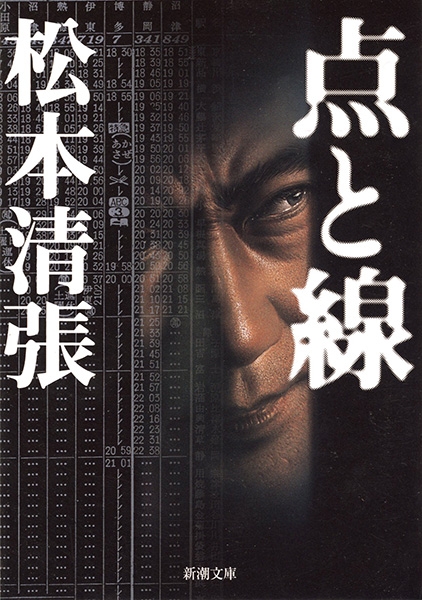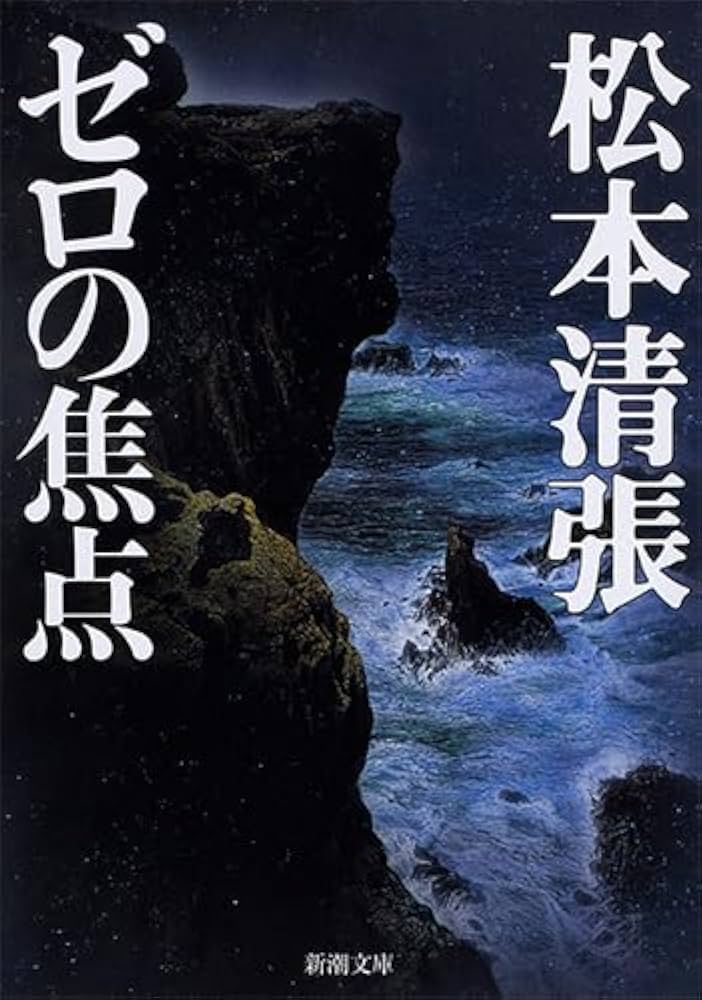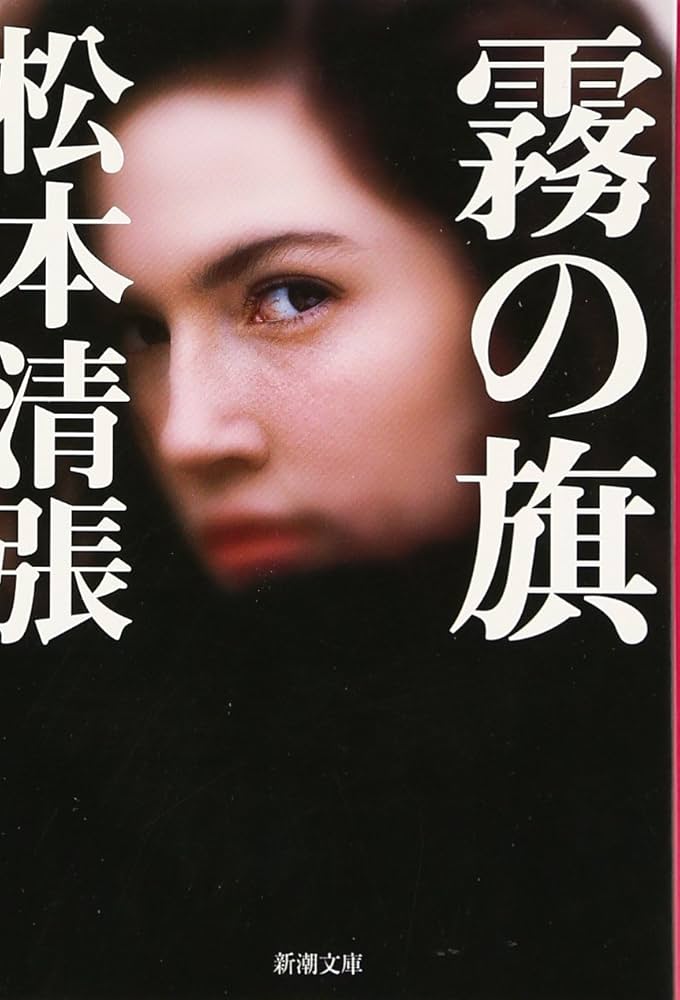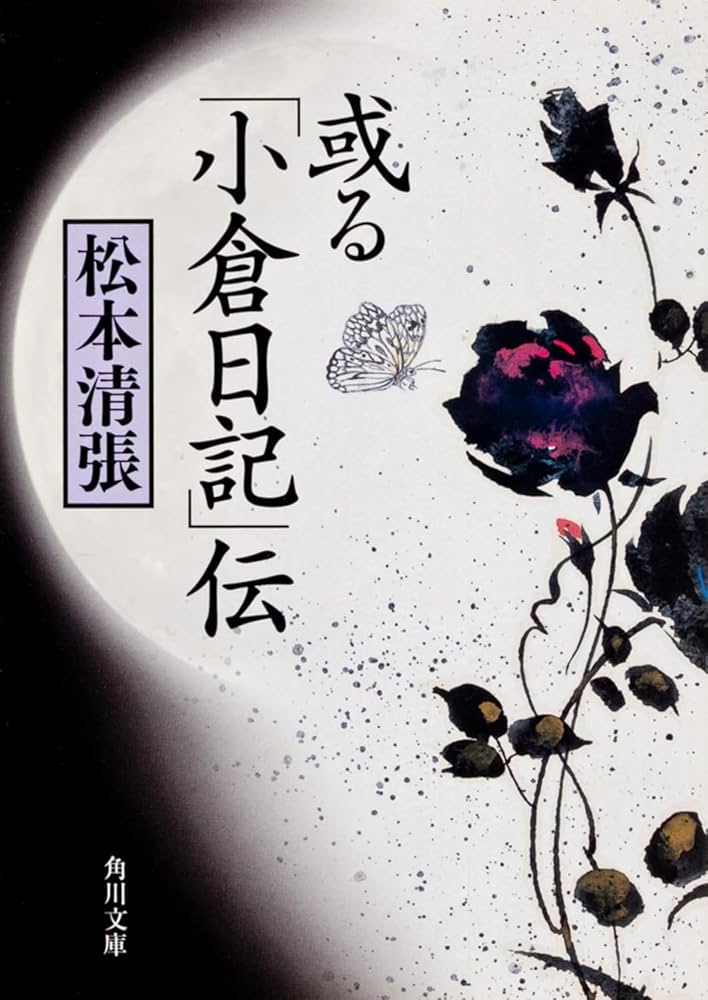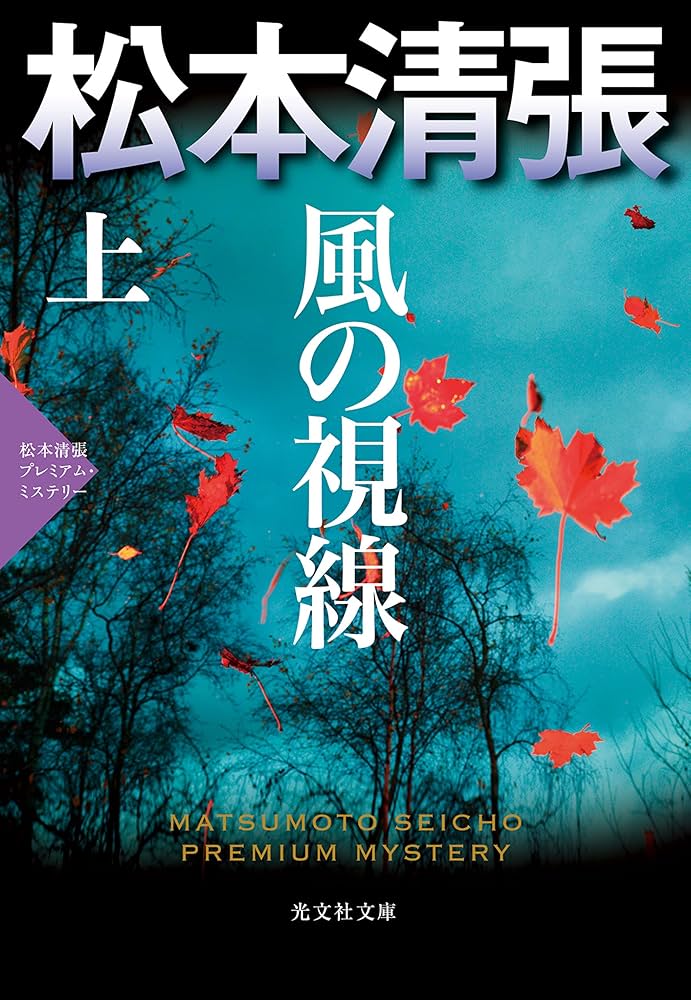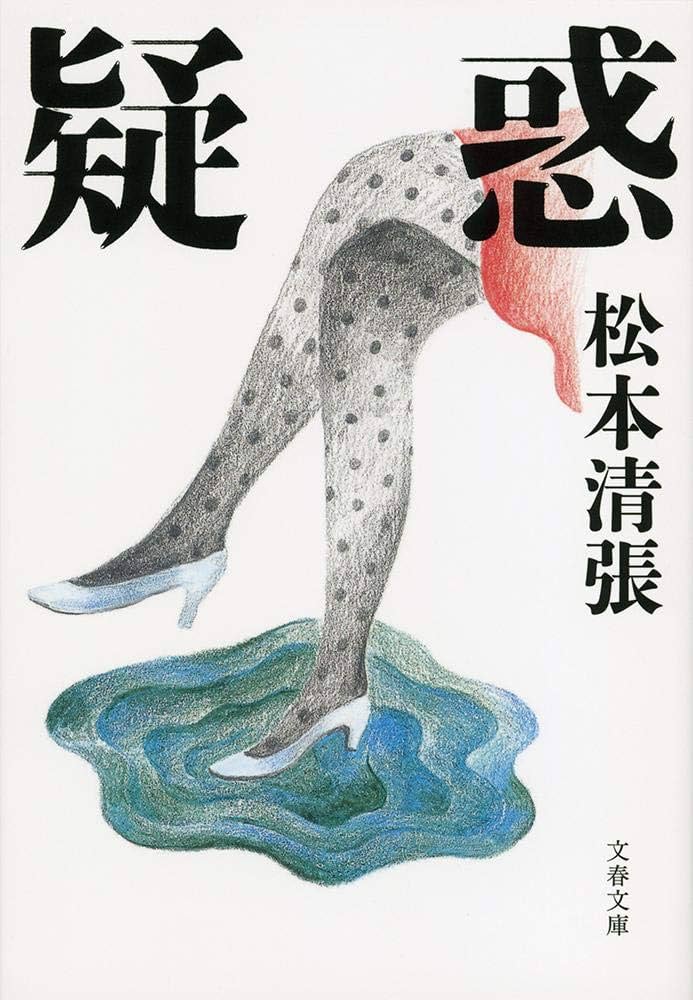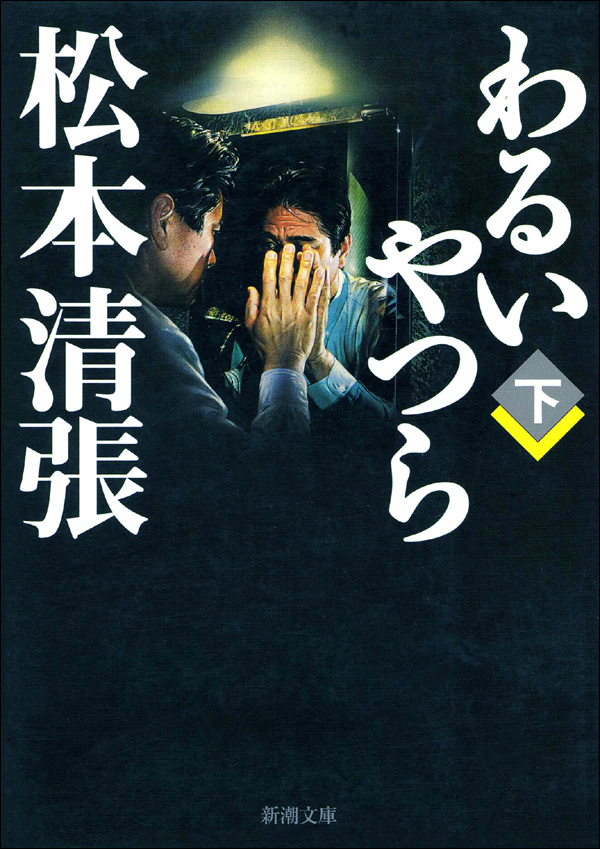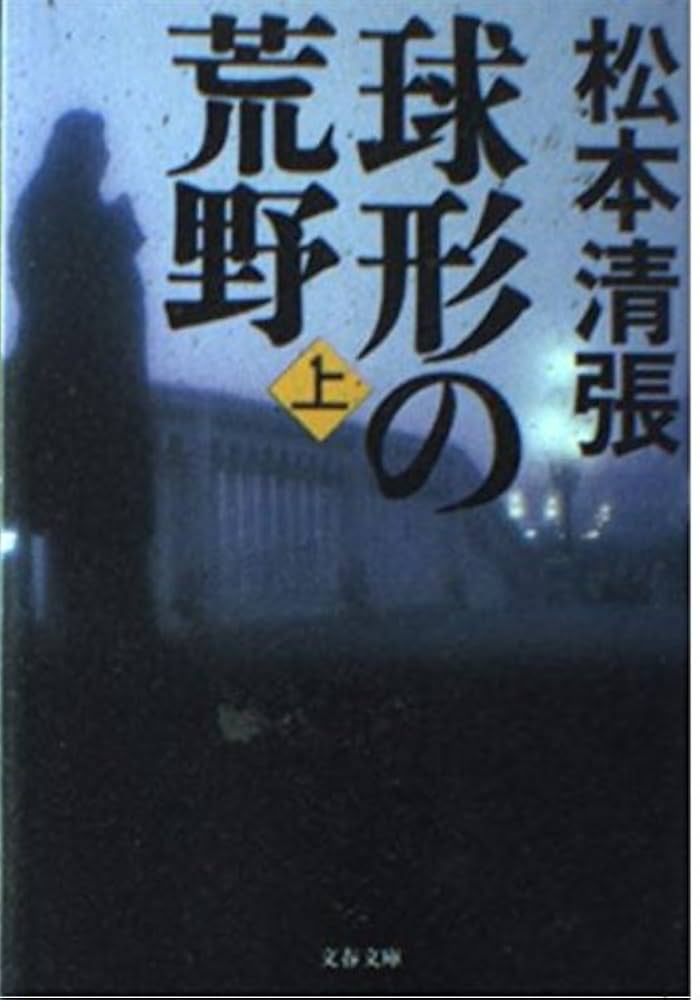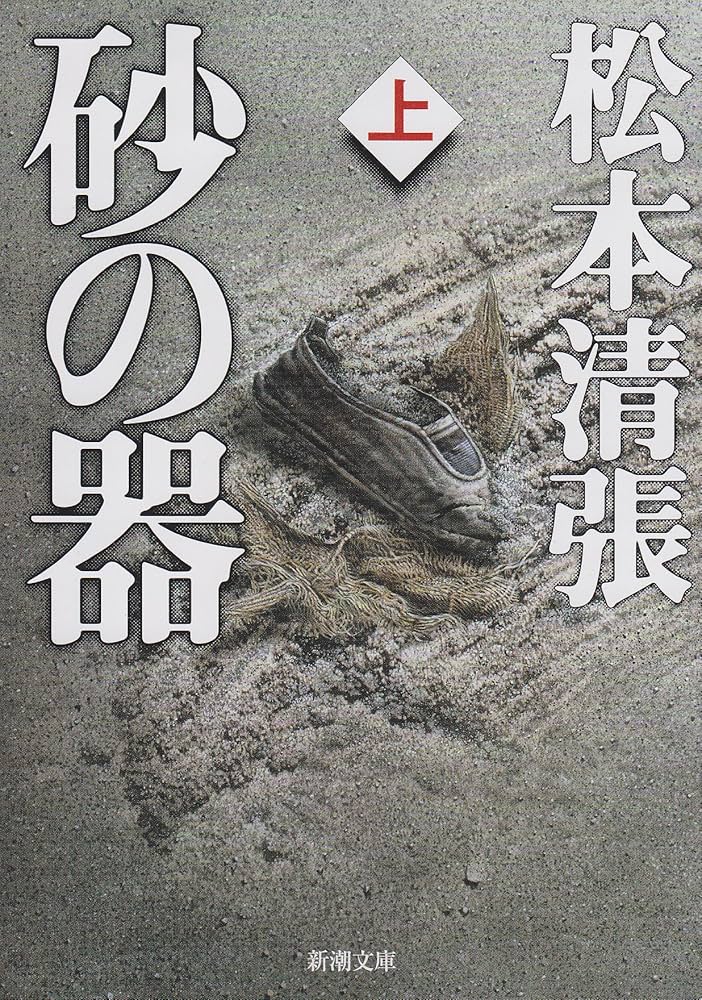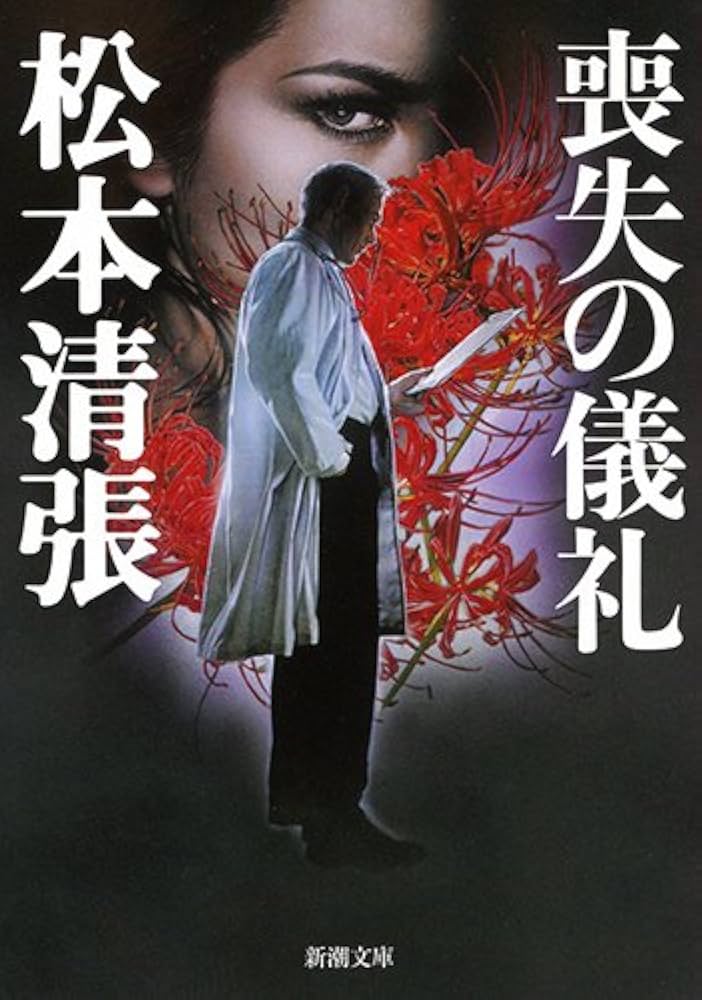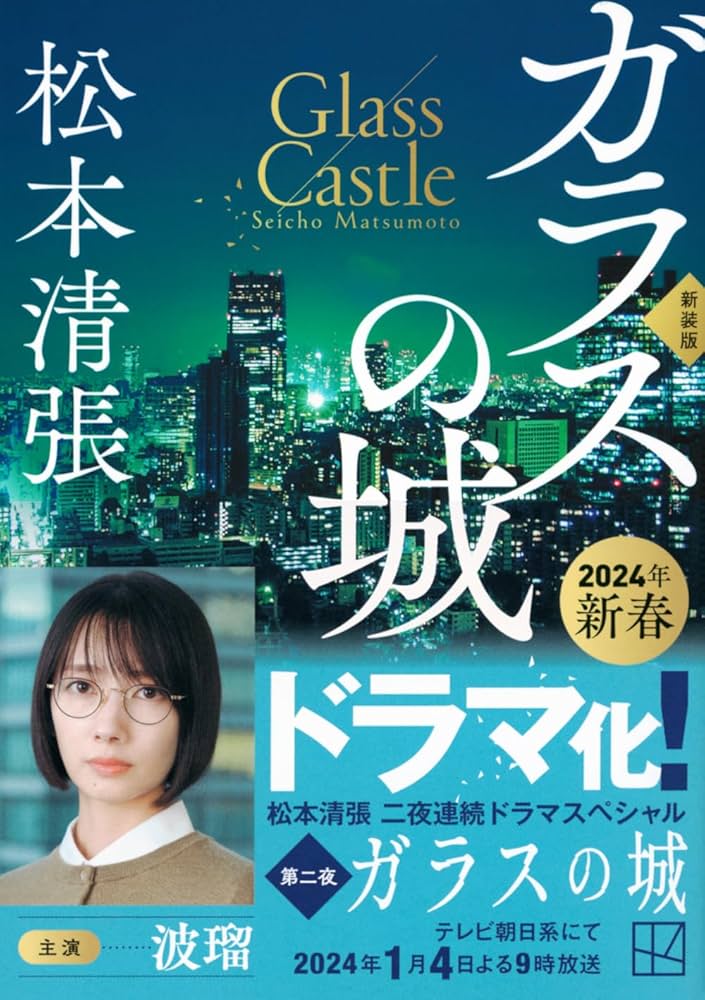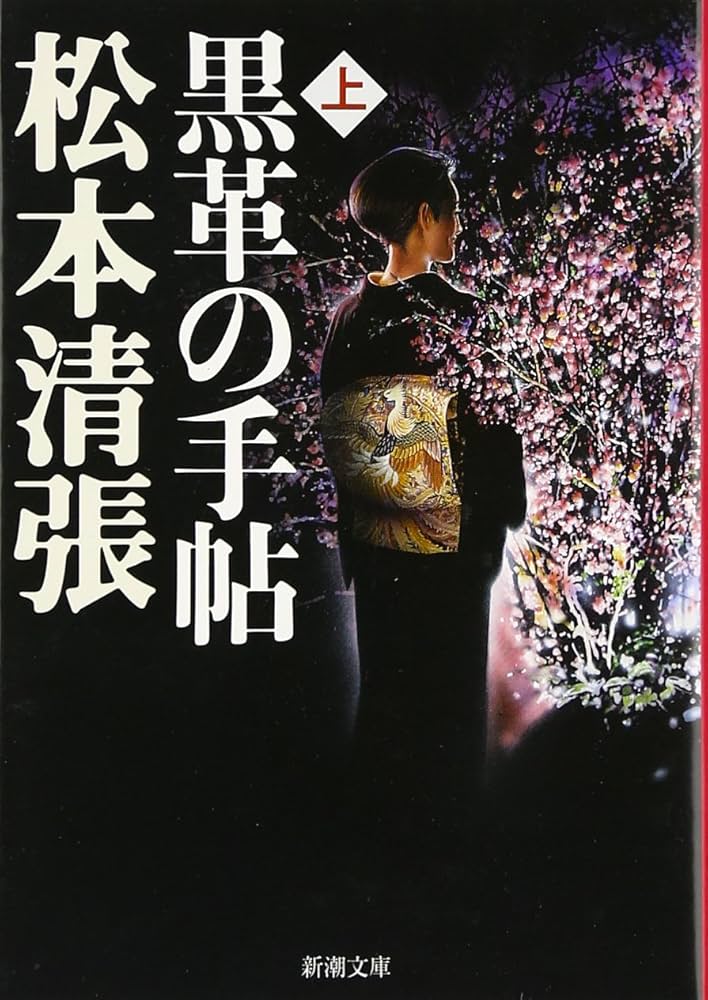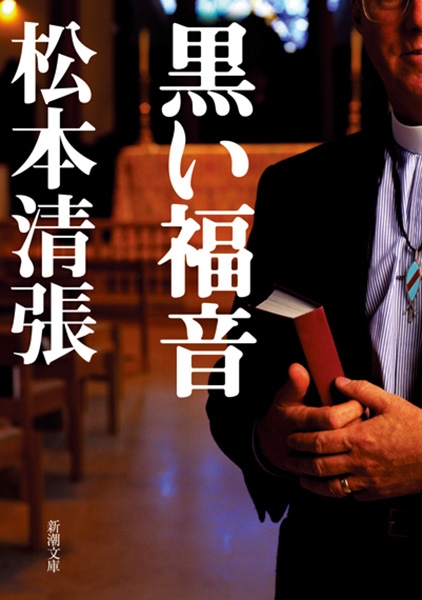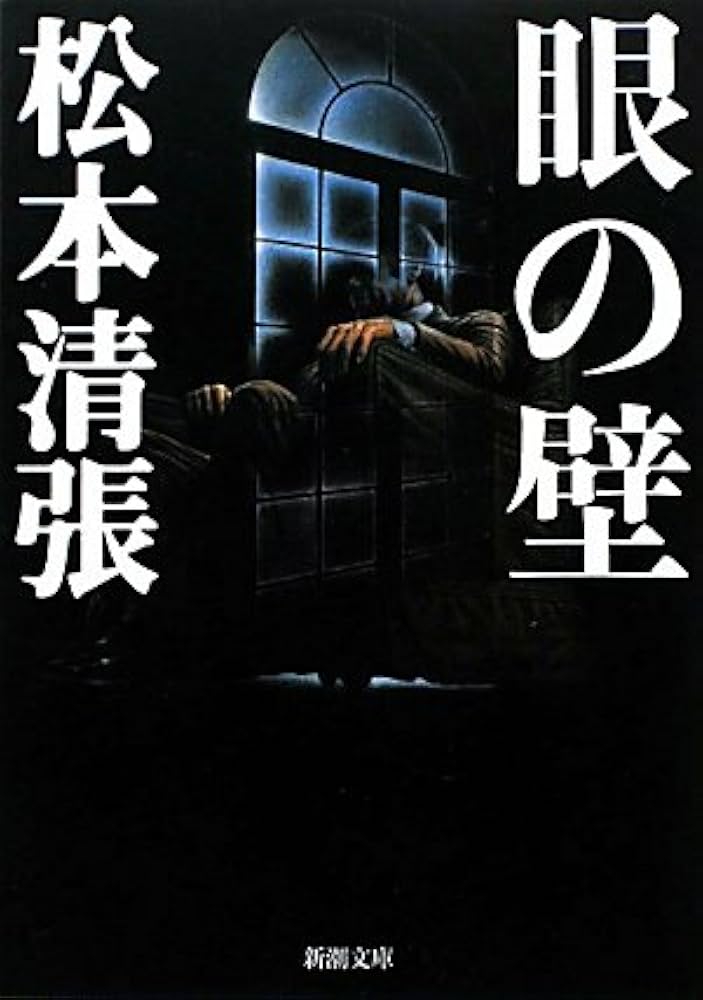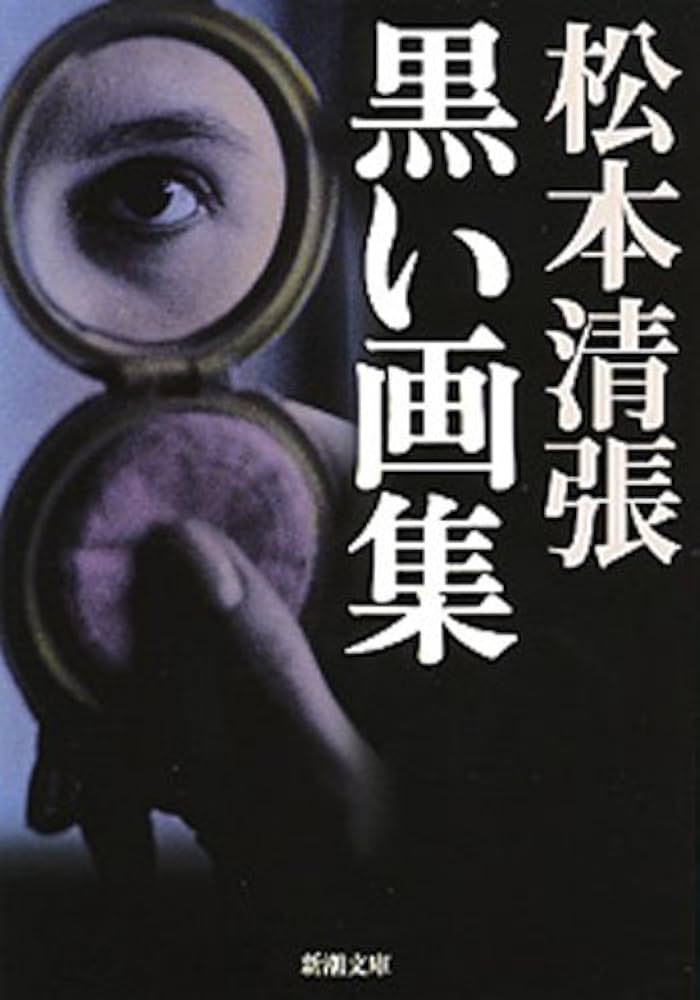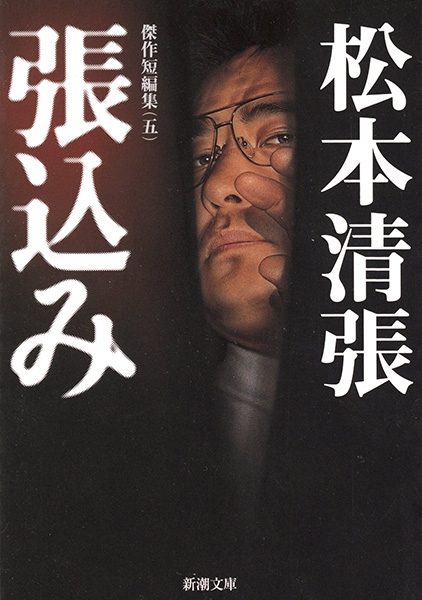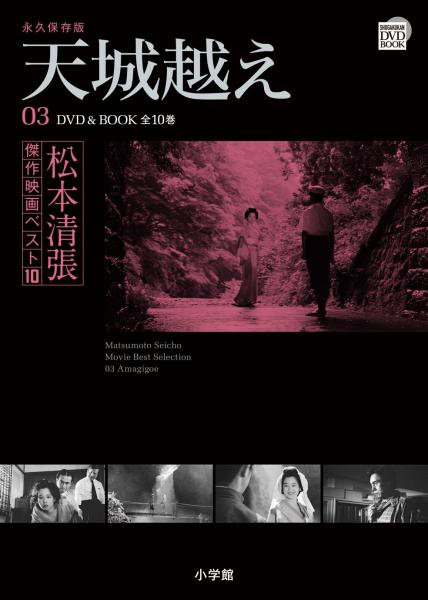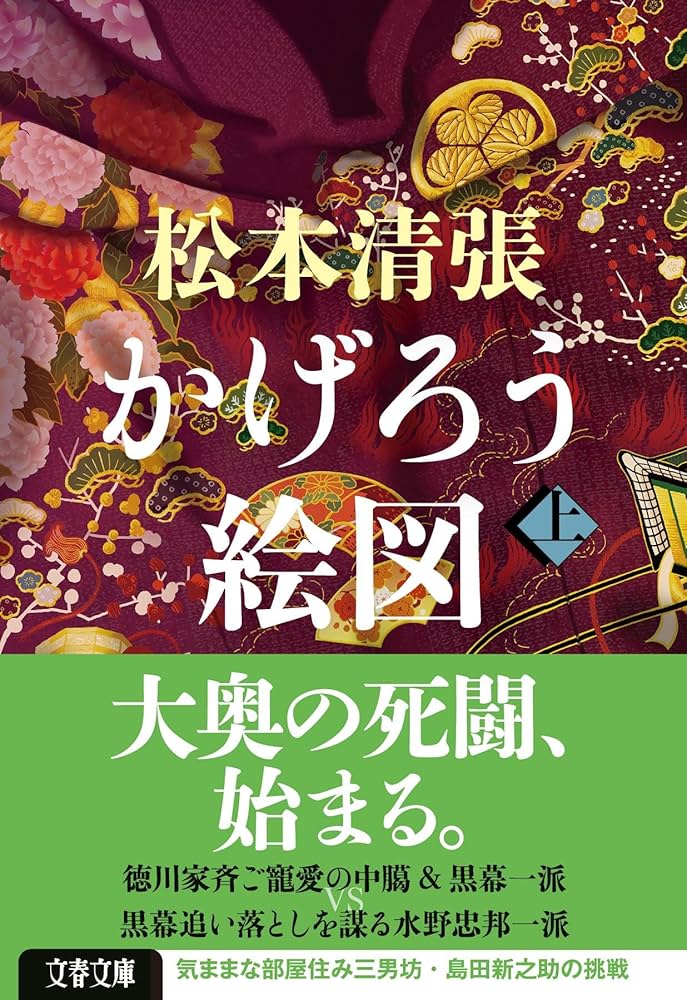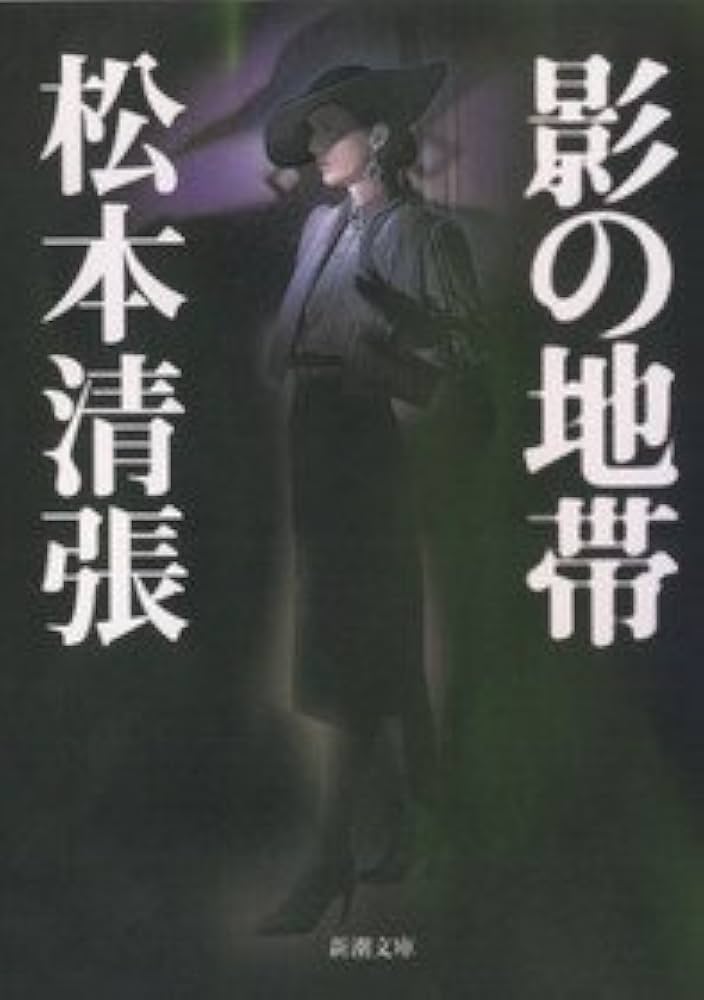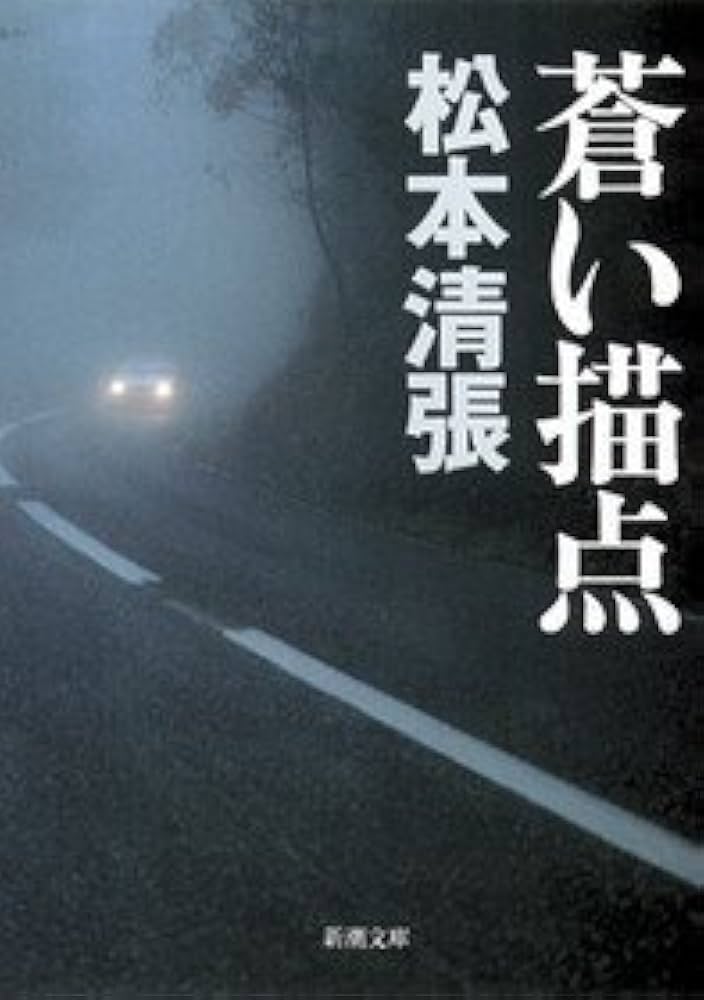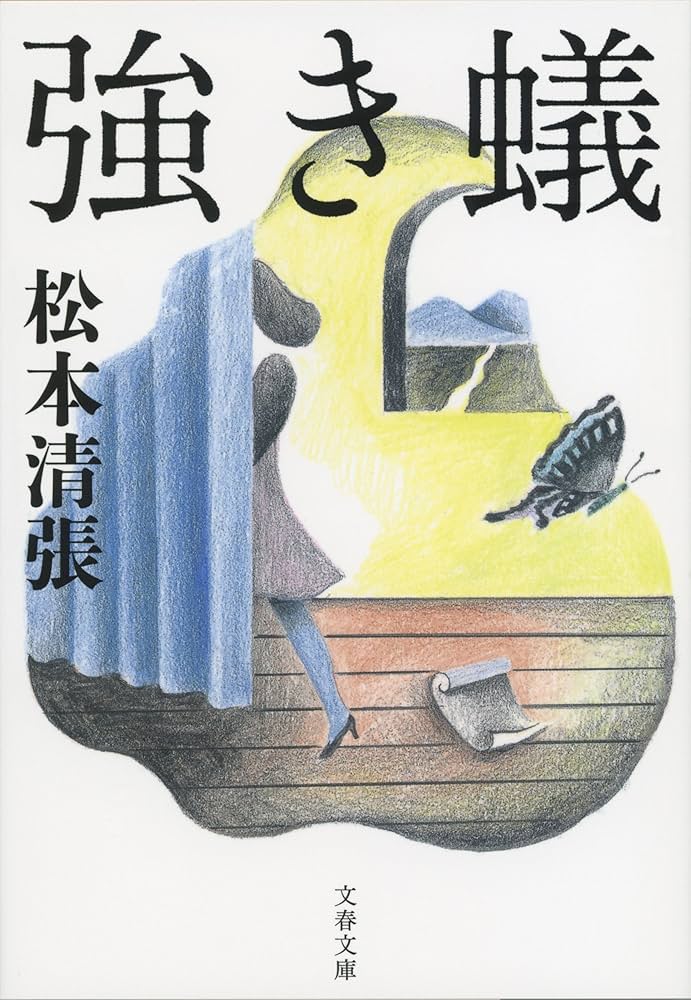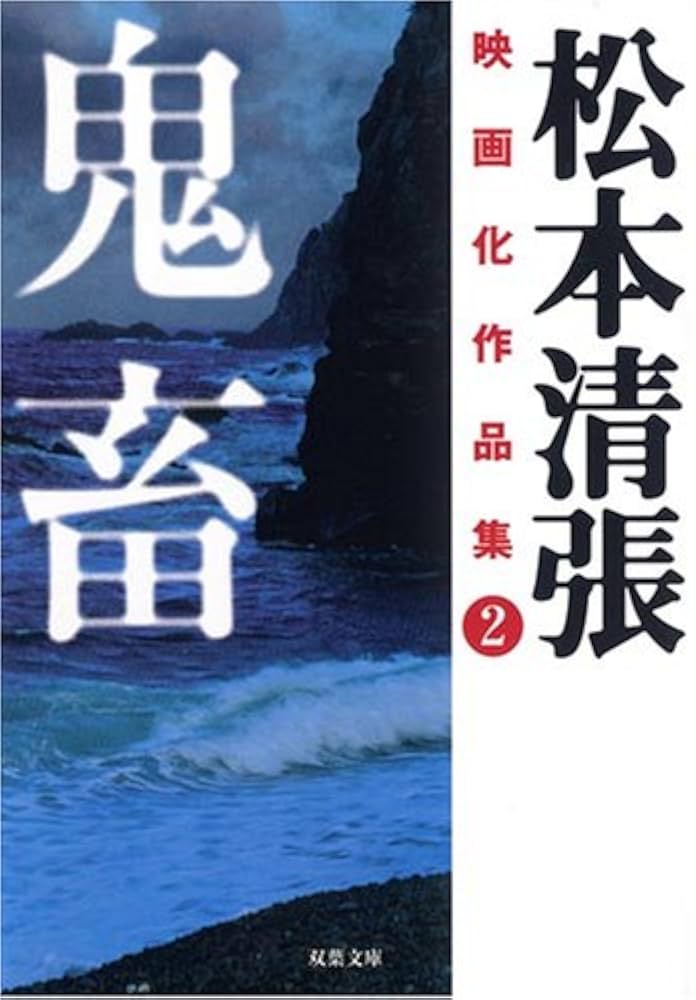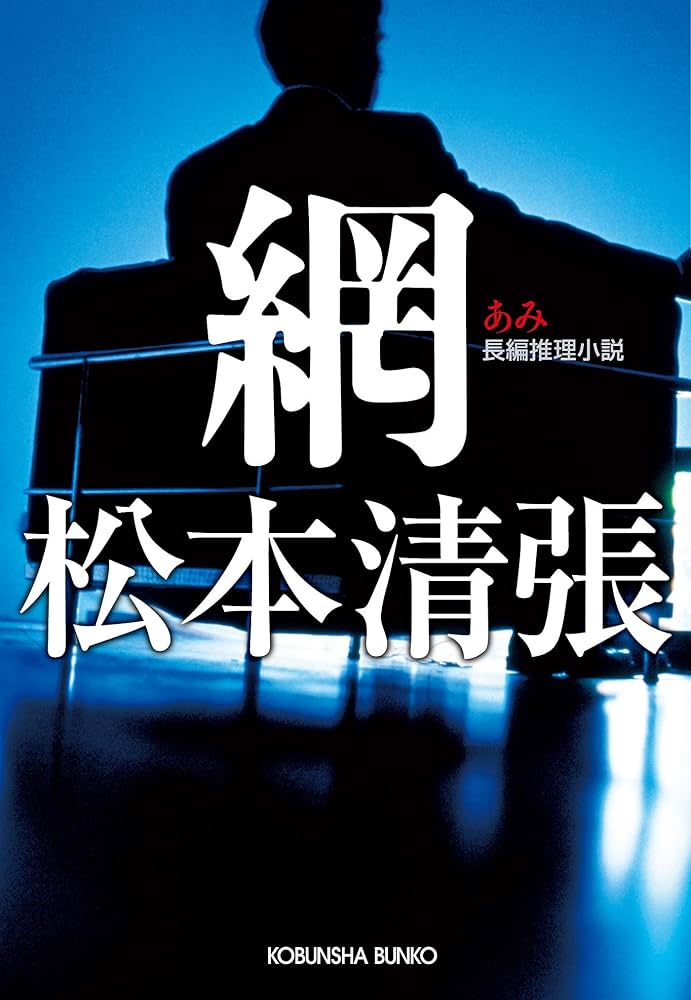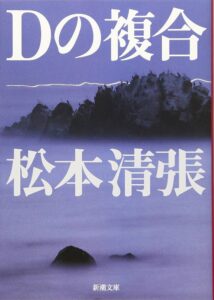 小説「Dの複合」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「Dの複合」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
松本清張作品の中でも、その壮大で緻密な構成から異色の傑作と名高い「Dの複合」。本作は、一人の売れない作家が、ひょんなことから奇妙な紀行文の連載を引き受けたことから、巨大な復讐計画の渦中へと巻き込まれていく様を描いた長編ミステリーです。
物語は、旅情あふれる紀行文の体裁をとりながら、その裏で静かに、そして着実に進行していく陰謀の気配が、読者の心を掴んで離しません。旅先で起こる不可解な出来事、民俗学的な伝説に隠された暗号、そして登場人物たちの謎めいた言動。一つ一つのピースが、やがて驚愕の真相へと繋がっていきます。
この記事では、そんな「Dの複合」の物語の概要から、事件の核心に迫る重大なネタバレまで、深く掘り下げていきます。なぜこの物語が多くの読者を惹きつけるのか、その魅力と悲劇性に満ちた結末について、私の想いを込めて語らせていただきます。
「Dの複合」のあらすじ
あまり売れない作家である伊瀬忠隆のもとに、天地社という小さな出版社から「僻地に伝説をさぐる旅」という紀行文の連載依頼が舞い込みます。担当編集者を名乗る好青年・浜中と共に、伊瀬は浦島太郎伝説が残る丹後半島へと旅立ちます。旅は一見、和やかに進むかのように思われました。
しかし、その旅先で奇妙な出来事が頻発します。温泉地で「死体が埋まっている」という投書による警察の捜索騒ぎに遭遇し、現場からは白骨ではなく「第二海竜丸」と書かれた木片が見つかるだけ。その後も、旅の行程には不可解な偶然がつきまといます。伊瀬は次第に、この旅そのものが、誰かによって巧妙に仕組まれたものであることに気づき始めます。
そんな中、伊瀬の連載の愛読者を名乗る坂口みま子という謎の女性が現れます。彼女は、旅の行程が東経135度線に沿って計画されているという驚くべき事実を指摘します。伊瀬がその意味を掴めぬうちに、みま子は熱海のホテルで死体となって発見されてしまいます。
ついに現実の殺人事件へと発展し、伊瀬は否応なく事件の当事者として巻き込まれていきます。連載は一方的に打ち切られ、担当編集長の武田も謎の死を遂げ、頼りの浜中は姿を消してしまいます。孤立無援となった伊瀬は、自ら真相を探るべく動き出しますが、それは巨大な陰謀のほんの入り口に過ぎませんでした。
「Dの複合」の長文感想(ネタバレあり)
「Dの複合」を読み終えたとき、心に残るのは、そのあまりにも壮大で緻密な計画への感嘆と、復讐という行為がもたらす深い虚しさ、そしてどうしようもない悲しみです。ここからは物語の核心に触れるネタバレを含みますので、ご注意ください。
物語の主人公、作家の伊瀬忠隆は、私たち読者の視点を代弁する存在です。彼は怪奇譚や歴史の周縁を好んで書くものの、決して成功しているとは言えない。そんな彼の前に現れたのが、天地社の浜中という青年でした。知的で誠実な浜中に、伊瀬が好感を抱くのは自然な流れです。
「僻地に伝説をさぐる旅」という企画も、伊瀬の専門性を考えれば、またとない魅力的な仕事に思えました。しかし、この依頼こそが、壮大な復讐劇の始まりであり、伊瀬自身がその計画の最も重要な「駒」として選ばれた瞬間だったのです。伊瀬の作家としての立場、そして比較的無名であるがゆえの扱いやすさが、計画実行者にとっては好都合だったわけです。
伊瀬と浜中の旅は、丹後半島の浦島太郎伝説から始まります。昭和40年代の旅情、風光明媚な景色の描写は、一見すると格調高い紀行文のようです。しかし、木津温泉での一件が、物語の空気を一変させます。「人間の死体が埋まっている」という投書。この騒動は、後に判明しますが、世間の注意を引き、ある人物の記憶を呼び覚ますための壮大な「演出」でした。
そして、現場に残された「第二海竜丸」の木片。これこそが、この物語のすべての元凶である天地社の社長・奈良林にだけ意味がわかる、過去の罪を告発する挑戦状だったのです。この時点では、伊瀬も読者もその意味を知る由もありません。この巧妙な情報提示が、本作の大きな魅力の一つだと感じます。
さらに巧みなのは、旅のテーマそのものが暗号となっている点です。故郷を追われ、帰るべき時を失った浦島太郎。羽衣を奪われ、天に帰れなくなった天女。これらの伝説が持つ「淹留(えんりゅう)」、つまり強制的に異郷に留め置かれるという側面が、浜中の父親が強いられた運命を暗示している。民俗学の知識を復讐の道具として利用する着想には、ただただ驚嘆するばかりです。
物語を大きく動かすのが、坂口みま子の登場です。彼女は「計算狂」という異様な個性を持つ女性で、伊瀬の連載記事から、旅程が東経135度線という地理的な法則に縛られていることを見抜きます。浜中の計画は、奈良林という特定の相手にだけ届くはずの、閉ざされた暗号でした。しかし、全くの部外者であるみま子が、その秘密の一端を解読してしまったのです。
彼女の存在は、浜中の計画における最大の誤算でした。おそらく彼女は、この秘密をネタに奈良林を強請ろうとしたのでしょう。その結果、彼女は殺害されてしまいます。この最初の殺人が、浜中の復讐計画を、彼の意図を超えた血塗られた悲劇へと変質させてしまったのです。ここから物語は、後戻りできない領域へと突き進んでいきます。
みま子殺害事件の後、天地社内部にも激震が走ります。心理的に追い詰められた奈良林は、雑誌の責任者である武田編集長を裏切り者と誤認し、殺害してしまいます。浜中が仕掛けた知的な心理戦に対し、奈良林は「殺害」という最も原始的な方法で応じたのです。何も知らなかった武田の死は、この物語における最も痛ましい悲劇の一つであり、私の心にも重くのしかかりました。
そして、物語の終盤。姿を消した浜中から伊瀬のもとに届けられた長い手紙によって、すべての謎が明らかになります。この手紙の内容こそが、この物語のあらすじであり、そして戦慄すべきネタバレのすべてです。事件の根源は、戦時中の昭和16年、奈良林が犯した密輸と殺人、そしてその罪を浜中の父親一人になすりつけたことにありました。
無実の罪で20年もの獄中生活を強いられた父の無念を晴らすため、浜中はその人生のすべてを復讐に捧げたのです。伊瀬という作家を「道具」として使い、紀行文という体裁で私的な告発を続け、地理と民俗学を「暗号」として奈良林を精神的に追い詰める。その計画の全貌は、まさに悪魔的としか言いようがありません。
浜中には協力者がいました。みま子殺害の容疑者とされた二宮、伊瀬を惑わせた藤村。彼らはおそらく、同じく奈良林に人生を狂わされた「海竜丸」乗組員の遺児たちだったのでしょう。「みんなグルだった」という事実は、この復讐がいかに根深く、多くの人間の人生を巻き込んだものであるかを物語っています。
ここで、タイトルの「Dの複合」の意味が重く響いてきます。この「D」が示すもの。それは第一に、浜中の父が強いられた不当な「Detention(抑留)」です。しかし、それだけではありません。計画全体を覆う「Deception(欺瞞)」、被害者たちの「Despair(絶望)」、そして奈良林が迎える「Downfall(破滅)」。これらの複数の意味が重なり合った「複合体(Complex)」こそが、この物語の核心なのです。
浜中の計画は、奈良林の社会的破滅という目的を達成しました。しかし、その代償はあまりにも大きかった。計画の過程で、坂口みま子や武田編集長という罪のない人々が命を落としました。浜中自身もまた、複数の死に関与したことで、もはや法の裁きから逃れることはできません。
この結末は、本当に悲しいものだと感じます。復讐は果たされた。しかし、そこに勝利の喜びはなく、ただ虚しさと静寂が広がっているだけです。伊瀬は、すべての真相を知った後、浜中を探すために新聞の尋ね人欄を使おうかと思案します。公的なメディアを利用して始まった私的な復讐が、最後は公的なメディアを通じた個人的な呼びかけで終わろうとする。この皮肉な対比が、物語の悲劇性をより一層際立たせています。
「Dの複合」は、単なる謎解きミステリーではありません。これは、正義とは何か、罪と罰とは何かを問いかける、重厚な人間ドラマです。壮大な計画の果てに残された、一つのささやかで絶望的な願い。その余韻が、読後も長く心に残り続ける、忘れがたい物語でした。この感想が、これから本作を手に取る方の、あるいは再読する方の心に届けば幸いです。
まとめ
松本清張の「Dの複合」は、売れない作家・伊瀬忠隆が、担当編集者・浜中と始めた紀行文の連載をきっかけに、壮大な復讐計画に巻き込まれていく物語です。旅先で起こる不可解な事件の数々は、すべてがある人物への告発のために仕組まれたものでした。
物語の核心には、戦時中に犯された罪と、無実の罪で人生を奪われた男、そしてその無念を晴らすために人生のすべてを捧げた息子の存在があります。地理や民俗学の知識を駆使した緻密な計画の全貌が明らかになる終盤は圧巻ですが、同時にネタバレを知ると、その結末の悲しさに胸が締め付けられます。
復讐という行為が、いかに多くの人間を不幸にし、関わったすべての者を破滅へと導くか。この物語は、その虚しさと悲劇性を克明に描き出しています。謎解きの面白さはもちろんのこと、人間の業の深さを描いた重厚なドラマとして、心に深く刻まれる作品です。
ミステリーファンだけでなく、人間の運命や宿命といったテーマに興味がある方にも、ぜひ読んでいただきたい一冊です。読後、きっと深い余韻とともに、物語の世界について考え込んでしまうことでしょう。