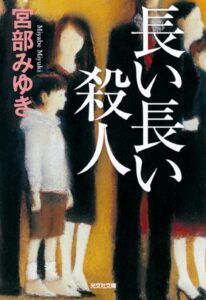 小説「長い長い殺人」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの作品の中でも、とりわけユニークな設定で知られる一冊ではないでしょうか。事件に関わる人々の「財布」が語り手となる、という大胆な手法が用いられています。
小説「長い長い殺人」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの作品の中でも、とりわけユニークな設定で知られる一冊ではないでしょうか。事件に関わる人々の「財布」が語り手となる、という大胆な手法が用いられています。
この物語は、単なるミステリーの枠を超えて、人間の内面や社会のあり様を鋭く描き出しているように感じます。財布という、持ち主の最も近くにありながら、決して声を発することのない存在。彼らの視点から紡がれる物語は、時に切なく、時にやるせなく、私たちの心に深く響くものがあります。
この記事では、まず「長い長い殺人」の物語の筋道、事件の核心部分に触れながら詳しくご紹介します。その後、私がこの作品を読んで感じたこと、考えたことを、結末の内容にも踏み込みながら、じっくりと述べていきたいと思います。少し長いお話になるかもしれませんが、お付き合いいただければ幸いです。
小説「長い長い殺人」のあらすじ
物語は、ある夜、会社員の森元隆一が無残な遺体で発見されるところから始まります。当初はひき逃げ事件として捜査が進められますが、担当刑事は被害者の妻・森元法子のどこか不自然な態度に疑念を抱きます。さらに、隆一には多額の生命保険がかけられていたことが判明。しかし、法子には鉄壁のアリバイが存在し、捜査は難航します。
時を同じくして、別の場所で塚田早苗という女性が新婚旅行から帰国直後に不審な死を遂げます。早苗は生前、夫である塚田和彦の素行に不安を感じ、私立探偵の河野に調査を依頼していました。和彦はやり手のレストラン経営者であり、森元法子とは愛人関係にありました。早苗の死もまた、事故か他殺か判然としないまま、和彦にはアリバイがありました。
これらの事件の裏で糸を引いていたのは、和彦と法子でした。彼らはそれぞれの配偶者にかけられた保険金を手に入れるため、ある人物を利用して殺害を実行させていたのです。その人物とは、通り魔的な犯行を繰り返していた無職の男、三木一也。和彦は偶然にも三木の弱みを握り、彼を意のままに操って隆一と早苗の殺害を指示したのでした。
当初は容疑者として世間の注目を浴びた法子と和彦でしたが、決定的な証拠はなく、次第にマスコミは彼らを悲劇の人物、あるいは時代の寵児としてもてはやすようになります。一方、早苗から依頼を受けていた探偵の河野は、独自の調査を続け、事件の真相に迫っていきます。そして、早苗の甥である小学生・小宮雅樹もまた、叔母の死と和彦に対して強い疑念を抱き続けていました。最終的に、河野と警察の捜査により三木が逮捕され、彼の財布から発見された隆一のネクタイピンと早苗の結婚指輪が決定的な証拠となり、和彦と法子の保険金殺人の企みは完全に露見することになります。
小説「長い長い殺人」の長文感想(ネタバレあり)
この「長い長い殺人」という作品を読み終えて、まず心に残ったのは、その語りの仕掛けの見事さでした。事件に関わる人々の「財布」が、それぞれの持ち主の視点から、あるいは持ち主を見つめる視点から物語を紡いでいく。この設定は、単に奇抜というだけでなく、物語に独特の深みと切実さを与えているように感じます。財布は、持ち主のお金、つまり生活や欲望の象徴を内包し、常にその人の傍らにあります。嬉しい時も、悲しい時も、そして、誰にも言えない秘密を抱えている時でさえも。しかし、財布は物言わぬ存在です。どんなに重大な事実を知っていても、どんなに持ち主の身を案じていても、自ら行動を起こすことはできません。
この「見ていることしかできない」もどかしさは、私たち読者の立ち位置とも重なります。私たちは、財布たちの語りを通して事件の全貌や登場人物たちの心情を知り得ますが、物語に介入することはできません。ただ、事の成り行きを見守るしかないのです。特に、塚田和彦の妻・早苗の危険を察知しながらも、大人たちに信じてもらえず、何もできなかった甥の雅樹少年のエピソードは、財布の視点と少年の無力感が重なり合い、読んでいて胸が締め付けられるようでした。彼の純粋な叔母への思いと、迫りくる脅威を前にしたときのやるせなさが、ひしひしと伝わってきます。宮部さんの描く少年像は、いつもどうしてこうも私たちの心を掴むのでしょうか。彼のスカイブルーの財布が語る、切ない思いが忘れられません。
物語の中心となる保険金殺人事件は、森元法子と塚田和彦という、自己愛と欲望にまみれた男女によって計画されます。彼らは、愛人関係にありながら、それぞれの配偶者を邪魔者として排除し、多額の保険金を手に入れようと画策します。その冷酷さ、計画性には寒気を覚えますが、さらに恐ろしいのは、彼らが事件後、マスコミを利用して世間の同情を集め、あまつさえ時代の寵児のようになっていく様です。ルックスが良く話術に長けた二人は、ワイドショーや雑誌の格好のネタとなり、悲劇のヒロイン、有能な経営者として祭り上げられます。この展開は、宮部さんの後の代表作「模倣犯」にも通じるテーマですが、「長い長い殺人」では、容疑者自身がメディアのスターとなるという、より倒錯した状況が描かれています。現実にはありえないと思いたいところですが、昨今のメディアの状況を見ていると、あながち完全なフィクションとも言い切れない怖さを感じさせます。
実行犯として利用される三木一也もまた、歪んだ自己顕示欲を持つ人物です。一流大学を出ながら定職に就かず、通り魔的な犯罪で鬱屈した感情を満たそうとする。彼が和彦に弱みを握られ、殺人に手を染めていく過程は、転落の物語としても読むことができます。そして、法子と和彦ばかりが注目される状況に不満を募らせていく心理描写も、人間の暗い一面を巧みに描き出しています。
ミステリーとして見た場合、真犯人が誰かという点については、物語の比較的早い段階で読者には示唆されます。むしろ、焦点は「どのようにして彼らの犯行が暴かれるのか」「財布たちの視点から何が見えるのか」という点にあると言えるでしょう。合計10個もの財布が登場し、それぞれの持ち主の人生や事件との関わりが語られますが、中には、物語の本筋とは少し距離のあるエピソードも含まれています。例えば、若手刑事とその恋人の話などは、もう少し事件に絡んでくるのかと期待してしまった部分もありました。しかし、全ての登場人物が密接に事件に関わっているわけではない、というリアリティも、この物語の一面なのかもしれません。事件の全体像は、様々な場所に散らばる財布たちの視点という、小さなモザイクタイルが集まって、ようやく一つの巨大な絵として完成するかのようです。
探偵・河野の存在も印象的です。亡き妻の面影を早苗に重ね、事件の真相を粘り強く追い続ける彼の孤独と執念。彼の古びた財布が語る、妻への変わらぬ愛情と、事件への使命感には、心を打たれました。そして、事件解決後、心に傷を負った雅樹少年にそっと寄り添う彼の姿は、物語の数少ない救いとなっています。早苗の忘れ形見であるイヤリングを、河野が自分の財布から雅樹の財布へと移す場面は、言葉少ないながらも、深い思いやりが伝わってくる名場面だと感じます。
この物語は、タイトルが示す通り、一つの殺人事件が、実に多くの人々の人生を巻き込み、長い時間をかけて真相が明らかになっていく様を描いています。財布たちのモノローグは、時に回りくどく感じられる部分もあるかもしれませんが、それこそが人間の営みの複雑さ、一筋縄ではいかない現実を映し出しているのかもしれません。単純な勧善懲悪では終わらない、人間の心の機微や社会の歪みを、財布というユニークな視点から見事に描ききった作品だと思います。読後には、ずしりとした重さと共に、登場人物たちの人生、そして自分自身の「財布」との関係について、改めて考えさせられるのではないでしょうか。
まとめ
宮部みゆきさんの小説「長い長い殺人」は、財布が語り手となる独創的な設定で描かれるミステリー作品です。保険金殺人を巡る事件の顛末を、被害者、加害者、刑事、探偵、そして事件とは直接関係のない人々の財布たちの視点を通して多角的に描き出しています。
物語は、単なる犯人当てに留まらず、人間の欲望、孤独、メディアの功罪、そして物言わぬ証人たちの声なき声に耳を傾けさせます。特に、叔母の死の真相を追う少年・雅樹と、亡き妻の面影を依頼人に重ねる探偵・河野の姿は、読む者の心に深く刻まれます。
この作品は、ミステリーとしての面白さはもちろん、深い人間ドラマとしても読み応えがあります。「長い長い殺人」というタイトルが示すように、一つの事件がもたらす波紋の広がりと、真相に至るまでの複雑な道のりを、じっくりと味わうことができる一冊です。































































