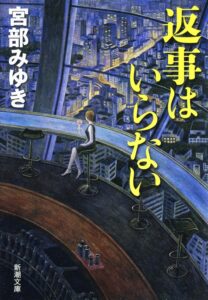 小説「返事はいらない」のあらすじを結末に触れつつ紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの初期の輝きが詰まったこの短編集は、発表された当時、直木賞の候補にもなりました。都会の片隅で起こるささやかな、しかし心に深く刻まれる出来事を描いた6つの物語が収められています。
小説「返事はいらない」のあらすじを結末に触れつつ紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの初期の輝きが詰まったこの短編集は、発表された当時、直木賞の候補にもなりました。都会の片隅で起こるささやかな、しかし心に深く刻まれる出来事を描いた6つの物語が収められています。
それぞれの物語は独立していますが、どこか共通する空気感、特にバブル期の残り香が漂う東京という街の光と影、そこで生きる人々の切なさや希望が通底しています。巧みな構成で読者を引き込み、登場人物たちの細やかな心の動きを描き出す手腕は、さすが宮部みゆきさんと言いたくなる見事さです。ミステリーとしての面白さはもちろん、読み終えた後にじんわりと温かい気持ちになったり、少し切なくなったりする、そんな余韻も魅力でしょう。
この記事では、各短編の物語の筋道を、結末まで含めて詳しくお伝えしていきます。さらに、それぞれの物語を読んで私が感じたこと、考えたことを、ネタバレを気にせずにたっぷりと語っていきたいと思います。これから読む予定の方、すでに読まれた方、どちらにも楽しんでいただけると嬉しいです。
小説「返事はいらない」のあらすじ
この作品集には、珠玉の短編が6つ収められています。表題作「返事はいらない」では、失恋の痛手から衝動的な行動に出ようとした女性・千賀子が、ある老夫婦との出会いをきっかけに思わぬ事件に関わることになります。元恋人への複雑な思いと、事件の真相が絡み合い、彼女の心が静かに変化していく様子が描かれます。
「ドルシネアにようこそ」は、速記士を目指す青年・伸治が主人公です。彼は毎週、駅の伝言板に架空の待ち合わせを書くというささやかな秘密を持っていました。ある日、その伝言に返事が来たことから、華やかな世界の裏側と、そこに生きる人々の現実、そして自身の抱えるコンプレックスと向き合うことになります。カード社会の危うさも垣間見える物語です。
「言わずにおいて」では、会社でのストレスから逃れるように夜道を歩いていた聡美が、目の前で起きた不可解な交通事故を目撃します。運転手が最後に発した言葉の意味を探るうち、事故の裏に隠された悲しい男女の真実が明らかになっていきます。聡美自身の悩みにも、そっと寄り添うような展開が待っています。
残る3編、「聞こえていますか」は、引っ越し先の家で不思議な体験をする少年の物語。「裏切らないで」は、歩道橋から転落死した女性の事件を追う刑事の物語で、東京という街が持つ魔力と危うさが描かれます。「私はついていない」は、少しおませな少年が、浪費家の従姉のために奔走する中で、人間の見栄や嫉妬、そして優しさに触れる物語です。どの話も、日常に潜む小さな謎と、そこに生きる人々の思いが丁寧に紡がれています。
小説「返事はいらない」の長文感想(ネタバレあり)
宮部みゆきさんの初期短編集「返事はいらない」、久しぶりに読み返してみましたが、やはり色褪せない魅力がありますね。バブル経済が弾ける少し前、1990年代初頭の東京の空気が濃厚に漂っていて、今読むと少し懐かしい描写もありつつ、描かれている人間の悩みや感情は、現代にも深く通じるものがあると感じます。6つの短編、それぞれに個性があり、ミステリーとしての仕掛けも鮮やかですが、それ以上に登場人物たちの心の機微が丁寧に描かれている点に、私は強く惹かれます。
まず表題作の「返事はいらない」。失恋して自暴自棄になりかけた千賀子が、老夫婦に誘われて偽造キャッシュカードの不正引き出しを手伝うことになる。でも、目的はお金ではなく、銀行システムの脆弱性を訴えるため。引き出したお金は警察に回収させ、事件は迷宮入り…のはずが、元刑事の滝口が彼女のもとを訪れます。なぜ彼女だと分かったのか。それは、彼女が使った偽造カードの口座名義人の一人が、偶然にも元彼の繁であり、その暗証番号が、千賀子が自分の誕生日で試した番号と全く同じだったから。なんという皮肉、なんという偶然でしょう。繁は、別れた後も千賀子の誕生日を暗証番号に使っていたのです。この事実が、千賀子の中に残っていた繁への未練を、静かに溶かしていくように感じられました。「さよならには、返事はいりませんよね」。最後に彼女が呟くこの言葉は、依存から抜け出し、自分の足で立とうとする決意の表れのようで、胸に沁みます。失恋の痛みからの再生、その過程がとても繊細に描かれていて、読後感が爽やかです。
「ドルシネアにようこそ」は、個人的にとても好きな作品です。速記士を目指す伸治の、駅の伝言板を使ったささやかな空想。高級ディスコ「ドルシネア」への憧れと、自分には縁がないという諦め。でも、伝言に返事が来たことで、彼の日常は動き出します。登場する小百合は、カード破産寸前の女性。きらびやかな東京の夜に隠された、個人の苦悩がリアルです。「地下鉄に乗ってやってきて、クレジットカードで豪遊するシンデレラ」という表現がありましたが、まさに言い得て妙。伸治が憧れていたドルシネアも、実は彼が勝手に作り上げた「敷居の高い幻」で、オーナーの嘉子はもっと気軽に来てほしいと願っていた。この対比が印象的でした。伸治が見ていた「ドルシネア」という幻と、その裏にある温かい現実。そして、伸治自身も一歩踏み出す勇気を得て、試験にも合格する。希望を感じさせるラストが良いですね。駅の伝言板というアイテムが、時代の空気を感じさせます。
「言わずにおいて」は、少し複雑な人間関係が描かれています。聡美が目撃した事故。運転手の芦原が叫んだ「見つけた」という言葉。その謎を追ううちに、芦原が愛人に裏切られて殺害し、その事実を妻に感づかれたため、妻を安心させながら心中しようとしていたことがわかります。愛人にそっくりな聡美を、わざと妻に見せて「(愛人を)見つけた」と嘘をつき、事故に見せかけて死ぬ…なんとも屈折した計画です。やるせない結末ではありますが、そこに至るまでの芦原の苦悩や、妻への後ろめたさのような感情も想像させられます。物語の導入部で描かれる、聡美が会社で受ける理不尽な扱い。これも当時の社会の一端を切り取っているようで、興味深いです。事件の真相を探る過程で、聡美自身も少しだけ前向きになれたような、そんな気配が感じられるのも、宮部さんらしい丁寧さだと思います。途中で出てくる掃除のおばさんの「男はだいたい十字砲火でやられちゃうもん」「夢と現実」というセリフも、短いながら深みがあって印象に残りました。
「聞こえていますか」は、少し不思議な雰囲気の物語です。勉少年が引っ越し先で見つける盗聴器。前の住人であるおじいさんが、駐車が下手な隣家の息子に頼んで、自分の家の電話に取り付けさせていたという事実。でも、なぜ? 結局、その理由ははっきりとは語られないまま終わります。ただ、勉の家庭の嫁姑問題と対比されるように、隣家の親子の間の、言葉にならない複雑な感情や、伝えられなかった思いのようなものが、静かに漂っているように感じました。「どうしようもないことはあるのだよ」という言葉が、静かな諦念とともに胸に残ります。多くを語らないからこその余韻がある作品です。
「裏切らないで」は、この短編集のテーマ性を最もはっきりと打ち出しているように感じました。歩道橋から転落死した道恵。刑事の加賀美は、彼女が抱えていた多額の借金から自殺と見られていた事件の裏に、隣人・陽子による殺人という真相を突き止めます。陽子が道恵を突き落とした動機は、道恵の美容院での変身ぶり、つまり「東京」によって簡単に変わっていく姿への嫉妬と、自分もまた「東京」に裏切られたという思いがあったからではないか、と加賀美は推測します。ここで語られる「東京」観は強烈です。「『東京』は幻だ」「しょせん虚像だ」「つかのまでもそこの住人になるためには、若くなければならない」。地方から見た憧れの「黄金郷東京」と、実際に住むことで感じる現実とのギャップ、そして若さという有限な時間の中で消費されていく人々…。宮部さんが描く「東京」は、まるで万華鏡のように、見る角度によって様々な顔を見せるけれど、その中心にはどこか冷たい虚無感が漂っているように感じられます。この作品を読むと、華やかな都市の裏側にある、人間の孤独や焦燥感がひしひしと伝わってきて、少し怖くもなります。
最後に「私はついていない」。この話が一番、エンターテイメント性が高く、読み味も軽やかかもしれません。主人公は、頭の回転が速い中学生(?)の裕。浪費家でトラブルメーカーの従姉・逸美が、婚約指輪を借金のカタに取られた挙句、それを返すために用意したお金でさらにトラブルに巻き込まれる。裕は、機転を利かせてそのピンチを救います。逸美のキャラクターは、本当にどうしようもないのですが、どこか憎めない。裕が言うように「自分の人生に起こる良くないことを、他人のせいにして、被害者顔することだけはないから」かもしれません。対照的に描かれるのが、逸美の同僚で、彼女に指輪を取り上げた井口。彼女は自分の不遇を逸美のせいにして「ツイてない」「運を食われてる」と愚痴る。この対比が鮮やかです。「ついていない」と感じたときに、どう振る舞うか。そこに人間の本質が現れるのかもしれない、と考えさせられました。そして、最後の最後にもう一つ仕掛けられた「母の指輪は偽物だった」というオチ。母のしたたかさというか、過去の清算の仕方に、思わずクスリとさせられました。家族というものの、一筋縄ではいかない面白さも感じます。
全体を通して、やはり宮部さんの物語作りの巧みさ、人物描写の深さには感嘆します。初期の作品でありながら、後の「火車」や「理由」といった社会派長編につながるテーマ(カード社会、都市と地方、家族の問題など)の萌芽が見られるのも興味深いです。バブル期という、今から見れば特殊な時代の空気を纏いながらも、そこで描かれる人間の感情——恋心、嫉妬、見栄、諦め、そして再生への小さな希望——は、普遍的で、いつ読んでも私たちの心に響くものがあります。派手さはないけれど、じっくりと味わえる。そんな短編集だと思います。
まとめ
宮部みゆきさんの短編集「返事はいらない」は、1990年代初頭の東京を舞台に、市井の人々が遭遇するささやかな事件と、それに伴う心の揺れ動きを描いた6つの物語が収められています。失恋からの再生、都会の幻想と現実、家族間の複雑な思い、お金に翻弄される人々など、様々なテーマが扱われており、ミステリーとしての面白さと、深い人間ドラマの両方を楽しむことができます。
派手なトリックやアクションがあるわけではありませんが、登場人物たちの心理描写が非常に丁寧で、読んでいるうちに彼らの感情に寄り添ってしまうような感覚になります。特に、バブル経済の残り香が漂う当時の東京の空気感が巧みに再現されており、その中で生きる人々の希望や切なさがリアルに伝わってきます。読み終えた後には、爽やかな感動や、少し切ない余韻が心に残るでしょう。
宮部みゆきさんのファンはもちろん、人間ドラマをじっくり味わいたい方、短編ミステリーが好きな方におすすめの一冊です。初期の作品ながら、後の傑作群にも通じる魅力が詰まっており、宮部作品の原点に触れるという意味でも、読む価値のある作品集だと感じます。































































