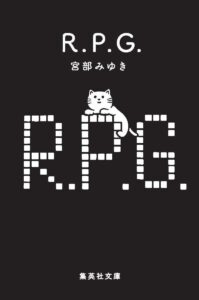 小説「R.P.G.」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの作品の中でも、特にタイトルが印象的で、その意味を知ったときにはっとさせられる、そんな一冊ではないでしょうか。ミステリーとしての面白さはもちろん、物語の構成やテーマ性にも注目していただきたい作品です。
小説「R.P.G.」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの作品の中でも、特にタイトルが印象的で、その意味を知ったときにはっとさせられる、そんな一冊ではないでしょうか。ミステリーとしての面白さはもちろん、物語の構成やテーマ性にも注目していただきたい作品です。
物語は、ある殺人事件から始まります。被害者はネット上で「お父さん」として、見知らぬ人々と「疑似家族」の関係を築いていた人物でした。このネット上の関係と現実の事件がどう結びつくのか、読み進めるうちにどんどん引き込まれていきます。登場人物たちの証言を通して、少しずつ見えてくる真実と、そこに隠された人間の複雑な心理模様が丁寧に描かれています。
この記事では、まず物語の概要、つまりどんなお話なのかを詳しくご紹介します。そして、読み終えた私が感じたこと、考えたことを、ネタバレも気にせずにたっぷりと語っていきたいと思います。少し長い文章になりますが、この作品の魅力を深くお伝えできれば嬉しいです。
小説「R.P.G.」のあらすじ
物語は、都内のある建築中の家で、中年男性・所田良介が刺殺体で発見される場面から始まります。彼はごく普通の家庭を持つサラリーマンでしたが、捜査を進めるうちに、意外な一面が明らかになります。所田はインターネット上のチャットルームで「お父さん」というハンドルネームを使い、素性も知らない赤の他人たちと「疑似家族」を作り、夜な夜な交流を楽しんでいたのです。現実の家族との間には、どこか満たされない思いがあったのかもしれません。
捜査を担当する警察は、このネット上の「疑似家族」の関係者たちが事件に関与している可能性を疑います。しかし、彼らはあくまでネット上の存在。顔も本名も知らない相手を探し出すのは容易ではありません。そこで警察は、所田良介の現実の娘である高校生・一美に協力を依頼します。マジックミラーが設置された特別な取調室で、一美に「疑似家族」のメンバーと思われる人物たちの取り調べの様子を見てもらい、何か気づいた点はないか、父の知らない一面に関する情報を得ようと考えたのです。
一美の目の前で、次々と「疑似家族」のメンバー、つまりネット上で「お母さん」「長男」「次男」「長女」などを名乗っていた人物たちが呼び出され、刑事たちの尋問を受けます。彼らは、ネット上の「お父さん」=所田良介について、そして自分たちの関係について語り始めます。チャットでのやり取り、オフ会での出来事、そして「お父さん」に対するそれぞれの思い…。彼らの証言は時に食い違い、時に新たな謎を生み出します。一美は、父の知らなかった姿に戸惑いながらも、必死に真実を見極めようとします。
取調室という限られた空間での会話劇を中心に、物語は進行していきます。登場人物たちの語りを通して、ネット上の仮面の下にある彼らの孤独や願望、そして現実世界での葛藤が浮き彫りになっていきます。果たして、所田良介を殺害したのは誰なのか?ネット上の「疑似家族」の中に犯人はいるのか、それとも現実世界の関係者なのか?そして、この奇妙な「ごっこ遊び」の果てに待っていた悲劇の真相とは…。物語は、予想もしない結末へと収束していくのです。
小説「R.P.G.」の長文感想(ネタバレあり)
読み終えた直後、まず感じたのは「やられた!」という驚きと、同時に深い感嘆のため息でした。宮部みゆきさんの「R.P.G.」は、単なるミステリー小説という枠には到底収まらない、非常に練り上げられた構成と、人間の心理、そして現代社会が抱える問題を鋭く突いた作品だと感じました。正直に言うと、ミステリーとしての犯人当てやトリックの斬新さという点では、もっと驚かされる作品もあるかもしれません。途中から、なんとなく「この人が怪しいかな?」と感じる部分もありましたし、動機に関しても、完全に共感できたかというと、少し難しい部分もありました。
しかし、この作品の真価は、そこだけではないのです。読み進めている間、ずっと頭の片隅にあったタイトル「R.P.G.」。これはもちろん、作中で描かれるネット上の「疑似家族ごっこ」、つまり「ロール・プレイング・ゲーム」のことを指しているのだろうと思っていました。所田良介が「お父さん」役を演じ、他のメンバーもそれぞれの「役割」を演じる。まさにゲームのような関係性です。でも、物語の終盤、その認識が根底から覆される瞬間が訪れます。
一美がマジックミラー越しに見ていた「疑似家族」のメンバーたち。彼らの証言を聞き、父の知られざる一面や事件の手がかりを探していたわけですが、実は、その場にいた「疑似家族」のメンバーたちは、本物ではなかった。彼らは全員、警察官が演じていた偽物だったのです。これもまた、一つの「ロール・プレイング・ゲーム」だったわけです。この事実に気づいた時の衝撃は、かなりのものでした。ネット上の「R.P.G.」と、警察による捜査のための「R.P.G.」。二重構造になっていたんですね。
この二重の「R.P.G.」という仕掛けは、ただ読者を驚かせるためだけのものではありません。それは、この物語の根幹にある「演じる」というテーマを、より深く、そして普遍的なものとして私たちに突きつけてくるように感じられました。ネット上で理想の役割を演じる人々。事件解決のために疑似家族を演じる警察官たち。そして、よく考えてみれば、主人公格である刑事の武上さんでさえ、本来その役を務めるはずだった先輩刑事「ナカさん」が入院したために、代役として捜査を指揮している。彼もまた、ある種の「役割」を演じているわけです。
そう考えていくと、私たちの生きるこの現実世界そのものが、巨大な「ロール・プレイング・ゲーム」なのではないか、という感覚にとらわれます。私たちは皆、社会の中で、家庭の中で、様々な「役割」を与えられ、それを意識的、あるいは無意識的に「演じて」生きているのではないか。会社員としての自分、親としての自分、友人としての自分…。場面場面で違う顔を見せ、期待される役割をこなそうとする。では、その役割を脱ぎ捨てた「本当の自分」とは、一体どこにあるのだろうか?そんな根源的な問いを投げかけられているような気がして、少し怖くもなりました。まるで、何層にも重なったベールの向こうにある真実を探るような読書体験でした。この「演じる」というテーマを、ミステリーのプロットと見事に融合させ、読後 に深い余韻を残す構成力には、本当に感服するばかりです。
そして、もう一つ、この作品の構成の見事さを示すのが、「A子」の存在です。物語の序盤、所田良介と共に殺害された愛人・今井直子に、過去に恋人を奪われた恨みを持つ人物として登場します。捜査線上にあがっているものの、確たる証拠がないため、捜査本部内では仮に「A子」と呼ばれている、と説明されます。読者も当然のように、その人物を「A子」として認識し、物語を読み進めます。しかし、なぜわざわざ「A子」という仮の名前で呼ばれ続けるのか?普通なら、捜査が進むにつれて本名が明らかになってもよさそうなものです。
その理由は、物語の最後に、一美が真相に気づくのと同じタイミングで、読者にも明かされます。「A子」と呼ばれていた人物は、実は、一美がマジックミラー越しに見ていた「疑似家族」のメンバーの中にいたのです。しかも、警察が用意した偽物ではなく、本物の「A子」が、別の役割を演じてその場に紛れ込んでいた…。これは見事な叙述トリックと言えるでしょう。地の文、つまり物語の語り手からの情報は基本的に真実である、というミステリーの暗黙のルールを逆手に取った仕掛けです。作者自身もあとがきで触れているように、これはある種の「ルール違反」かもしれませんが、それがこの物語においては、テーマ性を深め、読者を驚かせるための効果的な手法として機能しています。一美と読者が同時に「そういうことだったのか!」と膝を打つ。この一体感を生み出す構成は、まさに宮部みゆきさんならではの技だと感じました。
また、この作品が発表された2001年という時代背景も重要だと思います。インターネットが一般家庭に普及し始め、ネットコミュニティという新しい人間関係の形が生まれつつあった頃です。「疑似家族ごっこ」という設定は、今でこそ、ネット上の様々なコミュニティやSNSでの交流を考えれば、それほど突飛なものには感じられないかもしれませんが、当時はまだ目新しく、ある種の危うさや非現実感を伴うものとして捉えられていたかもしれません。しかし、宮部さんは、その設定にリアリティを与え、ネット空間での繋がりが、現実の人間関係における孤独や不全感を埋める場となりうることを描き出しました。
なぜ人は、顔も知らない相手と「家族」を演じようとするのか。作中で描かれる「疑似家族」のメンバーたちは、それぞれに現実世界で何らかの寂しさや満たされない思いを抱えています。現実の家族とうまくいかない、社会で自分の居場所を見つけられない…。そんな彼らにとって、ネット上の「役割」は、現実逃避の手段であると同時に、誰かに受け入れられ、必要とされる喜びを与えてくれるものでもあったのかもしれません。チャットでの他愛ない会話の中に、確かに温かみや繋がりが存在したことも描かれています。「サイバースペースで育まれる人間関係にも価値がある」という作中の言葉は、ネットコミュニケーションが当たり前になった現代を生きる私たちにとっても、深く考えさせられるものがあります。
一方で、その関係性の脆さや危うさも同時に描かれています。顔が見えないからこそ言える本音もあれば、顔が見えないからこその無責任さや欺瞞もある。ネット上の関係にのめり込むあまり、現実の家族や人間関係をないがしろにしてしまう危険性。所田良介の悲劇は、そのバランスを失ったことの結果とも言えるかもしれません。この作品は、インターネット黎明期に書かれたにも関わらず、現代にも通じるネット社会との向き合い方について、重要な問いを投げかけていると感じます。近年、是枝裕和監督の『万引き家族』のように、血縁によらない家族の形を描いた作品が多く見られますが、「R.P.G.」もまた、そうした「家族とは何か」「繋がりとは何か」という普遍的なテーマを、ミステリーという形式の中で深く掘り下げた先駆的な作品と言えるのではないでしょうか。
取調室での会話劇が中心となる構成も、非常に巧みだと感じました。限られた空間の中で、登場人物たちの言葉だけを頼りに、読者は事件の真相と彼らの心理を探っていくことになります。刑事たちの鋭い尋問、それに対する「疑似家族」メンバーたちの反応、そしてマジックミラー越しにそれを見つめる一美の視点。それぞれの言葉の裏にある感情や嘘、隠された真実が、少しずつ明らかになっていく過程は、緊張感があり、ページをめくる手が止まりませんでした。特に、多感な時期にある一美が、父親の知らなかった姿や、大人たちの世界の複雑さ、欺瞞に触れ、戸惑い、傷つきながらも、真実を知ろうとする姿は印象的です。彼女の視点を通して、読者もまた、事件の真相だけでなく、人間の心の奥底にある孤独や脆さ、そして繋がりを求める切実な思いに触れることができるのです。
「R.P.G.」は、読み解けば読み解くほど、様々な発見がある奥深い作品です。ミステリーとしてのどんでん返し、タイトルの意味が明らかになる瞬間の衝撃、そして「演じる」ことや「繋がり」をめぐる普遍的なテーマ。それらが緻密な構成によって一つに結び合わされ、読後に強い印象を残します。一度読み終えた後、もう一度最初から読み返してみると、伏線や登場人物の言葉の意味合いが違って見えてくるかもしれません。そんな再読の楽しみもある、長く付き合える一冊だと感じています。
まとめ
宮部みゆきさんの小説「R.P.G.」は、単なるミステリーの枠を超えた、非常に読み応えのある作品でした。インターネット上の「疑似家族ごっこ」という設定から始まる物語は、殺人事件の謎解きと共に、人間の心理や現代社会が抱える問題にも深く切り込んでいきます。
特に印象的だったのは、タイトル「R.P.G.」に込められた二重の意味と、それを明らかにする巧みな物語構成です。ネット上の役割演技だけでなく、捜査そのものにも「ロール・プレイング」の要素が隠されていたという展開には、思わず唸らされました。また、「A子」の扱いなど、叙述トリックを用いた仕掛けも効果的で、最後まで読者の予想を裏切る展開が待っています。
この物語は、ミステリーとしての面白さはもちろん、「演じる」とはどういうことか、本当の繋がりとは何か、そしてネット社会とどう向き合っていくべきかといった、普遍的で現代的なテーマについても考えさせてくれます。読み終えた後も、登場人物たちのことや物語の意味について、色々と想いを巡らせてしまうような、深い余韻の残る一冊です。ミステリーファンの方はもちろん、人間ドラマや社会派の物語が好きな方にも、ぜひ手に取っていただきたい作品です。































































