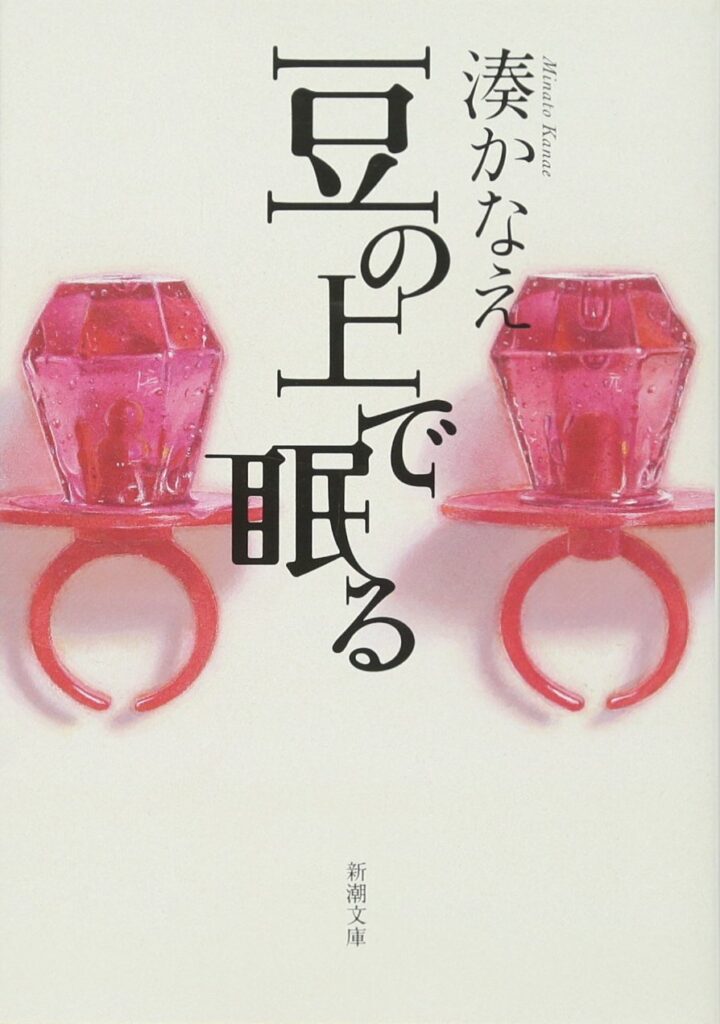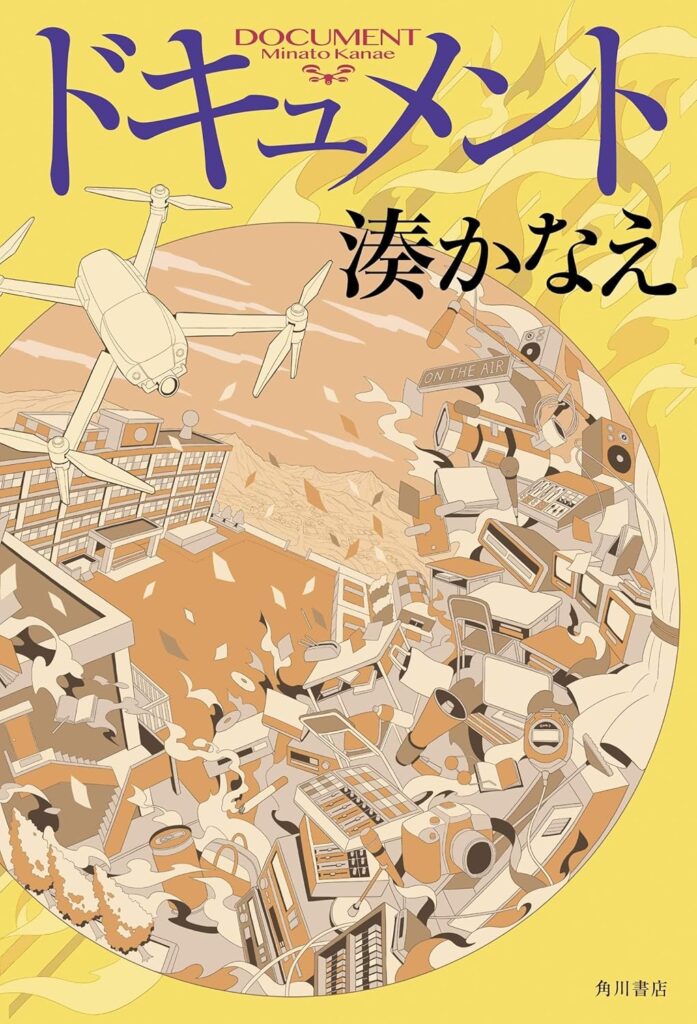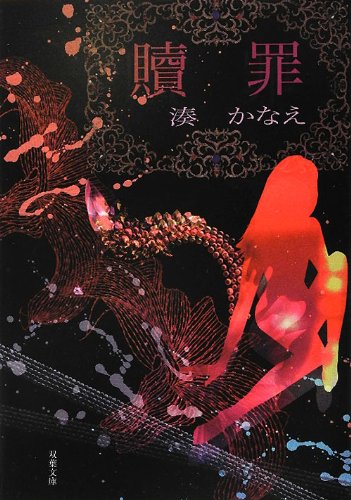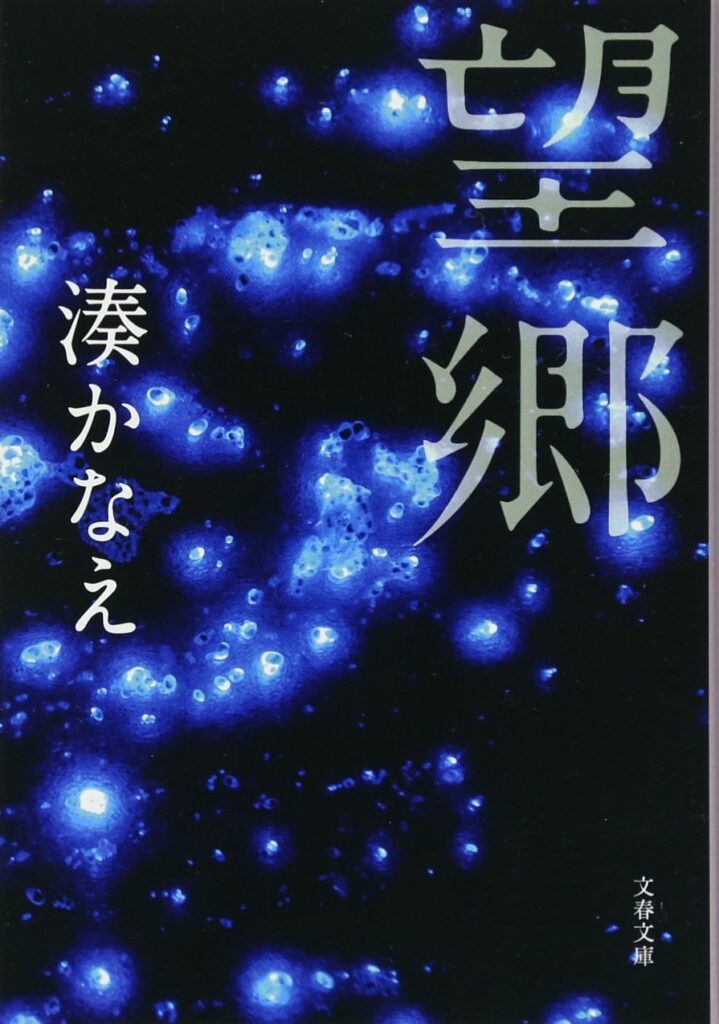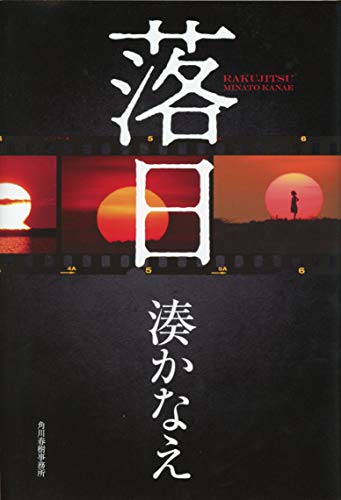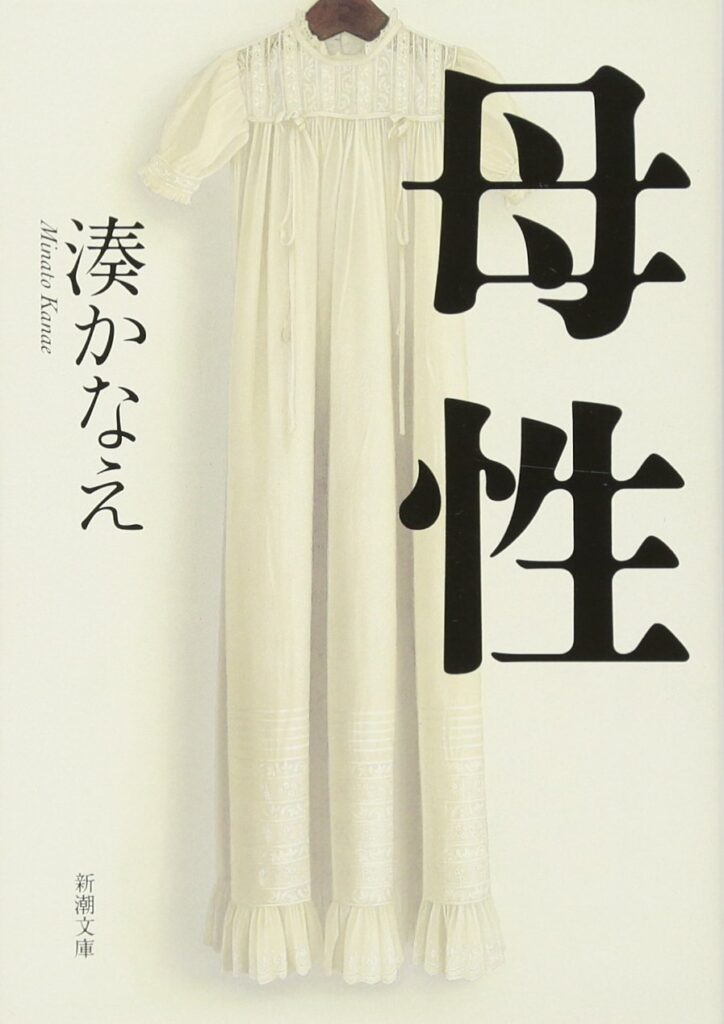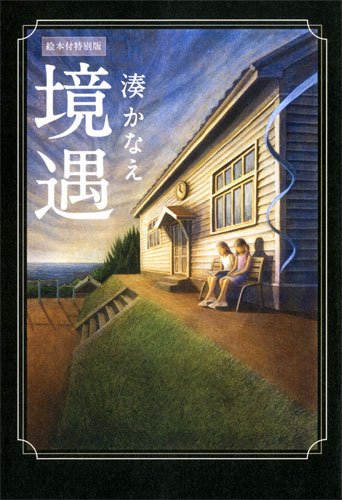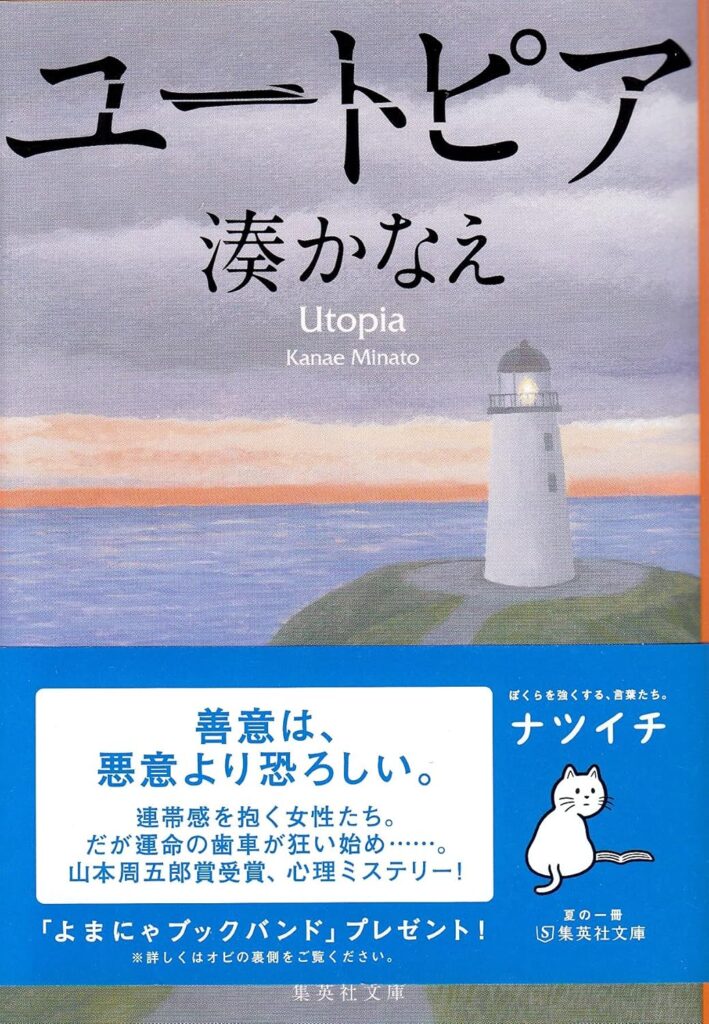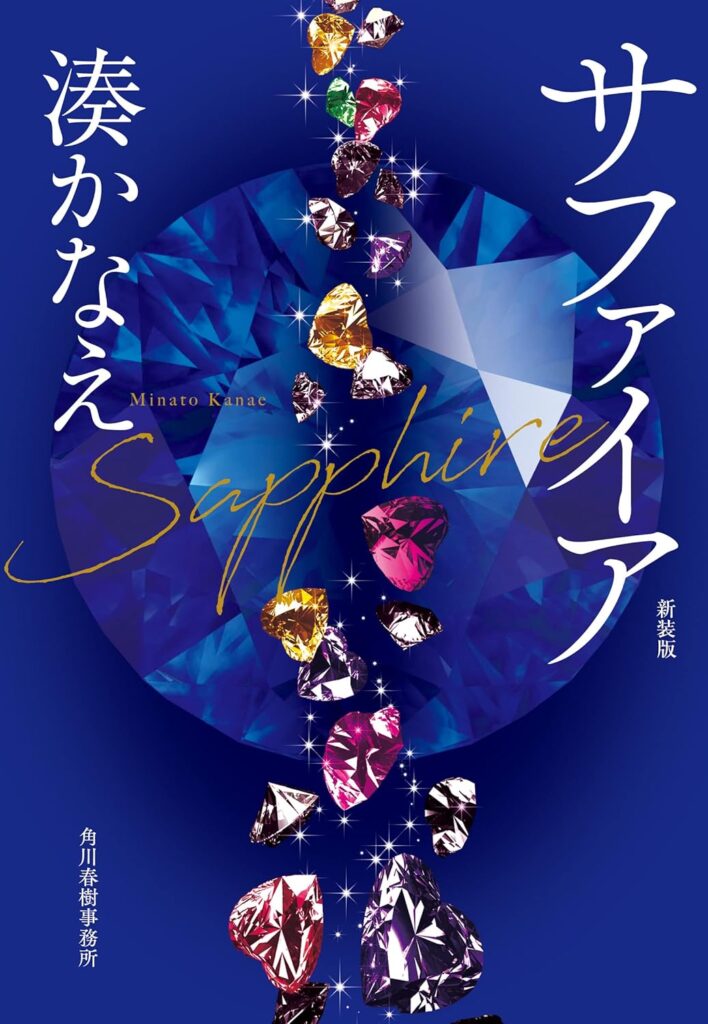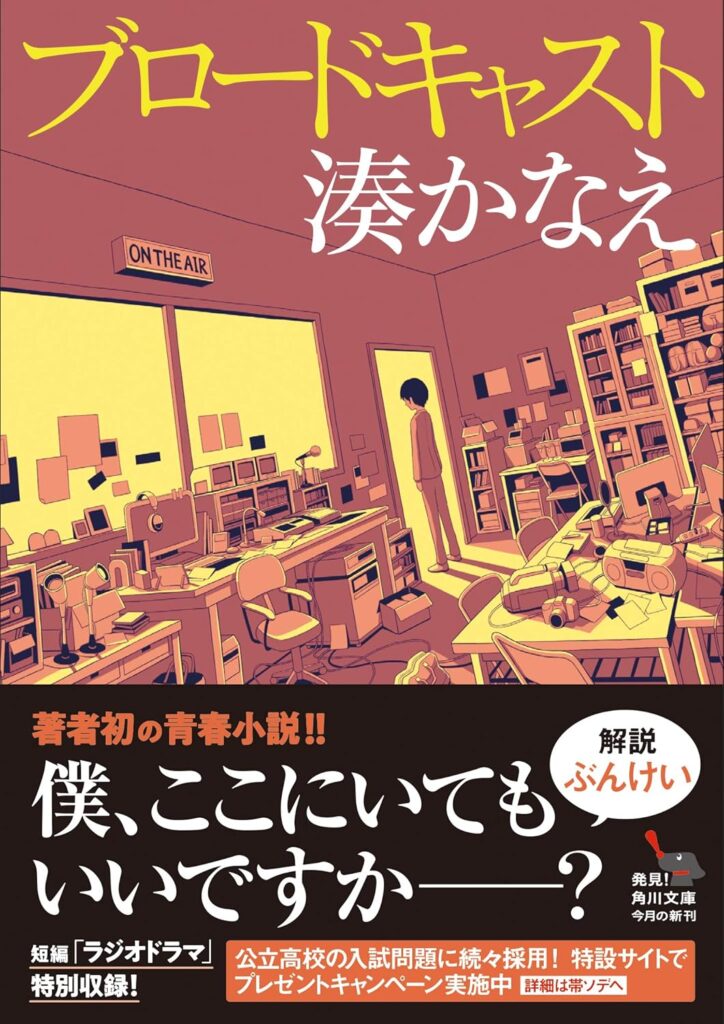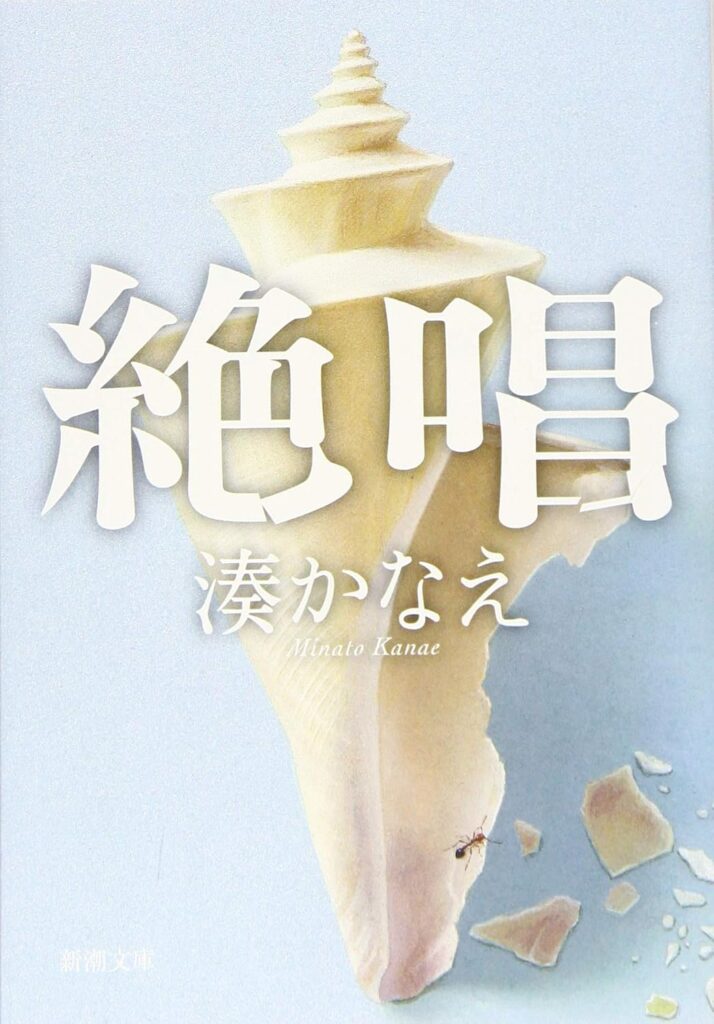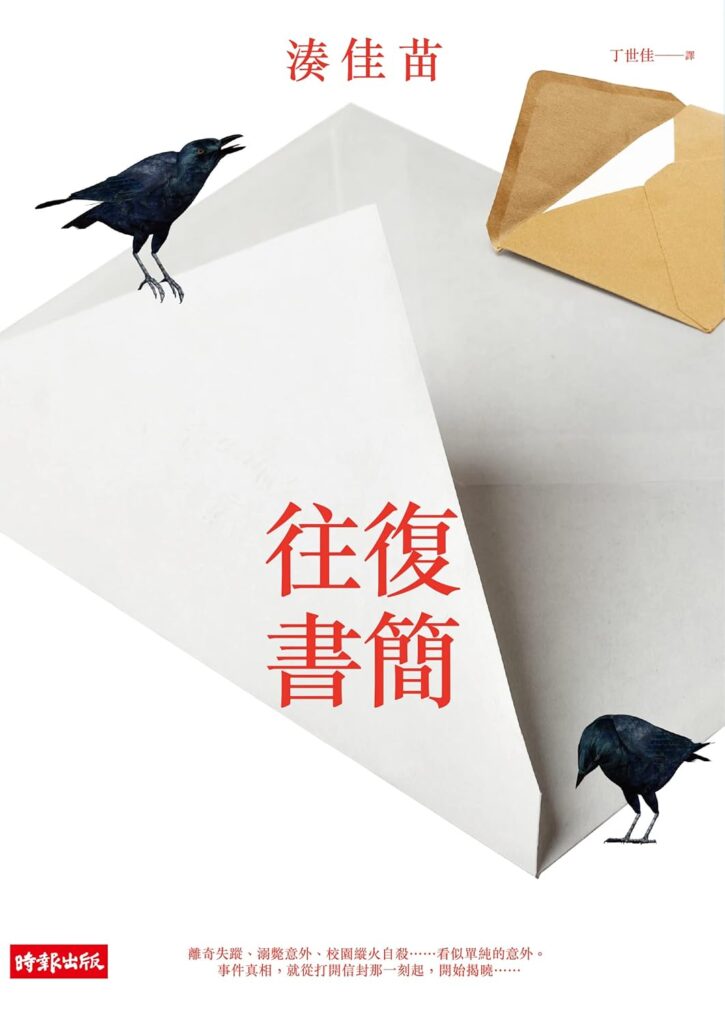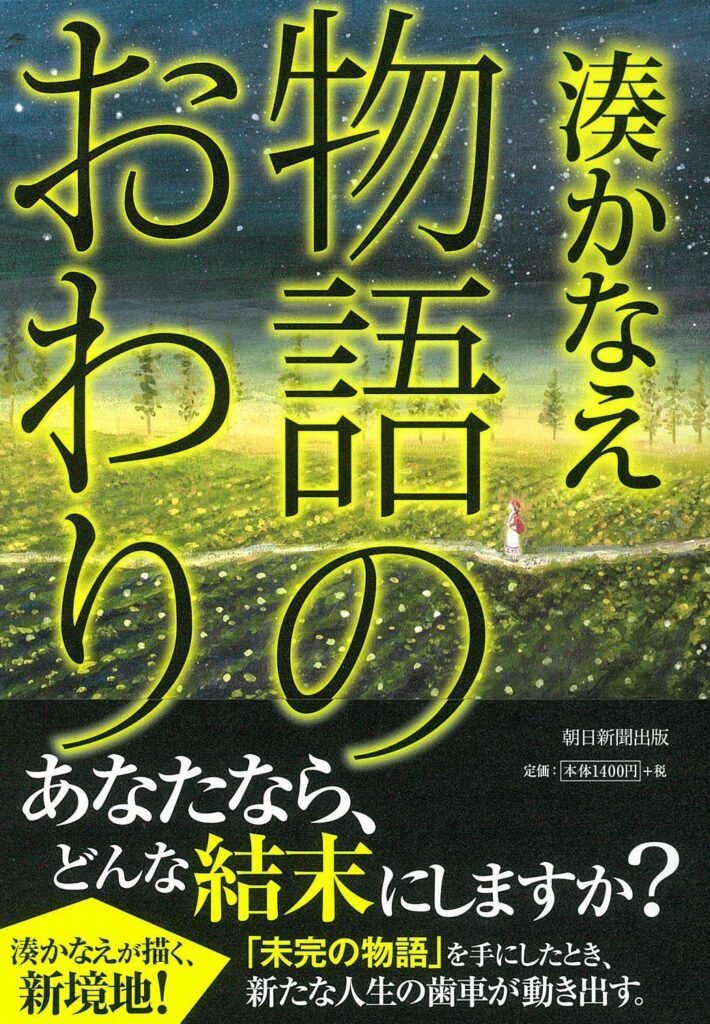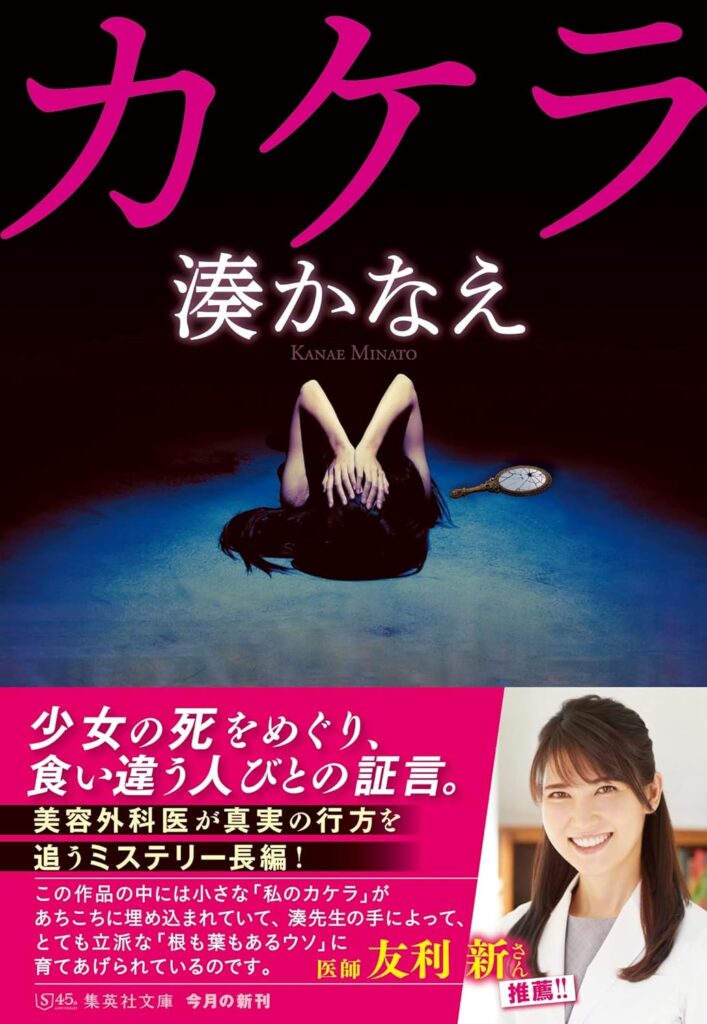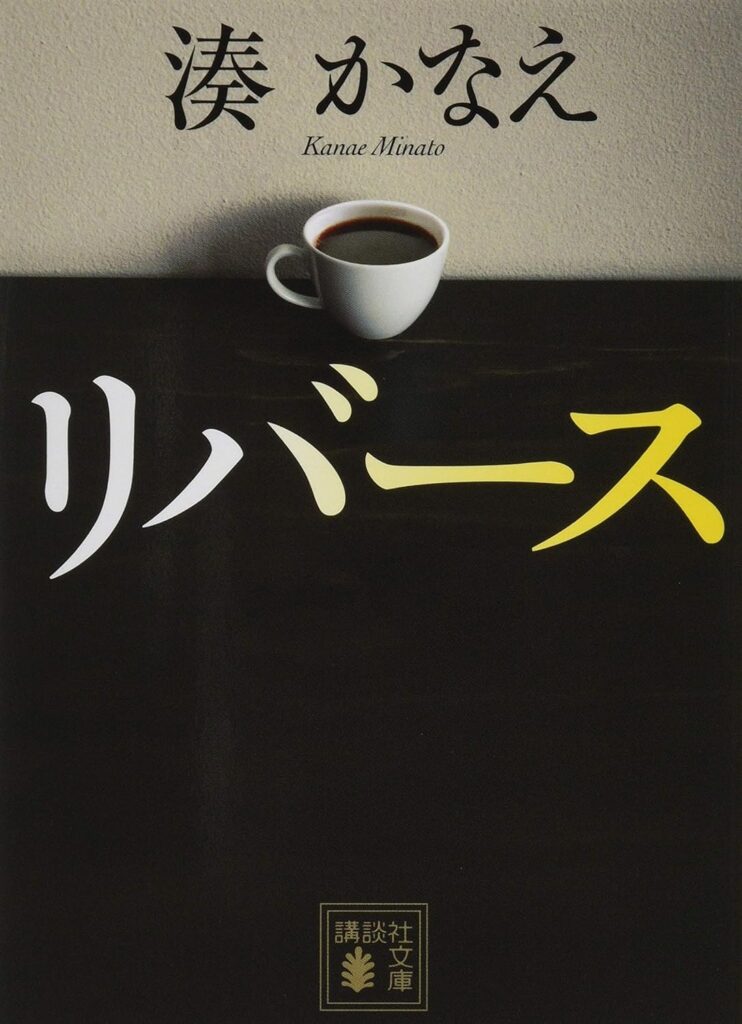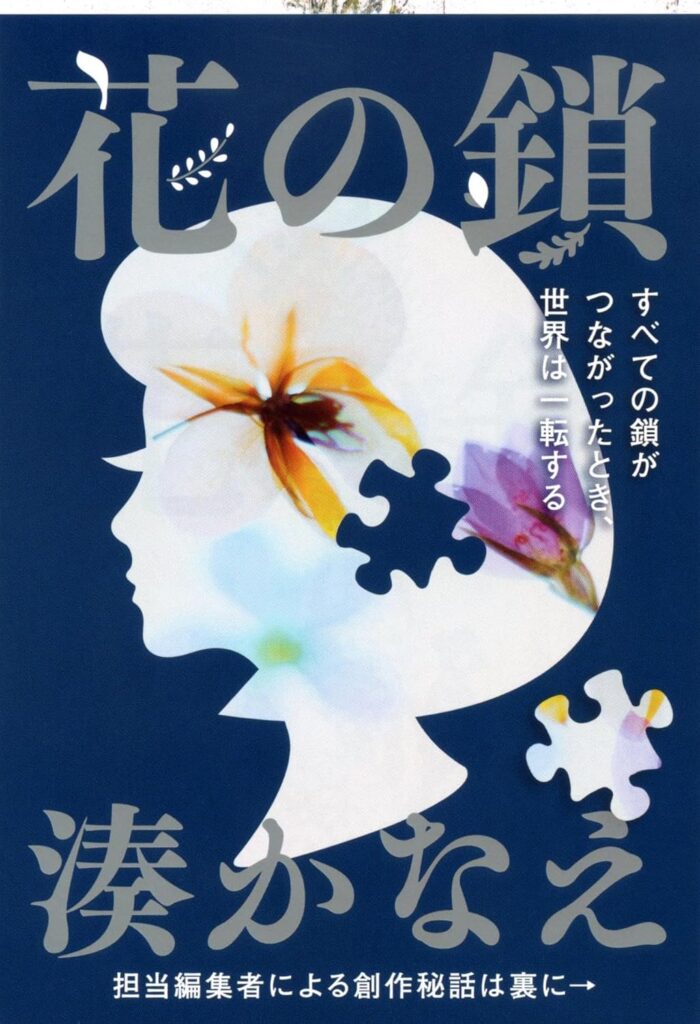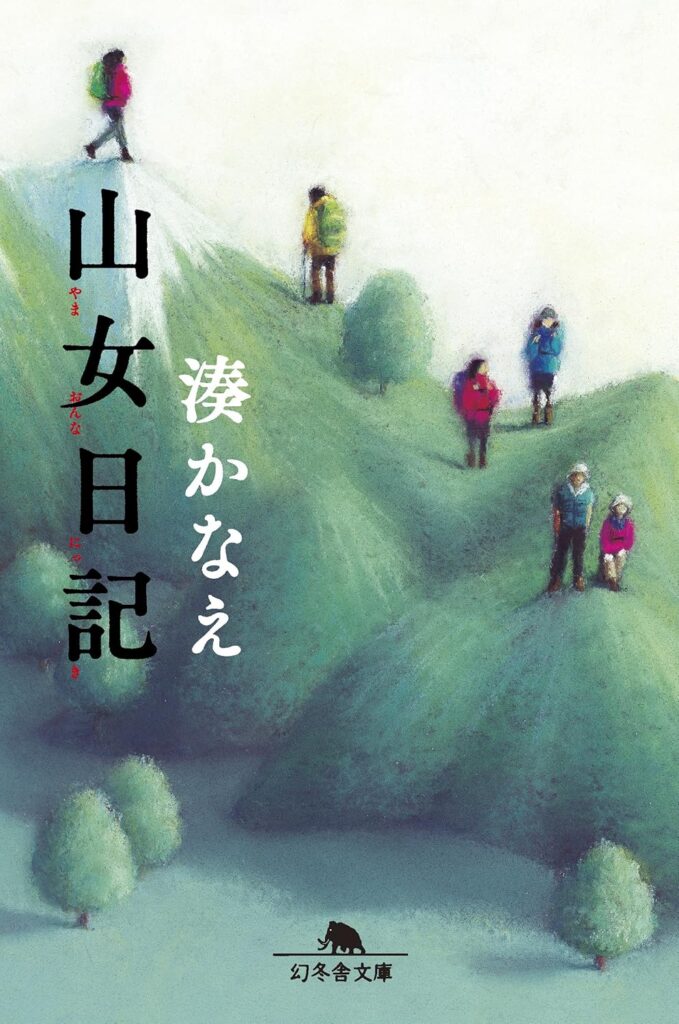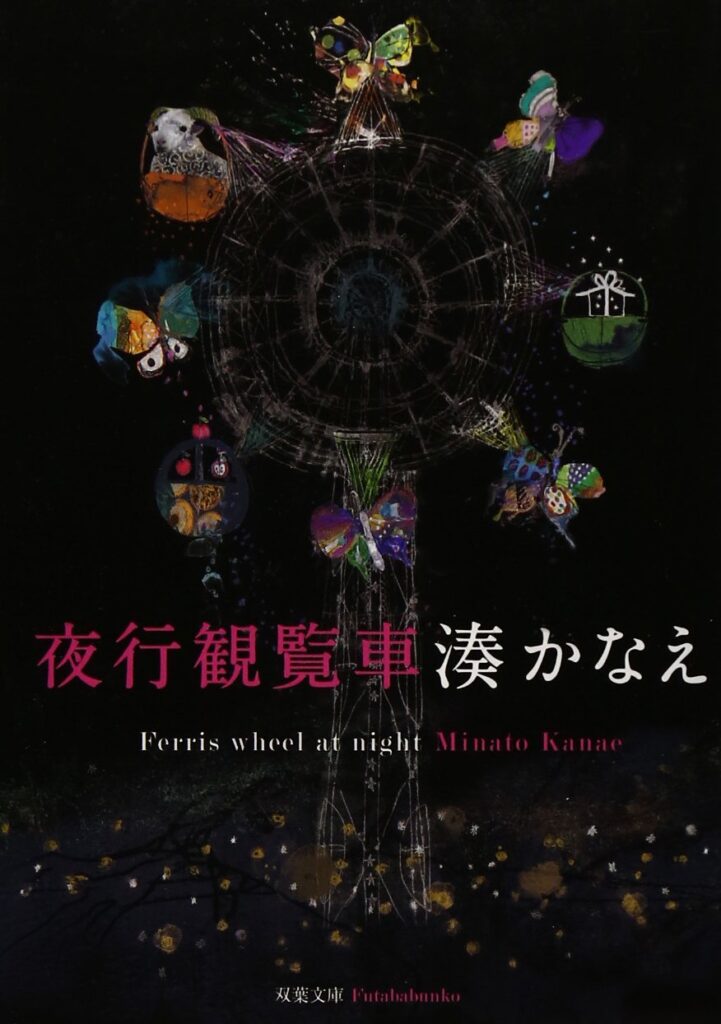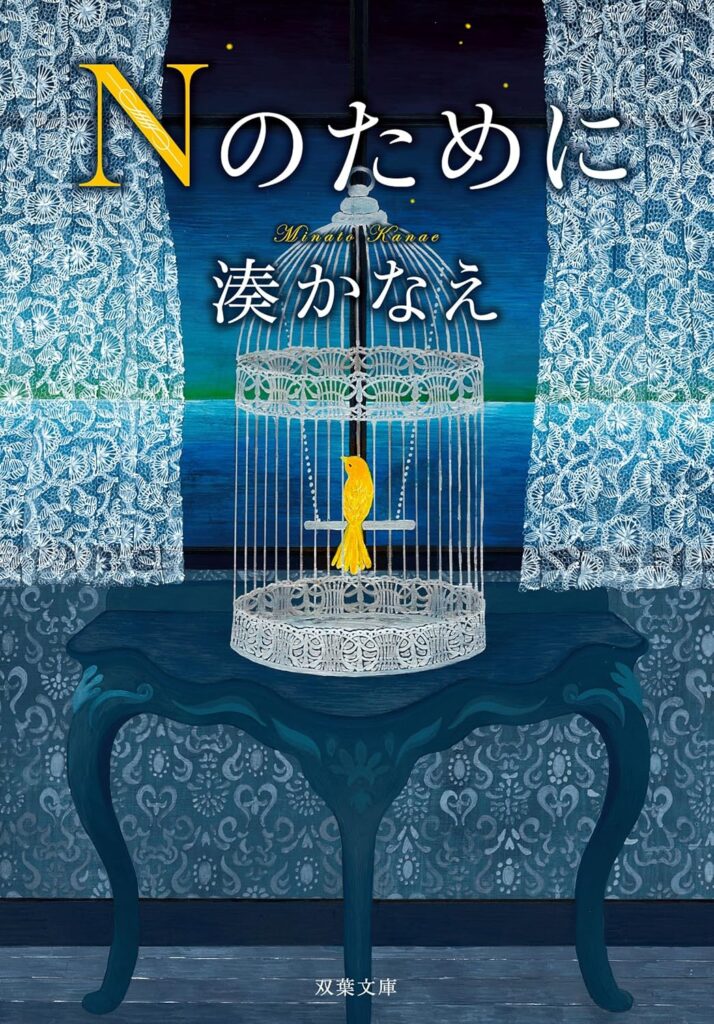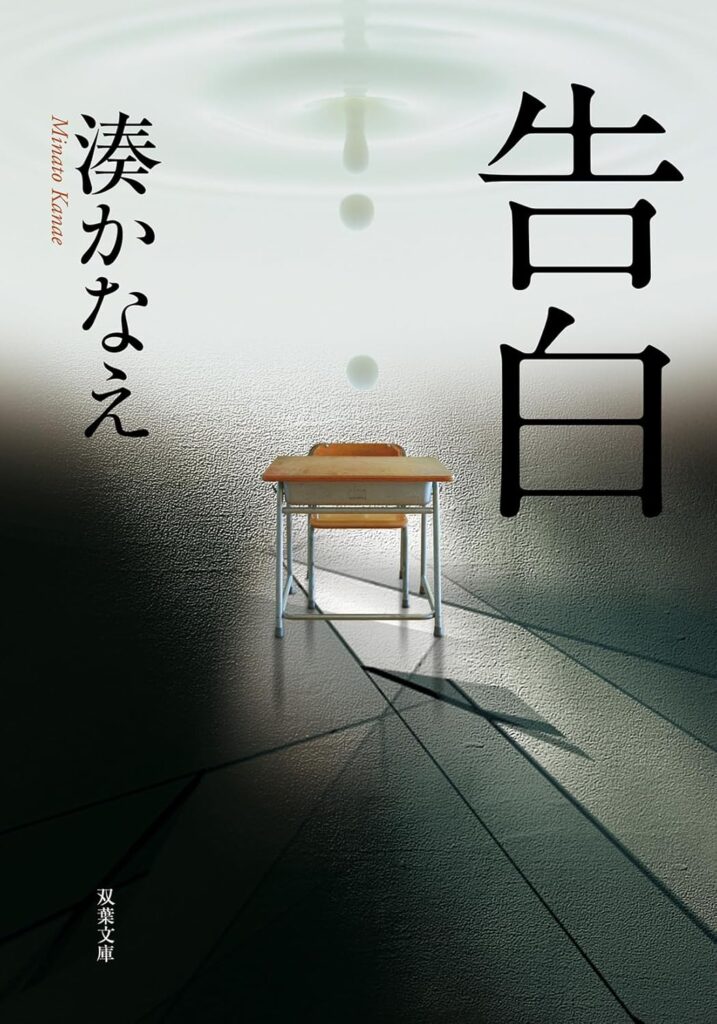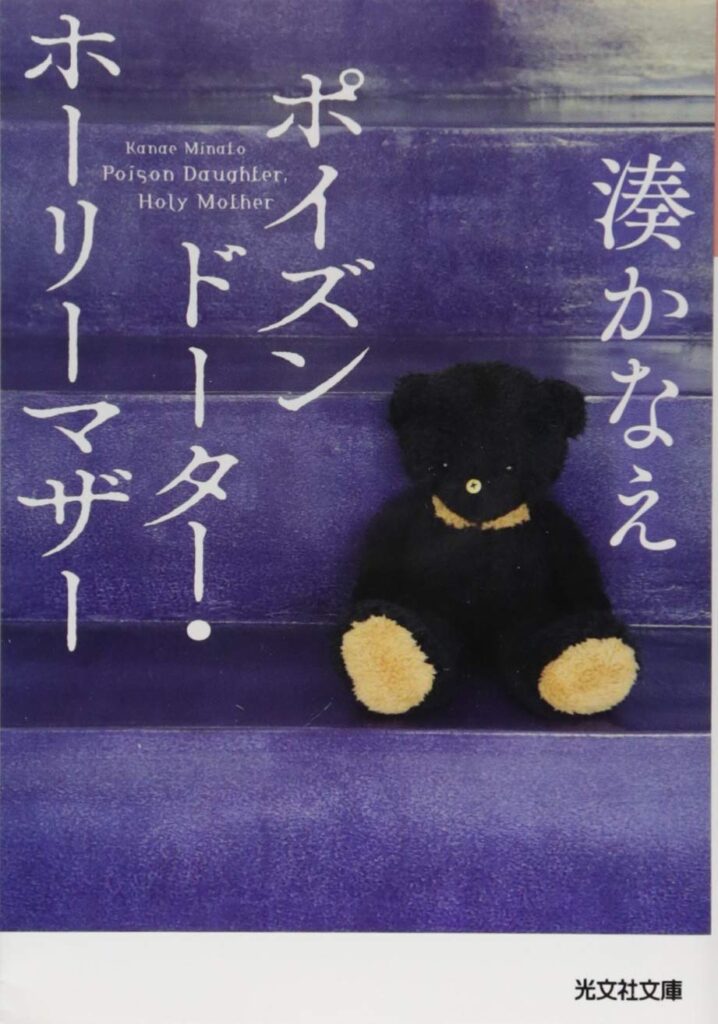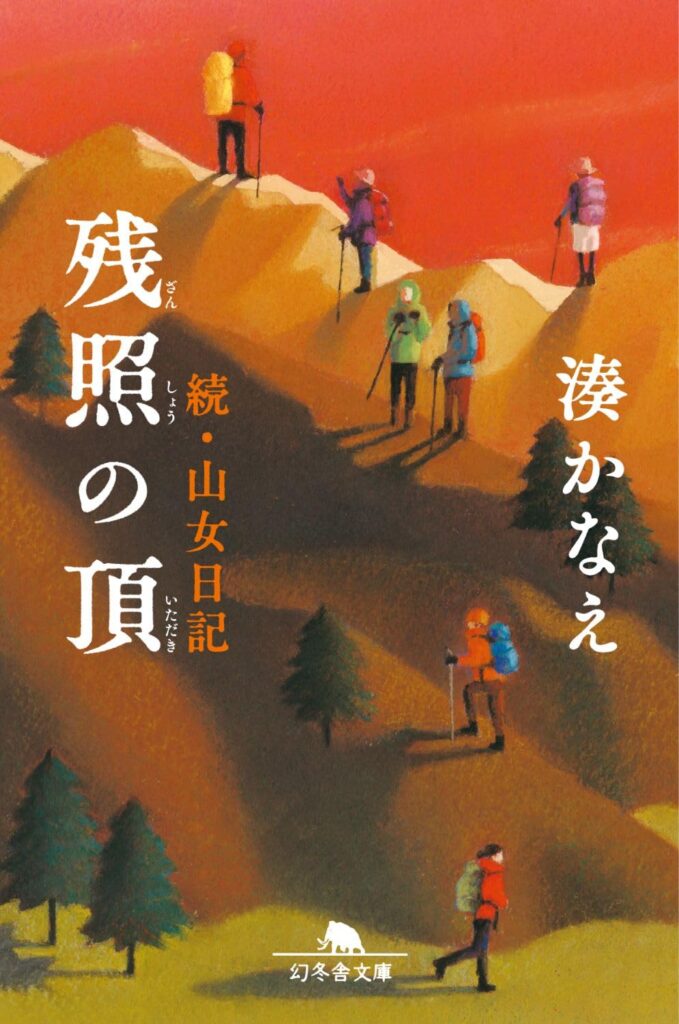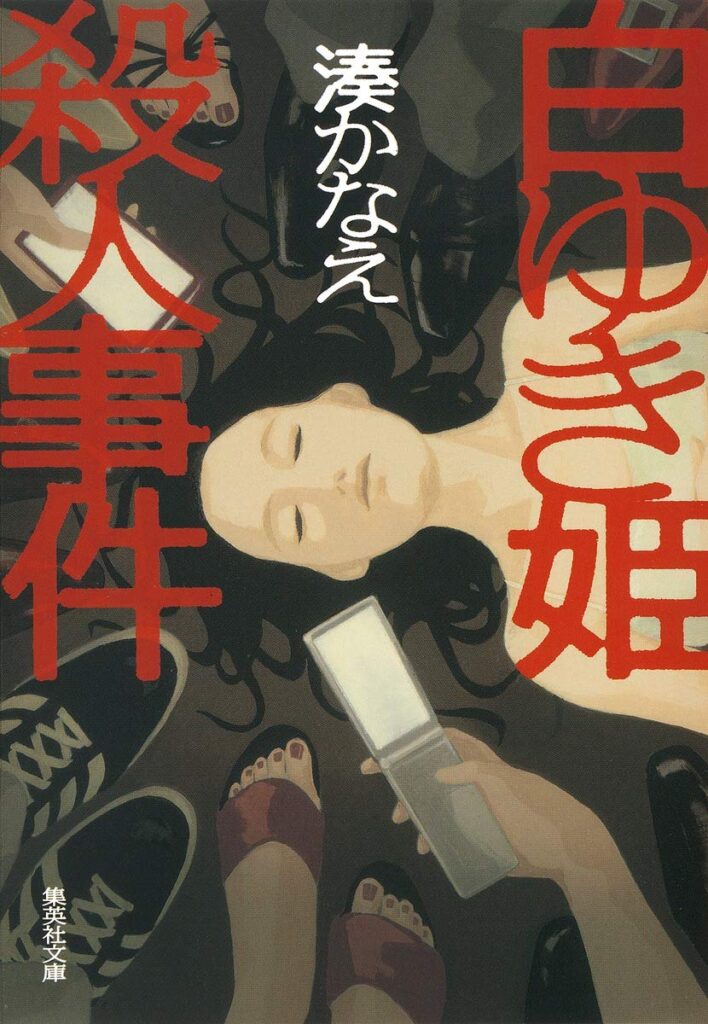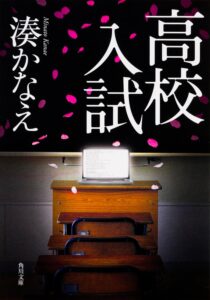 小説「高校入試」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。湊かなえさんの作品の中でも、特に学校という閉鎖的な空間で起こる出来事をリアルに描いた一作として知られていますね。入試という、多くの人が経験するであろう一大イベントの裏側で、こんなにも複雑な人間模様が渦巻いているのかと、読みながらハラハラさせられました。
小説「高校入試」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。湊かなえさんの作品の中でも、特に学校という閉鎖的な空間で起こる出来事をリアルに描いた一作として知られていますね。入試という、多くの人が経験するであろう一大イベントの裏側で、こんなにも複雑な人間模様が渦巻いているのかと、読みながらハラハラさせられました。
この記事では、まず物語の大まかな流れ、つまりどんなお話なのかを説明します。その後、物語の核心部分や結末にも触れながら、私がこの作品を読んで感じたこと、考えたことを詳しくお伝えしていこうと思います。登場人物たちの心理描写や、散りばめられた伏線、そして衝撃のラストについて、一緒に深く味わっていきましょう。
まだ小説「高校入試」を読んでいない方にとっては、物語の結末を知ってしまう情報も含まれていますので、その点はご注意くださいね。ですが、すでに読んだ方も、これから読もうと考えている方も、この作品の持つ魅力を再確認したり、新たな視点を発見したりするきっかけになれば嬉しいです。
小説「高校入試」のあらすじ
物語の舞台は、県下でも有数の進学校とされる県立橘第一高等学校、通称「一高」。多くの生徒や保護者にとって、この高校への入学は大きな目標であり、一種のステータスでもあります。物語は、この一高の入学試験前日から始まります。新任の英語教師である春山杏子は、校内の見回り中に、教室の黒板に「入試をぶっつぶす!」と書かれた不気味な貼り紙を発見します。教師たちの間には動揺が広がりますが、生徒のいたずらだろうと、ひとまずは厳重注意ということで落ち着きます。
しかし、入試当日、事態はさらに深刻化します。試験が進行する中、なんとインターネット上の匿名掲示板に、試験問題の内容や校内の状況がリアルタイムで書き込まれていることが発覚するのです。明らかに内部の人間、それも教師しか知り得ない情報が含まれており、教師たちは疑心暗鬼に陥ります。一体誰が、何の目的でこんなことをしているのか。外部からの問い合わせや保護者からのクレームも入り始め、学校側の対応は後手に回ります。
さらに、トラブルは続きます。最終科目である英語の試験中に、持ち込みが固く禁じられているはずの携帯電話の着信音が教室に鳴り響きます。鳴らしたのは受験生の芝田麻美。彼女は即座に退室させられますが、パニックを起こしてしまいます。駆けつけた母親は、携帯が鳴ったら失格という説明に納得せず、学校側の説明責任を追及します。時を同じくして、同窓会長の沢村も、試験妨害があったにも関わらず何の措置も取られないことに憤慨し、学校に乗り込んできます。
混乱の中、採点作業が始まろうとしますが、今度は英語の答案用紙が一枚足りないことが判明します。消えたのは、他の教科で軒並み高得点を取っている受験生・田辺淳一の答案用紙でした。さらに、なぜか空の答案用紙が一枚紛れ込んでいます。誰かが意図的にすり替えたのか?様々な憶測が飛び交う中、教師たちは必死に答案用紙の行方を捜しますが、見つかりません。そして、追い打ちをかけるように、沢村会長が息子・翔太のものだという別の答案用紙(しかも満点)を持って現れ、事態はますます混迷を深めていくのでした。
小説「高校入試」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは小説「高校入試」の核心に触れながら、私の感じたことを詳しくお話ししたいと思います。まだ結末を知りたくない方は、ご注意くださいね。
この物語を読んでまず強く感じたのは、高校入試という一日がいかに多くの人々の思惑や感情が交錯する、濃密な時間であるかということです。受験生はもちろんのこと、彼らを支える家族、そして合否判定という重責を担う教師たち。それぞれの立場から見える景色は全く異なり、そのズレが様々な軋轢や事件を生み出していく様子が、非常に巧みに描かれていました。
特に印象的だったのは、教師たちの姿です。主人公である新任教師の杏子は、純粋な気持ちで生徒と向き合おうとしますが、学校という組織の論理や、古くからの慣習、そして同僚たちの様々な思惑に翻弄されます。校長や教頭は、問題が大きくなることを恐れ、事なかれ主義に終始しようとします。一部の教師は自らの保身や評価ばかりを気にし、生徒のことよりも組織の体面を守ろうとする。教師たちの保身的な態度は、まるで嵐の中、自分の傘だけを必死に守ろうとする姿のようでした。もちろん、中には荻野先生のように、生徒のことを真剣に考え、過去の過ちと向き合おうとする教師もいますが、組織の中では少数派に見えてしまうのが、なんともやるせない気持ちになりました。
一方で、受験生たちもそれぞれに複雑な事情を抱えています。同窓会長の息子である翔太は、周囲からのプレッシャーに押しつぶされそうになりながらも、虚勢を張っています。県議会議員の娘である麻美は、母親からの過剰な期待と、本当の自分を見てくれない寂しさを抱えています。そして、物語の鍵を握る淳一は、兄・光一が過去に一高受験で経験した辛い出来事を引きずり、入試制度そのものに強い疑問を抱いています。彼らの抱える悩みや葛藤は、決して他人事ではなく、多かれ少なかれ、私たちが思春期に経験したような普遍的な感情と重なる部分があるように感じました。
この物語の構成も非常に特徴的です。視点が次々と切り替わり、それぞれの人物の心情や行動が断片的に描かれていきます。さらに、匿名掲示板への書き込みが挿入されることで、事件の客観的な状況(のように見える情報)と、登場人物たちの主観的な視点が交錯し、読者は誰が何を考え、何が真実なのか、常に惑わされることになります。この手法は、物語に臨場感とスピード感を与える一方で、登場人物が多く、場面転換も速いため、最初は少し戸惑うかもしれません。人物相関図を時折確認しながら読み進めるのがおすすめです。これは、元々テレビドラマの脚本として書かれたものが小説化された、という経緯も関係しているのでしょうね。
そして、いよいよ物語の真相です。一連の事件を引き起こした「入試をぶっつぶす!」計画の首謀者は、受験生の田辺淳一でした。彼の動機は、兄・光一が受験番号の書き忘れという単純なミスで不合格となり、その後の情報開示請求やネットでの誹謗中傷によって深く傷ついたことへの復讐、そして入試制度や学校側の対応への問題提起でした。そして、驚くべきことに、この計画には新任教師の春山杏子と、入試部長である荻野正夫、さらに在校生の石川衣里奈が協力していたのです。
杏子の動機は、過去に深く関わった熱血教師・寺島の死にありました。寺島は、担当した入試での採点ミスが原因で精神的に追い詰められ、事故死してしまいます。学校側が保身のために事実を隠蔽し、寺島に責任を押し付けたことへの怒りと、入試が生徒の人生を左右することの重みを学校側に突きつけたいという思いが、彼女を計画へと駆り立てました。荻野先生は、過去にネット上で光一を匿名で中傷してしまったことへの深い後悔から、淳一の計画に加担します。衣里奈は、体育教師の相田との複雑な恋愛関係のもつれから、騒ぎに加担することになります。
それぞれの動機は個人的なものでありながら、根底には学校や入試制度、あるいはネット社会の匿名性といった、より大きな問題への問いかけが含まれています。しかし、彼らの計画は、予想外の出来事(携帯電話の着信音や答案用紙の紛失など)によって、当初の思惑とは異なる方向へと転がっていきます。結局、計画は中途半端な形で露呈し、淳一は受験番号の書き忘れ(これは荻野が淳一をかばうために偽装したものですが)によって不合格となります。
結末では、荻野先生がすべての責任を負って辞職し、杏子も異動を申し出ます(最終的には校長に引き止められ、フリースクールへの異動を選びます)。衣里奈は停学処分を受けます。首謀者である淳一には、表向きの罰は与えられません。杏子が淳一に語る「私たちは、責任すら取らせてもらえない。その代わり、身代わりになってくれた人の思いを、背負わなければならない」という言葉は、非常に重く響きました。安易な解決やカタルシスではなく、それぞれの登場人物が犯した過ちや、背負うことになった思いと共に、新たな一歩を踏み出していくという結末は、苦さと共に、わずかな希望も感じさせてくれました。
湊かなえさんの作品というと、「イヤミス(読後感が悪いミステリー)」と呼ばれることが多いですが、この「高校入試」は、確かに人間の嫌な部分や組織の醜さも描かれてはいるものの、読後感としては比較的すっきりしている方だと感じました。もちろん、胸が締め付けられるような場面や、やるせない気持ちになる展開もありますが、最後には登場人物たちの再生への意志も描かれており、単なる暴露や告発に留まらない、深い余韻を残す物語でした。高校入試という誰もが通過するかもしれない一点に焦点を当てながら、人間の心理、組織の問題、そしてネット社会の功罪までをも描き出した、読み応えのある一作だと思います。
まとめ
湊かなえさんの小説「高校入試」は、県下有数の進学校を舞台に、入試当日に起こる不可解な事件を描いたミステリー作品です。入試前日に発見された脅迫状、当日のネット掲示板へのリアルタイム書き込み、試験中の携帯電話騒動、そして答案用紙の消失…。次々と起こるトラブルに、教師、受験生、保護者たちは翻弄され、疑心暗鬼に陥っていきます。
物語は、複数の登場人物の視点と匿名掲示板の書き込みが交錯しながら進み、読者は誰が犯人で、何が真実なのか、最後まで目が離せません。学校という閉鎖的な空間で繰り広げられる、保身に走る大人たちの姿、様々なプレッシャーの中で揺れ動く受験生たちの心理、そしてネット社会の匿名性がもたらす影響などが、リアルに描かれています。
結末では、一連の事件の意外な首謀者と共犯者、そしてそれぞれの動機が明らかになります。それは、過去の出来事への復讐心や後悔、学校や入試制度への問題提起、個人的な感情のもつれなど、複雑な要因が絡み合ったものでした。爽快な解決とはいきませんが、登場人物それぞれが自らの行動の結果と向き合い、新たな道を歩み始める姿が描かれ、深い余韻を残します。読後感が悪いとされる「イヤミス」要素は控えめで、人間の弱さや愚かさを描きつつも、わずかな希望も感じさせる作品です。