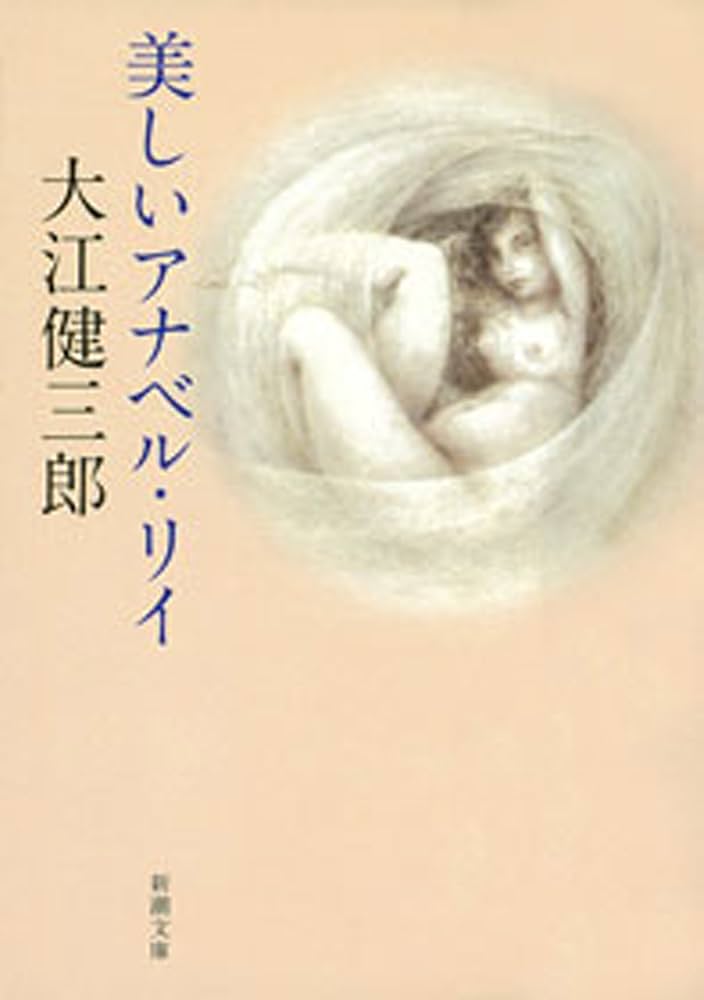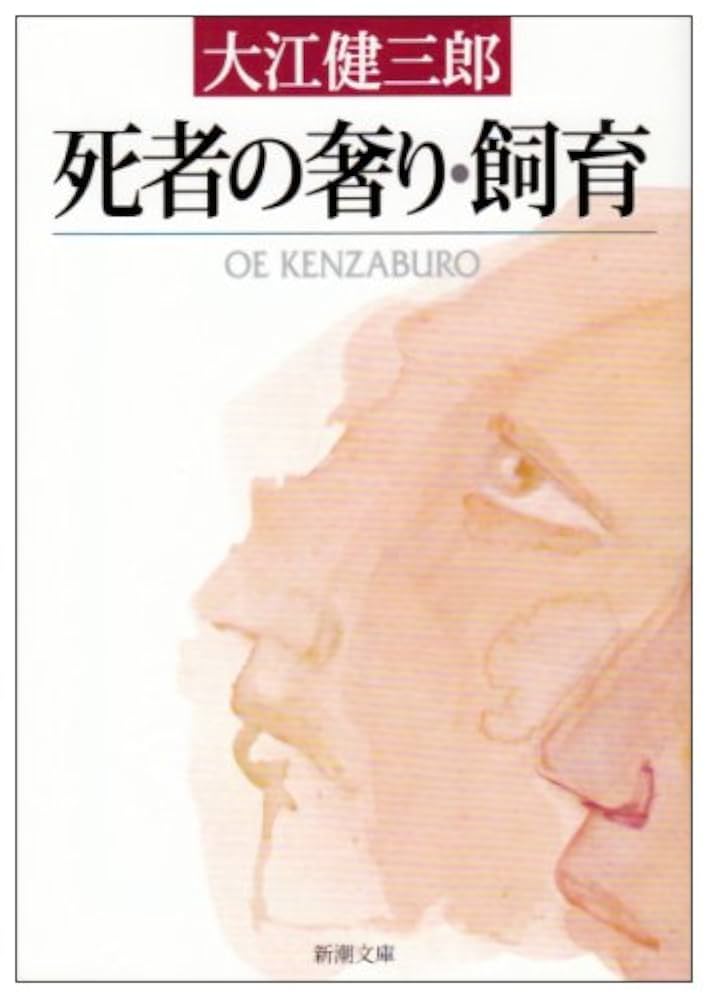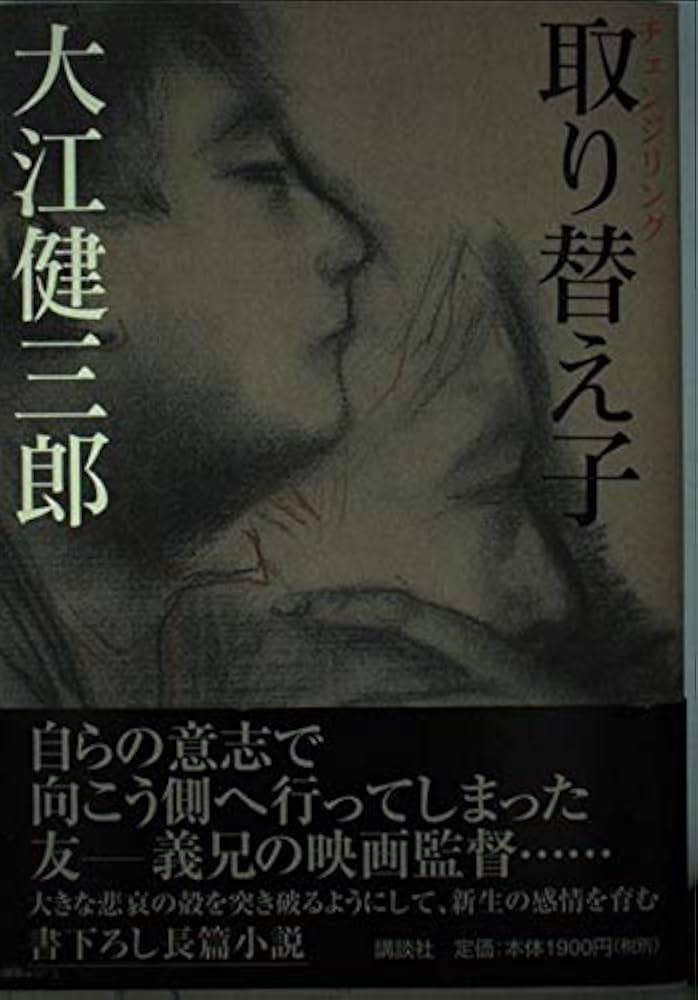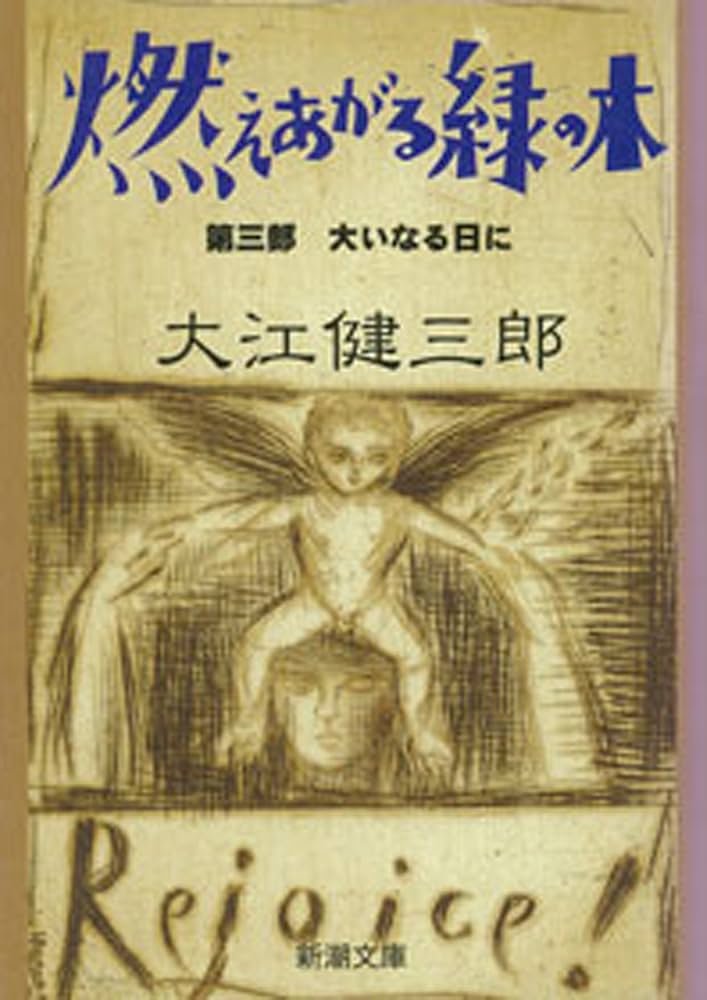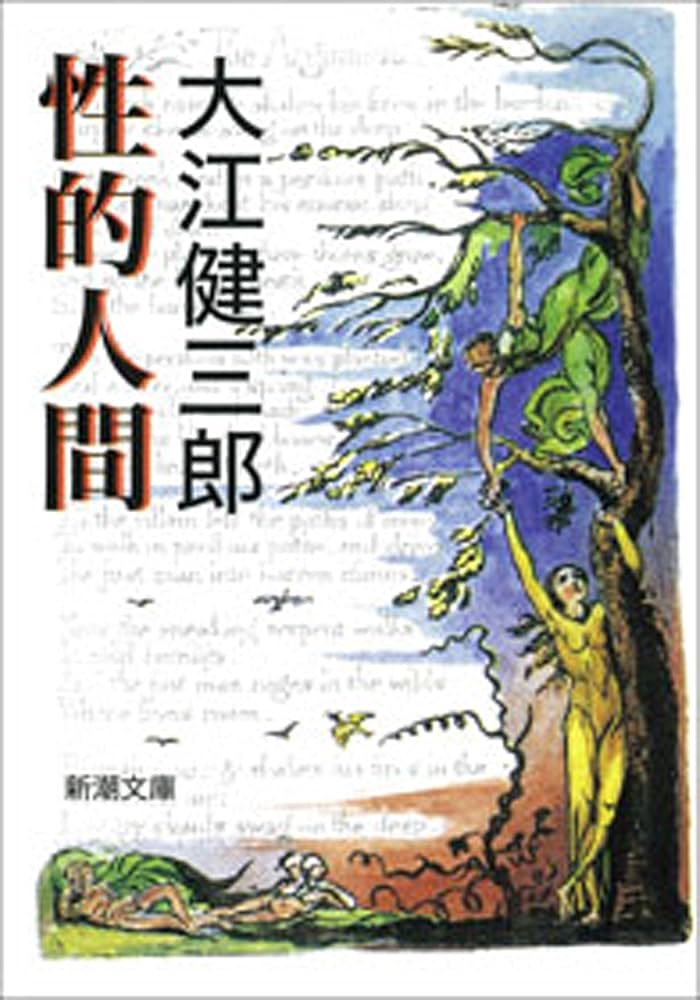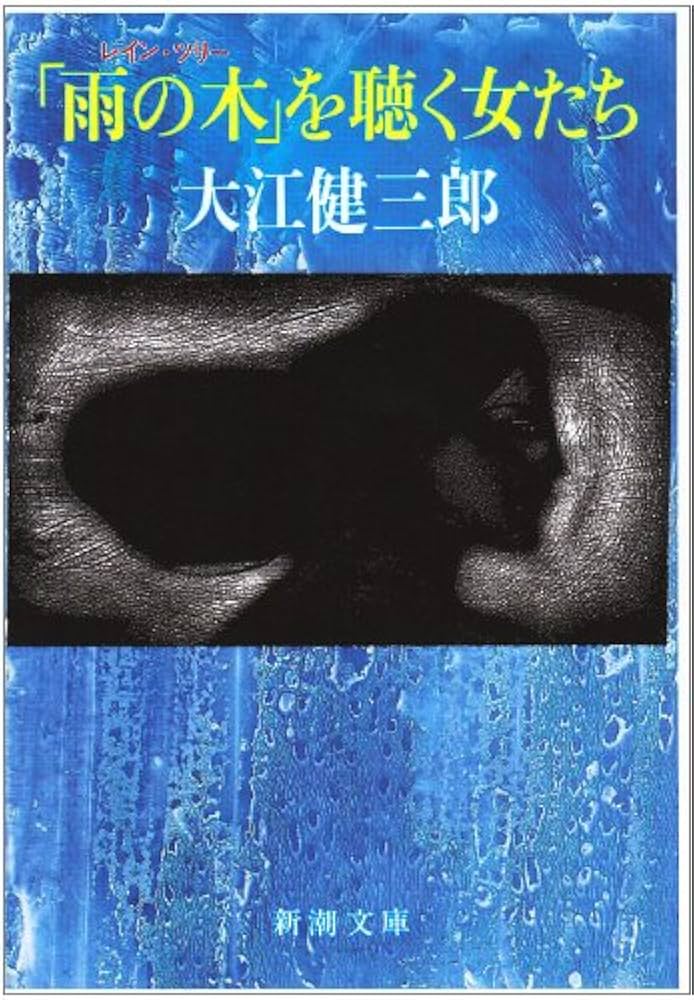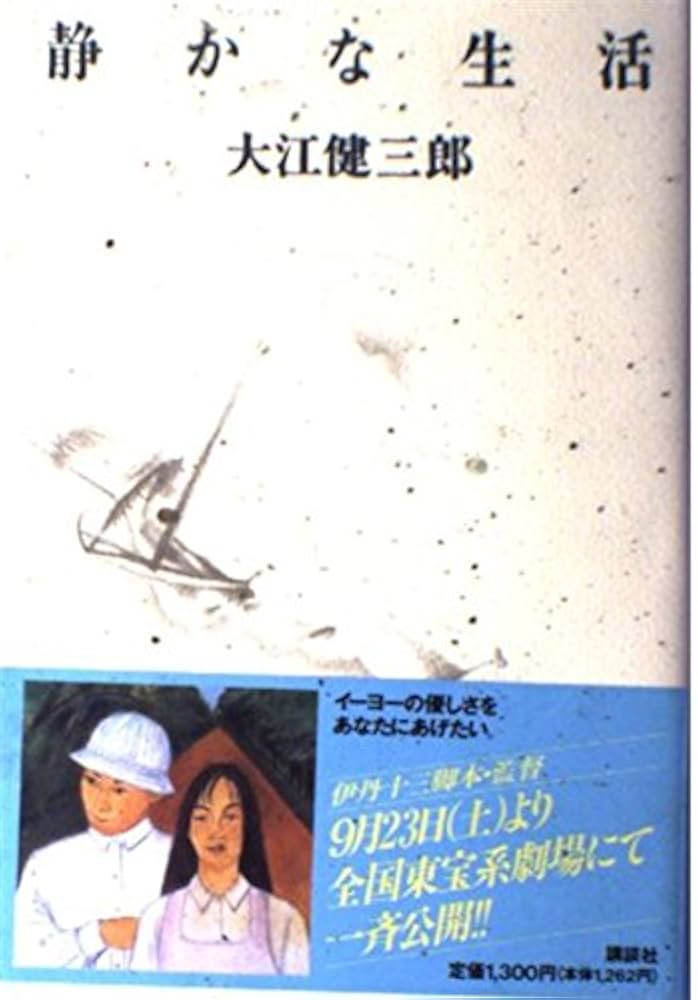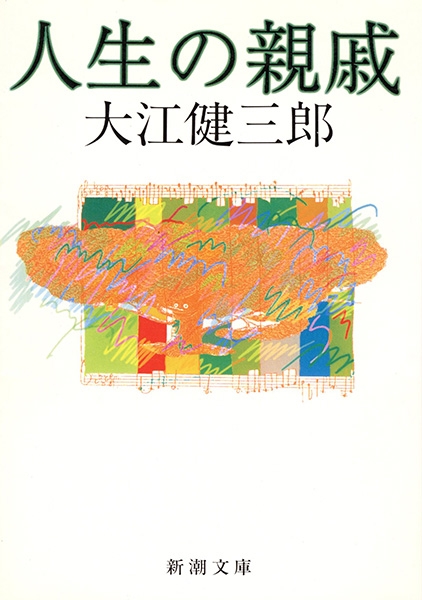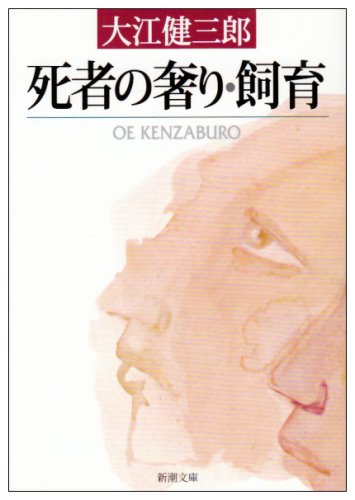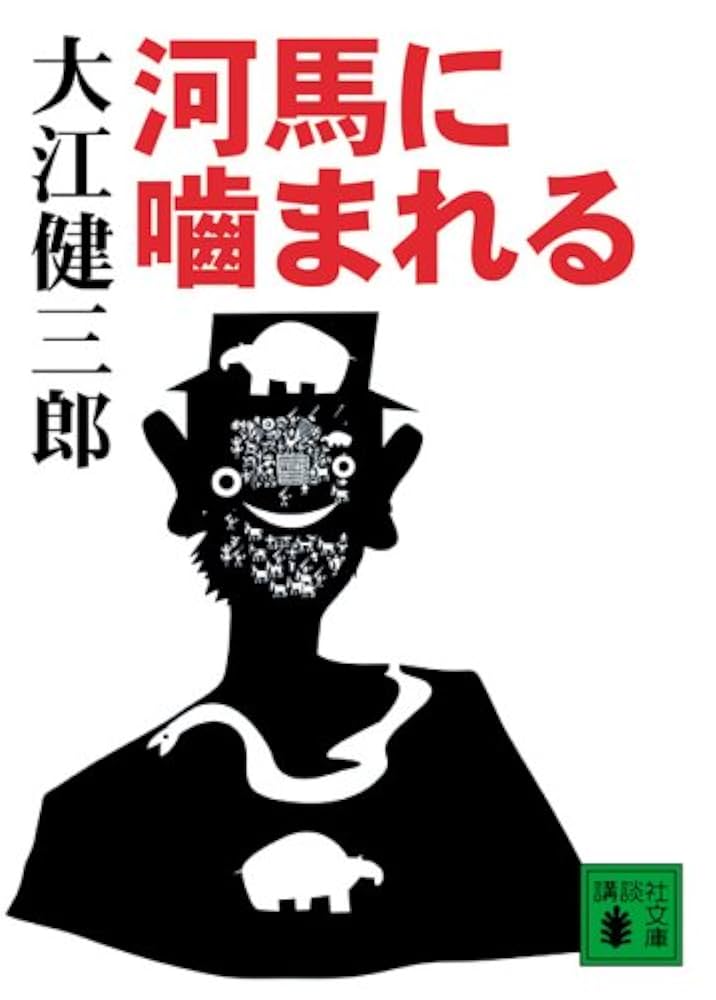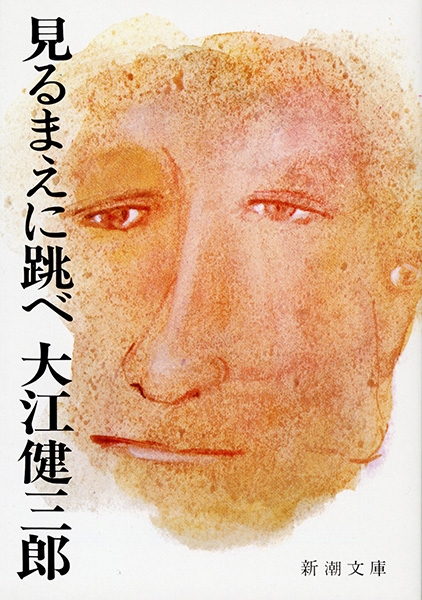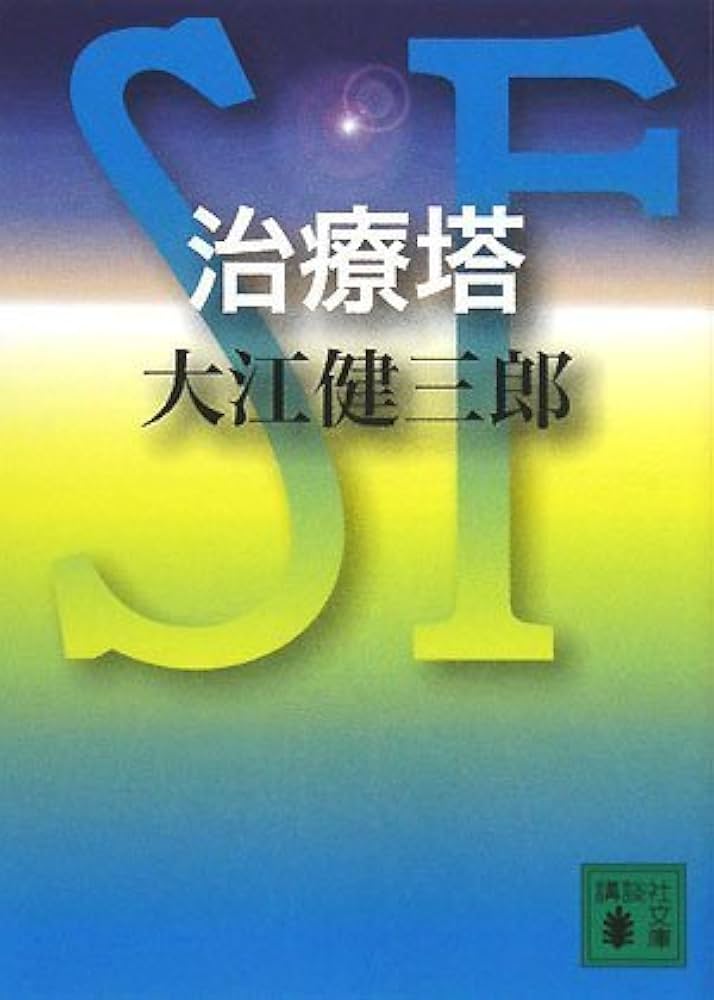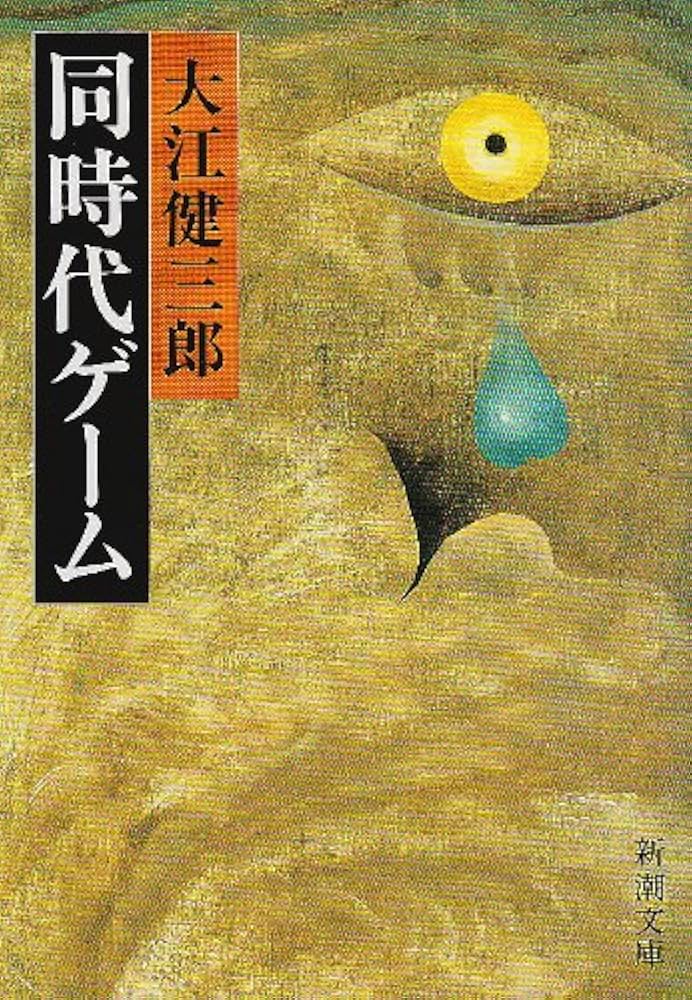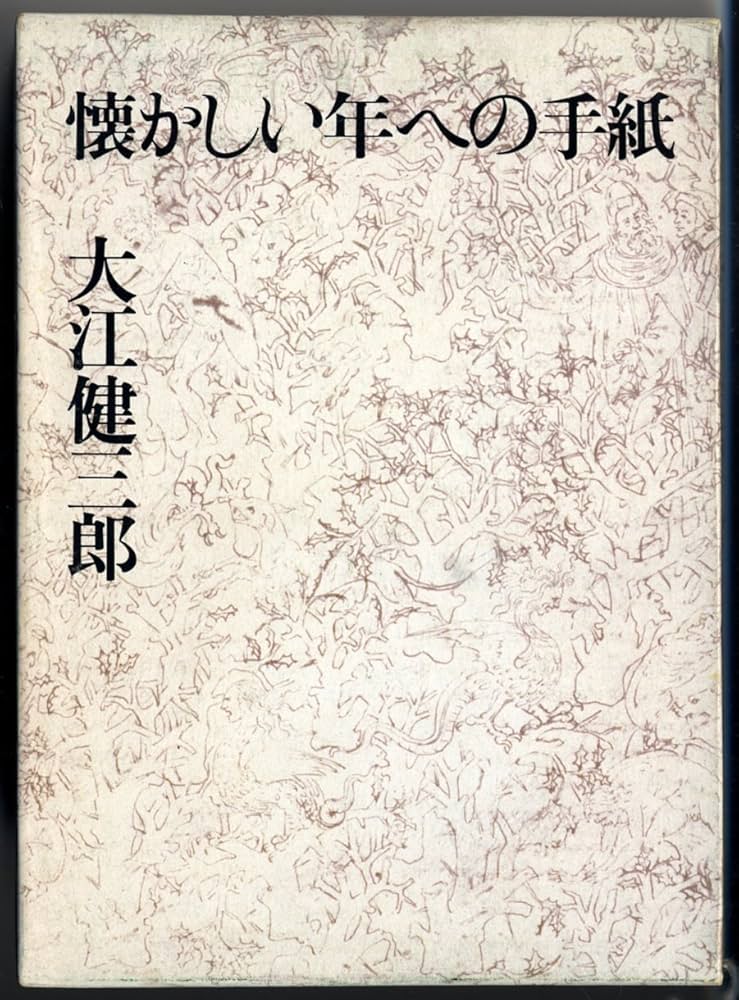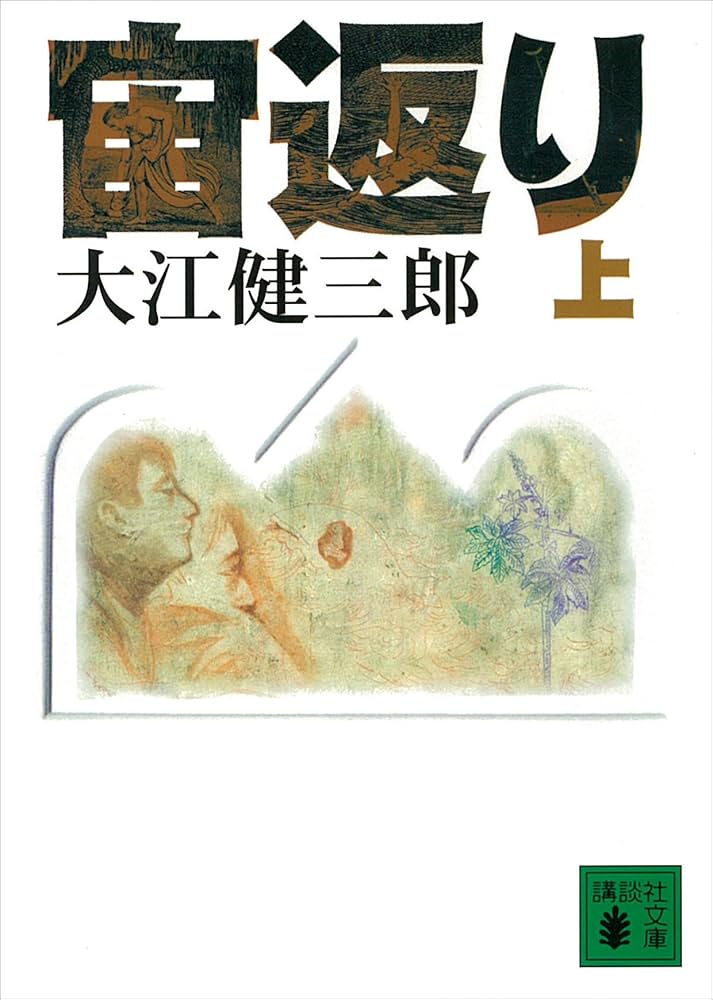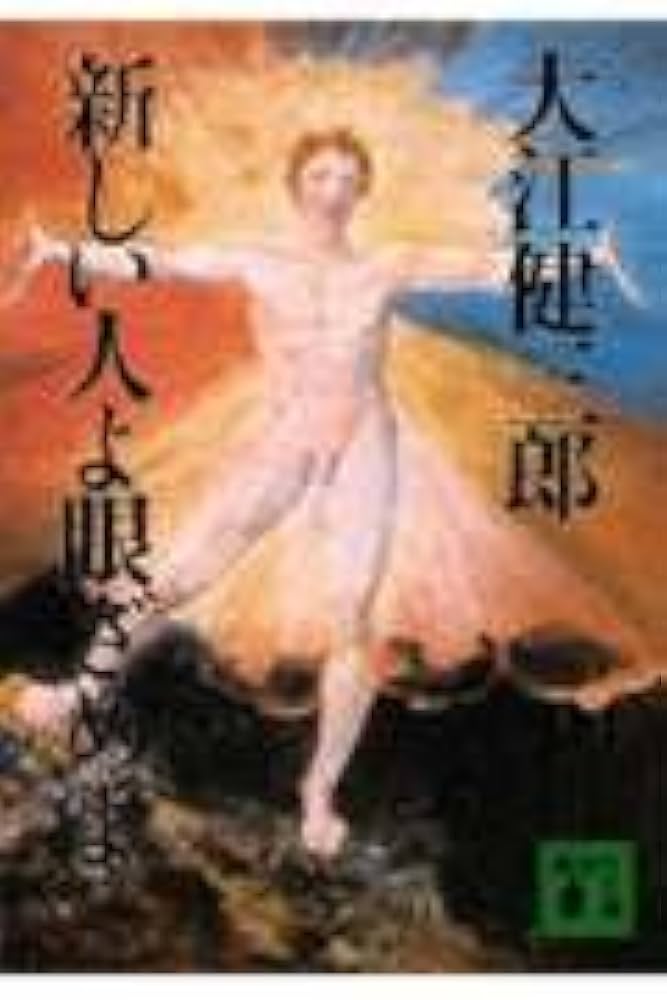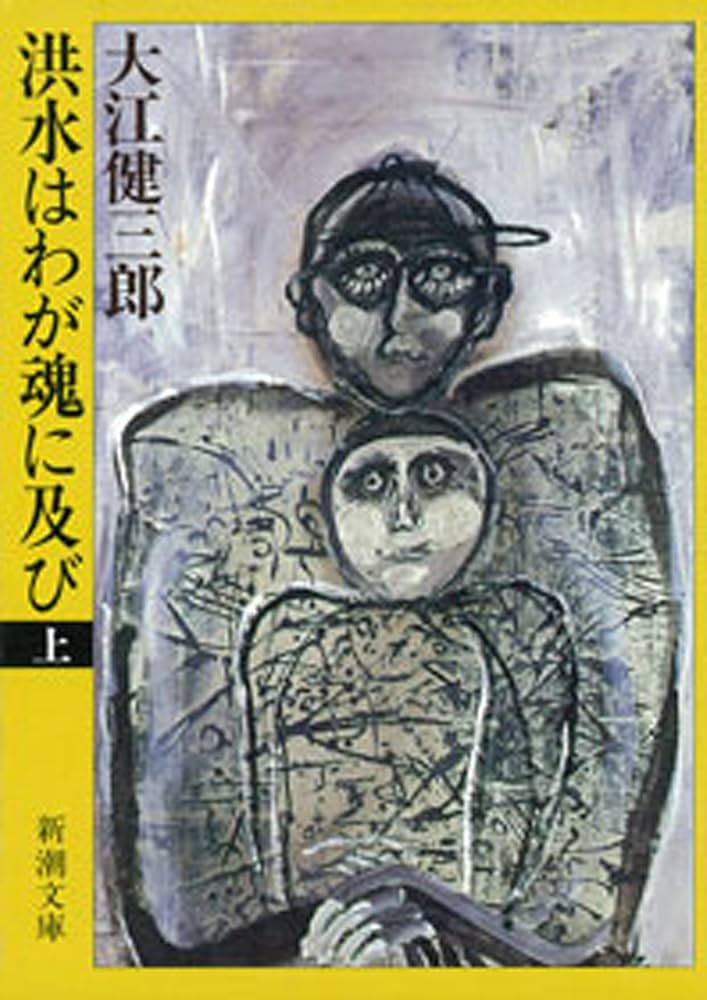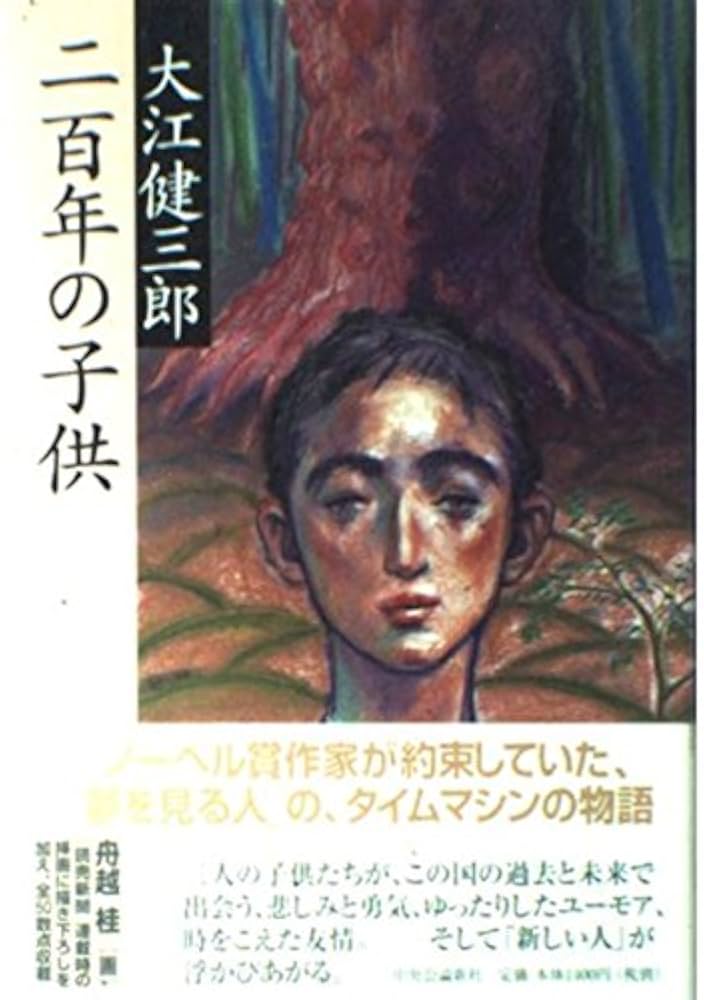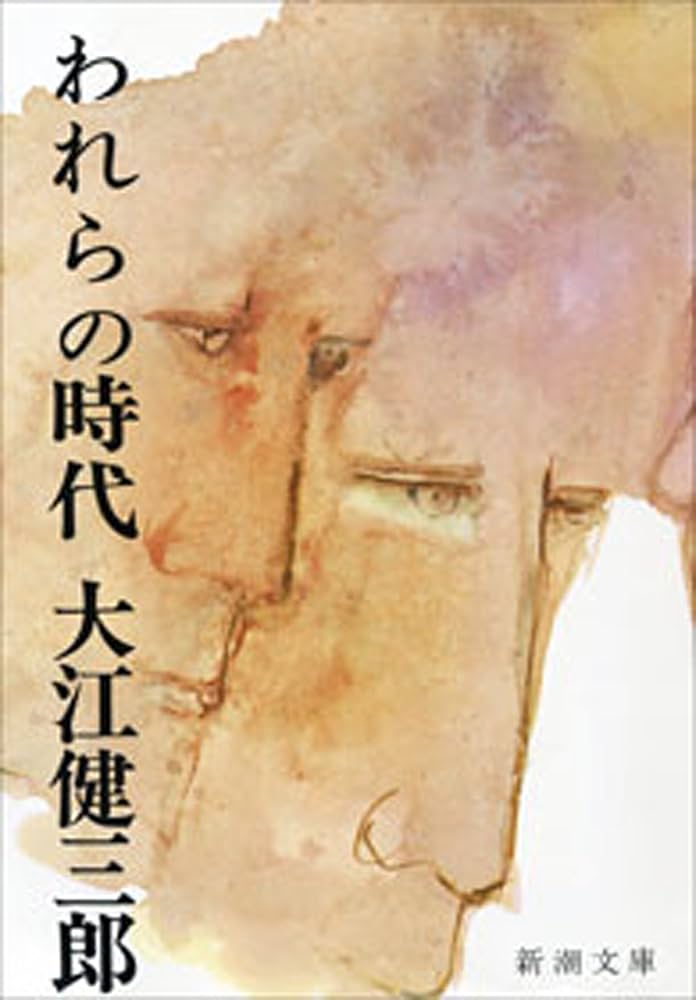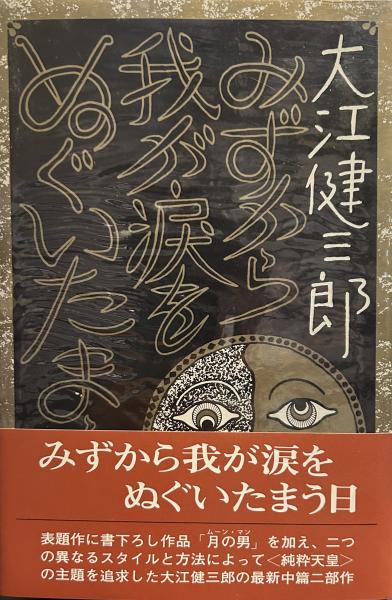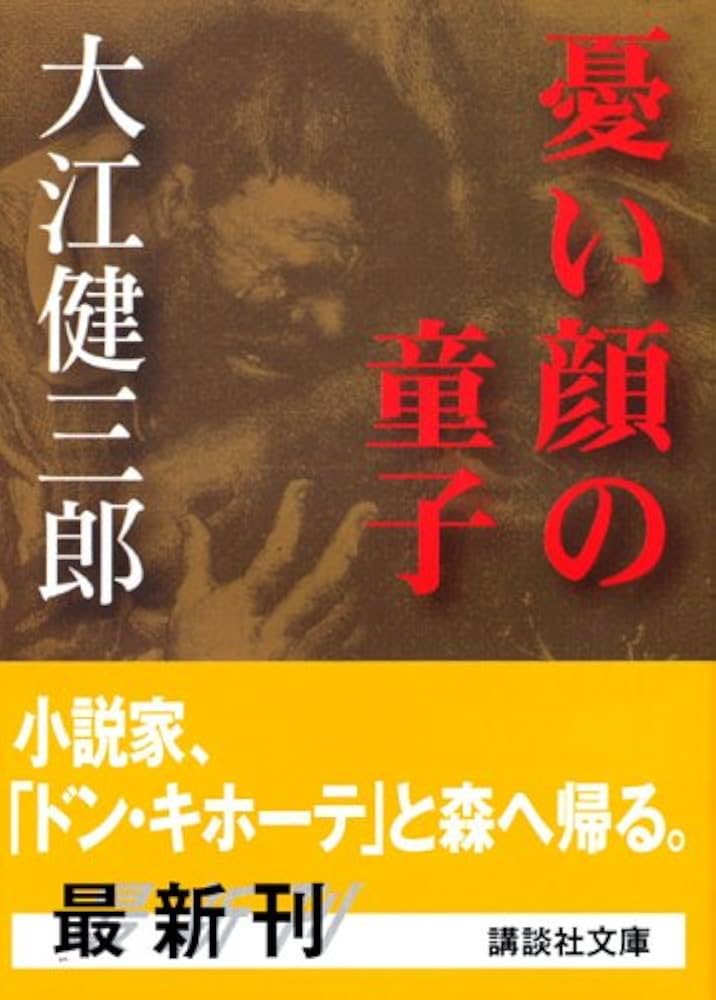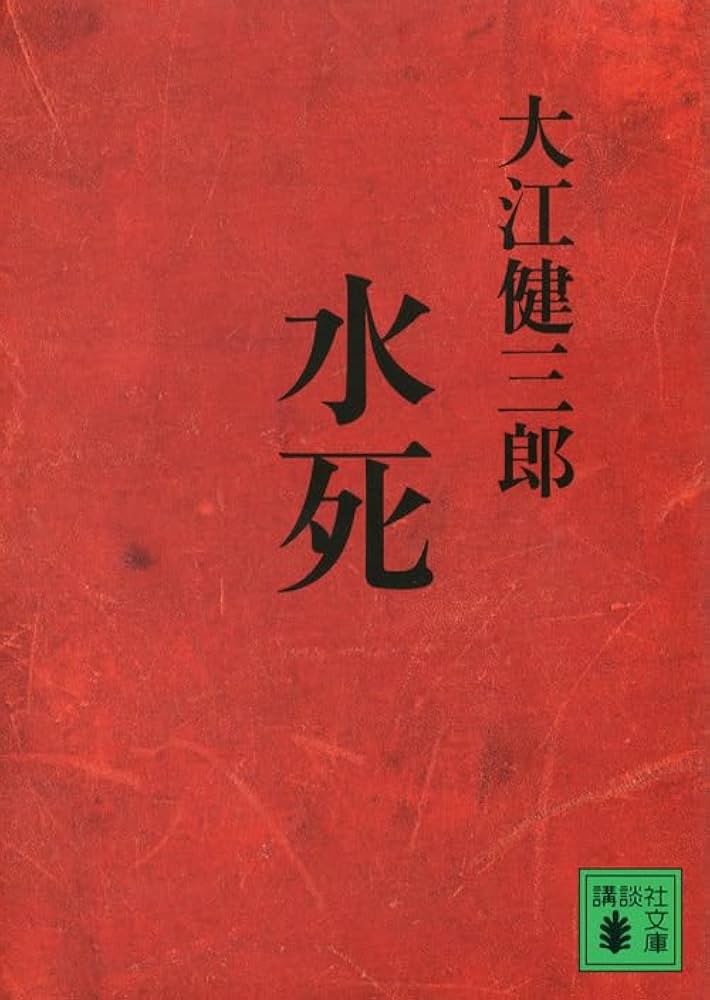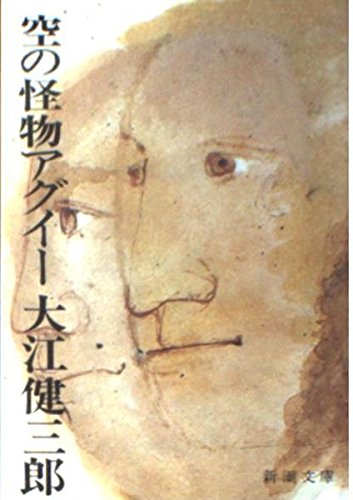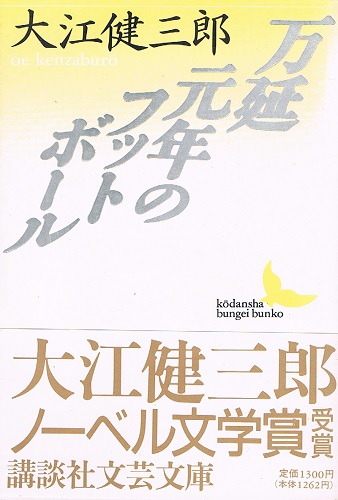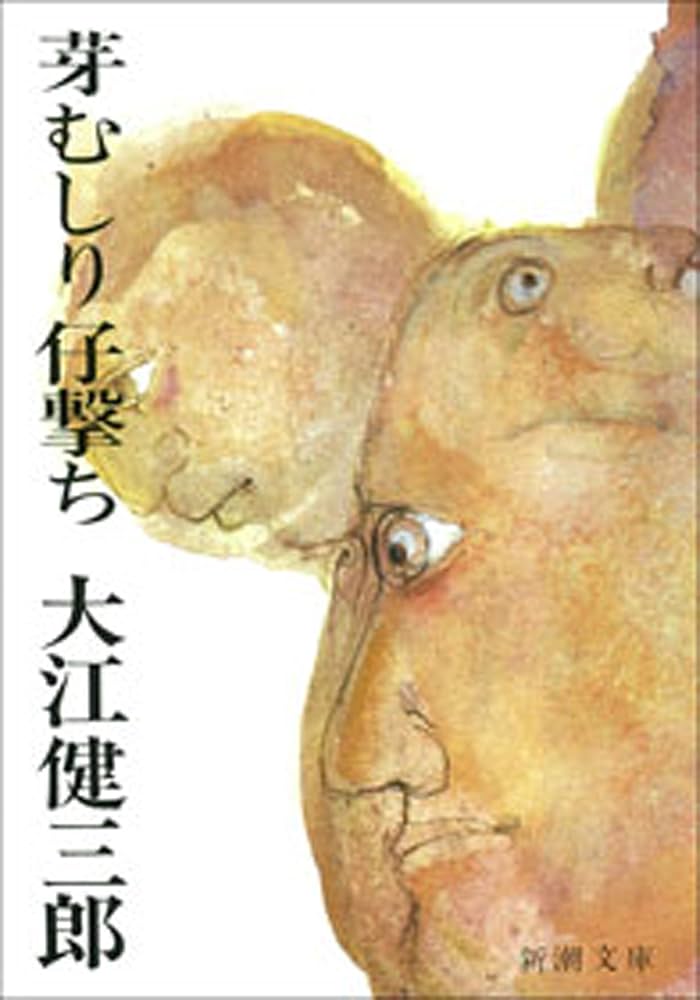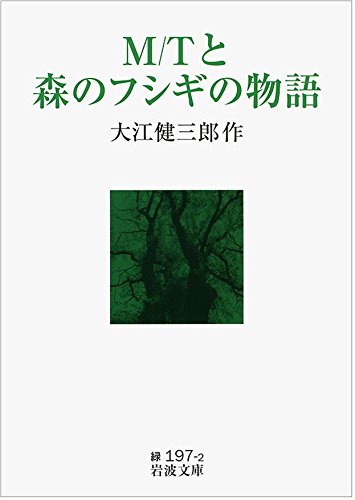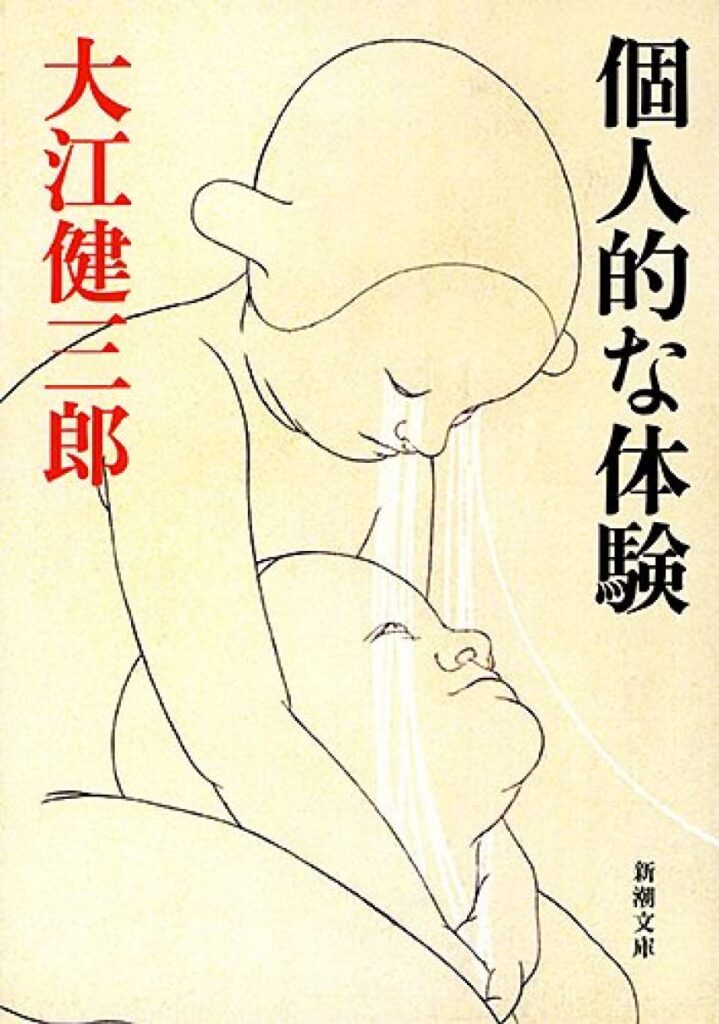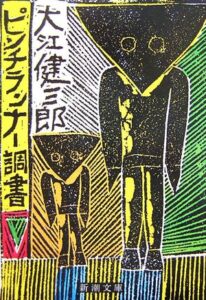 小説「ピンチランナー調書」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、1976年に発表された大江健三郎の長編小説で、核時代の閉塞感や政治的な陰謀といった重いテーマを扱いながらも、父と子の精神と肉体が入れ替わるという奇想天外な設定が特徴です。
小説「ピンチランナー調書」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、1976年に発表された大江健三郎の長編小説で、核時代の閉塞感や政治的な陰謀といった重いテーマを扱いながらも、父と子の精神と肉体が入れ替わるという奇想天外な設定が特徴です。
物語は非常に複雑な構造を持っており、知的障害を持つ息子の父親である「私」が、同じ境遇の持つ「森・父」という人物の体験を代筆するという形で進んでいきます。 この入れ子構造が、『ピンチランナー調書』という物語に独特の奥行きを与えています。
これから、この難解でありながらも非常に魅力的な『ピンチランナー調書』の世界を、あらすじからネタバレを含む深層まで、じっくりとご案内いたします。初めてこの作品に触れる方はもちろん、かつて読んだけれども再確認したいという方も、ぜひお付き合いください。
大江文学の中でも異色の輝きを放つ『ピンチランナー調書』。その核心に迫ることで、現代社会が抱える問題についても新たな視点が得られるかもしれません。それでは、物語の扉を開けていきましょう。
「ピンチランナー調書」のあらすじ
この物語の語り手は、知的障害を持つ息子の父親である「私」です。彼は、同じ特殊学級に子供を通わせる中で知り合った元原子力発電所技術者の「森・父」から、自らに起きた不思議な出来事を記録してほしいと頼まれ、彼のゴーストライターとして「調書」を作成することになります。 物語の大部分は、この森・父の一人称「おれ」の視点で語られていきます。
森・父はかつて、核物質を輸送中に『オズの魔法使い』のブリキの木こりのような姿をした謎の集団「ブリキマン」に襲われ、漏れ出たプルトニウムによって被曝した過去を持っています。 そしてある日、彼と息子の森に信じがたい出来事が起こります。「宇宙的な意思」によって、38歳の父と8歳の息子の年齢が入れ替わる「転換」が発生したのです。
父は18歳の若々しい青年に、そして知的障害があったはずの息子は28歳の知的な青年へと変貌を遂げました。 これまでとは完全に立場が逆転した親子は、地球の危機を救う「ピンチランナー」としての使命を自覚し、反原発の市民集会へ参加します。そこで彼らは、日本の裏社会で暗躍する巨大な陰謀へと巻き込まれていくことになるのです。
その陰謀の背後にいたのは、政財界を牛耳る右翼の黒幕「親方(パトロン)」でした。 親方は対立する二つの過激派組織にそれぞれ資金を提供して小型の原子爆弾を開発させ、両者を衝突させることでクーデターを起こそうと企てていました。 森親子は、この恐ろしい計画を阻止するため、様々な人々と協力しながら立ち向かっていきます。
「ピンチランナー調書」の長文感想(ネタバレあり)
『ピンチランナー調書』は、一度読んだだけでは全貌を掴むのが難しい、非常に多層的で複雑な物語です。しかし、その難解さの奥には、現代にも通じる鋭い問いかけと、人間存在の根源に迫るような深遠なテーマが隠されています。
まず、この小説の最も際立った特徴は、父と子の「転換」という設定でしょう。 知的障害を持つ息子を庇護する立場だった父親が、ある日突然、息子に導かれる若い肉体となる。この劇的な役割の逆転は、大江健三郎が一貫して描き続けてきた、障害を持つ子との共生というテーマを、全く新しい角度から描き出すことに成功しています。
守る側と守られる側という固定化された関係性が崩れ去った時、そこにどのようなコミュニケーションが生まれるのか。若返った父の戸惑いと、知的な青年へと変貌した息子の冷静な導きは、親子関係や人間関係の本質を私たちに問い直させます。
この奇抜な設定は、物語を単なる社会派小説に終わらせず、神話的な広がりを持たせるための重要な仕掛けとして機能しています。彼らは「宇宙的な意思」によって選ばれた「ピンチランナー」であり、その行動は個人的な動機を超えた、より大きな目的のためのものとして描かれます。
そして、物語の背景には1970年代という時代の空気が色濃く反映されています。核への恐怖、政治の季節の終焉、そして社会に漂う閉塞感。『ピンチランナー調書』は、そうした時代状況の中で、それでもなお希望を見出そうとする人々の格闘の記録でもあります。
物語の中心となるのは、右翼の黒幕「親方(パトロン)」が企てる陰謀です。対立する組織を裏で操り、混乱を引き起こして権力を掌握しようとする構図は、現実の政治の世界でも起こりうる恐ろしさを感じさせます。この陰謀に、転換した父子が立ち向かうという展開は、まるでヒーロー物語のようにも見えます。
しかし、大江健三郎は物語を単純な勧善懲悪にはしません。ここから先は物語の核心に触れる重大なネタバレを含みますので、ご注意ください。父子とその協力者たちは、ついに親方の潜む病院を突き止めます。国家を揺るがす巨大な悪の根源との対決に、読者の緊張は最高潮に達するでしょう。
ところが、彼らが対峙した黒幕の正体は、想像していたような怪物的な人物ではなく、ただの弱々しい老人でした。この巨悪の陳腐化ともいえる描写は、権力や悪というものの実態が、実は非常に空虚なものである可能性を示唆しています。この部分は、本作の大きなネタバレの一つです。
そして、物語は衝撃的な結末を迎えます。「宇宙的な意思」からの使命を帯びた息子・森は、もはや何の力も持たない老人を撲殺します。そして直後、彼は祭りの燃え盛る山車の中に自ら飛び込み、その命を絶つのです。
この自己犠牲的な結末は、一体何を意味するのでしょうか。ピンチランナーとしての使命を全うしたという達成感なのか、それとも巨大な悪と対峙し、それを滅ぼした後に残る虚無感なのか。この壮絶な結末は、簡単な解釈を許しません。これもまた、多くの読者に衝撃を与えるであろう『ピンチランナー調書』の重要なネタバレです。
悪を倒せば全てが解決するわけではない。むしろ、その先にある現実こそが、より厳しいものであるかもしれない。このビターな結末は、安易な希望を提示することを拒否し、読者一人ひとりに重い問いを投げかけます。
作中で多用される「哄笑」という表現も、この物語を理解する上で欠かせない要素です。絶望的な状況やグロテスクな現実を、登場人物たちはしばしば笑い飛ばします。これは、正気では耐えられないほどの過酷な現実を生き抜くための、一つの知恵であり、抵抗の形なのかもしれません。
『ピンチランナー調書』という作品は、父子の関係性を軸にしながらも、核、政治、障害、暴力といった様々な要素が複雑に絡み合っています。入れ子構造の文体も相まって、読解には確かに骨が折れます。
しかし、この物語が持つ熱量、そして現実の不条理に「哄笑」をもって立ち向かおうとする姿勢は、刊行から長い年月を経た今でも、私たちの心を強く揺さぶります。
特に、終盤のネタバレを含む展開は、読者の倫理観や価値観を根底から揺さぶる力を持っています。なぜ森は老人を殺し、そして自ら死を選ばなければならなかったのか。この問いについて考え続けること自体が、『ピンチランナー調書』を読むという体験の核心なのかもしれません。
この物語は、私たちに明確な答えを与えてはくれません。ただ、父と子の奇妙な冒険譚を通して、世界の複雑さと、その中で生きることの困難さ、そして、それでもなお存在するかもしれないかすかな希望の光を示してくれるのです。
『ピンチランナー調書』は、まさしく読む者の知性と感性に挑戦してくる一冊です。その挑戦を受け止め、物語の深部まで潜り込んだとき、私たちはかつてない読書体験を手にすることができるでしょう。
まとめ:「ピンチランナー調書」のあらすじ・ネタバレ・長文感想
この記事では、大江健三郎の長編小説『ピンチランナー調書』について、あらすじからネタバレを含む感想までを詳しく見てきました。父と子の精神と肉体が「転換」するという奇抜な設定から始まるこの物語は、私たちを現実と虚構が入り混じる迷宮のような世界へと誘います。
物語の前半では、反原発運動をきっかけに、日本の裏側でうごめく巨大な陰謀に巻き込まれていく父子の姿が描かれます。荒唐無稽とも思える展開の中に、1970年代の日本の社会状況が色濃く反映されており、そのリアリティに引き込まれます。
そして、ネタバレを含む後半では、黒幕である「親方」との対決と、その後の衝撃的な結末が待っています。巨悪の陳腐さと、使命を終えた主人公が選ぶ自己犠牲的な最期は、単純な勧善懲悪では割り切れない、この世界の複雑さを突き付けてきます。
『ピンチランナー調書』は、決して分かりやすい物語ではありません。しかし、その難解さの先に、人間存在の根源を問うような深い思索が広がっています。この作品が投げかける問いと向き合うことは、現代を生きる私たちにとっても、非常に価値のある体験となるはずです。