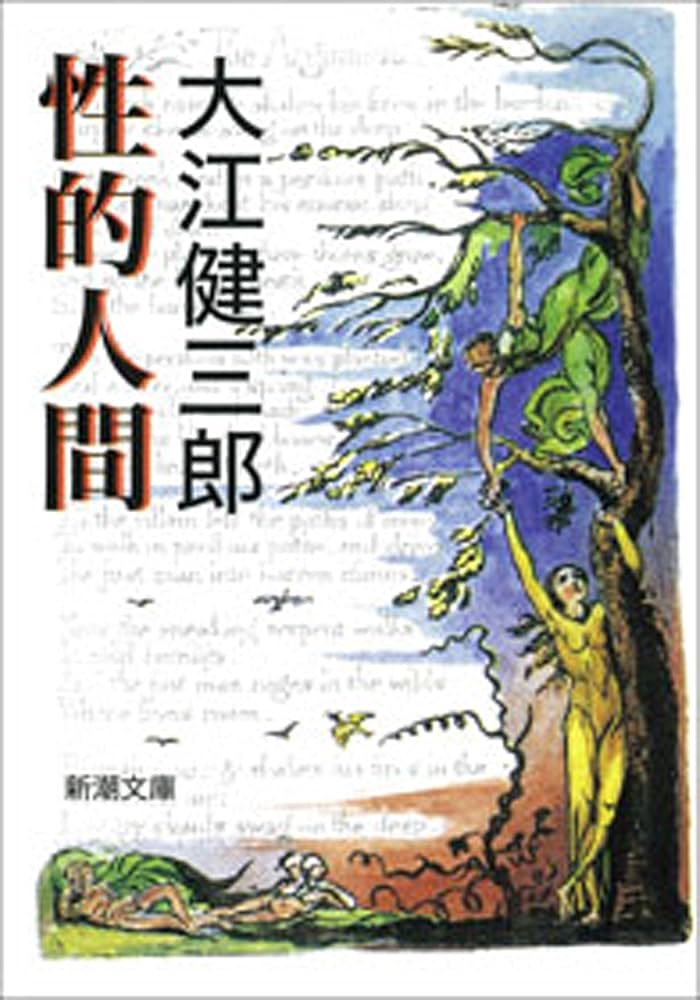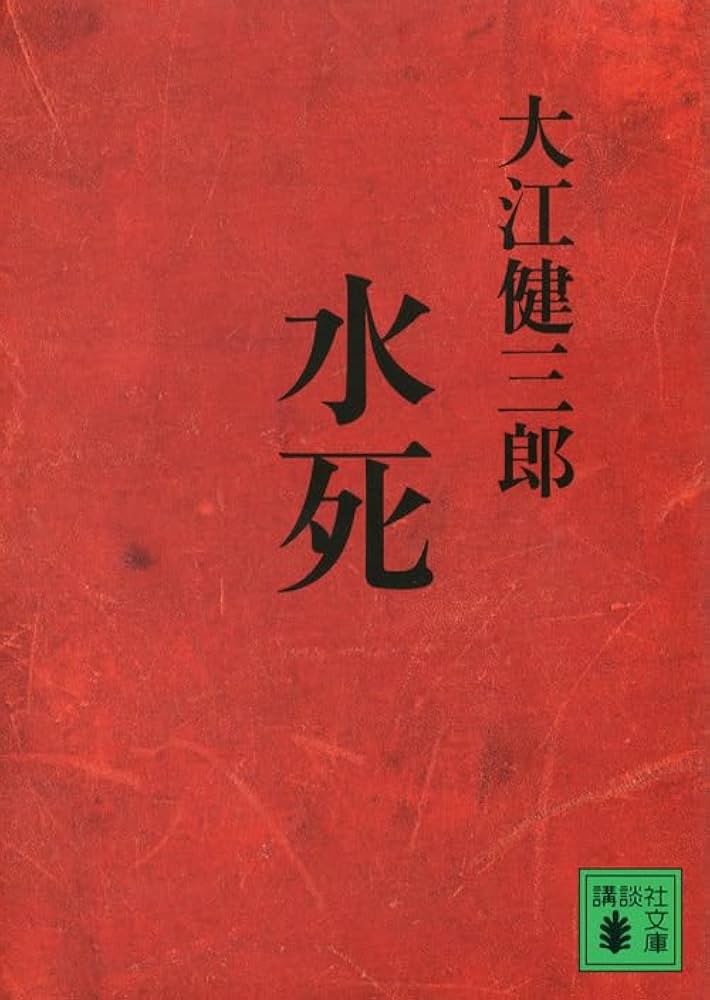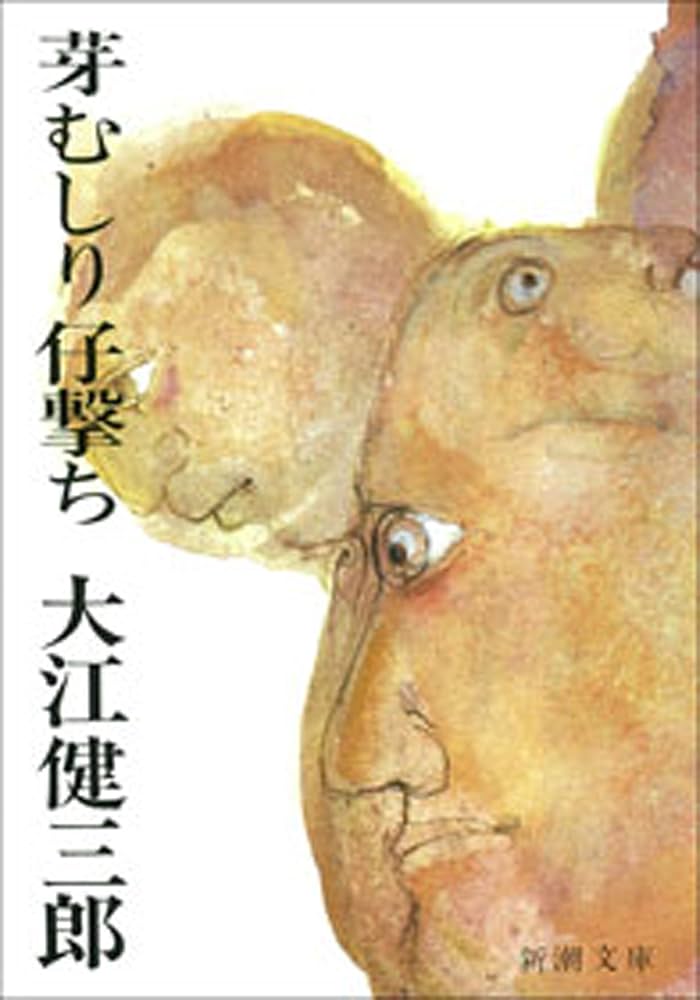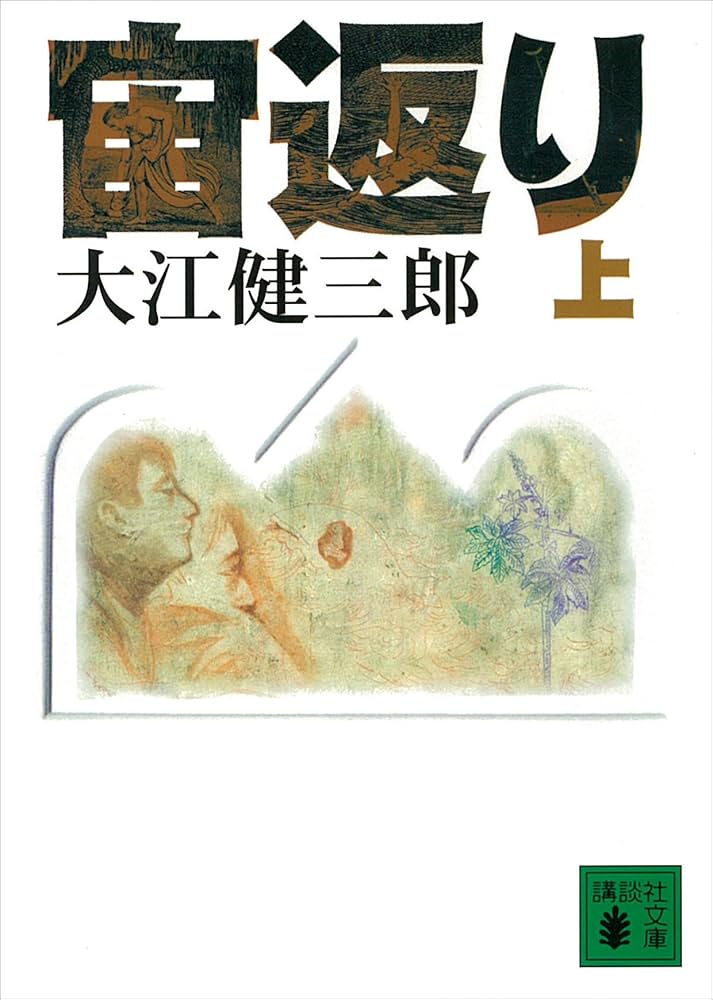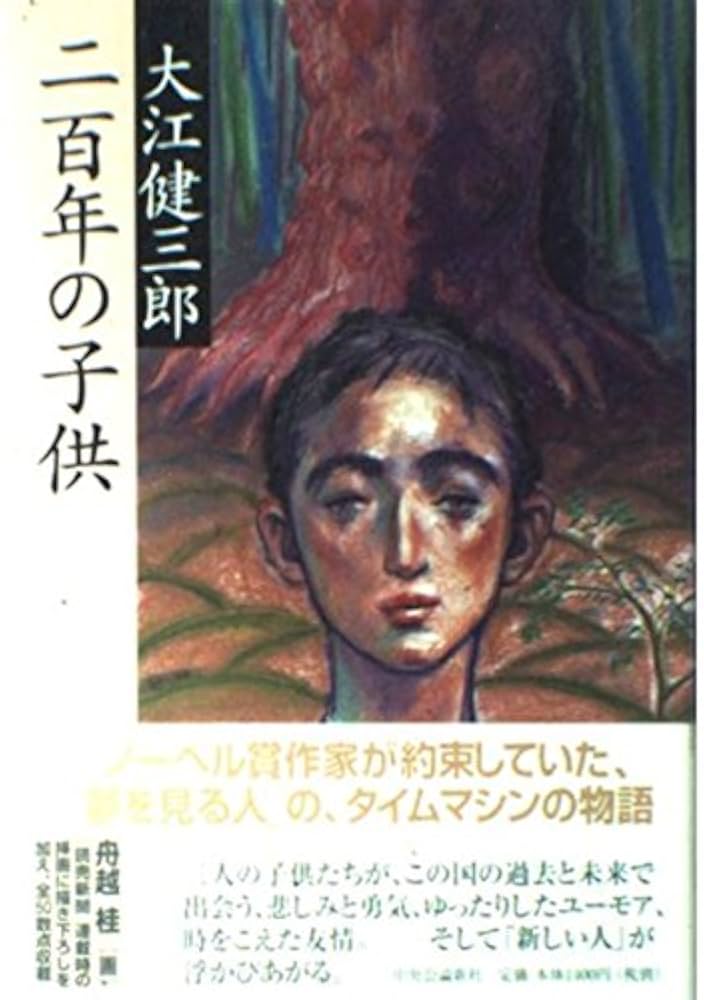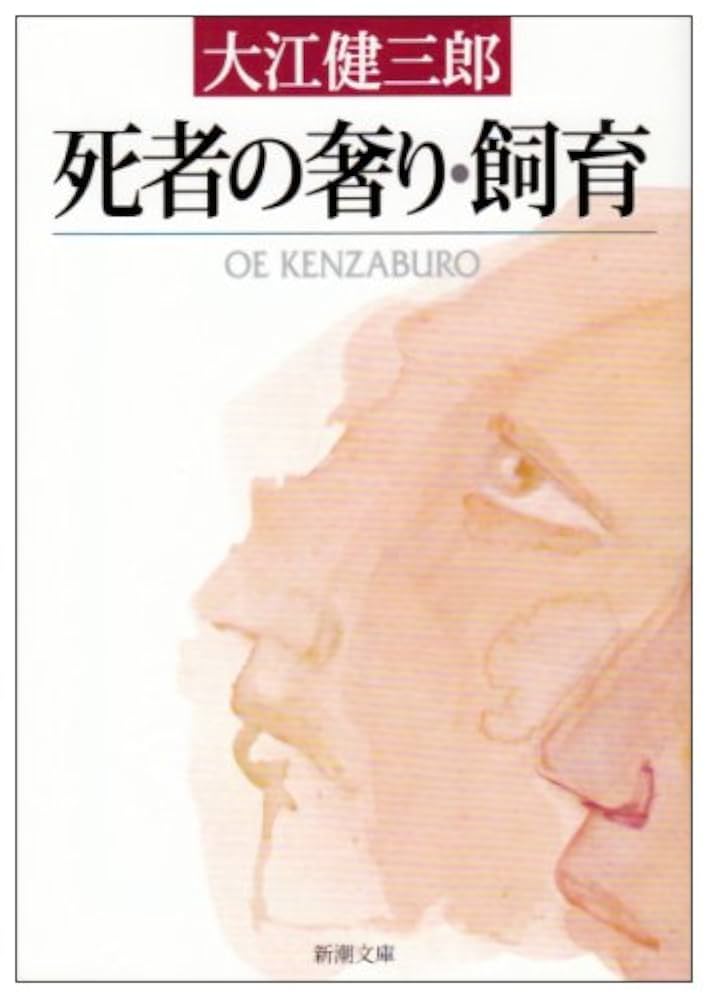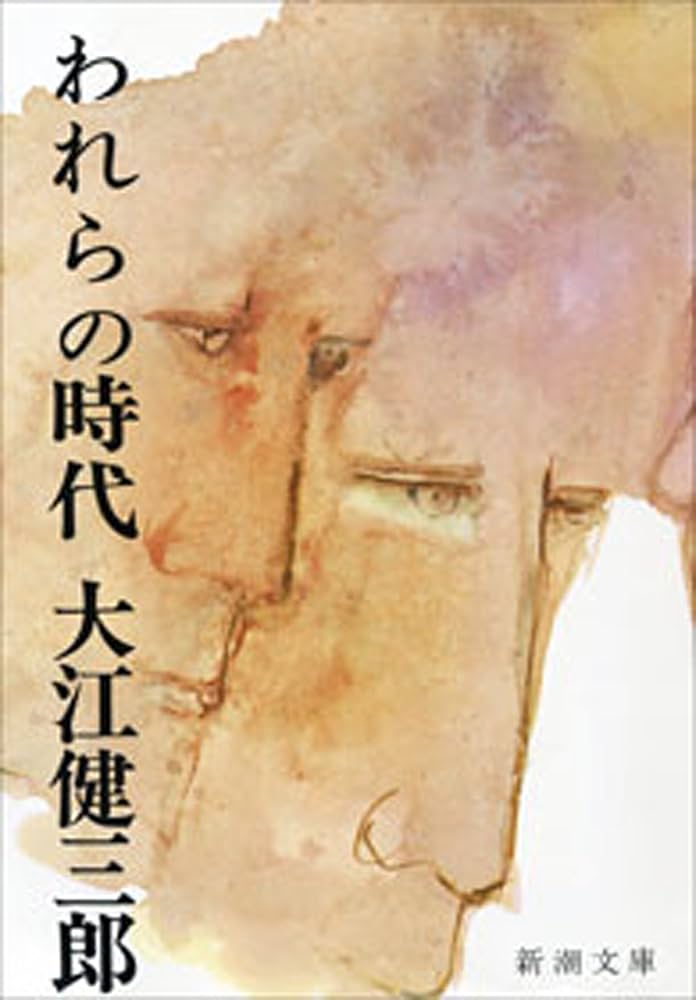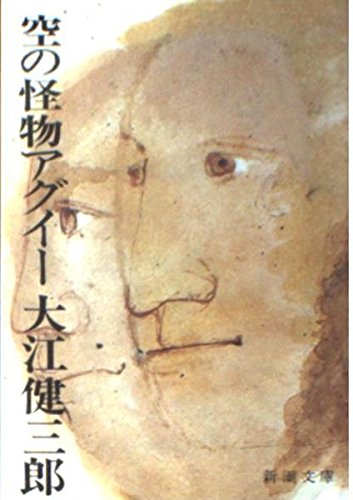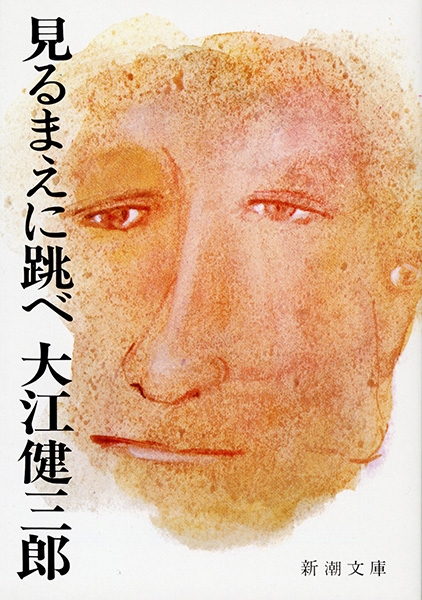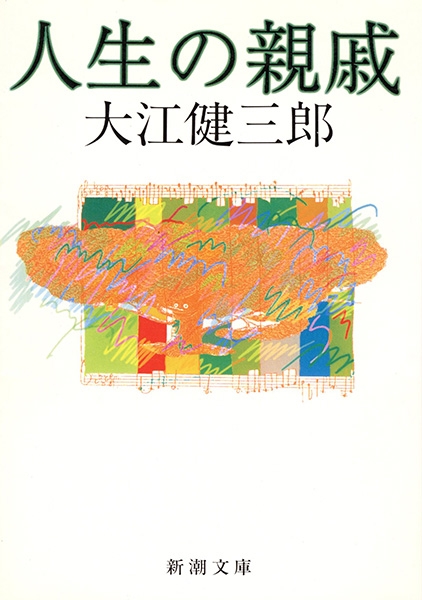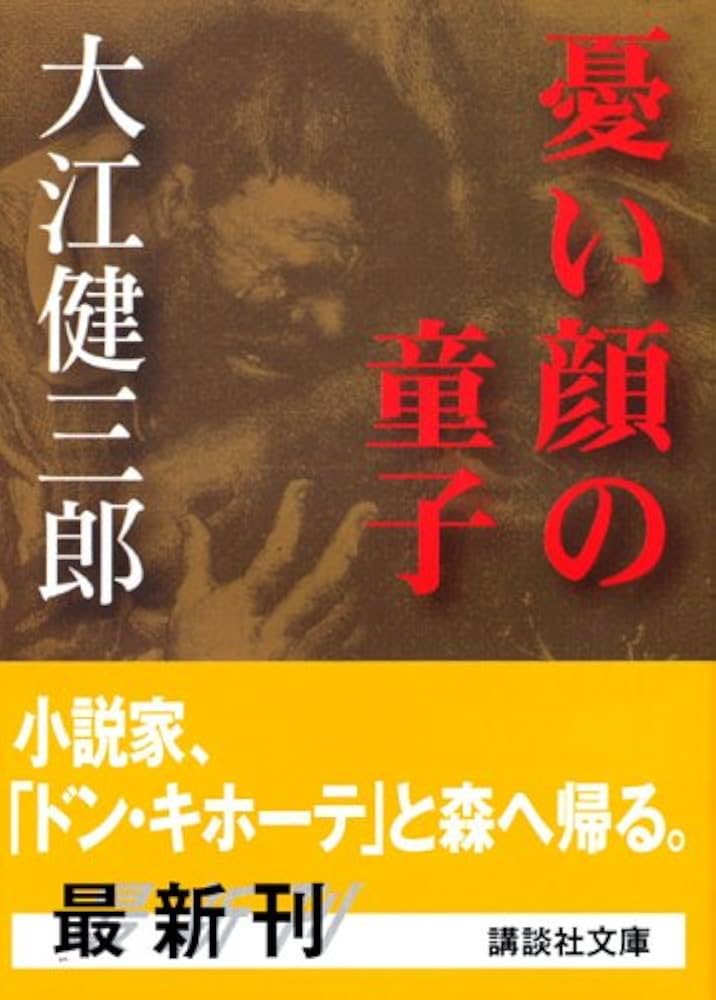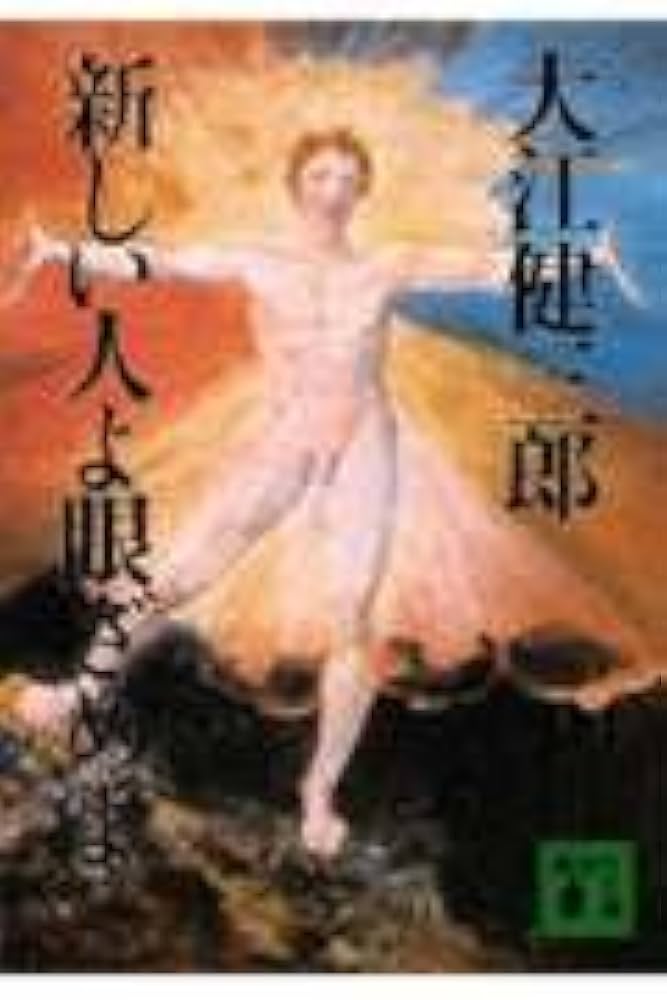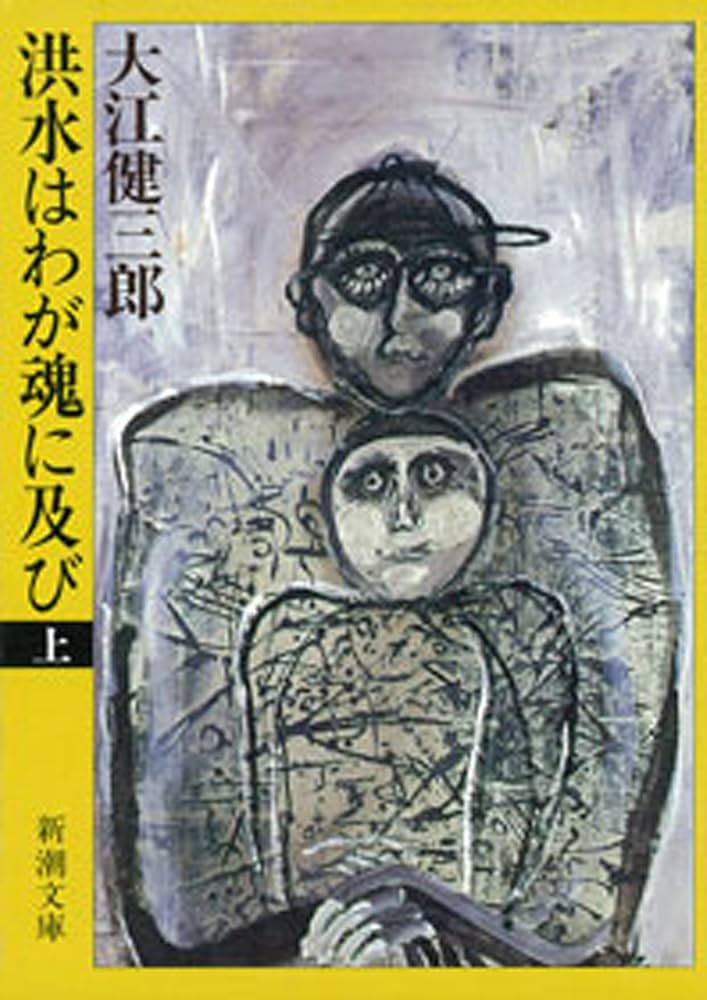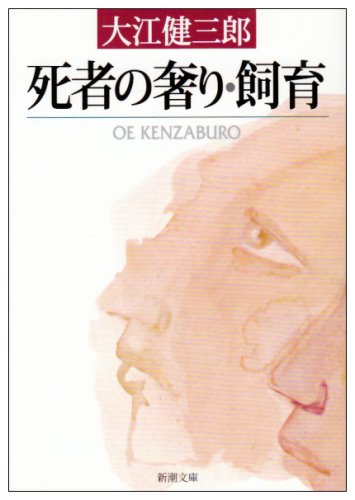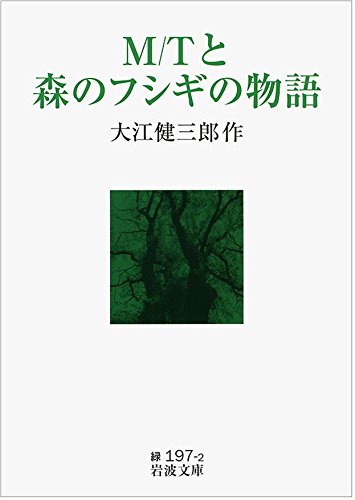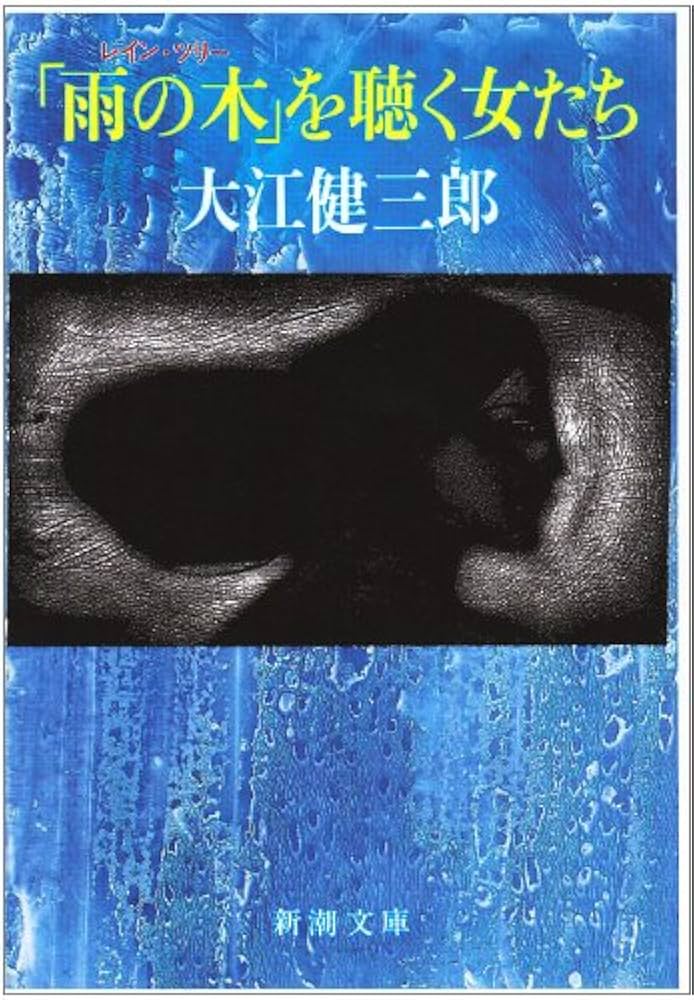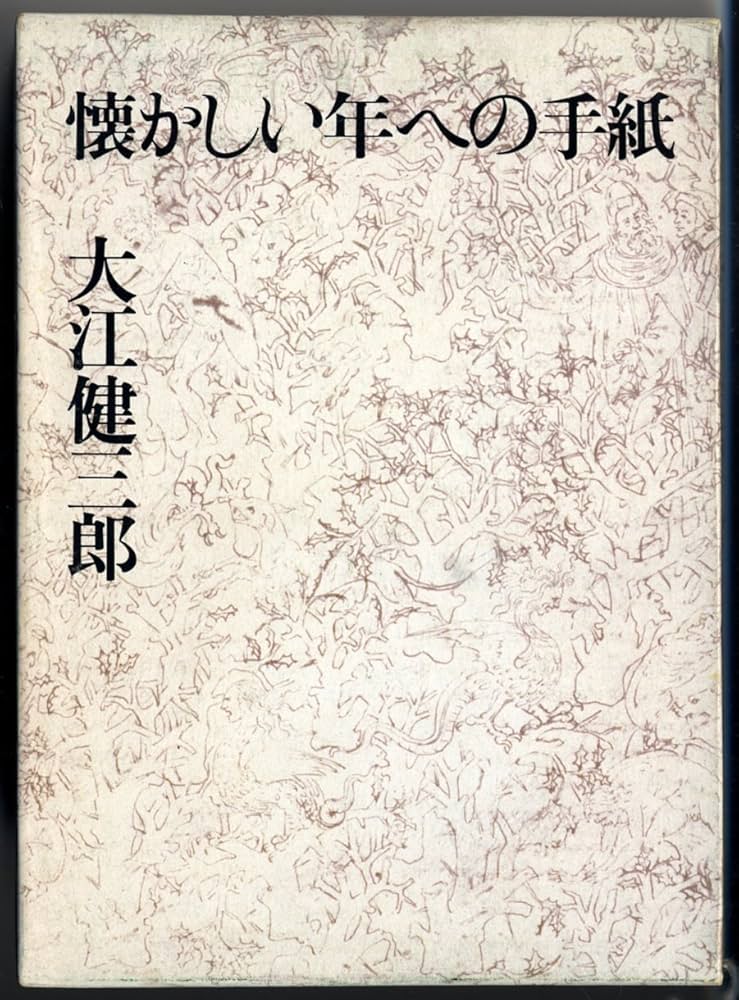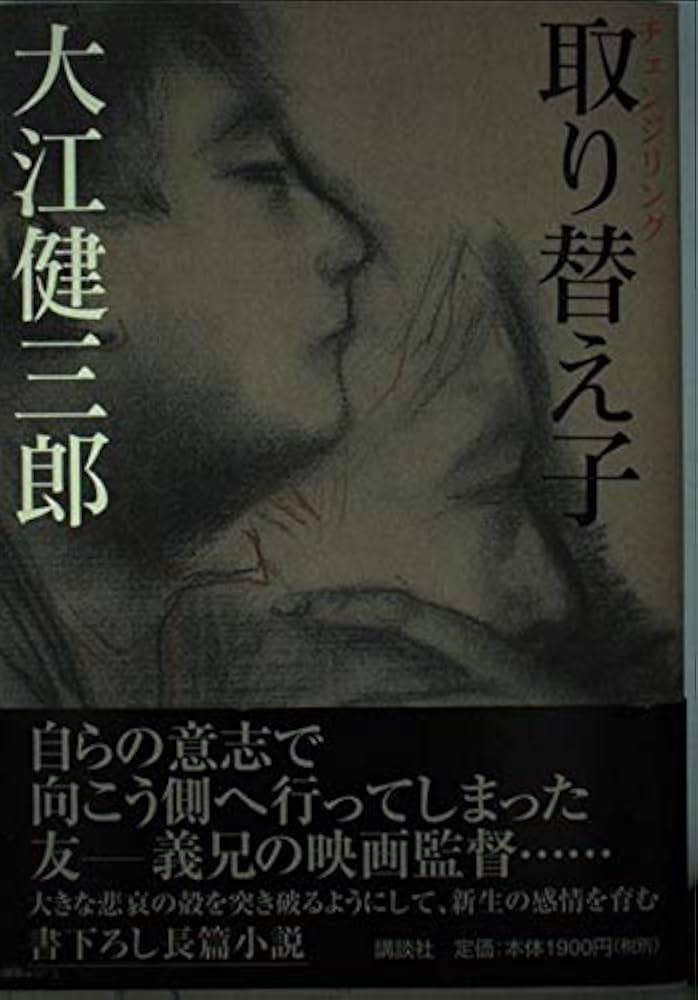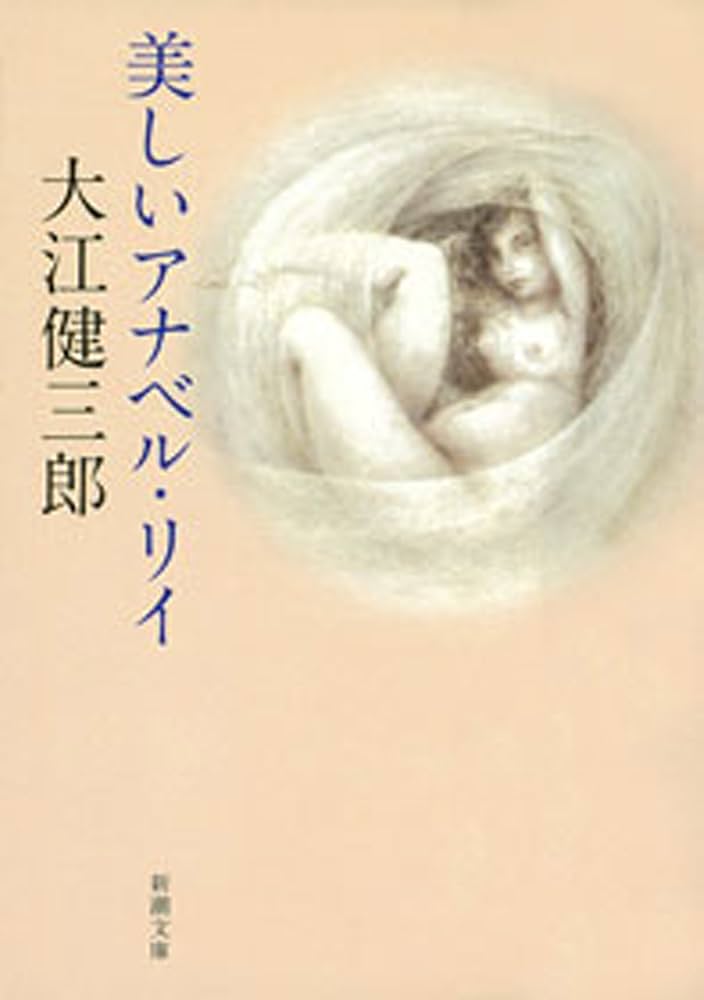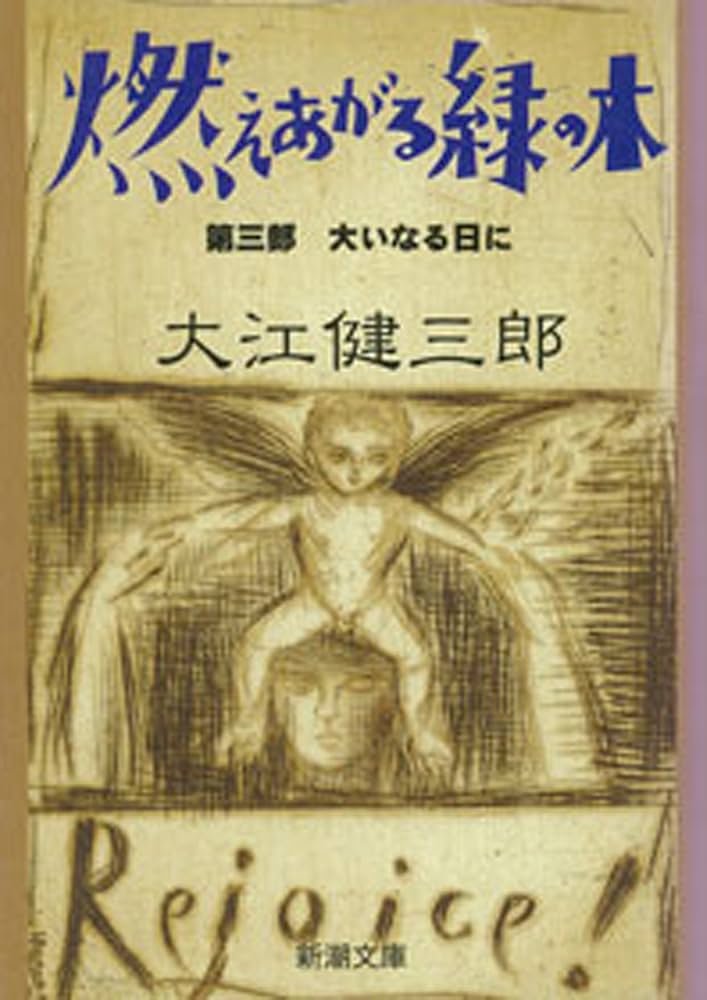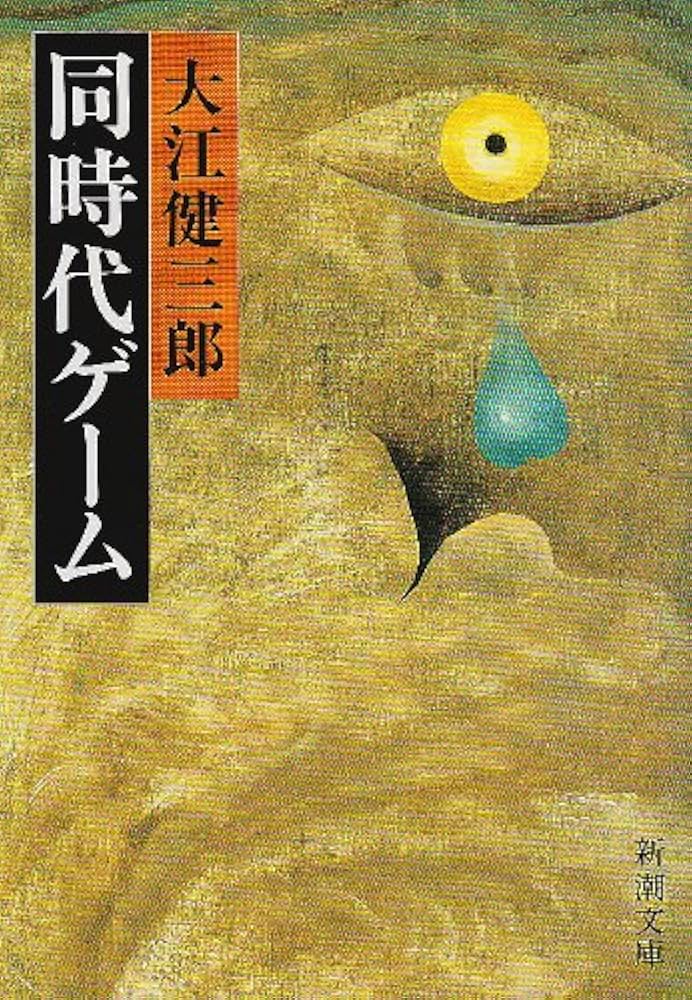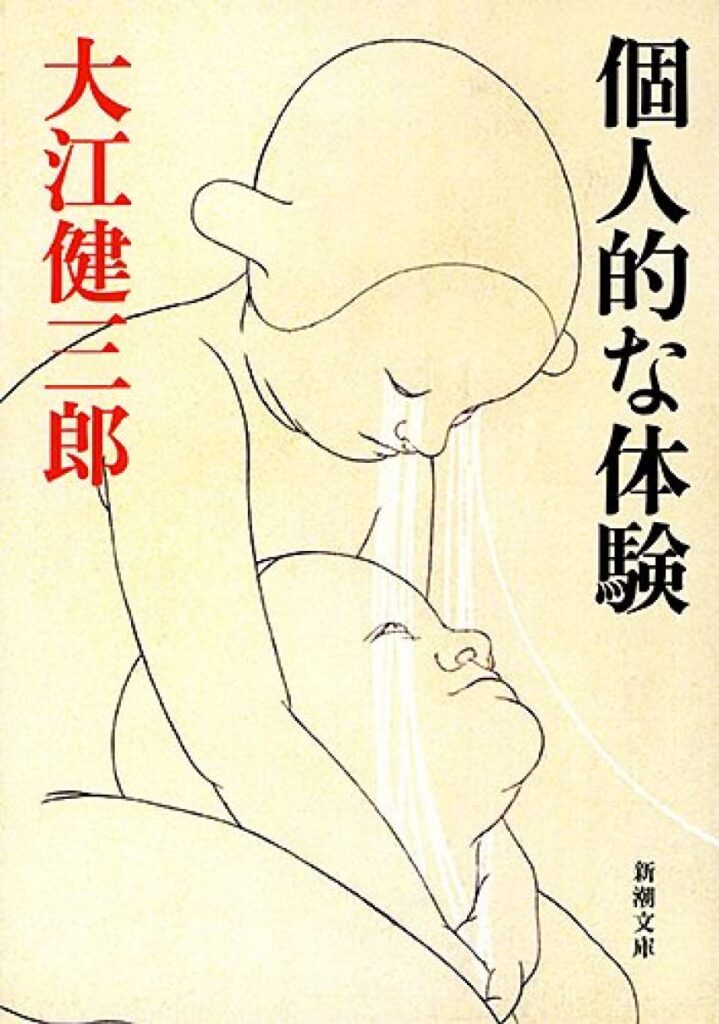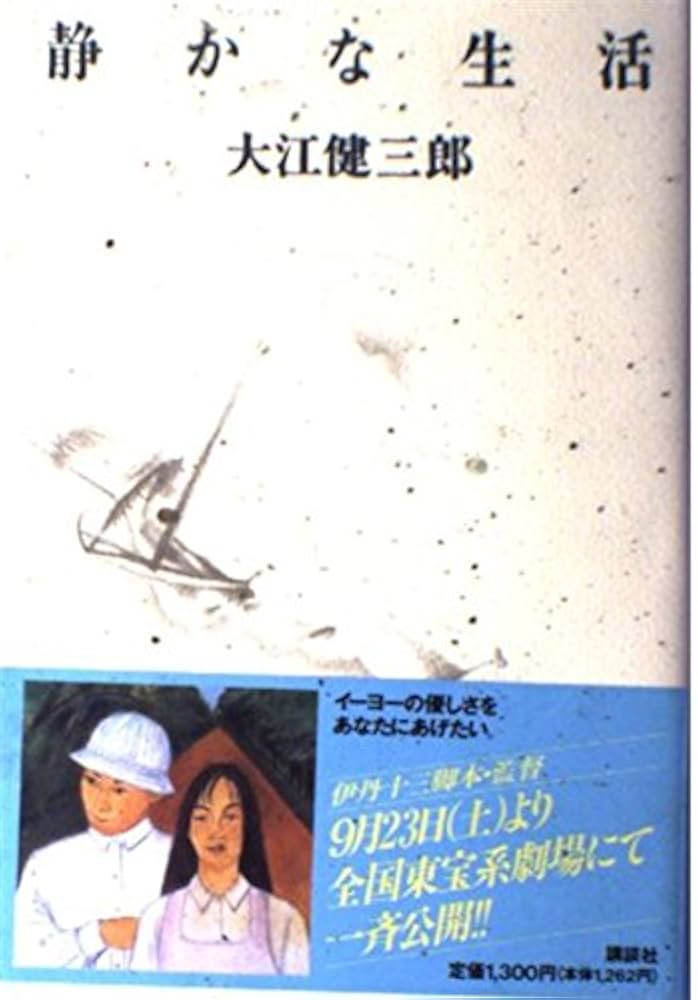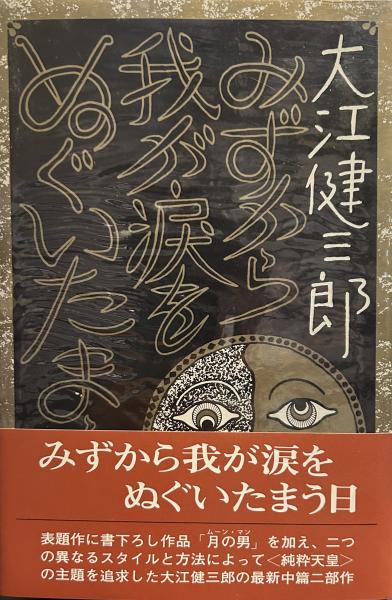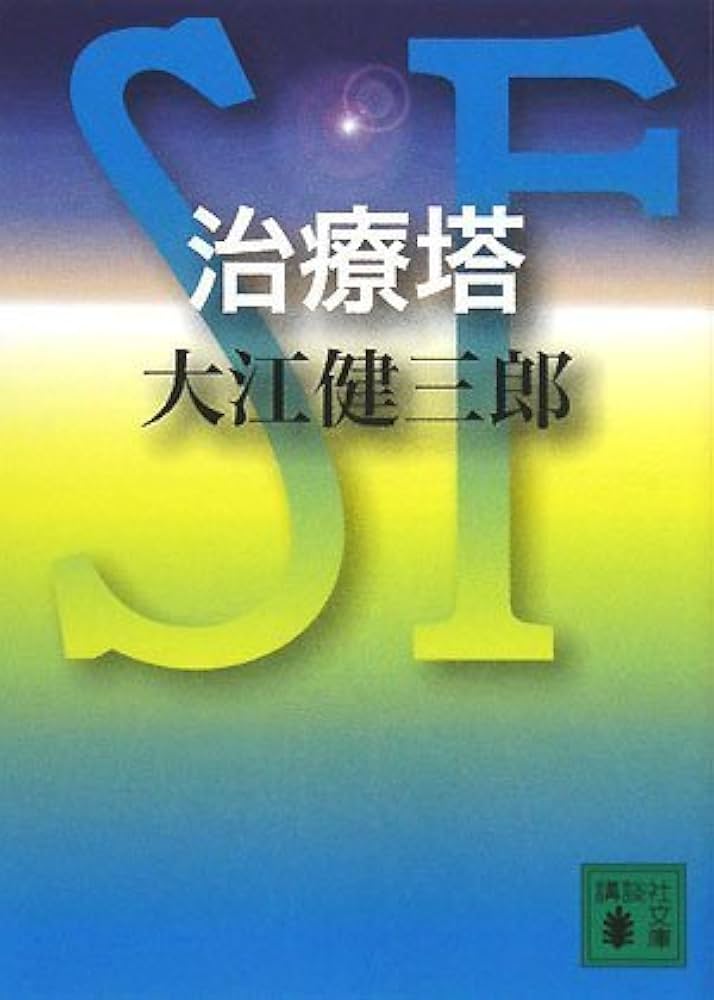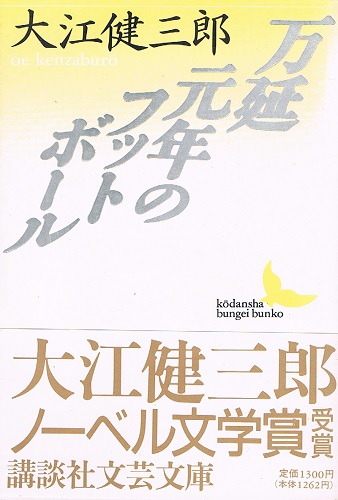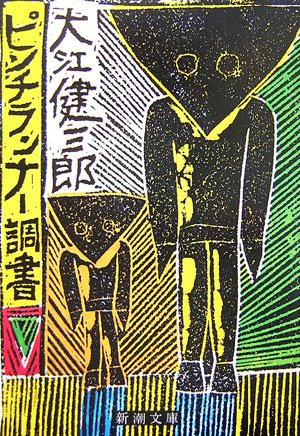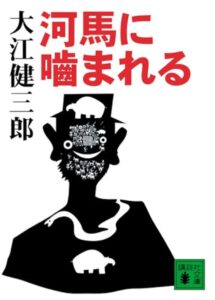 小説「河馬に噛まれる」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、単なる連作短編集という枠組みを超えて、読者の心に深く、そして静かに問いを投げかけてくる力を持っています。大江健三郎氏が描く世界は、時として難解に感じられるかもしれませんが、その奥底には人間の魂の救済という、普遍的なテーマが横たわっているのです。
小説「河馬に噛まれる」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、単なる連作短編集という枠組みを超えて、読者の心に深く、そして静かに問いを投げかけてくる力を持っています。大江健三郎氏が描く世界は、時として難解に感じられるかもしれませんが、その奥底には人間の魂の救済という、普遍的なテーマが横たわっているのです。
物語の核心に触れると、連合赤軍事件という、日本の戦後史における極めて痛ましい出来事が主題の一つとして扱われています。しかし「河馬に噛まれる」は、社会的な事件をただなぞるだけの作品ではありません。むしろ、その事件に巻き込まれた個人の内面に深く分け入り、極限状況における人間の精神のありようを、鮮烈に描き出しています。
これから語る内容は、物語の結末にも触れるネタバレを含みますので、もしご自身で読み解きたいとお考えの方はご注意ください。それでも、この「河馬に噛まれる」という作品が持つ重層的な魅力を、少しでも多くの方と共有できればと願っています。それでは、物語の世界へ一緒に分け入っていきましょう。
この記事では、「河馬に噛まれる」がなぜこれほどまでに読む者の心を揺さぶるのか、その理由をじっくりと探っていきます。単に物語の筋道を追うだけでなく、そこに込められた思想や、登場人物たちの魂の軌跡を丹念にたどることで、この作品の真価に迫りたいと考えています。
「河馬に噛まれる」のあらすじ
作家である「僕」のもとに、かつて世話になった女性から一通の手紙が届くところから物語は始まります。その手紙の内容は、彼女の息子についての相談でした。彼は17歳の時に、まるで「穴ぼこに落ちる」ように連合赤軍事件に関与してしまい、現在は獄中にいるというのです。「僕」は彼女の依頼を受け、その青年と手紙のやり取りを始めることになります。
この青年は、かつてアフリカで河馬に噛まれたという特異な経験から、「河馬の勇士」というあだ名で呼ばれていました。彼は、山岳ベースで起きた凄惨なリンチ事件の渦中にいながら、便所掃除という役割を担うことで生き延びた過去を持っていました。しかし事件後、刑務所での生活の中で、彼は生きる意欲そのものを失いかけていたのです。
「僕」は「河馬の勇士」との文通を通じて、彼が抱える心の闇や、事件が残した深い傷跡に触れていきます。同時に、「僕」自身の内面にも、この青年との交流を通じて様々な思索が生まれてきます。連合赤軍事件という歴史的な悲劇と、個人の魂の救済という問題が、二人の手紙の中で交錯していくのです。
物語は、この中心的な交流を軸としながら、いくつかの独立した短編が響き合う形で構成されています。リンチ事件で命を落とした若者の姉の視点や、作家である「僕」自身の日常、特に障害を持つ息子との生活などが織り交ぜられ、物語は重層的な深みをもって展開していきます。読者はこれらの断片的な物語を通して、事件の全体像と、そこに翻弄された人々の姿を多角的に見つめることになります。
「河馬に噛まれる」の長文感想(ネタバレあり)
大江健三郎氏の「河馬に噛まれる」は、読む者に覚悟を求める作品だと言えるでしょう。連合赤軍事件という、あまりにも重く、痛ましい歴史を扱いながら、物語は安易な感傷や断罪に流れることを一切拒否します。そこにあるのは、極限状況に置かれた人間の魂が、どのようにして尊厳を保ち、あるいは失っていくのかという、冷徹とも言えるほどの深い洞察です。
この物語の根幹をなしているのは、T.S.エリオットの「河馬」という詩です。詩の中では、泥の中にどっしりと横たわる醜い河馬と、岩の上に立つ「真の教会」が対比的に描かれます。しかし、詩の結末で翼を得て天に昇るのは、俗世の象徴である河馬の方であり、教会は地上に取り残されるのです。大江氏はこの構造を巧みに取り入れ、「教会」を連合赤軍のような組織や理念の象徴として描き出します。
そして、その「教会」の論理からこぼれ落ち、泥の中でもがきながらも生き延びようとする存在が、「河馬の勇士」と名付けられた青年なのです。彼は、組織のために仲間を粛清し、自らも死ぬという「教会」の論理を拒絶します。彼の「自分は河馬のほうがいいよ。苦しい所を、なんとかみっともなく生き延びた河馬がいいね」という言葉は、この物語の核心を突くものです。これこそが、この作品が提示する重要なネタバレと言えるでしょう。
この言葉は、いかなる高尚な理念や組織の大義名分も、個人の「生」を踏みにじることは許されないという、作者の強いメッセージとして響きます。山岳ベースでのリンチという狂気の中で、彼は便所掃除をすることで生き延びました。その行為は、傍から見れば決して英雄的なものではないかもしれません。しかし、そのみっともなさの中にこそ、生きることへの根源的な肯定が宿っているのです。
一方で、リンチで亡くなった青年の姉「ほそみ」は、妹の死が含まれる「教会」という理念の側に、それでもなお留まろうとします。彼女の存在は、「河馬の勇士」とは対照的な魂のあり方を読者に示します。悲劇的な結末を迎えたとしても、その死に意味を与えようとする彼女の姿は、また一つの人間の真実として描かれており、物語にさらなる奥行きを与えています。
「河馬に噛まれる」は、主人公である作家「僕」の私小説的な側面も色濃く反映されています。彼が「河馬の勇士」との交流を通して深めていく思索は、そのまま作者である大江健三郎氏自身の思索と重なります。特に、障害を持つ息子との日常が織り込まれることで、社会的な事件と極めて個人的な体験とが結びつき、独自の文学世界を構築しています。
この物語は、明確な結末や救いを提示してはくれません。読み終えた後に残るのは、ずっしりとした問いの重みです。しかし、それは決して絶望的なものではありません。「河馬の勇士」が体現する、泥にまみれても生き延びる「河馬」の姿に、私たちはかすかな、しかし確かな希望の光を見出すことができるのです。
この作品は、連作短編集という形式をとっています。中心となる四つの物語の間に、テーマを共有する別の短編が挟み込まれる構成は、まるで多重露光の写真のように、連合赤軍事件という一つの被写体を様々な角度から照らし出します。この手法によって、読者は事件を立体的に捉え、その複雑な様相をより深く理解することができるのです。
「河馬に噛まれる」という、一度聞いたら忘れられないタイトルもまた、秀逸です。文字通り、青年が河馬に噛まれたというエピソードに由来する一方で、それは理不尽な暴力や、抗いようのない巨大な力に翻弄される人間の姿を象徴しているようにも思えます。私たちは皆、人生において何らかの「河馬」に噛まれる可能性を秘めているのかもしれません。
この作品のネタバレをさらに深めるならば、それは「赦し」というテーマにも触れなければならないでしょう。「河馬の勇士」は、仲間を死に至らしめた組織の中にいながら、直接手を下すことはありませんでした。しかし、そのことに対する彼の罪悪感は計り知れないものがあります。彼が生き延びたことを、誰が赦すことができるのか。物語は、その問いを静かに投げかけます。
そして、その問いは巡り巡って、読者自身にも向けられます。私たちは、歴史の悲劇をどう受け止め、どう語り継いでいくべきなのか。他者の罪を、あるいは自らの罪を、どのように見つめれば良いのか。「河馬に噛まれる」は、そうした根源的な問いへと私たちを導いていくのです。
大江氏の文体は、緻密で、思弁的であり、時に粘り強い思考の軌跡をそのまま文章にしたかのようです。しかし、その文章を丹念に追っていくと、人間の魂の最も深い場所にある喜びや悲しみ、そして希望といった感情が、静かに、しかし鮮やかに浮かび上がってきます。
この物語が発表されたのは1985年ですが、そのテーマは現代においても全く色褪せることがありません。組織と個人の関係、理念の暴走、そしていかにして「よく生きるか」という問いは、いつの時代にも通じる普遍的な課題です。むしろ、社会が複雑化し、様々な分断が生まれている現代にこそ、「河馬に噛まれる」は読まれるべき作品なのかもしれません。
物語の終盤、「僕」は「河馬の勇士」との交流を通じて、自らの内なる「魂の危機」と向き合うことになります。歴史的な悲劇と個人の苦悩が共鳴し合う瞬間です。この共鳴こそが、大江文学の真骨頂と言えるでしょう。遠い世界の出来事が、自分の問題として生々しく迫ってくる感覚を、多くの読者が体験するはずです。
この感想の核心的なネタバレとして、もう一度「河馬」の詩に立ち返りたいと思います。天に昇った河馬は、聖人たちに迎え入れられ、黄金の竪琴を奏でます。一方で、岩の上に立つ「真の教会」は、瘴気の霧に包まれたまま地上に取り残されるのです。これは、組織の論理を超えた個人の魂の救済を高らかにうたったものに他なりません。
「河馬に噛まれる」は、この詩に託された思想を、小説という形で壮大に、そして繊細に描ききった作品です。みっともなく、格好悪くとも、ただひたすらに「生きる」こと。その営みの中にこそ、人間の最も尊い価値があるのだと、この物語は静かに語りかけてきます。
もしあなたが、日々の生活の中で何かしらの閉塞感や、生きることの困難さを感じているのなら、ぜひ「河馬に噛まれる」を手に取ってみてください。この物語は、簡単な答えを与えてはくれません。しかし、あなたの魂の深い部分に触れ、明日を生きるための静かな力を与えてくれるはずです。それこそが、文学が持つ本来の力なのだと、私は信じています。
まとめ:「河馬に噛まれる」のあらすじ・ネタバレ・長文感想
この記事では、大江健三郎氏の連作短編集「河馬に噛まれる」について、あらすじから結末のネタバレを含む深い感想までを述べてきました。この作品は、連合赤軍事件という重い歴史を背景に持ちながらも、その中心にあるのは個人の魂の救済という普遍的なテーマです。
物語の核心は、T.S.エリオットの詩「河馬」に託された思想にあります。組織や理念を象徴する「教会」よりも、泥にまみれながらも生き延びる「河馬」の側に立つこと。いかなる大義名分のもとであっても、個人の生が踏みにじられてはならないという強いメッセージが、作品全体を貫いています。
主人公の「僕」と、凄惨な事件を生き延びた「河馬の勇士」との手紙のやり取りを通じて、歴史的な悲劇と個人の内面的な危機が交錯し、物語は重層的な深みを帯びていきます。明確な救済が描かれるわけではありませんが、みっともなくとも生き続けることの意味を肯定する姿勢に、私たちはかすかな希望を見出すことができます。
「河馬に噛まれる」は、私たちに多くのことを問いかけます。組織と個人の関係、歴史との向き合い方、そして「生きる」ことそのものの意味について、深く考えさせられる作品です。この物語との出会いが、あなたにとって思索に満ちた豊かな時間となることを願っています。解きます。T.S.エリオットの詩をモチーフに、みっともなくとも「生き延びる」ことの意味を問う本作の核心に迫る長文感想です。