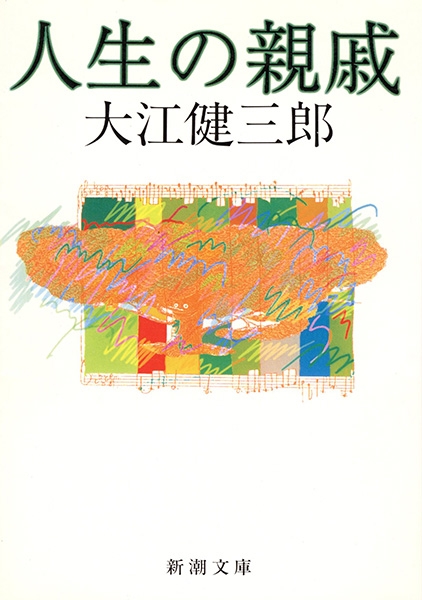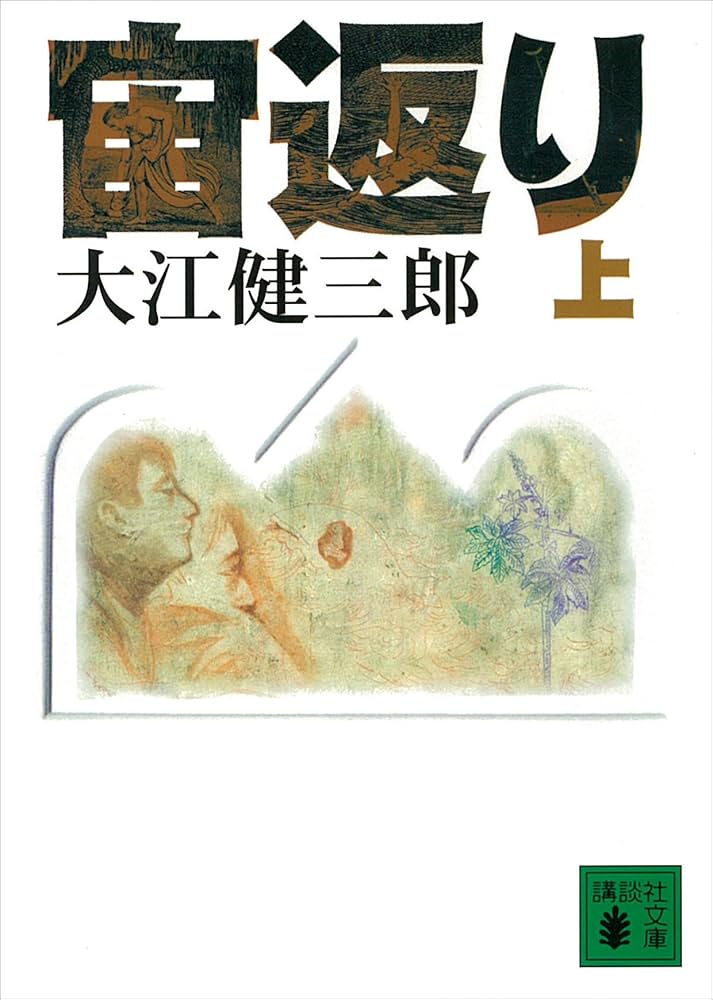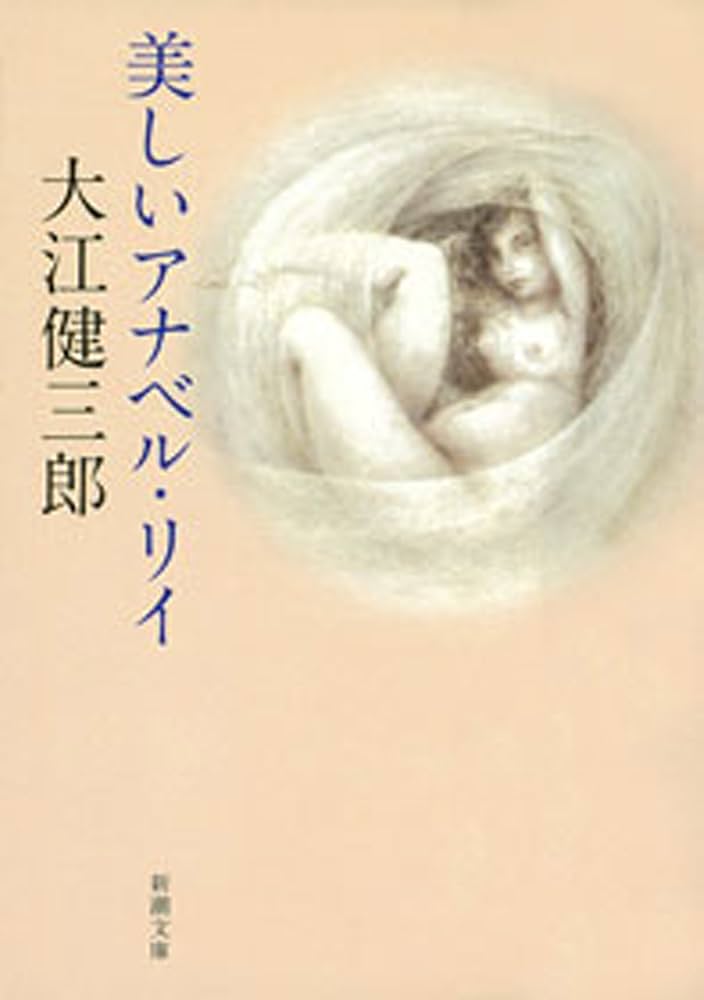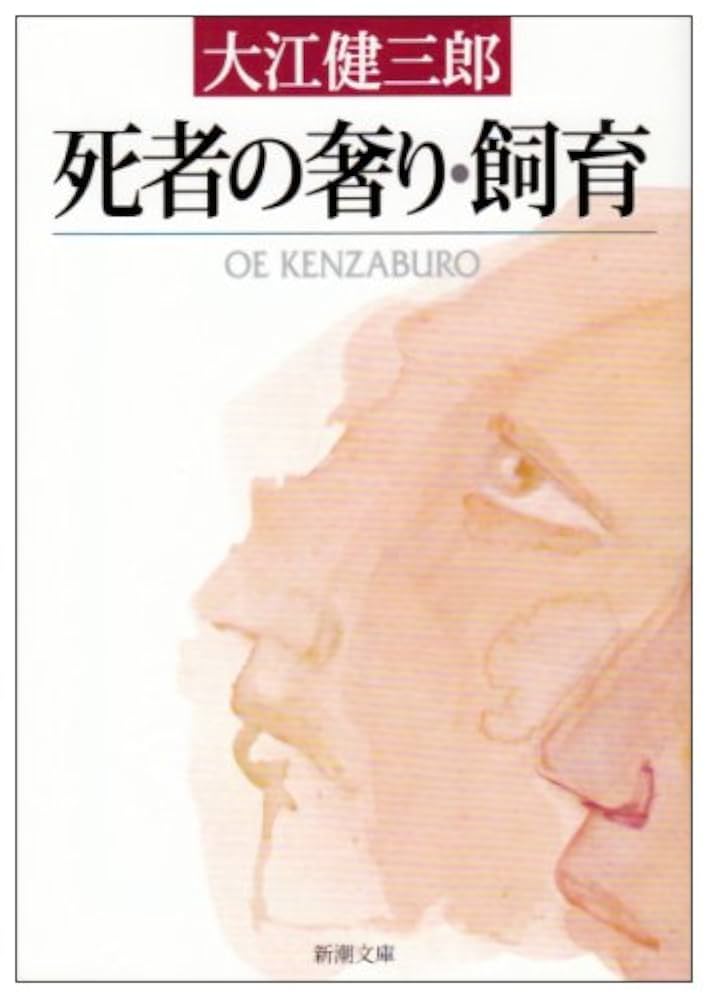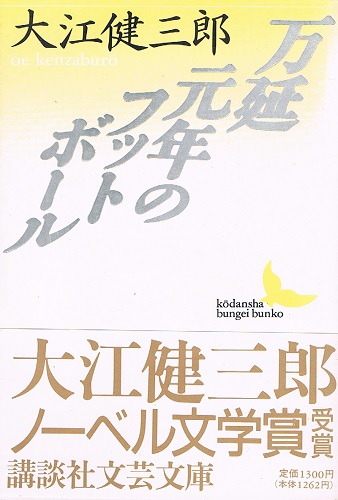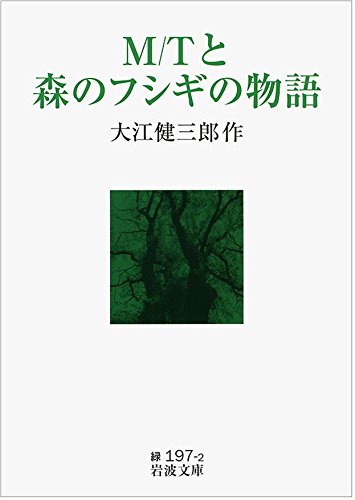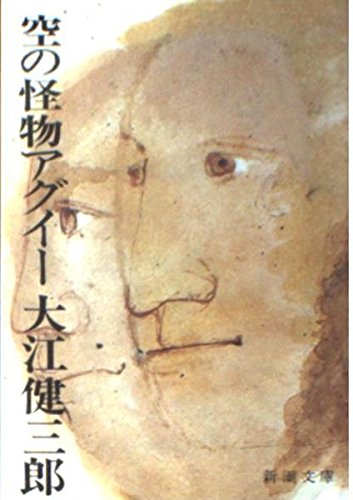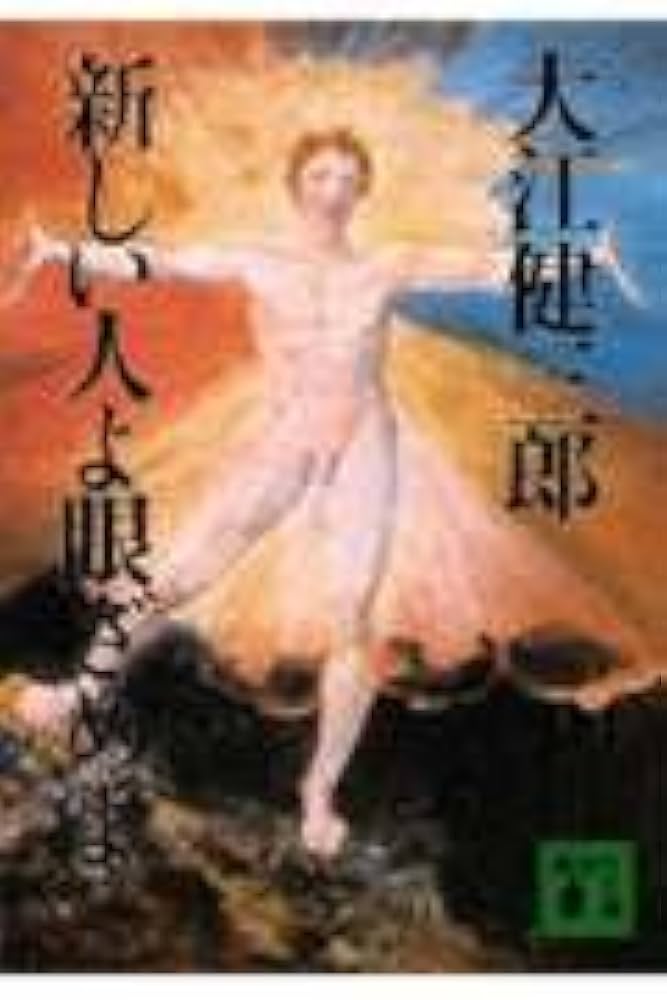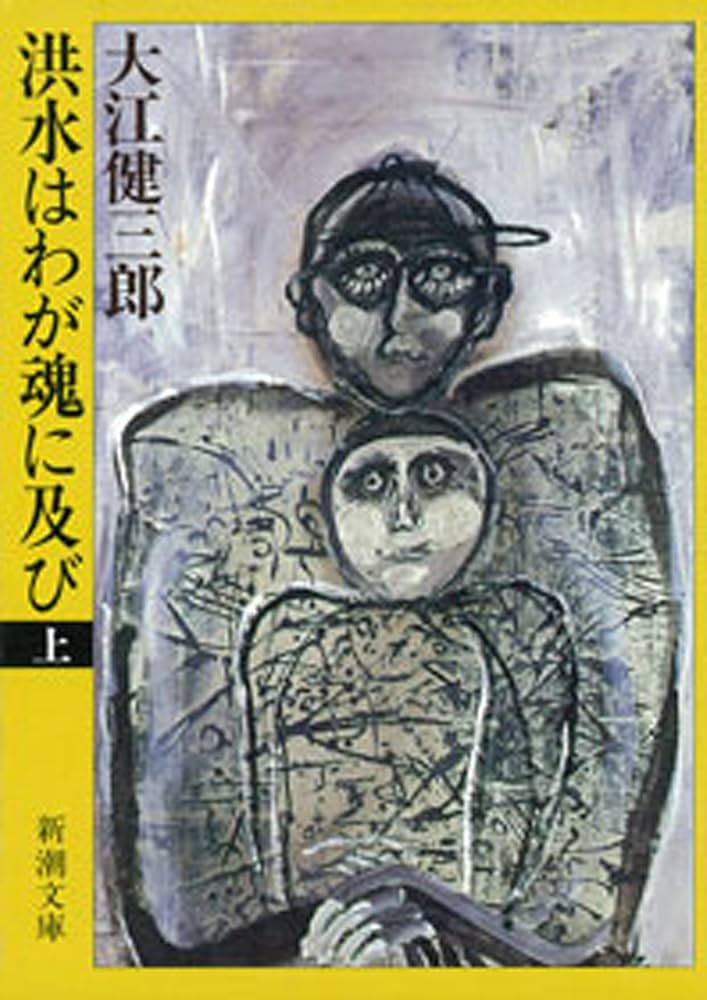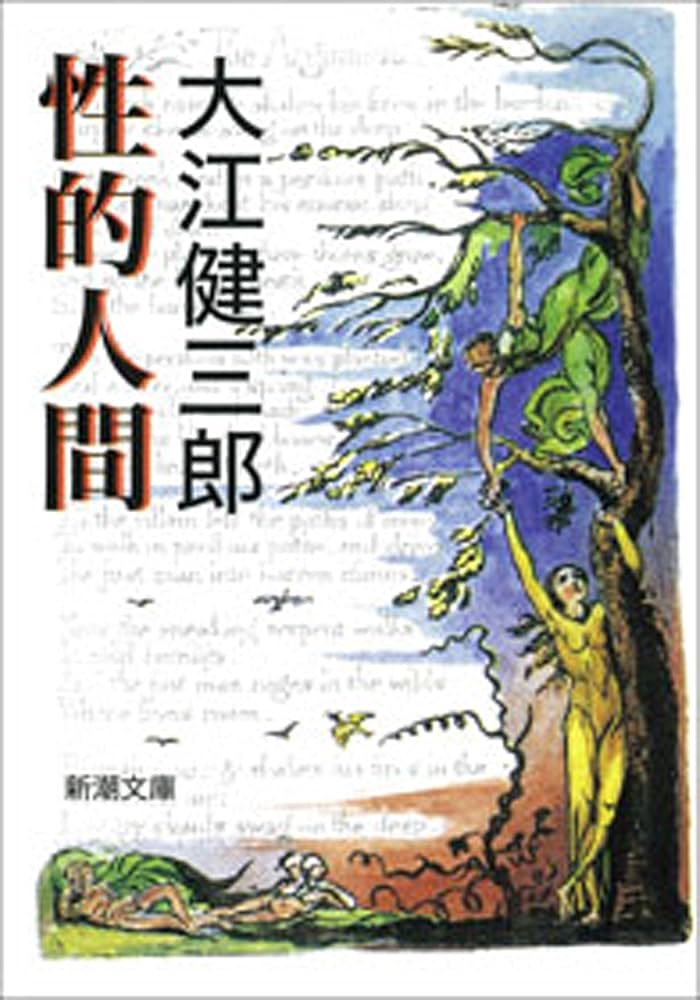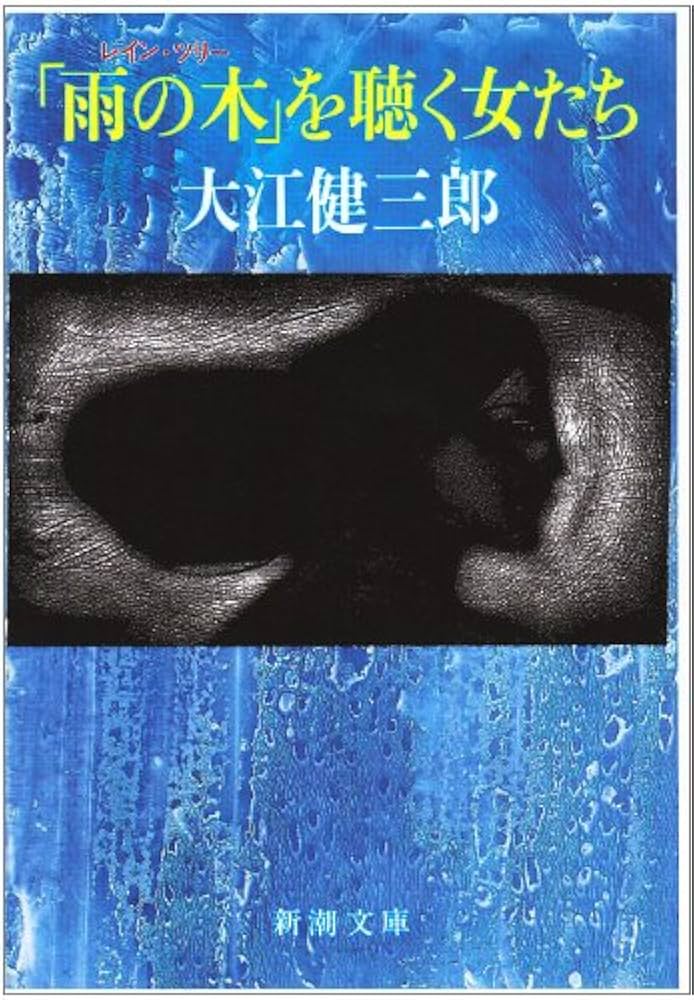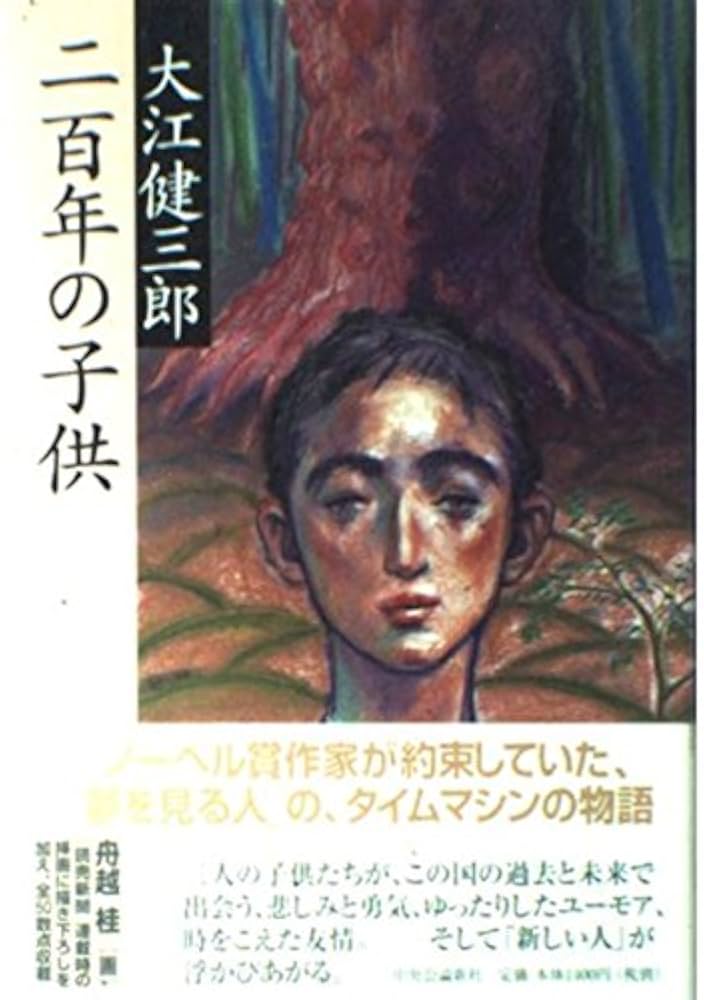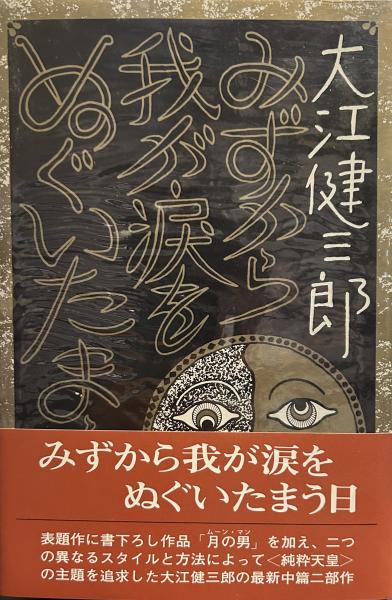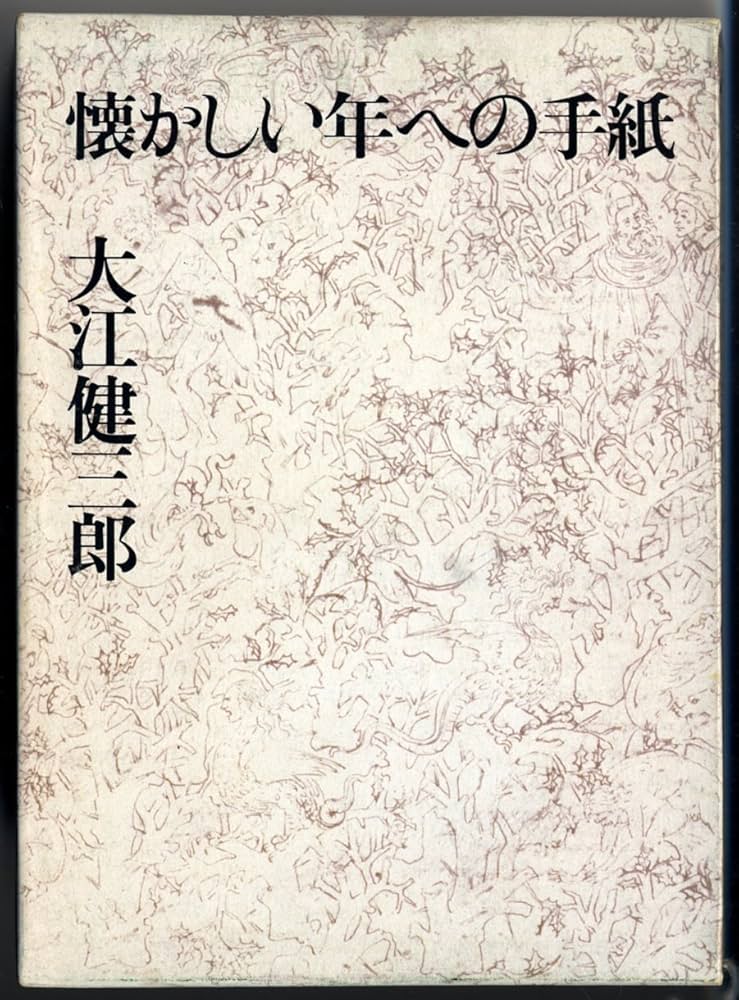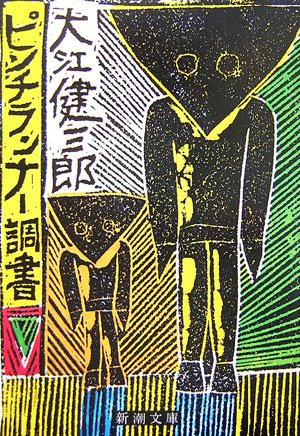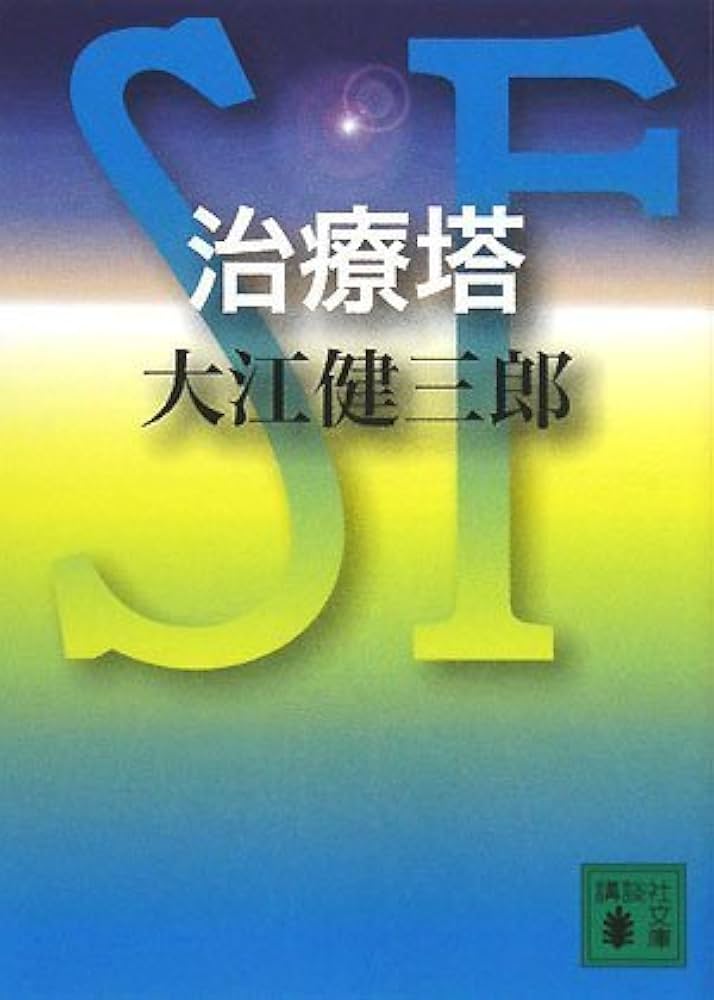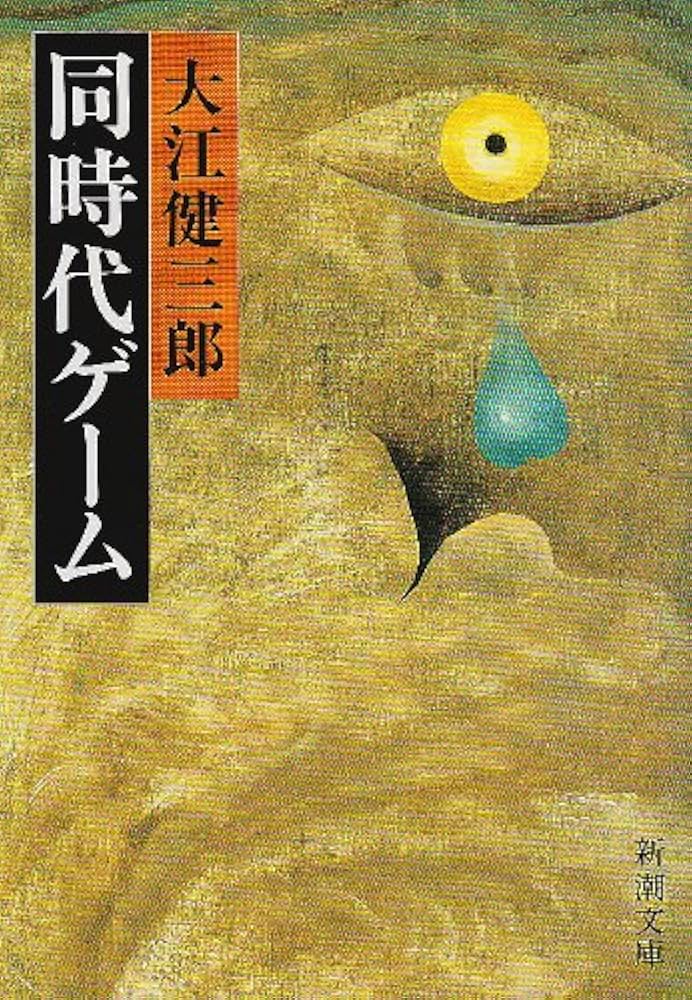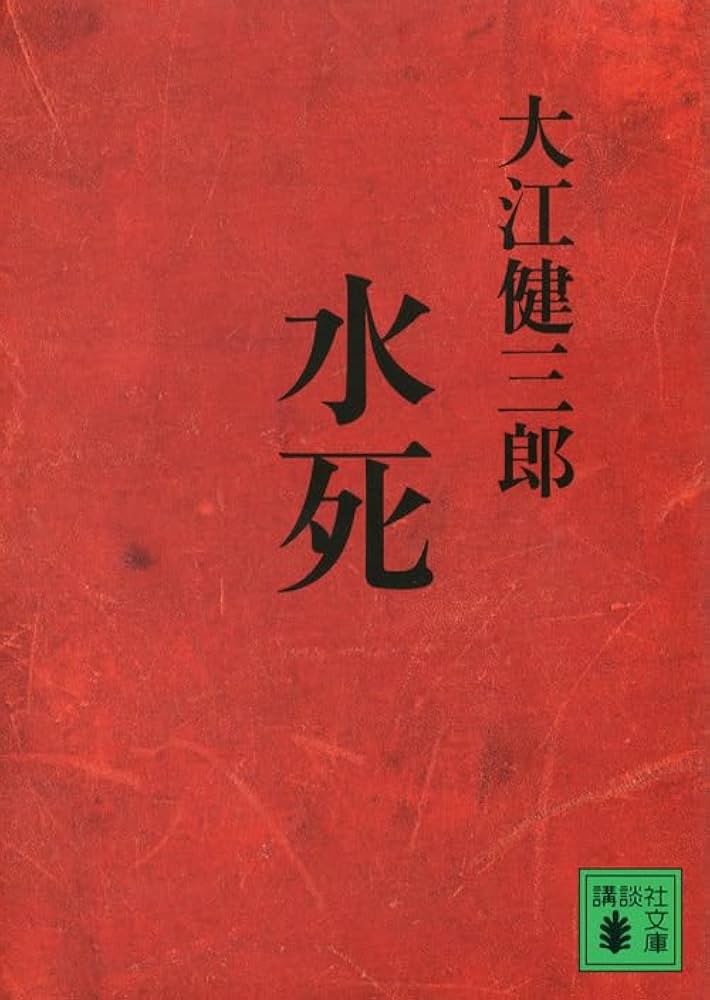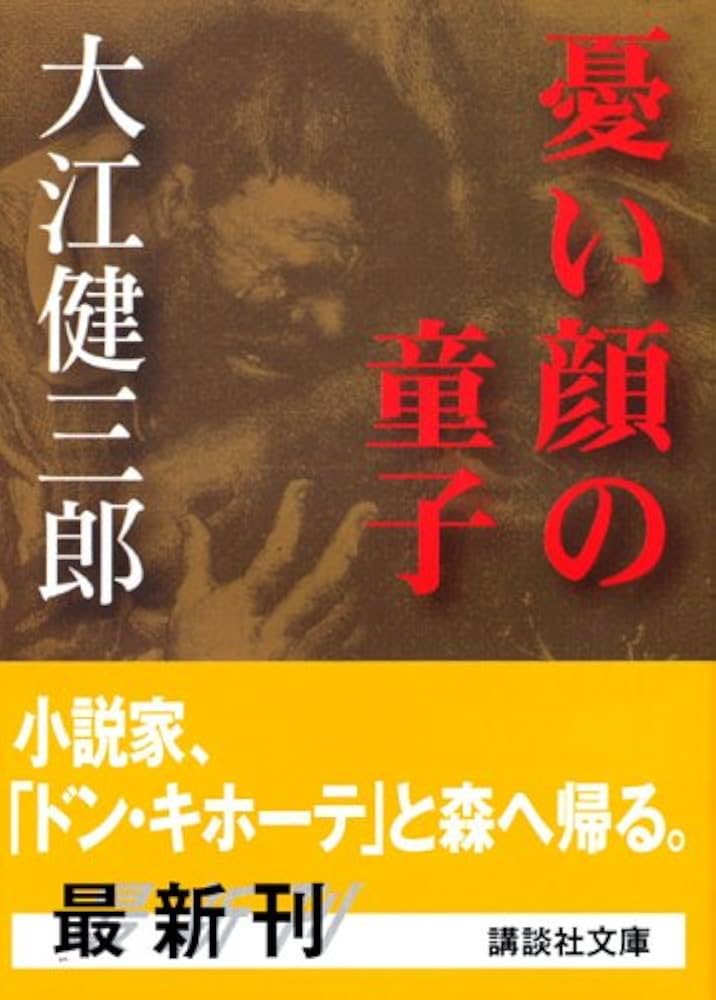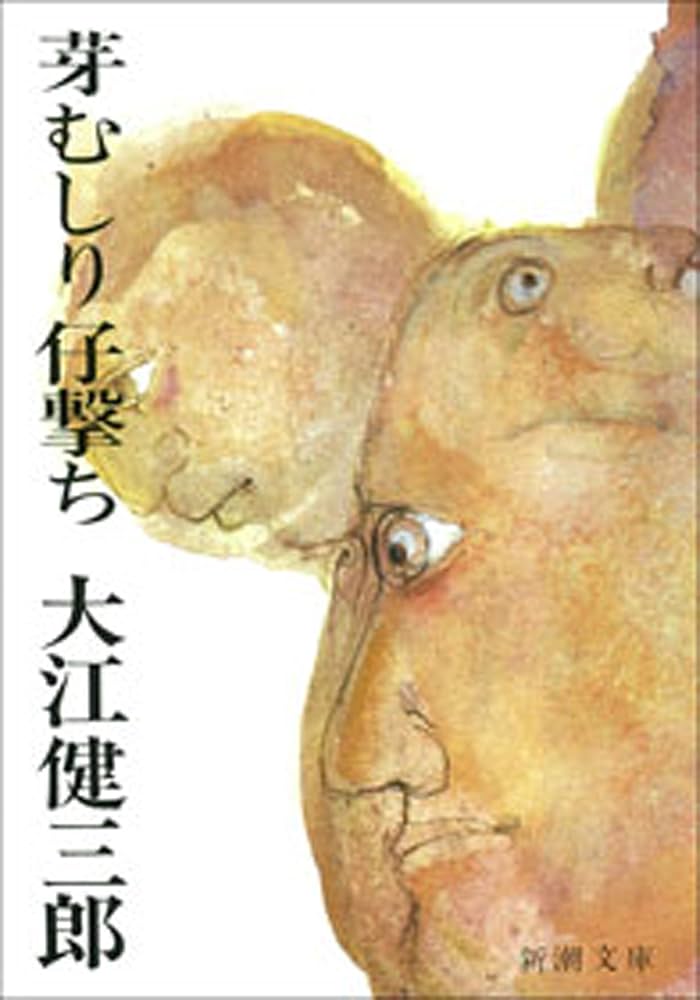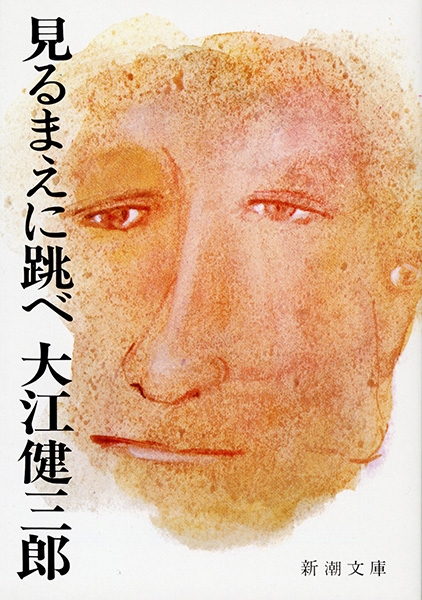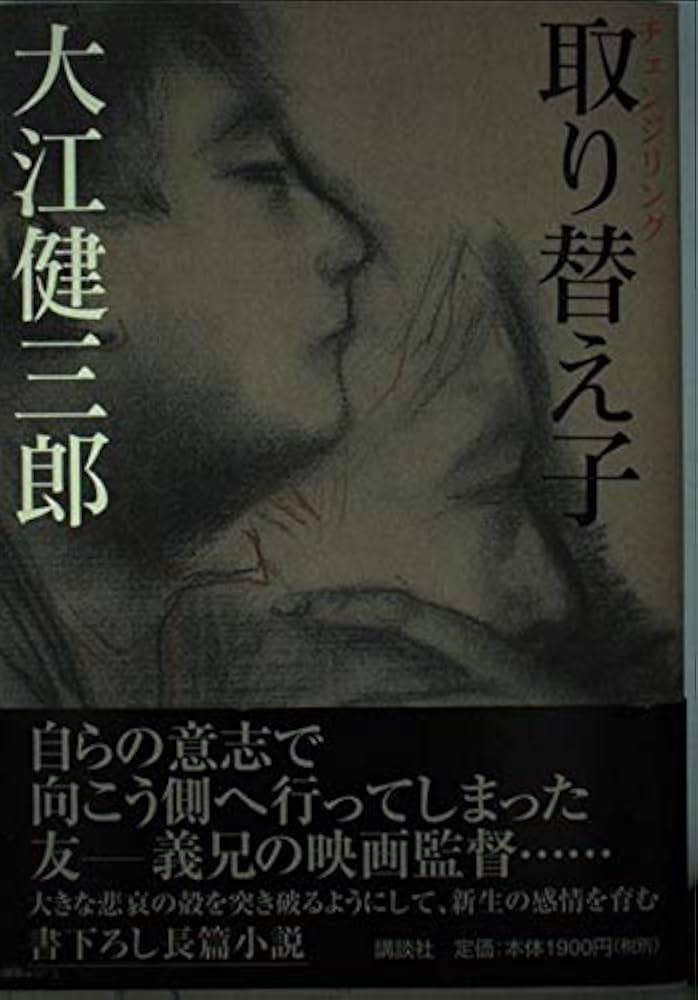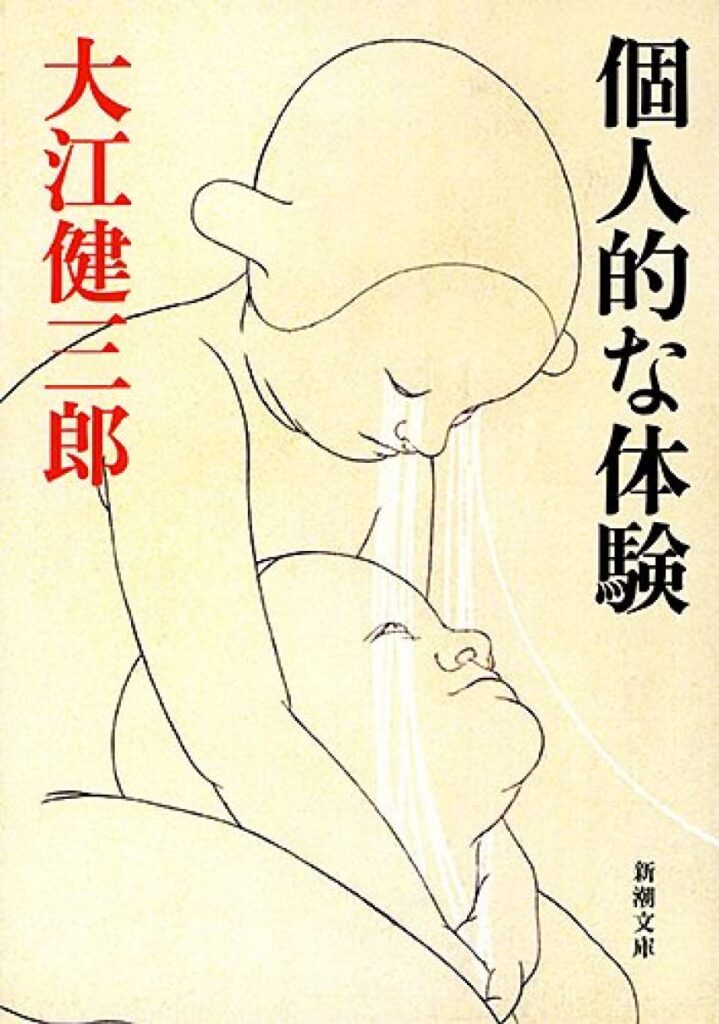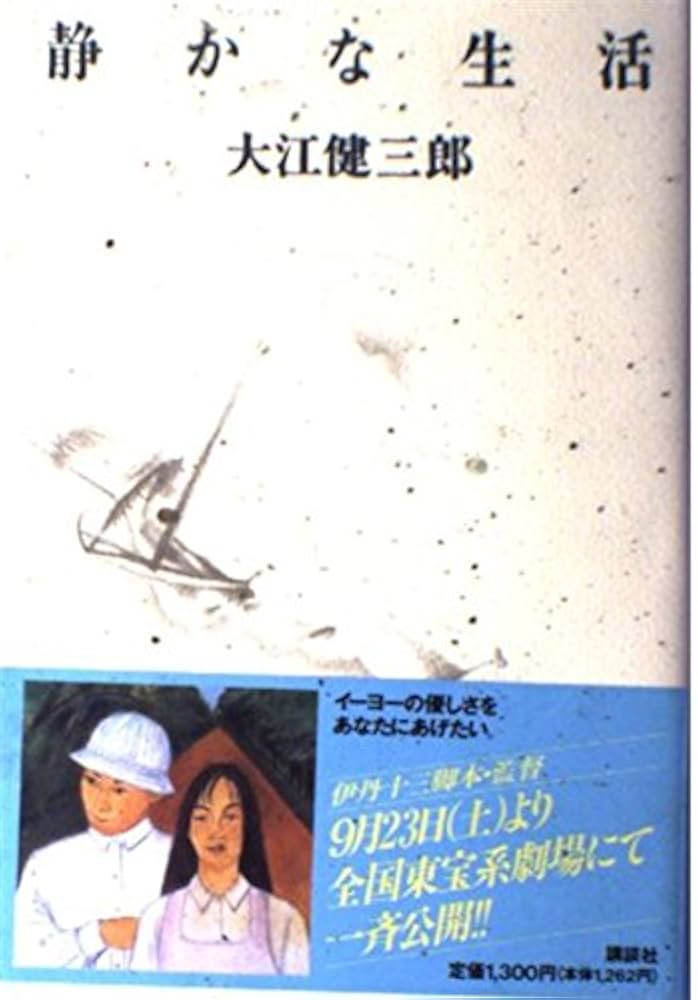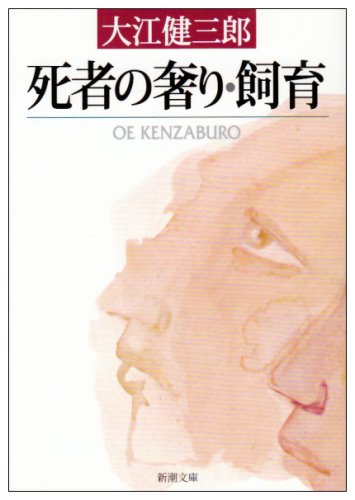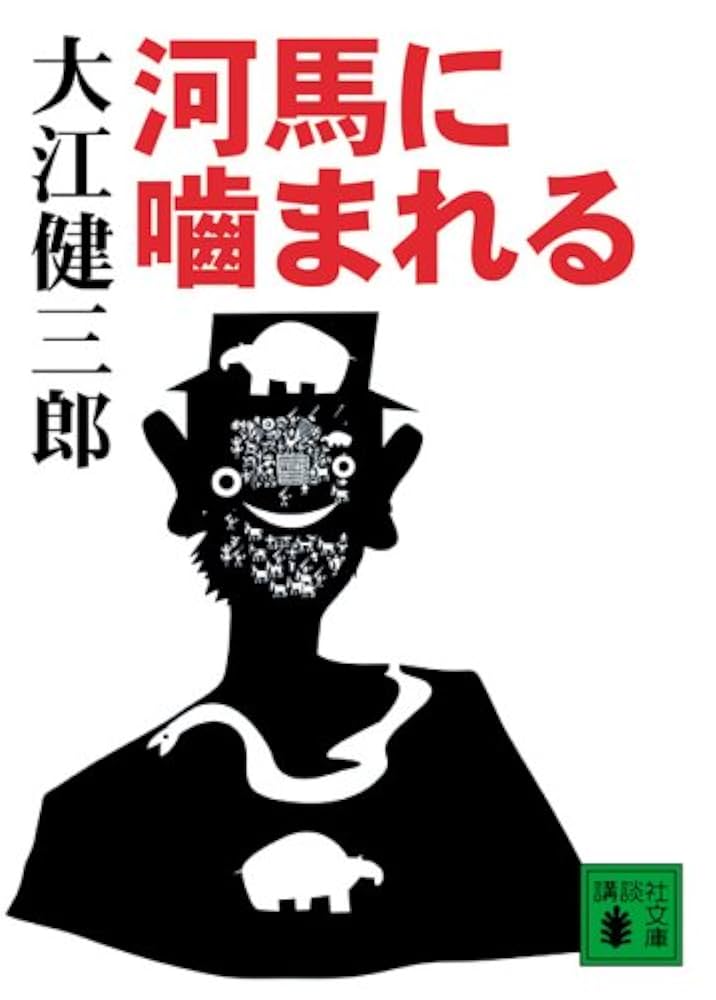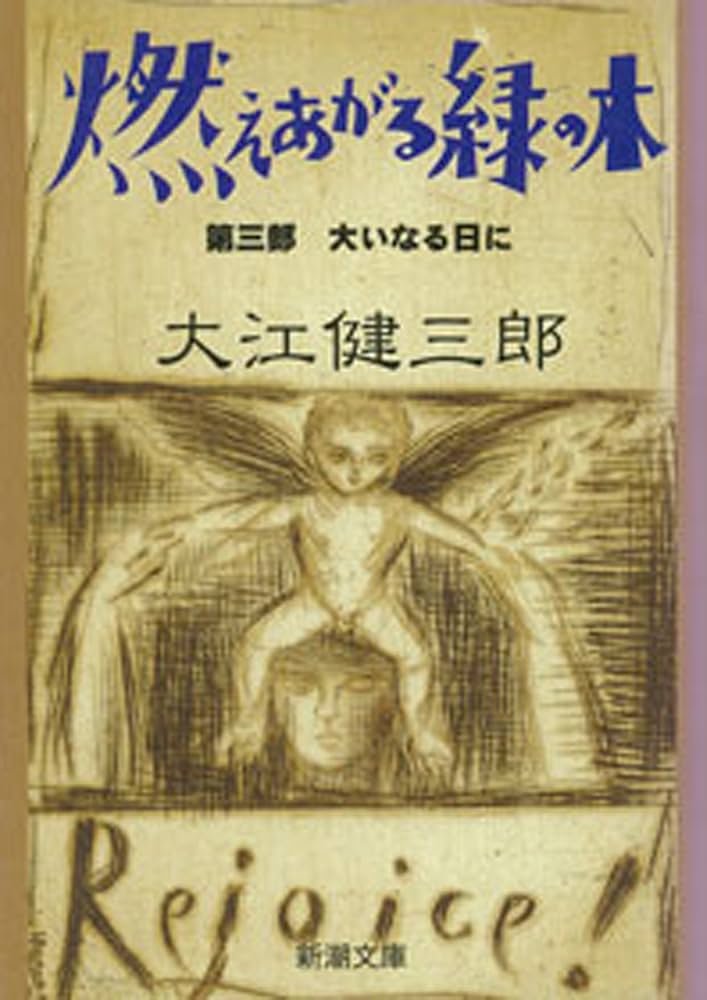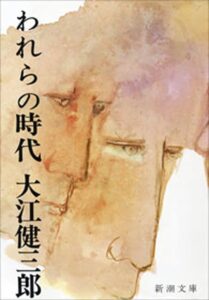 小説「われらの時代」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は1959年に発表された大江健三郎の初期長編小説で、その衝撃的な内容は今なお多くの読者に強烈な印象を与え続けています。戦後の日本が持つ独特の閉塞感や虚無感を背景に、若者たちの行き場のないエネルギーが生々しく描かれているのが特徴です。
小説「われらの時代」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は1959年に発表された大江健三郎の初期長編小説で、その衝撃的な内容は今なお多くの読者に強烈な印象を与え続けています。戦後の日本が持つ独特の閉塞感や虚無感を背景に、若者たちの行き場のないエネルギーが生々しく描かれているのが特徴です。
物語は、性や暴力といったテーマを真正面から扱っており、発表当時は批評家から厳しい批判も受けたと言われています。 しかし、それは裏を返せば、これまでの文学が触れてこなかった時代の深層に切り込んだ野心作であったことの証明ともいえるでしょう。この記事では、そんな『われらの時代』の核心に迫っていきます。
これから『われらの時代』を読もうと思っている方、あるいはすでに読んだけれどもっと深く理解したいという方のために、物語の概要から登場人物たちの心理、そして結末に至るまでの流れを詳しく解説していきます。特に、物語の重要な部分に関するネタバレも含まれていますので、その点はあらかじめご了承ください。
この記事を通じて、大江健三郎が『われらの時代』に込めたメッセージや、作品が持つ現代的な意義について、一緒に考えていければと思います。若者の抱える絶望と、それでも生きていくことの意味を問うこの物語は、きっとあなたの心にも何かを残すはずです。
「われらの時代」のあらすじ
主人公は、フランス文学を専攻する大学院生の南靖男です。 彼は未来に何の希望も見出せず、外国人専門の中年娼婦である頼子の情夫として、無気力で退廃的な毎日を送っていました。 靖男は、戦争という英雄的な時代を知らないことに劣等感を抱いており、頼子との関係に象徴される停滞した日常から抜け出したいと渇望しています。
そんな靖男にとっての唯一の希望は、懸賞論文でフランス留学の機会を勝ち取ることでした。 それは、彼にとって現在の自堕落な生活や、彼が「汚辱」と捉える湿っぽい日本の風土から脱出するための、たった一つの道筋に思えたのです。
一方、靖男の16歳の弟、滋はジャズバンドの仲間たちと共に、鬱屈したエネルギーを過激な思想へと傾倒させていきます。 特に滋は、かつての戦争指導者から「静かなる男」へと姿を変えた天皇に異常な執着を見せ、その存在を驚かすことで自分たちの存在を証明しようと企てます。
彼らは天皇の車列に手榴弾を投げつけるという無謀な計画を立てますが、実行直前に怖気づき失敗に終わります。 この失敗がきっかけとなり、仲間内での度胸試しへと発展し、悲劇的な結末へと物語は加速していくのでした。
「われらの時代」の長文感想(ネタバレあり)
大江健三郎の『われらの時代』を読了した後に残るのは、一種の打ちのめされたような感覚と、ずしりと重い問いかけでした。この物語は、単なる若者の青春群像劇ではありません。それは、戦後という特殊な時代が産み落とした、どうしようもない虚無と閉塞感、そしてその中で生きることの意味を、容赦なく突きつけてくる作品なのです。
物語の中心にいる南靖男という青年は、現代に生きる私たちの目から見ても、決して共感しやすい人物ではないかもしれません。中年娼婦の稼ぎに依存し、未来への希望もなく、ただただ停滞した日常を繰り返す。彼の姿は、あまりにも無気力で、自己中心的ですらあります。しかし、彼の内面に渦巻く焦燥感や劣等感は、時代を超えて若者が抱える普遍的な苦悩と地続きであるように感じられます。
靖男が自身の生きる時代を、何かを執行されるのを待つだけの「猶予」期間のようだと感じている点は、非常に印象的でした。英雄的な物語が存在した「戦争の時代」を知らない彼は、自らが生きる現代に価値を見いだせない。この感覚こそが、『われらの時代』という作品の根幹をなしていると言えるでしょう。フランス留学という希望も、結局は現状からの逃避でしかありませんでした。
物語の重要なネタバレになりますが、靖男のささやかな希望は、弟の事件によって無残にも打ち砕かれます。逃亡する弟を匿ったことで警察の聴取を受け、反フランス的なアラブ人との交流を理由に留学資格を剥奪されるのです。 この展開はあまりに救いがなく、読んでいるこちらも突き放されたような気持ちになります。希望を掴みかけた瞬間、それが足元から崩れ去る絶望感は、本作の持つ容赦のなさを象徴しています。
弟の滋の存在もまた、この物語に強烈な影を落としています。兄の靖男が無気力なインテリであるのに対し、滋は純粋さと行動への渇望から、過激で危険な思想に傾倒していきます。彼の天皇に対する屈折した崇拝は、絶対的な権威を失った戦後日本社会の歪みを体現しているかのようです。
滋たちの計画は稚拙で、結局は仲間割れと偶発的な死という悲劇的な結末を迎えます。 このあっけない幕切れは、彼らの抱いていた英雄願望がいかに空虚なものであったかを物語っています。ここにもネタバレが含まれますが、彼らの死は英雄的なものではなく、ただただ無意味なものとして描かれます。この冷徹な視線こそが、大江健三郎の描く世界の厳しさなのです。
『われらの時代』では、性と暴力の描写が非常に直接的であることも特徴です。 特に靖男と頼子の関係は、愛情や安らぎといったものからは程遠く、むしろ互いを蝕むような不毛なものとして描かれています。靖男が頼子のいる世界を「女陰的な世界」と呼び、そこからの脱出を願う場面は、彼の抱える閉塞感や自己嫌悪が生々しく伝わってきます。
これらの描写は、単に読者に衝撃を与えるためだけのものではありません。登場人物たちの内面に潜む暴力性や、社会全体に充満する抑圧されたエネルギーを表現するための、必要不可欠な要素だったのでしょう。彼らの行動は、言葉にならない叫びのように感じられました。
物語の結末は、多くの読者に衝撃を与えたのではないでしょうか。弟を失い、唯一の希望であったフランス行きも絶たれた靖男は、完全な孤独の中に放り出されます。 彼は自殺こそが自分に残された唯一の英雄的行為だと考えますが、結局、死ぬことすらできません。
そして彼は、橋の上から電車を見下ろしながら、ある種の悟りにも似た認識に至ります。「偏在する自殺の機会に見張られながらおれたちは生きてゆくのだ、これがおれたちの時代だ」と。この一文こそ、『われらの時代』が読者に突きつける核心的なメッセージです。
絶望の淵に立たされ、死ぬことさえ選べない。しかし、その絶望的な状況の中で、ただ生き続けること。それこそが、自分たちに課せられた宿命なのだという認識。これは、希望に満ちた結末とは到底言えません。しかし、そこには虚無を突き抜けた先にある、生の厳粛な肯定がかすかに感じられるのです。
この物語は、安易な救いや希望を与えてはくれません。むしろ、読者からそうしたものを奪い去っていくような側面すらあります。しかし、だからこそ『われら時代』は、読む者の心に深く突き刺さるのです。登場人物たちの苦悩や絶望を追体験することは、決して心地よい読書体験ではないかもしれません。
それでも、私たちがこの物語に惹きつけられるのは、そこに描かれているのが、決して他人事ではないと感じるからではないでしょうか。時代の空気は変わっても、若者が抱える閉塞感や、生きる意味を見出せない虚無感は、形を変えて現代にも存在しています。
『われらの時代』は、そうした普遍的な苦悩に対して、一つの厳しい答えを提示します。それは、「生き抜け」というような力強い言葉ではありません。ただ、絶望の中にあっても生は続いていくという、冷徹な事実です。
この作品を読み解く上で、もう一つ重要なのは、靖男と彼の友人である社会主義活動家の八木沢との関係です。八木沢は靖男に左翼活動への参加を促しますが、靖男はそれに対しても熱意を持つことができません。 彼は、集団的な運動の中に自己を解消することにも、希望を見いだせないのです。
ここにも、『われらの時代』の持つ複雑さが表れています。個人の内面における虚無からの脱却も、社会変革という外部への働きかけも、どちらも靖男にとっての救いにはならない。彼は、そのどちらにも与することができず、宙吊りの状態で生き続けるしかないのです。
この物語は、発表から半世紀以上が経過した今読んでも、その切れ味は全く鈍っていません。むしろ、未来への明るい展望が見えにくくなっている現代において、そのメッセージはより切実に響くのかもしれません。この重苦しい読後感こそが、『われらの時代』が傑作であることの証左なのだと、私は思います。
最終的に、この物語は読者一人ひとりに「あなたにとって『われらの時代』とは何か」と問いかけてくるようです。それは、決して簡単な問いではありません。しかし、この問いと向き合うこと自体に、この難解で、しかし重要な文学作品を読む価値があるのではないでしょうか。
まとめ:「われらの時代」のあらすじ・ネタバレ・長文感想
この記事では、大江健三郎の小説『われらの時代』について、物語の核心に触れるネタバレを含みながら、そのあらすじと深い感想を述べてきました。本作は、戦後の日本社会を覆う虚無感と閉塞感を背景に、若者たちの絶望と生の模索を描き出した、非常に衝撃的な作品です。
主人公・南靖男の退廃的な日常と、弟・滋の過激な行動は、希望を見失った時代の若者たちの肖像として、強烈な印象を残します。彼らが直面する現実は厳しく、物語は安易な救いを用意してはくれません。むしろ、一度掴みかけた希望すらも無慈悲に奪い去っていきます。
しかし、その絶望の果てに主人公が見出す「自殺すらできずに生き続けることこそが、われらの時代だ」という認識は、この物語の核心を突いています。それは消極的ながらも、生に対する一つの厳粛な向き合い方を示していると言えるでしょう。
『われらの時代』は、読む者に重い問いを投げかけ、心を揺さぶる作品です。その過激な描写や救いのない展開は、読む人を選ぶかもしれません。しかし、時代を超えて普遍的な若者の苦悩を描いたこの物語は、現代を生きる私たちにとっても、深く考えるきっかけを与えてくれるはずです。