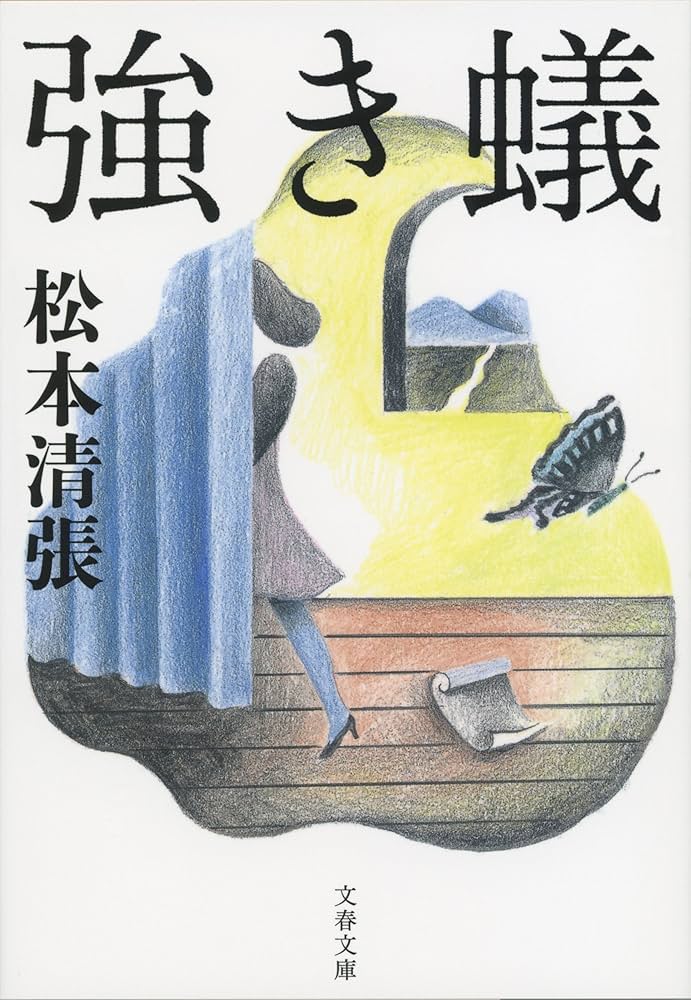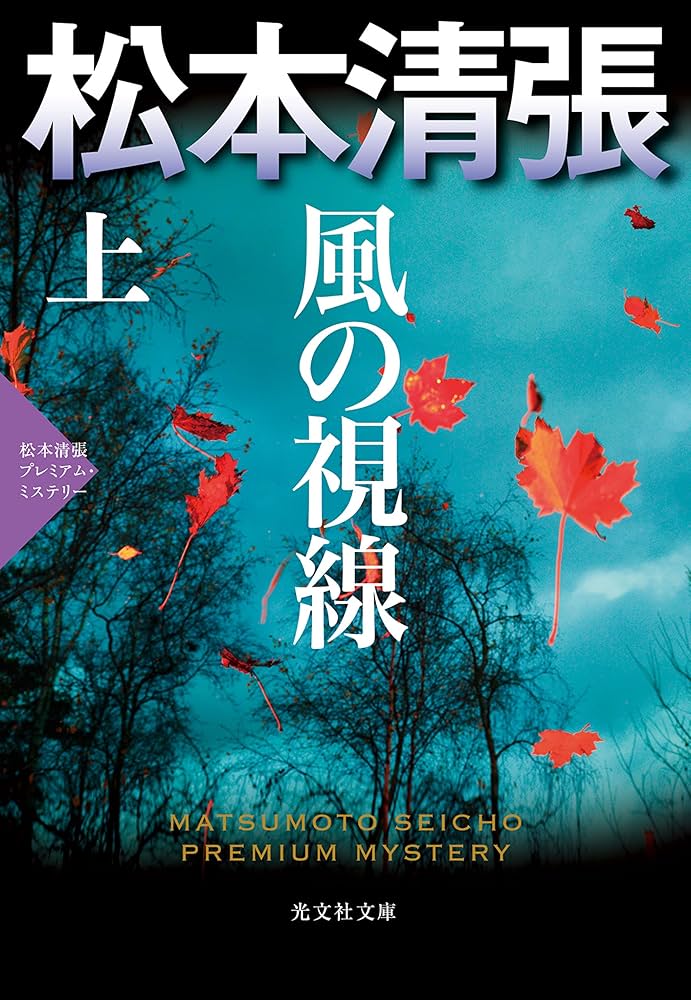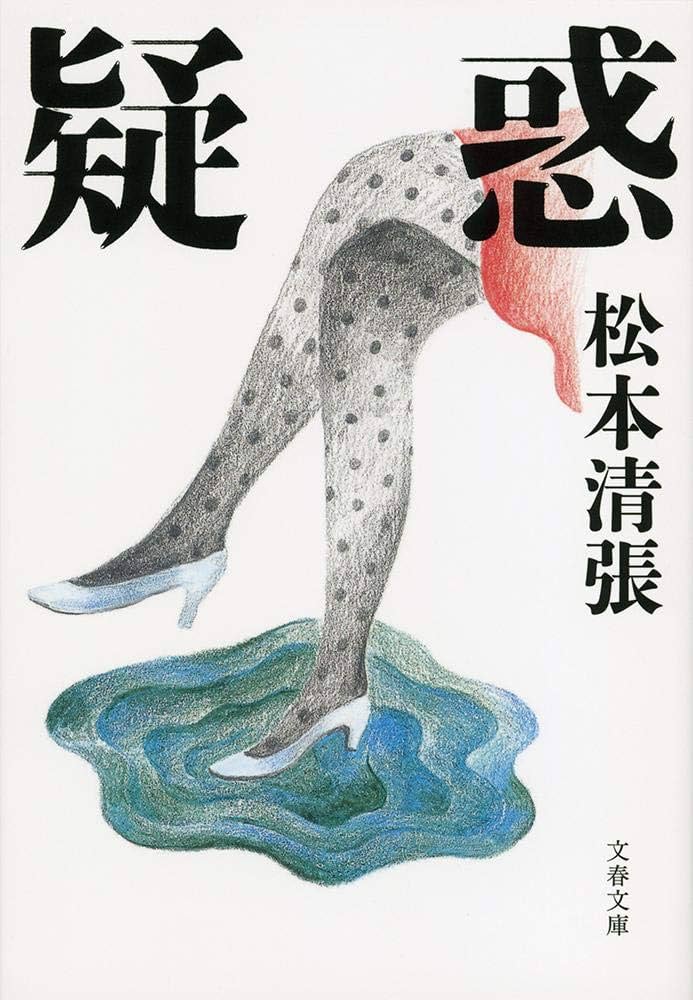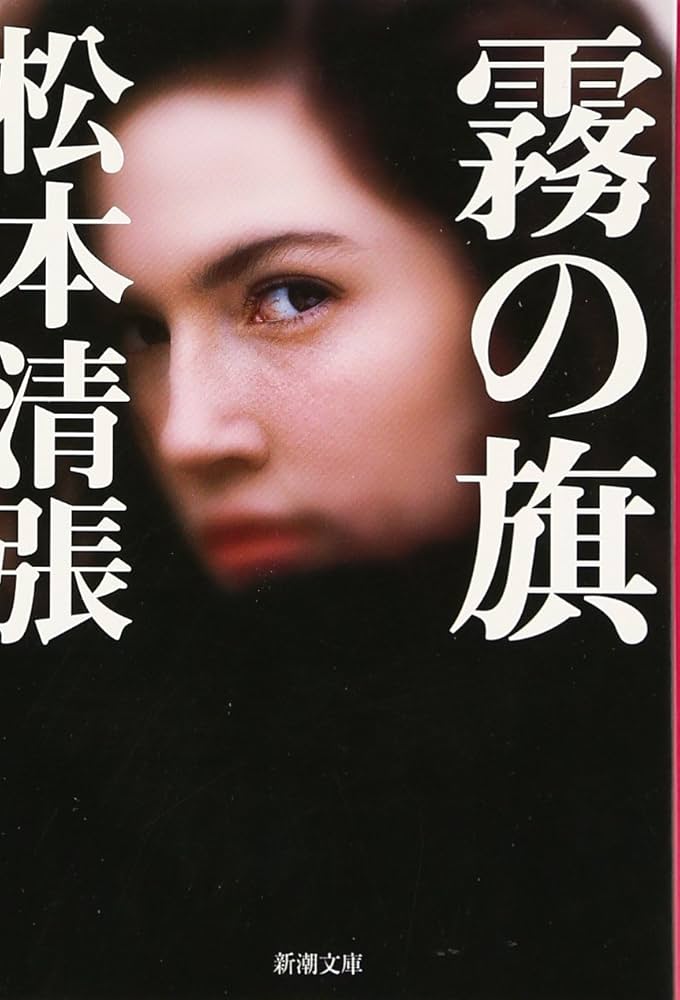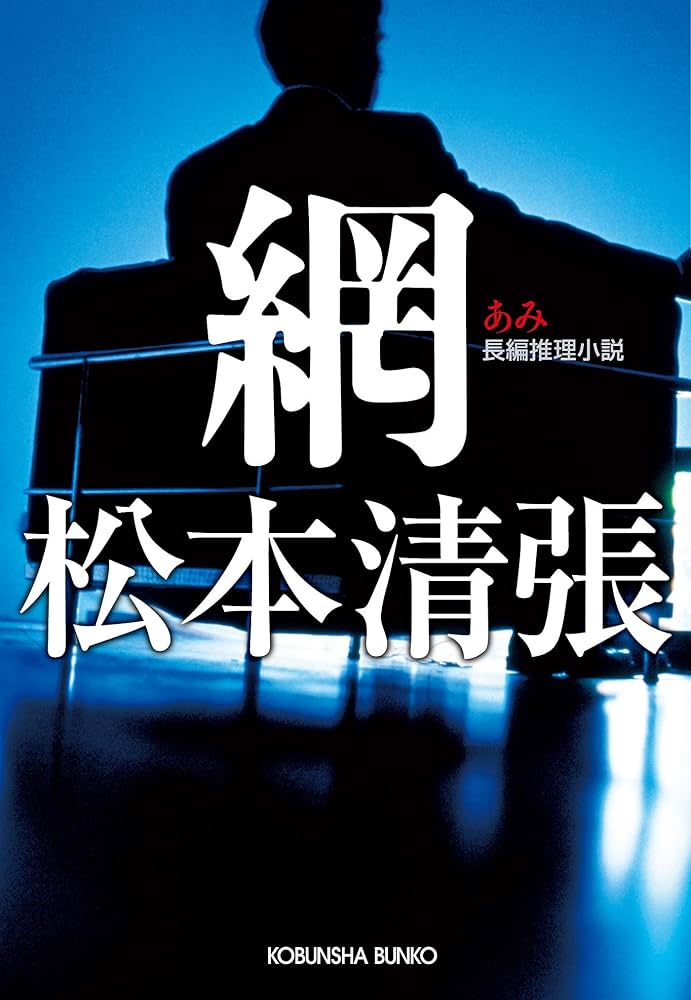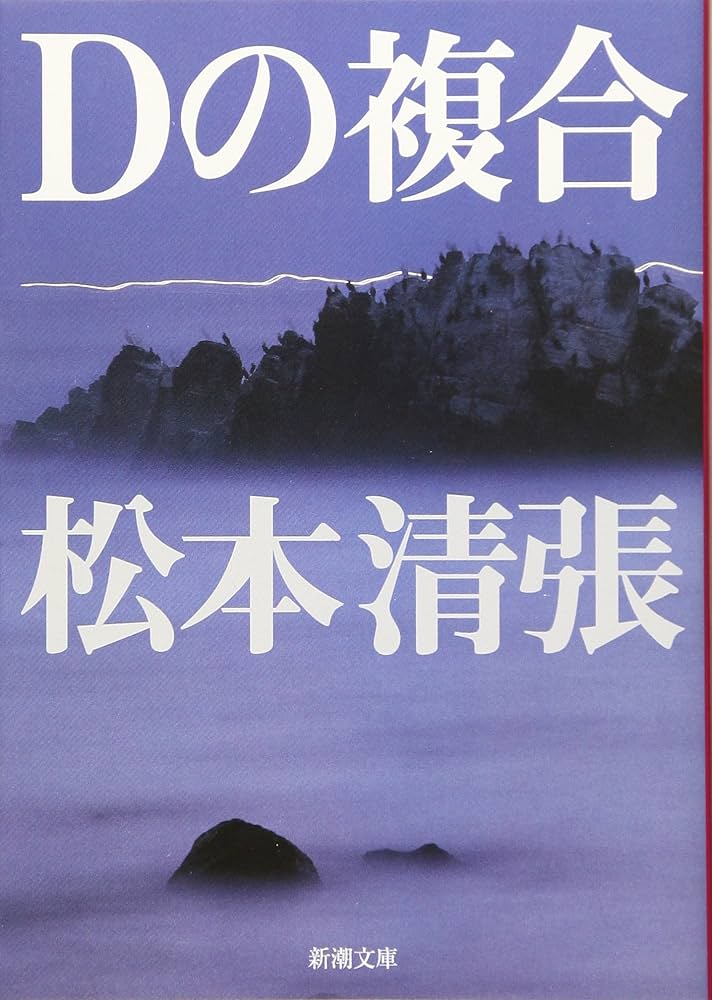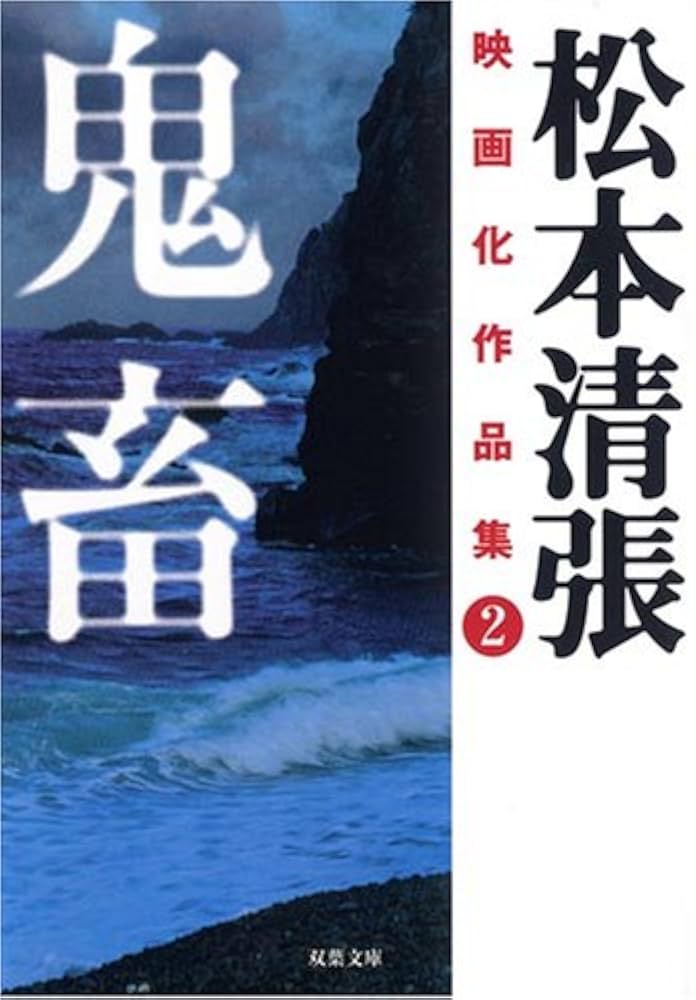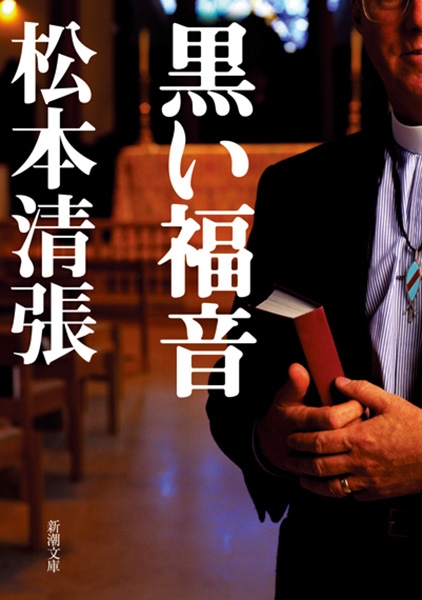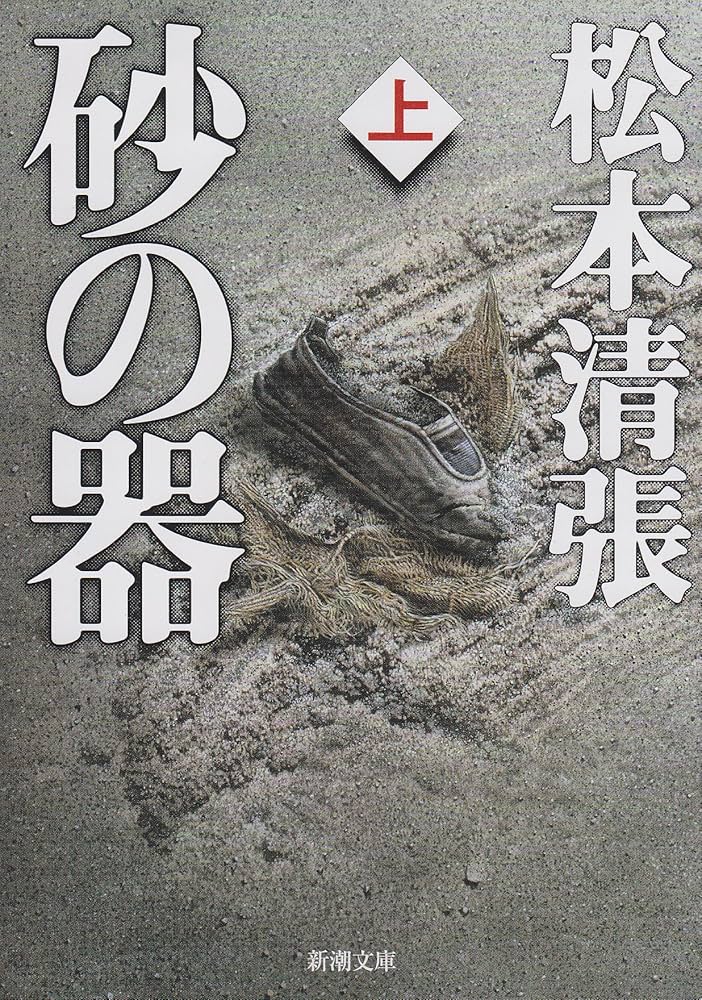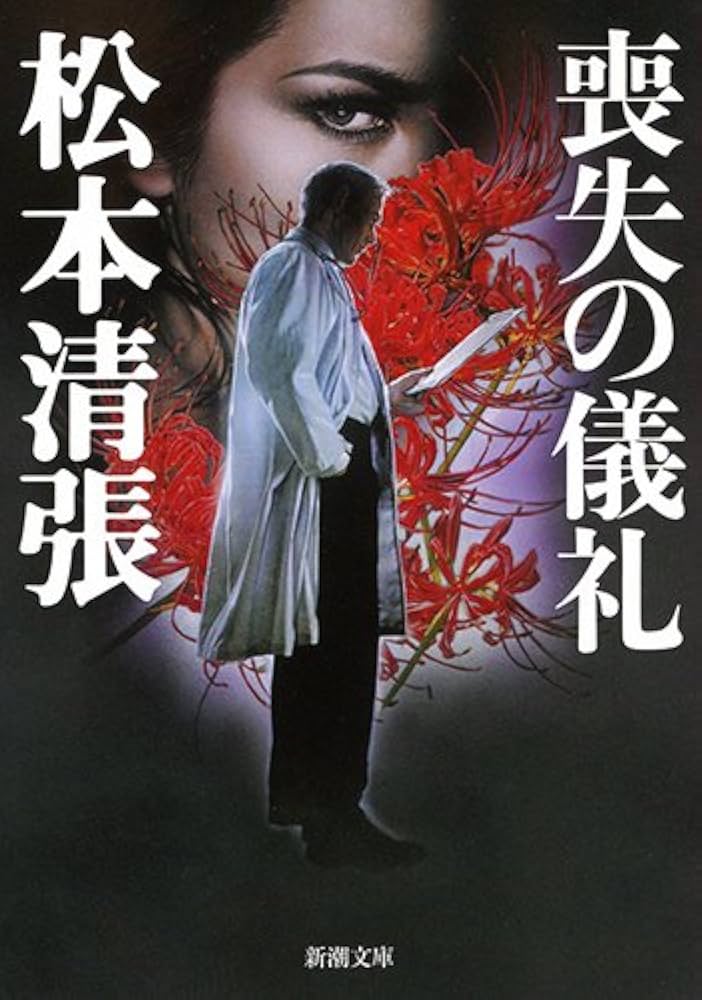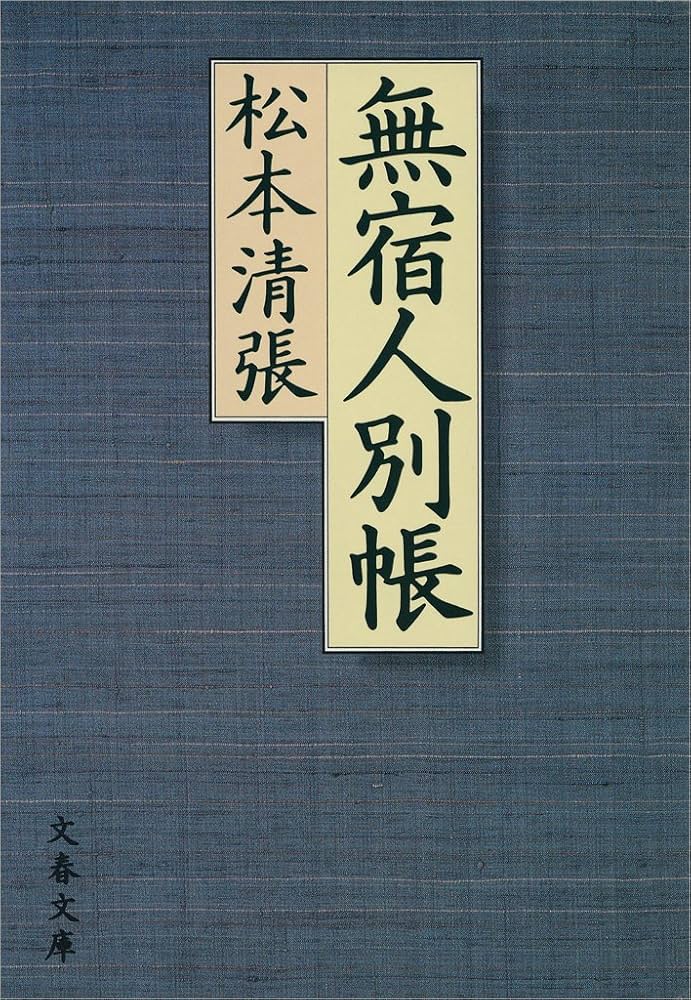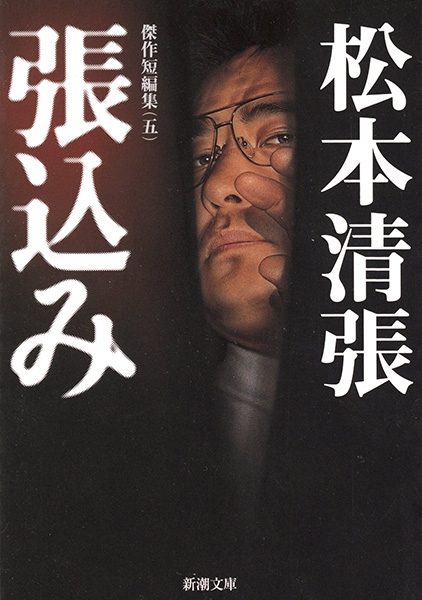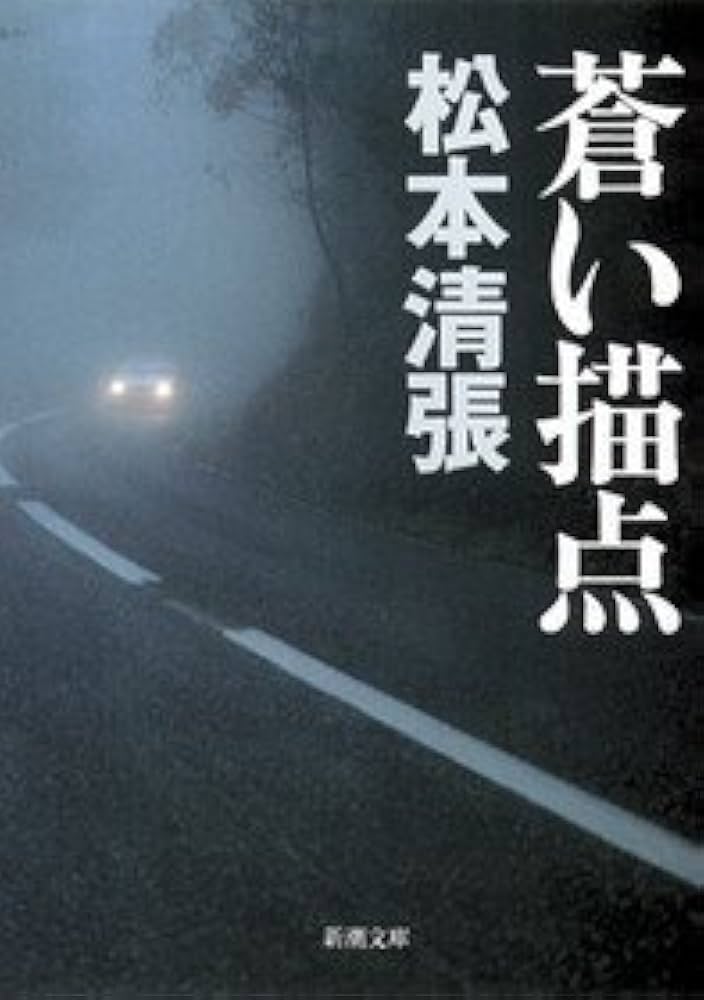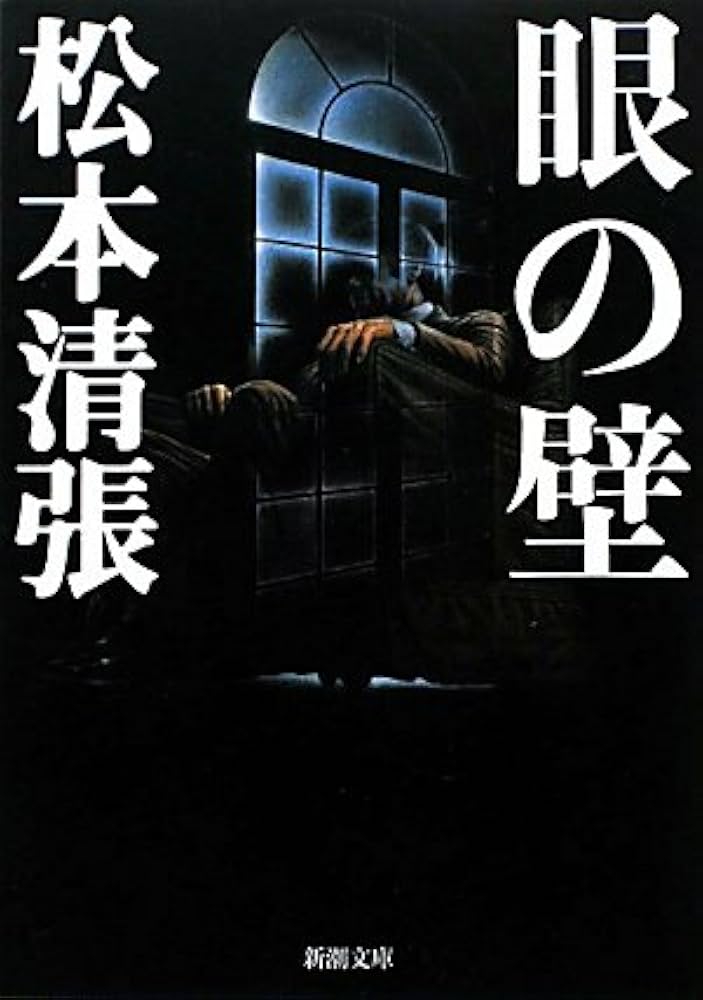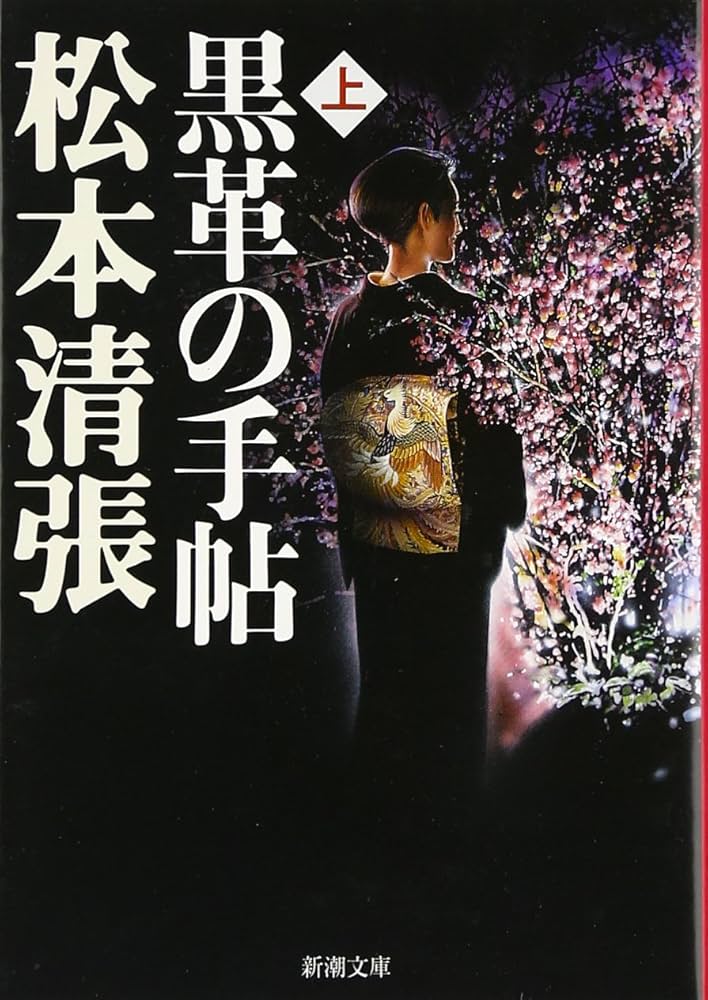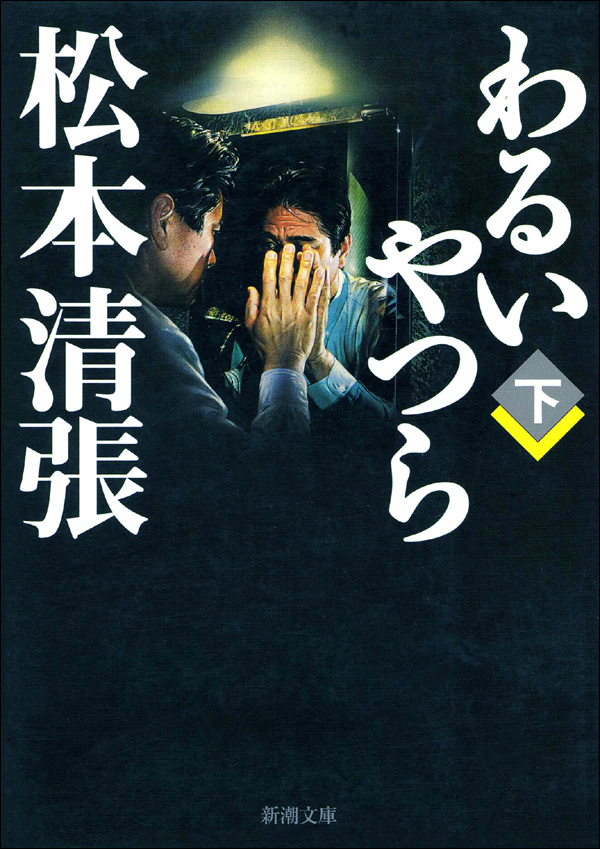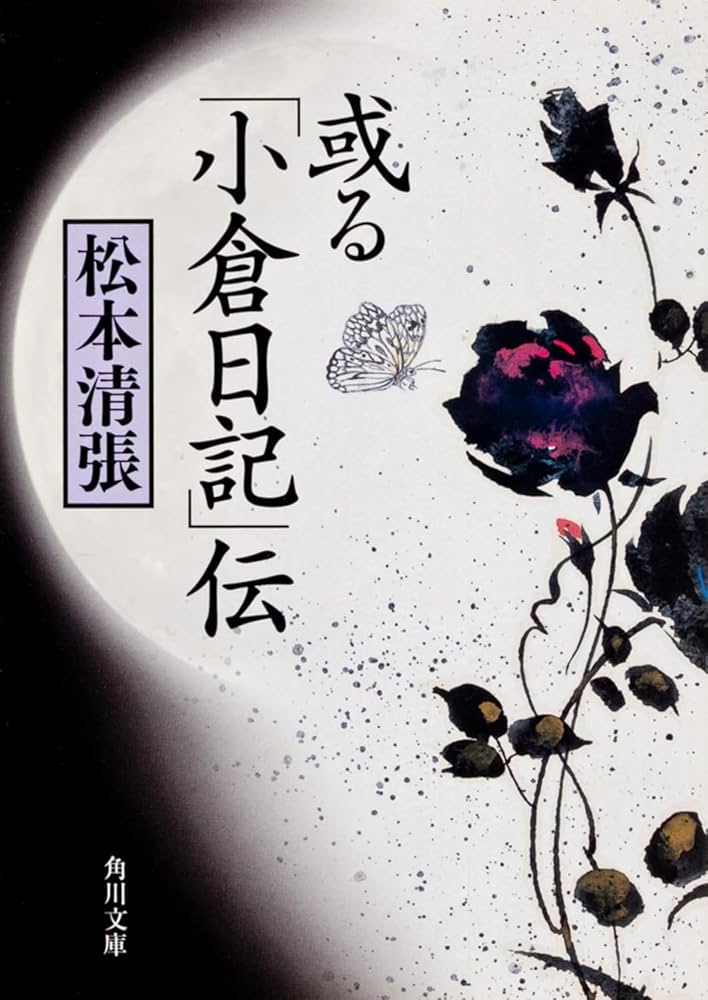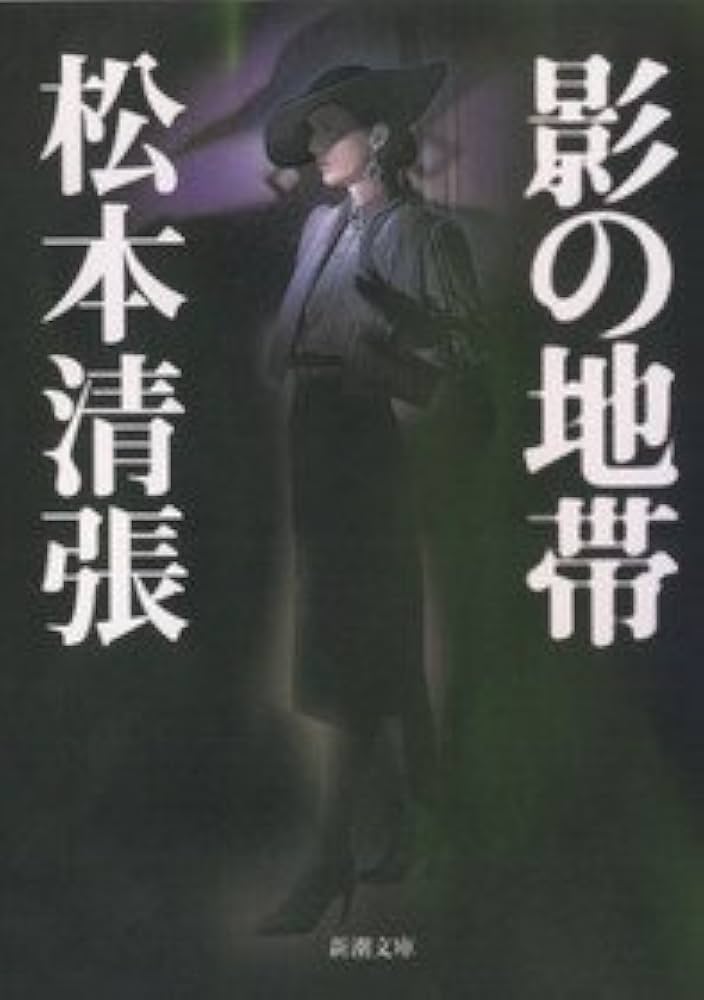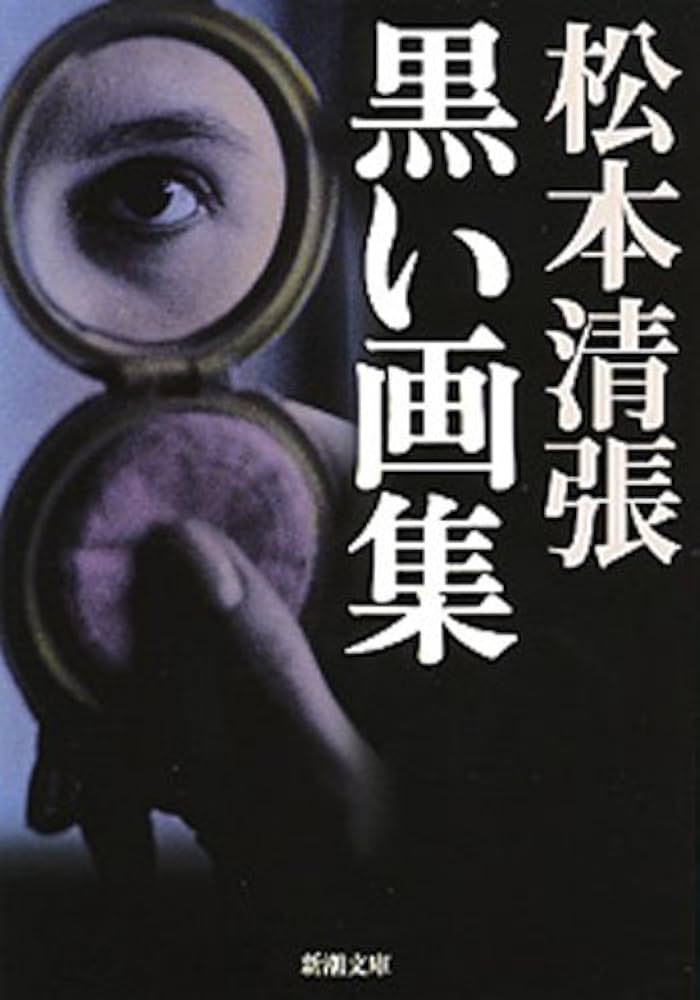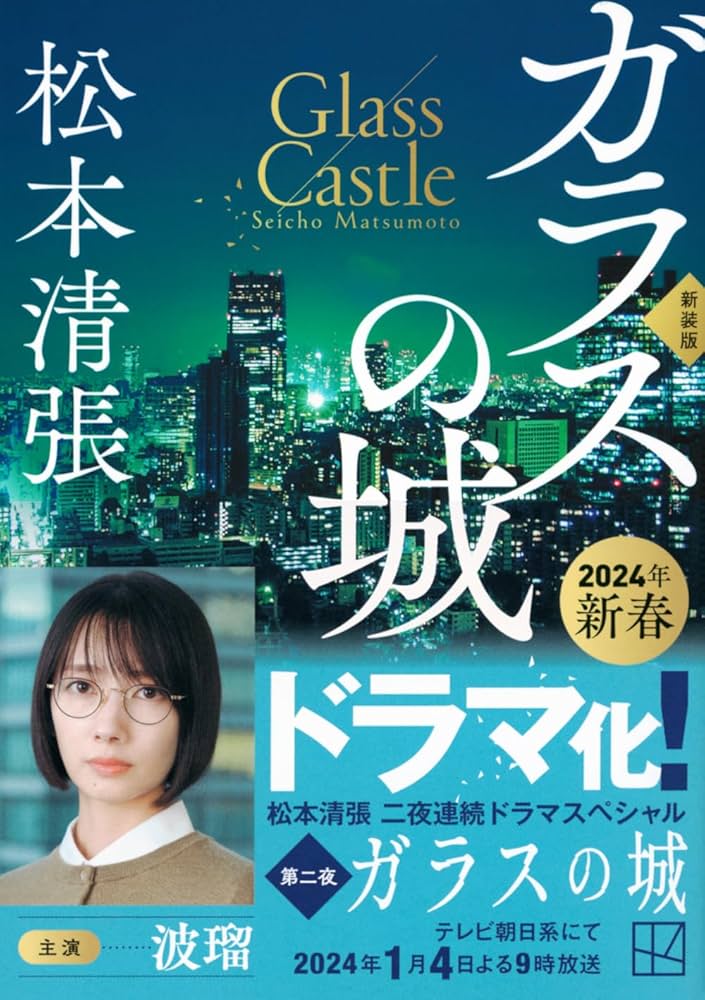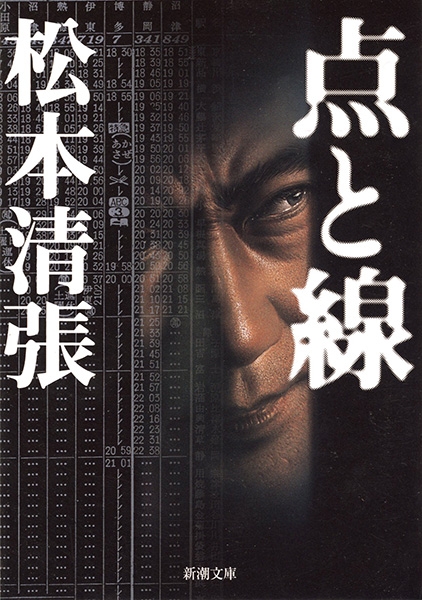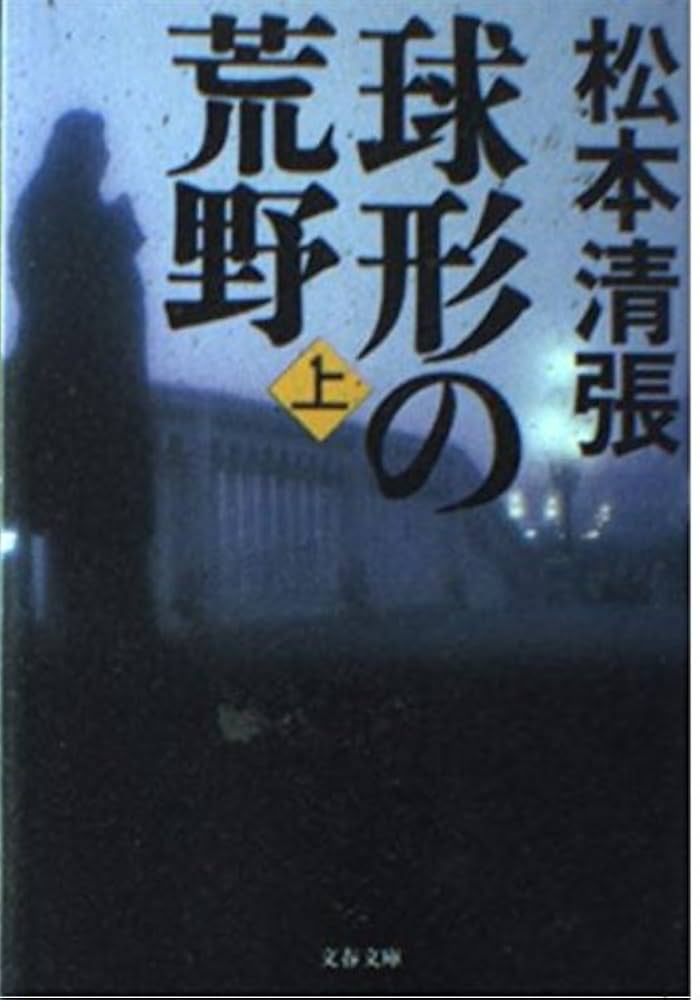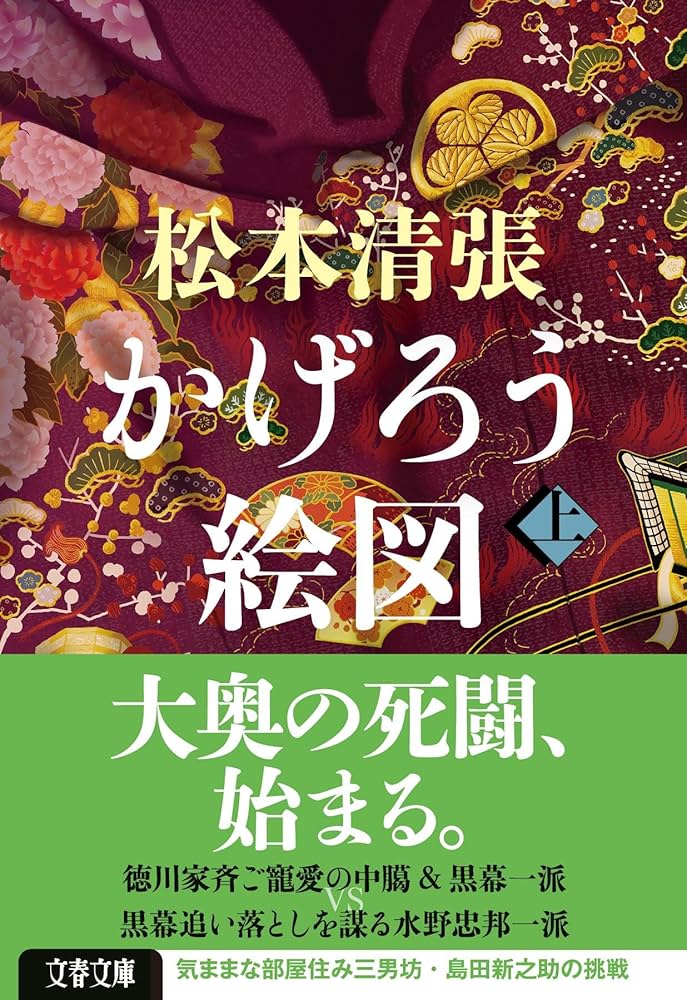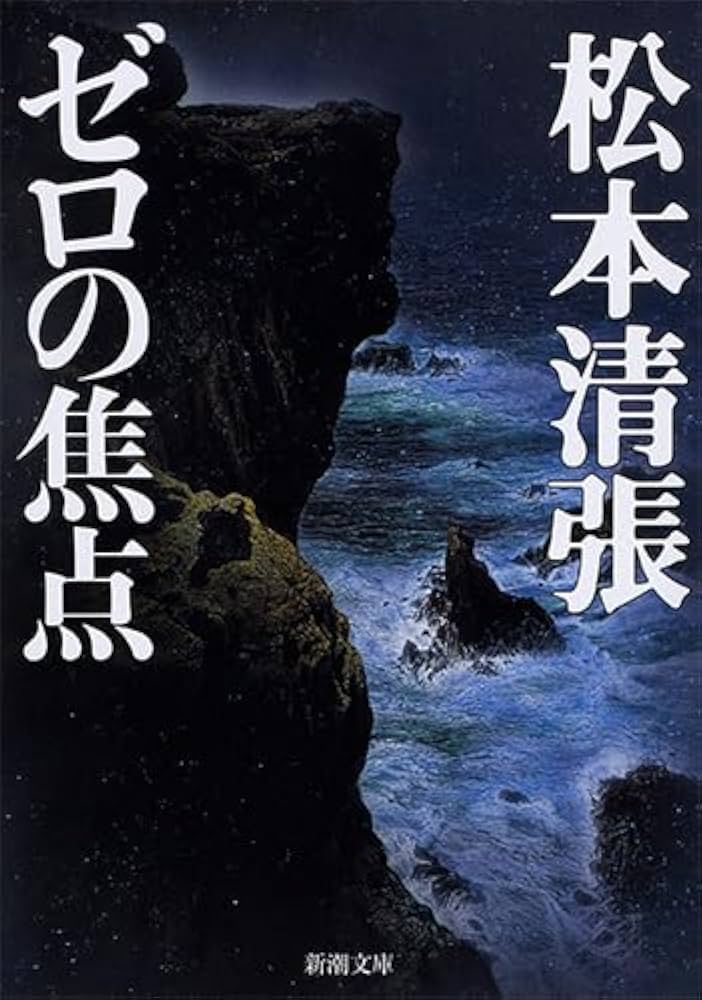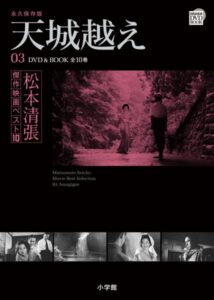 小説「天城越え」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「天城越え」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
松本清張の短編小説であり、彼の代表作の一つとして数えられるこの物語は、多くの人を惹きつけてやみません。単なる犯罪ミステリーという枠には到底収まらない、人間の心の深淵を鋭くえぐるような物語です。一度読めば、その暗くも美しい世界観と、登場人物たちのやるせない運命に心を揺さぶられることでしょう。
この記事では、まず物語の骨格となるあらすじを追いかけます。どのような事件が起こり、人々がどう関わっていくのかを見ていきましょう。事件の核心に触れる部分までは伏せますが、物語の不穏な空気は十分に感じ取っていただけるはずです。
そして、記事の後半では、物語の結末を含む重大なネタバレに踏み込みながら、詳細な感想を綴っていきます。なぜ少年はあの行為に及んだのか、酌婦ハナがとった行動の意味、そして三十年後に訪れる衝撃の真実。物語に隠されたテーマを深く読み解いていきますので、すでに作品を読んだ方も、新たな発見があるかもしれません。
「天城越え」のあらすじ
物語は、16歳の少年が家出を決意するところから始まります。静岡での奉公生活に嫌気がさし、「他国」への漠然とした憧れを胸に、彼は故郷を飛び出すのです。旅の目的地は、伊豆半島の向こう側。鬱蒼と茂る木々に囲まれた天城の山道を、少年はたった一人で歩き進んでいきます。
その道中、彼は一人の美しい女性と出会います。派手な着物をまとった、素足の女。大塚ハナと名乗る彼女は、訳ありの身の上らしく、どこか影のある雰囲気を漂わせていました。しかし、少年は一目で彼女に心を奪われます。二人は道連れとなり、天城峠の暗いトンネルを目指して、束の間の穏やかな時間を共に過ごすのでした。
しかし、その平穏は長くは続きません。二人の前に、不潔で無骨な風体の土工が現れます。少年が嫌悪感を抱くその男に、ハナは「大事な話があるから」と言い、少年を先に進ませます。嫉妬と裏切られたような気持ちで一人待つ少年の心は、不安でかき乱されていきます。
やがて、その土工が死体となって発見されます。警察の捜査線上に浮かび上がったのは、被害者と行動を共にしていた酌婦、大塚ハナでした。状況証拠は彼女に不利なものばかり。しかし、彼女は頑として犯行を否認します。果たして、本当に彼女が犯人なのでしょうか。それとも、真犯人は他にいるのでしょうか。事件は深い霧の中へと迷い込んでいきます。
「天城越え」の長文感想(ネタバレあり)
「天城越え」という物語は、なぜこれほどまでに私たちの心を捉えるのでしょうか。それは、この物語が単に「誰が犯人か」を当てる謎解きに留まらず、人間の心の奥底に潜む、光と闇の根源的な部分に触れているからに他なりません。特に、思春期という不安定な時期の少年が体験する出来事として描かれることで、その切実さと残酷さが際立つのです。
物語の主人公である16歳の少年。彼の家出の動機は、原作においては非常に曖昧に描かれています。後年の映画化などで加えられた「母親の不貞を目撃した」という分かりやすいトラウマは、実は原作にはありません。原作の彼は、もっと漠然とした、それでいて強烈な閉塞感から逃れるために旅に出ます。この「理由のなさ」こそが、思春期の少年が抱える、言葉にならない焦燥感や現実からの逃避願望を、より普遍的なものとして描き出しているように感じます。
そんな彼の前に現れるのが、酌婦の大塚ハナです。彼女は、少年が生まれて初めて強烈に惹かれた異性であり、母性を感じさせる庇護者であり、そして彼の短い旅を彩る聖女のような存在でした。少年は、世間の垢にまみれているはずの彼女に、純粋で汚されることのない理想の女性像を投影します。この理想化こそが、のちに起こる悲劇の引き金となってしまうのです。
この物語の構造を理解する上で、川端康成の「伊豆の踊子」との比較は欠かせません。同じく伊豆の天城路を舞台に、若い主人公と旅芸人の出会いを描いた「伊豆の踊子」が、淡く清らかな恋物語、いわば「陽」の世界であるのに対し、「天城越え」は生々しく、人間の欲望や社会の暗部を抉り出す「陰」の世界として描かれています。エリート学生と清純な踊り子ではなく、家出少年と酌婦。松本清張は、意図的にこの対比を用いることで、ロマンティックなだけではない、もう一つの伊豆の物語を私たちに提示したのです。
少年とハナの束の間の旅に割り込んでくるのが、土工の存在です。彼は、少年が抱いていた理想の世界を破壊する、圧倒的な「現実」の象徴と言えるでしょう。汚れた身なり、粗野な振る舞い。少年がハナに見ていた清らかなイメージとは正反対の、猥雑で暴力的な男性性の具現化です。少年が彼に抱く嫌悪感は、そのまま、彼が逃げ出してきた息苦しい現実世界への嫌悪感と重なります。
そして、物語は決定的な瞬間を迎えます。これが重大なネタバレになりますが、ハナが土工と体を重ねる場面を、少年は目撃してしまうのです。彼が聖女のように崇めていたハナが、最も忌み嫌っていた土工に「汚される」光景。それは、少年の脆い精神を根底から破壊するのに十分すぎる出来事でした。彼の理想は粉々に砕け散り、純粋な思慕は、嫉妬と所有欲、そして裏切りに対する激しい怒りへと変貌します。
土工がハナに金を渡して別れた後、少年は隠し持っていた刃物で土工に襲いかかります。この殺人行為は、単に恋敵を排除するという動機だけでは説明がつきません。それは、自らの聖域を汚した「不浄なもの」を排除し、破壊された理想の世界を回復させようとする、歪んだ儀式のようなものでした。彼は土工を殺すことで、ハナを汚した現実そのものを抹殺しようとしたのです。
事件後の警察の捜査は、当時の社会が持つ偏見を浮き彫りにします。担当の田島刑事らは、酌婦であるハナが金目当てに土工を殺害したに違いない、という先入観に囚われます。現場に残された小さな足跡を「女のものだ」と断定し、強引な取り調べでハナを追い詰めていく。ここには、真実の追求よりも、都合の良い物語を作り上げようとする権力の姿に対する、松本清張の鋭い批判精神が表れています。
この物語のもう一つの大きな謎、それはハナの「沈黙」です。彼女は、少年が犯人であることに薄々気づいていた、あるいは確信していたかもしれません。にもかかわらず、彼女は最後まで少年をかばい、自分にかけられた疑いを晴らす決定的な証言をしませんでした。なぜか。それは、彼女が「堕ちた女」として社会から扱われる自らの運命を諦観し、まだ未来のある少年の人生を守ろうとしたからではないでしょうか。自分に向けられた少年の純粋な眼差しに対する、あまりにも悲しく、そして気高い返礼だったのかもしれません。
結局、決定的な証拠不十分でハナは釈放され、事件は迷宮入りとなります。少年は罪を問われることなく、日常へと戻っていきました。この結末は、正義がいかに階級や性別、年齢といった社会的属性によって歪められるかを示しています。酌婦というだけで犯人扱いされるハナと、「子供」であるというだけで容疑者とすら見なされない少年。その対比は、社会の構造的な不条理を告発しているのです。
物語は、ここで終わりません。三十年の時が流れ、印刷業を営み、家庭を築いた主人公のもとを、一人の老人が訪れます。かつて事件を担当した、老いた田島刑事でした。彼は、時効となった「天城山土工殺し事件」の捜査資料の印刷を依頼しに来たのです。そして、静かに語り始めます。あの事件の失敗は、小さな足跡を女のものと決めつけたことだった、犯人は子供だったのだ、と。
この三十年後の再会の場面は、息を飲むほどの緊張感に満ちています。主人公は何も語りません。しかし、その沈黙と動揺が、すべてを物語っています。田島の訪問は、犯人を逮捕するためではありません。公訴時効はとっくに成立しています。彼の目的は、自らの刑事人生に突き刺さった棘を抜くための、個人的なケジメであり、遅すぎた真実との対峙でした。
そして、物語は主人公の内なる独白で締めくくられます。彼は悟るのです。法律上の犯罪には時効がある。しかし、自分の心に刻まれた罪の記憶、良心の呵責には時効がないのだ、と。老刑事によって再びこじ開けられた記憶の蓋。それは、彼にとって死ぬまで続く「終身刑」の始まりを告げるものでした。
「天城越え」というタイトルは、単に地理的な峠を越えることを意味しているのではありません。それは、少年が大人へと足を踏み入れるための、血塗られた「通過儀礼」の謂いでした。しかし、彼はその峠を越えた先で安息を得るのではなく、生涯消えることのない罪の意識という重荷を背負い続けることになったのです。
松本清張の乾いた筆致は、登場人物の感情を過度に描写することなく、その行動と状況設定の中から、人間のどうしようもない業(ごう)や悲しみを浮かび上がらせます。だからこそ、読者は行間から登場人物の胸の内を想像し、物語の世界に深く引き込まれるのでしょう。
この物語を読むたびに、私は人間の心の不可解さに思いを馳せます。一人の少年の心に宿った、聖なるものへの憧れと、それが裏切られた時の破壊的な衝動。そして、一人の女性が貫いた、あまりにも悲しい誠実さ。
それらはすべて、天城の深い緑と暗いトンネルの中に吸い込まれ、三十年という長い時間の底に沈んでいたかのようでした。しかし、記憶は決して消えません。罪は、法がそれを忘れ去ったとしても、犯した者の魂を永遠に苛み続ける。その普遍的な真理を、「天城越え」は静かに、しかし圧倒的な迫力をもって私たちに語りかけてくるのです。
まとめ
松本清張の「天城越え」は、単なる推理小説の枠を超え、読む者の心に深く突き刺さる作品です。家出した少年が天城路で出会った美しい酌婦ハナと、彼らの運命を狂わせる殺人事件。物語は、思春期の危うい心理と、どうしようもない現実との間で揺れ動く人間の姿を鮮烈に描き出しています。
この記事では、まず事件の核心には触れずに物語の導入となるあらすじを紹介し、その後、結末までのネタバレを含んだ詳細な感想と考察を展開しました。なぜ少年は罪を犯したのか、ハナはなぜ沈黙を守ったのか。そして、この物語の最大のテーマである「時効」がもたらす本当の意味について掘り下げています。
この物語の魅力は、その救いのない結末にあるのかもしれません。法的には罪を逃れた主人公が、三十年の時を経て、決して消えることのない心理的な刑罰を背負うことになるラストシーンは圧巻です。罪と罰、記憶と時間について、深く考えさせられることでしょう。
「天城越え」は、人間の心の闇と、その中に差し込む一筋の純粋な光の悲劇を描いた、不朽の名作です。この記事が、あなたがこの物語をより深く味わうための一助となれば幸いです。