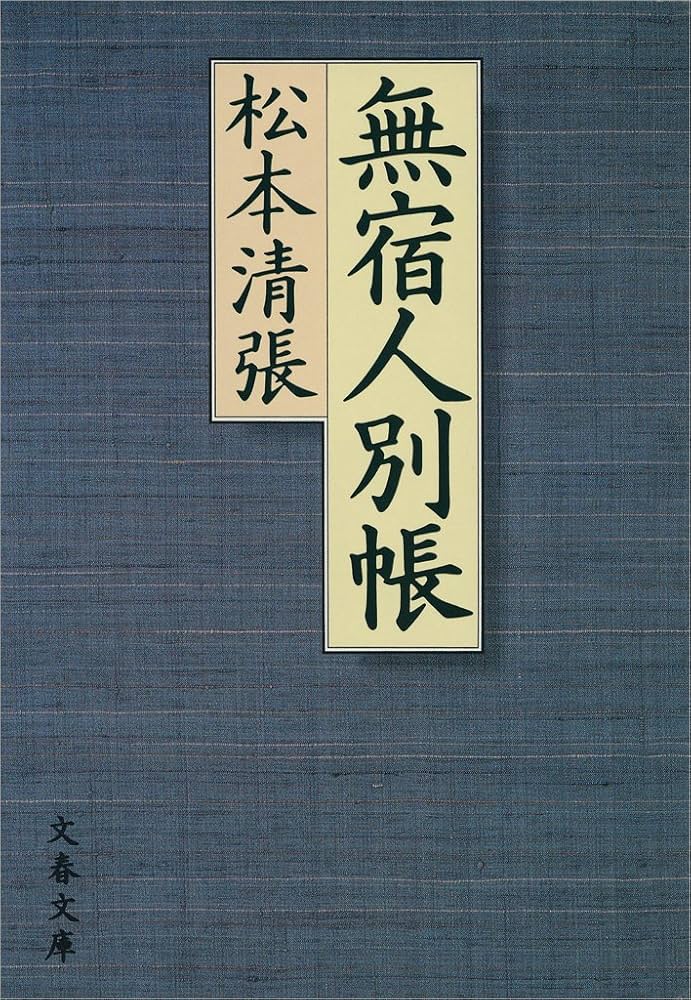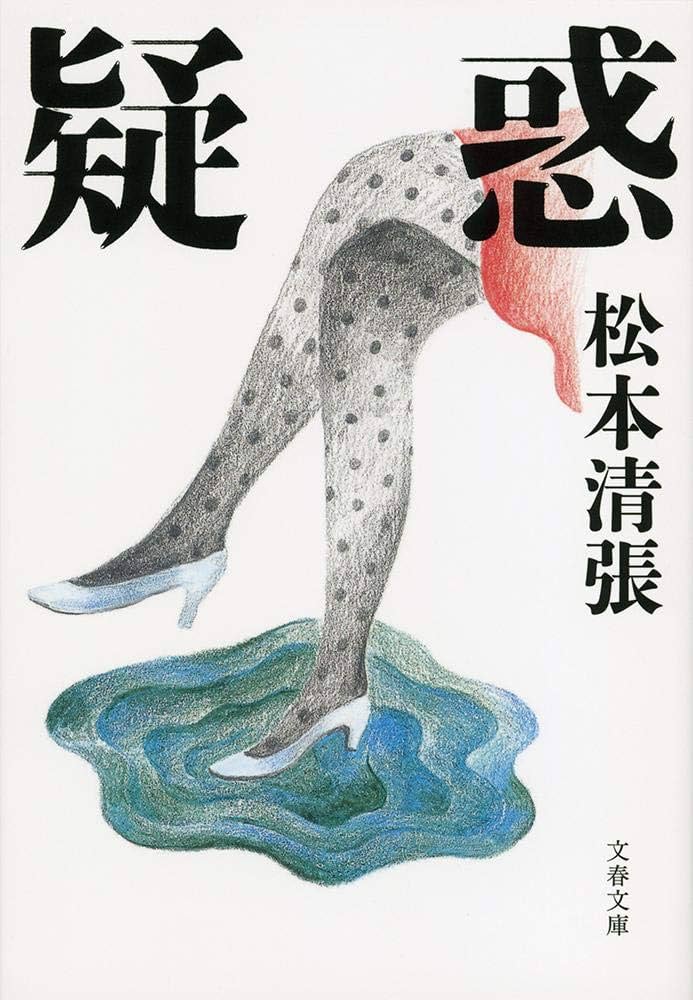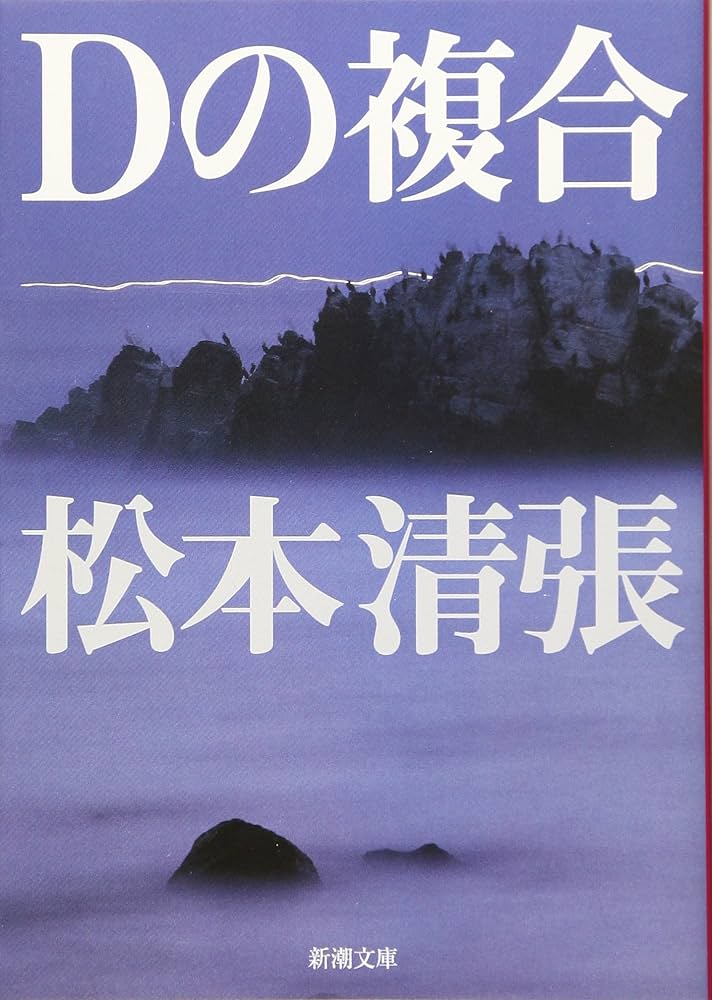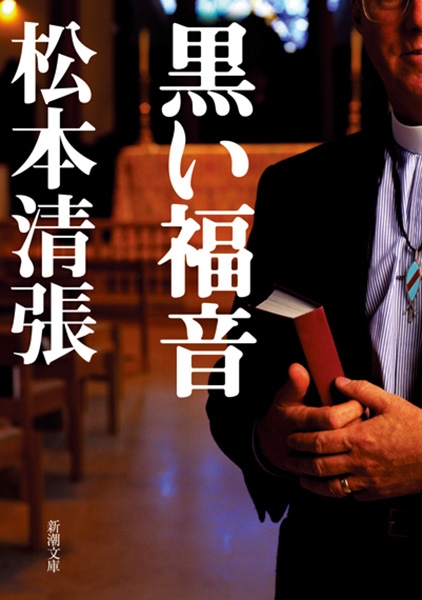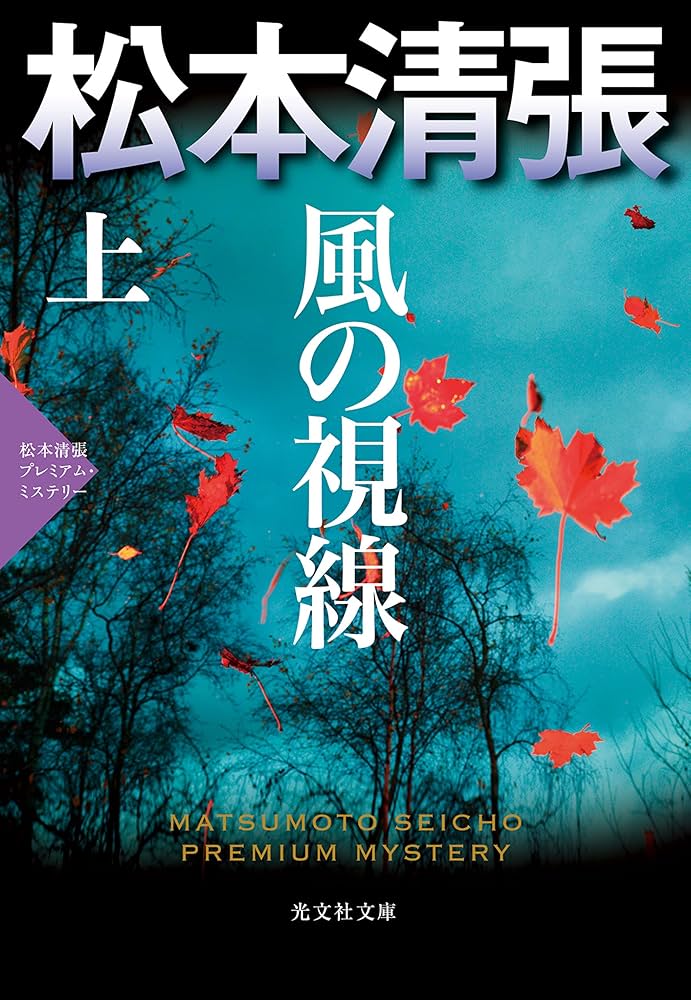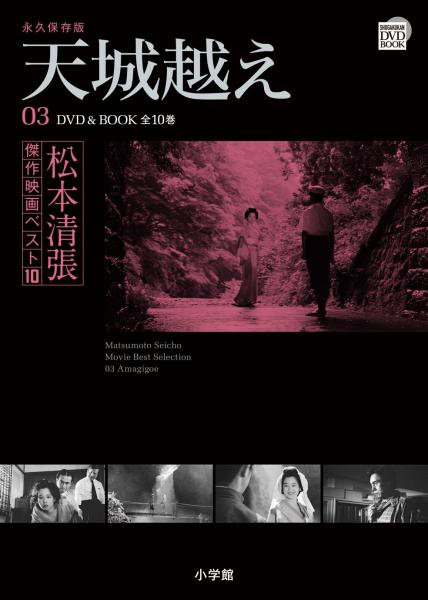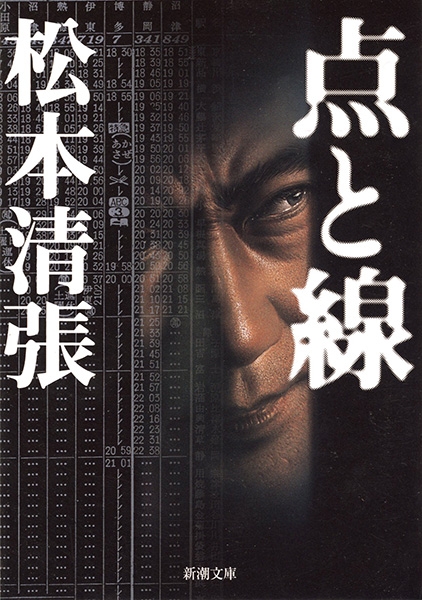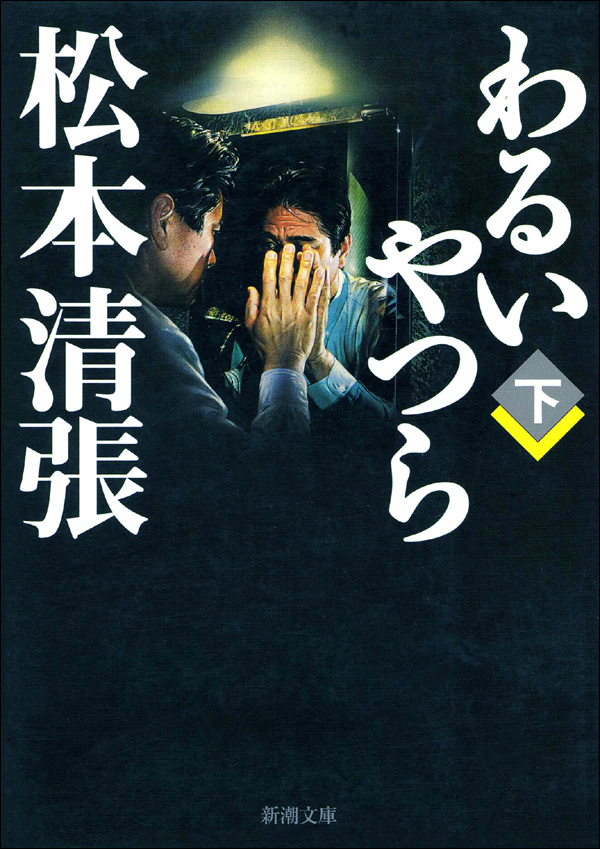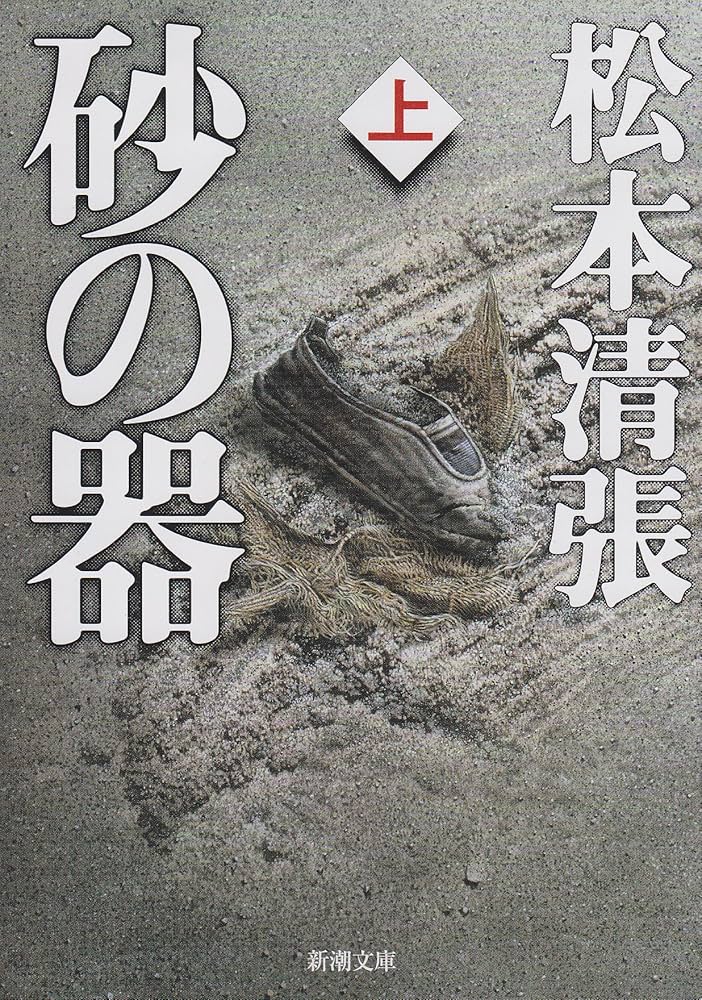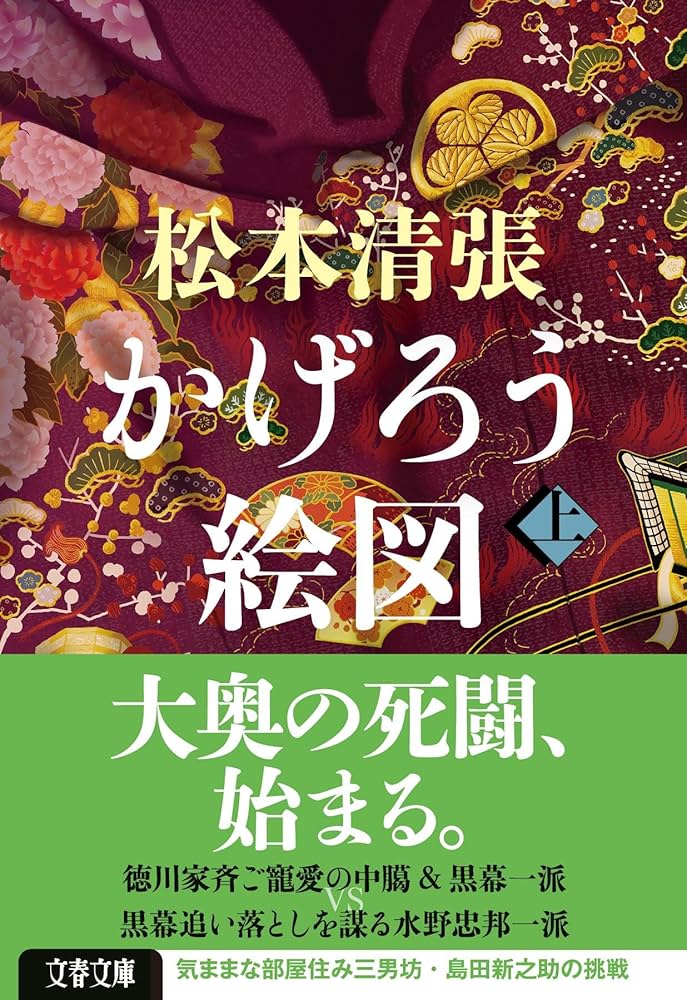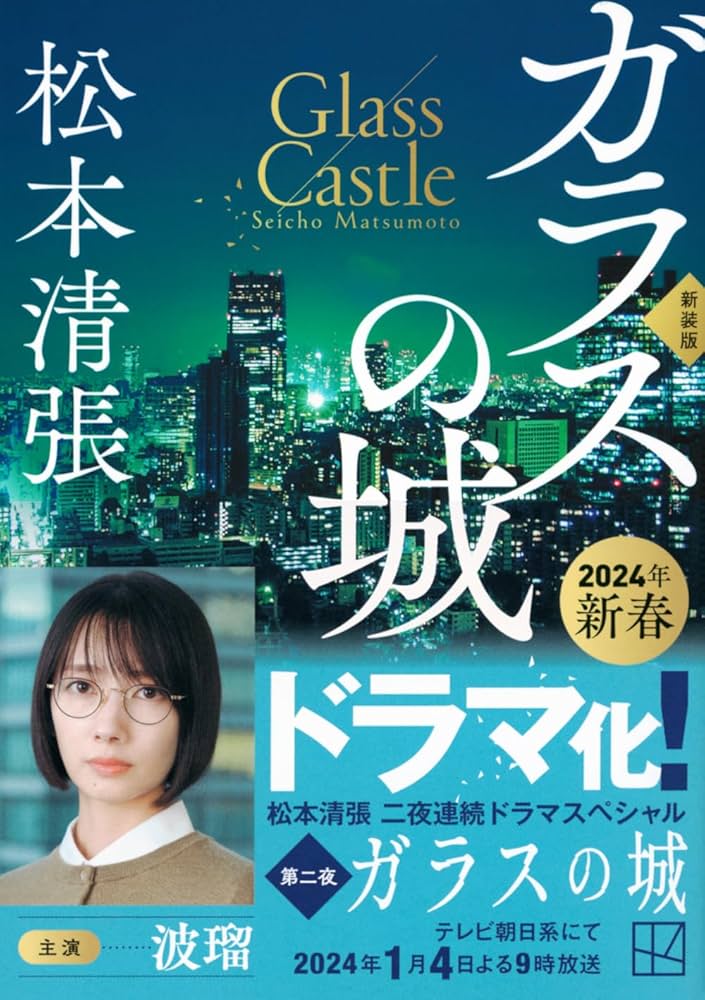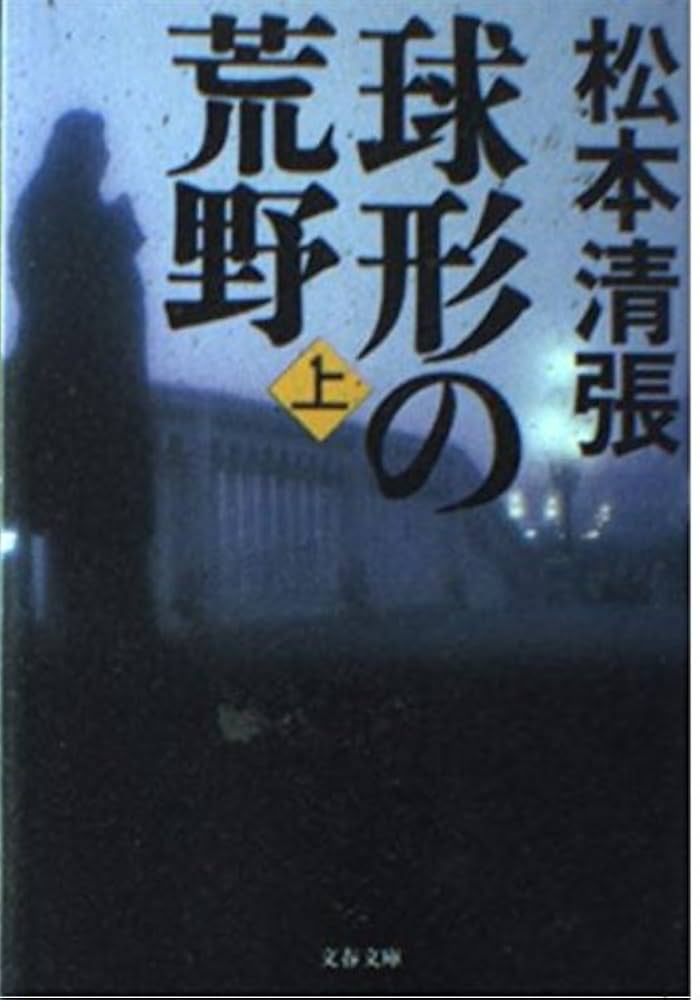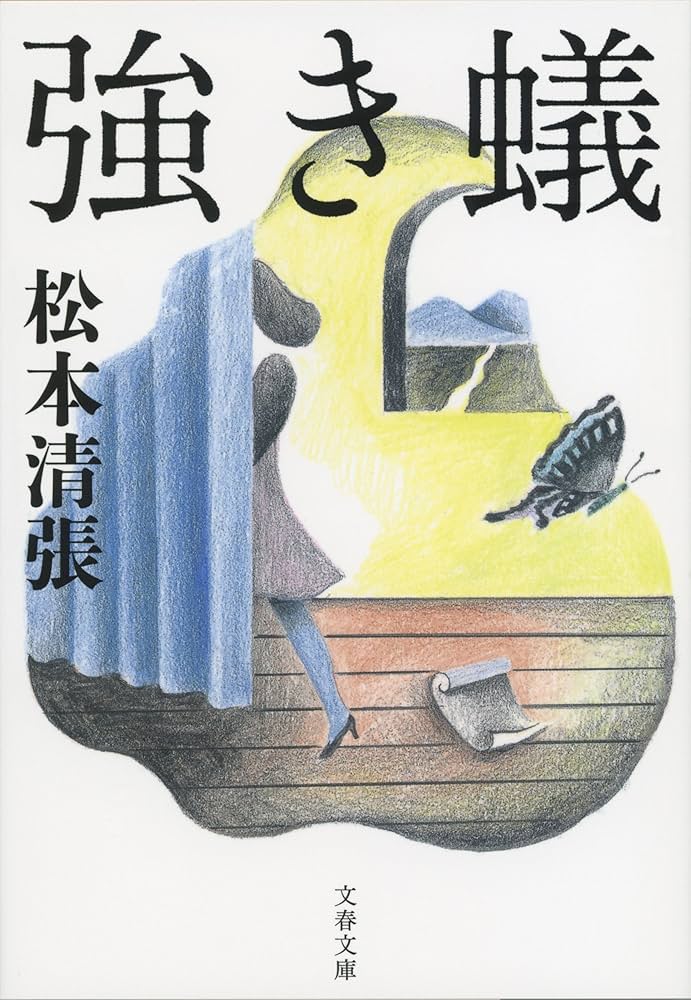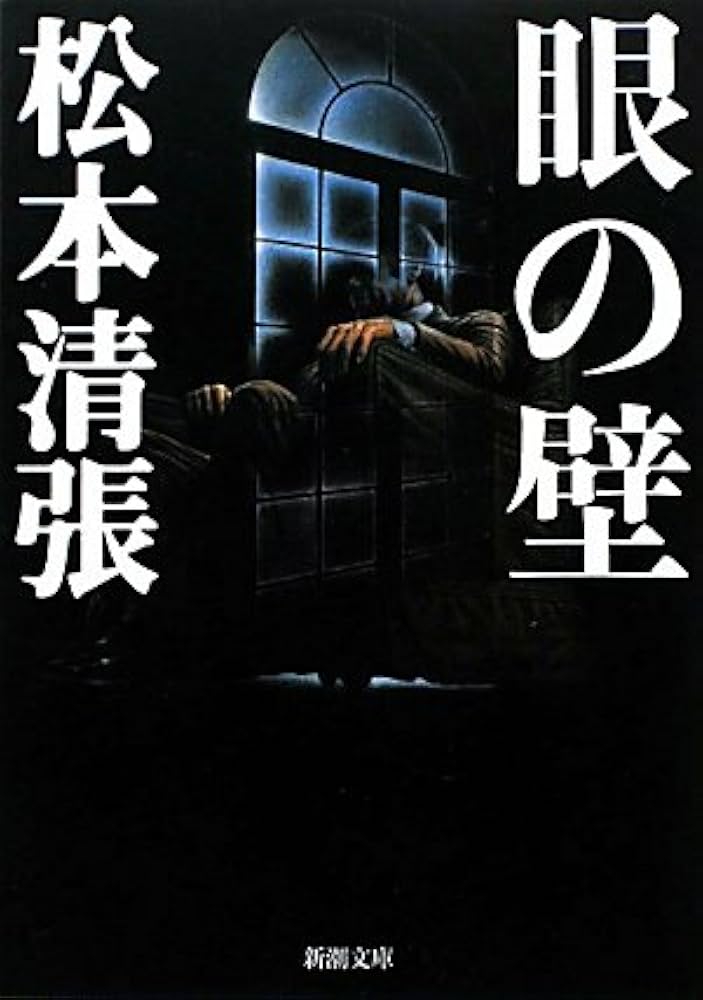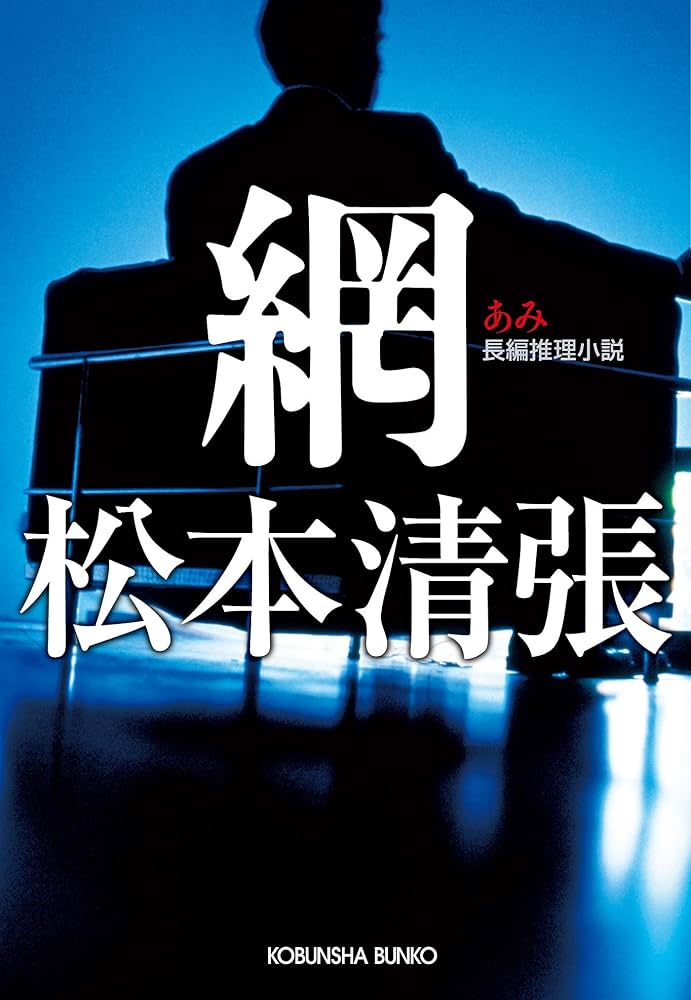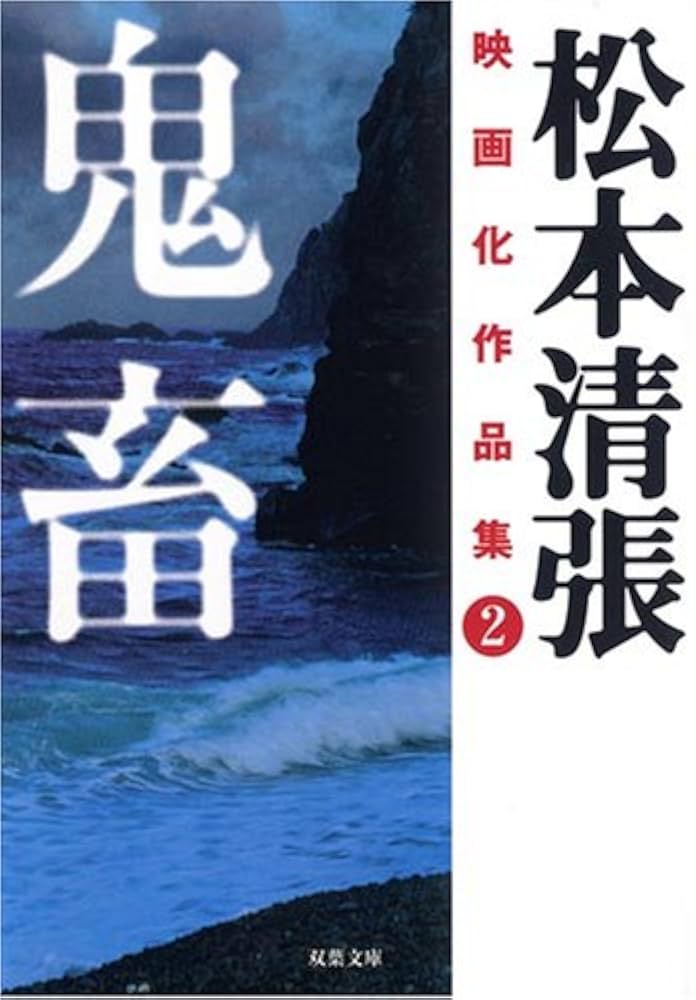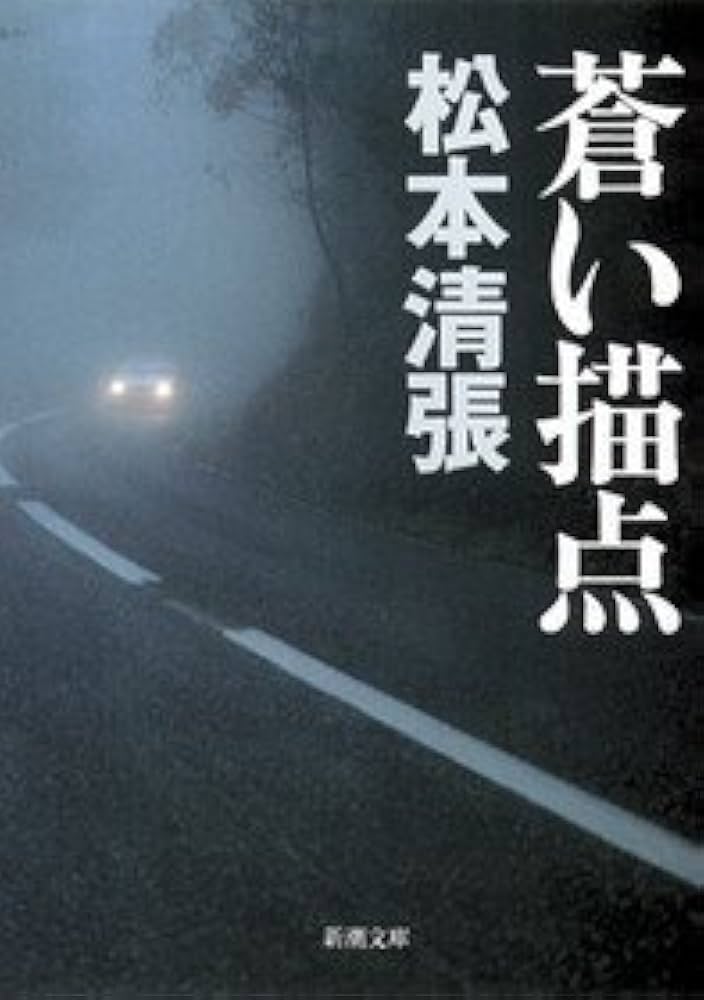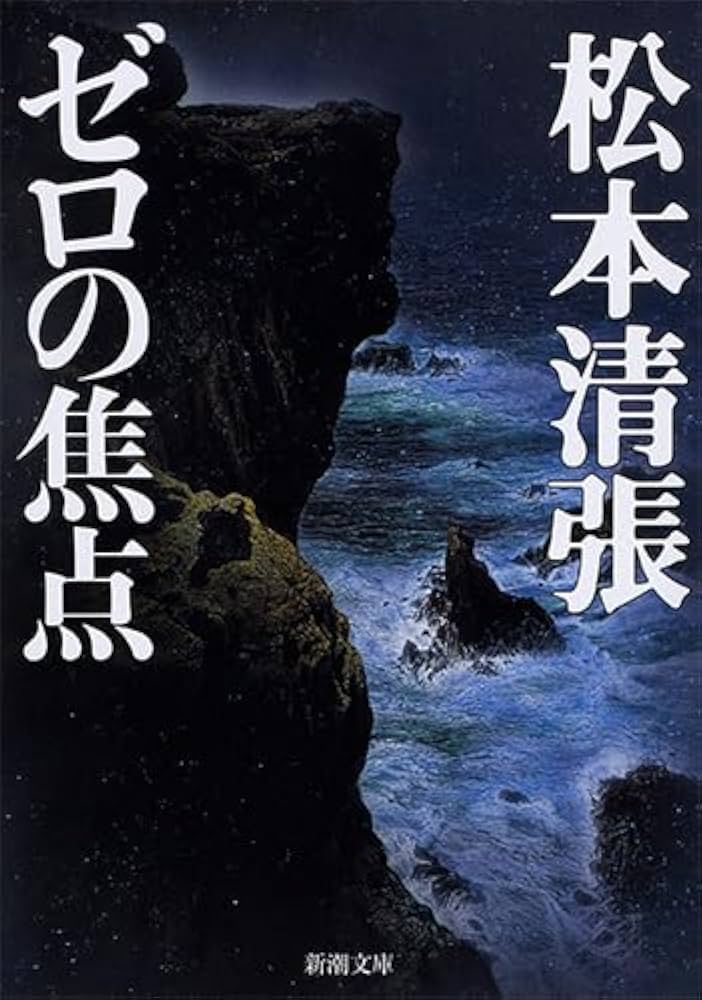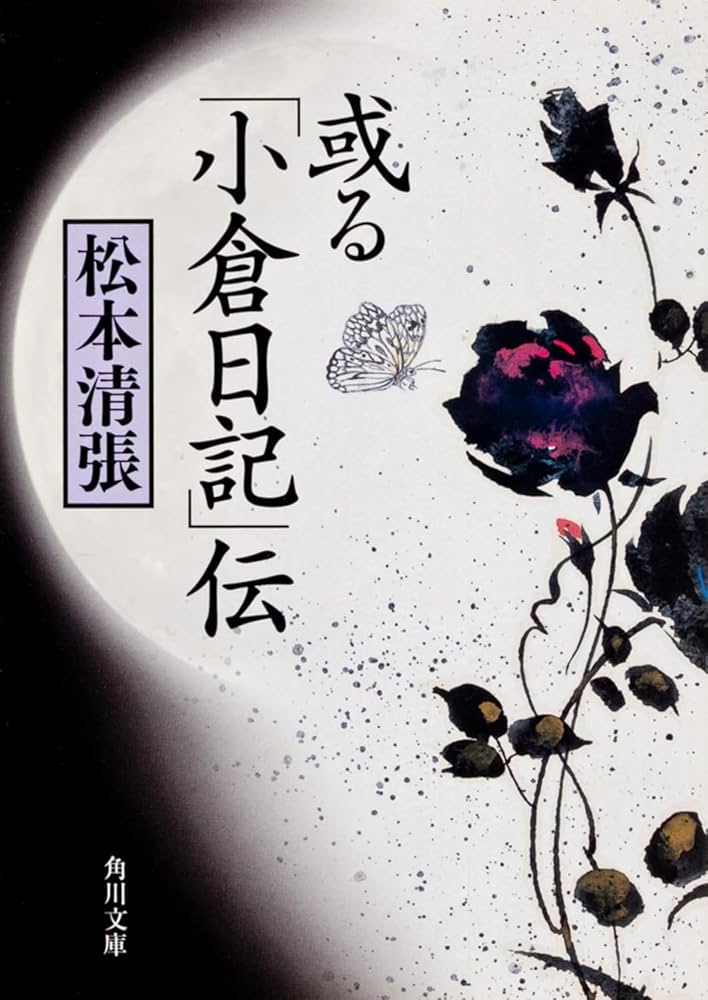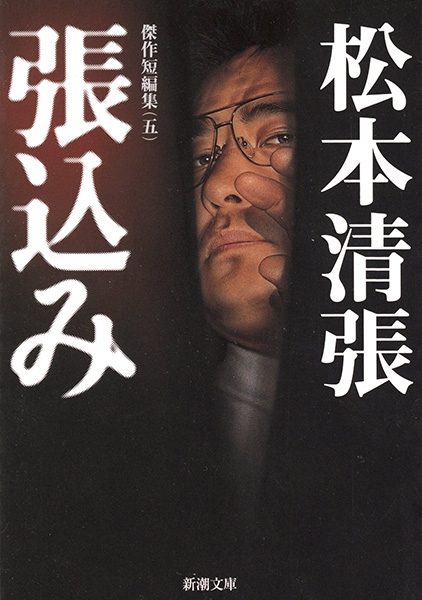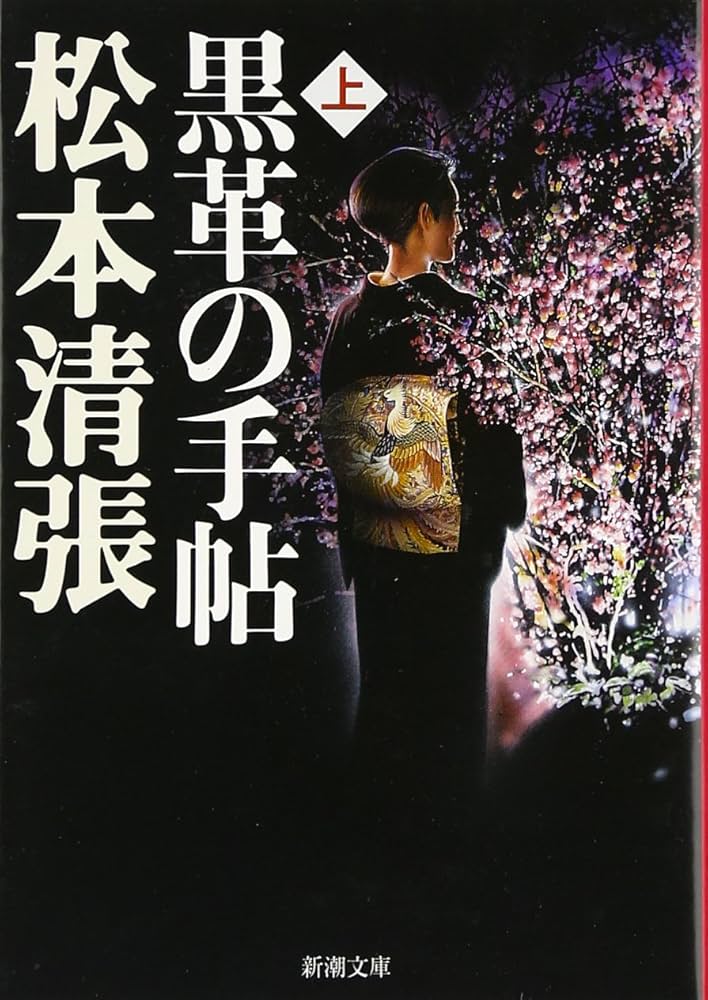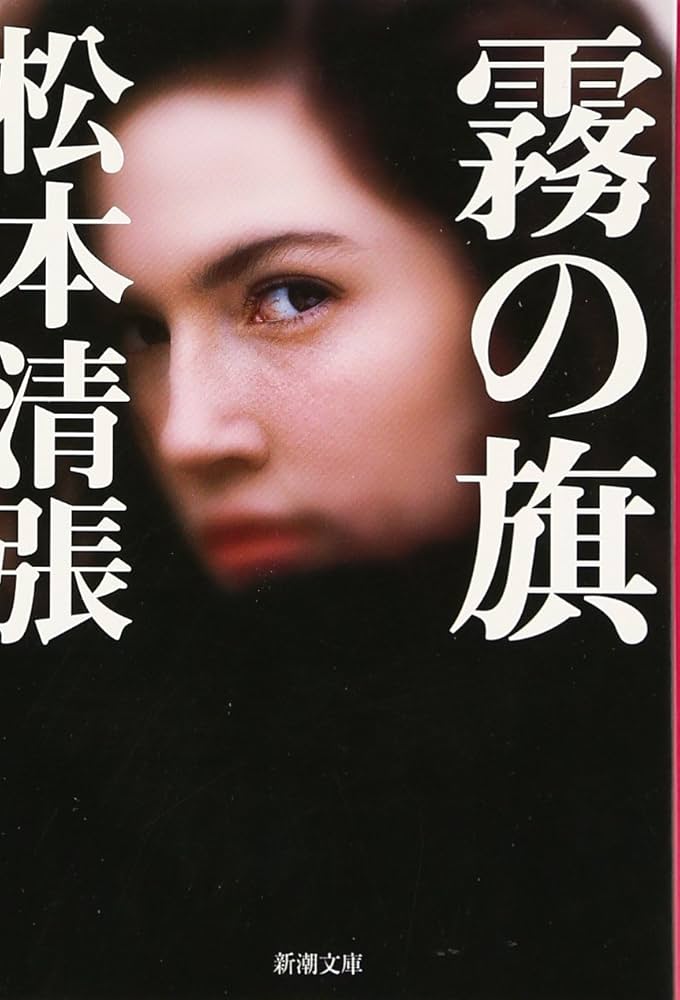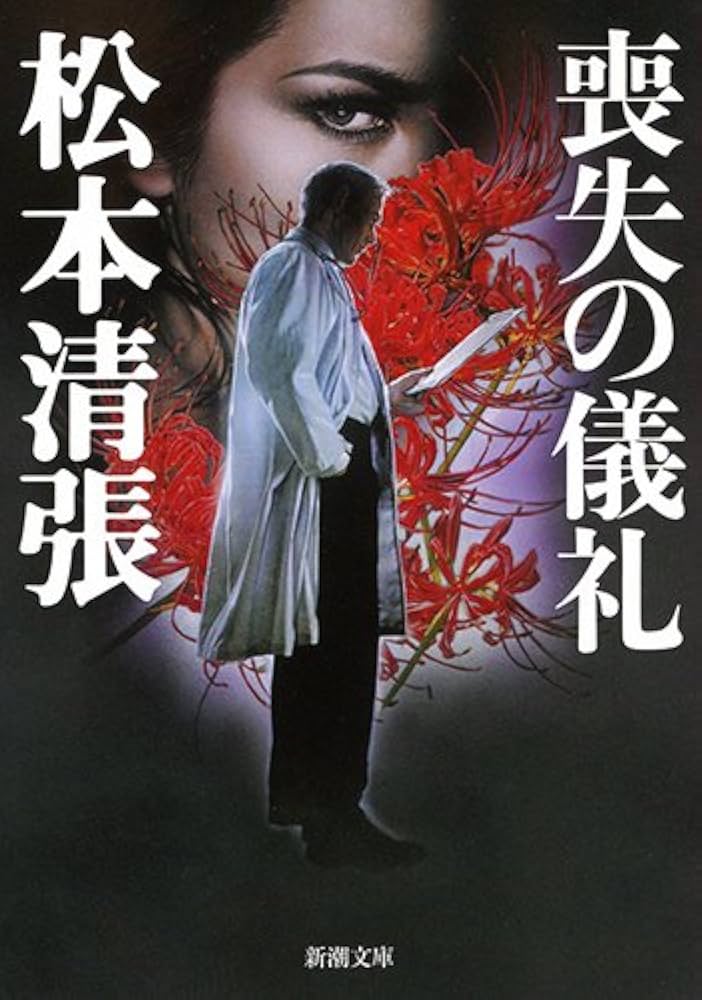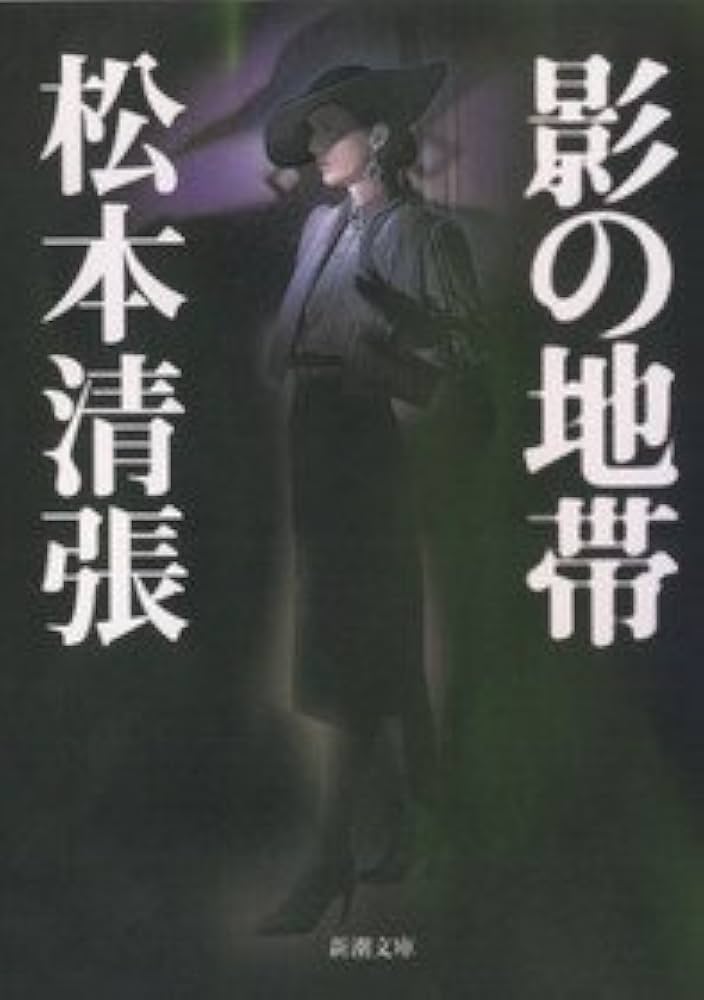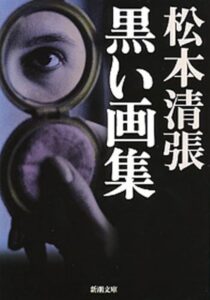 小説「黒い画集」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「黒い画集」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
松本清張の不朽の名作『黒い画集』は、単なるミステリー小説の枠に収まらない、人間の心理の深淵を鋭くえぐり出した作品群です。出版から長い年月を経ても、今なお多くの読者を魅了し続けているのは、ここに描かれている物語が、私たち自身の日常と決して無関係ではないからでしょう。
物語の主人公は、特殊な能力を持つ探偵や、世間を騒がせる大悪党ではありません。ごく平凡なサラリーマン、家庭を持つ主婦、実直に働いてきた店主といった、どこにでもいる普通の人々です。彼らがふとしたきっかけで、いかにして罪の領域に足を踏み入れてしまうのか。その過程を丹念に描くことで、人間の心の脆さや社会の歪みを浮き彫りにしていきます。
この記事では、そんな『黒い画集』シリーズの魅力について、ネタバレを含みつつ、その物語の核心に迫っていきたいと思います。なぜこの作品が社会派ミステリーの金字塔と呼ばれるのか、その理由を一緒に探っていきましょう。物語の結末を知ることで、より深く作品を味わえるはずです。
「黒い画集」のあらすじ
『黒い画集』は、私たちのありふれた日常に潜む、人間の心の闇を描き出した短編集です。物語は、一見すると何の変哲もない場面から始まります。会社の同僚との登山、愛人との密会、家庭を守るための小さな嘘。それらは、誰の身にも起こりうる出来事ばかりです。
しかし、その平穏な日常に生じたほんの僅かな亀裂が、やがて取り返しのつかない悲劇へと繋がっていきます。登場人物たちは、自らの社会的地位や家庭、ささやかな幸せを守ろうと必死にもがきます。その自己保身の気持ちが、結果として他者を、そして自分自身をも破滅の淵へと追いやってしまうのです。
この作品集が問いかけるのは、「誰が犯人か」ということ以上に、「なぜ人は罪を犯すのか」という根源的なテーマです。物語を読み進めるうちに、読者は登場人物たちの苦悩や葛藤に、自分の姿を重ね合わせてしまうかもしれません。
会社という組織の理不尽さ、男女間の愛憎、見栄や嫉妬。そうした普遍的な感情が引き起こす事件の数々は、私たちに人間の業の深さを見せつけます。それぞれの物語は独立していますが、その根底には「日常に潜む悪意」という一貫したテーマが流れています。
「黒い画集」の長文感想(ネタバレあり)
松本清張の『黒い画集』シリーズを初めて読んだときの衝撃は、今でも忘れられません。それは、巧みなトリックや意外な犯人に驚くというよりも、物語に描かれている人間の心理が、あまりにも生々しく、自分の心の中を見透かされているような感覚に陥ったからです。ここでは、ネタバレを交えながら、各作品が持つ強烈な魅力についての感想を詳しく語らせていただきたく思います。
この作品群が画期的だったのは、謎解きよりも「動機」の解明に重きを置いた点にあります。戦後日本の社会が抱える矛盾や、平凡な人々を犯罪へと駆り立てる心理的な圧力を、これでもかというほど克明に描き出しました。まさに社会派ミステリーの原点であり、頂点ともいえるでしょう。
『遭難』― 知的な完全犯罪の恐怖
まず、シリーズの幕開けを飾る『遭nan』からお話しします。この物語のネタバレは、犯人の江田が、同僚の岩瀬を殺害するために用いた方法の巧妙さにあります。彼は直接手を下すのではなく、悪天候の山という環境を利用し、水分補給や休憩のタイミングを巧みに操作することで、岩瀬を衰弱死させたのです。一つ一つの行為は善意に見せかけられており、物理的な証拠が一切残らないという、まさに「完全犯罪」でした。
この作品を読んで感じたのは、人間の知性が、いかに恐ろしい凶器になりうるかという戦慄です。真相を暴こうとした探偵役の槇田でさえ、最後は江田に殺されてしまうという結末は、あまりにも救いがありません。正義が必ずしも勝つわけではないという、松本清張の冷徹な現実認識が突きつけられます。このどうしようもない絶望感こそが、本作の忘れがたい感想の一つです。
『証言』― 一つの嘘がもたらす破滅
次に『証言』です。この物語の主人公・石野は、愛人との関係を隠すために、法廷で「殺人事件の容疑者を目撃していない」と嘘の証言をします。このたった一つの嘘が、無実の人間を追い詰め、そして最終的には自分自身の人生をも破滅させるという、強烈な皮肉に満ちた物語です。ネタバレになりますが、彼が守ろうとした地位も家庭も、その嘘が原因でより悲惨な形で失われていく結末には、言葉を失いました。
この物語を読んで強く印象に残ったのは、「人間の嘘には、人間の嘘が復讐する」という一文です。石野は決して極悪人ではありません。むしろ、私たちと同じように、自分の生活を守りたいと願う、ごく普通の人間です。だからこそ、彼の選択と転落の過程が、他人事とは思えないのです。誰の心にも潜む自己保身の怖ろしさについて、深く考えさせられる作品でした。
『坂道の家』― 抑圧された男の暴走
『坂道の家』は、平凡で真面目だけが取り柄だった男・吉太郎が、若く美しい女性りえ子にのめり込み、すべてを失っていく物語です。彼の純情は、やがて狂気的な妄執へと変わり、長年こつこつと貯めた財産を彼女につぎ込んでいきます。この物語の感想は、人間の抑圧された欲望が、一度噴出するとどれほど破壊的な力を持つかという点に尽きます。
ネタバレをすると、吉太郎は最終的に、りえ子に利用された末に命を落とします。しかし、りえ子自身もまた、不幸な過去を背負った女性として描かれることもあり、単純な悪女として断罪できない複雑さを持っています。どちらか一方が悪いのではなく、傷ついた人間同士が互いを破滅させてしまうという悲劇的な構造に、人間の関係性の哀しさを感じずにはいられませんでした。
『紐』― 歪んだ愛情の形
『紐』は、ある男性の絞殺死体が発見されるところから始まります。しかし、遺体の傍らには、殺害に使われたはずの紐が丁寧に解かれて置かれていました。この不可解な状況から、物語は驚くべき真相へと向かっていきます。ネタバレになりますが、この事件の真相は、家族に保険金を残すために夫が妻に殺害を依頼した「嘱託殺人」だったのです。
解かれた紐は、夫を殺めた後、その死を悼む妻の矛盾した愛情の証でした。このささやかな、しかし決定的な手がかりから事件の核心に迫っていく展開は見事です。愛情や犠牲といった美しい観念が、いかにして殺人を正当化する論理へと姿を変えてしまうのか。その恐ろしさと悲しさについての感想が、深く心に残りました。経済的な困窮が、人間をここまで追い詰める社会への批判も感じ取れます。
『寒流』― 組織と個人の非情な力学
『寒流』は、銀行という組織を舞台にした、権力闘争の物語です。上司に恋人を奪われ、左遷させられた主人公の沖野が、復讐を試みるも、組織という巨大な力の前にことごとく打ちのめされていきます。この物語には、ミステリー的な爽快感は一切ありません。残るのは、一個人の無力さと、巨大な機構には決して勝てないという厳しい現実だけです。
ネタバレすると、沖野の計画はすべて上司の桑山に見抜かれており、最後は完膚なきまでに叩きのめされて終わります。この救いのない結末は、サラリーマン経験のある読者にとっては、身につまされるものがあるのではないでしょうか。恋愛のもつれを発端としながら、その本質は企業社会の非情な力学を描いている点に、社会派作品としての真骨頂を感じました。読後には、重苦しい敗北感が残る作品です。
『凶器』― 食べてしまった凶器
『黒い画集』シリーズの中でも、ひときわ異彩を放つのが『凶器』です。この物語は、ある殺人事件の凶器がどうしても見つからない、という謎を扱っています。そして、時効成立後に明かされるその真相は、まさに悪魔的としか言いようがありません。ネタバレになりますが、犯人が使った凶器は、なんと巨大な「かき餅」だったのです。
犯人の女は、そのかき餅で相手を殴り殺した後、それを砕いてぜんざいを作り、捜査をしていた刑事たちにまで振る舞っていました。つまり、凶器は犯人を追う者たちによって「食べられて」消滅したのです。このブラックユーモアに満ちた結末には、恐怖と同時に、どこか乾いた笑いすら覚えました。人間の悪意の底知れなさと、そのしたたかさに対する、忘れられない感想を抱かせる傑作です。
『天城越え』― 少年の心に刻まれた罪
最後に、映像化も多くされている名作『天城越え』について触れないわけにはいきません。家出をした14歳の少年が、旅の途中で出会った美しい娼婦ハナ。彼女に淡い思慕を抱く少年ですが、ある出来事をきっかけに、その純粋な心は激しい殺意へと変わってしまいます。この物語は、思春期特有の揺れ動く心理を見事に描き切っています。
この物語の最も重要なネタバレは、ハナと一緒だった土工を殺害した真犯人が、少年自身であったという点です。そして、ハナは少年の犯行だと気づきながらも、彼を庇って黙秘を続けたのです。その沈黙が、少年の人生に三十年以上も続く重い十字架を背負わせることになります。これは単なる殺人事件の物語ではなく、一人の人間の心に深く刻まれた、決して消えることのない罪の記憶を巡る物語なのです。その文学的な深さに、ただただ圧倒されました。
これらの作品群を通じて感じるのは、松本清張の人間に対する冷徹でありながらも、どこか哀れみを含んだ眼差しです。彼は、犯罪という極限状況を通して、人間の本質とは何かを問い続けているように思えます。
『黒い画集』に描かれた物語は、決して過去のものではありません。現代社会に生きる私たちもまた、登場人物たちと同じように、様々なプレッシャーの中で生きています。この作品を読むことは、自分自身の心に潜む闇と向き合うことでもあるのです。だからこそ、この「画集」は、これからも多くの人々の心を捉え、静かな戦慄を与え続けるに違いありません。
まとめ
松本清張の『黒い画集』は、私たちの日常に潜む心の闇を見事に描き出した、日本ミステリー文学の金字塔です。この作品集が投げかけるのは、単なる謎解きではなく、「なぜ人は一線を越えてしまうのか」という、深く、そして普遍的な問いかけでした。
各物語で描かれる、平凡な人々が罪に堕ちていく過程は、非常に生々しく、読んでいるこちらの胸を締め付けます。自己保身のための嘘、抑えきれない嫉妬、組織の中での無力感。そうした感情は、現代を生きる私たちにとっても決して他人事ではありません。だからこそ、この作品は時代を超えて共感を呼び、多くの読者を惹きつけてやまないのでしょう。
この記事では、代表的な作品のあらすじと、結末に触れるネタバレを含む感想を記してきました。衝撃的な真相を知ることで、それぞれの物語に込められた人間の業の深さや、社会の矛盾といったテーマが、より鮮明に浮かび上がってきたのではないでしょうか。
まだ『黒い画集』を手に取ったことがない方も、あるいは昔読んだきりという方も、ぜひこの機会にページをめくってみてください。そこには、あなたの心を揺さぶり、深く考えさせる、忘れがたい読書体験が待っているはずです。