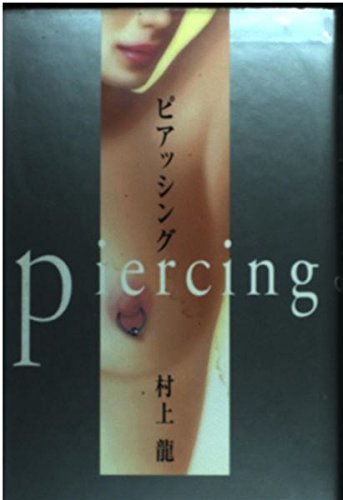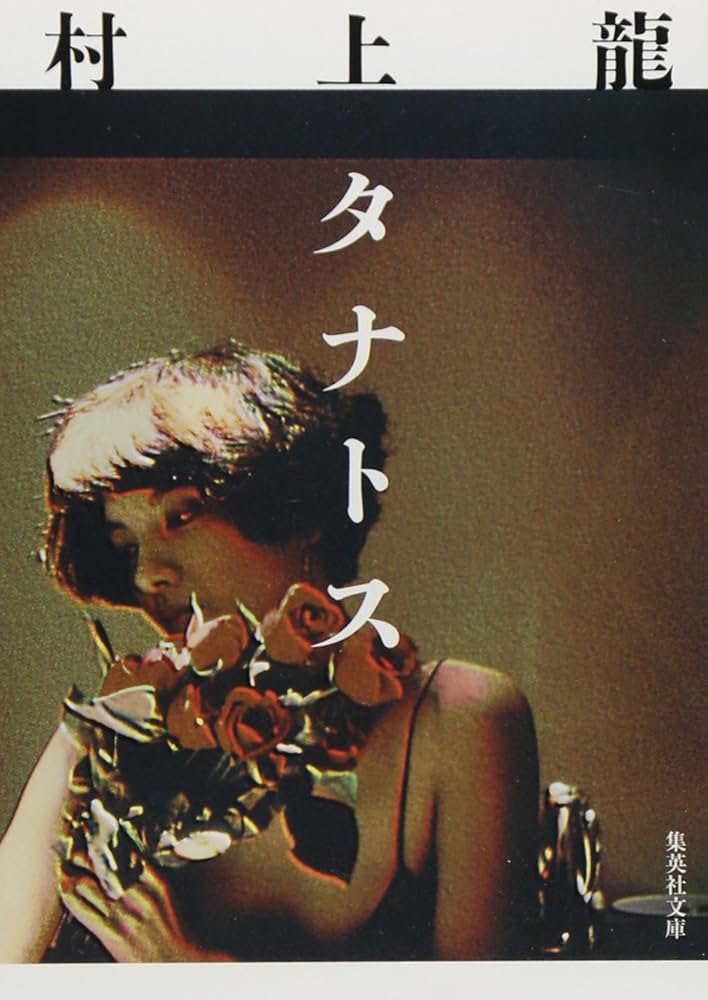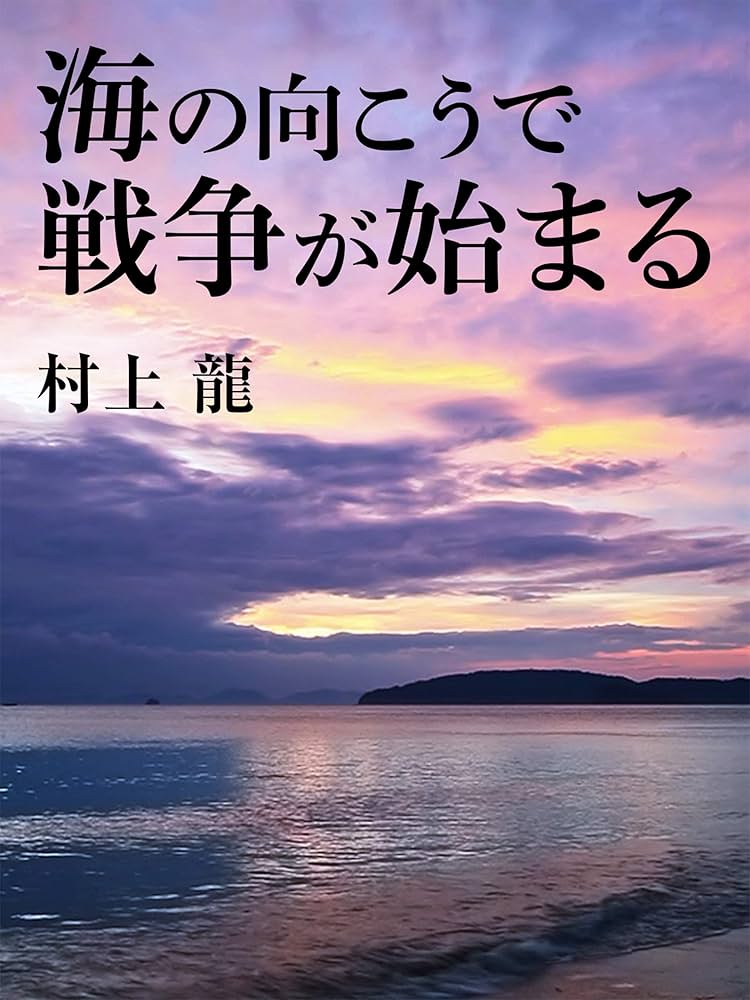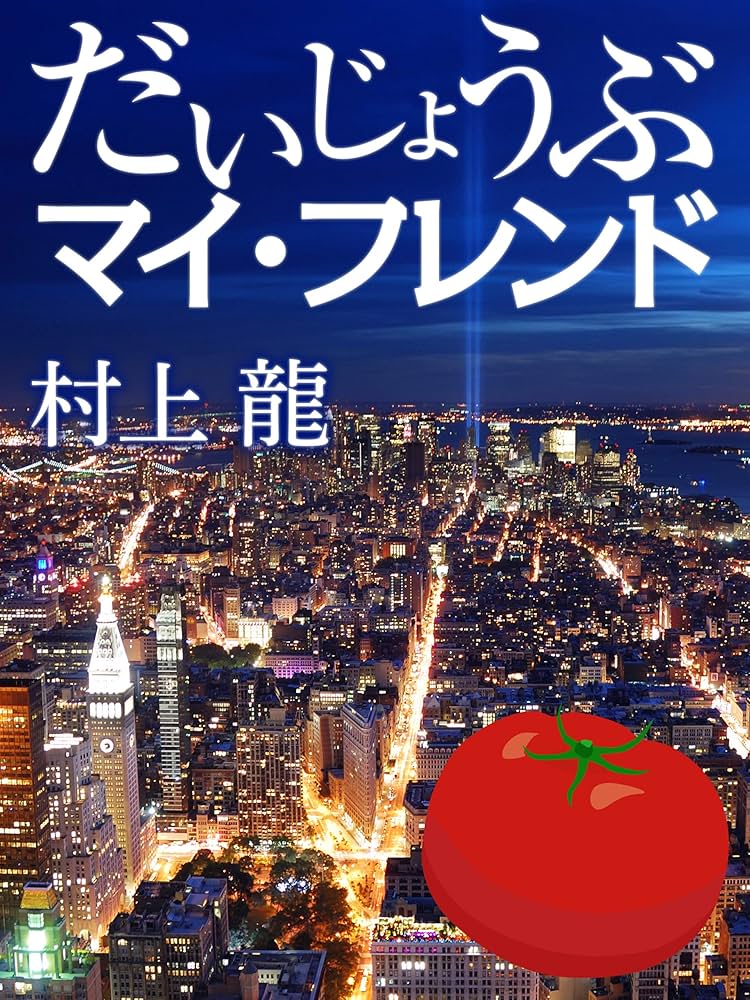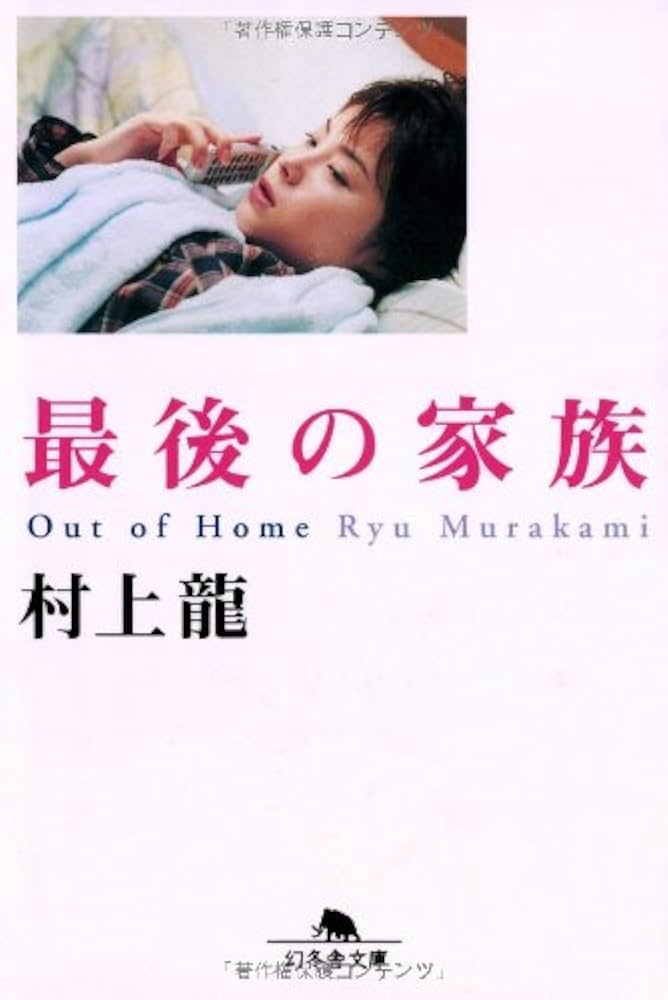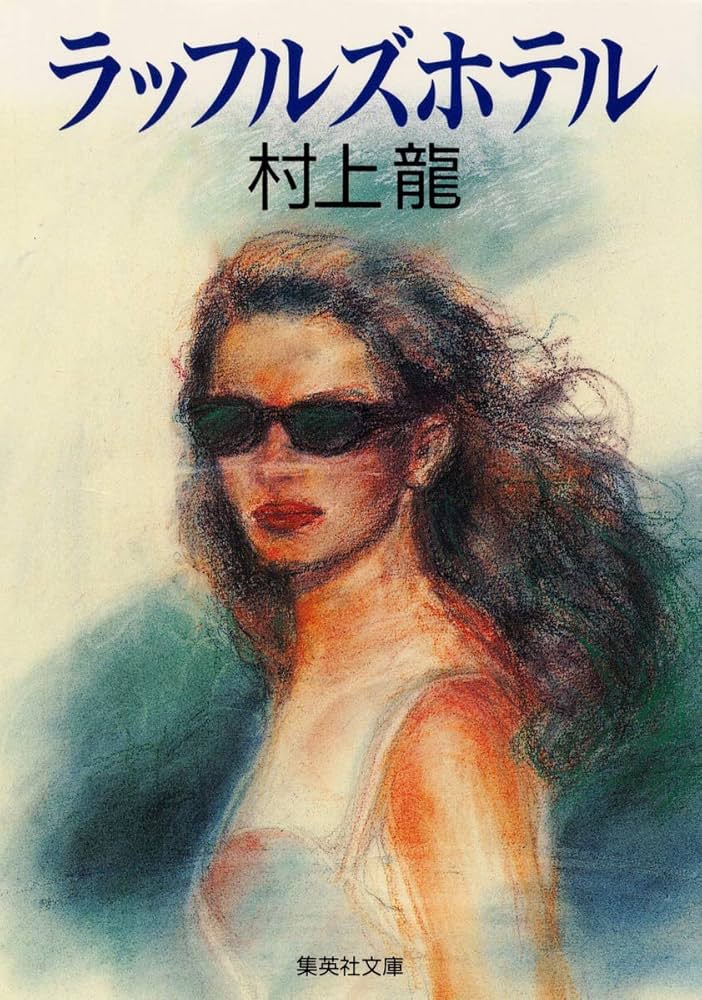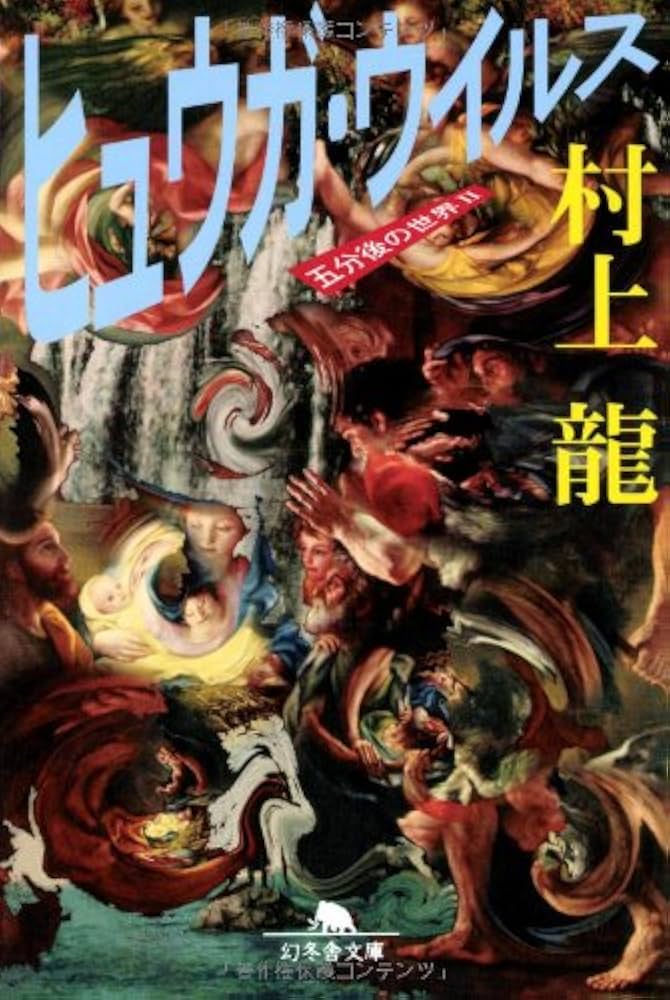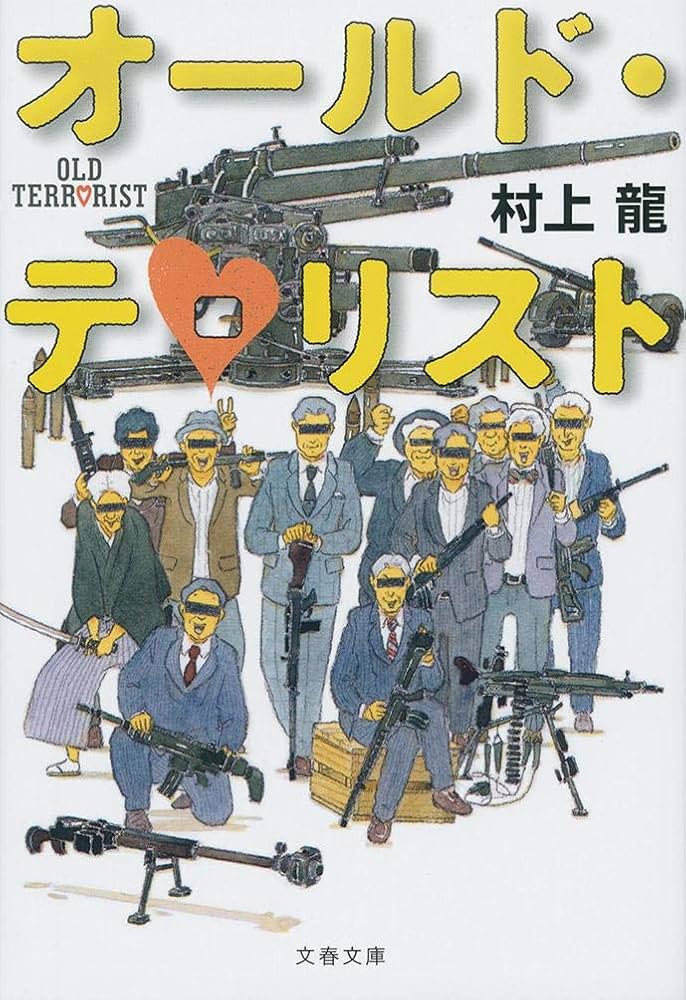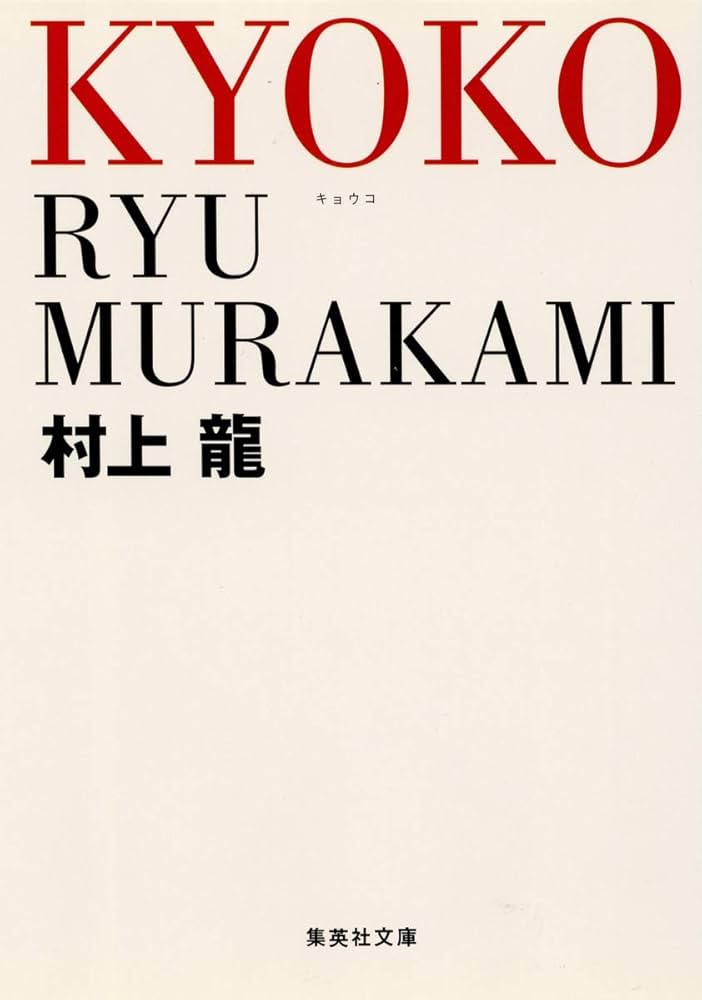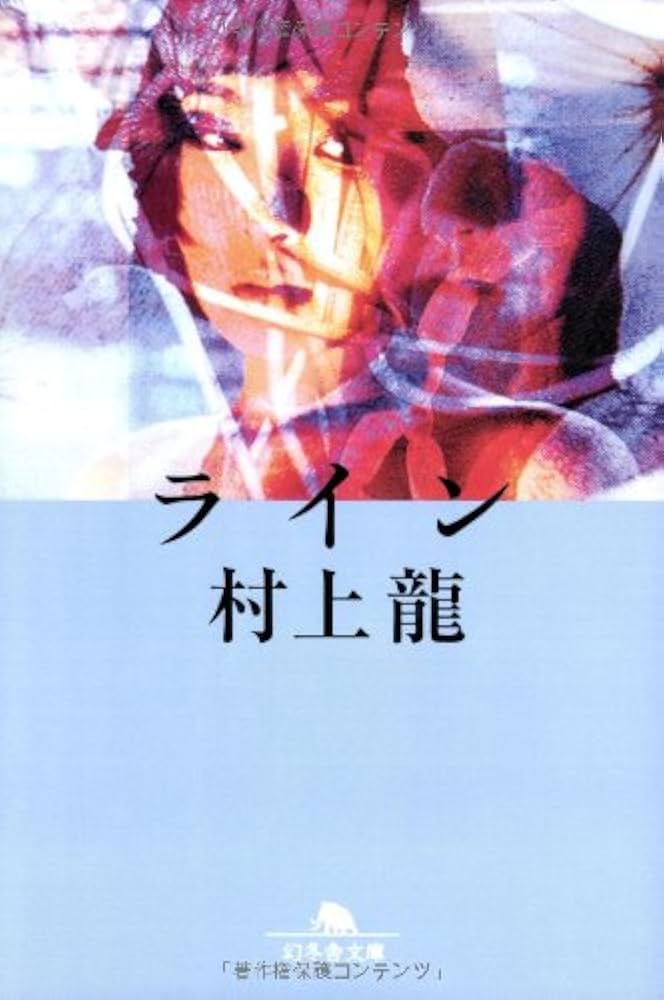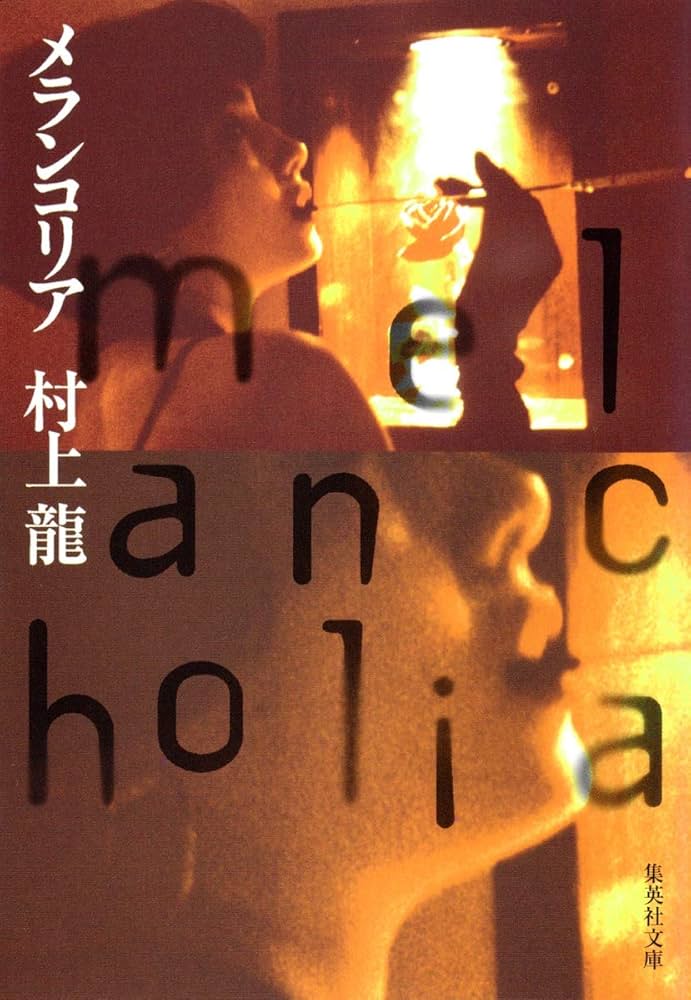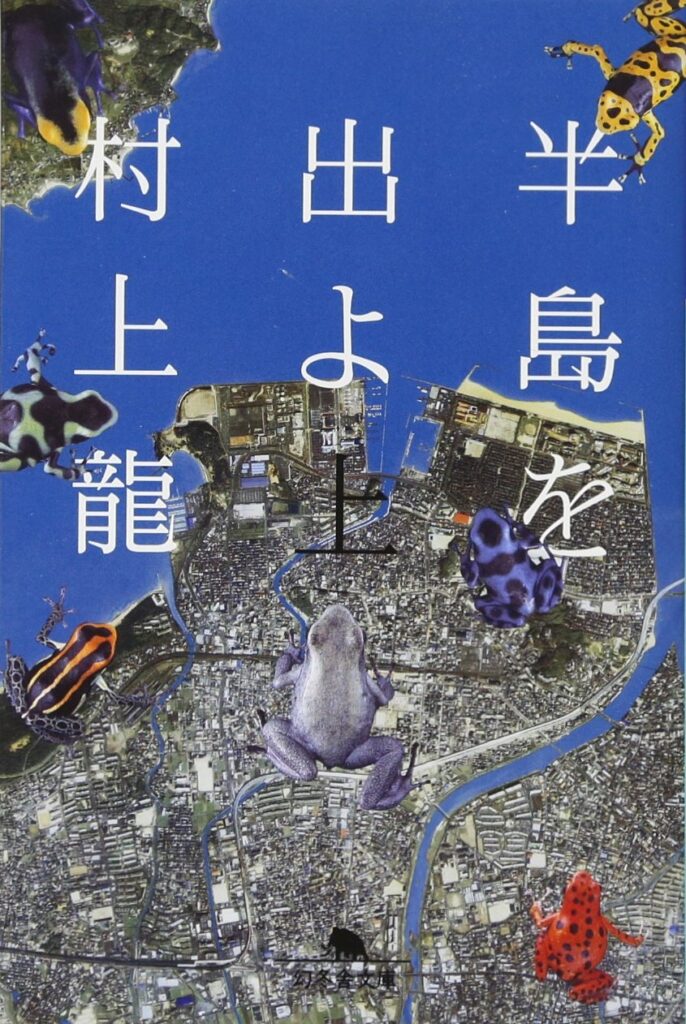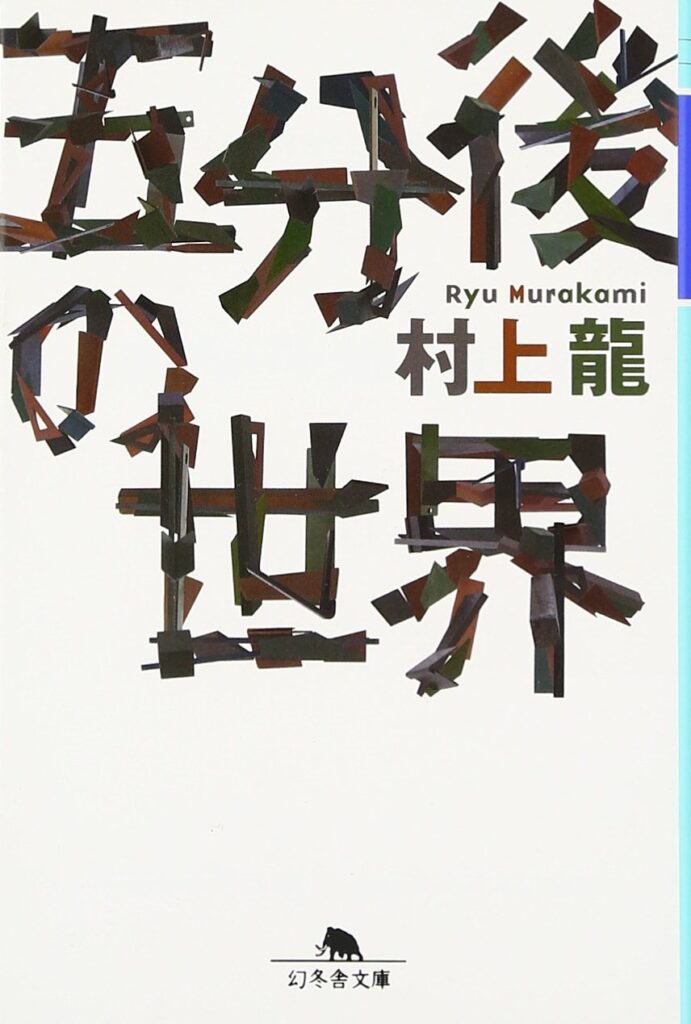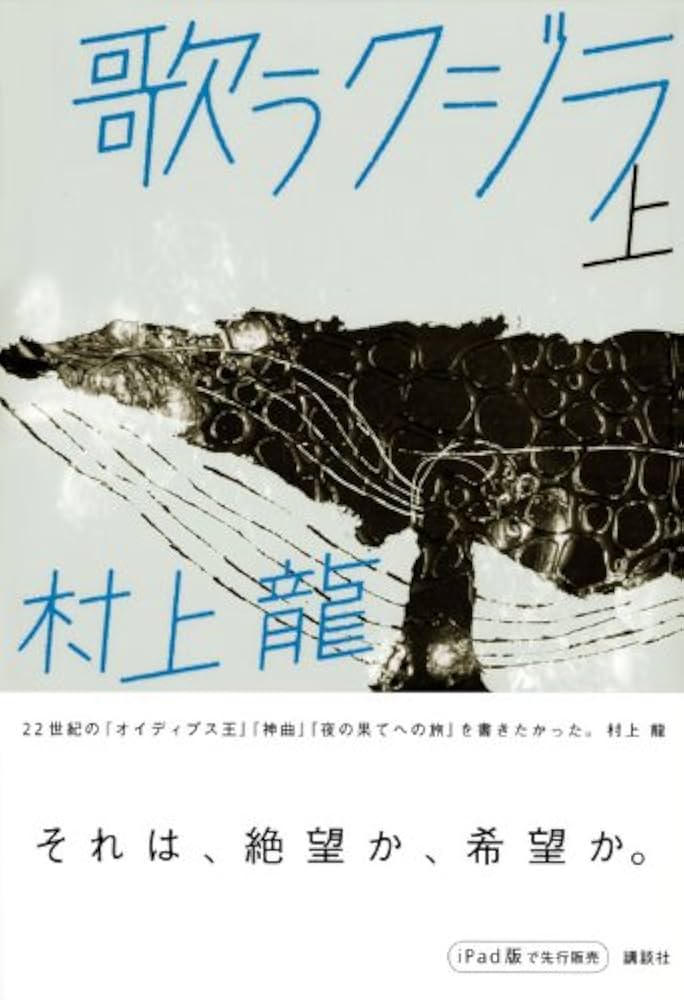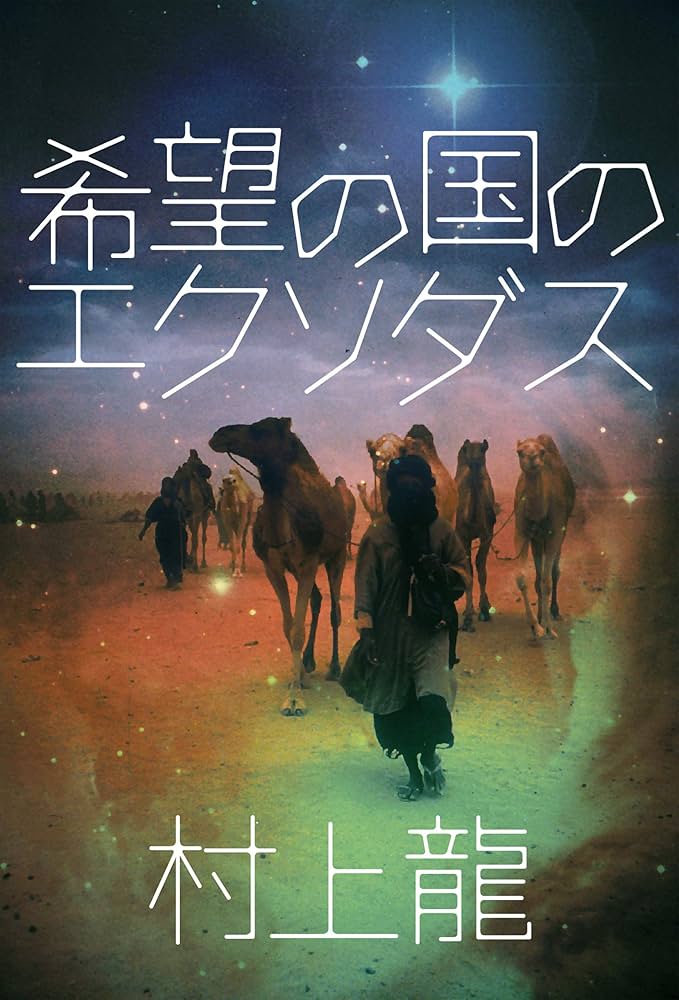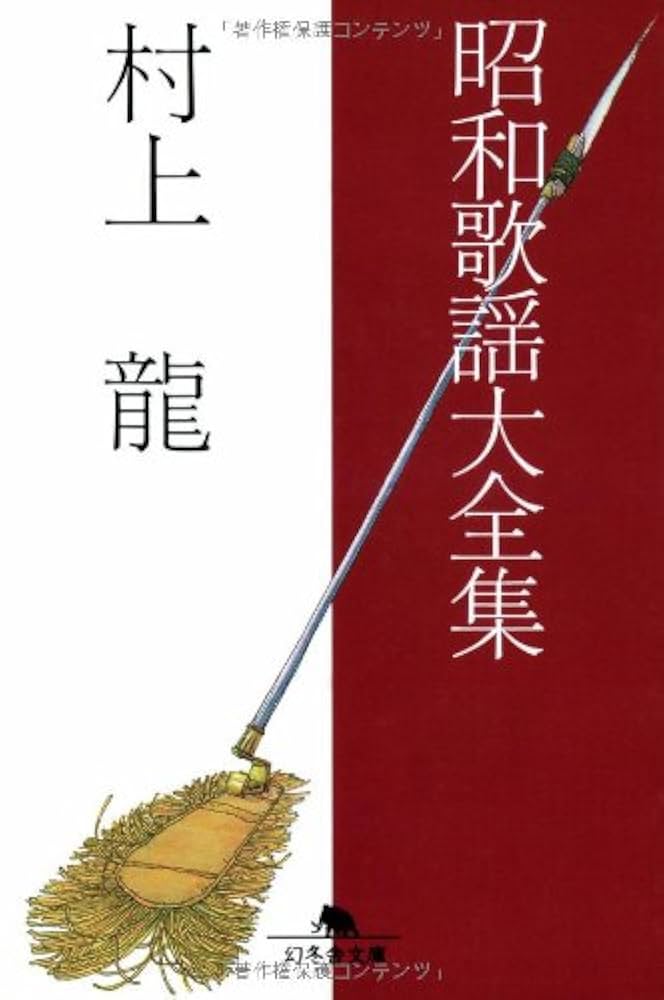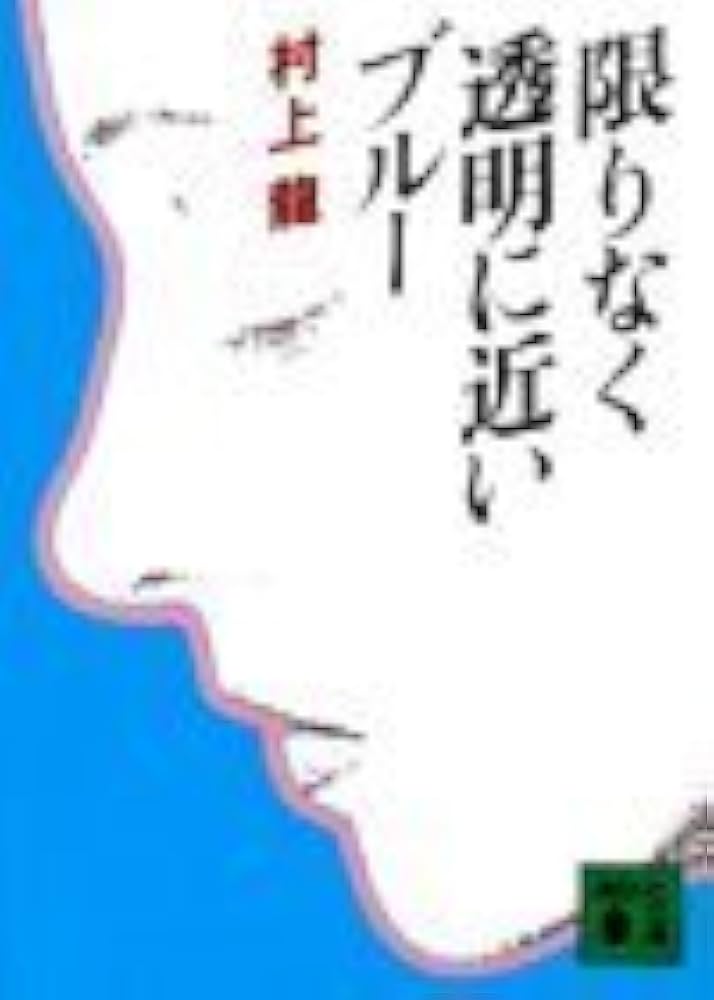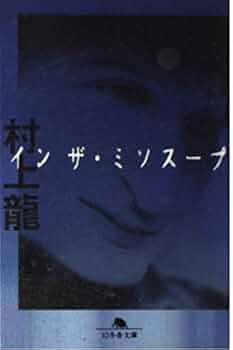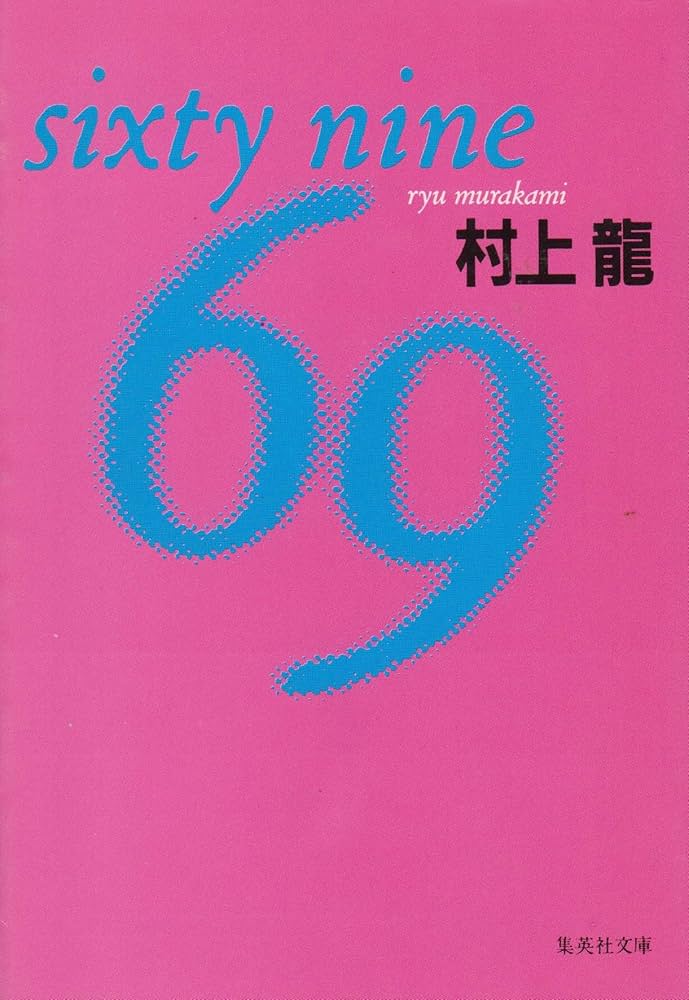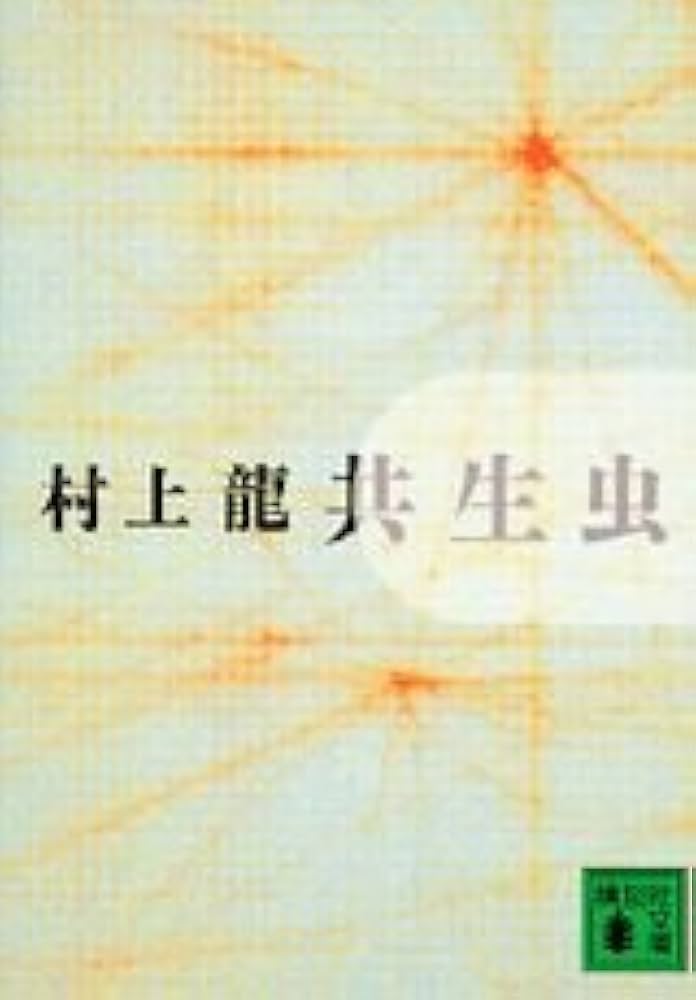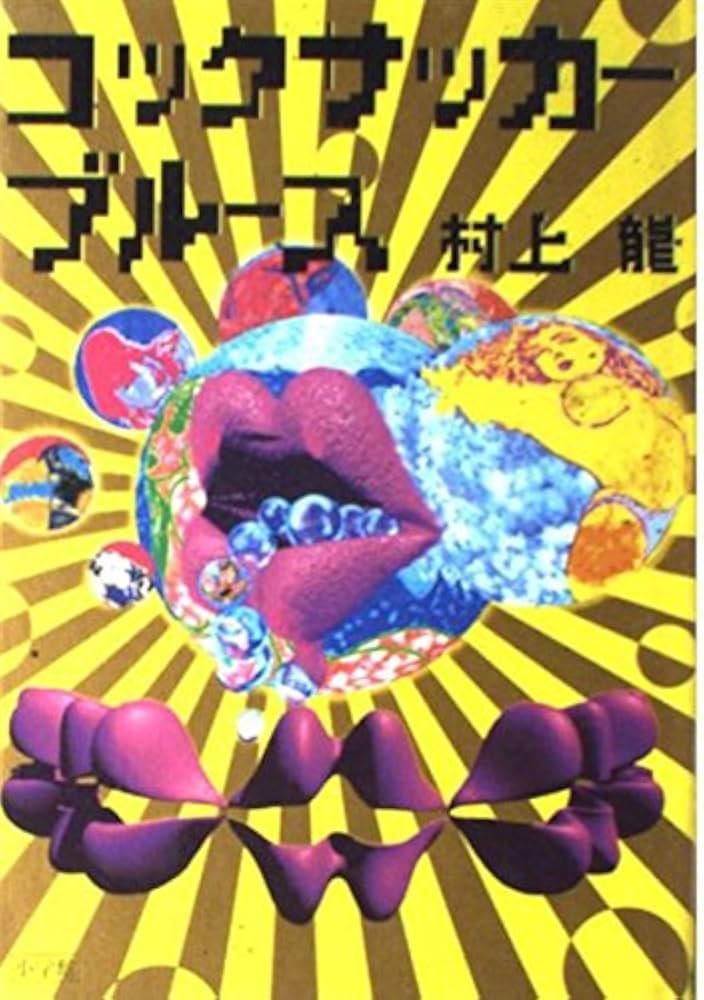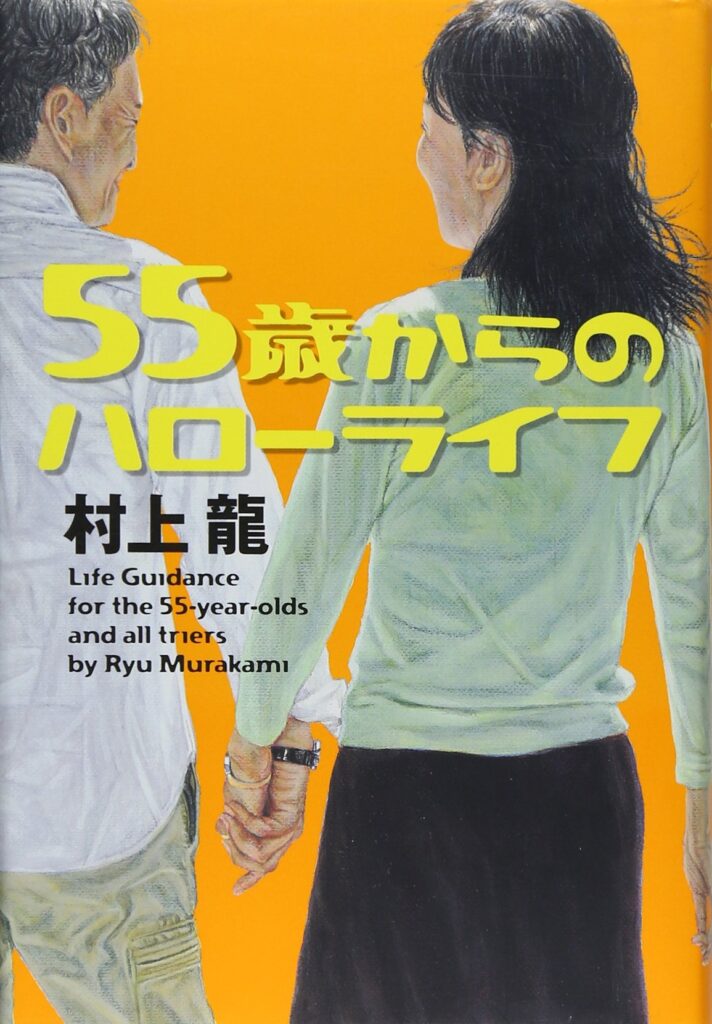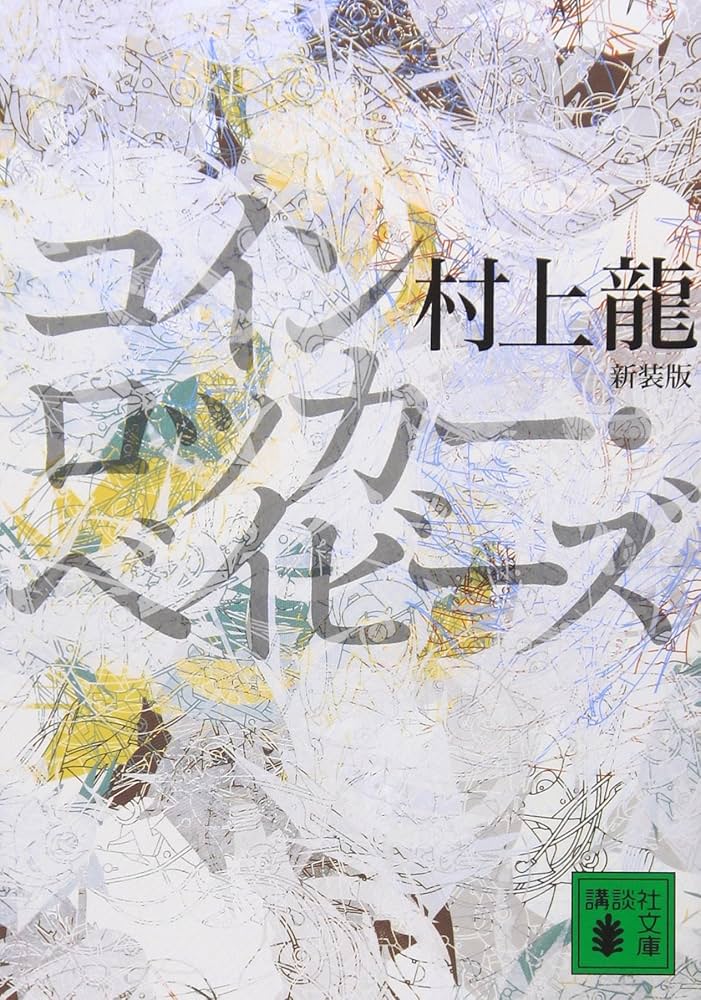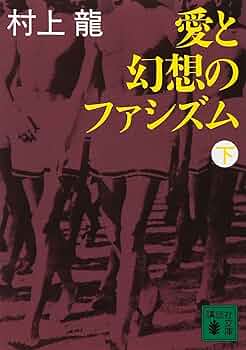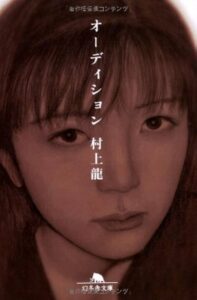 小説「オーディション」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「オーディション」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
村上龍さんの手によるこの物語は、多くの読者に強烈な印象を残しました。表面上は中年男性が再婚相手を探すという、どこにでもありそうな話から始まります。しかし、その内実を知れば、ページをめくる手が止まらなくなることでしょう。人間の心の奥底に潜む孤独と、それが歪んだ形で表出する瞬間の恐ろしさを描ききっています。
この記事では、まず物語の骨格となる展開を、結論には触れずにご紹介します。どのような経緯で主人公が「オーディション」という奇妙な計画を思いつき、運命の女性と出会うのか。その過程には、後の惨劇を予感させる不穏な空気が巧みに織り込まれています。初めてこの作品に触れる方は、まずはこちらで物語の雰囲気を掴んでみてください。
そして、核心部分では、物語の結末までを含めた詳細なネタバレと、私の個人的な思いを込めた感想を綴っていきます。なぜ、あれほど凄惨な出来事が起こらなければならなかったのか。登場人物たちの心理を深く掘り下げ、この物語が私たちに突きつけるものは何なのかを、じっくりと考えていきたいと思います。すでに読了された方も、新たな発見があるかもしれません。
「オーディション」のあらすじ
映像制作会社を経営する青山重治は、42歳。7年前に妻を亡くして以来、高校生の息子・重彦と穏やかながらもどこか空虚な日々を送っていました。その生活に変化が訪れたのは、重彦からの「再婚したら?」という一言がきっかけでした。真剣に再婚を考え始めた青山でしたが、ありきたりな出会いを求めようとはしませんでした。
友人で仕事仲間の吉川に相談し、彼が立てた計画は常軌を逸したものでした。それは、架空の映画のヒロインオーディションを開催し、その応募者の中から理想の結婚相手を探し出すという、あまりにも不誠実な企てだったのです。制作者という立場を利用し、数多の女性を一方的に選別する。この傲慢ともいえる計画が、彼の運命を大きく狂わせていきます。
約4000通もの応募の中から、青山の心は一人の女性に強く惹きつけられます。山崎麻美、24歳。クラシックバレエの道を怪我で断念したという経歴を持つ彼女は、儚げで、物静かで、知的な雰囲気を漂わせていました。書類審査、そして面接を経て、青山は麻美こそが探し求めていた理想の女性だと確信し、急速に彼女にのめり込んでいきます。
しかし、友人の吉川は「彼女は出来すぎている」と、その完璧さに言い知れぬ不信感を抱き、青山に繰り返し警告します。青山は恋に夢中になるあまり、その忠告に耳を貸そうとしません。デートを重ね、関係が深まるにつれて、麻美の純粋さの奥に隠された、異様なまでの独占欲や謎めいた過去が、少しずつその影を落とし始めるのでした。
「オーディション」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、物語の結末に触れるネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。この物語がなぜこれほどまでに読者の心に爪痕を残すのか、その理由を深く探っていきたいと思います。
物語の序盤、主人公である青山重治の人物像は、非常に丁寧に描かれています。彼は社会的成功を収め、思慮深い息子にも恵まれていますが、妻を亡くしたことによる根深い孤独を抱えています。この孤独こそが、彼の判断を狂わせる最初の引き金となるのです。読者は彼の孤独に共感しそうになりますが、物語は決して彼を単なる「可哀想な男性」としては描きません。
再婚相手を探すために彼が選んだ「オーディション」という手段は、本質的に欺瞞に満ちています。これは、彼が持つ特権意識の表れと言えるでしょう。彼は対等な関係でパートナーを見つけるのではなく、審査員という絶対的な立場から、女性たちを「審査」し、「選別」しようとします。この最初の過ち、つまり人間関係における誠実さの欠如が、後に彼を待ち受ける悲劇の種となるのです。
この物語は、彼が犯した「罪」に対する、あまりにも過酷な「罰」の物語という側面を持っています。もし彼がもっと誠実な方法で出会いを求めていたなら、結末は全く違ったものになっていたかもしれません。しかし彼は、最も安易で、そして最も傲慢な道を選んでしまいました。その選択自体が、彼の破滅への序曲だったのです。
オーディションに応募してきた山崎麻美は、まさに青山の理想を具現化したような存在でした。12年間打ち込んだバレエを怪我で諦めたという経歴。それは、彼が価値を置く「訓練による自信」と、彼が救済したいと感じる「脆さ」を同時に満たす、完璧なプロフィールでした。彼は、この「傷ついたバレリーナ」の物語に、すっかり魅了されてしまいます。
しかし、友人の吉川は、その完璧さにこそ罠があると直感します。彼の「出来すぎている」という警告は、物語の行く末を暗示する重要な伏線です。麻美が作り上げた人物像は、青山のような男性を惹きつけるために、周到に計算されたペルソナだった可能性が高いのです。彼女もまた、オーディションという場で、自分の「獲物」を審査していたのかもしれません。
つまり、このオーディションは、青山が麻美を選ぶ一方的な場ではなく、麻美が青山を「次の標的」として選別する、双方向の選考過程だった、と解釈することができます。支配していると思っていた青山が、実は最初から観察され、品定めされていた。この構造の逆転こそが、この物語の根幹にある恐怖なのです。
物語の大部分は、青山と麻美の恋愛模様に費やされます。この丁寧な描写が、読者を巧みに偽りの安心感へと誘います。デートを重ね、親密な会話を交わす二人の姿は、一見すると幸福な恋人たちそのものです。しかし、その甘やかな時間の合間に、不穏な空気が確実に流れ込んできます。
その象徴が、週末旅行での出来事です。麻美は自らの太腿にある火傷の痕を見せ、「私だけを愛して」と誓いを立てさせます。これは単なる恋人の甘い言葉ではありません。彼女が相手に課す、絶対的な契約の提示です。このルールを破ることが、彼女の世界では「罰」に値する行為となる。彼女の歪んだ愛の形が、初めて牙をむく瞬間です。
さらに読者を震撼させるのが、麻美の私生活の描写です。青山からの電話を、がらんとした畳の部屋で、身じろぎもせずに待つ彼女の姿。その傍らには、得体の知れない大きな布袋が置かれています。華やかで純粋な恋人を演じる表の顔と、この殺伐とした秘密の空間とのコントラストが、言いようのない恐怖を掻き立てます。あの袋の中身が何なのか、この時点ではまだ分かりませんが、それが恐ろしいものであることは明らかです。
麻美が忽然と姿を消した後、物語はミステリーの様相を呈します。彼女の語った経歴が嘘であったことが、青山の調査によって次々と暴かれていくのです。バレエ教室のあった場所で出会った、両足を失った彼女の継父。彼から語られる虐待の過去は、麻美の心の傷の根源を明らかにします。しかし、それは決して彼女の行動を正当化するものではありません。
彼女が働いていたはずの銀座のバーは、ママがバラバラにされて殺害されるという凄惨な未解決事件を機に閉店していました。身元引受人だったはずの音楽プロデューサーも、一年以上前から行方不明。これらの事実は、青山が恋した女性が、連続的な捕食者であったことを示唆します。彼が発見する一つ一つの断片は、彼自身の未来を予言するパズルのピースなのです。
特に、継父が両足を失っているという事実は、後の展開を直接的に暗示しています。青山は、彼女の過去を調べているようで、実は自分がこれから体験する恐怖の予告編を見せられているに過ぎません。この時点で、物語は恋愛サスペンスから、自分が怪物と深く関わってしまったことに気づく男の絶望的なスリラーへと、その姿を完全に変えるのです。
そして、物語は戦慄のクライマックスへと突き進みます。自宅に戻った青山が、麻美に盛られた薬によって身動きを封じられる場面。意識だけは明晰なまま、これから加えられるであろう暴力のすべてを、ただ受け入れるしかない。この絶望的な状況設定が、恐怖を極限まで増幅させます。
麻美が発する「キリキリキリ…」という不気味な声と共に、長い鍼が青山の体に突き立てられていきます。爪の下、そして両目へ。彼が彼女を品定めするために使った「視線」を奪うこの行為は、象徴的な罰そのものです。さらに、彼の左足をピアノ線で切断する場面の描写は、直視しがたいほどの痛みと恐怖を読者に与えます。「足がなければどこにも行けないでしょ?」という彼女の言葉は、歪んだ所有欲の究極の形と言えるでしょう。
この拷問は、物語の冒頭で描かれた力関係の完全な反転です。審査する者とされる者、支配する者と支配される者が、完全に入れ替わる。青山がオーディションという形で他者に行った客体化が、最も残忍な形で彼自身に返ってくるのです。彼の傲慢さが招いた、必然的な因果応報の結末とも言えます。
物語は、息子の重彦が帰宅することで、唐突に終幕へと向かいます。重彦は驚くべき冷静さで麻美を階段から突き落とし、その結果、彼女は命を落とします。青山を救ったのは、彼が息子のために設置した頑丈な手すりであり、息子への純粋な愛情でした。彼自身の狡猾さや力ではなく、純粋なものが彼を救うという結末は、非常に皮肉的です。
そして、最も恐ろしいのが、麻美が死の間際に口にする最後の言葉です。「分かってくれる人に出会ったのは初めて…」。これは、かつて青山を誘惑するために使ったセリフの繰り返しに過ぎません。彼女の存在そのものが、最後まで「演技」であったことを証明しています。彼女の中には、もはや本当の人格など残っておらず、ただ与えられた役割を演じる壊れた人形のようであったことが示唆されるのです。
この物語には、カタルシスがありません。青山は生き延びましたが、心身ともに回復不可能なほど破壊されてしまいました。恐怖は麻美の死では終わらず、彼の人生において、おそらくこれから永遠に続くのです。読者は解決されない恐怖の中に、青山と共に置き去りにされます。それこそが、この物語が突きつける、トラウマというものの本質なのかもしれません。
まとめ
村上龍さんの小説「オーディション」は、単なるサイコホラーという枠には収まらない、人間の心理に深く切り込んだ作品です。物語は、再婚相手を探す中年男性の日常から始まりますが、その安易な選択が、取り返しのつかない悲劇を呼び起こします。
主人公が犯した「オーディション」という名の欺瞞。それは、他者を自分の都合で選別しようとする傲慢さの表れでした。その行為が、山崎麻美という、完璧な仮面を被った捕食者を引き寄せてしまいます。物語の前半で丁寧に描かれる恋愛模様は、後半の凄惨な展開への長い助走となり、読者を偽りの安心感から恐怖のどん底へ突き落とします。
この記事では、物語のあらすじから、結末までの詳細なネタバレを含む長文の感想を綴りました。拷問シーンの象徴的な意味や、登場人物たちの心理、そして救いのない結末がもたらす読後感について、私なりの解釈を述べています。この物語は、愛と支配、加害と被害の関係性を、恐ろしい形で私たちに突きつけてくるのです。
もしあなたが、人間の心の奥底に潜む闇や、日常が崩壊していく過程を鋭く描いた物語を求めているのであれば、この「オーディション」は必読の一冊と言えるでしょう。読後、しばらくの間、その衝撃から逃れることは難しいかもしれません。