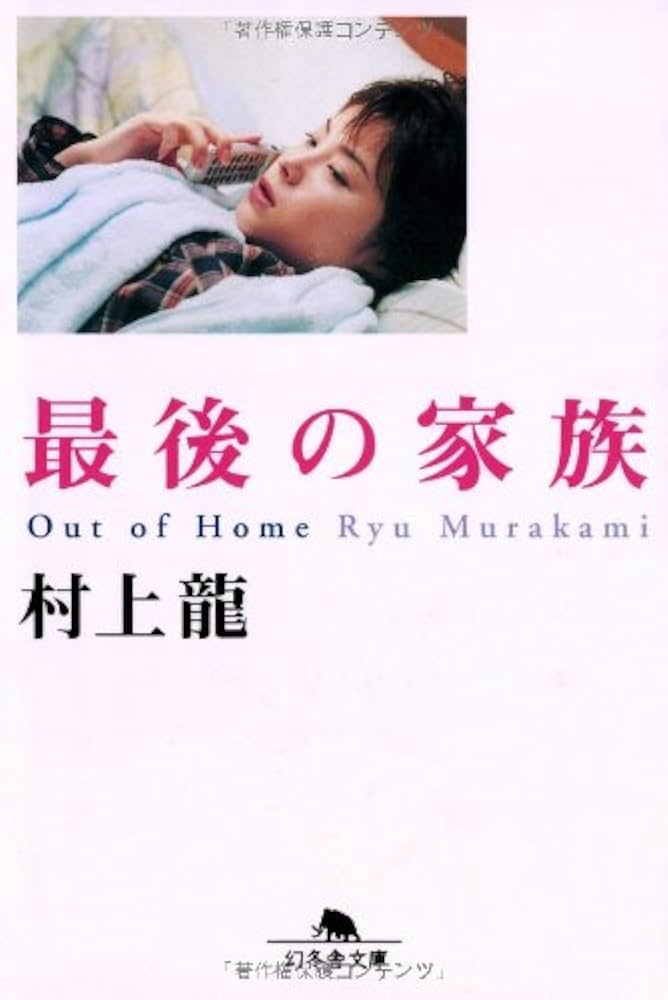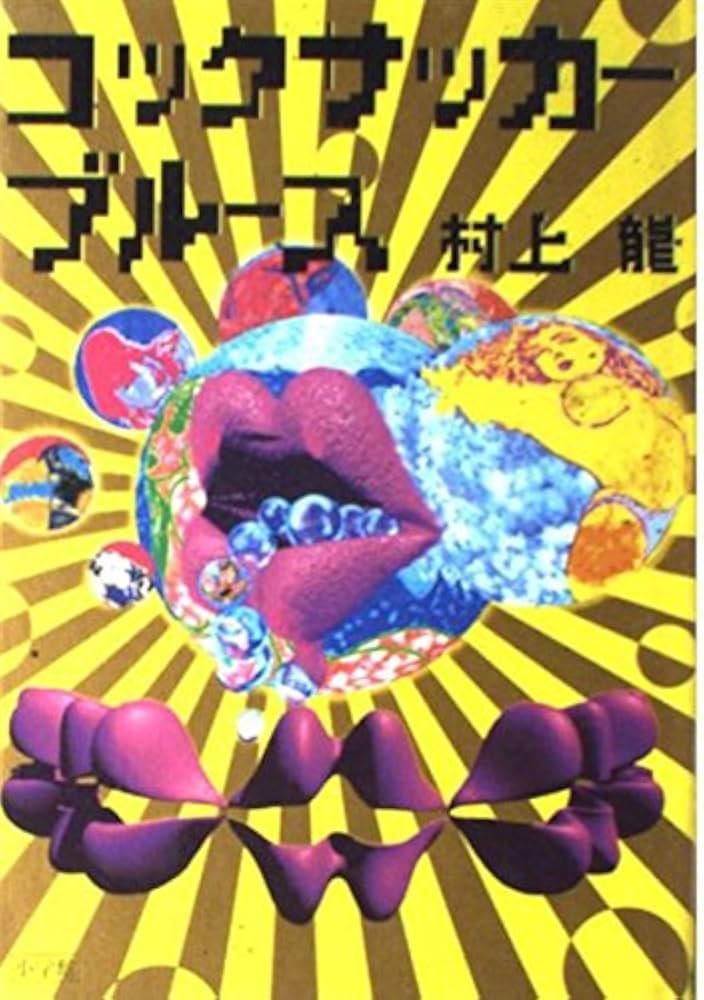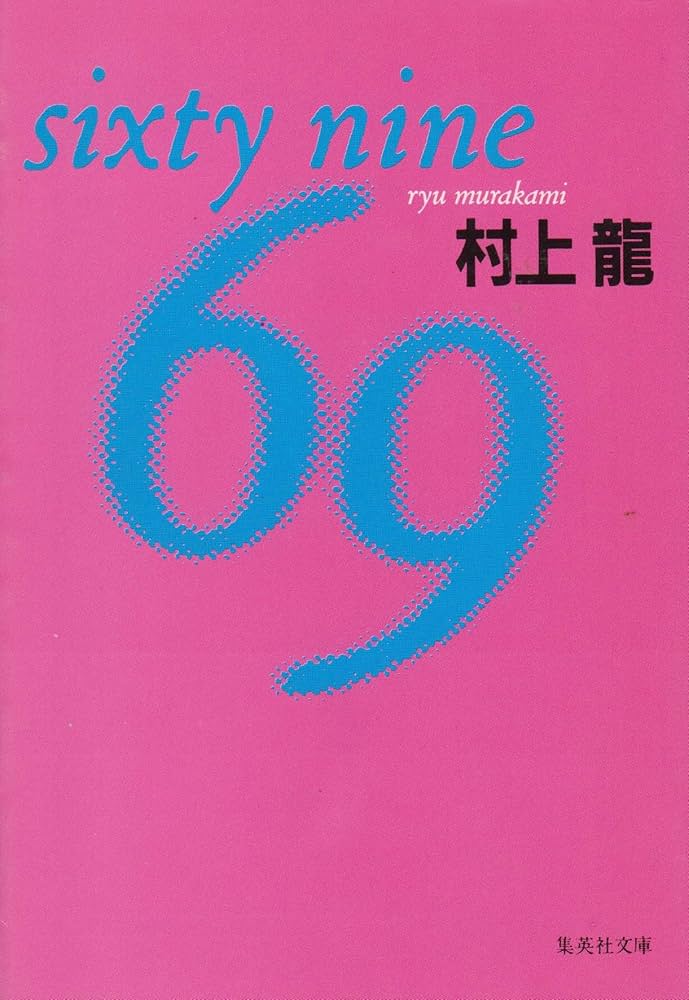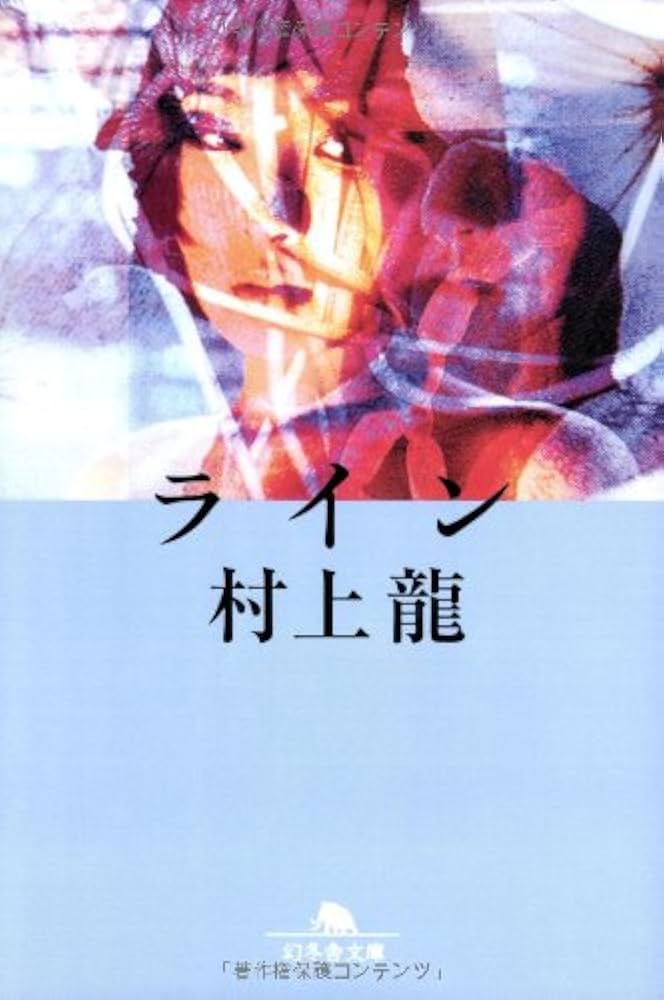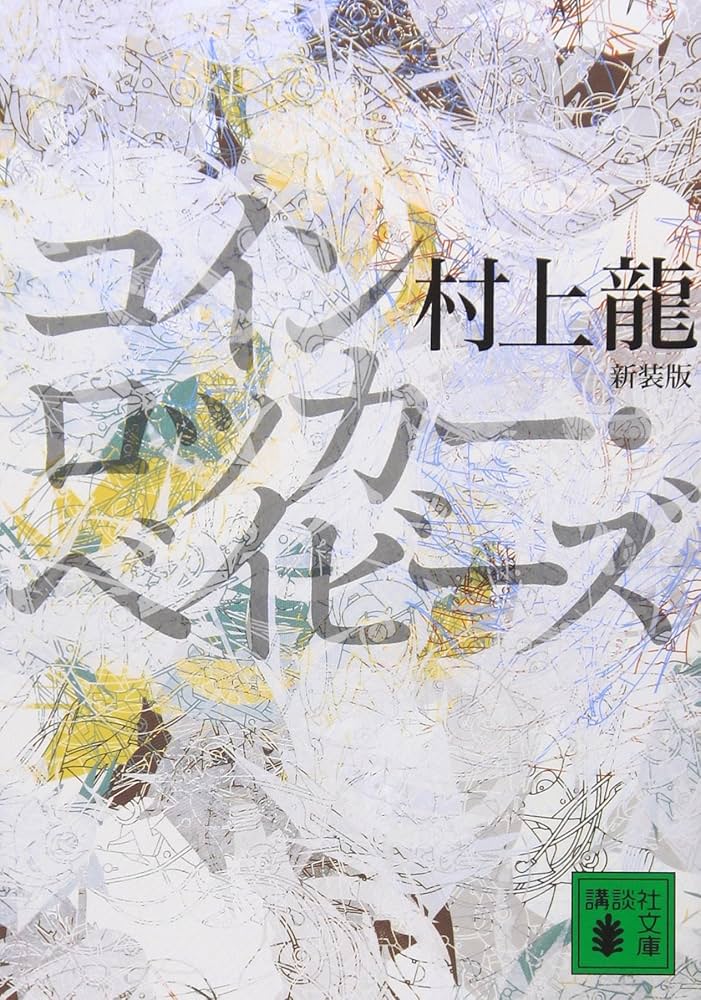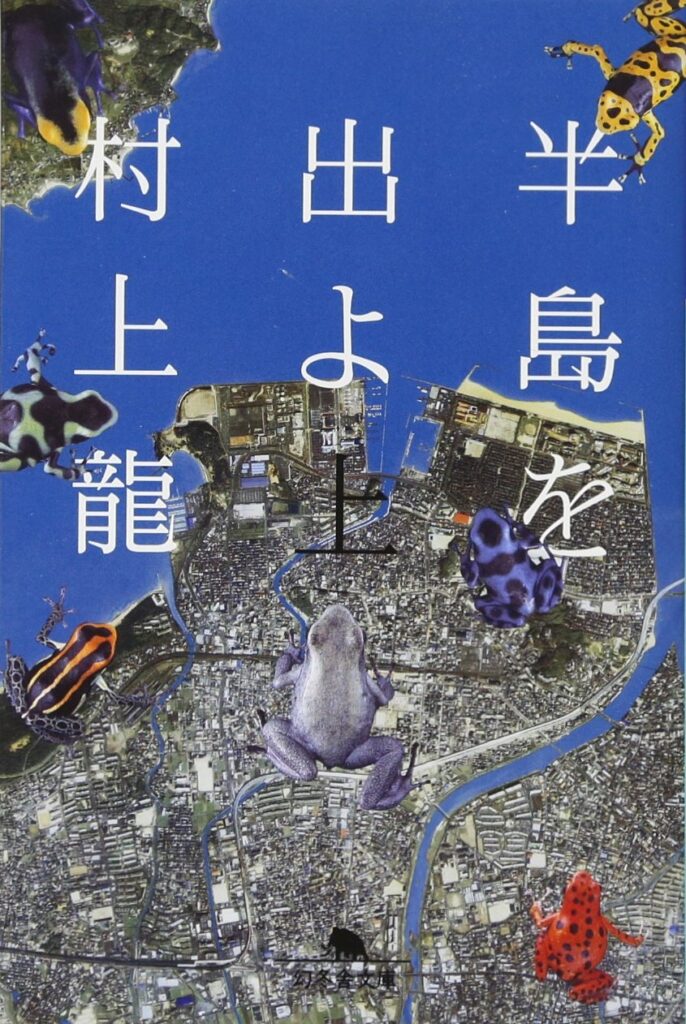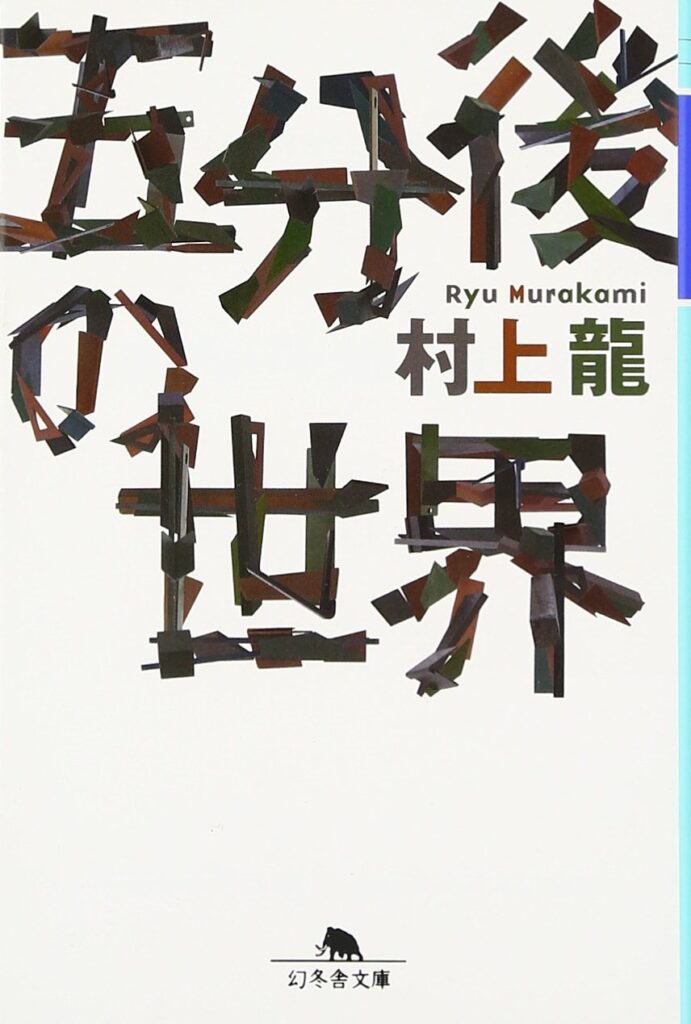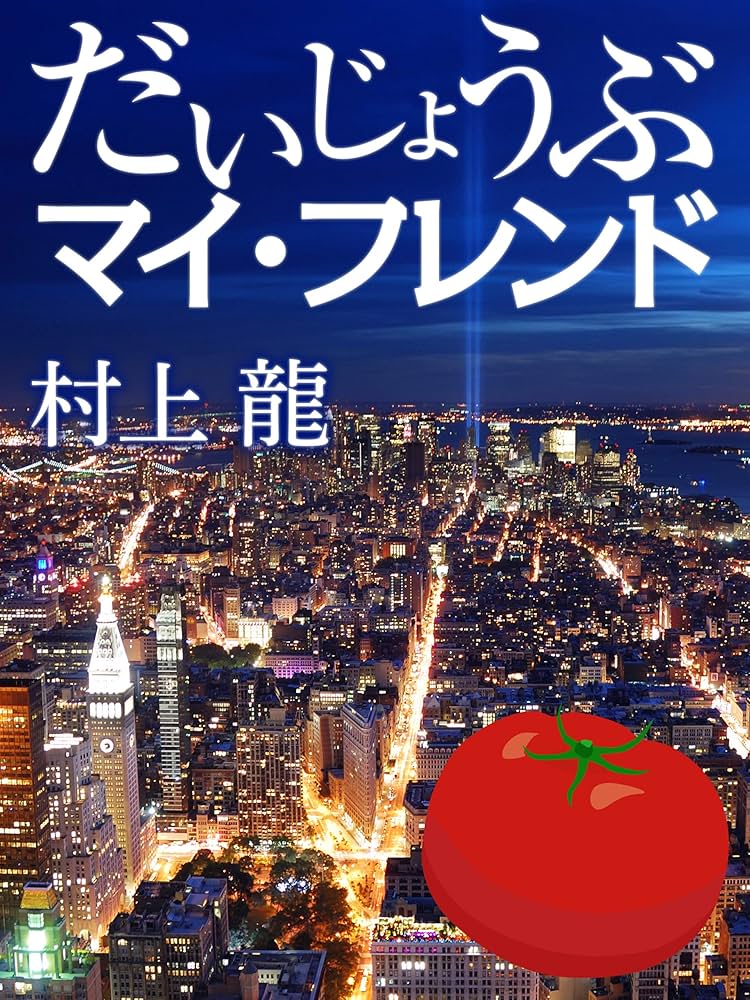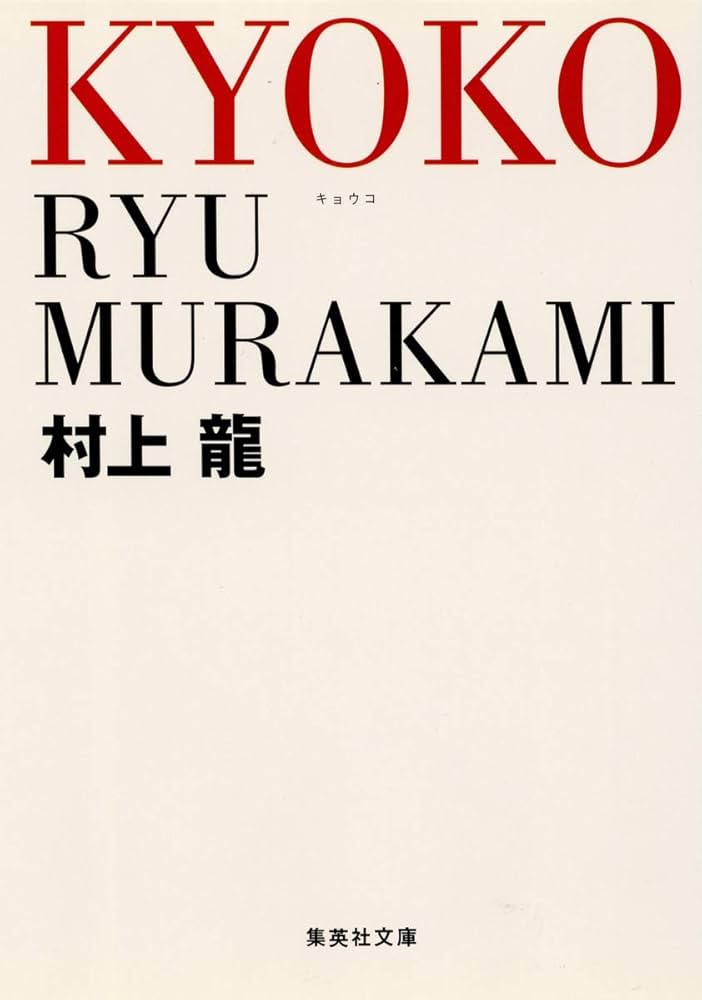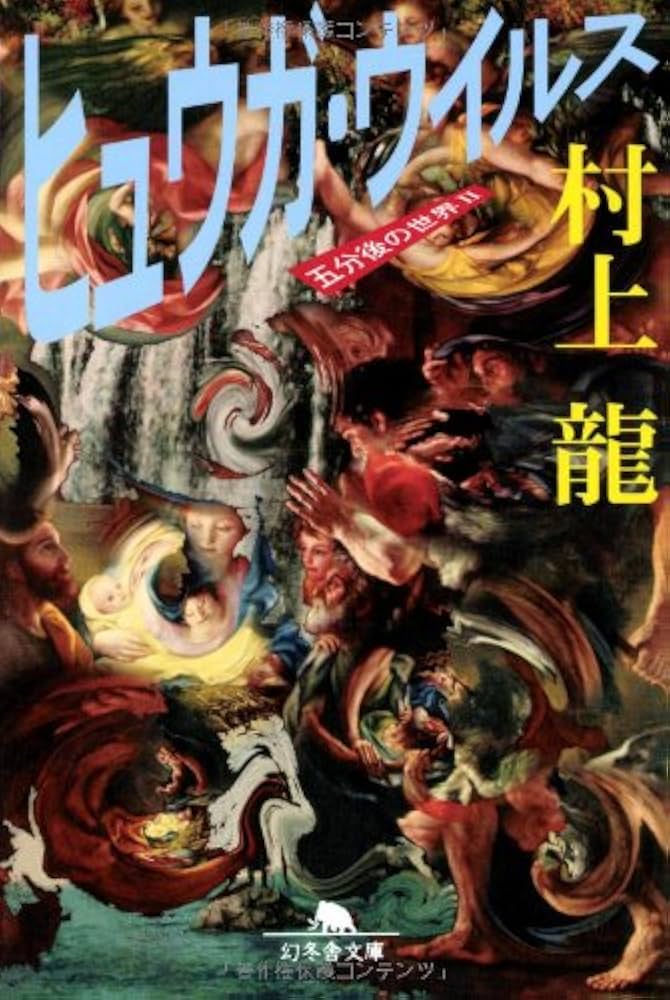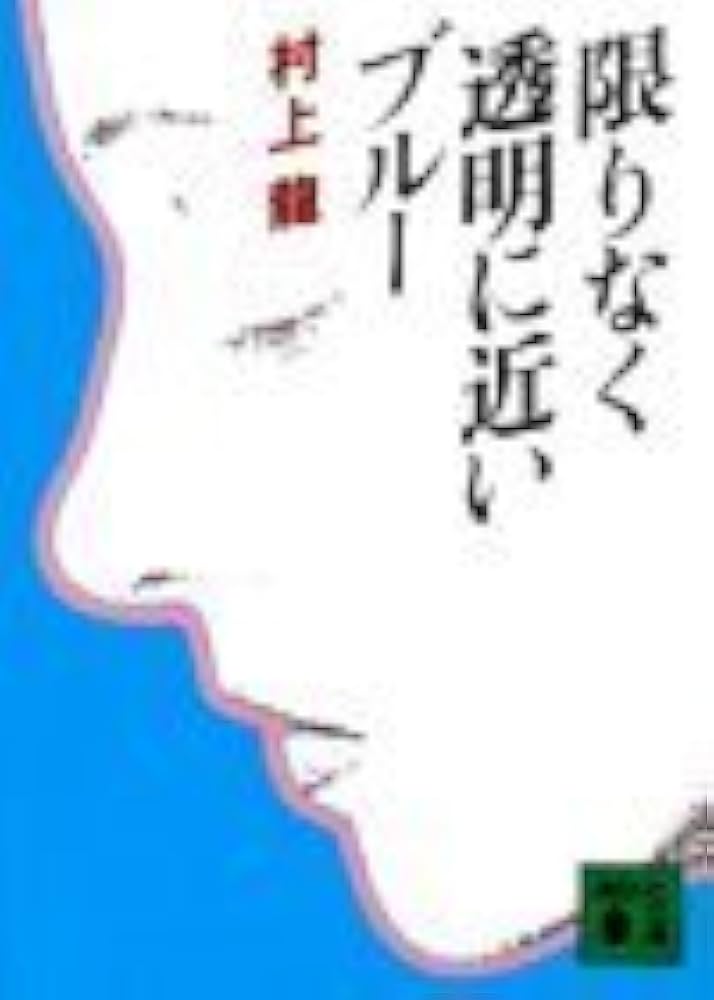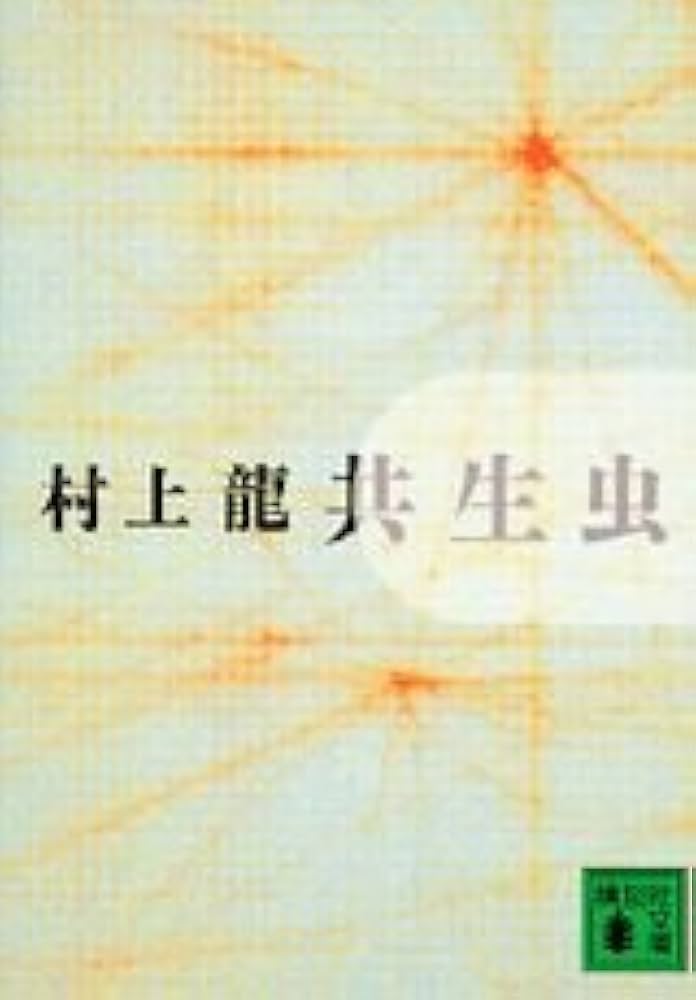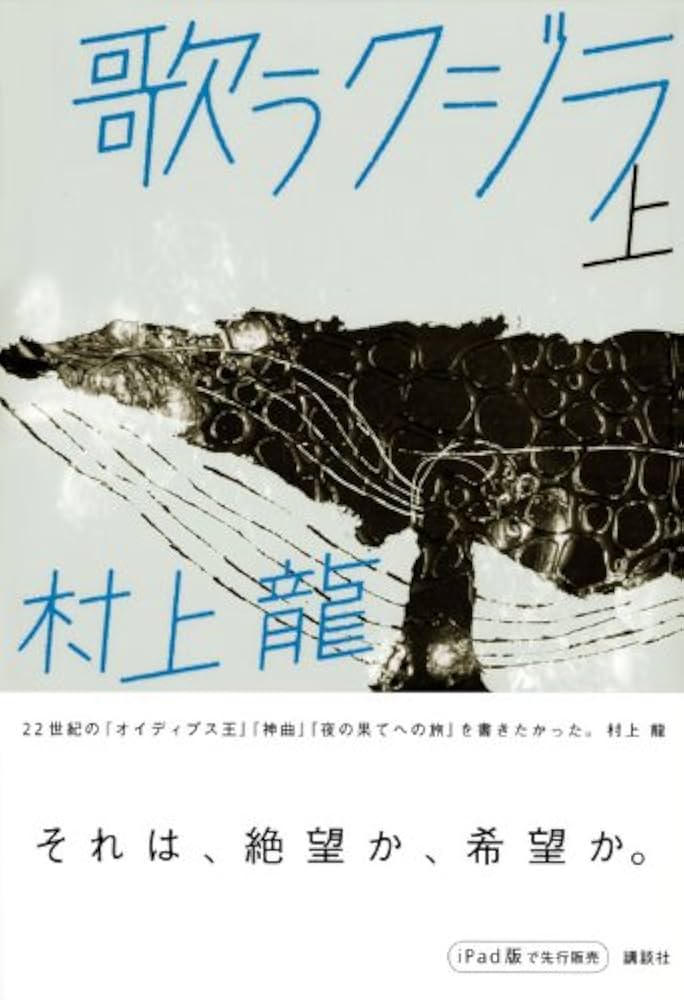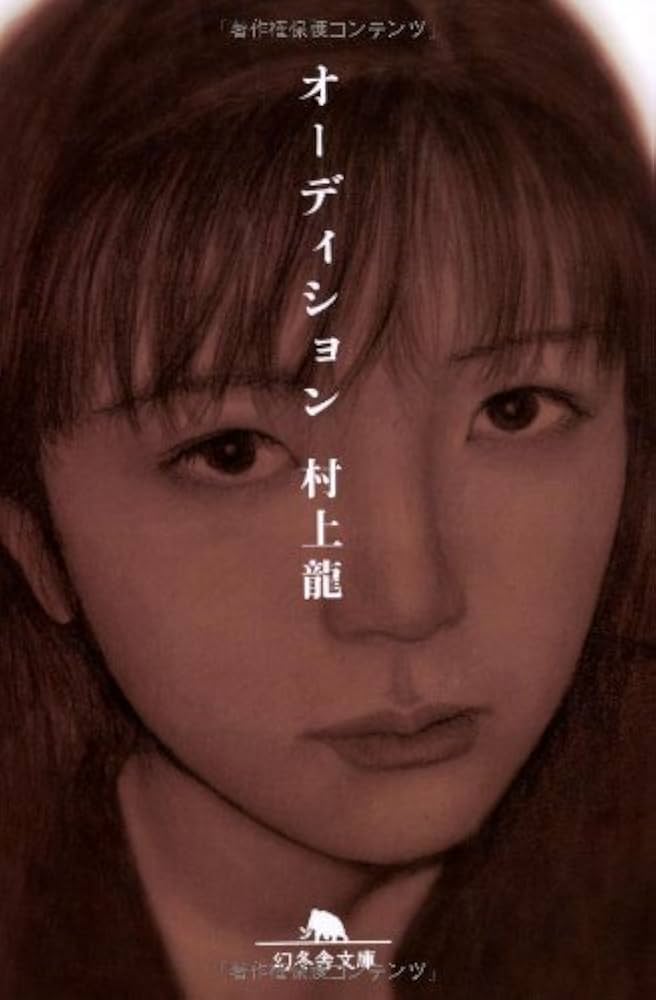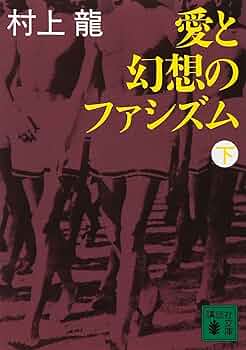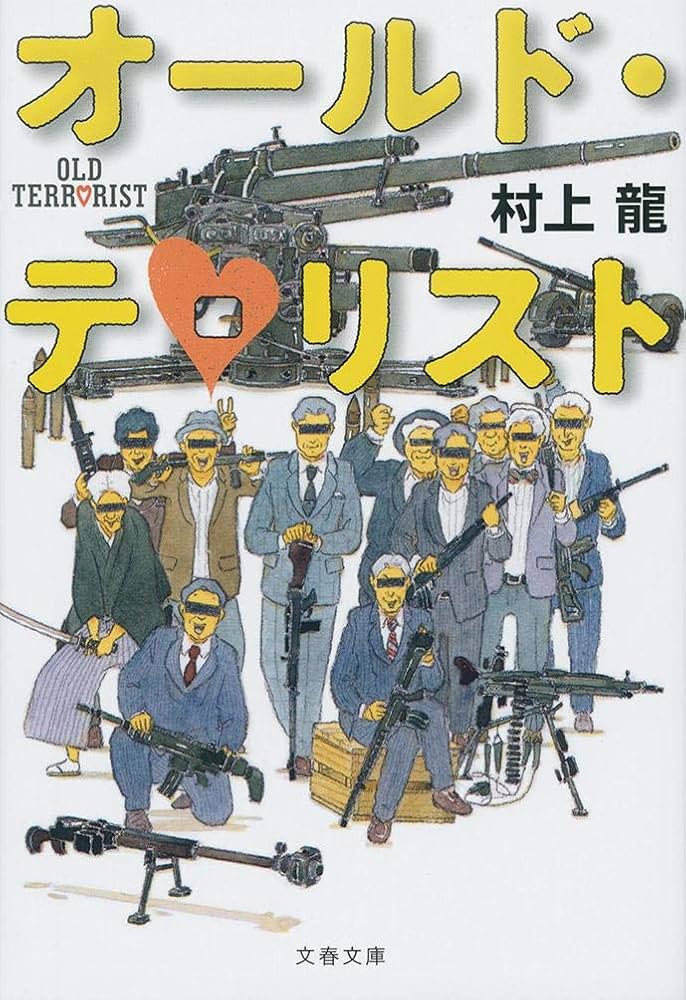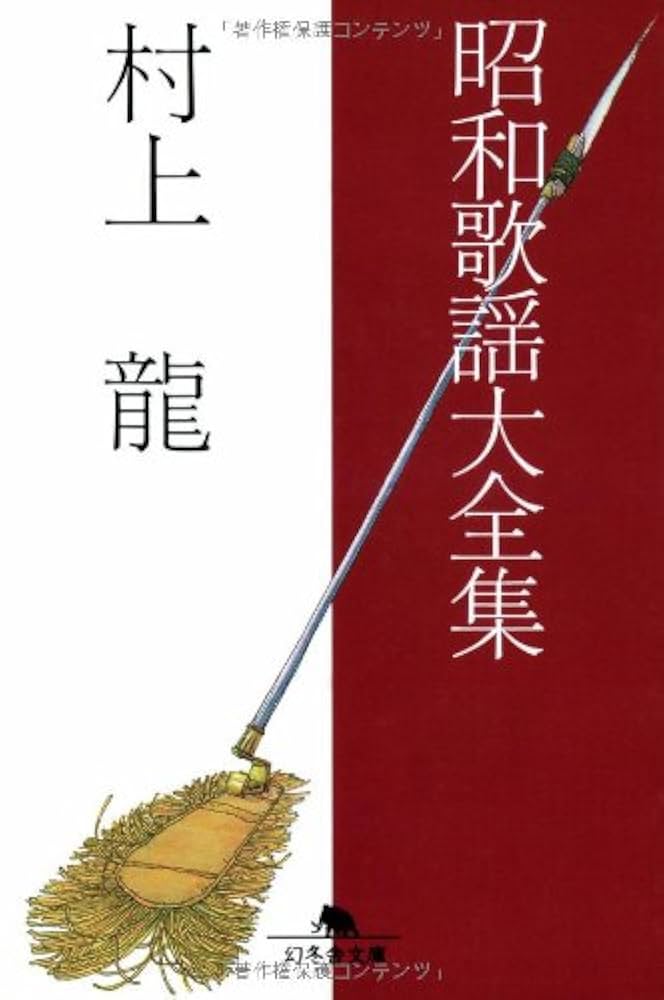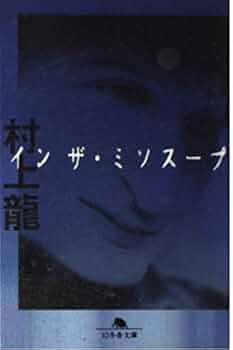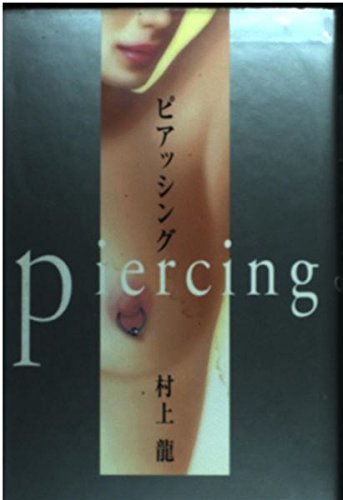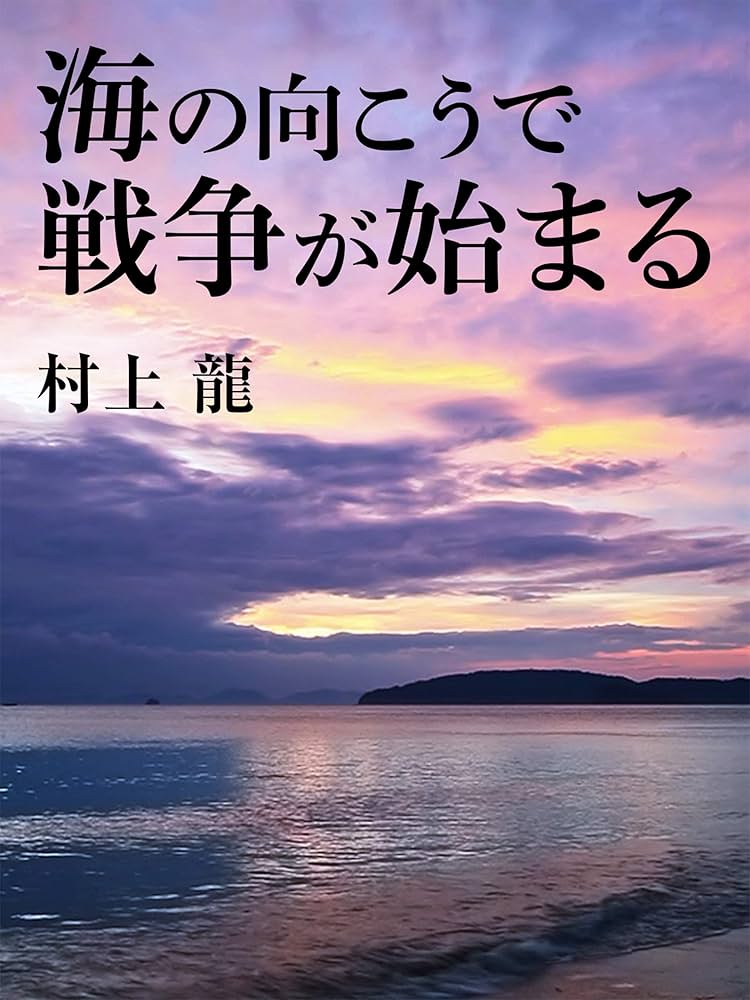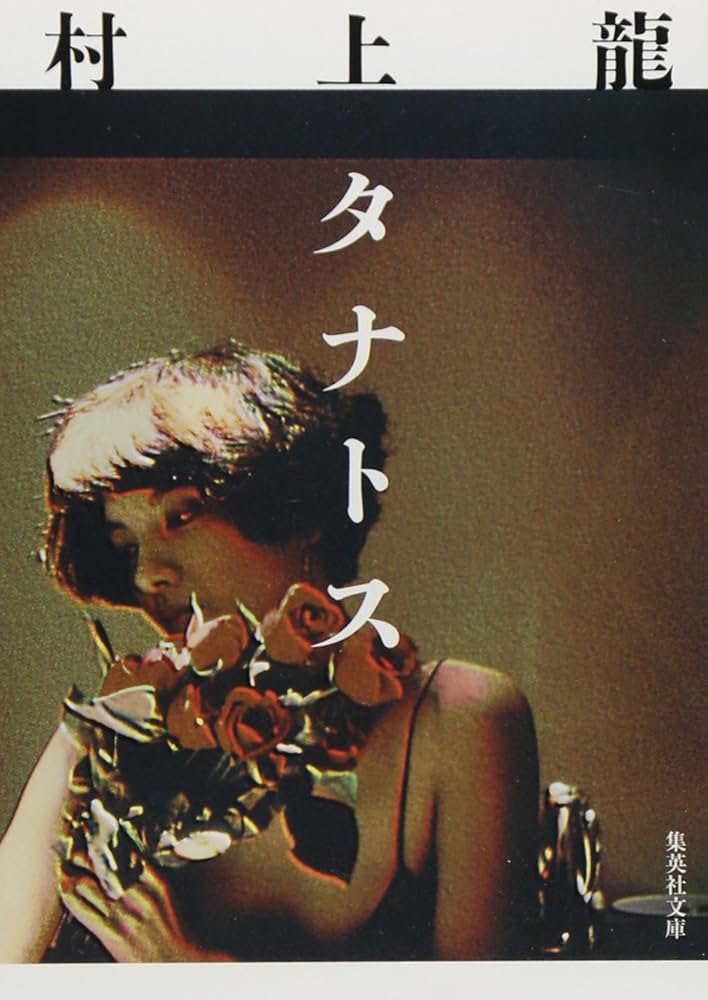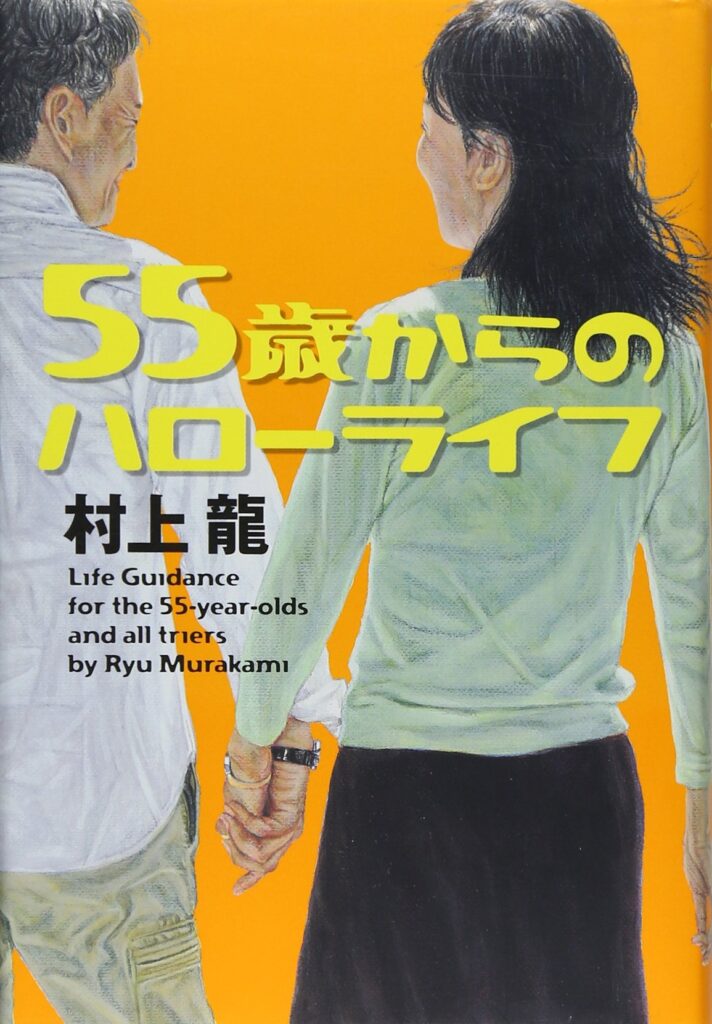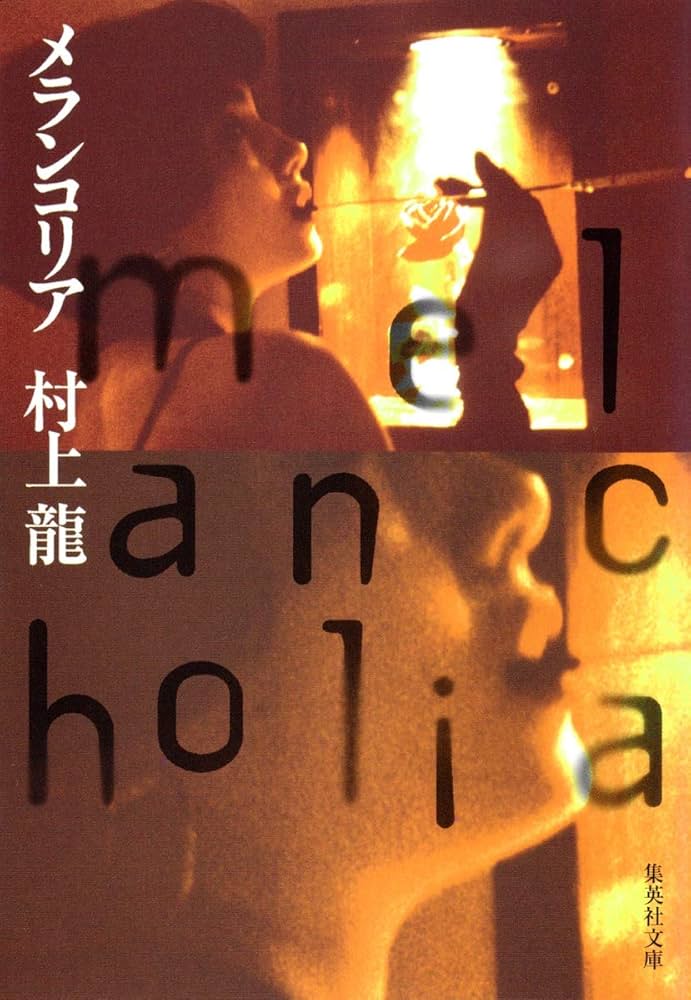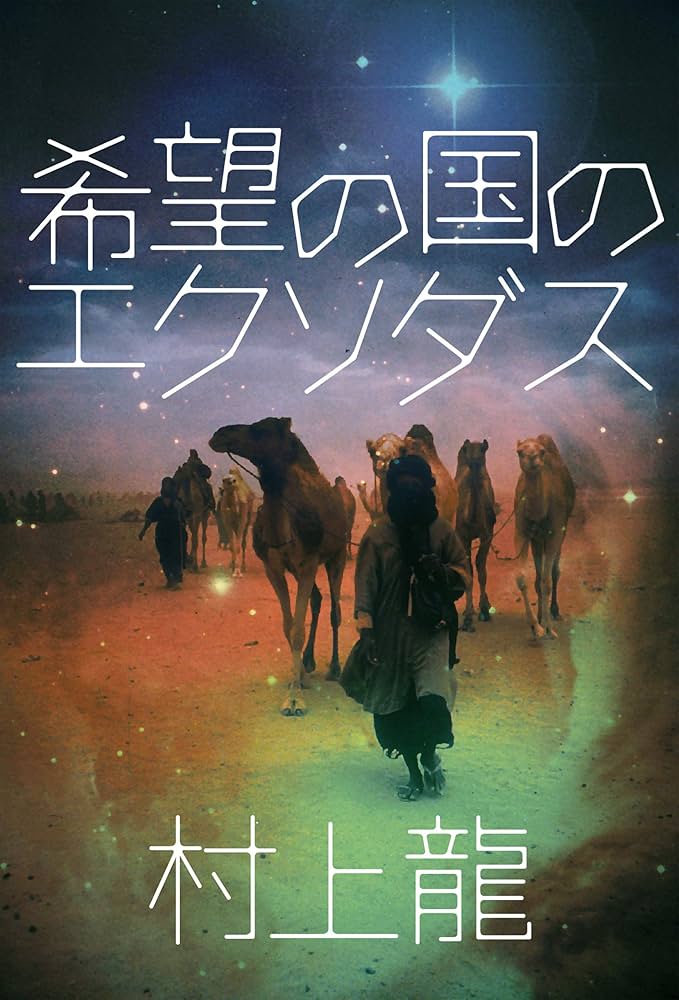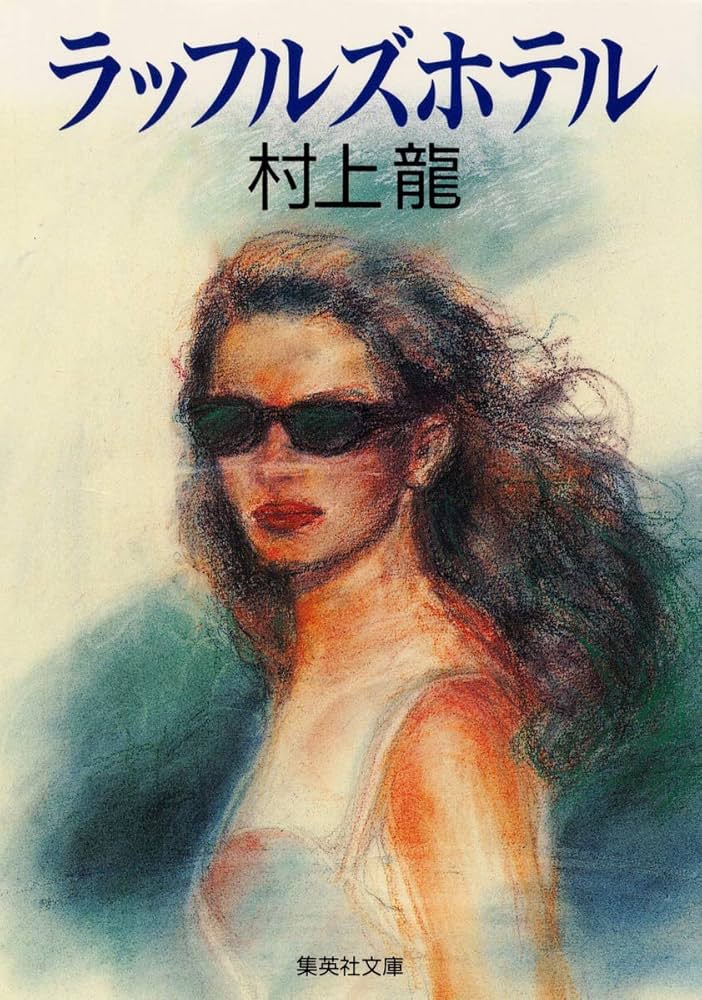小説「エクスタシー」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「エクスタシー」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
村上龍さんが1993年に発表したこの物語は、ただならぬ引力を持っています。バブルが崩壊し、日本全体がどこか浮足立ちながらも先の見えない不安に覆われていた時代。そんな空気感を背景に、ニューヨークで始まる一人の男の物語は、私たち読者を日常から非日常の、それも極限の世界へと有無を言わさず引きずり込んでいきます。
この作品に触れることは、安全な場所から危険なショーを眺めるような体験ではありません。むしろ、自分自身の価値観や理性が、ページをめくるごとに少しずつ侵食され、試されていくような感覚に陥ります。読み終えた後、世界が以前と同じには見えなくなるかもしれない。そんな予感をはらんだ、恐ろしくも魅力的な一冊なのです。
この記事では、まず物語の導入となる部分のあらましをご紹介し、その後、私自身の心に深く刻まれた読後感を、物語の核心に触れるネタバレを含みながら、じっくりと語っていきたいと思います。この危険なゲームの扉を、一緒に開けてみませんか。
「エクスタシー」のあらすじ
物語は、主人公である「僕」がニューヨークの街角で、日本人ホームレスから奇妙な問いを投げかけられる場面から始まります。「ゴッホがなぜ自分の耳を切ったか、わかるかい?」。かつて大手シンクタンクに勤めていたという経歴を持つ「僕」は、知的で論理的な思考の持ち主。しかし、彼の日常はどこか空虚で、明確な目的を失っているようにも見えます。
その謎めいたホームレス、ヤザキと名乗る男は、「僕」に一枚のメモを渡します。そこに書かれた電話番号にかければ金がもらえる、と。怪しみながらも、どこか引かれるように電話をかけた「僕」の耳に聞こえてきたのは、ヤザキ本人ではなく、カタオカケイコと名乗る女性の声でした。彼女こそ、日本を代表するSMの女王と呼ばれる人物だったのです。
ここから、物語は異様な展開を見せます。受話器の向こう側から、ケイコは自らの生い立ち、ヤザキとの関係、そして「支配」と「服従」に関する独自の哲学を、延々と語り続けます。彼女の言葉は、巧みで、抗いがたい力を持っていました。「人格がこの世の中を生きづらくしている」「恥のないところにエロスはない」。そんな言葉の奔流に、「僕」はただひたすら耳を傾けるしかありません。
それは、これから始まる「ゲーム」への、あまりにも長い序章でした。ケイコの声に耳を傾けるうちに、「僕」の常識や理性は少しずつ麻痺し、解体されていきます。電話を切った時、彼はもう後戻りのできない世界の入り口に立っていることを、まだ知る由もありませんでした。この後、彼はどのような運命を辿るのでしょうか。
「エクスタシー」の長文感想(ネタバレあり)
この物語について語ろうとすると、どこから話すべきか本当に迷います。読んでいる間の、あの奇妙な浮遊感と、読み終えた後の、あの得体の知れない衝撃。それを言葉で再現するのは、とても難しいことです。ここからは、物語の核心に触れるネタバレも交えながら、私の心を揺さぶった点について、段落を重ねて語っていきたいと思います。
まず、冒頭の問いかけです。「ゴッホがなぜ自分の耳を切ったか、わかるかい?」。この一文が、この物語の全てを象徴しているように感じます。常識では理解できない狂気的な行為。その裏にある、もしかしたら本人にしか分からない究極の真実や感覚。この問いは、読者である私たちにも向けられています。これから始まる常軌を逸した物語を、あなたは理解できるか、と。
主人公の「僕」が、かつてシンクタンクに勤めていたという設定が、非常に巧みだと感じました。彼は決して無知な若者ではなく、情報を処理し、論理的に物事を考える能力に長けた人間です。だからこそ、彼がこれから陥っていく非論理的で感覚的な世界との対比が、鮮烈なものになります。
彼の持つ合理性は、本来ならヤザキが仕掛ける「ゲーム」に対する強力な盾となるはずでした。しかし、そうはならない。この事実は、人間がいかに知性や理屈だけでは生きていないか、心の奥底にある抗いがたい渇望の前では、論理などいとも簡単に崩れ去ってしまうものなのかもしれない、ということを突きつけてきます。
物語の転換点となるのが、ヤザキとの出会い、そしてカタオカケイコからの電話です。特に、小説の序盤の大部分を占めるケイコの独白は、圧巻の一言に尽きます。物語の進行がほとんど止まり、読者は主人公と共に、ただ彼女の声を聞き続けることを強いられます。
この構造自体が、まさに「支配」と「服従」の関係性を体現していると感じました。ケイコが語り、物語を支配する。主人公と読者は、ただ受け身でそれを受け入れるしかない。私たちは、電話線に繋がれた主人公と同じように、彼女の言葉の世界に囚われてしまうのです。村上龍さんは、小説の形式そのものを使って、テーマを私たちに体験させているように思えます。
ケイコの語る哲学も、強烈な説得力を持っています。「人格を剥ぎ取られた奴隷はむしろ生きやすい」。社会的な役割や建前から解放され、ただ純粋な存在になることの心地よさ。彼女の言葉は、普段私たちが無意識に抱えている生きづらさの核心を突いてくるようで、抗いがたい魅力を放っています。
「恥のないところにエロスはない」という彼女の言葉も、深く心に残りました。管理され、何もかもが予測可能になった現代社会では、もはや本当の意味での情動や興奮は生まれないのではないか。そんな問いかけのようにも聞こえ、主人公の価値観が根底から揺さぶられていく様に、読んでいるこちらもめまいがするような感覚を覚えました。
そして、主人公はケイコの導きによって、コカインやSMといった、感覚を極限まで研ぎ澄ませる世界へと足を踏み入れていきます。ここで描かれるのは、自己というものが少しずつ解体されていく過程の、倒錯的な快感です。意志を放棄し、「奴隷」になることで得られる、逆説的な自由。
この部分を読んでいて思い出すのが、村上龍さんの独特の文体です。衝撃的な出来事も、日常の些細な出来事も、全てが同じトーンの、どこか乾いた静かな文章で淡々と綴られていきます。これにより、読者はまるで幽体離脱したかのように、どこか遠くから出来事を眺めているような、不思議な感覚に陥るのです。
句読点が少なく、どこまでも続いていくかのような長い文章は、まるで酩酊状態のリズムそのものです。現実と幻覚の境界線が曖昧になり、主人公の意識と読者の意識が混じり合っていく。この文体によって、私たちは無理やり、主人公と同じ認識の世界へと引きずり込まれてしまいます。
作中で語られる「生活水準はなかなか下げられない」という言葉は、この物語のもう一つの重要な側面を照らし出しているように感じます。一度強い刺激、より高いレベルの快楽を知ってしまうと、もう元には戻れない。満足するためには、さらに強い刺激を求めるしかない。これは薬物依存のメカニズムであると同時に、現代の資本主義社会そのものの比喩ではないでしょうか。
常に成長を、常に新しい何かを求め続ける社会。停滞は死を意味し、後退などありえない。主人公の「エクスタシー」への個人的な探求は、そんな社会全体の構造的な病理を、一身に背負っているかのようです。彼の依存は、私たちの社会が抱える依存の姿そのものなのかもしれません。
そして物語は、クライマックスへと向かいます。完全に教化された主人公は、ヤザキとケイコから「運び屋」になることを依頼されます。これは、彼が思考する主体から、完全に機能する「道具」へと変貌を遂げたことを意味します。ドラッグを詰めたコンドームを飲み込むという行為は、あまりにも象徴的です。
自らの身体を、他人の価値あるもの(ドラッグ)を運ぶための、単なる「器」として差し出す。彼の内臓は、物流システムの一部となる。思考する人間として始まった彼の物語は、ここで肉体という「モノ」になることで、一つの到達点を迎えるのです。それは自己の完全な否定であり、最も極端な服従の形でした。
ニューヨークからパリへ向かうコンコルドの機内での、彼の淡々とした独白は、もはや神々しささえ感じさせます。彼は一体、巧妙に仕組まれた罠の犠牲者だったのでしょうか。それとも、自らの意志でこの道を選んだのでしょうか。物語は、その答えを明確には示してくれません。
そして、衝撃の結末。読者がそれまで信じてきた物語の世界そのものが、ガラガラと崩れ去るような感覚。最後の一文の後に残された余白が、あまりにも多くのことを語りかけてきます。ヤザキの存在、ケイコの物語、それら全てが、一体何だったのか。
この曖昧な結末は、決して作者の怠慢ではありません。むしろ、これこそがこの物語の誠実さなのだと思います。明確な答えを与えてしまうことは、この物語が描いてきた「エクスタシー」という体験そのものを裏切ることになるでしょう。論理や理屈では割り切れない、説明不可能な体験。その混沌とした状態そのものが、最終的な着地点なのです。読者は、主人公と同じように、現実と虚構の区別がつかない不安な世界に、置き去りにされます。
まとめ
村上龍さんの「エクスタシー」は、間違いなく読む人を選ぶ一冊です。分かりやすい感動や、心温まる結末を求める方には、おそらく苦痛な読書体験になるかもしれません。物語は、あなたに安易な答えを与えてはくれません。
しかし、もしあなたが日常の退屈さに息苦しさを感じていたり、自分を縛り付けている常識や価値観を一度壊してみたいと密かに願っていたりするのなら。この物語は、忘れがたい強烈な一撃を与えてくれるはずです。それは、思考の限界、感覚の果てへと誘う、危険な旅への招待状です。
読み終えた後、あなたは心地よいカタルシスではなく、むしろ心のざわめきと、深い問いを抱えることになるでしょう。現実とは何か。自己とは何か。そして、人間が求める「恍惚」の正体とは、一体何なのか。
この物語が残す不穏な余韻は、きっとあなたの心に長く留まり続けます。安全な場所から抜け出して、自己が解体されるほどの体験に身を浸してみたい。そんな勇気のある方にこそ、手に取っていただきたい作品です。