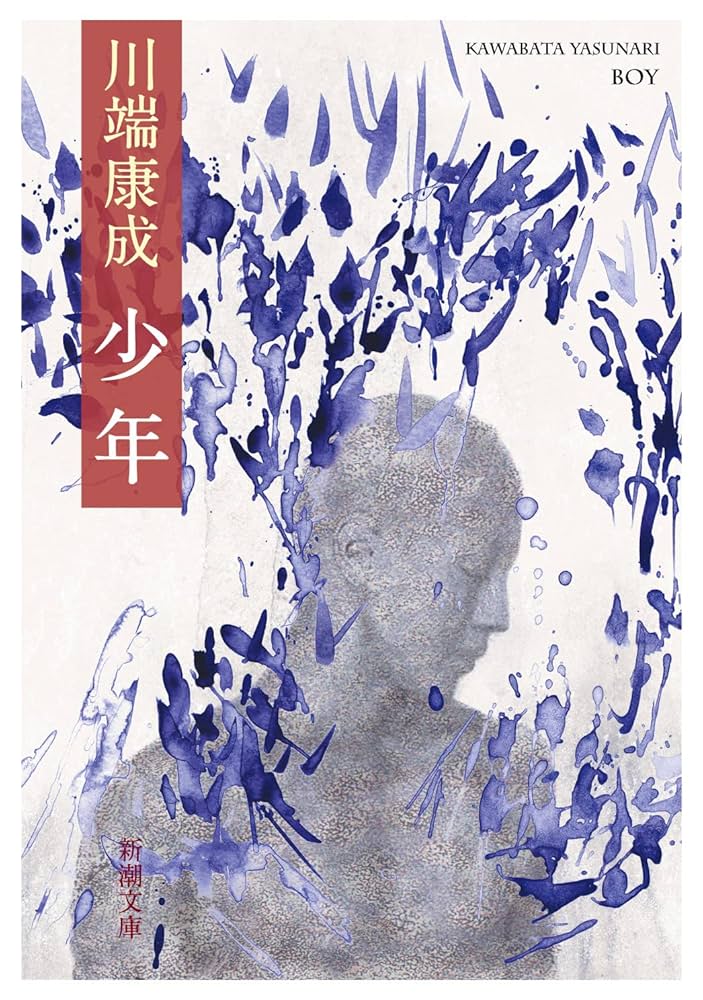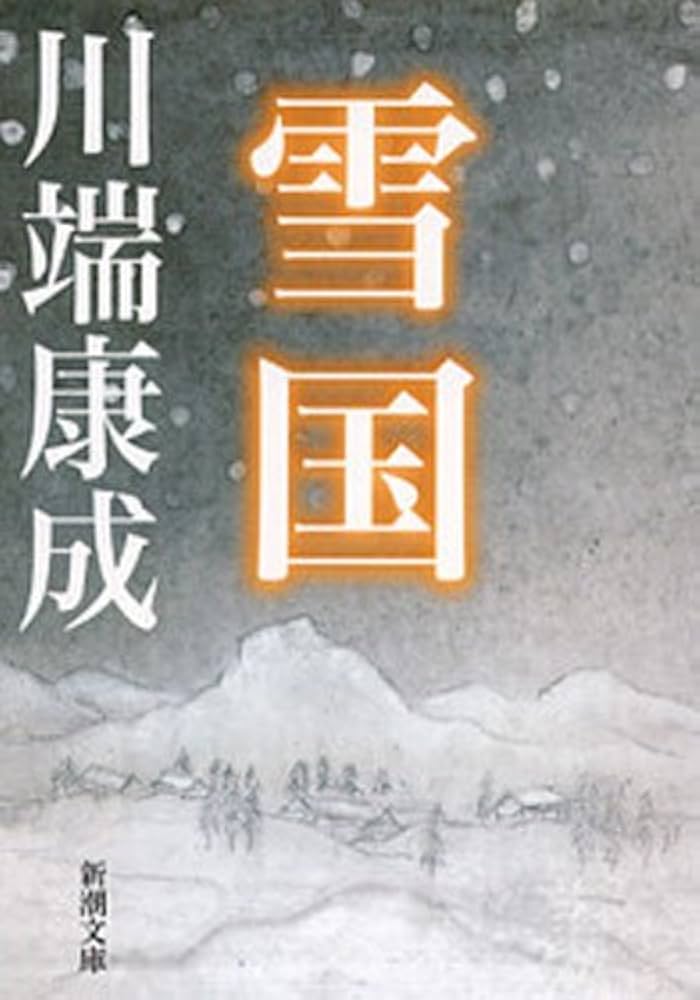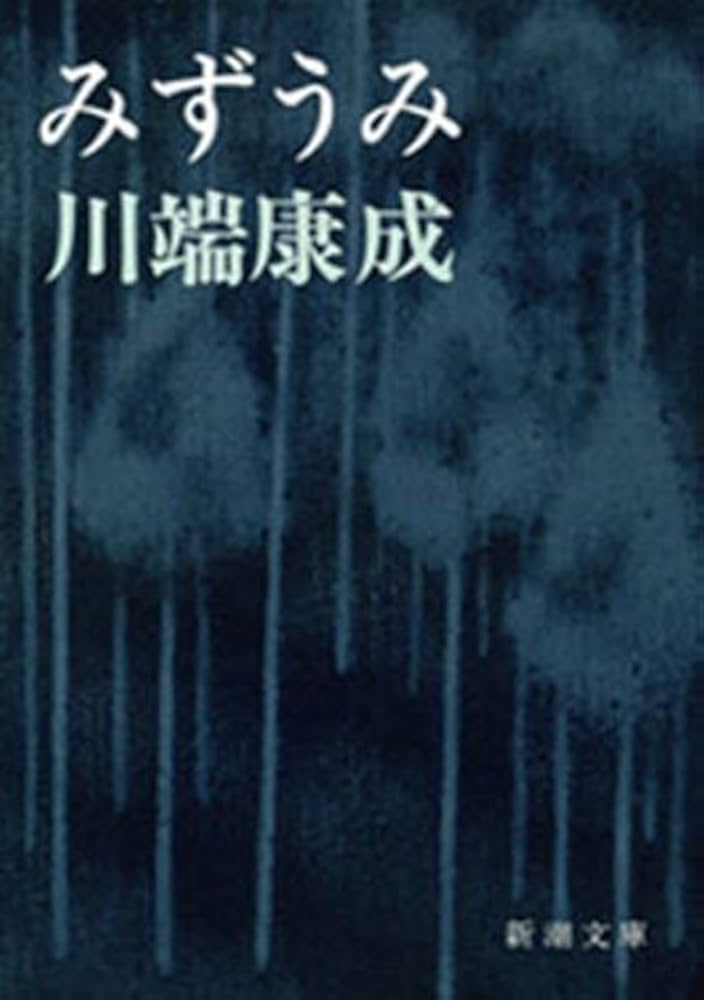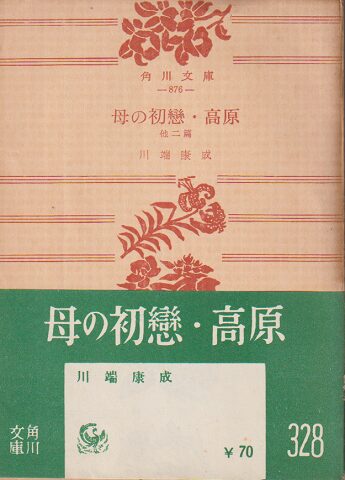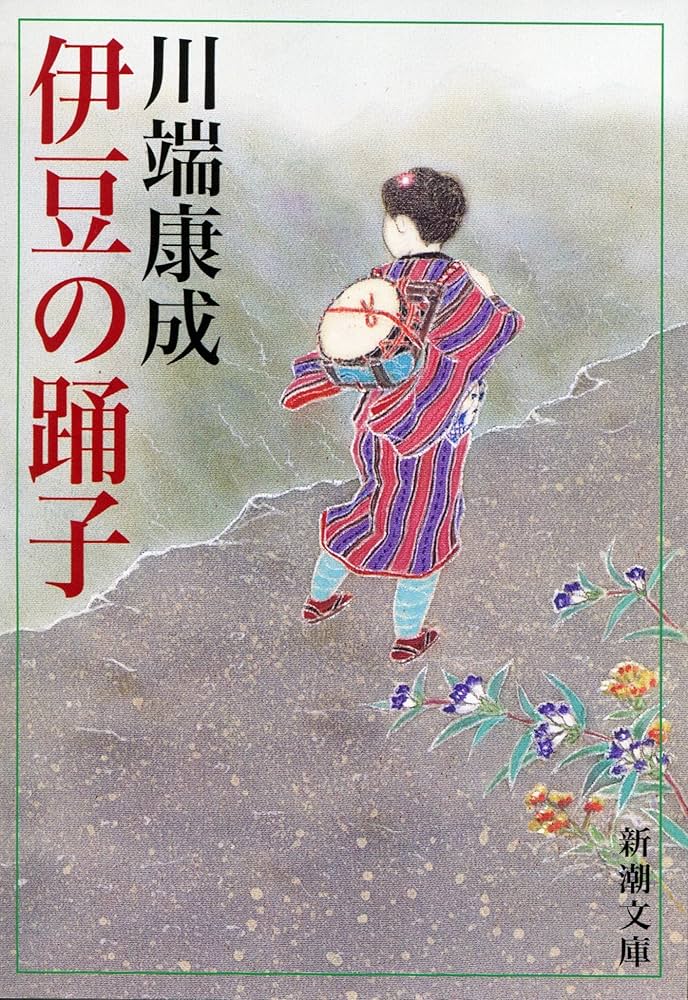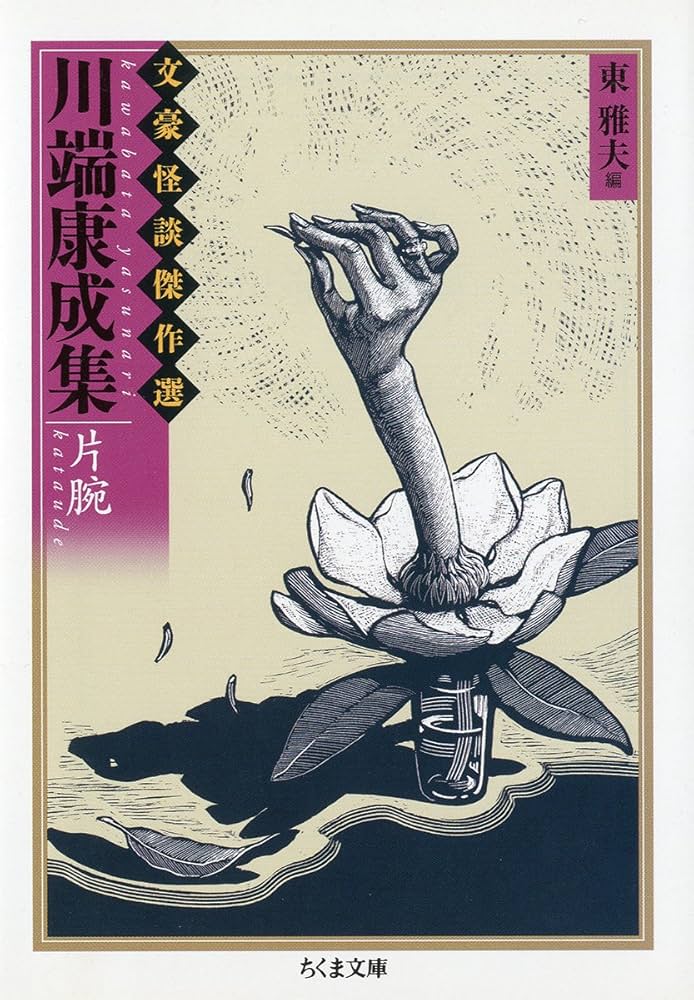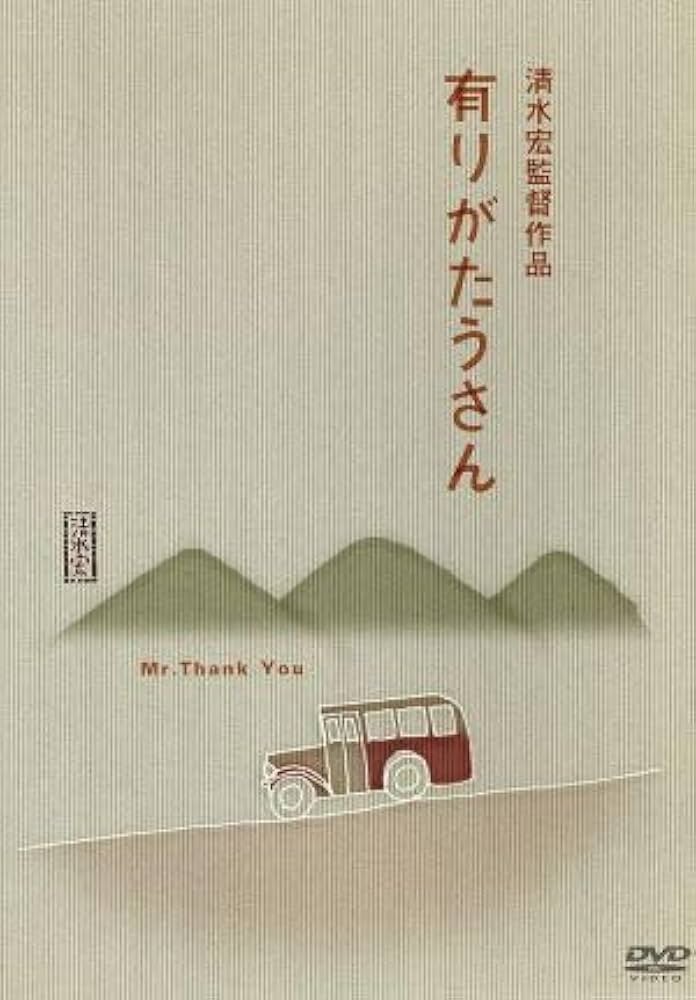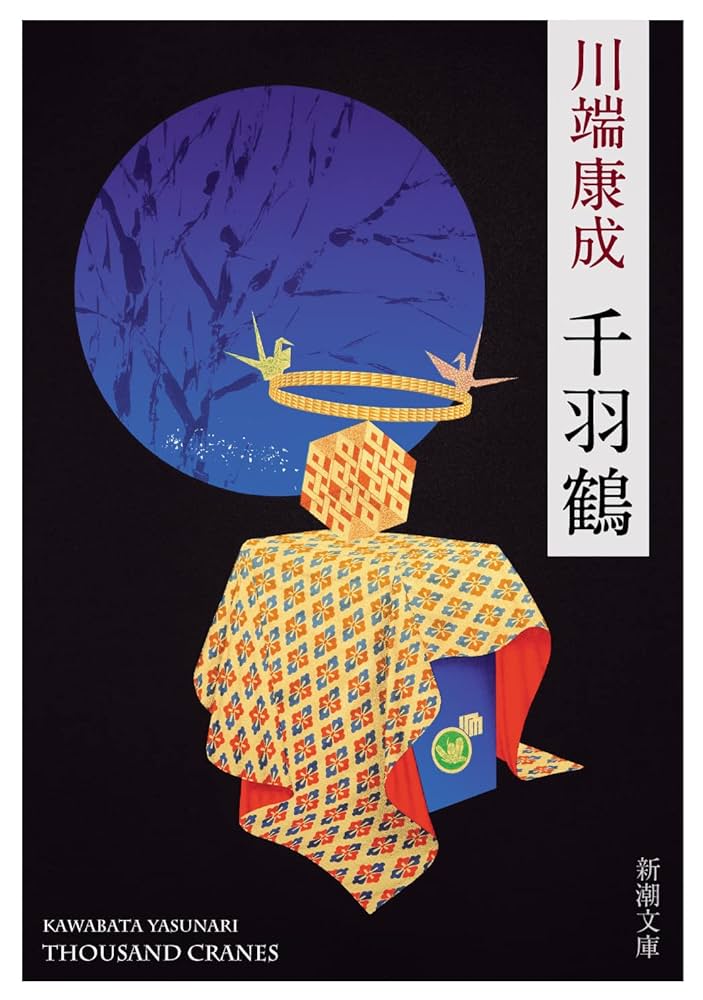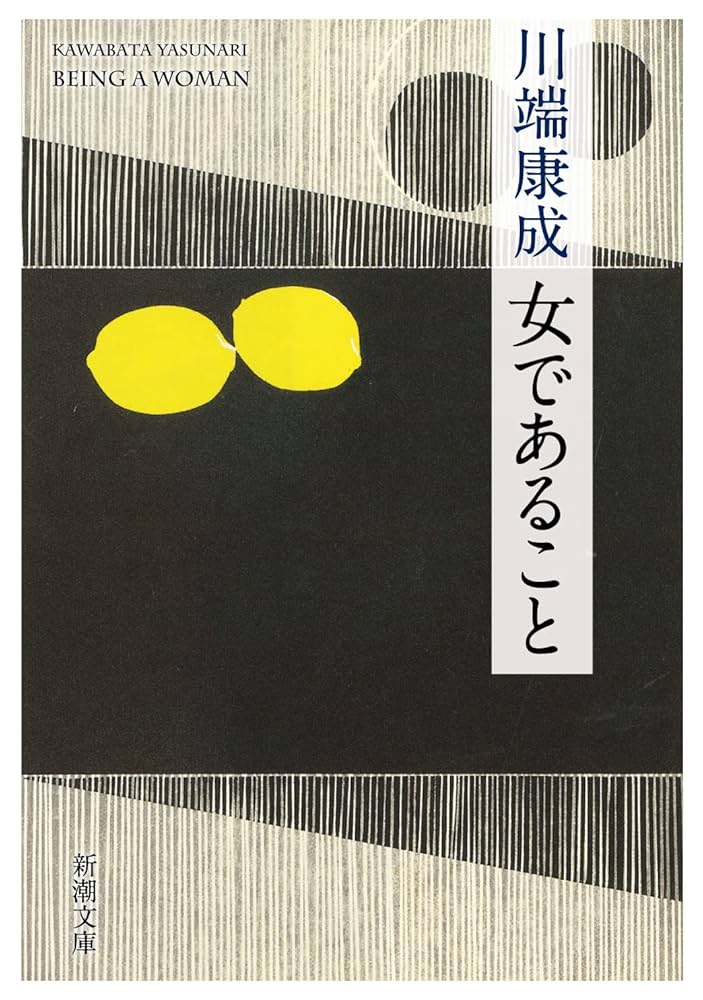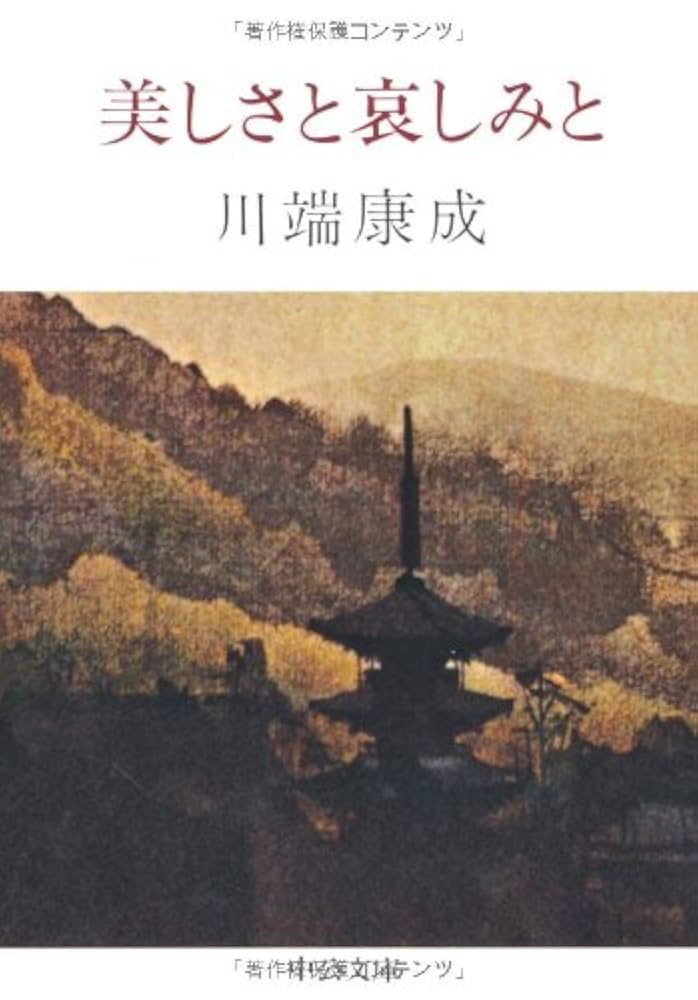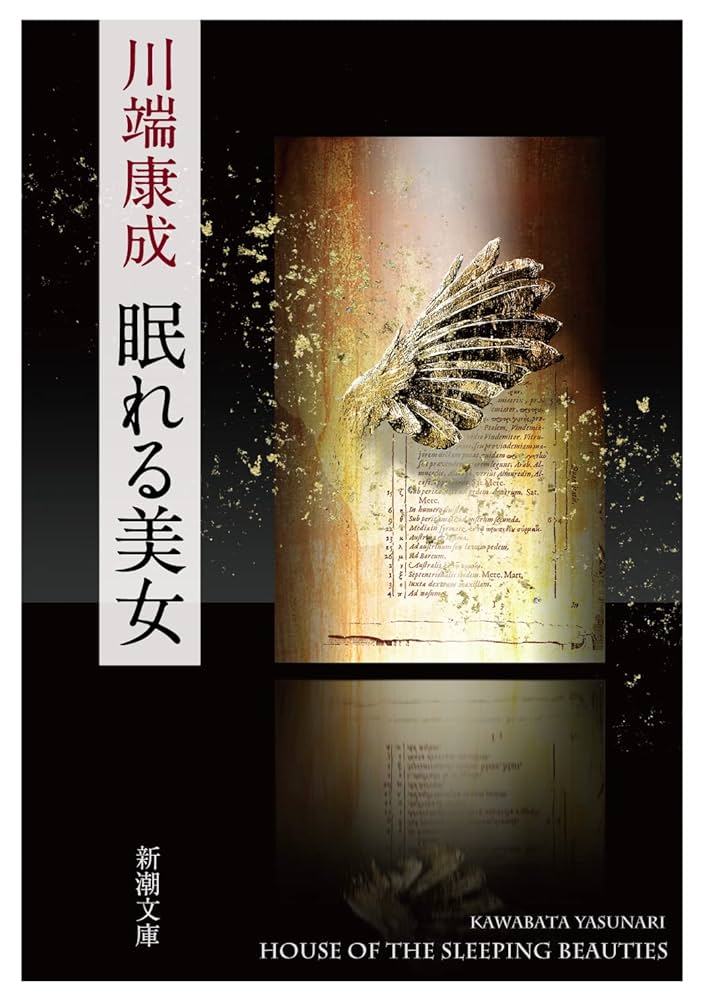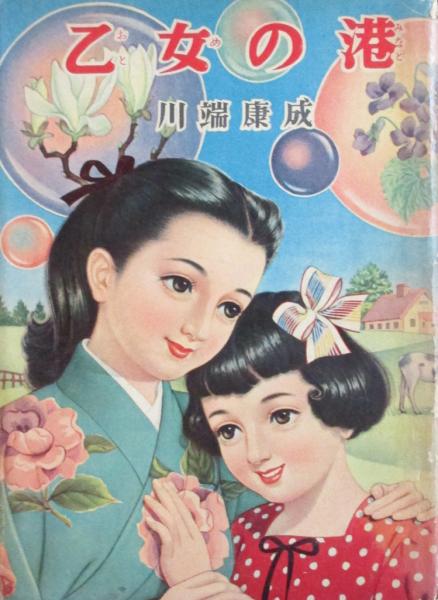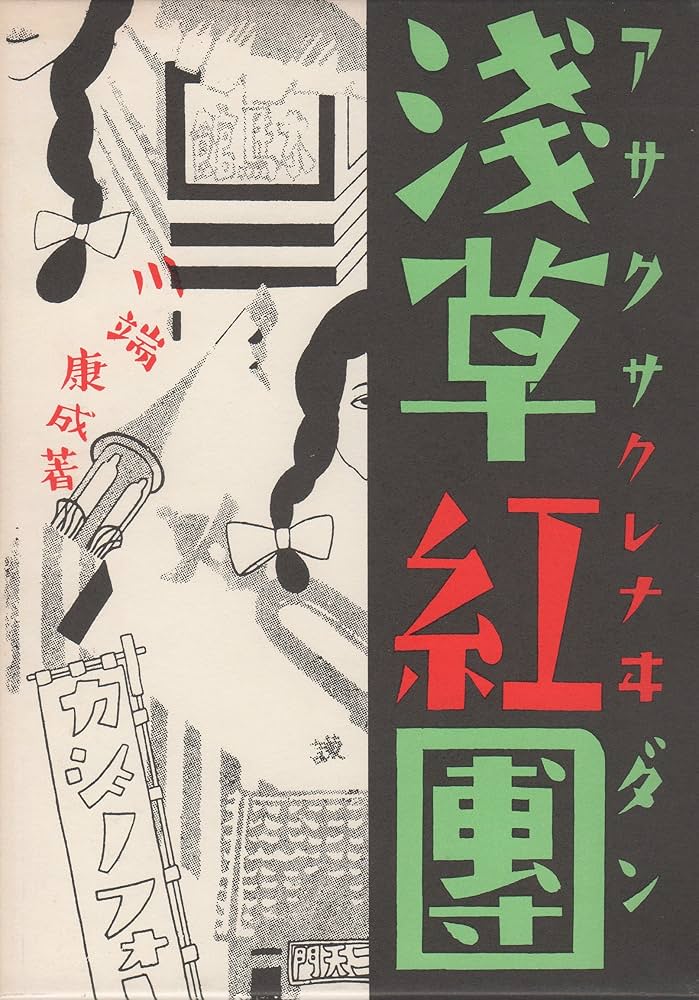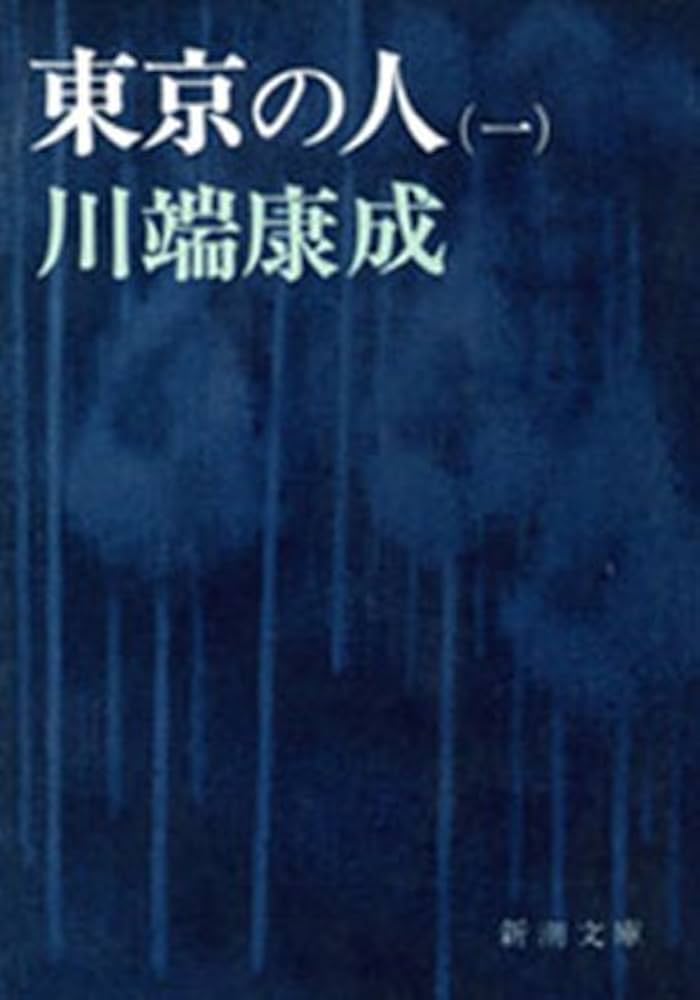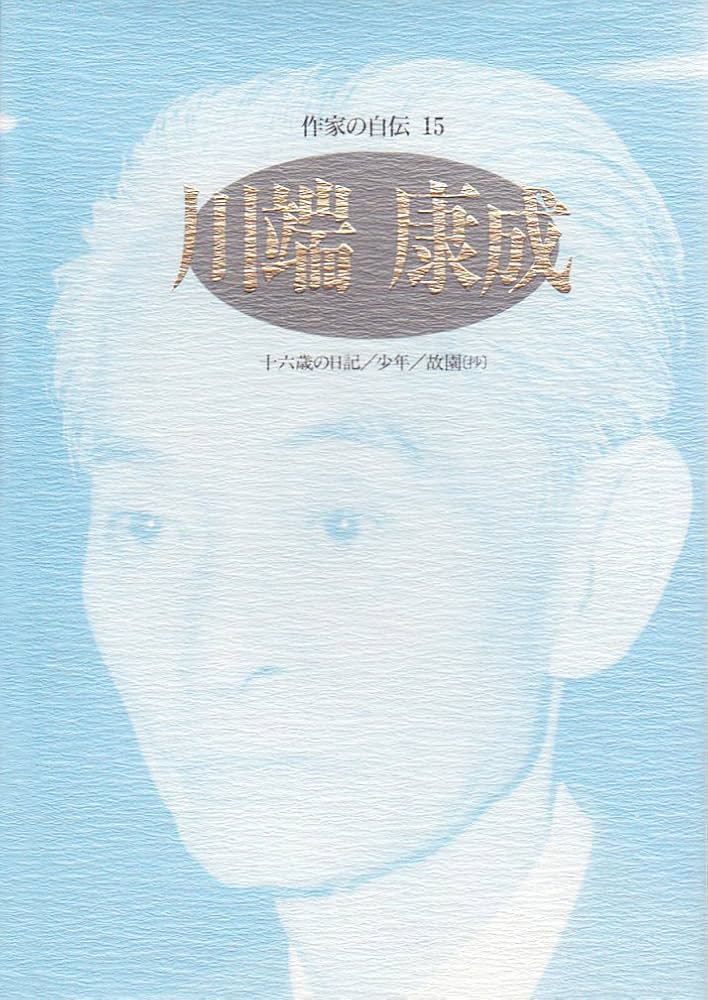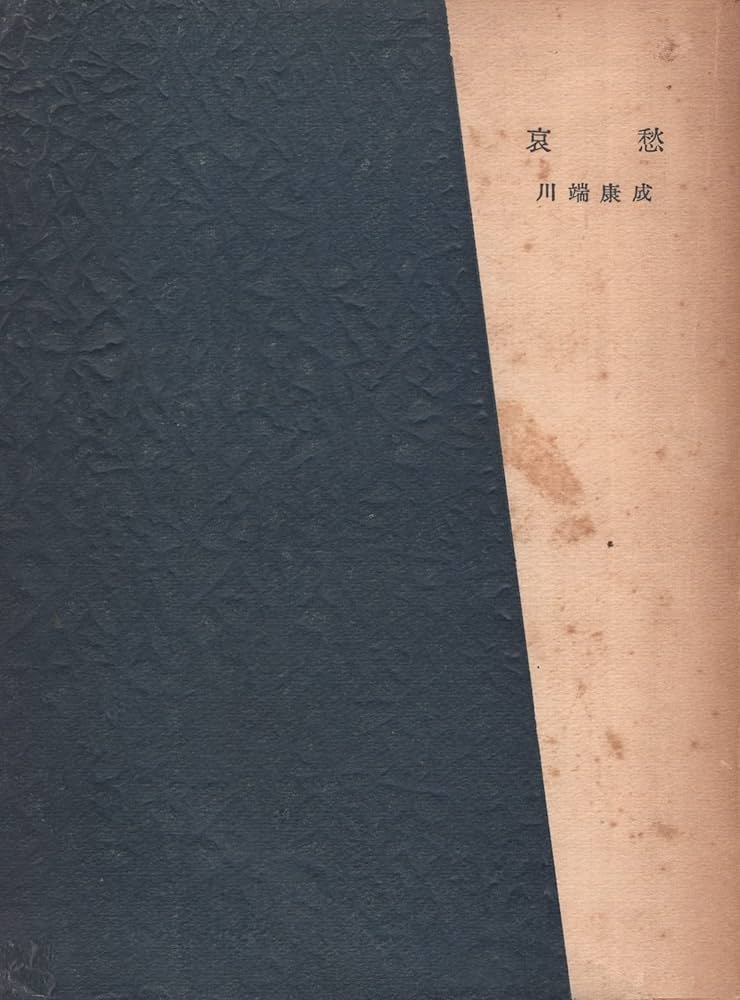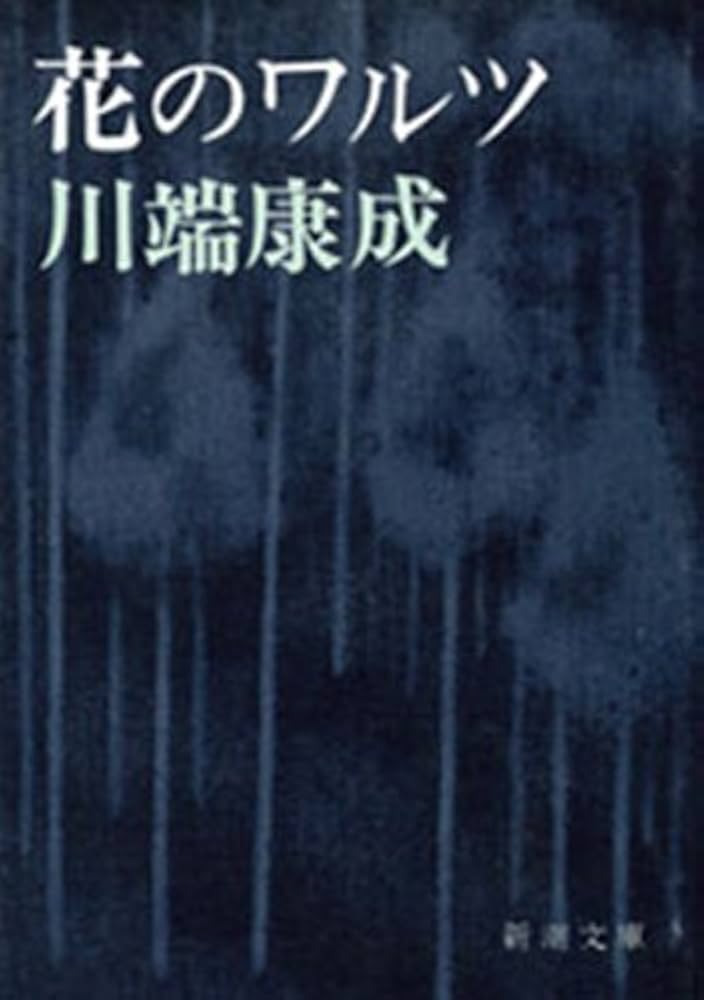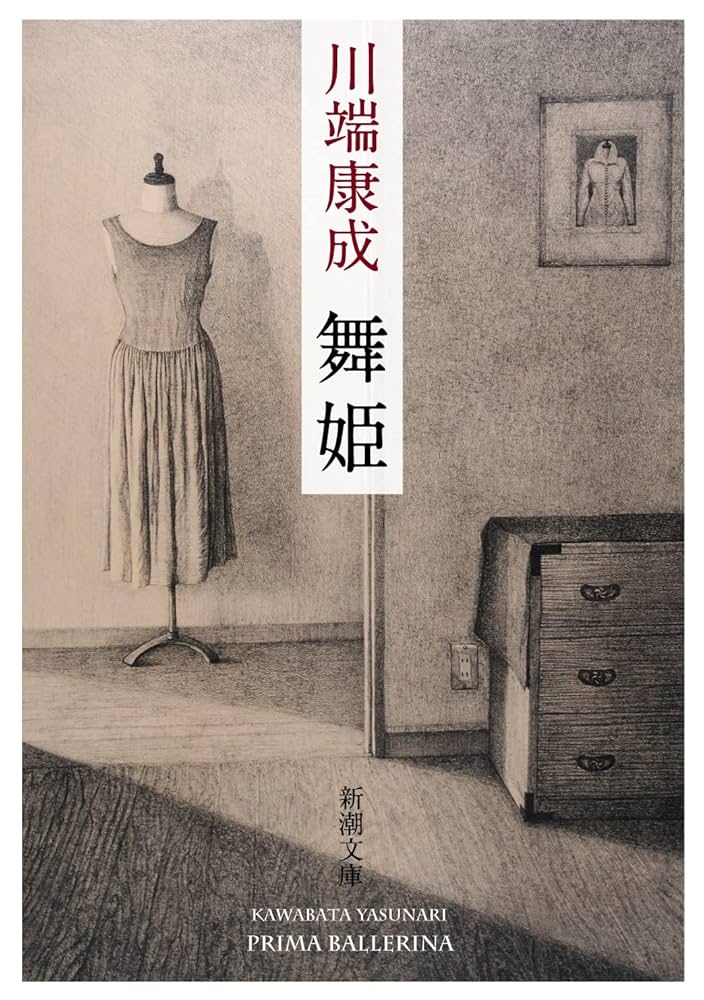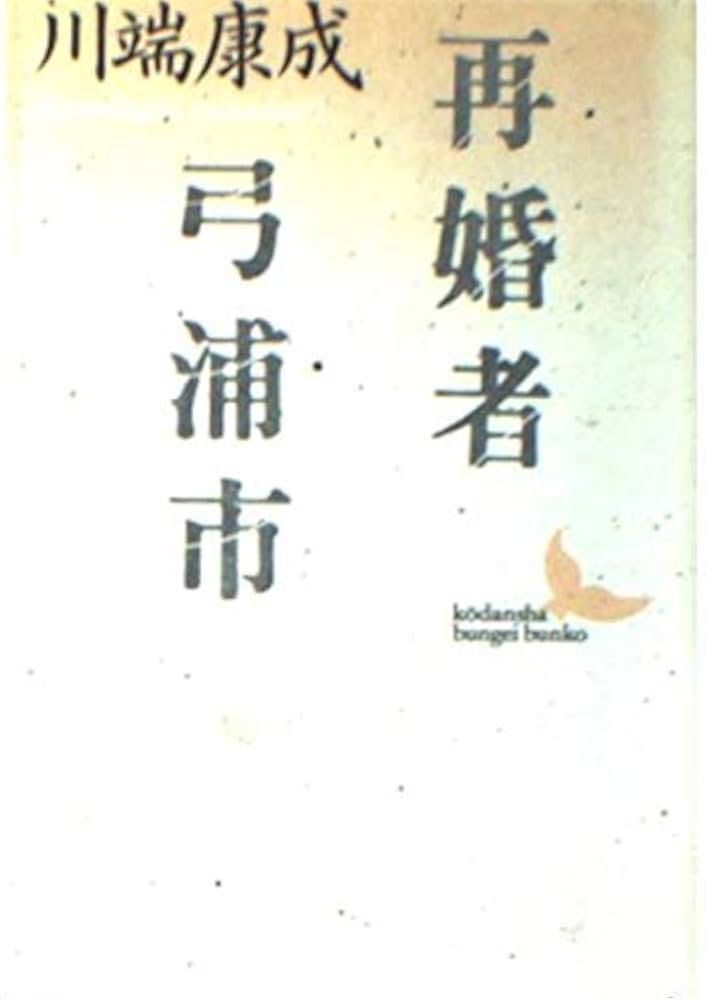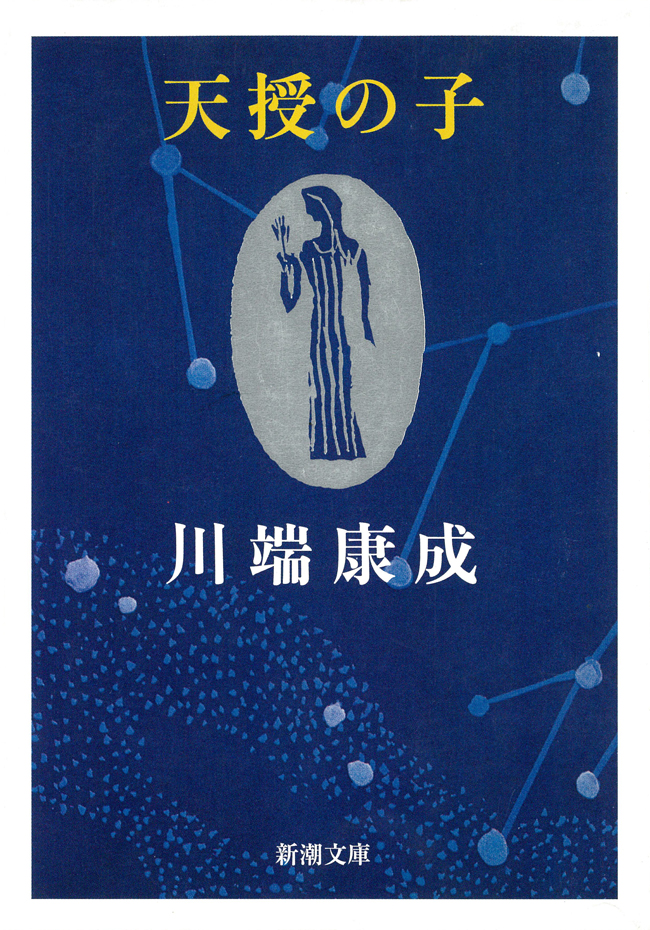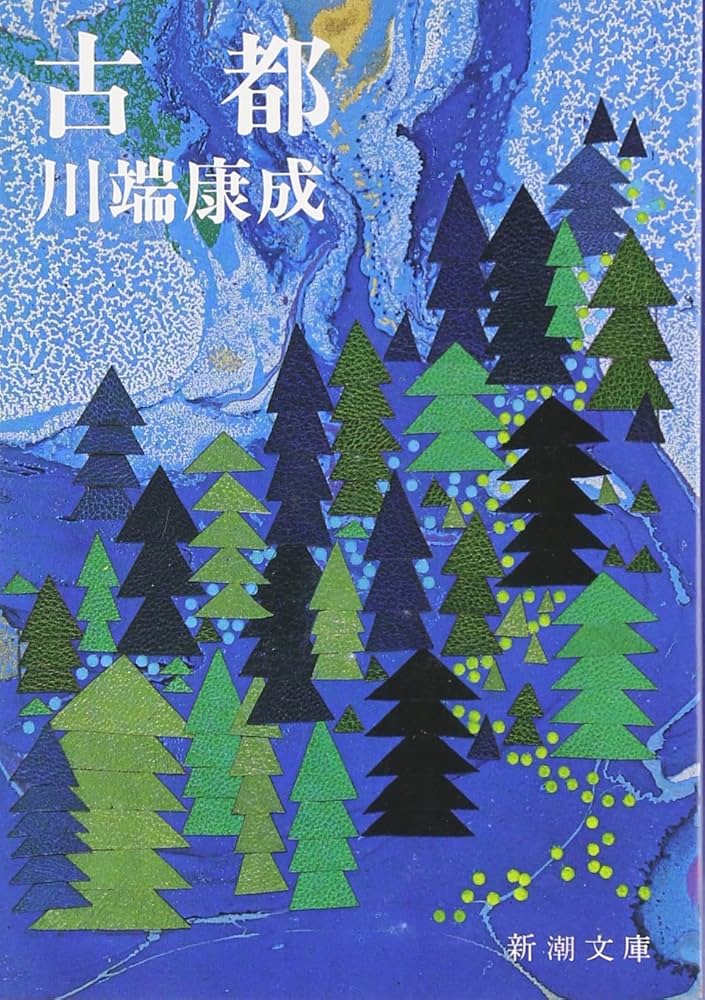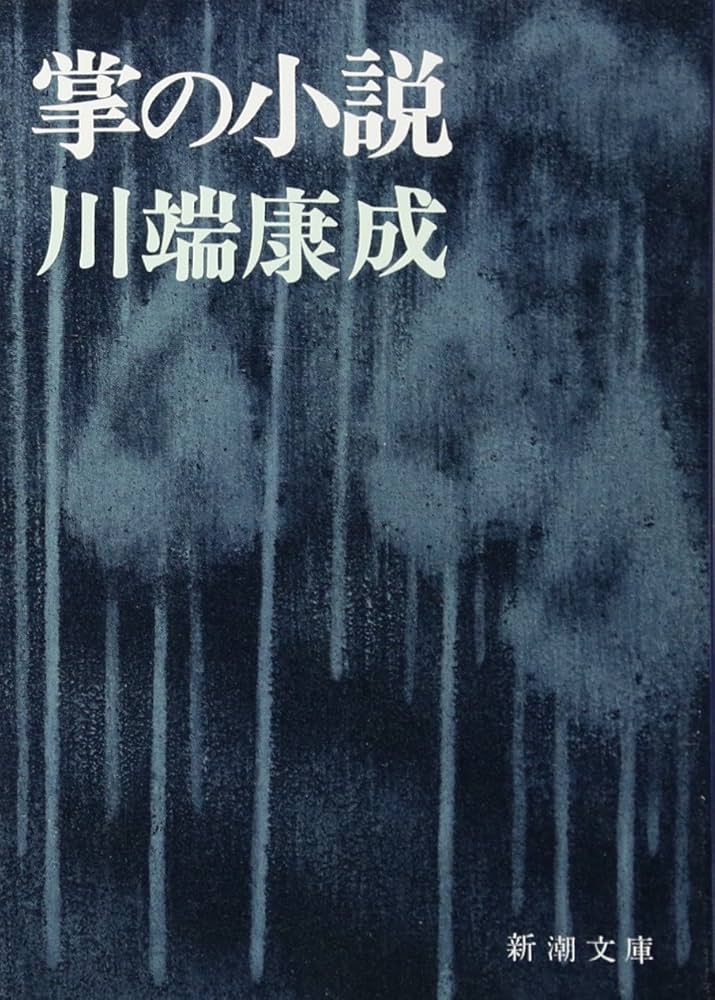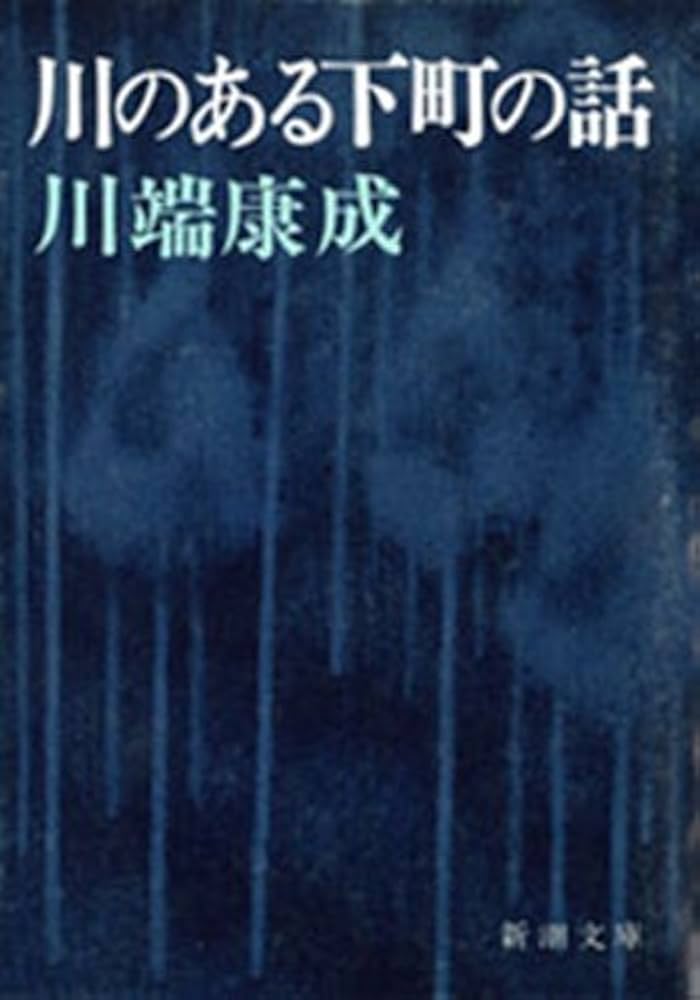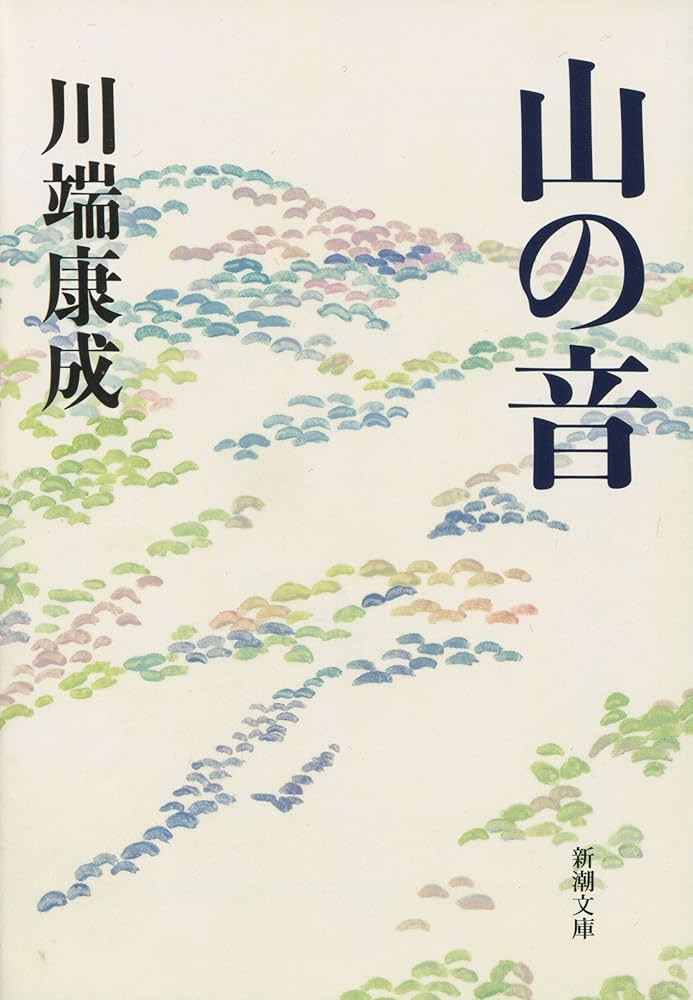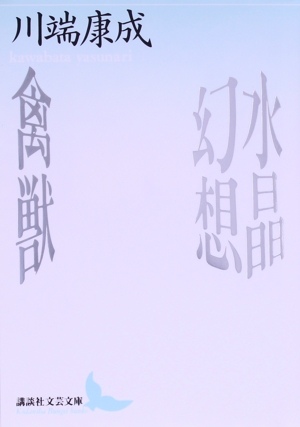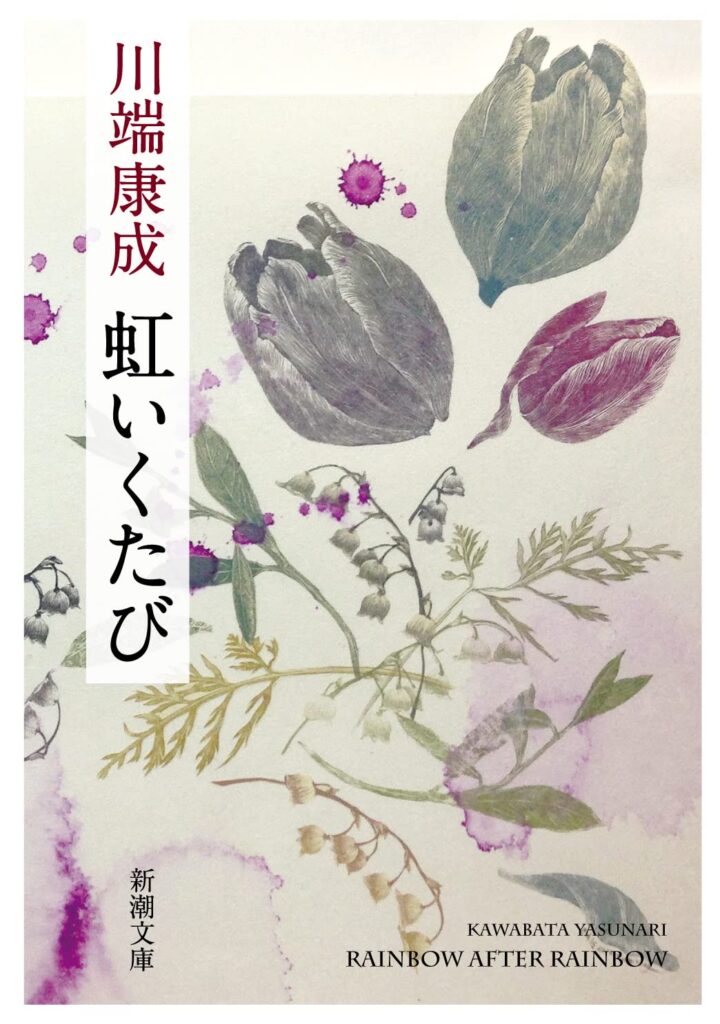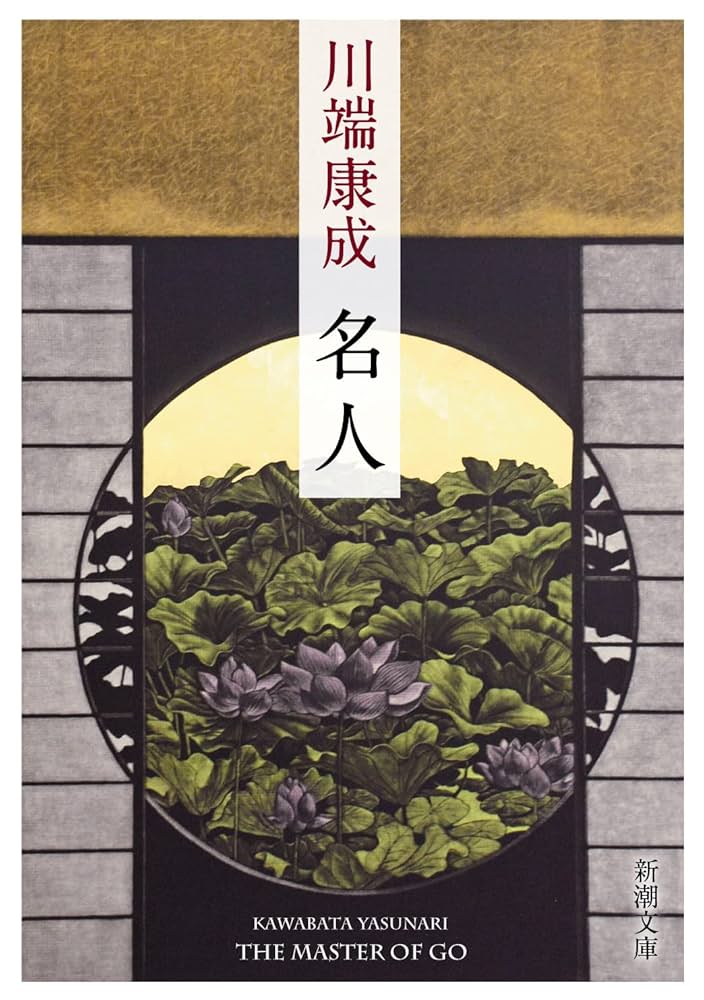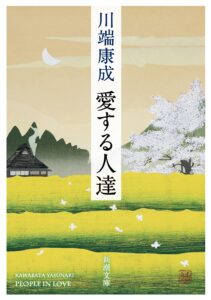 小説「愛する人達」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「愛する人達」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
川端康成の短編集『愛する人達』は、その優しい響きの題名とは裏腹に、読む者の心を静かに、そして深くかき乱す力を持っています。ここに描かれているのは、決して結ばれることのない、一方通行の愛の姿ばかり。登場人物たちは、愛する対象にその想いを伝えることなく、自身の内で燃え盛る孤独な炎を見つめています。
では、なぜ川端康成は、このような成就しない愛の物語ばかりを集めたのでしょうか。それは、愛という感情が本質的に孤独なものであり、人と人とが完全に理解し合うことの難しさを示しているのかもしれません。この短編集は、愛の喜びではなく、愛することそのものに伴う、切なくも美しい哀しみを私たちに教えてくれます。
この記事では、そんな『愛する人達』に収められた九つの物語を、ネタバレを含みながら一つひとつ丁寧に読み解いていきます。それぞれの物語が持つ独特の空気感と、登場人物たちの心のひだに触れることで、この作品の奥深い魅力に迫っていきたいと思います。
「愛する人達」のあらすじ
川端康成の『愛する人達』は、九つの短編からなる物語集です。それぞれの物語は独立していますが、全体を通して「一方通行の愛」や「すれ違う想い」といった、共通の哀しい旋律が流れています。登場人物たちは、心の中に大切な人を思い描きながらも、その気持ちが相手に届くことはほとんどありません。
例えば、この短編集を象徴するような『母の初恋』では、ある高名な作家が、亡き初恋の女性の娘を引き取ります。娘は、亡き母が愛したその人に、知らず知らずのうちに惹かれていくのです。また『ほくろの手紙』では、妻の無意識の仕草を、夫は自分への拒絶だと誤解し続けます。本当は、それが愛の表現だったとも知らずに。
このように、物語の中で描かれる愛は、記憶の中の幻影であったり、悲劇的な誤解から生まれたり、あるいは決して言葉にされることのないまま胸の内に秘められたりします。登場人物たちは、愛する人がいながらも、その実、深い孤独の中にいるのです。
彼らの想いがどのような結末を迎えるのか、その切ない運命の行方は、ぜひ物語を読んで確かめてみてください。そこには、ただ悲しいだけではない、忘れがたい美しさが確かに存在しています。
「愛する人達」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、各短編のネタバレを含んだ詳しい感想をお話しします。未読の方はご注意ください。九つの物語が織りなす、哀しくも美しい愛の世界を一緒に旅していきましょう。
『母の初恋』―― 運命は、稲妻のように。
この物語は、まさに『愛する人達』という短編集のテーマを凝縮したような作品です。高名な劇作家・佐山は、若くして亡くなった初恋の相手・民子の娘である雪子を引き取ります。妻の時枝の勧めもあって始まった共同生活でしたが、雪子は静かに佐山への想いを募らせていきます。それは、亡き母が果たせなかった恋心の、世代を超えた継承のようでした。このあたりの設定からして、もう切ないですよね。
物語の終盤、雪子は縁談を受け入れて嫁ぎますが、すぐに姿を消してしまいます。佐山が彼女を見つけ出したのは、かつて民子と過ごした思い出の場所でした。そこで明かされる雪子の本当の気持ち。それは「初恋は、結婚によっても、なにによっても、滅びないことを、お母さんが教えてくれた」という言葉に集約されています。母の愛が、まるで運命の稲妻のように娘の人生を貫き、佐山へと向けられている。この衝撃的なネタバレともいえる結末に、私は言葉を失いました。愛とは、これほどまでに宿命的で、抗いがたいものなのでしょうか。
『女の夢』―― 悲劇の仮面の下にある、本当の心。
次に『女の夢』です。この物語は、女性が社会の中で生きる上で、時に必要となる「嘘」や「夢」の哀しさを描いています。歯科医の久原と結婚した美しい治子。彼女が婚期を逃していたのは、「従兄が彼女への片思いから命を絶った」という悲劇的な過去のせいだとされていました。夫の久原も、そのロマンチックな過去に、ある種の魅力を感じていたのです。
しかし、物語が進むにつれて衝撃の事実が明らかになります。従兄の話は、実は本当の理由を隠すための「盾」でした。治子が本当に愛していたのは、片桐という別の男性だったのです。従兄の死によって、片桐との婚約が破談になってしまった。これが、彼女が独身を貫いていた本当の理由でした。治子は、夫には決して明かせない「女の夢」、つまり片桐への変わらぬ愛を胸に秘めて生きていく。このネタバレを知った時、治子のしたたかさと、その裏にあるどうしようもない一途さに胸が締め付けられました。
『ほくろの手紙』―― 愛は、言葉にならない場所に。
『ほくろの手紙』は、夫婦間のコミュニケーション不全が生む悲劇を、鮮やかに描き出しています。妻の小夜子には、肩にある大きなほくろを無意識に触る癖がありました。夫は、その仕草が「みじめに見える」とひどく嫌い、自分への反抗のしるしだと信じ込んでいます。彼のいら立ちは、時に妻への暴力にまで発展してしまいます。
この物語のネタバレは、小夜子からの手紙(あるいは心の声)によって明かされる、衝撃的な真実です。彼女のあの仕草は、拒絶のサインなどではありませんでした。それどころか、「ことばには出せませぬあなたへの愛を、あらわしていたのではないかしら」。なんと、それは夫への言葉にならない愛の表現だったのです。愛しているからこそ、無意識に触れてしまう。このあまりにも悲しいすれ違い。愛は、時に言葉よりも身体が正直に語ることがある。しかし、その「身体からの手紙」は、往々にして誤読されてしまうのですね。
『夜のさいころ』―― 闇に響く、運命の音。
旅芸人一座の物語『夜のさいころ』は、どこか幻想的な雰囲気に満ちています。一座を率いる水田は、若く清純な踊り子のみち子に惹かれています。彼女には、芸者だった母親から受け継いだ不思議な癖がありました。それは、毎晩床の中で、誰にも知られず五つのさいころを振ること。暗闇の中で続けられるその静かな儀式は、彼女の逃れられない運命を象徴しているかのようです。
水田は、父親のような気持ちから、彼女にさいころを海に捨てさせます。それは彼女を過去のしがらみから解放するための行為でした。しかし、同時に彼女が持つ神秘的な部分を奪ってしまう行為でもあったのかもしれません。この物語は、人の運命や血筋というものについて深く考えさせられます。さいころが偶然の象徴であるのに対し、それを振り続ける行為は遺伝的な宿命を感じさせる。人の純粋さを守りたいという善意が、時としてその人の本質を侵してしまうという皮肉が、ここに描かれています。
『燕の童女』―― 同じ景色を見ても、心は孤独。
『燕の童女』は、新婚旅行中の夫婦の、ほんの束の間の出来事を描いた短い物語です。船上で、二人は美しくも孤独な雰囲気を持つ混血の少女を見かけます。その少女を見て、夫は「人種が融和した未来の世界」といった壮大な理念を思い描きます。彼は、少女そのものよりも、彼女を通して見える抽象的な概念に心を奪われているのです。
一方、妻が心を寄せたのは、少女自身が抱えるであろう目の前の孤独や、その儚さでした。同じ少女を見ているはずなのに、夫婦の視点は全く異なっています。このささやかなエピソードは、どんなに親しい間柄であっても、人は究極的には孤独な存在であるという、川端作品に一貫して流れるテーマを浮き彫りにします。共有された経験が、かえってそれぞれの孤独を際立たせてしまう。なんとも寂しい真実ではないでしょうか。
『夫唱婦和』―― 調和という名の、見えない壁。
『夫唱婦和』という題名は、夫婦仲が非常に良いことを意味する言葉です。しかし、この物語で描かれるのは、その言葉とは全く逆の世界。表面上は穏やかに暮らしている夫婦の間に横たわる、決して交わることのない認識のズレが、静かに、しかし克明に描き出されていきます。
この物語は、二人の人間が「現実を共有する」ということ自体がいかに難しいかを問いかけてきます。私たちは誰もが、自分だけの主観的な世界の中で生きています。結婚という制度は、その全く異なる二つの世界が、あたかも同じものであるかのように見せかけるための、脆い約束事なのかもしれません。完璧な調和を意味する題名が、これ以上ないほど皮肉に響く作品です。
『子供一人』―― 生命の誕生は、美しい嵐。
この短編集の中で、ひときゅう生々しく、力強いエネルギーに満ちているのが『子供一人』です。若い芳子は、結婚前に身ごもった子供の出産を控えています。彼女の妊娠期間は、母性の輝きに満ちた穏やかな日々としてではなく、肉体的にも精神的にも激しい「嵐」として描かれます。
激しいつわりに苦しみ、人格まで変わってしまったかのような妻の姿を、夫の元田はただ戸惑いながら見守るしかありません。芳子にとって、お腹の子は愛しい我が子であると同時に、自分の身体と心を乗っ取ろうとする、得体のしれない力を持った存在でもあるかのようです。妊娠や出産というものを神聖視するのではなく、一人の女性のアイデンティティを根底から揺るがすほどの、壮絶な生物学的プロセスとして捉えている。この視点には、正直驚かされました。
『ゆくひと』―― 燃える空と、届かぬ想い。
『ゆくひと』は、思春期の少年が抱く、年上の女性への淡く切ない恋心を描いた、まさに川端康成の真骨頂ともいえる作品です。少年・佐紀雄は、よく知りもしない男性のもとへ嫁いでいく年上の女性・弘子に、言葉にできない複雑な感情を抱いています。
二人が過ごす最後のひととき。その背景には、噴煙を上げる浅間山の壮大な光景が広がっています。燃え盛る火山は、佐紀雄の心の中で渦巻く、喪失感や憧れ、そして悲しみといった、表現しようのない感情そのもののようです。去りゆく美しい人への、決して報われることのない清らかな愛。自然の風景を登場人物の心情と重ね合わせる手法が見事としか言いようがありません。短い物語ですが、読んだ後には一枚の美しい絵画を見たような、深い余韻が残ります。
『年の暮』―― 後悔は、芸術家の影。
最後の物語『年の暮』は、どこか作者自身の内面を吐露しているかのようで、非常に興味深い作品です。既婚の劇作家である泉太は、千代子という若い女性ファンと十年もの間、文通を続けています。彼は、自分の書く暗い芝居を、なぜこの純粋な少女が好むのか、不思議に思いながらも惹かれていました。
千代子の結婚が決まった時、彼は彼女に「夫を愛しなさい」と助言します。しかしその裏で、彼は自分が彼女を「精一杯愛さなかった」ことへの深い後悔に苛まれるのです。この後悔は、一体何なのでしょうか。それは、芸術家と鑑賞者という関係を超えられなかったことへの悔いなのか。あるいは、人生の多くを芸術に捧げてきた男が、現実の繋がりを逸してしまったことへの哀しみなのか。ネタバレになりますが、後に千代子の夫は戦死し、彼女からの便りは途絶えてしまいます。年の暮れ、一人で物思いにふける泉太の姿は、あまりにも寂しいです。
まとめ
川端康成の『愛する人達』を読んでみて、いかがでしたでしょうか。この短編集が描き出すのは、温かい結びつきというよりも、むしろ愛することの孤独さ、そしてその中に宿る切ない美しさだったように思います。九つの物語は、それぞれが繊細なガラス細工のようでした。
登場する人々は、決して報われることのない想いを抱きしめて生きています。それは、亡き人への思慕であったり、届かない憧れであったり、あるいは悲しい誤解が生んだすれ違いであったりします。彼らの愛は、相手と交わることなく、自分自身の心の中で完結してしまうのです。
しかし、その不完全さ、成就しないからこその純粋さが、かえって私たちの心に深く響くのではないでしょうか。川端康成は、愛がもたらす哀しみの中にこそ、消えることのない清らかな輝きがあることを見出していたのかもしれません。読み終えた後、ずっしりとした余韻が残ります。
この物語は、愛の幸福な側面だけではなく、その裏側にある痛みや孤独にも目を向けさせてくれます。もしあなたが、人間の心の奥深くにある、言葉にならない感情の揺らぎに触れてみたいなら、ぜひ手に取ってみてください。きっと、忘れられない一冊になるはずです。