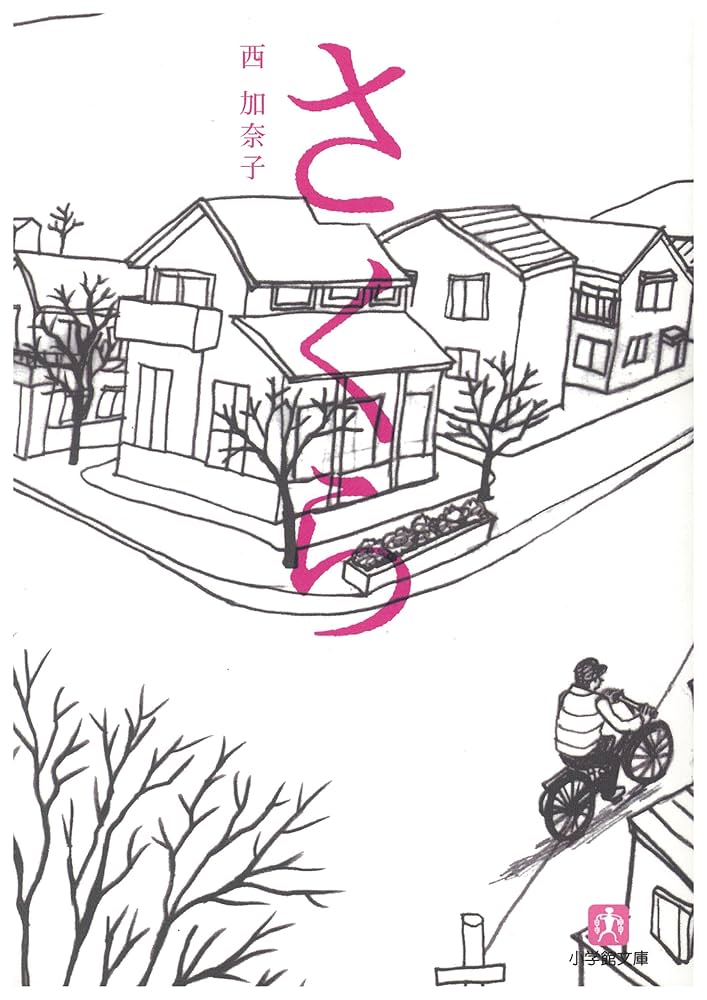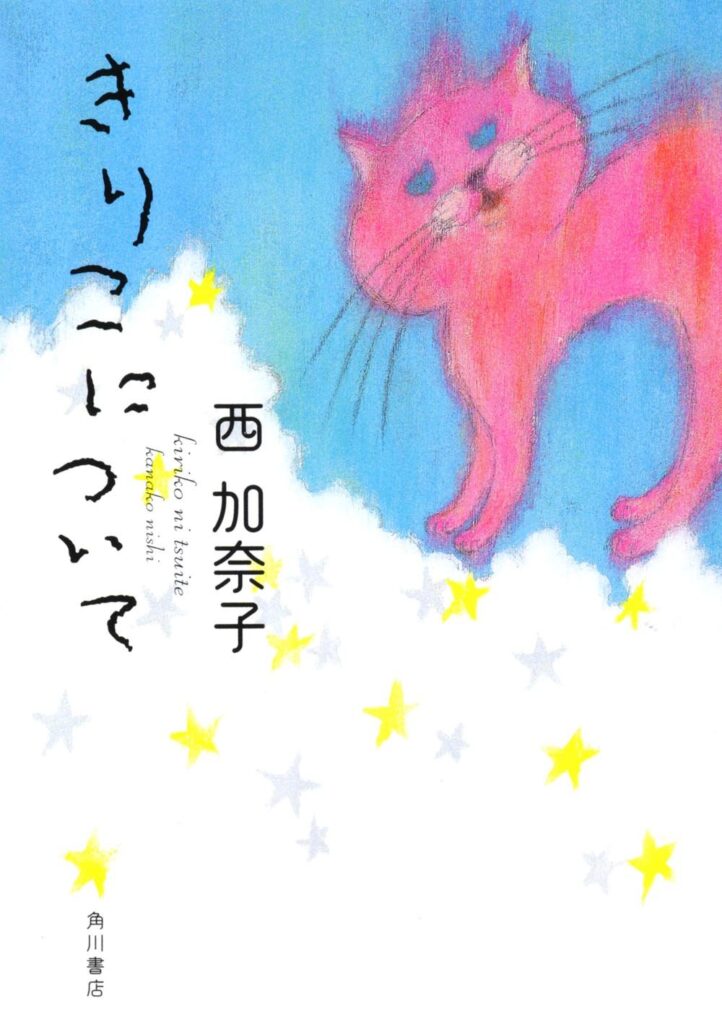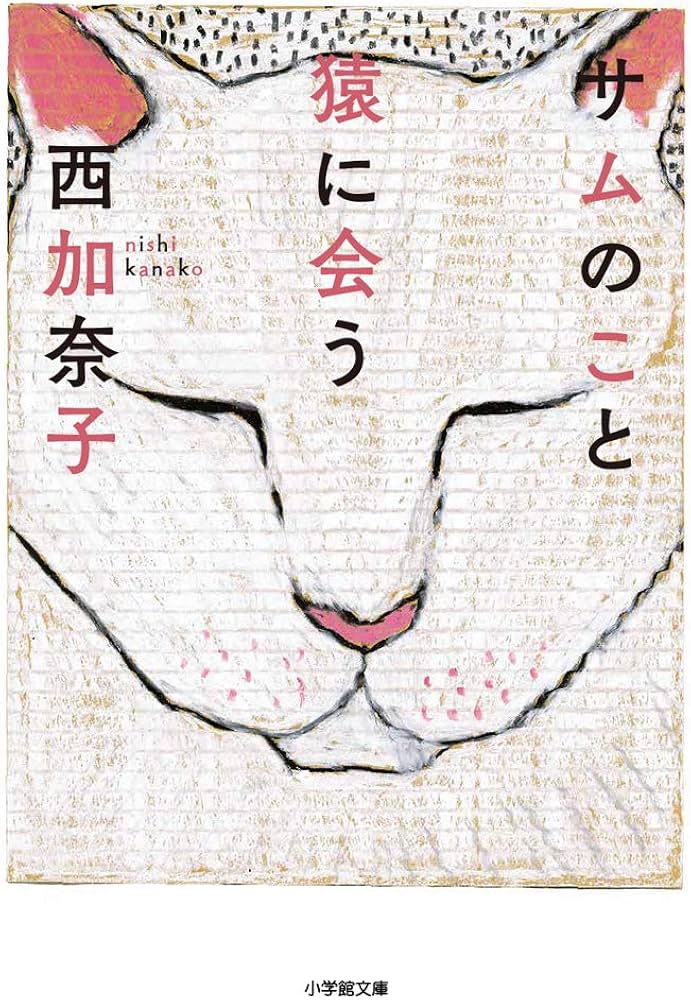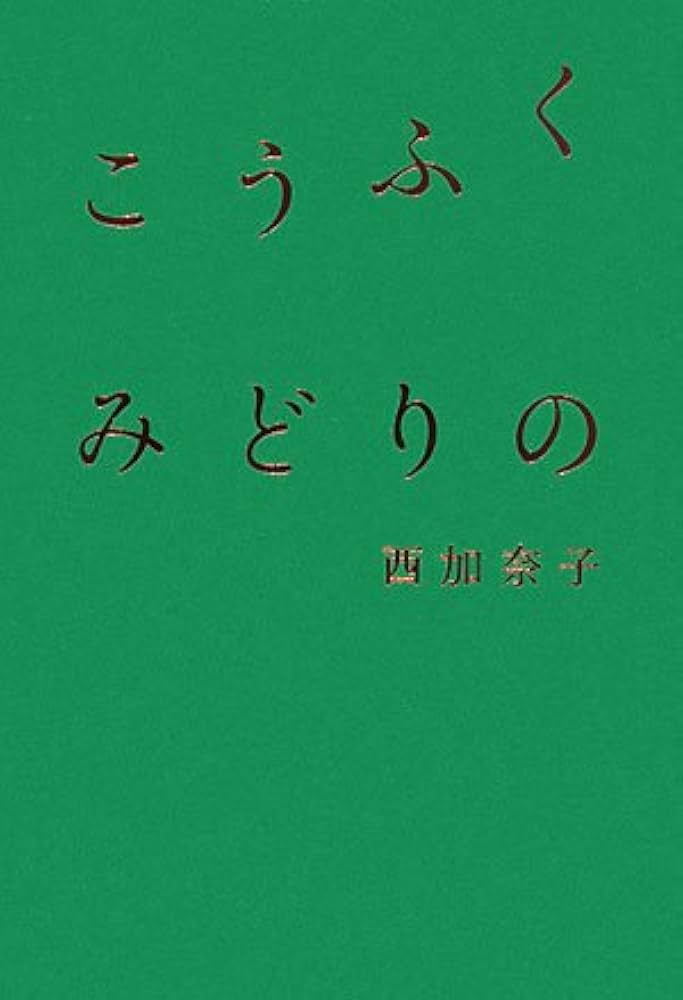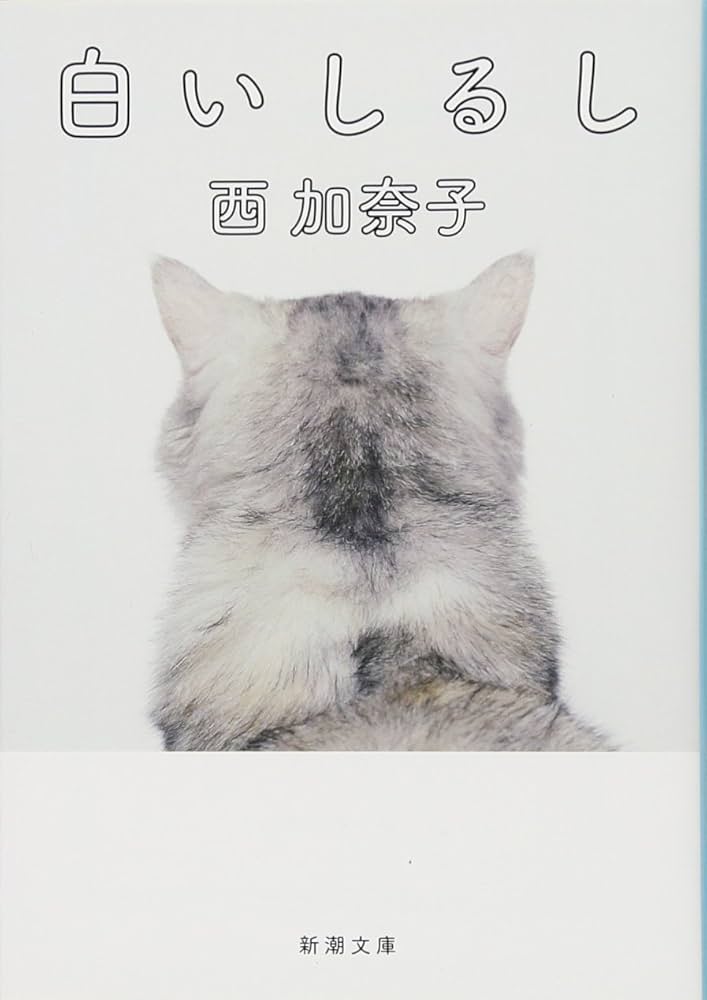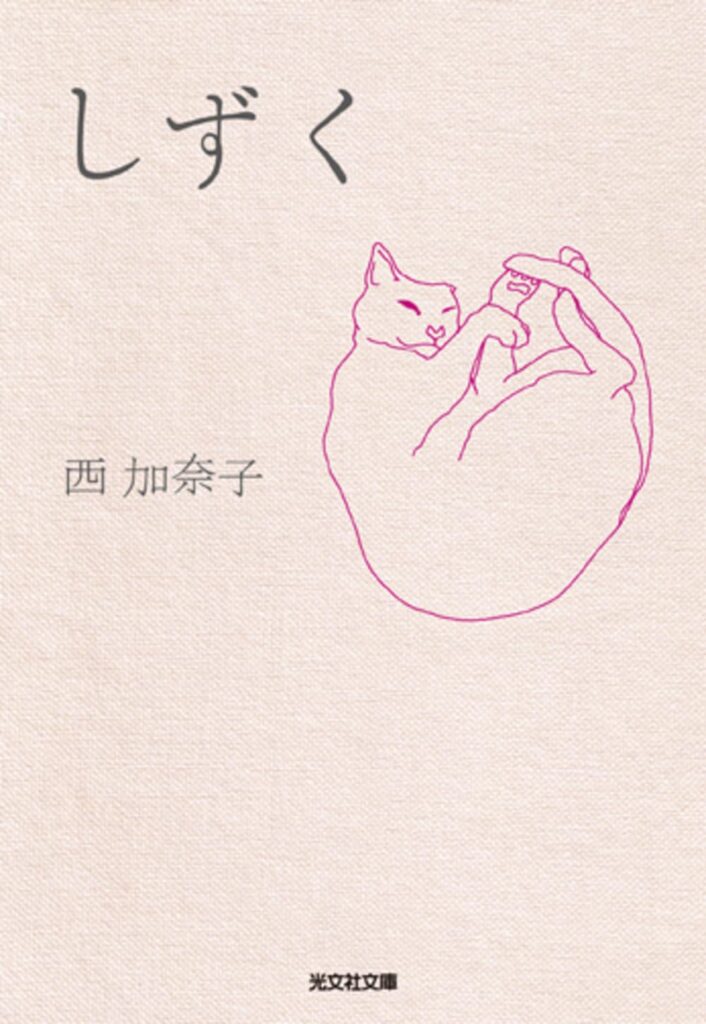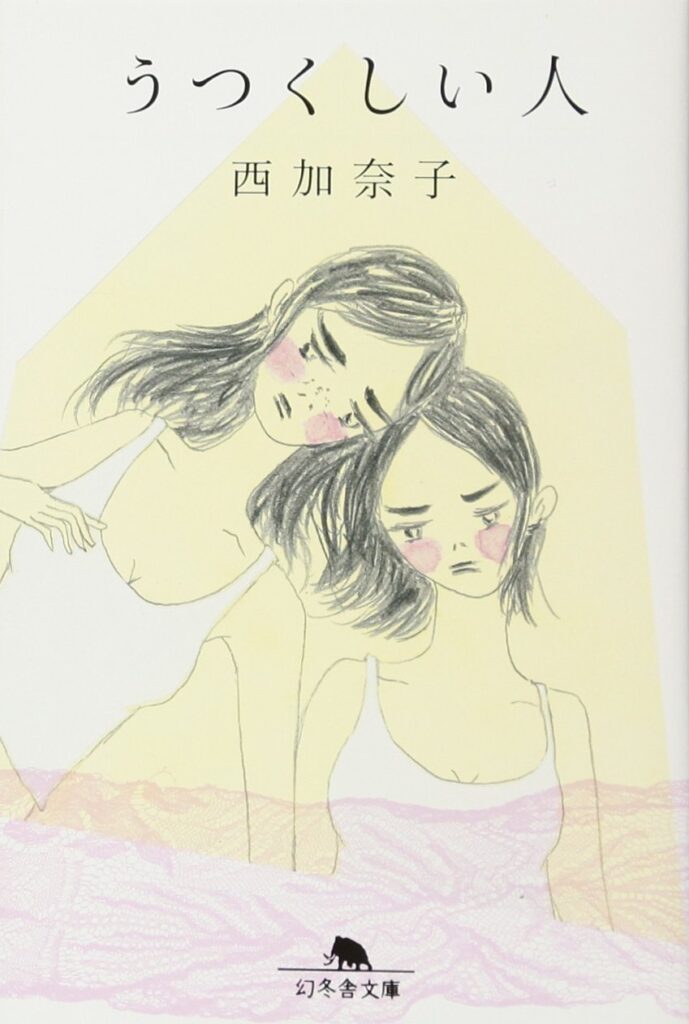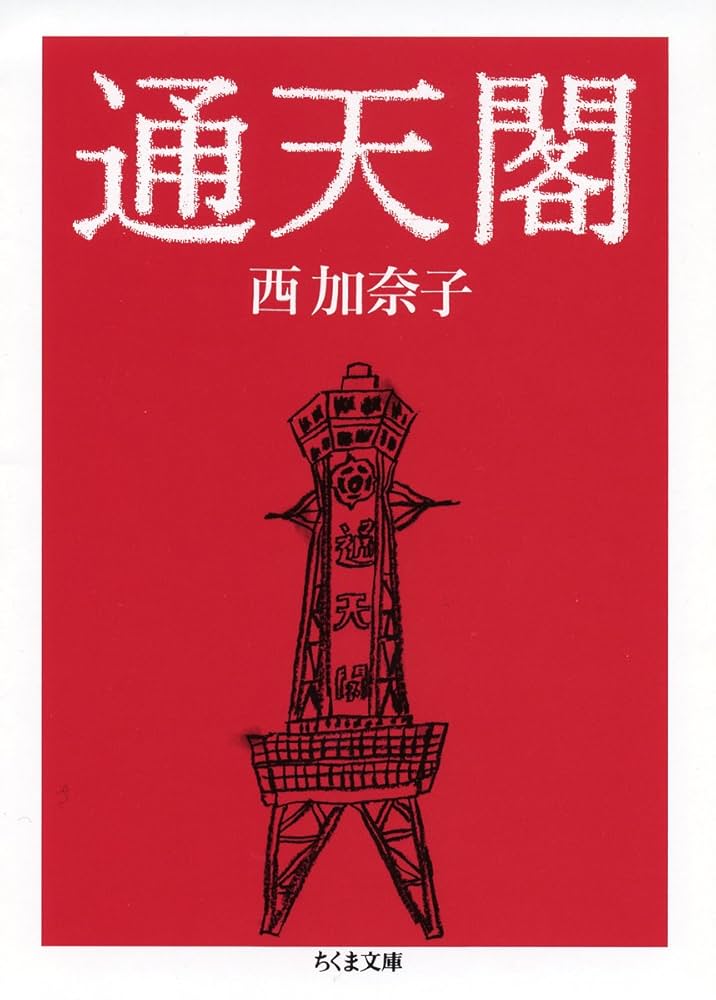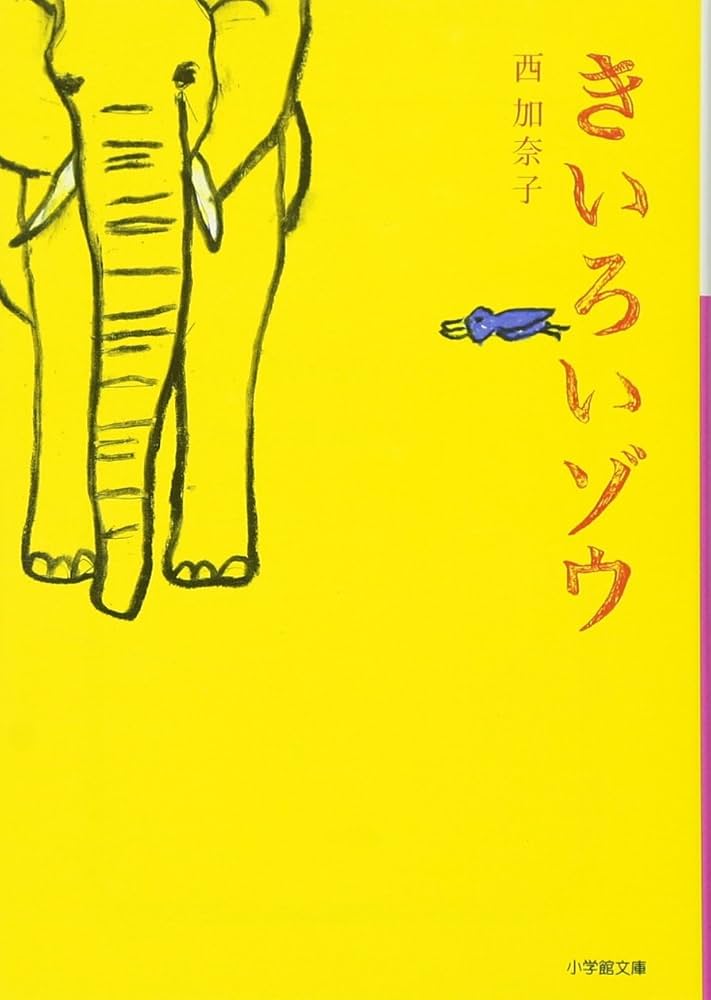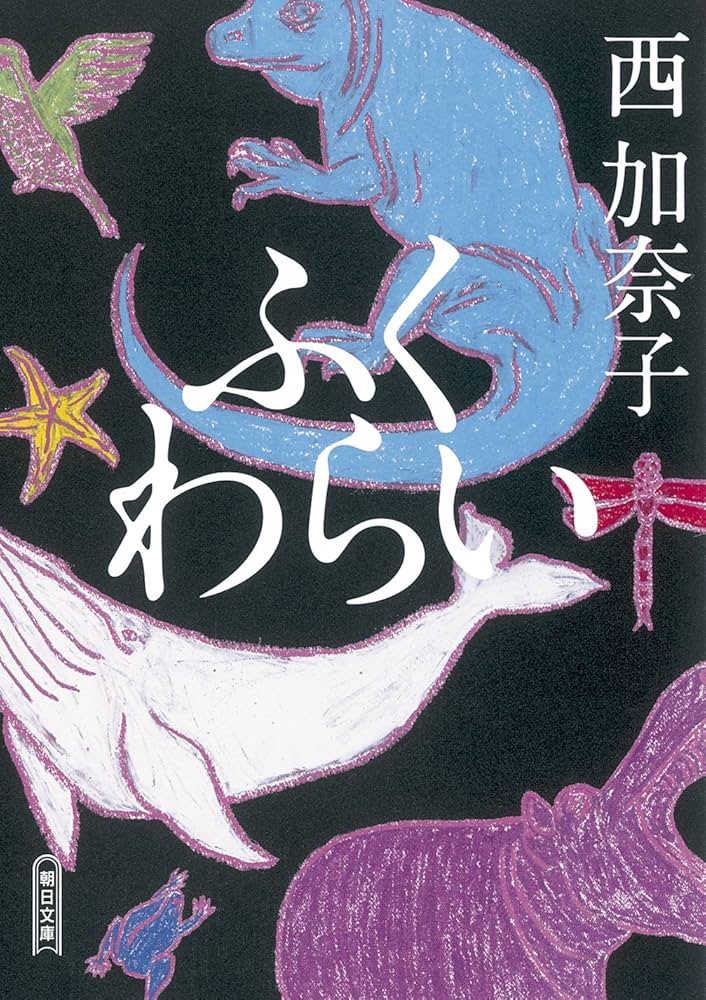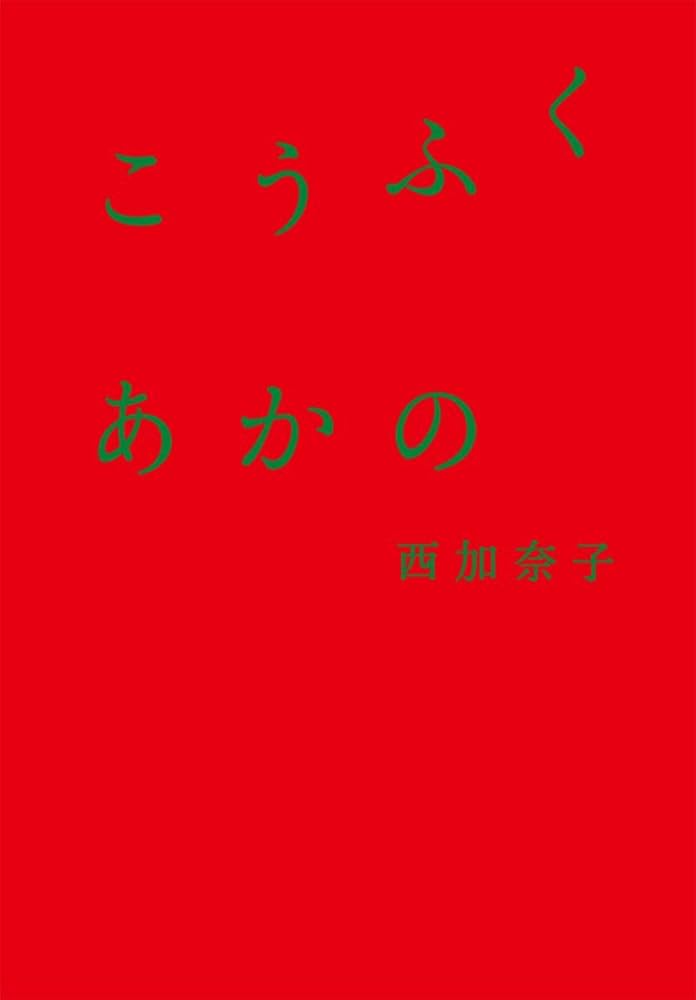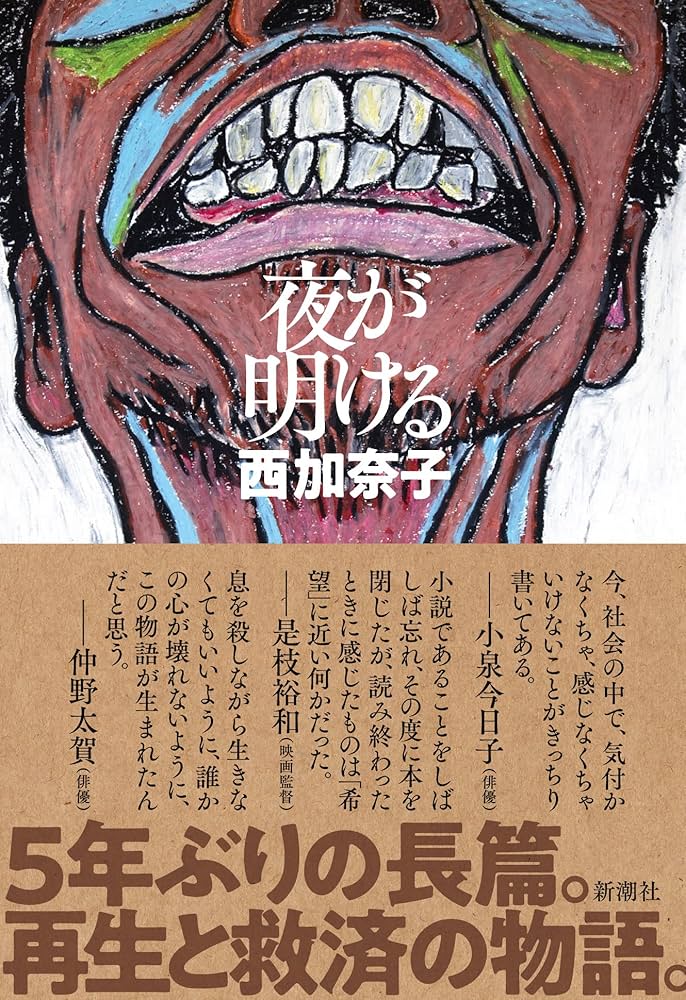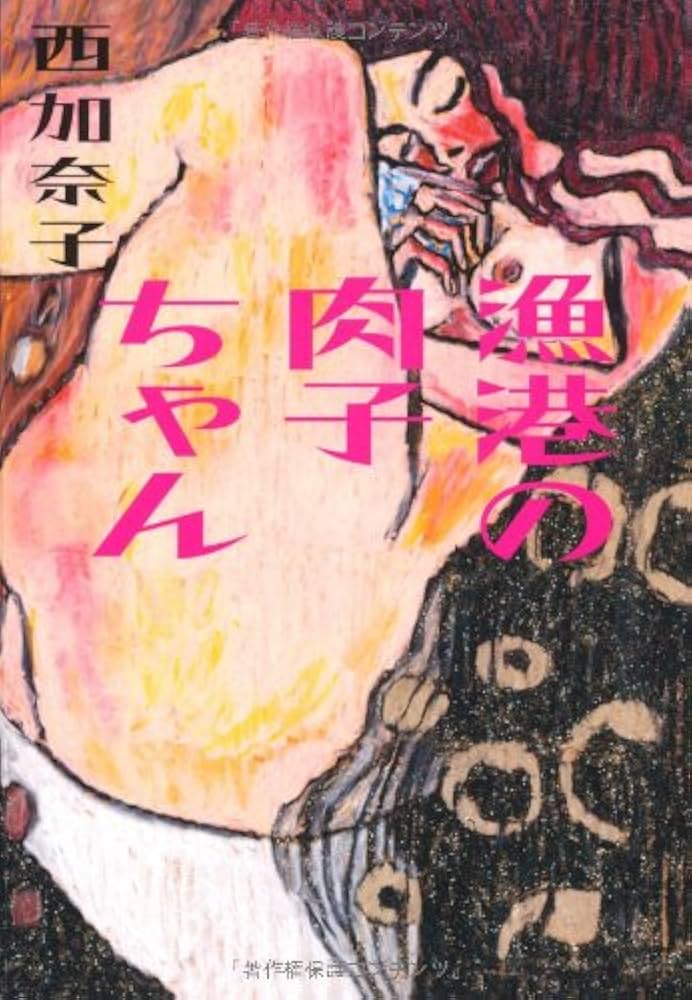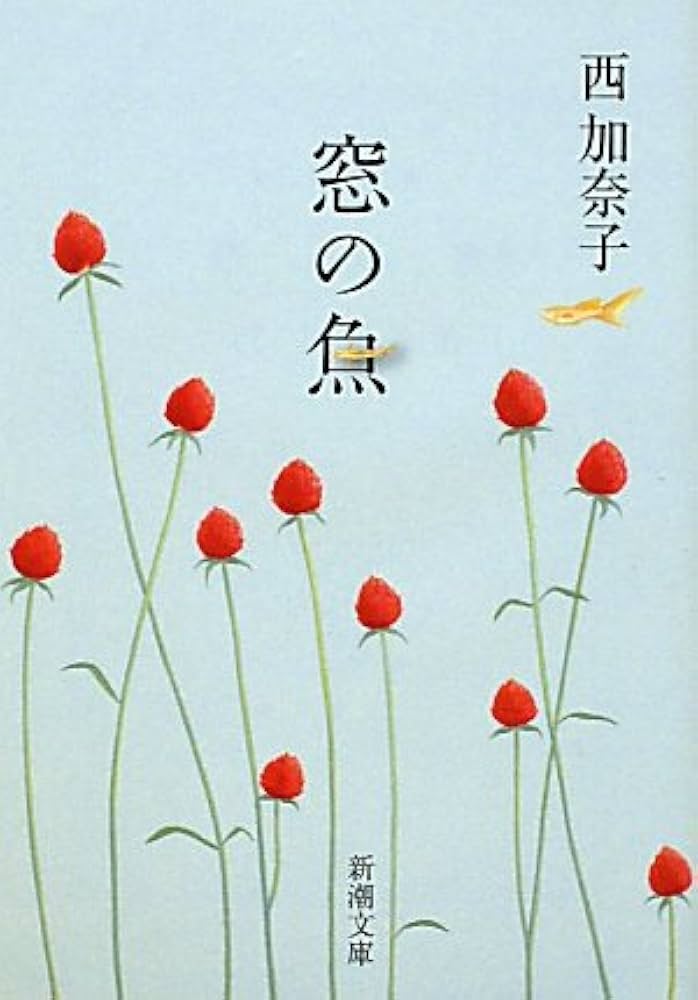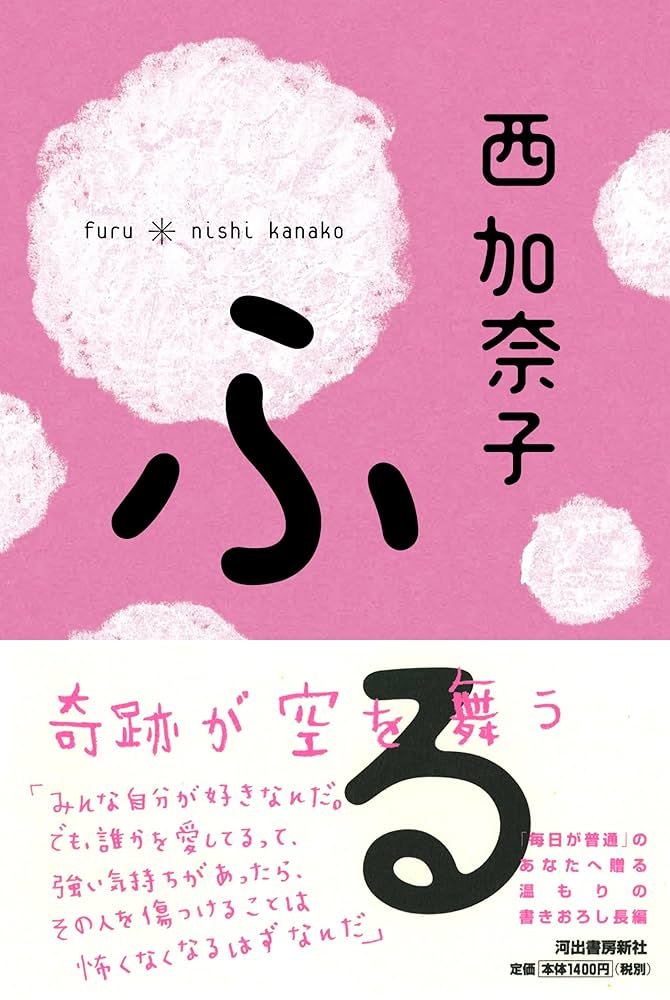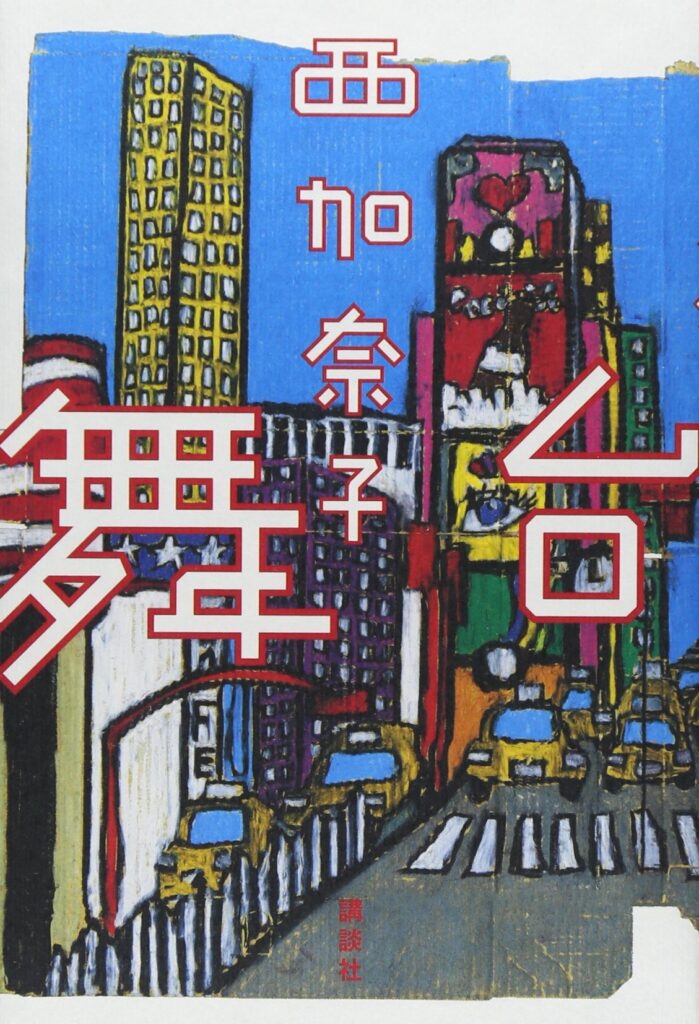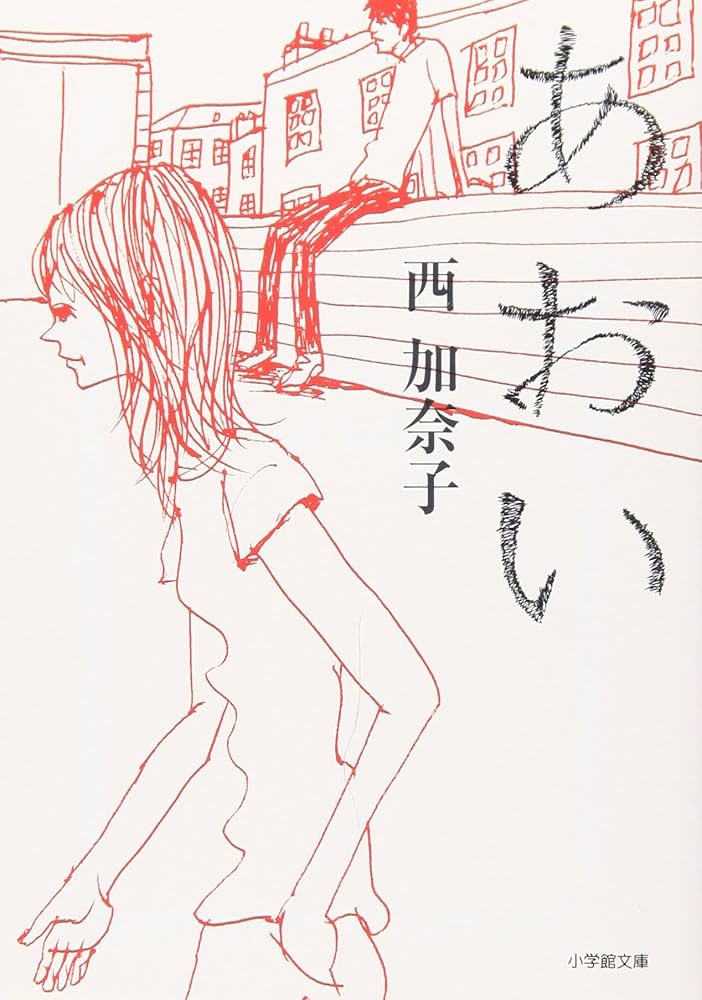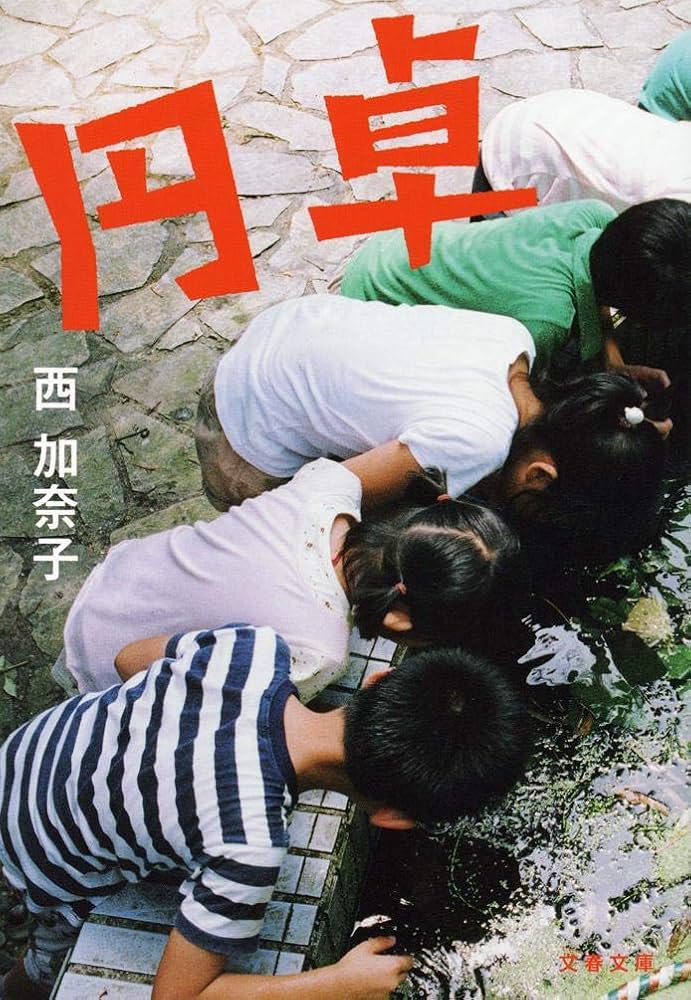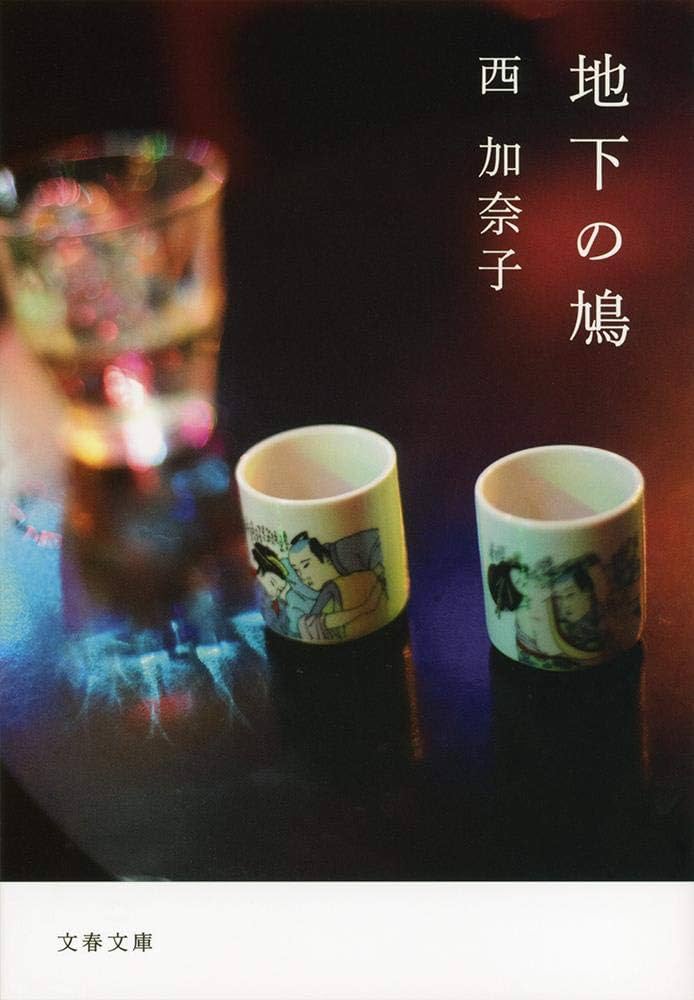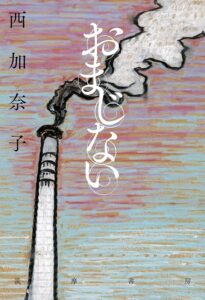 小説『おまじない』のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文での感想も綴っていますので、どうぞお楽しみください。
小説『おまじない』のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文での感想も綴っていますので、どうぞお楽しみください。
西加奈子さんの短編集『おまじない』は、2018年3月2日に筑摩書房から世に送り出されました。PR誌「ちくま」に連載された7編に、書き下ろし1編を加えた全8編で構成されています。特筆すべきは、作者自身が各短編のイラストまで手がけている点です。これは、西加奈子さんが小説執筆と絵画制作を並行して行うことを大切にしていることの表れで、『きいろいゾウ』以降、彼女の創作における重要な要素となっています。
本作は、2015年に直木賞を受賞した『サラバ!』や、2017年に本屋大賞7位に選ばれた『i』といった主要な長編作品を経て発表された待望の短編集であり、その刊行は文学界で大きな注目を集めました。この刊行時期は、『おまじない』が西加奈子さんが直木賞受賞作家としての地位を確立し、円熟期に入った後に書かれた作品であることを示唆しています。彼女が尊敬する作家である角田光代さんの「短編1000本ノック」という助言を受け、「息の長い作家になりたい」という思いから短編執筆を始めたという背景は、この短編集が単なる作品集に留まらず、自身の作家としての表現力を深めるための意図的な挑戦であったことを示しています。この背景は、本書のテーマやメッセージがより洗練され、凝縮された形で表現されている可能性を示しており、各「おまじない」の言葉が読者に与える影響がより強く設計されていると感じます。
また、西加奈子さん自身が各作品のイラストを手がけている点は、単なる装丁デザイン以上の意味合いを持っています。彼女は、小説と絵画を「良い振り子」として並行制作することを重視しており、言葉が持つ「決めつけすぎてしまう恐ろしさ」に対し、絵画は「受け手側に理解の自由度を残したい」という意図があることを明かしています。このことから、各短編のイラストは、物語の言葉だけでは伝えきれない感情の機微や、多義的な解釈の余地を視覚的に補完し、読者にさらなる内省を促す役割を担っていると考察できます。これは、『おまじない』が単なる文字情報だけでなく、視覚情報も統合した複合的な芸術作品として構築されていることを示唆していると私は考えます。
『おまじない』のあらすじ
『おまじない』は、少女、ファッションモデル、キャバ嬢、レズビアン、妊婦など、様々な人生を生きる「悩める女の子」たちが主人公の全8作の短編集です。これらの女性たちは、年齢や職業に関わらず「もろさを抱えた等身大の女性」として描かれ、読者が自身の経験と重ね合わせて共感しやすい普遍的な「生きづらさ」を抱えています。各物語には共通の構造が見られます。主人公が何らかの「生きづらさ」や「呪い」に直面し、そこに「おじさん」などの他者から何気ない、しかし本質を突く「おまじない」のような言葉が投げかけられることで、主人公が内面的な解放を経験し、自己肯定に至るというパターンです。
たとえば、「燃やす」の主人公は、綺麗で女性らしくあることを好む祖母と、がさつで鷹揚な母親という、異なる価値観の間で揺れ動く「私」です。母親の意に背いてスカートを履くようになった「私」は周囲から「可愛い」と言われるようになりますが、その直後にある性的な事件に巻き込まれてしまいます。この事件に対し、「私」は自分自身のせいであると思い込んでしまう(あるいはそう思い込まされる)葛藤を抱えていくのです。
「いちご」の主人公の「私」はファッションモデルとして東京で華やかな生活を送っています。一方、遠い親戚の浮ちゃんは、いちごに異常な愛情を寄せながら九州の田舎の村で一人暮らしをしており、「私」がモデルデビューした後も、芸能界や世事に全く興味を示さず、変わらない態度で接し続けてくれます。東京での華やかな世界と、自身の内面との乖離に悩む「私」の姿が描かれていくのです。
「マタニティ」の主人公は38歳の「私」で、交際相手との間に妊娠が判明します。喜ばしい出来事であるはずなのに、彼女の胸には数々のネガティブな感情が去来します。母親になることへの不安や、社会的に「禁忌」とされる「醜い考え」が赤裸々に綴られていく様子が描かれます。特に、妊婦に当然のように求められる「神聖さ」という、社会的な「呪縛」への鋭い問いかけがなされているのです。
『おまじない』の長文感想(ネタバレあり)
『おまじない』を読み終えた時、私の心には温かな光が灯り、まるで長い間抱えていた重荷がすっと軽くなったような感覚が残りました。西加奈子さんがこの短編集に込めた「すべての女の子を肯定したかった」という強い想いは、確かに私の心にも届きました。そして、「女の子らしさ」といった従来の性別に基づく価値観や、「こうしなければいけない」という社会的な期待や「呪縛」から心を解き放つことの重要性が、痛いほど伝わってきました。
私が特に印象に残ったのは、たとえかつて自分を救ってくれた言葉や、社会的に「正しい」とされている価値観であっても、それが自分にとってしっくりこなくなり、しんどさを感じるようになったら、それらと距離を置き、「捨てていい」という作者のメッセージです。その「呪い」を解いた先にこそ、「あなただけの言葉や感情に出会える」という言葉は、私たちが日々直面する多様な価値観の中で、真に自分らしく生きるための道標を示してくれているように感じました。かっこいい「王子さま」のような他者からの評価によって自己肯定を得るのではなく、本質的に自分で自分を認めることの重要性が繰り返し強調されている点は、現代社会において多くの人が悩むであろう自己肯定感の問題に対し、深く優しい問いかけをしているように思えてなりません。
西加奈子さんが提唱する「自己肯定」は、単にポジティブ思考を促すものではないと感じました。それは、自分を「しんどくさせているもの、心を縛っているもの」を特定し、それらが「呪い」であると認識し、積極的に「解除」するプロセスを含んでいます。この「呪いの解除」は、社会的な規範(「女の子らしさ」や「聖母的母親像」など)や、過去の経験から生じる自己否定といった、内面化された抑圧からの解放を意味しているのでしょう。このプロセスを通じて、登場人物たちは「自分らしさ」を取り戻し、自分自身をまるごと肯定できるようになります。これは、自己肯定が受動的な状態ではなく、能動的な自己変革の過程であることを明確に示していると感じます。
「こうしなければいけない」という社会の「呪い」を解くという西加奈子さんの創作意図は、現代社会における多様な価値観の肯定と、個人の自由な選択の尊重という点で、極めて重要な意義を持つものだと私は考えます。特に、フェミニズムのムーブメントが活発化する中で、「異議申し立ての内容がいつも必ずしも『全て正しい』わけでもない」という西加奈子さんの視点は、新たな規範がまた別の「呪い」とならないよう、常に個人の内面的な自由を優先すべきだという警鐘を鳴らしているように思えました。この作品は、読者に対し、既存の価値観を盲目的に受け入れるのではなく、常に自身の心に問いかけ、必要であれば「別の言葉で上書きしていく」ことの重要性を強く訴えかけているのです。
『おまじない』の中で特に印象的だったのは、主人公の「悩める女の子」たちに「おまじない」の言葉を贈るのが、多くの場合、社会の主流から少し逸脱した「はぐれ者、変わり者のおじさん」たちであるという点です。彼らは、一般的な「金言」や「王子さま」のような理想的な存在とは異なり、独自の価値観や生き方を持つ人物として描かれています。例えば、「いちご」の「いちご狂」の浮ちゃん、「孫係」のおじいちゃま、「あねご」のさえないモリさんなどが挙げられます。
西加奈子さんがこのような「はぐれ者のおじさん」たちを救済の担い手として描くことは、真の救いや本質的な気づきが、意外な場所や人物から生まれるという彼女の人間観を深く反映していると感じます。社会の周縁にいる彼らは、凝り固まった価値観に囚われず、主人公たちが抱える「呪い」を異なる視点から解き放つ力を持っています。彼らの言葉は、表面的な問題解決ではなく、主人公の内面に深く作用し、自己認識の変容を促します。これは、人間関係における「多様性」の重要性を示しており、異なる背景を持つ人々との交流が、自己の視野を広げ、新たな自己肯定へと繋がる可能性を提示していると言えるでしょう。
この作品における「おじさん」たちの存在は、単なる物語の装置に留まっていません。彼らは、社会が押し付ける「男性像」にも囚われず、弱さや不器用さをも肯定する存在として描かれています。西加奈子さんは、「この作品は女性だけではなく、これから年を重ねていく人も含め、未来のおじさんも救う物語でもある」と語っており、性別や年齢を超えて、誰もが抱える「生きづらさ」に対する普遍的な救済のメッセージを込めているのです。彼らの言葉は、読者にとっても、他者からの評価に依存せず、自分自身の内なる声に耳を傾けることの重要性を教えてくれます。
文学的技法という観点から見ると、『おまじない』は8つの独立した短編からなる連作短編集という構造が見事に機能していると感じます。各短編はそれぞれ異なる主人公と状況を描きながらも、共通して主人公が何らかの「生きづらさ」や「呪い」に直面し、そこへ他者から「おまじない」のような言葉が贈られ、内面的な解放に至るというパターンを繰り返します。この構造は、読者が各物語に深く没入しつつも、全体を通して「言葉の力」というテーマが多角的に提示されることで、その普遍性と多様性を実感できるよう、細部にわたって設計されているように思えてなりません。
読者からは、「短編なのに長編みたいに濃い世界観が広がった作品」、「8つの長編を読めるような“ぜいたく”な1冊」といった評価が寄せられており、個々の短編が持つ密度の高さが特筆されます。これは、西加奈子さんが「短編1000本ノック」という自身の作家としての挑戦を通じて、短い物語の中に深いテーマと感情を凝縮させる技法を磨いた結果であると考えられます。各物語は独立していながらも、全体として「あなたを救ってくれる言葉が、この世界にありますように」というメッセージを強固に提示し、読者に温かなエネルギーを流し込む効果を生み出しているのです。
西加奈子さんの文体は、「平易で読みやすく親しみやすい」と評される一方で、「豊かな文学性、そのレヴェルの高さに正直驚かされた」という評価も受けているように、私も感じました。読者が「身近な仲間たちの語りを愉しむかのような気軽さ」で読める一方で、その奥には「人生そのものを俯瞰するような奥深さ」が潜んでいます。
特に本作では、「これまでの西さんの文章とは違って“全てを書かない強さ”を感じました」という指摘があり、より洗練され、余白を持たせた表現が特徴的です。これは、読者に想像の余地を与え、物語の言葉だけでは伝えきれない「声にならない声」を描くことに成功していることを示唆しています。例えば、「まるで知らない人から急に牛糞をプレゼントされたみたいな顔」といったユニークで具体的な比喩表現は、読者に強烈なイメージを喚起させ、感情的な共感を深く引き出します。
西加奈子さんの文体は、読者の感情に直接訴えかける力を持っています。「西さんの紡ぐ物語は、優しい。生きてゆくことの辛さとか苦さとか痛さとか全部ひっくるめて、ふところ深い大きなものに包まれてる温かさを感じる」といった感想は、彼女の言葉が読者の心に深く響き、慰めと励ましを与えることを示しています。この「力強くて優しくて、読み終わった後は頑張ろうって気持ちにさせてくれる」文体は、読者が自身の「生きづらさ」を肯定し、前向きな気持ちになるための「心のお薬」として機能していると感じます。
『おまじない』では、抽象的な感情や心の状態を、読者が共感しやすい具体的な象徴や比喩を用いて表現する技法が効果的に用いられています。例えば、「燃やす」における「燃やす」という行為は、単なる物理的な行為を超え、過去の傷や自己否定を浄化し、新たな自己へと生まれ変わるための強力な儀式を象徴していると感じました。
「生きづらさ」を「呪い」と比喩的に表現し、それを解く「おまじない」のような言葉が「温かなエネルギー」として読者にも流れ込むという表現は、言葉が持つ癒しの力や、内面的な変化を視覚的・感覚的に表現しています。また、「焚き火に手をかざすみたいに心がほわっとする短編集」という読者の感想は、作品が読者の心に与える温かさや安らぎを、具体的な感覚として表現していると言えるでしょう。さらに、「一番星」というイメージは、希望や心の拠り所を象徴していると考えられます。
「いちご」の浮ちゃんが「固定観念をぶん回してぶん投げてくれるような快感」という比喩は、「固定観念」という抽象的な概念を、物理的な行動に例えることで、その解放感や爽快感を強調しています。これは、言葉が持つ破壊と創造の力をイメージさせる比喩であり、読者が自身の内なる「呪い」から解放される感覚を追体験できるよう促しているのです。これらの象徴的・比喩的な表現は、読者が物語の登場人物の感情に深く入り込み、自身の経験と重ね合わせることを可能にし、結果として「救われた」「励まされた」といった強い感情的な反応を引き出していると、強く感じました。
『おまじない』は、批評家や読者から非常に高い評価を受けています。詩人の文月悠光は、本書が「誰かの言葉に縛られる絶望を、誰かの言葉に守られる希望に変えていける力強さ」を告げていると評価しています。元「ダ・ヴィンチ」編集長の横里隆は、『サラバ!』や『i』といった長編小説の経験を経て、「密度の濃い、一段レベルが上の世界基準の作品になっている」と述べています。
書店員からの評価も高く、紀伊國屋書店新宿本店の今井麻夕美は、社会の理不尽に直面した際に「おまじない」が「女の子」に寄り添い、「小説を信じていてよかった」という気持ちになったと語り、「私の基準は私」という西加奈子さんのメッセージがより濃くなっていると評価しています。三省堂書店の内田剛は、「非常に密度の濃い短編集」であり、「男と女、生と死、善と悪、光と影といった対極にある要素を明確に意識させ、それらを乗り越えてありのままの自分を見出す圧倒的なパワーを感じた」と絶賛し、「悩み多き現代社会に必要とされる作品」と位置づけています。
読者からの反応も非常に肯定的であり、「ねるちゃんきっかけで手に取った本だけど、とても素敵な内容でどの話もどこか共感できるような、いつかに経験したことがあるような気持ちを思い出させてくれた」、「私たちにとってもおまじないになる言葉だと思う」といった声が多数寄せられています。特に「孫係」は読者からの人気が高く、「自分も周囲に求められている役割を演じながら生活している部分がある」と共感する声が多く見られます。また、「燃やす」の「私が可愛いことは、悪くなかった」や、「ドラゴン・スープレックス」の「お前がお前やと思うお前が、そのお前だけがお前やねん」といった言葉が、読者の心に深く刺さり、自己肯定や自由への道を示したという感想が多数報告されています。
『おまじない』自体が特定の文学賞を受賞したという記述は確認できませんが、西加奈子さん自身は『通天閣』で織田作之助賞(2007年)、『ふくわらい』で河合隼雄物語賞(2013年)、『サラバ!』で直木三十五賞(2015年)を受賞しており、その文学的評価は確立されていると言えるでしょう。
『おまじない』は、西加奈子さんのこれまでの作品群、特に『サラバ!』や『i』といった長編作品で追求してきたテーマを、短編という形式でより凝縮し、深化させた作品として位置づけられます。彼女の作品に通底する「生きづらさを抱えたすべての人たちへの、優しい視線」は本作でも健在であり、「不器用でも、前向きじゃなくたっていいんだよ、あなたらしく生きていることに意味があるんだから」というメッセージが強く打ち出されています。
本作は、西加奈子さんの初期の作品である『通天閣』が持つ「パワフルさ」や「作風」に通じる部分があるとも評されています。これは、彼女の作家としての表現が、初期の情熱的な作風と、長編を経て培われた洗練された深みを融合させていることを示唆しています。また、西加奈子さんが小説執筆と並行して絵画制作を重視し、自身の絵画を装画に用いることで、言葉だけでは伝えきれない感情や多義性を表現しようとしている点も、彼女の創作活動全体における『おまじない』の統合的な位置づけを示していると言えるでしょう。彼女は、小説と絵画を「良い振り子」として捉え、表現者としての「ラッキー」であると語っています。
現代日本文学において、『おまじない』は、多様な価値観の肯定、自己肯定の重要性、そして社会の規範にとらわれない個人の自由な選択を促す作品として、その意義を確立していると私は強く感じます。特に、既存の価値観を問い直し、読者自身が「別の言葉で上書き」していくことを促す姿勢は、現代社会における個人の内面的な変化と成長に焦点を当てた作品として意義深いと考えます。この作品は、性別や年齢、社会的立場に関わらず、誰もが抱える「呪い」から解放され、自分らしく生きるための「おまじない」を見つけることの重要性を力強く訴えかけています。その普遍的なテーマと、読者の心に深く寄り添う語り口は、現代の「生きづらさ」を抱える多くの人々にとって、確かな救いと希望となるでしょう。
まとめ
西加奈子さんの短編集『おまじない』は、現代社会に潜む見えない「呪い」と、それらを解き放つ「おまじない」の力を多角的に描いた、深く示唆に富む作品です。全8編の物語は、それぞれ異なる背景を持つ女性たちの「生きづらさ」を丁寧に描き出しながら、他者の何気ない、しかし本質を突く言葉によって内面的な解放と自己肯定へと至る普遍的なプロセスを示しています。
本作の核心には、「言葉の力」というテーマが据えられています。言葉は時に人を縛り、傷つける「呪い」となりうる一方で、同時に心を温め、救済をもたらす「祝福」となる両義性が綿密に描かれています。西加奈子さん自身が言葉の持つ「決めつけすぎてしまう恐ろしさ」を認識し、読者の自由な解釈を尊重する姿勢は、作家としての深い倫理観に基づいていると感じました。
また、社会の規範や期待に囚われず、自己を肯定し、自由に生きることの重要性が繰り返し強調されています。特に、「女の子らしさ」や「母性神話」といった既存の価値観が個人を縛る「呪い」となりうることを問題視し、たとえ善意から生まれた言葉であっても、それが不自由をもたらすならば「捨てていい」というラディカルなメッセージが提示されています。この「呪いの解除」のプロセスは、自己肯定が受動的な状態ではなく、能動的な自己変革の過程であることを示唆していると私は考えます。
さらに、社会の周縁にいる「はぐれ者のおじさん」たちが、主人公たちに真の救済の言葉を与えるという設定は、西加奈子さんの作品に共通する人間観を強化しています。彼らは、一般的な成功や規範から外れた視点を提供することで、主人公たちが自己の本質を見出し、凝り固まった価値観を打ち破るきっかけとなります。これは、真の共感と救済が、意外な場所や人物から生まれるという、多様性を肯定する作者の姿勢を反映していると言えるでしょう。
『おまじない』は、性別や年齢、社会的立場に関わらず、誰もが抱える「呪い」から解放され、自分らしく生きるための「おまじない」を見つけることの重要性を力強く訴えかけています。その普遍的なテーマと、読者の心に深く寄り添う語り口は、現代の「生きづらさ」を抱える多くの人々にとって、確かな救いと希望となるでしょう。