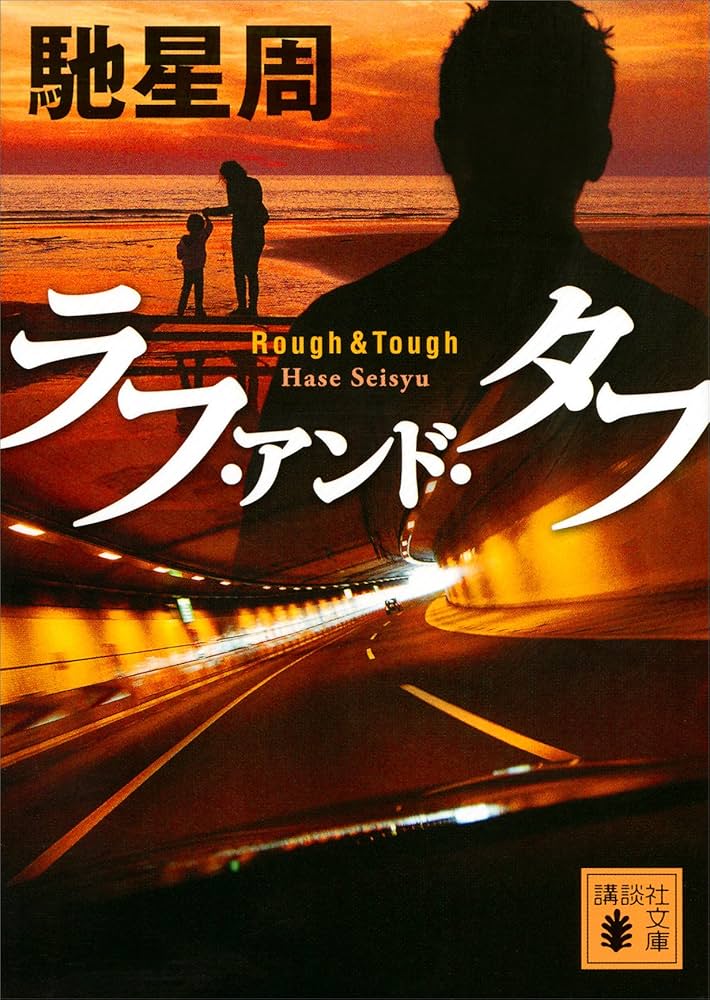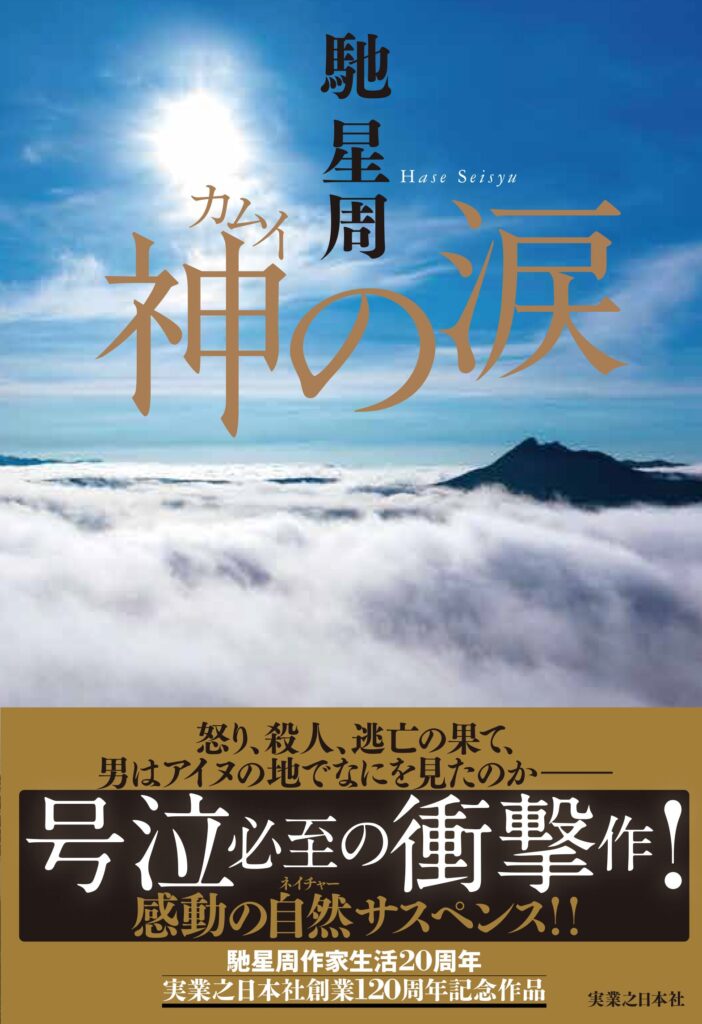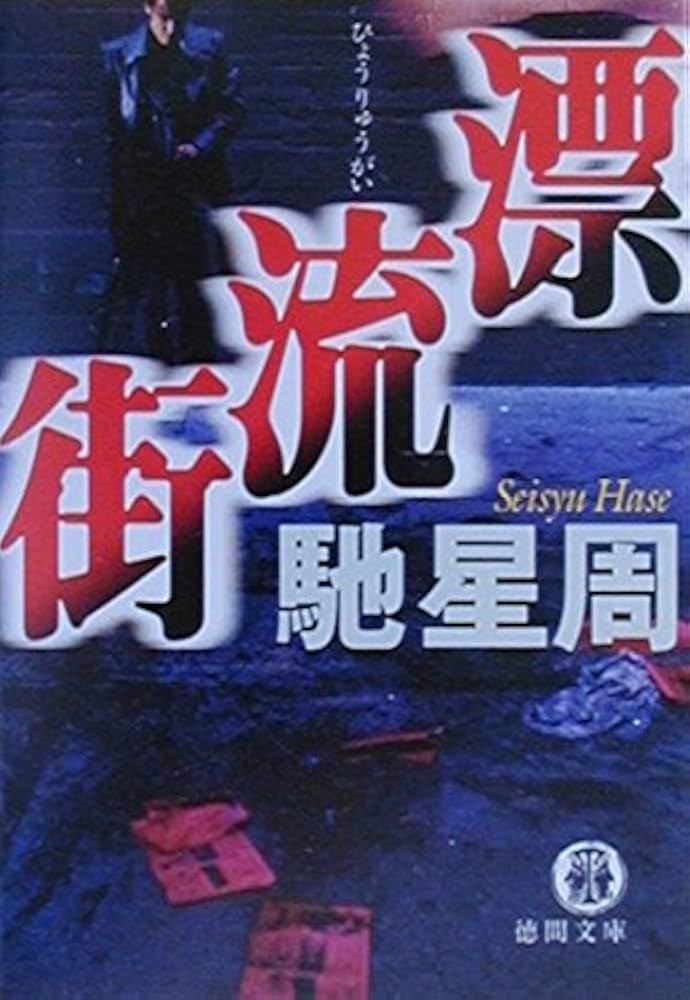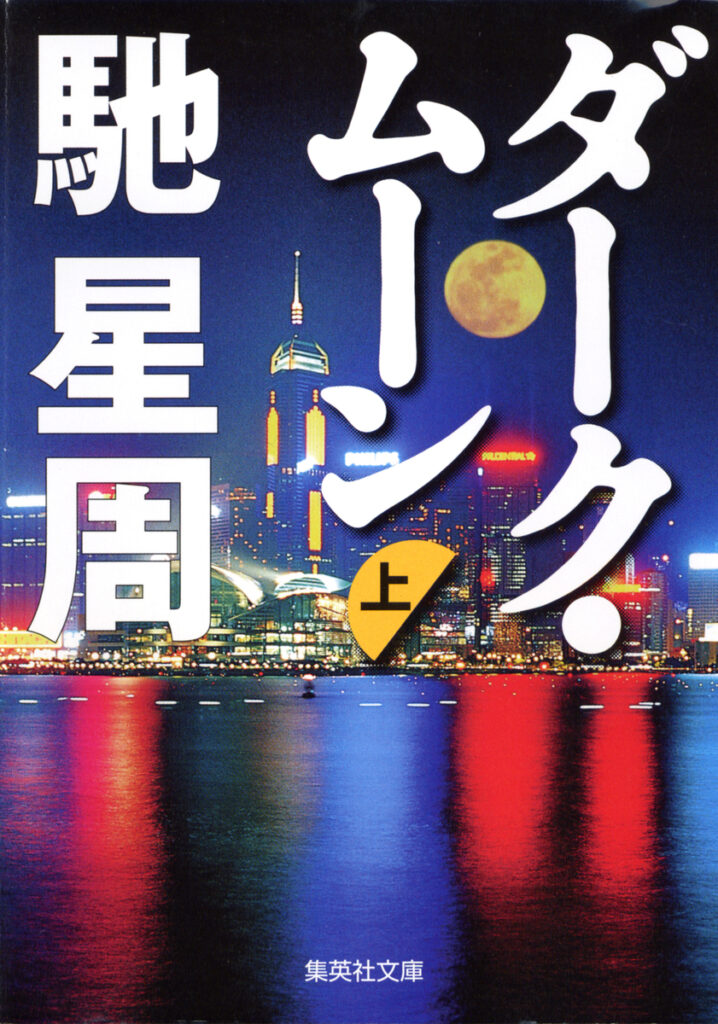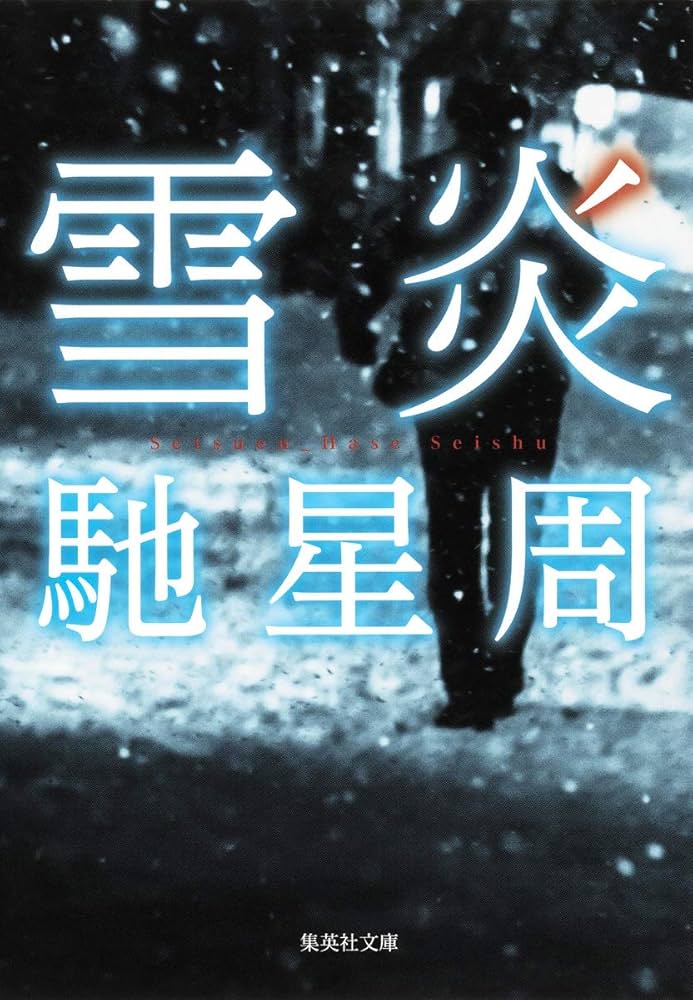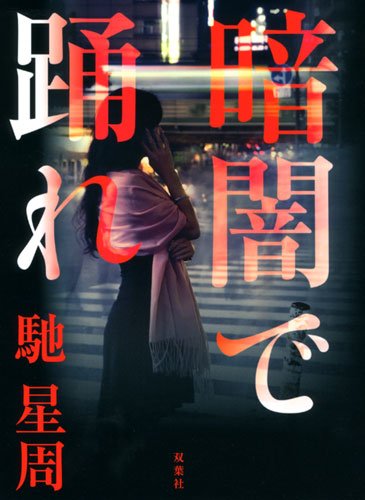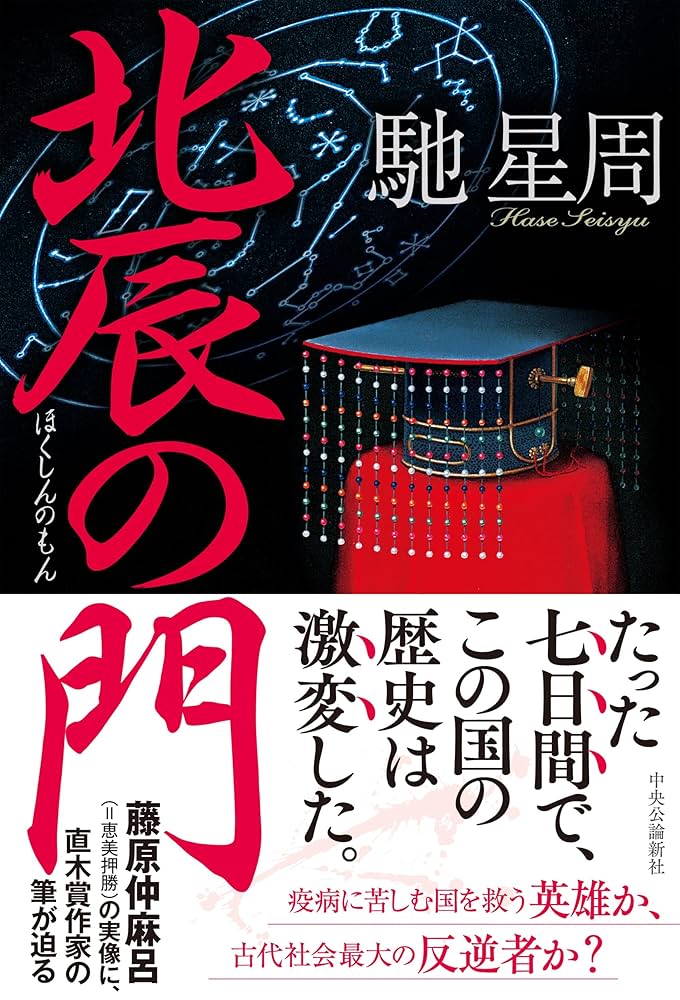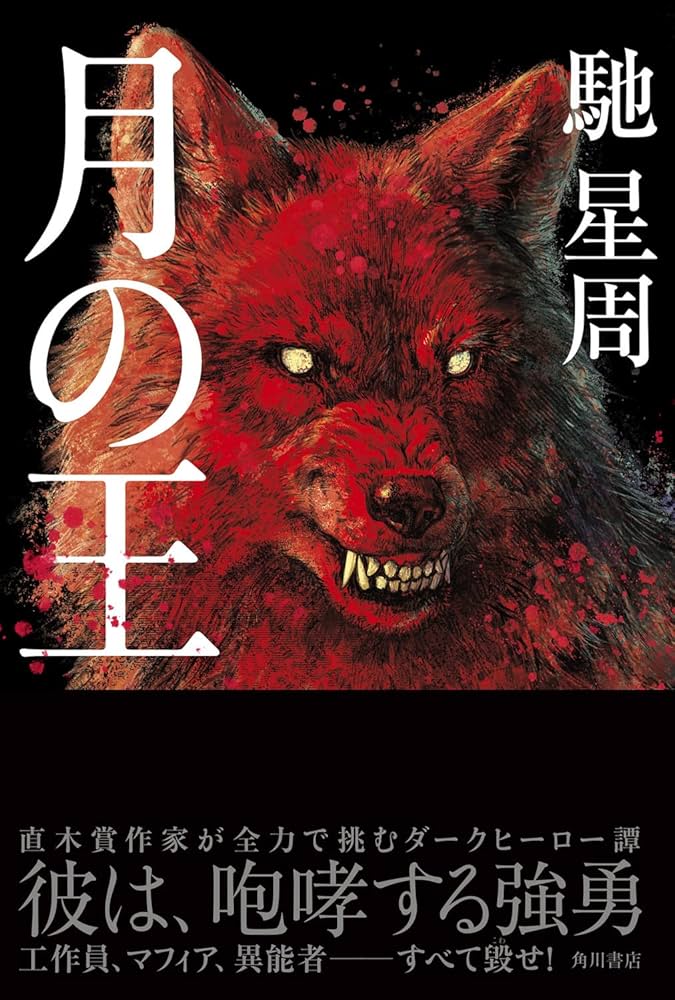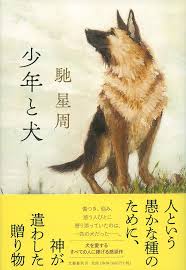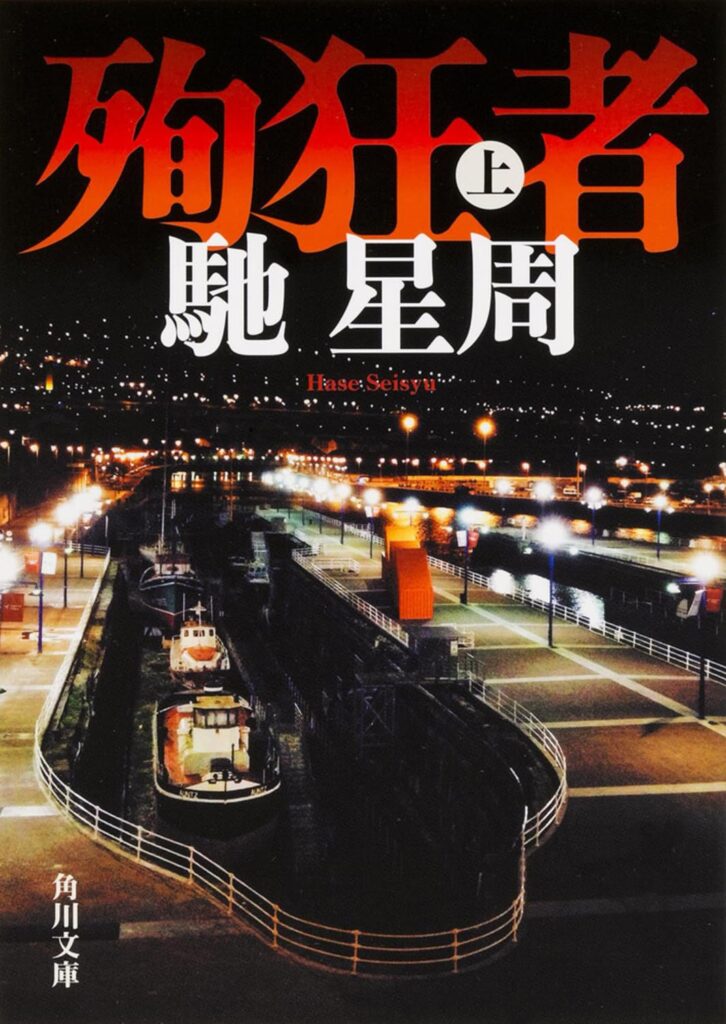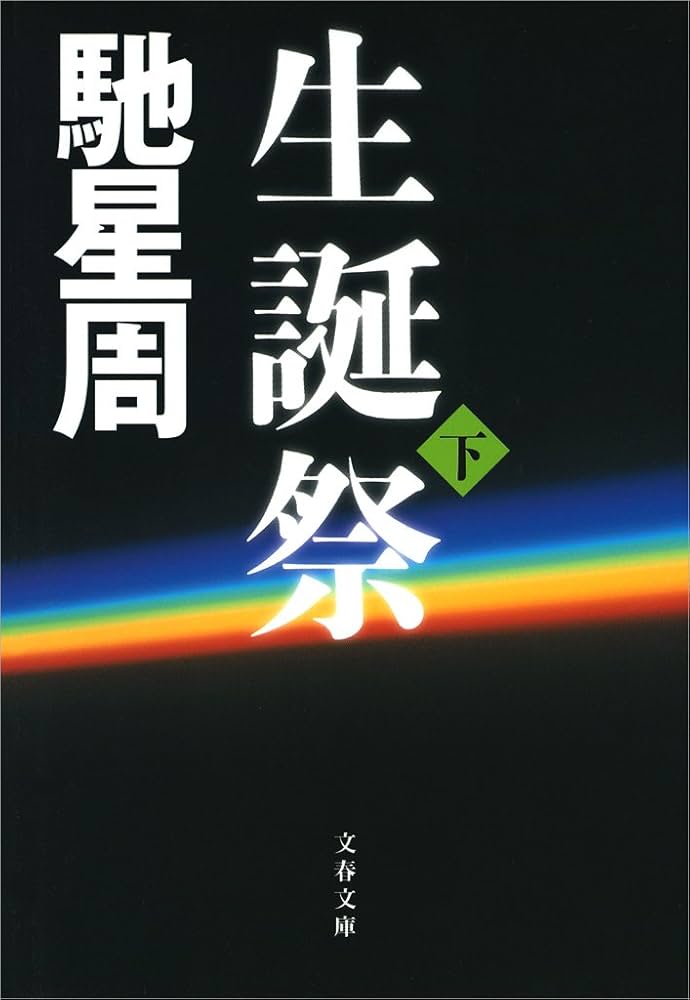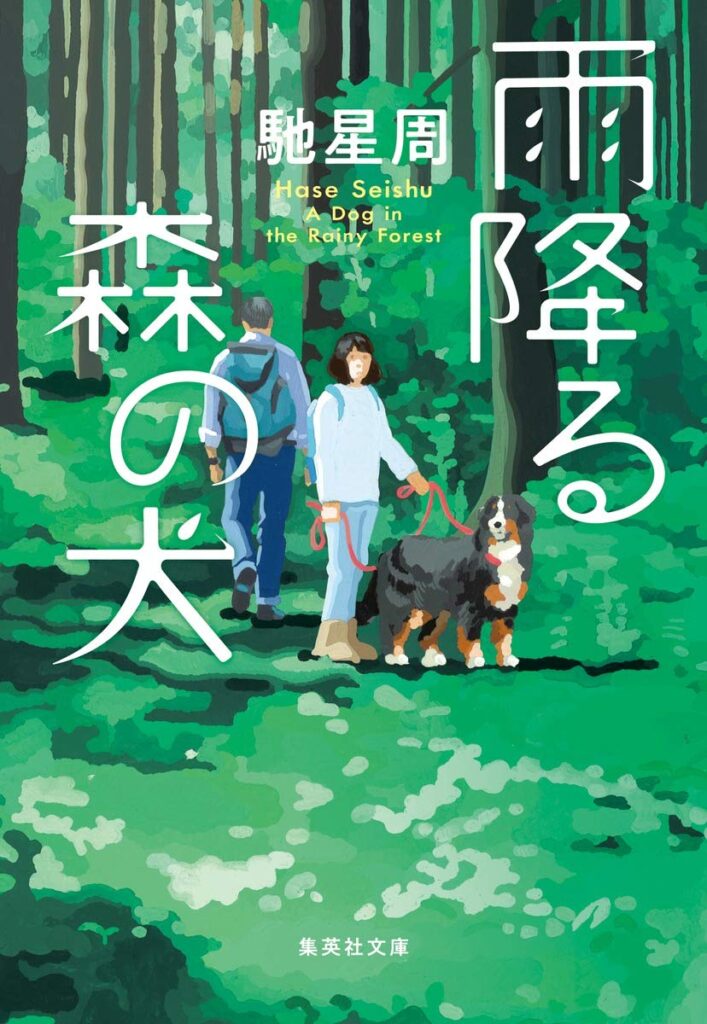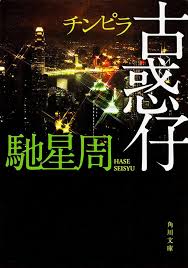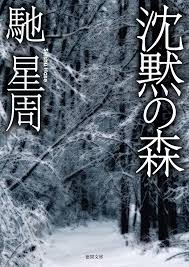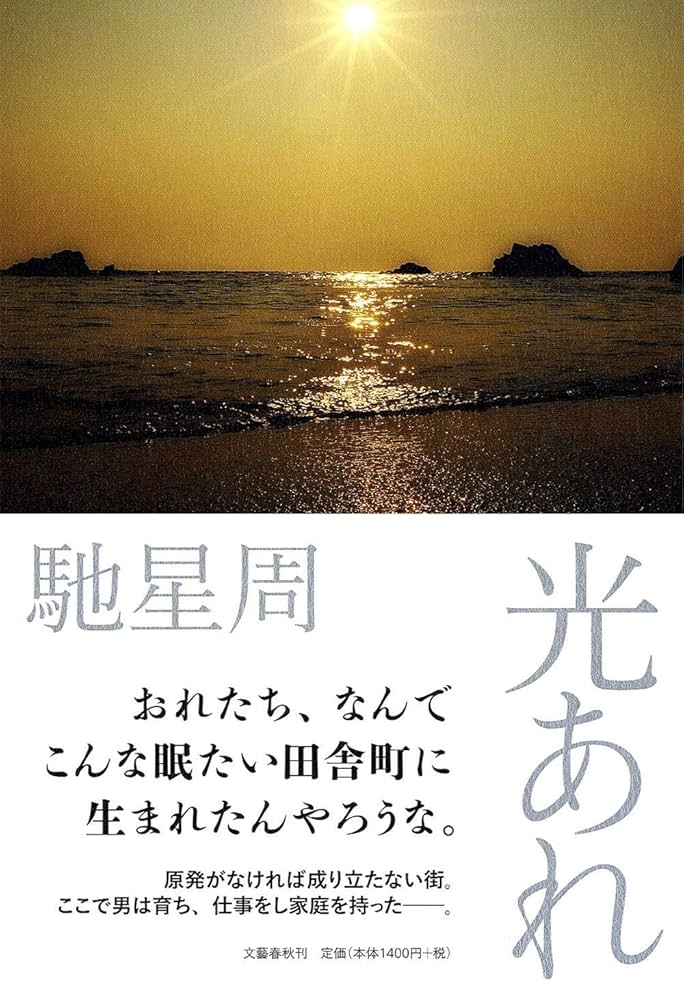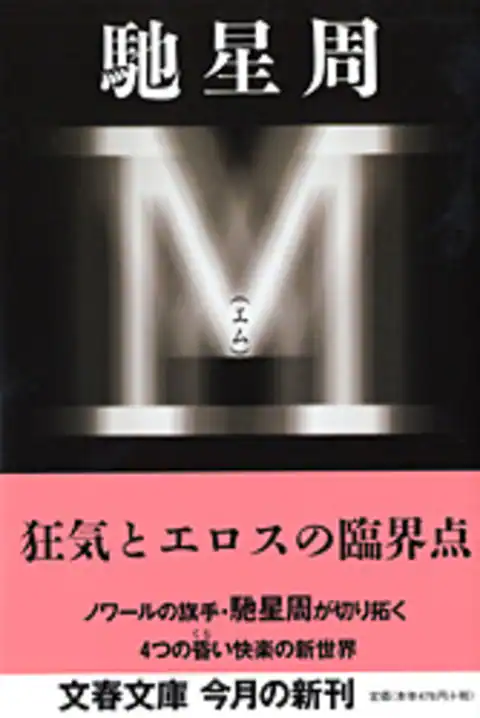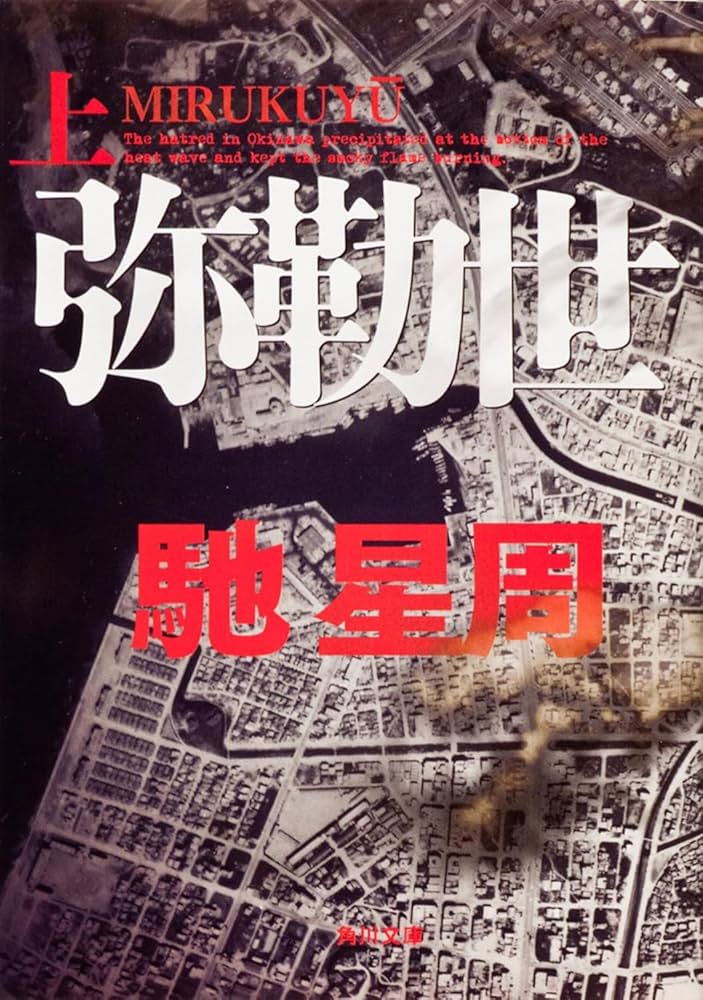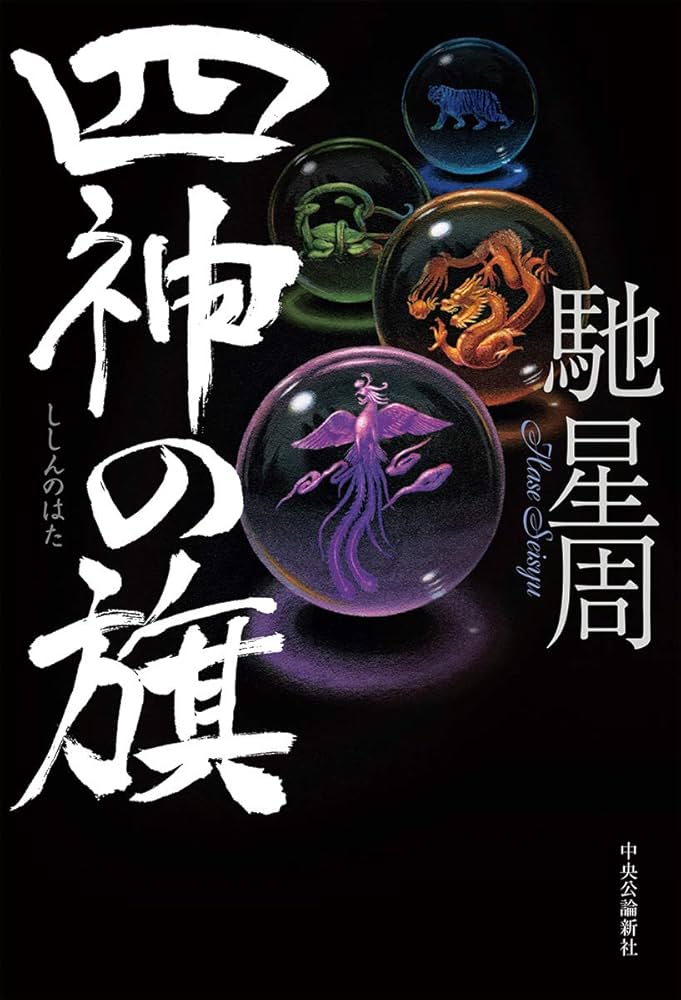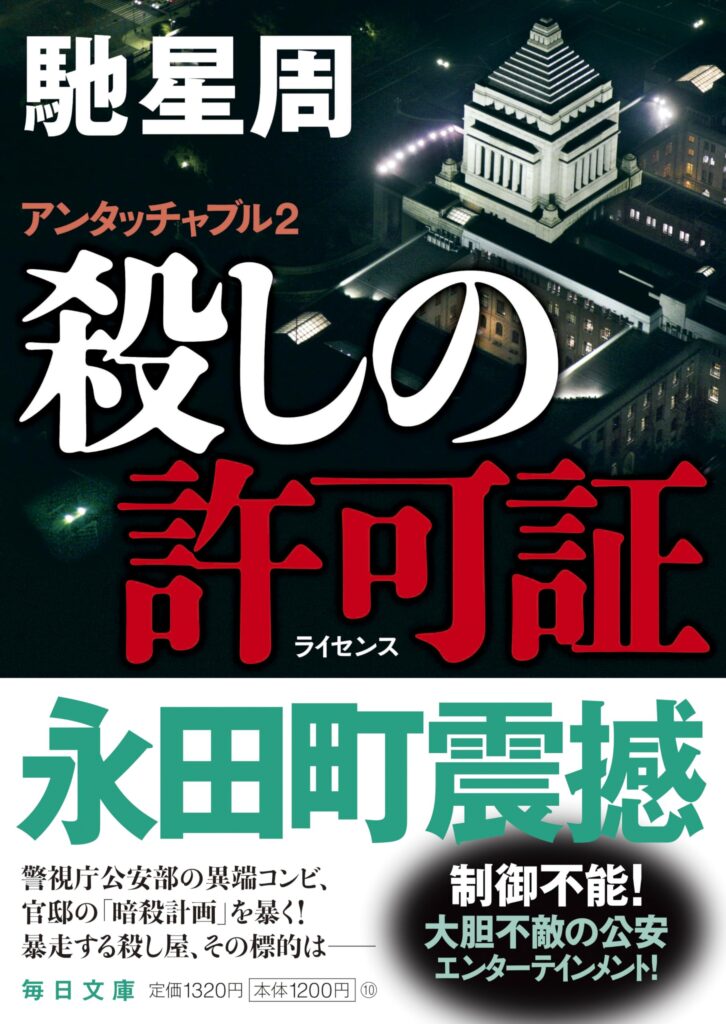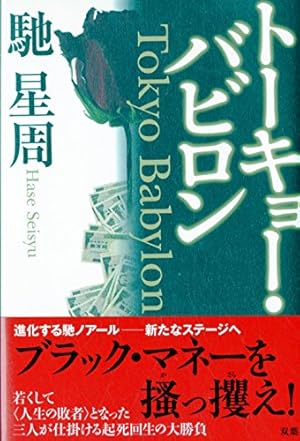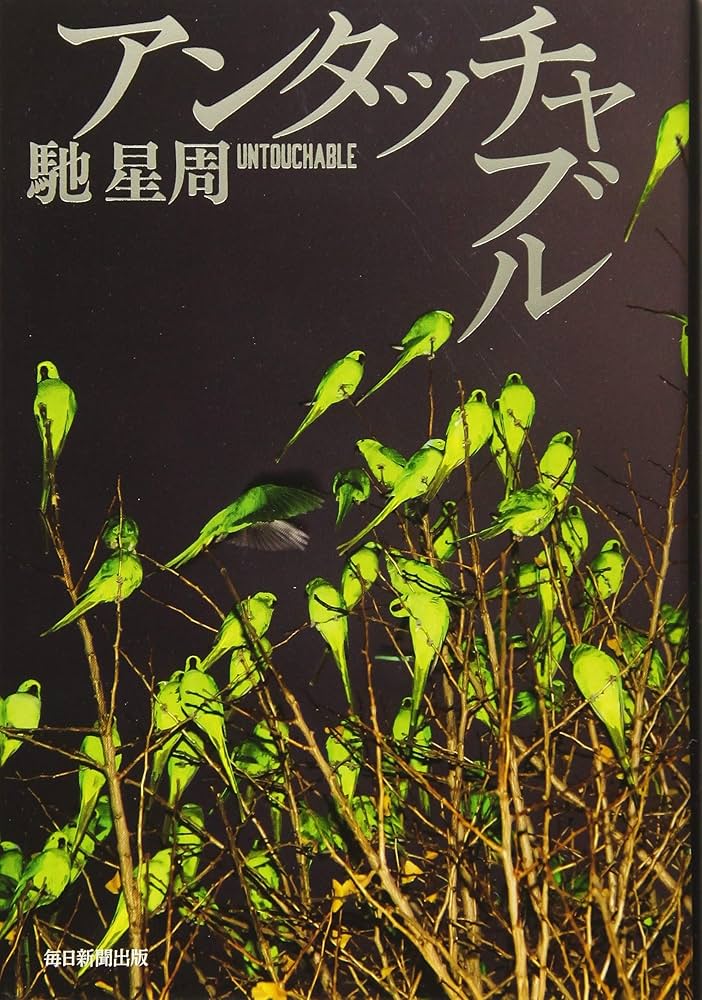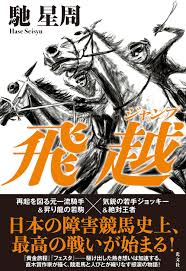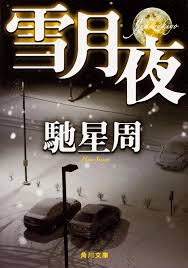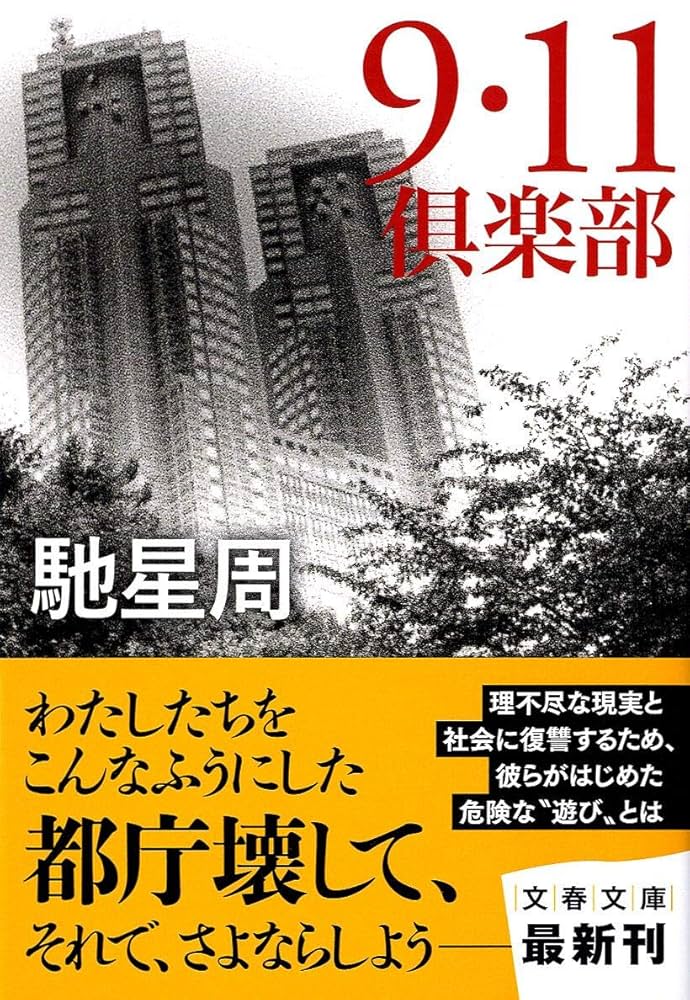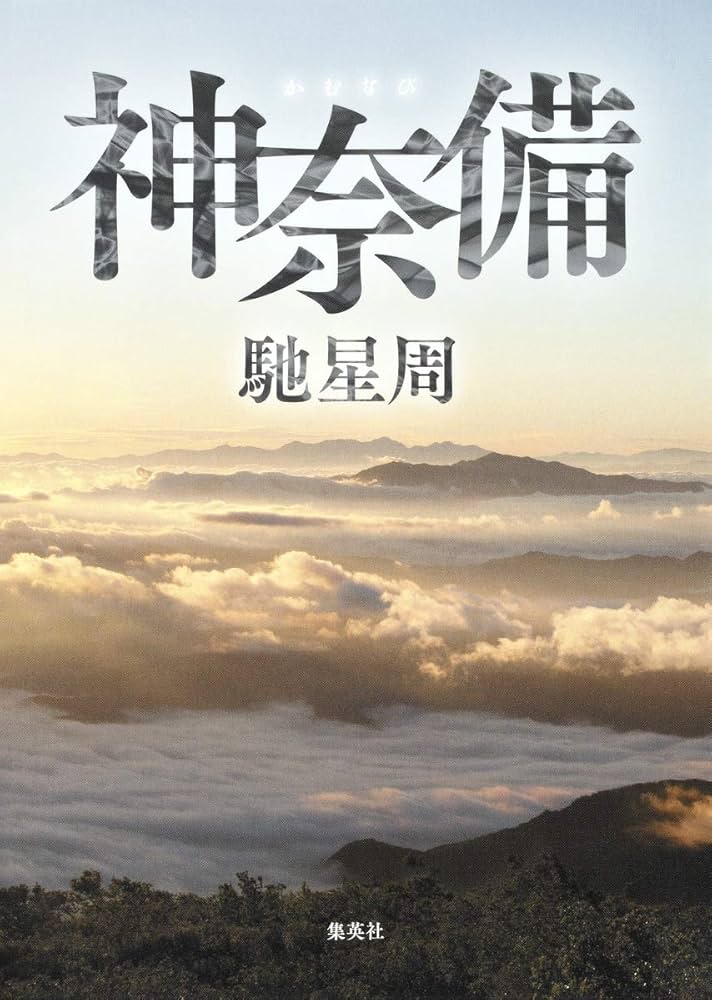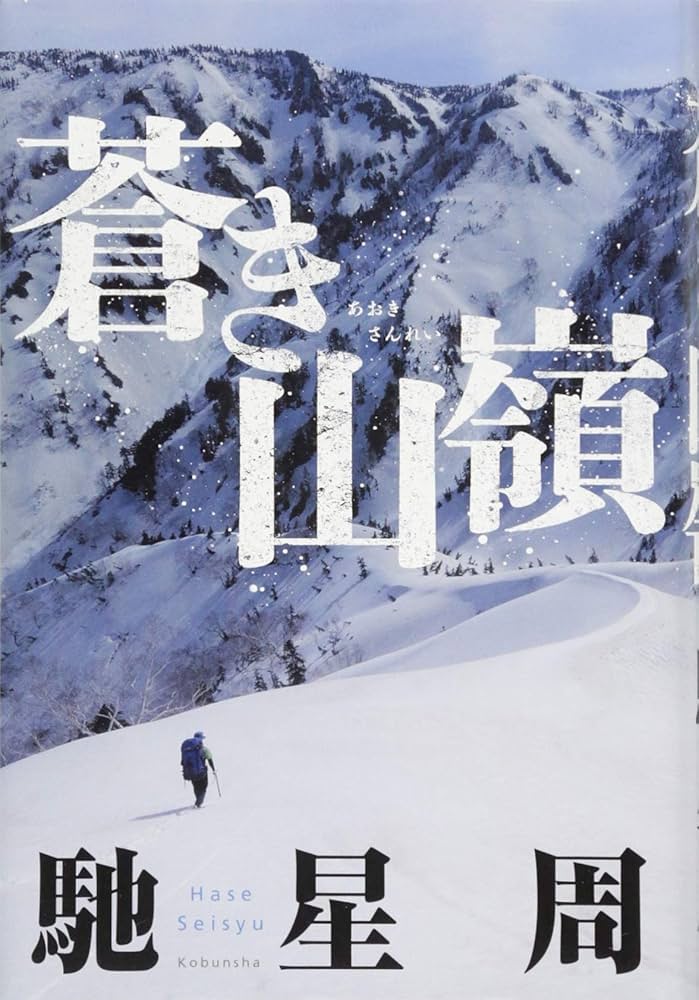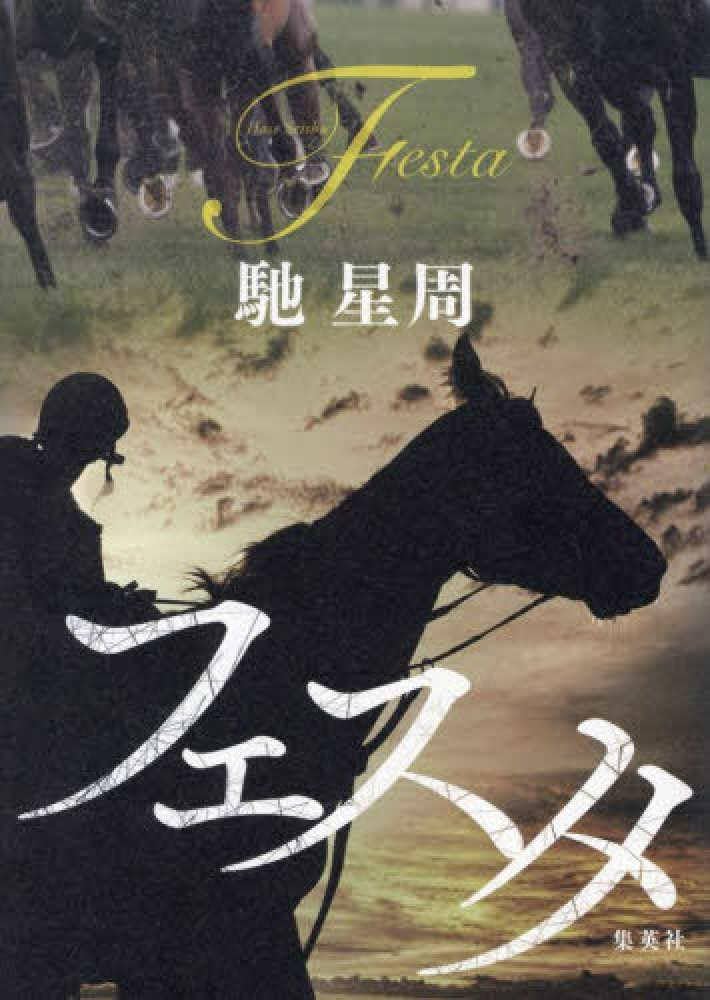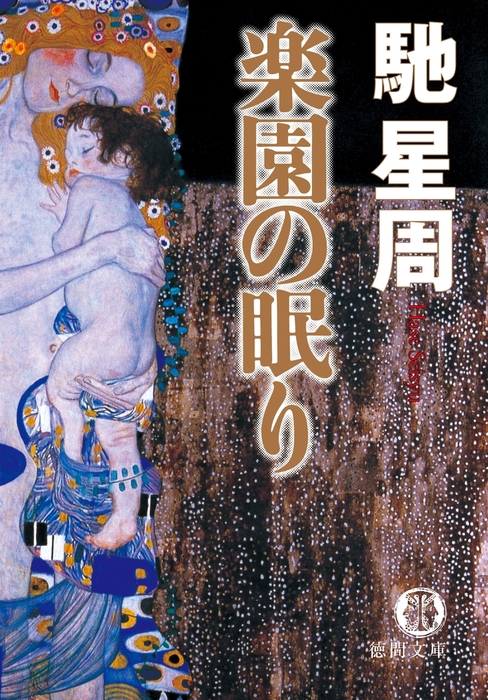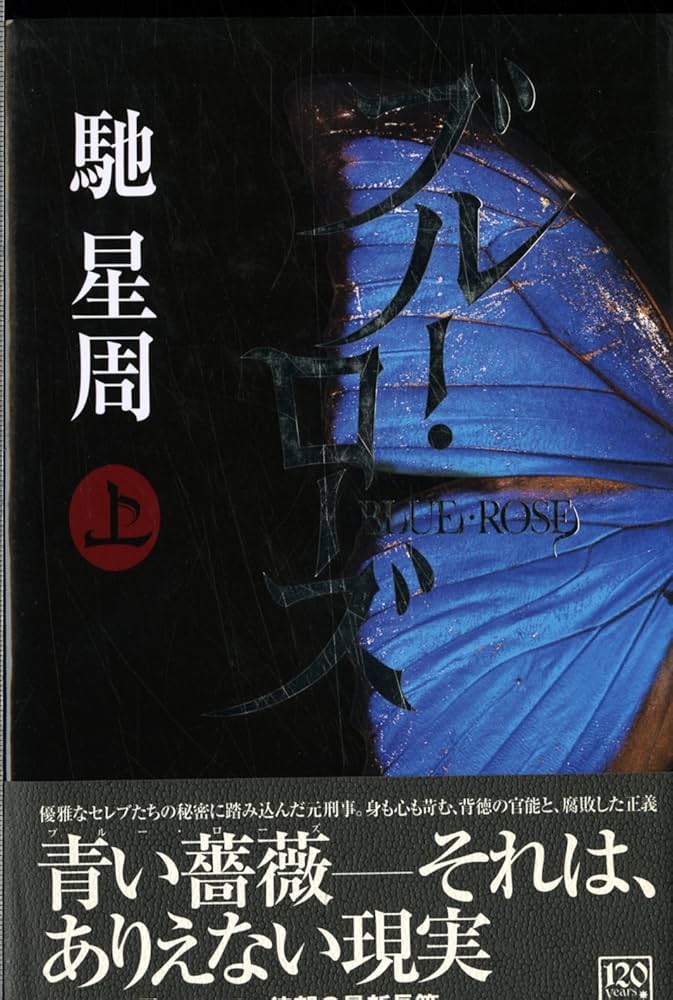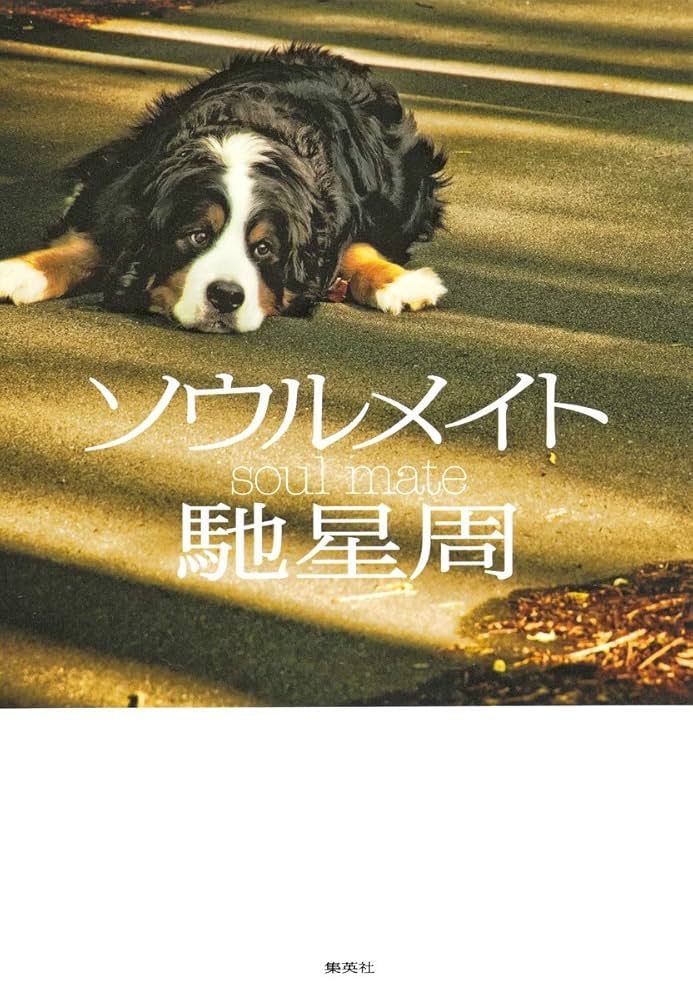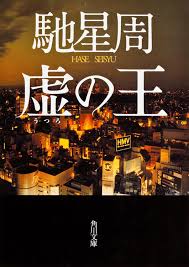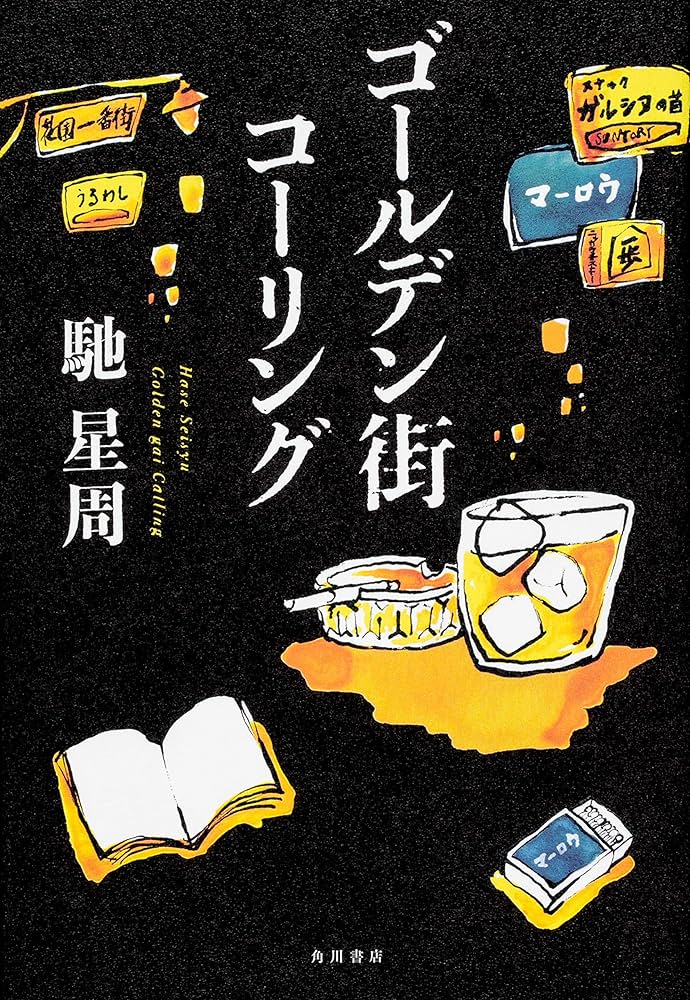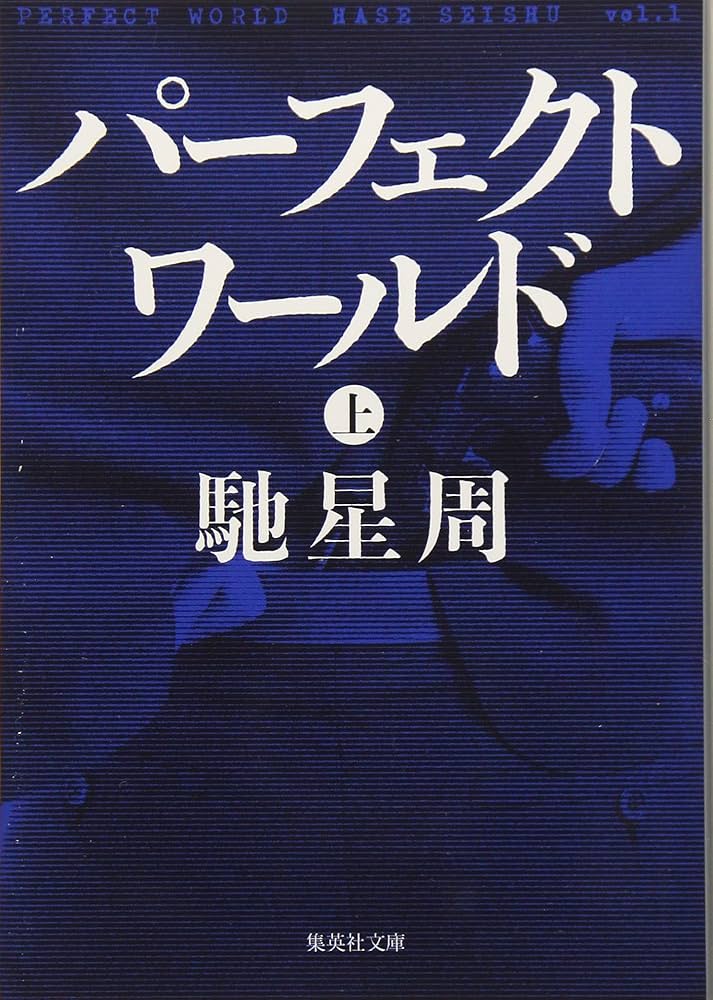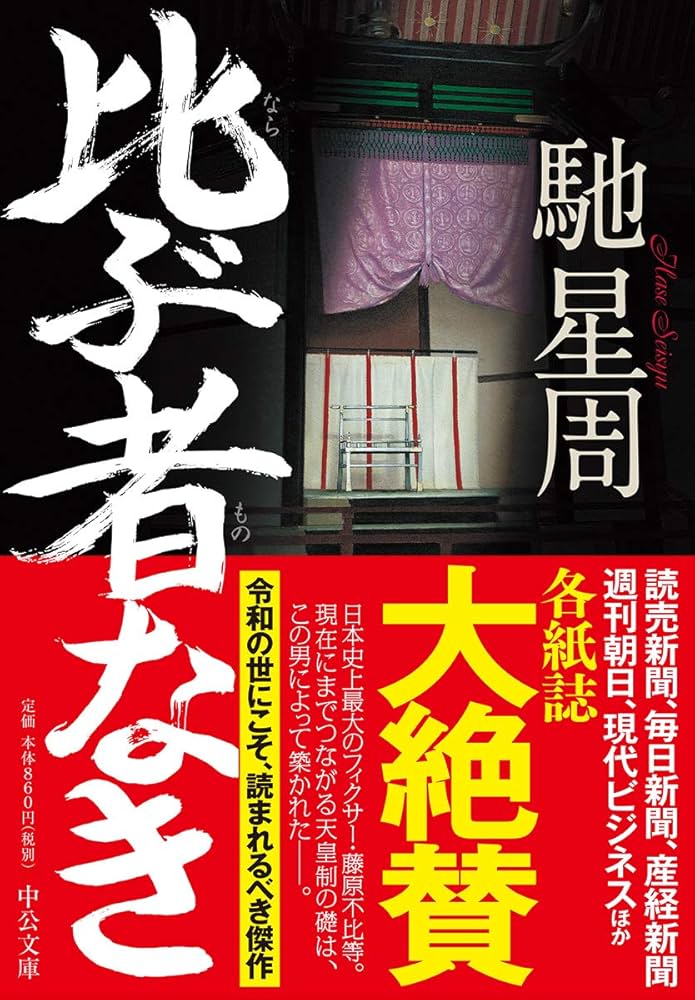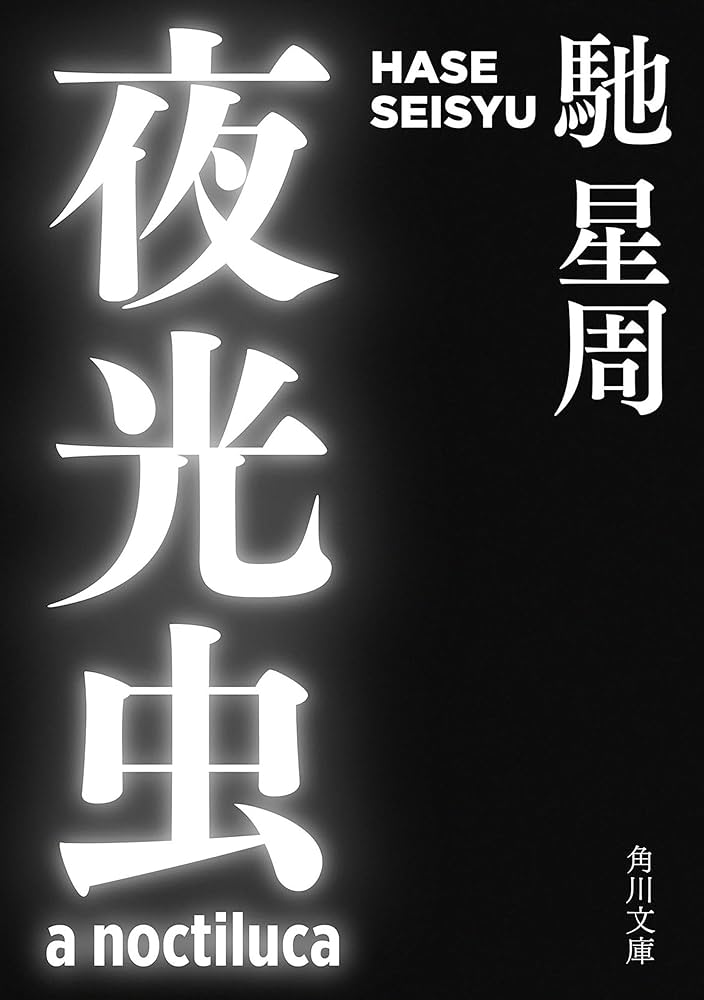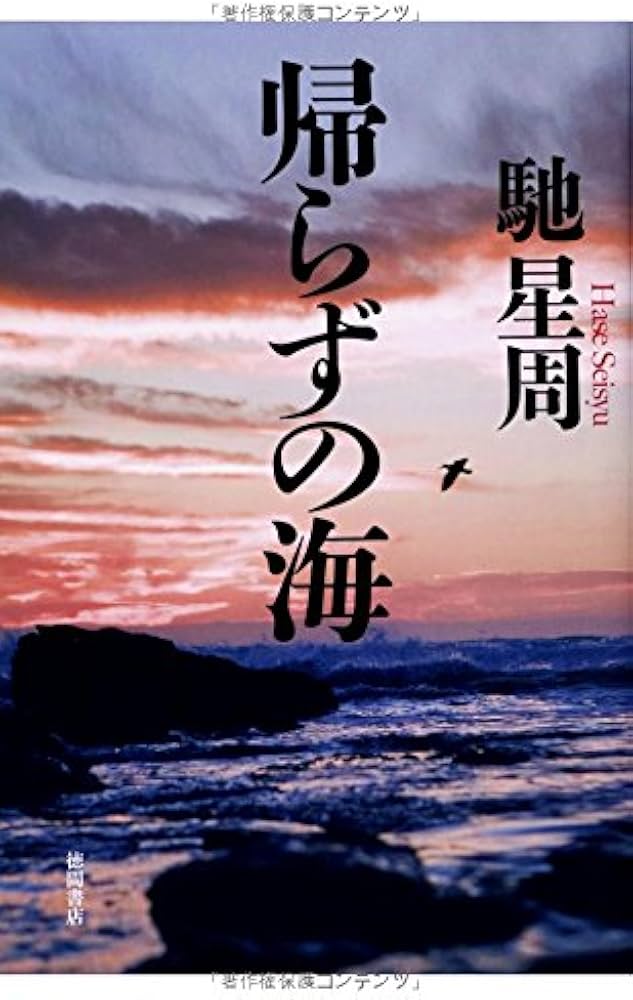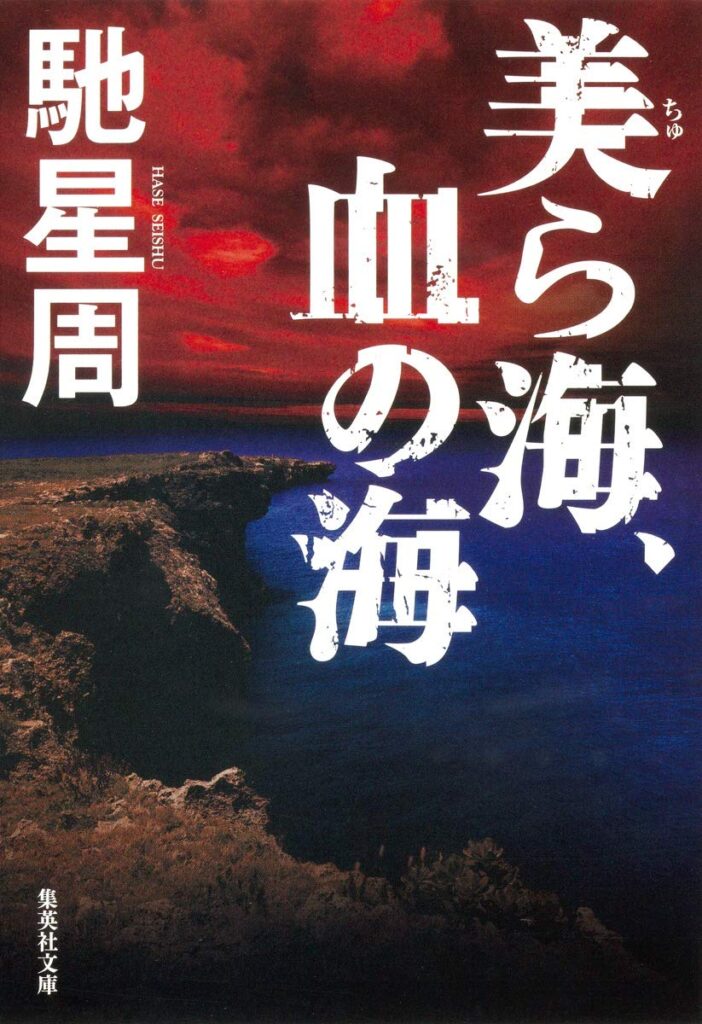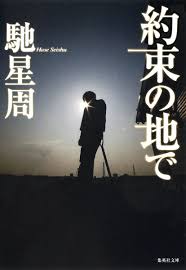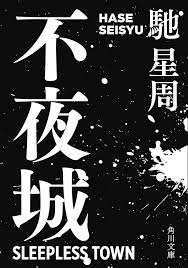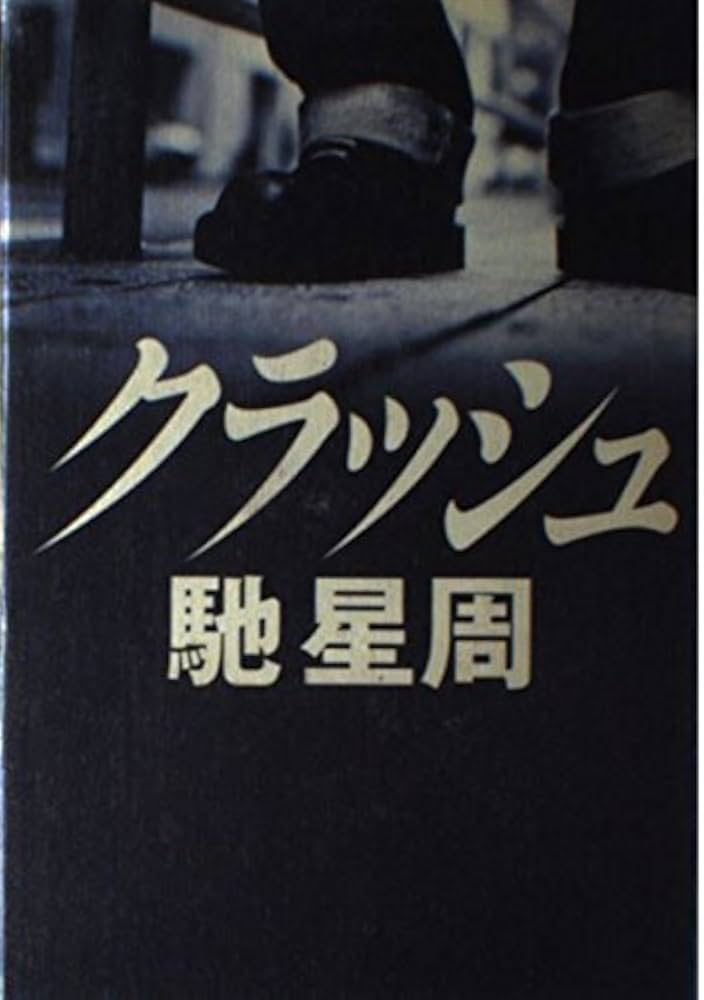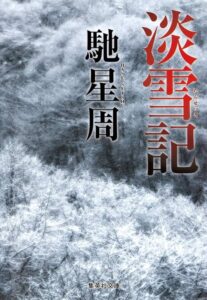 小説「淡雪記」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、冬の北海道を舞台にした、あまりにも純粋で、そして息が詰まるほどに痛ましい愛の記録です。馳星周さんが描く世界は、しばしば裏社会の厳しさや人間の業をえぐり出してきましたが、この「淡雪記」では、その切れ味が純愛というテーマに向けられています。
小説「淡雪記」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、冬の北海道を舞台にした、あまりにも純粋で、そして息が詰まるほどに痛ましい愛の記録です。馳星周さんが描く世界は、しばしば裏社会の厳しさや人間の業をえぐり出してきましたが、この「淡雪記」では、その切れ味が純愛というテーマに向けられています。
一見すると、傷ついた青年と無垢な少女が出会い、心を寄せ合う美しい恋物語のように思えるかもしれません。しかし、ページをめくるごとに、その淡雪のような幸福がいかにもろく、そして残酷な現実に溶かされていくのかを、私たちは目の当たりにすることになります。物語の序盤から散りばめられた不穏な空気は、やがて避けられない破滅の足音へと変わっていきます。
本記事では、物語の導入から結末まで、その詳細な流れと、心を揺さぶられずにはいられない登場人物たちの軌跡を追っていきます。この物語がなぜこれほどまでに読む者の胸を締め付け、そして同時に、ある種の荘厳な美しさを感じさせるのか。その核心に迫っていきたいと思います。
これから語られるのは、救いを求める魂が、その救いのなさ故に永遠の光を得る物語です。もしあなたが、ただ甘いだけの恋愛小説に物足りなさを感じているのなら、この雪のように白く、血のように赤い物語の世界に、ぜひ足を踏み入れてみてください。忘れられない読書体験が、あなたを待っているはずです。
「淡雪記」のあらすじ
写真家を目指す青年、三浦敦史は、ひと冬の間、義父が所有する北海道・大沼の別荘に籠り、作品制作に打ち込むことを決意します。彼は人との関わりを避けるかのように、静かで謎めいた雰囲気を漂わせていました。その心には、誰にも明かすことのできない深い傷と、重い秘密が隠されていました。ただひたすらにシャッターを切り、己の表現を模索する孤独な日々を送っていたのです。
そんなある日、敦史は雪深い森の中で、まるでこの世のものではない妖精のような少女、有紀と出会います。黒い髪と透けるように白い肌を持つ彼女は、著名な画家である伯父の屋敷で、世間から隔絶されたように暮らしていました。彼女は知的障害を抱えており、その心は無垢な子どものままでした。敦史は、有紀の穢れを知らない純粋さに強く惹きつけられます。
敦史は有紀をモデルに写真を撮り始め、二人は急速に心を通わせていきます。厳しい冬の自然に閉ざされた世界で、写真の撮影は二人だけの神聖な儀式となり、彼らの時間はかけがえのない幸福に満たされていきました。それは、これまでの人生で孤独と絶望しか知らなかった敦史にとって、初めて手にする温かい光のような日々でした。
しかし、その完璧すぎるほどの幸福な時間は、長くは続きません。敦史がひた隠しにしてきた過去が、彼らの聖域に暗い影を落とし始めます。そして、二人の淡雪のような恋は、逃れることのできない過酷な運命の渦へと、否応なく巻き込まれていくことになるのです。
「淡雪記」の長文感想(ネタバレあり)
この「淡雪記」という物語の本質は、一体どこにあるのでしょうか。それは、単なる悲恋物語という言葉では到底片付けられない、もっと根源的な魂の叫びであり、作者である馳星周さんが突きつける、冷徹で、しかしどこか慈悲深くもある世界観そのものだと感じます。読み終えた後に残るのは、胸を抉られるような痛みと、不思議なほどの静謐さでした。
この物語を理解する上で欠かせないのが、作者自身が語る「馳星周版『フランダースの犬』」という創作の原点です。幼い頃に見た、主人公ネロと愛犬パトラッシュが誰にも救われることなく凍え死んでいく結末。その理不尽なまでの悲劇こそが、馳さんの作家としての出発点であったといいます。努力しても報われない人生があるという厳しい現実。この物語は、その哲学を最も純粋な形で結晶させた作品なのです。
ですから、私たちはこの物語に安易な救いを期待してはなりません。物語が始まった瞬間から、敦史と有紀の運命は、美しくも悲劇的な結末へと向かうことが定められています。これは、絶望を描くための物語ではなく、絶望の中にしか見いだせない究極の愛と魂の救済を描いた、荘厳な鎮魂歌なのです。
物語の主人公である三浦敦史は、当初、心に厚い鎧をまとった青年として描かれます。プロの写真家を目指して北海道の別荘に籠る彼の姿は、どこか世捨て人のようであり、その瞳の奥には深い孤独が宿っています。彼が抱える「人に言えない秘密」とは何か。読者は、その謎めいた雰囲気に引き込まれ、彼の心の扉が開かれるのを息をのんで見守ることになります。
その扉の奥に隠されていたのは、あまりにもおぞましい過去でした。長年にわたる義父からの性的虐待。このトラウマこそが、敦史という人間のすべてを規定し、物語を駆動させるエンジンとなっています。彼の行動、彼の渇望、そして彼の内に潜む暴力性は、すべてこの一点から解き明かすことができます。
彼が有紀の持つ「純粋さ」に執着し、その姿を写真に収めようと必死になるのはなぜか。それは、自らが無残に奪われた無垢さを、彼女の中に見て、それを取り戻そう、守り抜こうとする無意識の叫びなのです。そして物語の後半、彼が解き放つ凄まじい暴力は、単に有紀を守るためだけではなく、長年抑圧され続けてきた怒りと絶望が、ついに堰を切って噴出した結果に他なりません。彼は被害者でありながら、同時に恐ろしい「モンスター」という側面をも内包した、まさにノワールの登場人物なのです。
そして、運命の出会いを果たすヒロイン、有紀。雪の森に佇む彼女は、まるで幻想の世界から舞い降りた「妖精」のようです。しかし、その幻想的な美しさとは裏腹に、彼女は知的障害を抱え、その精神は幼い子どものまま時を止めています。このアンバランスさが、彼女という存在をより一層儚く、守らなければならないものとして際立たせています。
有紀は、著名な画家である伯父と二人きりで、人里離れた洋館に暮らしています。この設定自体が、物語に不穏な空気を充満させています。無垢で抵抗するすべを持たない少女が、権威ある年長の男性保護者と隔離された空間にいる。このゴシック小説的な構図は、そこに潜む危険性を強く暗示し、読者は「何かがおかしい」という嫌な予感を抱きながら読み進めることになります。
敦史と有紀が、出会ってすぐに強く惹かれ合うのは、単なる一目惚れではありません。それは、言葉になる以前の、魂のレベルでの共鳴です。敦史は義父から、そして有紀もまた(詳細は語られずとも強く示唆される形で)伯父から、その尊厳を搾取されてきました。彼らは互いの瞳の奥に、同じ種類の傷と痛みを見出したのです。二匹の傷ついた獣が、互いの傷を嗅ぎ分け、寄り添い合う。彼らの絆は、その共有された絶望の上に、あまりにも固く結ばれていました。
二人が心を通わせる「淡雪の日々」は、この物語における束の間の、そして唯一の聖域として描かれます。敦史が有紀にカメラを向ける時間。それは、二人の汚された世界が、有紀の純粋さと、北海道の冬の圧倒的な自然の美しさによって浄化されていくかのような、奇跡的な時間です。彼らにとって、この写真撮影の日々は人生のすべてであったのではないか、と思えるほどに濃密で、完璧な幸福に満ちています。
しかし、その背景に広がる雪景色は、美しいと同時に、どこまでも冷たく無慈悲です。それは、彼らの愛が純粋であればあるほど、孤立し、やがては過酷な現実に呑み込まれていく運命を象徴しているかのようです。この幸福な時間が、あまりに完璧であればあるほど、その後に訪れる破滅の影は色濃くなっていきます。
この破滅の必然性を決定的にするのが、物語の中で『フランダースの犬』のネロとパトラッシュの名前が、登場人物の口から具体的に語られる場面です。この瞬間、彼らは自分たちの運命が、あの有名な悲劇の物語に重ねられていることを意識させられます。彼らの闘いは、単に現実の追手から逃れるだけでなく、物語そのものに組み込まれた「悲劇」という運命そのものへの、絶望的な抵抗となるのです。
二人が築いた聖域は、敦史の過去からの使者によって、あっけなく踏みにじられます。義父が差し向けたやくざの男たちの出現。これが、物語を後戻りできない悲劇へと突き落とす、最初の血の染みとなります。有紀を守るため、そして自分たちの世界を守るため、敦史は追ってきたやくざの一人を殺害します。この瞬間、彼の内面に眠っていた「モンスター」が完全に覚醒し、物語は静かな恋愛譚から、暴力と血にまみれたノワール・スリラーへとその姿を豹変させるのです。
ここから先は、凄惨な暴力が次々と連鎖する、絶望的な逃避行が始まります。失われていく命、汚れていく手。敦史は有紀を守るという大義名分のもと、次々と殺人を重ねていきます。その描写は苛烈を極め、「人が死に過ぎだ」と読者が驚くほどの死体の山が築かれていきます。さらに、有紀の保護者であるはずの伯父までもが、その歪んだ執着心から彼らの敵として立ちはだかり、二人の逃げ道を完全に塞いでしまいます。
この逃避行の中で、読者は敦史の行動に対し、強い苛立ちやもどかしさを感じるかもしれません。彼の行動は、有紀を守りたいという純粋な愛から発しているはずなのに、あまりにも無謀で、自己中心的にも見えます。特に、自らも瀕死の重傷を負いながら、有紀を連れて最後の逃走を試みる場面は、もはや愛ではなく、彼女を道連れにする身勝手なエゴと映るかもしれません。しかし、それこそが作者の狙いなのです。
この物語に、完全なる善人や、清廉潔白な英雄は一人も登場しません。敦史の「愛」は、彼の深い心の傷や絶望と分かちがたく結びついており、純粋なだけではありえないのです。彼は有紀を救いたいと願いながら、同時に、たとえそれが彼女の死を意味するとしても、彼女を手放すことができない。そこにいるのは、傷つき、歪み、それぞれの絶望を抱えた人間たちの姿だけなのです。
物語は、壮絶なクライマックスを経て、最後の場面へとたどり着きます。致命傷を負った敦史は、最後の力を振り絞って有紀を抱き、真っ白な雪原へと逃げ込みます。そして、雪の中で抱き合い、互いの体温を感じながら、共に血を流し、静かに死んでいくのです。「有紀ね、敦史の赤ちゃん生みたい」「ボクを好きになってくれてありがとう」。息絶える間際の有紀の無垢な言葉が、読む者の涙腺を容赦なく破壊します。
この結末は、あまりにも悲劇的です。しかし、この物語の冷徹な論理の中では、これこそが唯一可能な救済であり、最高の「ハッピーエンド」なのです。もし彼らが生き延びたとして、何が待っていたでしょうか。敦史は殺人者として裁かれ、有紀は保護者を失い施設での無味乾燥な人生を送るか、あるいはまた別の誰かに搾取されるかもしれません。彼らの前には、引き裂かれる運命しか残されていなかったのです。
だからこそ、二人が共に過ごしたあの「淡雪の日々」こそが、彼らの人生のすべてであり、唯一の真実でした。そして、雪の中で抱き合いながら共に死ぬことによって、彼らはその幸福な時間を永遠のものとし、誰にも汚されることのない絶対的な聖域を完成させたのです。それは、敦史が撮った一枚の写真のように、彼らの愛を完璧な形で凍結させる行為でした。この「美しい悲劇」によって、二人の魂は、彼らを苦しめ続けた世界から完全に解放され、永遠に結ばれたのです。これこそが、馳星周さんが描く「白の鎮魂歌」の、あまりにも気高く、痛ましい到達点なのだと、私は思います。
まとめ
馳星周さんの小説「淡雪記」は、純愛物語という衣をまとった、極めて苛烈なノワール作品でした。北海道の美しくも厳しい自然を背景に、心に深い傷を負った青年と、無垢な少女の出会いから破滅までを、容赦のない筆致で描いています。
物語の根底に流れるのは、作者が公言する「馳星周版『フランダースの犬』」というテーマです。それは、努力や純粋さだけでは決して乗り越えられない人生の理不尽さと、その中で見いだされる、死という形をとった究極の救済の物語です。読み進めるほどに胸が締め付けられ、その凄惨な展開に言葉を失います。
しかし、ただ残酷なだけでは終わらないのが、この物語の真骨頂です。あまりにも痛ましい結末の中に、不思議なほどの神々しさと、純粋な愛が永遠に昇華されたかのような美しさを見出すことができます。それは、登場人物たちが自らを苦しめた世界から解放され、二人だけの完璧な世界で結ばれた、唯一のハッピーエンドなのかもしれません。
読後、心にずっしりと重いものが残ることは間違いありません。ですが、それと同時に、忘れがたい強烈な感動と、物語の持つ力の大きさを改めて感じさせてくれる一冊です。生半可な気持ちでは読めませんが、魂を揺さぶるような読書体験を求める方には、ぜひ手に取っていただきたい傑作です。