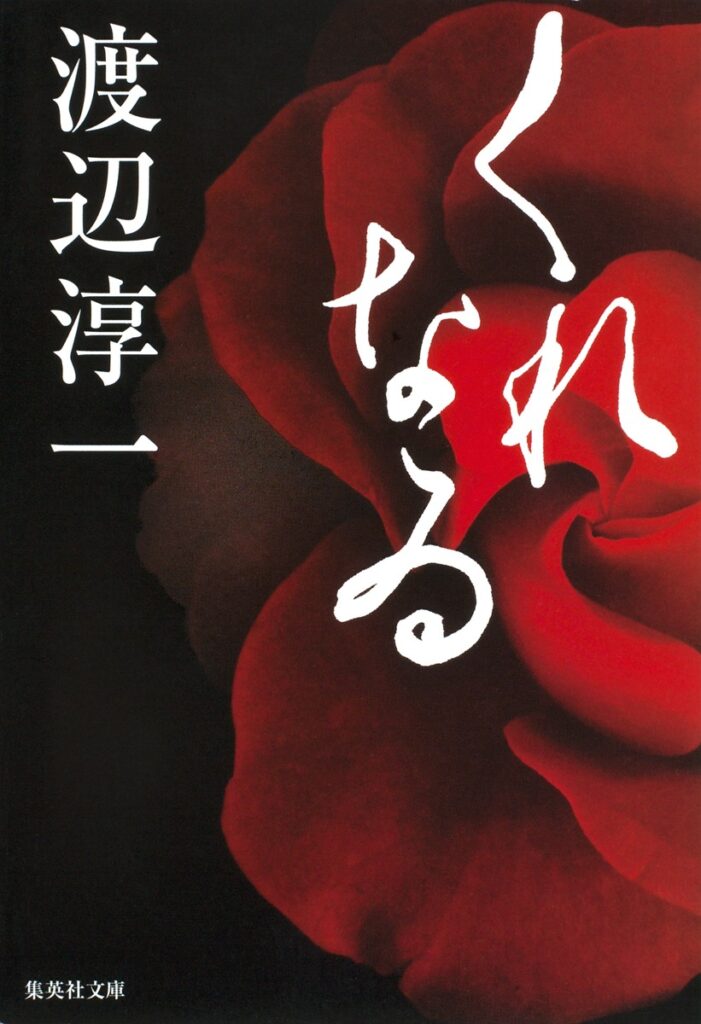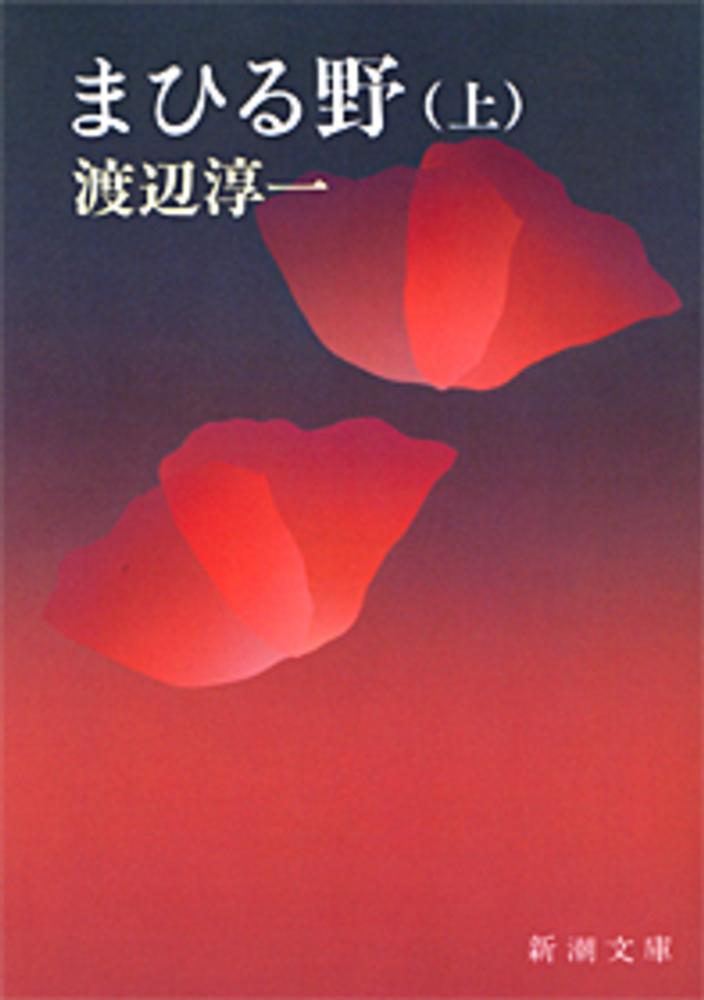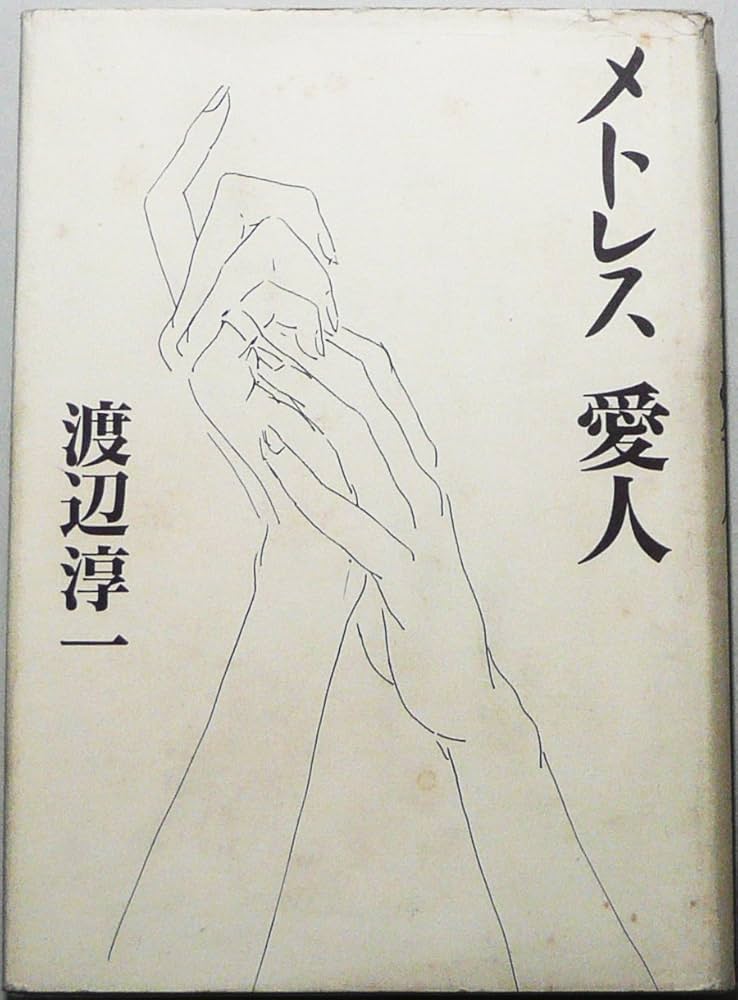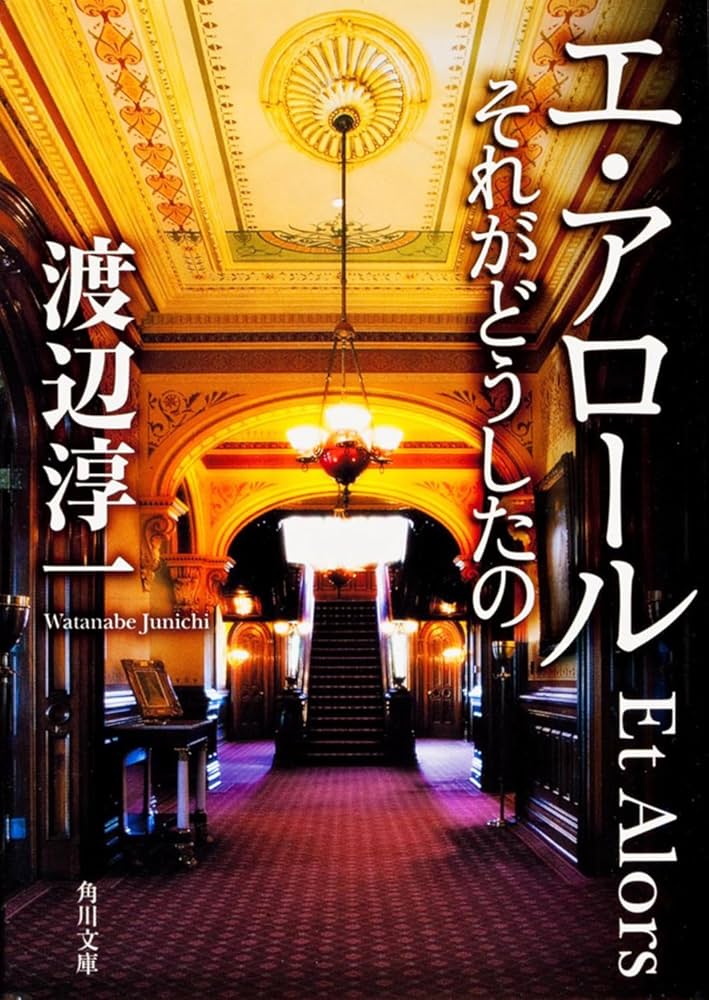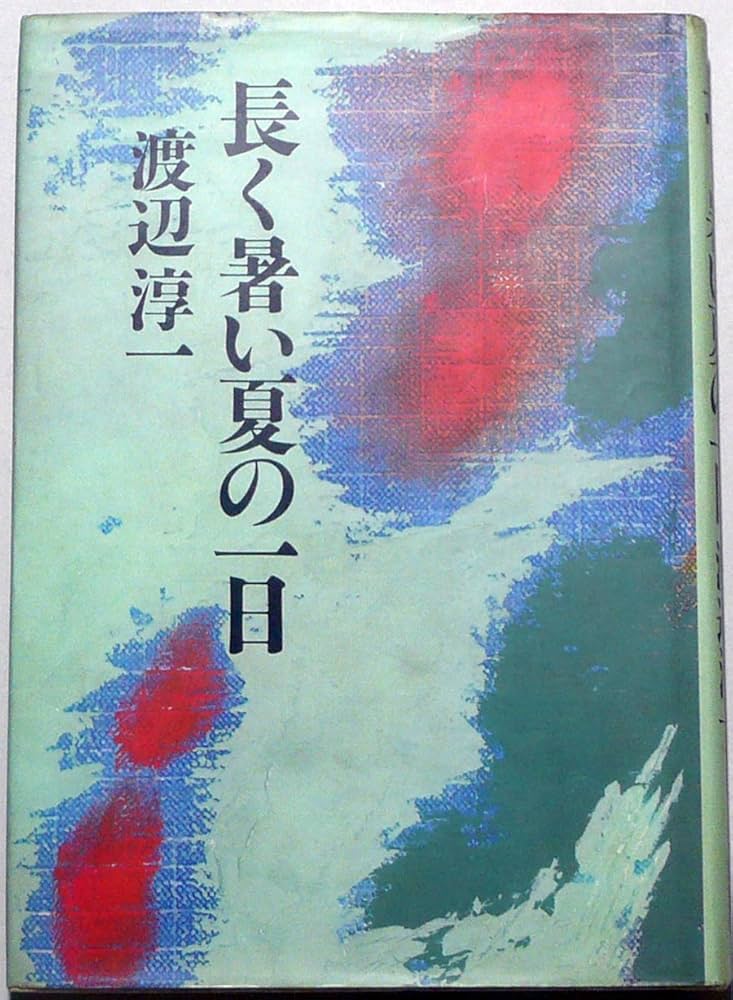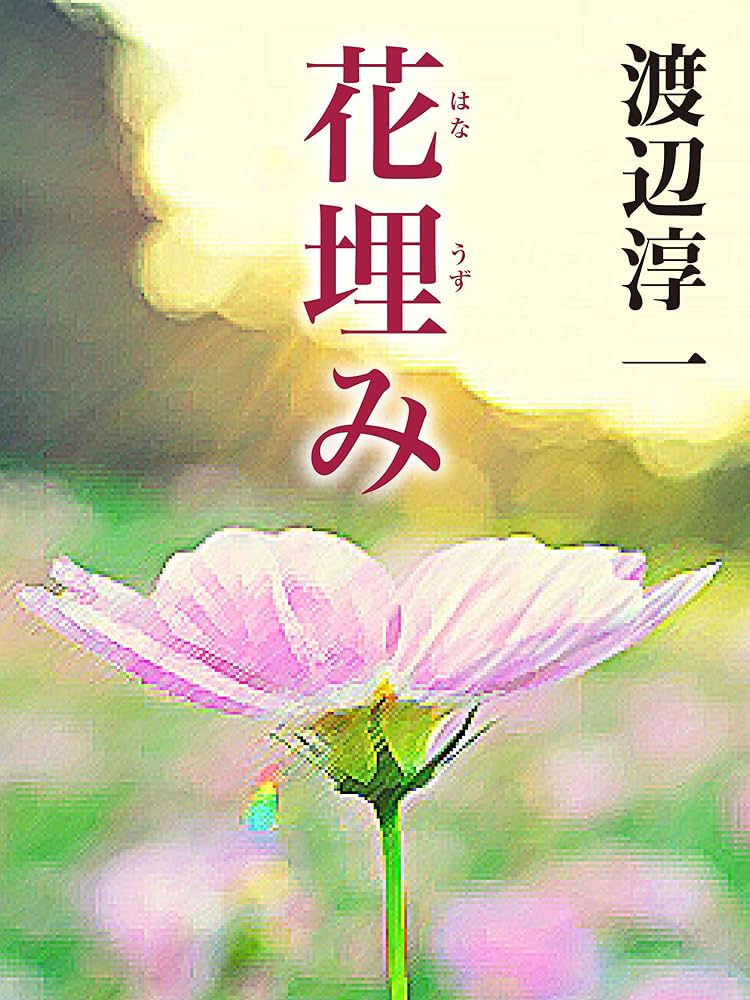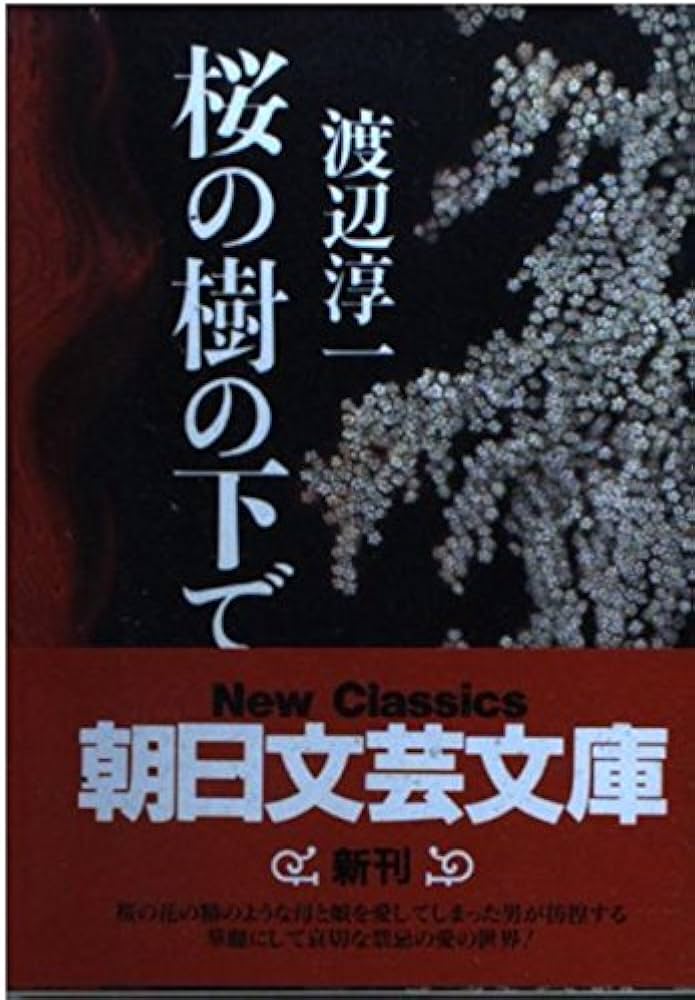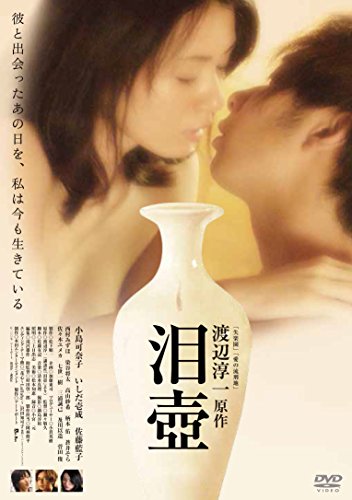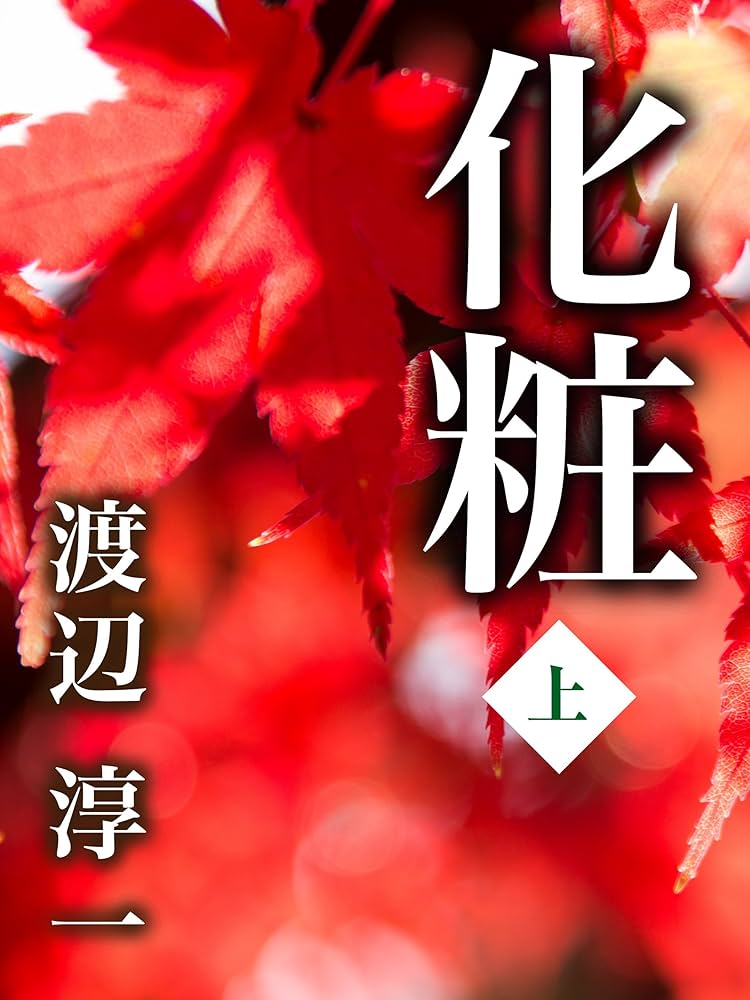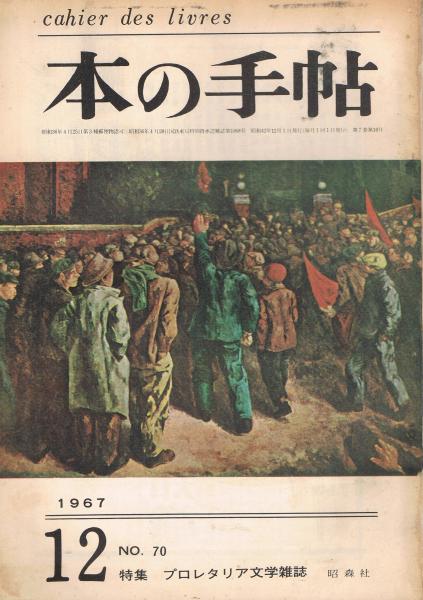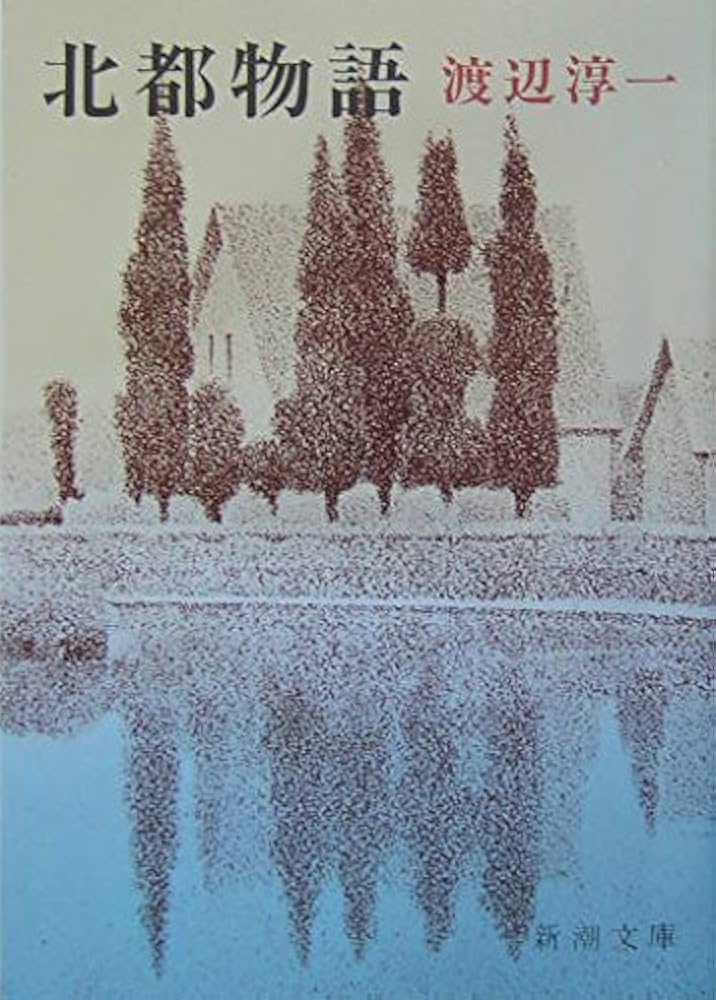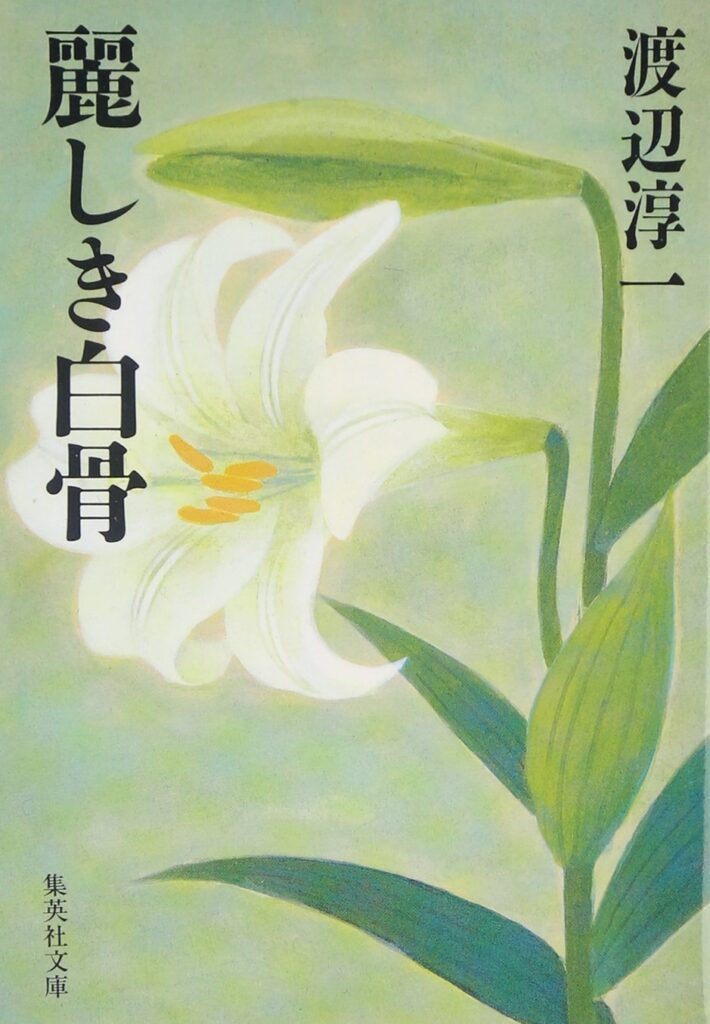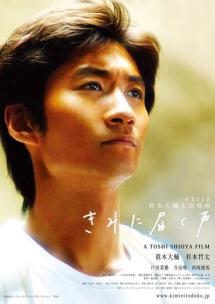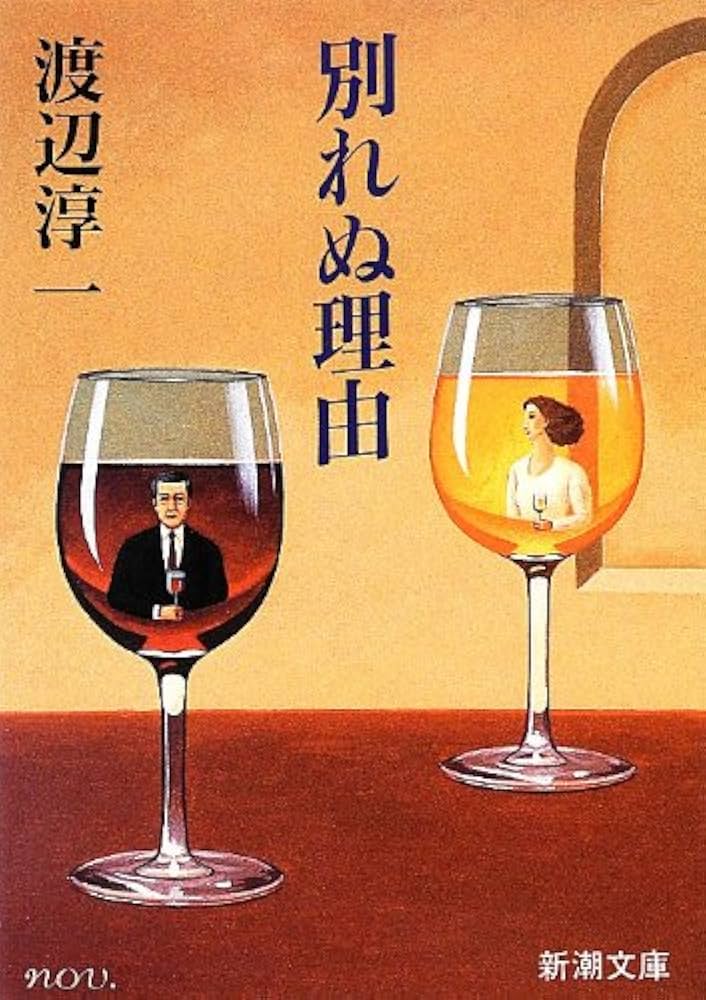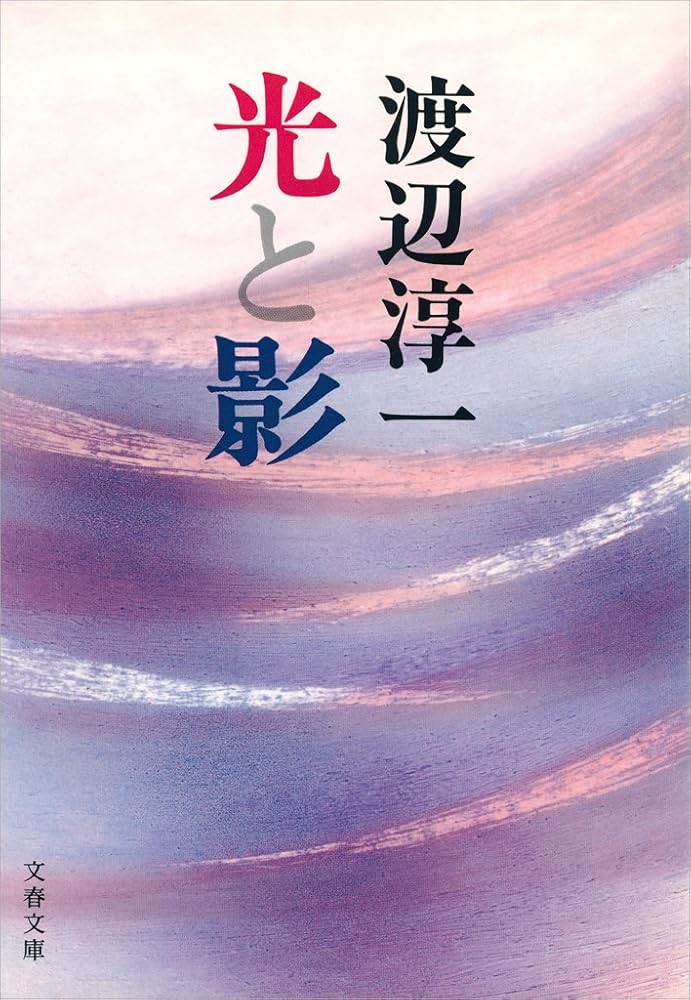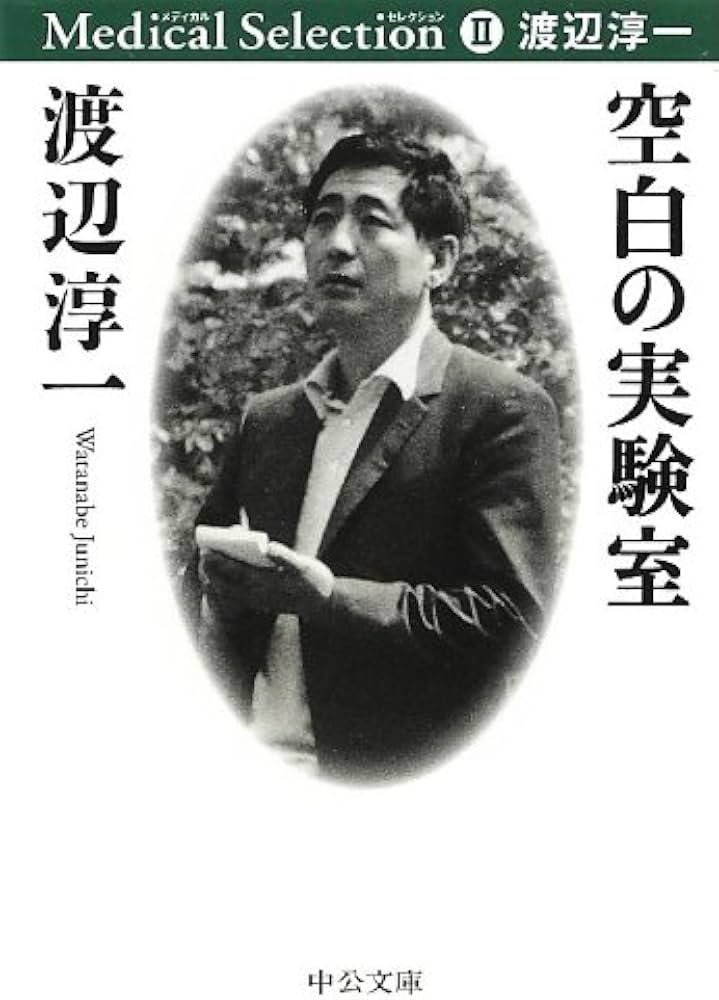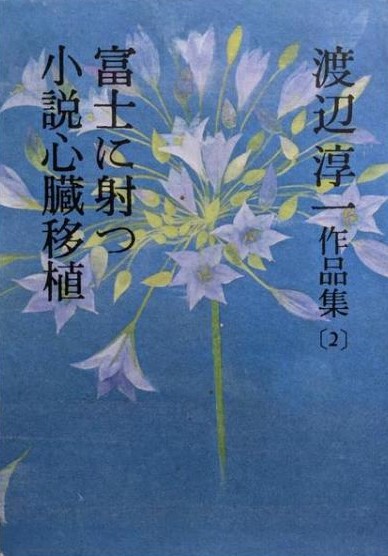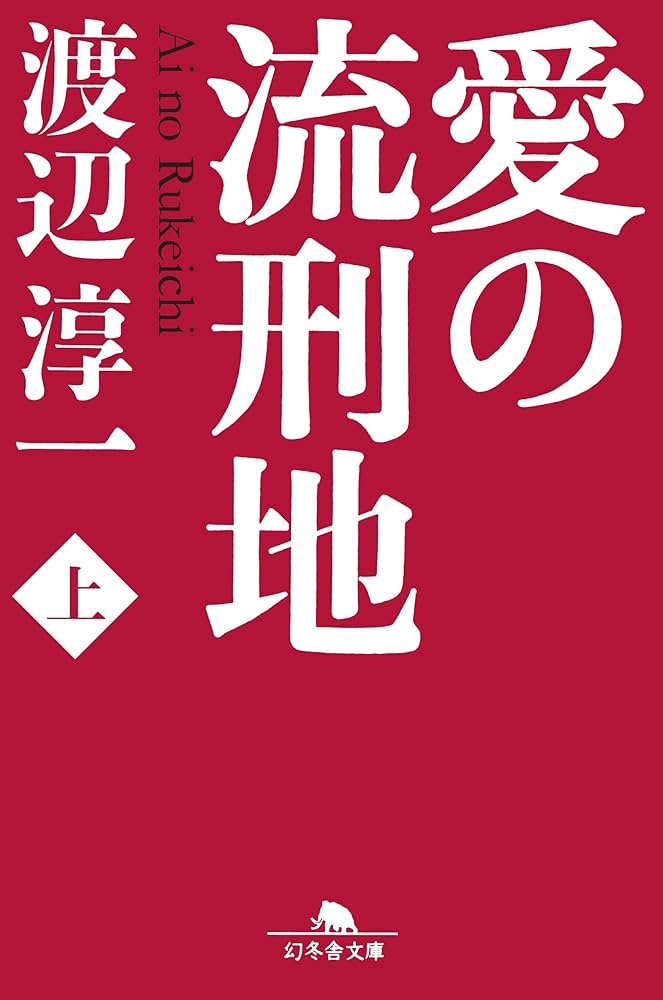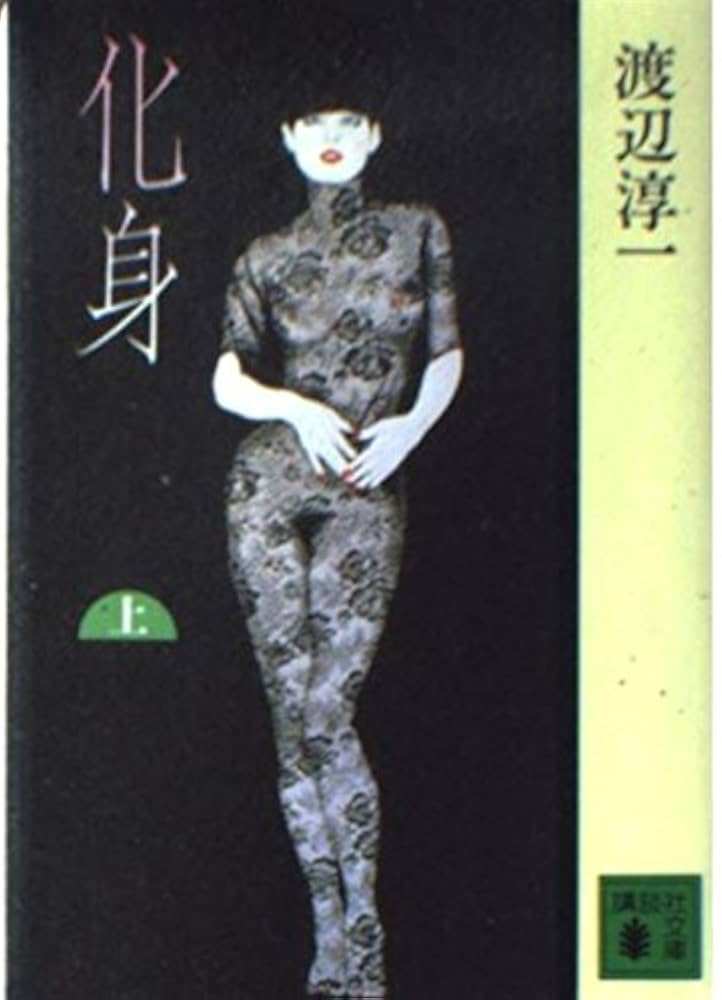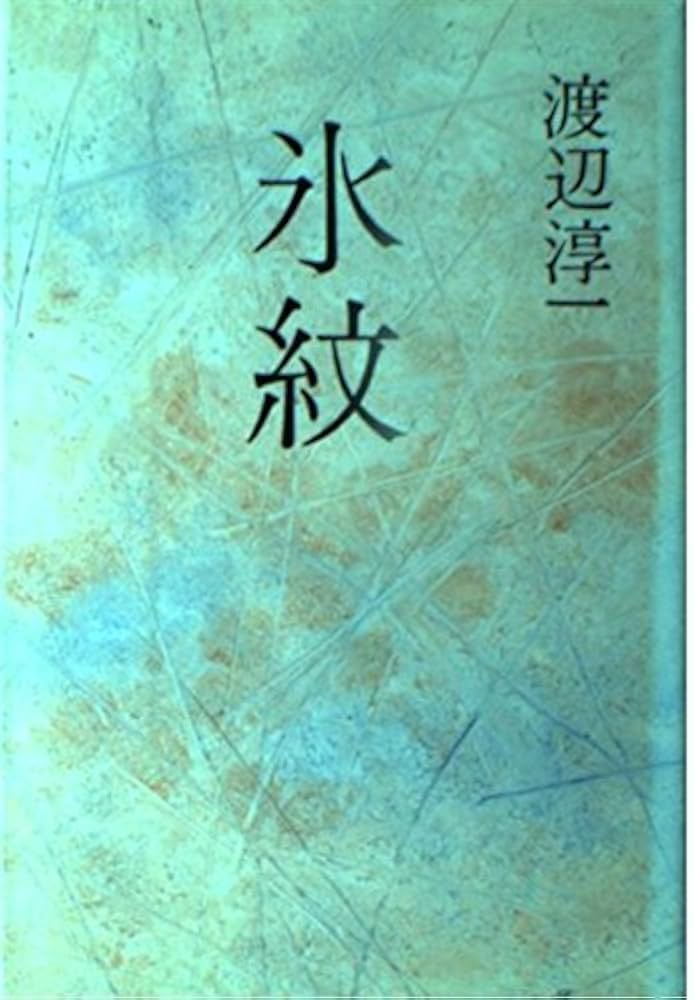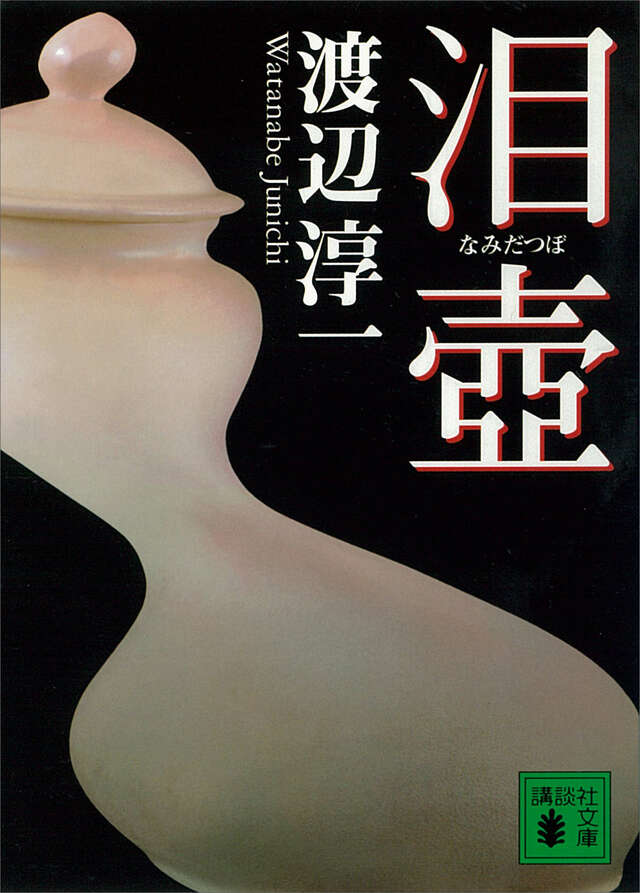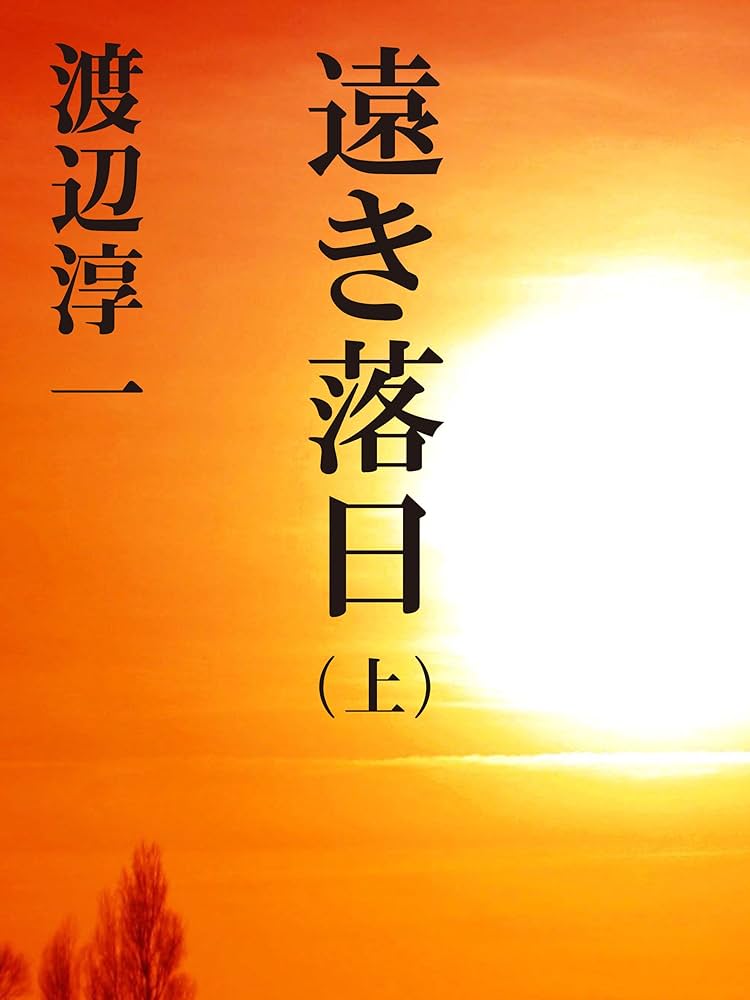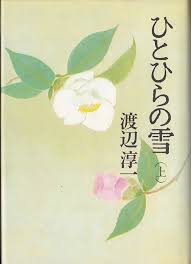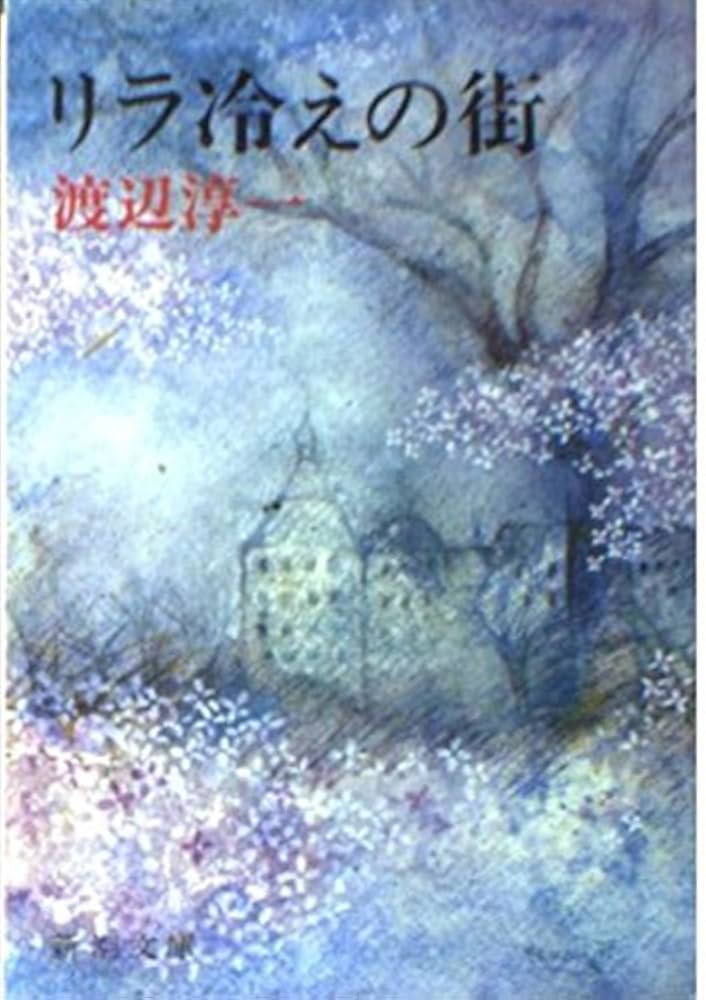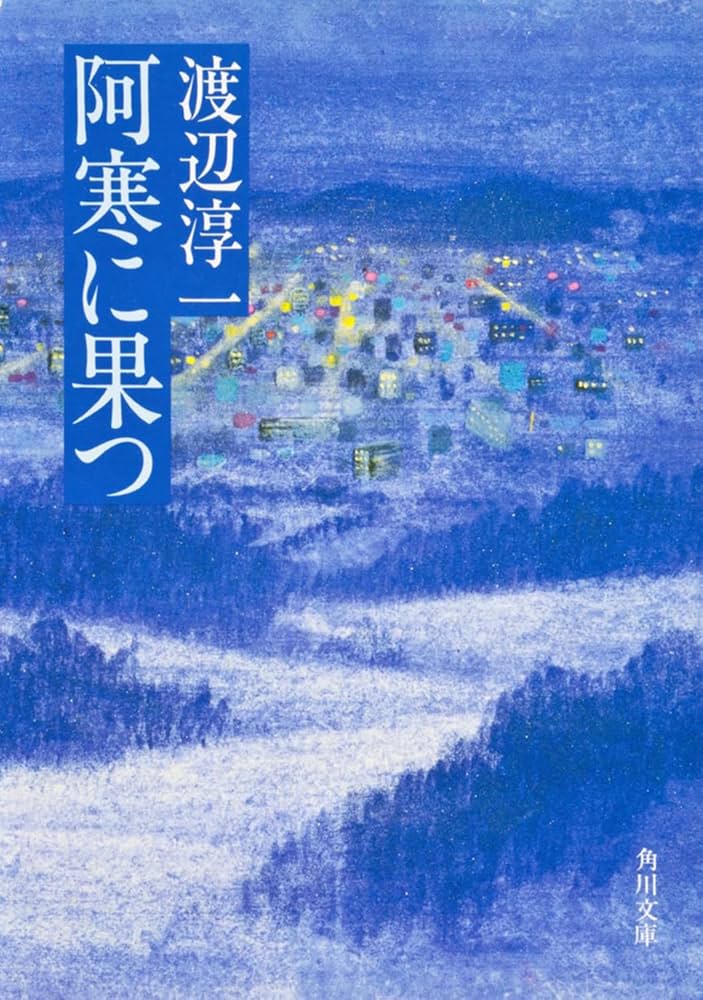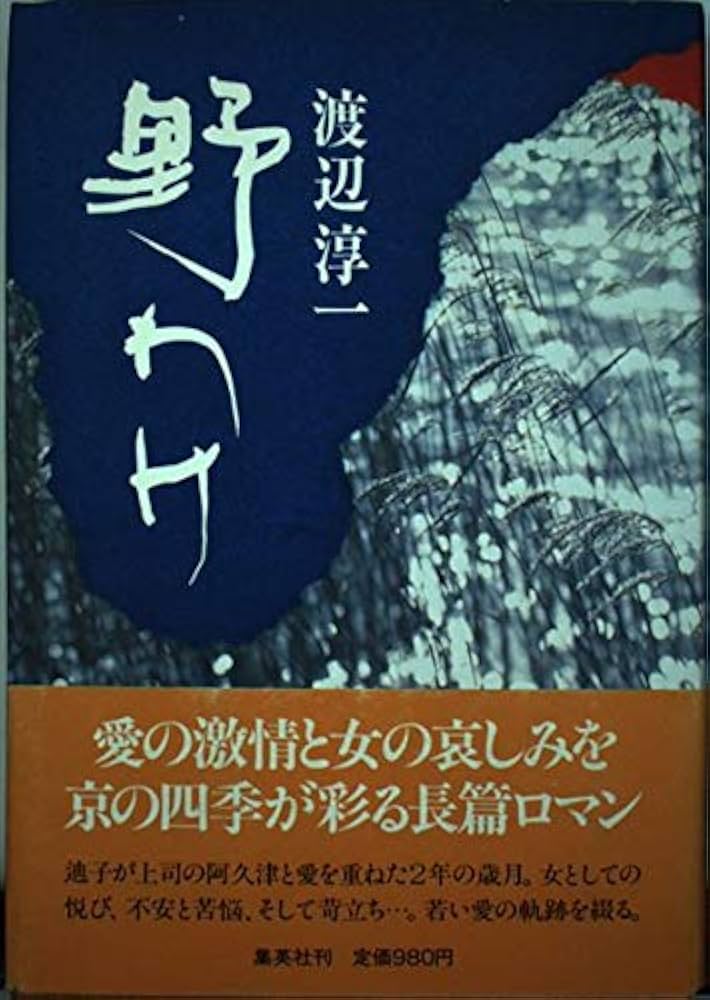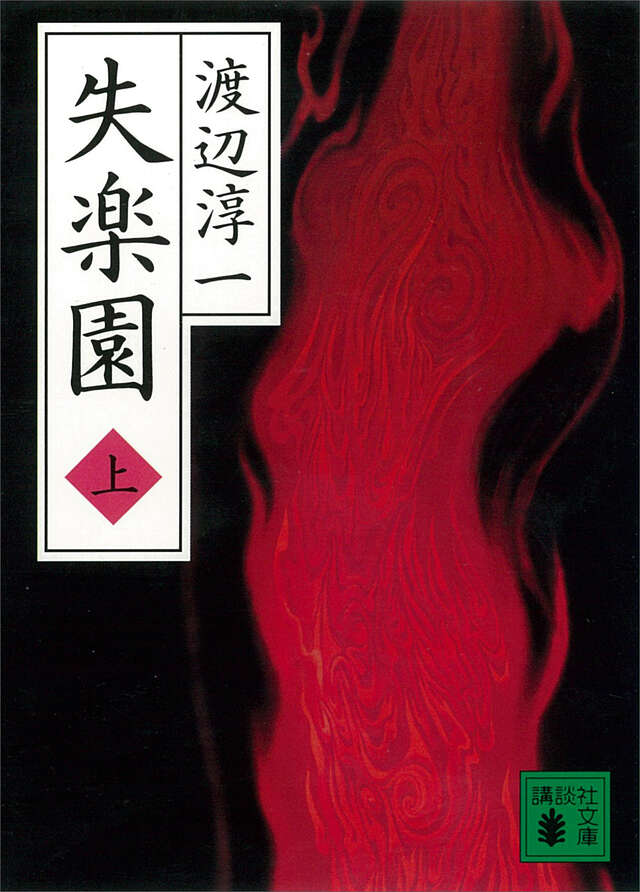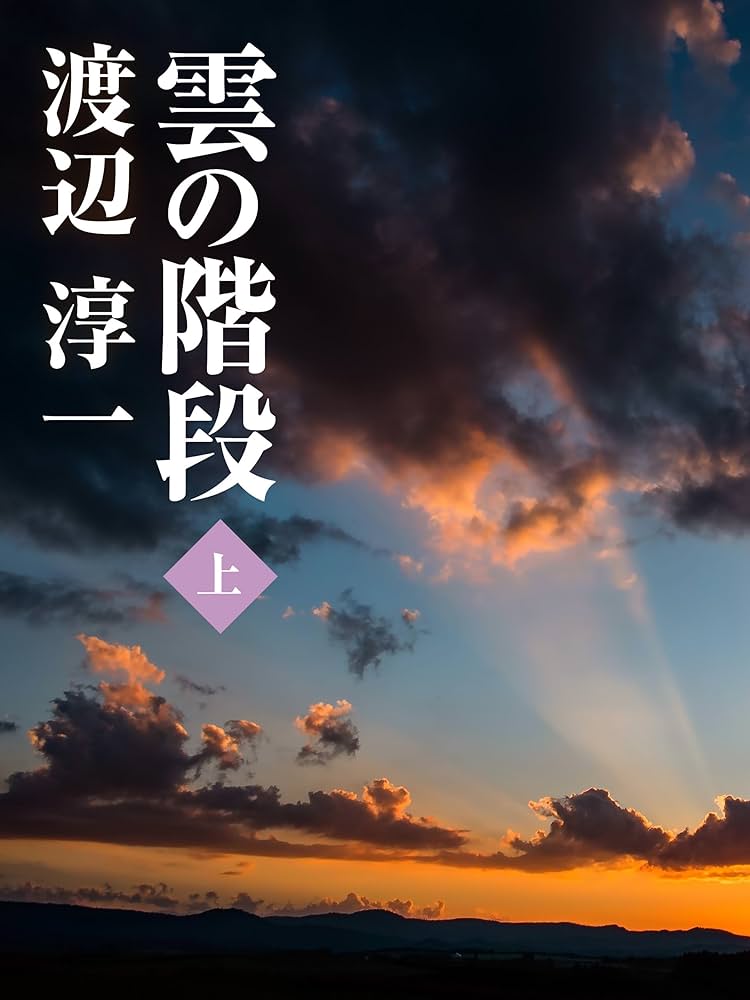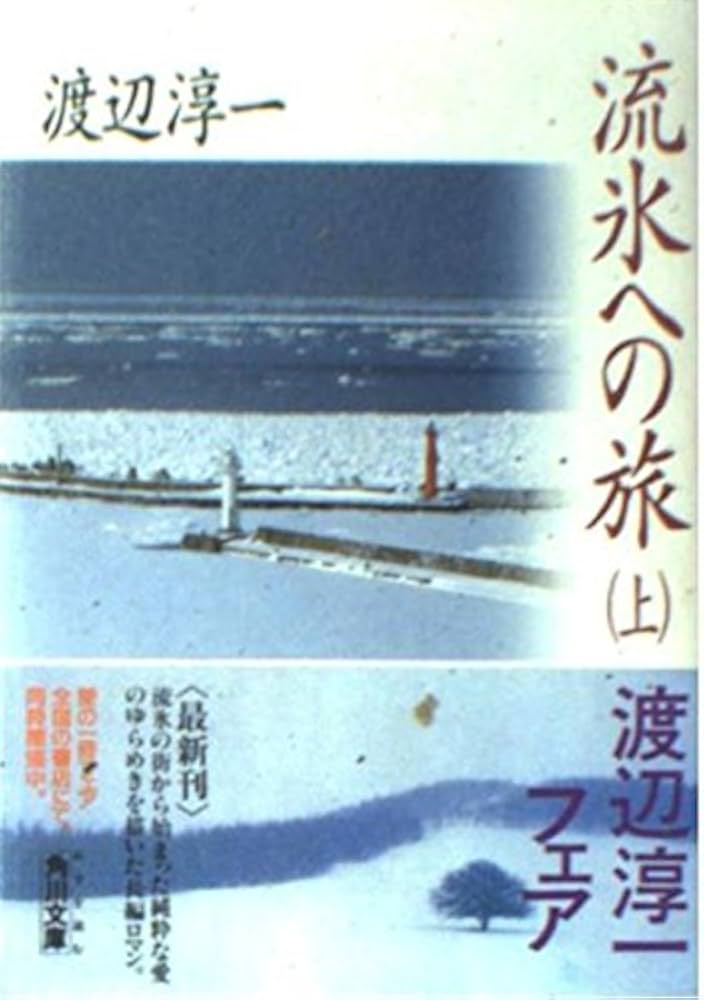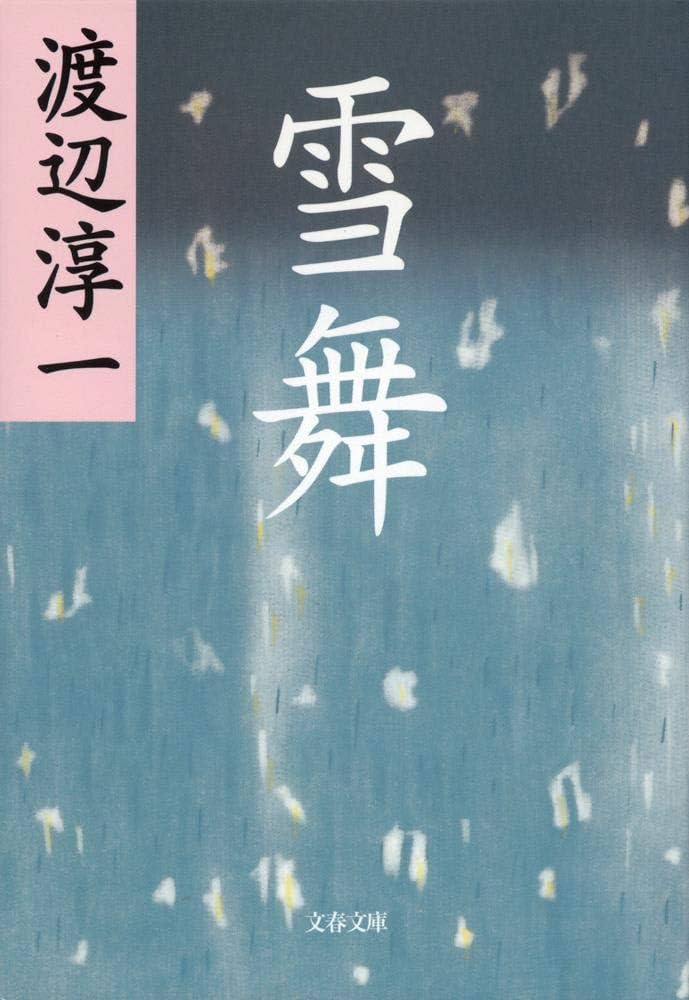小説「無影燈」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「無影燈」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この作品は、1972年に発表されて以来、多くの読者を魅了し続けてきた、渡辺淳一の代表作の一つと言えるでしょう。単なる医療小説や恋愛物語という枠には収まらない、人間の生と死の本質に迫る物語が、ここにはあります。
物語の中心にいるのは、天才的な腕を持つ外科医・直江庸介。彼の周りには常に謎の影がつきまといます。その一方で、彼に惹かれていく看護師・志村倫子。二人の関係を軸に、物語は医療現場のリアルな描写と、登場人物たちの複雑な心理を巧みに織り交ぜながら進んでいきます。
この記事では、まず物語の導入部となるあらすじを、結末には触れずにご紹介します。そして、その後に続く章では、物語の核心に迫る重大なネタバレを含んだ、詳細な考察と感想をたっぷりと綴っていきます。なぜ直江はあのような行動を取ったのか、そして彼が迎える結末が意味するものとは何か。
この記事を通して、「無影燈」という作品が持つ、深く、そして時に切ない魅力を余すところなくお伝えできればと思います。これから読み進めていただくことで、この不朽の名作が投げかける問いを、一緒に考えていけるはずです。
小説「無影燈」のあらすじ
将来を嘱望されながらも大学病院を去り、市井の個人病院に勤める天才外科医・直江庸介。彼はその卓越した技術と整った容姿から、患者や同僚の看護師たちから絶大な信頼と人気を集めていました。しかし、その完璧に見える姿の裏で、彼は深い虚無感を抱え、酒に溺れる日々を送っていたのです。
そんな直江の前に、一人の真面目で献身的な看護師・志村倫子が現れます。倫子は、直江の持つ不思議な魅力と、その奥に隠された影に、抗いがたく惹かれていきます。彼の不可解な行動に戸惑いながらも、その愛情は次第に深く、揺るぎないものへと変わっていきました。二人の関係は、倫子からの大胆なアプローチによって始まります。
物語の舞台となるオリエンタル病院では、院長親子や同僚の医師など、様々な人物の思惑が交錯します。特に、理想に燃える同僚の小橋医師は、患者の死に対してどこか突き放したような態度を見せる直江に、たびたび反発します。なぜ直江は末期患者にあえて「偽りの手術」を行うのか。彼の行動は、病院内に次々と波紋を広げていきました。
倫子は、直江の行動の裏にある真実を理解しようと努めますが、彼の謎は深まるばかり。ある日、彼女は直江のアパートで、一枚の奇妙なレントゲン写真を見つけます。そこに写っていた「白い影」が何を意味するのか、倫子にはまだ知る由もありませんでした。彼の破滅的な行動の理由、そして彼がひた隠しにする秘密とは一体何なのでしょうか。
小説「無影燈」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、「無影燈」の物語の核心に触れる内容、つまり結末までのすべてを明かした上で、私の深い思いを綴っていきます。もし、まだこの物語を読んでおらず、ご自身で結末を確かめたいという方は、ご注意ください。この物語の本当の価値は、その衝撃的な真実が明らかになった時にこそ、理解できるものだと私は考えています。
まず語らなければならないのは、主人公・直江庸介という人物の圧倒的な存在感でしょう。彼は、一見すると、将来有望なキャリアを捨て、刹那的な女性関係と深酒に溺れる、破滅的な魅力を持つ人物として描かれます。物語の序盤、私たちは看護師・倫子と同じ視点から、「なぜ彼はこんなにも投げやりなのだろう?」という恋愛ドラマ特有の問いを抱くように巧みに誘導されるのです。
しかし、物語が進むにつれて、彼の行動原理が単なる性格や過去のトラウマに起因するものではないことが、少しずつ明らかになっていきます。彼が末期癌の患者に対して、治る見込みがないと知りながら「偽りの手術」を施す場面は、その象徴です。同僚の小橋医師は、それを医療倫理に反する嘘だと激しく非難しますが、直江は患者が安らかに死を迎えるための「思いやり」なのだと反論します。
この対立は、単なる医療哲学の違いではありません。実は、直江が施していたのは、彼自身が受けたいと願う「慈悲深い嘘」だったのです。彼は、医師としての冷徹な知識によって、自らが不治の病に侵されていることを知っていました。その耐えがたい真実を知っているからこそ、患者から希望を奪う「告知」は残酷だと主張し、偽りの手術で心の安寧を与えようとしたのです。
物語の衝撃的な転換点は、直江の病名が「多発性骨髄腫」であると判明する場面です。骨の髄で血液細胞が癌化するこの病は、当時の医療では不治とされ、激しい痛みと衰弱が避けられない、絶望的な診断でした。この一つの医学的な事実が、これまでの彼のすべての不可解な行動に、一本の筋を通します。
彼が輝かしいキャリアを捨てたのは、未来そのものが無意味になったから。彼が酒に溺れ、虚無的な態度を取り続けたのは、絶え間ない肉体的な苦痛と、死の宣告という精神的な重圧から逃れるための、必死の抵抗だったのです。彼の行動は、すべて死にゆく者の論理に基づいていた、というわけです。
そして、彼の無差別とも思える女性関係にも、驚くべき理由が隠されていました。それは、単なる快楽主義や現実逃避ではありませんでした。消えゆく自らの存在を前にしたとき、彼の肉体は、自らの遺伝子、すなわち子孫を残すという、最も根源的で生物学的な命令に突き動かされていたのです。彼の遺書には、関係を持ったすべての女性が自分の子を宿すことを願っていた、という衝撃的な告白が記されています。
この事実は、物語を単なる悲恋の物語から、生と死、そして種の保存という、より普遍的で深遠なテーマへと昇華させています。直江の行動は、理性や感情を超えた、生命そのものの叫びだったのかもしれません。彼は、自らの肉体が滅びゆく中で、必死に生の証を残そうともがいていたのです。
この物語のもう一人の主人公、志村倫子の存在も忘れることはできません。彼女の直江に対する愛は、どこまでも献身的で、無私のものでした。直江の不可解な行動に傷つきながらも、彼女は彼を見捨てず、その苦悩を理解しようと努めます。彼女の存在は、冷たく暗い直江の世界に差し込む、唯一の温かい光のようでした。
物語の終盤、直江は倫子を連れて、故郷である北海道へ最後の旅に出ます。この旅の描写は、美しくも切ないものです。束の間、病の影から解放されたかのように、直江は心からの笑顔を見せ、倫子との穏やかな時間を過ごします。この幸福な時間は、しかし、悲劇的な結末への序章に過ぎませんでした。
旅の終わり、直江は偽りの口実を使って倫子だけを東京へ帰します。これは、愛する人に自分の無残な最期を見せたくないという、彼の最後の、そしてあまりにも残酷な優しさでした。彼は、人生の終わりを自らの手で選ぶことを、とうに決意していたのです。
直江が死に場所に選んだのは、支笏湖でした。一度沈めば二度と遺体は上がらないと言われるその湖は、彼の哲学を象徴しています。彼の遺書によれば、彼にとって死とは「無でもゼロでもない…なにもない」、完全な消滅を意味しました。彼は、自らの存在が跡形もなく消え去ることを望んだのです。
その遺書の中で、彼は倫子が自分の子を身ごもっていることを知っていると告げ、彼女だけが自分の遺伝子を未来に繋いでくれるかもしれないという、最後の希望を託します。これは、彼の生物学的な渇望の究極的な表現であり、倫子の愛を、ある意味で彼の種の保存という目的に利用したとも言える、非常に複雑な感情の表れです。
物語のラストシーンは、あまりにも鮮烈で忘れがたいものです。直江の死の知らせが届いた後、倫子は一人、誰もいない手術室に佇みます。彼女は、冷たく、すべてを照らし出す「無影燈」の光を浴びています。彼女のお腹には、直江の新しい命が宿っている。この場面は、死という絶対的な現実と、新しい生命というかすかな希望、そしてその両者を冷徹に照らし出す科学の光を、見事に描き出しています。
「無影燈」というタイトルが持つ意味は、ここで最大限に生きてきます。無影燈とは、手術の際に影を作らないための照明器具です。それは、すべてを白日の下に晒す、冷徹で客観的な科学の真実そのものを象徴しているのでしょう。直江は、その光から逃れるように、秘密や苦痛という「影」の中で生きていました。
しかし、物語の最後、彼のすべての影は剥ぎ取られ、病という動かしがたい真実がすべてを明らかにします。そして、彼の肉体が消滅した後には、彼の遺伝子を受け継いだ倫子が、再びその無影燈の光の下に立っている。それは希望の光なのでしょうか。それとも、彼の生物学的な欲求の道具とされてしまった彼女の、悲劇的な運命を照らす光なのでしょうか。答えは、読者一人ひとりに委ねられています。
この物語は、作者である渡辺淳一氏自身が医師であったからこそ描けた、圧倒的なリアリティに満ちています。医療現場の描写はもちろんのこと、死を目前にした人間の心理描写は、読む者の胸を激しく揺さぶります。それは、単なる想像力の産物ではなく、多くの死を見つめてきた者だけが持ちうる、深い洞察に基づいているからに違いありません。
「無影燈」は、読み終えた後も、私たちの心に重く、そして静かに問いかけ続けます。生きるとは何か、死ぬとは何か。愛とは、そして希望とは何か。直江庸介という一人の男の壮絶な生き様と死に様を通して、私たちは自らの生と死について、深く考えさせられるのです。これこそが、この作品が時代を超えて読み継がれる、最大の理由なのだと私は思います。
まとめ
渡辺淳一の「無影燈」は、単なる医療小説や恋愛物語の枠を超えた、人間の存在そのものに迫る傑作です。天才外科医・直江庸介が抱える秘密と、彼を愛し続けた看護師・倫子の姿を通して、物語は生と死という根源的なテーマを深く掘り下げていきます。
物語の核心にあるのは、直江が末期の不治の病「多発性骨髄腫」に侵されていたという事実です。彼の不可解で破滅的な行動のすべては、この死の宣告という一点から説明することができます。彼の行動は、消えゆく自らの生に対する、壮絶な抵抗の証だったのです。
この物語が特に心を打つのは、作者自身が医師であったという背景から生まれる、圧倒的なリアリティです。死を目前にした人間の心理、そしてそれを取り巻く人々の葛藤が、克明に描かれています。そして、すべてを照らし出す「無影燈」の光の下で迎えるラストシーンは、読者に強烈な印象と、重い問いを投げかけます。
もしあなたが、人生や愛、そして死について深く考えさせられるような物語を求めているのなら、「無影燈」は間違いなく心に残る一冊となるでしょう。直江の選択と倫子の愛が織りなすこの悲しくも美しい物語は、読む者の魂を強く揺さぶる力を持っています。