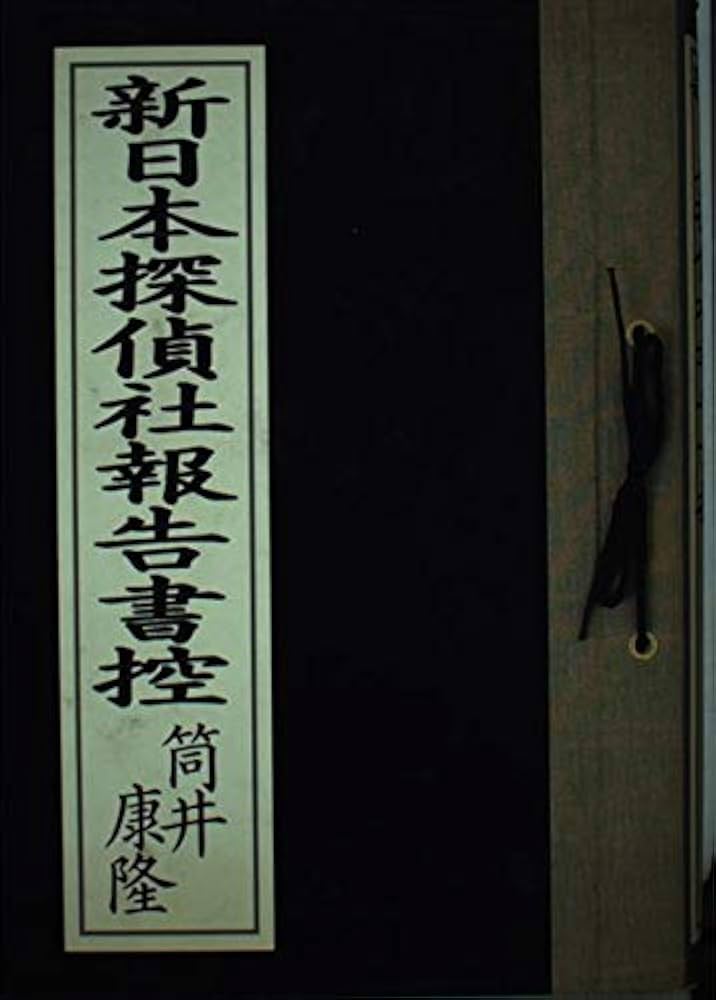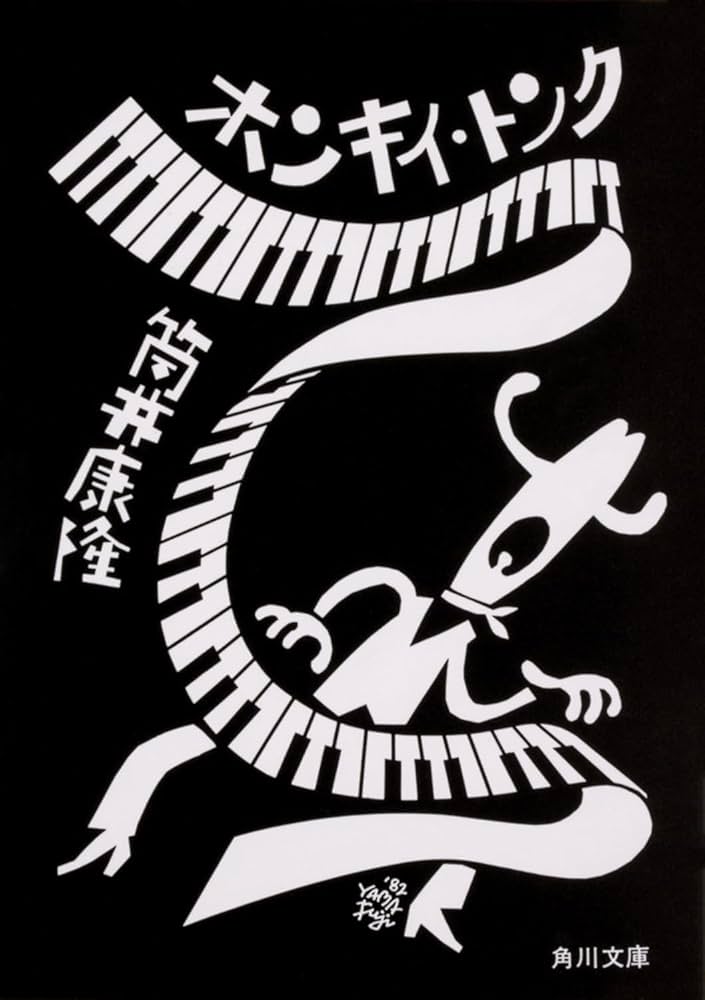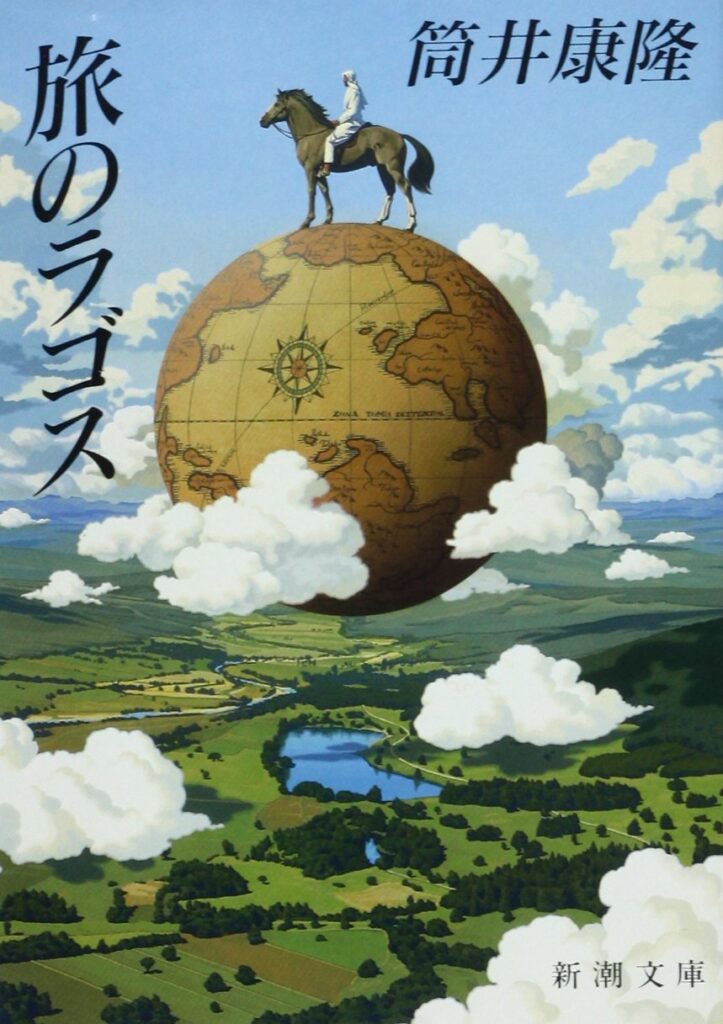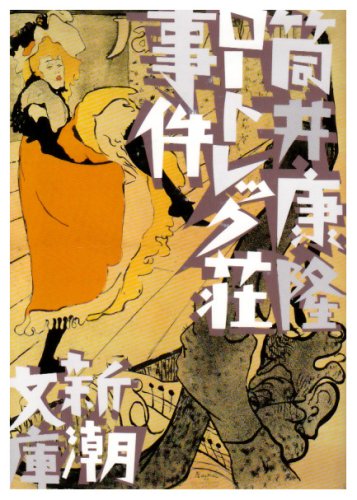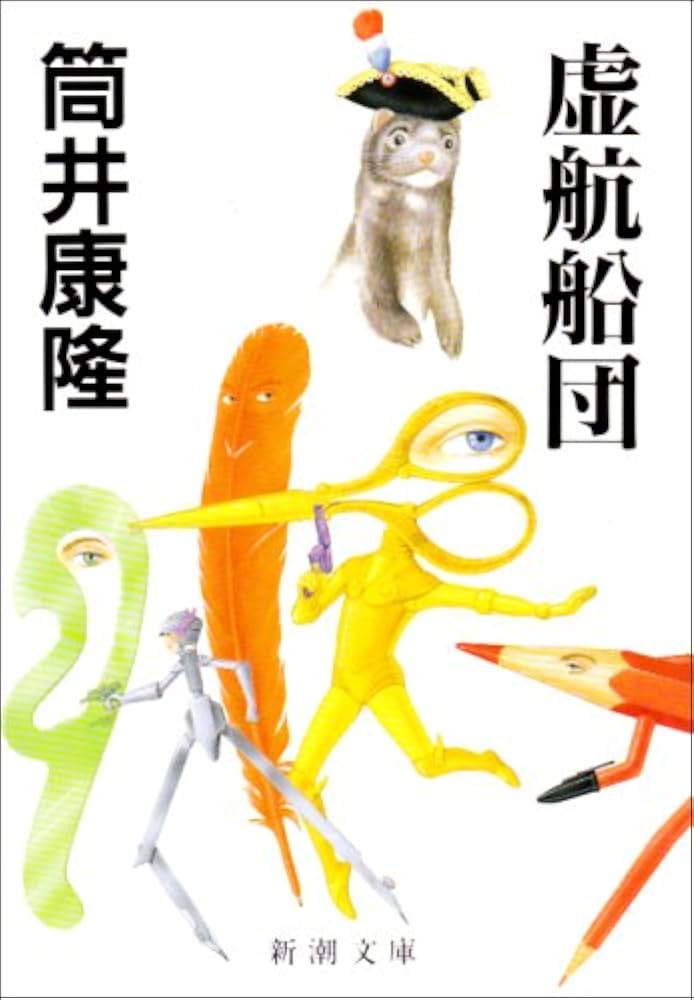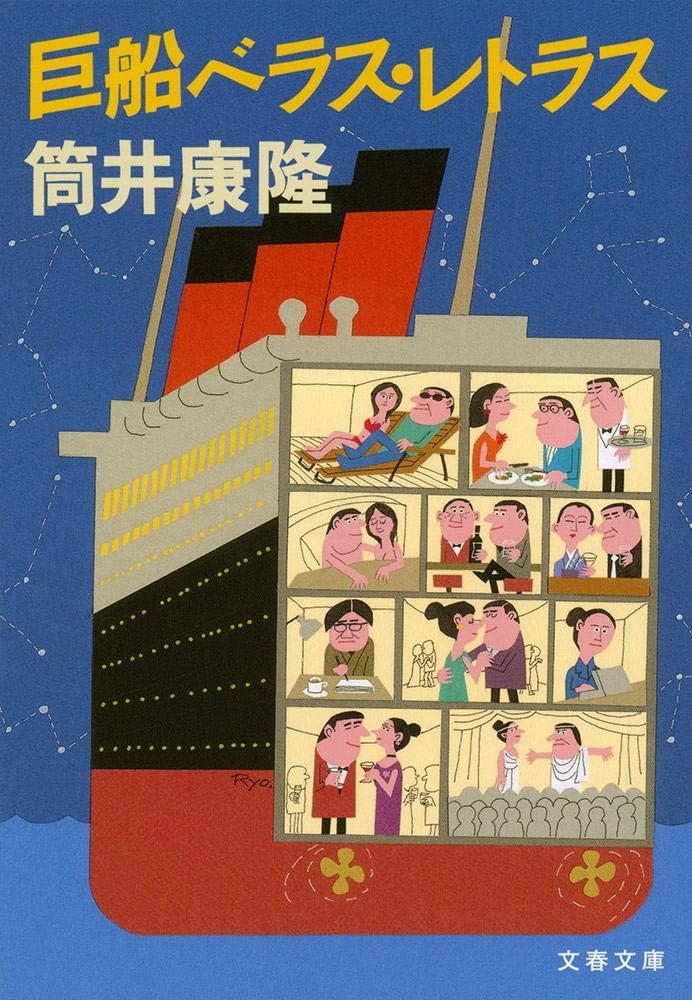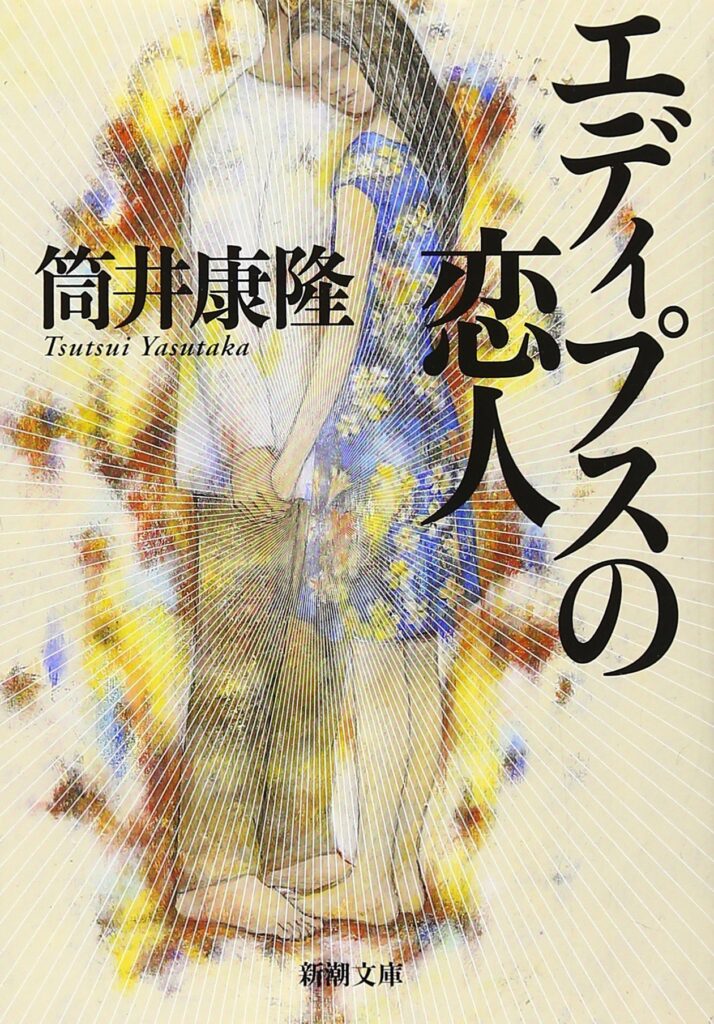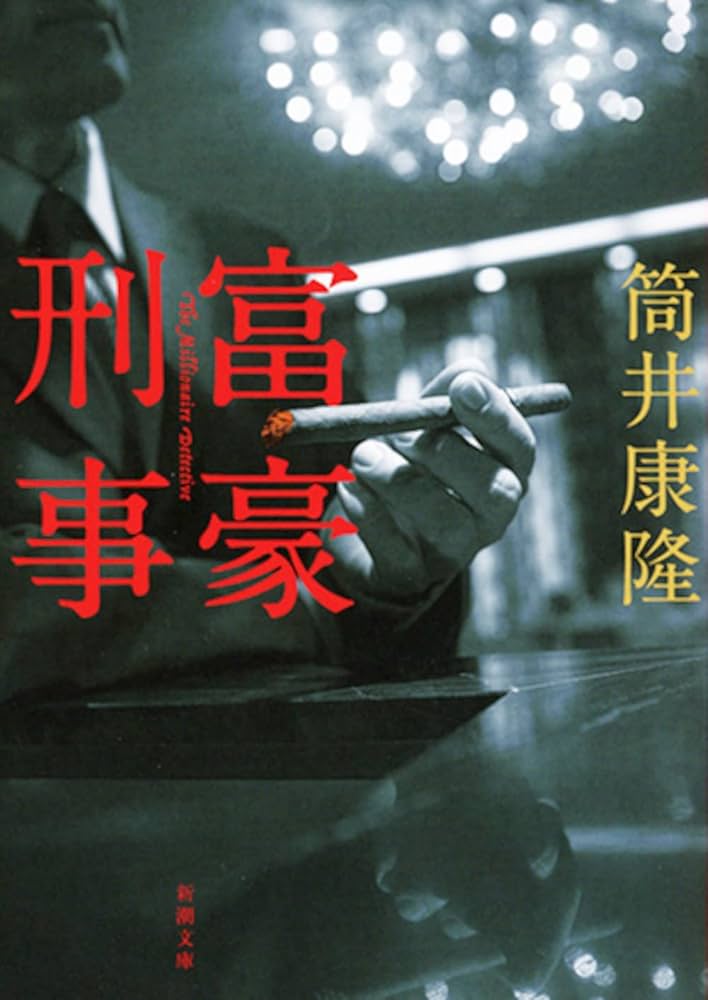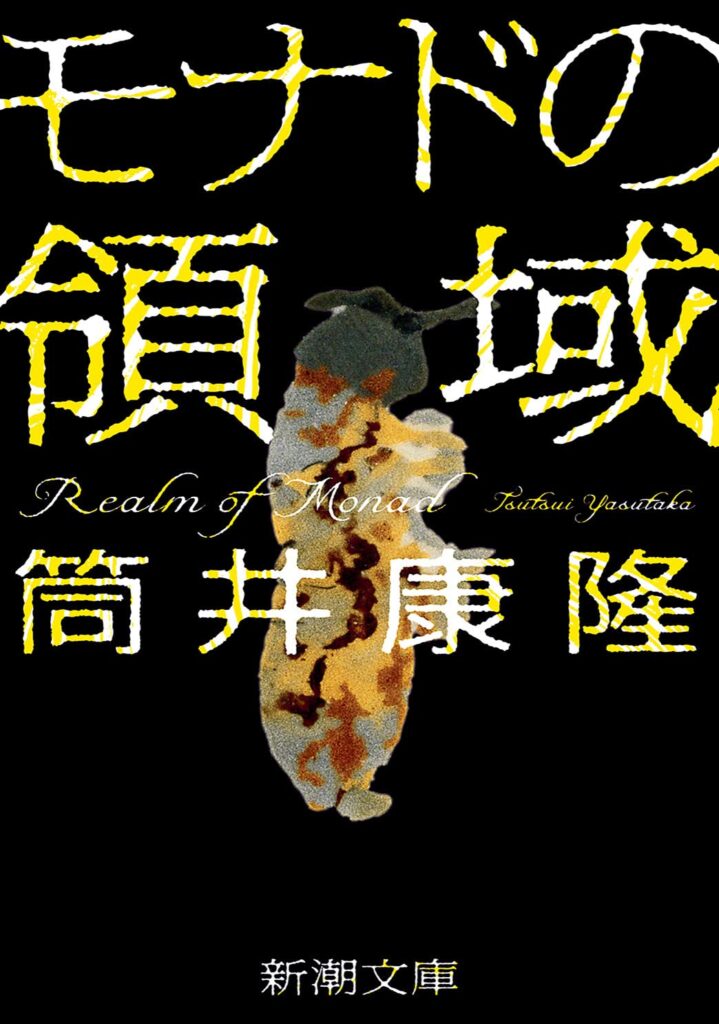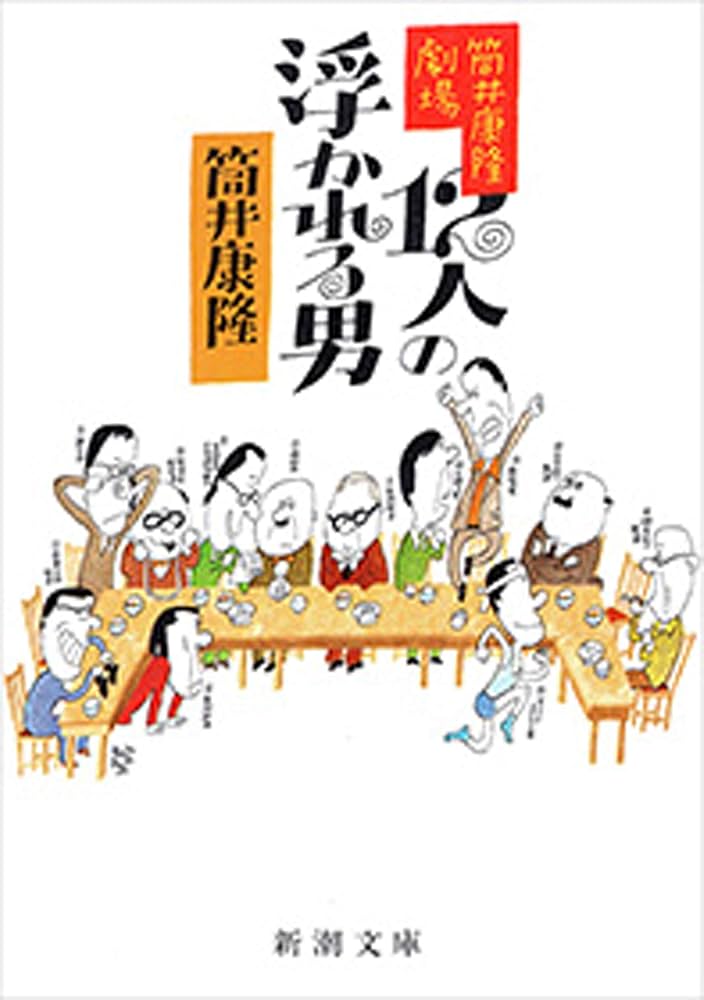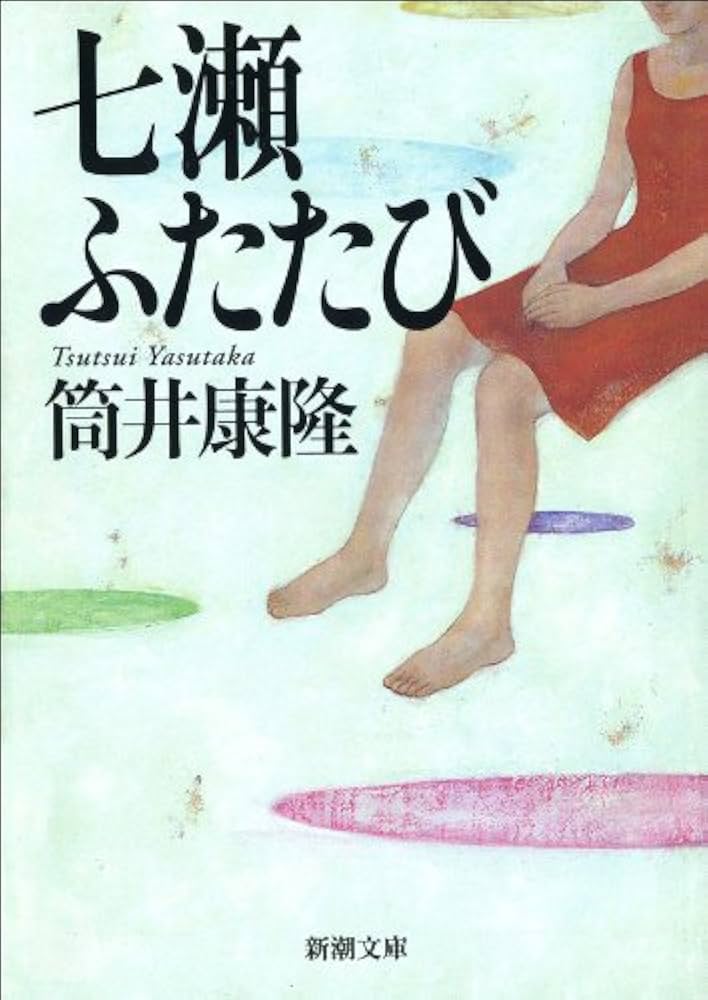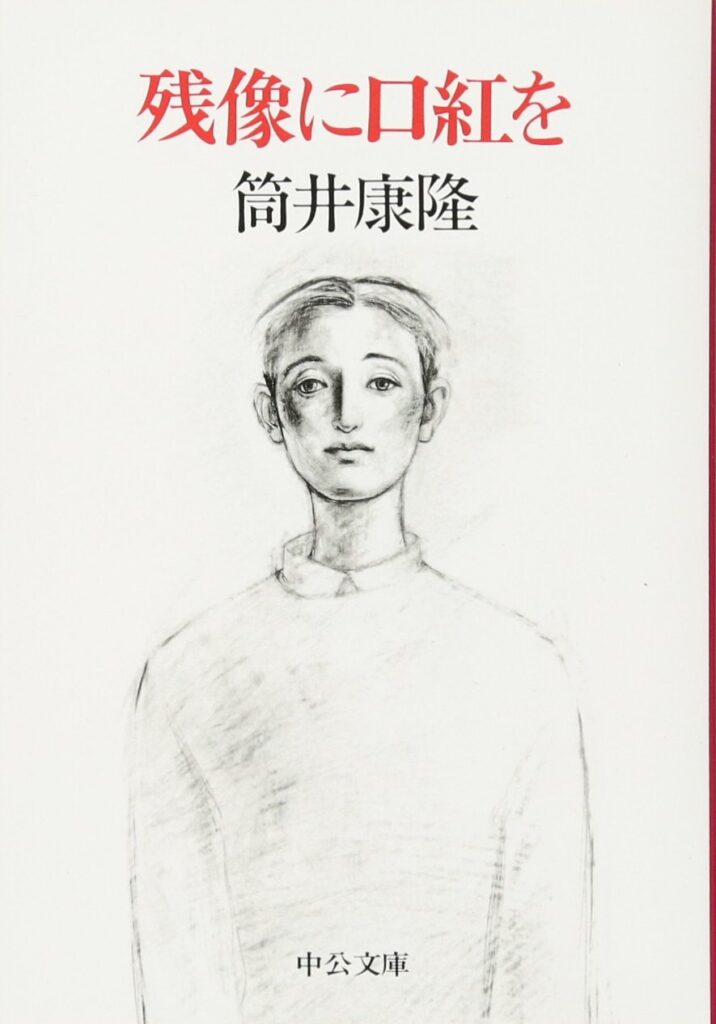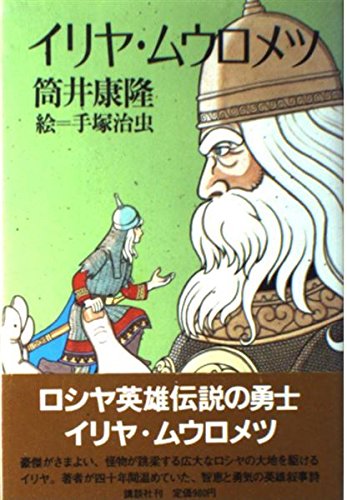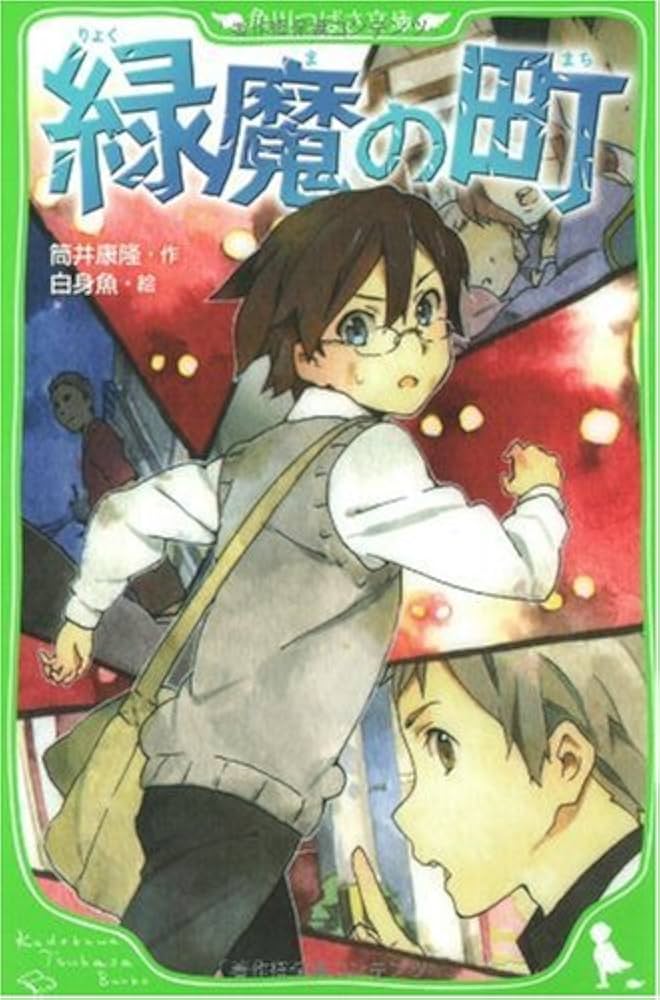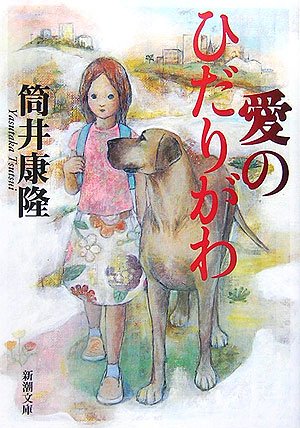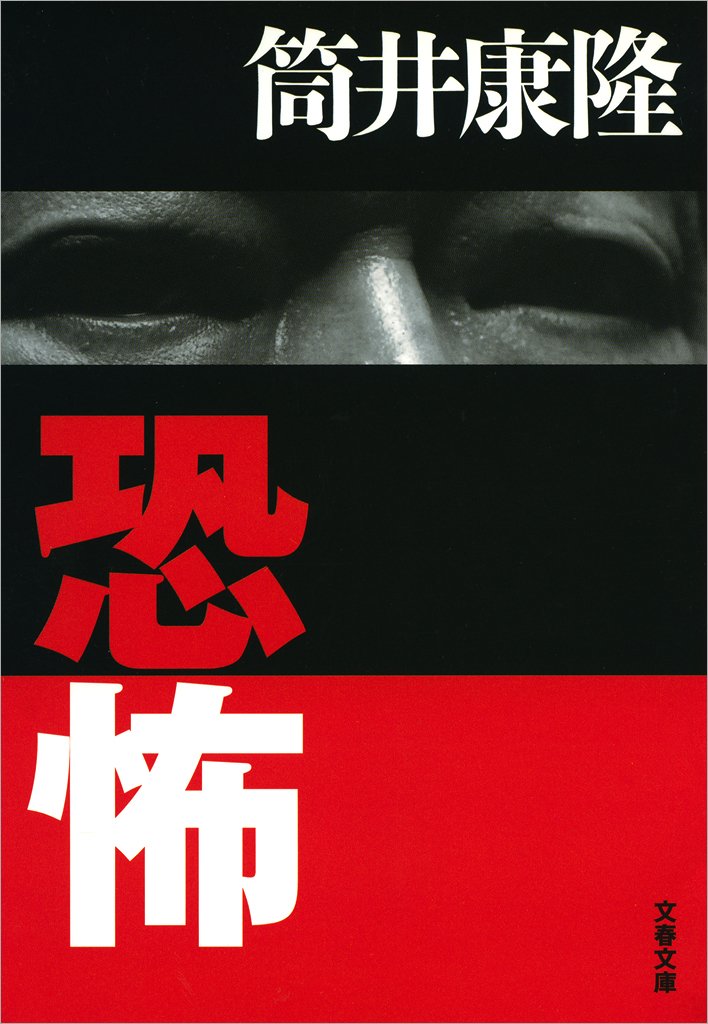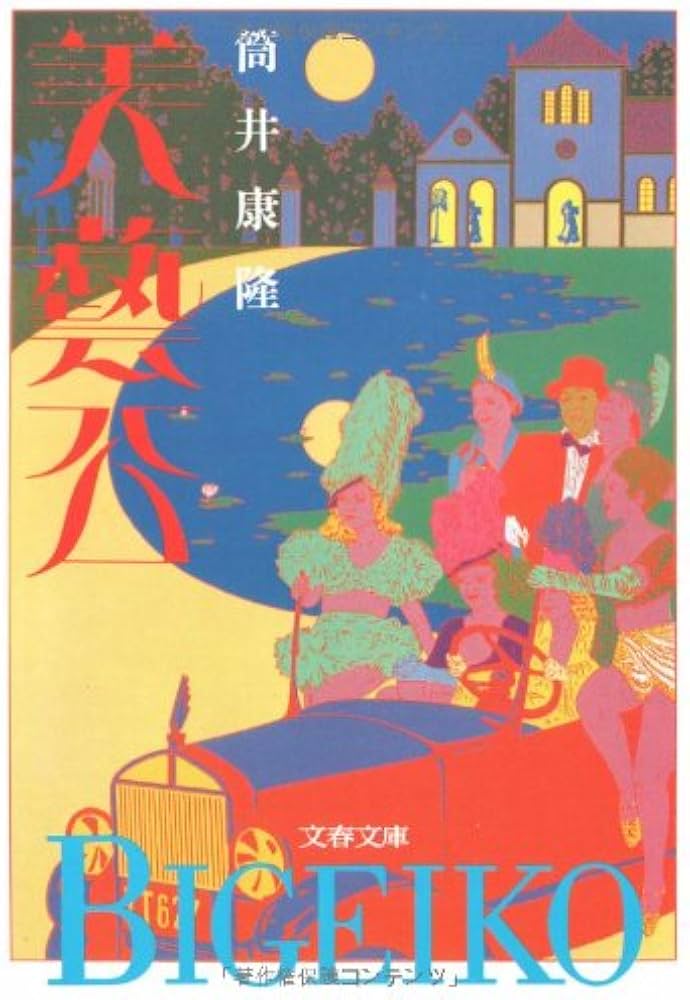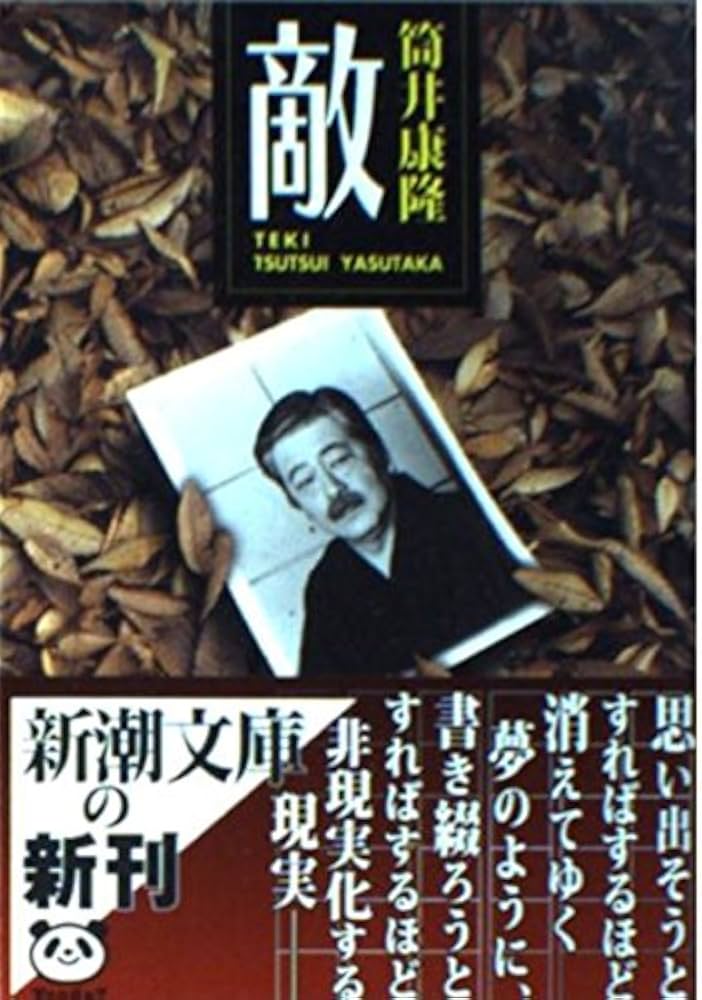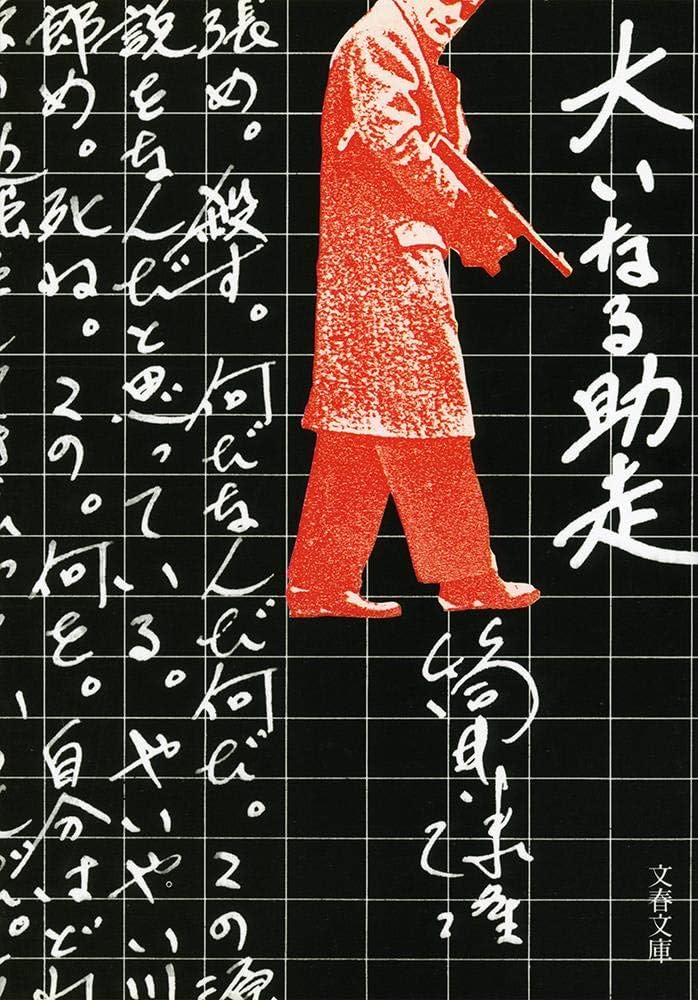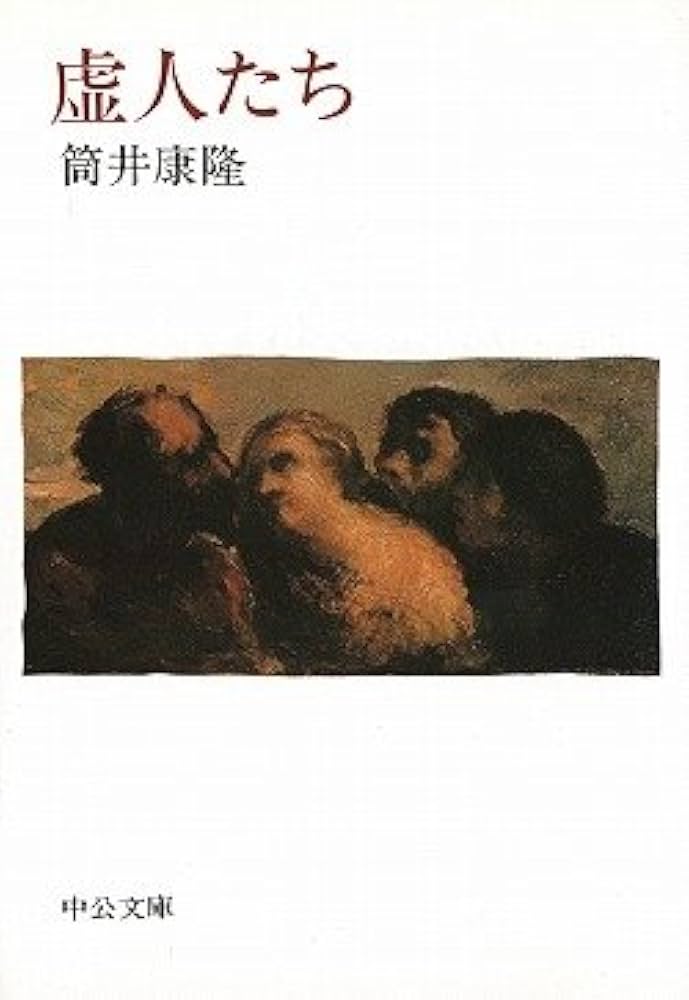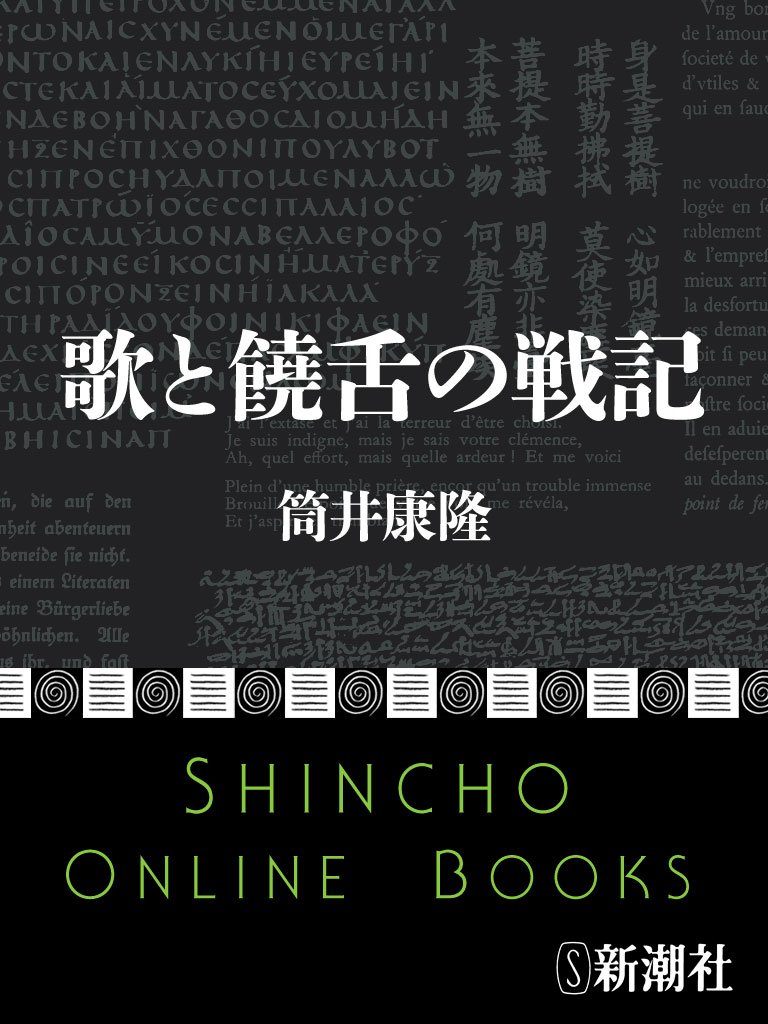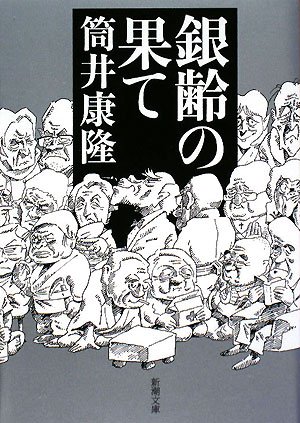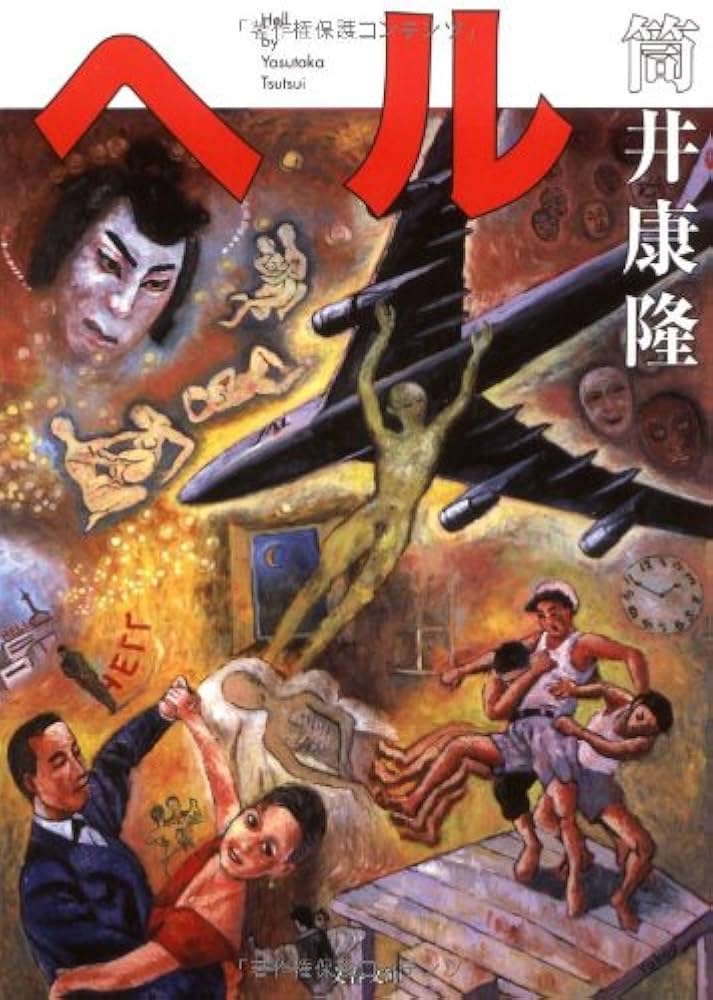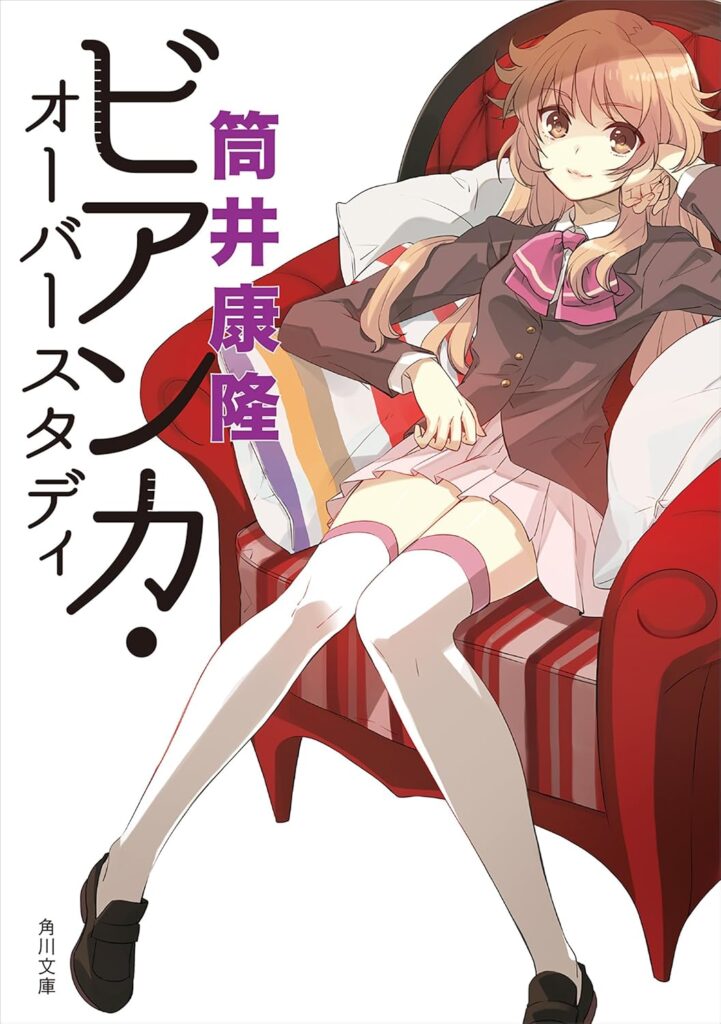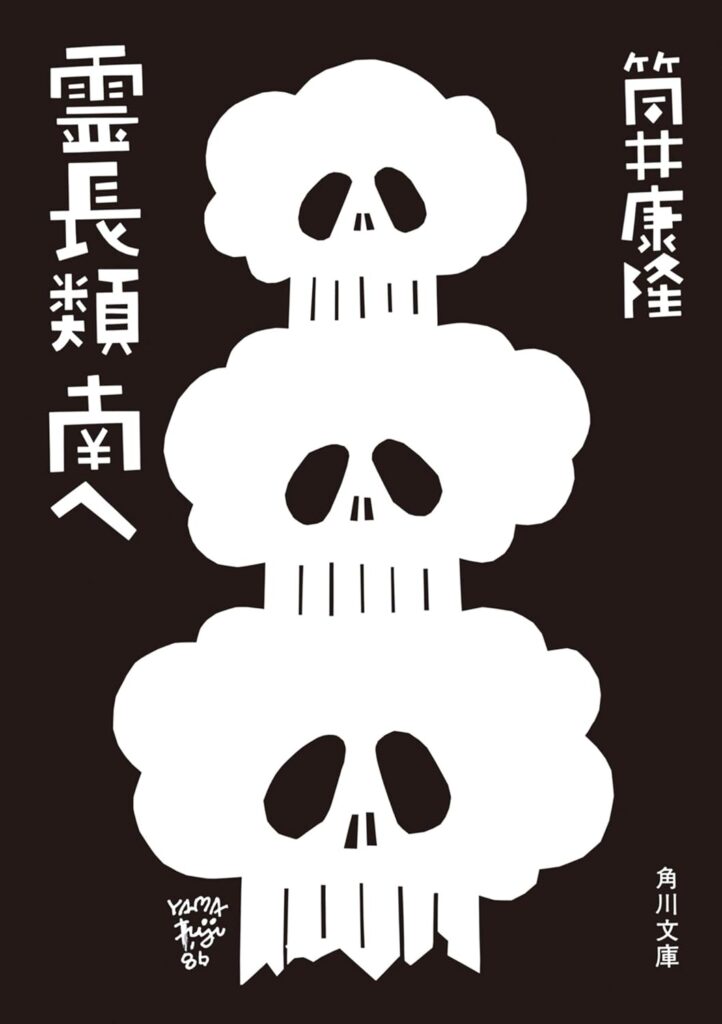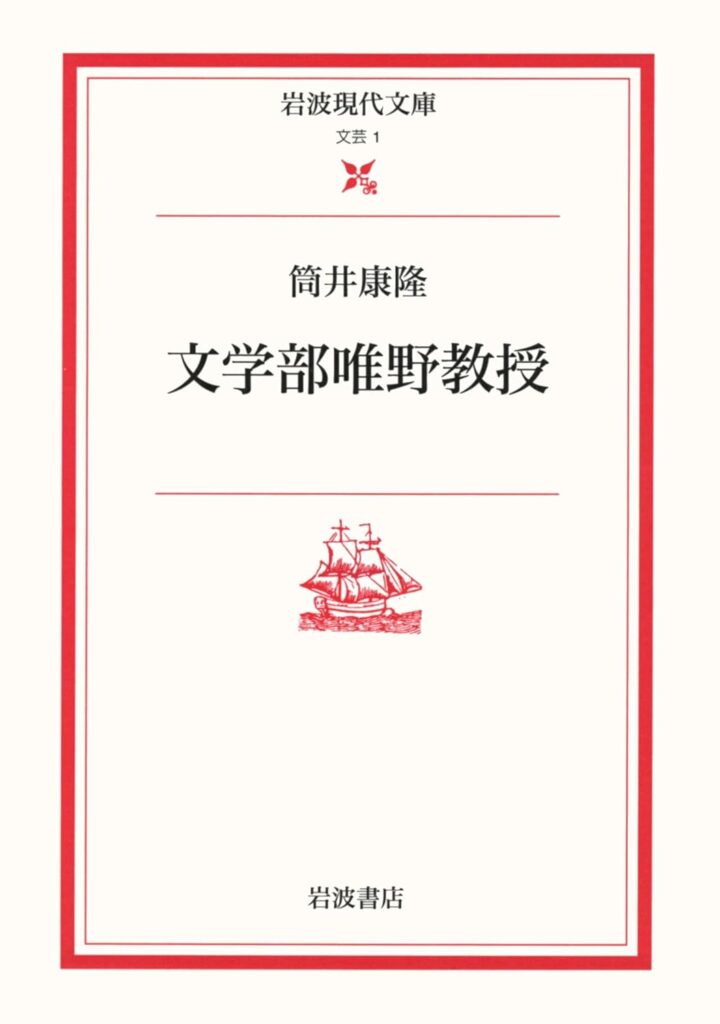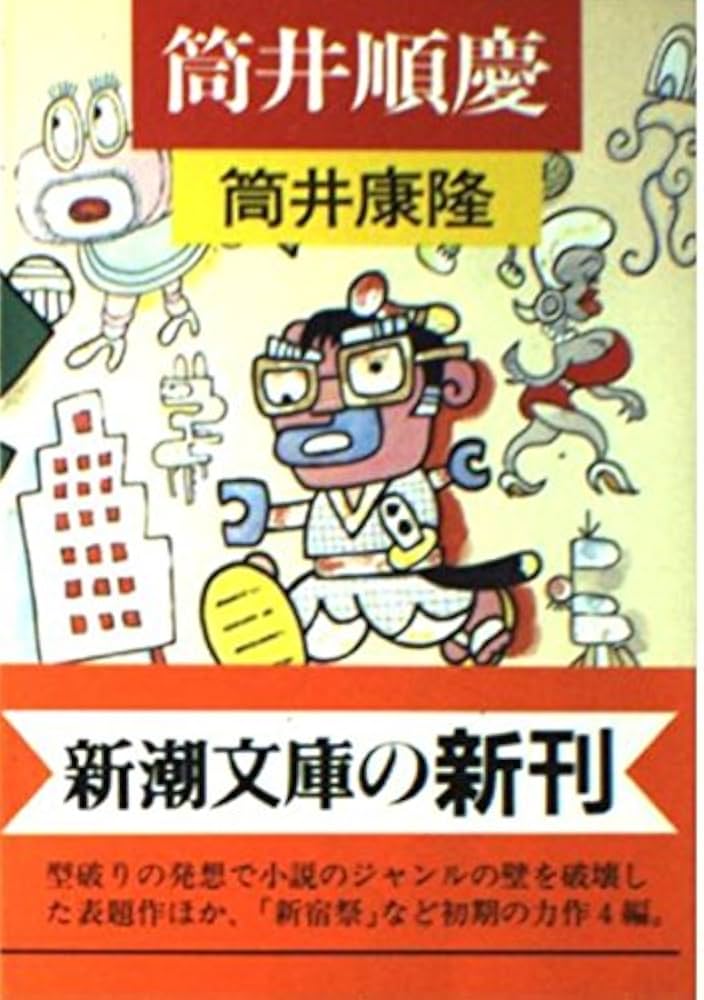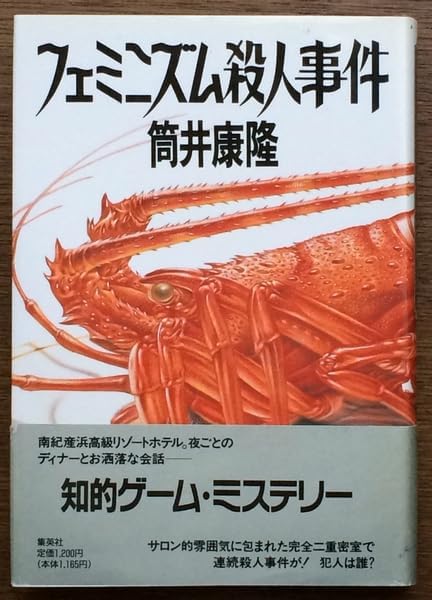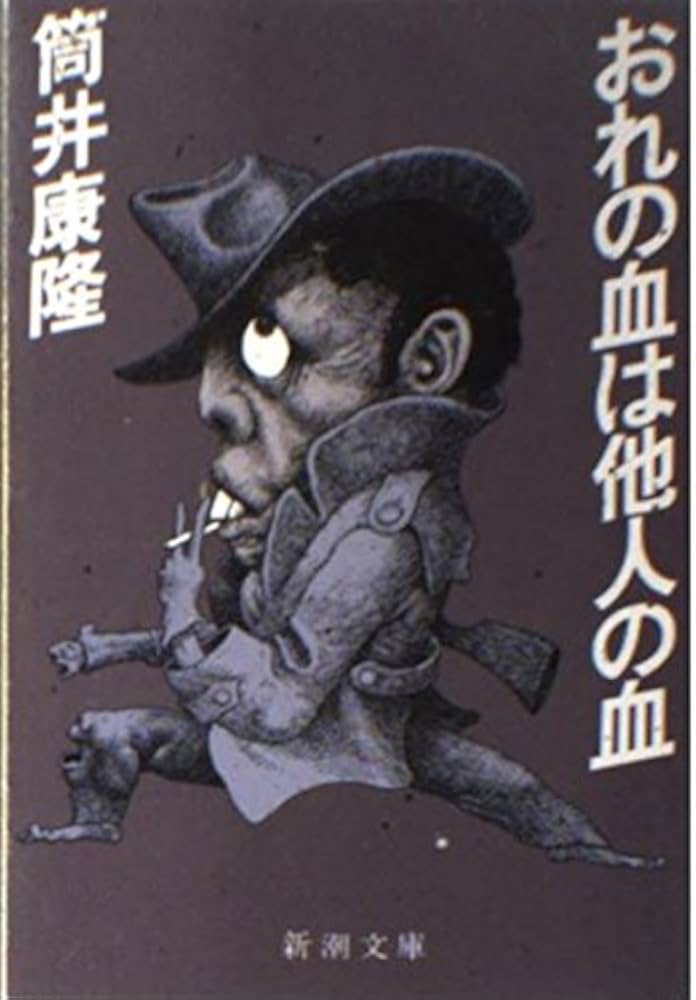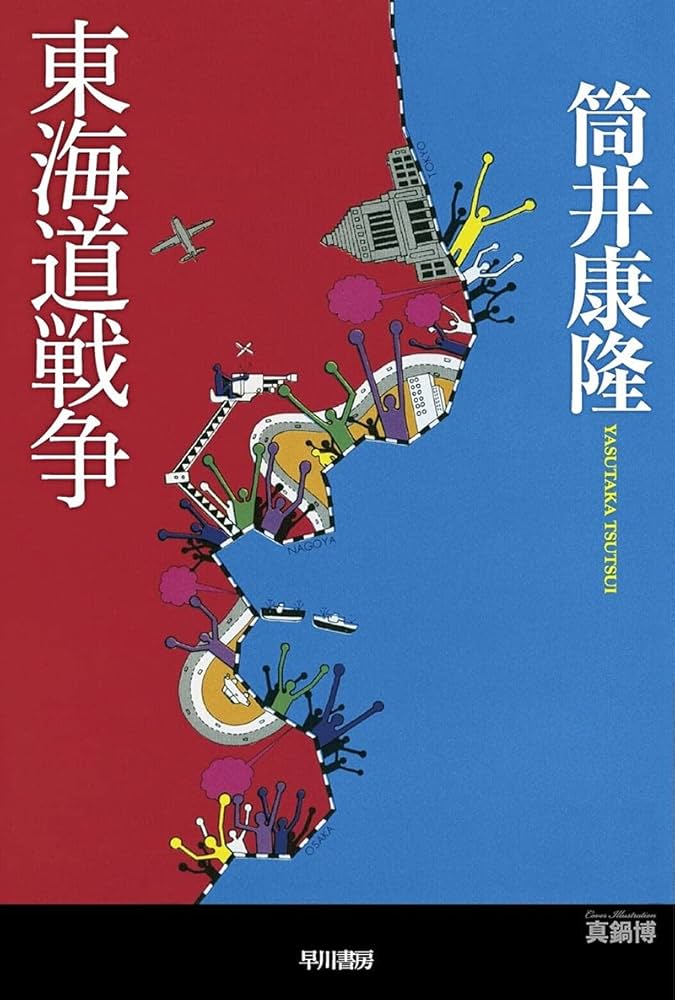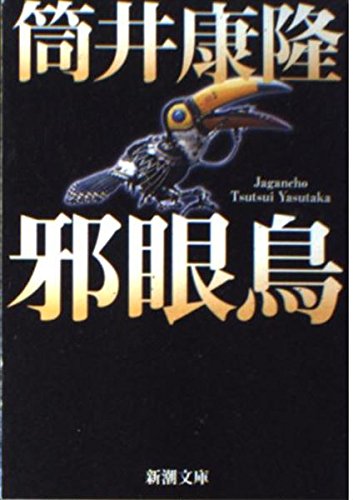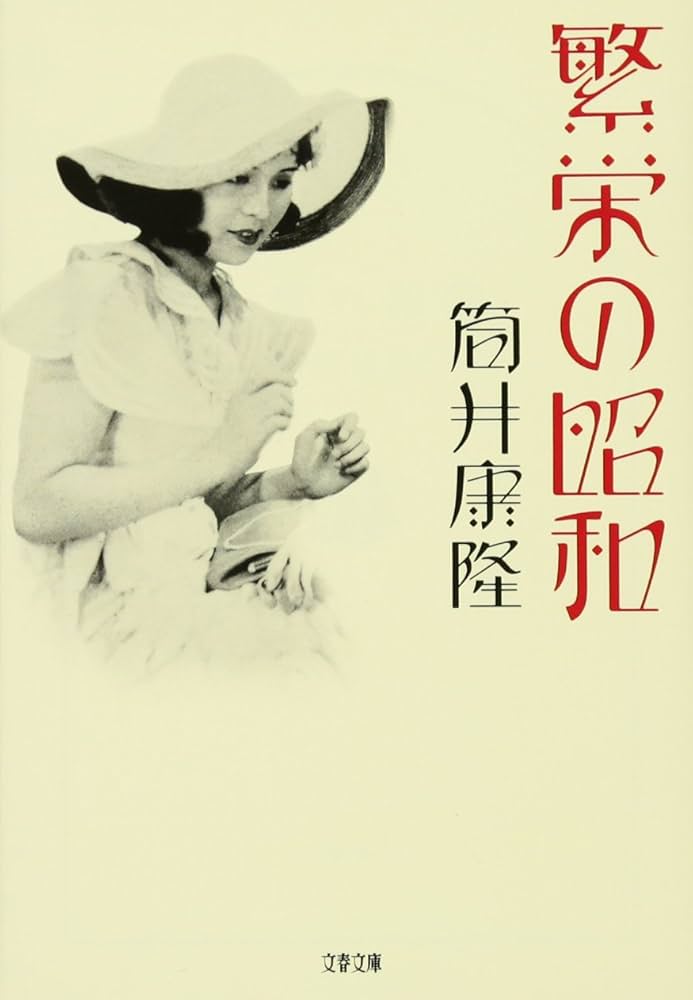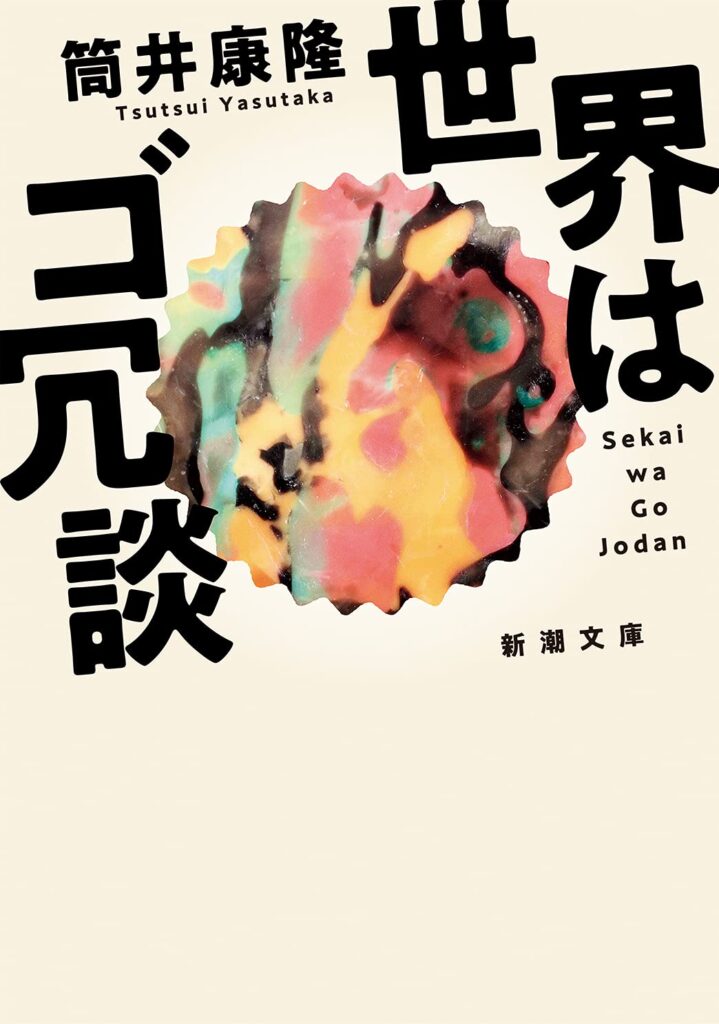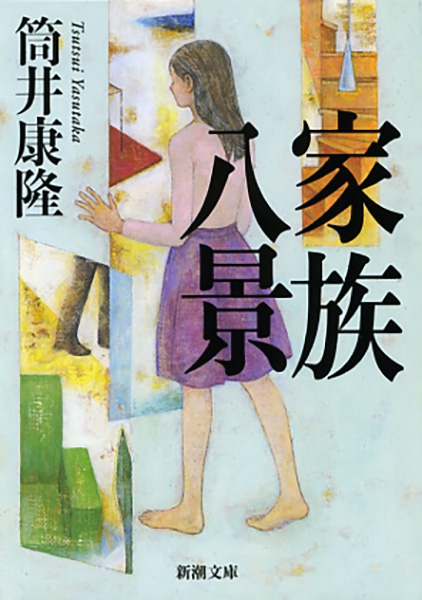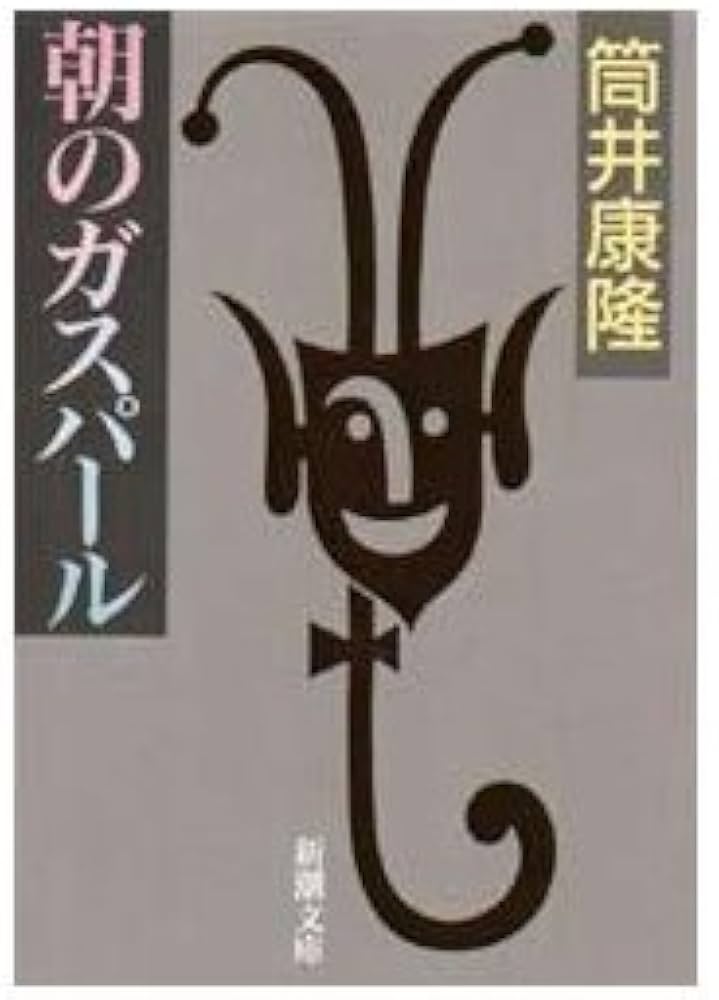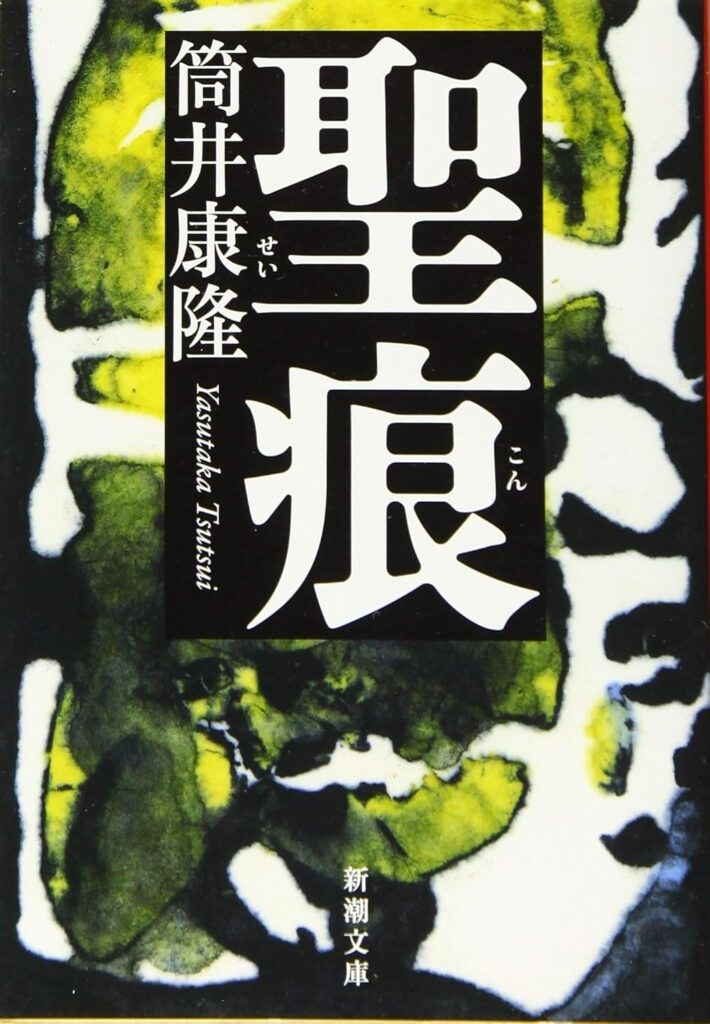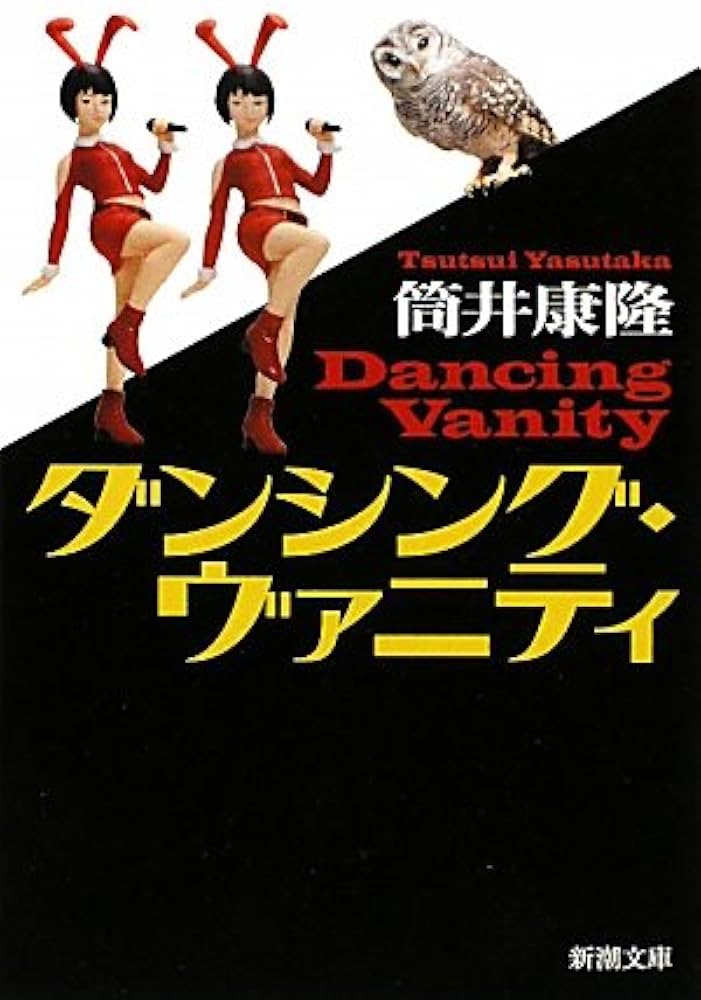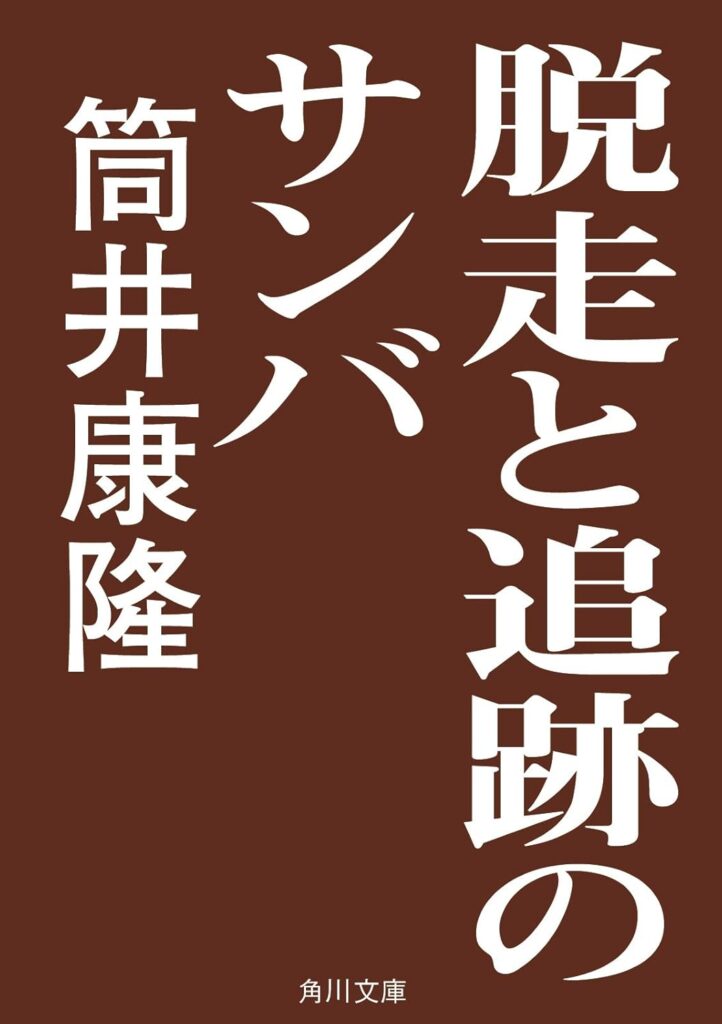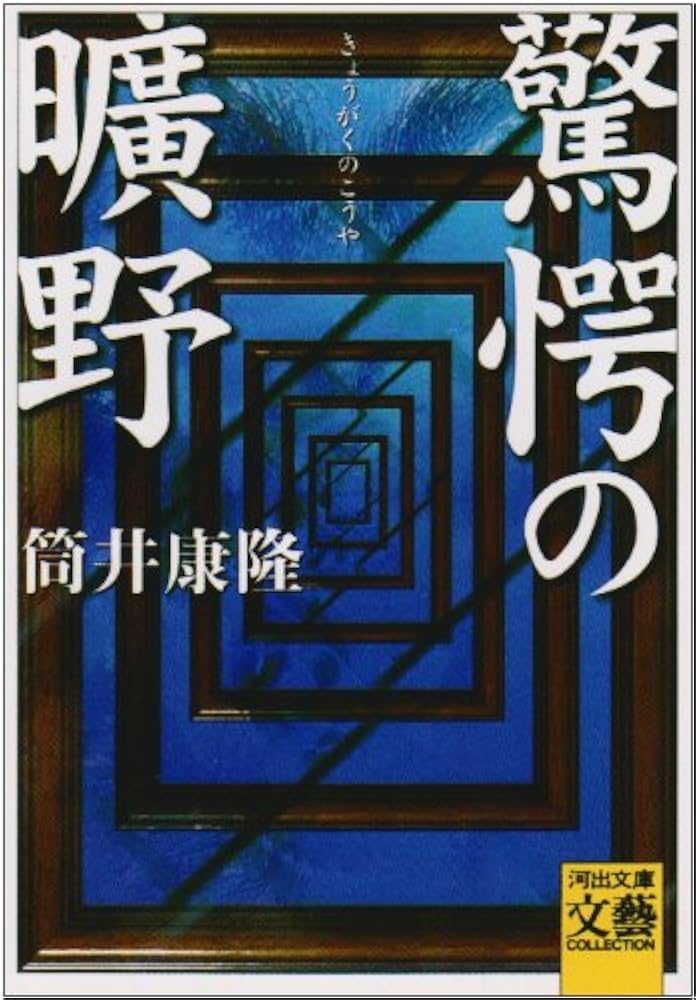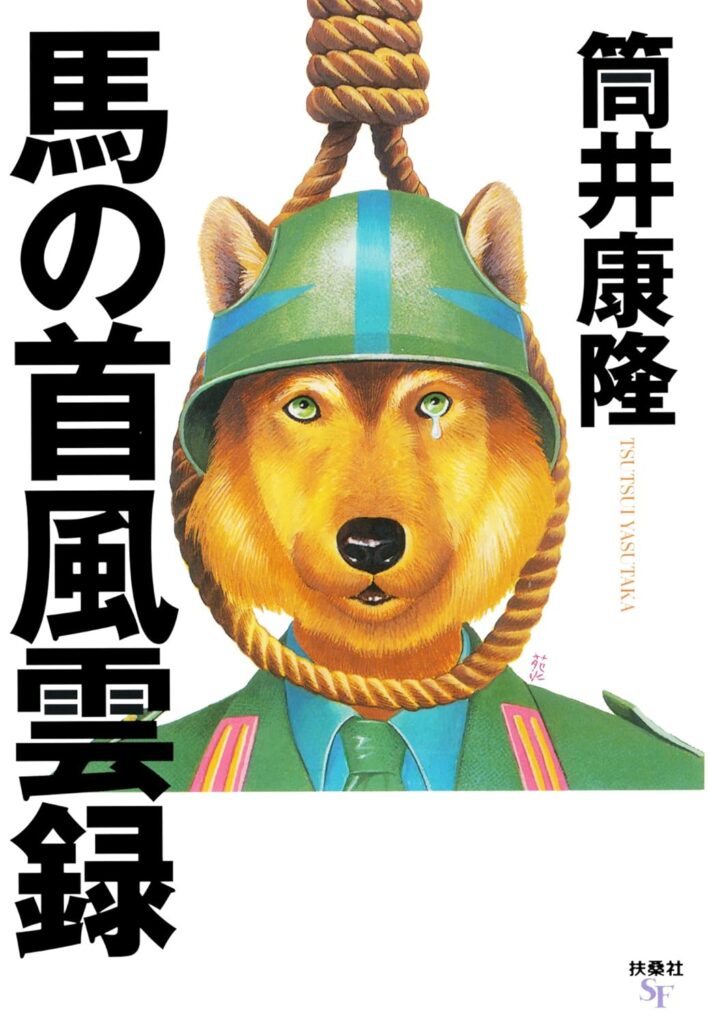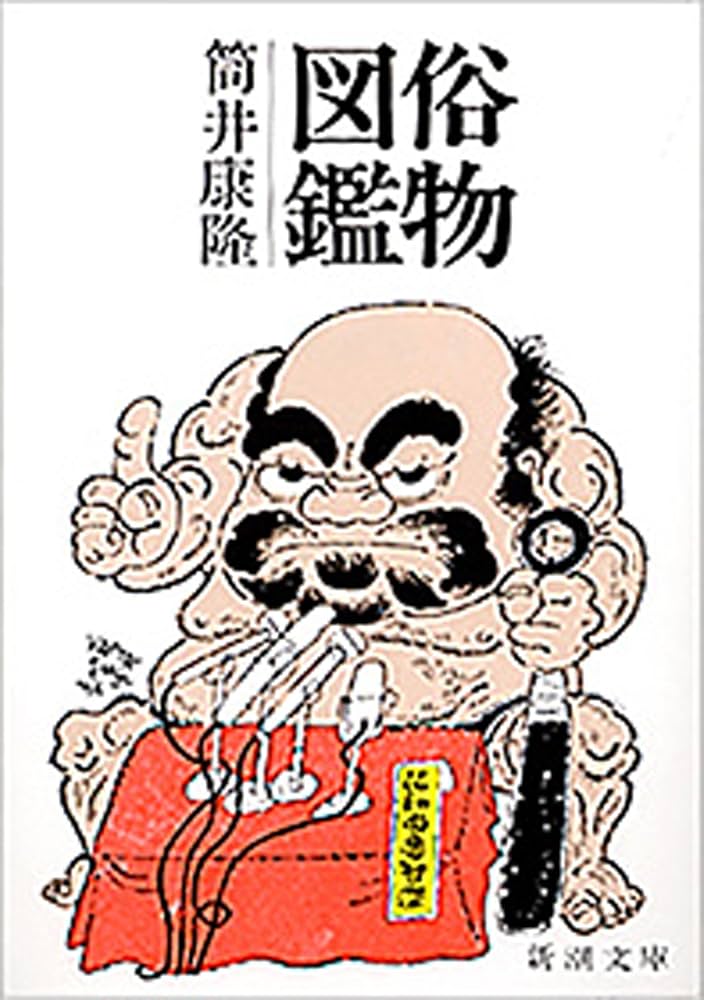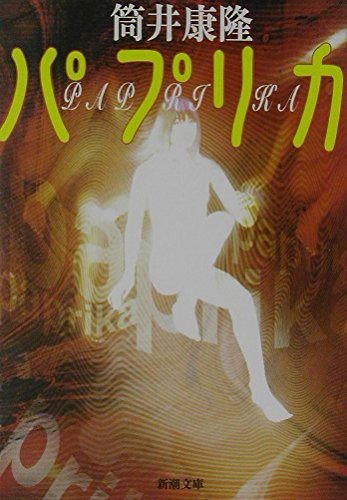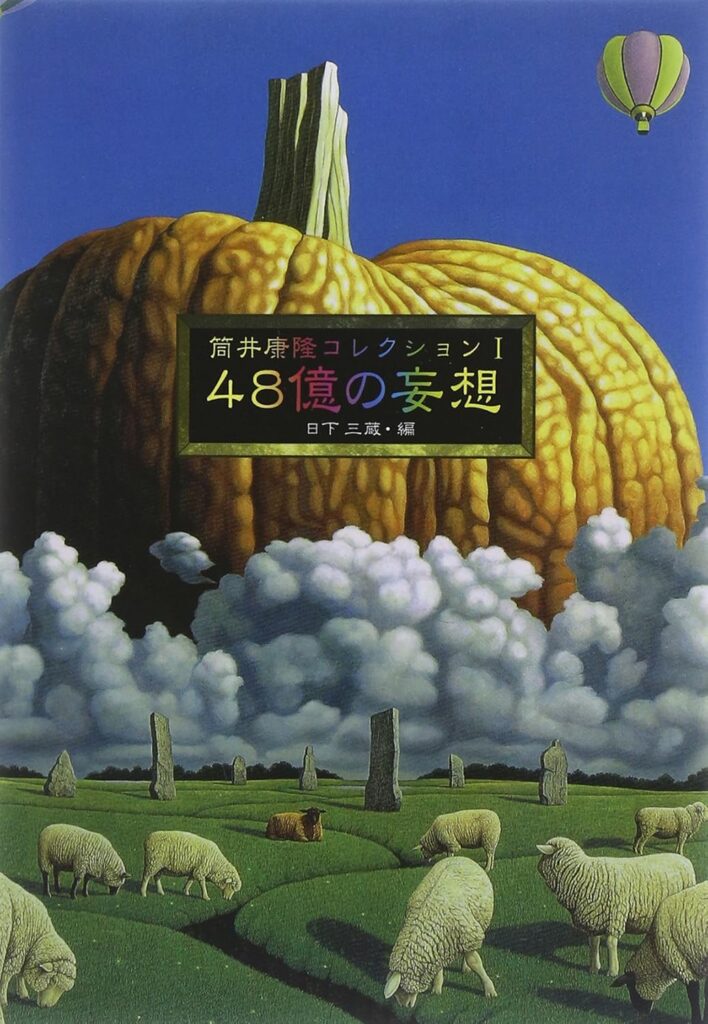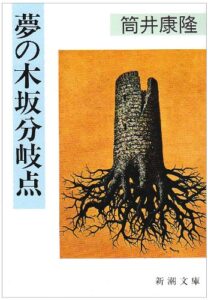 小説「夢の木坂分岐点」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「夢の木坂分岐点」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
もし、今見ているこの現実が、数ある可能性の一つに過ぎないとしたら。もし、眠りから覚めた先が、また別の夢の世界だとしたら。そんな、足元が崩れ落ちるような感覚を突き詰めていくと、一体どこへ行き着くのでしょうか。筒井康隆先生が1987年に発表したこの作品は、まさにそんな問いを私たちに投げかけてきます。
本作は、平凡なサラリーマンである主人公が、夢と現実、そしていくつものパラレルワールドをさまよう物語です。自分の名前や家族構成、職業までもが次々と変わっていく中で、「本当の自分」とは何なのかという根源的なテーマが浮かび上がってきます。第23回谷崎潤一郎賞を受賞したことからも、その文学的な評価の高さがうかがえます。
この記事では、まず物語の導入部分であるあらすじを追いかけ、その後、物語の核心に触れるネタバレを含んだ詳しい感想を綴っていきます。このめくるめく迷宮のような世界を、一緒に体験してみませんか。複雑で、少しばかり恐ろしく、そして抗いがたい魅力に満ちた『夢の木坂分岐点』の世界へ、ご案内いたしましょう。
小説「夢の木坂分岐点」のあらすじ
物語は、小畑重則という中年サラリーマンの視点から始まります。彼はプラスチック製造会社で課長を務めていますが、その日常は退屈と不満に満ちています。「出勤するのは背を裂かれるよりも憂鬱だ」と感じるほど、彼の心は乾ききっているのでした。
そんな彼の唯一の変化は、毎晩見る鮮明な夢でした。ある時はやくざになっていたり、またある時は時代劇の中にいたり。夢から覚めるたびに、灰色の現実との落差にうんざりする日々。しかし、そのうち夢と現実の境界線は、少しずつ曖昧になっていきます。
ある日、彼は通勤電車の中で、今まで降りたことのない「夢の木坂分岐点」という駅の存在に気づきます。その名前に強く惹かれた彼は、衝動的に電車を降りてしまいます。この駅から西へ向かえばサラリーマンの自分、東へ向かえば作家の自分、そして乗り換えずに進めばまた別の人生が待っているというのです。
この「分岐点」に降り立ったことをきっかけに、彼の自己は分裂し、増殖を始めます。小畑重則であり、小畑重昭であり、大村常賢であり、大村常昭でもある。それぞれの世界で異なる人生を歩む彼は、一体どこへ向かうのでしょうか。物語は、読者を現実と虚構が入り混じる迷宮の奥深くへと誘い込んでいくのです。
小説「夢の木坂分岐点」の長文感想(ネタバレあり)
この『夢の木坂分岐点』という作品を読み解くことは、まるで複雑な迷路に足を踏み入れる体験そのものだと思います。ここからは、物語の核心に触れながら、このめまいがするような世界の魅力をじっくりと語っていきたいと思います。
まず物語の冒頭、主人公である小畑重則の姿は、多くの現代人が共感できるものかもしれません。プラスチック製造会社の課長という、いかにも平凡な肩書。変化のない毎日に倦怠感を抱き、現実からの逃避を願う心。彼の「出勤するのは背を裂かれるよりも憂鬱だ」という感覚は、彼の精神がどれほど追い詰められているかを示しています。
この現実の息苦しさこそが、物語の重要な出発点なのです。彼は、やくざになる夢や、若侍が登場する夢など、現実とはかけ離れた世界を夢に見ます。それは単なる現実逃避ではなく、彼の心が「ここではないどこか」を渇望している証拠なのでしょう。そして、この渇望が、やがて彼の現実そのものを侵食し、解体していく力となっていきます。
物語が大きく動き出すのは、主人公の自己が分裂を始めてからです。小畑重則だったはずの彼は、いつの間にか小畑重昭という名前になっています。さらに、サラリーマンではなく作家として生きる大村常賢や大村常昭というペルソナまで現れるのです。この変化は唐突で、明確な説明はありません。読者も主人公と共に、大きな戸惑いの中に放り込まれます。
驚くべきことに、変化するのは主人公の名前や職業だけではありません。彼の妻や娘の名前、性格までもが、それぞれの世界で微妙に異なっているのです。これは、単なる「もしもの人生」を描いているのではありません。安定しているはずの自己という核が溶け出し、それに伴って彼を取り巻く世界のすべてが流動的になっていく。その恐ろしさと不安が、じわじわと伝わってきます。
この物語の象徴であり、まさにタイトルにもなっているのが「夢の木坂分岐点」という駅の存在です。主人公がそれまで存在すら知らなかったこの乗り換え駅は、異なる人生への入り口として描かれます。西へ行けばサラリーマンの小畑重則、東へ行けば作家の大村常賢、乗り換えなければ成功した作家の大村常昭の住む場所へと繋がっている。
彼がこの駅で電車を降りるという行為は、決められた日常のレールから自ら外れるという決意の表れです。彼はこの分岐点の先にあるという「夢の木」を探し求めますが、それは同時に「狂気」とも隣り合わせの危険な探求でもあります。果てしなく続く廊下のある日本家屋や、家の軒先を路面電車が走る下町など、彼が迷い込む風景は、どれも現実離れしていて、不安をかき立てます。
物語のもう一つの重要な仕掛けとして、「サイコドラマ(心理劇)」が登場します。特にサラリーマンである小畑重昭は、このサイコドラマのワークショップに傾倒していきます。参加者が即興で役割を演じることで、自身の内面を探るというこの手法は、本作のテーマと深く結びついています。
あるセッションでは、主人公は彼が苦手とする上司の槙口部長と役割を交換します。上司を演じることで、彼は普段意識していなかった自分自身の考えや感情に気づかされるのです。このようにサイコドラマは、彼の混乱した夢を解き明かす鍵として機能する一方で、物語の構造そのものを映し出す鏡のようにもなっています。
考えてみれば、この小説全体が、主人公が様々な「自分」という役割を演じる、壮大なサイコドラマのようではありませんか。「うまくいかないのは演技に失敗しただけ」で、「役割は唯一の自分ではない」という考え方は、アイデンティティが揺らぐ恐怖を乗り越えるための一つの答えなのかもしれません。
しかし、面白いのは、もう一人の自分である作家の大村常昭が、このサイコドラマを否定的に見ている点です。彼は、サイコドラマが他者の視点を介入させることで、かえって個性を破壊し、社会に従属させてしまうものだと考えます。一つの手法に対するこの両極端な見方は、自己を探求する道のりが、決して単純なものではないことを示唆しているように感じます。
物語が進行するにつれて、主人公は「夢の中で夢を見る」という、さらなる深みにはまっていきます。目覚めてもそこは安定した現実ではなく、また別の夢の階層でしかない。彼は次第に、自分自身が誰かの作った物語の登場人物なのではないか、という自覚さえ持ち始めます。
そして、ついに彼は一つの結論に至ります。それは、「現実と虚構と夢、この三つの世界を等価値と見做して生きる」という哲学です。どれが本物でどれが偽物か、などと区別すること自体を放棄する。それは、混乱の極致から生まれた、ある種の諦念であり、同時に新しい生き方の発見でもあったのかもしれません。
この境地は、「芸名であってもペンネームであっても役名であってもおれはただおれであればいいのだ」という言葉に集約されています。単一の「本当の自分」を探し求めるのではなく、変化し続ける多様な自己のすべてを受け入れる。それは、恐ろしいほどの孤独と引き換えに手に入れた、究極の自由だったのではないでしょうか。
物語の軌道は、どこか特定のゴールに向かって進むわけではありません。むしろ、蛇のように曲がりくねりながら、ひたすら深みへと沈んでいくようです。主人公たちは、夢のような世界の中で、固定された意味を求めることなく、ただ存在し、動き続けているように見えます。
やがて、「夜の夢こそまこと」という言葉が登場します。これは、私たちが普段拠り所にしている「現実」というものが、いかに脆く、不確かなものであるかを突きつける言葉です。目覚めとは、安定への回帰ではなく、「新たな夢への横滑り」に過ぎないのかもしれない。そう考えると、目の前の日常もまた、少し違って見えてくるから不思議です。
では、この物語はどこで終わるのでしょうか。筒井先生の作品には、明確な結末を用意せず、読者の解釈に委ねるものが少なくありません。『夢の木坂分岐点』もまた、その典型と言えるでしょう。物語の終盤、あるサイコドラマの場面がクライマックスとして描かれますが、それは解決というより、さらなる混迷への扉のようにさえ感じられます。
結局のところ、主人公が求めていたものは何だったのか。その問いに、明確な答えは与えられないまま物語は幕を閉じます。彼は夢の世界で消滅したのか、あるいは死を受け入れたのか。様々な解釈が可能ですが、私は、彼はどこにも辿り着かなかったのだと思います。いや、辿り着かないことこそが、この物語の「結末」だったのではないでしょうか。
タイトルの「分岐点」とは、通過する場所ではなく、存在の状態そのものを指しているのかもしれません。つまり彼は、無数の可能性が枝分かれし続ける「夢の木坂分岐点」という場所に、永遠に留まり続けるのです。それは、安定した自己という幻想の崩壊であり、同時に、絶え間なく変化し続ける意識の連続体として生きるという、新たな存在様式の確立だったとも言えるでしょう。この終わりなき流転こそが、人間の生の真実なのだと、この物語は静かに語りかけているように、私には思えるのです。
まとめ
小説『夢の木坂分岐点』は、単なるSFや幻想文学という枠には収まらない、私たちの自己認識そのものを揺さぶる力を持った作品でした。日常に埋没したサラリーマンが、夢と現実の境界を失い、いくつもの自分を生きる姿は、読んでいてめまいがするほどの体験です。
物語は、読者に明確な答えを与えてはくれません。サイコドラマという手法を通じて自己を探求するものの、そこには救いと同時に危うさも潜んでいます。最終的に主人公が行き着く「すべてを等価値と見なす」という境地は、解放であると同時に、永遠の迷宮に閉じ込められることでもあるのかもしれません。
この物語は、「本当の自分とは何か?」という問いに対して、唯一絶対の答えなど存在しない、ということを示してくれます。私たちは皆、無数の可能性が分岐する「夢の木坂分岐点」に立っているのかもしれません。自分の存在に確信が持てなくなった時、この物語は恐ろしくも魅力的な道標となってくれるはずです。
もしあなたが、きれいにまとまった物語よりも、読んだ後もずっと考えさせられるような、心に棘を残す作品を求めているのなら、『夢の木坂分岐点』はまさにうってつけの一冊です。ぜひ、この迷宮に足を踏み入れてみてください。