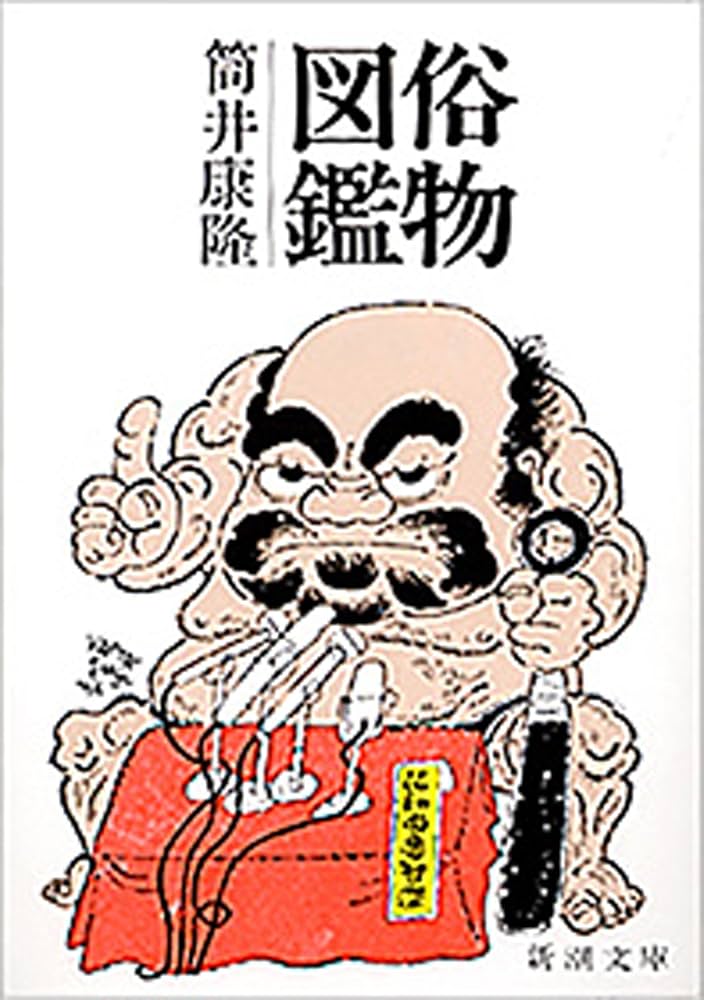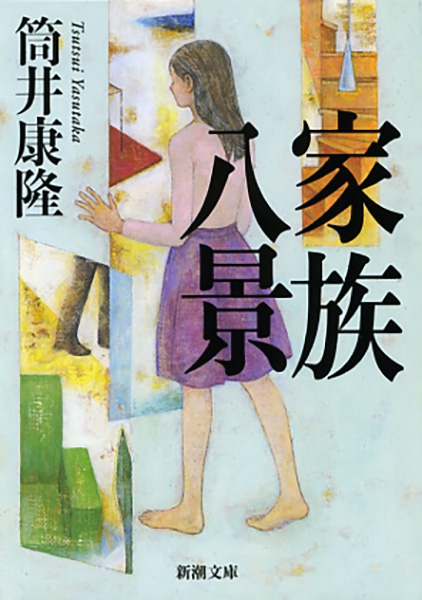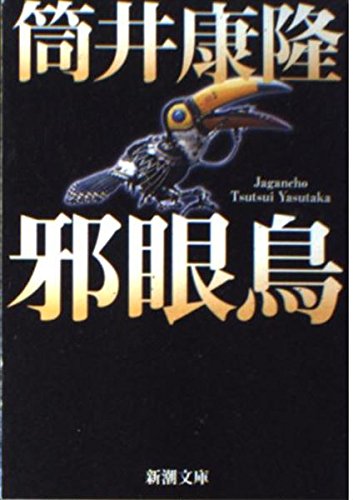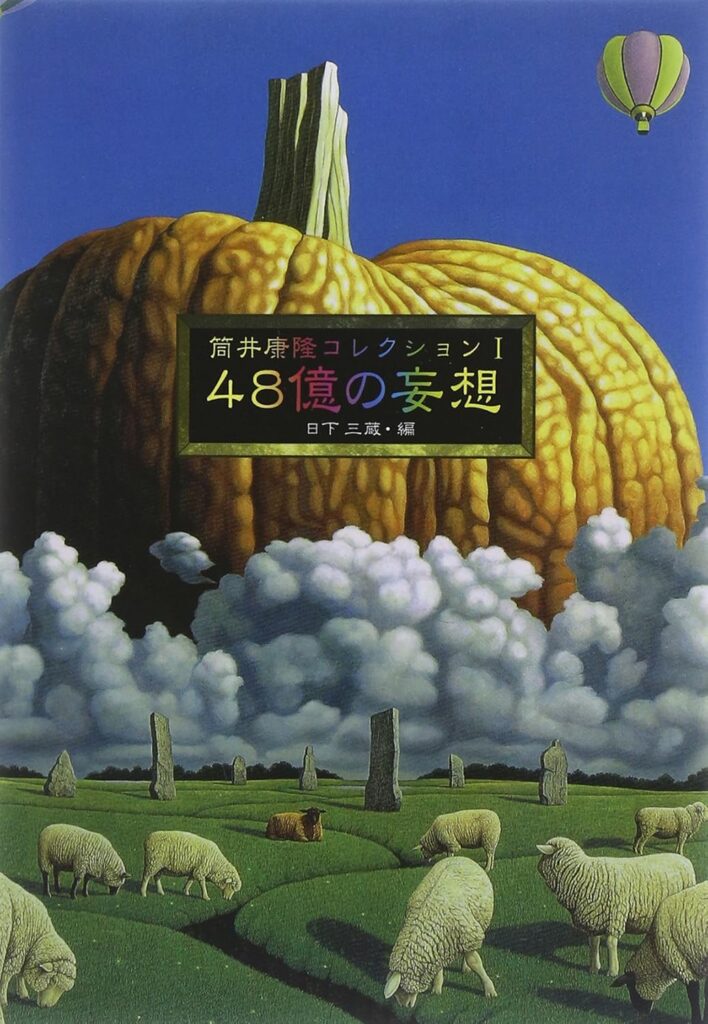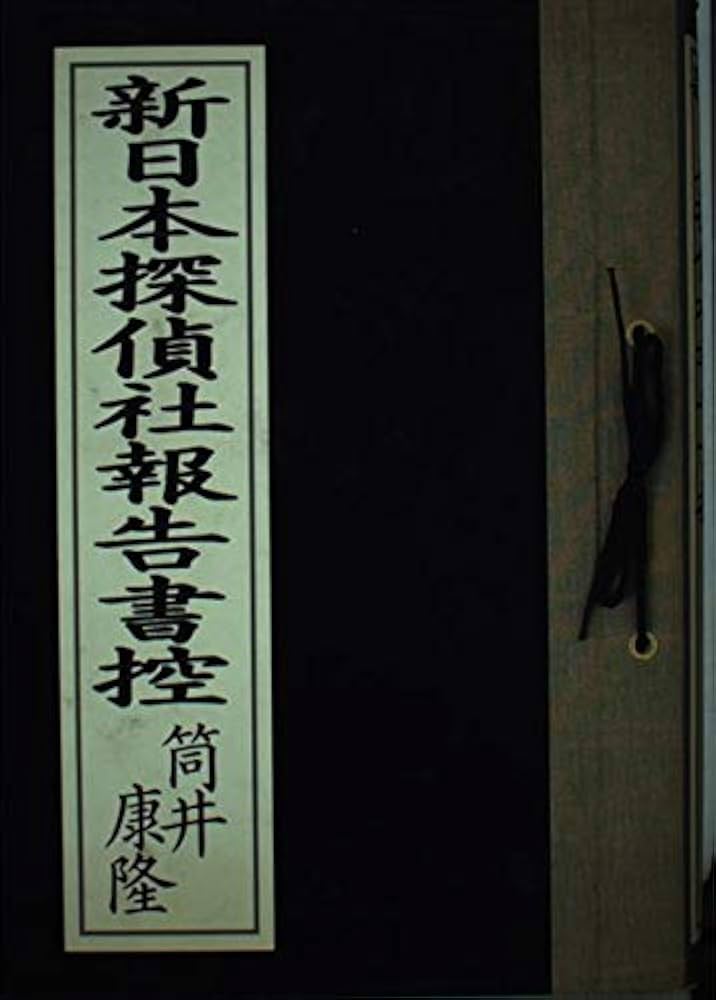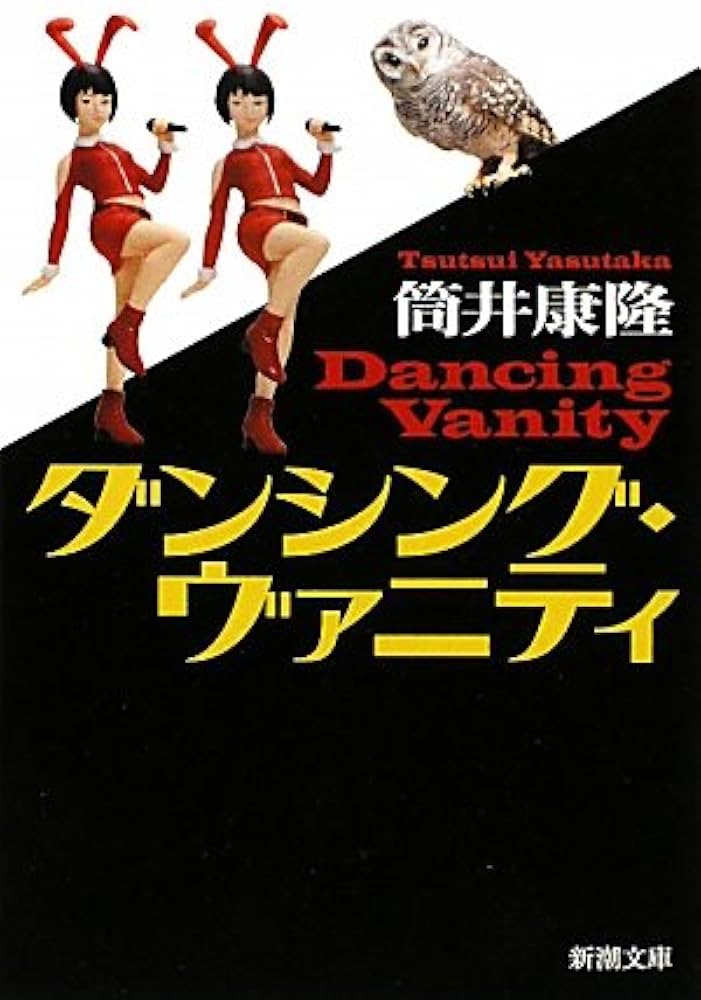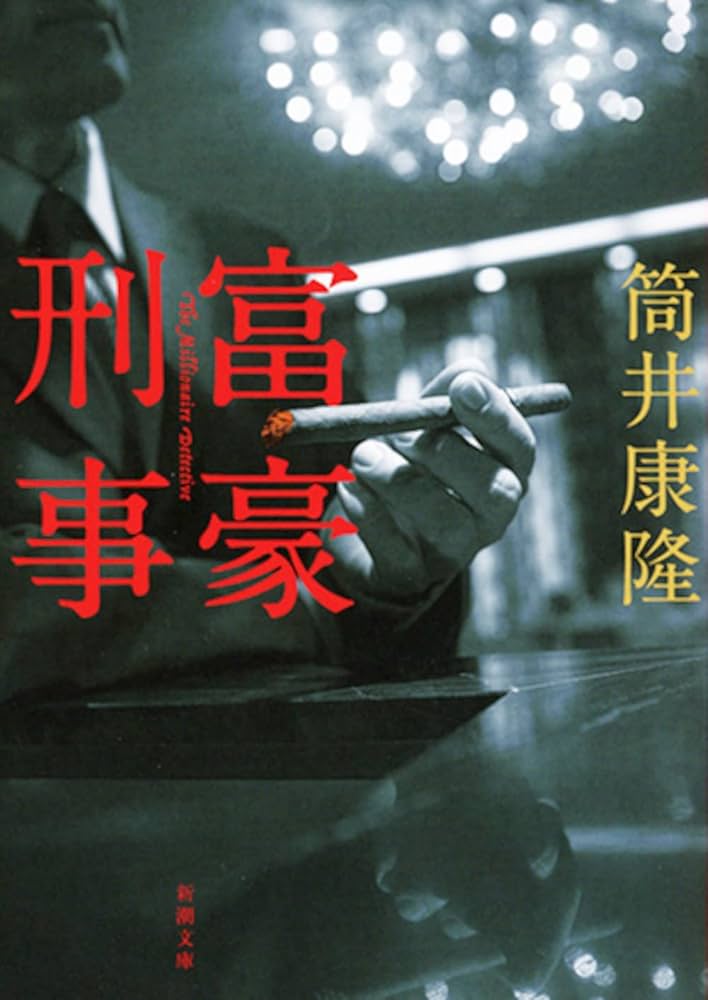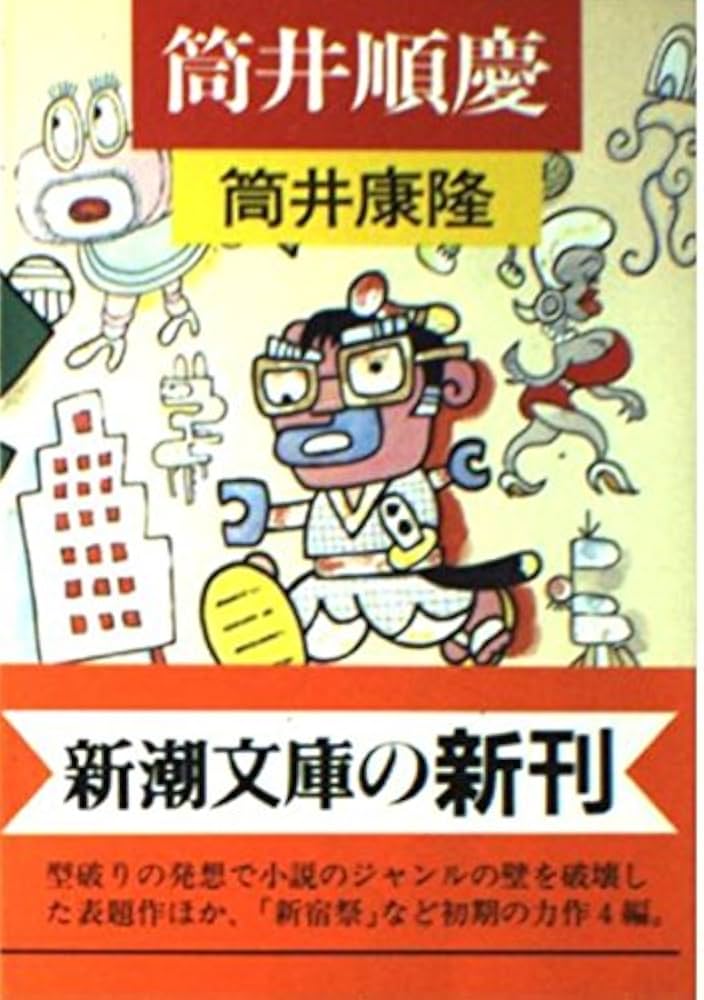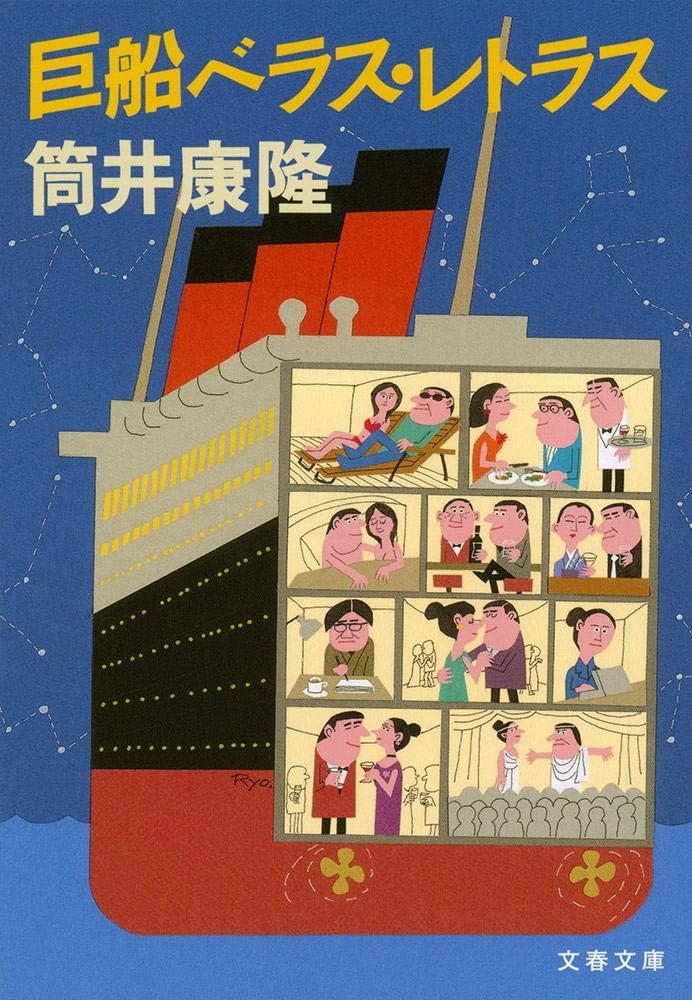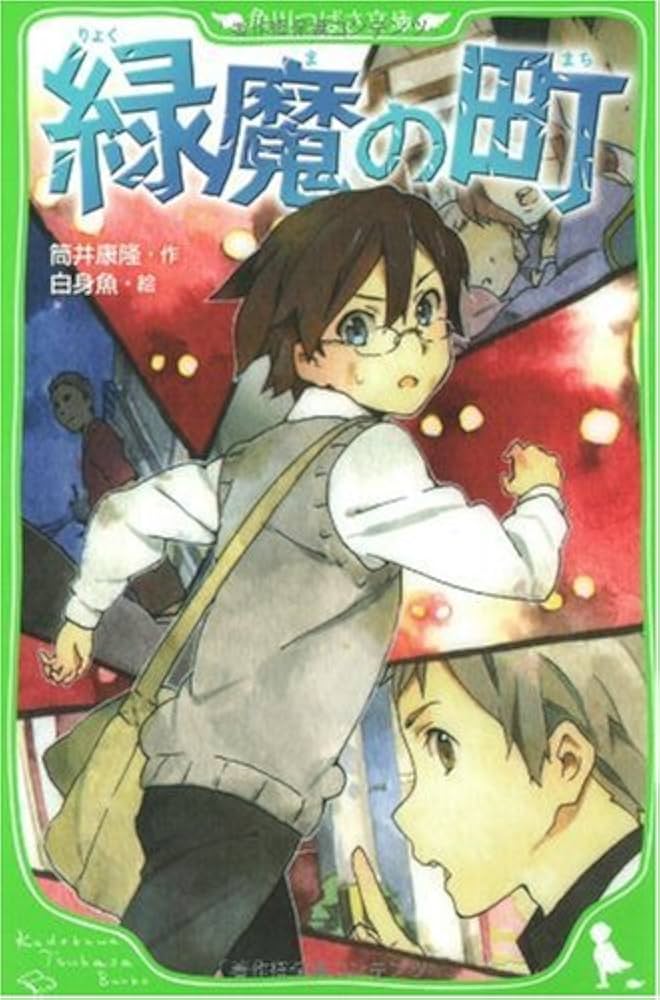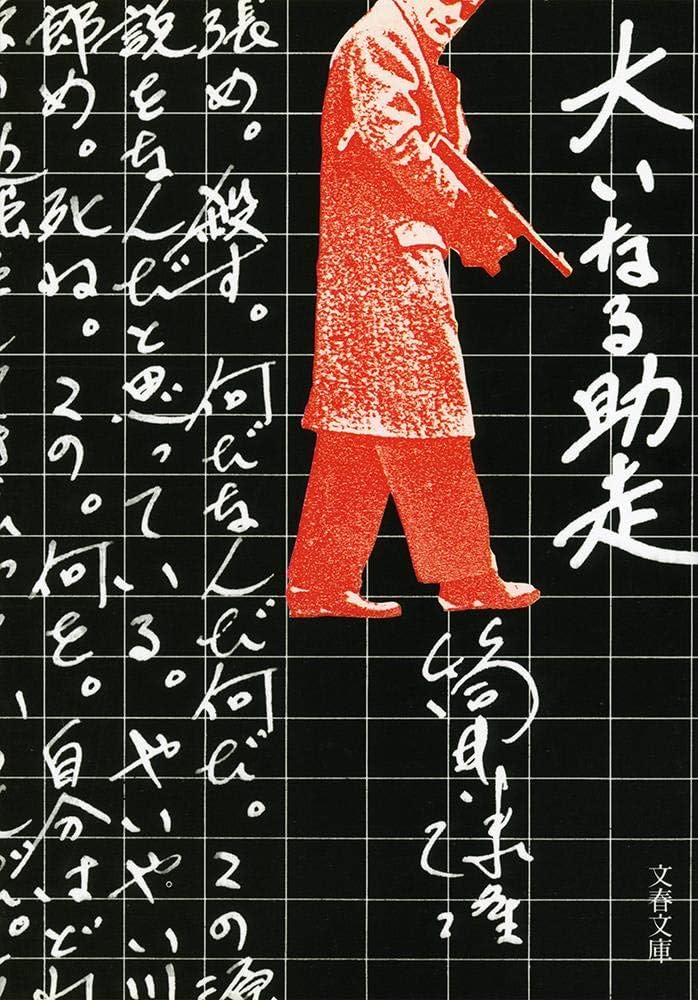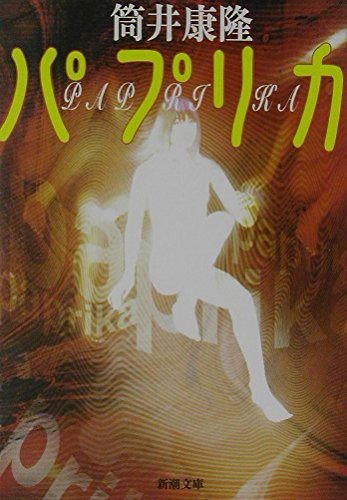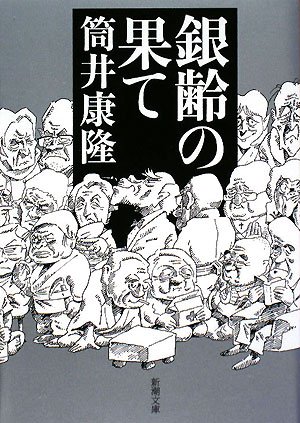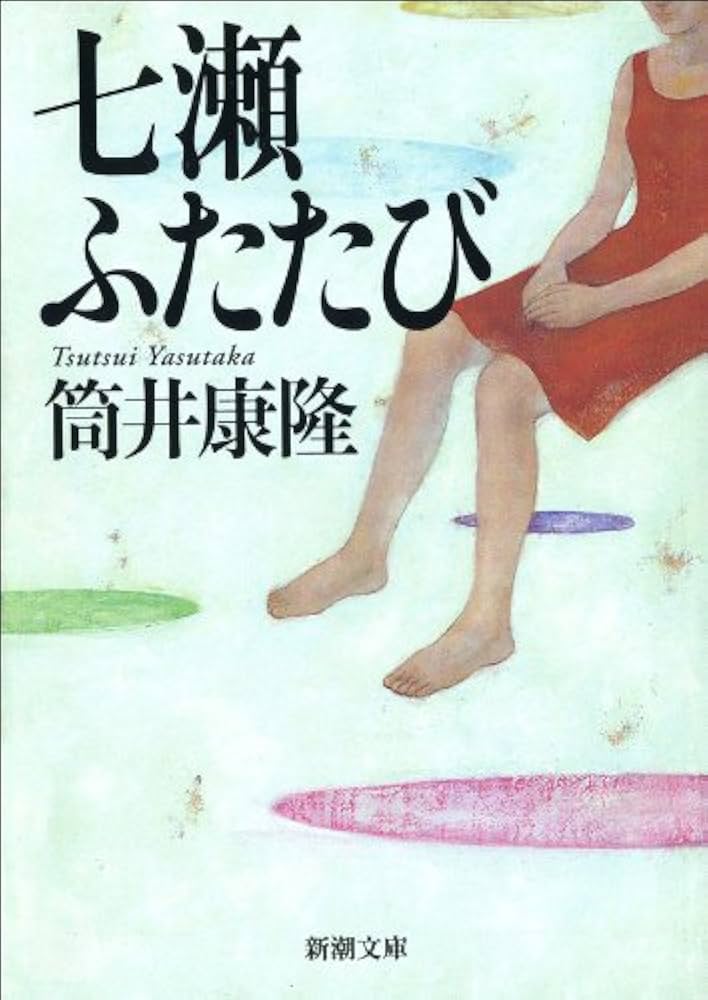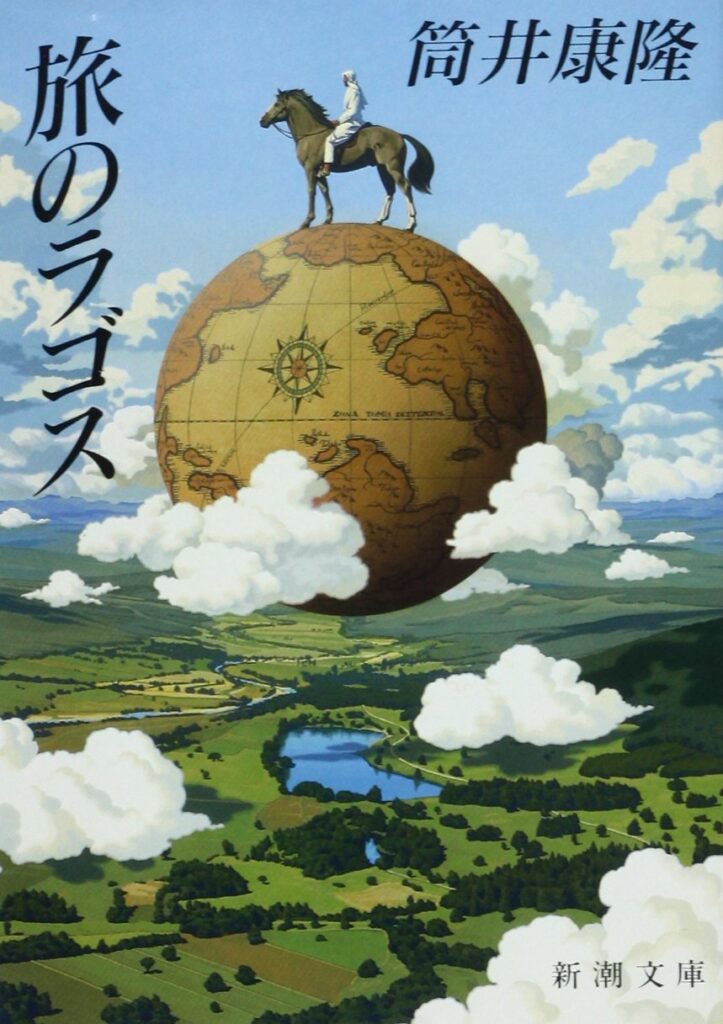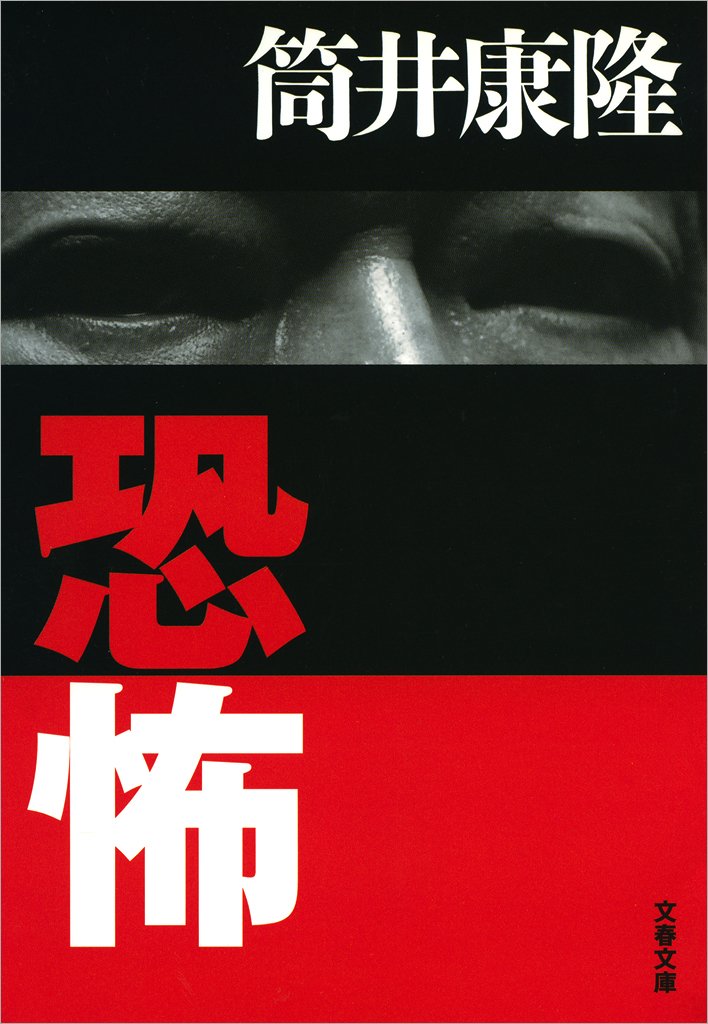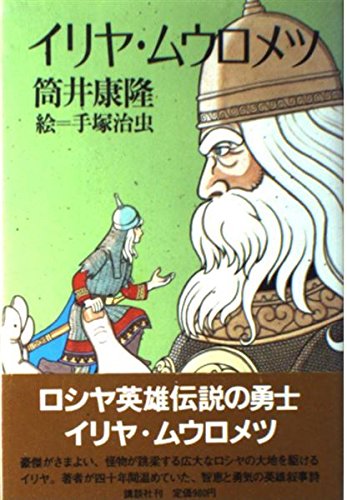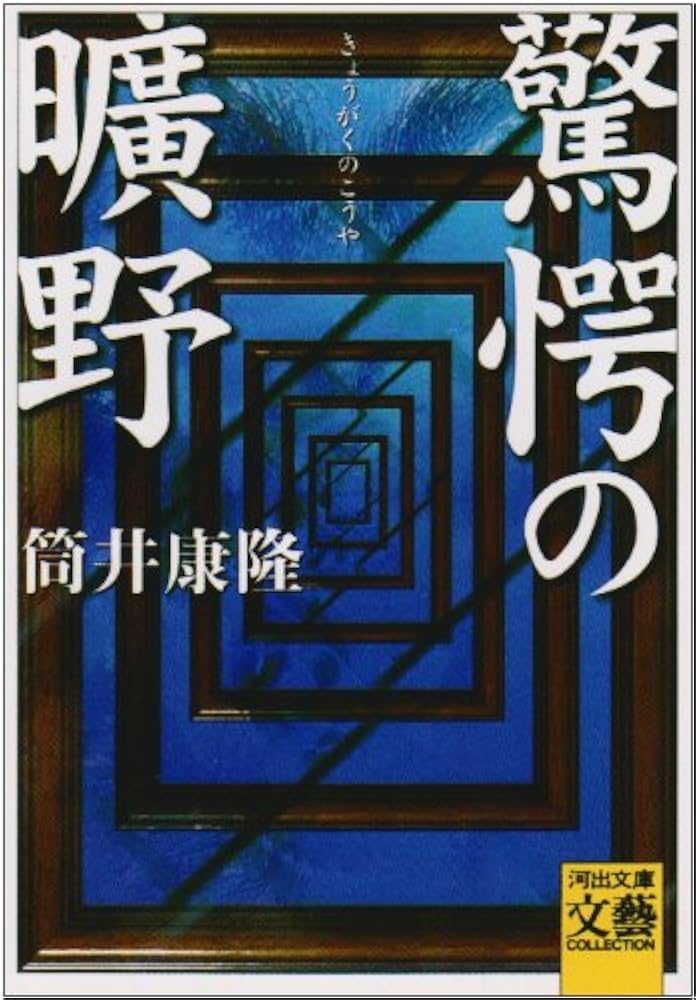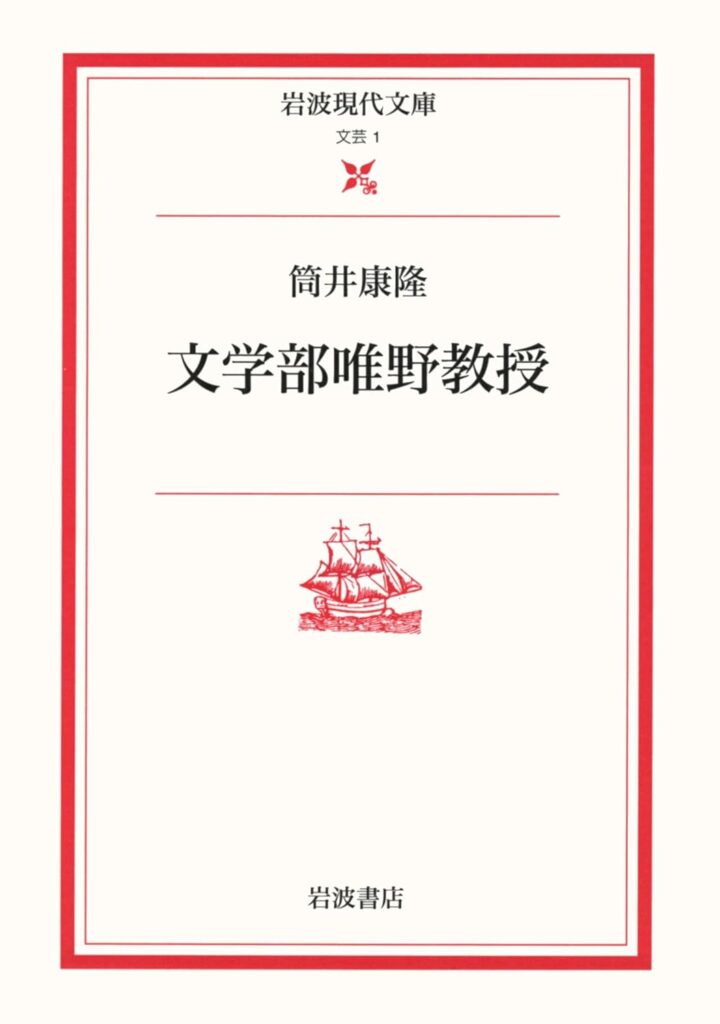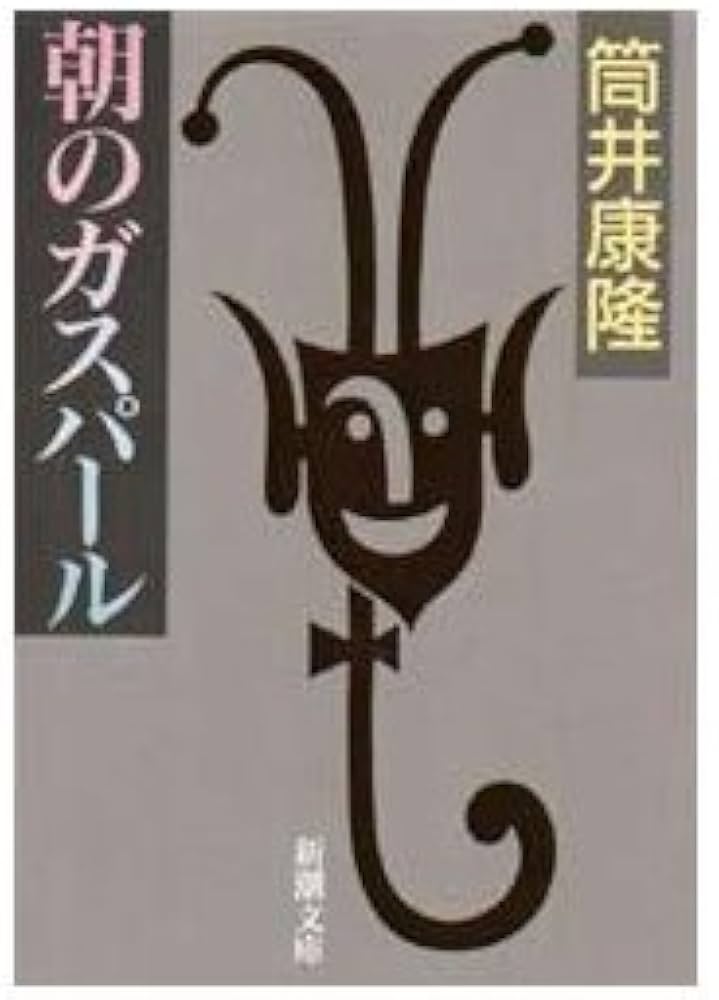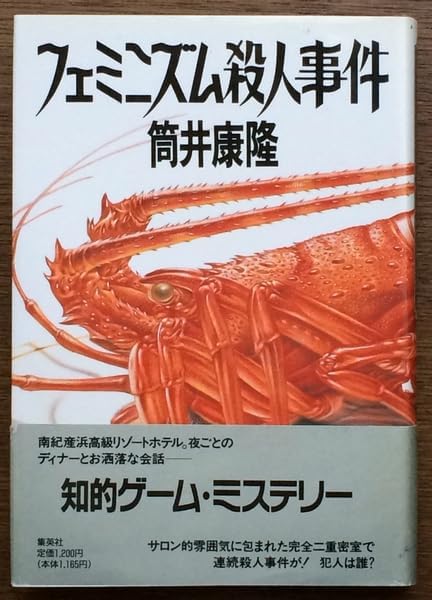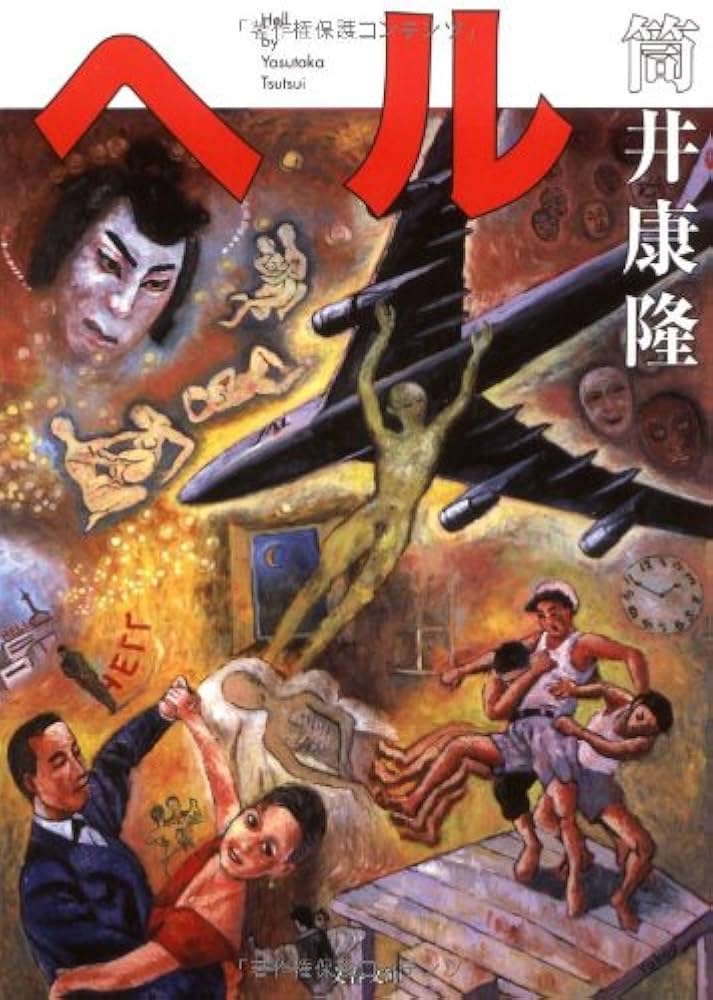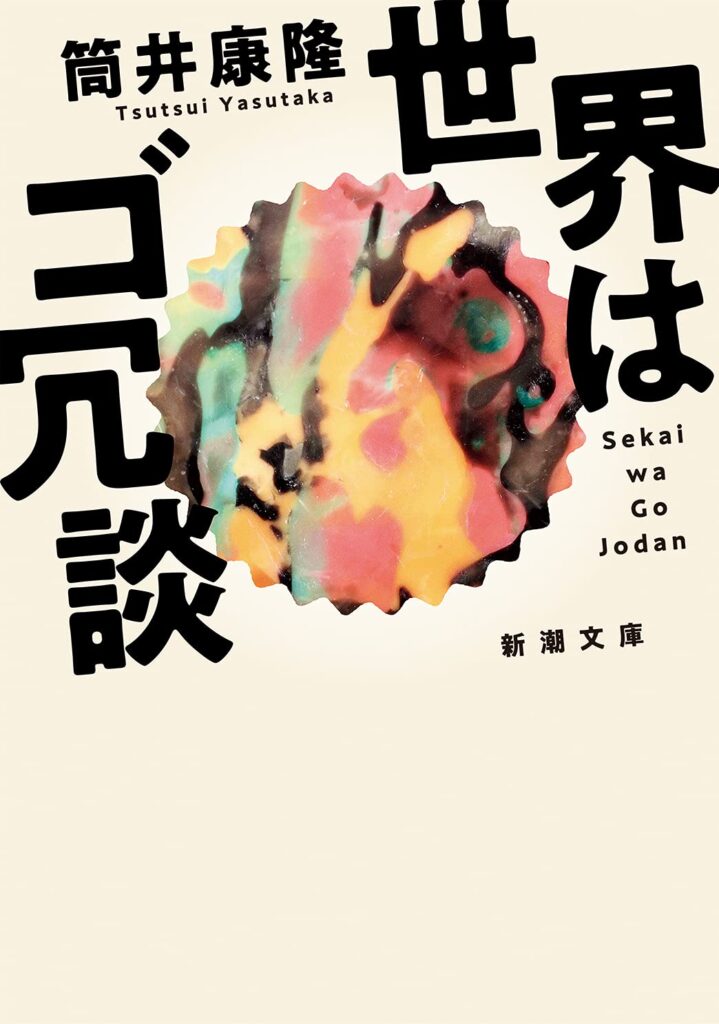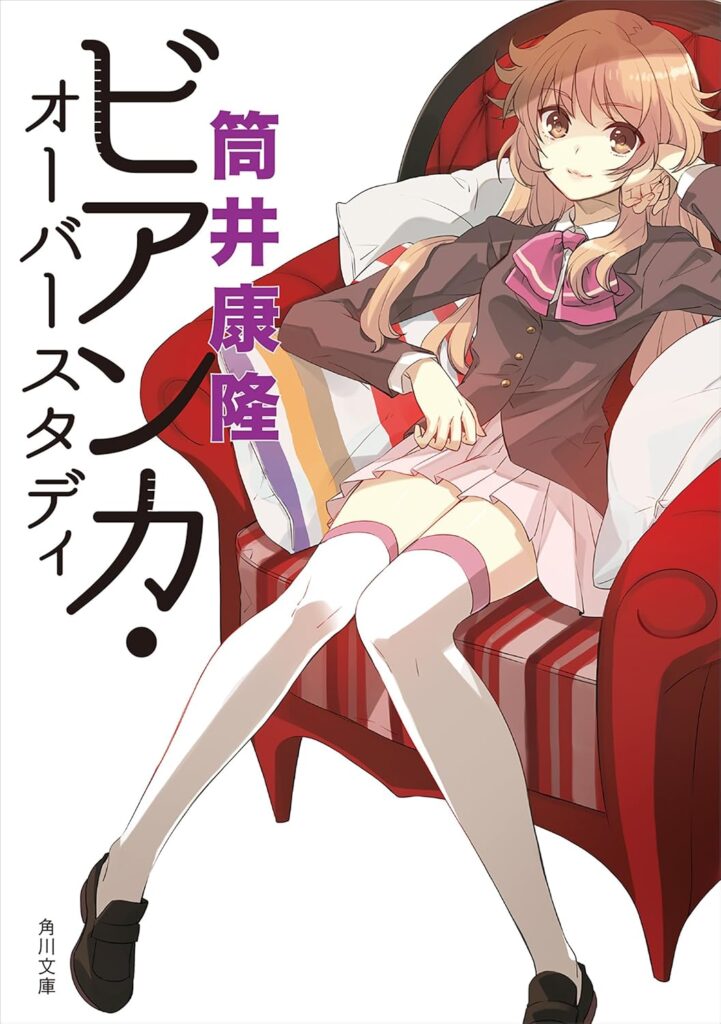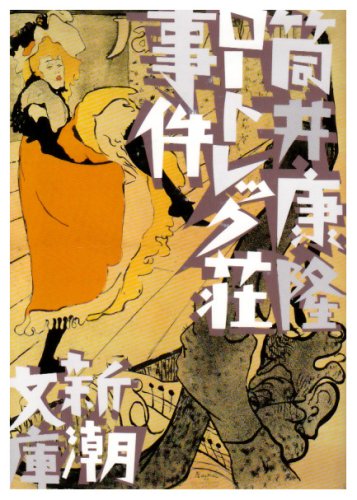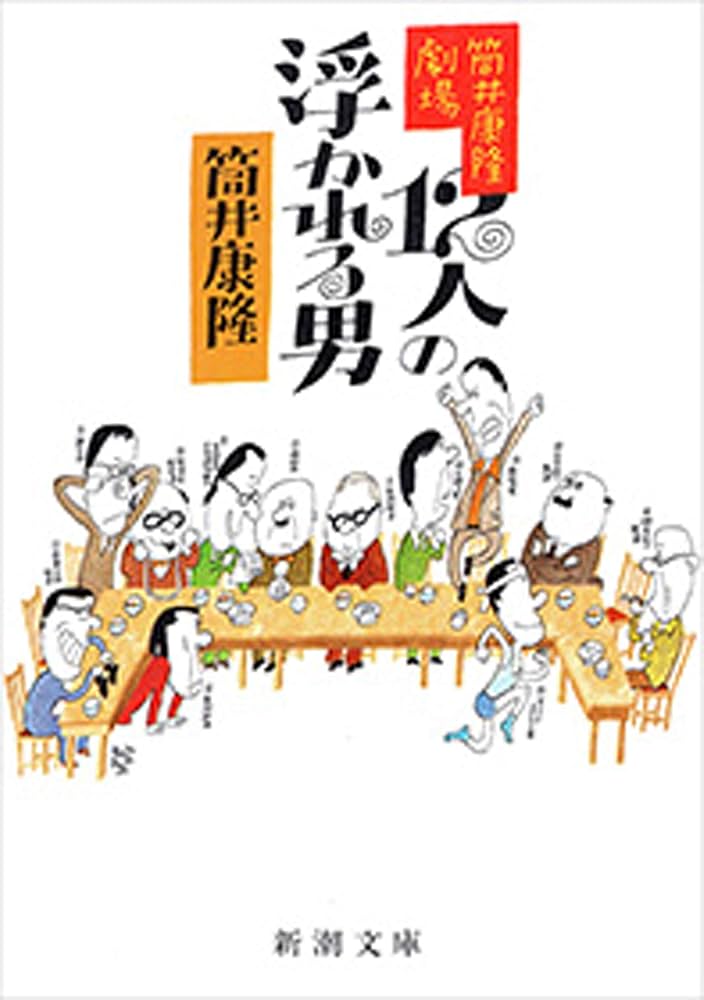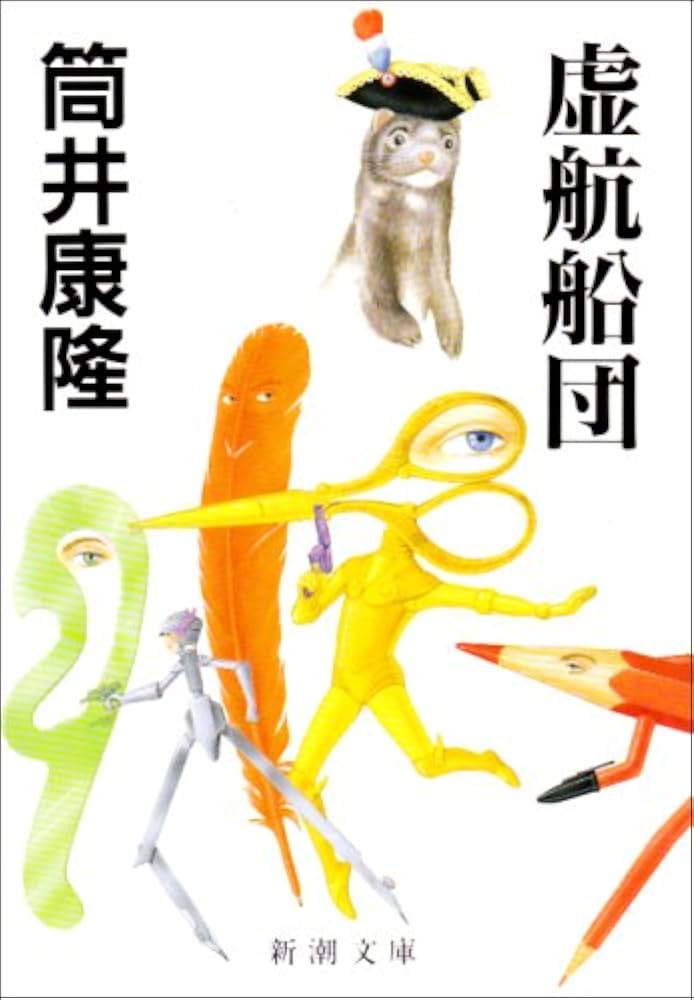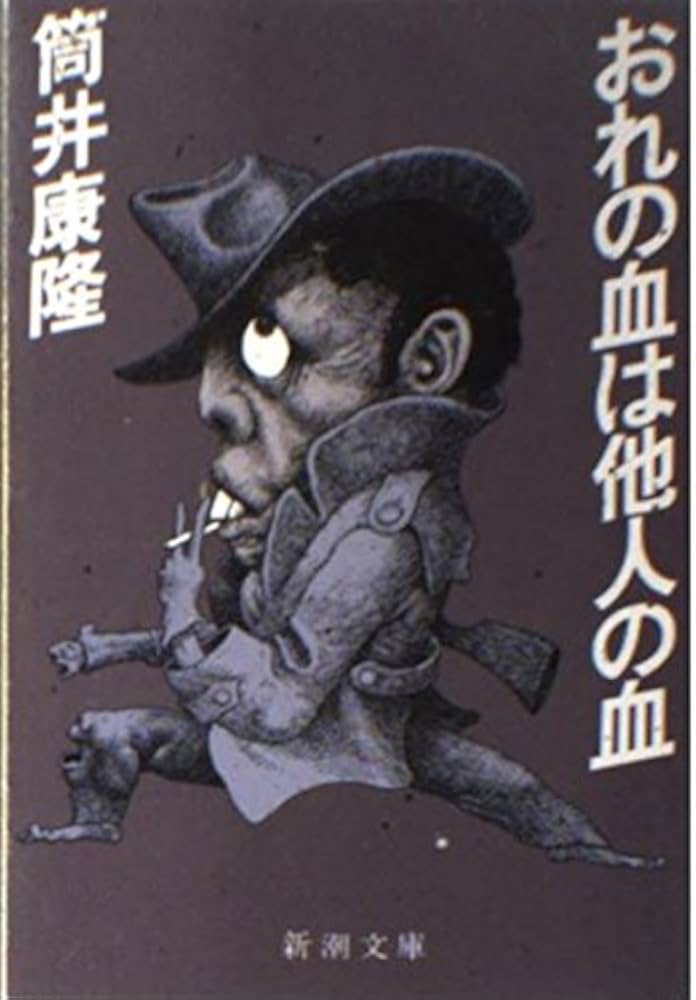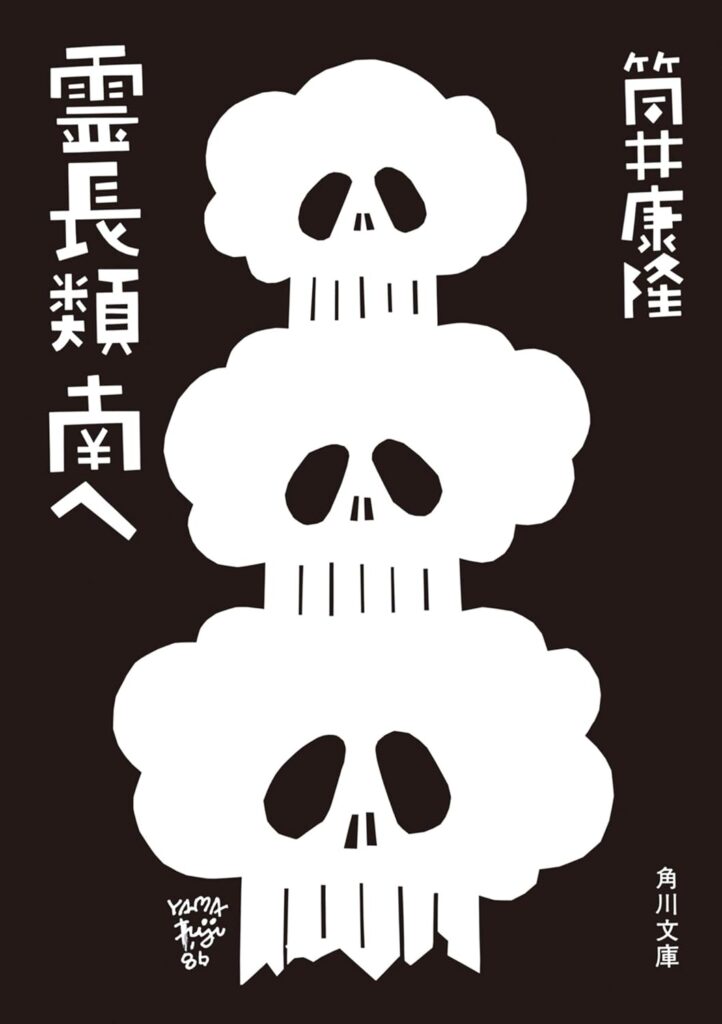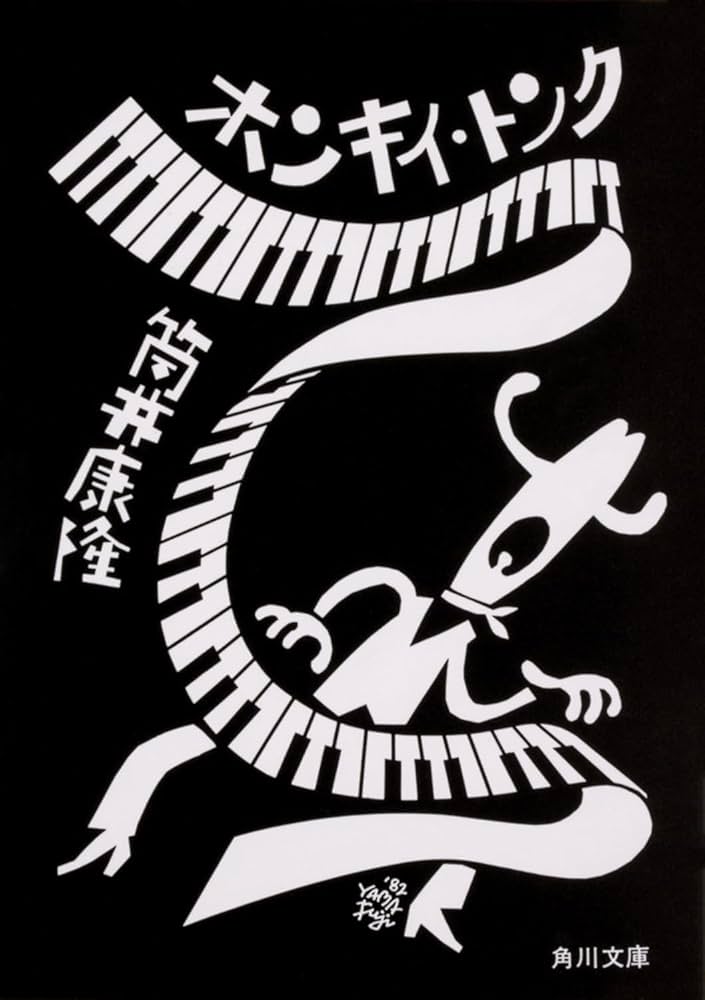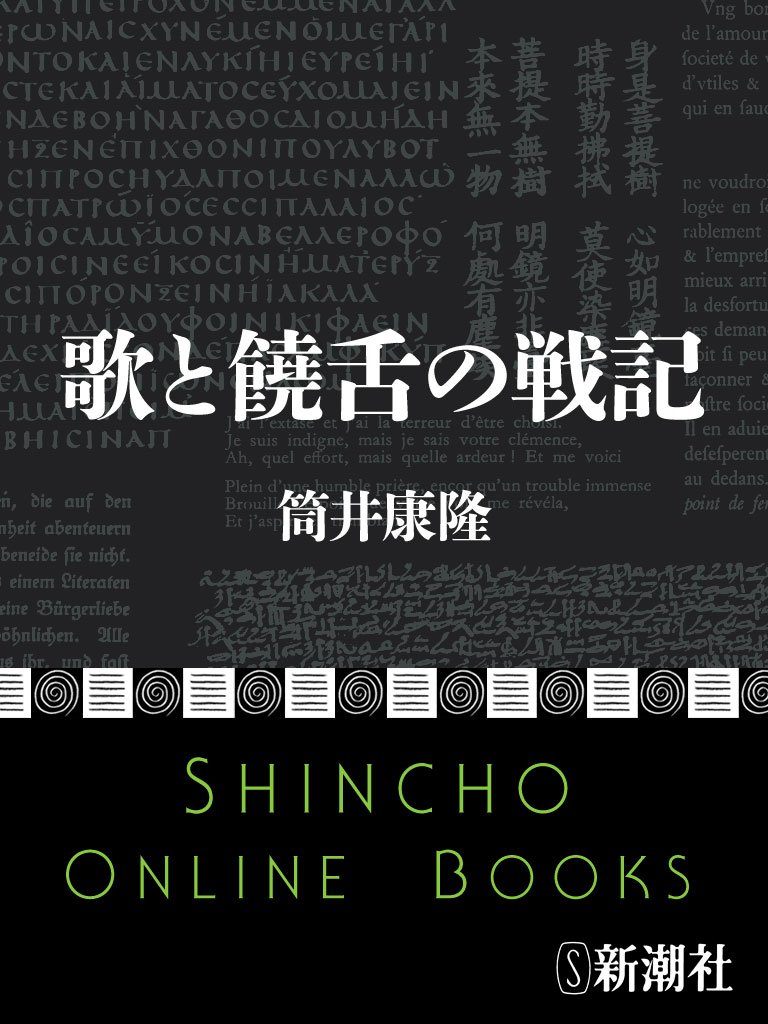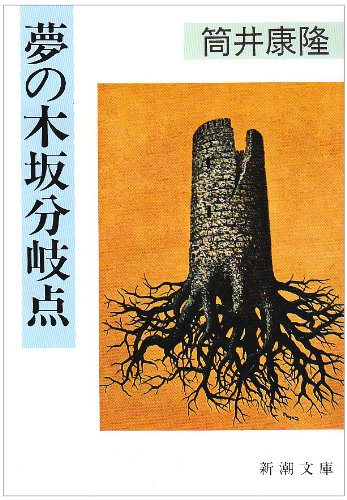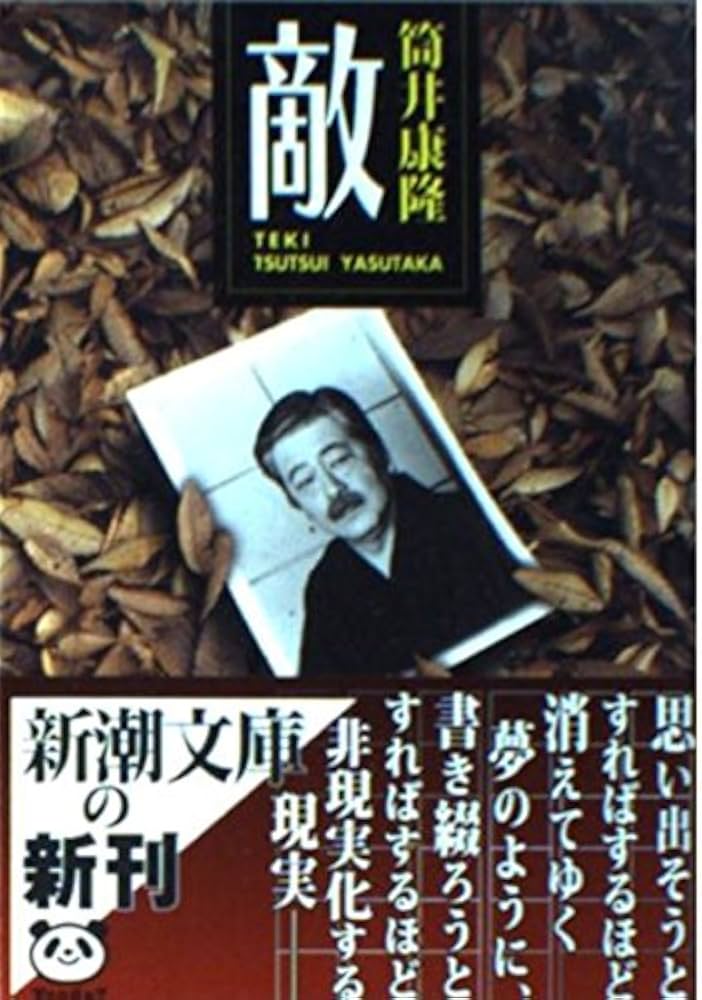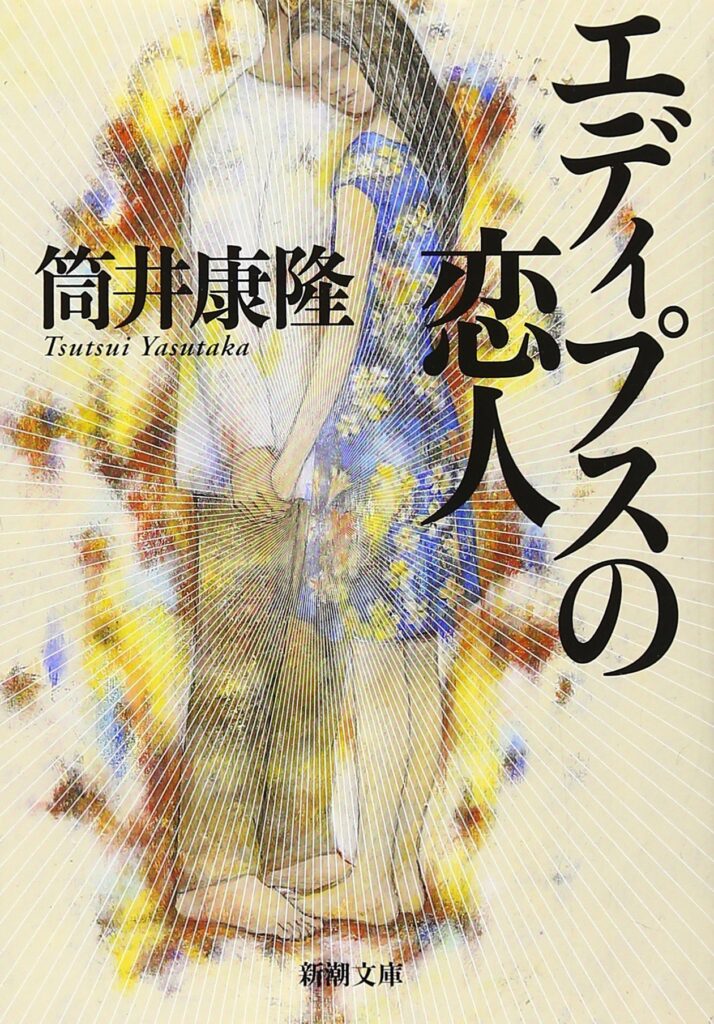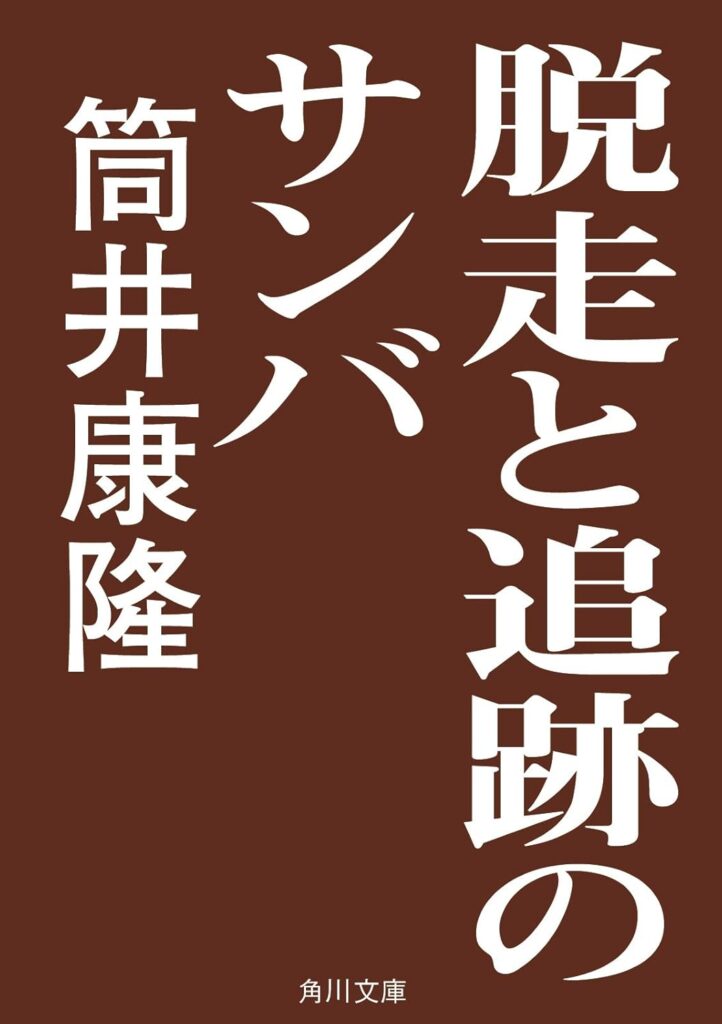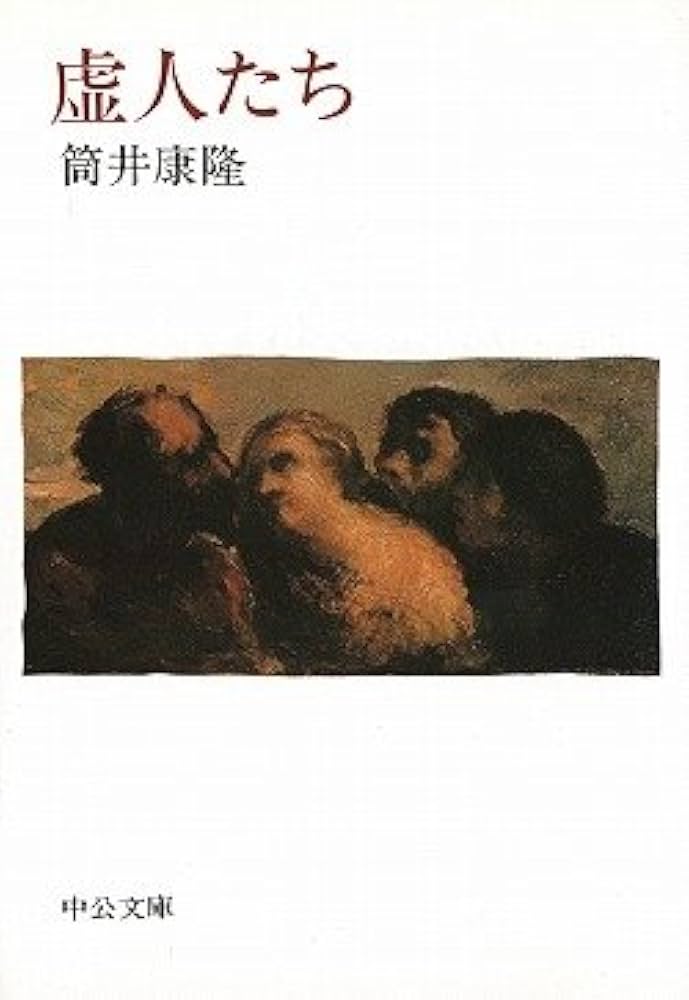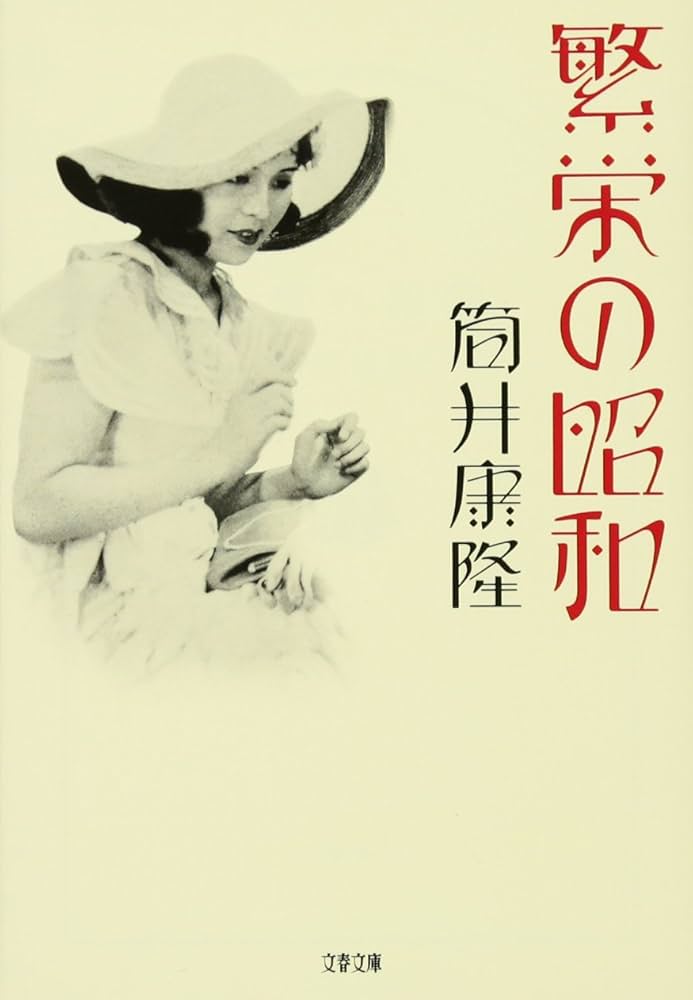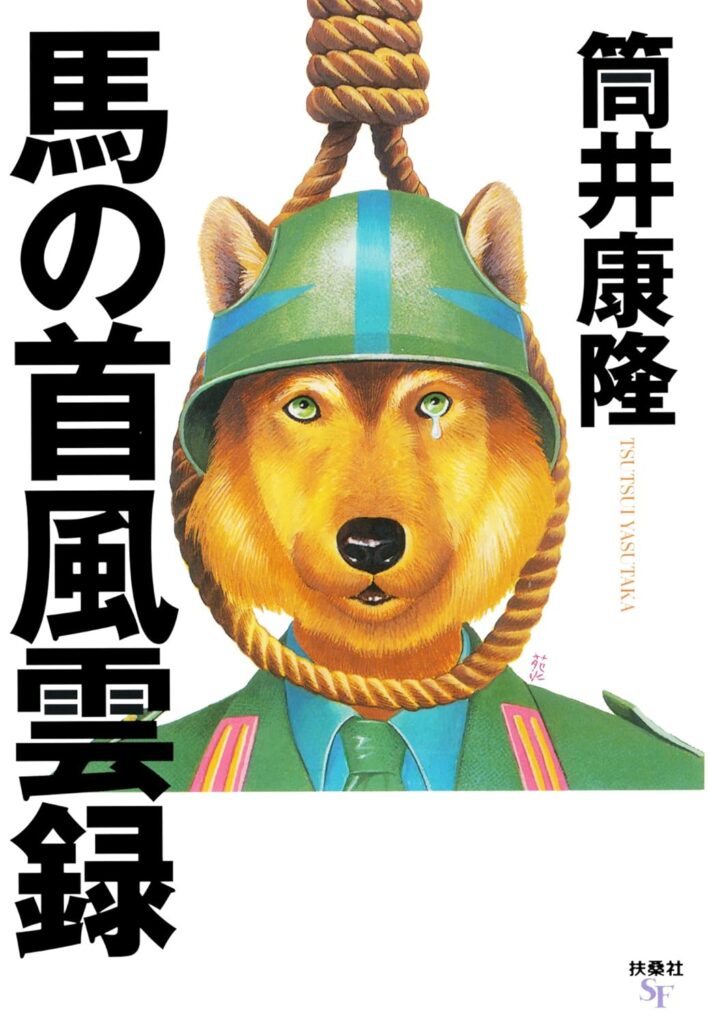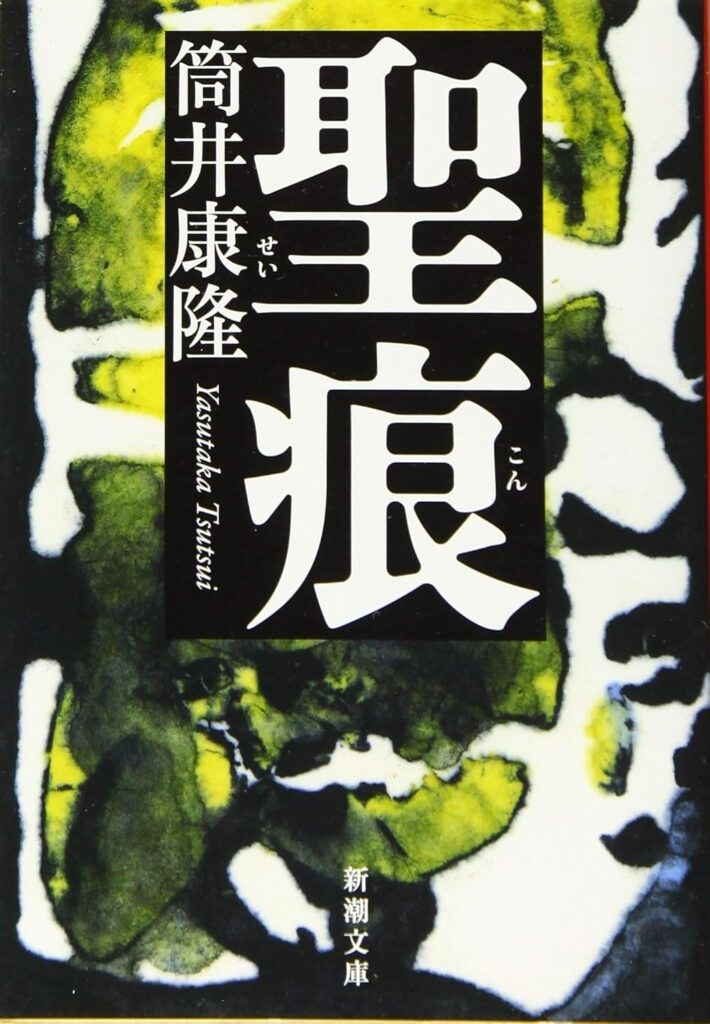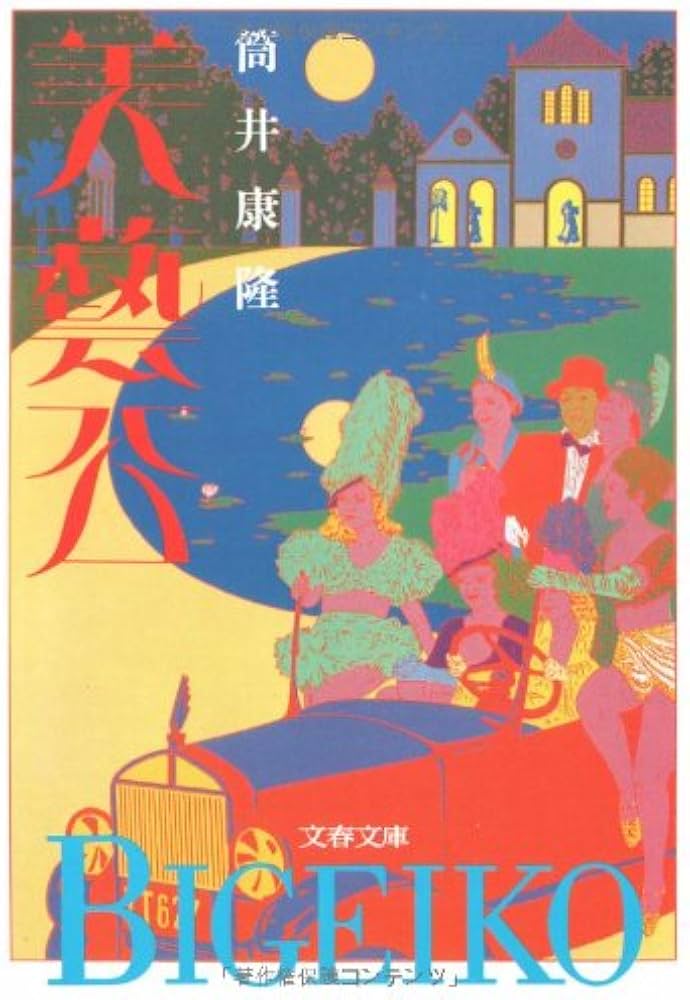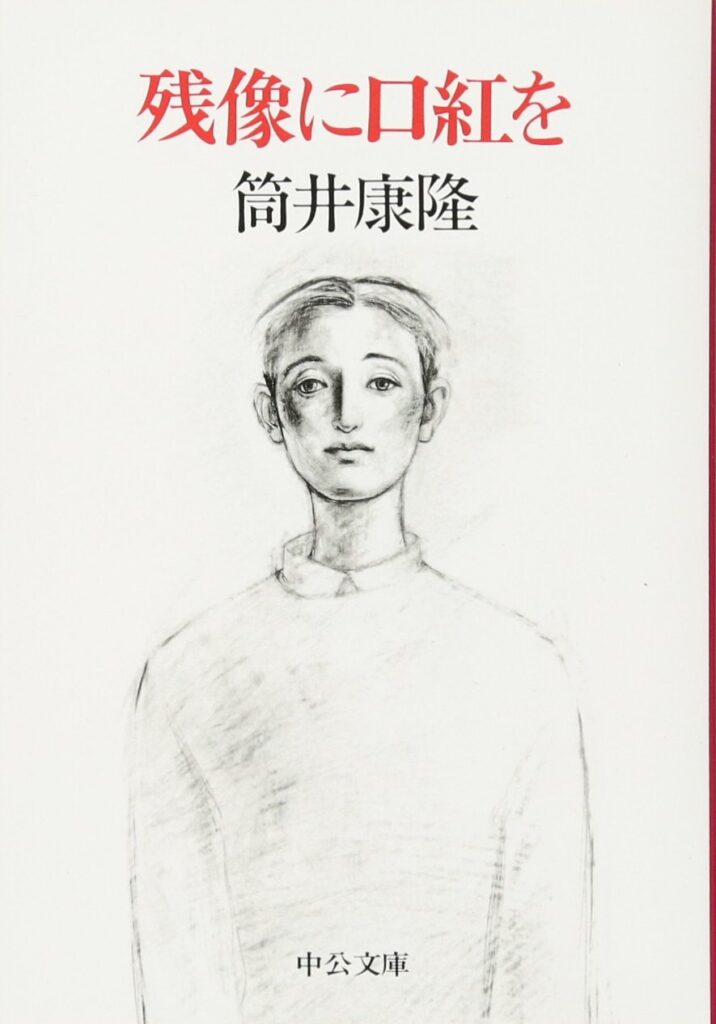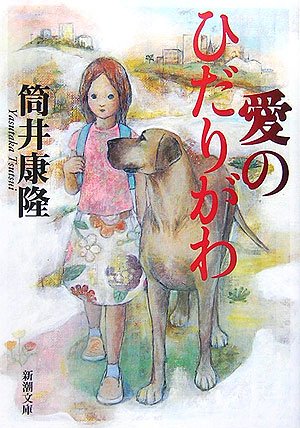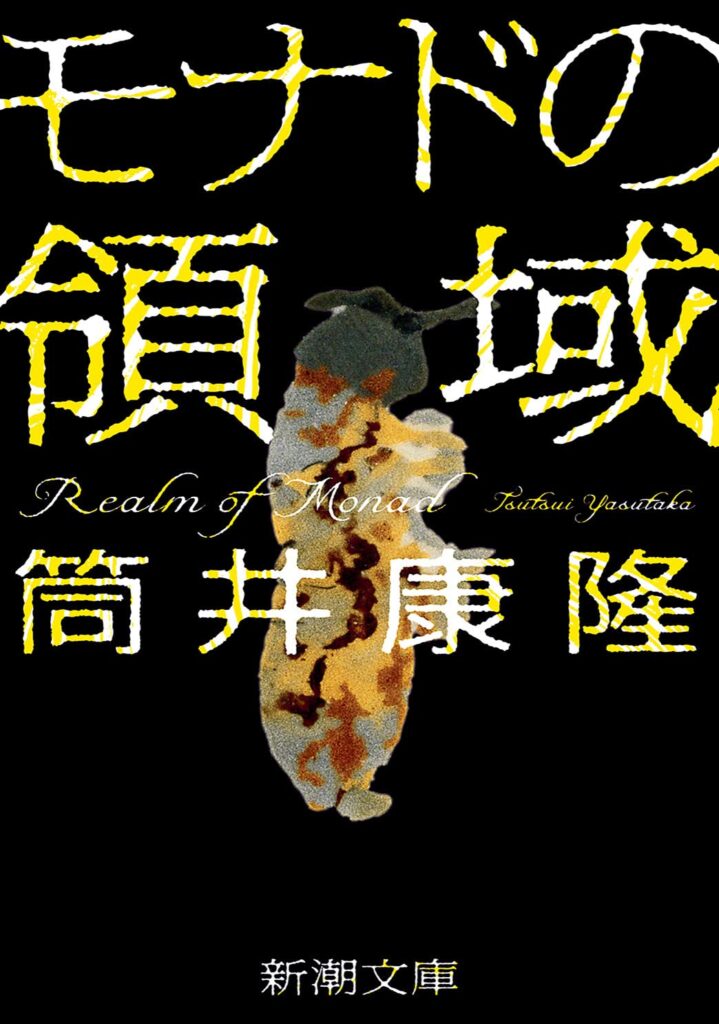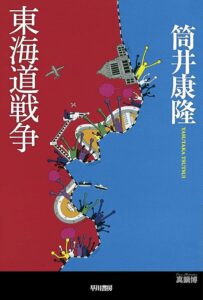 小説「東海道戦争」のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「東海道戦争」のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
筒井康隆氏の「東海道戦争」は、1960年代に発表されたとは思えないほど、現代社会に通じる風刺に満ちた作品です。デマが瞬く間に広がり、人々がそれに踊らされる様子は、まさにインターネット時代の到来を予見していたかのよう。この物語は、単なるSF作品としてだけでなく、人間の集団心理やメディアのあり方を鋭く描いた社会派作品としても読むことができます。
作品の舞台となるのは、東京と大阪が突如として戦争状態に陥るという荒唐無稽な事態。しかし、その根底にあるのは、些細な誤解や情報操作によって、いかに現実が歪められていくかという問いかけです。読者は、主人公のSF作家「俺」の視点を通して、最初は奇妙な出来事として傍観していた事態が、徐々に現実の脅威へと変貌していく過程を目撃することになります。
この作品は、滑稽さと恐ろしさが絶妙なバランスで同居している点が大きな魅力です。戦争という究極の非日常が、まるでお祭り騒ぎのように描かれる前半と、突如として現実の暴力が襲いかかる後半とのギャップは、読者に強烈な印象を与えます。筒井康隆氏ならではのブラックな視点が光る、まさに傑作と呼ぶにふさわしい一冊です。
小説「東海道戦争」のあらすじ
物語は、SF作家である「俺」が、いつもの日常に異変を感じるところから始まります。締切明けの酒で寝付けず、ようやく昼過ぎに眠りについた「俺」が目を覚ますと、そこには奇妙な光景が広がっていました。街には軍用機が飛び交い、日本刀を背負った男たちがトラックに乗り込んでいるのです。
なんとか放送局へたどり着いた「俺」は、友人であるアナウンサーの山口から、驚くべき事実を聞かされます。それは、東京と大阪の間で「東海道戦争」が勃発したという、にわかには信じがたいニュースでした。発端は、東京が大阪へ侵攻するというデマと、それに対抗する形で大阪が武装蜂起したという噂が、ほぼ同時に広まったことだといいます。
デマがデマを呼び、あれよあれよという間に日本は分断状態に陥ります。山口が最前線の取材を命じられたことに、好奇心旺盛な「俺」も同行することにしました。高槻方面へ向かう途中、舗装道路は軍用車や民間車で埋め尽くされ、途中からは徒歩で進まざるを得ません。
最前線と聞いていた場所は、想像とはかけ離れた光景でした。ラッパを吹く自衛官、馬に乗って刀を振り回す憲兵、そしてテレビ中継車やマスコミ関係者、テントを張って花火を打ち上げる若者グループまで。まるでお祭り騒ぎのような様相を呈しており、これが本当に戦争なのかと疑いたくなるほどです。
そんな中で、「俺」は大学の山岳部に所属するガールフレンドの邦子と再会します。彼女はなんと、レインジャー部隊の一員として、空気銃を片手にゲリラ掃討作戦に参加していると言い張ります。「俺」は家に帰って学業を続けるように説得しますが、彼女は全く耳を貸しません。
しかし、この奇妙な高揚感も長くは続きませんでした。夜が明け始めた頃、「俺」は遠方から聞こえる爆音で目を覚まします。警察官が手榴弾を配布し始め、「俺」はいつの間にか最前線に守備兵として配置されていることに気づきます。急ピッチで積み上げられた土嚢の向こうから現れたのは、戦争映画でしか見たことがない装甲車や戦車の大群でした。
小説「東海道戦争」の長文感想(ネタバレあり)
「東海道戦争」という作品を読み終えた時、まず感じたのは、筒井康隆氏の先見の明に対する深い驚きでした。この小説が発表されたのはインターネットやSNSが普及する遥か以前、1960年代のことです。しかし、デマや妄想が独り歩きし、それがやがて現実を侵食していくという物語の構造は、まさに現代社会が抱える問題を的確に予見しているかのようです。情報が瞬時に拡散され、真偽が定かでないまま人々が扇動されていく、そんな恐ろしい状況が、この作品の中には凝縮されています。
物語の序盤、主人公であるSF作家の「俺」は、突如として始まった「東海道戦争」という奇妙な事態を、まるで傍観者のように眺めています。最初は「東京が大阪へ侵攻する」というデマから始まり、それが東京側では「大阪が武装蜂起した」という噂となり、あっという間に日本は東西に分断されてしまいます。このあまりにも非現実的な設定に、読者も「俺」と同様に戸惑いを感じるはずです。しかし、筒井氏は、この荒唐無稽な設定の中にこそ、現代社会への鋭い風刺を忍び込ませています。人はなぜ、根拠のない情報に簡単に踊らされてしまうのか。そして、その結果、どのような悲劇が生まれるのか。
特に印象的なのは、戦争の「最前線」と称される場所が、まるでお祭り騒ぎのような様相を呈している描写です。ラッパを吹く自衛官、馬に乗って刀を振り回す憲兵、テレビ中継車がひしめき、マスコミ関係者がカメラを回す。さらには、テントを張って花火を打ち上げる若者グループまで現れ、そこは戦場というよりも、大規模なイベント会場とでも呼ぶべき光景です。仕出し弁当が配られ、酔っぱらいまで現れる始末。この滑稽な光景は、戦争という究極の非日常が、いかにメディアや大衆によって消費され、エンターテインメント化されてしまうかという、恐ろしい現実を突きつけます。私たちは、遠い国や地域で今現在も発生している戦争に対して、無関心になってしまうことについても考えさせられます。まるでテレビの向こう側の出来事のように捉え、自分とは関係のない遠い話として片付けてしまう。この作品は、そのような現代人の態度を痛烈に批判しているようにも感じられます。
「俺」が、ガールフレンドの邦子と最前線で再会するシーンも、この作品の重要な転換点となります。邦子は、空気銃を片手にゲリラ掃討作戦に加担すると息巻いており、「俺」が家に帰って学業を続けるように説得しても、全く耳を貸しません。彼女は、この「戦争ごっこ」に陶酔しているかのように見えます。この邦子の姿は、大衆が情報に踊らされ、自らの意思を失っていく姿を象徴しているかのようです。現実と虚構の境目が曖昧になり、「ごっこ」の延長線上に本物の暴力が潜んでいることに気づかない。その無邪気さは、後の悲劇を予感させ、読者の胸に不穏な影を落とします。
しかし、物語の終盤、この奇妙な高揚感は一瞬にして崩れ去ります。夜が明けた頃、「俺」が聞いたのは、遠方からの爆音でした。警察官が手榴弾を配布し始め、「俺」はいつの間にか最前線の守備兵として配置されることになります。そして、急ピッチで積み上げられた土嚢の向こうから出現したのは、戦争映画でしか見たことがない装甲車や戦車の大群でした。この瞬間、それまでの滑稽な「お祭り騒ぎ」は、一転してリアルな「戦争」へと変貌します。
この急展開は、読者に強烈なショックを与えます。まるで、「ごっこ」遊びのつもりでいた子供たちが、突然本物の銃を突きつけられた」ような感覚です。それまでのメディアが作り出した虚構が、現実の暴力によって一瞬にして打ち砕かれる。このコントラストこそが、「東海道戦争」という作品の真骨頂と言えるでしょう。
そして、物語の最も衝撃的な結末へと繋がります。「俺」は一目散に逃げ出しますが、負傷者を緊急搬送する病院車を取り囲んでいる一団の中に、泣き叫ぶ邦子の姿を見つけます。彼女に手を差し伸べようとしたまさにその時、敵の装甲車の砲口が火を吹き、邦子は木っ端微塵の肉片になってしまいます。この描写は、あまりにも生々しく、読者の心に深く突き刺さることでしょう。それまでの「お祭り騒ぎ」のような描写とは一線を画す、冷徹な暴力の描写です。
「俺」自身も爆風の巻き添えを喰らい、左腕を失い、助かる見込みはありません。最後の力を振り絞って手榴弾の信管を引き抜き、邦子の生命を奪った装甲車を道連れにしようとします。この絶望的な状況の中で、主人公が味わうリアルな痛みと無力感は、読者にもひしひしと伝わってきます。テレビや映画のスクリーンを通してしか知らなかった戦争の恐ろしさを、自分自身の肉体で存分に味わうことになるクライマックスは、まさに圧巻でした。
「東海道戦争」は、単なるSF小説として片付けられない、多層的なメッセージを内包した作品です。デマや情報操作の危険性、大衆心理の恐ろしさ、メディアの持つ力、そして戦争というものの本質。これらをブラックな視点と圧倒的な筆力で描き切った筒井康隆氏の才能には、ただただ感服するばかりです。
この作品は、発表から長い年月が経った今でも、そのメッセージ性は色褪せることなく、むしろ現代においてより一層の重みを持って響いてきます。情報社会に生きる私たちにとって、「東海道戦争」は、自らの頭で考え、情報を吟味することの重要性を改めて教えてくれる警鐘のような作品であると言えるでしょう。筒井康隆氏の代表作の一つとして、間違いなく読み継がれていくべき一冊です。
まとめ
筒井康隆氏の「東海道戦争」は、デマが拡散し、それが現実の分断へと発展する恐ろしいメカニズムを鮮やかに描いた作品です。発表された時代を考えると、インターネット時代における情報過多と集団心理の危うさを的確に予見していたことに驚きを禁じ得ません。
物語は、最初は奇妙なお祭り騒ぎのように描かれる戦争が、後半になると一転して生々しい暴力として読者に襲いかかります。このギャップが、虚構が現実を侵食する恐怖を浮き彫りにし、読者に深い問いかけを投げかけます。主人公「俺」が直面する絶望的な状況は、戦争の非情さを痛烈に示しています。
「東海道戦争」は、単なるSF作品としてだけでなく、現代社会が抱える情報と大衆のあり方について深く考えさせる社会派作品としての側面も持ち合わせています。筒井康隆氏ならではのブラックな視点と鋭い洞察力が光る、読み応えのある一冊です。
この作品は、デマに踊らされることの危険性や、情報リテラシーの重要性を改めて認識させてくれます。現代に生きる私たちにとって、必読の書であると言えるでしょう。