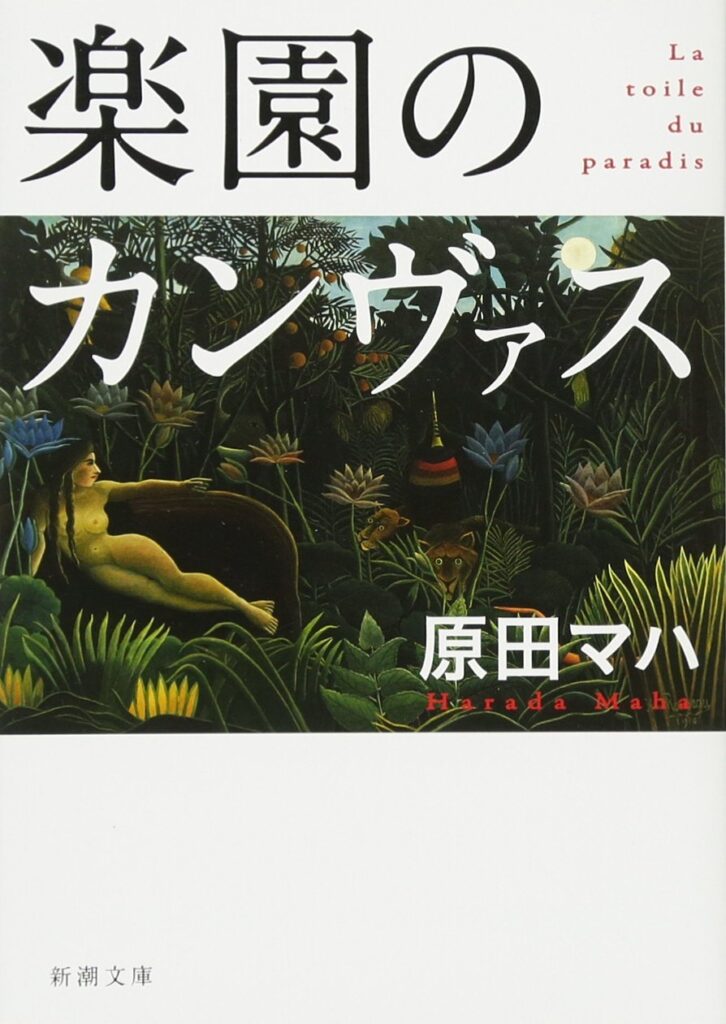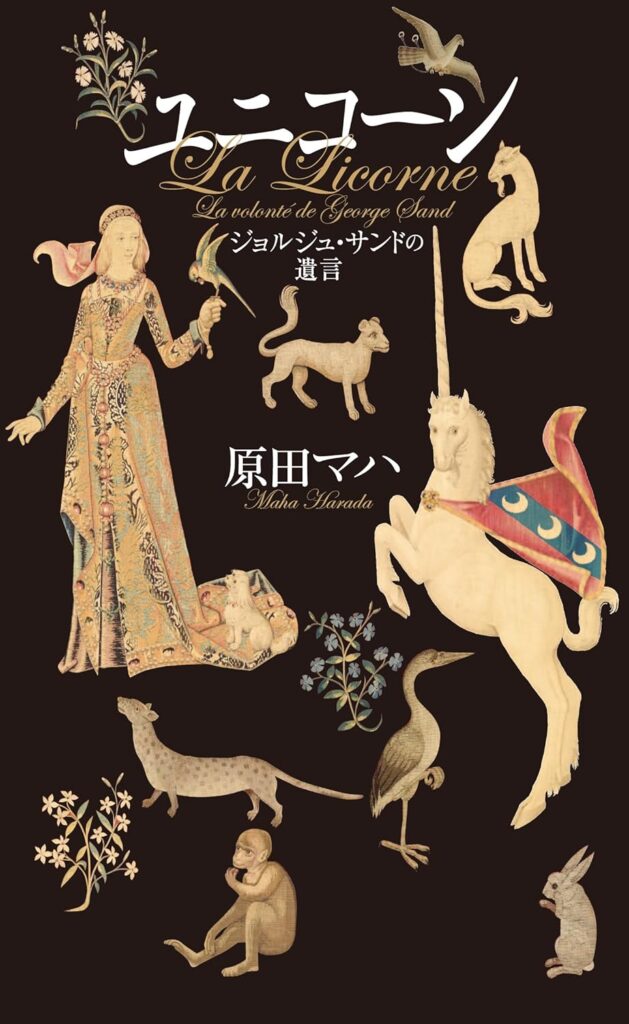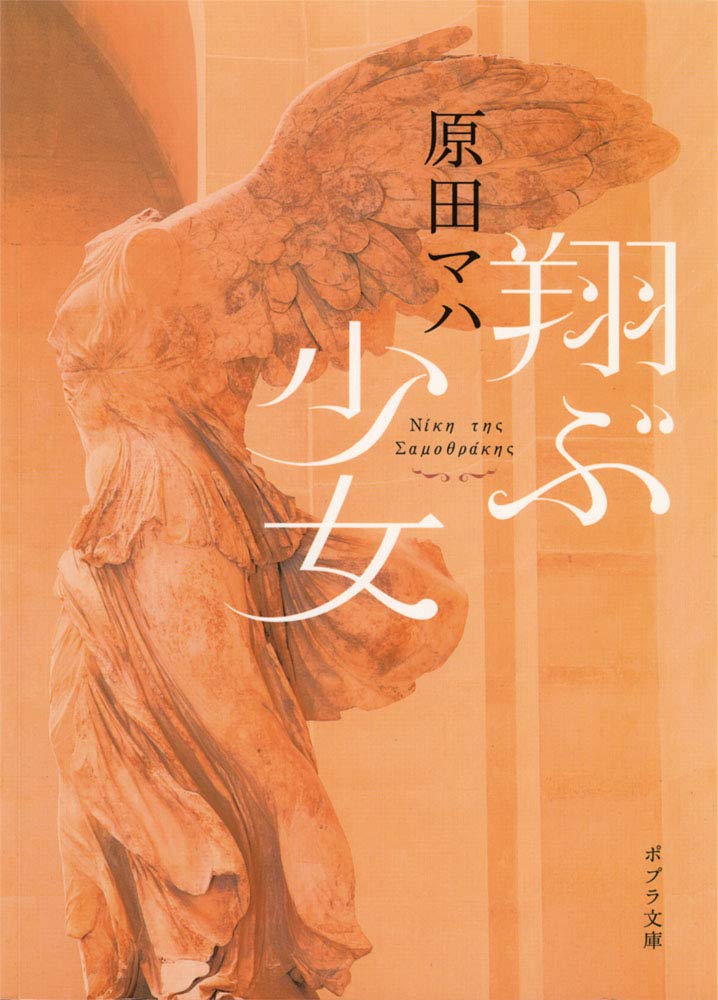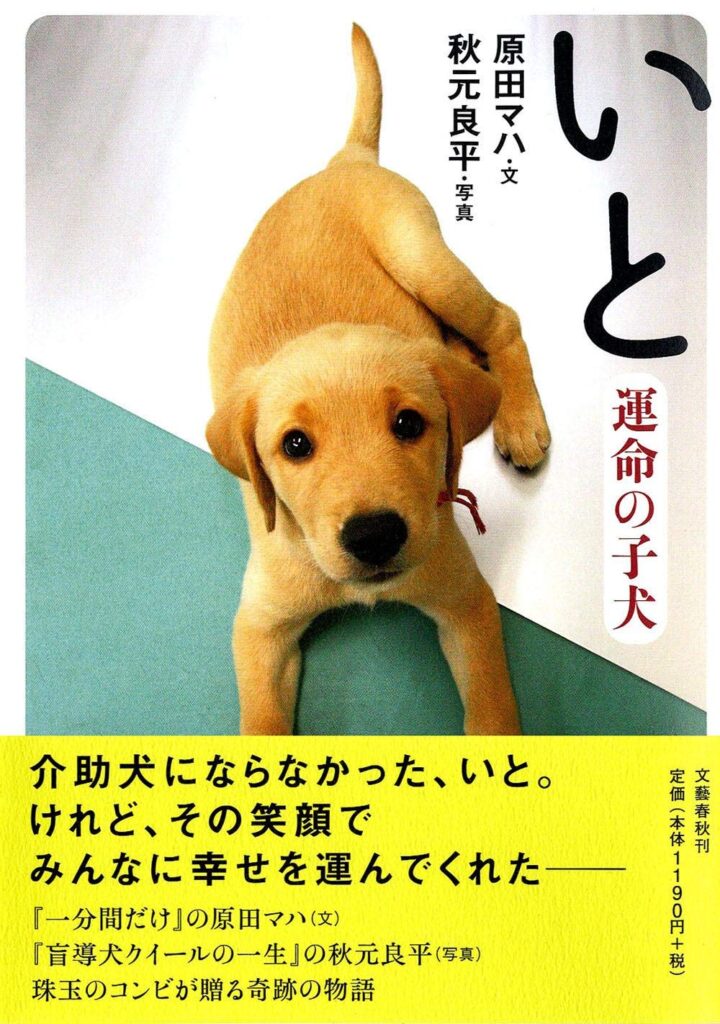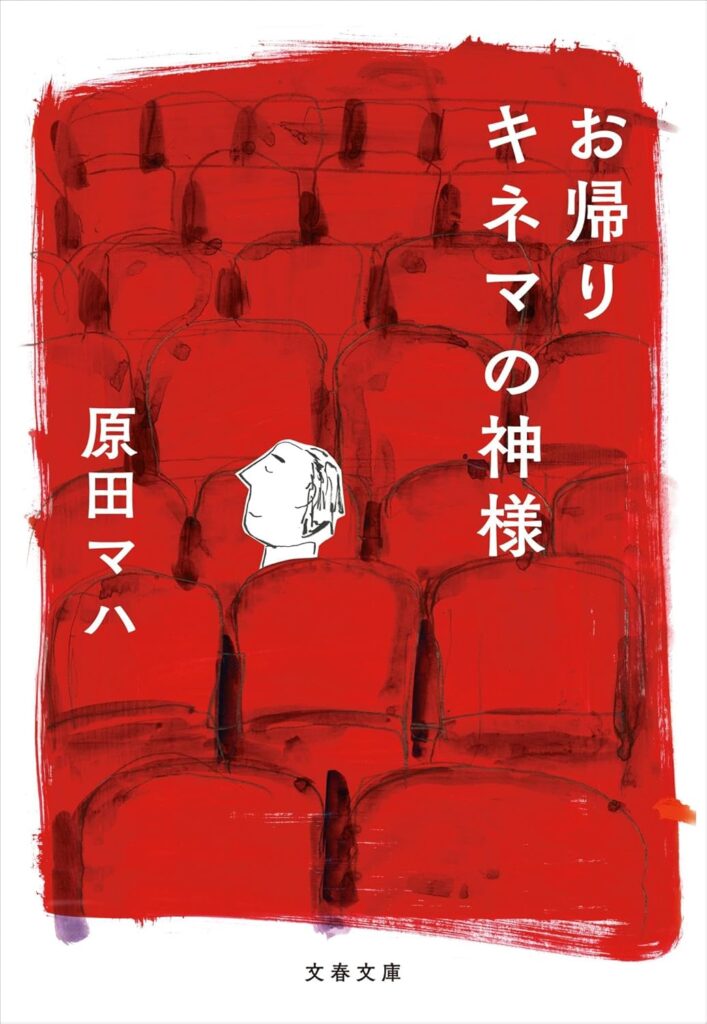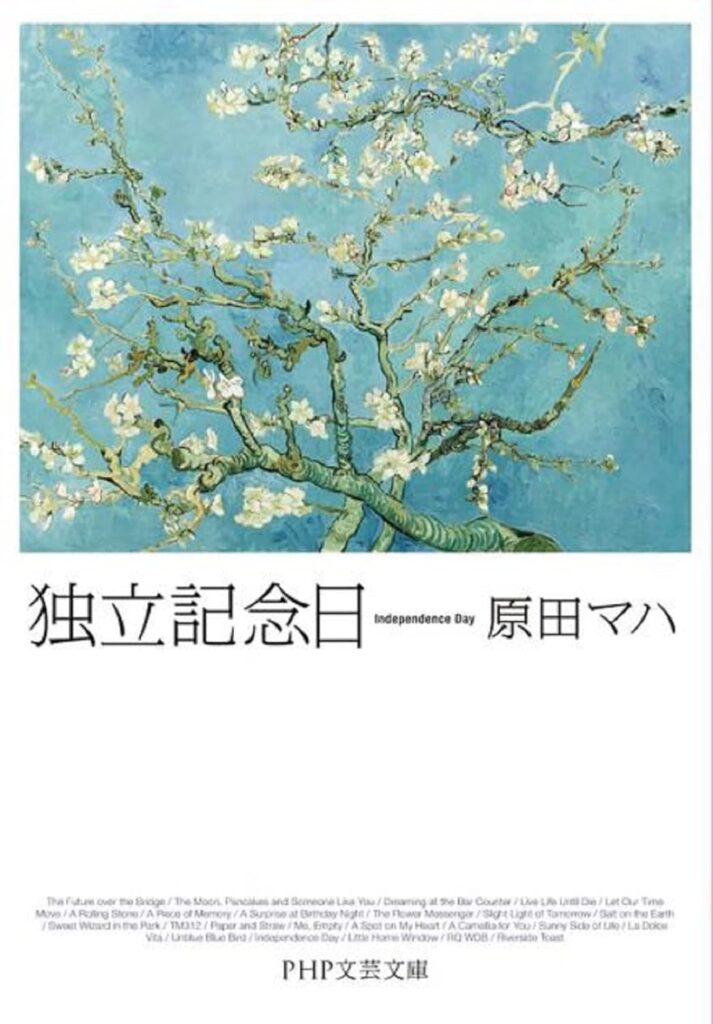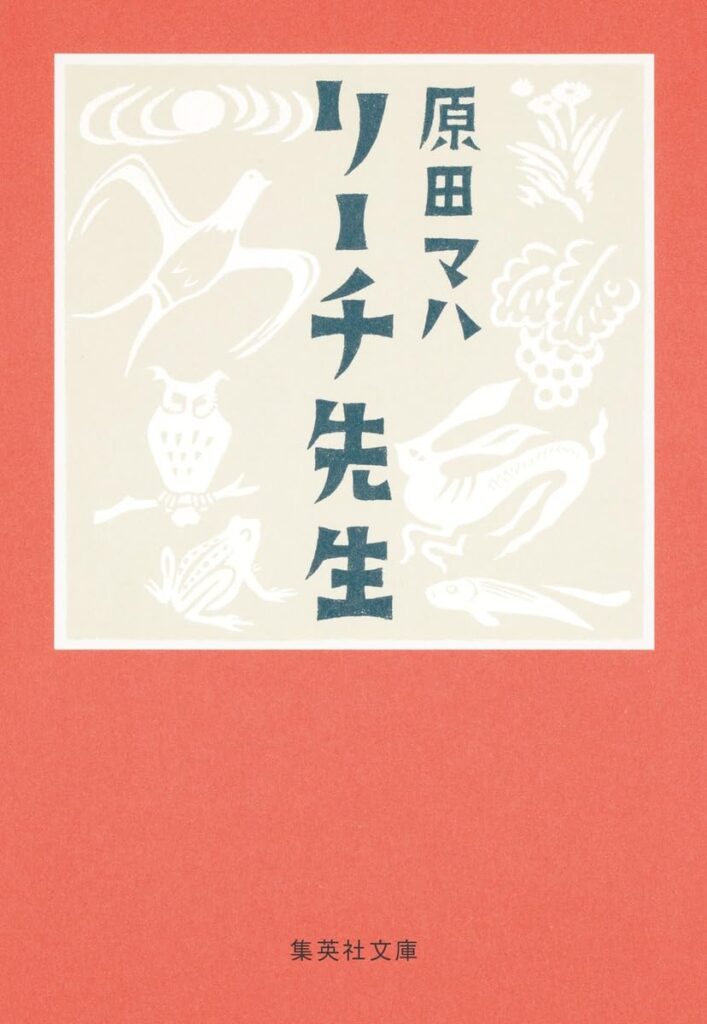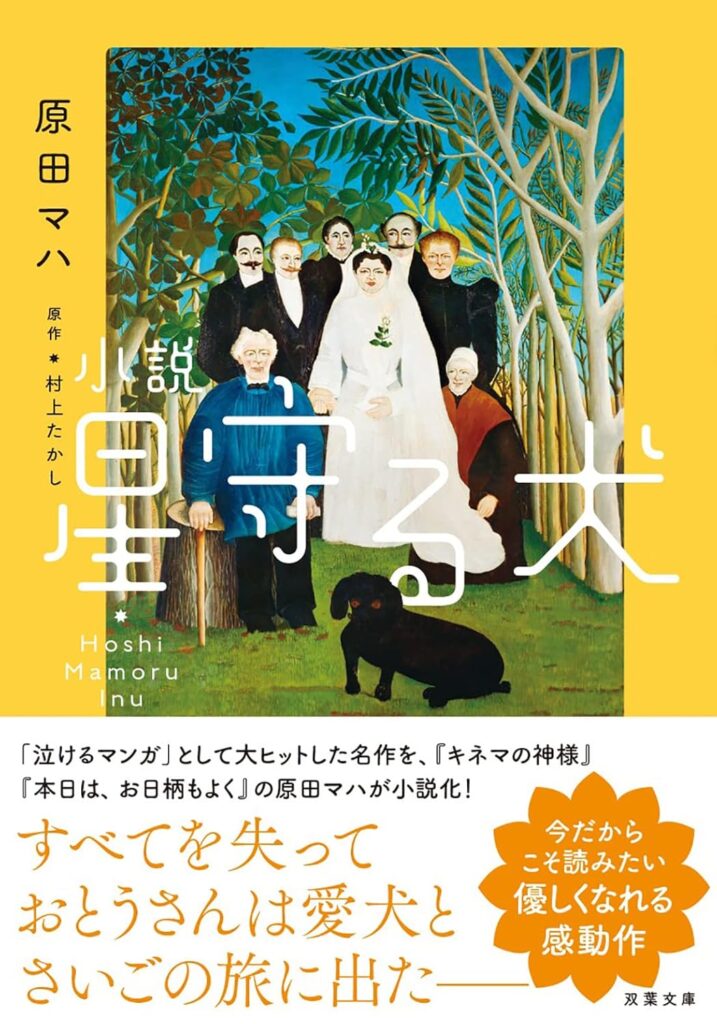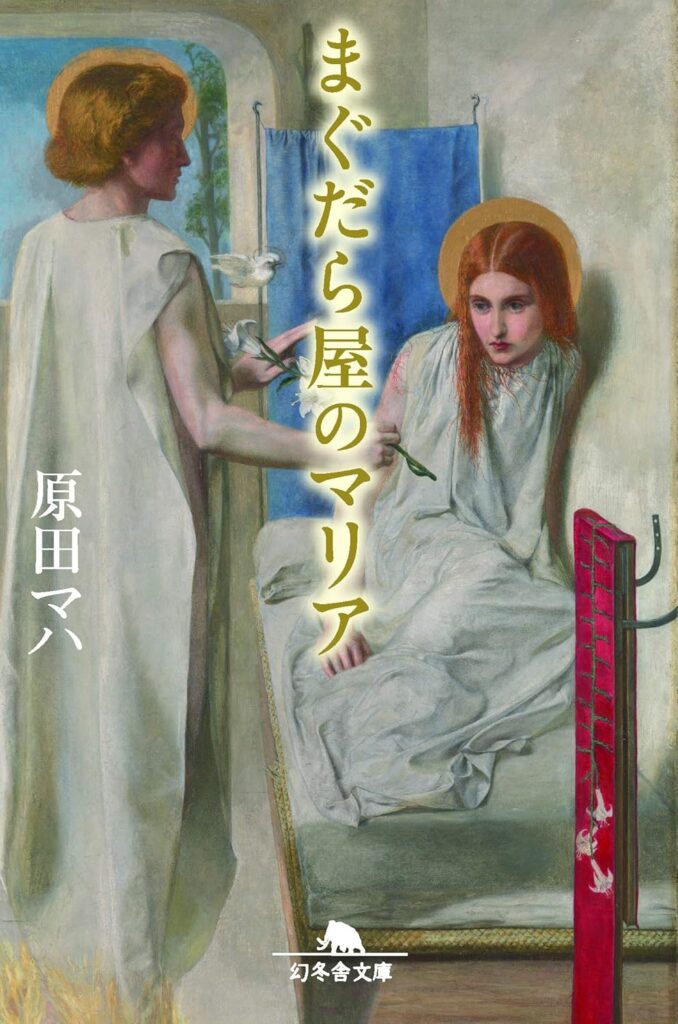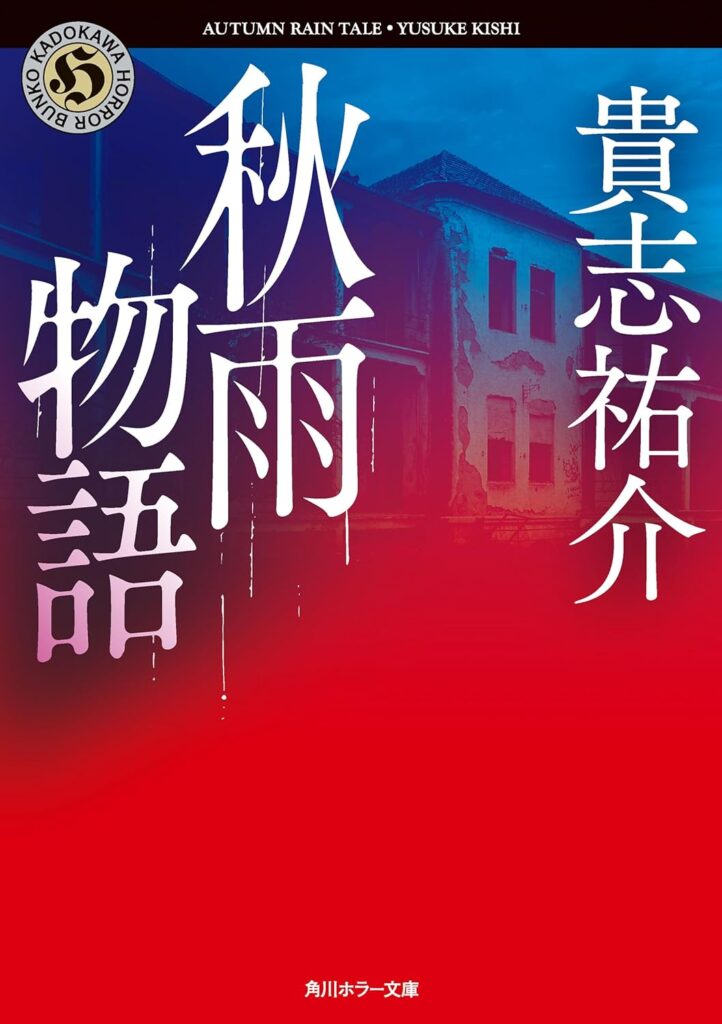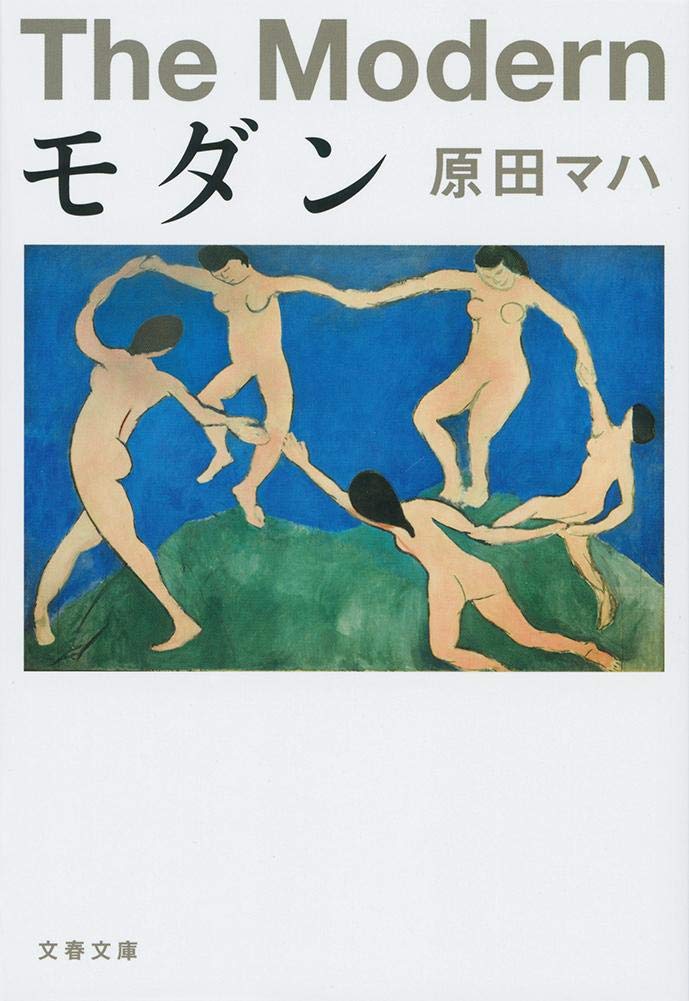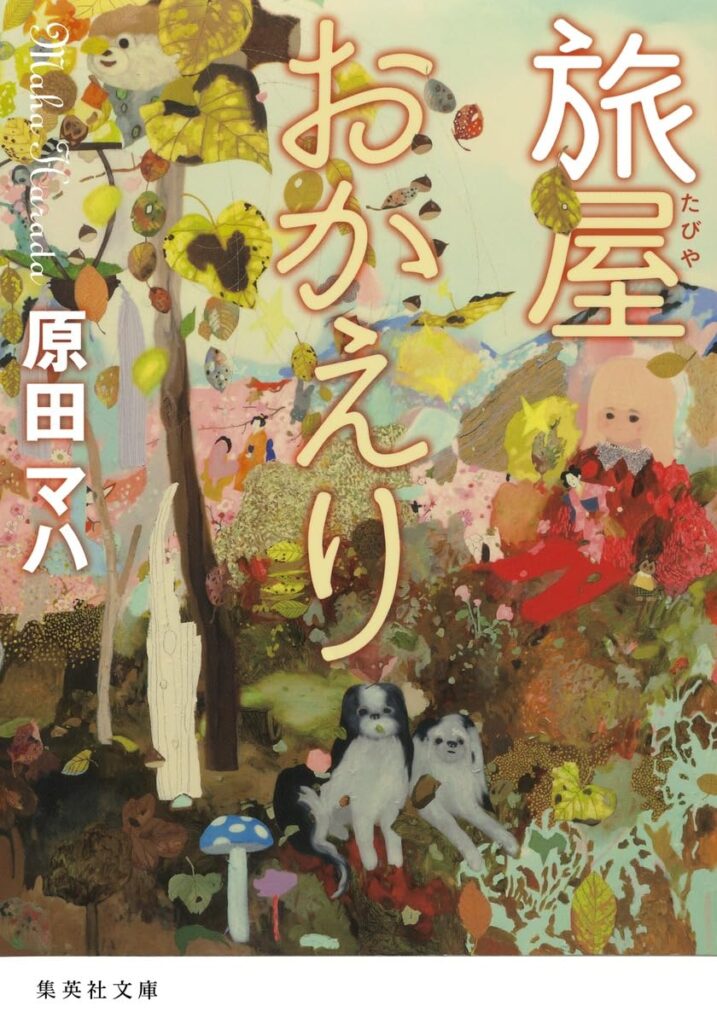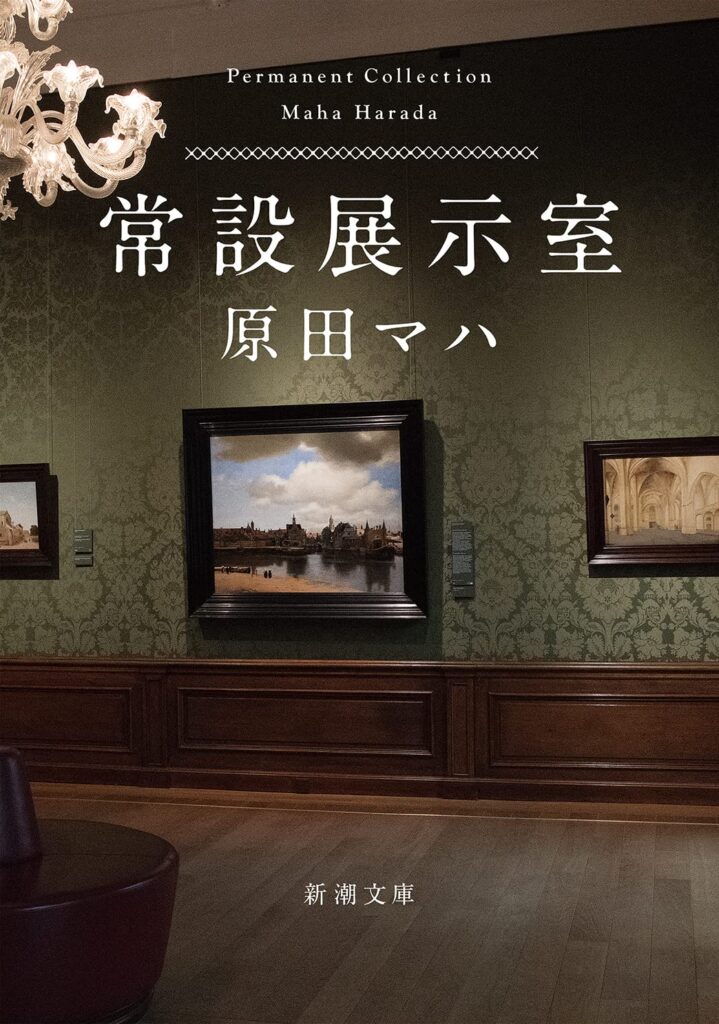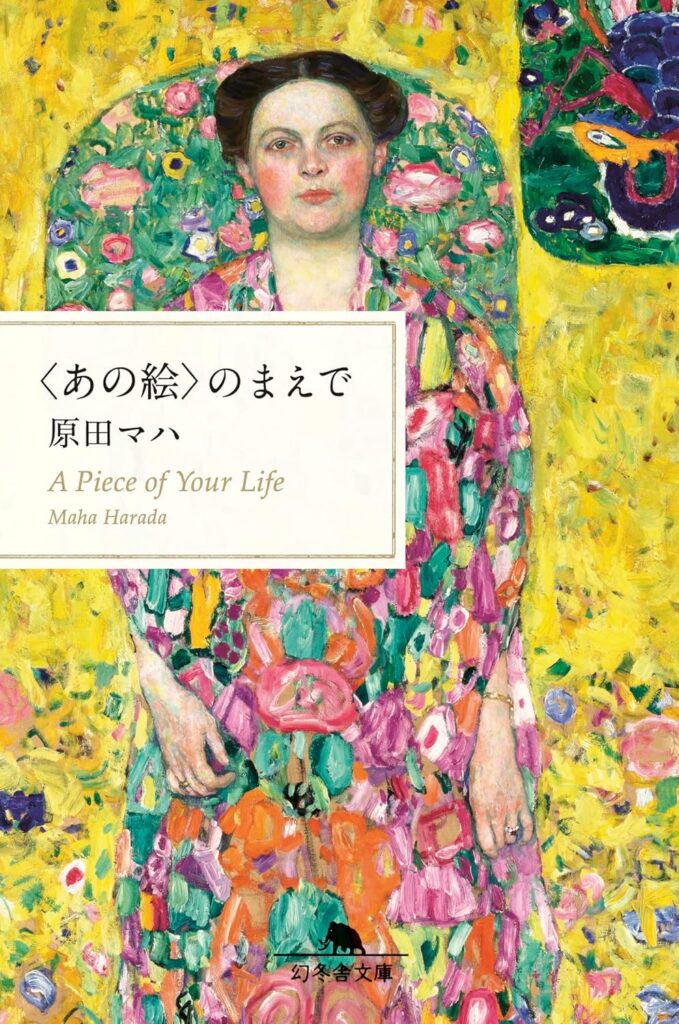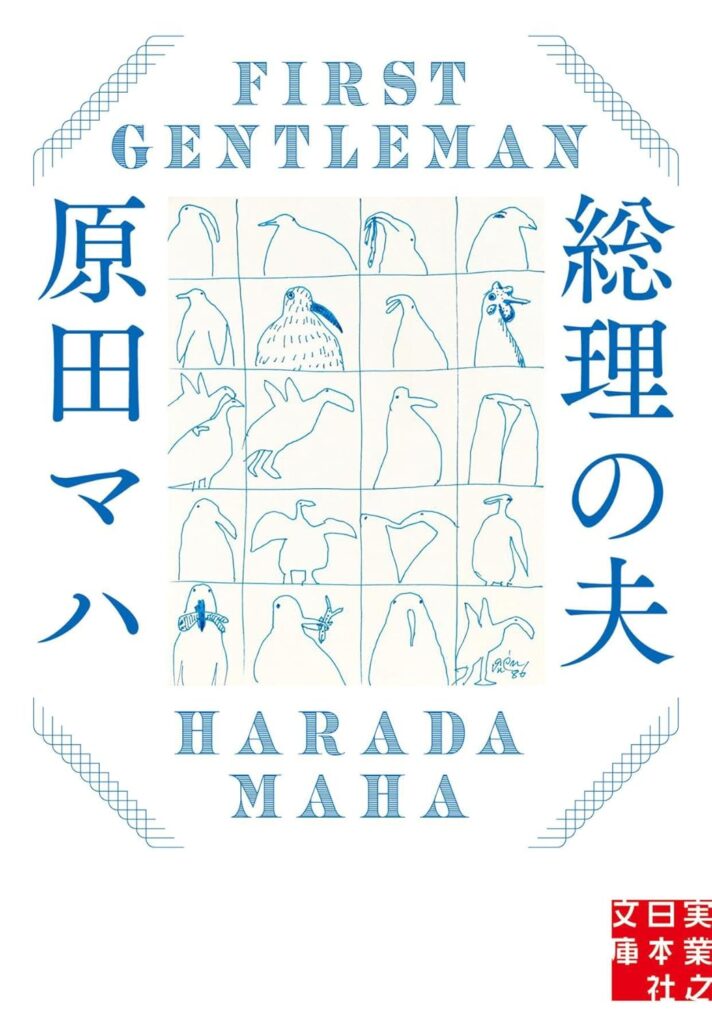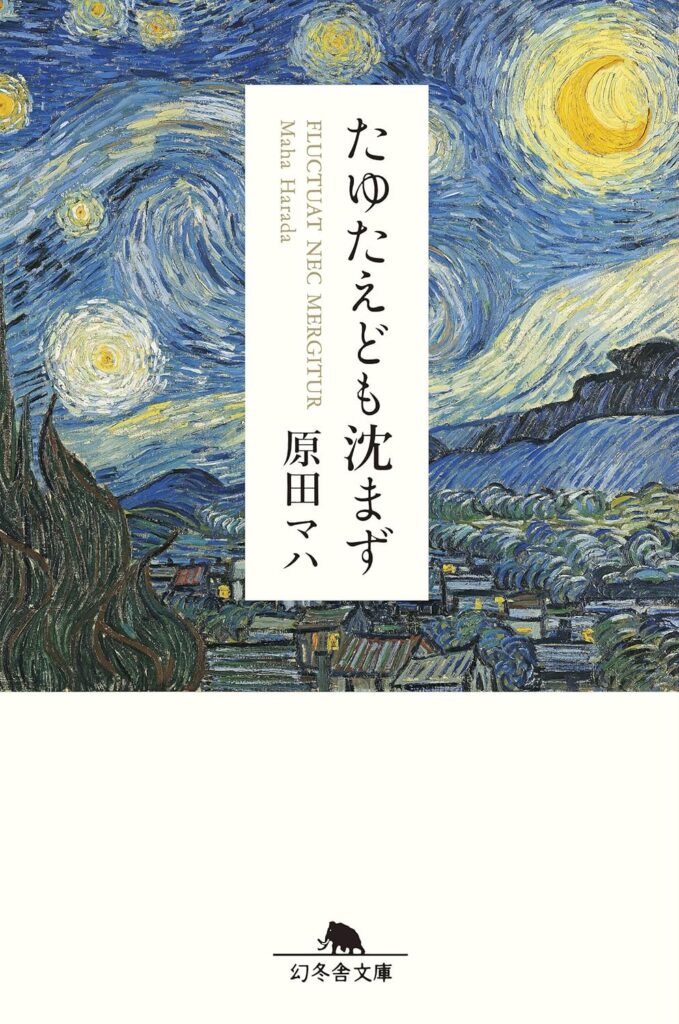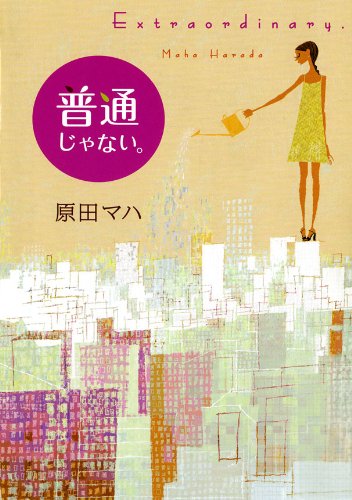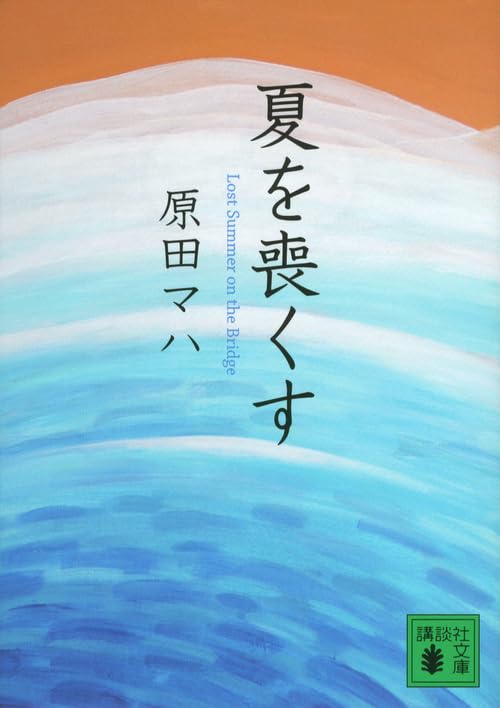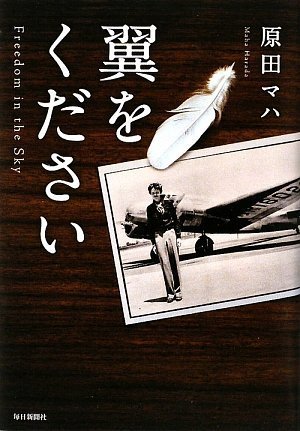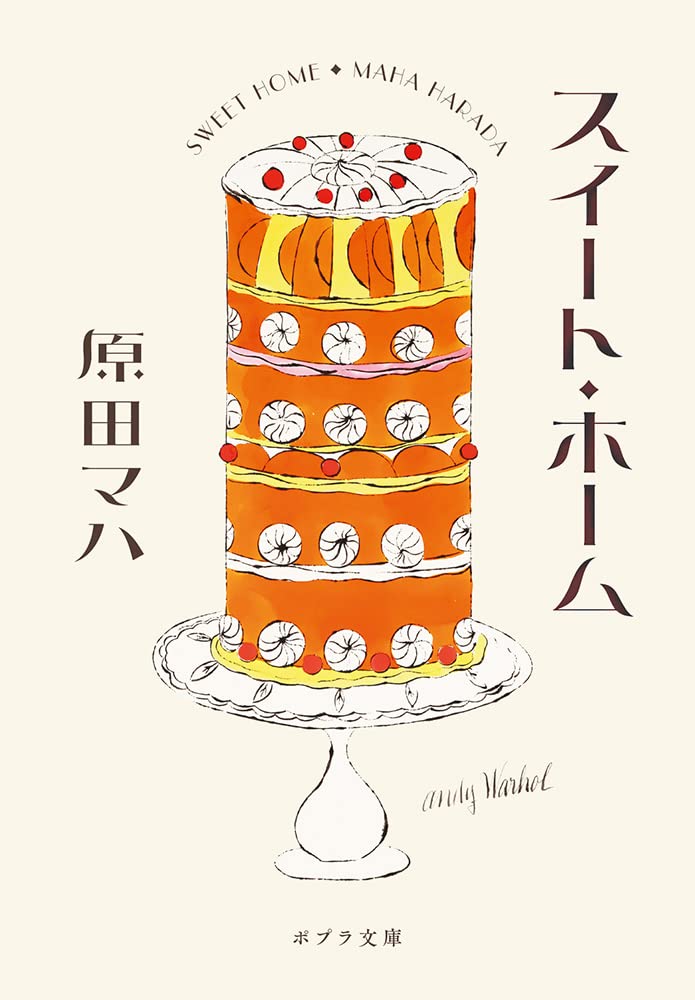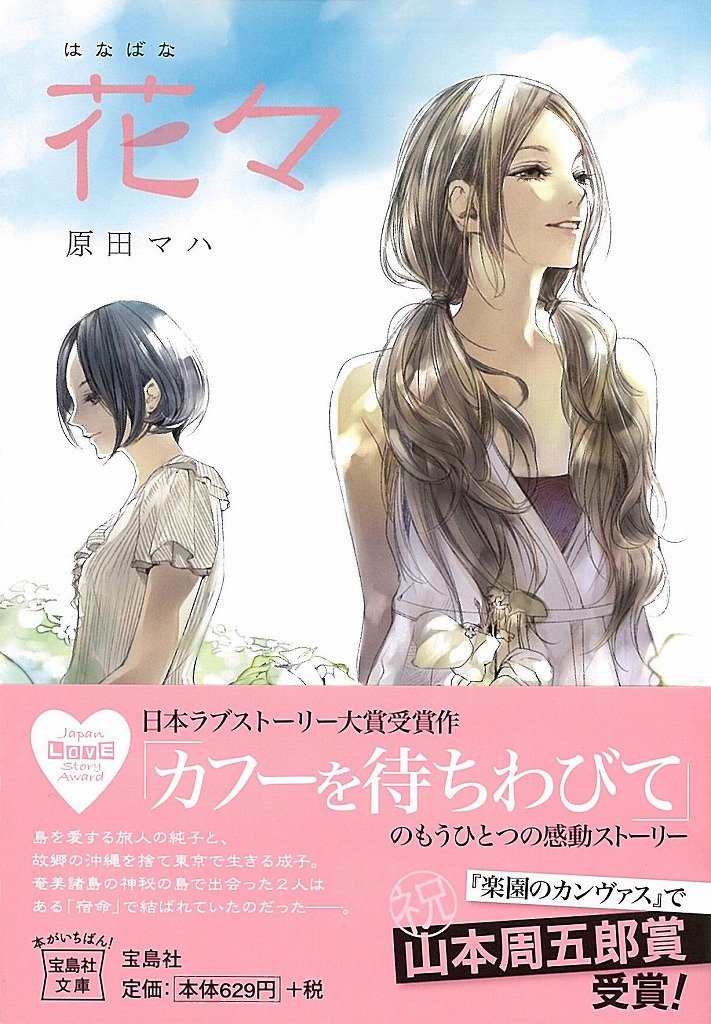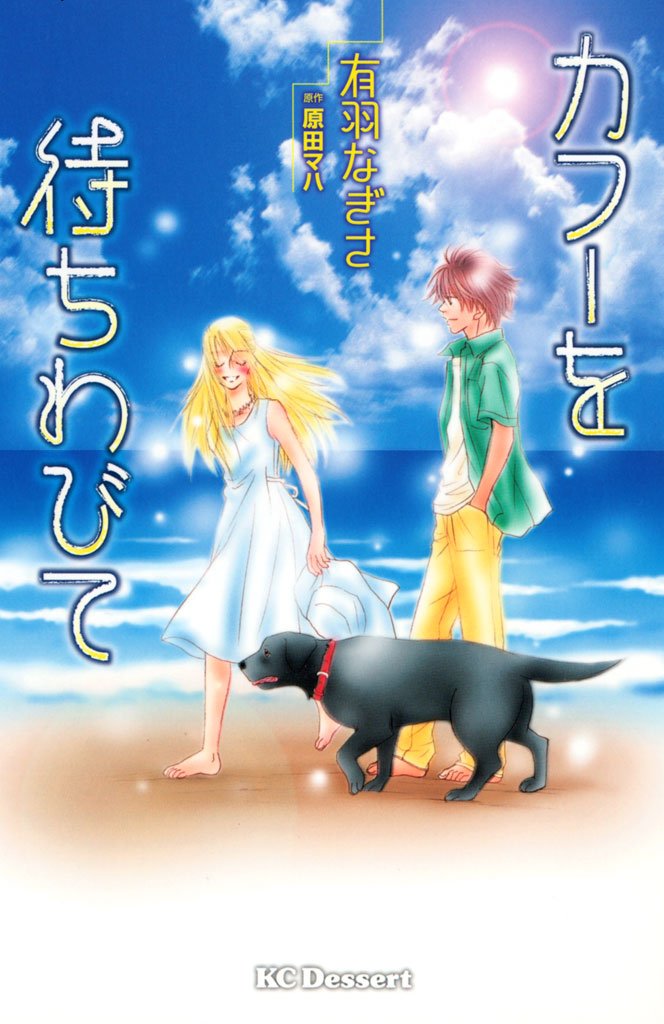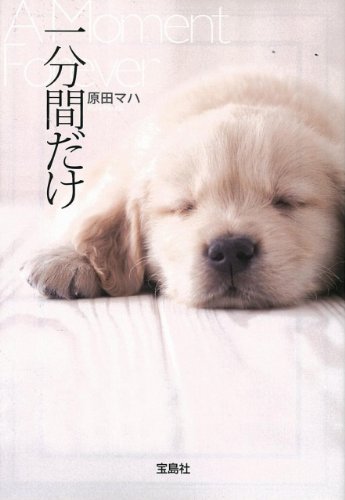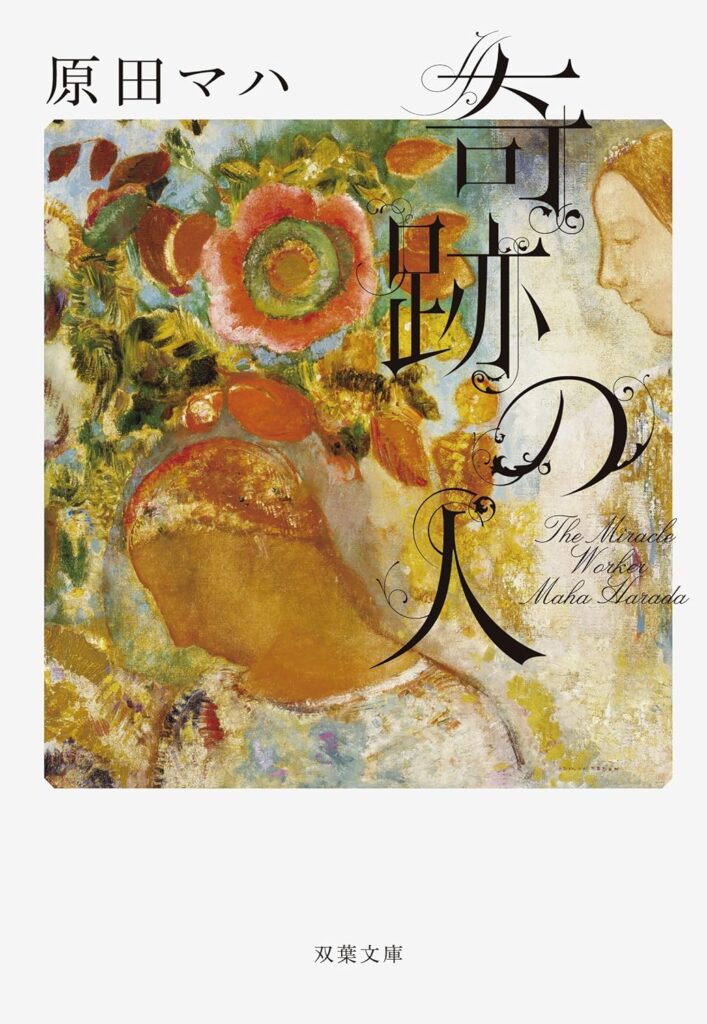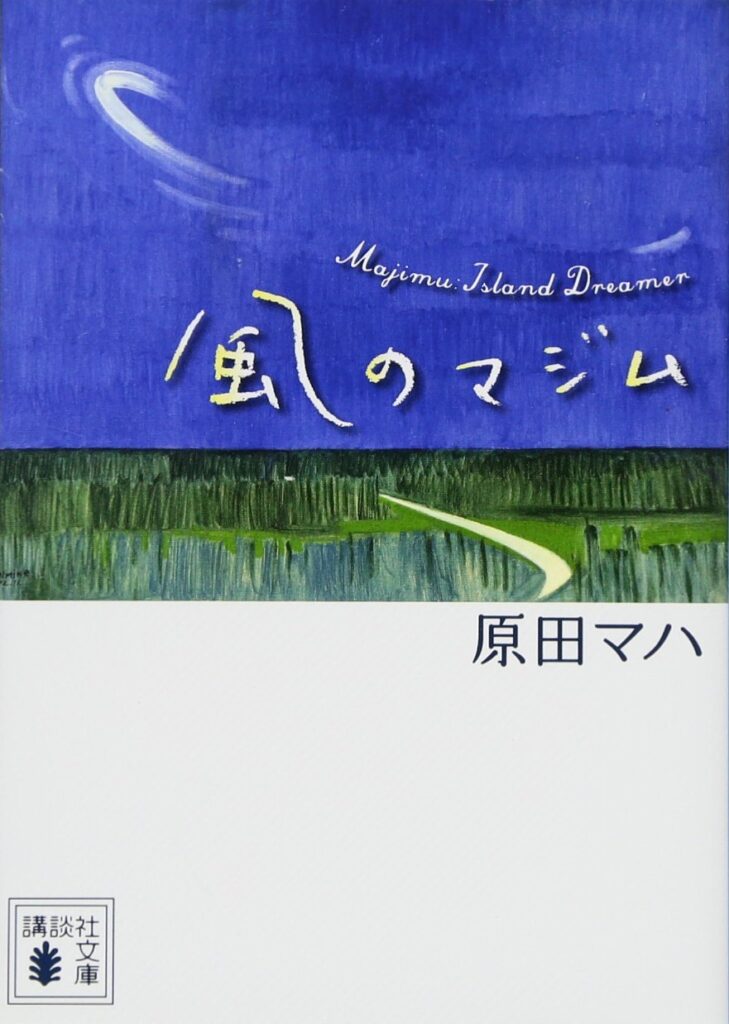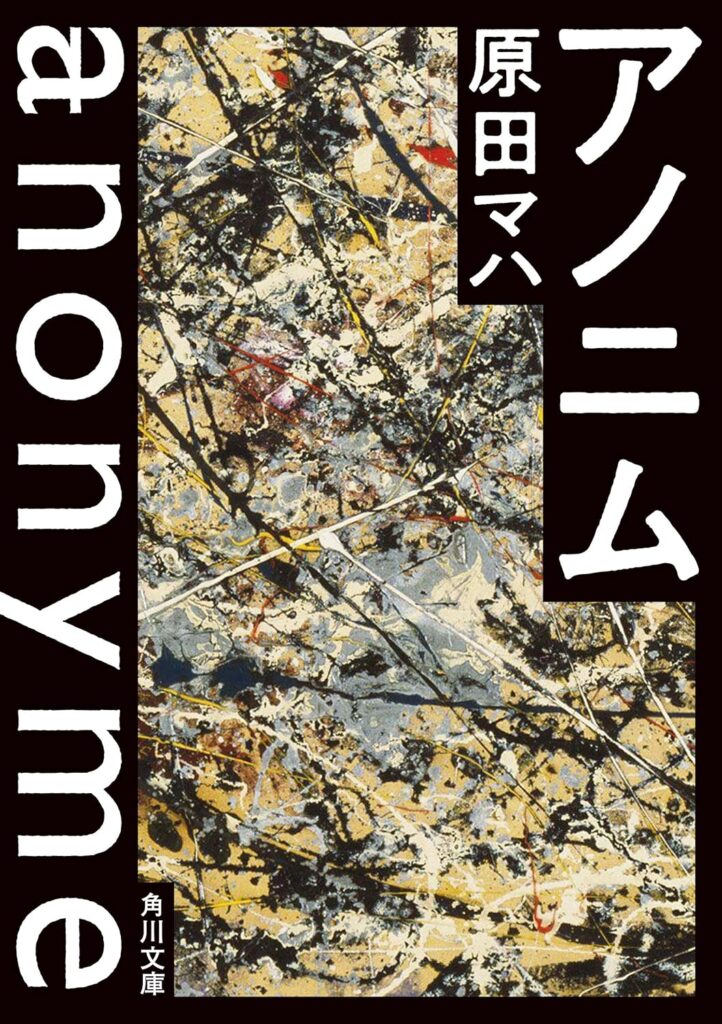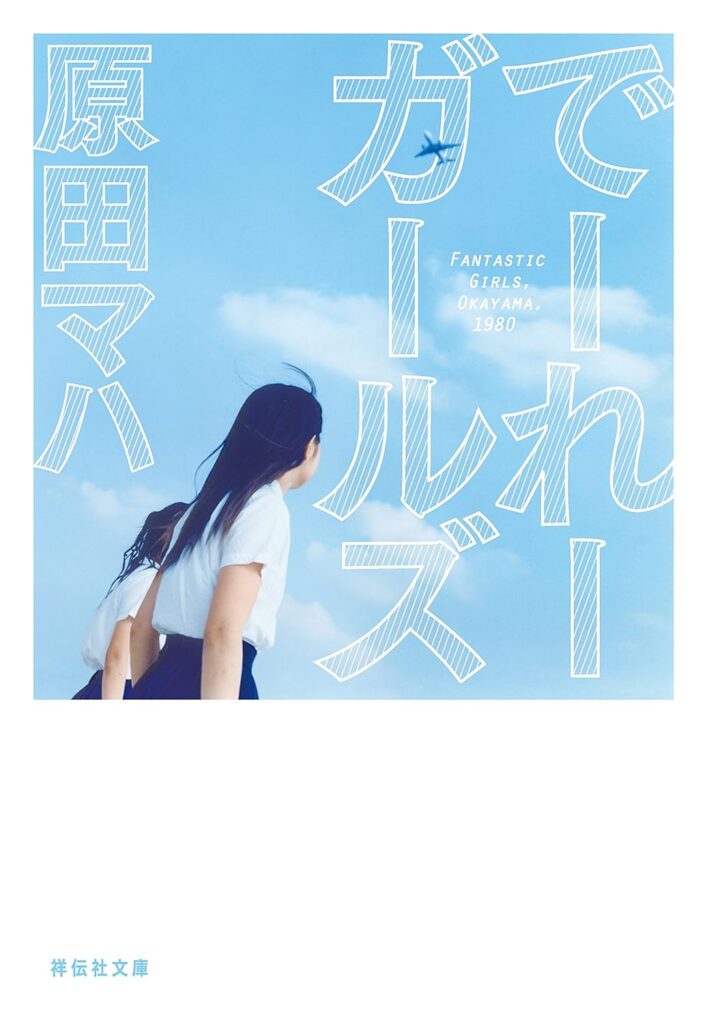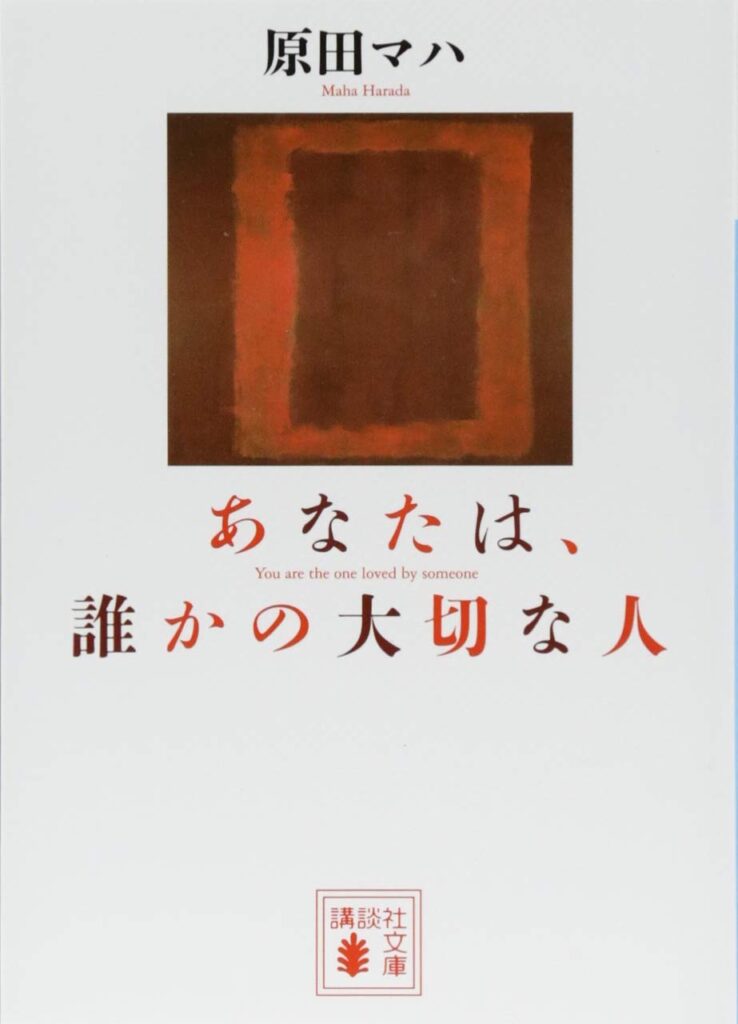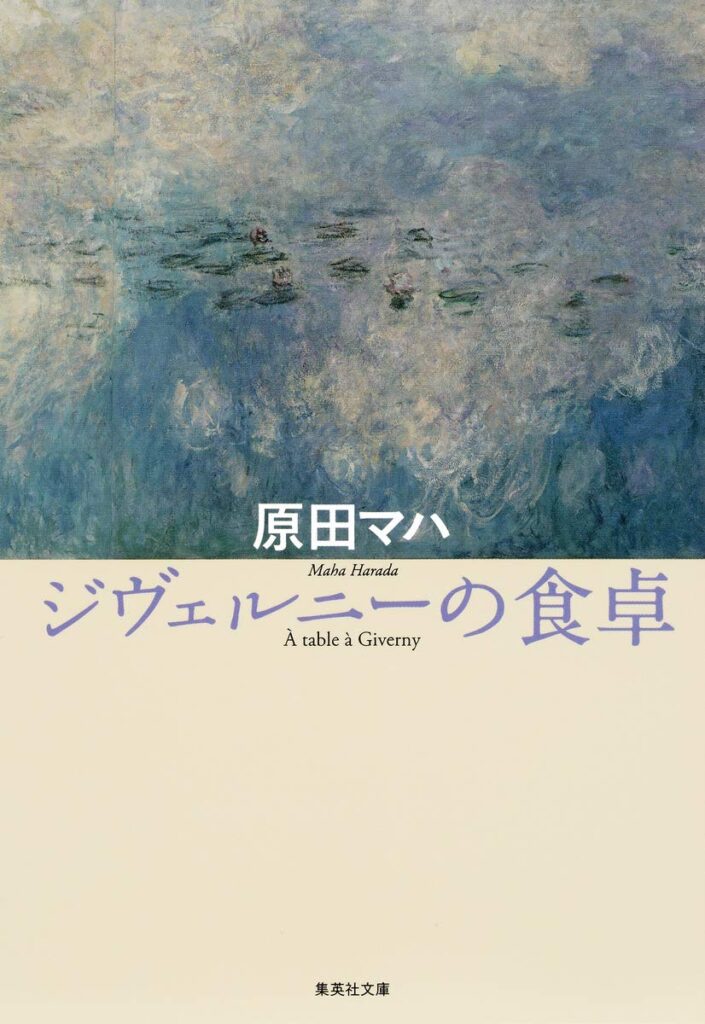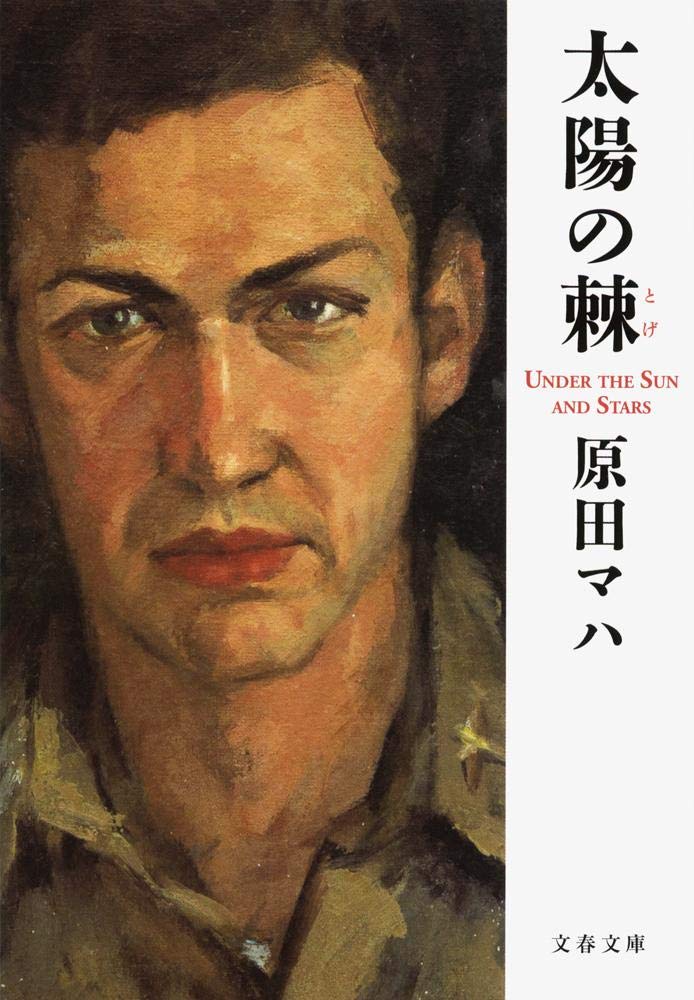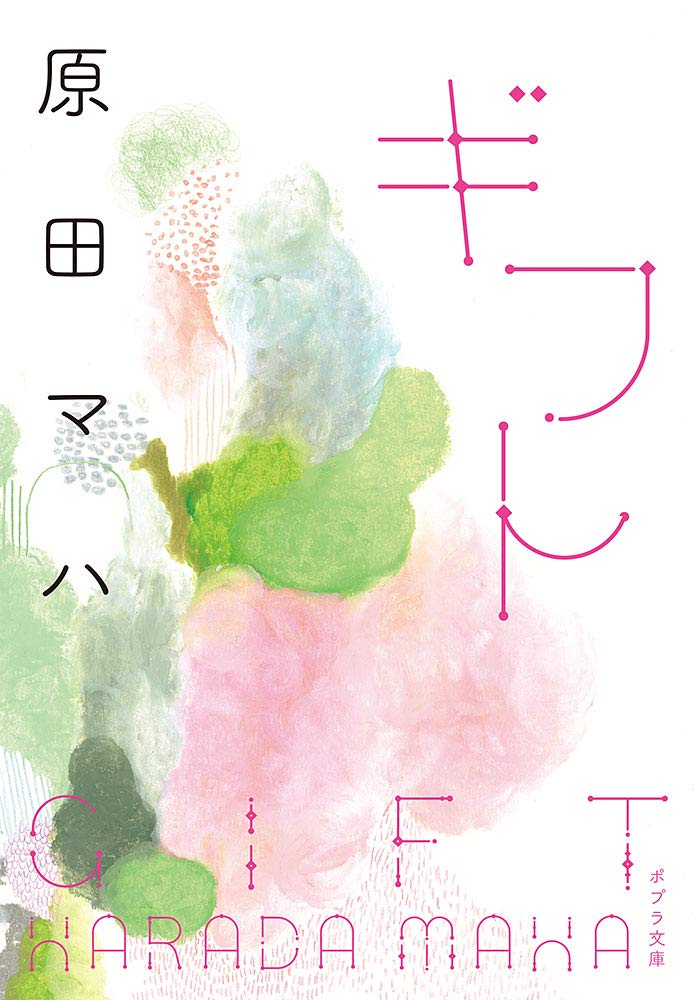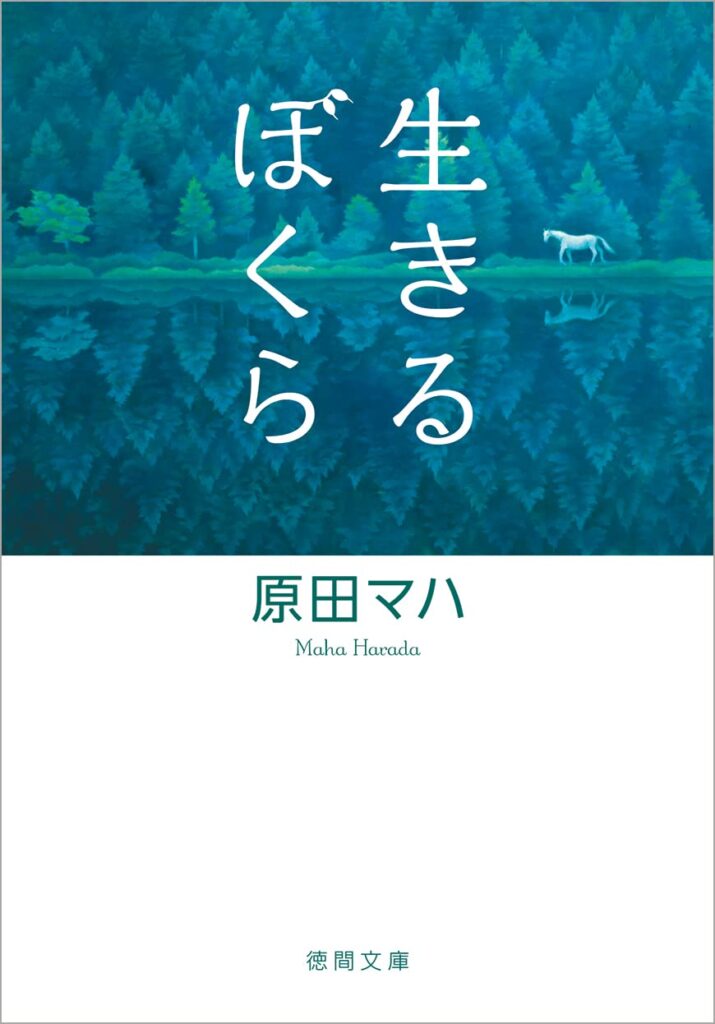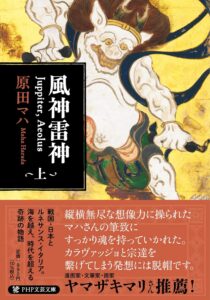 原田マハの『風神雷神』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
原田マハの『風神雷神』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
本書『風神雷神』は、現代の日本から始まり、過去へと読者を誘う「タイムカプセル」としての美術の役割を鮮やかに描き出しています。一つの謎めいた発見を契機に、読者は安土桃山時代へと誘われる壮大な歴史の旅へと導かれるでしょう。京都国立博物館に勤務する若き女性研究員、望月彩が、日本の至宝である「風神雷神図屏風」をはじめとする琳派の傑作群の展覧会を企画・運営する日常から物語は幕を開けます。彼女の専門性と芸術への情熱が、この物語の基盤を築いているのです。
平穏な研究生活は、マカオ博物館の学芸員を名乗るレイモンド・ウォンという男性の突然の来訪によって一変します。ウォンはキリスト教美術の専門家であり、彼の登場は、歴史の扉を開く決定的な触媒となるでしょう。ウォンの誘いを受け、彩がマカオを訪れると、そこで驚くべき発見が彼女を待っていました。それは、日本の象徴ともいえる「風神雷神」が描かれた西洋絵画でした。
この絵画は、本書『風神雷神』の副題にもなっている「ユピテル、アイオロス」(Juppiter, Aeolus)と題されており、その存在自体が東西美術の予期せぬ交錯を示唆しています。さらに、ウォンは天正遣欧少年使節の一員である原マルティノの署名が残る古文書を彩に提示します。これら二つの発見が、現代における美術史の謎として、物語の核心を形成していくのです。
小説『風神雷神』あらすじ
本書『風神雷神』は、現代と過去、日本と西洋という二つの時間軸と空間を縦横無尽に行き交いながら、歴史の謎に挑む壮大な物語です。物語の始まりは、京都国立博物館で働く若き研究員、望月彩の元にマカオ博物館の学芸員を名乗るレイモンド・ウォンが訪れる場面から始まります。ウォンは、マカオで発見された「風神雷神」が描かれた西洋絵画と、天正遣欧少年使節の一員であった原マルティノの署名が残る古文書を彩に見せます。
彩が古文書を調査する中で発見したのは、「俵屋宗達」という日本の美術史に燦然と輝く天才絵師の名でした。この発見が、本書『風神雷神』の最も大胆な設定へと繋がります。歴史上、その生涯に多くの謎が包まれている俵屋宗達が、実は天正遣欧少年使節団に同行し、ヨーロッパへ渡っていたのではないかという、作者原田マハの奇想天外な想像力が具現化されるのです。
物語は一転して安土桃山時代へと遡り、幼き日の宗達、すなわち伊三郎の非凡な才能が描かれます。彼は幼い頃から絵画において天賦の才を発揮し、その才能は天下統一を目指す織田信長の耳に届きます。12歳の伊三郎は信長が築いた安土城に召し出され、御前で絵の腕前を披露。信長は彼の独創的な絵に深く感銘を受け、「宗達」という名を与え、絵師としての道を正式に認めるのです。
信長に見出された宗達は、当代随一の絵師である狩野永徳と共に「洛中洛外図屏風」を制作する重要な命を受けます。この共同作業を通じて、宗達は絵師としてだけでなく、人間としても大きく成長していきます。永徳は宗達の才能に感銘を受け、彼を養子に迎えたいとまで考えるほどでした。
しかし、信長は宗達にさらなる極秘の任を課します。それは、イエズス会宣教師ヴァリニャーノの発案により派遣される天正遣欧少年使節団に同行し、永徳と共作した「洛中洛外図屏風」をローマ教皇グレゴリウス13世に献上するという、前代未聞の使命でした。時に宗達は14歳。これは歴史的事実としては確認されていない、本書『風神雷神』の最も大胆なフィクション的設定です。
日本からヨーロッパへの3年にも及ぶ命がけの航海、過酷な船旅、そしてアジアや中東での異文化体験を通じて、宗達と少年使節団の間に深い友情が芽生えていきます。彼らはポルトガルのリスボンに上陸し、ヨーロッパの壮麗な街並みや圧倒的な絵画や彫刻の数々に深い衝撃を受けます。イタリアへと進んだ宗達は、レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」や、ミケランジェロのシスティーナ礼拝堂天井画といったルネサンス美術の金字塔と対峙し、その芸術的視野を劇的に拡大させていくのです。
小説『風神雷神』の長文感想(ネタバレあり)
本書『風神雷神』を読み終え、私は深い感動と、美術史、そして人間の探求心というものについて、改めて深く考えるきっかけをいただきました。原田マハさんの作品にはいつも、芸術への深い愛情と、それを取り巻く人々のドラマが息づいています。しかし、この『風神雷神』は、その中でも一際、壮大で、そして大胆な物語の構築に挑戦されていると感じました。
物語の導入からして、私たち読者は、まるで時空を超える冒険のチケットを手渡されたかのような感覚に陥ります。現代の京都国立博物館という、静謐な学術の場から、遠くマカオ、そして安土桃山時代へと、舞台が目まぐるしく、しかしスムーズに展開していくのです。望月彩という現代の女性研究員の視点を通じて、私たちが慣れ親しんだ「風神雷神図屏風」という国宝に、全く新しい光が当てられることに、まず心を奪われました。西洋絵画の中に「風神雷神」が描かれているという発見、そして原マルティノの古文書に「俵屋宗達」の名が記されているという奇跡。これらが、現代の謎解きとして非常に巧妙に機能しており、読者の知的好奇心を刺激してやみません。
この現代の謎解きが、そのまま過去への扉を開く鍵となる構成が、本書『風神雷神』の最大の魅力の一つでしょう。歴史上、その生涯に多くの謎を持つ俵屋宗達が、実は天正遣欧少年使節団に同行していたという、この原田マハさんの「奇想天外な」想像力には、ただただ脱帽するばかりです。この大胆な設定こそが、この物語を単なる歴史小説に留まらない、唯一無二の存在へと昇華させているのだと感じました。歴史の空白に、これほどまでに説得力があり、かつ心躍るフィクションを紡ぎ出す手腕は、まさに圧巻の一言です。
安土桃山時代へと遡り、幼き日の伊三郎が、後に宗達となるまでの道のりが丹念に描かれている点も、非常に興味深く拝読しました。彼が幼い頃から絵の才能に恵まれ、それが織田信長の目に留まるという流れは、物語としてのドラマ性を高めると同時に、宗達という芸術家が、いかにしてその才能を開花させていったのかを、読者に自然に理解させてくれます。特に、信長が伊三郎に「宗達」という名を授ける場面は、彼の芸術的運命が決定づけられる瞬間として、強く印象に残りました。信長という当時の絶対的な権力者からの命名は、宗達が単なる職人から、天下に認められた「絵師」へと昇華したことを象徴しており、この歴史的ロマンには胸が高鳴りました。
そして、狩野永徳との共作という設定もまた、物語に深みを与えています。歴史上、宗達の師は不明とされることが多い中で、彼が当時の画壇の巨匠から直接指導を受けるという、理想的な環境が描かれていることで、宗達の芸術的背景に説得力が増しているように感じました。永徳との交流を通じて、宗達が絵師としてだけでなく、人間としても成長していく姿は、非常に温かい気持ちにさせてくれます。特に「洛中洛外図屏風」という、当時の日本の文化と社会を凝縮した作品を制作する過程は、宗達が自国の芸術的伝統を深く理解し、それを表現する力を養う上で極めて重要だったと解釈できます。
しかし、物語の本当の核心は、宗達が天正遣欧少年使節団に同行し、ローマ教皇グレゴリウス13世に「洛中洛外図屏風」を献上するという、極秘の使命を帯びるところから始まります。この「もしも」の歴史は、読者に想像の翼を広げさせ、同時に、当時の世界がどれほど広く、そして危険に満ちたものであったかを改めて認識させてくれます。14歳という若さで、宗達が単身でこのような長期間の、まさに死と隣り合わせの旅に出ることは、並外れた勇気と精神力を要する行為だったことが、本書『風神雷神』では繰り返し強調されます。
3年にも及ぶ命がけの航海は、まさに少年たちの人間的な成長を促す「試練の場」として描かれています。嵐に遭遇し、常に船が沈没する危険と隣り合わせの状況で、宗達と少年使節団の間に芽生える友情は、読者の心を強く打ちます。当初はキリシタンではない宗達と、敬虔なキリスト教徒である少年使節団の間にあった距離が、過酷な旅路を共にする中で、深い絆へと変わっていく様は、感動的としか言いようがありません。特に原マルティノとの強い絆は、この旅が単なる地理的な移動ではなく、少年たちの人間的な成長を促す「育成の場」であったことを強く示唆しています。彼らが異なる生い立ちや信仰を持ちながらも、共通の困難を乗り越え、互いを理解し、尊重し合う姿は、時代や文化を超えた普遍的なテーマを私たちに提示しています。
アジアや中東での寄港地の描写も、旅の彩りを豊かにしています。それぞれの地で目にする多様な文化、言語、風習は、日本の常識とは異なる世界があることを彼らに認識させ、その後のヨーロッパでの経験に対する心の準備を促します。これらの初期の異文化体験は、少年たちの視野を広げ、彼らが西洋文明の芸術や思想に触れる際の受容性を高める上で、重要な役割を果たしたことでしょう。彼らは、異文化の洗礼を段階的に受けながら、来るべきルネサンスとの出会いに備えていくのです。
そして、ついにヨーロッパ上陸です。ポルトガルのリスボンに足を踏み入れた宗達をはじめとする少年たちが、その壮麗で異質な街並み、そして至る所に溢れる圧倒的な絵画や彫刻の数々に深い衝撃を受ける場面は、読者もその感動を共有できるほどに鮮やかに描かれています。このヨーロッパ上陸の描写は、宗達の芸術的感性にとって決定的な瞬間となったと確信しました。日本の伝統的な美意識の中で育った彼が、全く異なる表現様式を持つ西洋美術に触れることで、その芸術的視野が劇的に拡大していく過程は、非常に胸が熱くなるものがありました。この強烈な視覚的、精神的な刺激が、宗達の絵画への情熱を再燃させ、彼自身の芸術が新たな次元へと進化していくための重要な触媒となることは、想像に難くありません。
イタリアへと旅が進み、ルネサンスの中心地で、宗達がレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」や、ミケランジェロによるシスティーナ礼拝堂天井画といった傑作群を目の当たりにする場面は、まさに圧巻でした。これらの作品との出会いが、宗達の心に深い感動と衝撃を与え、彼の絵画に対する情熱を一層掻き立てる様子は、私たち読者も彼と共にその場に立ち会っているかのような臨場感を与えてくれます。宗達が「イタリア・ルネサンスを体験する」というこの設定は、東西の芸術が時を超えて響き合う、本書『風神雷神』の根幹をなすテーマを象徴しているのだと感じました。西洋美術の圧倒的なスケールと表現力は、宗達の芸術観に新たな地平を切り拓いていくことになります。
しかし、ルネサンスの芸術的宝庫に囲まれながらも、宗達が深い葛藤を抱えていたという描写は、彼の人物像に奥行きを与えています。使節団の一員という「貴族の使者」としての立場が、彼に最高の歓待とアクセスを保証する一方で、彼が心から望む行動、つまりヨーロッパの画家たちの工房を自由に訪れ、彼らの技法を直接学びたいという強い願望を妨げていたという皮肉な状況は、彼の内面に大きな葛藤を生み出します。この内面的な苦悩は、宗達が単なる受動的な観察者ではなく、自らの芸術を深く追求しようとする情熱的な芸術家であることを浮き彫りにしています。この葛藤を乗り越えた先に、彼の真の芸術的開花が待っているのだと、期待に胸を膨らませました。
そして、物語の最も劇的な瞬間は、使節団がイタリアを出発する直前に訪れます。宗達が、後にバロック絵画の巨匠となる若きミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョと運命的な出会いを果たす場面は、まさに本書『風神雷神』の白眉と言えるでしょう。歴史上は接点がないとされるこの二人の天才を、原田マハさんが大胆な想像力で結びつけるその筆致には、感嘆符をつけざるを得ません。作者は、宗達とカラヴァッジョが同時代を生きていたという歴史的事実を強調し、当時ミラノで修行中であったカラヴァッジョが、遠い日本から来た少年使節団のニュースを知らないはずがないという説得力のある背景を設定しています。
この出会いが、わずか「一日限り」の短いものであったにもかかわらず、「まばゆいほどに美しい場面」として描かれ、二人の若き芸術家の間に瞬く間に強い絆が生まれる様は、読者の心に深く刻まれます。カラヴァッジョの写実的な描写と、明暗をはっきりと分けた表現(キアロスクーロ)が、後の宗達の作品、特に「風神雷神図屏風」における斬新な表現に、間接的な影響を与えた可能性を示唆しているという視点は、非常に説得力がありました。例えば、伝統的に赤や青で描かれることの多かった雷神を白で表現した点や、屏風の左右両端ぎりぎりに風神雷神を配し、無限の広がりを想起させる動的な構図は、西洋美術のドラマティックな表現や構図の影響を読み解くことができるかもしれないという考察には、はっとさせられました。この架空の邂逅は、芸術の普遍性と、時代や文化を超えて魂が共鳴し合う奇跡を象徴しているのだと感じました。原田マハさんは、この出会いを描くことで、歴史の残酷さ(使節団の帰国後の運命やカラヴァッジョの波乱の生涯)を知る後世の読者にとって、一瞬の「慰め」となるような、希望に満ちた瞬間を創造しようとしたのだと、その意図に深く共感しました。
天正遣欧少年使節団の旅の最大の目的であった、ローマ法王グレゴリウス13世との謁見、そして信長の命を受けた宗達が、永徳と共作した「洛中洛外図屏風」を法王の御前で自ら広げ、披露する場面は、本書『風神雷神』の壮大な旅のクライマックスとして描かれています。臨場感あふれる筆致で描かれたこの場面は、読者をまるでその場に立ち会わせているかのような興奮を与えてくれます。この謁見は、宗達に課せられた極秘の使命の達成を意味し、同時に、日本の文化と芸術が西洋世界の最高峰に紹介された、画期的な文化外交の瞬間として、深く記憶に残りました。それは、東西文明が芸術を通じて対話し、相互に影響を与え合う可能性を象徴する、壮大な旅の終着点として描かれているのです。
壮大な旅を終え、物語が少年たちの帰路と、彼らを待ち受ける歴史の現実、そして現代へと回帰する終章は、芸術の普遍性と、それが時代を超えて人々の魂に語りかける意義を深く問いかけるものでした。往復3年にも及ぶ長旅を通じて、宗達をはじめとする少年たちが、精神的にも肉体的にも大きく成長を遂げる姿は、彼らが幼い少年から逞しい若者へと変貌を遂げたことを明確に示しています。彼らが未来への「まぶしい」希望を胸に抱いていたことを示唆する描写は、その後の歴史が持つ悲劇性との対比を際立たせ、読者に深い「切なさ」や「悲しみ」という感情的な層を加えることに成功しています。
本書『風神雷神』は、天正遣欧少年使節団の帰国後の運命については、直接的な詳細を避けているものの、その後の彼らを待ち受ける過酷な現実、特にキリスト教弾圧の激化という歴史的事実を暗示的に示唆しています。読者が持つ歴史的知識、すなわち使節団のメンバーが帰国後に直面した苦難や殉教といった悲劇は、物語の希望に満ちた旅路の描写に、一層の深みを与えます。エピローグでは、この過酷な現実にわずか二行で触れるに留め、物語の主要な焦点が、旅の途上での芸術的探求と少年たちの成長に置かれていることを明確にしている点は、作者の意図が明確に伝わってきました。この叙述の選択は、歴史の残酷さを認識しつつも、芸術の持つ超越的な力と、人間的な絆の尊さを強調する作者の意図を反映しているのだと感じました。歴史は時に残酷な側面を持つが、それゆえにこそ、人々は過去から学び、先人たちが残した知恵を現在に活かすことができる。本書『風神雷神』は、この歴史の真理を、芸術という「タイムカプセル」を通じて表現しているのだと強く感じ入りました。個人の人生は有限であり、悲劇に見舞われることもあるが、彼らが創造した芸術作品は、時代を超えて生き続け、人々の魂を揺さぶり続ける。これは、天正遣欧少年使節団の少年たちや、カラヴァッジョが辿った波乱の生涯と対比され、芸術が持つ不朽の価値を際立たせる効果を生み出しています。
物語は再び現代の望月彩の元へと戻り、西洋の「風神雷神」絵画を巡る謎が、宗達の旅の物語と結びつくことで、現代と過去、そして芸術の普遍性というテーマが鮮やかに結びつきます。宗達の代表作である「風神雷神図屏風」における、伝統的な表現からの逸脱(例えば、雷神が白く描かれている点や、風神雷神が屏風の端に配置されている動的な構図)が、彼がヨーロッパで経験したルネサンス美術やバロック美術からの影響を、物語の枠組みの中で示唆している点は、美術史の知識とフィクションが融合した、まさに原田マハさんならではの醍醐味だと感じました。この現代への回帰は、芸術作品が単なる過去の遺物ではなく、常に新たな問いを投げかけ、現代の私たちに語りかける「タイムカプセル」であることを改めて強調しています。過去と現在が交錯する二重構造は、歴史と芸術の遺産がいかに現代に響き、新たな探求を促すかを示すものとして、見事に機能しています。
原田マハさんの『風神雷神』は、単なる歴史冒険物語の枠を超え、芸術そのものの本質と、その普遍的な意義を深く考察する作品です。作者は、真の傑作には「純度の高い魂の煌めき」が宿っており、それが何世紀もの時を経ても色褪せることなく、時代や文化を超えて人々の魂を揺さぶり続けると訴えかけます。本書『風神雷神』は、作者自身の「アートとアーティストへの静かな祈り」が込められていると評されており、読者に対して、美術館を訪れ、傑作を直接体験し、芸術を次世代へと守り伝えることの重要性を暗に促していると感じました。それは「アートに満ちた壮大な冒険物語」であり、東西の文化を壮大なスケールで繋ぎ、「時を経て受け継がれる傑作の奇跡」を描き出しています。この作品は、歴史の残酷な現実や個人の悲劇的な運命を超えて、芸術が希望と慰め、そして不朽の美をもたらすという、原田マハさんの芸術哲学を体現しているのだと確信しました。宗達の「風神雷神図屏風」は、この物語の中で、東西の芸術的対話と影響の象徴となり、その革新的な表現は、彼の架空のヨーロッパ体験によって深みを与えられています。最終的に、本書『風神雷神』は芸術が持つ時空を超えた力、そしてそれが人間精神に与える計り知れない影響を力強く示唆し、私たち読者に深い感動と考察の機会を提供してくれる、まさに珠玉の一冊と言えるでしょう。
まとめ
本書『風神雷神』は、原田マハさんが紡ぎ出す、時空を超えた壮大な芸術の旅を描いた物語です。現代の京都国立博物館の女性研究員・望月彩が、マカオで発見された「風神雷神」が描かれた西洋絵画と古文書をきっかけに、日本の天才絵師・俵屋宗達が天正遣欧少年使節団に同行し、ヨーロッパへ渡っていたという大胆な仮説へと辿り着くという、歴史の謎と現代の探求が巧妙に絡み合っています。
物語は、幼き日の宗達が織田信長に見出され、「宗達」という名を授かることから始まり、狩野永徳との共作を経て、14歳にしてローマ教皇への「洛中洛外図屏風」献上という極秘の使命を帯びるまでの過程が、詳細かつドラマティックに描かれます。3年にも及ぶ命がけの航海、過酷な試練、そして少年使節団との間に育まれる友情が、読者の心を強く揺さぶるでしょう。
特に、イタリアで宗達がルネサンス美術の傑作群に触れる場面、そして後のバロック絵画の巨匠となる若きカラヴァッジョとの運命的な出会いは、本書『風神雷神』のクライマックスです。歴史上は接点がないとされる二人の天才を、原田マハさんが大胆な想像力で結びつけ、芸術が持つ普遍的な力と、時代や文化を超えて魂が共鳴し合う奇跡を見事に描き出しています。
本書『風神雷神』は、歴史の残酷さや個人の悲劇的な運命を超えて、芸術が希望と慰め、そして不朽の美をもたらすという、原田マハさんの芸術哲学を力強く提示しています。宗達の「風神雷神図屏風」が、東西の芸術的対話と影響の象徴として描かれ、その革新的な表現が、彼の架空のヨーロッパ体験によって深みを与えられている点も注目すべきです。この物語は、芸術が持つ時空を超えた力、そしてそれが人間精神に与える計り知れない影響を私たちに示唆し、深い感動と考察の機会を提供してくれることでしょう。

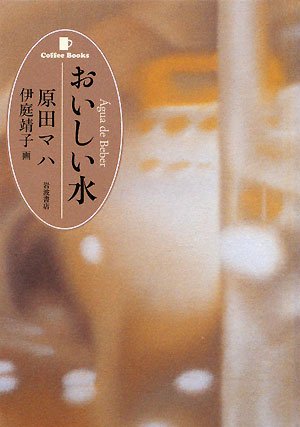
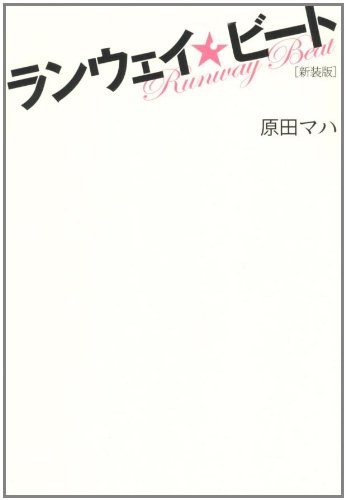
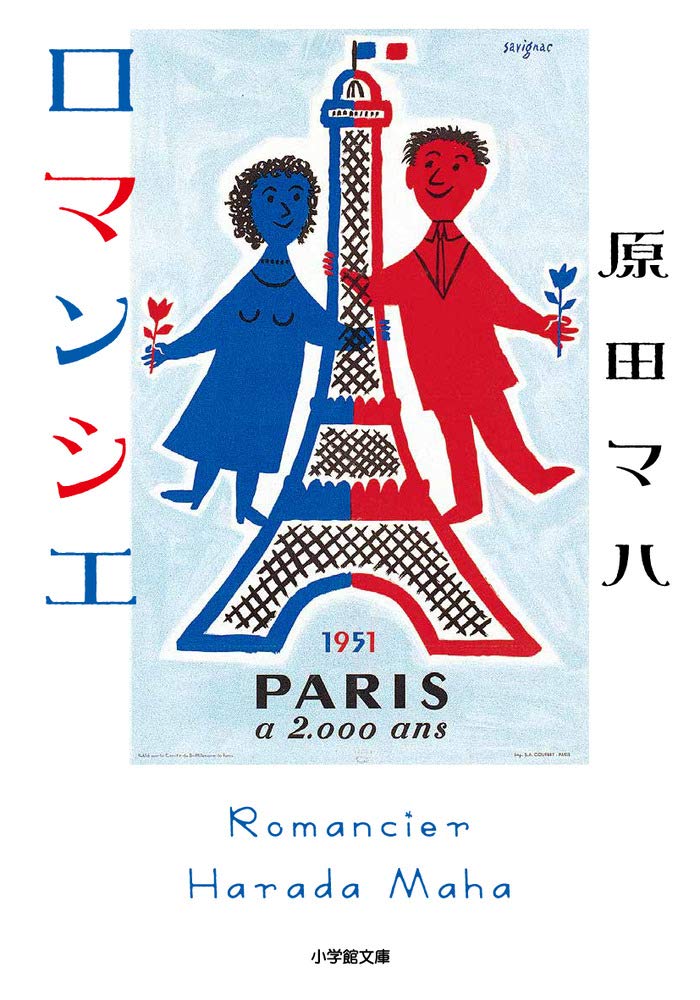
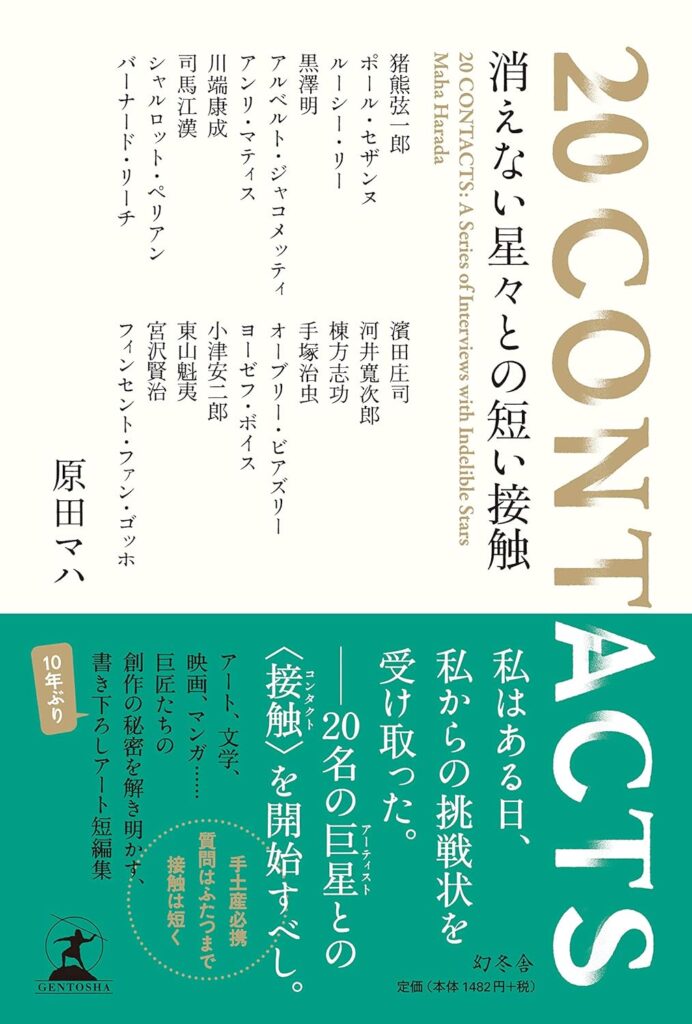
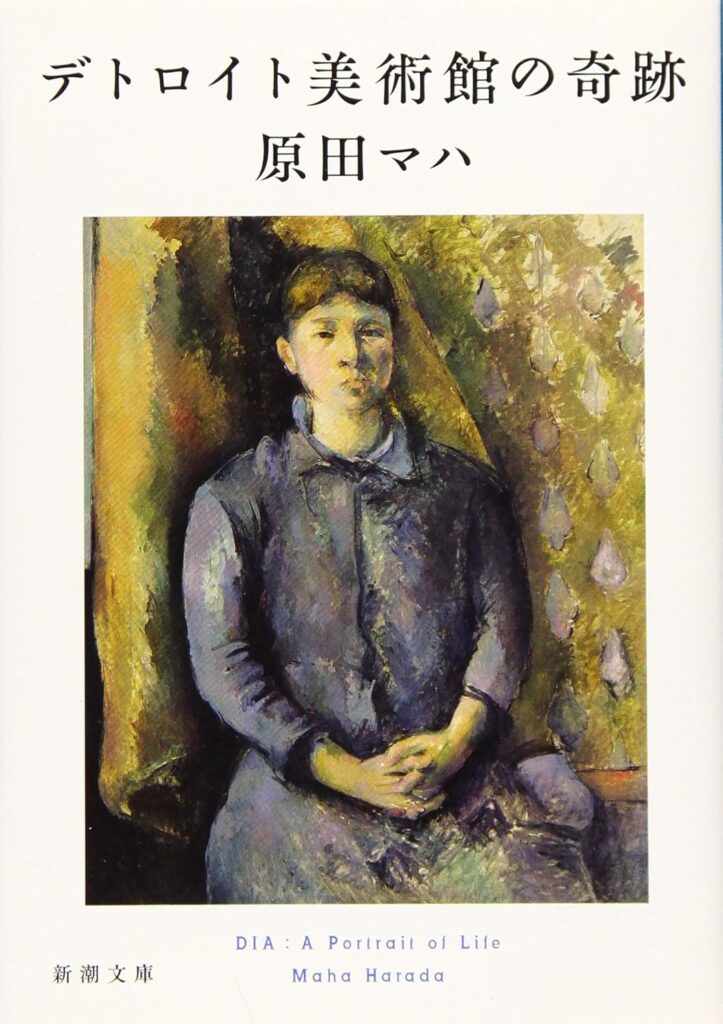
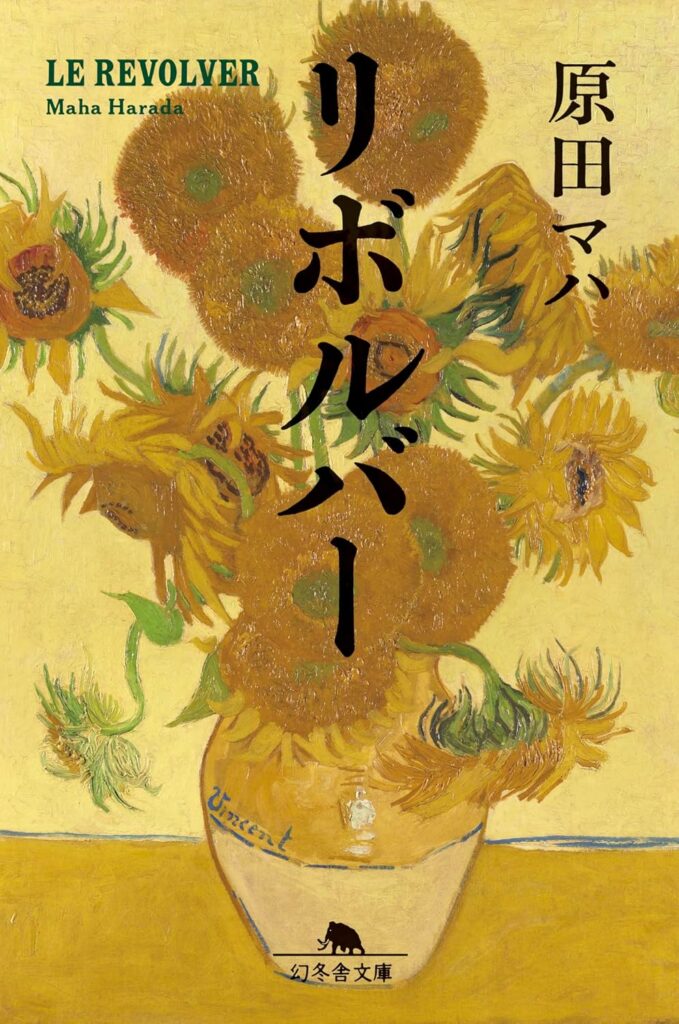
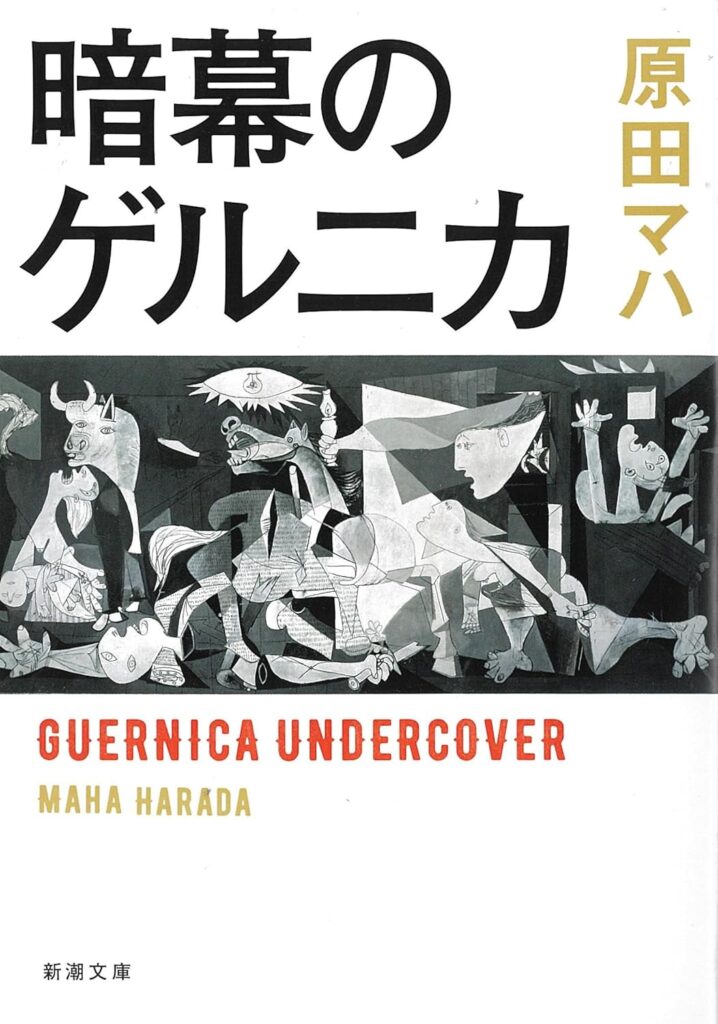
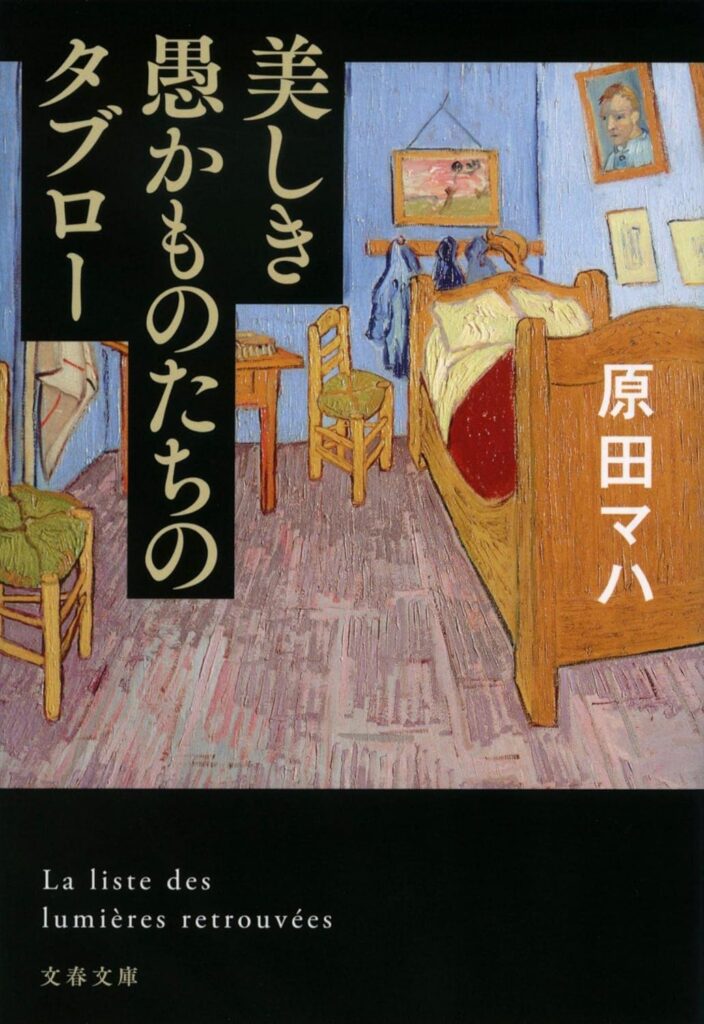
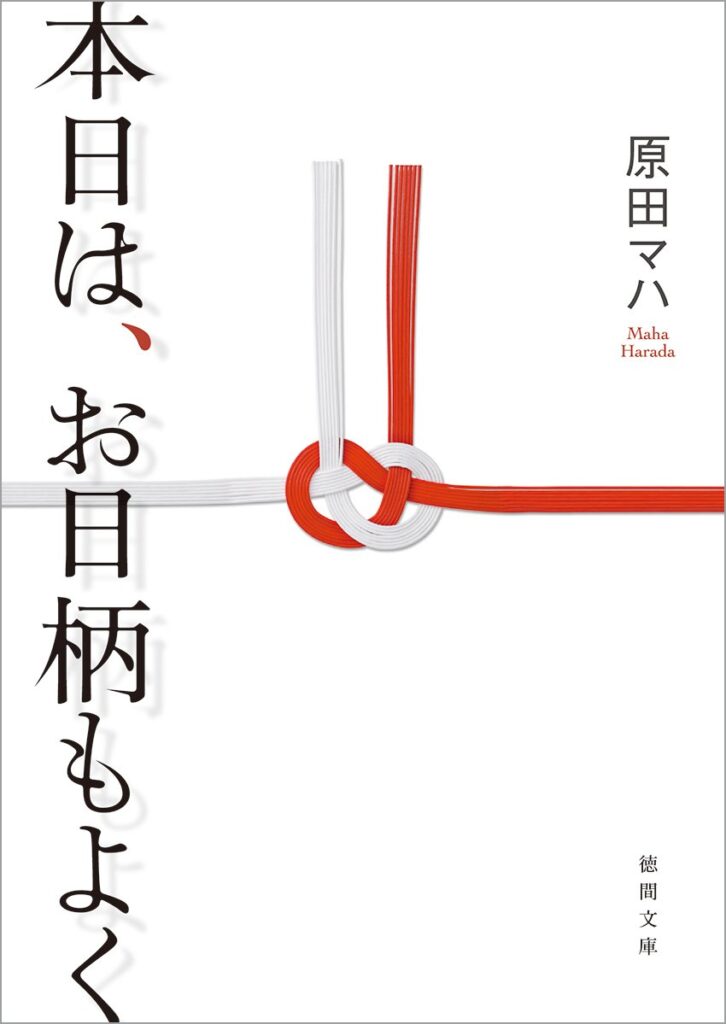
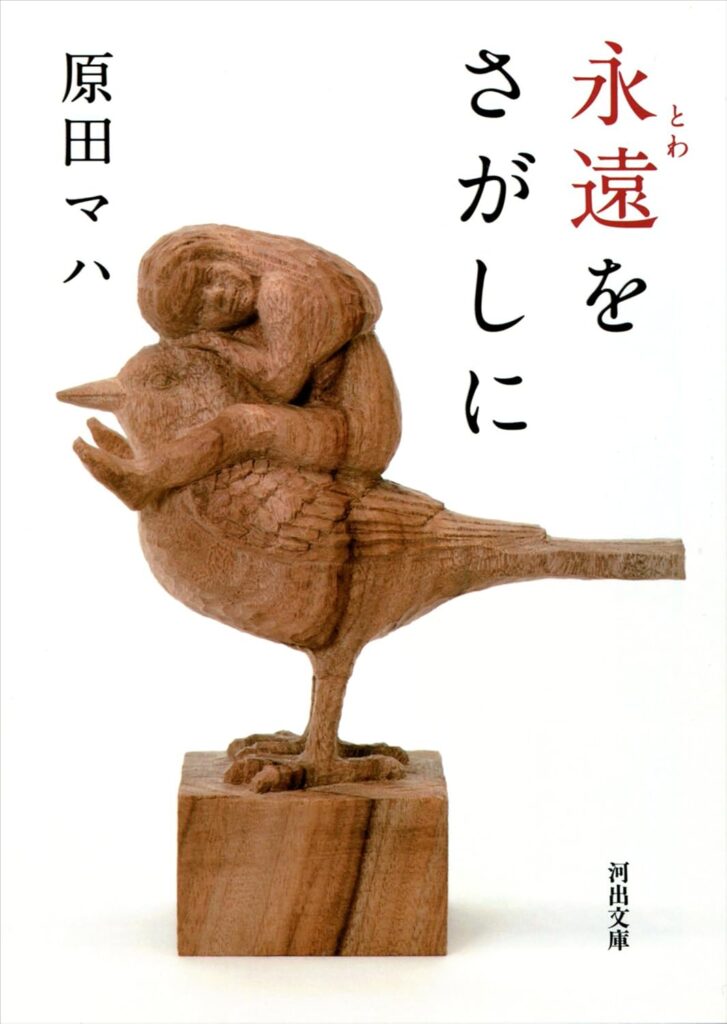
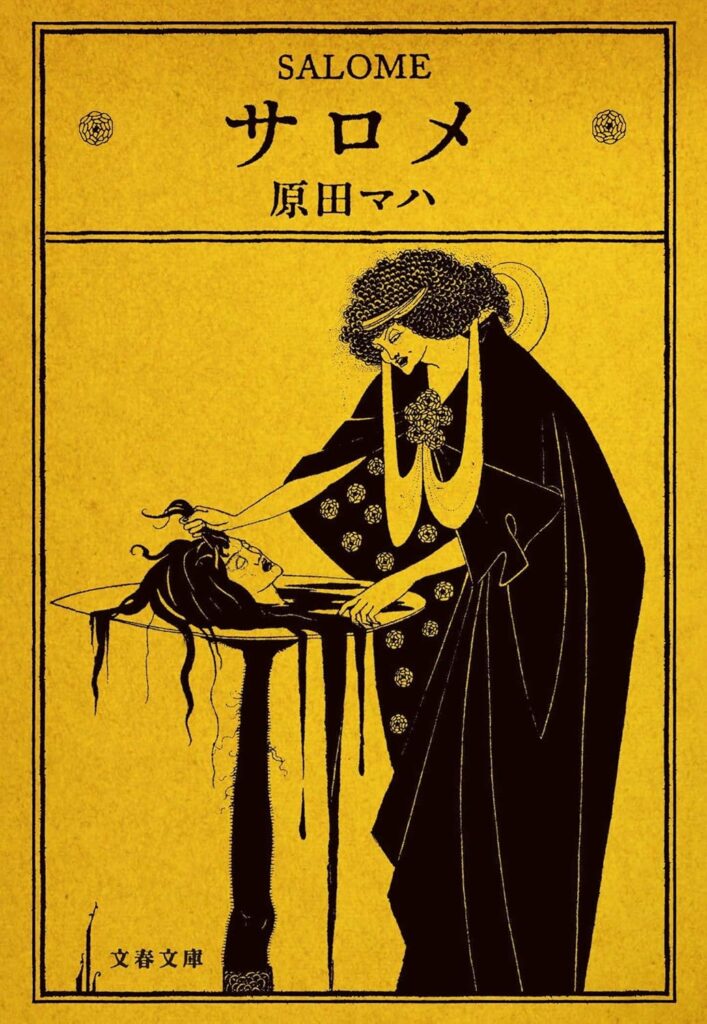

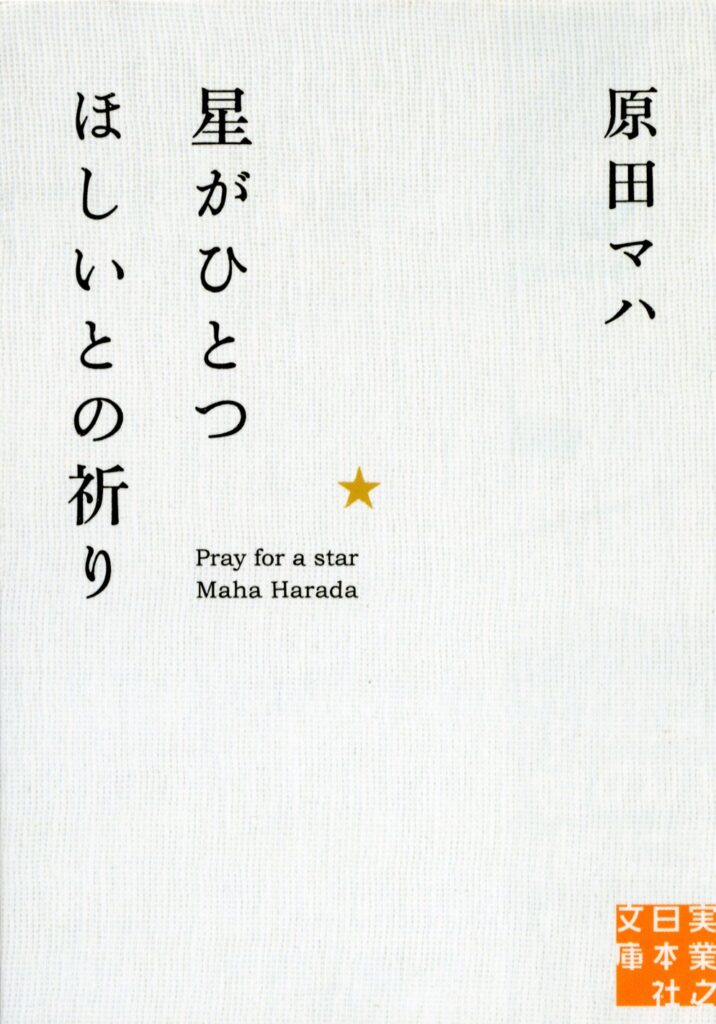
-710x1024.jpg)