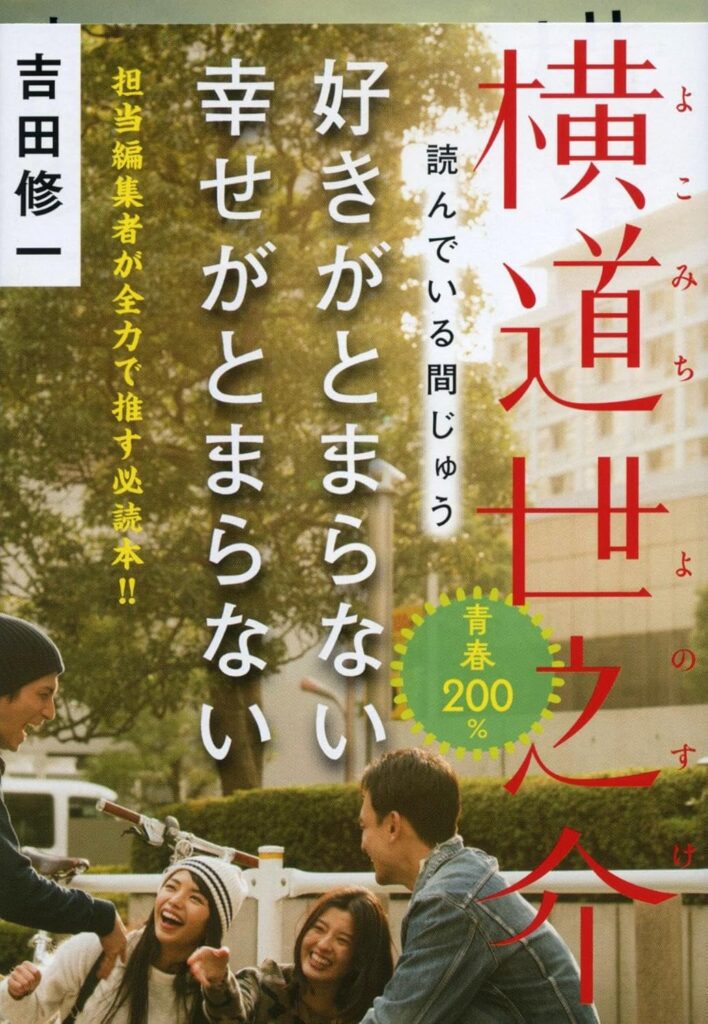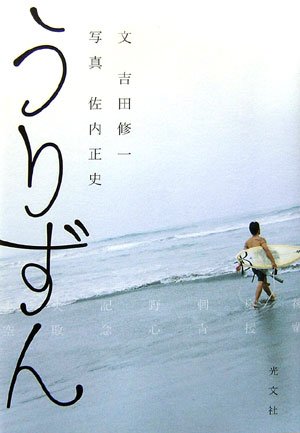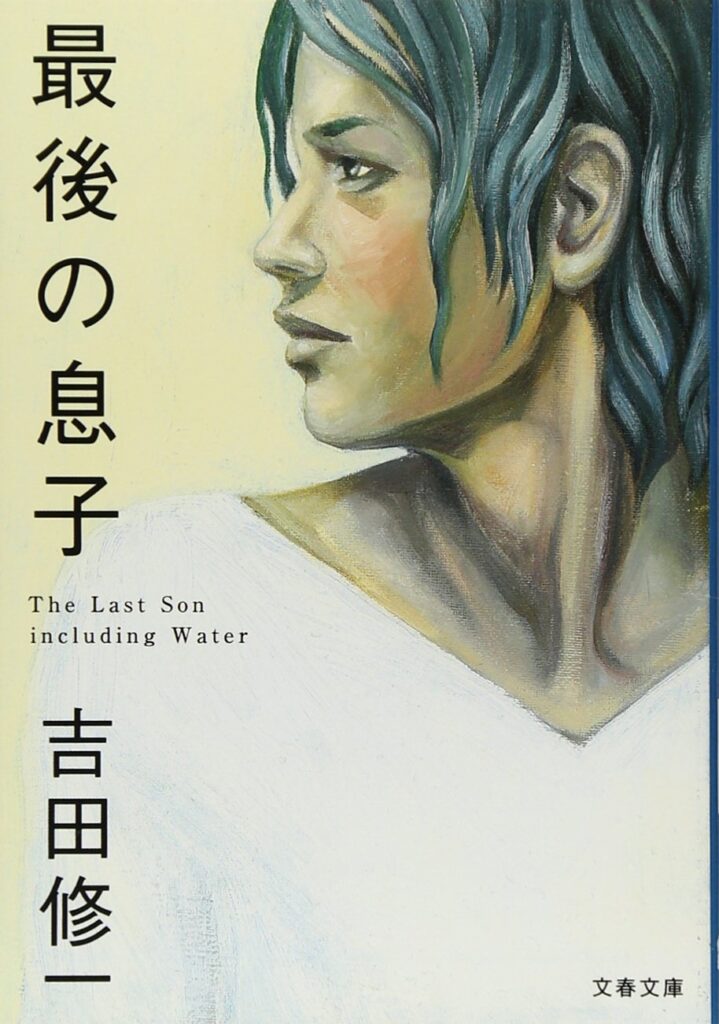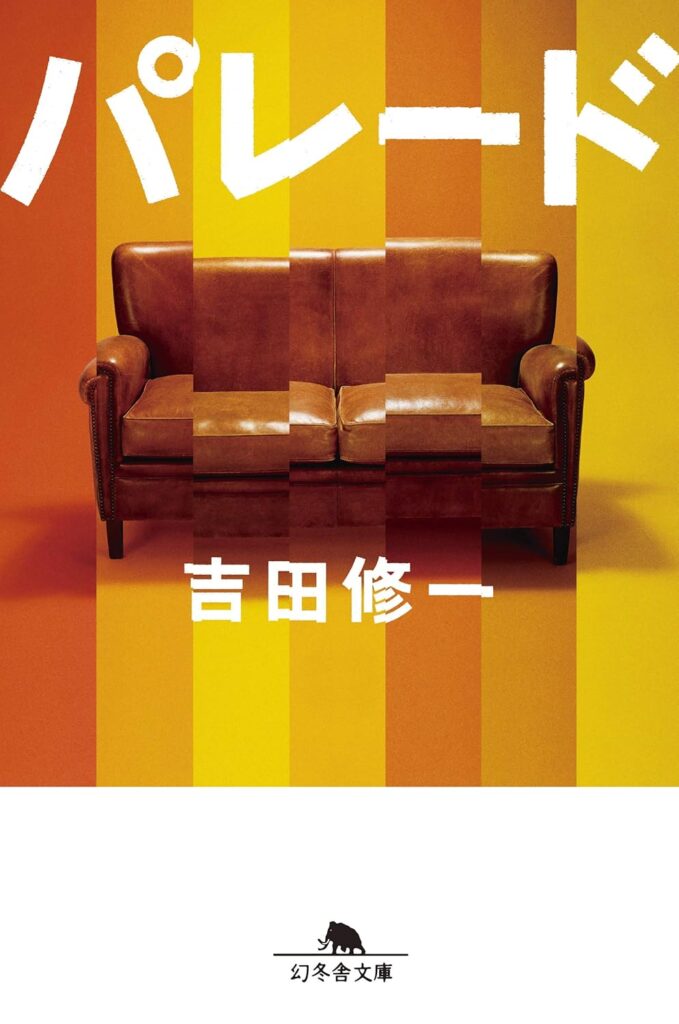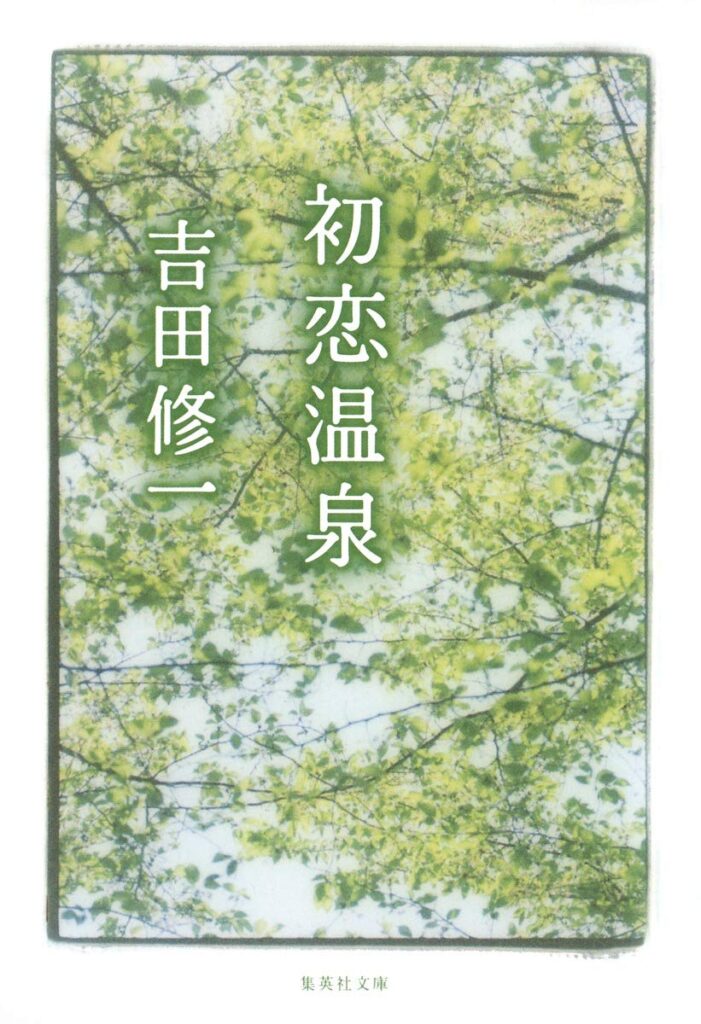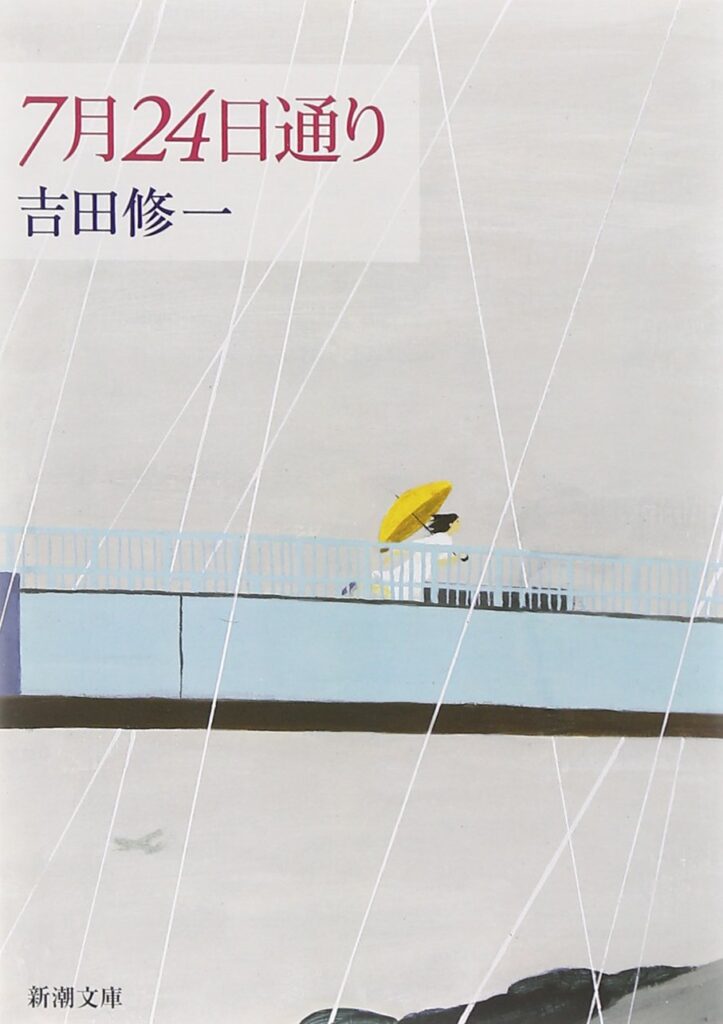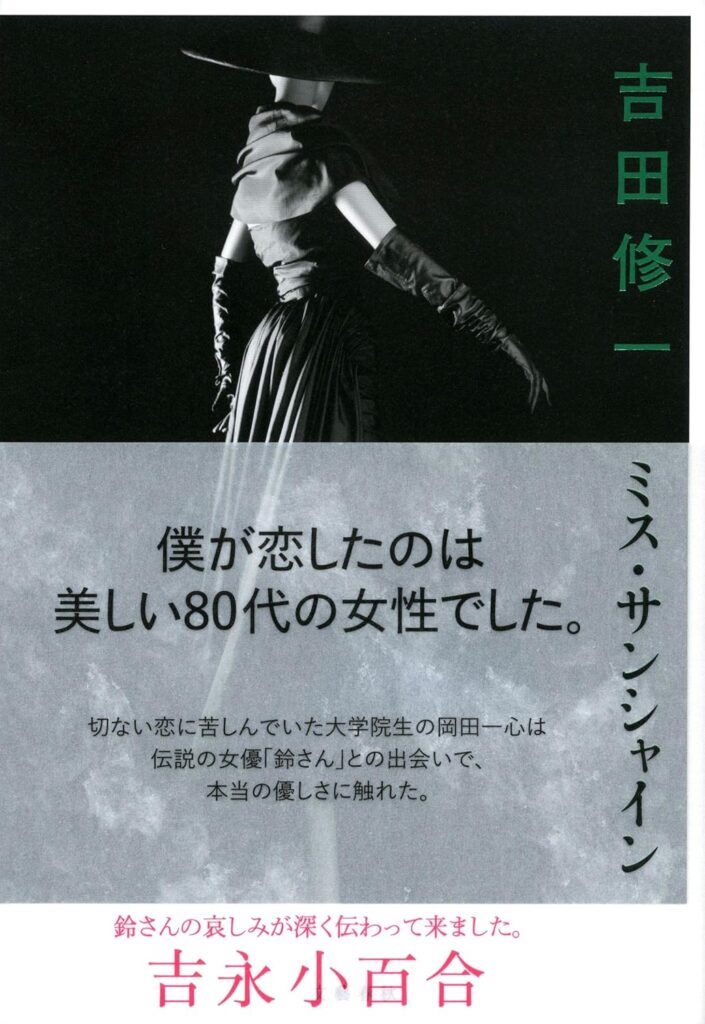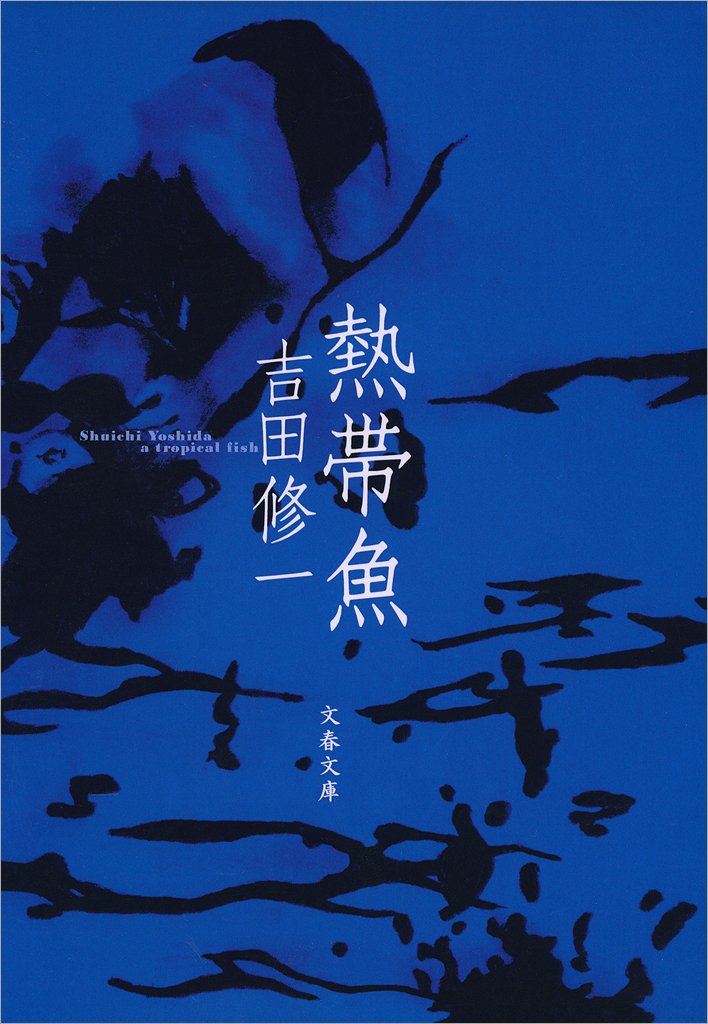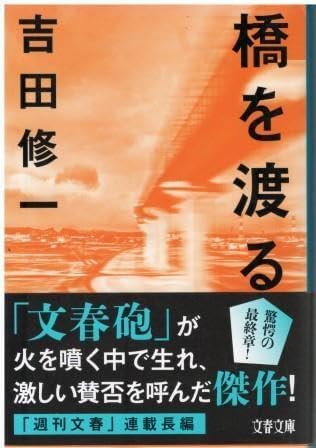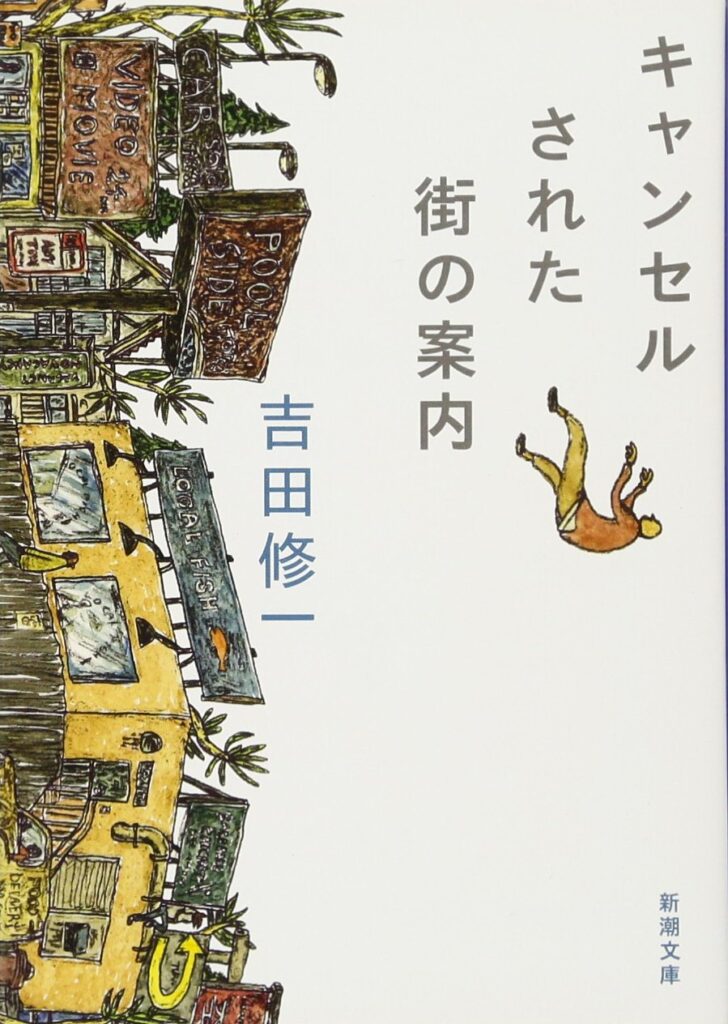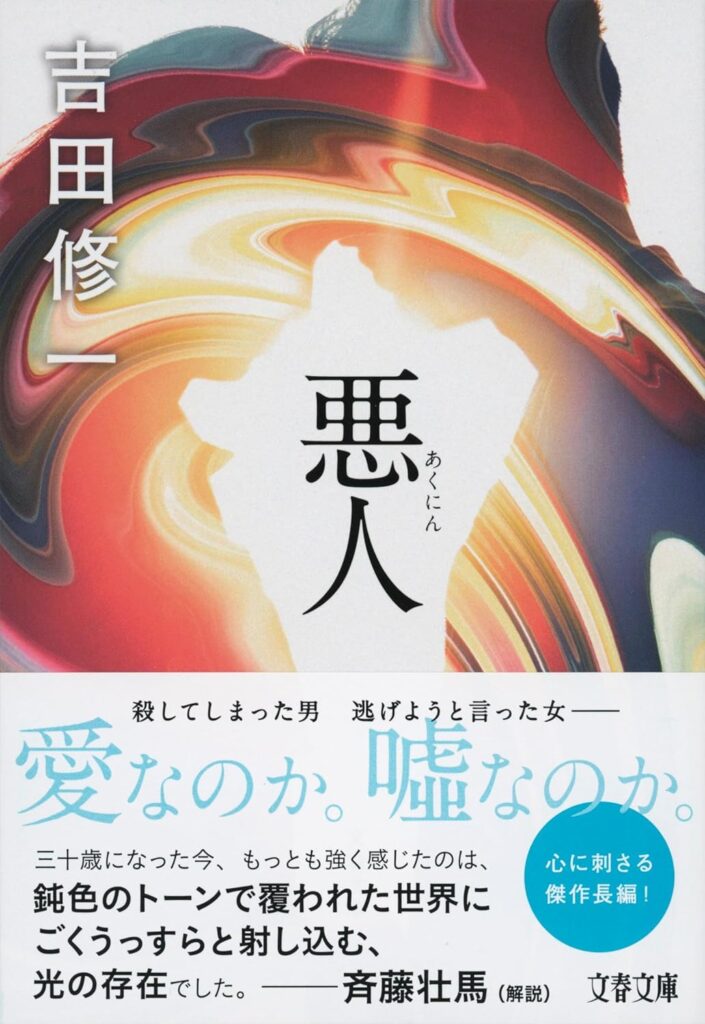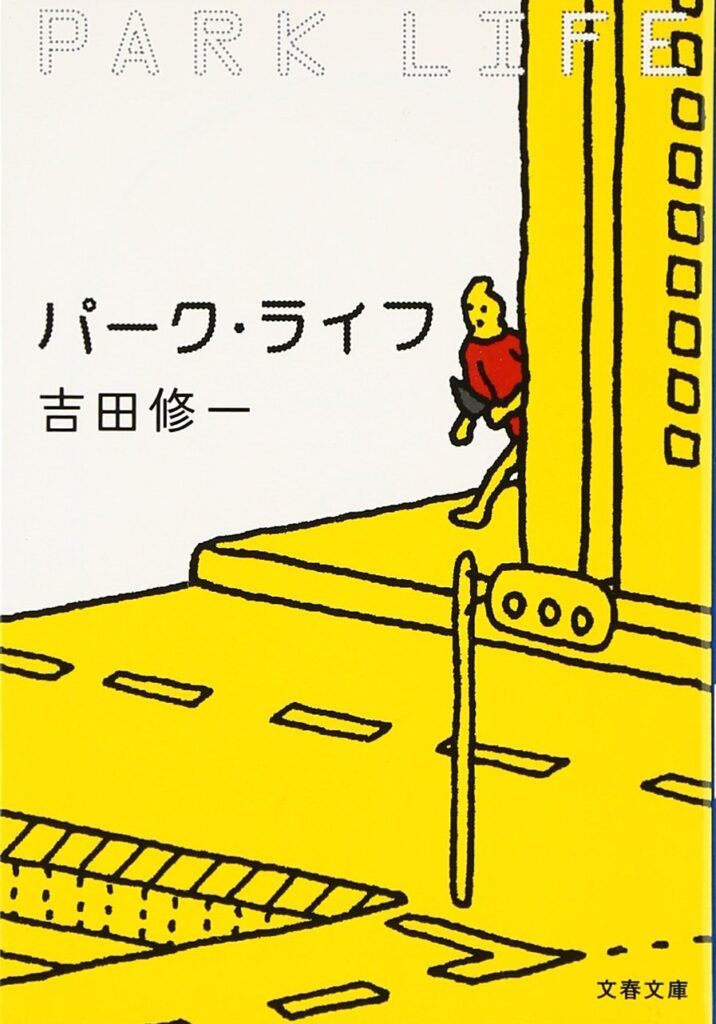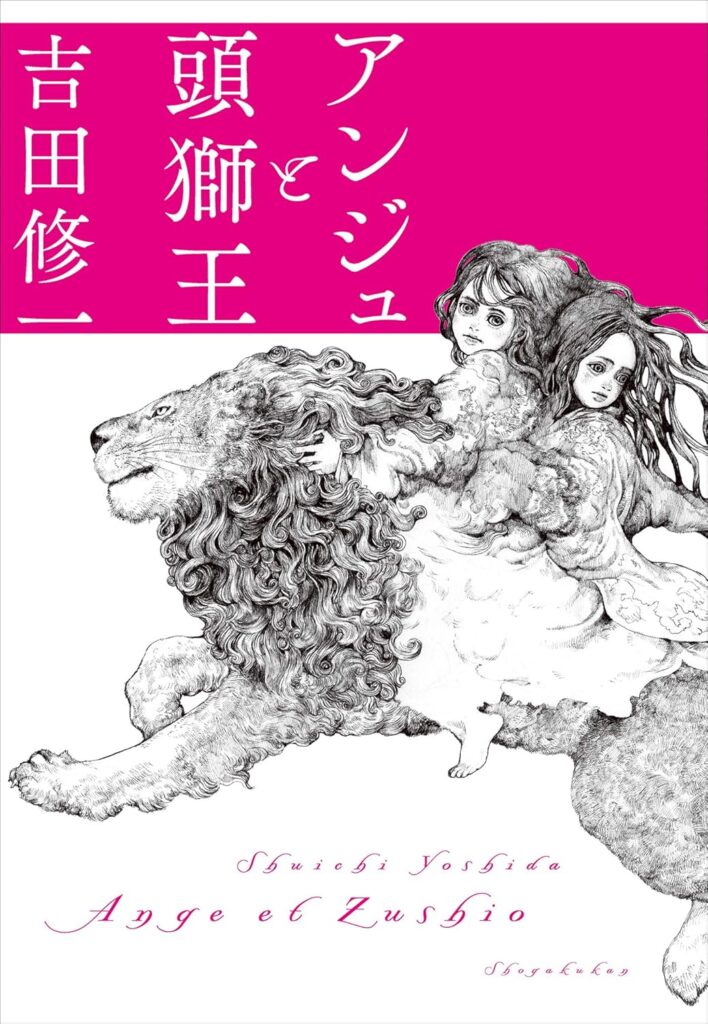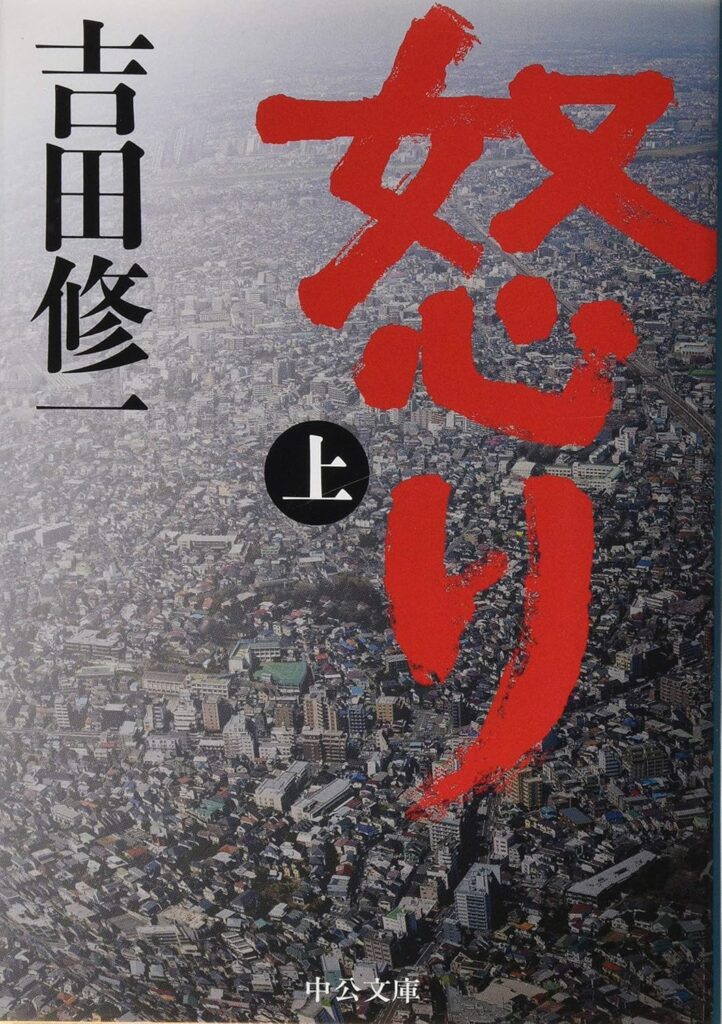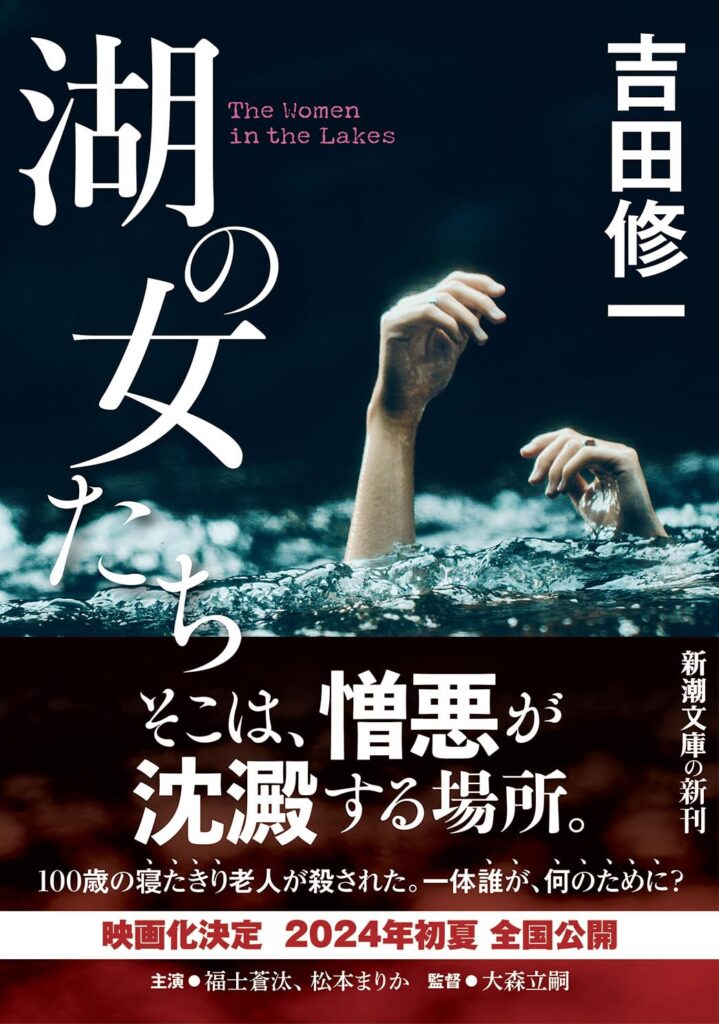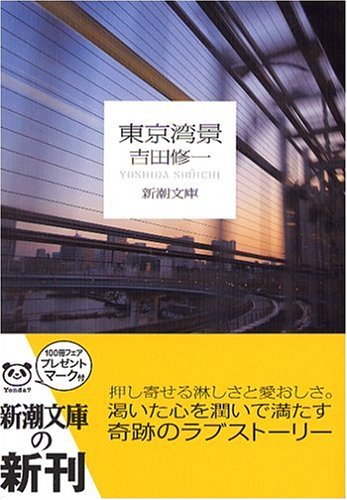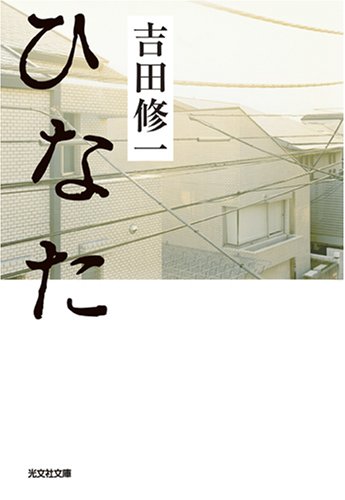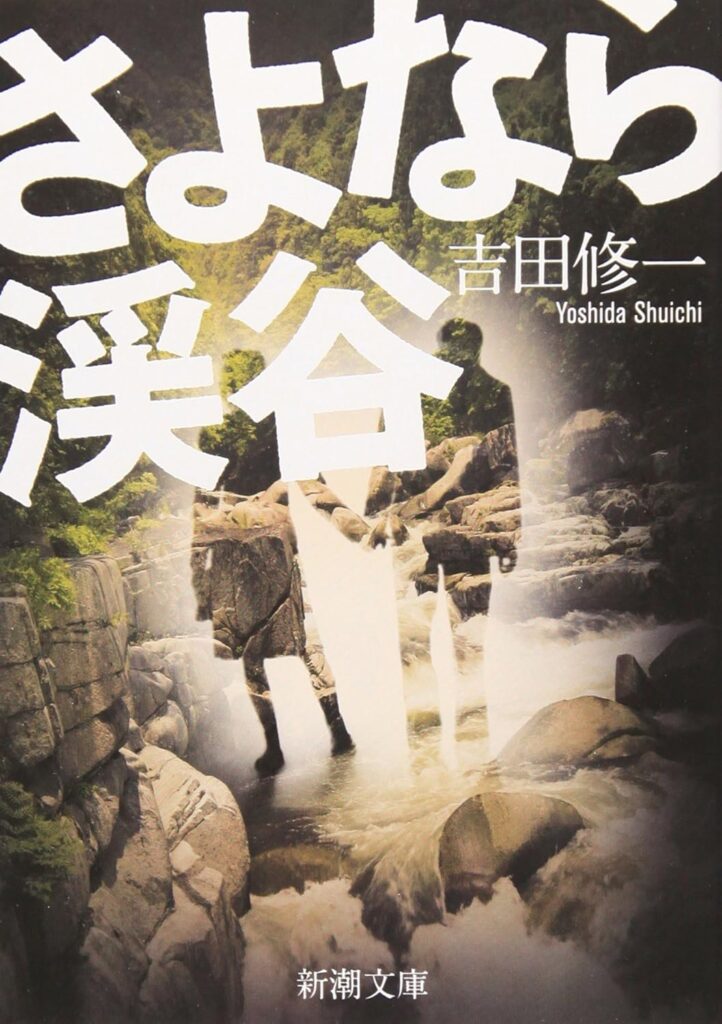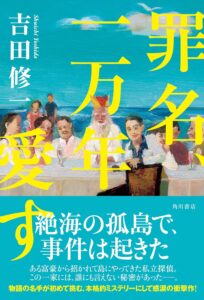 小説「罪名、一万年愛す」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「罪名、一万年愛す」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
吉田修一さんの手によるこの物語は、ただのミステリーという言葉では括れない、人間の心の奥深くに横たわる愛と罪、そして記憶の物語です。読み進めるうちに、登場人物たちの複雑な感情の絡み合いに引き込まれ、彼らが背負うものの重さに胸が締め付けられるような感覚に陥るかもしれません。
物語は、一見古典的な探偵譚のように幕を開けますが、すぐに過去の未解決事件と現在が交錯し、壮大な時間軸の中で、個人の人生がいかに時代や社会と結びついているのかを浮き彫りにしていきます。そして、読者は次第に、タイトルに冠された「罪名」と「一万年愛す」という言葉の真の意味へと導かれていくのです。
この記事では、物語の骨子に触れつつ、その魅力や読みどころ、そして私が抱いた深い感慨について、余すところなくお伝えしたいと思います。どうぞ最後までお付き合いいただければ幸いです。
小説「罪名、一万年愛す」のあらすじ
物語の始まりは、横浜で探偵業を営む遠刈田蘭平(とおがった らんぺい)のもとに舞い込んだ、一風変わった依頼でした。依頼主は、九州の百貨店王である梅田一族の三代目、梅田豊大。彼の祖父であり、梅田家創業者である梅田壮吾が認知症の兆候を見せ、夜な夜な家の中を探し回っているというのです。その探し物とは、かつてナポレオンの近親者も身に着けたとされ、時価35億円とも言われる伝説のルビー「一万年愛す」。壮吾はこの宝石をオークションで手に入れたとされていました。
蘭平は手がかりを求め、壮吾が私有する長崎県九十九島の一つ、野良島へ向かいます。島では壮吾の米寿の祝いが催される予定で、一族の他に、壮吾が過去の事件で容疑者となった際に捜査を担当した元刑事・坂巻丈一郎も招かれていました。総勢10名が島に集い、嵐の予報もあって、どこか不穏な空気が漂います。
米寿の祝いが和やかに終わった翌朝、事態は急変します。当主である梅田壮吾が、屋敷から忽然と姿を消してしまうのです。現場には「私の遺言書は、昨晩の私が持っている。」という謎めいた書き置きだけが残されていました。宝石探しから一転、当主失踪事件へと発展し、蘭平は孤島という閉鎖空間で捜査を開始します。
物語は、この壮吾の失踪と並行して、45年前の1978年に起きた未解決事件「多摩ニュータウン主婦失踪事件」の謎を追う形で進んでいきます。失踪した主婦・藤谷詩子は元遊郭の女性であり、当時、若き実業家だった梅田壮吾も容疑者の一人として捜査線上に浮かんでいました。担当刑事だった坂巻は、壮吾には鉄壁のアリバイがあったものの、今もなお壮吾が犯人であるとの疑念を抱き続けています。
現在の孤島での失踪事件と、45年前の都市部での未解決事件。二つの事件は複雑に絡み合い、壮吾の秘められた過去、そして戦争の影が色濃く落とされた彼の人生が徐々に明らかになっていきます。壮吾の部屋に残された『飢餓海峡』『砂の器』『人間の証明』という三本の古い日本映画は、何を意味するのでしょうか。
蘭平の捜査が進むにつれ、伝説の宝石「一万年愛す」が単なる高価なルビーではなく、壮吾の壮絶な人生と、彼が生涯をかけて守り通そうとした何か、あるいは償おうとした何かを象徴するものであることが見えてきます。そして物語は、全ての謎が収束する衝撃的なクライマックスへと向かっていくのです。
小説「罪名、一万年愛す」の長文感想(ネタバレあり)
吉田修一さんの『罪名、一万年愛す』を読み終えた今、私の心には深い感動と、そしてある種の戦慄にも似た感情が渦巻いています。これは単なるミステリーの枠を超え、人間の存在そのもの、愛のあり方、そして罪と記憶という普遍的でありながらも極めて個人的なテーマを、壮大なスケールで描ききった傑作だと感じています。
物語は、現在の孤島で起きた梅田壮吾の失踪事件と、45年前の多摩ニュータウン主婦失踪事件という、二つの時間軸が巧みに交錯しながら進行します。この二つの事件が、まるで綾なす糸のように絡み合い、次第に一つの壮大なタペストリーを織り上げていく様に、私は序盤からぐいぐいと引き込まれました。特に、昭和という時代の空気感、高度経済成長期の光と影、そしてその底流に横たわる戦争の傷跡といったものが、登場人物たちの運命に深く影響を与えている様は、まさに吉田修一さんならではの筆致と言えるでしょう。
壮吾が過去に関わったとされる45年前の事件の被害者、藤谷詩子。彼女が元遊郭の女性であったという設定は、当時の社会の偏見や、個人の尊厳といった問題を想起させます。そして、若き日の壮吾がこの事件の容疑者であったという事実は、彼の輝かしい成功の裏に隠された、語られることのない過去の存在を強く匂わせます。元刑事・坂巻が、45年もの長きにわたりこの事件を追い続けている執念もまた、物語に深みと緊張感を与えていました。
私が特に心を揺さぶられたのは、梅田壮吾という人物の造形、そして彼の秘められた過去が明らかになるにつれて浮かび上がってくる、その壮絶な人生です。彼の部屋、あるいはシアタールームに残された三本の映画、『飢餓海峡』『砂の器』『人間の証明』。これらはいずれも、過去の罪や出自を隠し、成功を手にした人物が、やがて逃れられない宿命に追いつかれるという、重厚なテーマを扱った作品群です。これらの映画が、壮吾自身の人生と深く共鳴しているであろうことは想像に難くなく、彼が何を思い、何を残そうとしていたのかを考える上で、非常に重要な手がかりとなっていました。
そして、物語の核心に迫るにつれて明かされる、壮吾の戦後の上野での浮浪児としての体験。そこで出会った知性的な少年「ケロ」、人間愛に溢れた少女「詩子」、そして一匹の猫。過酷な状況下で育まれた彼らの絆の描写は、胸に迫るものがありました。「戦争の犠牲になった二人の思いを叶えてあげた」という壮吾の言葉。この「二人」とは、おそらくケロと子供時代の詩子のことでしょう。この過去の出来事が、壮吾のその後の人生の行動原理となり、そして「一万年愛す」というタイトルに込められた愛の対象、あるいは彼が背負うことになった「罪名」の本質へと繋がっていくのだと、私は解釈しました。
この戦後の上野での「詩子」と、45年前に失踪した「藤谷詩子」。二人の「詩子」の存在は、物語の大きな謎であり、読者の推理を様々に掻き立てます。彼女たちは同一人物なのか、それとも壮吾が過去の詩子の面影を藤谷詩子に重ねていたのか。いずれにしても、壮吾の行動の根底には、過去の詩子への消えることのない深い愛情、あるいは彼女との間に交わされたであろう約束を果たすという、純粋で強靭な意志があったのではないでしょうか。そして、その純粋な思いが、何らかの形で法や社会の規範と衝突し、「罪」として彼の人生に刻印されることになったのではないか、そう思えてなりませんでした。
探偵・遠刈田蘭平の捜査は、論理的な推理だけでなく、関係者たちの心の奥底に触れ、彼らの魂の叫びに耳を傾ける旅でもあったように感じます。彼が一つ一つ謎のピースを繋ぎ合わせていく過程は、読者にとっても、壮吾という人間の複雑で深い内面へと分け入っていく体験となります。そして、宝石「一万年愛す」が、単なる物質的な価値を持つものではなく、壮吾の波乱に満ちた人生、そこで育まれた愛、そして彼が生涯をかけて守り通そうとしたもの、あるいは償おうとしたものの象徴であることが明らかになるにつれ、物語は「本格ミステリー」の枠を超え、「感涙のミステリー」「愛の物語」と評されるゆえんが、痛いほどに伝わってきました。
クライマックス、全ての謎が収束し、梅田壮吾自身の口から、あるいは彼が残した記録によって、その壮絶な過去と、過酷な運命の中で育まれた純粋で強靭な愛の物語が語られる場面は、圧巻の一言です。多くの読者が涙したと伝えられるのも頷けます。戦争という大きな暴力によって奪われたもの、それでもなお失われなかった人間の絆の尊さ、そして愛する者を守るためならば、人はどれほどのものを背負い、どれほどの犠牲を払うことができるのか。そういった根源的な問いが、静かに、しかし力強く胸に響きました。
そして、物語の結末。これは本当に衝撃的で、一部では「SF的」とも評される、予想を大きく裏切るものでした。この結末については、おそらく読者の間で賛否が分かれるところかもしれません。しかし私は、この一見突飛とも思える結末こそが、「一万年愛す」という壮大なテーマを、文字通り、あるいはそれに近い形で具現化するための、作者・吉田修一さんによる大胆かつ野心的な試みだったのではないかと考えています。
壮吾の愛を、通常の人間的な時間スケールを超えて存続させるための、文学的実験。それは、彼の過去の「罪」と、それにもかかわらず貫かれた「愛」のコントラストをより一層際立たせ、読者に強烈な印象と、ある種の畏敬の念にも似た感情を与える装置として機能していたのではないでしょうか。「一万年」という途方もない時間。それは、壮吾が抱き続けた愛の深さと永遠性を象徴すると同時に、人間の記憶や想いが、どのようにして時を超えて継承され得るのかという、壮大な問いかけを私たちに投げかけているようにも思えました。
最終章で、「罪名、一万年愛す」というタイトルに込められた深い意味が明らかになる時、私たちは改めて、壮吾が背負った「罪名」とは何だったのかを考えさせられます。それは法的な罪なのか、社会的な罪なのか、それとも愛する者を守るため、過去の約束を果たすために犯さざるを得なかった、個人的で道徳的な葛藤を伴う、心の奥深くに刻まれた罪だったのか。「殺人罪の反対の罪は、なんというんでしょうね」という作中の問いかけが、この複雑なテーマを象徴しているように感じます。善悪二元論では到底割り切れない、人間の業と愛の深淵。それを見事に描ききった作品です。
吉田修一さんは、これまでも『悪人』や『怒り』といった作品で、人間の愛と罪、加害と被害の境界線といった重いテーマを扱ってこられました。本作は、それらのテーマを、戦後史という日本の近現代史の大きなうねりの中で捉え直し、さらにSF的な要素をも取り入れるという大胆な手法を用いることで、氏の文学的探求の新たな境地を示しているのかもしれません。
物語の舞台となった野良島や雪島といった島の名前の由来も、作品世界に奥行きを与え、この感動的な物語と深く結びついているように感じました。読み終えた後も、梅田壮吾という男の生き様、彼が貫いた愛の形が、深く心に残り続けます。
狂おしいまでに切実な愛の物語であり、同時に、戦争という時代が生んだ悲劇と、それでもなお生き抜こうとした人々の強靭な生命力を描いた鎮魂歌でもある。そして、ミステリーとしての精緻な構成と、読者の予想を裏切る大胆な展開。様々な要素が高次元で融合した、まさに吉田修一ワールドの真骨頂と言えるのではないでしょうか。この重厚な読書体験は、きっと長く記憶に残ることでしょう。
まとめ
吉田修一さんの小説「罪名、一万年愛す」は、一言で言い表すのが難しい、多層的で奥深い物語でした。横浜の探偵が奇妙な依頼を受けるところから始まる物語は、絶海の孤島での当主失踪事件、そして45年前の未解決事件へと繋がり、読者を複雑な謎解きへと誘います。
しかし、本作の魅力はそれだけにとどまりません。物語の核心には、戦争という大きな歴史のうねりに翻弄されながらも、強く生き抜いた主人公・梅田壮吾の壮絶な人生と、彼が胸に秘めた純粋で強靭な愛があります。その愛の対象は誰なのか、そして彼が背負った「罪名」とは何を意味するのか。これらの謎が解き明かされる過程で、読者は人間の愛と罪、記憶と時間といった普遍的なテーマについて深く考えさせられることでしょう。
特に、戦後の混乱期を生きた人々の描写や、三本の古典映画が象徴する意味、そして多くの読者に衝撃を与えたSF的とも言える結末は、この物語を忘れがたいものにしています。ミステリーとしての面白さはもちろんのこと、登場人物たちの感情の機微を丁寧に描き出す人間ドラマとしても、非常に読み応えのある作品です。
読後には、きっと登場人物たちの運命に思いを馳せ、タイトルの持つ深い意味を噛みしめることになるはずです。切なくも美しい、そしてどこか壮大な愛の物語に触れたいと願うすべての方に、心からお勧めしたい一冊です。

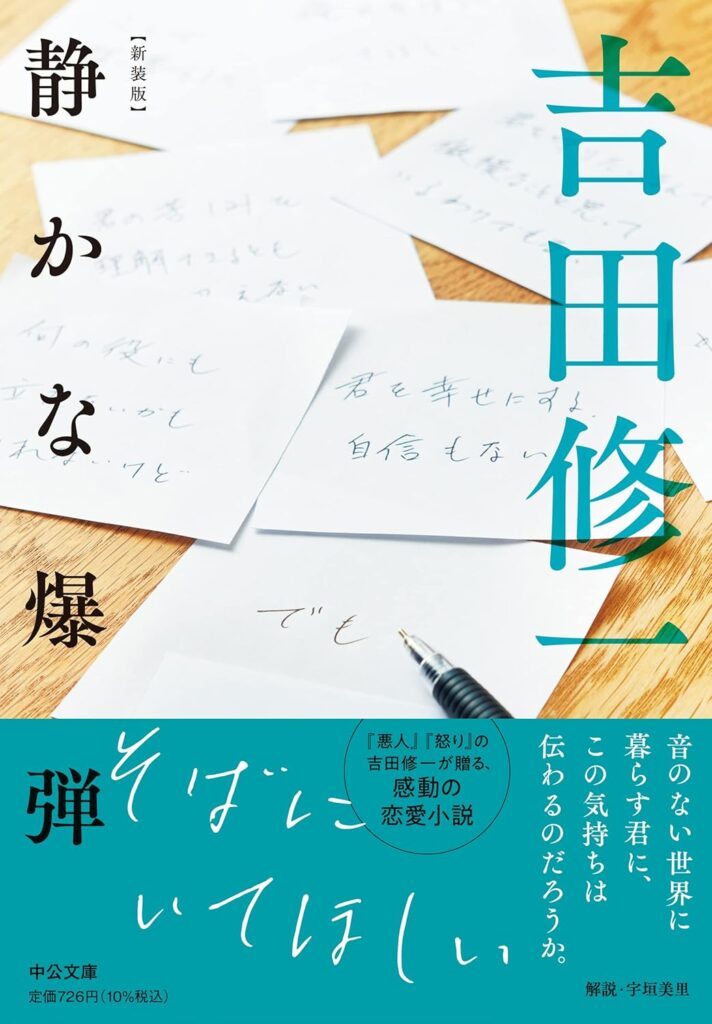

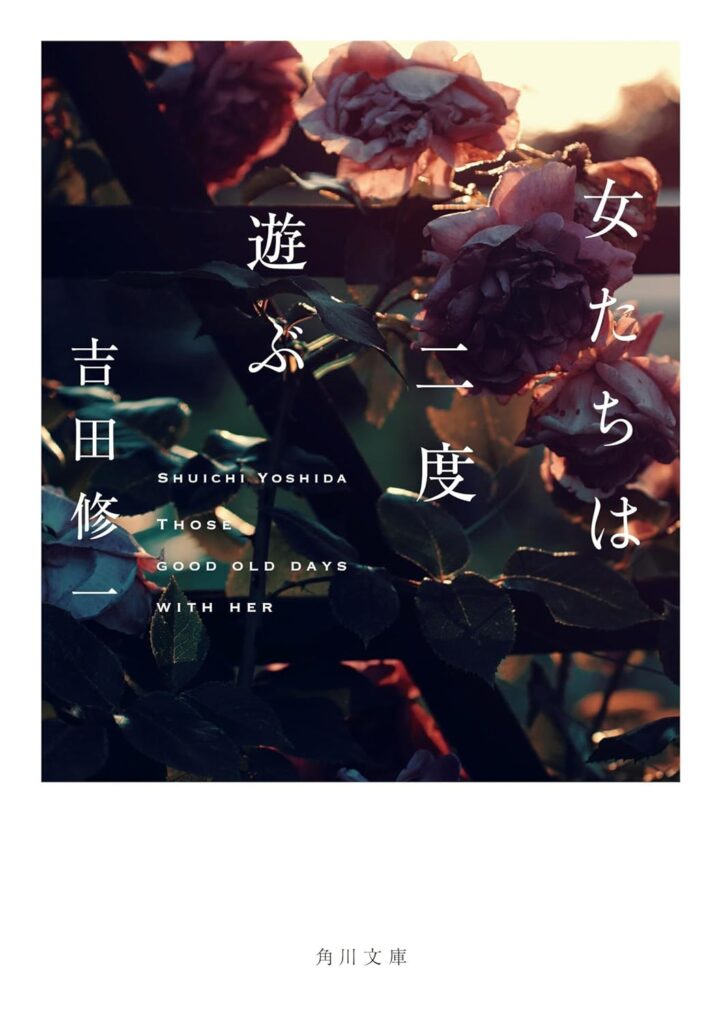
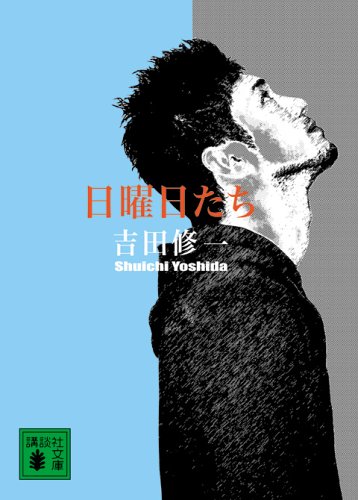
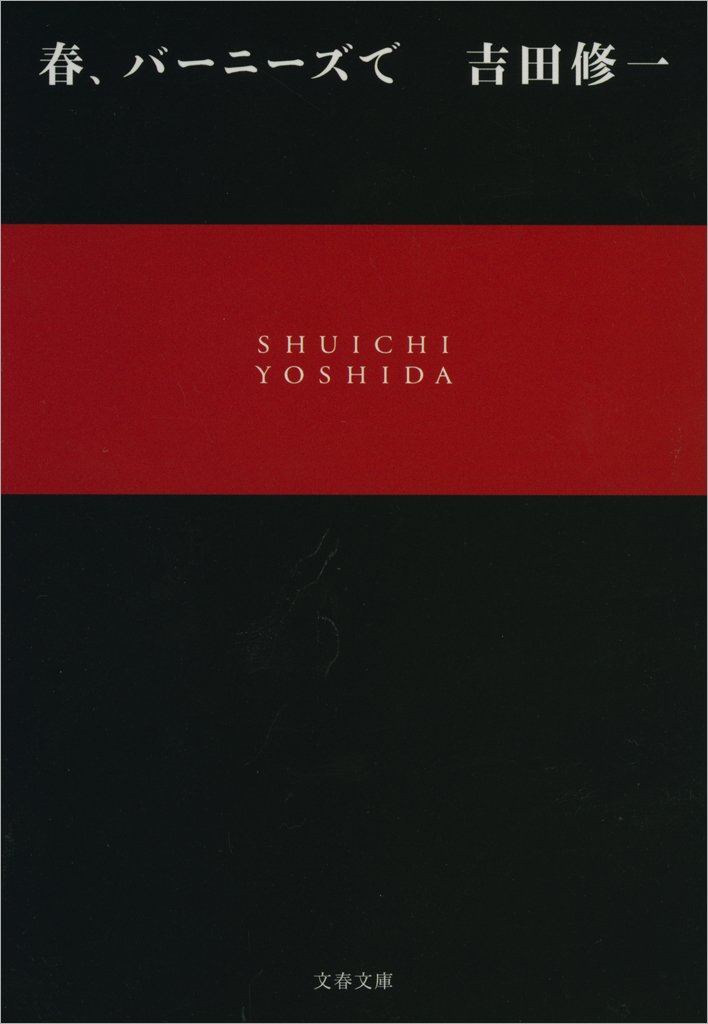
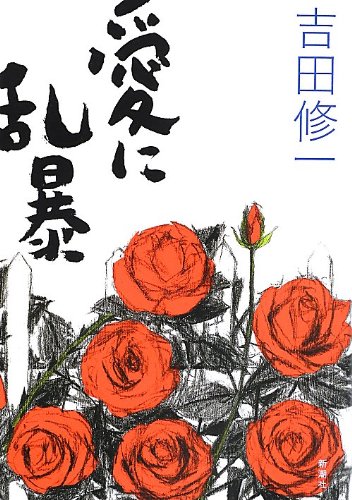
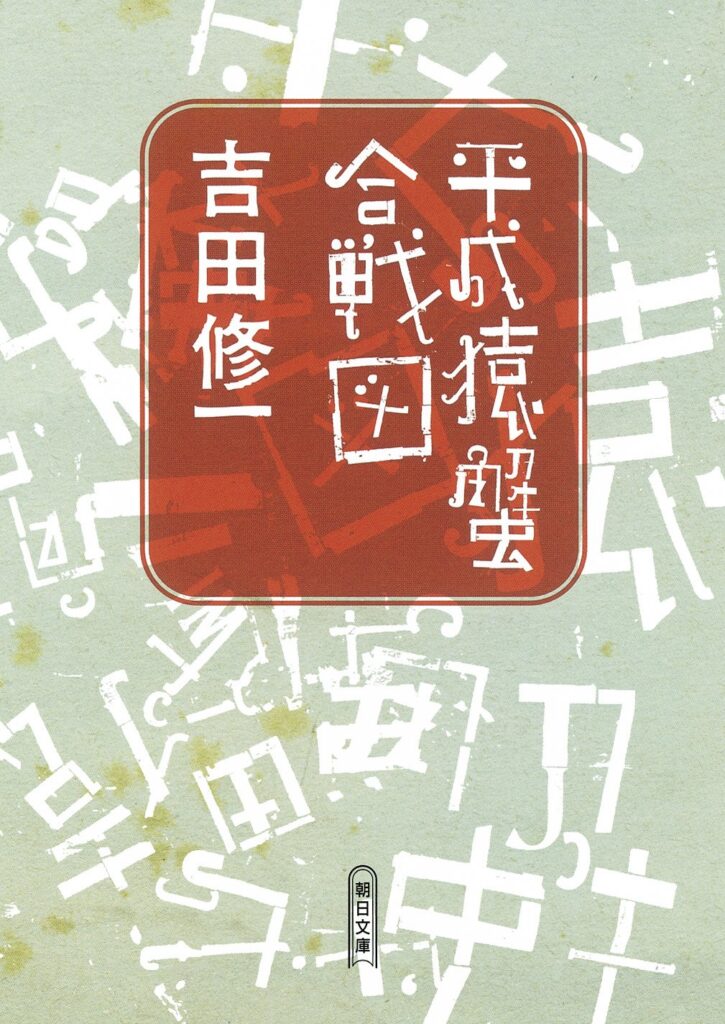
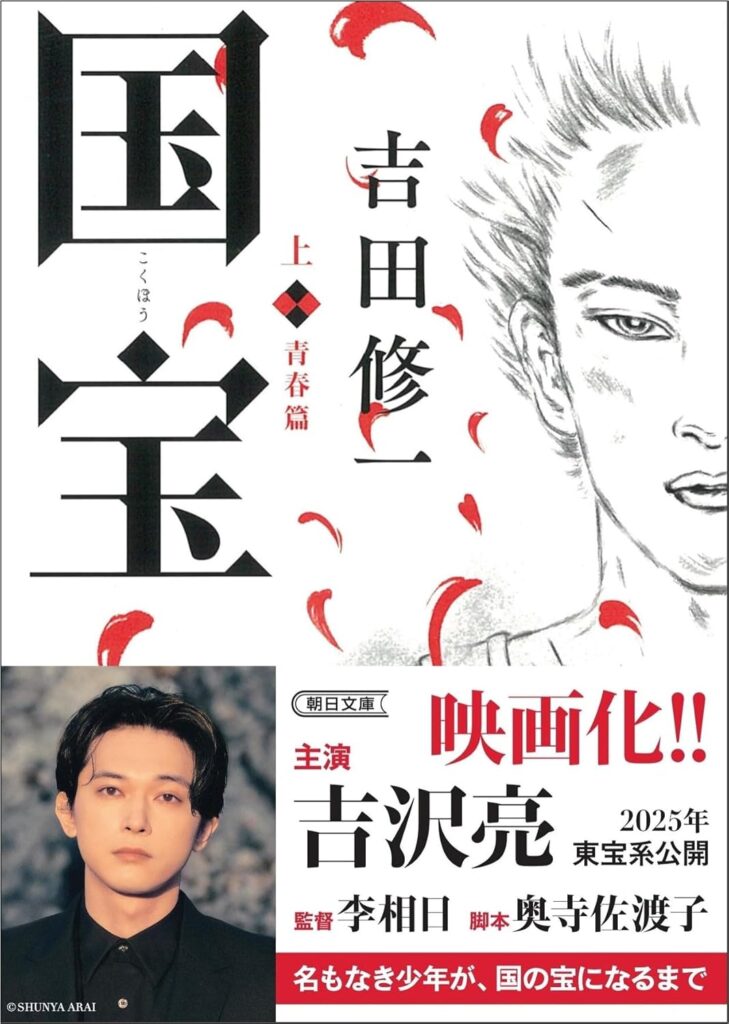
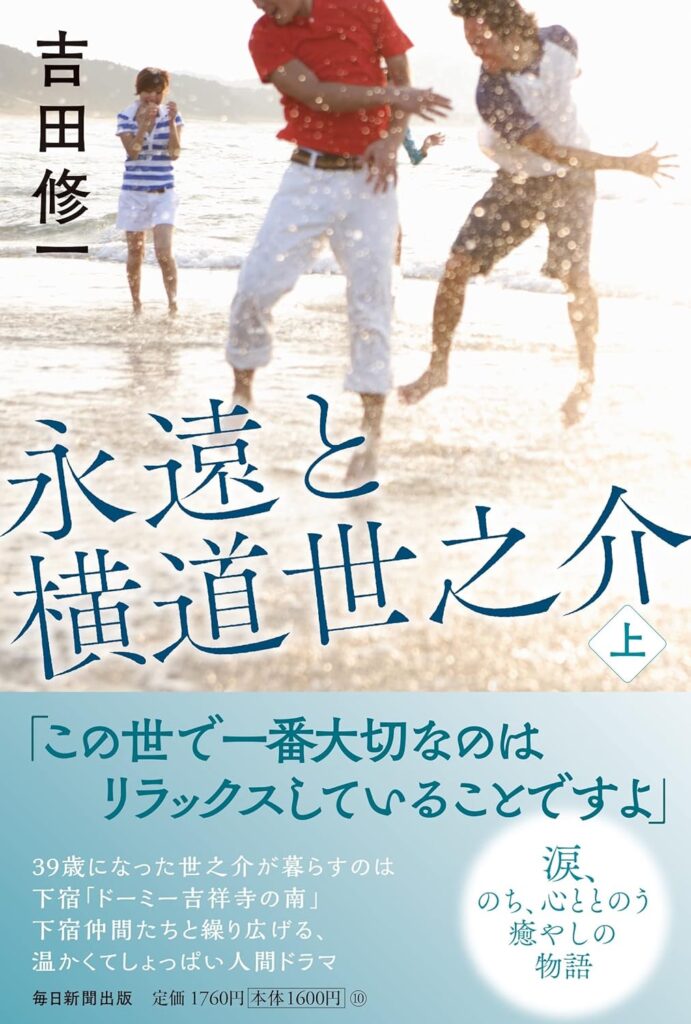
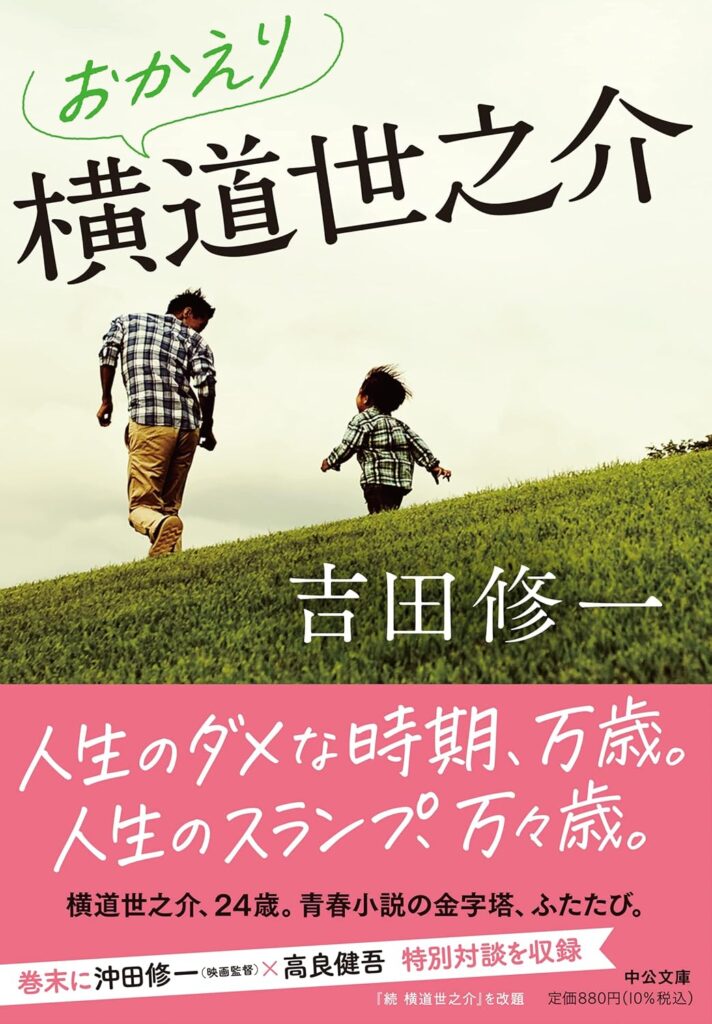
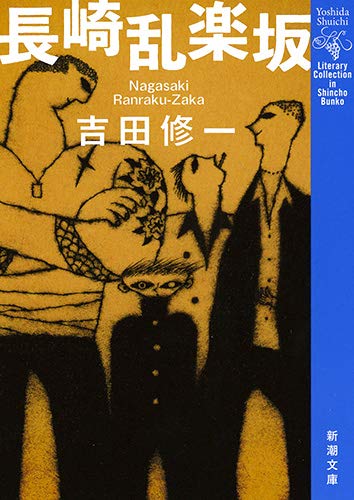
-728x1024.jpg)