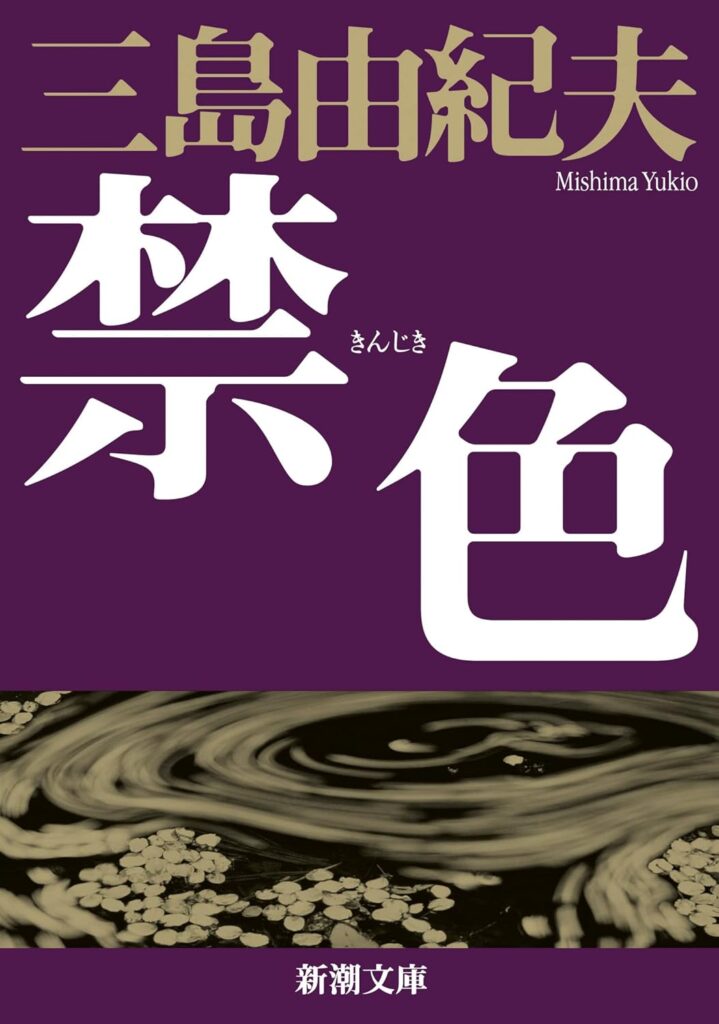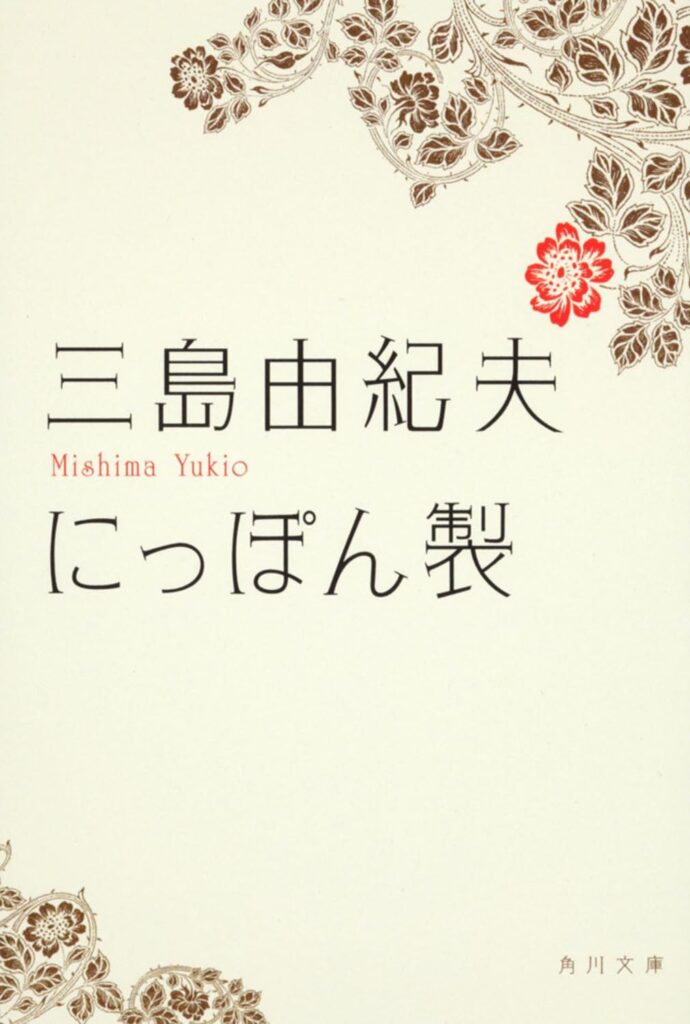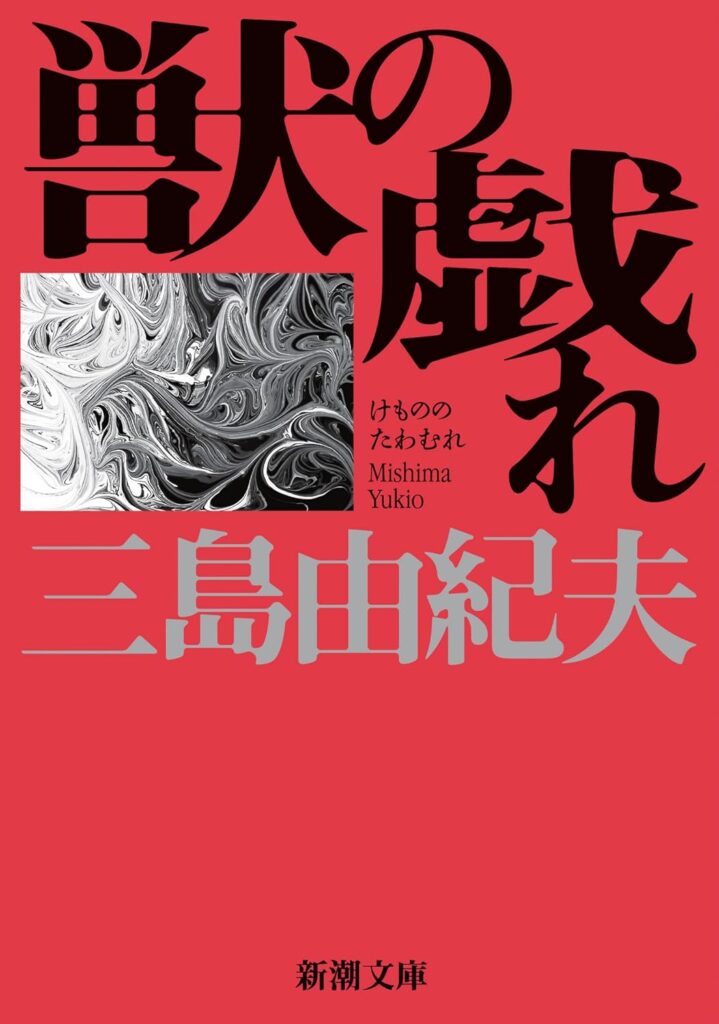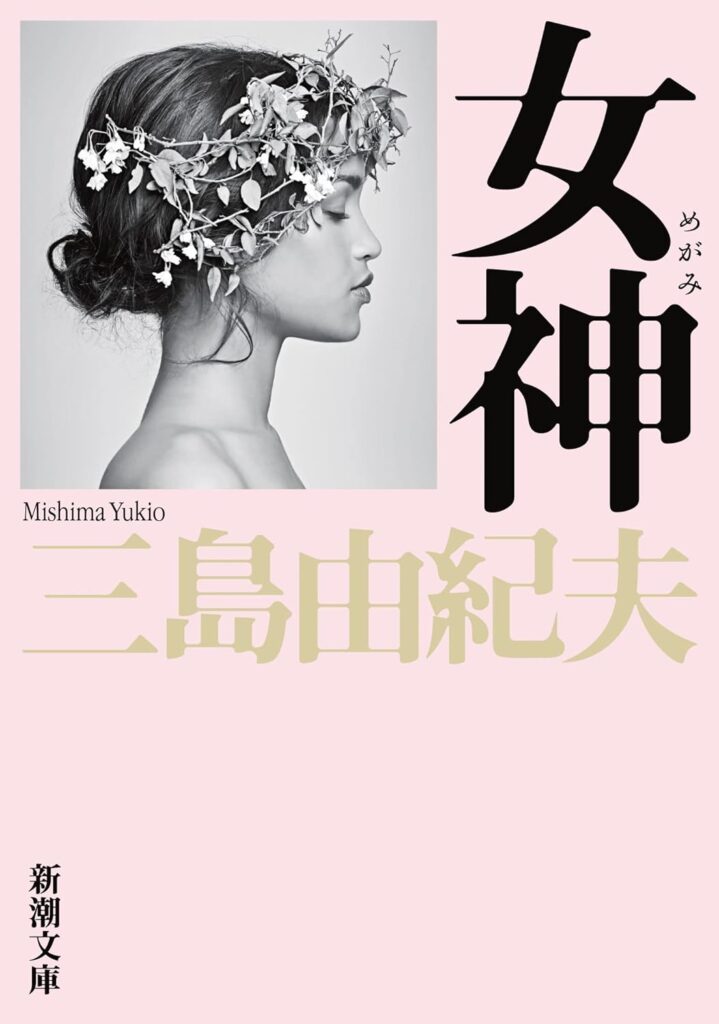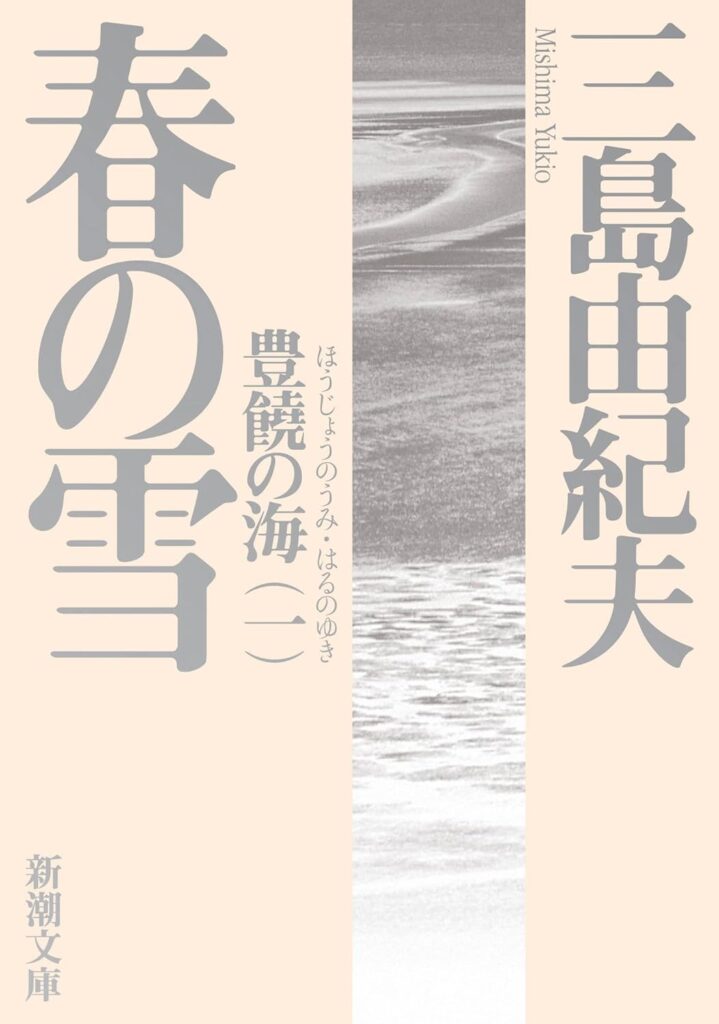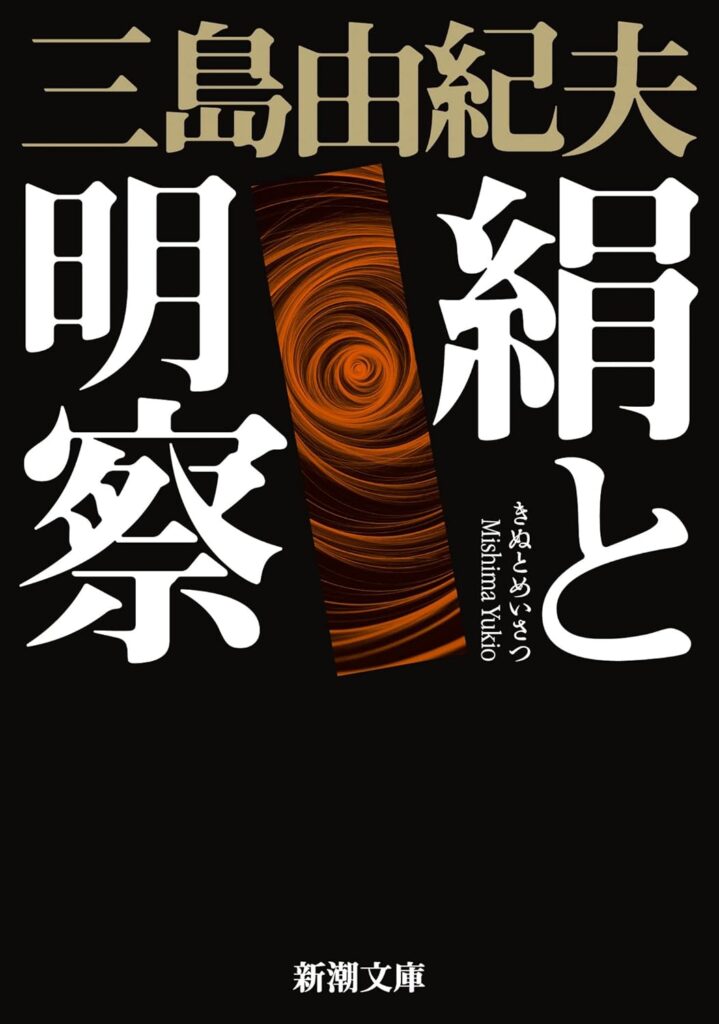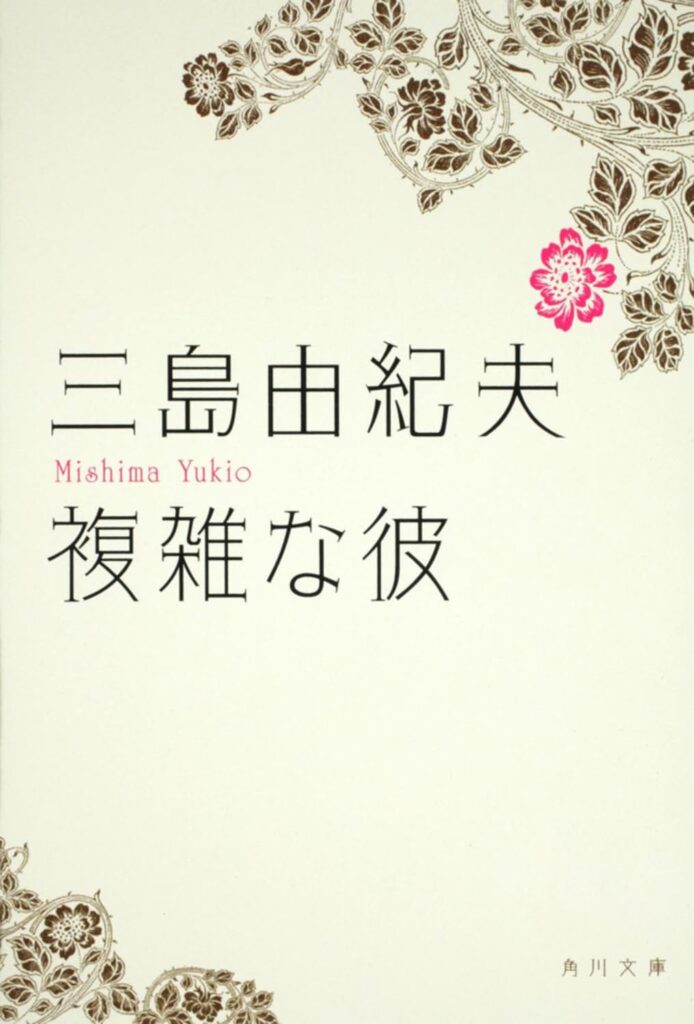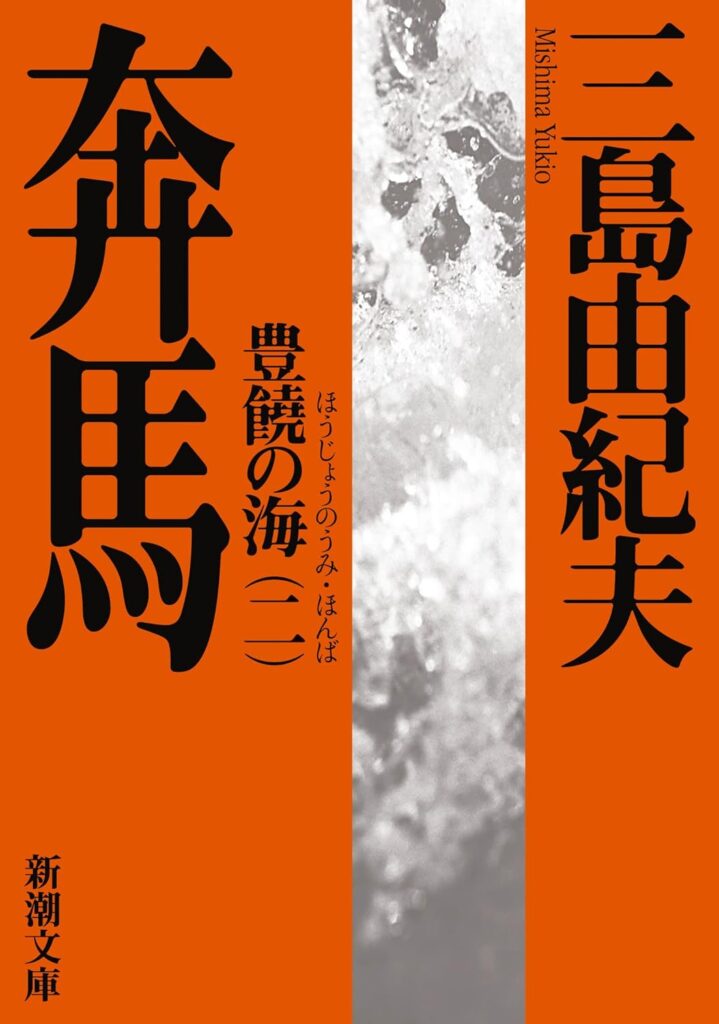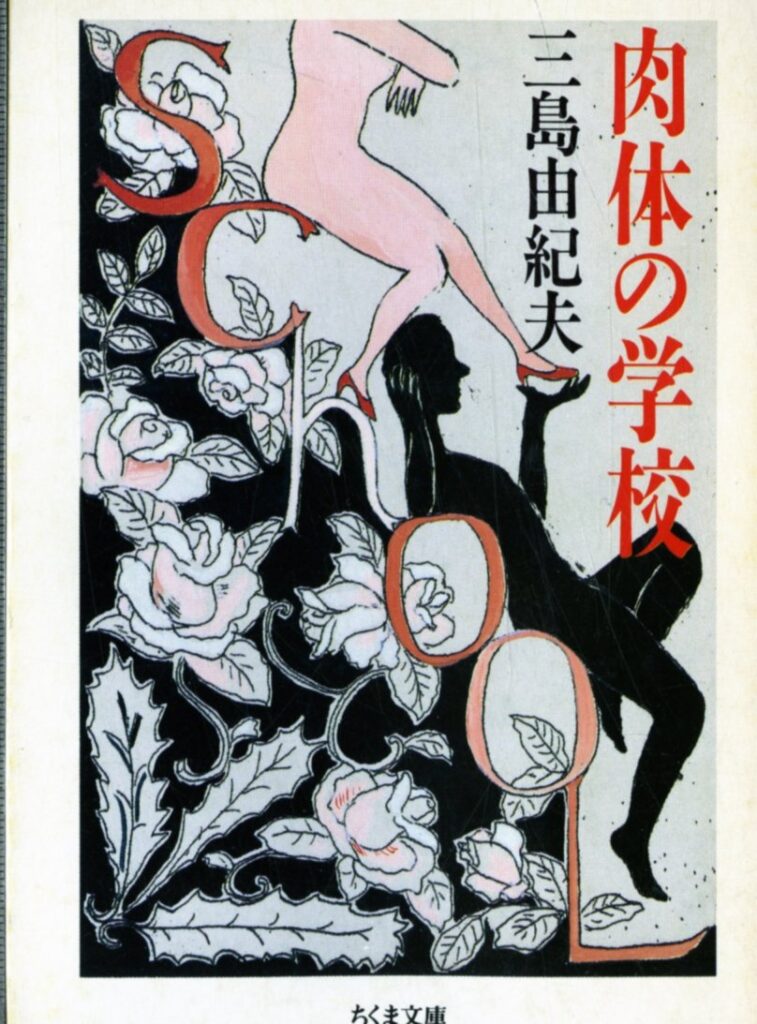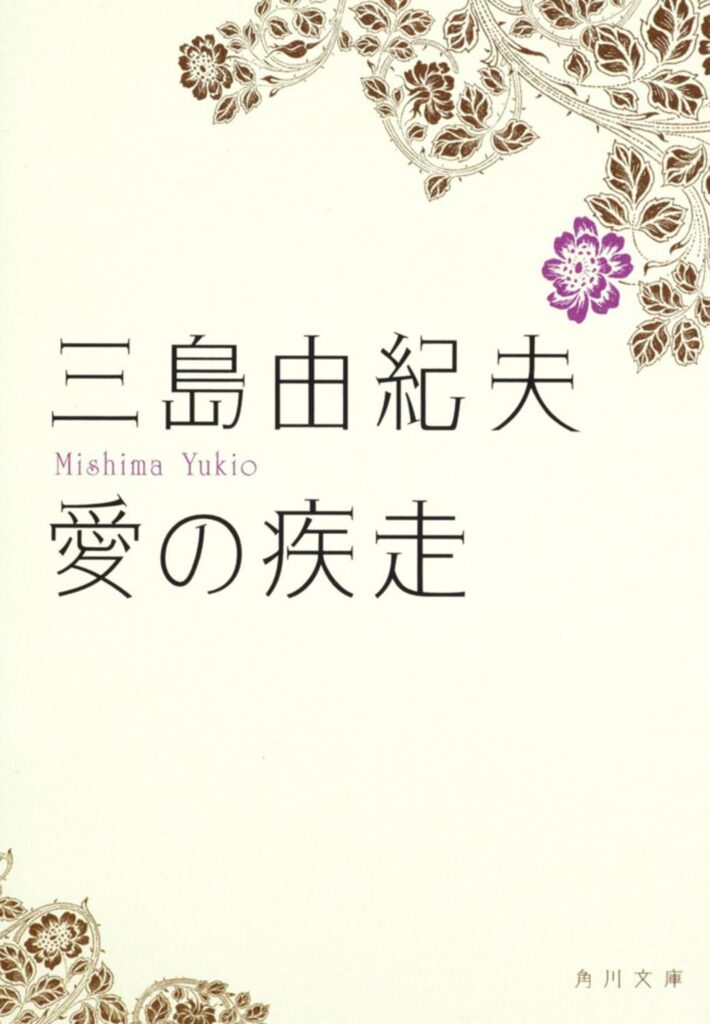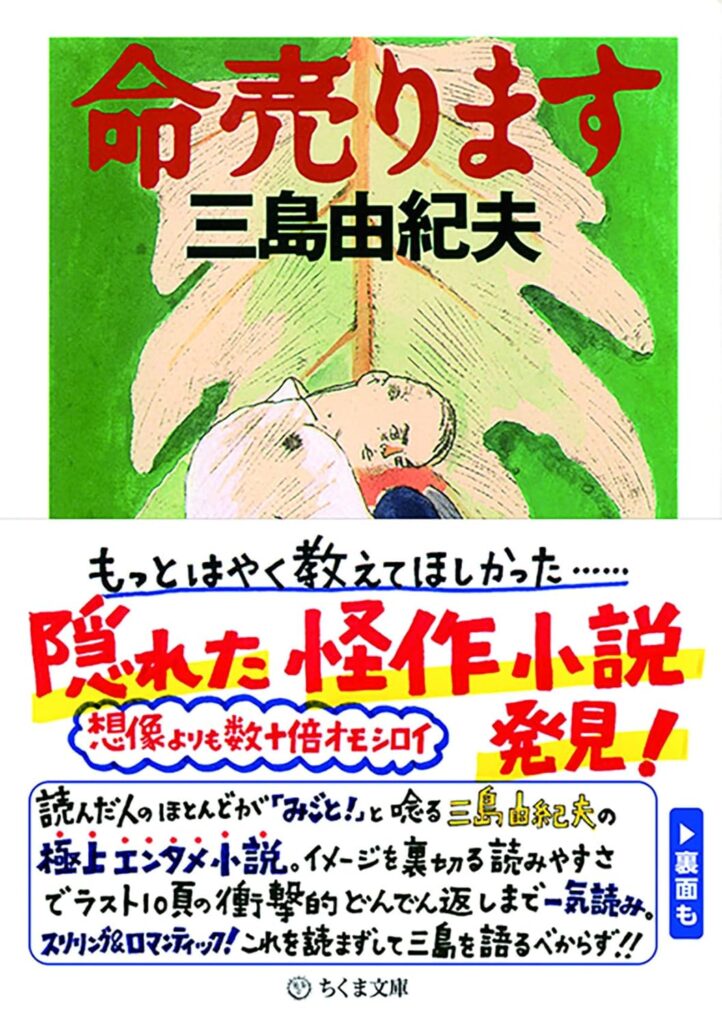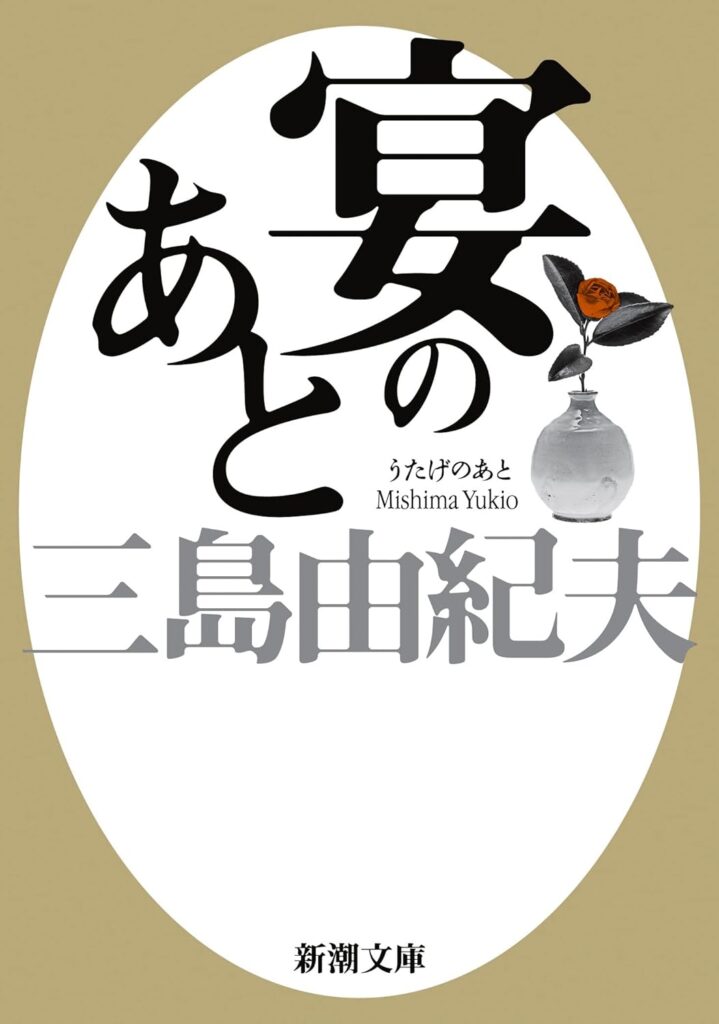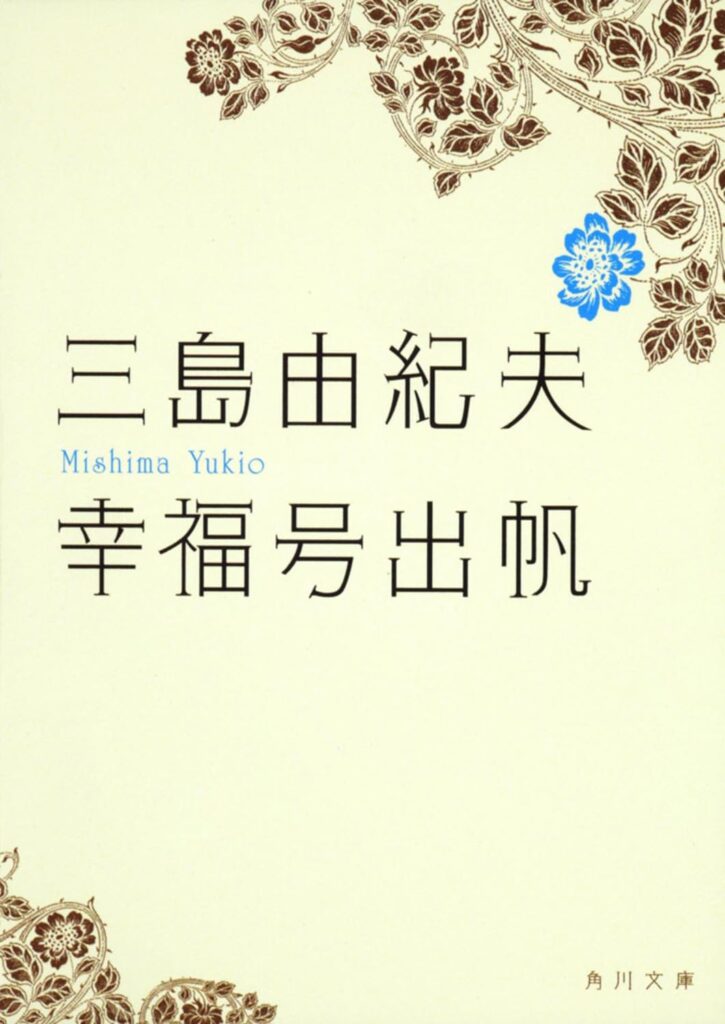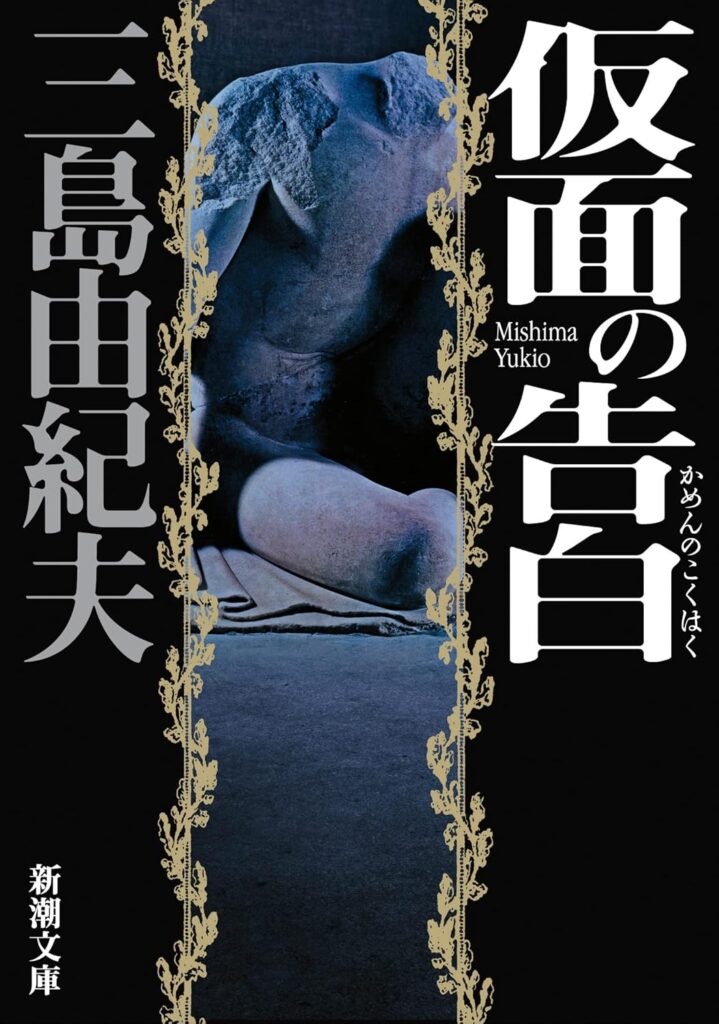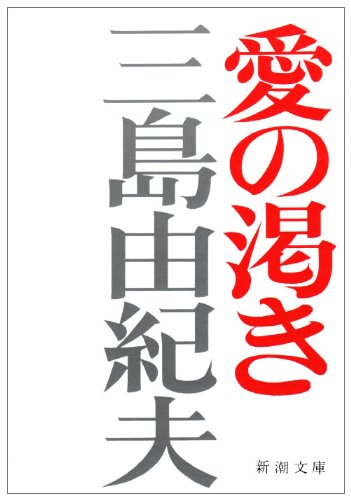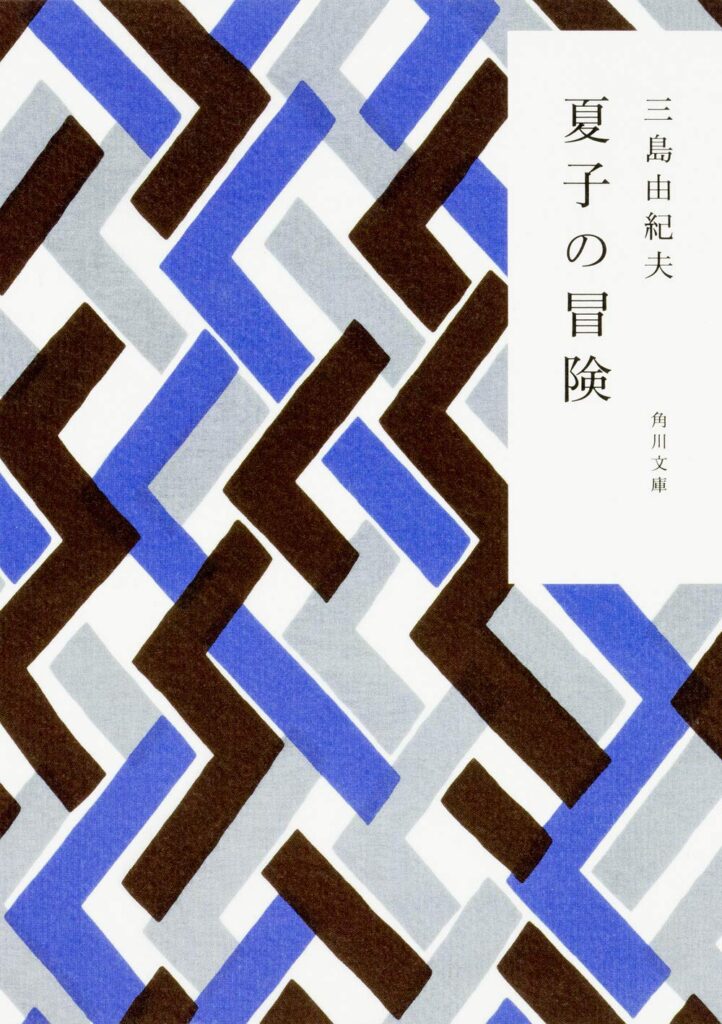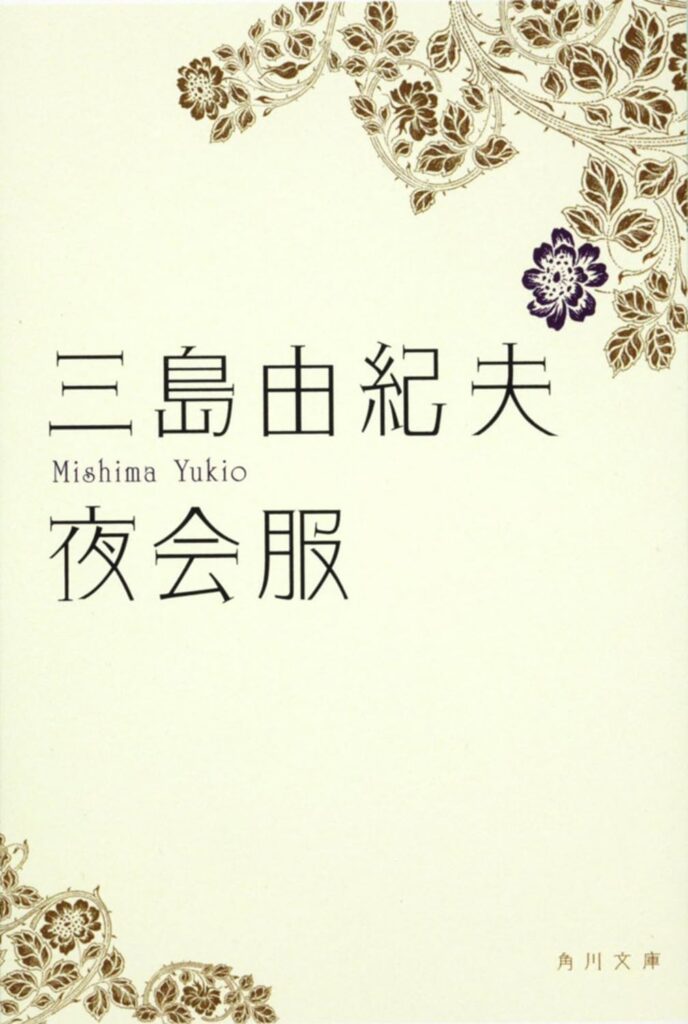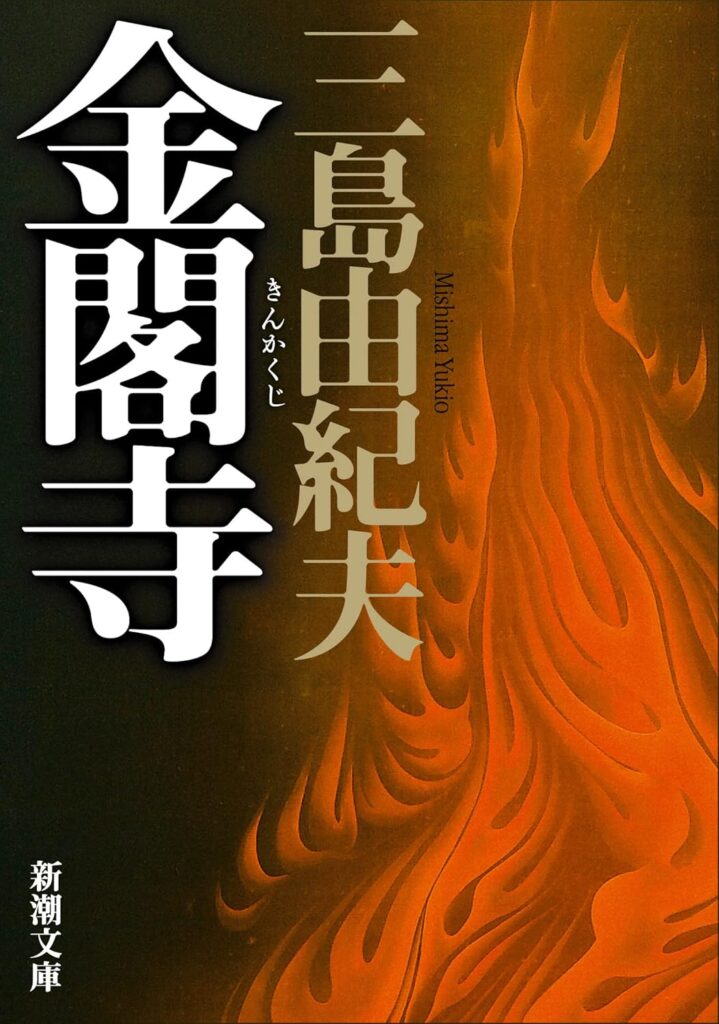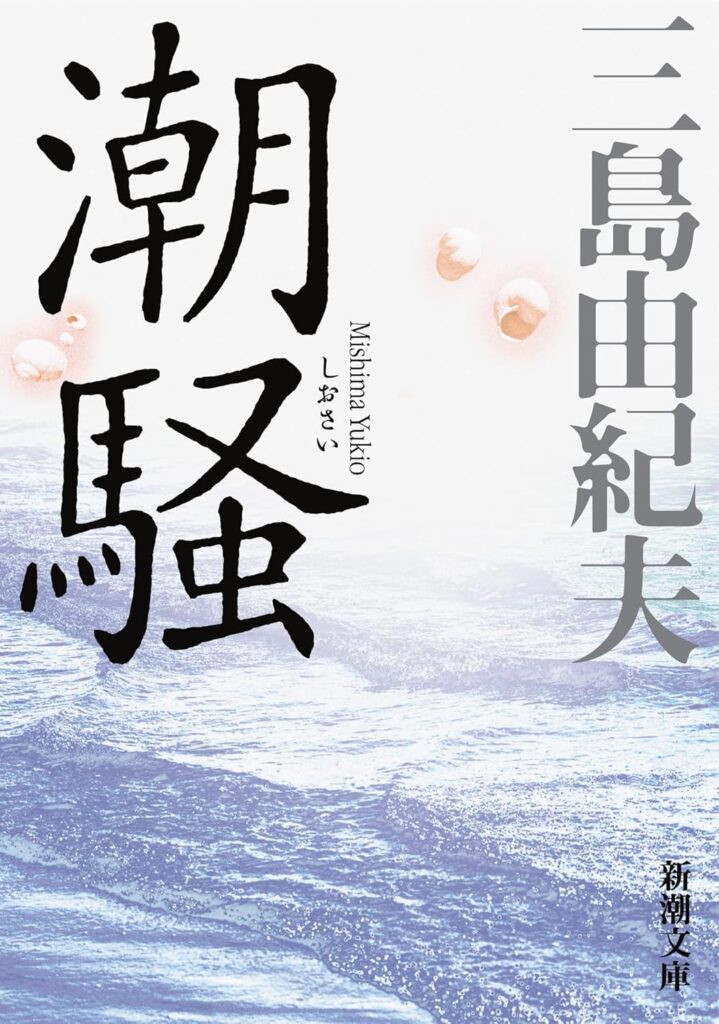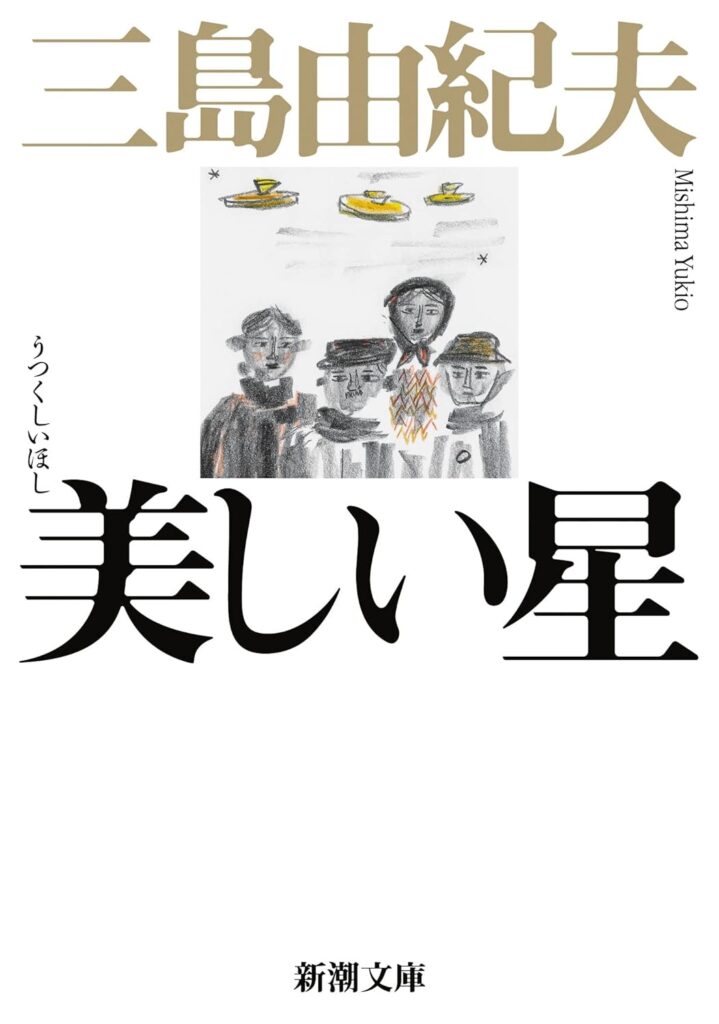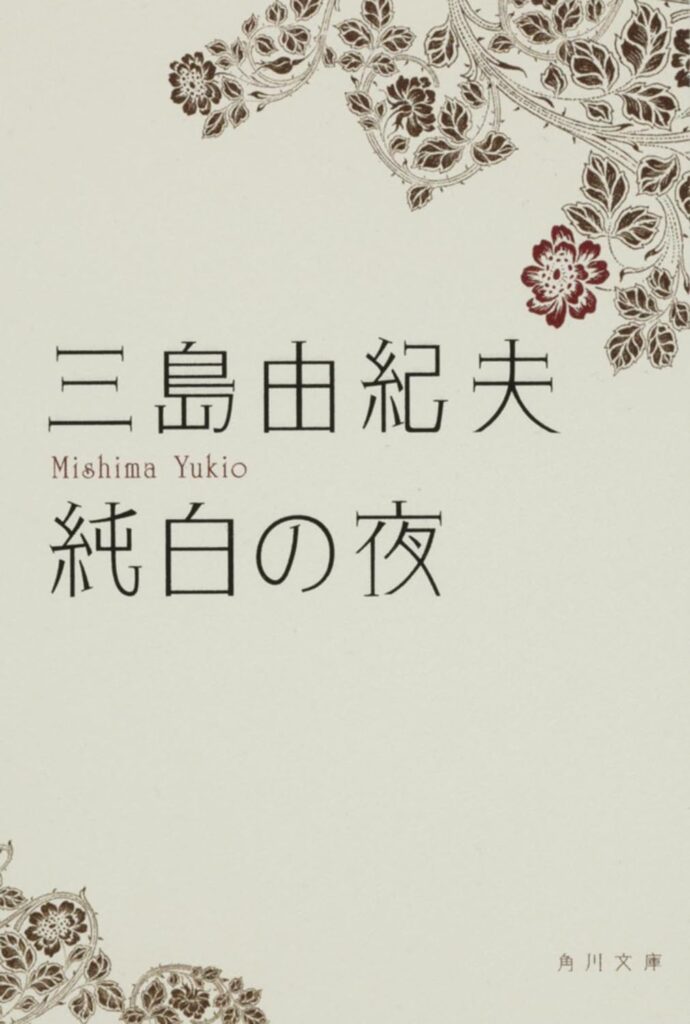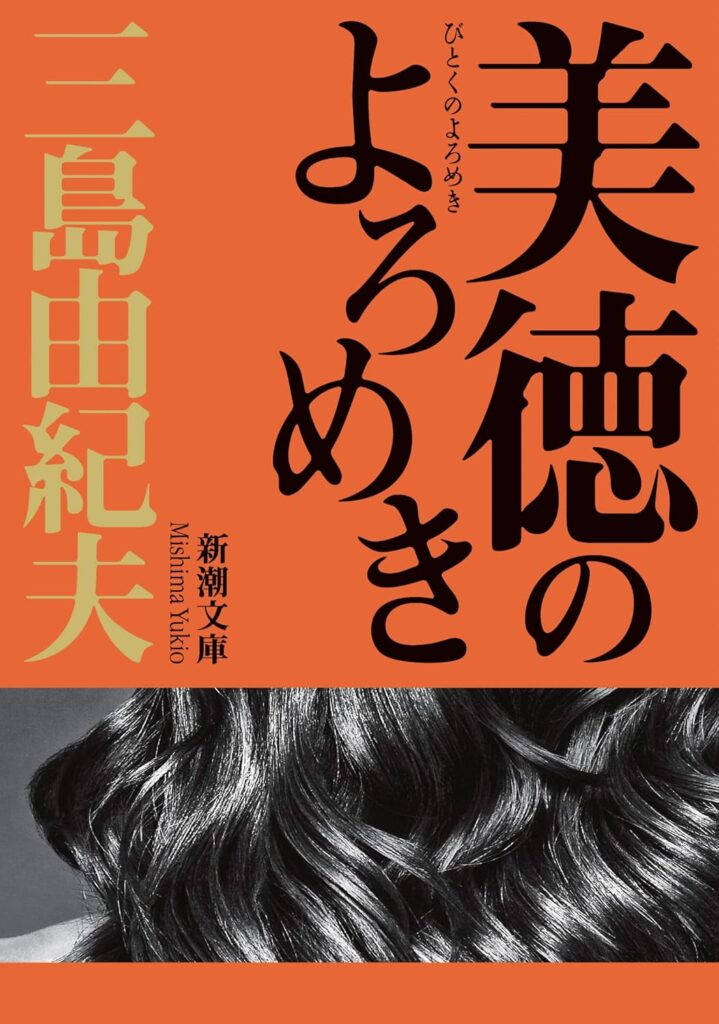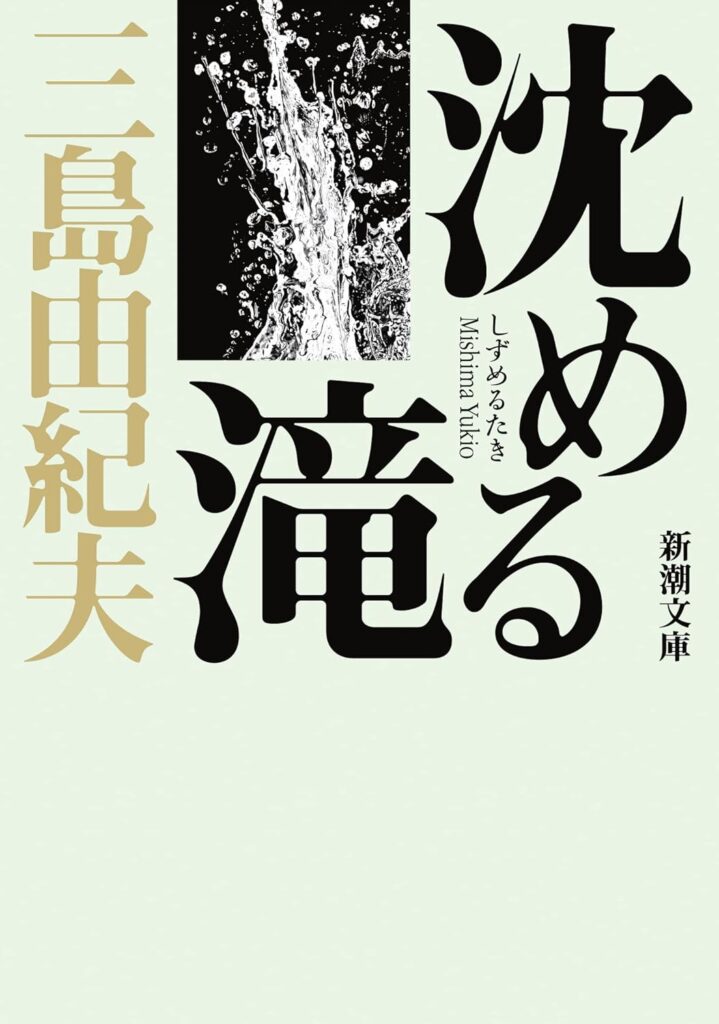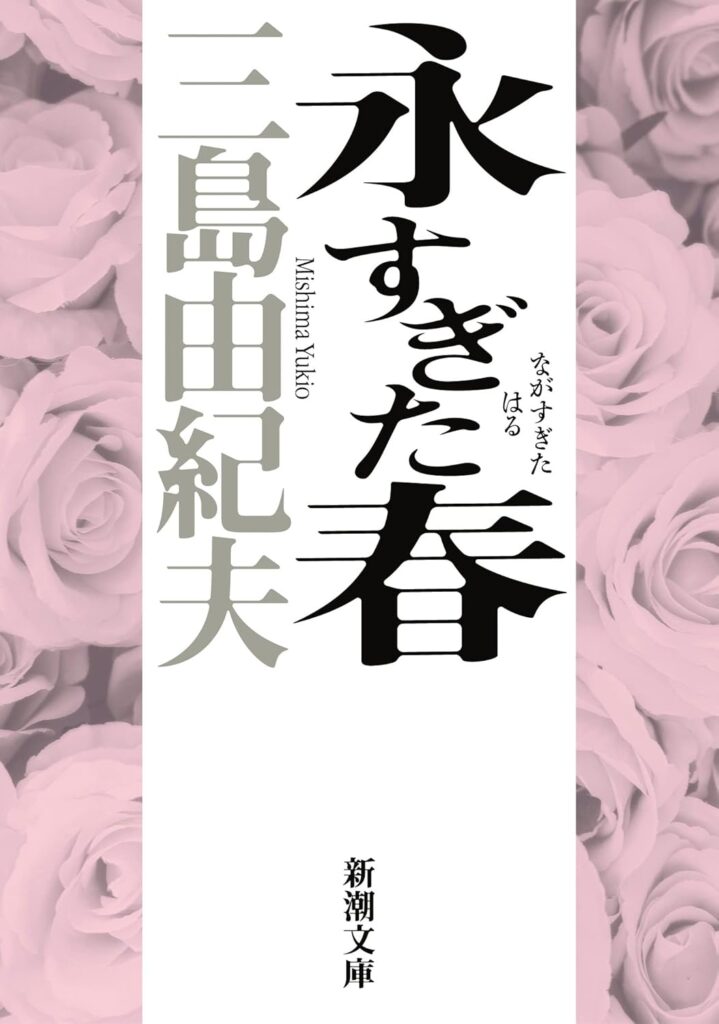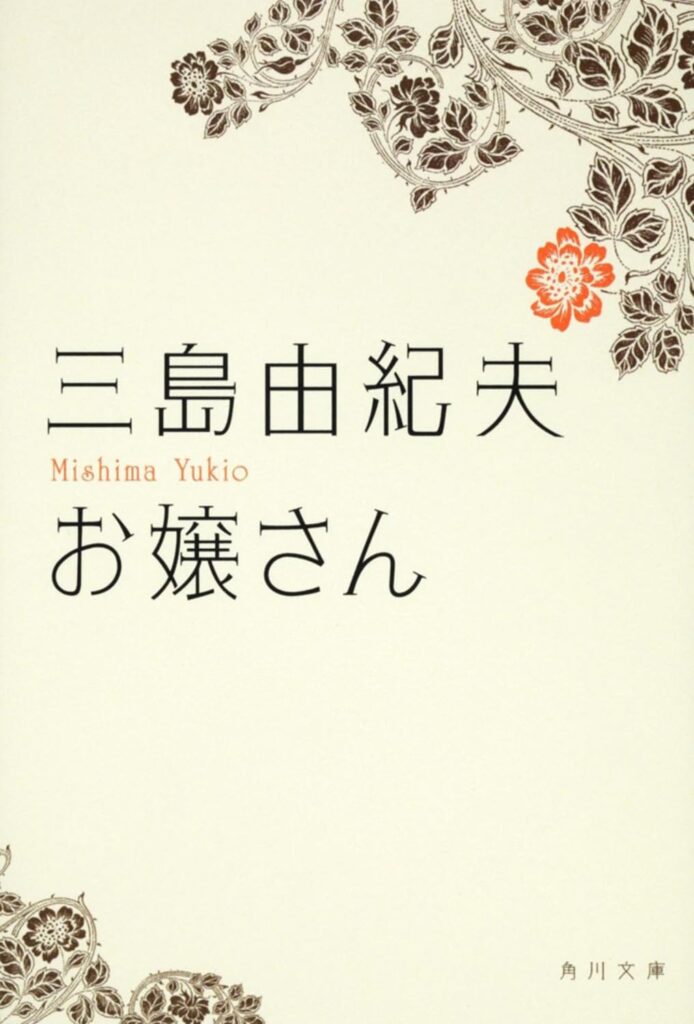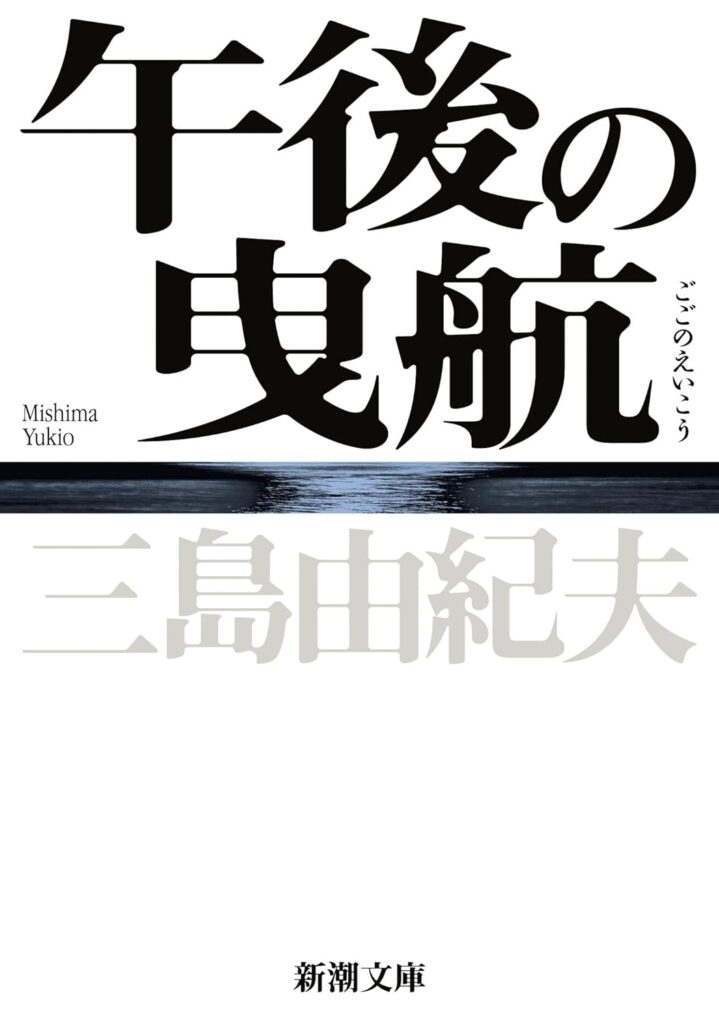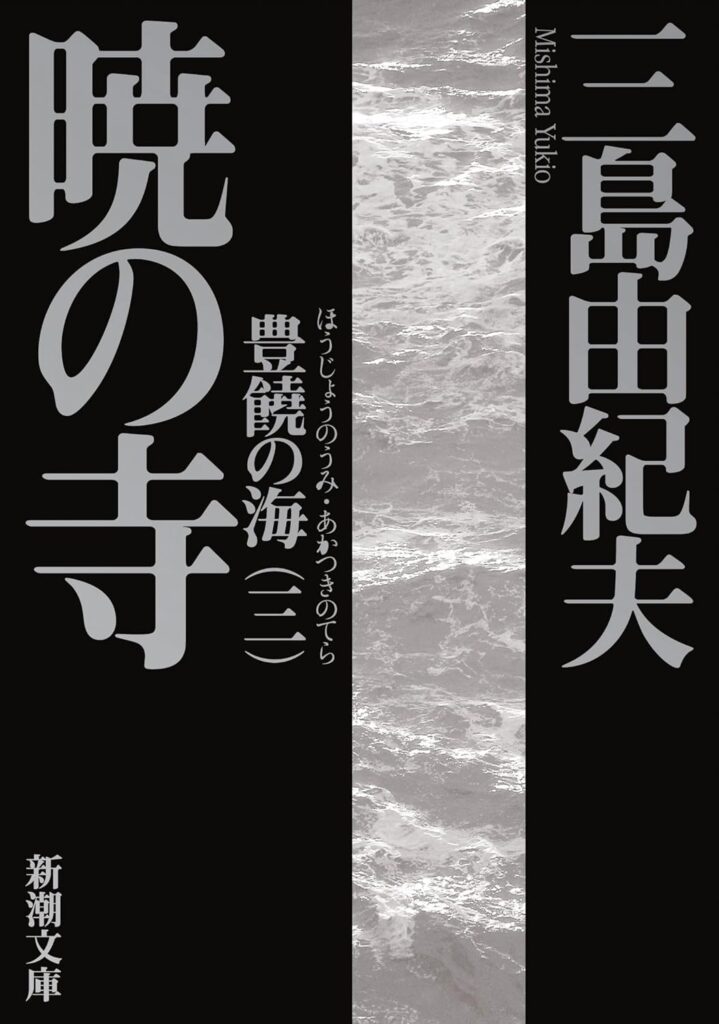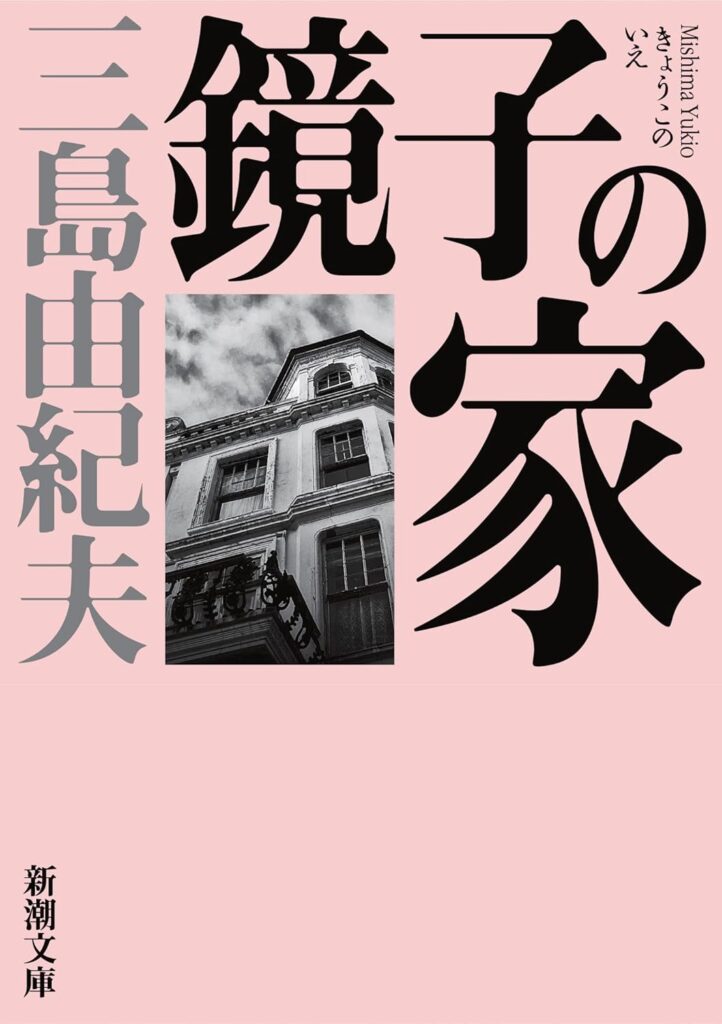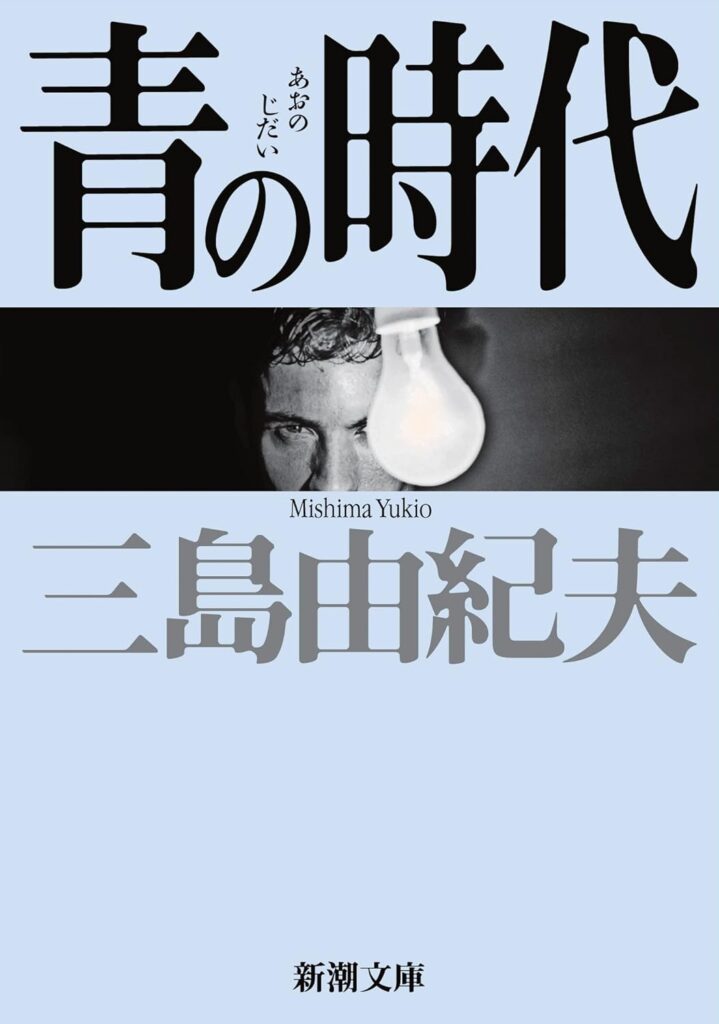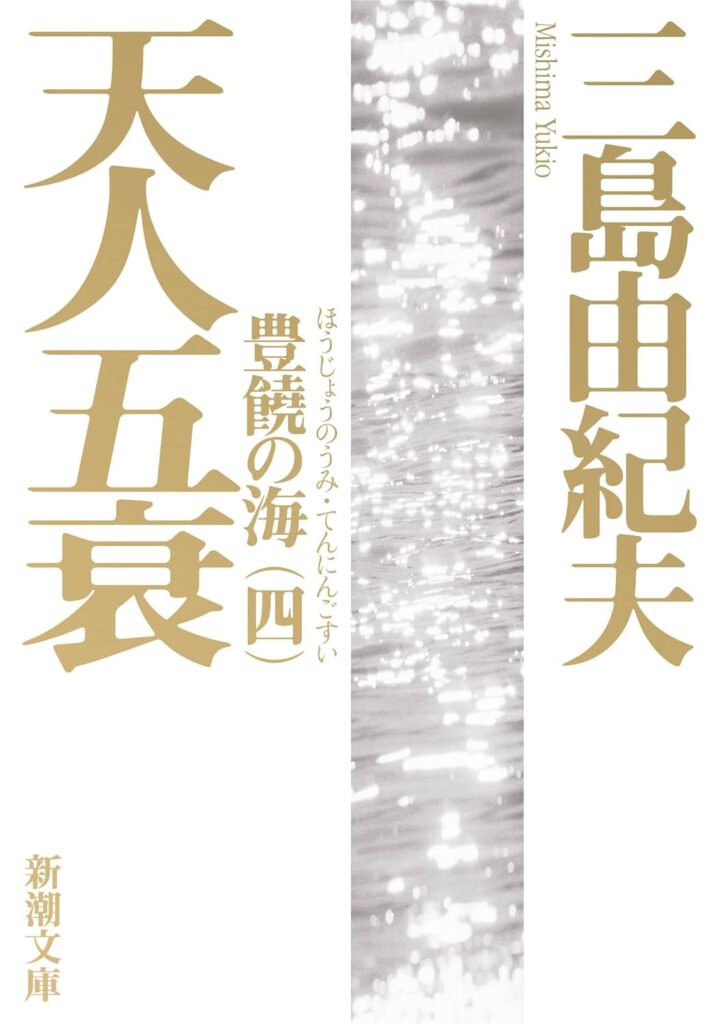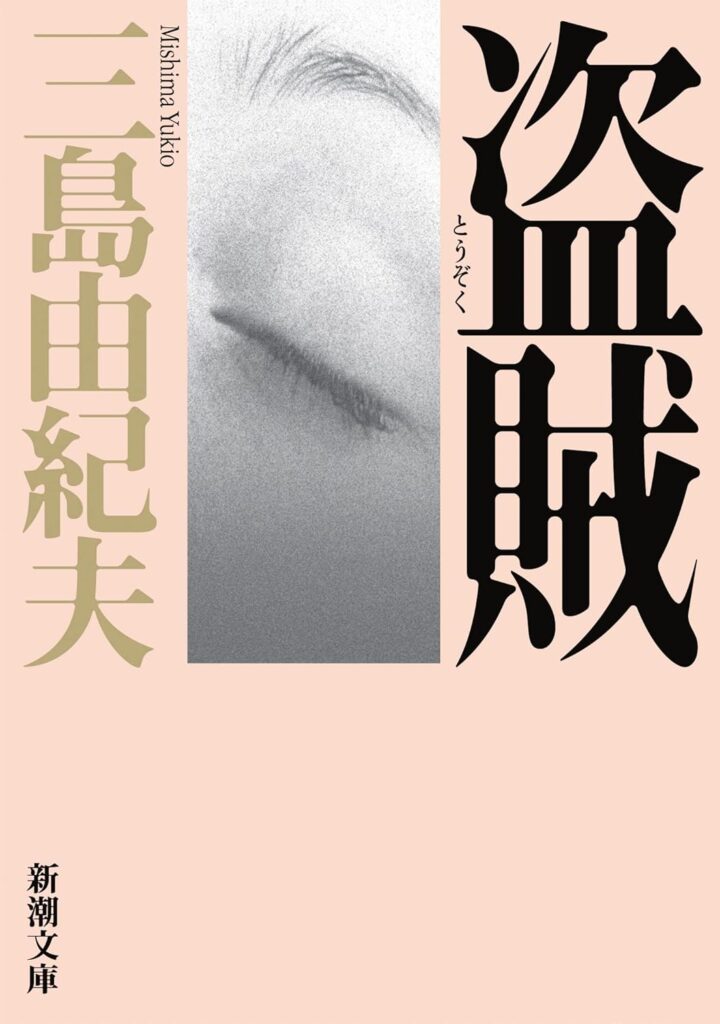小説「音楽」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、一見華やかに見える女性が抱える性の不感症という悩みを軸に、精神分析医との対話を通じて彼女の深層心理と過去のトラウマが解き明かされていく過程を描いています。三島由紀夫氏ならではの緻密な心理描写と、人間の内面に潜む複雑な感情が見事に描き出されている作品と言えるでしょう。
小説「音楽」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、一見華やかに見える女性が抱える性の不感症という悩みを軸に、精神分析医との対話を通じて彼女の深層心理と過去のトラウマが解き明かされていく過程を描いています。三島由紀夫氏ならではの緻密な心理描写と、人間の内面に潜む複雑な感情が見事に描き出されている作品と言えるでしょう。
物語の舞台は1950年代後半から1960年代初頭の日本。西洋文化が急速に浸透し、人々の価値観が揺れ動いていた時代です。主人公の弓川麗子は、美貌と知性を兼ね備え、何不自由ない生活を送っているように見えますが、恋人との関係において肉体的な喜びを感じることができません。彼女はこの状態を「音楽がきこえない」と表現します。
この記事では、そんな麗子が精神分析医・汐見の元を訪れるところから始まる物語の展開と、衝撃的な結末までを詳しく解説していきます。そして、物語の奥深さや登場人物たちの心の動きについて、ネタバレを含みつつ、私の視点からの詳細な感想を述べさせていただきます。三島文学の深淵に触れる一助となれば幸いです。
読み進めるうちに、あなたも麗子と共に彼女の心の奥底へと旅をし、やがて鳴り響く「音楽」の意味について深く考えさせられるかもしれません。それでは、三島由紀夫が奏でる魂の物語、「音楽」の世界へご案内いたしましょう。
小説「音楽」のあらすじ
精神分析医である汐見が東京の日比谷に診療所を構えて五年目の秋、弓川麗子という二十代半ばの美しい女性が彼の元を訪れます。麗子は名家の出身で、一流貿易会社に勤める才媛。誰から見ても申し分のない生活を送っているように見えましたが、彼女は深刻な悩みを抱えていました。それは、婚約者である江上隆一と愛し合っても、全く肉体的な喜びを感じることができない、いわゆる不感症であるということでした。麗子は自身のこの状態を「音楽がきこえない」と独特の言葉で表現します。
汐見医師とのカウンセリングが重ねられる中で、麗子の心の奥深くに隠された衝撃的な過去が徐々に明らかになっていきます。麗子がまだ少女だった頃、彼女には十歳年上の兄がいました。兄妹仲は非常に良好でしたが、ある日、麗子は受験勉強のために山梨の昇仙峡の宿に籠っていた兄と、同道した伯母との近親相姦の現場を目撃してしまいます。この出来事は麗子の心に深い傷を残し、間もなく兄は大学受験に失敗し、家を出て行方不明となっていました。
そんな中、麗子のまたいとこであり、幼い頃からの許婚であった俊が癌で若くして亡くなります。俊の死の床で、麗子は不思議な感覚に包まれ、初めて「音楽」を聞いたと汐見に告白します。それは、死にゆく者、あるいは生命力の希薄な者に寄り添うことで得られる倒錯的な恍惚感のようでした。その後、麗子は伊豆へ一人旅に出かけ、そこで花井という男性機能を持たない青年と出会い、彼との関係においても同様の「音楽」を聞くのです。
汐見医師は、麗子が真の意味で「音楽」を聞き、健やかな愛を育むためには、すべての元凶である行方不明の兄と再会し、過去と対峙する必要があると判断します。麗子の婚約者である江上も彼女の壮絶な過去を知りながらも深く理解し、協力を申し出ます。ある日、麗子はドキュメンタリー番組で偶然、山谷のドヤ街で暮らす兄の姿を発見します。
汐見、江上、そして麗子の三人は、兄との対面を果たすため、身なりを変えて山谷へと潜入します。そこで彼らが見たのは、赤ん坊を背負い、おでん屋で酒を飲む、かつての聡明な兄の見る影もない姿でした。麗子は幼い頃から無意識に抱いていた「兄の子供を産みたい」という倒錯した願望が消え去り、心の平安を取り戻します。兄に現金を渡し、過去との決別を果たした麗子は、涙を流しながらその場を後にするのでした。
それから半年後、麗子と江上は無事に結婚します。そして汐見医師の元には、麗子から「オンガク オコル オンガク タエマナイ」という短い電報が届くのでした。それは、彼女がようやく真の愛と喜びに目覚め、心からの「音楽」を聴くことができるようになったことを示す、祝福のメッセージだったのです。
小説「音楽」の長文感想(ネタバレあり)
小説「音楽」は、三島由紀夫氏が人間の深層心理、特に性と愛、そしてトラウマからの解放というテーマに鋭く切り込んだ作品だと感じます。物語を読み終えた後も、登場人物たちの心の葛藤や、彼らがたどり着いた境地について、深く考えさせられる余韻が残りました。
まず、主人公である弓川麗子の「音楽がきこえない」という訴えは、単なる性的な不感症を超えて、現代人が抱える精神的な空虚さや、生きる実感の希薄さをも象徴しているように思えます。彼女は美貌、家柄、知性といった外面的な要素には恵まれていますが、内面では深い孤独と疎外感を抱えています。この内と外の乖離こそが、彼女の苦悩の根源なのでしょう。
精神分析医である汐見の存在は、この物語において非常に重要です。彼は冷静かつ客観的な視点を持ちながらも、麗子の複雑な内面世界に辛抱強く寄り添い、彼女自身が問題の核心に気づく手助けをします。汐見のカウンセリングは、単に症状を取り除くだけでなく、麗子が人間として成長し、真の自己を確立するためのプロセスそのものとして描かれています。彼の分析は鋭く、時に読者である私たち自身の心の奥底をも見透かされているような感覚に陥りました。
麗子のトラウマの根源として描かれる、兄と伯母の近親相姦の目撃。そして、その兄への無意識の思慕と、それが屈折した形で表出する「兄の子供を産みたい」という願望。これらは非常に衝撃的であり、人間の心の闇の深さを感じさせます。三島氏は、このような禁忌とされる領域にも臆することなく踏み込み、人間の本能的な部分を赤裸々に描き出していると感じました。
麗子が初めて「音楽」を聞く瞬間、それはまたいとこである俊の死に際してでした。死にゆく者、あるいは生命力の欠如した存在に寄り添うことで得られる倒錯したエクスタシー。これは、彼女のトラウマと深く結びついた、歪んだ形の自己救済なのかもしれません。伊豆で出会った不能の青年、花井との関係においても同様の「音楽」を聞くことから、彼女の心が正常な愛を受け入れることを拒絶し、ある種の「安全な」対象にしか反応できない状態にあったことがうかがえます。
汐見医師が下した診断と治療方針――すなわち、麗子が健全な「音楽」を聞くためには、トラウマの元凶である兄と対峙し、過去を清算する必要があるというもの――は、物語の転換点となります。この対決の場面は、読者に強烈な印象を残します。江上という婚約者の存在も、麗子にとっては大きな支えとなったことでしょう。彼は麗子の壮絶な過去を知ってもなお、彼女を受け入れ、共に困難に立ち向かおうとします。彼の深い愛情と理解がなければ、麗子の再生はより困難なものだったかもしれません。
山谷のドヤ街で再会した兄の姿は、かつての聡明な面影はなく、落ちぶれ果てたものでした。しかし、この再会こそが、麗子を長年の呪縛から解き放つ鍵となります。兄の現在の姿を目の当たりにし、そして彼が他人の子供を育てているという現実を知ることで、麗子の心の中で神格化されていた兄のイメージは崩壊し、同時に「兄の子供を産みたい」という倒錯した願望も消滅します。これは、彼女にとって痛みを伴うプロセスであったでしょうが、同時に真の自己を取り戻すための不可欠な通過儀礼だったのです。
この兄との再会のシーンは、単に麗子の個人的なトラウマの解消にとどまらず、当時の日本の社会構造や格差といった問題をも暗示しているように感じられました。華やかな世界の住人である麗子と、社会の底辺で生きる兄との対比は鮮烈であり、読者に様々なことを考えさせます。
物語の結末で、麗子から汐見医師の元に届く「オンガク オコル オンガク タエマナイ」という電報は、まさにカタルシスそのものです。彼女が過去のトラウマを乗り越え、江上との間に真実の愛と喜びを見出し、心からの「音楽」を聴くことができるようになったことを高らかに宣言しています。それは、暗く長いトンネルを抜け、ようやく光を見出した人間の魂の賛歌のようにも聞こえます。
三島由紀夫氏は、この「音楽」という作品を通して、人間の精神の複雑さと、その再生の可能性を描ききったのではないでしょうか。愛とは何か、性とは何か、そして人間が真に「生きている」と感じる瞬間とはどのようなものなのか。そうした根源的な問いを、読者に投げかけているように思います。単なる恋愛物語や精神分析の記録ではなく、人間の魂のドラマとして深く心に刻まれる作品です。
麗子の「音楽がきこえない」状態は、彼女の心が外界からの刺激を拒絶し、内側に閉じこもっていた状態の象徴であったのでしょう。それは、過去のトラウマによって形成された厚い壁であり、彼女自身を守るための鎧でもあったのかもしれません。しかし、その壁は同時に、彼女が真の喜びや他者との深いつながりを感じることをも妨げていました。
汐見医師との対話は、その壁に少しずつ亀裂を入れていく作業でした。そして、俊の死や花井との出会いといった出来事が、その亀裂から漏れ出す歪んだ「音楽」として表出します。これらは不完全で倒錯したものでありながらも、麗子にとっては自己の存在をかろうじて確認できる唯一の手段だったのかもしれません。その意味では、これらの体験もまた、彼女が真の「音楽」に至るための必要なステップだったと言えるでしょう。
最終的に兄との対面を果たし、過去の幻影を振り払った麗子は、初めて自分自身の力で、そして江上という他者の愛を通じて、健全な「音楽」を奏でることができるようになります。それは、他者との調和の中で生まれる魂の響きであり、生命の躍動そのものなのでしょう。この変化の過程は、非常に説得力を持って描かれており、読者は麗子と共に安堵と喜びを感じることができます。
この物語は、トラウマというものが一個人の人生にどれほど深く、そして長期にわたって影響を及ぼすかということを改めて教えてくれます。しかし同時に、適切な導きと本人の強い意志、そして周囲の理解と支えがあれば、人はその苦しみから解放され、新たな人生を歩み出すことができるという希望も示してくれているように感じます。
三島由紀夫氏の美しくも鋭利な文体は、登場人物たちの繊細な心の機微や、時に倒錯的とも言える感情を見事に捉えています。その筆致は、読者を物語の世界へと深く引き込み、まるで自分がその場に立ち会っているかのような臨場感を与えてくれます。「音楽」というタイトルが示すように、この作品は言葉によって奏でられる魂の旋律であり、読後もその響きが心の中で鳴り続けるような、深い感動を伴う物語でした。
まとめ
三島由紀夫の小説「音楽」は、一人の女性が抱える性の不感症という問題を通して、人間の深層心理とトラウマからの再生を描いた重厚な物語です。主人公・弓川麗子が「音楽がきこえない」と表現する苦悩は、現代社会に生きる私たちが抱える可能性のある、より広範な精神的課題とも共鳴するように感じられます。
精神分析医・汐見との対話を通じて、麗子の過去の傷が明らかになり、その克服の過程が丁寧に描かれています。特に、行方不明だった兄との再会は、物語のクライマックスであり、麗子が長年抱えてきた心のわだかまりを解消する重要な転機となります。この過程で、読者は人間の心の複雑さ、そしてそこからの解放の可能性について深く考えさせられるでしょう。
この作品は、単に個人の問題を描くだけでなく、愛や性、家族という普遍的なテーマについても深く掘り下げています。三島由紀夫氏の緻密な心理描写と美しい文章は、読者を物語の世界に引き込み、登場人物たちの感情の揺れ動きを鮮やかに伝えてくれます。読み終えた後には、心に響く「音楽」とは何か、そして真の幸福とは何かについて、改めて思いを巡らせることになるでしょう。
もしあなたが、人間の内面世界や心の謎に興味をお持ちであれば、この「音楽」という作品は、きっと深い感銘と考察の機会を与えてくれるはずです。ぜひ一度、手に取って、麗子の魂の軌跡を追体験してみてはいかがでしょうか。そこには、時代を超えて私たちの心に訴えかける、力強いメッセージが込められています。