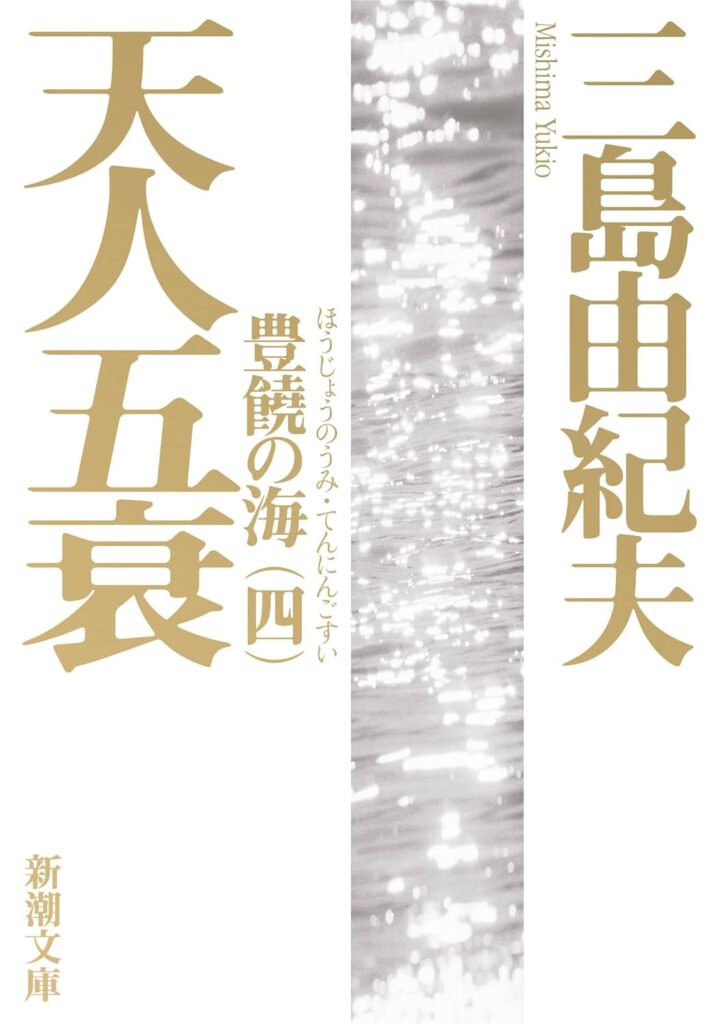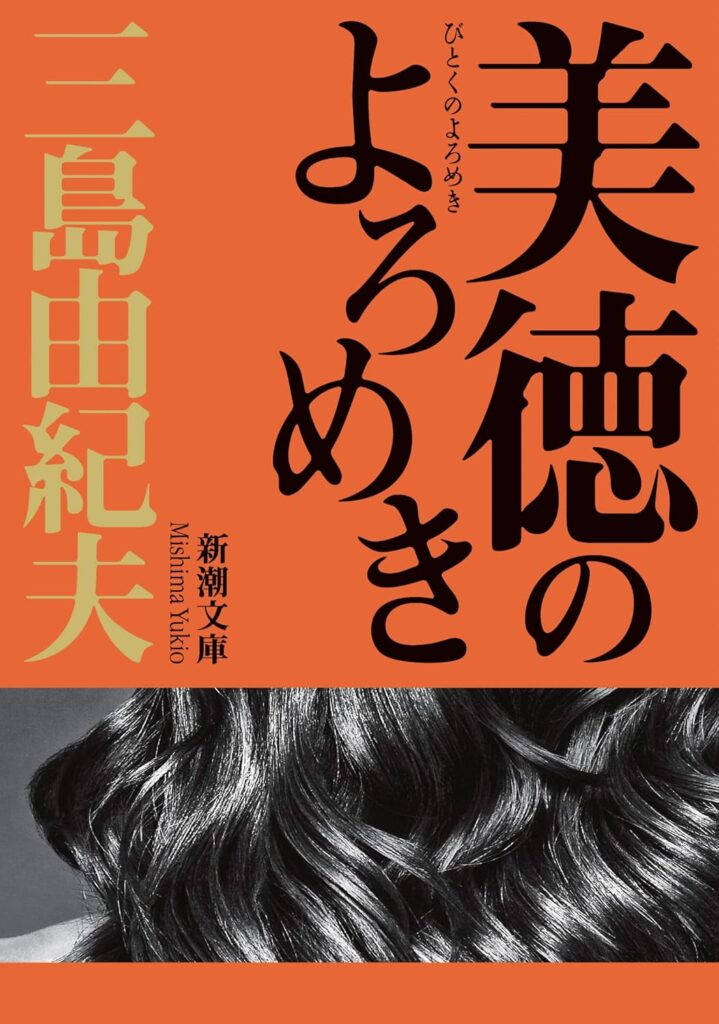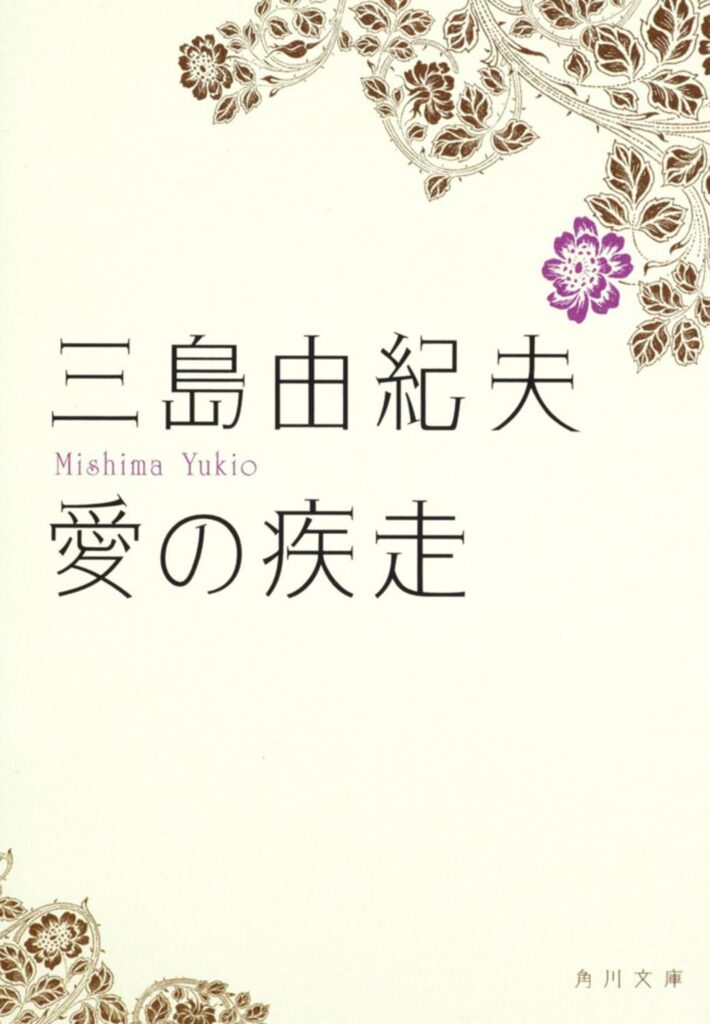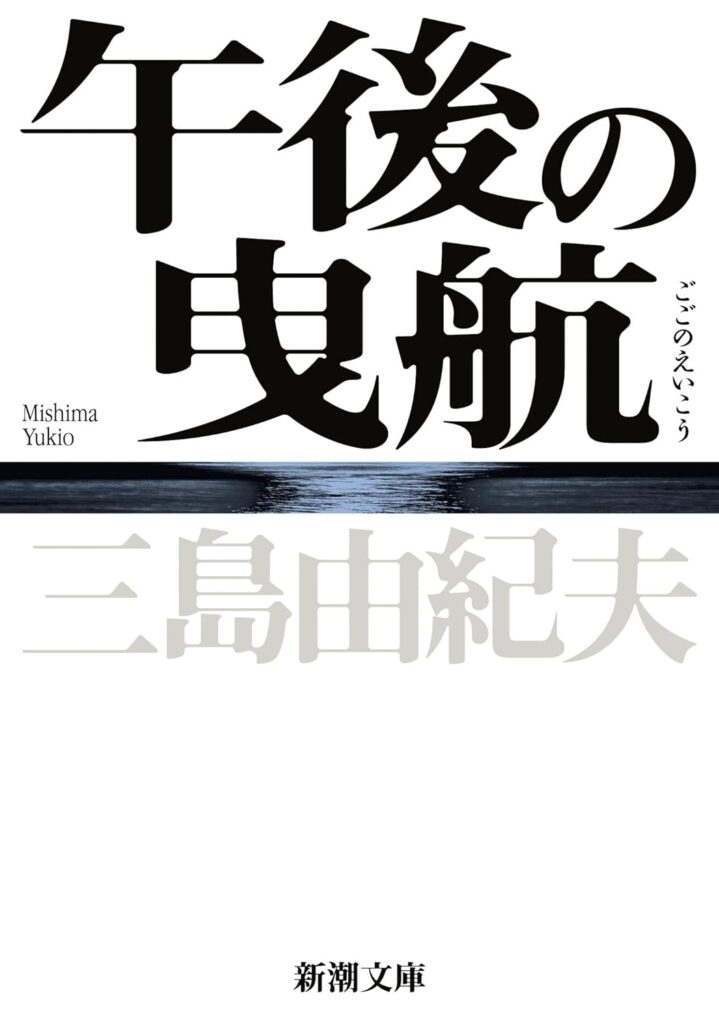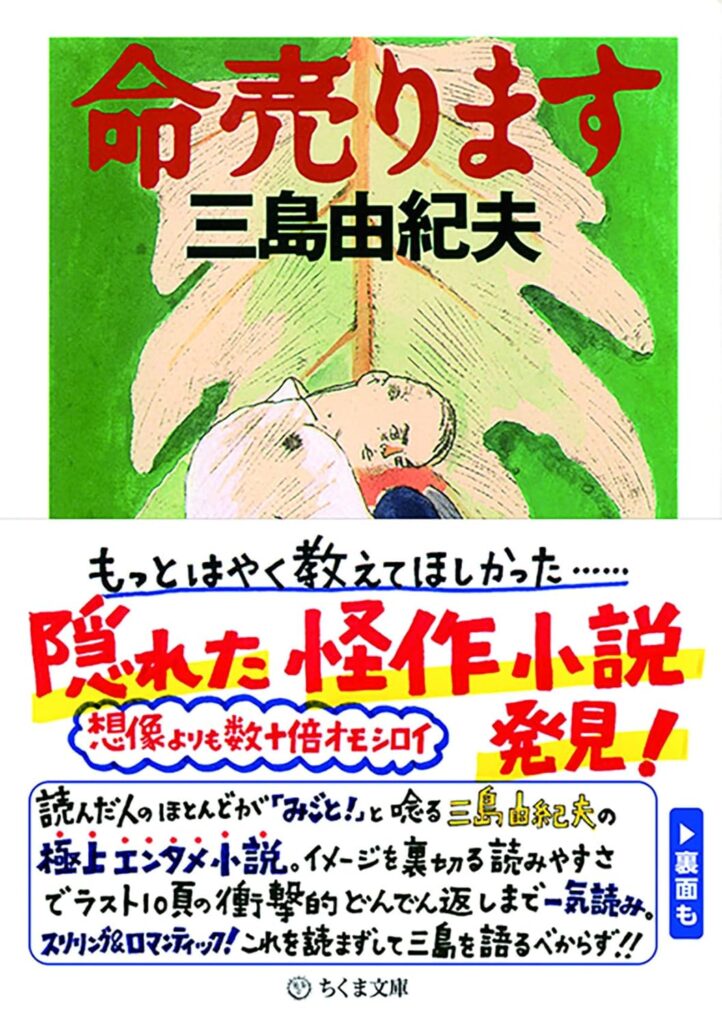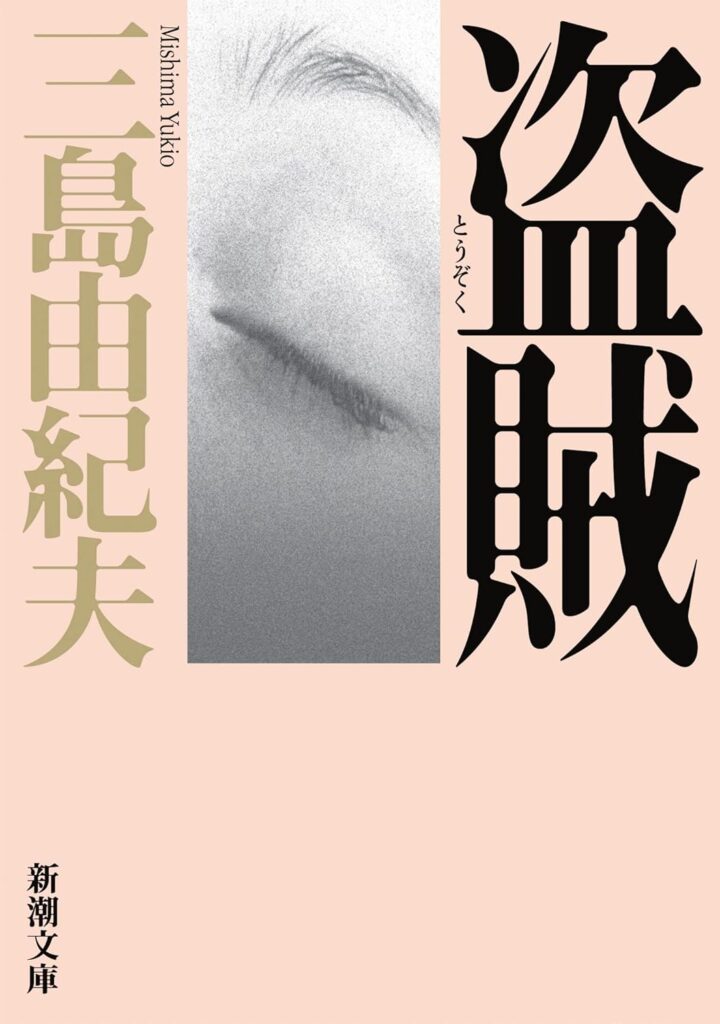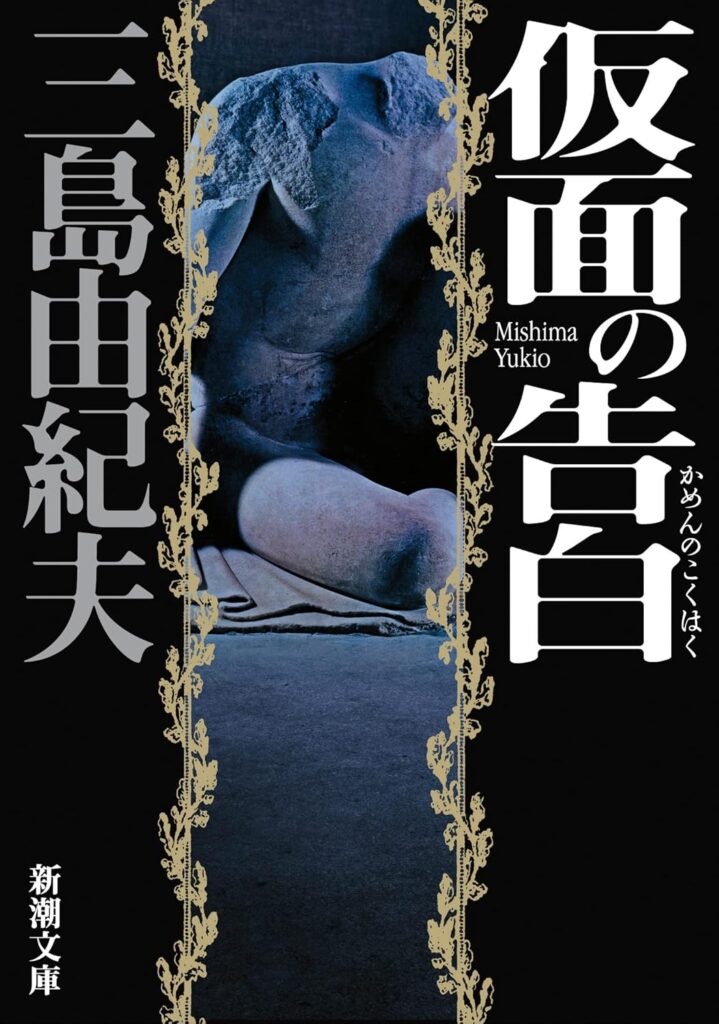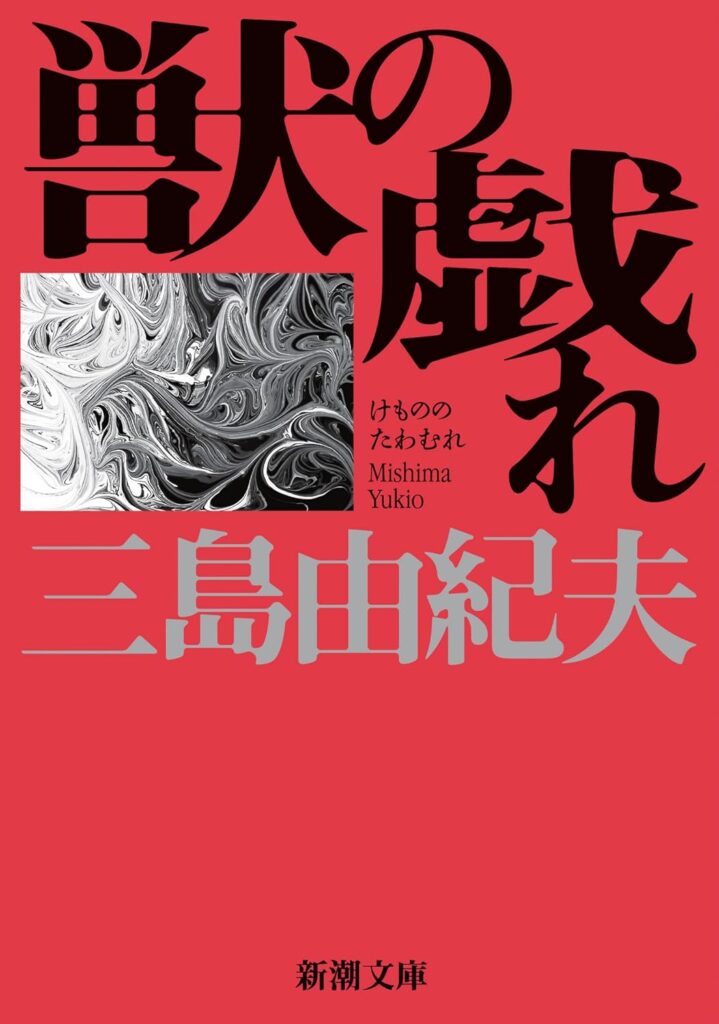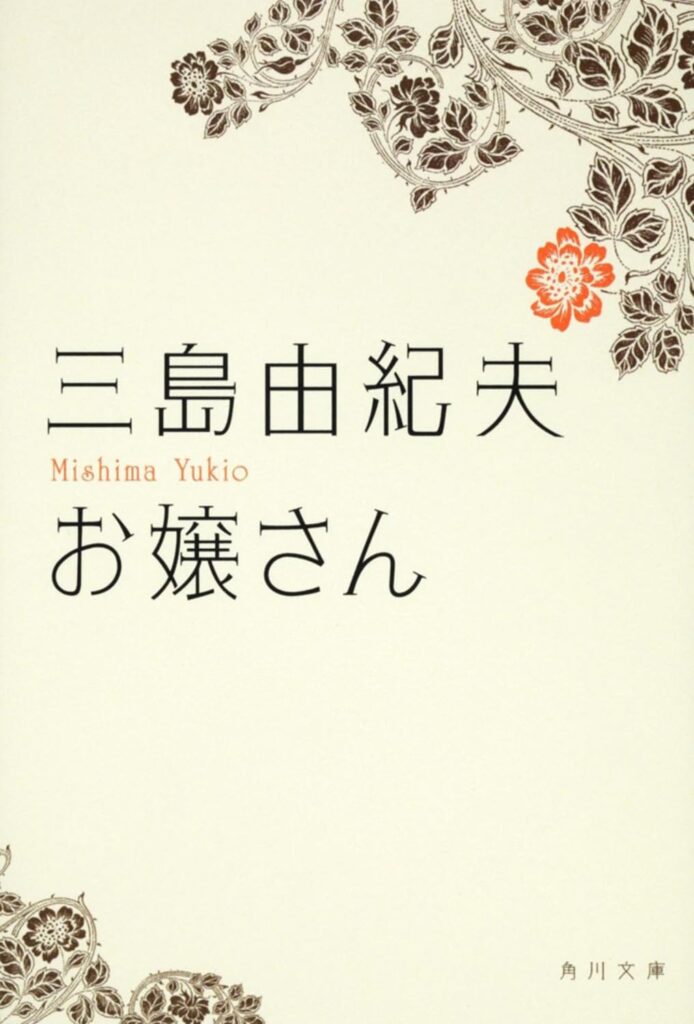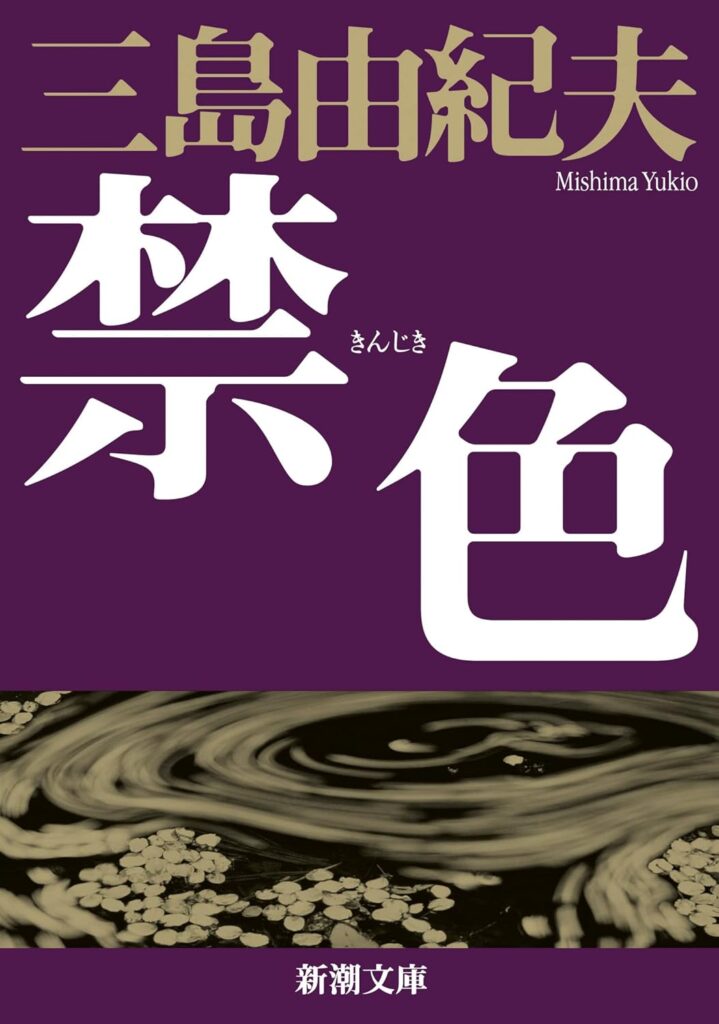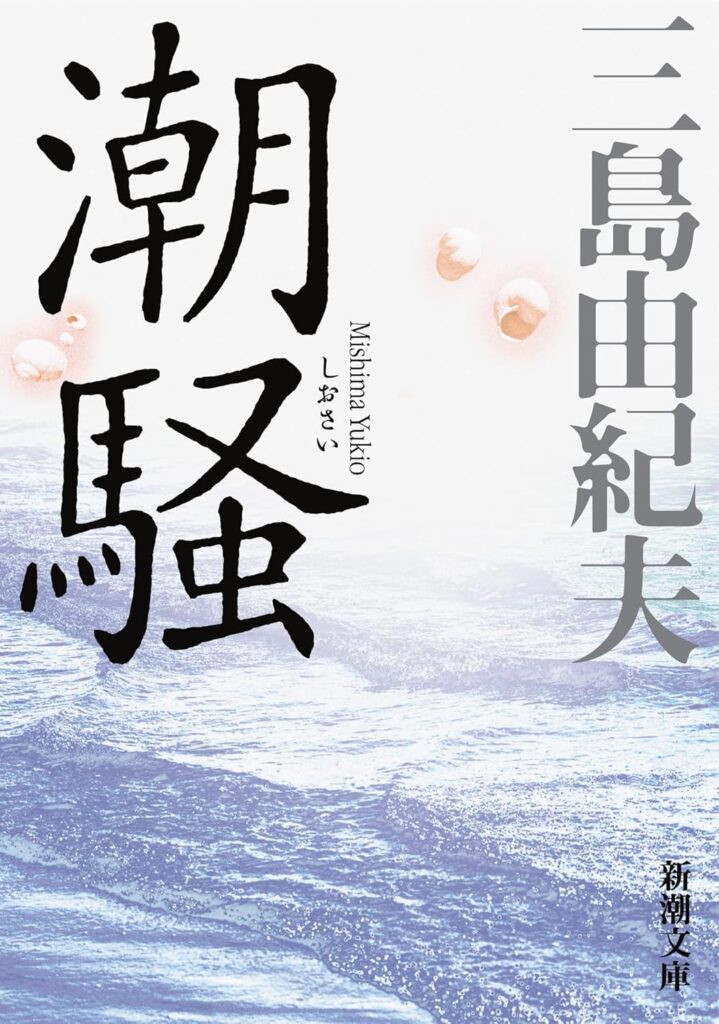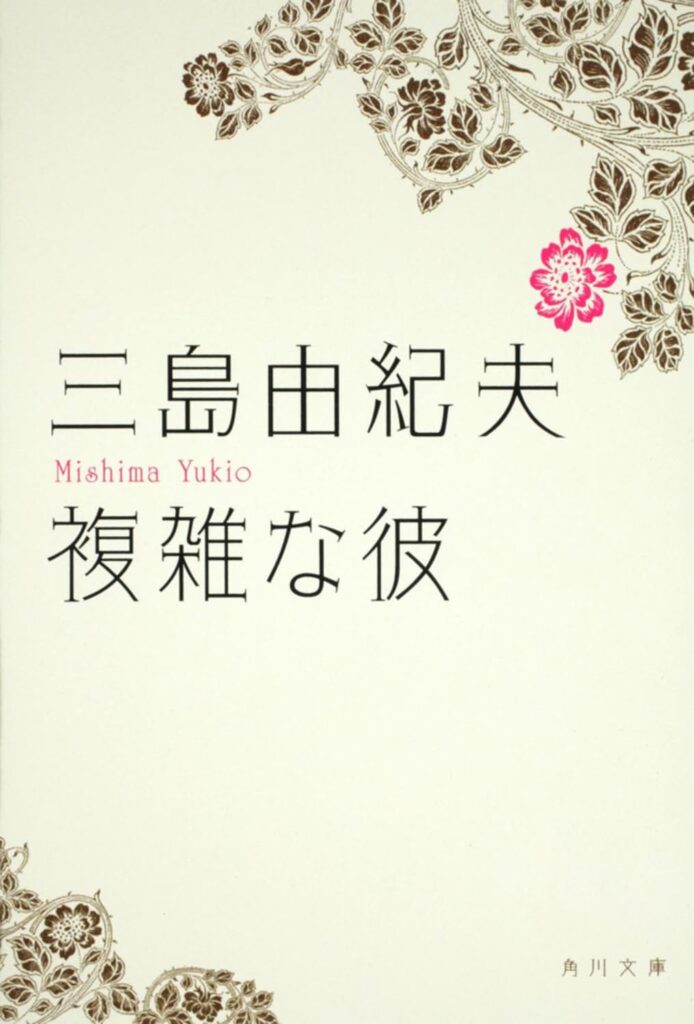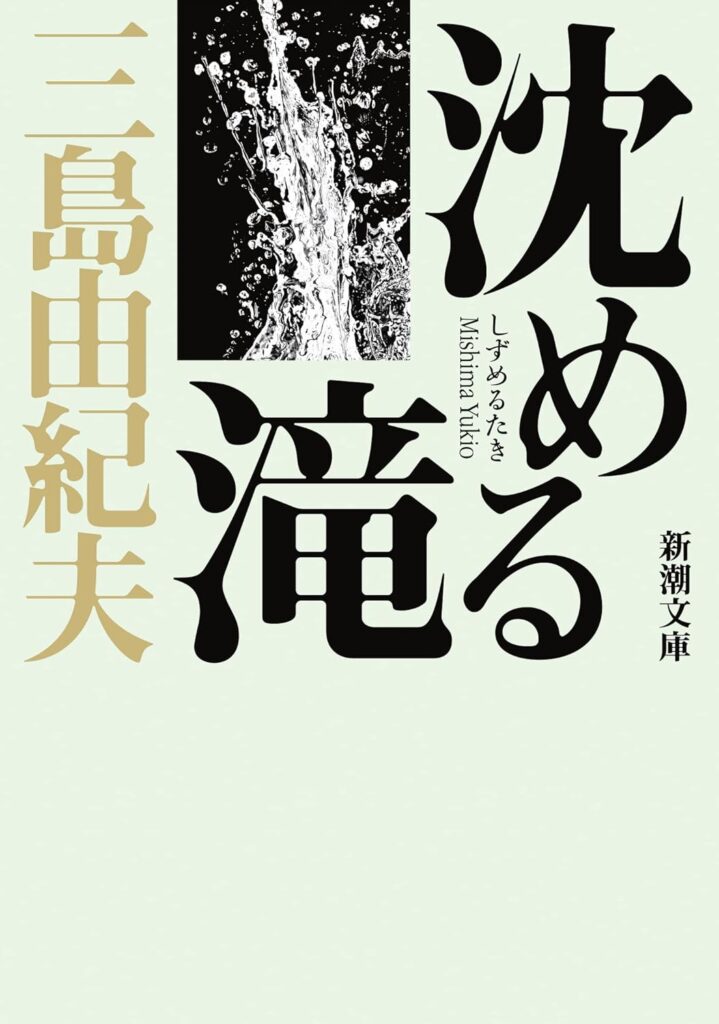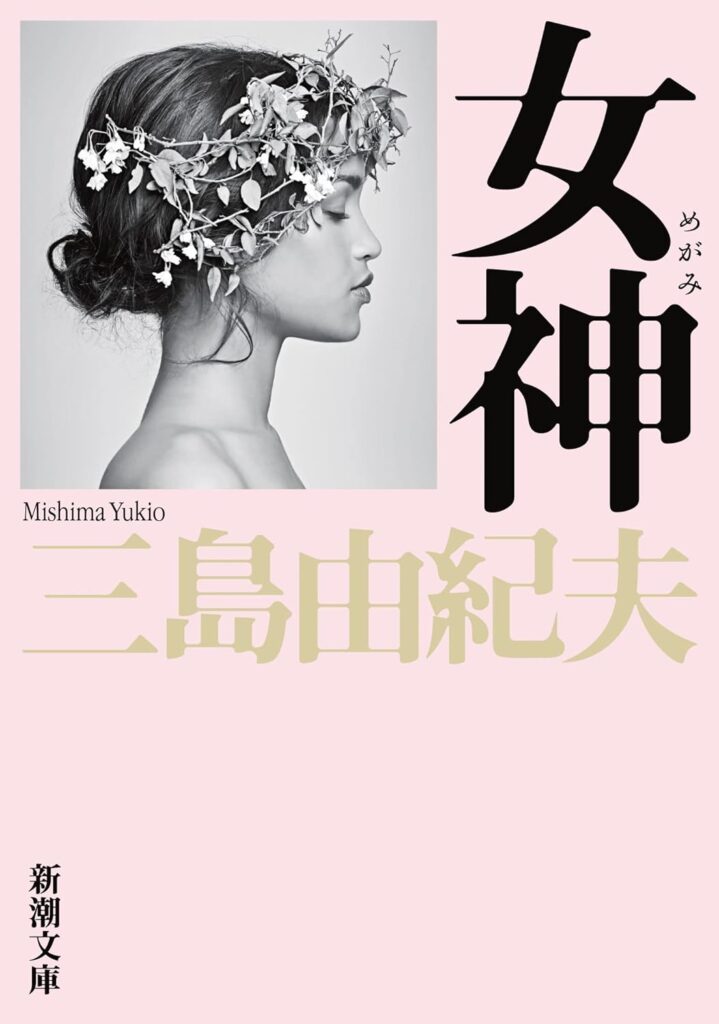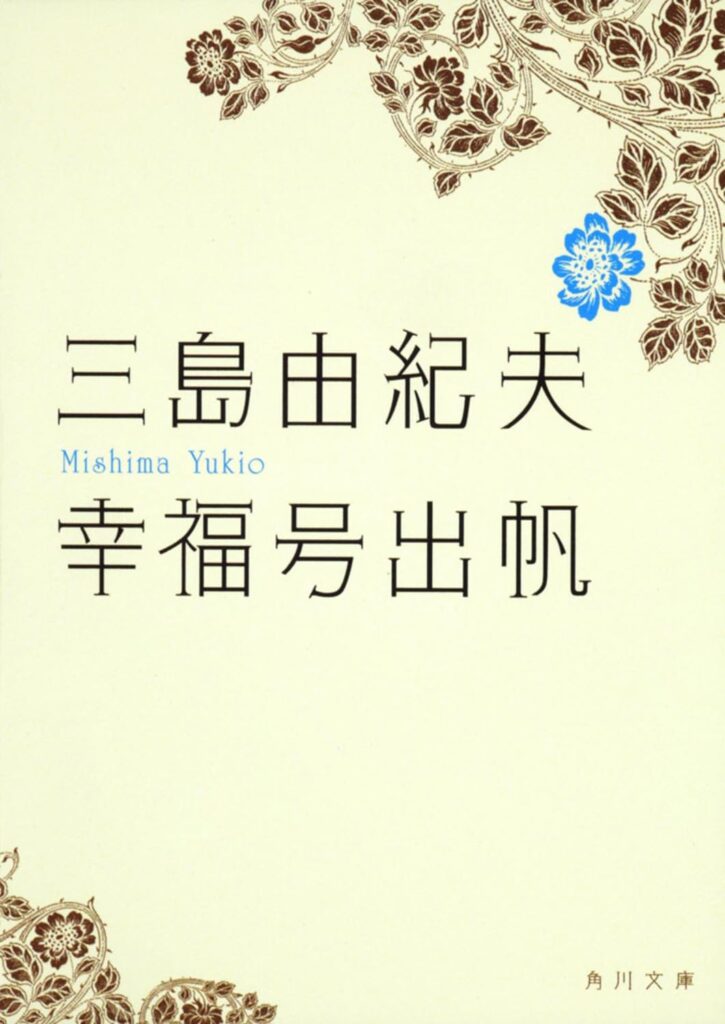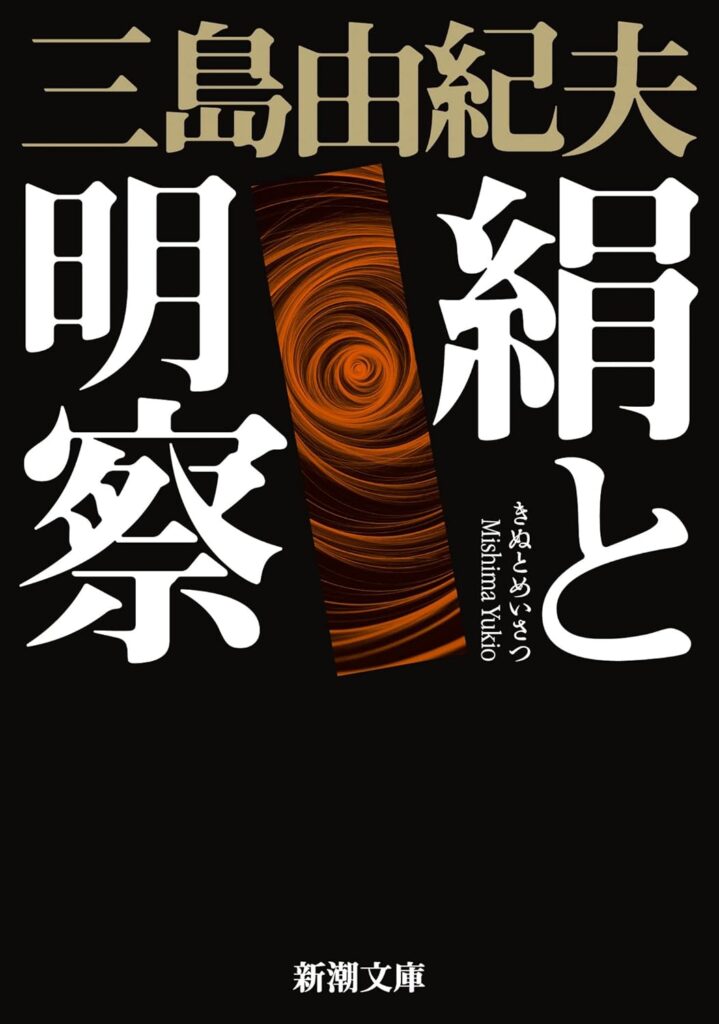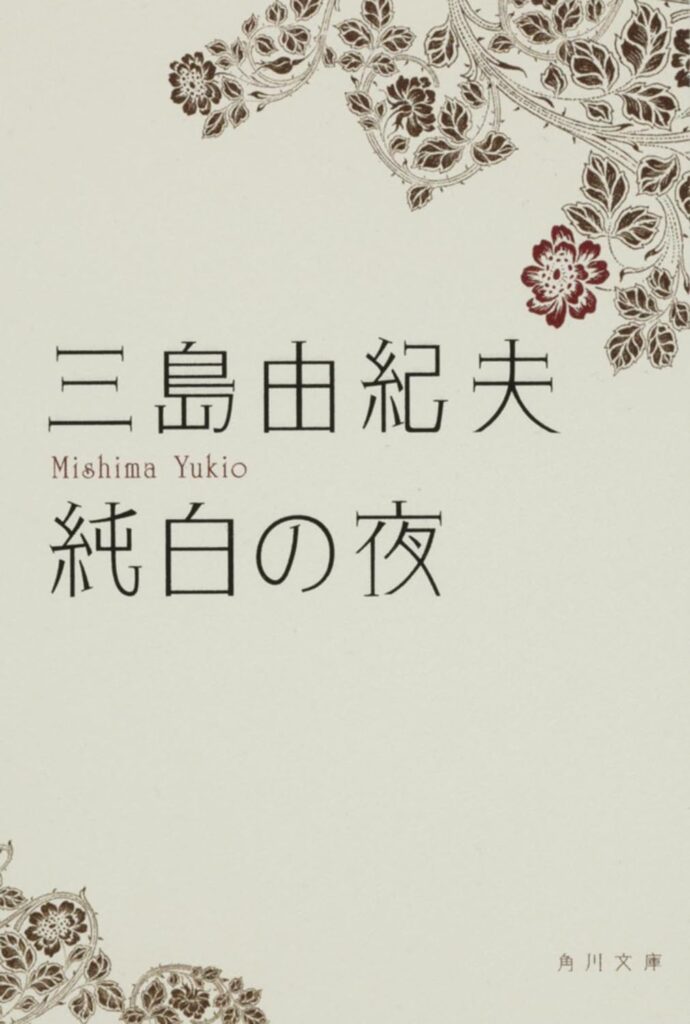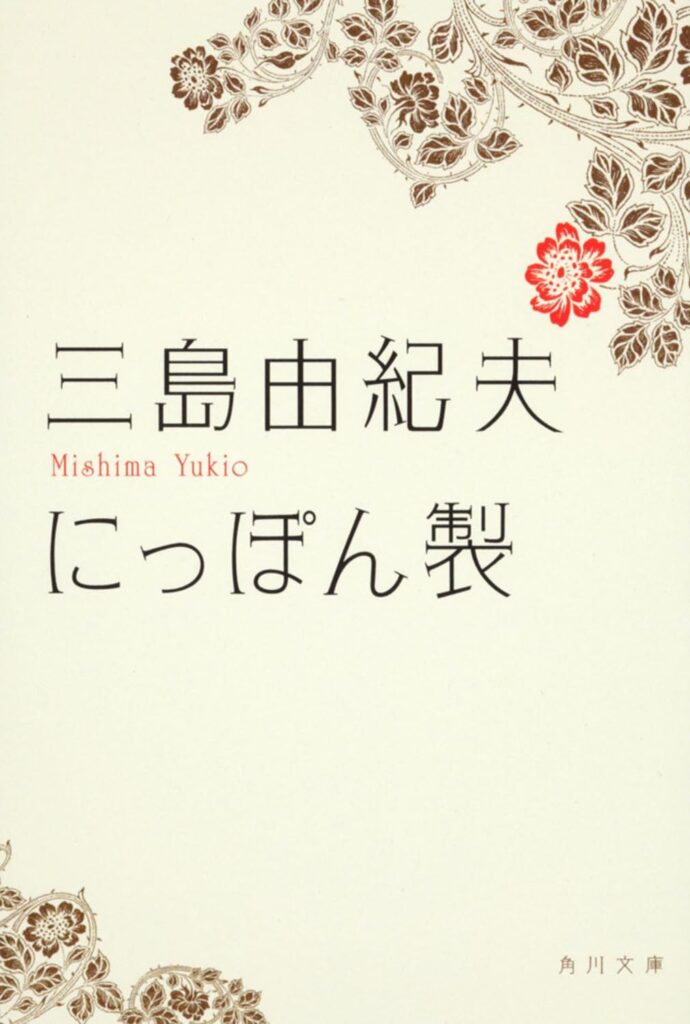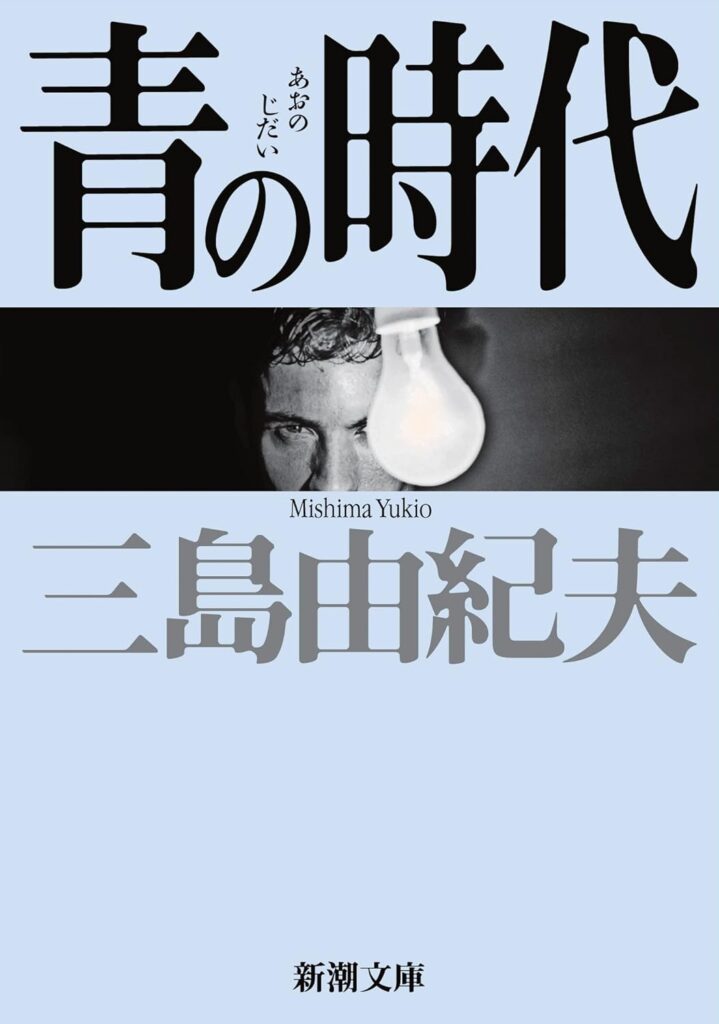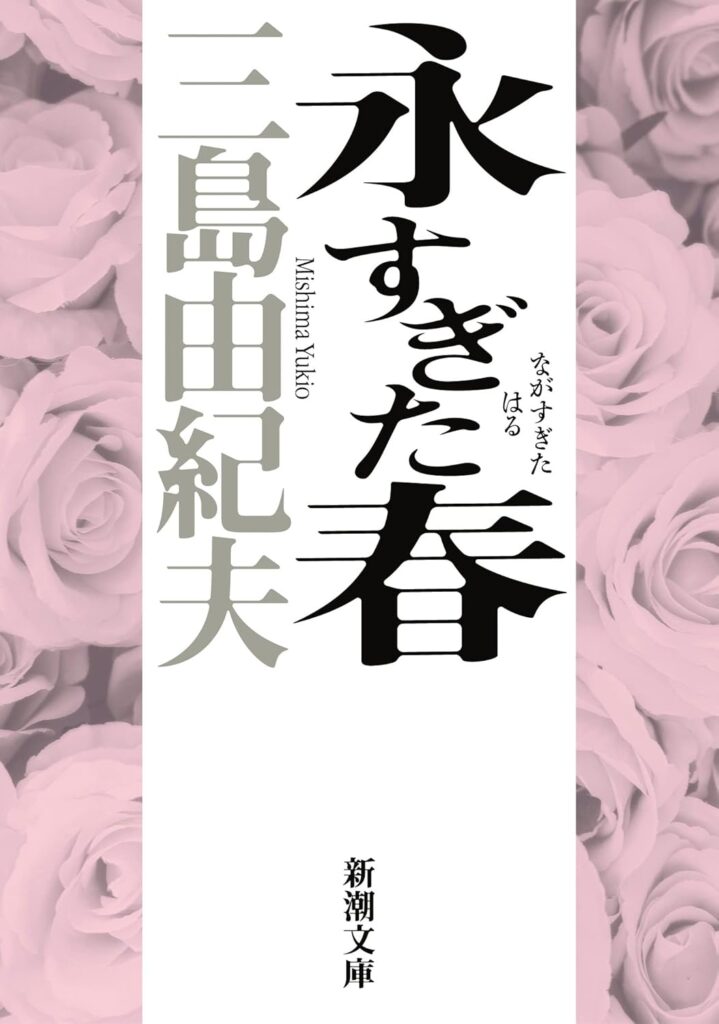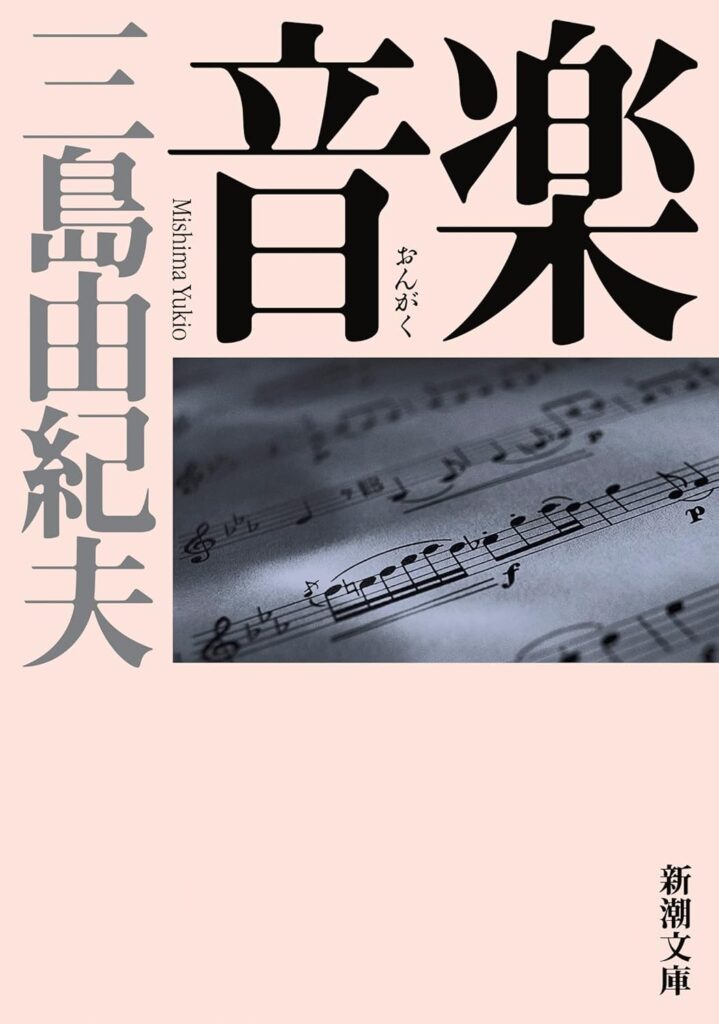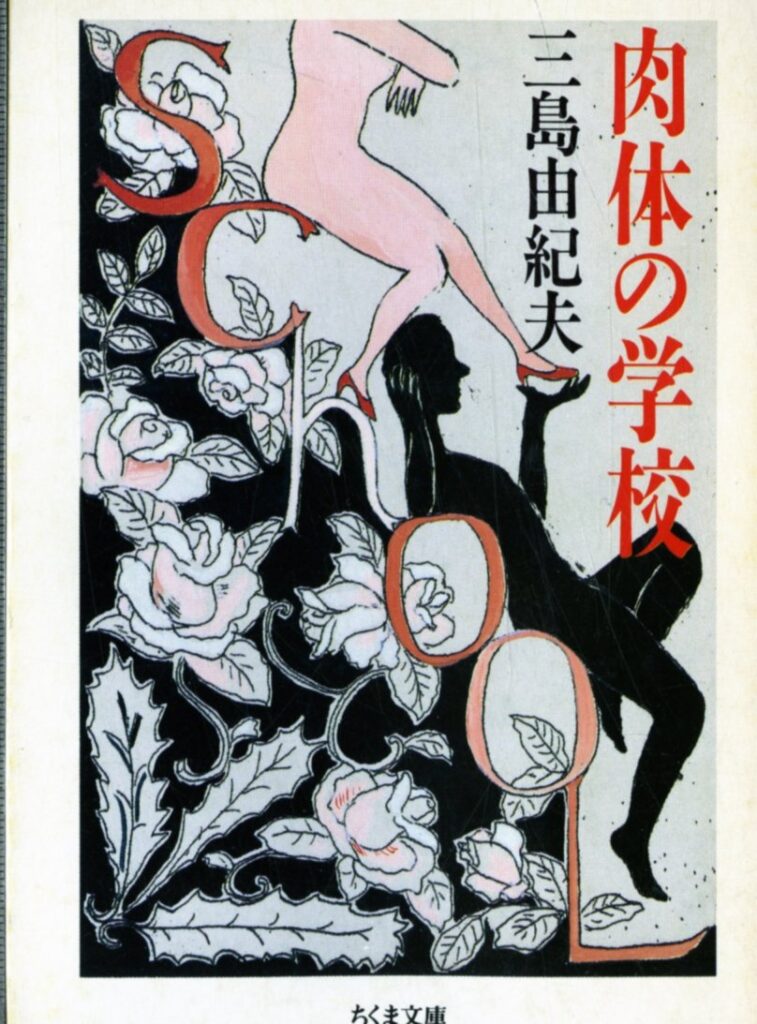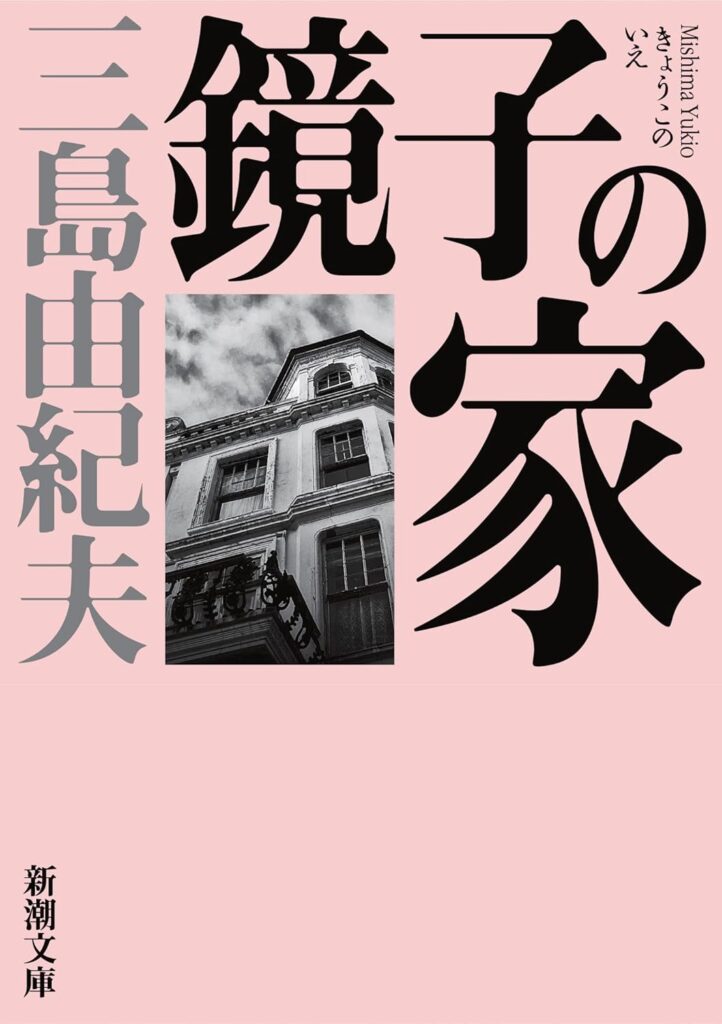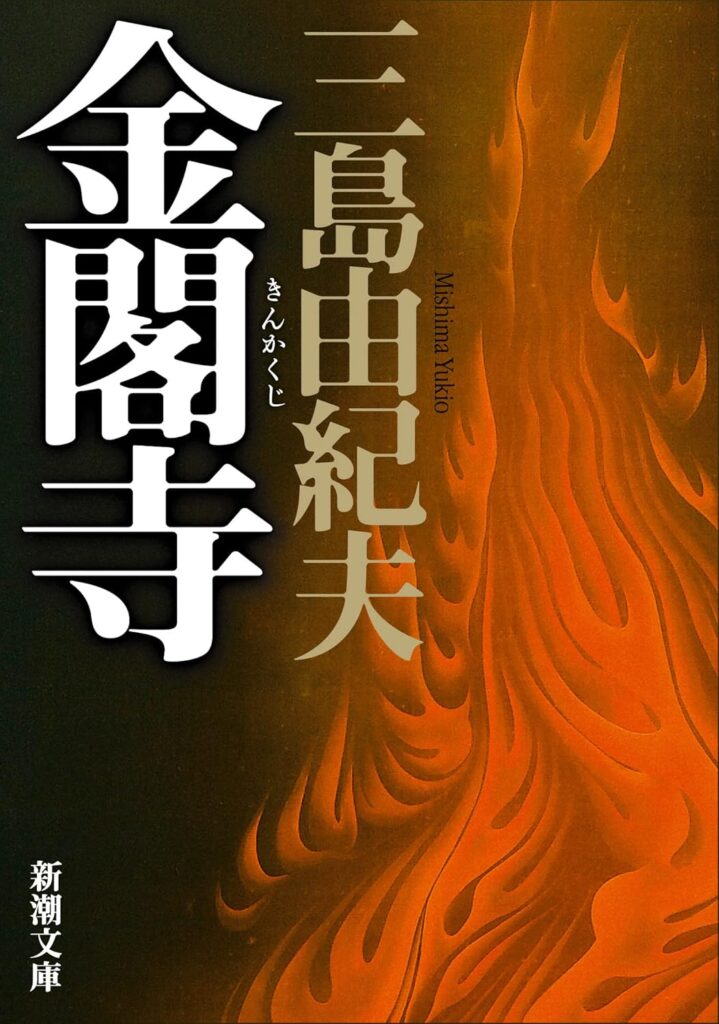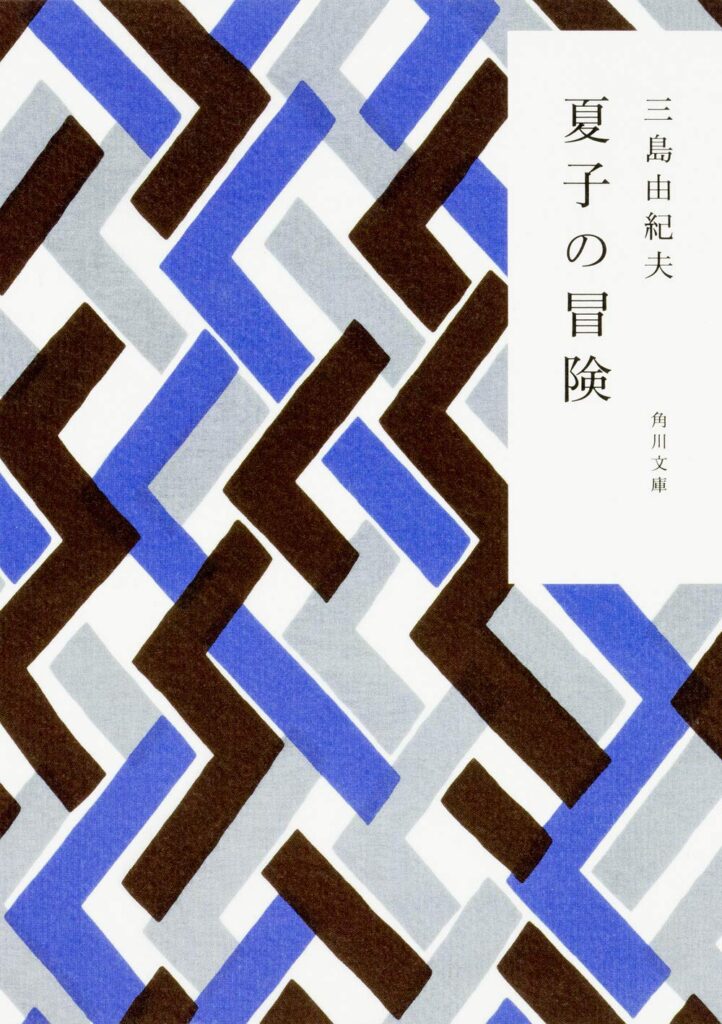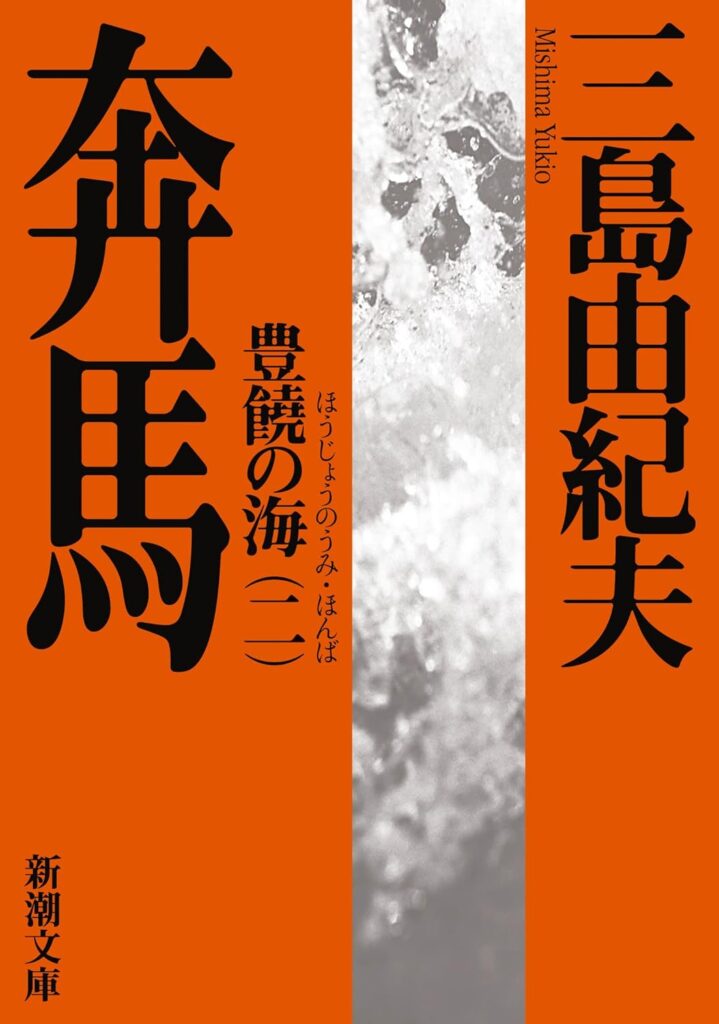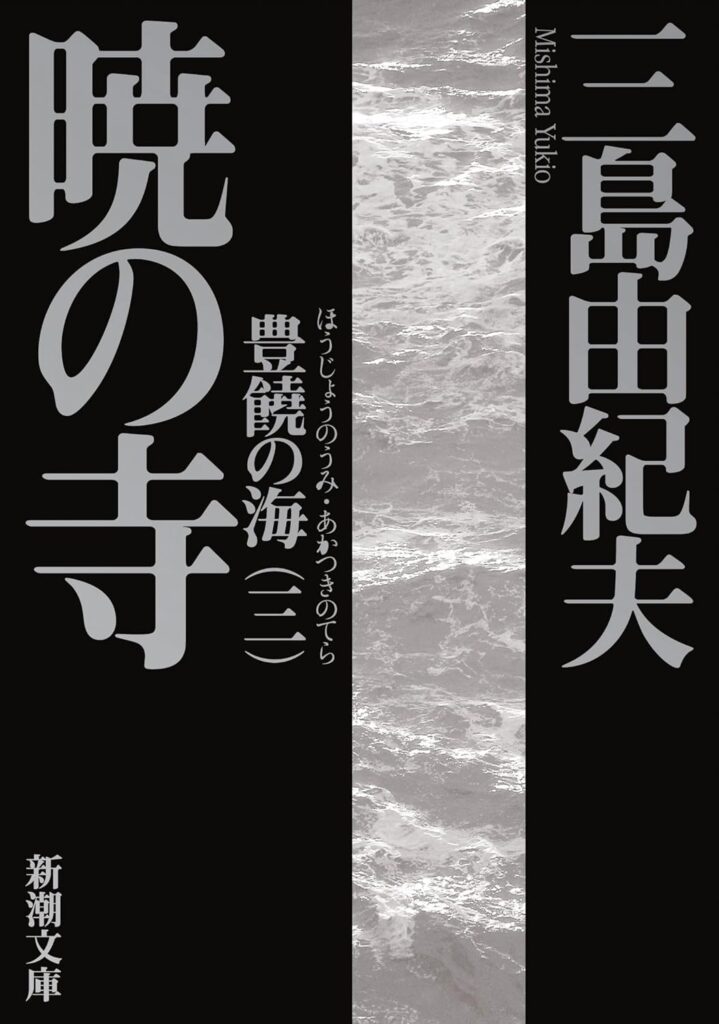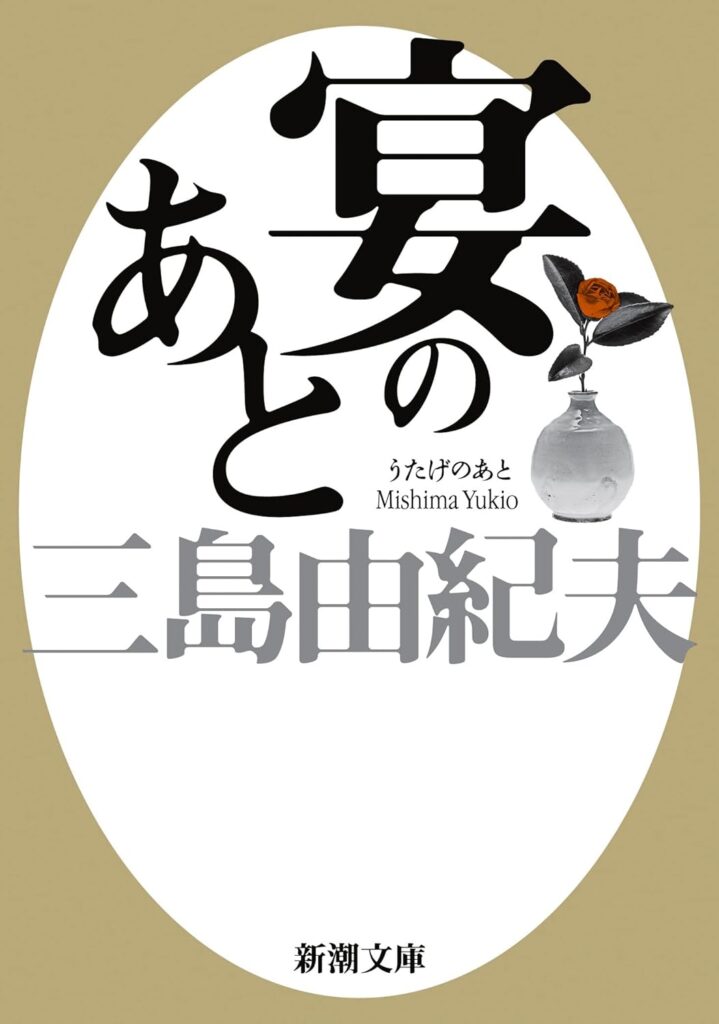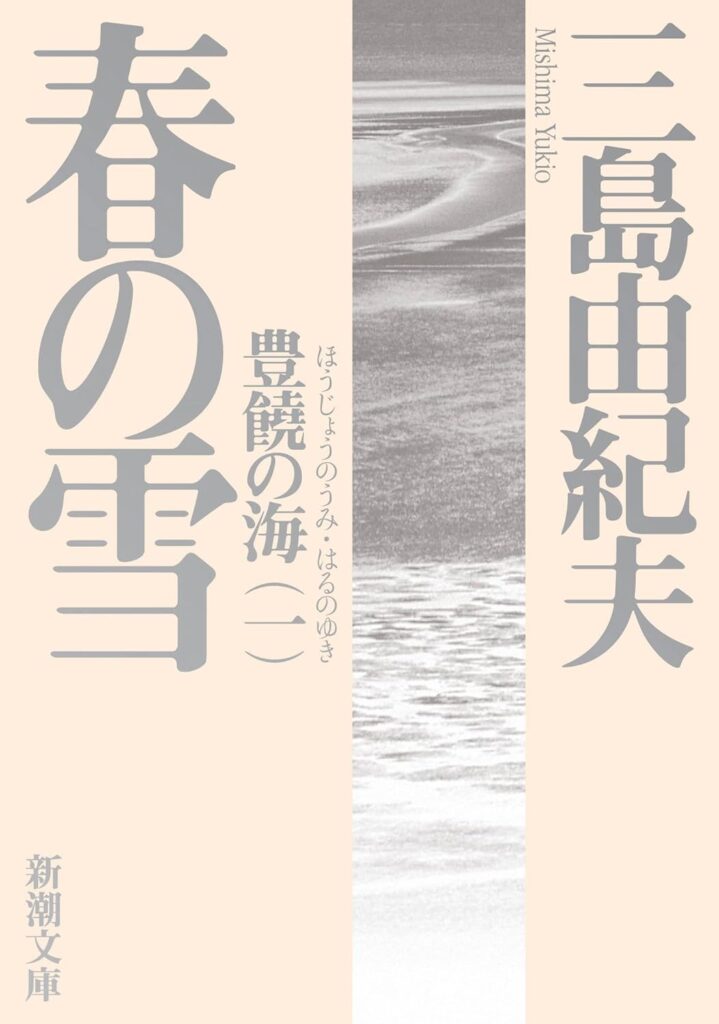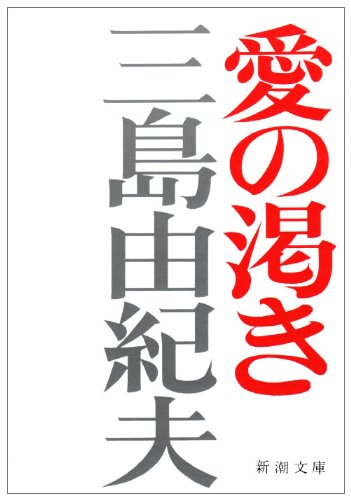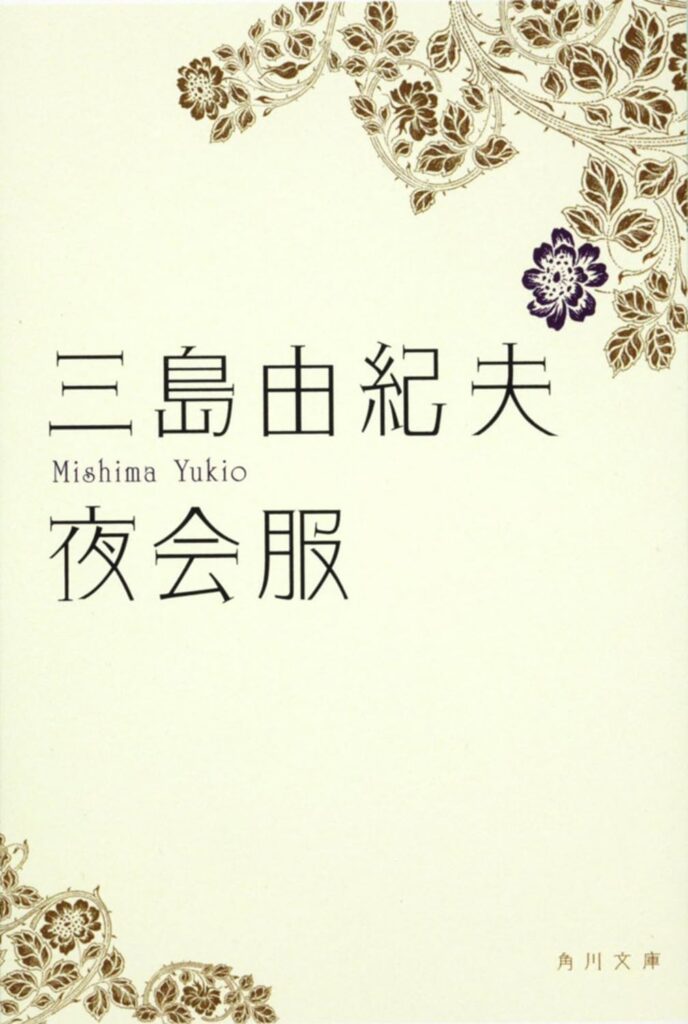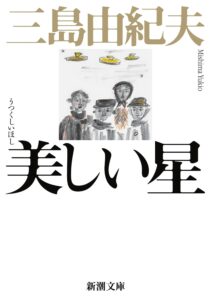 小説「美しい星」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「美しい星」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、一見すると平凡な一家が、ある日突然、自分たちはそれぞれ異なる星からやってきた宇宙人であると覚醒するところから始まります。地球が核戦争によって滅亡の危機に瀕していることを知り、それを救うという壮大な使命を帯びるのです。しかし、彼らの前には、同じく宇宙人でありながら地球の滅亡を望む者たちが立ちはだかります。
三島由紀夫氏の作品群の中でも、SF的要素を大胆に取り入れた異色の長編として知られています。発表されたのは1962年。東西冷戦が激化し、核の脅威が現実味を帯びていた時代です。そんな時代背景を色濃く反映しつつも、物語は単なる空想科学の枠を超え、人間存在の根源的な問いを私たちに投げかけてきます。
「美」とは何か、生きることの意味とは何か、そして「狂気」と「正気」の境界線はどこにあるのか。宇宙的スケールで展開される物語を通じて、三島氏ならではの美意識と哲学が色濃く映し出されています。この物語を読み解くことは、私たち自身の生き方を見つめ直すきっかけになるかもしれません。
この記事では、「美しい星」がどのような物語であるのか、その魅力と奥深さを、物語の結末に触れつつ、読み応えのある形で綴っていきたいと思います。初めてこの作品に触れる方も、再読を考えている方も、新たな発見をしていただけるのではないでしょうか。
小説「美しい星」のあらすじ
物語の舞台は、埼玉県飯能市に暮らす大杉家。父の重一郎、母の伊余子、息子の大学生・一雄、そして美しい娘・暁子。彼らはある日、それぞれがUFOとの遭遇体験を通じて、自分たちが地球人ではなく、重一郎は火星、伊余子は木星、一雄は水星、暁子は金星から来た宇宙人であるという自覚を持ちます。彼らの使命は、核戦争による人類の滅亡を防ぎ、地球を救うこと。この共通の目的のもと、大杉一家は団結します。
重一郎は「宇宙友朋会」なる団体を設立し、UFOの存在を訴え、核廃絶を呼びかける講演活動を開始します。美貌の持ち主である暁子は、その美しさを武器に、海外の指導者へ手紙を送るなど、独自の活動を展開。一方、現実主義者の一雄は、父のやり方に疑問を感じつつも、政治の力で世界を救おうと、ある代議士の秘書となり政界への道を歩み始めます。伊余子は、家族の活動を静かに見守り、支えるのでした。
しかし、彼らの前には同じように宇宙人としての覚醒を体験しながらも、全く異なる思想を持つ者たちが現れます。仙台に住む大学助教授の羽黒真澄とその仲間たちは、自らを白鳥座61番星系の惑星から来たと信じ、愚かな人類は核によって滅亡し、浄化されるべきだと考えていました。彼らは、大杉一家の活動を阻止しようと画策し始めます。
暁子は、自分と同じ金星人を名乗る魅力的な青年・竹宮と出会い、恋に落ちますが、彼に裏切られ、妊娠してしまうという悲劇に見舞われます。一雄もまた、師事していた代議士が実は羽黒の仲間であり、利用されていただけだったことを知り、理想と現実の狭間で苦悩します。大杉家には次々と暗い影が差し始めるのです。
やがて、地球の救済を掲げる重一郎と、地球の滅亡を企む羽黒は直接対決の時を迎えます。激しい舌戦が繰り広げられる中、重一郎は突然倒れてしまいます。診断の結果は末期の胃癌。自らの死期を悟った重一郎は、宇宙人としての使命感と、人間としての家族への愛情、そして死への恐怖の間で揺れ動きます。
最終的に、重一郎は人間としての限界を悟りつつも、宇宙人としての信念を貫こうとします。彼は病床を抜け出し、家族と共に最後のUFOを目撃するために丘へ向かいます。そして、彼らが見たものとは…。物語は、救済の確証も、完全な破滅もなく、ある種の静謐さと共に幕を閉じ、読者に深い問いを残すのです。
小説「美しい星」の長文感想(ネタバレあり)
三島由紀夫氏が遺した数々の作品の中で、「美しい星」はひときときらめきを放つ、しかしどこか異質な手触りの物語だと感じます。初めてこの本を手に取った時の衝撃は、今でも鮮明に覚えています。宇宙人として覚醒した家族が地球を救う、という、ともすれば荒唐無稽にも聞こえる設定。しかし、ページをめくるうちに、その奇抜な設定は三島氏ならではの重厚な思索と、絢爛たる言葉遣いによって、抗い難い魅力を持つ物語世界へと昇華されていくのです。
この物語の核心に触れるとき、まず考えさせられるのは「人間とは何か」という根源的な問いでしょう。主人公である大杉重一郎は、火星人としての使命感に燃え、人類の愚かさを嘆きつつも、その救済に身を捧げようとします。彼の対極に位置するのが、地球の滅亡こそが救済であると説く羽黒真澄です。羽黒の人間に対する徹底的な不信と断罪は、ある意味で非常に論理的であり、聞く者を引き込む力を持っています。この二人の対立軸を通じて、人間存在の矛盾や不条理、そしてそれでもなお捨てきれない愛おしさのようなものが浮かび上がってきます。
重一郎が最終的に羽黒に投げかける「気まぐれこそ人間の美しさだ」という言葉は、この物語の一つの到達点を示しているように思えます。論理や整合性だけでは測れない、非合理的な感情や衝動こそが人間を人間たらしめているのだ、と。これは、理知的であろうとしながらも情念に揺れ動く、三島氏自身の人間観の表れなのかもしれません。私たちは、完璧ではないからこそ、過ちを犯すからこそ、人間なのであり、そこにこそある種の「美」が宿るのかもしれない、という逆説的な救いです。
そして、「美」という観念もまた、この物語を読み解く上で欠かせない要素です。娘の暁子は金星人としての「美」を体現する存在として描かれます。彼女の圧倒的な美しさは、周囲を魅了し、時には破滅へと導く力すら持っています。しかし、その美しさは、彼女自身にとっても絶対的な幸福をもたらすものではありません。竹宮に裏切られ、未婚の母となる暁子の姿は、「美」の持つ残酷さや、それだけでは人間は救われないという厳しい現実を突きつけてきます。三島氏が生涯をかけて追求した「美」の観念が、この作品では宇宙的な視点と結びつき、より複雑な様相を呈しているように感じられます。
SFというジャンルを用いたことも、この作品の特異性を際立たせています。1960年代初頭、UFOや宇宙人への関心が高まっていた時代背景も無視できませんが、三島氏が描くSFは、科学的な考証を重視するタイプのものではなく、あくまで人間存在や社会を映し出すための鏡、あるいは思想を飛翔させるための装置として機能しています。宇宙人という設定は、日常から切り離された極限状況を作り出し、そこで人間がいかに振る舞うのか、何を信じ、何に絶望するのかを鮮烈に描き出すことを可能にしています。
大杉家の人々が本当に宇宙人だったのか、それとも集団的な妄想に取り憑かれていただけなのか。この問いは、読み手によって解釈が分かれるところでしょう。しかし、そのどちらであったとしても、彼らが抱える苦悩や葛藤、そして互いを思いやる心は、紛れもなく人間的なものです。伊余子の静かな強さ、一雄の現実と理想の間での揺らぎ、そして重一郎の使命感と父性の間で引き裂かれる姿。彼らは宇宙人であると同時に、どこにでもいるような、弱さを抱えた家族でもあるのです。この二重性が、物語に深みを与えています。
特に印象深いのは、伊余子の存在です。彼女は木星人として覚醒したとされていますが、他の家族ほど熱狂的ではなく、どこか達観したような態度で事態の推移を見守ります。彼女の言葉は少なく、行動も目立たないかもしれませんが、その静かな存在感が、崩壊しかねない家族を繋ぎ止めているようにも見えます。彼女の覚醒は本物だったのか、それとも家族を思うあまりに同調したのか。その曖昧さが、かえって彼女の人間的な深さを感じさせます。
羽黒真澄というキャラクターもまた、強烈な印象を残します。彼のペシミズムとニヒリズムは、現代社会にも通じるものがあります。情報が氾濫し、価値観が多様化する中で、何が正義で何が悪なのかを見失い、全てが無意味に思えてしまう。そんな虚無感に取り憑かれた人々の姿を、羽黒は先取りしていたのかもしれません。彼の論理は、重一郎の理想論よりも、ある意味では現実の冷酷な一面を的確に捉えているとも言えます。だからこそ、重一郎と羽黒の対決は、単なる善悪の戦いではなく、異なる世界観を持つ者同士の、魂のぶつかり合いとして胸に迫るのです。
物語の終盤、重一郎が末期の癌に侵されていることが判明する場面は、宇宙的なスケールの物語が一気に個人的な、そして肉体的な次元へと引き戻される瞬間です。宇宙の救済という壮大な使命も、一個人の死という厳粛な事実の前では、その意味合いを変容させざるを得ません。「宇宙人として死ぬべきか、人間として死ぬべきか」。この重一郎の苦悩は、私たち自身の生と死に対する向き合い方を問うているようです。
そして、最後の場面。病身をおして家族と共にUFOを目撃しようとする重一郎。彼らが丘の上で目にする光景は、果たして本物のUFOだったのか、それとも彼らの願望が見せた幻だったのか。三島氏の筆致は、ここでも断定的な答えを与えません。ただ、そこにはある種の荘厳さと、悲劇的なまでの美しさが漂っています。それは、絶望の中に見出される一条の光のようでもあり、あるいは、壮大な自己欺瞞の完成形とも解釈できるかもしれません。この多義性こそが、「美しい星」が長く読み継がれる理由の一つなのでしょう。
この作品を読むたびに、新たな発見があります。それは、私自身の年齢や経験によって、物語の響き方が変わってくるからかもしれません。若い頃には、大杉一家の特異な使命感や、暁子の悲劇的な運命に心を揺さぶられました。しかし、時を経て再読すると、むしろ伊余子の静かな受容や、一雄の現実的な葛藤、そして重一郎の人間的な弱さにこそ、より深く共感するようになりました。
三島由紀夫氏の文体は、しばしば華麗で装飾的と評されますが、「美しい星」においては、その文体がSF的な設定と奇妙なほど調和し、独特の世界観を構築しています。観念的な会話や、登場人物たちの内面描写は、時に難解に感じられるかもしれませんが、その言葉の一つ一つには、作者の鋭敏な感性と深い洞察が込められています。
「美しい星」は、単なるエンターテイメントとして消費されるべき作品ではありません。それは、私たちに「生きる」ということを、そして「信じる」ということを、根本から問い直させる力を持った、稀有な文学作品です。核の脅威が再び現実のものとして語られる現代において、この物語が持つメッセージは、より一層切実な響きを帯びてくるのではないでしょうか。
人間は愚かで、過ちを繰り返し、自ら滅亡の道を歩んでいるのかもしれません。しかし、それでもなお、この不完全で、矛盾に満ちた存在の中に、救いようのないほどの「美しさ」を見出そうとした三島由紀夫氏のまなざし。それを感じ取ることができたとき、「美しい星」は私たちにとって、忘れられない一冊となるはずです。この物語は、私たち自身の心の中にある「美しい星」を探す旅へと誘ってくれるのです。
最後に、この物語の「救い」について考えてみたいと思います。大杉家は地球を救えたのか。明確な答えはありません。しかし、彼らが信じ、行動し、苦悩した軌跡そのものに、ある種の救済の形があったのではないかと感じます。結果がどうであれ、信じるもののために生きるという人間の姿は、それ自体が尊いものです。そして、家族が最後に共にUFO(かもしれないもの)を目撃するシーンは、たとえそれが幻想であったとしても、彼らにとっては一つの到達点であり、絆の証だったのではないでしょうか。そう信じたい、と思わせる余韻が、この物語にはあります。
まとめ
三島由紀夫氏の「美しい星」は、宇宙人として覚醒した一家が地球の危機に立ち向かうというSF的な設定の中に、人間存在の根源的な問いを織り込んだ、深遠な物語です。発表当時の冷戦下の世相を反映しつつ、核戦争の脅威や人類の未来といったテーマを扱いながらも、その射程は現代にも通じる普遍性を備えています。
この物語は、主人公・大杉重一郎とその家族、そして彼らと対立する羽黒真澄らを通して、「美とは何か」「人間とは何か」「信じるとは何か」といった問いを読者に投げかけます。登場人物たちは、宇宙人としての使命感と人間的な感情の間で揺れ動き、苦悩し、それぞれの形で答えを見出そうとします。その姿は、時に滑稽で、時に痛ましく、そしてどこまでも人間的です。
SFという枠組みを用いながらも、三島氏特有の華麗な文体と哲学的な思索が融合し、他に類を見ない独特な文学世界を創り上げています。結末の解釈は読者に委ねられており、それゆえに何度でも読み返すたびに新たな発見と感動を与えてくれるでしょう。「美しい星」は、私たち自身の内なる宇宙を見つめ、生きることの意味を深く考えさせてくれる、まさしく「美しい」一冊と言えるでしょう。
もしあなたが、日常に埋もれがちな根源的な問いと向き合いたいと願うなら、あるいは文学の持つ豊饒な世界に浸りたいと考えるなら、この「美しい星」を手に取ってみることをお勧めします。きっと、あなたの心に深く刻まれる体験となるはずです。