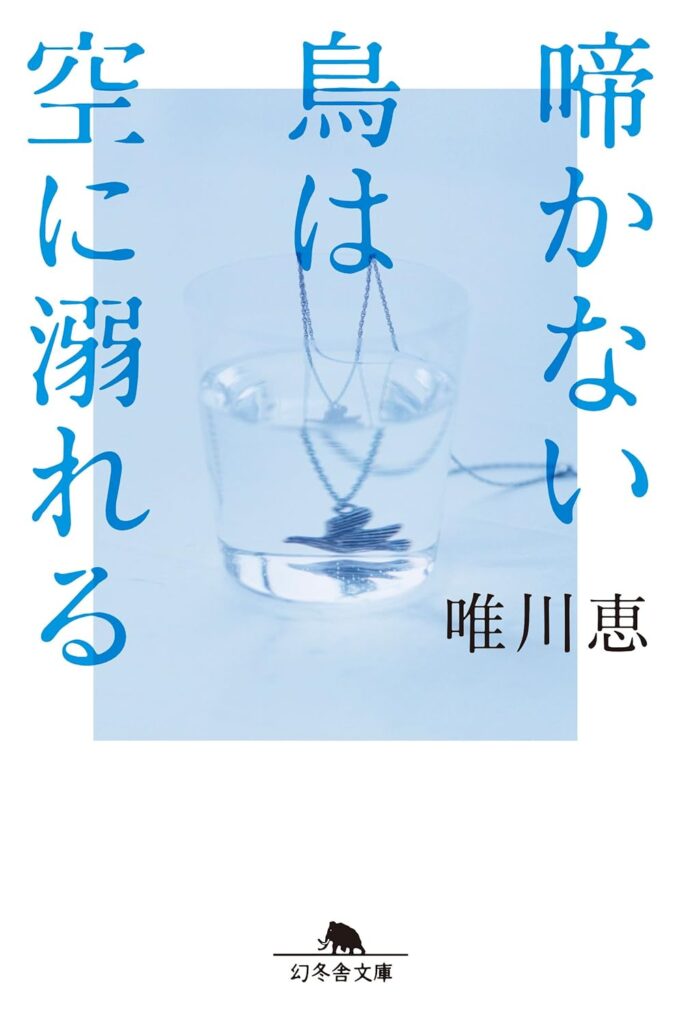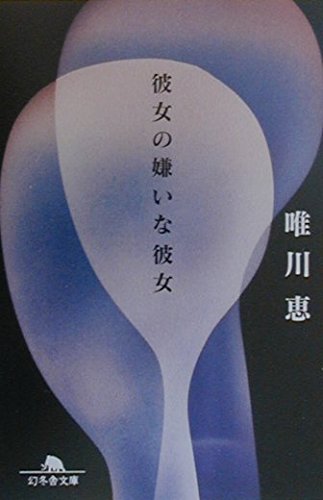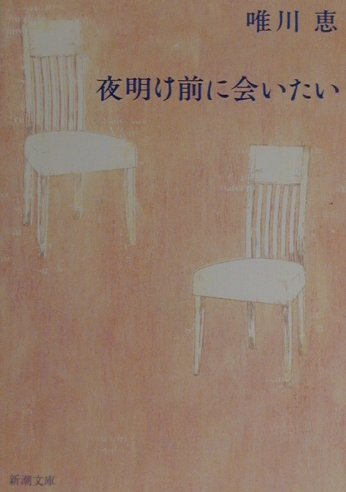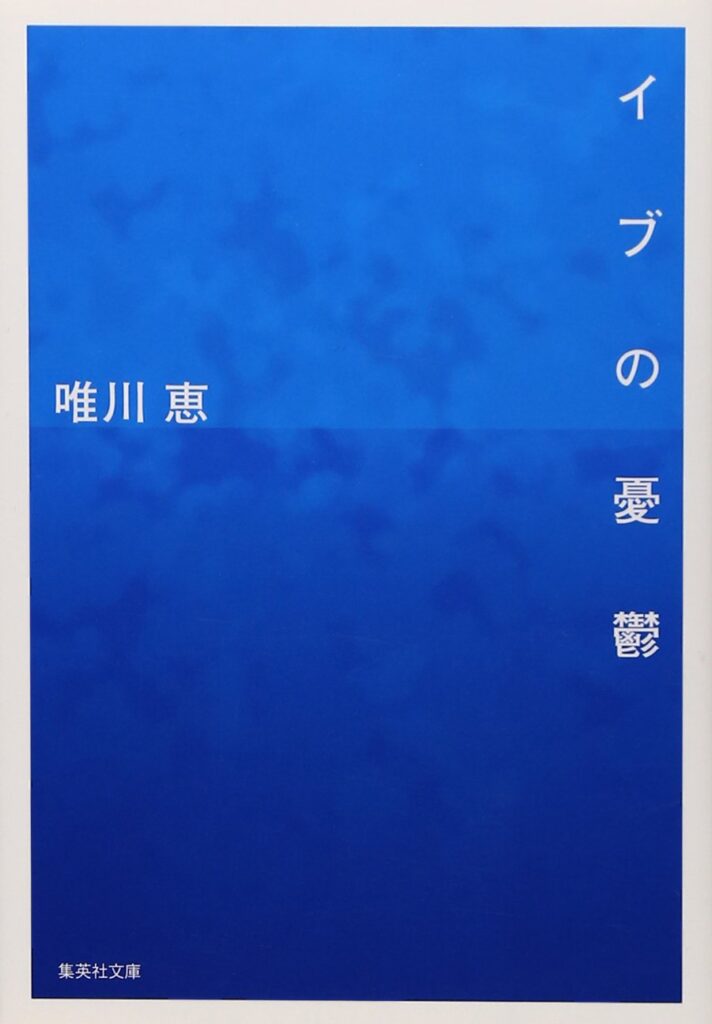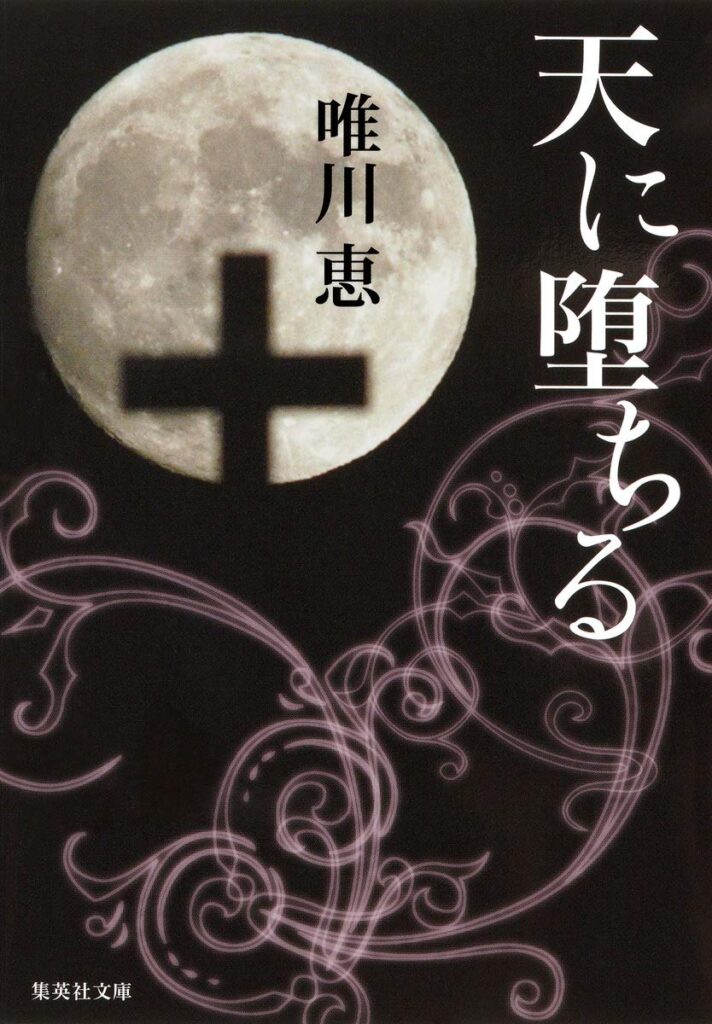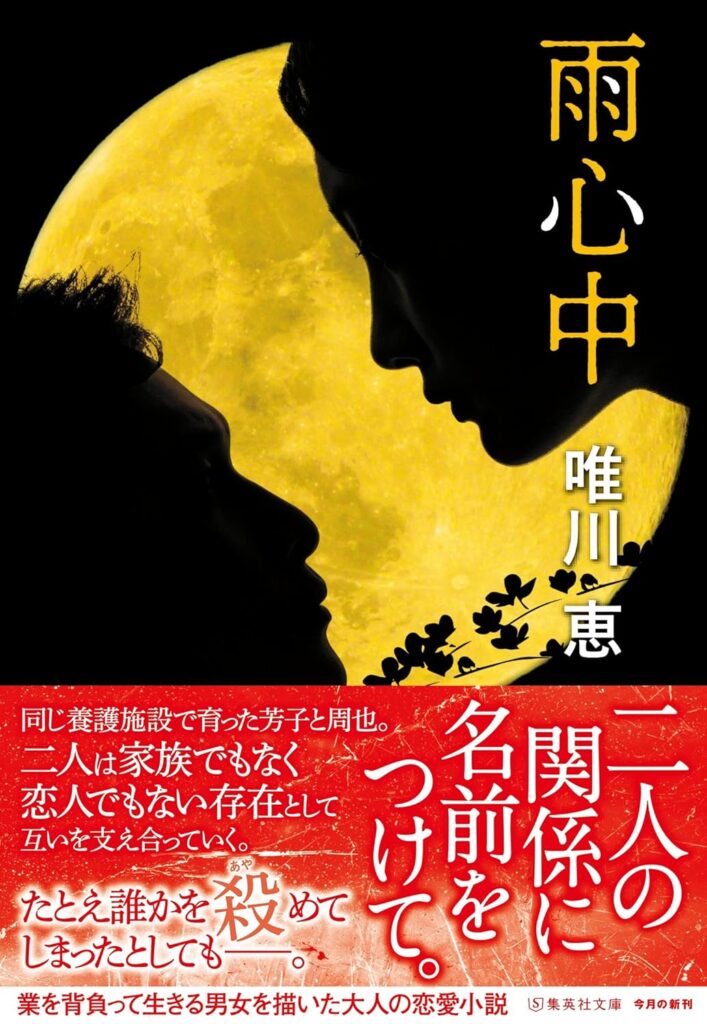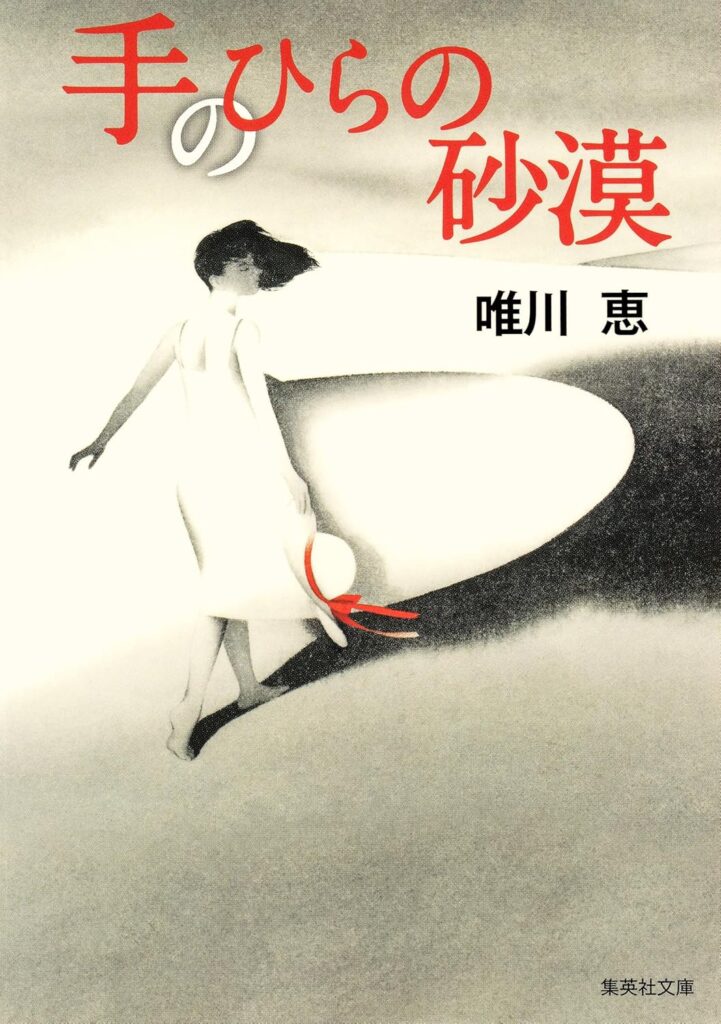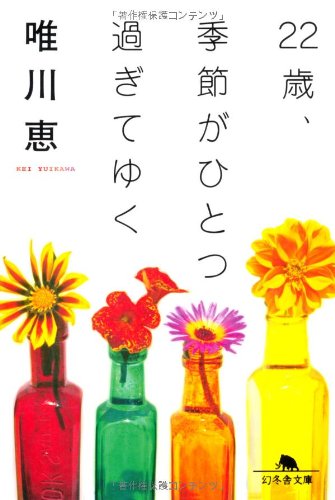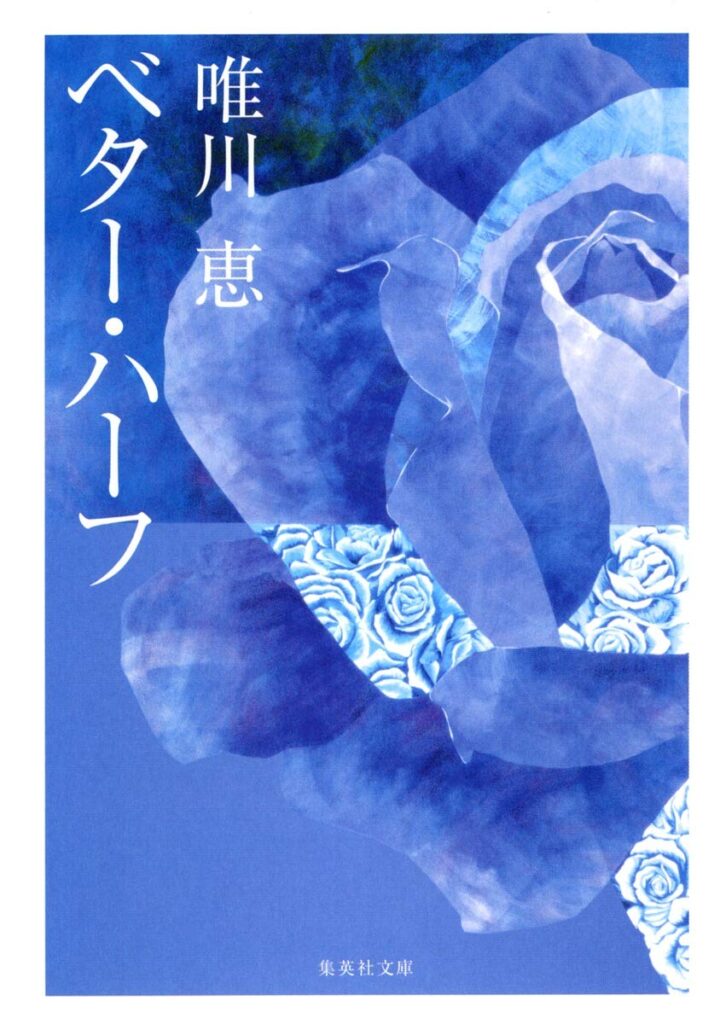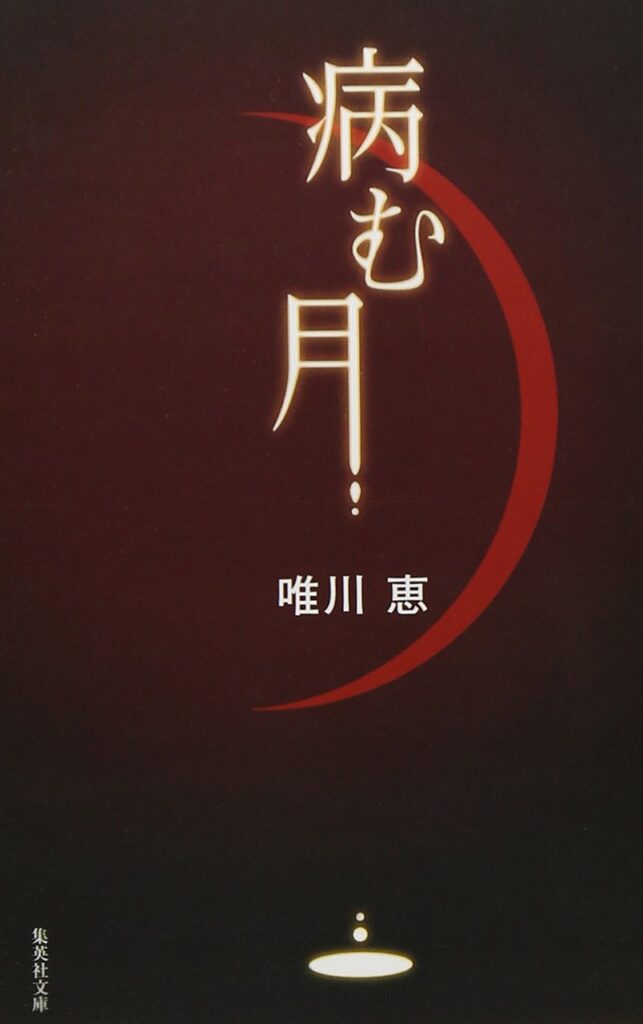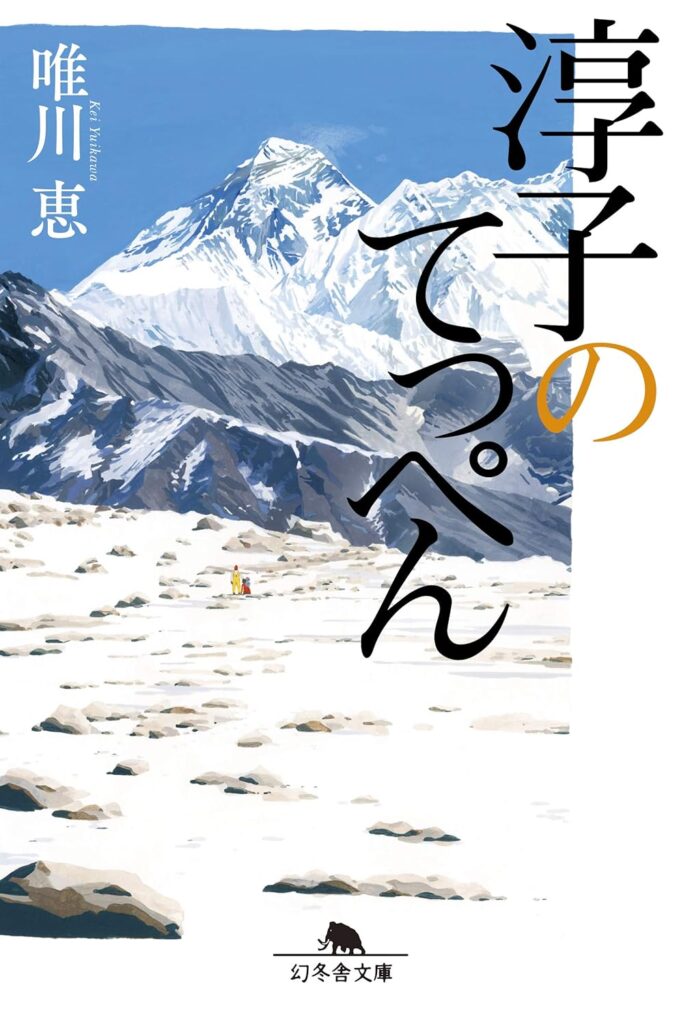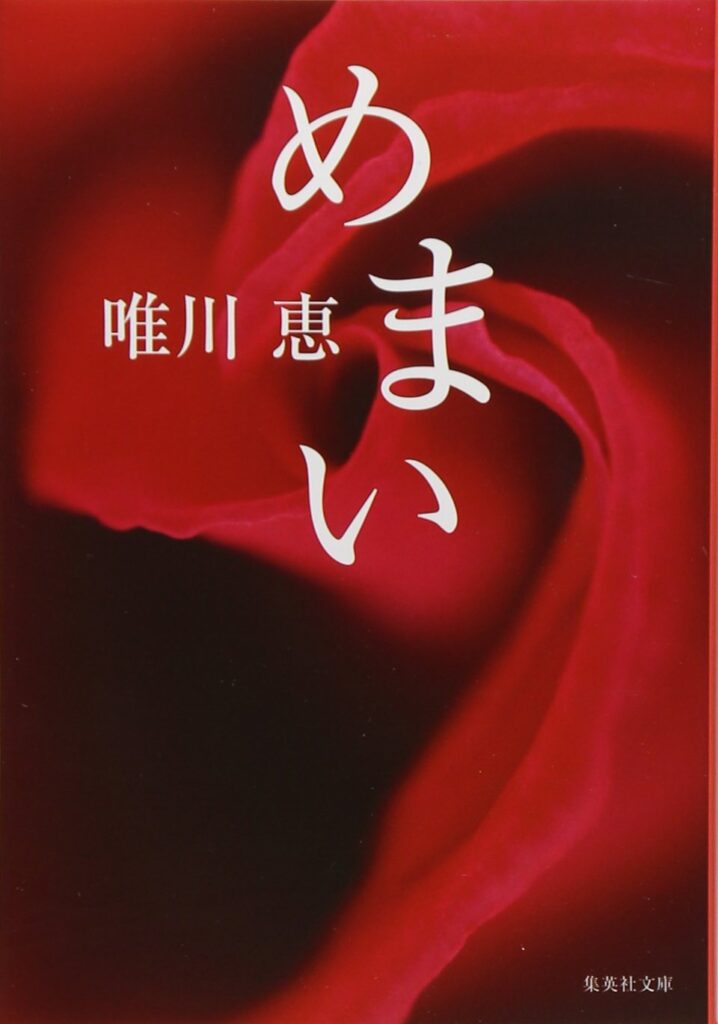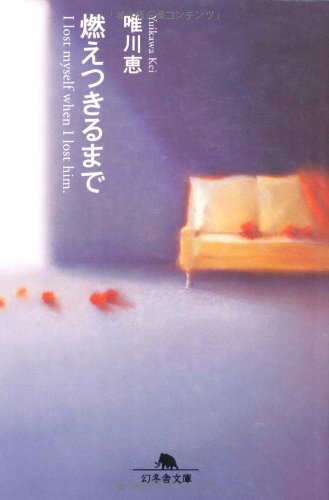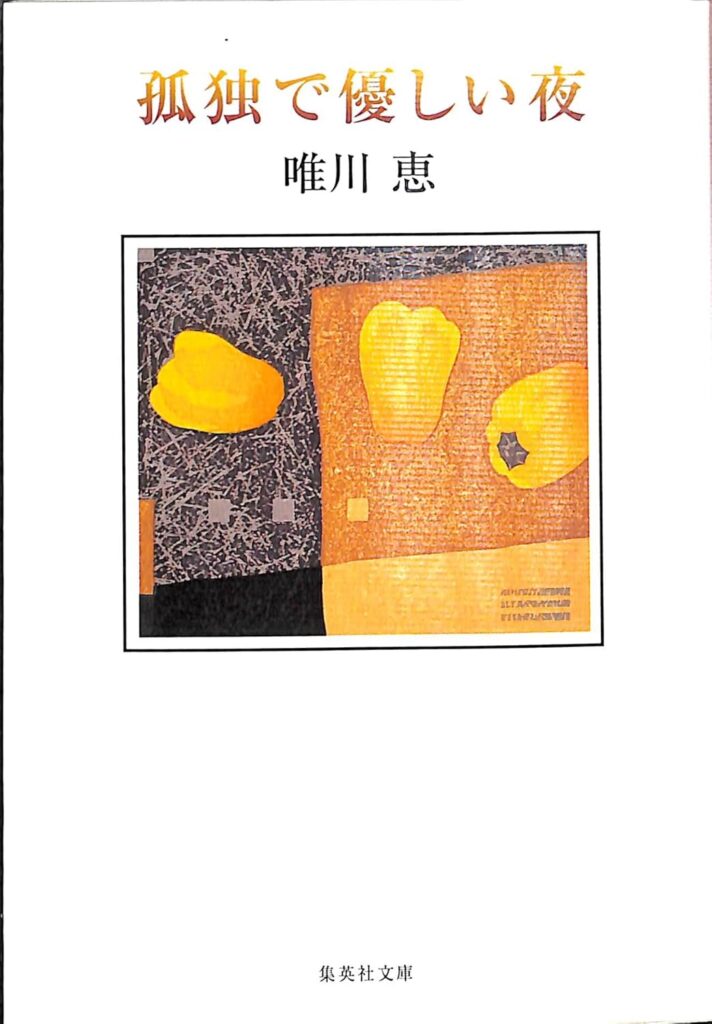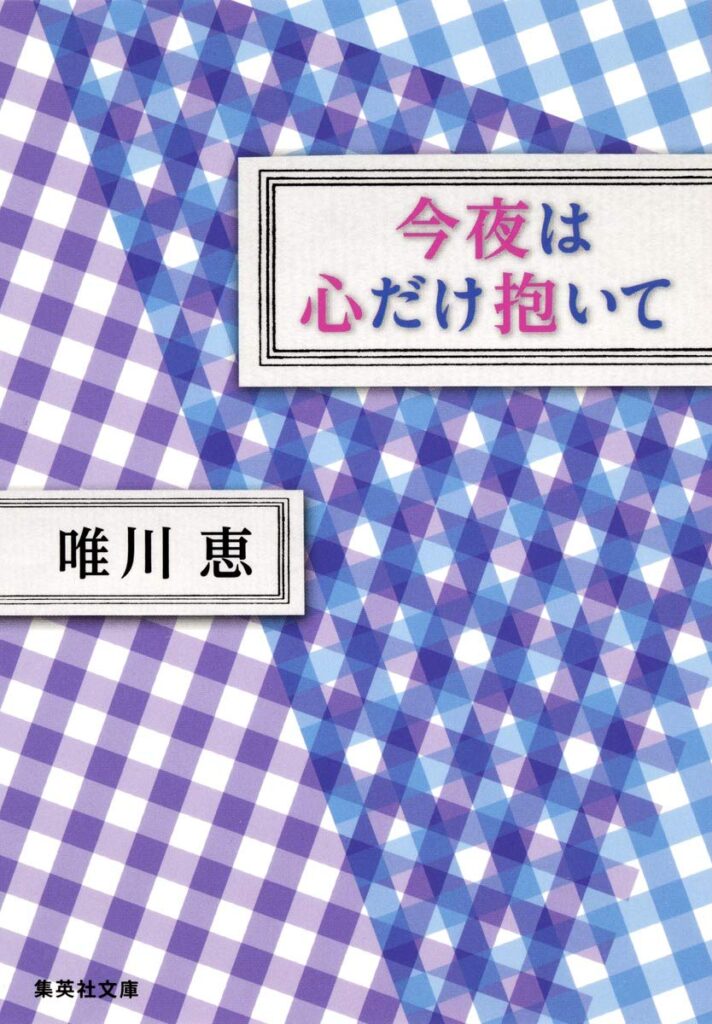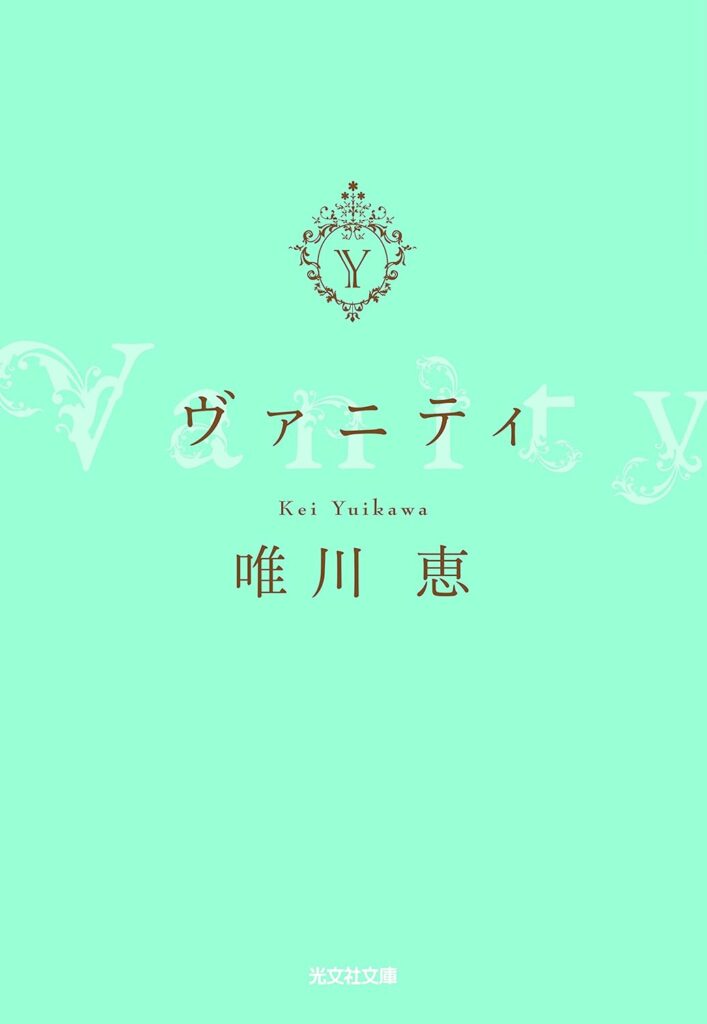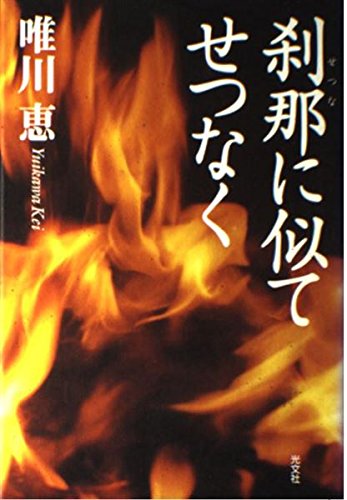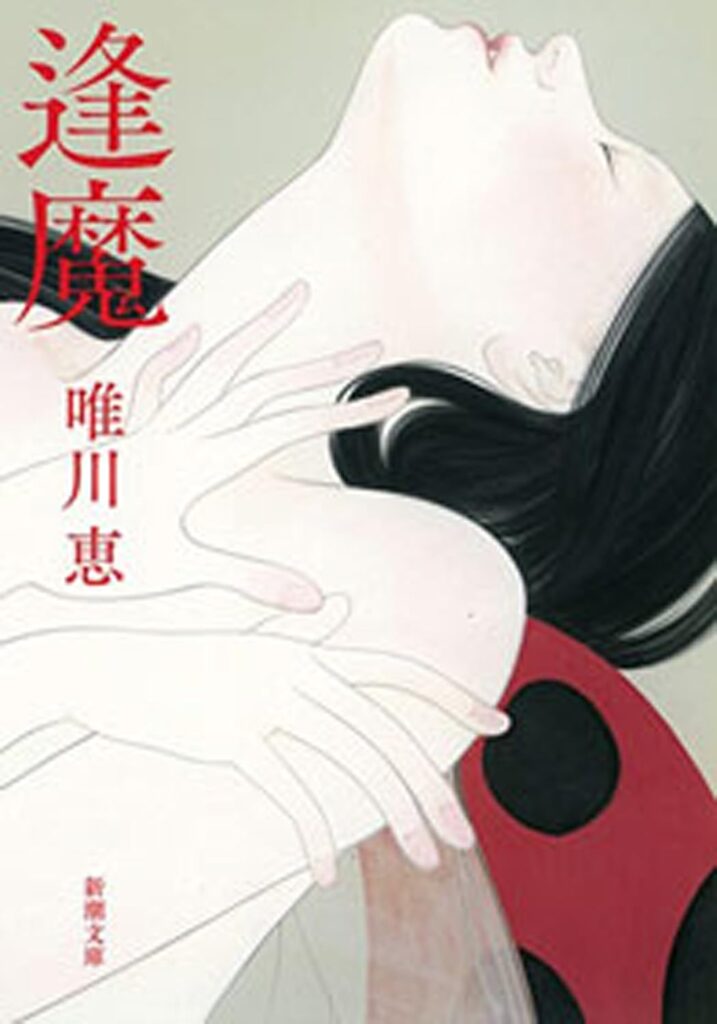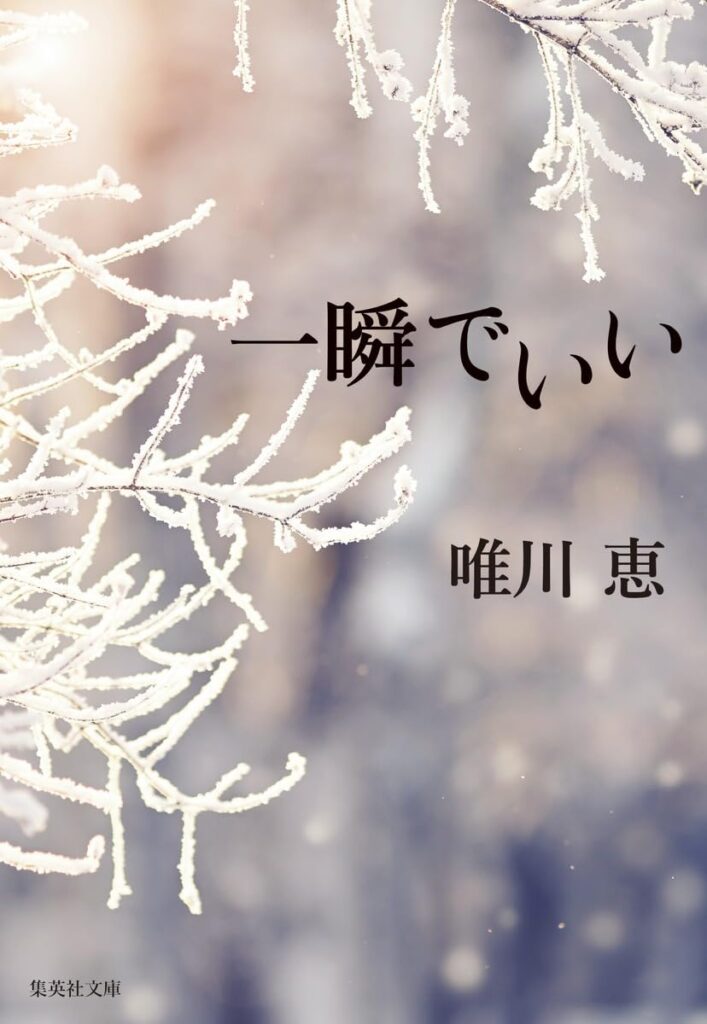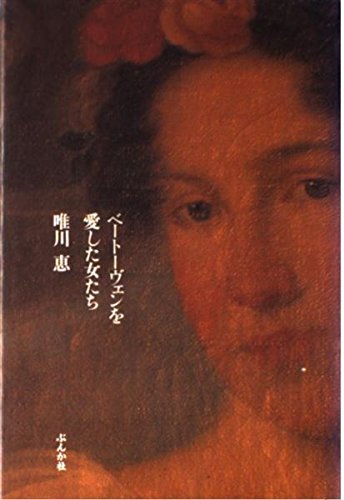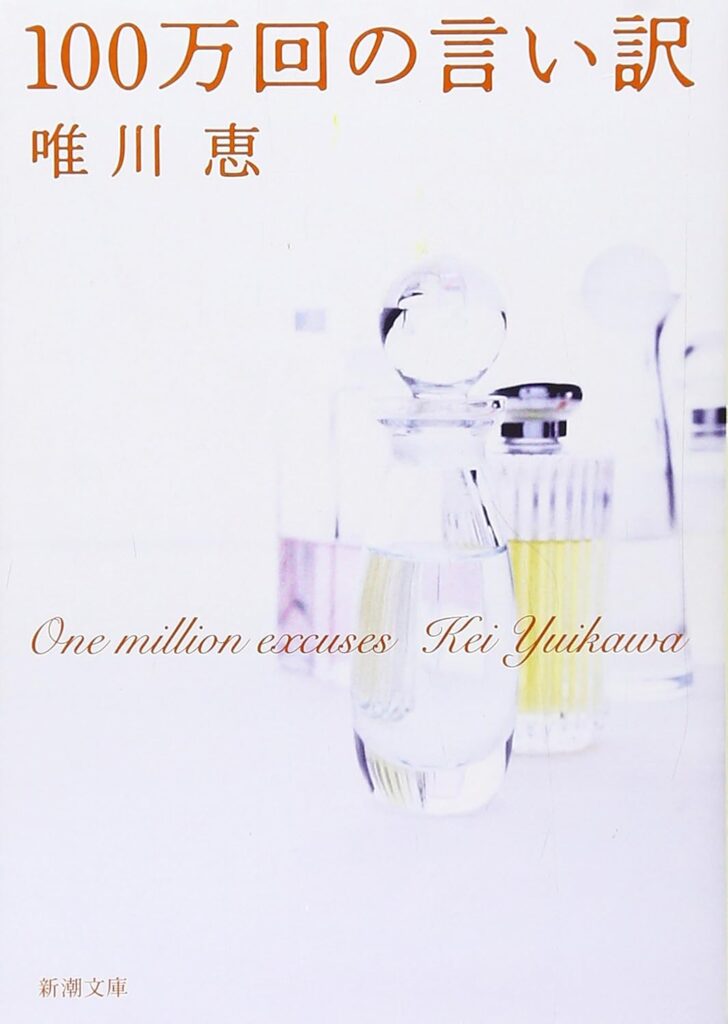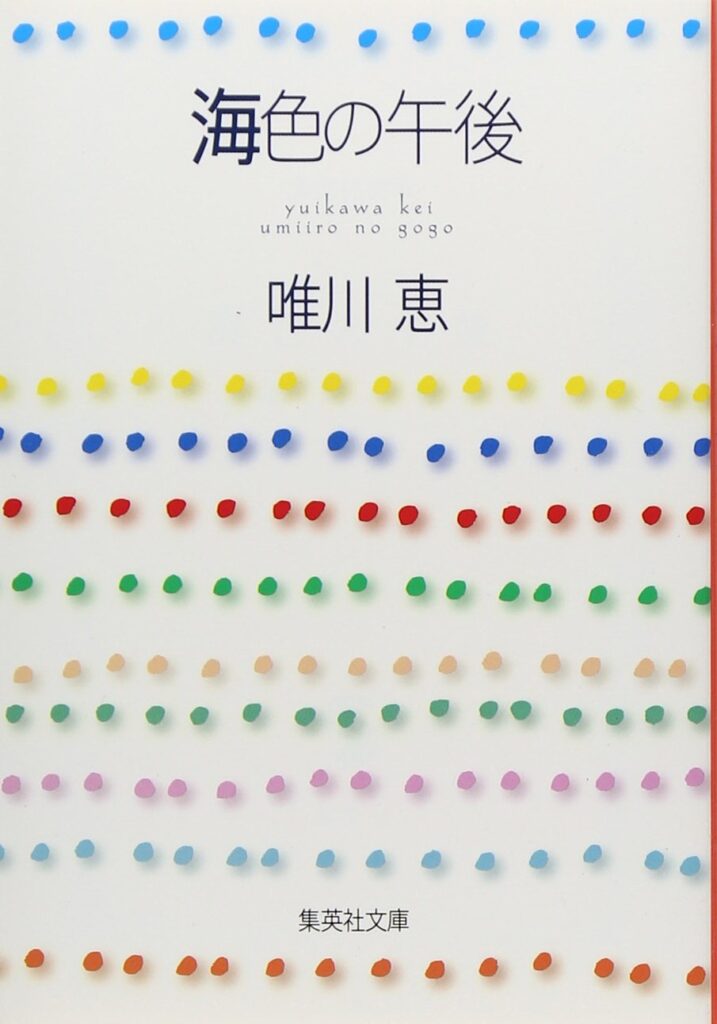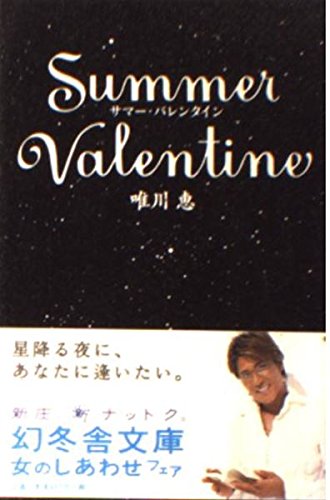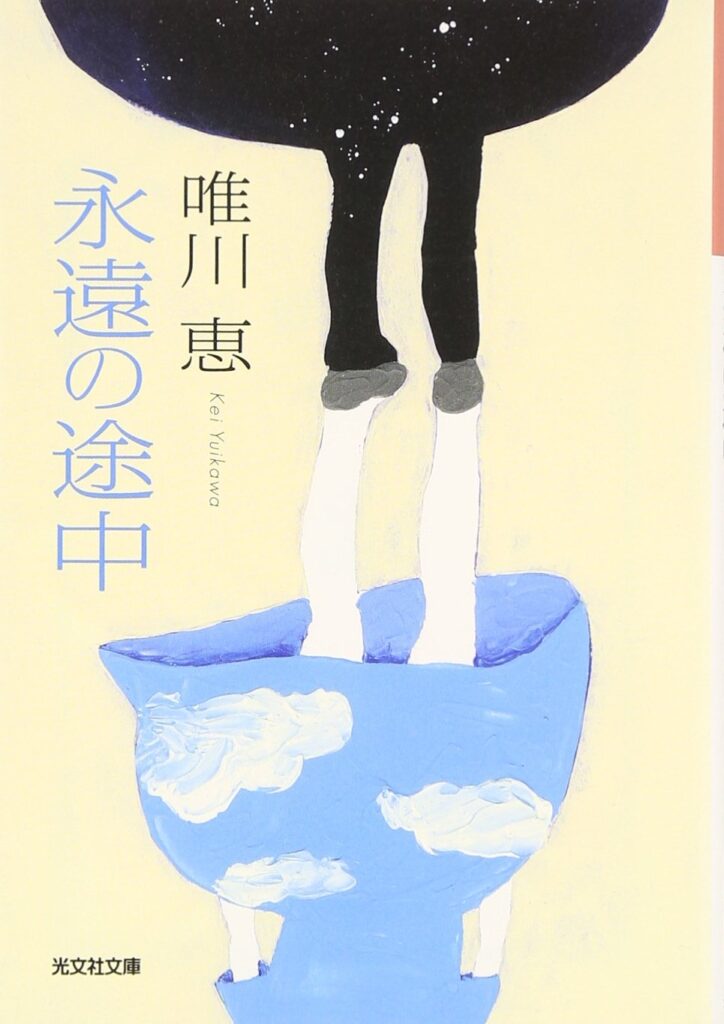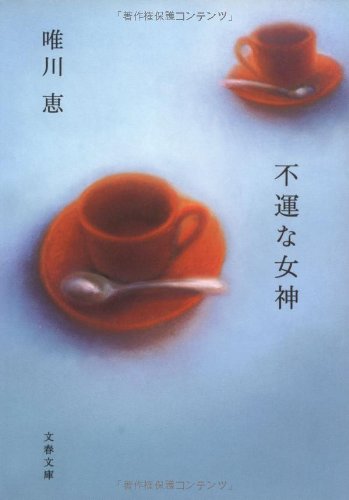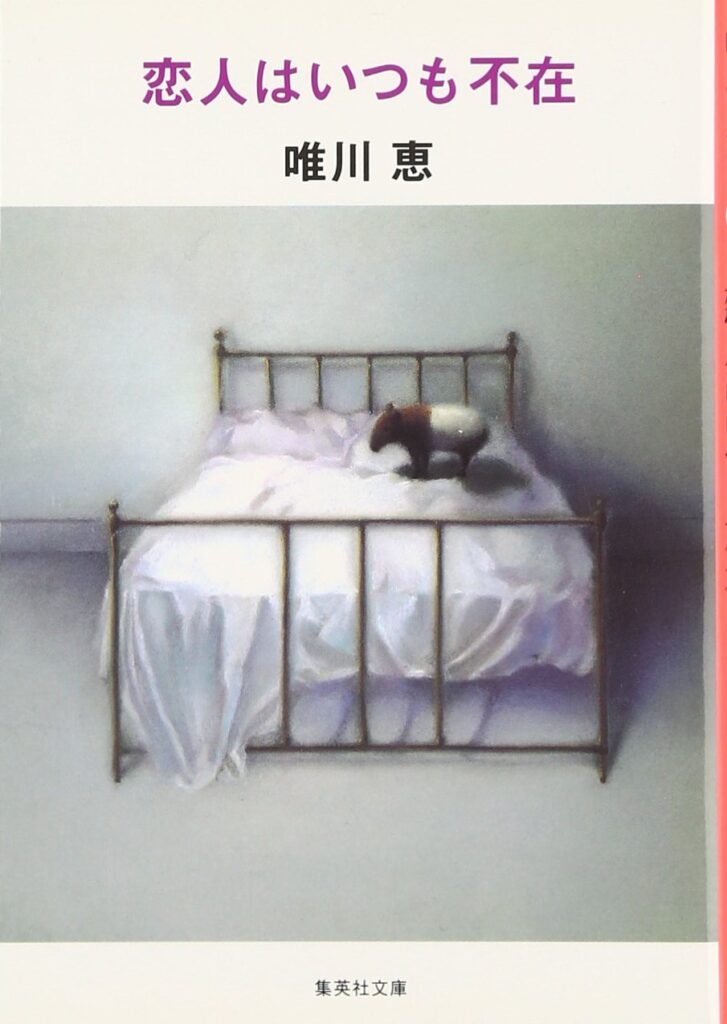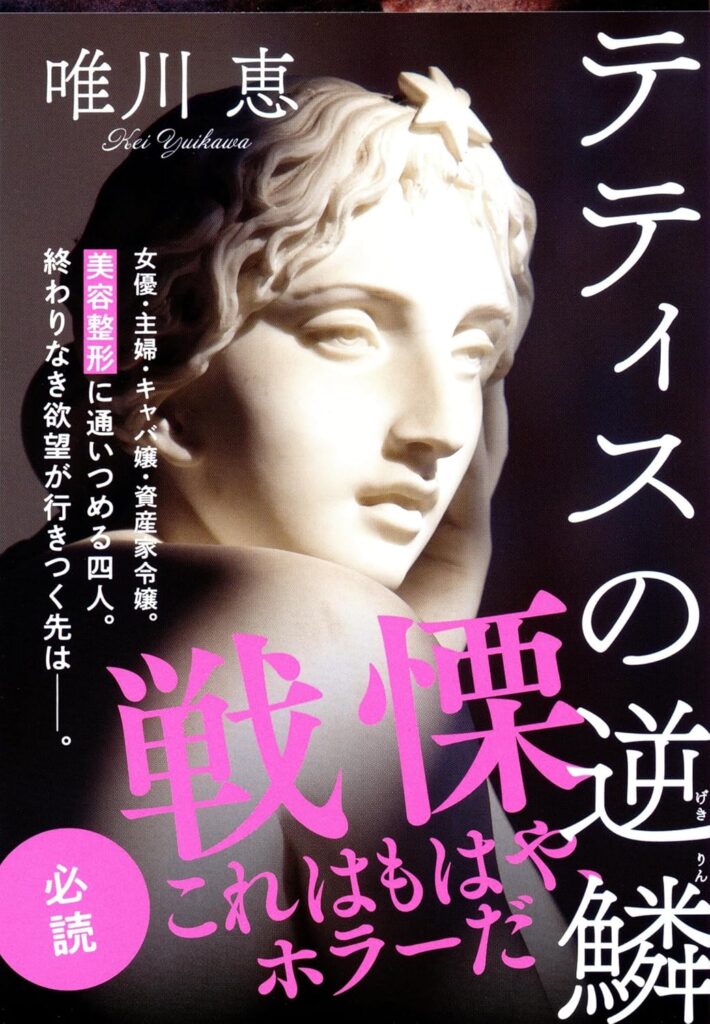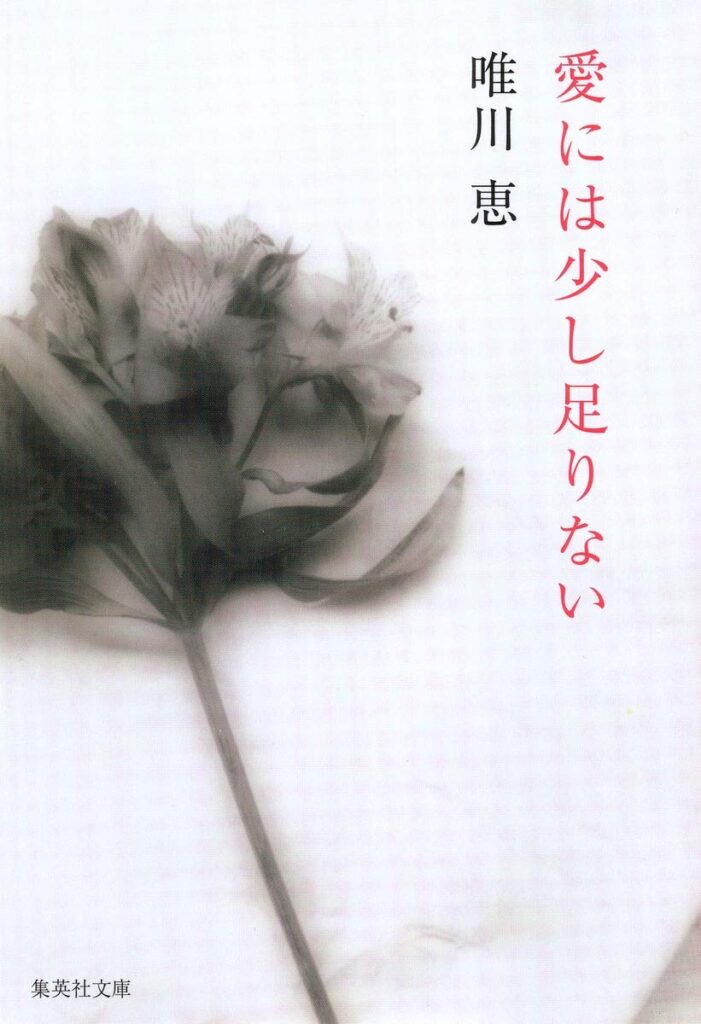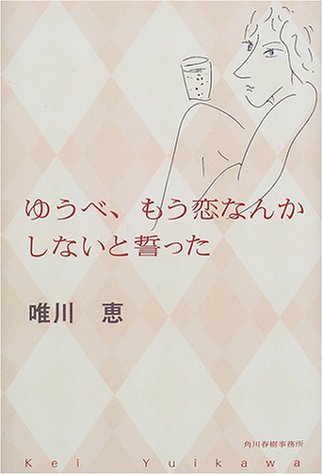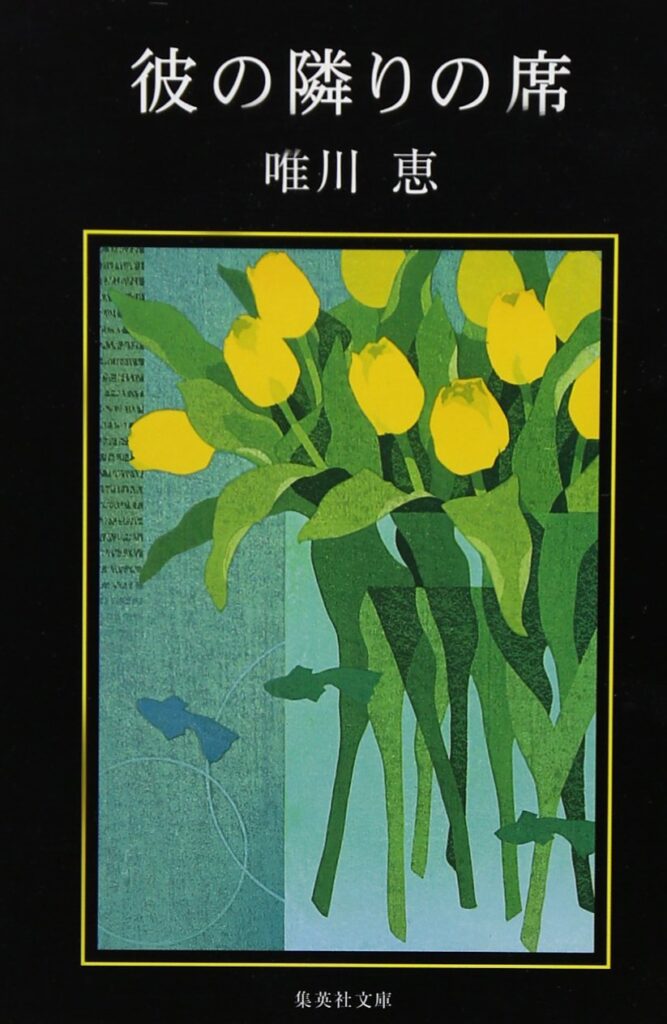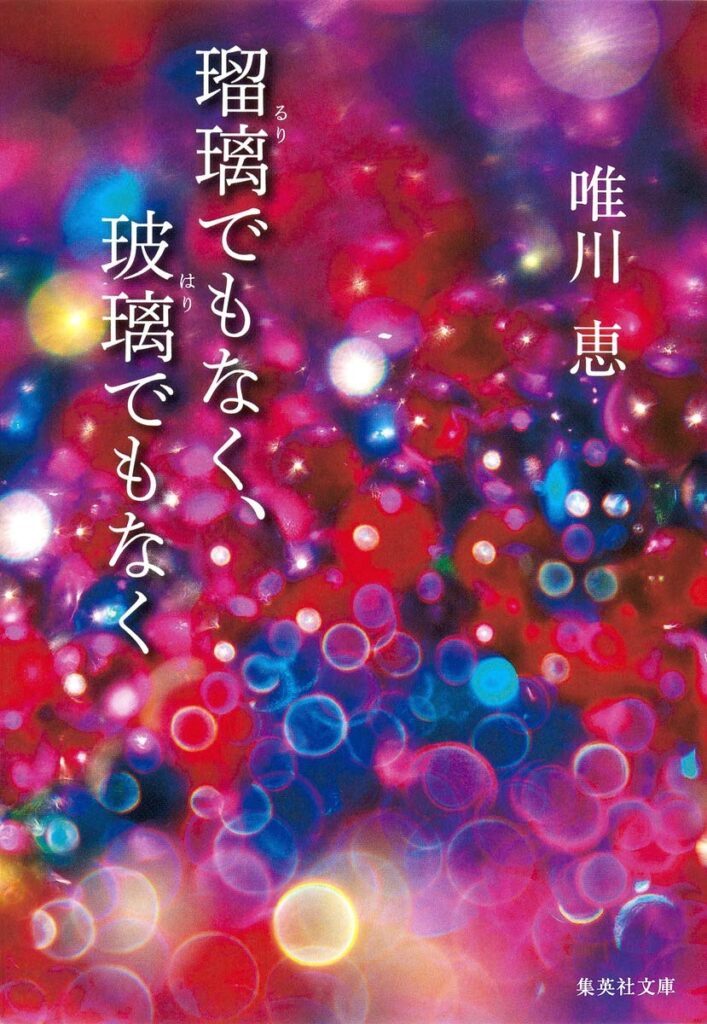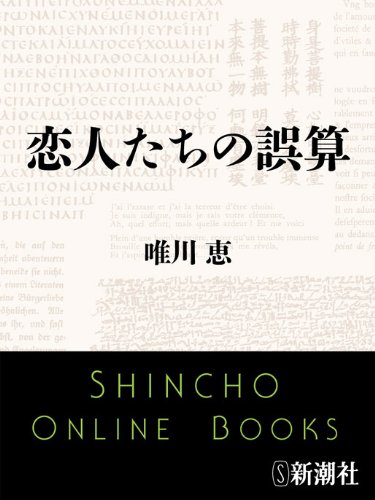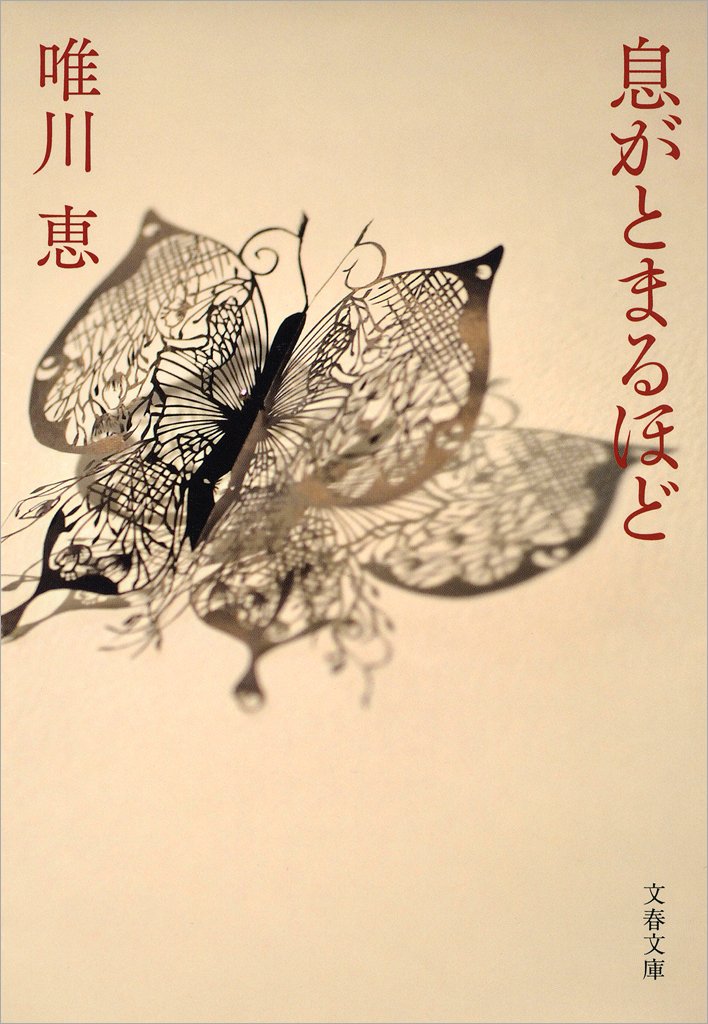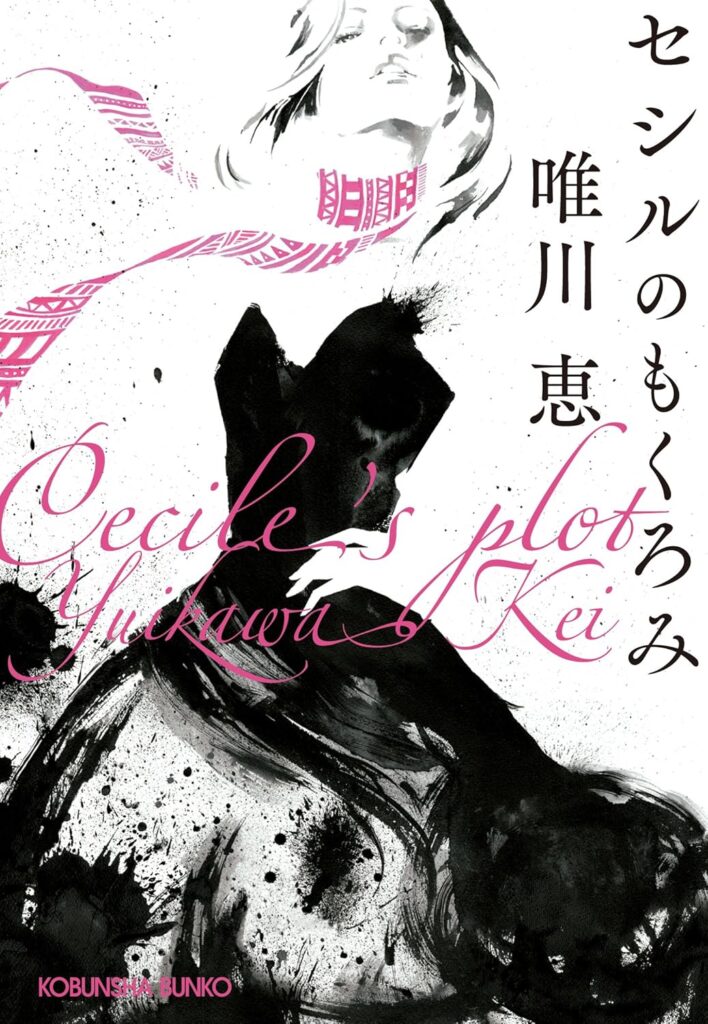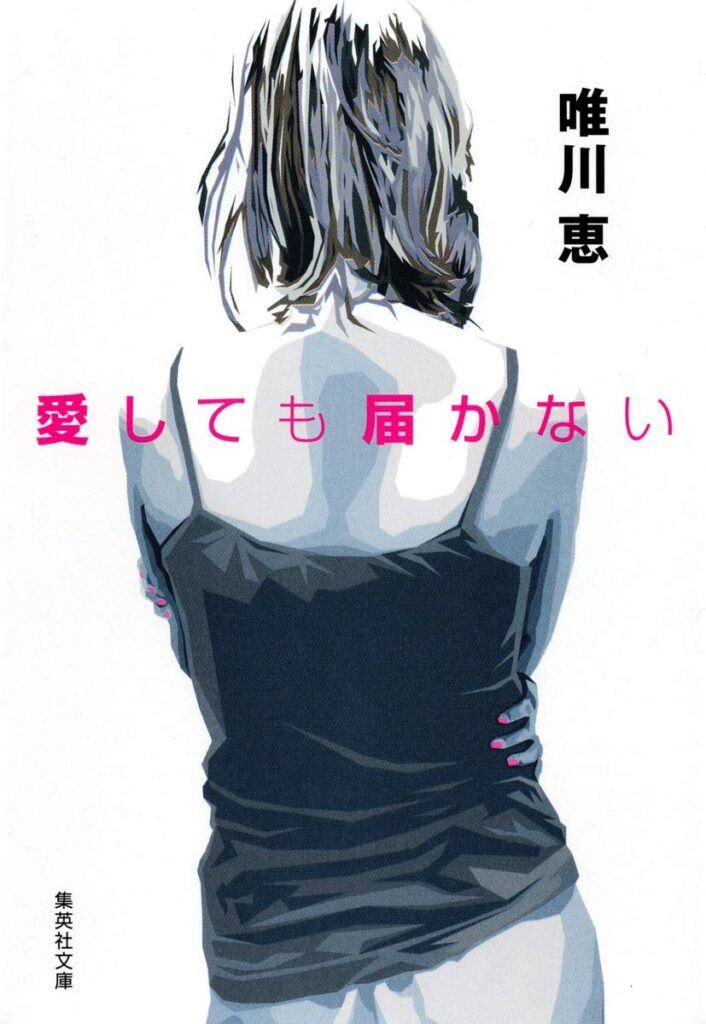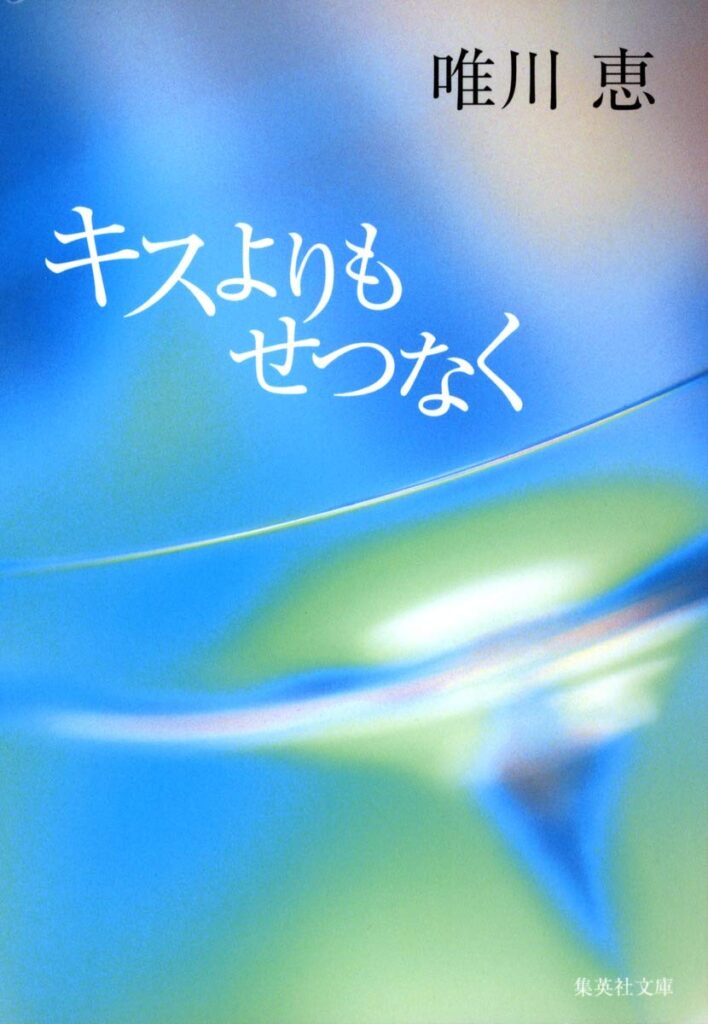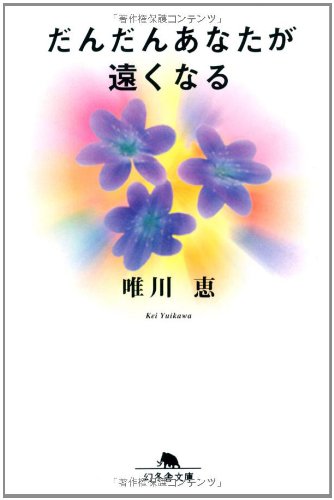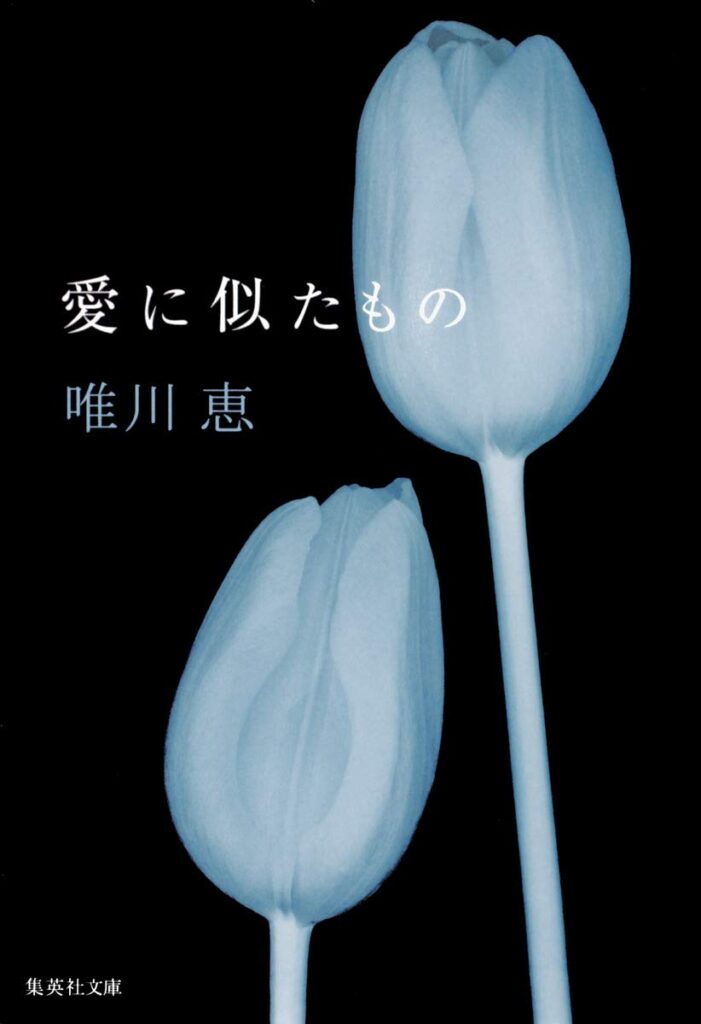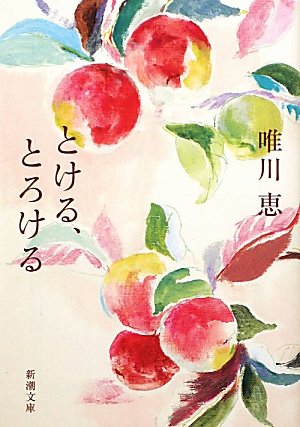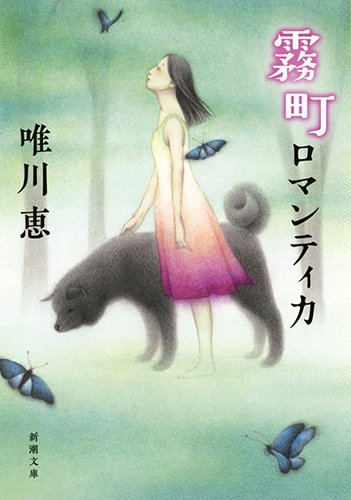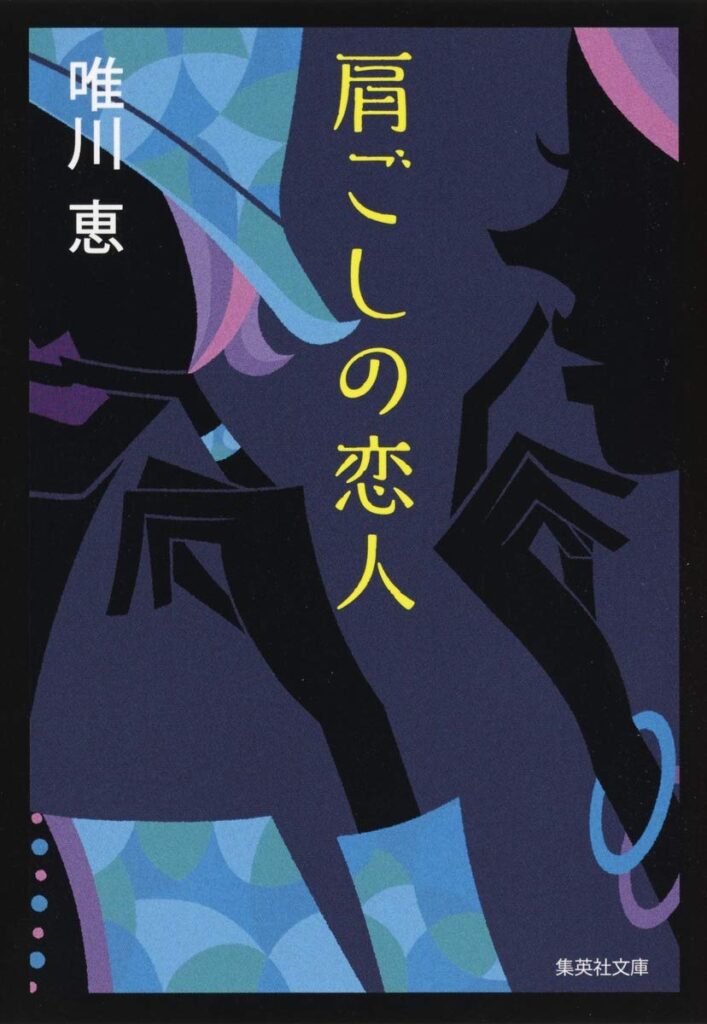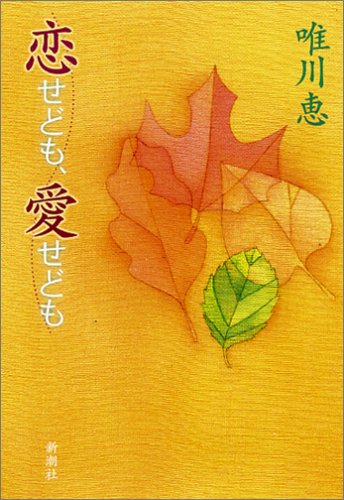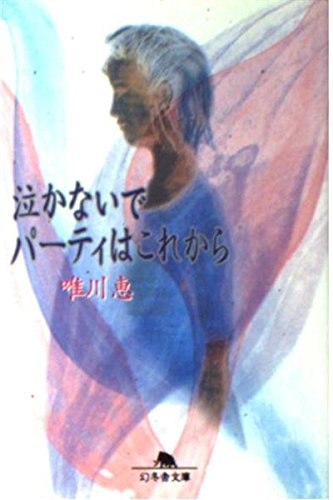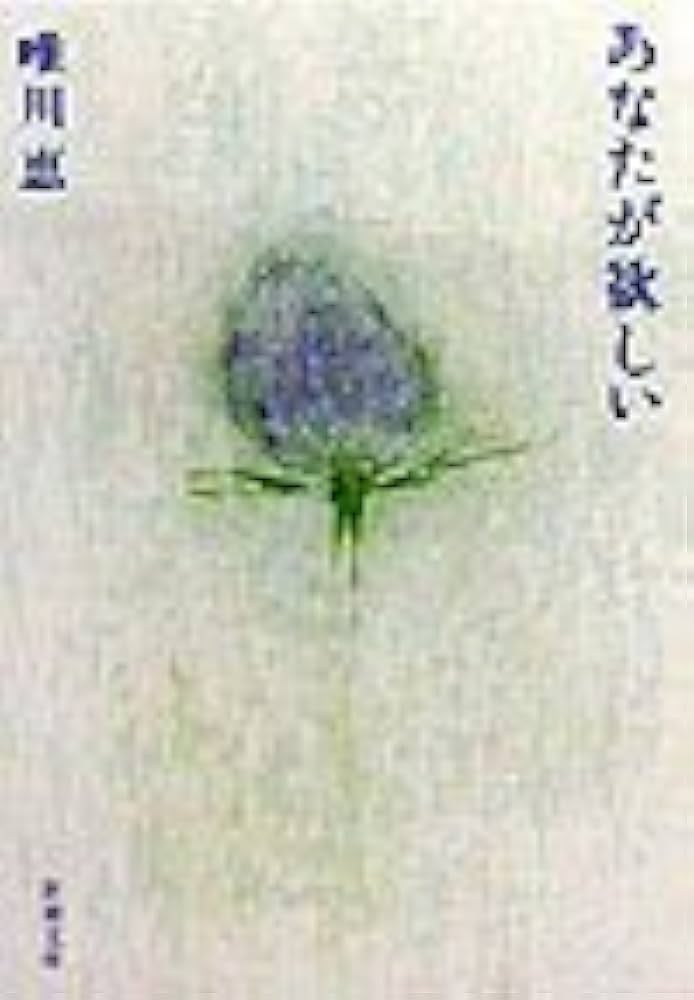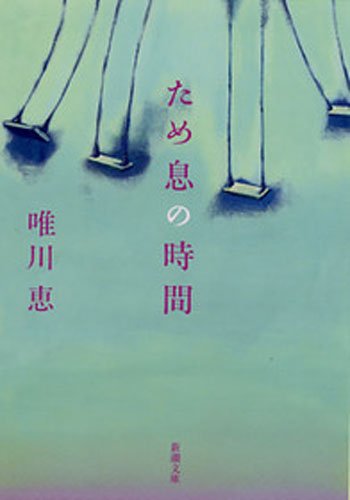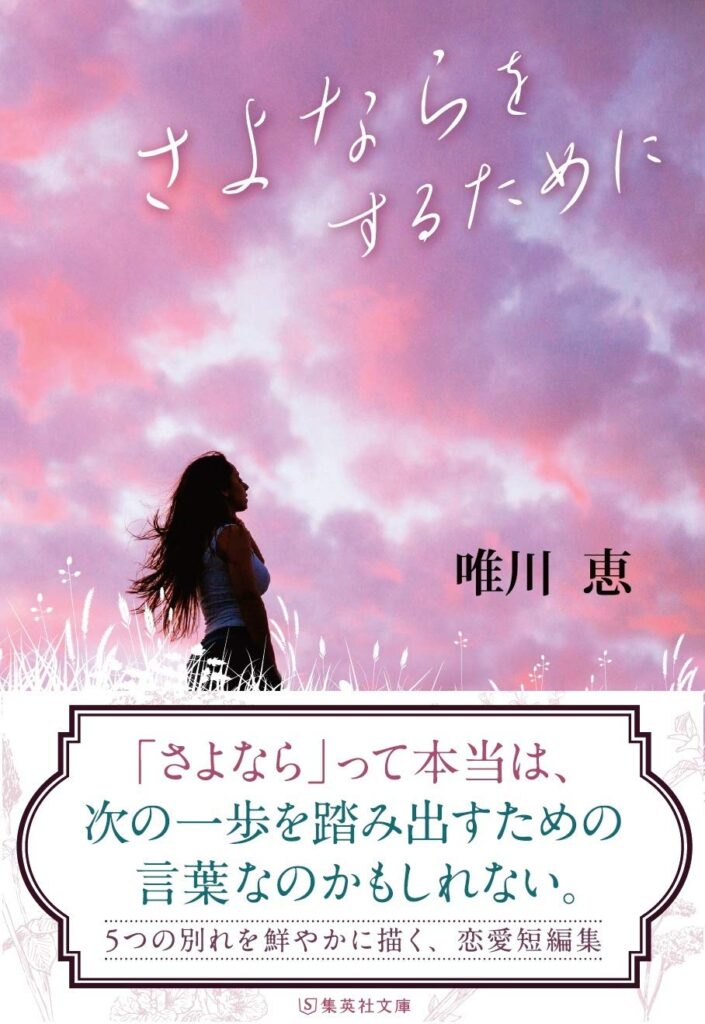小説「愛なんか」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「愛なんか」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
唯川恵さんの手になる『愛なんか』は、私たち現代を生きる女性たちの心の奥底に潜む、複雑で一言では言い表せない感情の機微を、鮮やかに描き出した短編集です。恋愛というテーマを扱いながらも、そこには甘美なだけではない、ほろ苦さや痛みが伴う愛のさまざまな姿が映し出されています。
この物語集には、12編の独立したお話が収められており、それぞれに異なる主人公たちが登場します。仕事、結婚、人間関係といった人生の岐路に立ち、答えを見つけられずに揺れ動く彼女たち。孤独や痛みを抱えながらも、自分なりの幸福の形を模索し、覚悟を決めて新たな一歩を踏み出そうとする姿には、胸を打つものがあります。
この記事では、そんな『愛なんか』に収められた物語一つひとつの詳しい筋道や、登場人物たちの心の動き、そして物語が私たちに問いかけるテーマについて、深く掘り下げていきます。それぞれの物語がどのような結末を迎えるのか、その核心にも触れていきますので、これから作品を読もうとされている方や、既読の方でより深く内容を理解したいと考えている方にも、読み応えのある内容となっているはずです。
どうぞ、唯川恵さんが紡ぐ、愛をめぐる奥深い世界を、ご一緒にお楽しみください。この記事が、あなたの心に残る一冊との出会いの一助となれば幸いです。
小説「愛なんか」のあらすじ
唯川恵さんの『愛なんか』は、12の愛の形を綴った、珠玉の短編集です。それぞれの物語は独立しており、異なる背景を持つ女性たちが主人公として登場します。彼女たちは、恋愛、結婚、仕事、そして自分自身の生き方について悩み、時に迷い、そして決断を下していきます。甘いだけではない、むしろ苦味や痛みを伴うような、リアルな愛の姿がそこには描かれています。
例えば、「ただ狂おしく」では、平凡な結婚を目前にした女性が、偶然出会った男性との激しい関係に溺れ、すべてを捨てて新たな道を選びます。一般的な幸福とはかけ離れた選択をする彼女の姿は、愛の多様なあり方と、人が何を幸福と感じるのかを問いかけます。また、「夜が傷つける」では、愛情が冷めてしまった関係を終わらせられない女性の葛藤が描かれ、最終的に彼女がどのようにして自分自身の心と向き合い、一歩を踏み出すのかが見どころです。
「世にも優しい、さよなら」は、裏切りに対する女性の静かで計算された仕返しを描いた物語です。感情的になるのではなく、冷静に相手を追い詰めていく様は、ある種の恐ろしさとともに、どこか解放感も感じさせるかもしれません。一方で、「私が愛した男」では、かつて情熱的に愛した夫の変貌に苦しみながらも、離れることができない女性の複雑な心情が綴られます。愛と執着、そして共依存のような関係性が、痛々しいほどにリアルに迫ってきます。
さらに、「偏愛」では、好意を抱いた相手への想いがエスカレートし、常軌を逸した行動に走ってしまう女性の姿が描かれます。純粋な愛情と紙一重の狂気が、読む者に強い印象を残すでしょう。「霧の海」では、主人公が抱く想いの対象が、予想外の人物であったことが明らかになり、愛の形がいかに多様であるかを改めて気づかされます。固定観念を揺さぶられるような展開が待っています。
これらの物語に共通して流れているのは、愛という感情が持つ、ままならなさや複雑さです。幸福を求めながらも、時には傷つき、迷い、あるいは誰かを傷つけてしまうこともある。登場人物たちは、そんな愛の深淵を覗き込みながら、自分自身の人生を懸命に生きています。彼女たちの選択や生き様は、私たち自身の心に深く問いかけてくるでしょう。
『愛なんか』というタイトルが示す通り、この作品集は「愛なんて所詮こんなものだ」という諦観と、「それでも愛なしでは生きられない」という切実な想いの両面を描き出しているのかもしれません。一筋縄ではいかない愛の物語を通して、読者は自分自身の恋愛観や人生観を見つめ直すきっかけを得られるのではないでしょうか。
小説「愛なんか」の長文感想(ネタバレあり)
唯川恵さんの『愛なんか』を読み終えたとき、心に残るのは甘い余韻というよりも、むしろ胸の奥がちくりと痛むような、それでいてどこか解放されるような、複雑な感覚でした。この短編集に収められた12の物語は、愛というものの綺麗事だけではない、人間の生々しい感情や業のようなものまでをも描き出していて、読む者の心を強く揺さぶります。それぞれの物語の結末や、登場人物たちが辿る心の軌跡について、深く語っていきたいと思います。
まず「ただ狂おしく」。主人公の公美は、安定した未来を捨て、刹那的な快楽と情熱に身を投じます。世間一般の価値観からすれば、彼女の選択は理解しがたいかもしれません。しかし、彼女が最後に言い放つ「幸せだ」という言葉には、他人の評価ではなく、自分自身の心の声に従って生きるという強い意志が感じられます。愛の形は一つではない、幸福の基準も人それぞれであるという、本作のテーマを象呈するような作品です。彼女の潔さ、あるいは危うさに、読者は何を思うでしょうか。
続く「夜が傷つける」は、終わらせたいけれど終わらせられない関係の息苦しさを描きます。愛情が冷え切った相手との惰性の日々は、まるで薄氷を踏むような緊張感に満ちています。主人公が最終的にどのような形で関係に終止符を打つのか、その過程には、受動的な立場から能動的に自分の人生を取り戻そうとする女性の、静かな強さが描かれています。些細なきっかけが、大きな決断へと繋がることもあるのだと気づかされます。
「世にも優しい、さよなら」は、ある意味で非常に現代的な復讐譚かもしれません。二股をかけられた女性が、ただ泣き寝入りするのではなく、周到な計画で相手を社会的に貶める。その手口の巧妙さには舌を巻きますが、同時に、裏切られた側の深い傷と怒りがひしひしと伝わってきます。果たしてこれが本当の「優しいさよなら」なのか、読者によって意見が分かれるところでしょう。しかし、この物語が持つある種の爽快感は、抑圧された感情の解放を求める現代人の心に響くのかもしれません。
「私が愛した男」は、読んでいて最も胸が苦しくなった物語の一つです。かつて才能を信じ、深く愛したはずの夫が、酒と暴力に溺れ、不倫を繰り返す。それでも離れられない主人公の姿は、共依存の恐ろしさと、愛という名の呪縛の深さを感じさせます。「なぜ別れないのか」という単純な疑問では片付けられない、複雑な感情の絡み合いがそこにはあります。愛が憎しみに変わり、それでも断ち切れない絆のありようを考えさせられます。
「共犯者」というタイトルからして、どこか危うい響きを持つこの物語は、情報が少ないながらも、「愛してる」という言葉を切望するあまり、常軌を逸した行動に出てしまう人物の姿が浮かび上がります。ダブル不倫なのか、あるいは別の形の秘密の共有なのか。いずれにしても、承認欲求の果てにある歪んだ関係性が描かれているのではないでしょうか。人は愛を求めるあまり、時に大きな過ちを犯してしまう生き物なのかもしれません。
「偏愛」は、ストーカーという現代的な病理を描き、読む者に強烈な不快感と恐怖を与えます。好意が一方的な執着へと変わり、相手の領域を侵犯していく様は、まさに狂気そのものです。山下という登場人物が「一番狂ってる」と評されるのも頷けます。この物語は、愛と狂気の境界線がいかに曖昧で脆いものであるかを突きつけてきます。結末の「怖さ」は、読者の心に深い爪痕を残すでしょう。
「霧の海」は、巧みな叙述トリックによって、読者の先入観を鮮やかに裏切ります。主人公が想いを寄せる相手が、実は同性であったという結末は、恋愛における異性愛規範という無意識の前提を揺るがします。愛に性別は関係ない、というメッセージが込められているのかもしれません。「霧」が晴れたときに見える真実は、時に私たちを驚かせ、そして新たな視点を与えてくれます。
「朝な夕な」は、「恋は狂うこと」という言葉が象徴するように、不倫関係における破滅的な愛の様相を描きます。決して幸せにはなれないと分かりながらも、激しい情熱に身を焦がす登場人物たち。その姿は、ある人には愚かしく映り、またある人には羨望の対象となるかもしれません。理性では抑えきれない感情の奔流と、その先にある避けられない結末の予感が、この物語を貫いています。
「長い旅」は、次々と恋愛を繰り返しながらも、真の幸福を見つけられない女性の人生を描きます。彼女の旅は、まるで終わりのない探求のようです。この物語は、単なる恋愛遍歴ではなく、一人の人間の「生き方」そのものに焦点を当てています。私たちは何を求めて生きるのか、幸福とは一体どこにあるのか。そんな根源的な問いを投げかけてくる作品です。
「幸福の向こう側」では、婚約者がいながら別の男性に惹かれてしまう女性の心の揺らぎが描かれます。安定した幸福を目前にしながらも、なぜ人は新たな刺激や別の可能性に目を向けてしまうのでしょうか。この物語に登場する女性が「たくましい」と評されるのは、彼女が自分の感情に正直に向き合い、困難な状況下でも自分なりの道を選び取ろうとするからかもしれません。幸福の形は、決して一つではないのです。
「恋愛勘定」は、バーという閉じた空間で繰り広げられる、女性たちの静かで熾烈な駆け引きを描いた小品です。言葉には出さないものの、互いを牽制し合い、値踏みし合うような空気感が漂います。そして、予想外の結末が訪れることで、人間関係の皮肉や、見かけとは裏腹の真実が明らかになります。短いながらも、人間観察の鋭さが光る物語です。
そして最後の「悪女のごとく」。主人公は自ら「悪女」を演じることで、周囲からの羨望を得ようとします。彼女の行動は、社会的な規範や「良き女性」という型にはまることへの反発であり、自分自身の存在価値を確かめようとする足掻きなのかもしれません。「平凡でつまんない女たち」を見下すことで得られる優越感の裏には、深い孤独や承認欲求が隠されているのではないでしょうか。この主人公の「たくましさ」は、逆境を跳ね返す力というよりも、自分自身の欲望に忠実に生きようとする、ある種の覚悟から来ているように感じます。
これら12の物語を通して見えてくるのは、唯川恵さんの一貫した人間観、特に女性に対する深い洞察です。彼女たちは決して聖女ではなく、時には計算高く、時には嫉妬深く、そして時には自分でも制御できないほどの強い情念に突き動かされます。しかし、その生々しさこそが、彼女たちの魅力であり、物語に深みを与えているのです。
愛は美しいもの、素晴らしいものと語られがちですが、『愛なんか』は、その言葉だけでは捉えきれない愛の側面――執着、依存、裏切り、嫉妬、そしてそれらがない交ぜになった複雑な感情――を、容赦なく描き出します。だからこそ、読者は登場人物たちの誰かに自分を重ね合わせたり、あるいはまったく理解できないと感じたりしながらも、目が離せなくなるのではないでしょうか。
読み終えて改めて思うのは、『愛なんか』というタイトルに込められた、作者の絶妙な距離感です。「愛なんて、しょせんはこんなものよ」と突き放すような響きと、「それでも、私たちは愛を求めずにはいられない」という切実な叫びが、同時に聞こえてくるようです。この短編集は、愛に傷つき、愛に悩み、それでも愛とともに生きていこうとするすべての人々にとって、深く心に刻まれる一冊となるでしょう。甘い夢を見せてくれるのではなく、愛の現実を突きつけながらも、その先に微かな光を見出させてくれる、そんな力強さを秘めた作品だと感じました。
まとめ
唯川恵さんの短編集『愛なんか』は、一言で言えば、愛というものの多様性と複雑性、そしてその奥深さを私たちに教えてくれる作品です。12の物語に登場する女性たちは、それぞれに異なる愛の形を生き、喜び、苦しみ、そして選択を重ねていきます。そこには、甘い恋愛物語とは一線を画す、現実的で時に痛みを伴う愛の姿が克明に描かれています。
この記事では、それぞれの物語がどのような結末を迎えるのか、その詳しい筋道や登場人物たちの心の奥底にある想い、そして作品全体を貫くテーマについて考察を重ねてきました。平凡な日常から逸脱する愛、終わりゆく関係の静かな痛み、計算された復讐、断ち切れない執着、そして予期せぬ愛の形。これらの物語は、読む者の心を様々な形で揺さぶり、私たち自身の経験や感情と重ね合わせて考えるきっかけを与えてくれます。
『愛なんか』というタイトルは、もしかしたら愛に対するある種の諦念や皮肉を含んでいるのかもしれません。しかし、物語を読み進めるうちに感じられるのは、むしろそうした割り切れない感情を抱えながらも、懸命に生きる人々の姿への、作者の温かい眼差しではないでしょうか。愛は決して万能薬ではなく、時には私たちを深く傷つけることさえあります。それでもなお、人が愛を求め、愛に翻弄され、愛によって成長していく姿が、ここにはあります。
この短編集は、恋愛小説という枠組みを超えて、人間の心の複雑さ、そして生きることのままならなさと愛おしさを教えてくれます。読後には、きっとあなた自身の「愛」について、そして「人生」について、深く思いを巡らせていることでしょう。ぜひ一度手に取って、唯川恵さんが描き出す、ほろ苦くも美しい愛の世界に触れてみてください。