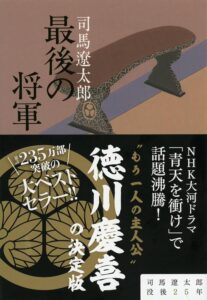 小説「最後の将軍」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。司馬遼太郎さんが描く歴史上の人物は、いつも生き生きとしていて、まるでその時代にタイムスリップしたかのような感覚を覚えますよね。この作品も、その例に漏れません。
小説「最後の将軍」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。司馬遼太郎さんが描く歴史上の人物は、いつも生き生きとしていて、まるでその時代にタイムスリップしたかのような感覚を覚えますよね。この作品も、その例に漏れません。
主人公は、江戸幕府最後の将軍、徳川慶喜。歴史の教科書では、大政奉還を行い、幕府を終わらせた人物として、どちらかというと影の薄い、あるいは少し頼りない印象で語られがちかもしれません。しかし、司馬さんの筆にかかると、そのイメージは大きく覆されます。聡明で、多芸多才、そして時代の流れを冷静に見極める目を持った、非常に魅力的な人物として描かれているのです。
幕末という、日本の歴史の中でも特に激動の時代。黒船が来航し、国内は開国か攘夷かで揺れ動き、尊王思想が高まりを見せる中、慶喜はどのように考え、行動したのか。彼が下した大きな決断は、日本の未来にどのような影響を与えたのでしょうか。
この記事では、まず「最後の将軍」がどのような物語なのか、その骨子となる部分をお伝えします。そして、物語の核心に触れる部分も含めて、私自身がこの作品を読んで何を感じ、考えたのかを、詳しくお話ししていきたいと思います。慶喜という人物の奥深さ、そして幕末という時代の熱気を、少しでも感じていただけたら嬉しいです。
小説「最後の将軍」のあらすじ
物語は、徳川慶喜、幼名・七郎麿が、徳川御三家の一つである水戸藩に生まれたところから始まります。水戸藩は、徳川光圀(水戸黄門)以来、独自の学問「水戸学」を発展させ、尊王思想が強い土地柄でした。この環境が、後の慶喜の考え方に大きな影響を与えることになります。七男でありながら、その類まれな聡明さを見込まれ、御三卿の一つである一橋家の養子となり、将軍継嗣問題にその名が挙がるようになります。
当時の日本は、ペリー率いる黒船の来航によって、大きな転換期を迎えていました。開国か攘夷か、国論は二分し、幕府内でも意見が対立。井伊直弼による安政の大獄など、厳しい弾圧も行われる不安定な状況でした。慶喜は、早くから世界情勢を理解し、日本の進むべき道を冷静に考えていましたが、その聡明さゆえに、幕府の中枢からは警戒される存在でもありました。
紆余曲折を経て、慶喜は第十五代将軍に就任します。しかし、時代はすでに徳川幕府の権威が揺らぎ、薩摩藩や長州藩を中心とする倒幕の動きが加速していました。国内をまとめ、諸外国とも渡り合わなければならない、まさに日本の命運を一身に背負う立場となったのです。
慶喜は、将軍という立場にありながら、旧来の慣習にとらわれず、諸大名との会議では敬語を使い、時には写真撮影を提案するなど、柔軟な姿勢で難局に当たろうとします。彼は、徳川家の存続よりも、日本という国全体の未来を優先して考えていました。外国の脅威を前に、国内で争っている場合ではない、と。
そして、慶喜は歴史的な決断を下します。それが「大政奉還」です。約260年続いた徳川幕府の統治権を、朝廷に返上するという前代未聞の決断でした。これにより、武力衝突を避け、平和裏に政権を移譲しようとしたのです。しかし、薩長を中心とする新政府軍はこれを良しとせず、鳥羽・伏見の戦いが勃発します。
戦況不利と見るや、慶喜は自ら大坂城を脱出し、江戸へ戻ります。この行動は後に「敵前逃亡」と批判されることもありますが、徹底して戦を避け、内乱による国の疲弊を防ごうとした彼の意思の表れでもありました。その後、江戸城の無血開城へとつながり、日本は大きな内戦を回避することができたのです。将軍職を退いた慶喜は、静岡で隠棲生活を送り、趣味に没頭する穏やかな晩年を過ごしました。
小説「最後の将軍」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは「最後の将軍」を読んだ私の詳しい感想を、物語の核心にも触れながらお話ししていきたいと思います。この作品を読む前、私にとって徳川慶喜という人物は、正直なところ、あまりはっきりとした像を結んでいませんでした。「幕府を終わらせた将軍」という事実だけが頭にあり、どこか掴みどころのない、もしかしたら少し頼りない人物なのかな、くらいの印象でした。学校の歴史の授業でも、彼の個性や内面に深く触れる機会は少なかったように思います。
しかし、司馬遼太郎さんの手によって描かれた慶喜像は、そんな私の浅はかなイメージを根底から覆すものでした。まず驚かされたのは、彼の出自と、それが彼の思考や行動に与えた深い影響です。水戸藩、徳川御三家の一角でありながら、どこか幕府中枢とは距離があり、尊王思想を育んできた土地柄。そこで育った慶喜が、幕府の頂点に立ちながらも、絶対的な忠誠心や執着を持たなかったであろうことは、想像に難くありません。むしろ、幕府という組織を客観的に、どこか冷めた目で見ていたのかもしれない、と感じました。
そして、慶喜自身の多才ぶりには目を見張るものがあります。学問や弁舌に優れていたことはもちろん、投網を短期間で習得したり、自ら料理をしたり、馬を乗りこなしたり、さらには写真や油絵、自転車にまで興味を示す。まるで現代人のような好奇心と行動力です。「何でも自分でやってみないと気が済まない」という性質は、世襲で地位が決まることが多かった当時の支配階級の中では、異質だったのではないでしょうか。この多才さと行動力が、彼の柔軟な思考や、旧弊にとらわれない政治姿勢にも繋がっていたように思えます。
一方で、彼は驚くほど権力そのものへの執着が薄い人物としても描かれています。将軍継嗣問題で名前が挙がった際も、決して自ら積極的に動こうとはしませんでした。むしろ、時代の大きな流れの中で、周りに推される形でその立場に就いた、という印象です。「考えてもみよ、政体が古すぎる。たれがやってもうまくゆかぬ」という彼の言葉には、現状に対する深い洞察と、ある種の諦観すら感じられます。攘夷論が吹き荒れる中でも、彼は冷静に国際情勢を分析し、日本の置かれた状況を理解していました。この冷静さが、彼の最大の武器であり、同時に周囲との温度差を生む要因にもなったのかもしれません。
将軍に就任してからの慶喜の振る舞いも、非常に興味深いものでした。諸大名を集めた会議で、自ら敬語を使い、煙草盆を用意し、茶菓子を勧め、しまいには記念撮影まで提案する。これは、従来の将軍のイメージからはかけ離れた行動です。形式や権威にこだわらず、実質的な議論を進め、人心を掴もうとする。現代のリーダーシップ論にも通じるような、合理性と柔軟性を感じさせます。もし彼が平時において将軍であったなら、その才覚をさらに発揮できたのかもしれない、と思わずにはいられません。
そして、物語のクライマックスとも言える「大政奉還」。なぜ彼は、先祖代々受け継いできた政権を、あっさりと手放す決断ができたのでしょうか。そこには、水戸学以来の尊王思想、幕府内での孤立感、そして何よりも、欧米列強との圧倒的な国力差を前にして、国内で争っている場合ではないという強い危機感があったのだと思います。徳川家の安泰よりも、日本という国全体の未来を優先した、苦渋の、しかし極めて合理的な判断だったのではないでしょうか。
もちろん、この決断がすべての問題を解決したわけではありません。薩長を中心とする勢力は、なおも武力による倒幕を目指し、鳥羽・伏見の戦いが起こります。ここで慶喜が取った行動、つまり大坂城からの脱出は、長らく「敵前逃亡」として非難されてきました。しかし、司馬さんは、これもまた慶喜なりの合理的な判断、すなわち、自らが徹底して戦意のないことを示し、内戦の拡大を防ぐための行動だったのではないか、という視点を提示しています。結果的に、江戸城は無血開城され、首都が火の海になる事態は避けられました。もし慶喜が徹底抗戦を選んでいたら、日本はどのような運命を辿っていたでしょうか。想像すると、彼の決断の重みを改めて感じます。
ただ、慶面白いのは、慶喜のそうした合理性や冷静さが、一方で「情の薄さ」「貴族的な冷淡さ」として、家臣たちの離反を招いたり、最後まで幕府を守り抜こうとする勢力との間に溝を生んだりした側面も、きちんと描かれている点です。彼は、最後まで徳川家や幕臣たちへの強い「忠義」や「共感」といった感情を表に出すことが少なかったように見えます。それが、彼を「最後の将軍」たらしめた要因の一つであり、同時に彼の限界でもあったのかもしれません。熱い情熱で人を引っ張るタイプのリーダーではなかった、ということです。
将軍職を退いた後の慶喜の人生も、非常に示唆に富んでいます。彼は政治の世界から完全に身を引き、静岡で趣味に没頭する生活を送ります。油絵、写真、狩猟、囲碁、自転車…。まるで、これまで背負ってきた重荷から解放されたかのように、自分の好きなことに打ち込む姿は、どこか羨ましくもあります。「将軍をやめてよかったとおもうのは、この油絵をかいているときだ」という言葉は、彼の本心だったのかもしれません。激動の時代に翻弄されながらも、最後は自分らしい静かな生き方を見つけた、とも言えるでしょう。
この「最後の将軍」という作品を通して、司馬遼太郎さんは、徳川慶喜という人物を、単なる歴史上の記号ではなく、血の通った一人の人間として見事に描き出しています。聡明で、多才で、合理的でありながら、どこか掴みどころがなく、冷めているようにも見える。単純な「名君」でも「暗君」でもない、非常に複雑で多面的な魅力を持った人物。そして、その彼が「最後の将軍」であったことが、日本の近代化において、ある種の幸運だったのかもしれない、と。
他の幕末の物語では、坂本龍馬や西郷隆盛、あるいは新選組といった、より情熱的で行動的な人物が中心に描かれることが多いように思います。しかし、この「最後の将軍」を読むことで、そうした熱いエネルギーとは対照的な、冷静な知性によって時代を動かそうとしたリーダーがいたことを知ることができます。そして、彼の選択が、結果的に日本の破局的な内乱を回避し、比較的スムーズな政権移行を可能にした側面があったことを理解できるのです。
歴史に「もし」はありませんが、もし慶喜がもっと権力に執着し、徹底抗戦を選んでいたら? もし彼が幕府内の旧守派に押し切られていたら? そう考えると、彼の存在と決断の意義は、非常に大きかったと言わざるを得ません。彼は、自らの手で徳川幕府の歴史に幕を引くという、極めて困難な役回りを引き受け、そしてそれを成し遂げた人物なのです。
この物語は、徳川慶喜という一人の人間の生涯を通して、幕末という時代の複雑さ、そして歴史の大きな転換点におけるリーダーシップのあり方を考えさせてくれます。読みやすい文章でありながら、内容は非常に深く、読後には慶喜に対する見方が大きく変わっていることでしょう。歴史小説の面白さ、そして司馬遼太郎作品の魅力を改めて感じさせてくれる一冊でした。
まとめ
司馬遼太郎さんの「最後の将軍」は、江戸幕府最後の将軍、徳川慶喜の生涯を描いた、非常に読み応えのある歴史小説でした。一般的に持たれがちな慶喜のイメージを覆し、聡明で多才、そして冷静な判断力を持った人物として、その魅力と複雑な内面を深く掘り下げています。
水戸藩出身という出自、将軍就任までの経緯、そして大政奉還という歴史的な決断に至る背景が、当時の激動の時代状況と共に詳細に描かれています。特に、内乱を避け、日本の未来を見据えて自ら政権を返上した慶喜の行動は、単なる「敗北」や「逃亡」ではなく、彼なりの合理性と苦渋に満ちた選択であったことが伝わってきます。
将軍職を退いた後の、趣味に没頭する隠棲生活の描写も印象的で、慶喜という人間の多面性を感じさせます。彼が「最後の将軍」であったことが、結果的に日本の平和的な政権移行に繋がったのかもしれない、と考えさせられる点も、この作品の大きな魅力です。
幕末という時代や徳川慶喜という人物に興味がある方はもちろん、歴史の転換期におけるリーダーシップについて考えたい方にも、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。読めばきっと、歴史を見る目が少し変わるかもしれませんよ。






































