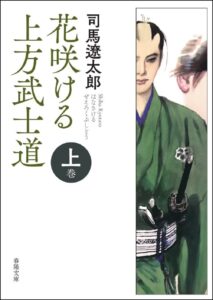 小説「花咲ける上方武士道」の物語の筋を、結末に触れつつ紹介します。長文の所感も書いていますのでどうぞ。
小説「花咲ける上方武士道」の物語の筋を、結末に触れつつ紹介します。長文の所感も書いていますのでどうぞ。
司馬遼太郎さんの作品といえば、史実に基づいた重厚な歴史小説を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、この「花咲ける上方武士道」は、司馬作品の中では少し珍しい、架空の人物を主人公とした完全なフィクション、エンターテイメント性の高い時代活劇なんです。
舞台は幕末。主人公は高野則近(たかののりちか)という名の公家です。公家でありながら剣の腕は一流、しかもひょんなことから大坂商人の養子になるという、型破りな設定がまず面白いですね。彼が朝廷の密命を受け、個性的な仲間たちと共に江戸へ向かう道中を描いた物語です。
この記事では、まず「花咲ける上方武士道」がどのようなお話なのか、その概要をお伝えします。その後、物語の核心部分にも触れながら、私がこの作品を読んで抱いた詳しい思いや考えを、たっぷりと語らせていただこうと思います。
小説「花咲ける上方武士道」のあらすじ
物語の始まりは幕末の京の都。主人公の高野則近は、由緒ある公家の生まれでありながら、なぜか剣術に並々ならぬ才能を持つ若者です。当時の公家社会は、武家政権下で逼迫しており、経済的に困窮する家も少なくありませんでした。則近の生家も例外ではなく、なんと彼は一万両という大金で大坂の豪商・和泉屋の養子として売られてしまいます。
しかし、彼の運命はそれで終わりません。彼の持つ類まれな剣の腕と公家としての知識、そして商人としての経験(養子としてですが)を見込まれ、朝廷から「公家密偵使」という特別な任務を命じられるのです。その任務とは、幕府の動向を探るため、密かに江戸へ下向することでした。当時の公家は、幕府の許可なく京から出ることは厳禁。見つかれば命の保証はありません。
則近の江戸への旅には、頼もしい(そして一癖も二癖もある)仲間が同行します。一人は、百済ノ門兵衛(くだらのもんべえ)。元は武士でありながら、すっかり商人根性が染みついた現実主義者ですが、いざという時には腕が立ちます。もう一人は、名張ノ青不動(なばりのあおふどう)。伊賀忍者の流れを汲む「軒猿」と呼ばれる存在で、古風で朴訥ながら、忍者としての技は確かな人物です。
東海道を下る道中、則近一行の前には様々な困難が待ち受けます。幕府の意を受けた甲賀の刺客たちが、次々と襲いかかってくるのです。公家でありながら武芸に秀でた則近は、門兵衛や青不動と共に、これらの刺客たちと手に汗握る戦いを繰り広げます。そのアクションシーンは、まさに痛快娯楽時代劇といった趣です。
道中では、刺客との戦いだけでなく、様々な人々との出会いもあります。勝ち気で魅力的な町娘との淡い恋模様や、当時の風俗、特に公家と武家、そして庶民との間にある厳格な身分差や価値観の違いなどが、司馬遼太郎さんらしい筆致で描かれています。例えば、公家の行列が大名行列と鉢合わせした際の駆け引きや、庶民が公家をどのように見ていたかなど、興味深い描写が随所に見られます。
物語は、一行が様々な困難を乗り越え、江戸へ向かう道程を中心に描かれていきます。しかし、意外なことに、物語は江戸に到着する直前、その道中で幕を閉じるのです。多くの読者が期待するであろう、江戸での活躍は描かれません。この結末については、様々な解釈や感想があるところでしょう。
小説「花咲ける上方武士道」の長文感想(ネタバレあり)
いやあ、面白かったですね!司馬遼太郎さんの作品は数多く読んできましたが、「花咲ける上方武士道」は、その中でも特にエンターテイメントに振り切った、読んでいて心が躍るような一作でした。歴史の勉強になる、という側面は他の作品に比べると薄いかもしれませんが、純粋な物語としての面白さ、登場人物たちの魅力にぐいぐい引き込まれました。
まず何と言っても、主人公の高野則近がいいですね。公家という、普通なら雅やかで非力なイメージがある身分でありながら、滅法剣が強い。しかも、大坂商人の養子になった経験からか、世間の裏表にも通じていて、どこか飄々として掴みどころがない。それでいて、女性にはめっぽうもてる。まさに、時代劇のヒーローといった風格です。彼の言動には、公家としての気品と、武士のような胆力、そして商人譲りのしたたかさが同居していて、非常に多面的な魅力があります。
そして、彼を取り巻く脇役たちも負けず劣らず個性的です。百済ノ門兵衛は、口を開けば金勘定の話ばかりするような現実的な侍ですが、その抜け目のなさが頼りになる場面も多い。一方、忍者の名張ノ青不動は、時代に取り残されたかのような古風な価値観を持ちながら、忠義に厚く、超人的な技で則近を助けます。この二人の対照的なキャラクターと、主人公・則近との掛け合いが、物語に軽妙な味わいを加えていますね。特に青不動の朴訥とした人柄は、読んでいて何だか応援したくなります。
物語の構成は、京都から江戸へ向かう東海道の道中記、いわばロードムービーのような形式です。次から次へと現れる甲賀の刺客たちとの対決は、ハラハラドキドキの連続。剣術だけでなく、忍術や策略も駆使した戦いは、読んでいて飽きることがありません。司馬さんの筆にかかると、アクションシーンも実に生き生きと描かれます。
また、道中で出会う人々との交流も、物語の大きな魅力の一つです。特に、則近が心惹かれる勝ち気な町娘との関係は、殺伐としがちな道中譚の中に、ほのかな彩りを添えています。則近が、公家の身分を隠したり利用したりしながら、様々な状況を切り抜けていく様子も面白い。当時の身分制度の厳しさや、公家という存在が庶民からいかに特別な目で見られていたかが、具体的なエピソードを通して伝わってきます。公家の行列が、その権威を笠に着て大名行列から金品をせしめようとする場面などは、当時の世相の一端を垣間見るようで興味深かったです。
この作品は、司馬さんが比較的若い頃、昭和35年に書かれた初期のものです。そのためか、後年の「余談」と呼ばれるような、歴史背景や人物に関する深い考察や解説は少なめです。その分、ストーリー展開はスピーディーで、物語そのものの面白さに集中できるとも言えます。歴史の知識を深めたいというよりは、純粋に面白い時代小説を読みたい、という気分の時にはぴったりでしょう。
ただ、史実を深く掘り下げた司馬作品に慣れ親しんだ読者にとっては、少し物足りなさを感じる部分もあるかもしれません。「ああ、面白かった!」という満足感はあるものの、「なるほど、勉強になった!」という知的な興奮は、例えば『竜馬がゆく』や『坂の上の雲』といった作品に比べると、確かに少ないかもしれませんね。完全なフィクションであるがゆえの、ある種の「軽さ」とも言えるかもしれません。
そして、この作品について語る上で避けて通れないのが、その結末です。あれだけ道中の苦難を描いておきながら、物語は江戸に到着する寸前でぷっつりと終わってしまう。え、ここで終わり?江戸での活躍はないの?と、拍子抜けした読者も少なくないのではないでしょうか。私も最初はそう感じました。まるで、連載が途中で打ち切りになってしまったかのような、尻切れトンボな印象は否めません。
この結末については、もしかしたら本当に何らかの事情で連載が中断されたのかもしれない、という推測もあるようです。しかし、敢えてこの終わり方にしたのだとしたら、それはそれで一つの解釈ができるかもしれません。この物語の主題は、江戸での則近の活躍そのものではなく、彼が様々な価値観や困難に直面しながら東海道を下る「過程」にあったのではないか、と。あるいは、読者の想像力にその後の展開を委ねる、という意図があったのかもしれません。いずれにしても、少し消化不良な感じが残るのは事実ですが、それも含めてこの作品の個性なのかもしれません。
また、この作品のタイトルについても触れておきたい点があります。元々は『花咲ける上方武士道』として連載が開始されましたが、すぐに『上方武士道』(ぜえろくぶしどう)と改題され、単行本もそのタイトルで刊行されました。「ぜえろく」というのは、本来「贅六」などと書き、上方(関西)で丁稚などを指す言葉の江戸訛りで、江戸の人が関西人を見下して使う侮蔑的な響きも持っていました。
ジャーナリストの大宅壮一氏の助言で改題されたそうですが、上方出身である司馬さんの夫人はこの「ぜえろく」という言葉が好きではなかったと語っています。司馬さんの没後、中央公論社から再刊される際に、再び元の『花咲ける上方武士道』に戻されました。このタイトル変更の経緯を知ると、作品に対する見方も少し変わってくるかもしれませんね。「上方武士道」という言葉自体が、ある種の皮肉や諧謔を含んでいたのかもしれません。
司馬遼太郎さんの作品群の中で見ると、「花咲ける上方武士道」は、彼の歴史小説家としての側面とは少し違う、エンターテイナーとしての一面を見せてくれる作品と言えるでしょう。史実の重みからは少し離れて、剣と恋と冒険が詰まった、純粋な娯楽時代劇を楽しみたい方には、ぜひお勧めしたい一冊です。
初期の作品ということで、文章には若々しい勢いが感じられますし、後の大作群とはまた違った魅力があります。深刻になりすぎず、かといって軽薄でもない、絶妙なバランス感覚で描かれた登場人物たちと共に、幕末の東海道を旅するような気分を味わえます。
個人的には、もっと則近たちの活躍を見たかった、という気持ちはありますが、それでも読後感は非常に爽やかでした。司馬作品の入り口としても、あるいは、普段あまり時代小説を読まない方にも、気軽に手に取っていただけるのではないでしょうか。痛快で、読んでいて元気が出るような物語です。
まとめ
この記事では、司馬遼太郎さんの小説「花咲ける上方武士道」について、物語の概要と、結末にも触れた詳しい所感をお話しさせていただきました。
本作は、司馬作品としては珍しく、架空の人物である公家剣士・高野則近を主人公とした、エンターテイメント性の高い時代活劇です。朝廷の密命を受けて江戸へ向かう則近と、個性的な仲間たちが繰り広げる道中記であり、次々と現れる刺客とのスリリングな戦いや、様々な人々との出会いが描かれています。
史実に基づいた重厚な歴史小説とは少し趣が異なりますが、その分、純粋な物語としての面白さ、キャラクターの魅力、痛快な展開を存分に楽しむことができます。特に、公家でありながら剣の達人という型破りな主人公・則近のキャラクター造形は秀逸です。
物語が江戸到着前に終わってしまう点については、少し物足りなさを感じるかもしれませんが、それもまた本作の特徴の一つと言えるでしょう。司馬遼太郎さんの初期の作品として、また、気軽に楽しめる娯楽時代小説として、多くの方にお勧めしたい一冊です。






































