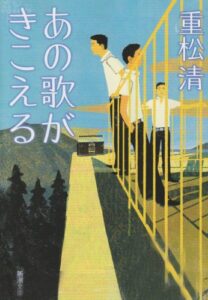 小説「あの歌がきこえる」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「あの歌がきこえる」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
重松清さんが描く、音楽と青春が交差する物語、「あの歌がきこえる」。読んでいると、まるで自分の青春時代が蘇ってくるような、そんな懐かしさと切なさに包まれます。特に、物語の節目節目で流れる昭和の名曲たちが、登場人物たちの心情や時代の空気を見事に映し出していて、胸が熱くなります。
この物語は、地方都市で育った3人の少年、シュウ、コウジ、ヤスオの友情と成長の記録です。中学時代から高校卒業、そしてそれぞれの道へと進むまでの多感な時期が、当時のヒット曲と共に丁寧に描かれています。甘酸っぱい初恋のような気持ち、友人との別れ、家族との葛藤など、誰もが経験するであろう青春の光と影が、そこにはあります。
この記事では、「あの歌がきこえる」の物語の概要、そしてネタバレを含む詳しい出来事、さらに私個人の深い思い入れを込めた考察をお届けします。読み進めるうちに、きっとあなた自身の「あの歌」と大切な記憶がよみがえってくるはずです。
小説「あの歌がきこえる」のあらすじ
物語の舞台は、1970年代後半から1980年にかけての日本の地方都市。主人公は、ごく普通の少年シュウ。彼には中学時代からの親友、コウジとヤスオがいます。3人はいつも一緒で、思春期特有の悩みや他愛ないおしゃべりを共有しながら日々を過ごしていました。
高校受験を控え、シュウとコウジは地元の進学校を目指しますが、ヤスオは別の道を選びます。そして、シュウが淡い想いを寄せていた同級生の女子も、受験の失敗を機に遠くへ引っ越してしまうことに。初めて経験する大きな別れは、シュウの心に影を落とします。
高校に進学したシュウとコウジ。しかし、コウジは家庭の事情(母親の家出)から次第に学校から足が遠のき、中退してしまいます。一方、中学時代の同級生で、かつては優等生だったタッちゃんは、高校で道を踏み外し、不良グループとつるむようになっていました。シュウは、変わりゆく友人たちの姿に戸惑いながらも、関係を保とうとします。
物語には、シュウの父親のエピソードも織り込まれます。真面目だけが取り柄のような父親が、小学校の同級生に騙されてお金を取られてしまう事件が発生。完璧だと思っていた大人の脆さを目の当たりにし、シュウはまた一つ成長の階段を上ります。教育実習でやってきた、少し頼りないけれど浜田省吾を熱く語る先生との出会いも、シュウにとっては印象的な出来事でした。
各章のタイトルは、中村雅俊「いつか街で会ったなら」、中島みゆき「さよなら」、さだまさし「案山子」、サザンオールスターズ「いなせなロコモーション」、ジョン・レノン「スターティング・オーバー」、浜田省吾「トランジスタラジオ」など、当時のヒット曲から取られています。これらの曲が、それぞれの章で描かれる出来事や登場人物の心情と深く結びつき、物語に彩りを与えています。
ジョン・レノンが凶弾に倒れた1980年12月8日。その衝撃的なニュースは、シュウたちの青春時代にも大きな影響を与えます。やがてシュウは高校を卒業し、早稲田大学への進学を決意。故郷を離れ、東京へと旅立つところで物語は幕を閉じます。青春の日々への別れと、未来への希望を胸に抱いて。
小説「あの歌がきこえる」の長文感想(ネタバレあり)
「あの歌がきこえる」を読み終えたとき、深い感動と共に、自分の過ぎ去った日々への強いノスタルジーを感じずにはいられませんでした。重松清さんの描く世界は、いつも私たちの心の柔らかな部分に触れ、忘れかけていた感情を呼び覚ましてくれます。この作品もまた、音楽というタイムマシンのような存在を通して、読者をそれぞれの青春時代へと誘ってくれる、素晴らしい物語でした。
物語は、シュウ、コウジ、ヤスオという3人の少年たちの友情を軸に進みます。彼らが過ごした中学から高校にかけての時間は、まさに激動の季節。いつも一緒だったはずの仲間が、受験や家庭の事情、あるいは本人の選択によって、少しずつ違う道を歩み始める。その過程で生まれる距離感や、それでも断ち切れない絆のありようが、非常にリアルに描かれています。特に、コウジが母親の家出という重い現実を背負い、学校を去っていく場面は胸が締め付けられました。シュウが何もできない自分にもどかしさを感じる姿は、多くの読者が共感するところではないでしょうか。
そして、もう一人、忘れられないのがタッちゃんです。中学時代は成績も良く、真面目な生徒だった彼が、高校で不良となり、矢沢永吉を信奉するようになる。進学校に進んだシュウとは住む世界が違ってしまったように見えるけれど、ある日、タッちゃんの運転する車で二人きりになる場面があります。タッちゃんは、シュウの前ではお気に入りの矢沢永吉ではなく、サザンオールスターズの「いなせなロコモーション」をかけるのです。「どっちがええ思う?」と尋ねるシュウに対する「……そげなこと決められるか、アホ」というタッちゃんの返答。この短いやり取りの中に、言葉にはできない複雑な友情、お互いの世界を認めつつも、簡単には割り切れない感情が凝縮されているように感じました。かつて同じ場所で過ごした記憶は、たとえ進む道が大きく異なったとしても、簡単には消えない。そんな普遍的な真実を教えてくれるエピソードです。
この物語の大きな魅力は、各章を彩る昭和の名曲たちです。単なるBGMとしてではなく、それぞれの楽曲が、登場人物たちの心情や時代の空気感と深く結びついています。ユーミンの「DESTINY」が流れる中で意識し始める異性への気持ち、さだまさしの「案山子」と共に感じる故郷や家族への想い、そしてジョン・レノンの「スターティング・オーバー」が響く中で向き合うことになる父親の変化と、時代の転換点。これらの曲を知っている世代にとっては、イントロが流れただけで当時の記憶がフラッシュバックするような、特別な体験となるでしょう。
特に印象深いのは、「スターティング・オーバー」の章です。シュウの父親が、かつての親友に裏切られ、お金を騙し取られてしまう。いつもは厳格で正しい存在だと思っていた父親の、弱く、情けない姿。シュウはショックを受けますが、同時に、大人もまた迷い、傷つく存在なのだと知ります。ジョン・レノンが「(ジャスト・ライク)スターティング・オーバー」で再起を宣言した矢先に凶弾に倒れるという衝撃的な出来事と、父親の挫折と再生への願いが重ね合わされ、深い余韻を残します。人は皆、何度も躓きながら、それでも「やり直したい」と願うのかもしれない、そんなことを考えさせられました。
浜田省吾を愛する教育実習生のエピソードも心に残ります。少し頼りなく、生徒たちからも軽く見られがちな先生ですが、浜省の歌について語るときだけは熱を帯びる。その一途さが、シュウの心に何かを響かせます。誰もが格好良く生きられるわけではないけれど、好きなものへの情熱は、人を支え、輝かせることができる。そんなメッセージを感じ取りました。
重松清さんの文章は、派手さはないけれど、日常の中にある小さな喜びや悲しみ、人の心の機微を丁寧に掬い取っています。登場人物たちの会話やモノローグは、まるで隣で彼らの声を聞いているかのように自然で、すっと心に入ってきます。思春期の少年特有の、言葉にならない感情や、大人になることへの戸惑い、未来への漠然とした不安と期待。そうしたものが、飾らない言葉で綴られているからこそ、強く胸を打つのです。
読みながら、五木寛之さんの「青春の門」を思い出したという感想を目にしましたが、私も同じような感覚を覚えました。時代背景や主人公の境遇は全く異なりますが、若さゆえの危うさ、まだ何者でもないがゆえの可能性、そして過ぎ去った日々へのほろ苦いノスタルジーといった点で、通底するものがあるように感じます。「青春の門」が持つ熱量や力強さとはまた違う、重松清さんならではの温かくも切ない視線が、「あの歌がきこえる」には流れています。
この物語は、シュウが早稲田大学に合格し、上京するところで終わります。それは、一つの時代の終わりであり、新しい人生の始まりでもあります。故郷に残る友人たち、変わっていく家族、そして数々の出来事と思い出が詰まった町を後にして、シュウは未来へと歩き出す。その背中には、希望と共に、一抹の寂しさが漂っているように見えます。青春とは、輝かしいけれど、同時に多くのものを置き去りにして進んでいく、そういう季節なのかもしれません。
音楽は、不思議な力を持っています。数十年前に聴いた曲でも、メロディーが流れれば、その頃の情景や感情が一瞬にして蘇る。この小説は、まさにその音楽の魔法を巧みに使いながら、読者一人ひとりの記憶の扉を開けてくれます。「あなたの『あの歌』は何ですか?」そう問いかけられているような気がしました。
シュウたちが生きた時代は、私が直接経験した時代とは少しずれているかもしれません。それでも、彼らが感じたであろう友情の喜びや痛み、恋のときめきや切なさ、大人になることへの不安は、世代を超えて共感できる普遍的な感情です。だからこそ、「あの歌がきこえる」は、多くの人の心に響き続けるのでしょう。
読み終えて改めて思うのは、友だちとは、そして青春とは何だったのか、ということです。いつも一緒にバカなことをして笑い合った日々。時にはぶつかり、傷つけ合い、それでも離れがたく感じた絆。進む道が分かれても、心のどこかで繋がっている感覚。そうしたものが、甘酸っぱいメロディーと共に胸に込み上げてきます。
重松清さんは、決して声高に何かを主張するわけではありません。ただ、そこに生きた人々の姿を、彼らが聴いた音楽と共に、丁寧に描き出すだけです。しかし、その静かな筆致の中に、人生の複雑さや愛おしさ、そして人が生きていく上で抱える切実な想いが、確かに込められています。だからこそ、読み手の心に深く、長く残り続けるのだと思います。
もし、あなたが青春時代に夢中になった歌があるなら、忘れられない友人がいるなら、そして少しだけ昔を懐かしみたい気持ちになっているなら、「あの歌がきこえる」を手に取ってみてください。きっと、あなたの心の琴線に触れる「あの歌」が、この物語の中からきこえてくるはずです。それは、遠い日の自分からのメッセージかもしれません。
まとめ
重松清さんの小説「あの歌がきこえる」は、1970年代後半から1980年にかけての地方都市を舞台に、シュウ、コウジ、ヤスオという3人の少年たちの友情と成長を描いた青春物語です。彼らの多感な時期が、当時の流行歌と共に瑞々しく、そして切なく綴られています。
物語には、高校受験による友人との別れ、家庭の事情による親友の変化、不良になった同級生との複雑な関係、そして父親の挫折を通して知る大人の現実など、青春時代特有の様々な出来事が織り込まれています。これらの経験を通して、主人公のシュウは少しずつ大人への階段を上っていきます。
各章のタイトルにもなっているユーミン、サザン、さだまさし、ジョン・レノンといったアーティストたちの名曲が、物語の情景や登場人物の心情と深くリンクし、作品に特別な彩りを与えています。音楽が、個人の記憶や時代の空気を呼び覚ます力を持っていることを改めて感じさせてくれます。
読者は、シュウたちの物語を通して、自身の青春時代や、当時聴いていた音楽、大切な友人たちのことを思い出すかもしれません。世代を超えて共感できる友情、家族、成長といったテーマが、温かくも切ない筆致で描かれており、読後には深い感動とノスタルジーが残る、心に残る一冊と言えるでしょう。
































































