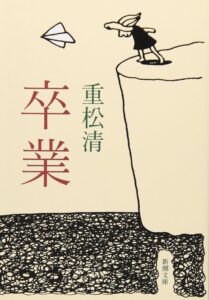 小説「卒業」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。重松清さんの作品は、いつも私たちの心の琴線に触れる何かがありますよね。「流星ワゴン」や「その日の前に」などで描かれた家族の絆や人生の機微は、この「卒業」という短編集にも通底しています。
小説「卒業」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。重松清さんの作品は、いつも私たちの心の琴線に触れる何かがありますよね。「流星ワゴン」や「その日の前に」などで描かれた家族の絆や人生の機微は、この「卒業」という短編集にも通底しています。
「卒業」と聞くと、学校を終える、あの春の少し切なくて、でも希望に満ちた風景を思い浮かべる方が多いかもしれません。桜の花びらが舞う中で、友との別れを惜しみつつ、新しい道へと歩み出す、そんな爽やかなイメージです。
しかし、重松さんが描く「卒業」は、それだけではありません。もっと深く、私たちの人生における様々な「区切り」や「終わり」、そしてそこからの「新たな始まり」を描いています。それは時に温かく、時にほろ苦く、そしてどうしようもなく人間らしい物語たちなのです。
この短編集には、四つの異なる家族の物語が収められています。それぞれの物語が「卒業」というテーマを異なる角度から描き出し、読み終えた後には、静かだけれど確かな感動と、自身の人生や家族について深く考えさせられる、そんな余韻を残してくれます。これから、その物語の核心に触れながら、私の心に響いた部分を丁寧にお伝えしていきたいと思います。
小説「卒業」のあらすじ
この短編集「卒業」は、人生の様々な局面における「終わり」と「始まり」を描いた四つの物語から構成されています。それぞれが独立した物語でありながら、「卒業」という共通のテーマで繋がっており、家族の形や人との繋がり、そして生と死について深く考えさせられます。
最初の物語「まゆみのマーチ」では、エリート街道を進む兄・幸司と、少し風変わりな妹・まゆみの関係が描かれます。まゆみは小学生の頃、歌が好きすぎて授業中でも鼻歌を歌ってしまい、先生からマスク着用を命じられます。それが原因で心を閉ざし不登校になってしまったまゆみを、母は自作の「まゆみのマーチ」を歌いながら励まし、再び学校へ通えるように導きました。時が経ち、幸司の息子・亮介が受験に成功したものの、燃え尽き症候群で不登校になってしまいます。幸司は、かつて母がまゆみにしたように、亮介を支えようと試みます。これは母からの愛情の卒業、そして息子への愛情の継承の物語とも言えるでしょう。
続く「仰げば尊し」は、小学校教師の光一が主人公です。彼の父は病で余命いくばくもなく、自宅療養をしています。一方、光一のクラスには、死に異常な関心を持つ生徒・田上康弘がいました。光一は「命の授業」として、康弘たち生徒に父の介護を手伝わせることを思いつきますが、他の生徒や保護者からの反発を受け、中止に追い込まれます。しかし、康弘だけは真剣に介護に参加していました。ある日、康弘が父の姿を写真に撮ろうとしたことで、光一は彼を拒絶してしまいます。死とは何か、命の尊さとはどう教えるべきか、そして人の死にどう向き合うべきか、重い問いを投げかける作品です。
三番目の「卒業」は、表題作であり、中学二年生の少女・亜弥が主人公です。亜弥は学校でのいじめを苦にして自殺未遂を起こします。実は亜弥の父親も過去に自殺しており、そのことが影を落としています。亜弥の母は、娘を必死に支えようとしますが、周囲からは「親が自殺したから子どもも」という無理解な視線に晒されます。親の死が子どもに与える影響、そして残された家族がどのようにその事実と向き合い、乗り越えていくのか、繊細な心の動きが描かれます。生きていくことの難しさ、そしてそれでも希望を見出そうとする姿が印象的です。
最後の「追伸」は、幼い頃にガンで母親を亡くした作家志望の青年・敬一の物語です。彼は、亡き母が遺した闘病日記を心の支えにしていましたが、父の再婚相手である新しい母・ハルさんとの関係に悩み、「お母さん」と呼ぶことができません。仕事で母親に関するエッセイを書くことになるものの、そこに描かれるのは実体験とは異なる理想化された母親像でした。ハルさんとの間にあったわだかまりが、ある出来事をきっかけに少しずつ変化していきます。亡き母への想いからの卒業、そして新しい家族との関係構築という、心の成長が描かれています。
これらの物語は、それぞれ異なる状況を描きながらも、人が何かから「卒業」し、新たな一歩を踏み出す際の痛みや葛藤、そしてその先にある希望や愛情を丁寧に描き出しています。読む人自身の経験や感情と重なり合い、深い共感を呼ぶ作品集です。
小説「卒業」の長文感想(ネタバレあり)
重松清さんの「卒業」を読み終えて、心の中にじんわりと広がる温かさと、少しの切なさが残りました。四つの物語は、どれも「卒業」という言葉が持つ多層的な意味合い…学校からの旅立ちだけでなく、人生における様々な別れや区切り、そしてそこからの再生を見事に描き出していました。ここからは、各編について、ネタバレを含む形で、私の心に響いた部分を詳しくお話しさせてください。
まず「まゆみのマーチ」。この物語で描かれるのは、幸司とまゆみという兄妹、そして彼らの母親の姿です。しっかり者の兄と、どこか掴みどころのない妹。まゆみが授業中に鼻歌を歌うのをやめさせるために、先生がマスクをつけさせた、というエピソードは、現代にも通じる、少し息苦しい「正しさ」のようなものを感じさせます。先生の立場からすれば、授業の進行や他の生徒への配慮という点で、苦肉の策だったのかもしれません。しかし、その「解決策」がまゆみの心を深く傷つけ、不登校へと繋がってしまった。この部分で、何が本当に「正しい」ことなのか、誰にとっての「正しさ」なのかを考えさせられました。
先生は、まゆみの鼻歌を止めることには成功したけれど、その代償としてまゆみが抱えた心の痛みには気づけなかった、あるいは気づく余裕がなかったのかもしれません。ここに、集団の中での個性の扱い方や、教育現場の難しさが見て取れます。一方で、まゆみの母親が素晴らしい。彼女は、世間の基準や学校のルールといったものから少し離れた場所で、ただひたすらに娘の心に寄り添おうとします。「まゆみのマーチ」というオリジナルの歌で、娘を励まし、再び歩き出す力を与える。この母親の無償の愛、娘を丸ごと受け入れる姿勢には、心を打たれずにはいられません。
そして、物語は時を経て、幸司の息子・亮介がまゆみと同じような状況に陥るところで、テーマがより深まります。優秀な学校に入ったものの、燃え尽きて学校に行けなくなってしまった亮介。幸司は、かつて母がまゆみにしてくれたように、亮介を支えようとします。ここで描かれるのは、親から子へと受け継がれる愛情の連鎖です。幸司自身も、エリートとして生きてきた中で見失いかけていた大切なもの、つまり、誰かを無条件に支え、励ますという母の姿を思い出し、実践しようとする。これは、幸司自身の過去からの「卒業」であり、新しい父親としての役割への「始まり」でもあるように感じられました。まゆみが最後まで幸司に「まゆみのマーチ」のメロディーを教えなかったのに、最終的には教えていたという部分。これは、亮介を励ますために、幸司に「亮介のマーチ」を歌ってほしいという、まゆみなりの愛情表現だったのかもしれませんね。幸司が亮介をおんぶして学校へ連れて行こうとする姿は、不器用ながらも、母から受け継いだ愛情を彼なりに表現しようとしているようで、胸が熱くなりました。
次に「仰げば尊し」。この物語は、より直接的に「死」というテーマと向き合っています。小学校教師の光一が、死にゆく父の姿と、死に異常な関心を示す生徒・康弘との間で葛藤する姿が描かれます。光一が「命の授業」として、生徒に父の介護を手伝わせるという試みは、非常に大胆であり、賛否両論あるでしょう。実際に、他の生徒や保護者からは強い反発を受けます。死にゆく人間の生々しい姿を子どもたちに見せることの是非。これは本当に難しい問題です。
しかし、康弘だけはその授業に真剣に取り組みます。彼がただの好奇心から死に関心を持っていたわけではないことが、徐々に明らかになっていきます。彼が父の姿を写真に撮ろうとした行為は、一見すると不謹慎極まりない。光一が激怒し、彼を拒絶するのも無理はありません。しかし、康弘はネットに載せるためなどではなく、何か別の、彼なりの理由があったのかもしれない。その真意が明確に語られないところに、この物語の深さがあるように思います。もしかしたら、彼は消えゆく命の姿を、自分なりに留めておきたかったのかもしれません。
光一自身もまた、父の死を前にして、死とは何か、どう向き合うべきか悩み続けます。「死ぬことは消えることでも無くなることでもなく、人の心に残ることだと思う」という彼の考えには、共感する部分が多くありました。人は肉体的には消滅しても、誰かの記憶や心の中で生き続ける。康弘の行動も、もしかしたらそうした「残す」ための一つの形だったのかもしれない、と後から考えさせられました。この物語は、安易な答えを与えず、読者一人ひとりに「死」について深く考えることを促します。教育現場における「命の授業」の難しさ、そして家族の死を目前にした個人の葛藤が、リアルに描かれていました。
三番目の表題作「卒業」。この物語は、中学生の亜弥の自殺未遂という、非常にショッキングな出来事から始まります。彼女がいじめを苦にしていたという背景、そして父親が過去に自殺していたという事実が重くのしかかります。作中で示唆される「親の自殺が子どもに伝染する」というような考え方には、正直、強い違和感を覚えました。それはあまりにも短絡的で、残された家族をさらに苦しめる偏見ではないでしょうか。亜弥が死を選ぼうとしたのは、父親の影響というよりも、今、彼女が直面しているいじめという現実的な苦しみがあったからだと感じます。
しかし、親が自ら命を絶ったという事実は、やはり子どもにとって計り知れない影響を与えるのでしょう。亜弥がその事実をどのように受け止め、向き合っているのか。そして、母親が娘を支えながら、周囲の無理解な視線とどう戦っているのか。その描写は読んでいて胸が痛みました。特に、夫を自殺で亡くした妻に対して、「なぜ支えてやれなかったのか」というような非難が向けられることがある、という現実は、本当に息苦しいものだと感じます。残された者は、ただでさえ深い悲しみと喪失感の中にいるのに、さらに追い詰められてしまう。
この物語は、そうした過酷な状況の中で、母娘がどのように絆を確かめ、生きていく希望を見出そうとするかを描いています。亜弥が少しずつ前を向こうとする姿、そしてそれを懸命に支える母親の姿には、人間の持つ強さや再生への意志を感じます。ここでの「卒業」は、過去のトラウマや、世間の偏見からの卒業、そして自分自身の弱さからの卒業、という意味合いを持っているのかもしれません。簡単に乗り越えられるものではないけれど、それでも生きていくことを選ぶ、その決意のようなものが伝わってきました。
最後に「追伸」。これは、亡き母への思慕と、新しい母との関係に悩む青年・敬一の物語です。幼い頃に実母を亡くし、その母が遺した闘病日記を宝物のように大切にしている敬一。しかし、父の再婚相手であるハルさんを「お母さん」と呼べず、わだかまりを抱えています。この気持ち、すごくよく分かります。頭では理解しようとしても、心が追いつかない。特に、亡くなった母親への強い想いがあればあるほど、新しい母親を受け入れるのは難しいでしょう。
敬一が作家志望で、母親に関するエッセイを書くことになる、という設定も興味深い。彼は、読者が期待するような「感動的な母と子の物語」を、フィクションとして書き上げます。そこには、彼自身の複雑な感情や、ハルさんとのぎくしゃくした関係性は描かれません。これは、彼がまだ本当の意味で過去と向き合えていないことの表れでもあるのでしょう。亡き母を理想化し、現実の(新しい)母との間に壁を作ってしまっている。
そんな敬一とハルさんの関係が、ある出来事をきっかけに変化していきます。ハルさんが、敬一の宝物である日記を取り上げ、「お母さん」と呼べば返す、と言う場面。これは一見、意地悪なようにも見えますが、見方を変えれば、ハルさんなりの不器用な歩み寄りだったのかもしれません。彼女もまた、敬一との関係をどう築けばいいのか悩み、もがいていたのではないでしょうか。引用されていた編集者の「親子って、もっとざらざらしてると思うんですよ」という言葉が、まさにこの物語の核心を表しているように感じます。綺麗ごとだけではない、ぶつかり合い、傷つけ合いながらも、それでもどこかで繋がっている。それが家族というものなのかもしれません。
最終的に、敬一はハルさんとの関係を少しずつ修復していきます。それは、亡き母への想いを捨てることではなく、その想いを抱えたまま、新しい現実を受け入れ、前に進むということ。亡き母からの、そして過去の自分からの「卒業」。そして、ハルさんという新しい家族との関係における「始まり」。この物語は、血の繋がりだけではない、人と人との関係性の築き方、そして心の成長を温かく描いていて、読後感がとても良かったです。
「卒業」という短編集は、人生における様々な「終わり」が、必ずしも悲しいだけのものではなく、新たな「始まり」への扉でもあることを教えてくれます。それは、学校の卒業のような華々しいものばかりではなく、もっと個人的で、内面的な変化や成長を伴うものです。家族との関係、自分自身の過去、そして避けられない「死」というもの。そうしたものと向き合い、受け入れ、そして乗り越えていく過程が、重松さんならではの温かくも鋭い視点で描かれていました。登場人物たちの葛藤や痛みに共感し、彼らがささやかな希望を見出す姿に、励まされるような気持ちになりました。読後、自分の人生や大切な人たちとの関係について、改めて考えさせられる、そんな深い余韻の残る作品集でした。
まとめ
重松清さんの小説「卒業」は、「卒業」という言葉が持つ、学校生活の終わりだけではない、もっと広くて深い意味…人生における様々な区切りや変化、そしてそこからの新たな出発を、四つの異なる物語を通して描き出した短編集です。
各編で描かれるのは、家族の絆、親子の愛情、生と死との向き合い方、そして過去を乗り越えていくことの難しさと尊さです。不登校になった妹を支えた母の愛を受け継ぐ兄、死にゆく父と死に関心を持つ生徒の間で揺れる教師、親の自殺という重い過去と向き合う少女、そして亡き母への想いと新しい母との間で葛PLINGする青年。彼らの物語は、時に切なく、時に温かく、私たちの心に深く響きます。
これらの物語は、決して綺麗ごとだけを描いているわけではありません。むしろ、人間関係のざらざらした部分や、どうしようもない葛藤、逃れられない現実といった、生きていく上での困難さが丁寧に描かれています。だからこそ、登場人物たちが悩み、苦しみながらも、ささやかな光を見出し、一歩を踏み出そうとする姿に、私たちは強く共感し、励まされるのかもしれません。
読み終えた後には、爽やかな感動というよりは、じんわりと心に染み入るような温かさと、自身の人生や家族、そして様々な「卒業」について静かに思いを馳せる時間が訪れるでしょう。重松清さんの作品が好きな方はもちろん、人生の岐路に立っている方、家族との関係について考えている方にとっても、心に残る一冊となるはずです。
































































