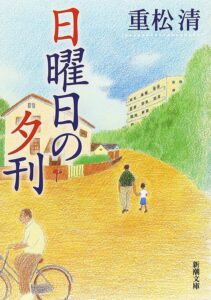 小説「日曜日の夕刊」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「日曜日の夕刊」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
重松清さんの作品に触れると、いつも私たちのすぐそばにある日常の、なんとも言えない温かさや、時には胸が締め付けられるような切なさを感じさせてくれますよね。「日曜日の夕刊」も、まさにそんな重松さんらしい魅力が詰まった一冊です。このタイトル、初めて見た時「あれ?日曜日に夕刊ってあったっけ?」なんて思った方もいるかもしれません。そのちょっとした違和感が、物語の世界への入り口なのかもしれませんね。
この本は、全部で12の短いお話が集まった短編集です。ひとつひとつのお話は独立しているんですが、読み進めていくうちに、登場人物たちの抱える悩みや喜び、そして家族や誰かを想う気持ちが、静かに、でも確かに伝わってきて、心に響きます。どのお話も、私たちの日常とどこか重なる部分があって、「ああ、こういう気持ちわかるなあ」とか「こんなことあったなあ」と感じさせてくれるはずです。
この記事では、そんな「日曜日の夕刊」に収められた12編の物語について、詳しい物語の流れ、そして結末まで触れながらお話ししていきます。さらに、私自身がこの本を読んでみてどう感じたのか、心に残ったことなどを、少し長くなるかもしれませんが、正直な気持ちを込めて書いてみました。まだ読んでいない方にとっては、物語の結末を知ってしまうことになる部分もありますので、その点だけご了承くださいね。
小説「日曜日の夕刊」のあらすじ
「日曜日の夕刊」は、私たちの周りにいるような、ごく普通の人々の日常に起こる、ささやかな、でも忘れがたい出来事を描いた12編の物語を集めた作品集です。タイトルにある「日曜日の夕刊」は、現実には存在しないものですが、だからこそ、そこには日常の中に潜む、ちょっと特別な瞬間や、普段は見過ごしてしまいがちな大切な感情が込められているのかもしれません。
例えば、「チマ男とガサ子」というお話では、几帳面すぎる男性と、おっちょこちょいな女性という、正反対な二人が出会い、ぶつかり合いながらも、少しずつ距離を縮めていく様子が描かれます。最初は互いの欠点ばかりが目についていたのに、ある出来事をきっかけに、相手を受け入れ、共に歩んでいこうとする姿には、思わず応援したくなる温かさがあります。
また、「カーネーション」では、母の日に電車で偶然乗り合わせた、それぞれに事情を抱えた男女三人の物語が展開されます。網棚に忘れられた一輪のカーネーションをめぐり、三人の心の中には、母親への複雑な想いや、現在の自分の状況が映し出されます。そして、思わぬ出来事を通して、彼らの心に小さな変化が訪れるラストは、胸にじんわりと響きます。
他にも、父親との関係に悩む娘を描いた「柑橘系パパ」、浪人生の青年がクリスマスに出会った少女との不思議な一夜を描く「サンタにお願い」、いじめという過去の記憶に向き合うことになった同窓会の夜を描いた「後藤を待ちながら」など、収録されている物語は多岐にわたります。
少年野球チームの監督を務める父親と、その息子である少年の最後の試合を描いた「卒業ホームラン」では、勝敗だけではない、スポーツを通して得られる大切なものや、親子の絆が感動的に描かれています。父として、監督として葛藤する姿、そして息子の純粋な「野球が好き」という気持ちが、読む人の心を打ちます。
これら12編の物語は、それぞれ異なる主人公、異なる状況を描いていますが、どの物語にも共通して流れているのは、うまくいかないことや、寂しさ、後悔を抱えながらも、懸命に日々を生きる人々の姿と、その中に見出す小さな希望や、人との繋がりの温かさです。派手な事件が起こるわけではありませんが、読後には、自分の日常や周りの人々を、少しだけ優しい気持ちで見つめ直したくなるような、そんな読書体験を与えてくれます。
小説「日曜日の夕刊」の長文感想(ネタバレあり)
「日曜日の夕刊」を読み終えて、まず感じたのは、やはり重松清さんならではの、人の心の襞(ひだ)を丁寧にすくい取るような眼差しの温かさでした。12編の物語は、どれも私たちの日常の延長線上にあるような出来事を描いていて、登場人物たちの喜びや悲しみ、迷いや決意が、まるで自分のことのように感じられる瞬間がたくさんありました。読みながら、何度も胸が熱くなったり、ふと考えさせられたり…。読み終わった後も、物語の風景や登場人物たちの言葉が、心の中に静かに残り続ける、そんな作品集でしたね。ここからは、物語の結末にも触れながら、各短編について感じたことを詳しくお話ししていきたいと思います。
第1話「チマ男とガサ子」
几帳面すぎる「チマ男」くんと、どこか抜けている「ガサ子」さん。最初は「この二人、大丈夫かな?」なんて思いながら読んでいました。チマ男くんの細かすぎる指摘に、ガサ子さんじゃなくても「もう!」って言いたくなる気持ち、よく分かります(笑)。玄関に確認リストを貼るなんて、私も似たようなこと、やったことあるかも…。でも、そんな二人が、互いの欠点も含めて受け入れ合っていく過程が、とても微笑ましく、そして素敵でした。特に、最後のプロポーズの場面。「がさつなところも含めて、君がいい」というストレートな言葉、定番かもしれないけれど、やっぱり心に響きました。完璧じゃないからこそ、惹かれ合い、支え合える。そんな関係性の良さを感じさせてくれるお話でした。個人的なお気に入り度は高いです。
第2話「カーネーション」
母の日に、電車の中で出会った三人の男女。それぞれが抱える母親への想いや、自身の状況が、網棚の一輪のカーネーションを通して交錯していく様子が印象的でした。再婚相手を子供に紹介しようとする父親、居場所のない女子高生、認知症の母を持つ男性。彼らが、傍若無人な若者からカーネーションを守ろうと、咄嗟に声を合わせる場面は、バラバラだった三人の心が、一瞬重なったように感じられて、ぐっときました。そして、終点で降りた後のそれぞれの行動。特に、父親の誠司さんが家に帰り、子供たちが用意していたサプライズには、思わず涙腺が緩んでしまいました。亡くなったお母さん(妻)への想いが、ちゃんと子供たちに受け継がれている。その事実に、救われるような気持ちになりました。最後の最後で、物語の温かさが一気に込み上げてくる、そんな構成が見事でした。
第3話「桜桃忌の恋人」
大学に入学したばかりの広瀬くんと、太宰治マニアの少し危うい雰囲気を持つ永原さん。広瀬くんが太宰の「宰」の字を間違えて書いたことから始まる、ちょっと変わった関係性のお話です。永原さんが広瀬くんを太宰の生まれ変わりだと思い込み、危うい行動を繰り返す展開には、正直少しハラハラしました。彼女の抱える孤独や心の歪みが痛々しく感じられます。でも、最後、彼女が一人で太宰の後を追ってしまった後、残された広瀬くんがとった行動が、この物語を単なるホラーや悲劇で終わらせていないと感じました。彼は、永原さんの存在をただ忘れるのではなく、彼女が好きだった太宰の作品を読み始める。それは、彼女への追悼であり、彼女が生きた証を受け止めようとする行為のように思えました。読後感は少し複雑ですが、心に残るものがありました。
第4話「サマーキャンプへようこそ」
頭の良い小学生の圭太くんと、アウトドアが苦手なパパ。子供らしくない息子を心配する母親の計らいで参加したサマーキャンプでのドタバタ劇です。正直に言うと、私自身はこのお話、少し苦手かもしれませんでした。パパの不器用さや、周りの家族との対比が、読んでいて少し辛く感じてしまったんです。でも、圭太くんの大人びた言動の中に垣間見える子供らしさや、父親を気遣う優しさが救いでした。キャンプを通して、二人の関係が劇的に変わるわけではないけれど、少しだけお互いを理解し合えたような、そんな小さな変化が描かれている点に、重松さんらしさを感じました。子供を持つ親の立場になったら、また違った感想を持つのかもしれません。
第5話「セプテンバー’81」
37歳の誕生日を迎えた男性が、19歳の頃の誕生日の出来事を回想するお話。仲間とディスコで過ごした夜、不思議なカラスとの出会い…。若かった頃の、どこか自由で、少し無鉄砲だった日々へのノスタルジーが、切なくも温かく描かれています。30年ローンで買ったマンションという現実と、キラキラしていた(ように思える)過去との対比が、人生の時間の流れを感じさせます。「あの頃、出会ったあの子はどうしているだろう?」そんな風に、ふと過去を振り返ってしまう気持ち、男性ならずとも、誰にでもあるのではないでしょうか。少しセンチメンタルな気分に浸れる、そんな物語でした。
第6話「寂しさ霜降り」
父親に捨てられた過去を持つ姉妹のお話。過食症になってしまった姉と、そんな姉を見守る妹。父親が危篤だと知らされた姉が、突然猛烈なダイエットを始める展開には、最初、正直戸惑いました。「なぜ今、痩せようとするんだろう?」と。妹と同じように、父親に痩せた姿を見せてやりたいという復讐心なのかとも思いましたが、読み進めるうちに、それは違うのかもしれないと感じました。彼女は、父親と別れた「あの頃の自分」に戻ろうとしたのかもしれません。それは、失われた時間を取り戻そうとする、痛々しくも切実な願いだったのではないでしょうか。結末は少しやるせないものでしたが、家族というものの複雑さ、愛憎の深さを考えさせられる物語でした。
第7話「さかあがりの神様」
弟が生まれ、少し寂しい思いをしている娘のために、父親が逆上がりの練習を手伝うお話。父親自身も、かつて再婚相手である義父(逆上がりの神様と呼ばれていた)に、同じように逆上がりを教えてもらった経験がありました。自分が子供の頃に受けた不器用だけれど温かい支えを、今度は自分の娘にしてあげる。その世代間の優しい連鎖が、とても素敵だと感じました。特に、父親が娘の手を「ソッ」と添える描写。力ずくで教えるのではなく、ただ傍にいて、静かに支える。その距離感が絶妙で、親子の温かい絆を感じさせてくれます。物語の中に、父親自身の故郷や家族(亡くなった母、疎遠な義父や弟)の話も織り込まれていて、短編ながら深みのある物語になっていると思います。読後、心がじんわりと温かくなる、良いお話でした。
第8話「すし、食いねェ」
誕生日のプレゼントを巡って喧嘩してしまった夫婦と、その息子・翔太くんのお話。母親の企みで、テレビ番組の企画(庶民が高級寿司店で戸惑う様子を笑う、という悪趣味なもの)に参加させられてしまう父親と翔太くん。正直、こういう展開は読んでいてハラハラしますよね。恥をかかされるのが分かっている状況というのは、どうにも落ち着きません。でも、結果的には、この出来事が家族の絆を再確認するきっかけになるのが、この物語の救いであり、面白さでもあります。特に、翔太くんがお寿司屋さんで臆することなく振る舞う姿や、父親を気遣う言葉には、子供の純粋さや強さを感じました。最後は、喧嘩していた夫婦も仲直りし、家族の温かさが戻ってくる。少しドキドキする展開でしたが、読後感は悪くありませんでした。
第9話「サンタにお願い」
クリスマス間近、予備校に行かずピザの配達バイトをする浪人生と、援助交際で得たお金の使い道に困るギャルの女の子との出会いを描いた物語。サンタの格好をした浪人生が、少女の「誰もいない学校に行きたい」という願いを叶えるために、夜の校舎に忍び込む。そこで語られる少女の家庭の事情や、孤独。最初は危うい関係に見えましたが、浪人生の青年が思いついた「プレゼント」が、とても温かくて、素敵でした。少女が援助交際で得たお金を、匿名で父親(学校の先生)の机に入れてあげるという計画。それは、お金という形ではなく、父親への想いを伝えるための、彼なりの精一杯の優しさだったのだと思います。物語のテンポも良く、浪人生の青年のモノローグも共感できる部分が多くて、個人的にはかなり好きなお話です。読んだ後、なんだか心がスッとするような、爽やかな気持ちになりました。
第10話「後藤を待ちながら」
中学時代の同窓会で、「いじめていた」後藤くんが来るかもしれない、とざわつく元クラスメイトたち。「いじめていたわけじゃない、遊んでいただけだ」と言いながらも、誰もが罪悪感を抱えている。そんな中、主人公の息子がいなくなってしまう…。いじめという重いテーマを扱いながら、過去の過ちとどう向き合うか、そして親になったからこそ気づくことを描いた物語です。同窓生たちの会話や、主人公の心の揺れ動きが、非常にリアルに感じられました。子供の頃の無邪気な残酷さと、大人になってからの後悔。誰もが心のどこかに抱えているかもしれない、チクッとした痛みを思い出させるようなお話です。息子を探しながら、後藤くんを待つ主人公たちの焦燥感。結末で、いじめに対する明確な答えが示されるわけではありませんが、過去から逃げずに向き合うことの大切さ、そして子供を守ろうとする親の必死な想いが伝わってきました。
第11話「柑橘系パパ」
単身赴任から帰ってきた父親に、どう接していいか分からず戸惑う中学3年生の娘・ヒトミの物語。母親と二人で築いてきた生活リズムの中に、突然「異物」のように父親が入ってきた違和感。嬉しそうな母親への反発。思春期の娘の複雑な感情が、痛いほど伝わってきます。消臭剤を手に、父親の存在という「異臭」を取り除こうとするヒトミの行動は、少しショッキングですが、それだけ彼女が混乱し、苦しんでいるということなのでしょう。父親からすれば、娘に嫌われているようで、とても寂しい状況だと思います。私自身も、姪っ子に小さい頃は懐かれていたのに、年頃になったら急に避けられるようになって、寂しい思いをした経験があるので、ヒトミの父親の気持ちも少し分かる気がします。家族の関係性が時間と共に変化していくことの難しさ、切なさを感じさせる物語でした。
第12話「卒業ホームラン」
少年野球チームの監督を務める父親と、その息子・智くんの最後の試合を描いた物語。これがもう、本当に素晴らしかった。父親としては、息子に最後の試合に出してあげたい。でも監督としては、チームの勝利を優先しなければならない。その葛藤が痛いほど伝わってきます。結局、父親は監督としての判断を優先し、智くんをベンチから外してしまう。そして試合は惨敗。「あそこで智を出してやればよかった」と後悔する父親に、智くんが言った言葉。「中学でも野球をやるよ」「だって、ぼく、野球好きだもん」。この言葉に、私は完全に心を掴まれました。勝つことや、レギュラーになることだけが全てじゃない。ただ「好き」だから続ける。その純粋な気持ちこそが、何よりも尊いのだと、改めて教えられた気がしました。私自身も、決して上手くはなかったけれど、ただ好きで続けていた習い事があったことを思い出し、胸が熱くなりました。「頑張れば必ず報われる」わけではないけれど、「好き」という気持ちがあれば、人は前に進んでいける。そんな力強いメッセージを感じさせてくれる、感動的な物語でした。この短編集の最後にこの話があることで、読後感がとても清々しいものになったと思います。
「日曜日の夕刊」は、派手さはないけれど、心に深く染み入る物語ばかりでした。登場人物たちの抱える痛みや寂しさに寄り添いながらも、決してそれだけで終わらせず、その先に微かな光や希望、人との繋がりの温かさを描き出しているところに、重松清さんの真骨頂を感じます。日常の中で見過ごしてしまいがちな、でも本当はとても大切な感情や出来事を、もう一度見つめ直すきっかけを与えてくれる、そんな素敵な作品集でした。
まとめ
重松清さんの短編集「日曜日の夕刊」、いかがでしたでしょうか。この記事では、12編それぞれの物語の詳しい流れや結末、そして私が感じたことを詳しくお伝えしてきました。存在しないはずの「日曜日の夕刊」というタイトルが示すように、ここには日常の中に隠された、少し特別で、心に残る瞬間が詰まっています。
一つ一つのお話は短く、読みやすいのですが、描かれているテーマは、家族の絆、人生の選択、過去との向き合い方、そして「好き」という気持ちの力など、深く考えさせられるものばかりです。几帳面な男と大雑把な女の恋模様、母の日に電車で交錯する想い、父と子の不器用な関係、少年野球の最後の試合…。登場人物たちの悩みや喜びが、まるで自分のことのように感じられ、読み終えた後には、温かい気持ちや、少し切ない気持ちが心に残ります。
特に印象的だったのは、やはりどの物語にも通底する、登場人物たちへの優しい眼差しです。うまくいかないことや、悲しいことがあっても、それでも前を向こうとする人々の姿に、勇気づけられるような気がしました。また、「卒業ホームラン」で描かれたように、「好き」という純粋な気持ちの大切さを改めて教えてくれたことも、この本を読んで良かったと感じた点です。
もし、あなたが日々の生活に少し疲れていたり、家族や大切な人との関係について考えたりする時間が必要だと感じていたりするなら、この「日曜日の夕刊」は、きっと心に寄り添ってくれるはずです。重松清さんの他の作品にも、心温まる物語がたくさんありますので、この本をきっかけに、さらに読み進めてみるのも良いかもしれませんね。
































































