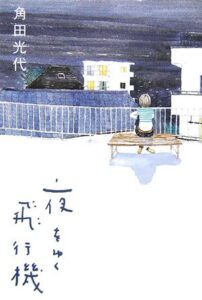 小説「夜をゆく飛行機」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんの描く家族の物語は、いつも私たちの心のどこか柔らかい部分に触れてくるような気がします。この作品もまた、読む人の心に静かな波紋を広げる力を持っていると感じました。
小説「夜をゆく飛行機」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんの描く家族の物語は、いつも私たちの心のどこか柔らかい部分に触れてくるような気がします。この作品もまた、読む人の心に静かな波紋を広げる力を持っていると感じました。
物語の中心となるのは、東京の下町で酒屋を営む谷島家。四人の姉妹とその両親が織りなす日常と、そこに訪れる変化の兆しが、末娘である里々子の視点を通して淡々と、しかし深く描かれています。誰もが経験するかもしれない家族の関係性の移ろいや、個々の成長、そして避けられない別れ。そういった普遍的なテーマが、谷島家という一つの家族の肖像を通して、私たち自身の経験や感情と重なり合ってくるのです。
この記事では、まず「夜をゆく飛行機」の物語の筋道を、結末に触れる部分も含めて詳しくお伝えします。物語の展開を知りたい方、あるいは読後に内容を振り返りたい方にとって、参考になるかと思います。
そして後半では、私がこの物語を読んで何を感じ、どう考えたのかを、ネタバレを気にせずに率直に書き連ねていきます。登場人物たちの魅力や、心に残った場面、作品全体から受け取ったメッセージなど、個人的な思い入れを込めて語っていきたいと思います。少し長くなりますが、お付き合いいただけると嬉しいです。
小説「夜をゆく飛行機」のあらすじ
物語は1999年の秋、東京都内の古くからの商店街で酒屋「谷島酒店」を営む谷島家から始まります。語り手は、四人姉妹の末っ子で高校三年生の里々子(りりこ)。彼女には、長女で結婚して家を出た有子(ありこ)、引きこもりがちな次女の寿子(ことこ)、読者モデルに憧れる活発な三女の素子(もとこ)という三人の姉がいます。それに加え、学歴に劣等感を抱く父・謙三と、母がいます。里々子は、現実にはいない弟「ぴょん吉」に心の中で語りかける癖がありました。
谷島家の日常は、一見すると平凡で変わり映えしないように見えます。しかし、時代の変化の波は確実に押し寄せ、近所に大型のショッピングセンターができたことで、古くからの酒屋の経営は厳しくなっていきます。そんな中、家族それぞれにも転機が訪れ始めます。まず、長女の有子が夫との関係に悩み、実家に出戻ってきます。彼女の存在は、それまでの家族の微妙なバランスを揺るがします。
次女の寿子は、内向的な性格で自室にこもりがちでしたが、自分の家族をモデルにした小説を書き上げ、それがなんと新人賞を受賞。突然の作家デビューは家族を驚かせ、特に他の姉妹に少なารからぬ影響を与えます。寿子の小説の内容が、現実の家族の関係性に波紋を広げる場面も見られます。
一方、三女の素子は、店の経営不振を打開しようと、ワインなども扱うおしゃれな「リカーショップヤジマ」への改装計画を立て、実現に向けて動き出します。彼女の積極性は、停滞気味だった家族に新たな風を吹き込みますが、同時に父親との意見の対立も生みます。また、素子は店の常連客だった大学生、松本健にアプローチされますが、里々子もまた、彼に淡い思いを寄せていました。
語り手である里々子自身も、高校三年生として大学受験を控えていますが、家族に次々と起こる出来事に心を乱され、なかなか勉強に集中できません。第一志望の大学の試験前日には、姉の有子の不倫調査のようなことに付き合わされ、結局受験に失敗。浪人生活を送ることになります。浪人中に出会ったアルバイト先の大学生、篠崎怜二に惹かれていく里々子ですが、その恋も一筋縄ではいきません。
そんな中、一家にとって大きな出来事が起こります。父の妹である叔母のミハルが急逝するのです。父の謙三は、なぜかその死を正月明けまで親戚に隠そうとします。この出来事は、家族それぞれに死や別れというものを改めて意識させ、谷島家の結びつき、そしてその脆さを浮き彫りにします。様々な出来事を経て、里々子は少しずつ自分の殻を破り、現実と向き合い始めます。心の中の弟「ぴょん吉」との対話も次第に減っていき、物語の終わりには、彼女なりの新たな一歩を踏み出す決意が描かれます。家族の形は変わりながらも、それぞれの人生は続いていくのです。
小説「夜をゆく飛行機」の長文感想(ネタバレあり)
角田光代さんの「夜をゆく飛行機」を読み終えて、まず感じたのは、じんわりと心に広がる、少しばかり切なくて、でも温かいような、複雑な感情でした。それは、かつて自分が過ごした家族との時間や、成長する中で経験した変化の記憶を呼び覚ますような感覚に近いかもしれません。特別な大事件が起こるわけではないけれど、日常の中に散りばめられた小さな出来事の積み重ねが、登場人物たちの心を、そして家族という関係性を、静かに、しかし確実に変えていく様子が、とても丁寧に描かれていると感じました。
物語の語り手である四女の里々子。彼女の視点を通して、私たちは谷島家の日常を覗き見ることになります。高校生から浪人生へという多感な時期を過ごす彼女の目線は、時に鋭く、時に感傷的で、家族や周りの人々に対する観察眼には、思わず頷いてしまうような的確さがあります。姉たちの行動に内心で毒づいたり、両親の老いや弱さを感じ取ったり。でも、それをストレートに口に出すことは少ない。彼女の内面に渦巻く苛立ちや戸惑い、そして愛情が、読者である私にもひしひしと伝わってきました。特に、彼女が心の中で対話する「ぴょん吉」の存在は、彼女の孤独や、現実から少し距離を置きたいという気持ちの表れなのかもしれないと感じました。
谷島家の四姉妹は、それぞれが個性的で魅力的です。結婚生活に問題を抱え、実家と夫の間で揺れ動く長女の有子。内向的でありながら、内に秘めた創作への情熱を開花させる次女の寿子。現実的で行動力があり、家の未来を考えて奔走する三女の素子。そして、物事を冷静に見つめながらも、恋や将来に悩む末っ子の里々子。彼女たちの姿は、決して特別な存在ではなく、どこにでもいる姉妹のようでありながら、それぞれが抱える問題や感情は、とてもリアルに感じられました。特に、寿子の小説が家族に与える影響は興味深い点でした。家族という身近な存在を題材にすることの難しさや、それが現実の関係に及ぼす微妙な変化が、巧みに描かれていたと思います。
この物語の大きなテーマの一つは、やはり「家族の変化」でしょう。子供たちが成長し、それぞれの道を歩み始めるとき、それまで当たり前だと思っていた家族の形は、否応なく変わっていきます。有子の出戻り、寿子の作家デビュー、素子の店のリフォーム計画、そして里々子の受験と恋愛。これらの出来事は、谷島家という安定していた(ように見えた)システムに波紋を投げかけ、家族一人ひとりが自立し、同時に家族という枠組みから少しずつ離れていく過程を描き出しています。それは寂しいことでもあるけれど、決して悪いことばかりではない。むしろ、変化を受け入れ、新しい関係性を築いていくための、必要なプロセスなのかもしれません。参考文章にあった「家族という幻想に別れを告げたあとには、きっと新しい関係が待っている」という言葉は、まさにこの物語の本質を捉えているように感じます。
父親の謙三というキャラクターも印象的でした。昔気質の頑固な部分があり、時代の変化についていけない不器用さも感じさせます。特に、叔母ミハルの死をしばらく隠そうとした行動は、一見すると理解しがたいものでしたが、彼の混乱や、家族を守ろうとする(あるいは、平静を保とうとする)彼なりのやり方だったのかもしれません。学歴コンプレックスを抱え、娘たちの成長に戸惑いながらも、父親としての威厳を保とうとする姿には、どこか哀愁が漂い、共感を覚える部分もありました。母親の存在は、父親や娘たちに比べると少し影が薄いように感じられましたが、彼女なりに家族の変化を見守り、支えている様子がうかがえました。
里々子の恋愛模様も、物語の重要な要素です。最初に登場する松本健への淡い思いと、その後アルバイト先で出会う篠崎怜二への強い惹かれ方。特に篠崎への恋は、浪人生という不安定な時期の彼女にとって、大きな心の支えであると同時に、悩みの種にもなります。彼の掴みどころのない態度や、他の女性の影に、里々子は一喜一憂します。このあたりの描写は、若い日の恋の苦しさや切なさを思い出させて、胸が締め付けられるようでした。しかし、この恋愛を通して、彼女は自分の感情と向き合い、相手との関係性の中で自分自身を見つめ直す機会を得たのではないでしょうか。
物語の舞台となっている1999年から2000年にかけての時代設定も、作品の雰囲気に影響を与えていると感じます。世紀末という漠然とした不安感や、新しい時代への期待感が漂う中で、古くからの商店街や酒屋といった、失われつつある風景が描かれていることに、ノスタルジーを感じずにはいられません。大型ショッピングセンターの出現による個人商店の衰退は、時代の流れを象徴しており、谷島家の変化とも重なって見えます。
里々子が時折見上げる「夜をゆく飛行機」のイメージは、この物語全体を象徴しているように思えます。遠くに見える飛行機の明滅は、手の届かない憧れや、どこかへ向かっていく変化の象徴であり、同時に、変わらない日常の中にある確かな存在のようにも感じられます。里々子自身も、そして谷島家全体も、まるで夜空を進む飛行機のように、それぞれの目的地に向かって、ゆっくりと、しかし確実に進んでいく。その過程は、時に心細く、孤独を感じさせるものであったとしても。
物語の終盤、里々子は大きな変化を遂げます。心の中の弟「ぴょん吉」は姿を消し、彼女は現実の世界で自分の足で立とうと決意します。失恋の痛みや受験のプレッシャーを乗り越え、彼女が見出した新たな目標(それは少々子供っぽいものではありますが)は、彼女が過去の感傷から抜け出し、未来へ向かおうとしている証拠でしょう。それは、劇的な成長というよりは、さなぎが蝶になるような、静かで自然な変化のように感じられました。この結末には、爽やかさと同時に、一抹の寂しさも覚えました。失われたものへの郷愁と、未来への希望が入り混じったような読後感です。
角田さんの文体は、淡々としていながらも、登場人物たちの細やかな感情の機微を巧みに捉えています。派手な表現や劇的な展開に頼ることなく、日常の会話や風景の描写を通して、物語の世界に深く引き込まれていきます。里々子の内面の声は、時に辛辣でさえありますが、その根底には家族への愛情や、自分自身へのもどかしさが感じられ、共感を呼びます。読みながら、登場人物たちの誰かに自分を重ね合わせたり、かつての自分の家族のことを思い出したりする人も多いのではないでしょうか。
特に心に残ったのは、家族が集まる場面の描写です。正月や法事など、親戚一同が集まる賑やかさの中に、微妙な人間関係や、世代間のギャップ、そして変わらない絆のようなものが垣間見えます。騒がしさの中にふと訪れる静寂や、何気ない会話の中に隠された本音など、家族という集団の持つ独特の空気感が、見事に表現されていると感じました。それは、心地よいものであると同時に、少し息苦しさを感じるものでもあり、非常にリアルでした。
参考文章にあったように、この作品の感想を書くのは、たしかに少し難しいかもしれません。明確なカタルシスがあるわけでもなく、善悪がはっきりしているわけでもない。ただ、そこにある家族の姿と、流れていく時間が描かれている。しかし、その「ただそこにある」という描写の中にこそ、深い味わいがあるのだと思います。読み手は、谷島家の出来事を追体験しながら、自分自身の人生や家族について、静かに思いを馳せることになるでしょう。
「夜をゆく飛行機」は、派手さはないかもしれませんが、読めば読むほど、登場人物たちの息遣いや、物語の持つ空気感が体に染み込んでくるような作品です。家族とは何か、成長とは何か、そして人生とは何か。そんな普遍的な問いについて、改めて考えさせてくれる力を持っています。読後、しばらくの間、谷島家の人々のことが頭から離れませんでした。彼らがこれからどんな人生を歩んでいくのか、想像せずにはいられませんでした。それは、この物語が、私たちの心の中に確かな何かを残してくれた証拠なのだと思います。
読み返すたびに、新たな発見や共感があるかもしれません。里々子の視点だけでなく、他の姉妹や両親の視点から物語を想像してみるのも面白いかもしれません。角田光代さんの作品の中でも、特にじっくりと味わいたい一冊だと感じています。家族という、当たり前だけれど複雑で、愛おしくて厄介な存在について、深く考えさせられる、忘れられない物語となりました。
まとめ
角田光代さんの小説「夜をゆく飛行機」は、東京の下町で酒屋を営む谷島家四姉妹と両親の、変わりゆく日常を描いた物語です。末娘・里々子の視点を通して、家族の関係性の変化、個々の成長、恋愛、そして避けられない別れといったテーマが、静かに、しかし深く掘り下げられています。
物語には、劇的な事件が起こるわけではありません。しかし、長女の出戻り、次女の作家デビュー、三女の店の改装計画、そして里々子自身の受験失敗や恋愛、叔母の死など、日常の中で起こる様々な出来事が積み重なり、家族の形を少しずつ変えていきます。その過程は、時に切なく、時に温かく、読者の心にじんわりと響きます。
登場人物一人ひとりの描写が丁寧で、特に語り手である里々子の内面の葛藤や、他の姉妹たちの個性的な生き様が印象的です。家族という普遍的なテーマを扱いながらも、谷島家ならではの空気感や、1999年から2000年という時代の雰囲気が巧みに描かれており、物語の世界に深く引き込まれます。
読み終えた後には、自分自身の家族や、過ぎ去った時間について思いを馳せることになるかもしれません。派手さはないけれど、心に長く残り、じっくりと味わいたい、そんな深みのある作品です。家族の物語が好きな方、日常の中に潜む機微を描いた作品が好きな方には、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。

























































