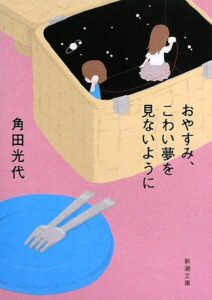 小説「おやすみ、こわい夢を見ないように」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんの描く世界は、日常に潜む人間の感情の深い部分を巧みに描き出すことで知られています。この作品もその例に漏れず、読者の心に静かに、しかし確実に波紋を広げる力を持っています。
小説「おやすみ、こわい夢を見ないように」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんの描く世界は、日常に潜む人間の感情の深い部分を巧みに描き出すことで知られています。この作品もその例に漏れず、読者の心に静かに、しかし確実に波紋を広げる力を持っています。
本書は7つの短編から構成されており、それぞれが独立した物語でありながら、「憎しみ」や「悪意」といった、普段は目を背けたくなるような感情を共通のテーマとして扱っています。登場人物たちは、私たちが日々すれ違うかもしれない、ごく普通の人々。しかし、彼らの内面には、ふとしたきっかけで噴出する、暗く重たい感情が渦巻いています。
この記事では、まず各短編がどのような物語なのか、その筋立てを追いかけます。その後、物語の核心に触れる部分にも言及しながら、私がこの作品を読んで何を感じ、考えたのかを、できる限り詳しくお伝えしたいと思います。読後感が決して明るいものではないかもしれませんが、人間の心の奥底を覗き込むような体験は、きっと忘れられないものになるはずです。
これから「おやすみ、こわい夢を見ないように」の世界に触れる方も、すでに読まれた方も、この記事を通して作品への理解を深めたり、新たな視点を発見したりするきっかけになれば幸いです。それでは、一緒に物語の世界へ入っていきましょう。
小説「おやすみ、こわい夢を見ないように」のあらすじ
この作品集は、私たちの日常に潜む、見過ごされがちな、しかし確実に存在する「悪意」や「憎しみ」という感情に焦点を当てた7つの物語で構成されています。それぞれの物語は、異なる登場人物と状況を描きながら、読者の心の琴線に触れる普遍的なテーマを探求しています。
「イノセント」では、小学校時代の担任教師に理由もなく嫌われていた記憶を持つ女性、くり子が主人公です。大人になった彼女は、なぜ自分が憎まれなければならなかったのか、その答えを求めて恩師との再会を試みます。過去の理不尽な経験と向き合う中で、彼女の心に去来するものは何なのでしょうか。
「スイート・チリソース」は、結婚生活を送る夫婦、翠とその夫の物語。些細な意見の食い違いや価値観のずれが積み重なり、二人の間には見えない溝が生まれていきます。日常の小さな亀裂が、やがて大きな感情のうねりへと発展していく様子が、リアルに描かれています。
表題作でもある「おやすみ、こわい夢を見ないように」は、元恋人からの執拗な嫌がらせに苦しむ女子高生、沙織の物語です。学校で孤立し、精神的に追い詰められた彼女は、引きこもりの弟と共に、ある計画を立て始めます。復讐という暗い衝動と、家族との複雑な関係性が交錯します。
「うつくしい娘」では、かつて美貌を謳われながらも、今は工場で働き、心を閉ざした娘・加代子との息苦しい生活を送る母親が描かれます。娘に対する愛情と憎しみの間で揺れ動き、母親の心には殺意に近い感情さえ芽生え始めます。母と娘という最も近い関係性の中に潜む闇が、痛々しく映し出されます。
「彼方の城」は、妻の浮気が発覚した後、家庭内で奴隷のような扱いを受けるようになった夫、重春の視点から語られます。失われた信頼と歪んだ力関係の中で、彼は何を思い、どのように日々を過ごしているのでしょうか。夫婦関係の崩壊と再生(あるいは完全な破滅)の可能性を探ります。
「晴れた日に犬を乗せて」は、できちゃった結婚を目前にして、一方的に恋人から別れを告げられた男性、典行の物語です。かつての恋人が、自分との子を中絶し、新しい恋人と新しい生活を始めている姿を偶然目撃してしまった彼の心に、激しい感情が沸き起こります。愛と裏切り、そして喪失感がテーマです。
最後の「私たちの逃亡」では、かつてクラスの中心的存在でありながら、今は毒を吐き続け、肥満して引きこもってしまった元同級生・理沙の行方を、「私」が追う物語です。周囲への憎悪を募らせて孤立した理沙と、彼女から距離を置いた「私」。過去の記憶と現在の状況が交錯し、人の心の脆さや関係性の変化が描かれます。
これらの物語は、決して気分の良いものではないかもしれません。しかし、登場人物たちが抱える葛藤や苦悩は、どこか私たちの日常と地続きであり、他人事とは思えないリアリティを持っています。
小説「おやすみ、こわい夢を見ないように」の長文感想(ネタバレあり)
角田光代さんの「おやすみ、こわい夢を見ないように」を読み終えたとき、まず感じたのは、ずっしりとした重さでした。それは決して不快なだけのものではなく、人間の心の奥底にある、普段は蓋をしている部分に触れてしまったような、ある種の戸惑いと共感が入り混じった複雑な感覚でした。この作品集に収められた7つの物語は、どれも私たちの日常に転がっているかもしれない「悪意」や「憎しみ」といった感情を、容赦なく、しかし非常に繊細な筆致で描き出しています。
多くのレビューで語られているように、読後感が「悪い」「滅入る」「怖い」と感じるのは、ある意味当然かもしれません。なぜなら、角田さんは、私たちが普段目を背けがちな、人間関係の中に潜む澱(おり)のような感情を、まるで拡大鏡で覗き込むように描き出すからです。そこには、安易な救いや希望は用意されていません。しかし、だからこそ、これらの物語は強烈なリアリティをもって私たちに迫ってくるのだと思います。
例えば、「イノセント」のくり子が抱える、理由のわからない憎しみを受けた記憶。誰しも、子供の頃に理不尽な扱いを受けたり、漠然とした悪意に晒されたりした経験が、少なからずあるのではないでしょうか。大人になっても、その記憶は棘のように心に残り続けることがあります。くり子が恩師に再会しようとする行動は、過去の清算を求める切実な思いの表れですが、結局のところ、明確な答えや謝罪が得られるわけではありません。それでも、彼女がその経験と向き合おうとしたこと自体に、小さな一歩を感じさせる終わり方には、かすかな光が見えるような気もしました。
「スイート・チリソース」で描かれる夫婦間の溝も、非常に身につまされるものがあります。結婚生活とは、愛や喜びだけでなく、些細な価値観の違いやコミュニケーション不足から生まれるすれ違いとの戦いでもあります。翠が夫に対して感じる苛立ちや不満は、決して特別なものではありません。しかし、その小さな不満が積み重なり、やがて相手への嫌悪感や、もっと言えば「殺意」に近い感情へと膨らんでいく過程は、読んでいて背筋が寒くなるほどのリアリティがありました。日常の中に潜む危険性を、これほどまでに巧みに描き出す角田さんの筆力には、改めて驚かされます。
表題作「おやすみ、こわい夢を見ないように」は、特に印象深い作品でした。元恋人からの陰湿な嫌がらせという、現代的な問題設定の中で、主人公の沙織が抱える孤独や恐怖、そして怒りが痛いほど伝わってきます。引きこもりの弟と協力して復讐を計画するという展開は、一見突飛に思えるかもしれませんが、追い詰められた人間の心理としては、あり得ないことではないのかもしれません。結局、沙織は直接的な復讐を果たせませんが、その過程で弟との間に生まれた奇妙な連帯感や、最後に苛立ちの矛先が意外な方向へ向かう展開は、単純な勧善懲悪では終わらない、人間の複雑な感情のもつれを示唆しているように感じられました。弟との間で交わされる「ラロリー」という言葉は、暗闇の中で見つけた小さな灯りのように、心に残ります。
「うつくしい娘」は、母と娘という、本来最も深い愛情で結ばれているはずの関係性に潜む、強烈な憎悪を描いた作品で、読むのが辛いと感じる人も多いかもしれません。娘の醜さや心の歪みに対する母親の嫌悪感は、一般的な母性愛のイメージとはかけ離れています。しかし、娘の身に危険が及んだときに母親が見せる動揺や悲しみは、やはり母親としての本能的な感情なのでしょう。愛情と憎しみは表裏一体であり、最も近い存在だからこそ、その感情はより複雑で、時に残酷な形をとるのかもしれません。この物語は、母性の理想化に対する痛烈な問いかけとも受け取れます。
「彼方の城」の重春のように、パートナーの裏切りによって尊厳を踏みにじられ、歪んだ関係性の中に閉じ込められてしまう状況も、決して他人事ではないかもしれません。浮気をした妻への怒りや憎しみを感じながらも、経済的な理由や子供の存在など、様々な要因から関係を断ち切れない。その中で、じわじわと心が蝕まれていく様子は、読んでいて息苦しさを感じました。この物語は、関係性の修復がいかに困難であるか、そして一度壊れた信頼を取り戻すことの難しさを突きつけてきます。
「晴れた日に犬を乗せて」は、失恋と裏切りの痛みを、非常に生々しく描いています。元恋人が、自分との子を中絶し、すぐに新しい恋人と幸せそうにしている姿を目撃してしまう典行の絶望と怒りは、想像に難くありません。特に、かつて二人で胎児につけた名前を、新しい恋人と飼い始めた犬につけているという描写は、あまりにも残酷で、人間の無神経さや身勝手さに対する強い憤りを感じさせます。恋愛における記憶の上書きというテーマは、男女間の認識の違いを浮き彫りにし、読者に強い印象を残します。
最後の「私たちの逃亡」は、過去の友人関係と、そこに潜んでいた(あるいは、いつの間にか生まれていた)憎悪についての物語です。かつて輝いていた理沙が、なぜ周囲への憎悪を募らせ、孤立していったのか。その明確な理由は語られませんが、「私」が彼女の足跡を辿る中で見えてくるのは、集団の中で生じる同調圧力や、無自覚な悪意、そしてそれに対する過敏な反応といった、思春期特有の(しかし、大人になっても形を変えて存在する)人間関係の難しさです。理沙の抱える憎悪の深さに共感はできなくとも、理解できる部分は少なからずあるのではないでしょうか。彼女がその後どうなったのかが描かれない終わり方は、問題が解決したわけではない現実の厳しさを象徴しているようです。
角田さんが描く「悪意」や「憎しみ」は、決して突飛なものではなく、私たちの日常の中に、ごく当たり前のように存在しているものだということです。登場人物たちは、特別な悪人ではありません。むしろ、どこにでもいるような普通の人々です。だからこそ、彼らが抱える闇が、より一層リアルに感じられ、読んでいる自分の心の中にも、同じような感情の種が存在するのではないか、と考えさせられます。
これらの物語は、決して読者を心地よくさせるものではありません。むしろ、不安にさせたり、気分を滅入らせたりするかもしれません。しかし、それは角田さんが、人間の感情の複雑さや矛盾、そして綺麗事だけでは済まされない現実を、真摯に見つめているからだと思います。安易な共感や同情を誘うのではなく、読者一人ひとりに、自分自身の心と向き合うことを促す。それが、この作品集の持つ力ではないでしょうか。
「おやすみ、こわい夢を見ないように」というタイトルは、一見すると優しく、穏やかな響きを持っています。しかし、物語を読み進めるうちに、このタイトルが持つ深い意味合いに気づかされます。それは、悪意や憎しみという「こわい夢」から目を覚まし、穏やかな眠りにつきたいという切実な願いの表れなのかもしれません。あるいは、そのような感情を抱えたまま生きていかなければならない私たちへの、皮肉めいた子守唄なのかもしれません。
読み終えて時間が経っても、物語のいくつかの場面や、登場人物たちの表情が、ふとした瞬間に思い出されます。それは、この作品が、私の心の深い部分に、確かに何かを残していった証拠なのだと思います。すぐに答えが出るような問いではありませんが、人間関係や自分自身の感情について、改めて考えさせられるきっかけを与えてくれる、重厚な読書体験でした。
角田光代さんの作品は、しばしば「読むのが辛い」けれど「引き込まれる」と評されますが、「おやすみ、こわい夢を見ないように」は、まさにその言葉が当てはまる作品集だと言えるでしょう。もし、あなたが人間の心の暗部や、日常に潜むリアリティに触れたいと考えているなら、この本を手に取ってみる価値は十分にあると思います。ただし、読む際には、ある程度の心の準備が必要かもしれません。
まとめ
角田光代さんの短編集「おやすみ、こわい夢を見ないように」は、私たちの日常に潜む「悪意」や「憎しみ」といった、目を背けたくなるような感情をテーマにした7つの物語を集めた作品です。登場人物たちは、ごく普通の生活を送る人々ですが、彼らの内面には、ふとしたきっかけで噴出する暗い感情が渦巻いています。
各短編は、夫婦関係の亀裂、過去のトラウマ、恋愛における裏切り、親子間の確執など、様々な人間関係の中に潜む闇を、角田さんならではの鋭い観察眼と繊細な筆致で描き出しています。読後感は決して明るいものではなく、むしろ重く、考えさせられるものが多いかもしれません。しかし、そのリアリティと心理描写の巧みさゆえに、読者は登場人物たちの感情に引き込まれ、自分自身の心の内を見つめ直すきっかけを得ることでしょう。
物語の核心に触れる部分もありますが、安易な解決やハッピーエンドは用意されていません。むしろ、問題が解決しないまま、あるいは新たな問題を抱えたまま終わる物語も少なくありません。それが、この作品集が持つリアリティであり、読者に深い余韻を残す理由の一つと言えます。人間の感情の複雑さ、綺麗事だけでは済まされない現実を、真摯に描ききっています。
もしあなたが、人間の心の深淵を覗き込むような、重厚な読書体験を求めているのであれば、この「おやすみ、こわい夢を見ないように」は、間違いなく読む価値のある一冊です。ただし、軽い気持ちで楽しめるエンターテイメント作品とは異なりますので、その点は心に留めておくと良いかもしれません。日常に潜む「こわい夢」と向き合う覚悟を持って、ページを開いてみてください。

























































