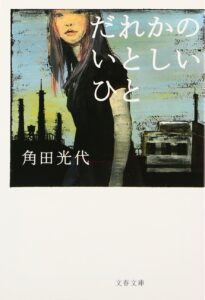 小説「だれかのいとしいひと」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんの作品に初めて触れる方、あるいは再読したいと考えている方の参考になれば嬉しいです。
小説「だれかのいとしいひと」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんの作品に初めて触れる方、あるいは再読したいと考えている方の参考になれば嬉しいです。
この作品は、日常の中に潜む、ちょっと切なくて、どこか不器用な恋愛や人間関係を描いた短編集です。表紙の酒井駒子さんのイラストが、まず物語の世界観へと誘ってくれますよね。かわいらしさと透明感、そしてどこか物憂げな雰囲気が、収録されている物語に通じているように感じます。
失恋の痛みを抱えたり、過去の出来事に心を揺さぶられたり、あるいは予期せぬ出会いに戸惑ったり。登場人物たちは、決してドラマティックなヒーローやヒロインではありません。むしろ、私たちのすぐ隣にいそうな、ごく普通の人々です。だからこそ、彼らの抱えるやるせなさや、ふとした瞬間の心の動きに、強く共感してしまうのかもしれません。
この記事では、各短編がどのような物語なのか、その流れを追いながら、物語の核心にも触れていきます。そして、読み終えて私が何を感じ、考えたのか、ネタバレも気にせずに、率直な気持ちを綴っていこうと思います。少し長くなりますが、お付き合いいただけると幸いです。
小説「だれかのいとしいひと」の物語の概要
この本は、八つの短編から構成されています。それぞれの物語は独立していますが、どこか共通する空気感を持っています。それは、失われた恋や、うまくいかない人間関係、日常の中のふとした心の揺らぎを描いている点です。
「転校生の会」では、転校を繰り返した元彼を理解しようと、主人公が奇妙な会合に参加します。そこで出会った人々の話を聞くうちに、彼女自身の心にも変化が訪れます。出会いや別れをバスの乗り降りに例えることで、過去の恋愛を乗り越えるきっかけを見つけるのです。
「ジミ、ひまわり、夏のギャング」は、別れた彼の部屋に忘れ物を取りに行く、少しスリリングな物語。合い鍵を使って忍び込んだ部屋で、彼女は過去の自分自身の幻影を見ます。結局、忘れ物は持ち帰らずに部屋を出るのですが、そこには過去との向き合い方に対する彼女なりの答えが見え隠れします。
「バーベキュー日和(夏でもなく、秋でもなく)」は、少し危うい魅力を持つ女性が主人公です。友人の恋人と関係を持ってしまいながらも、心のどこかでは皆との調和を願っている。その複雑な心情が、人間の欲望の形が変わっていく様子に例えられて描かれます。
表題作でもある「だれかのいとしいひと」は、大人の男女の関係に、子供が関わる二つの状況を描きます。不安定な大人の世界と、無邪気な子供の世界が対比され、それが登場人物たちの心にどのような影響を与えるのかが印象的です。
他にも、日常からの脱却を願う女性がハワイで偶然の出会いを経験する「誕生日休暇」、不幸続きの日常からふと抜け出す瞬間を描く「花畑」、独特のキスへのこだわりを持つ男性の回想を描く「完璧なキス」、そして些細な口論の裏で、実は関係性の核心に触れる会話をしているカップルの姿を描く「海と凧」が収録されています。どの物語も、登場人物たちの繊細な心の動きが丁寧に描かれています。
小説「だれかのいとしいひと」の長文感想(ネタバレあり)
角田光代さんの『だれかのいとしいひと』、読み終えてまず感じたのは、登場人物たちの「不器用さ」への強い共感でした。収録されている八つの物語は、どれも劇的な事件が起こるわけではありません。むしろ、私たちの日常の延長線上にあるような、ささやかな出来事と、それに伴う心の揺れ動きが丁寧に描かれています。
特に心に残ったのは、登場人物たちが抱える、言葉にしにくい感情の描写です。失恋の痛み、過去への執着、人間関係のぎこちなさ、将来への漠然とした不安。そういった感情は、誰しもが経験したことがあるのではないでしょうか。角田さんは、そうした普遍的な感情を、非常にリアルな、それでいて詩的な筆致で掬い取っていきます。
例えば、「転校生の会」。転校を繰り返した元彼の気持ちを知りたくて会に参加する主人公の行動は、少し変わっているかもしれません。でも、失った恋の理由を探してしまう気持ちは、痛いほどよく分かります。彼女が最終的に「もう行かない」と決めたのは、漆原さんの話や、バスの乗り合わせという考え方を通して、「彼との別れは、人生における一つの出来事に過ぎない」と、ある種の諦めとともに受け入れることができたからではないでしょうか。それは決してネガティブな諦めではなく、過去を手放し、前に進むための静かな決意のように感じられました。
「ジミ、ひまわり、夏のギャング」は、雰囲気がとても好きでした。別れた彼の部屋に忍び込むという行為自体は褒められたものではありませんが、その背後にある、過去への断ち切れない思いが切なく伝わってきます。部屋で見えた「半透明のあたし」は、まさに過去の記憶そのもの。ジミヘンのポスターを持ち帰らなかったのは、彼との思い出を完全に消し去ってしまうことへの恐れ、そして、その過去があったからこそ今の自分がいるのだと、確認できたからなのかもしれません。過去を無理に忘れようとするのではなく、そっと心の中にしまって、また歩き出す。そんな強さを感じました。
「バーベキュー日和(夏でもなく、秋でもなく)」の主人公には、正直、少し戸惑いを覚えました。友人の恋人を奪ってしまうような行動は、共感しがたい部分もあります。しかし、彼女が抱える「みんなと仲良くありたい」というピュアな願いもまた、嘘ではないのでしょう。人間の欲望や関係性が、単純な善悪では割り切れない複雑さを持っていることを、この物語は突きつけてくるようです。「知育玩具」のたとえは秀逸で、私たちの心がいかに変わりやすく、掴みどころのないものかを象徴しているように思えました。
表題作「だれかのいとしいひと」は、子供の存在が、不安定な大人の関係性に奇妙な光と影を落とす様子が印象的でした。子供の無邪気さが、かえって大人たちの間の緊張感や、隠された本音を浮かび上がらせる。子供の頃に経験した、よく分からないけれど妙に心に残っている大人の世界の断片。そんな記憶を呼び覚まされるような、少しほろ苦い読後感がありました。
「誕生日休暇」は、他の短編と少し毛色が違う、希望を感じさせる物語でした。習慣に縛られ、変化を恐れていた主人公が、ハワイという非日常の空間で、偶然の連鎖によって新しい出会いを果たします。流されるように見えて、実はそれが自分を縛っていた何かから解放されるきっかけになる。人生には、そんな予期せぬ展開もあるのだと、少しだけ心が軽くなるような気持ちになりました。
「花畑」は、個人的に特に強く心を揺さぶられた作品です。家族にも恋人にも裏切られ、孤独の中で生きる意味を見失いそうになる主人公。その絶望感は読んでいて苦しくなるほどでした。しかし、あてもなく歩いた先で見つけた緑の風景に、彼女はふと「きれい」だと感じます。どんなに打ちのめされていても、美しいものに心を動かされる瞬間がある。その小さな感動が、生きる希望の糸口になる。このラストには、静かな、しかし確かな救いを感じました。「こんなにもいやなことだらけだというのに、こんなにもまいっているというのに、あたしはまだ、何かを見て、きれい、などと感嘆の言葉をつぶやくことができるのだ。」という一文は、深く胸に響きました。
「完璧なキス」は、日常の何気ない場面(喫茶店での時間)と、過去の鮮烈な記憶(完璧なキス)が交錯する構成が巧みでした。キスという行為を通して、相手の存在そのものを深く感じ取ろうとする主人公の感覚は、非常に独特で面白いです。特に、キスで相手が食べたものや話したことまで共有したように感じてしまう描写は、生々しくも切ない。過去の特定の瞬間にだけ存在する「完璧」な記憶。それは美しくもありますが、同時に、現在を生きる私たちを少しだけ寂しくさせるのかもしれません。
最後の「海と凧」は、一見すると些細なことで言い争うカップルの話ですが、その言葉の裏には、お互いへの不満や、関係性そのものへの問いかけが隠されています。過去の恋人の思い出の品である「凧」を探すという、どこか馬鹿げた行為を通して、二人はいつの間にか、いがみ合いではなく、純粋な時間を共有し始めます。見つからないものを探すという無意味に見える行動が、かえって二人の関係に新しい風を吹き込む。この結末には、さわやかな感動がありました。問題を直接解決するのではなく、別の何かを通して関係性が修復されていく。そんな希望を感じさせてくれました。
全体を通して感じるのは、角田さんの、人間の心の機微に対する洞察力の深さです。登場人物たちは、決して強くもなければ、特別でもありません。むしろ、弱さや矛盾を抱え、迷いながら生きています。しかし、だからこそ、彼らの物語は私たちの心に深く響くのかもしれません。
地に足がついていないような浮遊感、周りだけがうまく回っているように見える焦燥感。そんな感覚を覚えたことがある人なら、きっとこの物語の登場人物たちに、自分自身の一部を重ねてしまうのではないでしょうか。
読んでいると、まるで夢から覚めた直後のような、不思議な感覚に包まれることがあります。経験したことのないはずの場面なのに、なぜか「知っている」と感じる。それは、角田さんが描く感情のディテールが、私たちの心の奥底にある、言葉にならない部分に触れるからなのかもしれません。
失われた恋、うまくいかない日々、それでも続いていく日常。この短編集は、そんな人生の断片を、静かに、しかし深く描き出しています。読後には、切なさとともに、どこか前を向けるような、不思議な温かさが残りました。それは、登場人物たちが、不器用ながらも、それぞれの方法で現実と向き合い、ささやかな変化や成長を遂げていくからなのかもしれません。
まとめ
角田光代さんの短編集『だれかのいとしいひと』は、私たちの日常に潜む、恋愛や人間関係の切なさ、もどかしさ、そしてほんの少しの希望を、繊細な筆致で描いた作品です。八つの物語に登場するのは、特別な誰かではなく、どこにでもいるような、不器用で、迷いを抱えた人々です。
彼らが経験する失恋や人間関係の摩擦、過去へのとらわれといった感情は、多くの読者が共感できる普遍的なものでしょう。角田さんは、そうした心の機微を、まるでレントゲン写真のように鮮やかに、しかし温かい視線で描き出しています。読んでいると、登場人物たちの息遣いや、心の揺れがすぐそばで感じられるようです。
物語は、劇的な展開を見せるわけではありません。むしろ、静かに、淡々と進んでいきます。しかし、その静けさの中にこそ、深い感情の波が隠されています。読後は、登場人物たちが経験したささやかな変化や気づきが、じんわりと心に広がり、切なさとともに、明日へ踏み出すための小さな勇気を与えてくれるような気がします。
派手さはないけれど、心に長く残り、何度も読み返したくなる。そんな魅力を持った一冊です。恋愛小説という枠にとどまらず、人生の様々な局面で感じるであろう、言葉にしにくい感情にそっと寄り添ってくれるような、深い余韻を残す作品でした。

























































