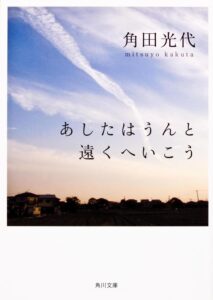 小説「あしたはうんと遠くへいこう」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんが描く、ひとりの女性の十数年にわたる恋愛と人生の物語です。読んでいると、まるで自分の過去を覗き見ているような、あるいは親しい友人の話を聞いているような、そんな不思議な感覚に包まれるかもしれません。
小説「あしたはうんと遠くへいこう」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんが描く、ひとりの女性の十数年にわたる恋愛と人生の物語です。読んでいると、まるで自分の過去を覗き見ているような、あるいは親しい友人の話を聞いているような、そんな不思議な感覚に包まれるかもしれません。
この物語の主人公、泉(いずみ)は、どこにでもいるような、でもどこか特別な危うさを持った女の子。彼女の1985年から2000年までの日々が、その時々の音楽と共に綴られていきます。恋をして、傷ついて、また恋をして…その繰り返しの中で、彼女は何を見つけ、どこへ向かおうとするのでしょうか。
この記事では、まず物語の詳しい流れ、結末に触れる部分も含めてお伝えします。そして後半では、この作品を読んで私が感じたこと、考えたことを、ネタバレを気にせずに、たっぷりと語っていきたいと思います。読後感が爽やかだという声もあれば、主人公に共感できない、読んでいて辛かったという声もある、評価の分かれる作品でもあります。
あなたはこの物語をどう感じるでしょうか。泉の生き方に、何を思うでしょうか。この記事が、作品への理解を深めたり、あるいはこれから読んでみようかなと思うきっかけになったりすれば嬉しいです。それでは、少し長いお話になりますが、お付き合いください。
小説「あしたはうんと遠くへいこう」のあらすじ
物語は1985年、主人公の泉が高校生のころから始まります。地方の温泉町で、レコードを編集してカセットテープを作ることに夢中な泉。彼女はどこか満たされない気持ちを抱えながら、日常を送っていました。そんな彼女の前に現れたのが、バンドマンで年上の恋人、真澄でした。彼との出会いは泉の世界を広げますが、同時に危うい道へと彼女を引き込みます。
真澄との関係は長くは続かず、泉は東京の大学へ進学します。新しい環境で、泉は様々な男性と出会い、恋を重ねていきます。ドレッドヘアの男性と同棲したり、年上の妻子ある男性と不倫関係になったり。その時々で付き合う男性の影響を強く受け、聴く音楽や服装、考え方まで変わっていく泉。彼女は常に「ここではないどこか」へ連れて行ってくれる誰かを求めているかのようです。
しかし、どの恋愛も長続きはしません。相手に依存し、自分を見失い、関係は破綻してしまうのです。恋が終わるたびに深く傷つき、「今度こそ」と誓う泉ですが、また同じような失敗を繰り返してしまいます。友人からは心配され、時には呆れられながらも、泉は「性懲りもなく」恋をせずにはいられません。ドラッグに手を出したり、ストーカー被害に遭ったりと、その恋愛遍歴は波乱に満ちています。
泉は、自分が何者なのか、どこにいるのか、わからなくなる瞬間が度々訪れます。「好きになった男抜きでは、自分は語れない」と感じ、恋愛を通してしか自分の輪郭を確かめられないような脆さを抱えています。彼女は、相手を変えることで自分自身が変われるのではないかと、無意識のうちに期待しているのかもしれません。
物語の後半、泉は家族との関係にも向き合うことになります。特に、あまりコミュニケーションを取ってこなかった父親との再会は、彼女にとって一つの転機となる出来事です。しかし、そこで彼女が安らぎや答えを見つけられるわけではありません。彼女の抱える問題は、そう簡単には解決しないのです。
2000年、32歳になった泉は、新たな恋人と出会います。そして、彼を追いかけてアイルランドへ旅立つことを決意します。「あしたはうんと遠くへいこう」。そう心に決めて、彼女は未知の場所へと一歩を踏み出すのです。この旅が彼女にとってどのような意味を持つのか、そこで何を見つけるのか、物語は明確な答えを示さずに幕を閉じます。泉の「自分探し」とも言える彷徨は、まだ続いていくのかもしれません。
小説「あしたはうんと遠くへいこう」の長文感想(ネタバレあり)
角田光代さんの「あしたはうんと遠くへいこう」、読み終えて、なんとも言えない気持ちになりました。爽やかさとは少し違う、かといって絶望でもない。ただ、主人公・泉の十数年間の軌跡が、ずっしりと心に残りました。これは、単なる恋愛小説という枠には収まらない、ひとりの人間の「生きること」そのものを描いた物語なのだと感じます。
まず、泉という主人公について。彼女は非常に危うく、脆い人間として描かれていますね。常に誰かに、特に恋愛対象の男性に依存し、その影響を色濃く受けてしまう。聴く音楽、服装、住む場所、考え方まで、付き合う相手によってころころと変わる。彼女自身も「好きになった男抜きでは、自分は語れない」と自覚している通り、他者を通してしか自分の存在を確認できないような不安定さを持っています。
この泉の姿に、読んでいて正直、イライラしたり、もどかしさを感じたりする人も多いのではないでしょうか。提供された感想の中にも「大嫌いなタイプ」「読んでいて苦痛だった」「自分に負けている」といった厳しい意見がありました。確かに、失敗から学ばず、同じような過ちを繰り返し、周りを振り回す彼女の姿は、見ていて決して気持ちの良いものではありません。特に、ドラッグに手を出したり、安易に関係を持ったりするあたりは、読んでいて「おいおい」と突っ込みたくなる場面も多かったです。
しかし、一方で、泉の弱さや不器用さに、どこか共感してしまう自分もいるのです。「人は人に自分を探す」という作中の言葉がありますが、程度の差こそあれ、私たちは誰しも他者の影響を受け、関係性の中で自分というものを形作っていく部分があるのではないでしょうか。泉の場合はその度合いが極端で、自己という核が非常に希薄なのかもしれませんが、彼女が抱える「自分が何者かわからない」という不安や、「ここではないどこかへ行きたい」という渇望は、普遍的なものとも言える気がします。
泉の恋愛は、まるでジェットコースターのようです。激しく燃え上がり、そして急速に冷めていく。彼女は相手の中に「自分を変えてくれる何か」を期待し、理想化しますが、現実の相手とのズレに失望し、関係は破綻する。このパターンが何度も繰り返されます。阪本さんの感想にあるように、恋愛相手の男性たちの顔が見えにくく、泉に感情移入しにくいという指摘も、なるほどと思いました。男性たちは、泉の「自分探し」の触媒として機能している側面が強いのかもしれません。彼らがその後どうなったのか、ほとんど描かれないのは、泉自身の視点、彼女にとっての男性たちの意味合いを反映しているのでしょう。
この物語のもう一つの重要な要素は「音楽」です。各章のタイトルには当時のヒット曲やアーティスト名が使われ、物語の時代背景を示すと同時に、泉の心情を代弁する役割も果たしています。泉は「自分で選んだ音楽を聴けばとりあえず持ちこたえられる」と言いますが、音楽は彼女にとって、不安定な自分を支えるための、数少ない拠り所なのかもしれません。中川さんの感想のように、同世代で洋楽好きの読者にとっては、より一層、ノスタルジックな共感を呼ぶ仕掛けになっているのでしょう。ただ、今井さんの感想のように、音楽名の連呼が鼻につくという意見も理解できます。それが効果的な演出と感じるか、あざとく感じるかは、受け手次第かもしれません。
家族との関係も、泉の人物像を理解する上で見逃せない点です。特に、父親との希薄な関係は、彼女の男性観やコミュニケーションの取り方に影響を与えているように思えます。家族との間で健全な愛情表現や対話が不足していたことが、彼女が恋愛において相手に過剰な期待を寄せたり、本音を伝えられずに破綻を繰り返したりする一因になっているのかもしれません。最後の父親との再会の場面も、完全な和解や解決には至らず、むしろ彼女の抱える問題の根深さを示唆しているように感じました。家族という、本来なら最も基本的な人間関係の基盤が揺らいでいることが、彼女の人生全体の不安定さにつながっているのではないでしょうか。
物語の終盤、泉はアイルランドへ旅立ちます。「あしたはうんと遠くへいこう」というタイトル通り、物理的に遠くへ行くことを決意するわけですが、これが彼女にとっての成長や希望の始まりなのかどうかは、読者に委ねられています。阪本さんの感想では、現在の恋人の存在感が希薄で、希望の源としては弱いのではないかと指摘されていますし、他の感想でも「最後まで大きな変化なく終わってしまった」という意見がありました。確かに、泉が根本的に変わったという確証はありません。また同じように、誰かに依存し、自分を見失う旅になる可能性も否定できません。
しかし、私はこの結末に、わずかながらも前向きな響きを感じ取りたいと思いました。これまでの泉は、どちらかというと流されるままに、あるいは衝動的に関係を結び、場所を変えてきた印象があります。しかし、最後の旅立ちは、これまでの受動的な態度とは少し異なり、「自分で選んだ」決意のように感じられるのです。「好きになった男抜きでは、自分は語れない」という認識は変わらないかもしれないけれど、その自分を否定するのではなく、ある意味で受け入れた上で、それでも「遠くへ」行こうとしている。それは、完全な克服ではなくても、次の一歩を踏み出す意志の表れではないでしょうか。
仲田さんの感想にある「わかっちゃいるけど、やめられない、という馬鹿」という表現が、泉の本質を鋭く突いているように思います。頭では理解していても、感情や衝動に突き動かされてしまう。それは、人間なら誰しもが持っている側面かもしれません。泉の「馬鹿さ加減」は、痛々しく、見ていて辛いけれど、どこか他人事とは思えない。だからこそ、彼女を一方的に断罪する気にはなれないのです。
唐木さんの感想にあるように、会話に力みや誇張がなく自然な点も、この作品の魅力だと思います。泉の行動は時に突飛ですが、彼女の心情や周りの人々とのやり取りは非常にリアルです。だからこそ、読者は泉の感情の起伏に寄り添い、イライラしたり、共感したり、悲しくなったりするのでしょう。等身大の女性像として、印象に残ります。
この作品は、読む人によって評価が大きく分かれるでしょう。泉に共感し、その不器用な生き方を応援したくなる人もいれば、彼女の弱さや依存性に嫌悪感を抱く人もいるはずです。「いい気なものだなあ」「自己陶酔しているだけ」という石井さんの厳しい評価も、一つの真実かもしれません。しかし、それだけ多様な反応を引き出すところに、この物語の力があるとも言えます。
結局のところ、泉は幸せになれたのでしょうか?物語は明確な答えを与えません。「幸せな”あした”」に辿り着けるかどうかは、わからないままです。でも、それでいいのかもしれない、とも思います。人生は、常に明確な答えやハッピーエンドがあるわけではありません。迷い、傷つき、それでも生きていく。その過程そのものが人生なのだと、この物語は語りかけているような気がします。「あしたはうんと遠くへいこう」という決意は、幸せへの保証ではなく、ただ前へ進もうとする意志表示。その不確かさこそが、リアルな人生の姿なのかもしれません。
角田光代さんという作家は、人間のどうしようもなさや、ままならなさを、非常に巧みに、そして時に容赦なく描き出す方だと感じます。この作品もまた、綺麗な恋愛物語や成長物語を期待して読むと、肩透かしを食らうかもしれません。しかし、剥き出しの感情や、泥臭い人間の姿に触れたいと思う読者にとっては、深く心に刺さる一冊になるのではないでしょうか。読み終えて、しばらく泉のことが頭から離れませんでした。彼女の未来が、少しでも穏やかなものであることを願わずにはいられません。
まとめ
角田光代さんの小説「あしたはうんと遠くへいこう」について、物語の詳しい流れと、ネタバレを含む長文の感想をお届けしました。主人公・泉の高校時代から30代前半までの、波乱に満ちた恋愛遍歴と人生を描いた作品です。
泉は、恋に依存し、失敗を繰り返しながらも、必死に自分の居場所や意味を探し求めます。その姿は痛々しくもあり、共感を呼ぶ部分もあり、読む人によって様々な感情を抱かせるでしょう。音楽が時代背景や心情描写に効果的に使われている点も特徴です。
結末は明確なハッピーエンドではなく、泉の旅がまだ続くことを示唆しています。彼女が本当に「遠くへ」行けるのか、幸せを見つけられるのかはわかりません。しかし、その不確かさの中に、生きることのリアルさが描かれているように感じます。
「あしたはうんと遠くへいこう」は、単なる恋愛小説を超えて、人間の弱さや脆さ、そしてそれでも生きていこうとする姿を描いた、深く考えさせられる物語です。読後感は人それぞれだと思いますが、きっとあなたの心にも何かを残す一冊となるはずです。

























































