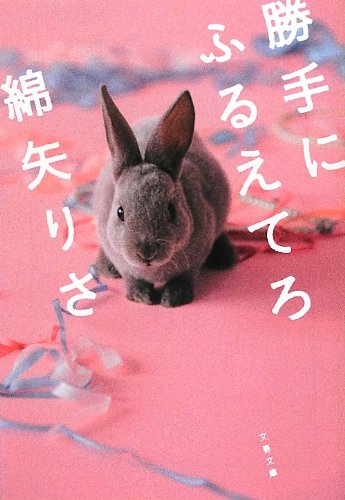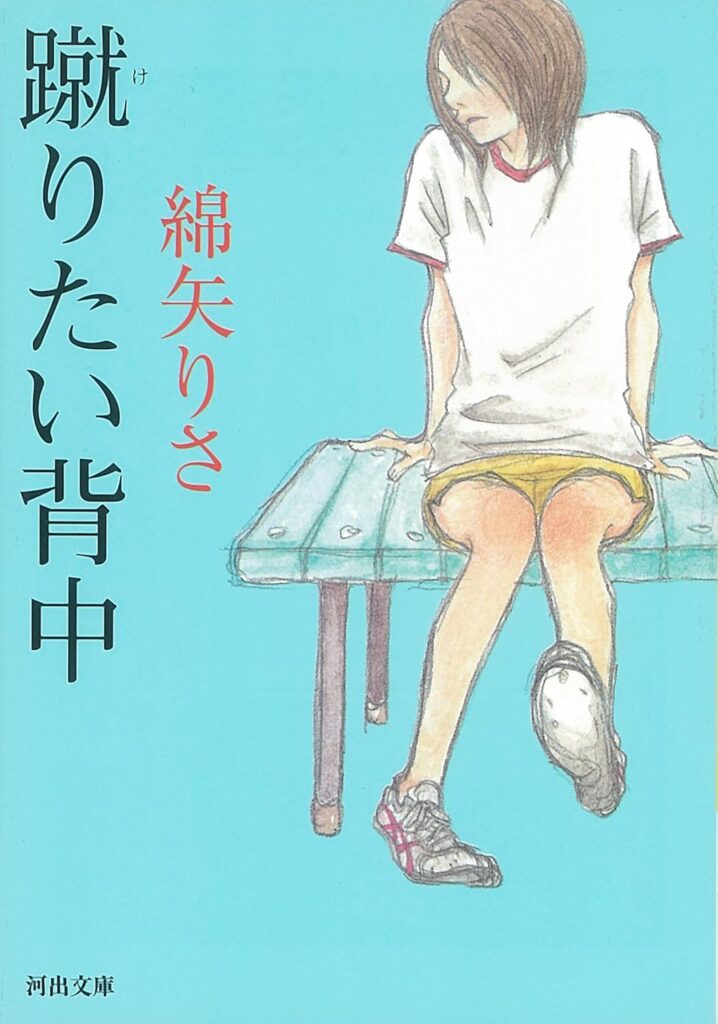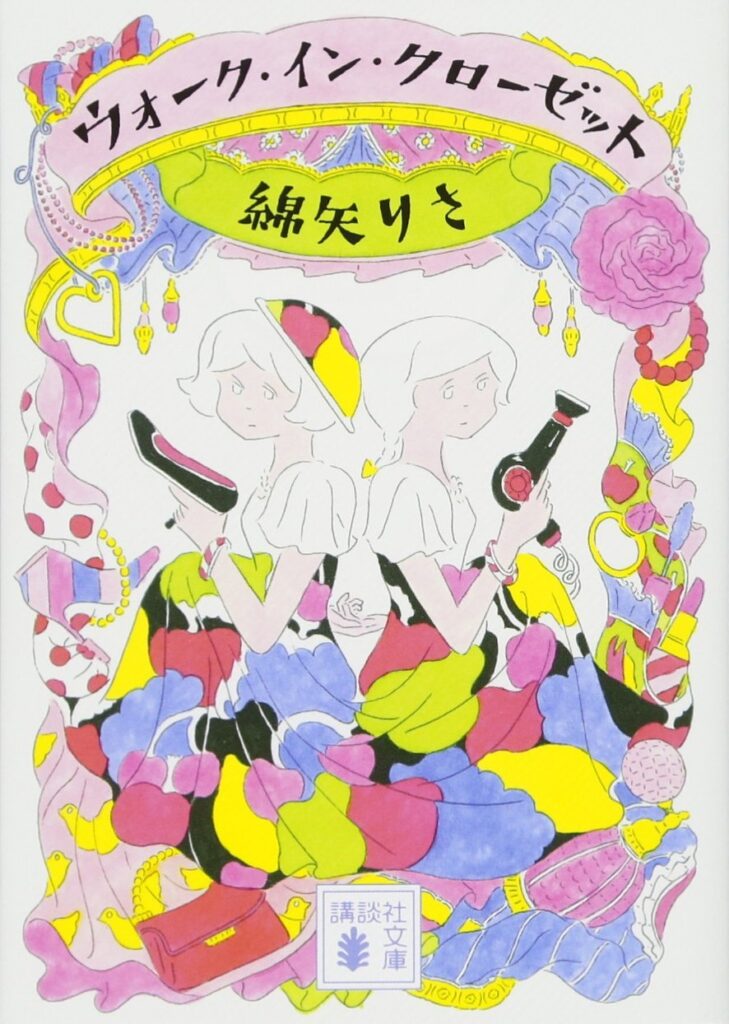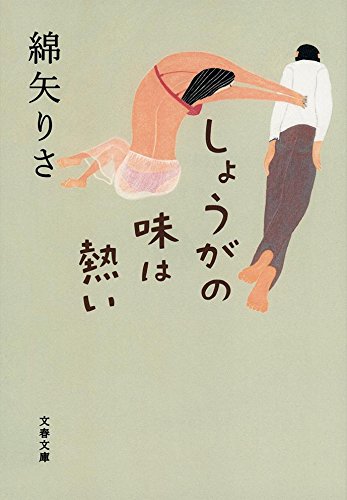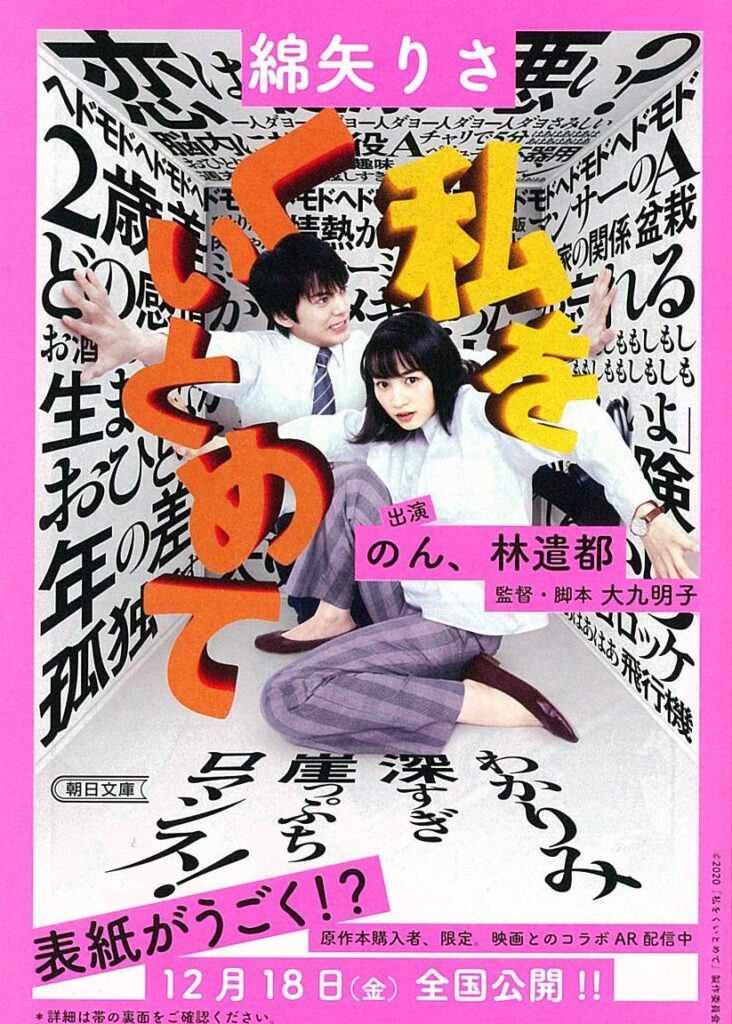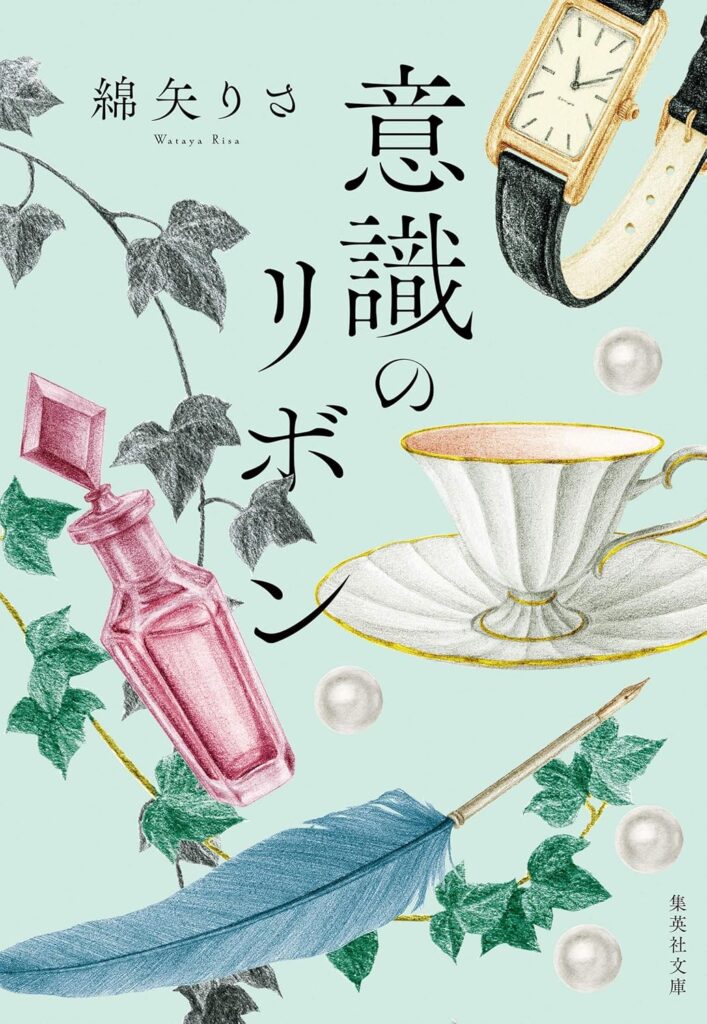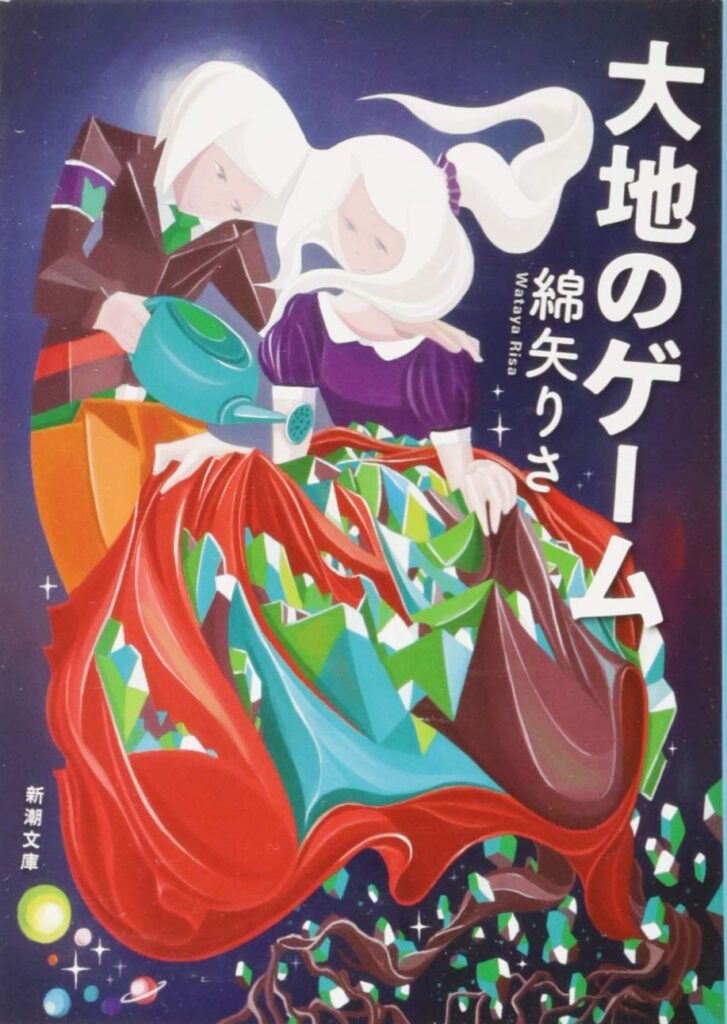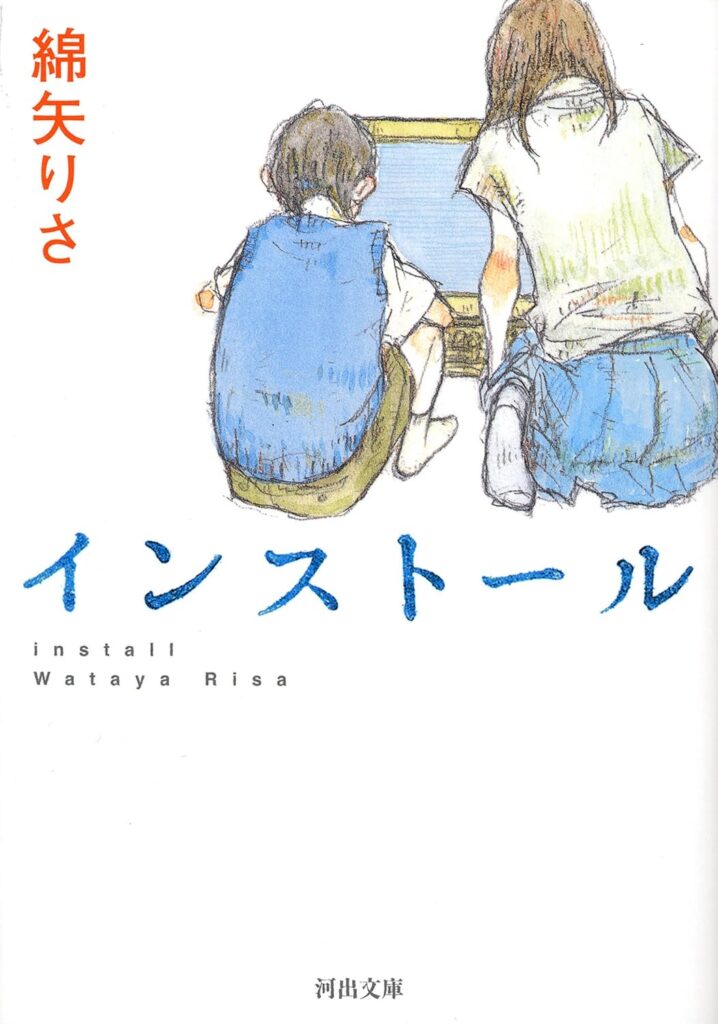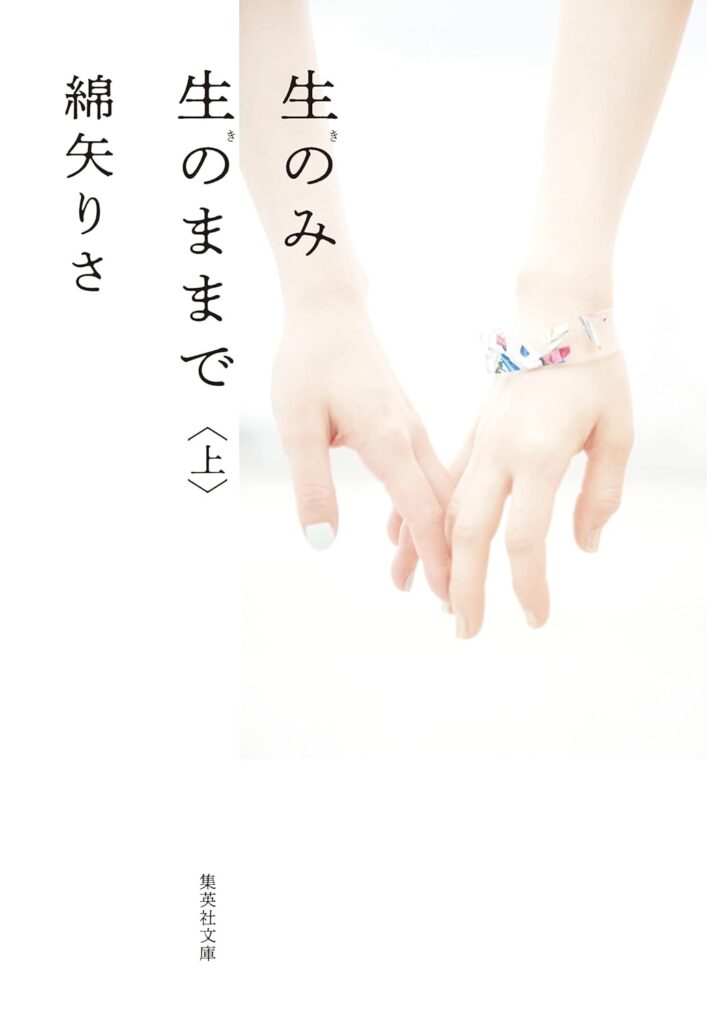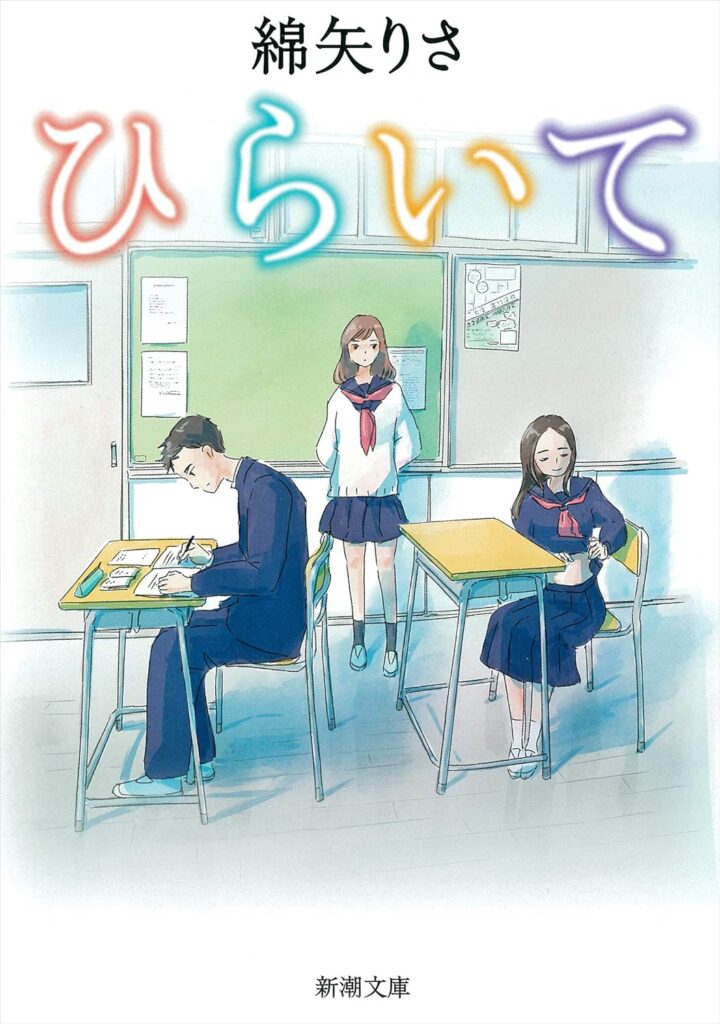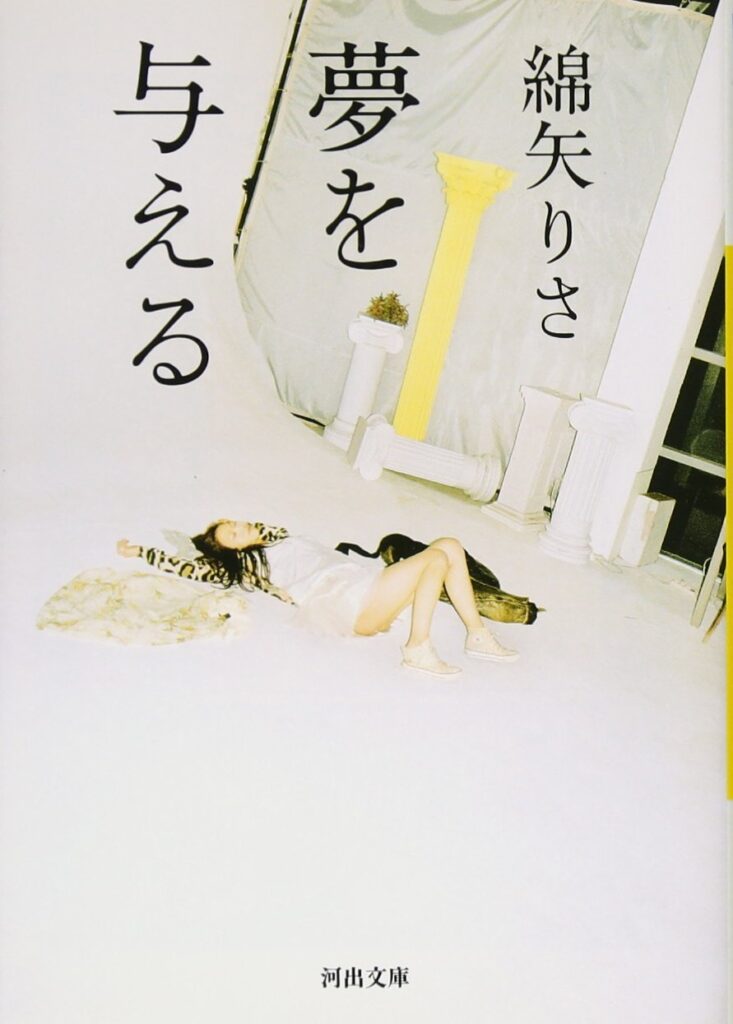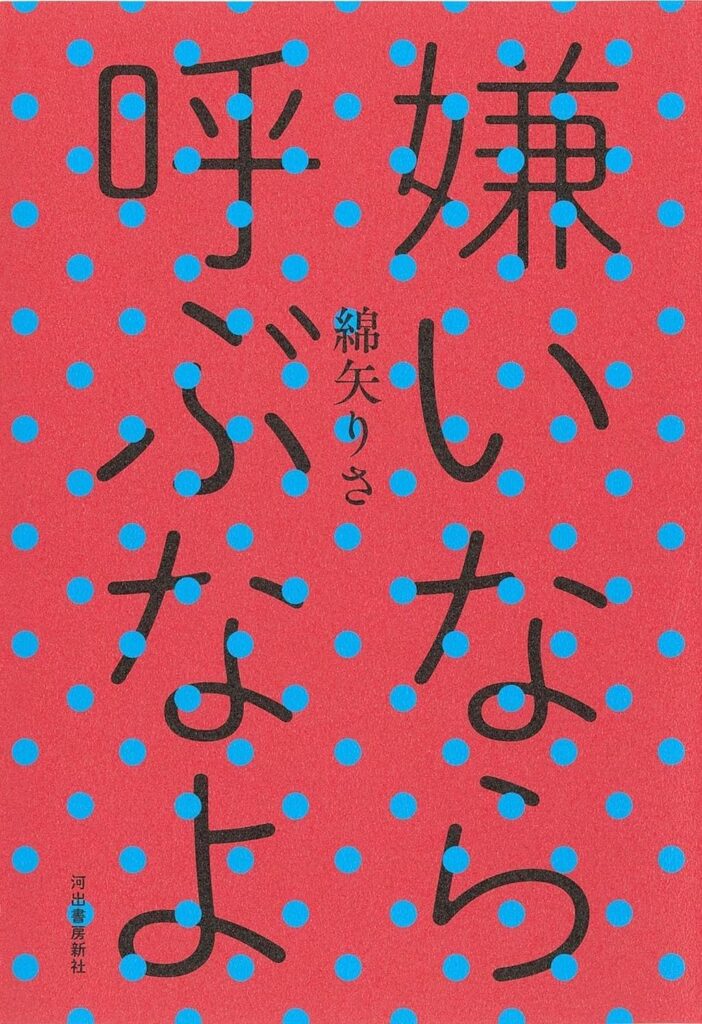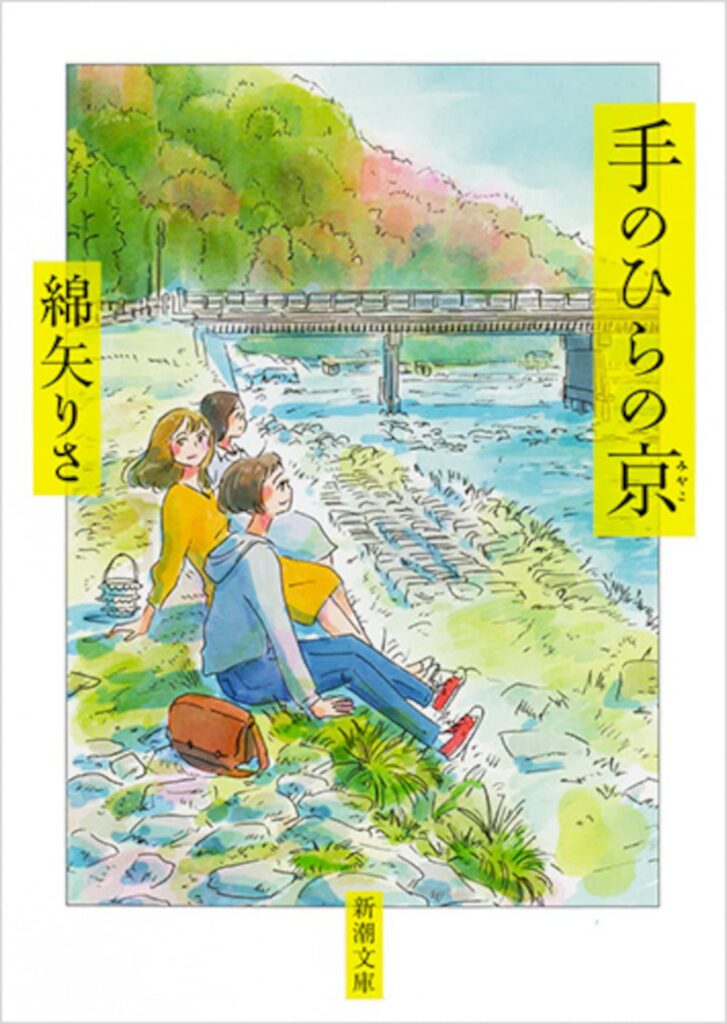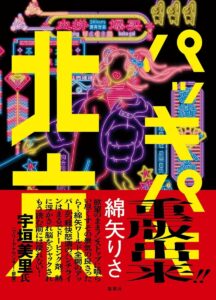
小説「パッキパキ北京」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。綿矢りささんのこの作品、タイトルからしてインパクトがありますよね。「パッキパキ」という響きが、冬の北京の凍てつく空気や、あるいは主人公の性格を表しているのでしょうか。
この物語は、現代の北京を舞台にした、ある日本人女性の滞在記です。コロナ禍という特殊な状況下で、彼女が見たもの、感じたこと、そして変化していく(あるいはしない?)心模様が描かれます。異文化との遭遇、夫との関係、そして自分自身の生き方について、深く考えさせられる部分がたくさんありました。
この記事では、まず「パッキパキ北京」の物語の筋道を、結末に触れながらお伝えします。その後、私がこの作品を読んで考えたこと、感じたことを、ネタバレを気にせずに詳しく書いていきます。読んだ方それぞれの受け取り方があると思いますが、一つの解釈として楽しんでいただけると嬉しいです。
綿矢りささんのファンの方はもちろん、現代中国に興味がある方、ちょっと変わった主人公の物語を読みたい方にも、ぜひ読んでいただきたい作品です。それでは、一緒に「パッキパキ北京」の世界を覗いてみましょう。
小説「パッキパキ北京」のあらすじ
主人公は菖蒲(あやめ)、36歳。元銀座のホステスで、現在は20歳年上の駐在員の夫と結婚しています。彼女はファッションが大好きで、特にシャネルがお気に入り。自分を飾ることに強いこだわりを持っています。当初、夫の駐在先である中国には全く興味がなく、日本で気ままな生活を送っていました。愛犬の名前はペイペイ。当初はペペでしたが、キャッシュレス決済のPayPayを使い始めてからペイペイと呼ぶようになったという、現代的な一面も。
ある日、コロナ禍の北京で単身赴任中の夫から悲痛な連絡が入ります。「北京での生活に適応できず、適応障害になった。一緒に暮らしてほしい。さもなければ離婚も考える」と。離婚されて生活の基盤を失うことを恐れた菖蒲は、しぶしぶ北京へ渡ることを決意します。彼女にとって、夫への愛情というよりは、生活を守るための選択でした。
北京での生活が始まると、菖蒲は持ち前の(ある種の)適応能力を発揮します。中国語は話せないものの、ネットショッピングサイトの淘宝網(タオバオ)や美容情報アプリ小紅書(シャオホンシュー)を駆使し、現地の生活を自分なりに楽しみ始めます。北京ダックはもちろん、雲南省の鯉の火鍋やウズラの丸焼き、アヒルの脳といったゲテモノ(?)料理にも果敢に挑戦。厳寒の北京で、現地で買った安物のダウンコートが高級ブランドのコートより暖かいことを発見したり、マスクの内側が凍る体験をしたりと、五感を通して異文化に触れていきます。
一方、夫は相変わらず家に引きこもりがちで、菖蒲の行動力に驚きつつも、心配と戸惑いを隠せません。菖蒲は夫の「情報強者ぶって消耗している」姿を内心冷ややかに見ており、二人の価値観のずれは広がるばかり。菖蒲は現地で知り合った大学院生のカップルにちょっかいを出したり、夫の制止を振り切って街へ繰り出したりと、自由奔放に振る舞います。
そんな中、夫婦ともにコロナに感染してしまいます。高熱に苦しむ夫を菖蒲は懸命に看病し、回復後に仕事の電話をする夫の姿を見て、「いつか彼がこんな風にできなくなる日が来るんだろうな。そのときは、私が支えてやる。それが夫婦ってもんだ」と、一瞬、夫婦としての情を感じます。しかし、その後、夫から子供が欲しいと告げられると、「身重にならず、身軽なまんまでいたい」と拒否。
最終的に、夫は菖蒲の生き方を受け入れられず、離婚を示唆します。「妊活もしない、北京にも残らないというのなら、僕に考えがある」と。菖蒲は日本にいる元同僚の美杏(みあ)にテレビ電話をし、帰国すること、そして「男紹介して」と頼みます。夫との関係は終わりを迎え、彼女は新たな「寄生先」を探し始めます。しかし、同時に「シャネルが無くても完全勝利できる女になる」「精神勝利法を極めるの」と宣言。美杏に「お姉ちゃん、アタマ大丈夫?」と心配されながら、物語は幕を閉じます。
小説「パッキパキ北京」の長文感想(ネタバレあり)
綿矢りささんの「パッキパキ北京」を読み終えて、なんとも複雑な気持ちになりました。北京という都市の描写は非常に鮮やかで、コロナ禍の閉塞感と、それでもたくましく生きる人々のエネルギーが伝わってくるようでした。特に、食べ物の描写は強烈で、読んでいるだけで口の中に様々な味が広がるような感覚を覚えました。冬の凍てつく空気感、街の色彩、人々の喧騒、そういったディテールが巧みに描かれていて、まるで自分が北京を歩いているような気にさせられます。
しかし、物語の中心人物である菖蒲の造型については、正直なところ、かなりの違和感を覚えました。36歳の元銀座ホステスという設定ですが、彼女の言動はあまりにも幼く、思慮に欠けるように感じられる場面が多かったです。例えば、魯迅を知らないという設定。中学の教科書にも載っているレベルの知識がないというのは、銀座のホステスという、ある種の知性や教養が求められるであろう職業経験を持つ女性として、不自然ではないでしょうか。作者は意図的に彼女を「無知な女性」として描いているのかもしれませんが、それがステレオタイプな女性蔑視に基づいているように感じられて、読んでいて不快感を覚える部分もありました。
彼女のファッションへの執着や、シャネルなどの高級ブランドへのこだわりも、どこか表層的に描かれている印象を受けました。それが彼女のアイデンティティの一部であることは理解できますが、「ハイブランド好きの虚栄心の強い女性」という、あまりにも紋切り型のイメージに収まってしまっている気がします。もう少し彼女の内面、なぜそこまで物や外見にこだわるのか、その背景にあるものが深く描かれていれば、キャラクターにより奥行きが出たのではないでしょうか。
また、菖蒲と夫との関係性も、最後まで腑に落ちない点が多く残りました。20歳も年上で、エリート駐在員の夫が、なぜ菖蒲のような女性と結婚したのか。彼女のどこに惹かれたのか。物語からは、その理由が明確には読み取れませんでした。夫の台詞回しも、どこか芝居がかっていて現実味が薄く、「知的でプライドの高いエリート」というよりは、型にはまった記号的なキャラクターに見えてしまいました。二人の会話には常にすれ違いや価値観の断絶があり、それが意図された描写だとしても、共感や理解を寄せることが難しい関係性でした。
特に、夫が菖蒲に子供を望む場面。前妻との間にすでに子供がいる56歳の男性が、なぜそこまで新たな子供を欲しがるのか。菖蒲がそれを拒否する理由も、「身軽でいたい」「気まぐれだから」というものでは、36歳という年齢を考えるとあまりにも現実感がありません。高齢出産のリスクや、人生設計について、もう少しリアルな葛藤が描かれていても良かったのではないかと感じます。このあたりの描写の浅さが、物語全体のリアリティを損なっているように思えました。
菖蒲が現地で知り合った大学院生カップルにちょっかいを出すエピソードも、彼女の未熟さや、ある種の残酷さを際立たせるものでした。年下の異性をからかって楽しむ姿は、「奔放な魔性の女」というよりは、むしろ痛々しく、読んでいて気分の良いものではありませんでした。そこには、異国で優位に立ちたいという無意識の欲求や、あるいは中国人に対する潜在的な見下しの感情が見え隠れしているようで、後味の悪さが残りました。
物語の終盤、菖蒲が「精神勝利法」に目覚める(?)場面は、この作品の核心に触れる部分なのでしょう。夫との関係が破綻し、日本へ帰国することを決めながらも、彼女は「シャネルが無くても完全勝利できる女になる」と宣言します。これは、物質的な豊かさや他者からの評価に依存してきた生き方からの決別を意味するのでしょうか。それとも、単なる強がり、あるいは現実逃避の新たな形なのでしょうか。
魯迅の「阿Q正伝」における精神勝利法は、自己欺瞞によって現実の敗北から目をそらす、哀れで滑稽な姿として描かれています。菖蒲がその本質を理解しないまま(夫の話でしか知らないため)、それを「極める」と宣言するラストは、非常に皮肉であり、彼女の未来に明るい展望を見出すことを難しくさせます。妹分の美杏が「アタマ大丈夫?」と問いかけるのは、読者の疑問を代弁しているようでもあります。
もしかしたら、作者は菖蒲というキャラクターを通して、現代社会における女性の生きづらさや、消費社会への批判、あるいは日中関係の複雑さといったテーマを描こうとしたのかもしれません。北京の鮮やかな描写の中に、そうした批評的な視線を忍ばせているとも解釈できます。しかし、主人公のキャラクター造形における問題点や、物語の展開における不自然さが、そうしたテーマ性を十分に伝えることを妨げているように感じられました。
特に気になったのは、作中に見られる女性に対する冷ややかな視線です。菖蒲だけでなく、彼女の友人である由紀乃や瑞穂、妹分の美杏といった登場人物たちも、どこかステレオタイプで、深みに欠ける描かれ方をしています。「女同士の付き合いなんてこんなもの」「水商売の女はこうだ」といった、ある種の偏見に基づいたような描写が散見され、それが作品全体の印象をネガティブなものにしている側面は否めません。
また、中国の芸能界について触れる場面で、中高年の女性芸能人が全く言及されない点も気になりました。若い女性、若い男性、中高年男性については分析があるのに、鞏俐(コン・リー)や章子怡(チャン・ツィイー)のような存在感のある中高年女優が完全に無視されているのは、不自然であり、エイジズム(年齢による偏見)的な視線を感じさせます。菖蒲自身が36歳という年齢でありながら、同世代以上の女性への関心が薄いという設定も、キャラクターのリアリティというよりは、作者の視点の偏りを反映しているのではないかと疑ってしまいます。
さらに、「ハーフ」という言葉の使用についても指摘しておきたいです。現在は「ダブル」などの表現が推奨されている中で、菖蒲の無知さを理由にこの言葉を使うのは、配慮に欠けると言わざるを得ません。登場人物の設定を言い訳に、差別的なニュアンスを含む言葉を安易に使用するべきではないと考えます。
とはいえ、この作品には魅力的な部分も多くあります。コロナ禍の北京という、今しか描けないであろう時代の空気を切り取った点、異文化の中でたくましく(あるいは自分勝手に)生き抜こうとする主人公のエネルギー、そして「精神勝利法」というキーワードを通して、現代人の生き方や価値観に問いを投げかける姿勢は評価できると思います。読む人によって、菖蒲に共感する人もいれば、私のように強い違和感を覚える人もいるでしょう。それだけ、議論を呼ぶ力を持った作品であるとも言えます。
最終的に、菖蒲は「シャネルが無くても完全勝利できる」境地に至るのでしょうか。それとも、結局は同じように男性に依存し、物質的な豊かさを追い求める生活に戻るのでしょうか。結末は読者に委ねられていますが、彼女が真の意味で「勝利」する未来を想像するのは、私には少し難しいと感じられました。北京の描写は素晴らしかっただけに、人物描写における不満点が残念に思える作品でした。
まとめ
綿矢りささんの小説「パッキパキ北京」は、コロナ禍の北京を舞台に、36歳の日本人女性・菖蒲の滞在を描いた物語です。鮮やかな北京の都市風景や食文化の描写は非常に魅力的で、読者を異国の地へと誘います。タオバオや小紅書といった現代中国ならではのツールを使いこなす菖蒲の姿も印象的でした。
一方で、主人公・菖蒲のキャラクター造形や、夫との関係性の描写には、読む人によって評価が大きく分かれるかもしれません。彼女の言動に見られる無知さや自己中心的な側面、ステレオタイプに感じられる部分に、違和感を覚える読者もいるでしょう。特に、物語の結末で示される「精神勝利法」をどう解釈するかで、作品全体の受け止め方が変わってきそうです。
この作品は、現代中国のリアルな空気感に触れたい方、そして、一筋縄ではいかない主人公の生き様を通して、現代社会や人間関係について考えてみたい方におすすめです。菖蒲というキャラクターに共感するか反発するか、ぜひご自身の目で見極めてみてください。
読後、様々な感想や意見が飛び交うであろう、刺激的な一冊であることは間違いありません。綿矢りささんの描く、一風変わった北京紀行を体験してみてはいかがでしょうか。