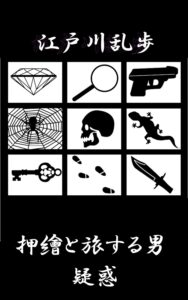 小説「疑惑」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。江戸川乱歩の短編の中でも、人間の心理、特に「疑い」という感情の恐ろしさを見事に描き出した作品として知られていますね。家族という最も身近な存在の間で繰り広げられる疑心暗鬼の渦は、読む者の心を強く揺さぶります。
小説「疑惑」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。江戸川乱歩の短編の中でも、人間の心理、特に「疑い」という感情の恐ろしさを見事に描き出した作品として知られていますね。家族という最も身近な存在の間で繰り広げられる疑心暗鬼の渦は、読む者の心を強く揺さぶります。
物語は、ある一家の主が殺害されるという衝撃的な事件から幕を開けます。容疑者はなんと、残された家族全員。父の死体のそばには、兄か主人公しか持っていないはずのハンカチが…。誰が犯人なのか、互いに疑いの目を向け合う家族の姿は、息苦しささえ感じさせます。
この物語の面白さは、単なる犯人当てに留まらない点にあると私は思います。会話形式で進む独特の構成、そして明らかになる意外な真相と、その真相が主人公にもたらす深い苦悩。人間の心の複雑さ、そして「疑う心」そのものが持つ罪深さについて、深く考えさせられるのです。
この記事では、そんな「疑惑」の物語の顛末と、私が感じたこと、考えたことを詳しくお伝えしていきたいと思います。少し長くなりますが、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。
小説「疑惑」のあらすじ
物語は、主人公「おれ」が友人に語りかける形で進みます。彼の父親が自宅の庭で、斧のようなもので殴られ殺害されたのです。父親は酒と女に溺れ、家族に暴力を振るうような人物で、正直なところ、家族の中にも彼を快く思わない者はいました。事件の翌日、「おれ」は友人に事件のあらましと、家族への疑念を打ち明けます。
事件が起きた夜、「おれ」は二階の自室で目が覚めていました。階下で物音がし、兄が部屋を出て一階へ下り、しばらくして戻ってくる足音を聞いていたのです。そして朝、庭で父親の遺体を発見したのは妹でした。騒ぎを聞きつけて庭へ駆けつけた「おれ」は、遺体のそばに見慣れたハンカチが落ちているのを見つけます。それは、自分と兄だけが持っているはずの特別なものでした。
その瞬間、「おれ」の心には兄への疑いが芽生えます。さらに兄が慌てて何かを拾い上げ、帯の中に隠すような素振りを見せたことも、「おれ」の疑いを深くします。しかし、観察していると、兄は母親を疑っているようなのです。兄が拾ったのは、母親が落とした櫛か何かだったのではないか、と「おれ」は考えます。
一方で、母親は妹の行動を怪しんでいる様子。「おれ」はある日、妹が庭の隅にある祠の後ろに何かを埋めている姿を目撃します。その様子を母親が縁側からじっと見ていました。後にそこから発見されたのは、血の付いた斧。父親殺害の凶器と見られるものでした。これで妹が犯人なのかと思いきや、当の妹は、「おれ」のことを心配そうに見つめ、(大丈夫、わたしはお兄ちゃんの味方だから)とでも言いたげな視線を送ってくるのです。妹は「おれ」を犯人だと思っているのでしょうか。
家族はお互いを疑い合い、家の中は針のような空気に満たされます。「おれ」は兄を、兄は母を、母は妹を、そして妹は「おれ」を…。警察の捜査も進み、外部の容疑者の疑いは晴れ、次第に家族へと疑いの目が向けられていきます。誰もが家族の中に犯人がいるのではないかという恐怖と疑念に苛まれ、「おれ」は心身ともに衰弱していきます。こんな状況はまさに地獄だと、「おれ」は友人に嘆くのでした。
事件から約一ヶ月後、「おれ」はついに事件の真相にたどり着きます。そして、友人にその驚くべき結末を告白するのでした。それは、誰も予想しなかった、そして「おれ」自身にとってもあまりにも残酷な真実だったのです。
小説「疑惑」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは小説「疑惑」を読んだ私の詳しい感想を、物語の核心に触れながらお話ししたいと思います。ネタバレを大いに含みますので、まだ結末を知りたくない方はご注意くださいね。この作品、本当にタイトルの「疑惑」という言葉が深く、重く響いてくる物語でした。
まず驚かされるのは、その構成です。主人公である「おれ」が友人に事件の経過や心境を語り、友人が相槌を打ったり質問したりする、という会話だけで物語が進行します。地の文が一切ない、まるで戯曲の台本のような形式ですね。これにより、読者は「おれ」の主観を通して事件を追体験することになります。彼の混乱や恐怖、そして家族への疑いが、ダイレクトに伝わってくるのです。
物語の序盤、傍若無人な父親が殺害され、家族全員に疑いがかかるという状況設定からして、もう引き込まれます。父親は決して良い人物ではなく、家族は複雑な感情を抱えていたでしょう。だからこそ、誰が犯人でもおかしくない、という空気が漂います。兄が怪しい、母が怪しい、妹が怪しい…「おれ」の視点を通して、次々と疑いの対象が移り変わっていく展開は、ミステリーとしての興味を掻き立てます。
特に印象的だったのは、それぞれの家族が見つけた「証拠」を隠す場面です。「おれ」は兄のハンカチを見つけ、兄は母の櫛(かもしれないもの)を拾い、母は妹が斧を隠すのを目撃します。普通のミステリーなら、これらは犯人を特定するための重要な手がかりとなるはずです。しかし、この物語では、彼らはそれを警察に届け出るのではなく、隠してしまう。なぜなら、それぞれが他の家族を「犯人かもしれない」と思い、そして無意識のうちに「かばおう」としているからです。この、疑いながらもかばおうとする複雑な心理描写が、実に巧みだと感じました。
家族がお互いを疑い合い、家の中がギスギスしていく様子は読んでいて本当に辛いものがあります。「おれ」は兄を疑い、兄は母を疑い、母は妹を、そして妹は「おれ」を疑っているように見える…。誰もが善意から他の家族をかばおうとしているのに、その行動がさらなる疑念を生み、疑心暗鬼の連鎖に陥っていく。まさに「疑惑」が生み出す地獄絵図です。家族という最も信頼し合えるはずの共同体が、疑いによって崩壊していく様は恐ろしく、そして悲しいですね。
そして、物語は衝撃的な結末を迎えます。犯人は、なんと「おれ」自身だった、というのです。しかし、それは彼が意図的に父親を殺害したという意味ではありません。真相は、偶然の産物でした。事件の夜、「おれ」は窓の外の猫の騒ぎに気づき、窓を開けます。驚いた猫が松の木に飛びつき、その衝撃で、以前「おれ」が枝を切るために置き忘れていた斧が落下。ちょうどその下で涼んでいた父親の頭を直撃した、というのです。落ちていたハンカチも、その斧の柄に巻き付けていた「おれ」自身のものだったのです。
この「無意識の犯行」という結末には、正直なところ、少し驚きました。フロイトの精神分析学を持ち出して、「物忘れ」や「無意識の願望」で説明しようとしていますが、現代の感覚からすると、やや強引に感じる部分もあるかもしれません。斧を置き忘れていたこと、猫が騒いだこと、父親がたまたまそこにいたこと…あまりにも偶然が重なりすぎている、と。ミステリーとしてのトリックや論理性を重視する読者にとっては、少し物足りなさを感じる可能性はあるでしょう。
しかし、私が思うに、この物語の本当の核心は、この「無意識の犯行」というトリックそのものではないのです。重要なのは、この真相を知った後の「おれ」の苦悩です。彼は、自分が物理的に父親を殺した(たとえ偶然であっても)こと以上に、もっと深い罪悪感に苛まれます。
それは何かというと、「自分だけが家族を疑っていた」という事実です。真相が明らかになってみれば、兄も、母も、妹も、それぞれが「おれ」を犯人だと思い、彼をかばうために証拠を隠したり、心配したりしていたことが分かります。彼らは皆、「おれ」を思いやる「無類の善人」だったのです。その中で、「おれ」ただ一人が、彼らの善意に気づかず、疑心暗鬼に陥り、大切な家族を疑いの目で見ていた。この「疑惑の心」こそが、何よりも醜く、罪深いものだったのだ、と彼は悟るのです。
「みんな無類の善人だった。その中で一人、みんなを疑う疑惑の心を持っていたおれだけは、まさに悪人だったというほかにないではないか。」という彼の言葉は、胸に突き刺さります。物理的な加害行為よりも、人を疑う心のほうが罪深い、というこの価値観の転換。これこそが、江戸川乱歩がこの作品を通して伝えたかったメッセージなのではないでしょうか。タイトルの「疑惑」が、単なるミステリーの要素ではなく、物語の主題そのものであることが、ここで鮮やかに浮かび上がってきます。
もちろん、だからといって父親が亡くなったこと自体が良いことだった、とは言えません。どんなにひどい父親であっても、命が失われたことは悲劇です。しかし、物語はそこを単純な善悪で割り切るのではなく、「おれ」の内面的な葛藤、罪悪感に焦点を当てています。父親の死を悲しめない自分、そして家族を疑ってしまった自分。その二重の苦しみが、「おれ」を深く苛むのです。
この物語はまた、友人関係の重要性も示唆しているように感じます。「おれ」は終始、友人に自分の苦しい胸の内を打ち明けます。事件の不可解さ、家族への疑念、そして最終的な告白まで。この友人がいなければ、「おれ」は一人で抱え込み、もっと早く精神的に破綻してしまっていたかもしれません。何でも話せる友人の存在が、彼にとってどれほどの救いになっていたことか。信頼できる他者がいることの大切さを、改めて考えさせられました。
会話形式で進む物語は、読みやすさにも繋がっています。登場人物は実質的に「おれ」と友人の二人だけなので、複雑な人間関係に惑わされることなく、「おれ」の心理変化に集中できます。短い作品ながら、人間の心の闇と、そこからかろうじて見出される一条の光(家族の愛や友情)を描き切っている点は、さすが江戸川乱歩だと感じ入りました。
「疑惑」という感情は、誰の心にも潜むものです。些細なきっかけで芽生え、一度根付くとどんどん大きく膨らんで、人間関係を蝕んでいく。この物語は、そんな「疑惑」の恐ろしさを、家族という最も身近な関係性を通して、まざまざと見せつけてくれます。
そして同時に、たとえ疑心暗鬼に陥ったとしても、その根底には家族を思う気持ちがあったのだという救いも示唆されているように思います。結果的に「おれ」以外の家族は、彼をかばおうとしていたわけですから。その事実に気づいた時の「おれ」の衝撃と罪悪感は計り知れませんが、同時に、家族の深い愛情を再認識するきっかけにもなったのではないでしょうか。
読み終えた後、自分自身の心の中にある「疑い」について、少し考えてしまいました。人を信じることの難しさ、そして大切さ。この「疑惑」という作品は、ミステリーの面白さだけでなく、人間心理の深淵を覗かせてくれる、味わい深い一作だと言えるでしょう。考えさせられる点の多い、印象的な読書体験でした。
まとめ
江戸川乱歩の「疑惑」は、単なる犯人探しのミステリーを超えた、人間の心理、特に「疑う心」の恐ろしさと罪深さを鋭く描いた作品でしたね。主人公「おれ」が、殺害された父親の事件を巡り、兄、母、妹といった家族を次々と疑っていく過程は、読んでいて息苦しくなるほどでした。
会話形式で進む独特の構成は、「おれ」の主観的な視点や感情の揺れ動きを際立たせ、読者を引き込みます。家族それぞれが、互いをかばおうとして証拠を隠す行動が、かえって疑念を増幅させていく展開は、皮肉でありながらも人間の心理を巧みに捉えていると感じました。
そして明かされる「無意識の犯行」という真相。トリックとしては賛否あるかもしれませんが、重要なのはその後の「おれ」の気づきです。自分以外の家族は皆、自分をかばおうとしていた善人であり、自分だけが彼らを疑っていた。その「疑惑の心」こそが悪であった、という結論は、物語の核心であり、タイトルの意味を深く考えさせられます。
この作品は、家族間の愛憎や信頼、そして友情といったテーマにも触れながら、「疑い」という普遍的な感情がいかに人間関係を蝕むかを教えてくれます。ミステリーとしての面白さはもちろん、読後に人間の心の複雑さについて深く考えさせられる、忘れがたい一作です。






































































