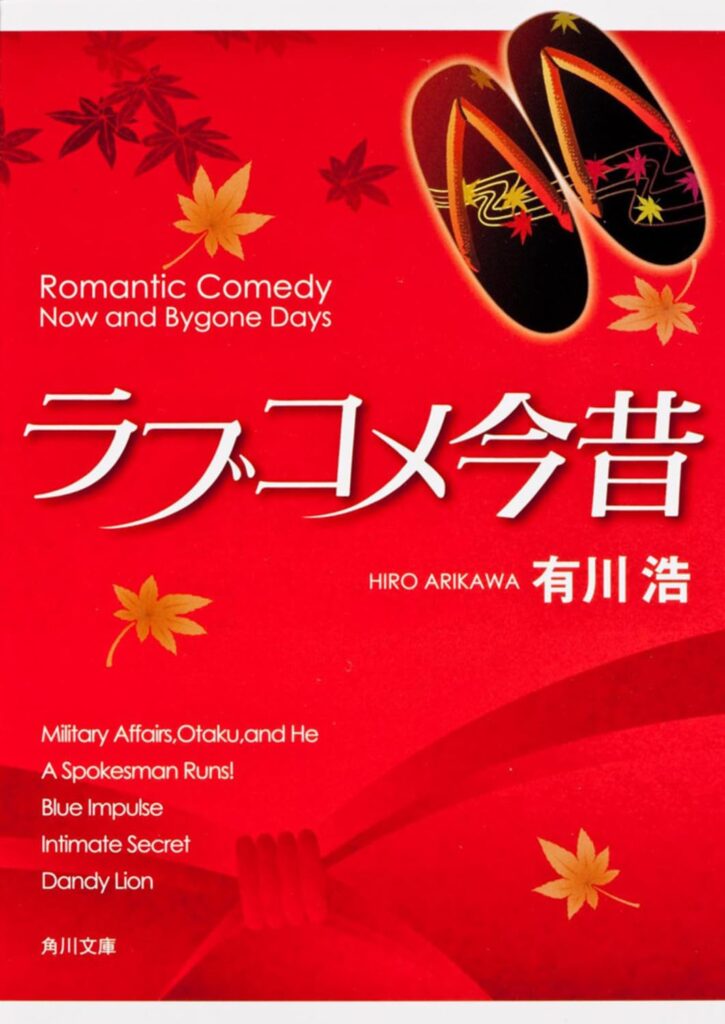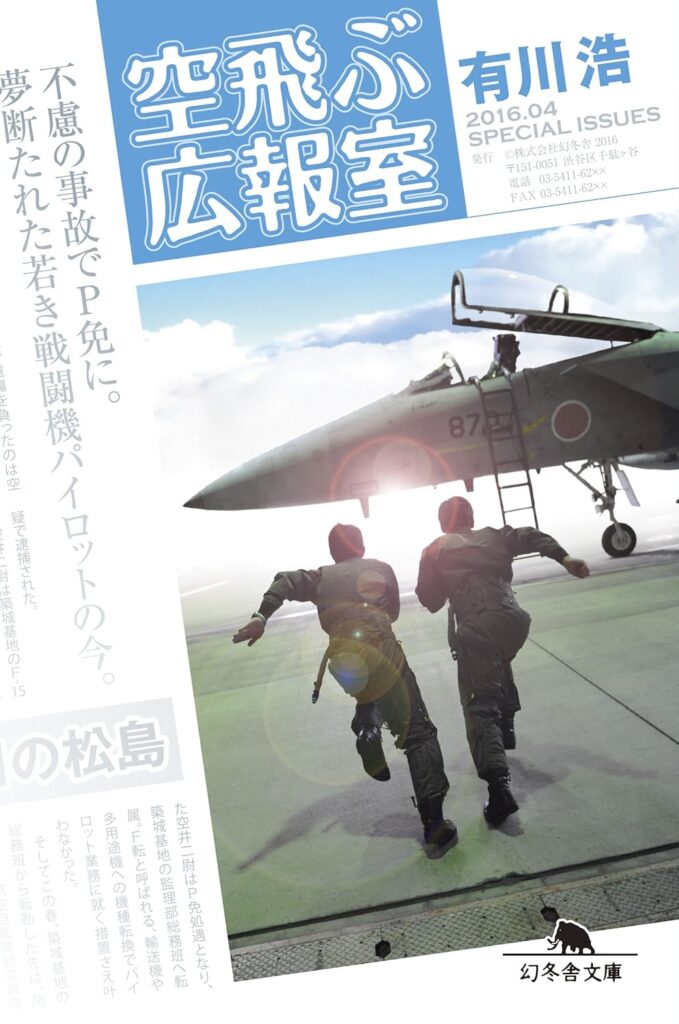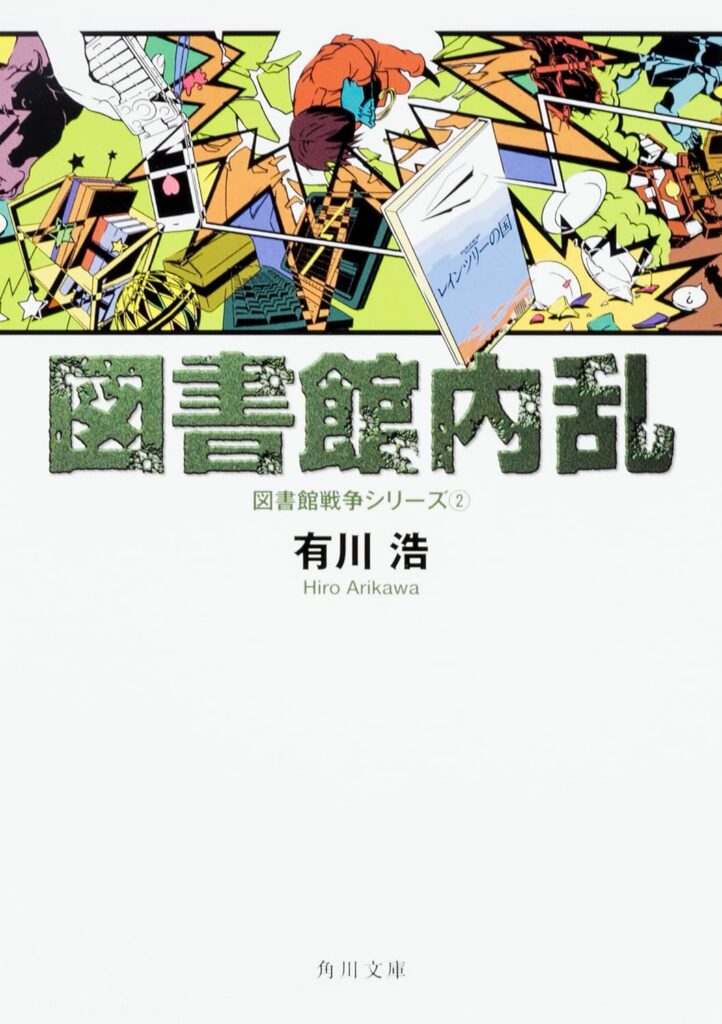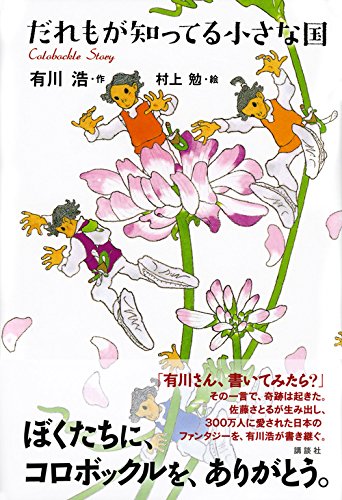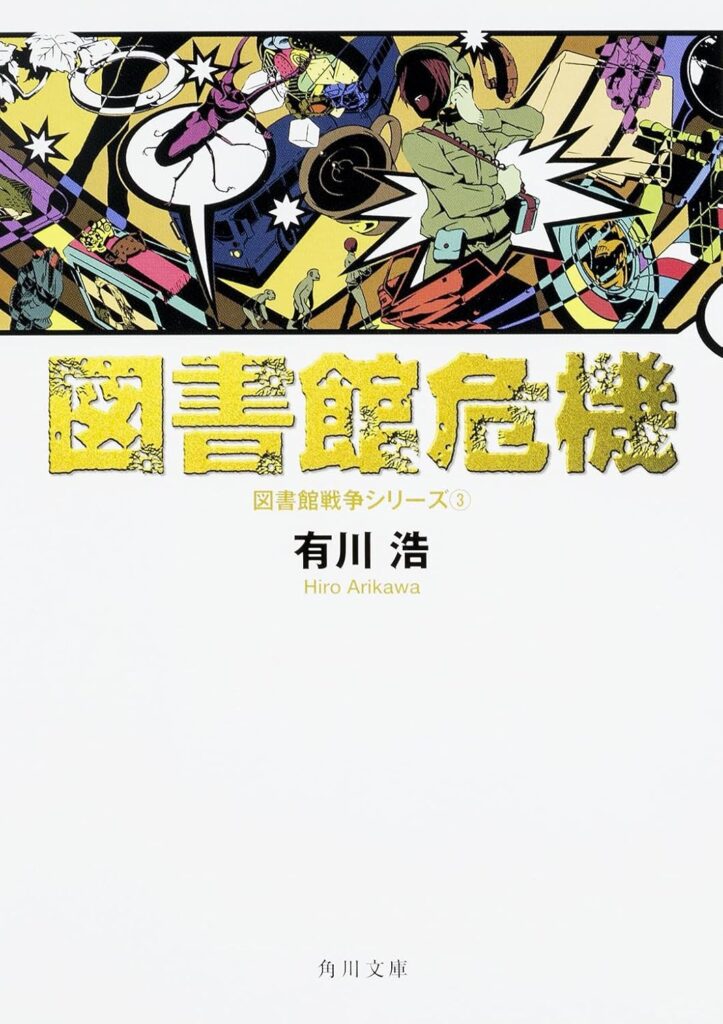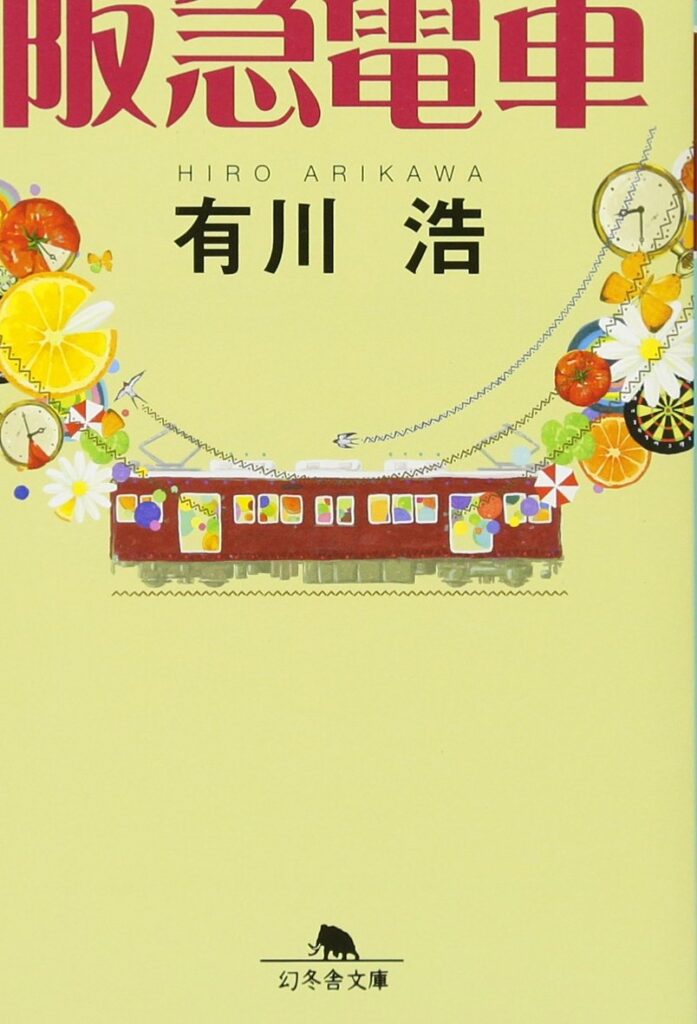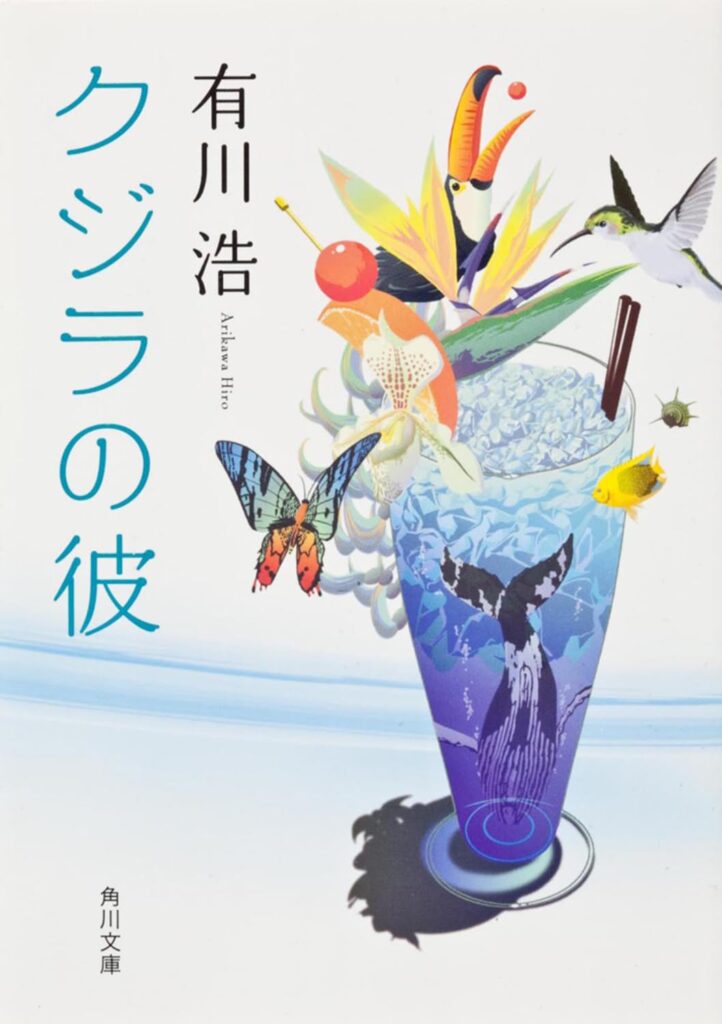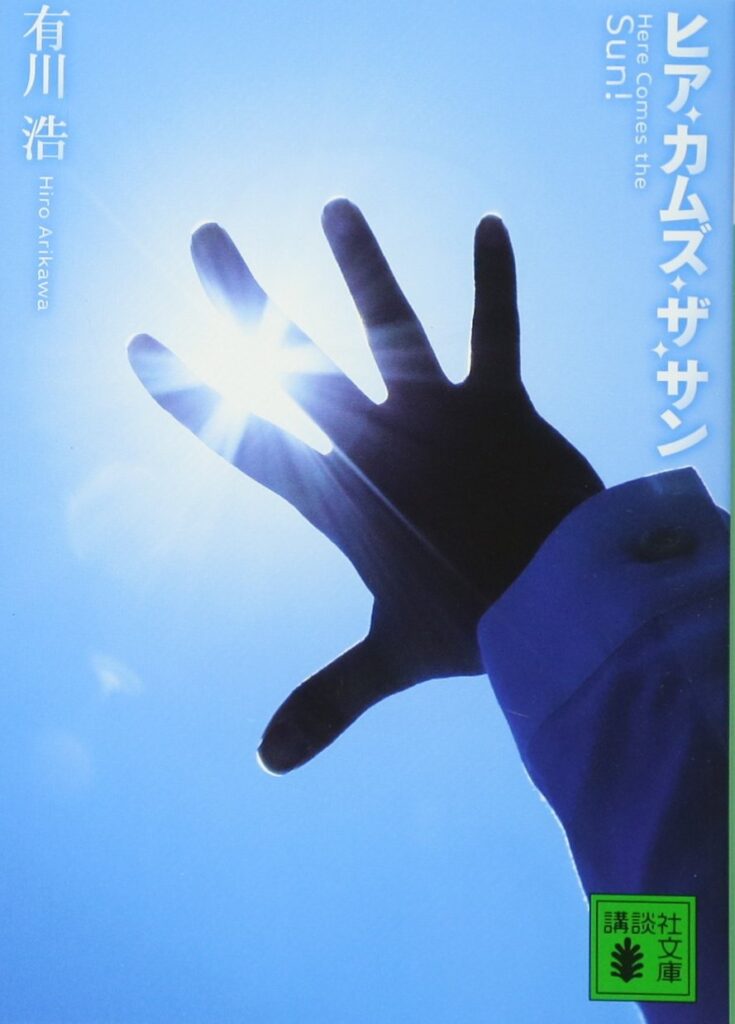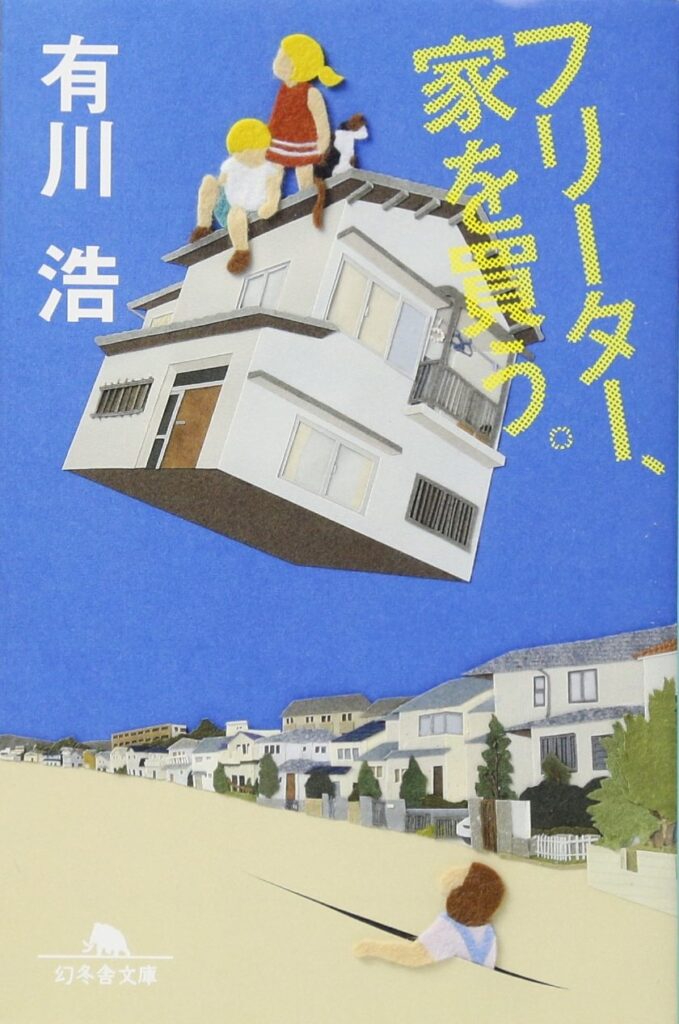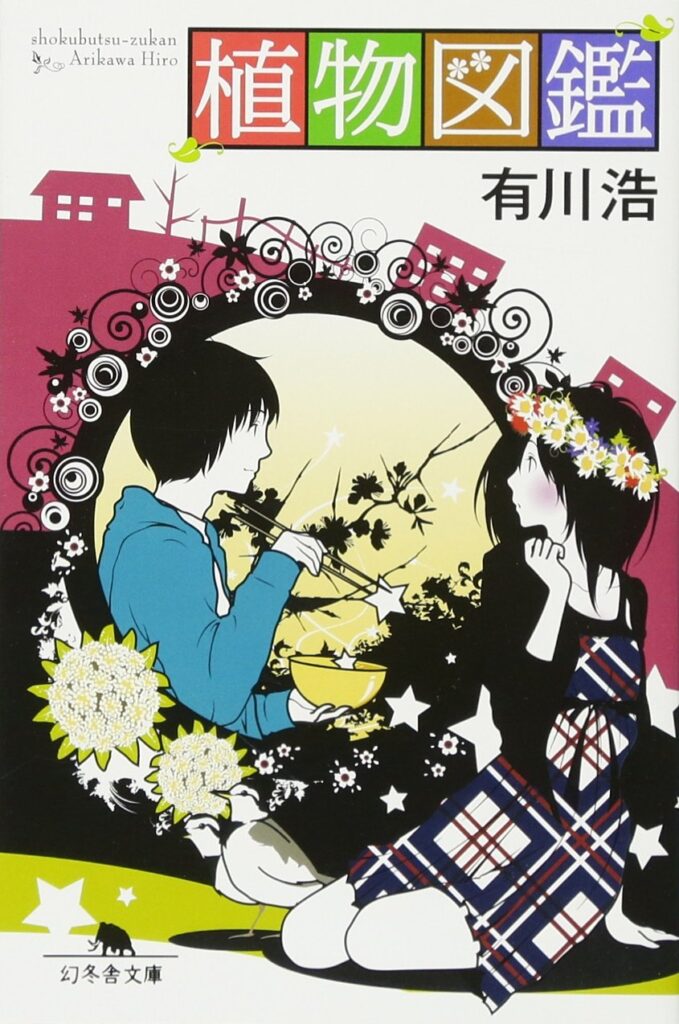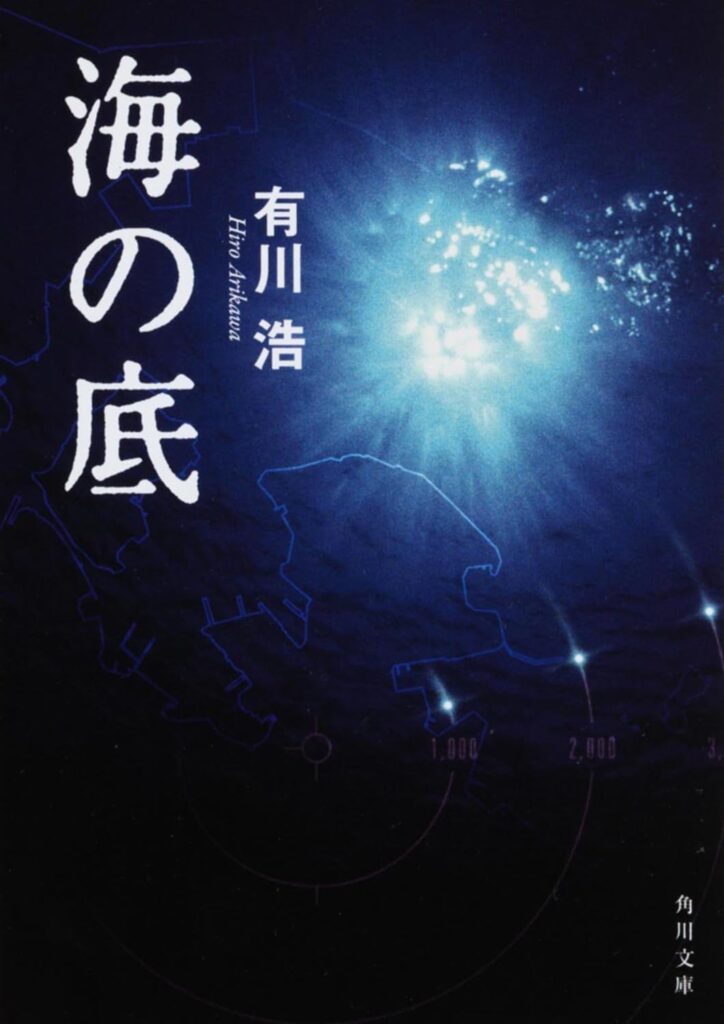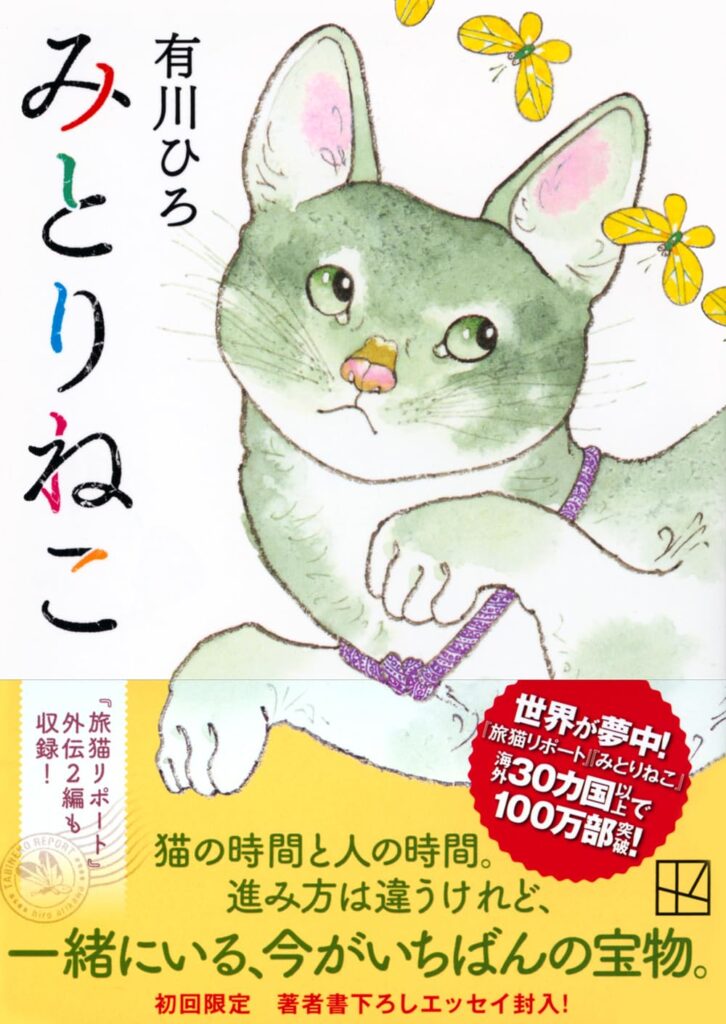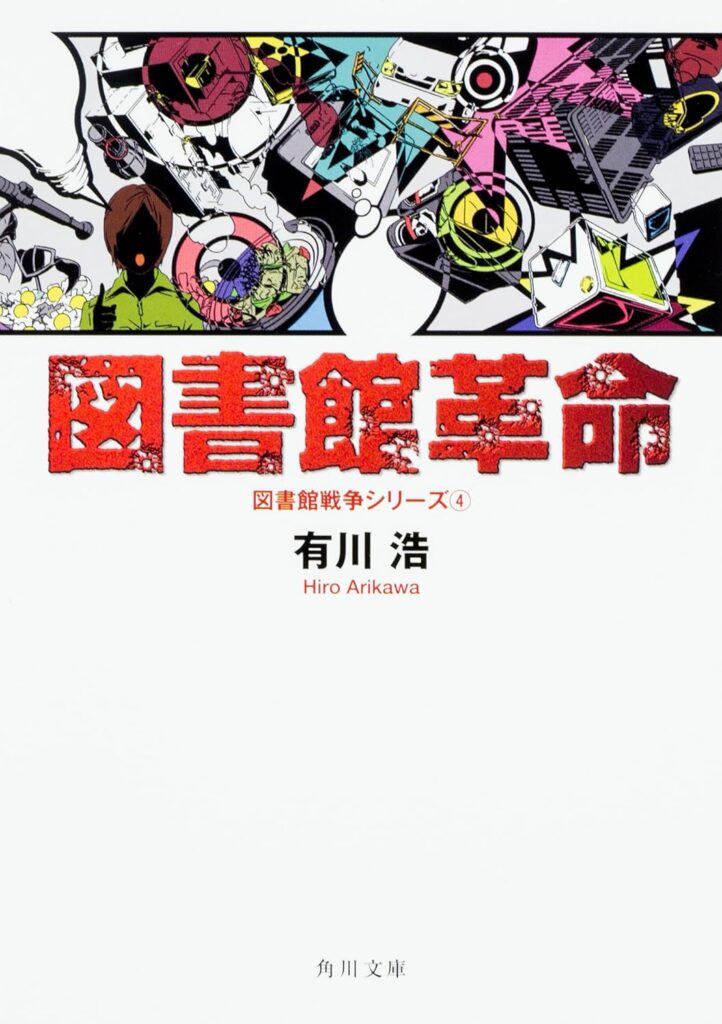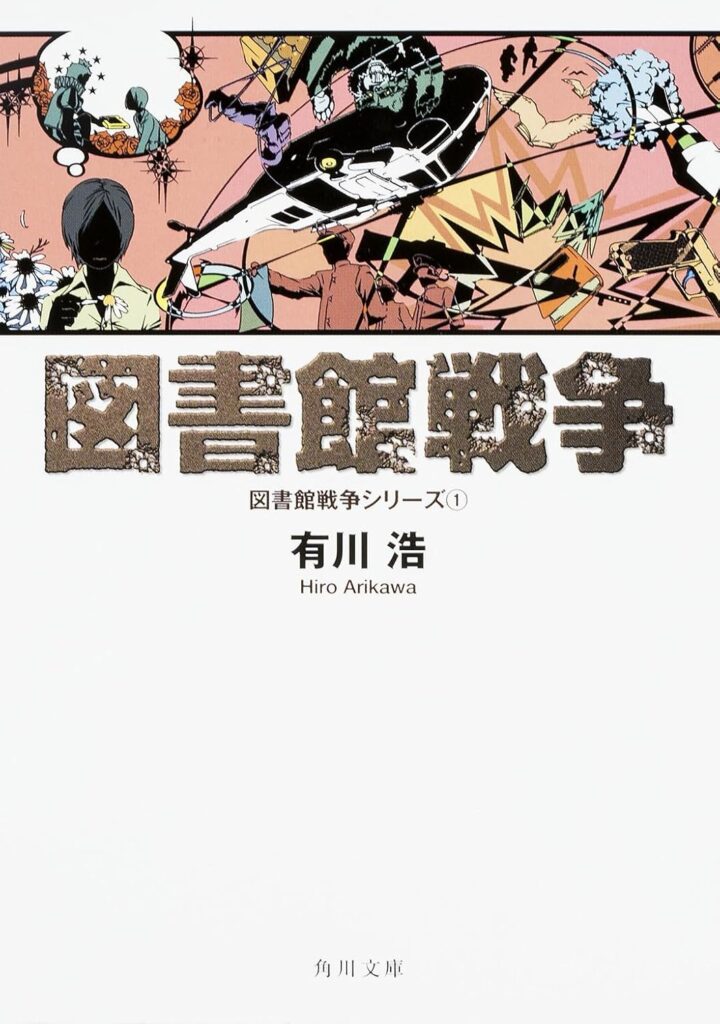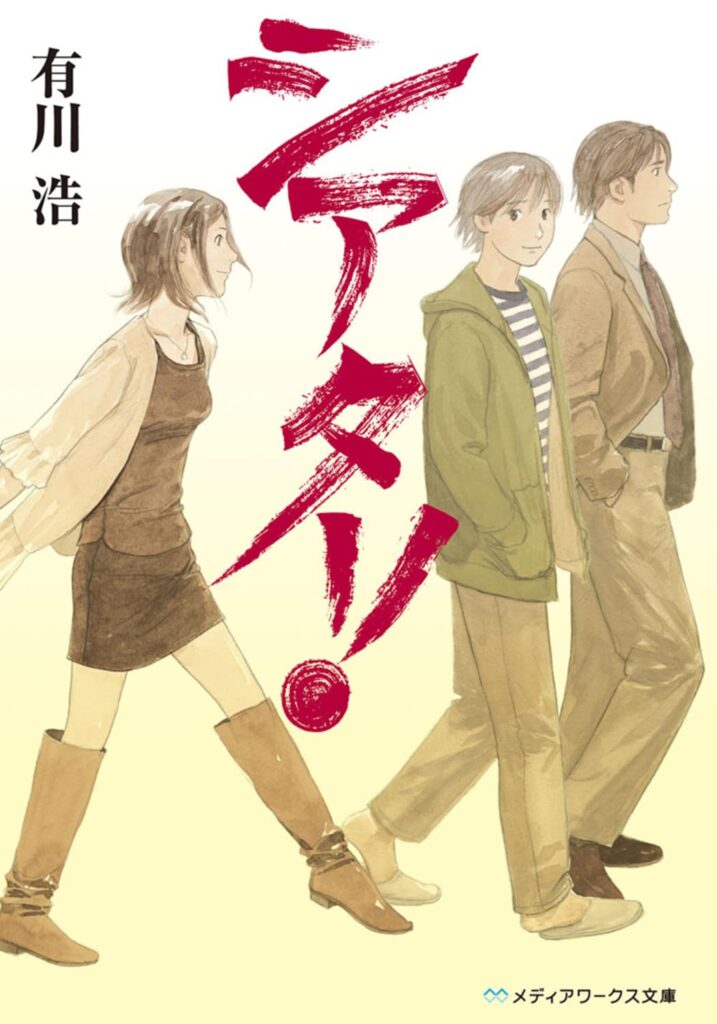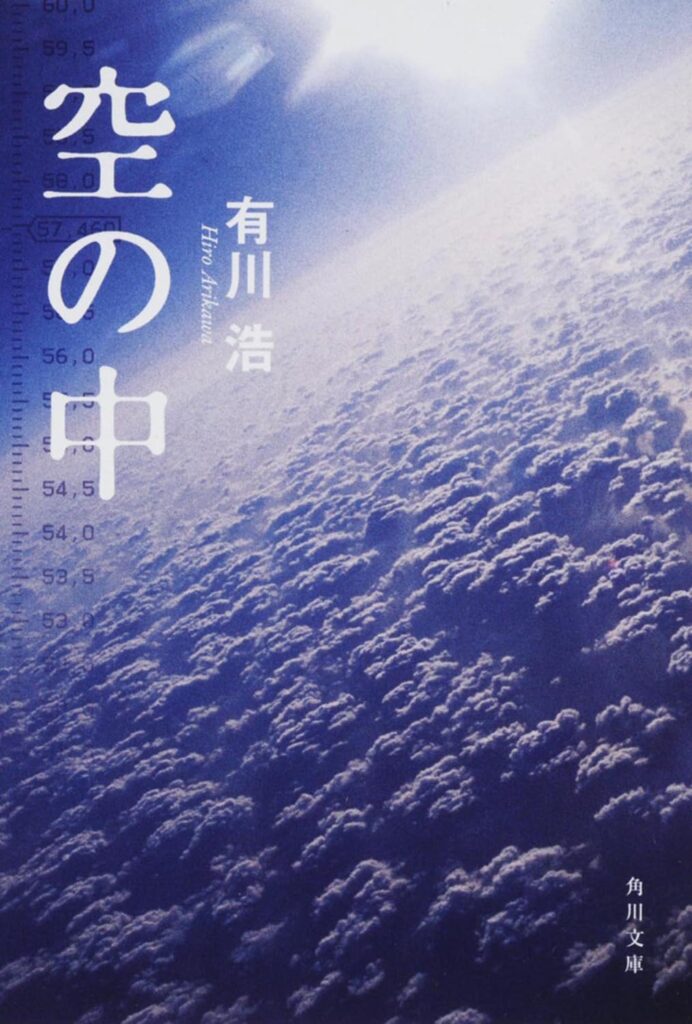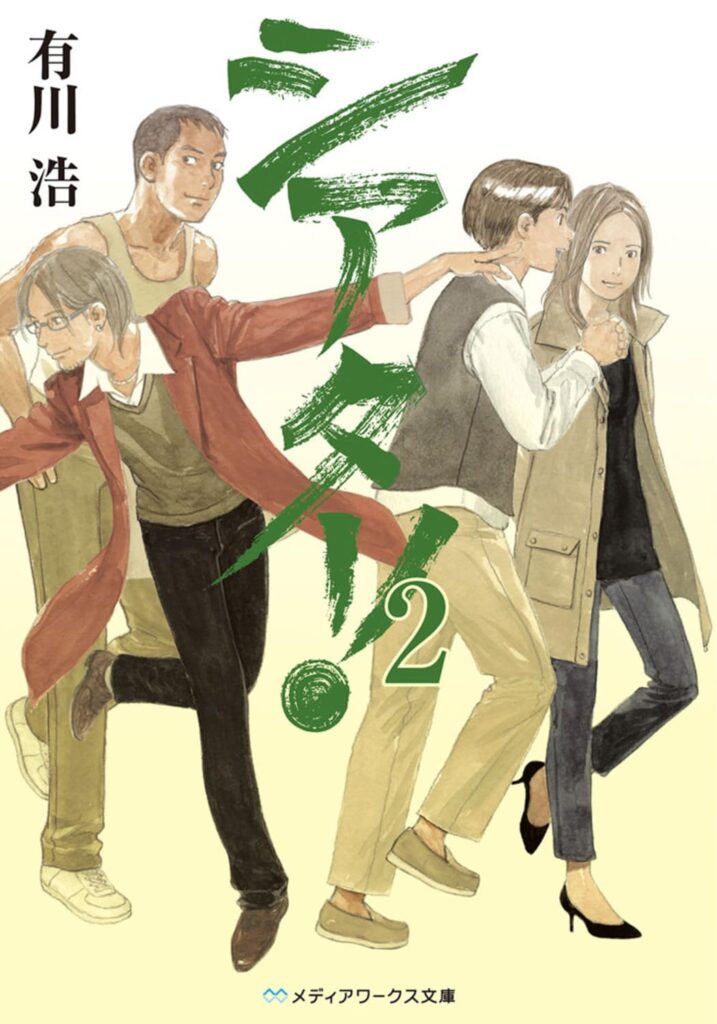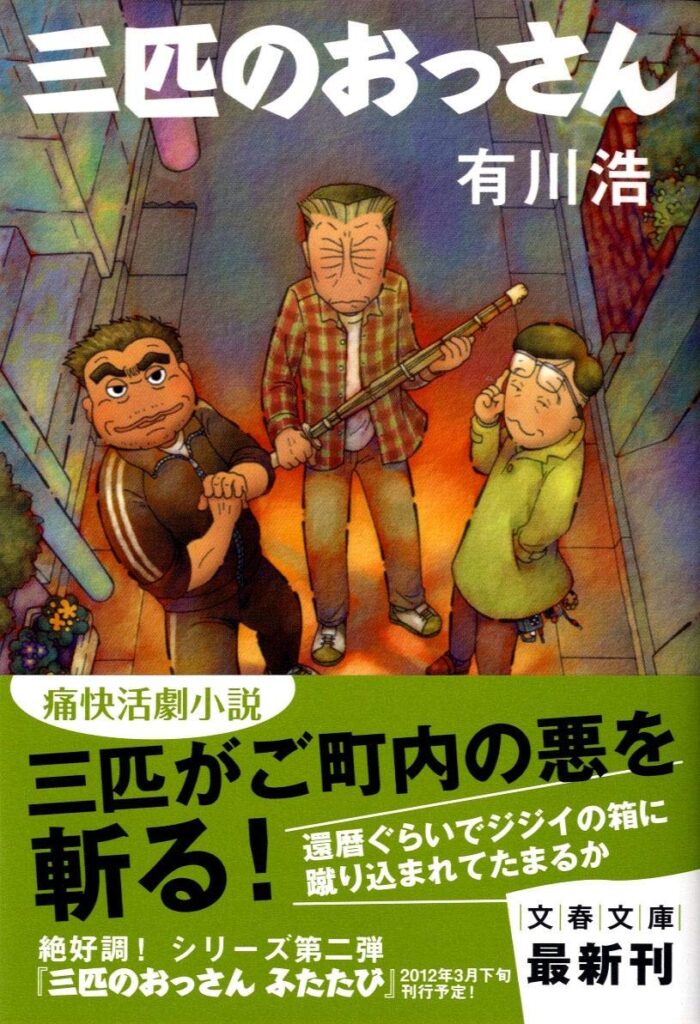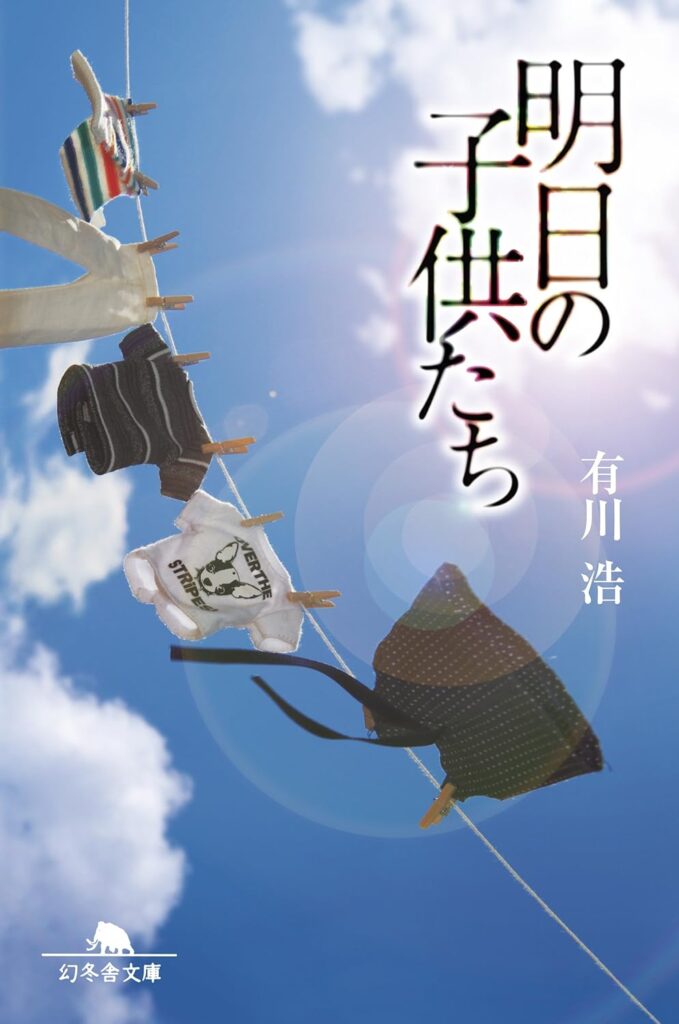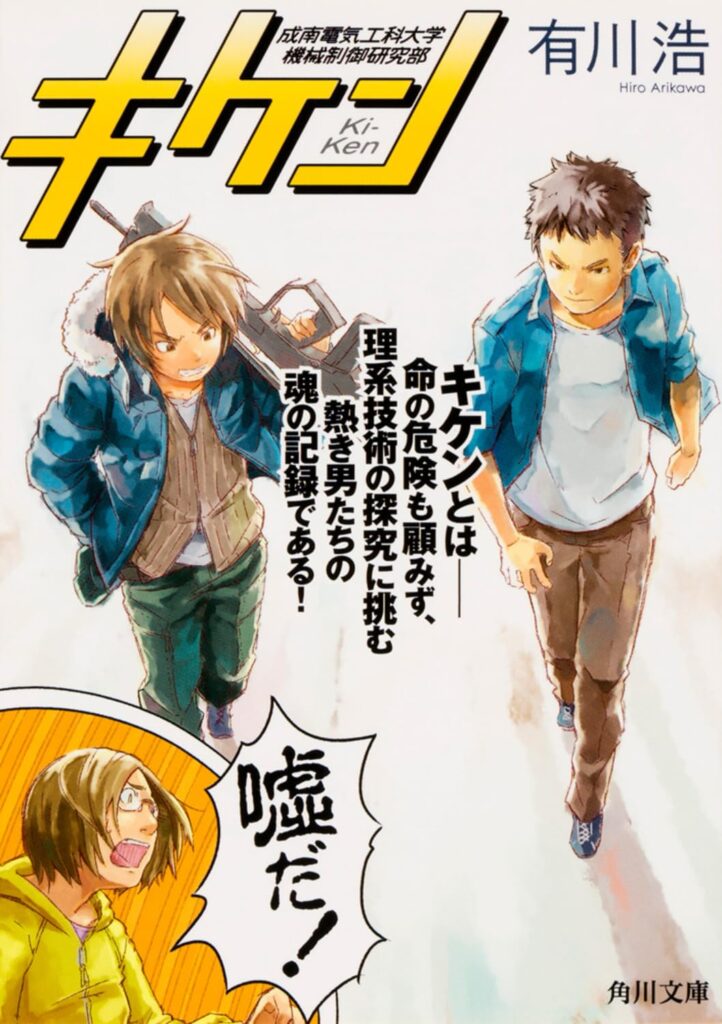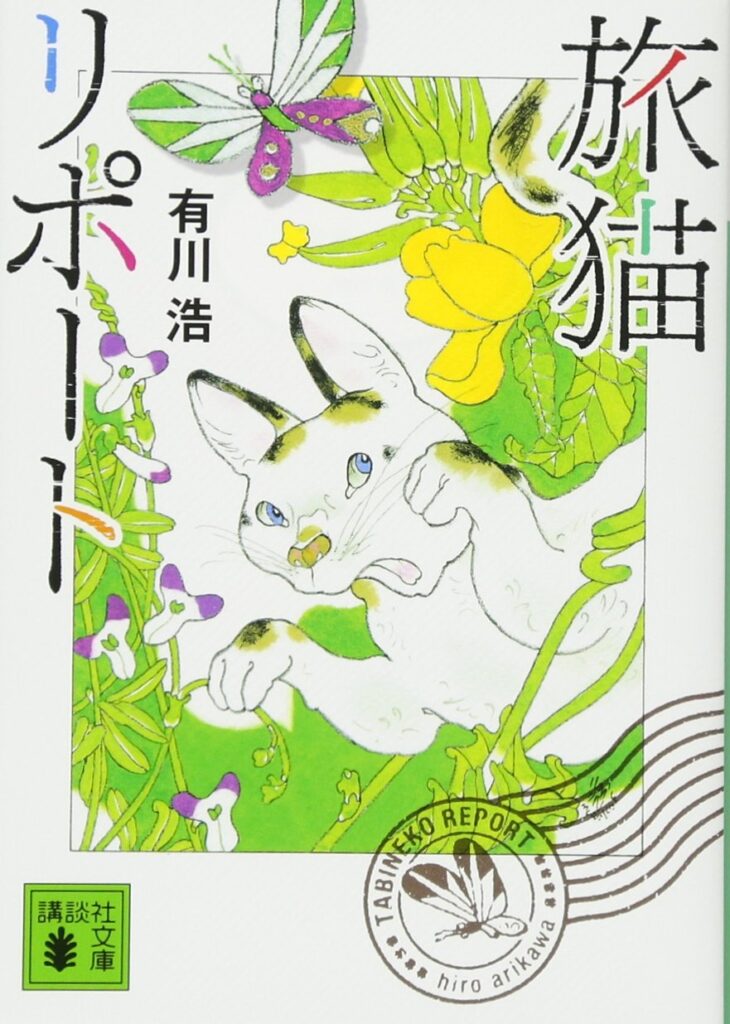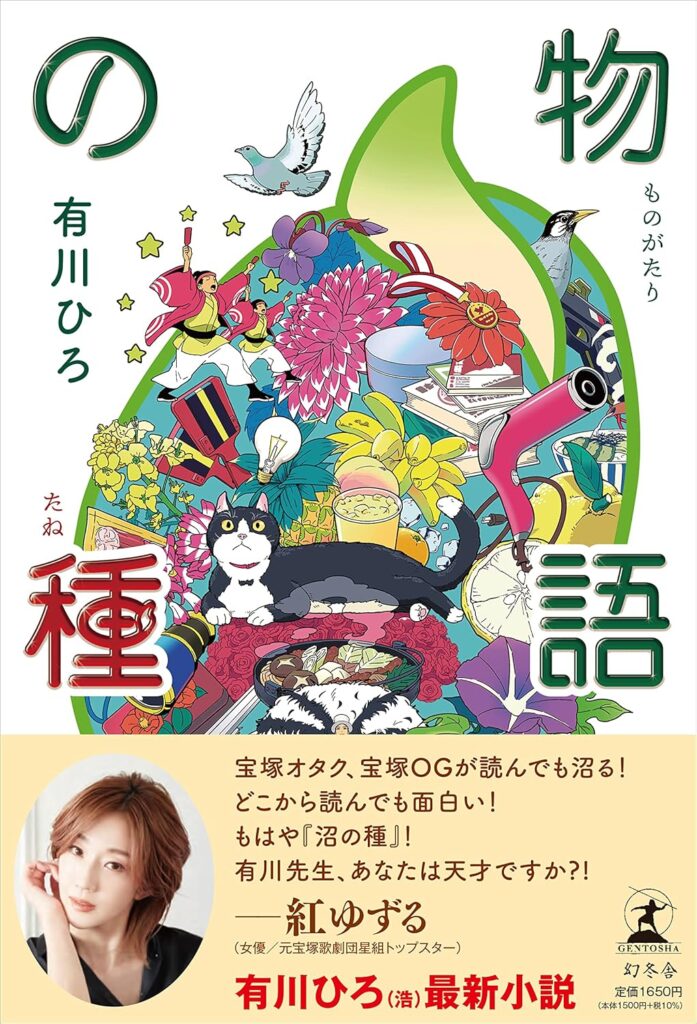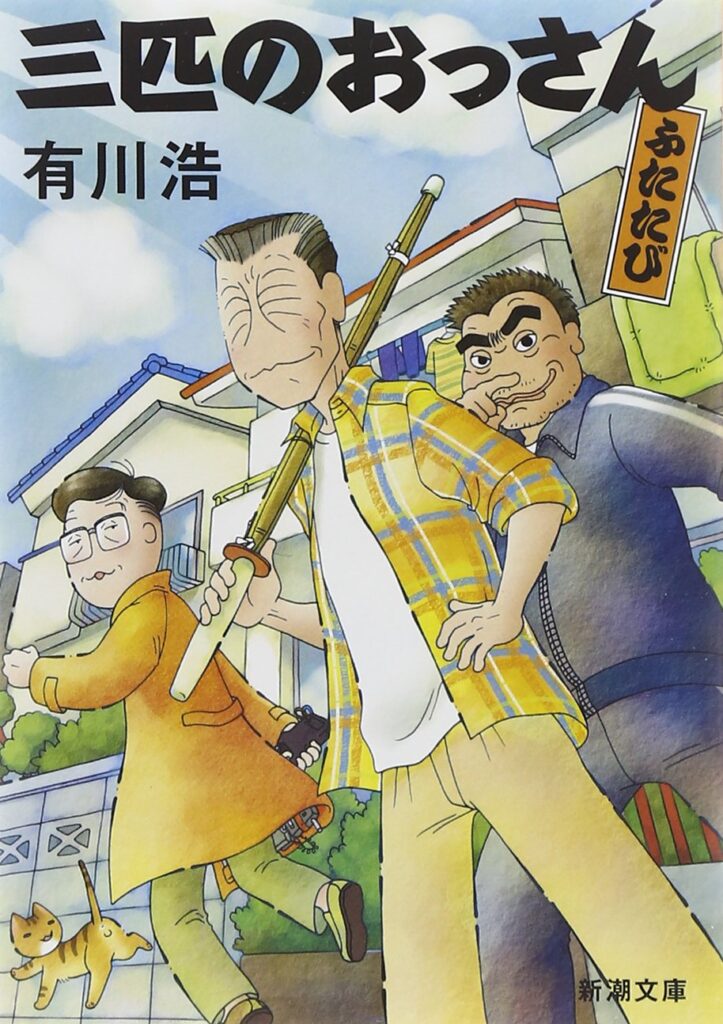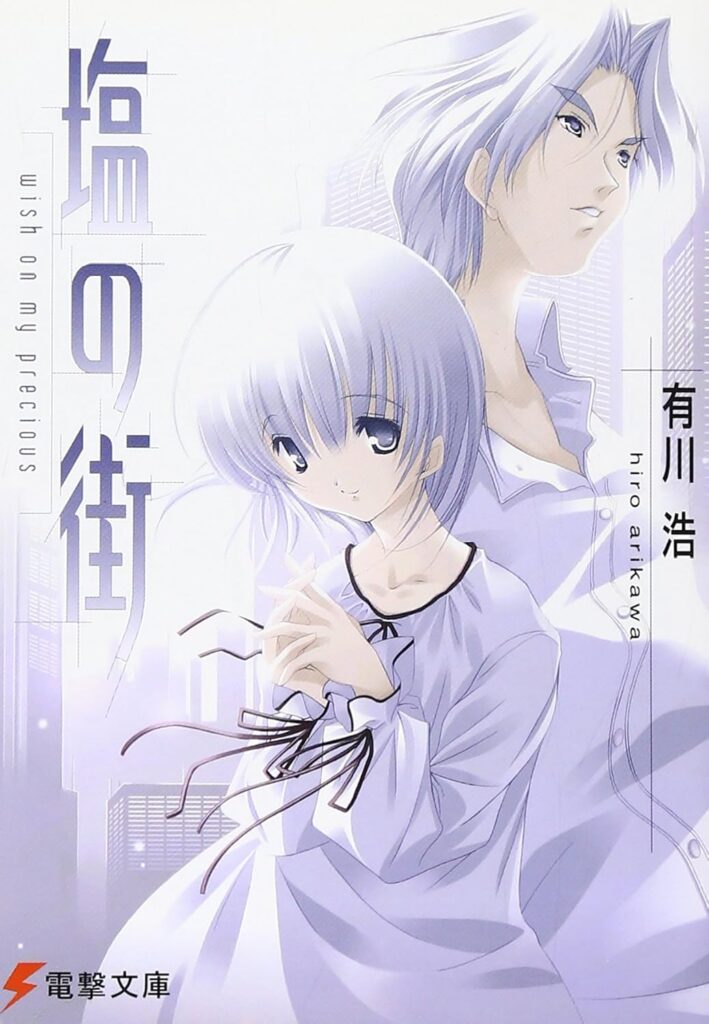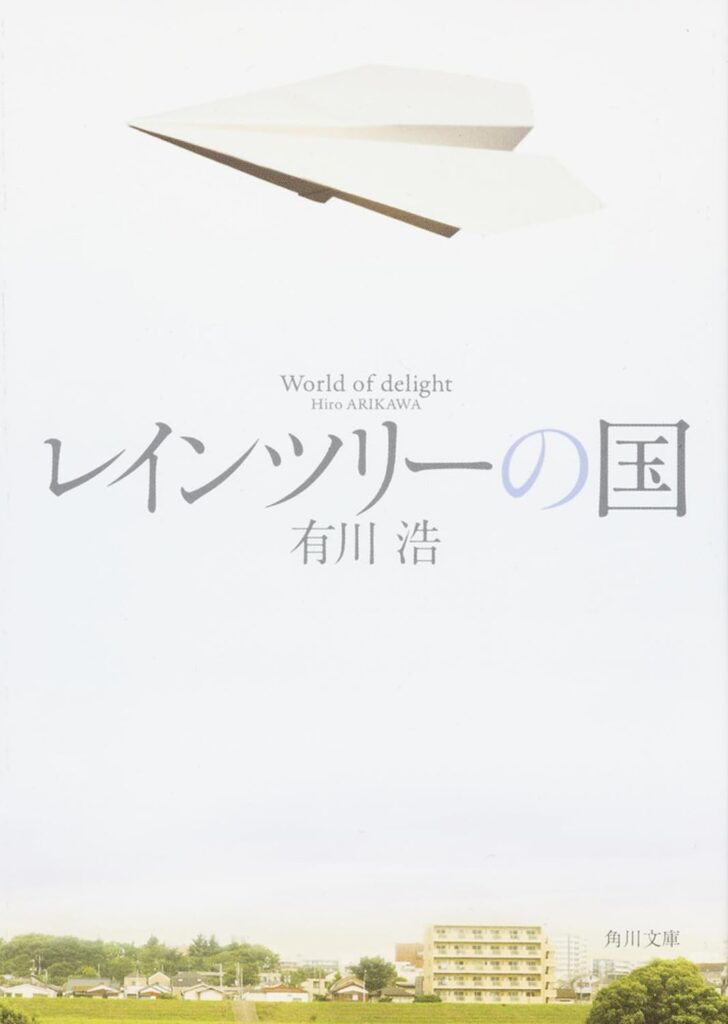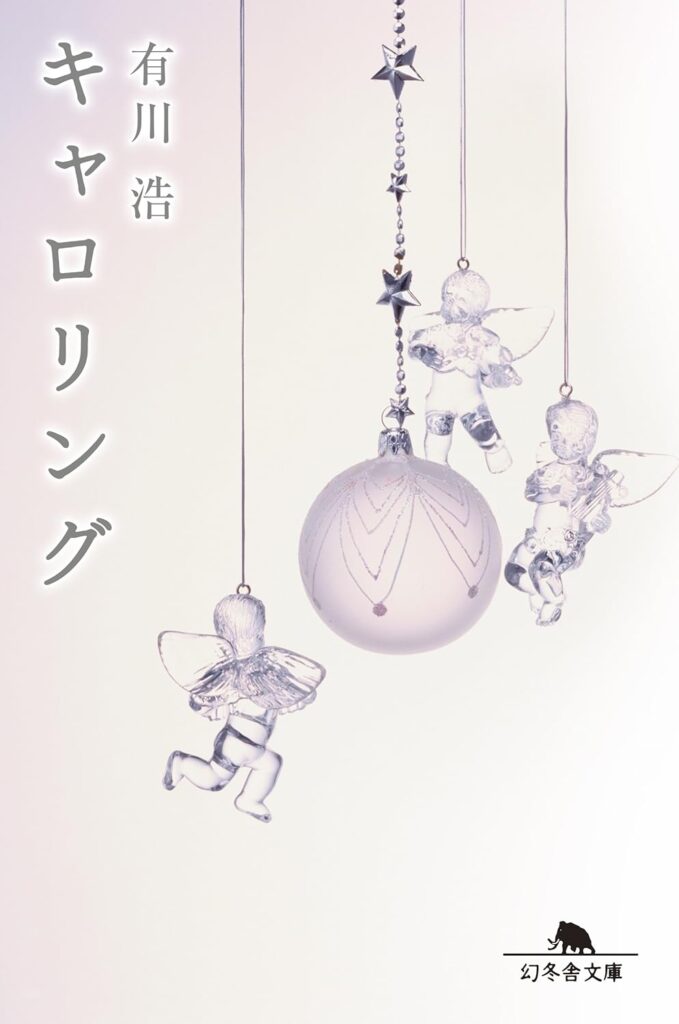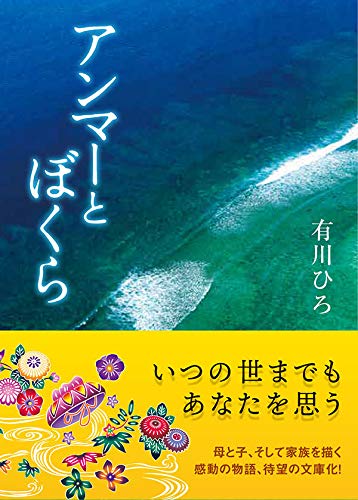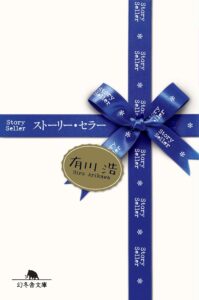 小説「ストーリー・セラー」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。有川浩さんが紡ぎ出す、愛と創作、そして切ない運命の物語は、多くの読者の心を掴んで離しません。一組の夫婦が直面する過酷な試練と、それでも失われない深い絆が描かれています。
小説「ストーリー・セラー」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。有川浩さんが紡ぎ出す、愛と創作、そして切ない運命の物語は、多くの読者の心を掴んで離しません。一組の夫婦が直面する過酷な試練と、それでも失われない深い絆が描かれています。
この物語は、単なる恋愛小説ではありません。創作活動とは何か、生きるとはどういうことか、そして愛する人を想う気持ちの強さとはどれほどのものなのかを、私たちに問いかけてきます。「Side-A」と「Side-B」という二つのパートから成る構成も特徴的で、物語の奥深さをより一層引き立てています。
本記事では、物語の核心に触れる部分も含めて、その概要と、私が感じたこと、考えさせられたことを詳しくお伝えしていきたいと思います。読み進めるうちに、きっとあなたもこの物語の世界に引き込まれることでしょう。
小説「ストーリー・セラー」のあらすじ
物語は、デザイン事務所で働く「彼女」が趣味で書いていた小説を、同僚の「彼」が偶然見つけるところから始まります。彼は彼女の才能に心惹かれ、唯一の読者となります。やがて二人は恋に落ち、結婚。彼女は彼の後押しもあり、兼業作家から専業作家へと転身し、大きな成功を収めます。多額の印税、次々と舞い込む執筆依頼。順風満帆に見えた作家人生でした。
しかし、成功には影が伴います。妬みやっかみ、心ない誹謗中傷が彼女を襲います。大学時代の文芸部の先輩による悪意ある記事、疎遠だった親戚からの金の無心、そして実の父親からの嫉妬と中傷。心身ともに疲弊した彼女はうつ病と診断され、投薬治療を余儀なくされます。それでも彼女にとって、書くことは生きることそのものでした。
そんな彼女を更なる悲劇が襲います。ある日倒れた彼女は、精密検査の結果、「致死性脳劣化症候群」という架空の難病に侵されていることが判明します。それは、思考を重ねるほど脳の機能が劣化し、死に至るという、作家にとってはあまりにも残酷な病でした。医師からは思考を極力避けるよう宣告されますが、彼女は書くことを完全には諦められません。
彼女は、残された時間の中で、ただ一人、愛する「彼」のためだけに物語を書き続けることを決意します。自分の命を削りながら、彼への愛と感謝を込めて、最後の物語を紡いでいくのでした。そして、彼が帰宅したある日、彼女は机に向かったまま、静かに息を引き取っていました。彼女が遺した原稿は、彼と彼女自身の物語「ストーリー・セラー」を含む作品集として出版され、大きな反響を呼ぶことになります。この「Side-A」の物語は、実は「Side-B」で彼女が書いた作中作であることが示唆され、物語は入れ子構造を成していきます。
小説「ストーリー・セラー」の長文感想(ネタバレあり)
この「ストーリー・セラー」という作品に、私は深く心を揺さぶられました。読み終えた後、しばらくの間、物語の世界から抜け出せずに、登場人物たちの運命や、そこに込められた想いについて考え続けてしまいました。有川浩さんの作品はこれまでもいくつか読んできましたが、この物語が持つ切実さ、そして愛の深さは、格別なものがあるように感じています。
物語の前半、「彼」と「彼女」の出会いから、彼女が作家として成功していく過程は、どこか微笑ましく、希望に満ちています。互いの才能を認め合い、支え合う二人の姿は、理想的なパートナーシップそのものです。彼が彼女の最初の読者となり、彼女の背中を押し、彼女がそれに応えて才能を開花させていく。創作という共通項が二人を結びつけ、愛を育んでいく様子は、読んでいて心が温かくなりました。特に、彼が彼女の才能を信じ、専業作家になることを後押しする場面は、相手への深い信頼と愛情が感じられて印象的でした。
しかし、物語はすぐにその輝きに影を落とし始めます。成功に伴う妬みや誹謗中傷。これは現実の世界でも、多かれ少なかれ起こりうることなのかもしれませんが、作中で描かれるそれは、読んでいて胸が痛くなるほど執拗で悪意に満ちています。特に、かつて同じ場で創作を志したであろう大学の先輩や、実の父親からの攻撃は、彼女の心を深く傷つけます。信頼していたはずの人々からの裏切りや否定は、どれほど辛かったことでしょう。それでも彼女が書くことをやめなかったのは、それが彼女自身のアイデンティティであり、彼との繋がりを確かめる術でもあったからなのかもしれません。彼の変わらない支えが、暗闇の中の一筋の光となっていたのでしょう。
そして、物語を決定的に悲劇の色に染めるのが、「致死性脳劣化症候群」という病の宣告です。考えることが、つまりは物語を紡ぐことが、自らの命を縮める行為になる。作家にとって、これほど残酷な宣告があるでしょうか。生きるために書くことを諦めるか、書くために死を選ぶか。究極の選択を迫られた彼女の絶望は計り知れません。医師から「考えないように」と言われ、料理や掃除といった単純作業に没頭しようとする彼女の姿は、痛々しく、切なくてなりませんでした。
それでも、彼女は書くことを選びます。ただし、それは不特定多数の読者のためではなく、ただ一人、愛する彼のためだけに。この決断に、私は彼女の覚悟と、彼への深い愛情を感じずにはいられませんでした。自分の命と引き換えにしてでも、彼に伝えたい想いがある。物語を紡ぐという行為が、彼女にとって彼への最大の愛の表現となったのです。まるで、残り少ない蝋燭の火を燃やし尽くすように、彼女は最後の力を振り絞ってペンを(あるいはキーボードを)走らせます。その姿を想像すると、涙が止まりませんでした。
彼女が亡くなり、彼が遺された原稿を読む場面。そして、それが「ストーリー・セラー」というタイトルで出版される経緯。ここにも、深い愛の形が見て取れます。彼女の最期の想いを、彼はきちんと受け止め、世に送り出す。それは、彼女が生きた証であり、二人の愛の物語を永遠にするための行為だったのでしょう。読者からの賛否両論を受け止めながらも、彼は彼女の意志を守り抜こうとします。
ここで物語は、「Side-A」が実は彼女の書いた作中作であった可能性を示唆する「Side-B」へと繋がっていきます。この入れ子構造が、この物語を単なる悲劇的な恋愛物語以上のものにしています。「Side-B」では、病に倒れるのが彼であり、彼女が彼を看病する立場になります。これは、「Side-A」で描かれた物語が、彼女の現実(あるいは願望)を反映したものだったのかもしれない、という解釈を可能にします。
もし「Side-A」が彼女の創作物だとしたら、彼女はなぜ、自分自身が難病で死ぬという物語を書いたのでしょうか。それは、来るべき(あるいは既に訪れている)現実の苦難を、物語の力で乗り越えようとしたからかもしれません。あるいは、彼を失うことへの恐怖を、物語の中で反転させることで、現実の彼が生き続けることを願った「逆夢」のようなものだったのかもしれません。
この構造によって、私たちは「物語を書くこと」「物語を読むこと」の意味を改めて考えさせられます。物語は、現実逃避の手段であると同時に、現実と向き合い、それを乗り越えるための力を与えてくれるものでもある。彼女にとって書くことは、生きることであり、愛することであり、そして祈ることであったのかもしれません。
「致死性脳劣化症候群」という架空の病気の設定も、非常に考えさせられるものでした。これは、創作活動に伴う精神的な消耗や、自己犠牲を極端な形で象徴しているようにも思えます。何かを生み出すためには、自分自身を削らなければならない。その苦しみと、それでもなお表現せずにはいられない衝動。作家やクリエイターに限らず、何かを成し遂げようとする人が抱える葛藤を、この病は鮮やかに描き出していると感じました。
また、この物語は「読む側」と「書ける側」の関係性についても深く問いかけてきます。彼は彼女の最初の読者であり、最高の理解者でした。彼の存在がなければ、彼女の才能は開花しなかったかもしれない。そして、彼女の物語は、彼への想いを伝えるためのものでした。書く者と読む者は、互いに影響を与え合い、支え合う存在である。その理想的な関係性が、二人の間にあったからこそ、この物語はこれほどまでに切なく、美しいのかもしれません。
読み終えて、心に残るのは、深い悲しみだけではありません。どんなに過酷な運命に見舞われても、人を愛し、想いを伝えようとすることの尊さ。そして、物語が持つ、人の心を支え、繋ぎ止める力の大きさ。そういった、静かだけれど確かな希望のようなものも感じることができました。彼女が遺した物語は、彼の中で生き続け、そして私たち読者の心にも、何か大切なものを残してくれたように思います。
有川浩さんの作品には、エンターテイメント性の高いものや、心温まるヒューマンドラマが多い印象ですが、「ストーリー・セラー」は、そうした作品群の中でも、特に人間の生と死、愛と創作という根源的なテーマに深く切り込んだ、重厚な作品だと感じました。切なくて、苦しくて、それでも読むのをやめられない。そんな不思議な引力を持つ物語です。この物語に出会えて本当に良かった、そう心から思える一冊でした。何度も読み返し、その度に新しい発見や感動を与えてくれる、そんな作品だと思います。
まとめ
有川浩さんの小説「ストーリー・セラー」は、読む人の心を深く揺さぶる、愛と創作、そして命の物語です。物語は、作家である「彼女」と、その夫であり最初の読者である「彼」を中心に展開します。二人の穏やかな日常は、彼女が「致死性脳劣化症候群」という難病に侵されたことで一変します。
思考することが命取りになるという過酷な状況下で、彼女は愛する彼のためだけに、自らの命を削りながら最後の物語を紡ぐことを決意します。その姿は痛々しくも、気高く、深い愛情に満ちています。彼女の死後、遺された原稿が出版され、物語は「Side-A」と「Side-B」からなる入れ子構造を持っていることが示唆されます。
この構成は、現実とフィクションの境界線を曖昧にし、物語を書くこと、読むことの意味を読者に問いかけます。愛する人を想う気持ちの強さ、創作活動の本質、そして生きることの尊さを、切なくも美しく描き出した本作は、忘れられない読書体験となるでしょう。