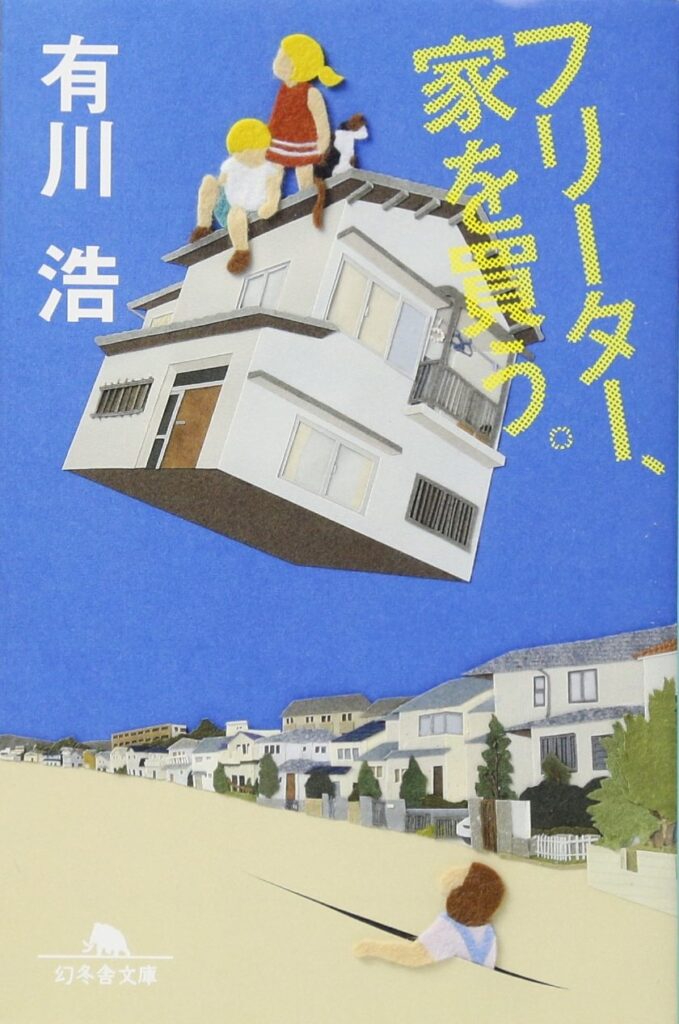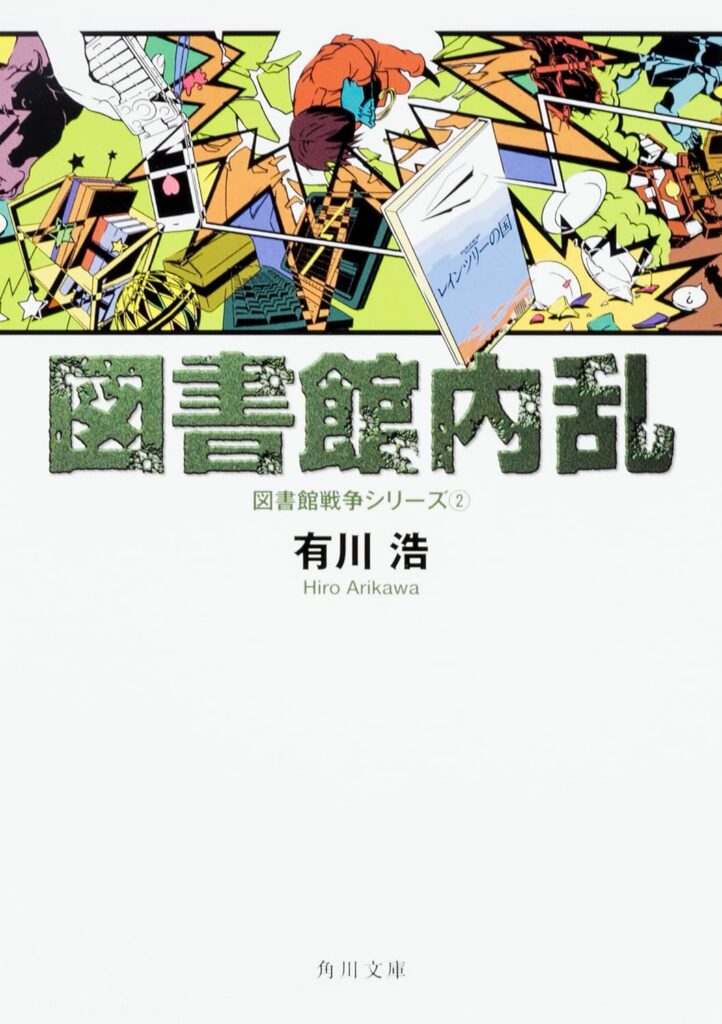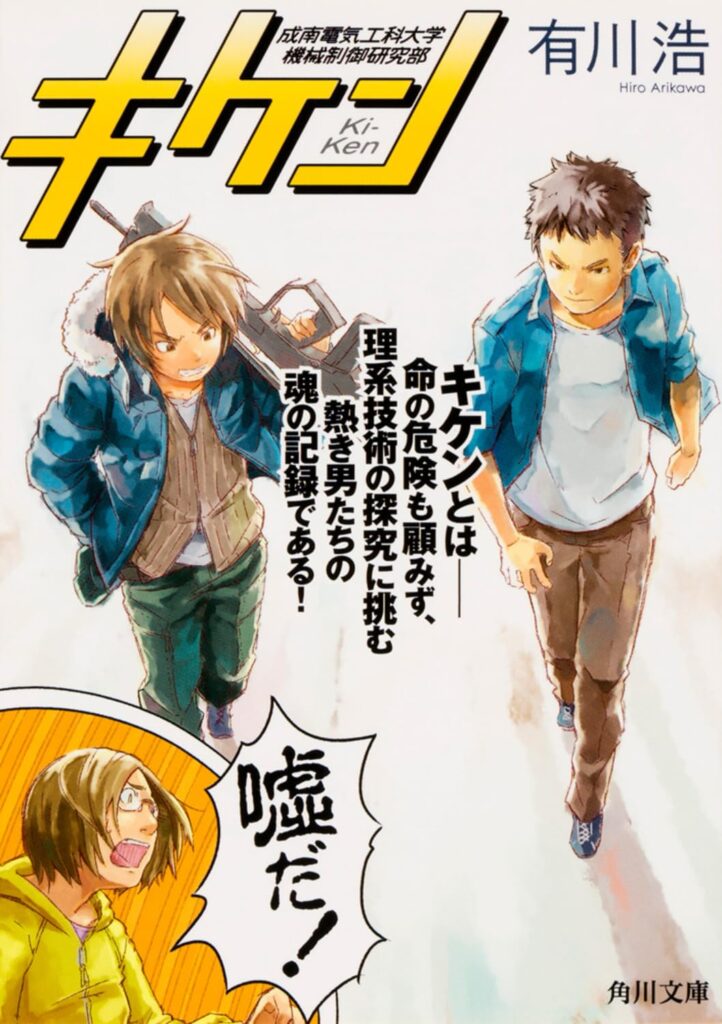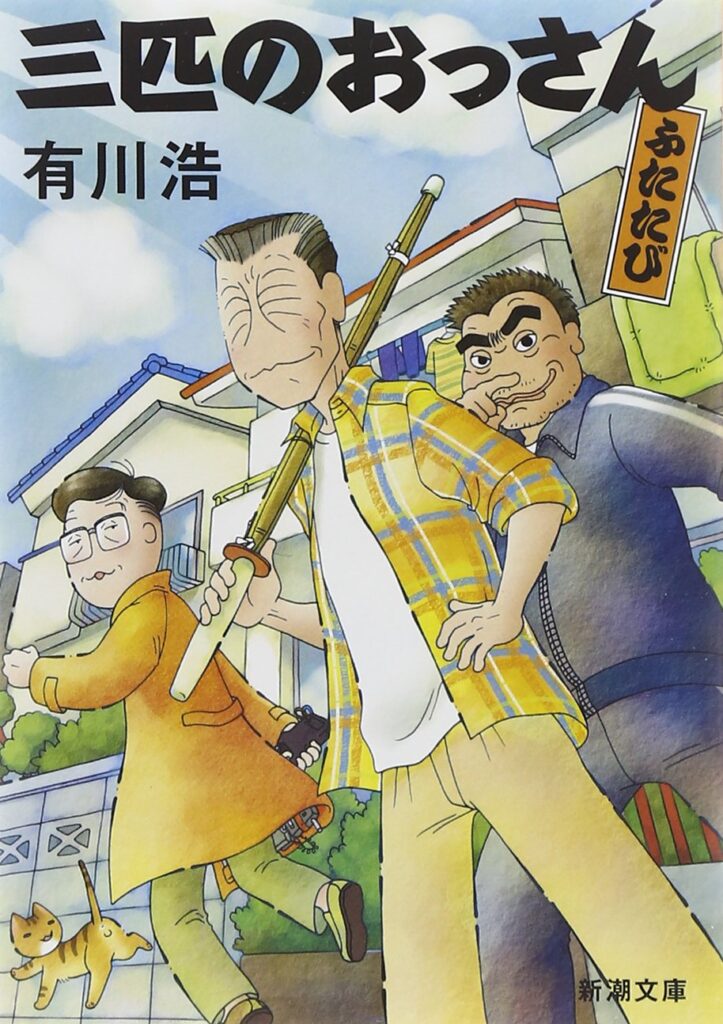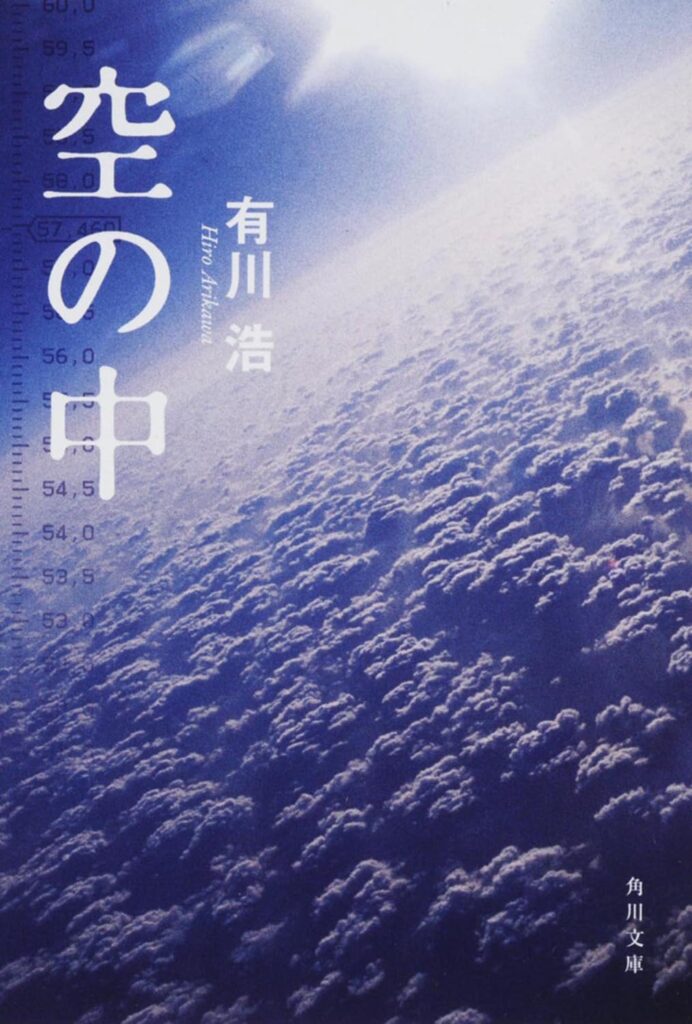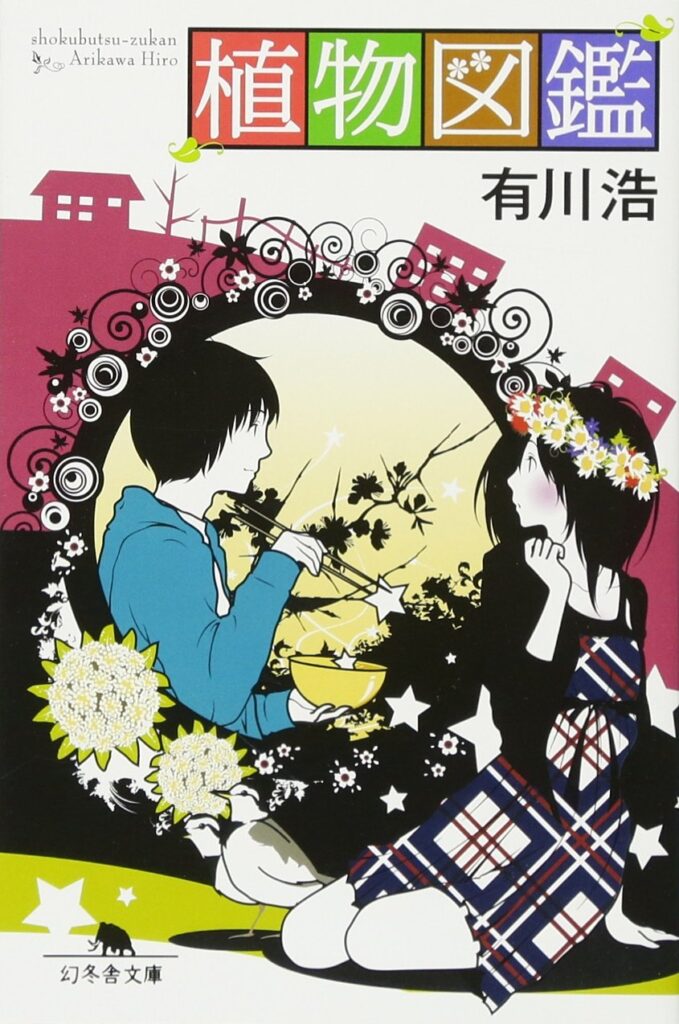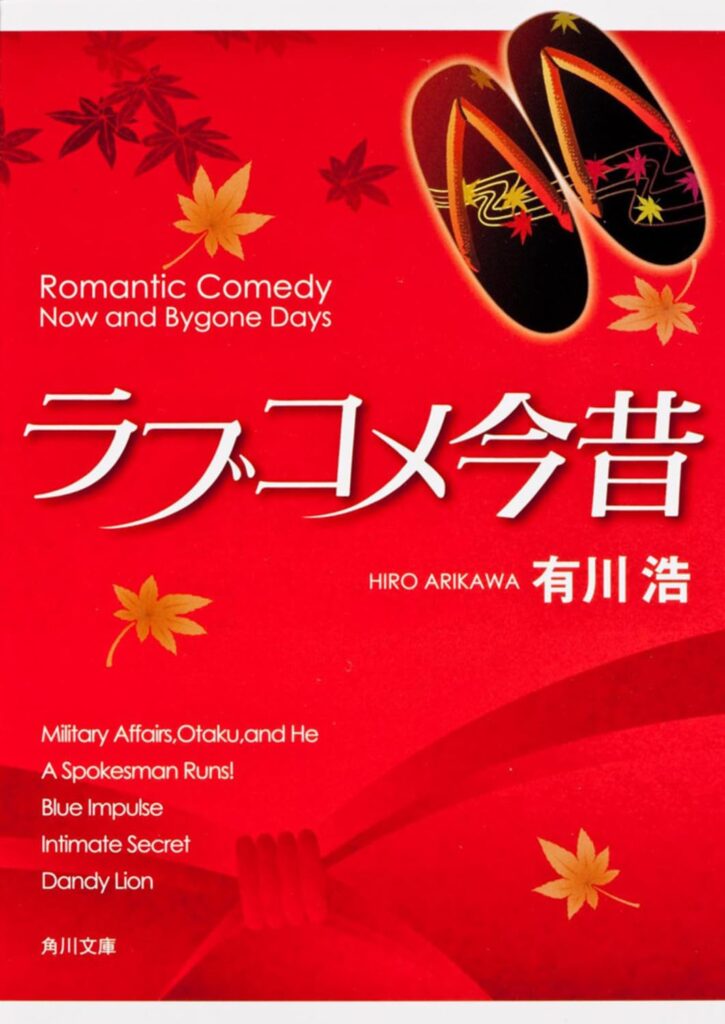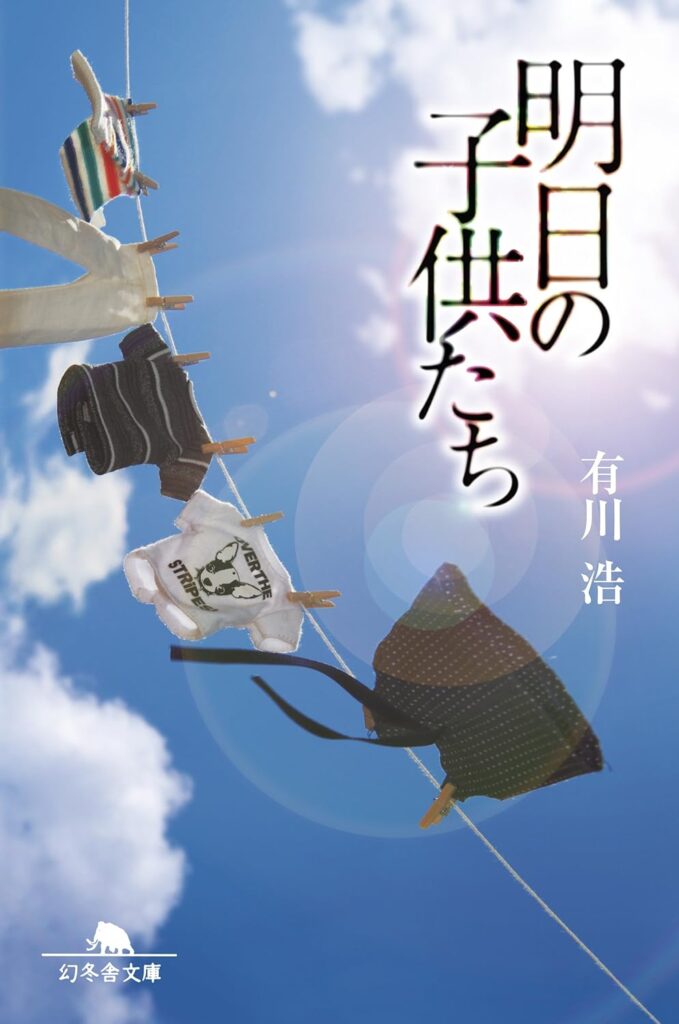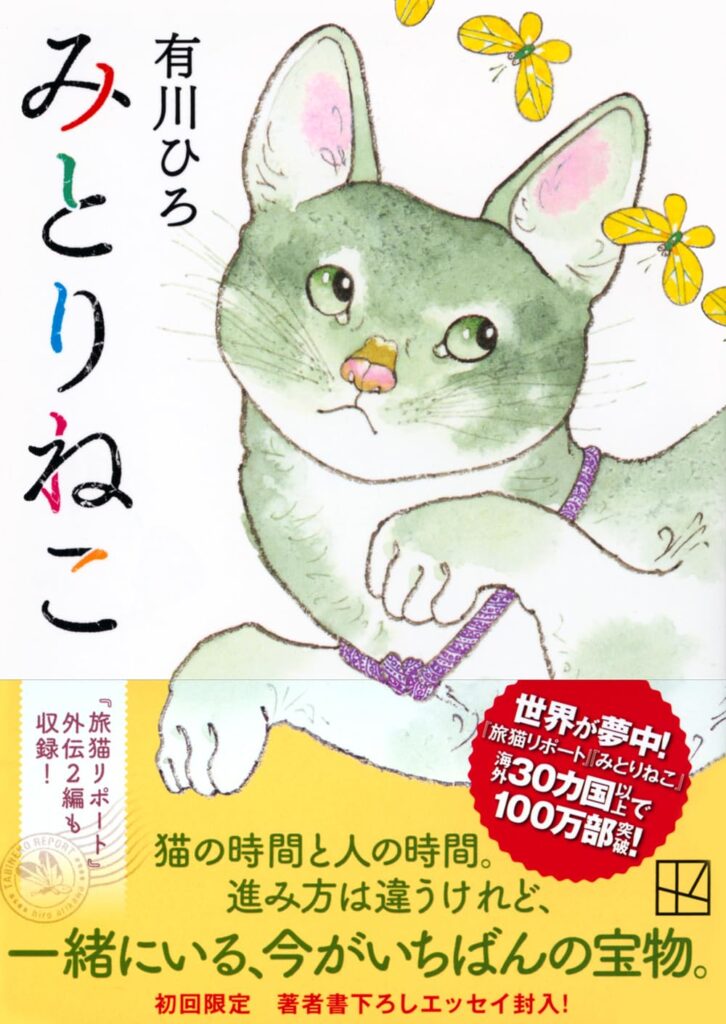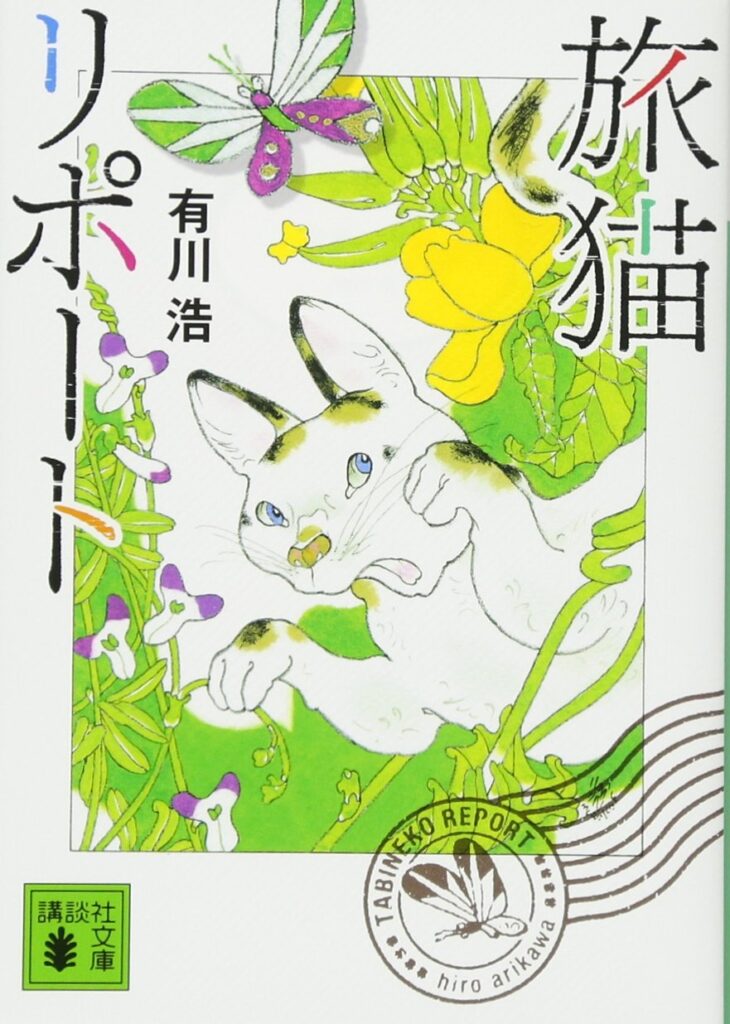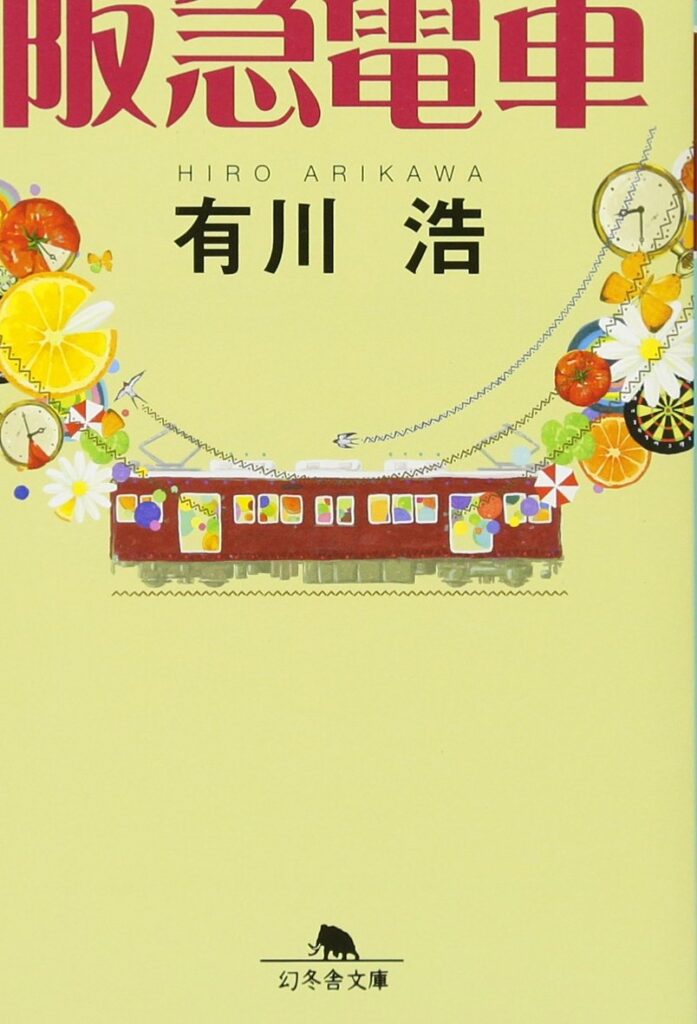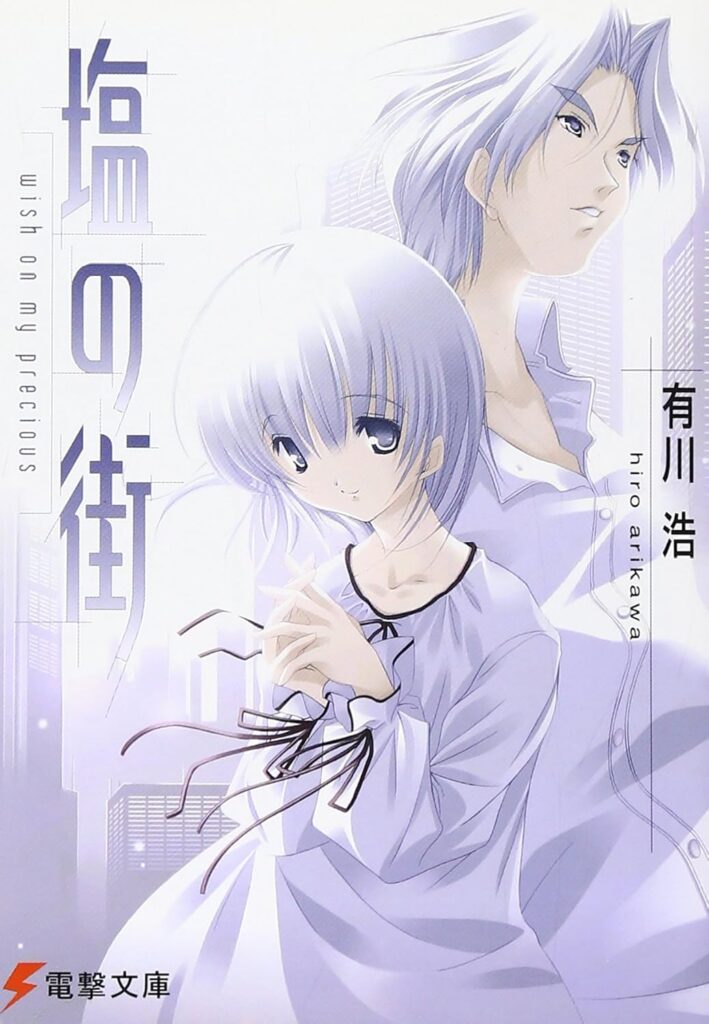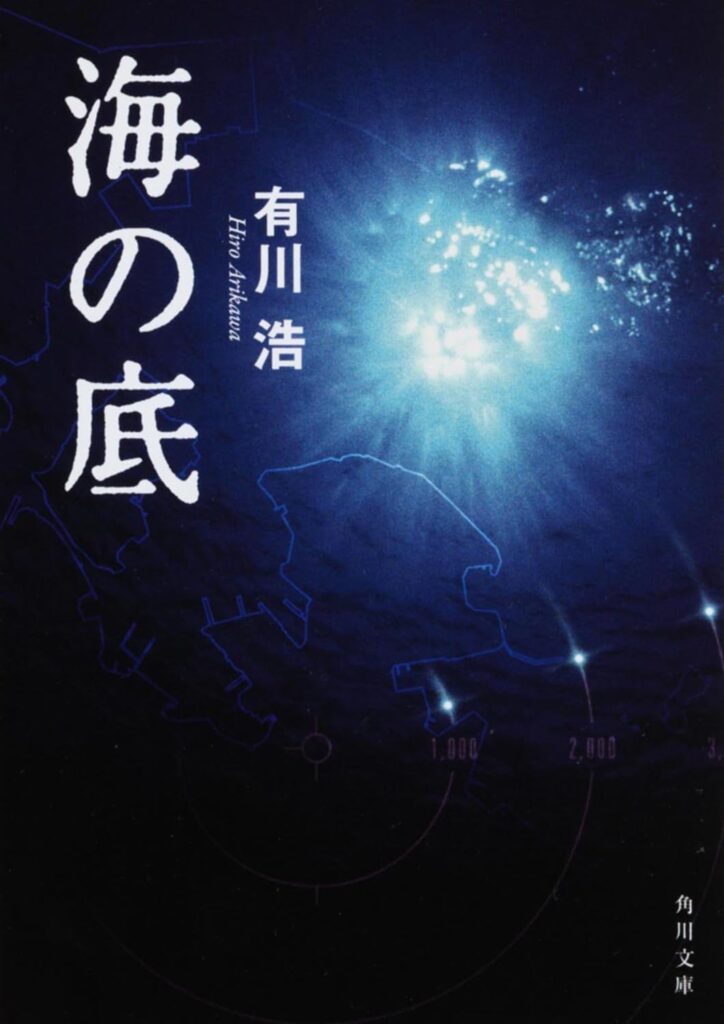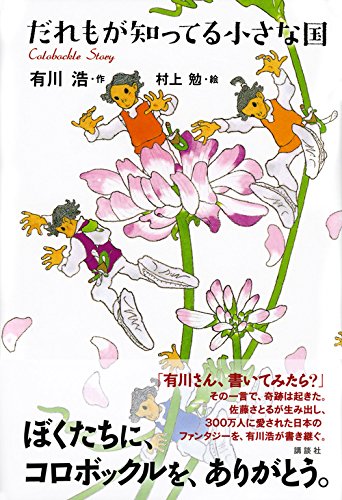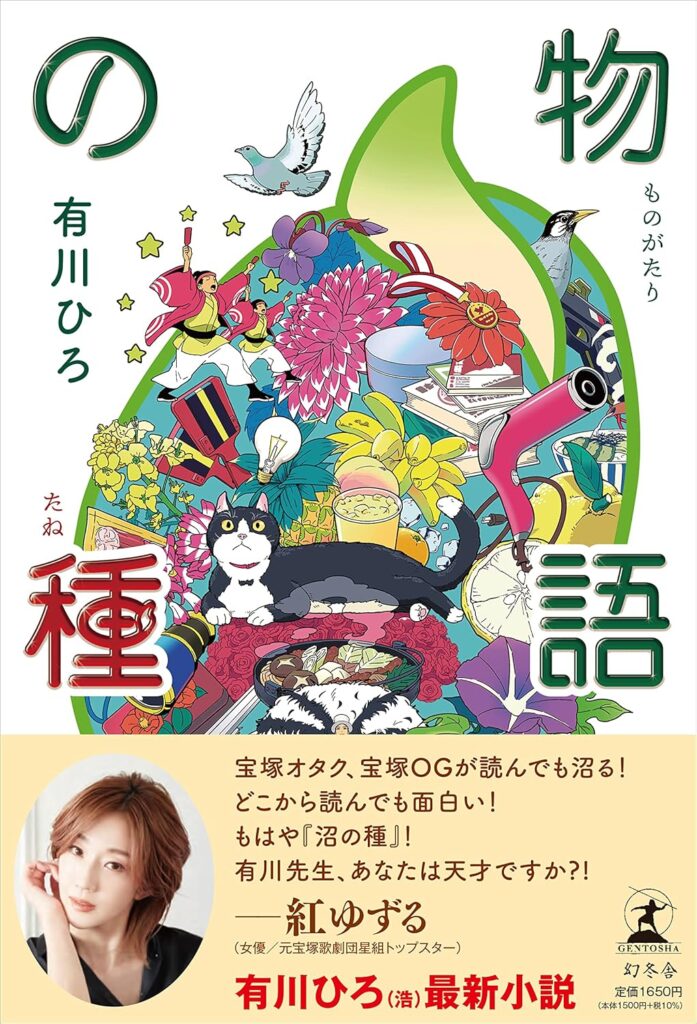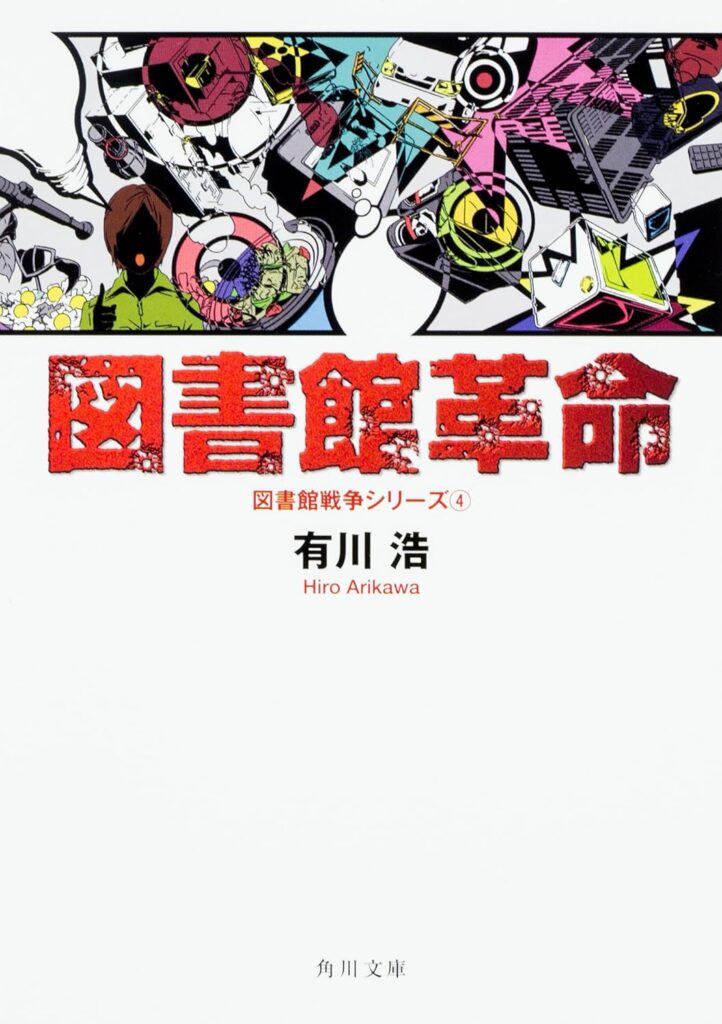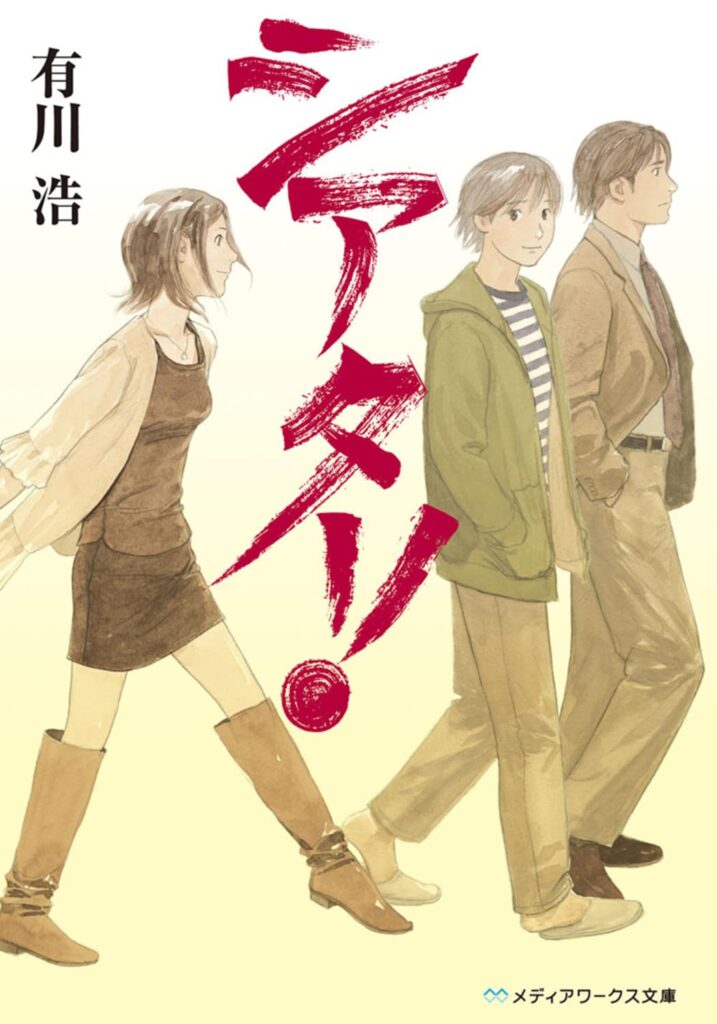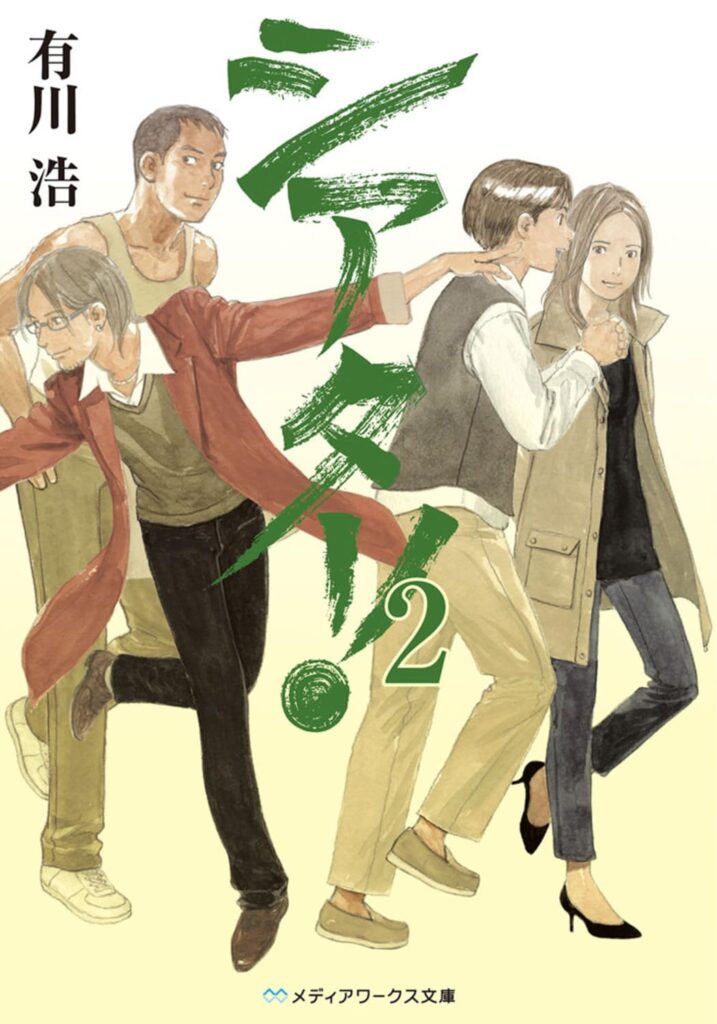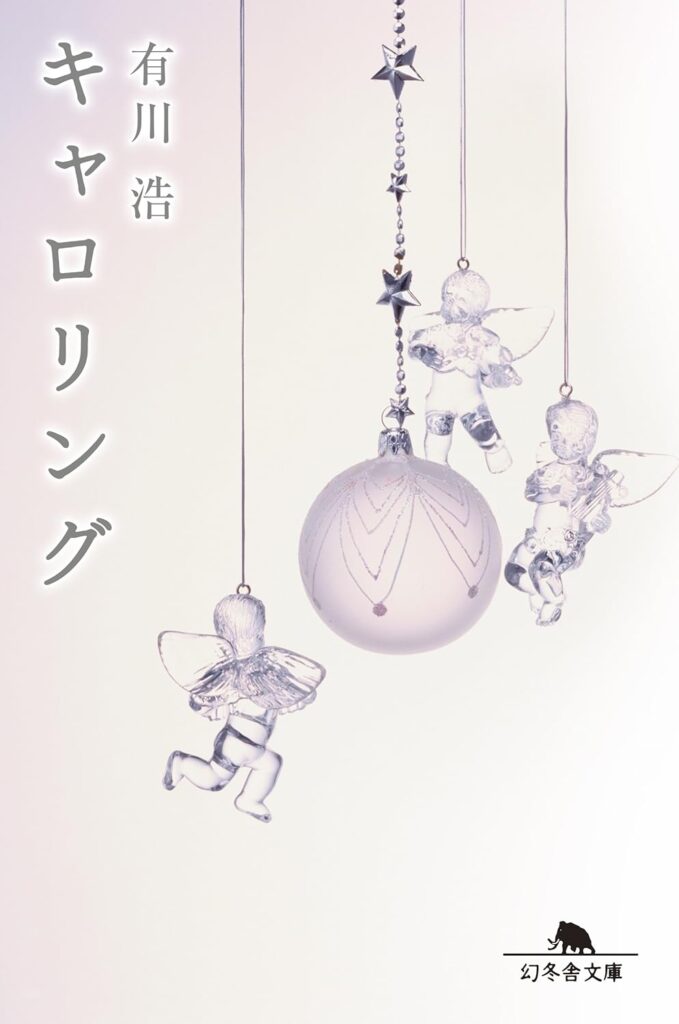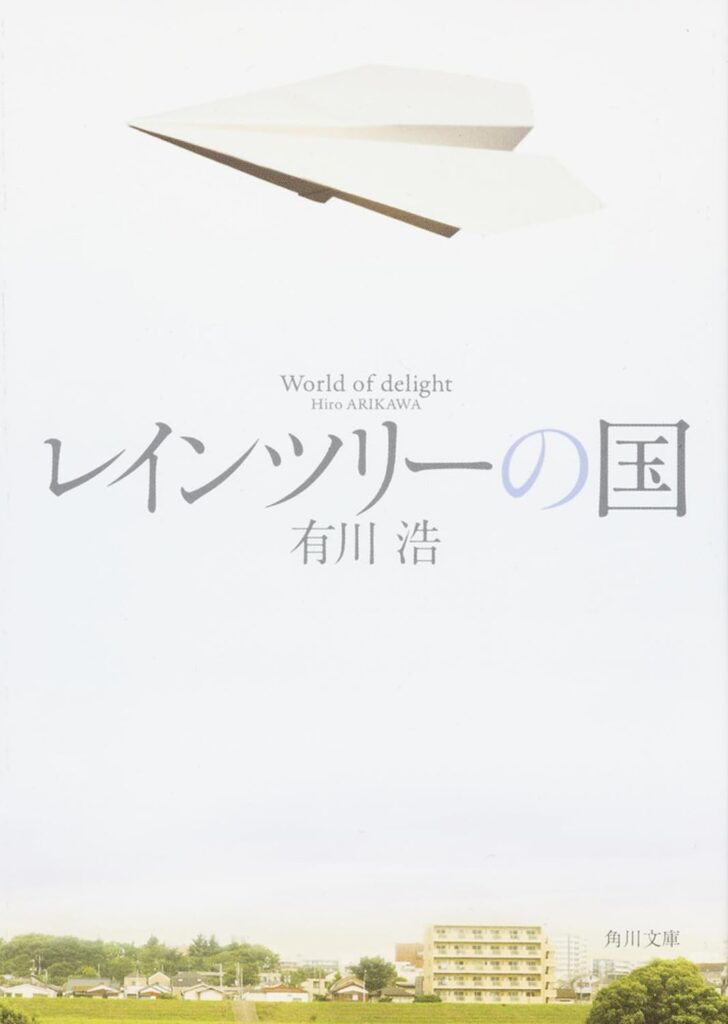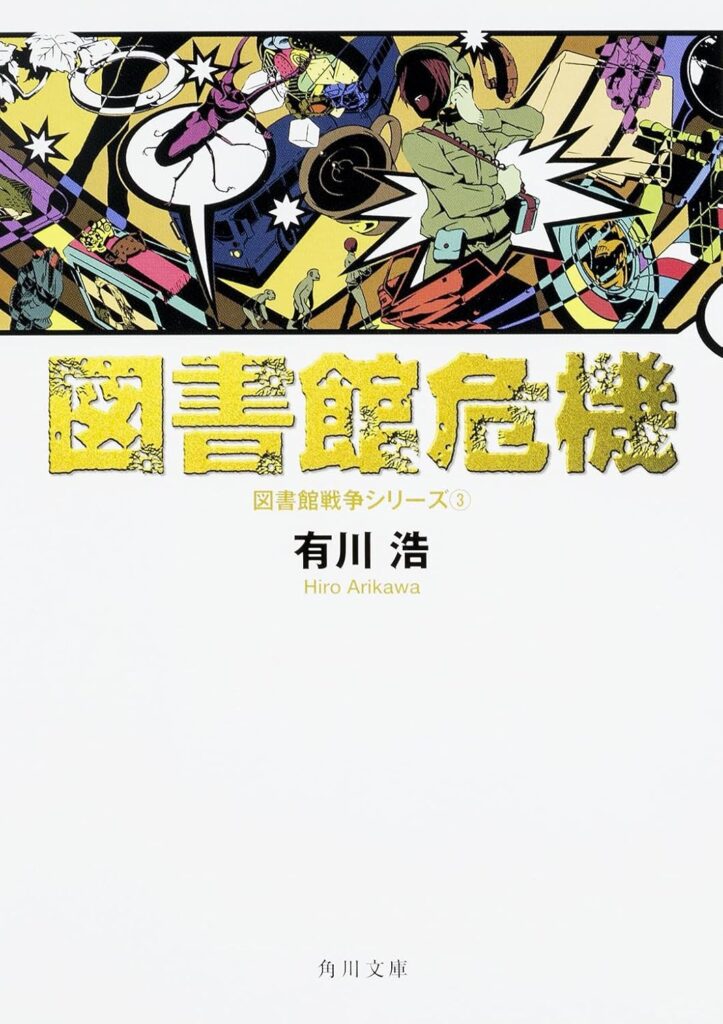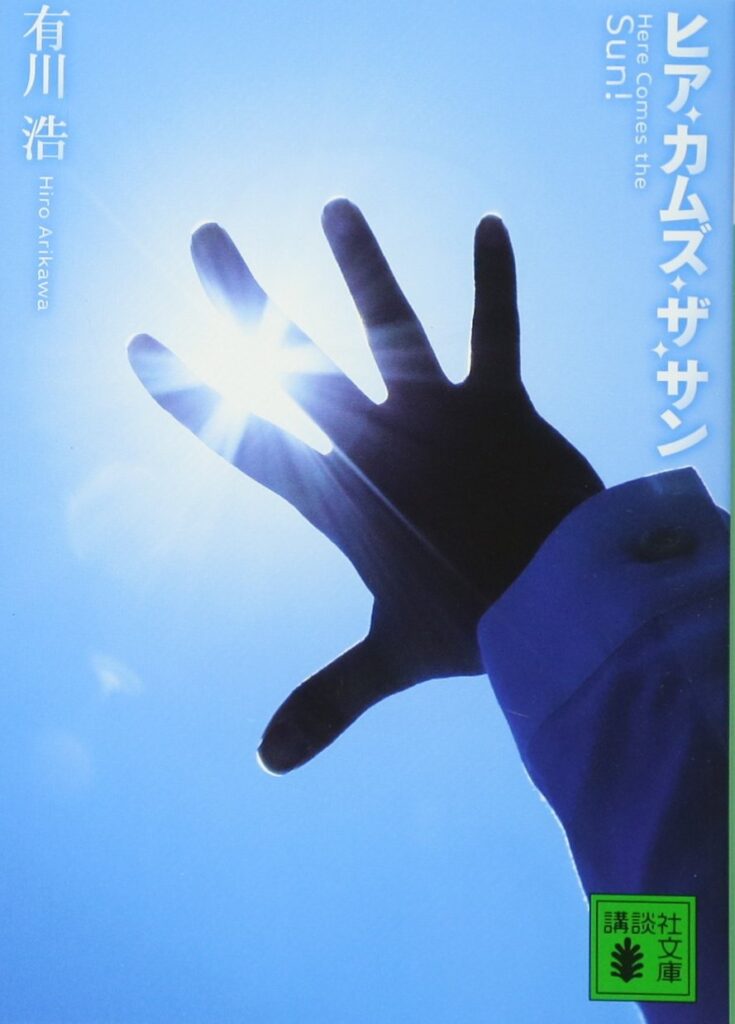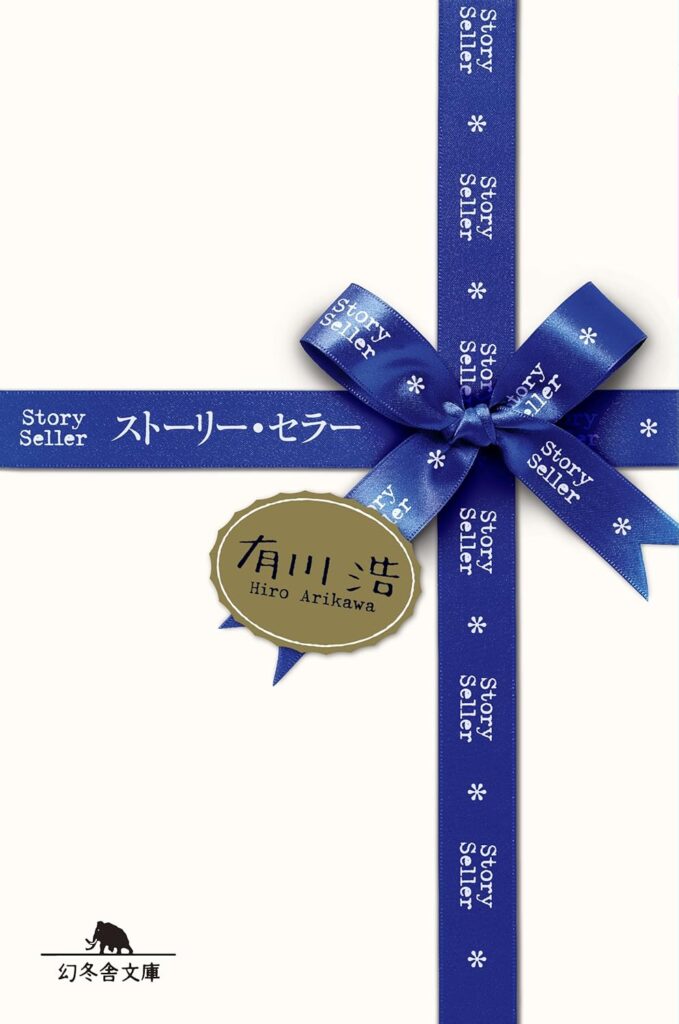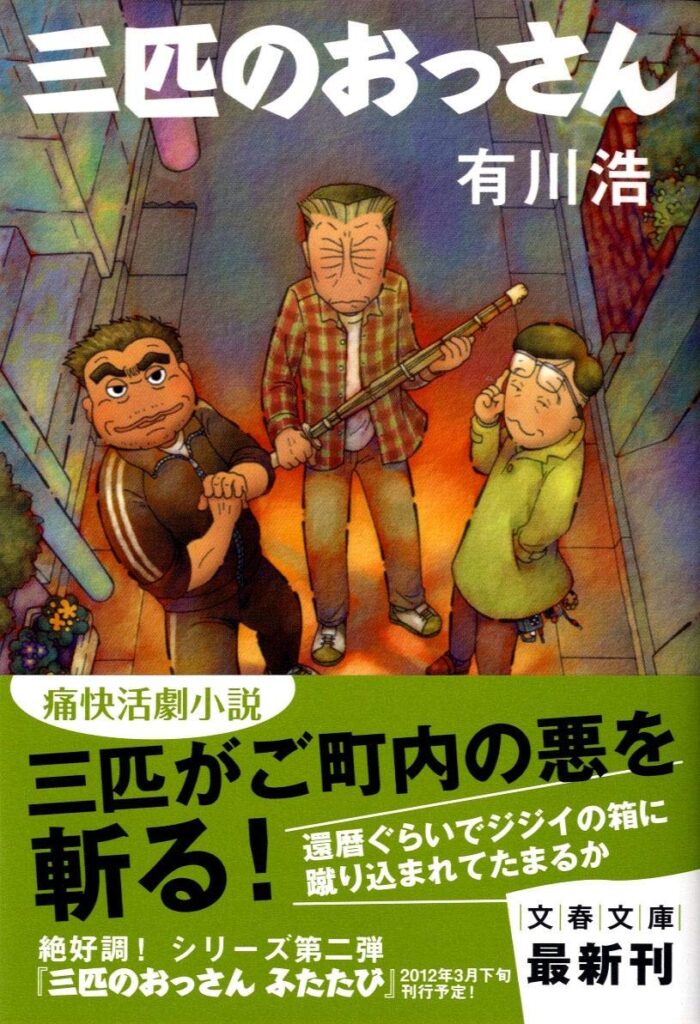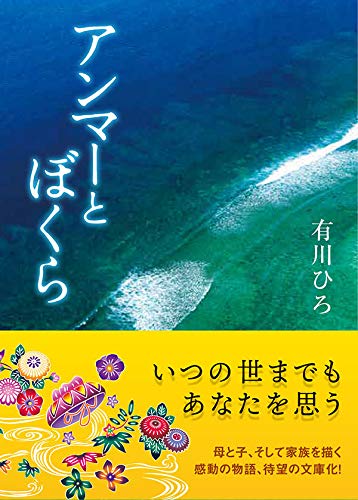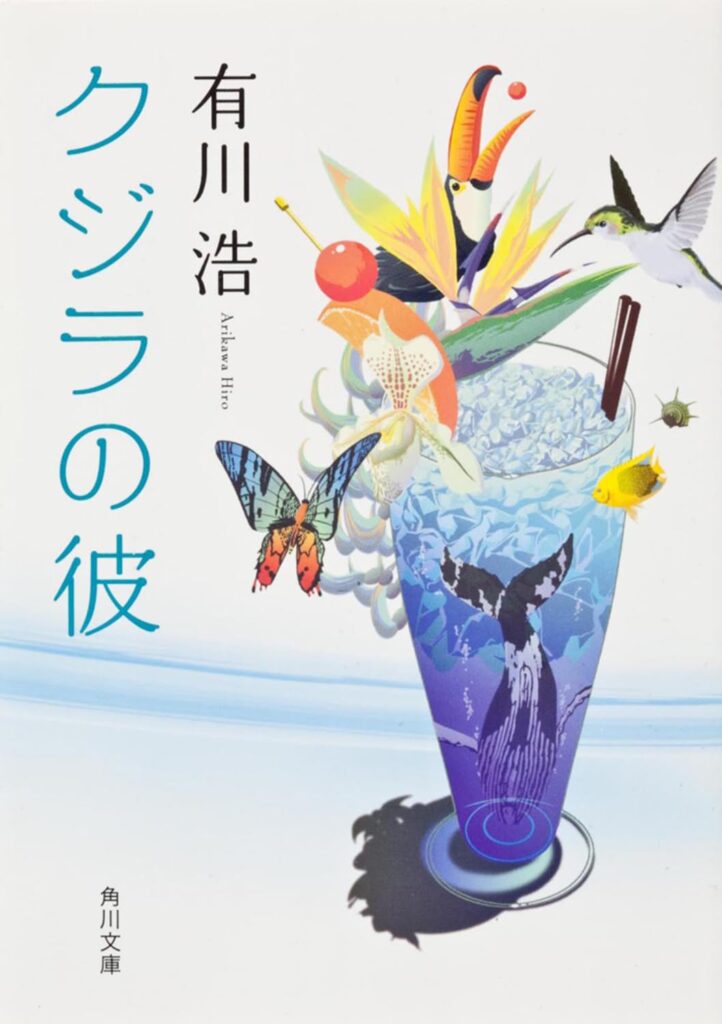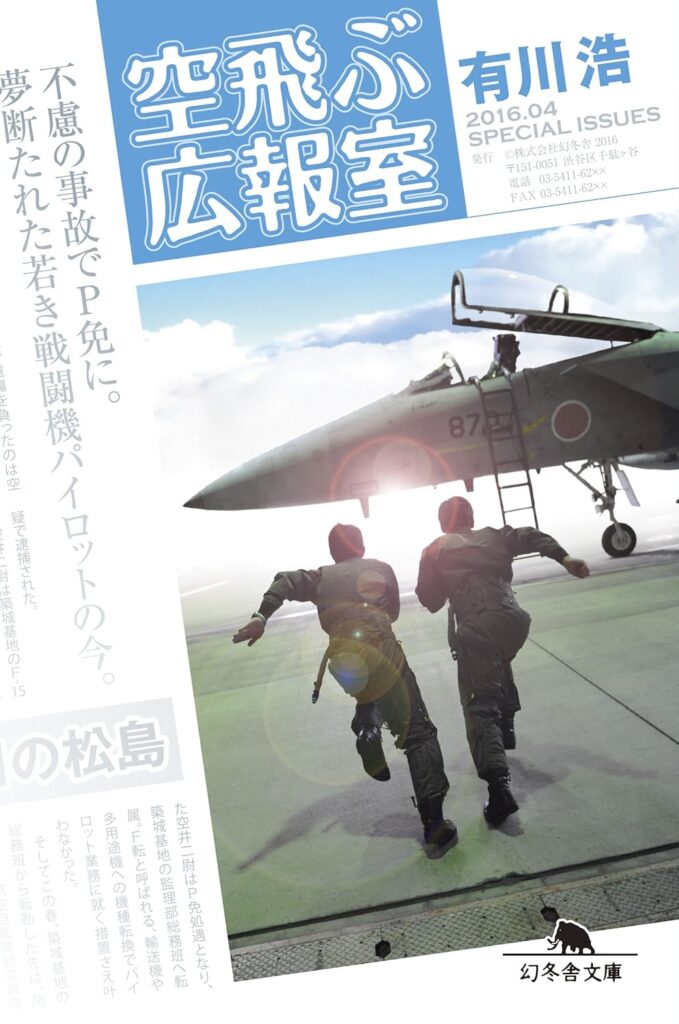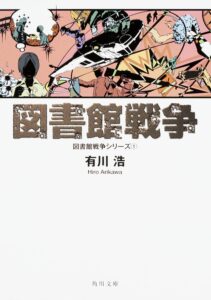 小説「図書館戦争」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、「本を読む自由」が脅かされる近未来の日本を舞台に、その自由を守るために戦う組織「図書隊」の活躍を描いた、胸が熱くなるエンターテイメント作品です。
小説「図書館戦争」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、「本を読む自由」が脅かされる近未来の日本を舞台に、その自由を守るために戦う組織「図書隊」の活躍を描いた、胸が熱くなるエンターテイメント作品です。
物語の中心となるのは、高校時代に出会った図書隊員に憧れて入隊した、真っ直ぐで熱血漢の新米隊員・笠原郁。彼女が、厳しいけれど実は優しい鬼教官・堂上篤や、個性豊かな仲間たちと共に、様々な困難に立ち向かいながら成長していく姿が、時に激しく、時に切なく、そして温かく描かれています。
この記事では、物語の詳しい流れから、登場人物たちの魅力、そして作品が問いかける「表現の自由」という深いテーマまで、ネタバレを含みつつ詳しく掘り下げていきます。「図書館戦争」の世界に、どっぷりと浸ってみませんか?
小説「図書館戦争」のあらすじ
物語の舞台は、公序良俗を乱す表現を取り締まる「メディア良化法」が施行されて30年が経過した、正化31年(2019年)の日本。この法律による不当な検閲から本を守るため、「図書館の自由法」を根拠に設立された防衛組織が「図書隊」です。彼らは、時にメディア良化委員会(良化隊)との武力衝突も辞さず、日々「本」と「自由」を守るために戦っています。
主人公の笠原郁は、高校3年生の時、書店で良化隊による検閲(狩り)に遭遇し、大切な本を取り上げられそうになったところを、一人の図書隊員に救われます。その凛々しい姿に憧れ、「王子様」と慕うようになった郁は、彼を追って図書隊への入隊を決意します。抜群の運動神経と情熱は認められるものの、座学は苦手で、直情的な性格が災いすることも少なくありません。
入隊後、郁を待っていたのは、彼女をことあるごとに「チビ」「アホ」と罵倒する鬼教官・堂上篤でした。厳しい指導に反発しながらも、郁は必死に訓練に食らいつき、その潜在能力を開花させていきます。そして、女性としては異例の抜擢を受け、図書隊の中でもエリート中のエリートが集まる「図書特殊部隊(ライブラリー・タスクフォース)」に配属されることになります。そこには、堂上教官や、温厚な小牧幹久、同期でライバルの手塚光といった面々が待っていました。
特殊部隊員として、激しい戦闘訓練と図書館業務の両立に奮闘する郁。同期の手塚とは衝突を繰り返しながらも、次第に互いを認め合い、連携を深めていきます。そんな中、良化隊による図書館襲撃事件や、少年犯罪者の読書傾向を巡る社会的な批判、そして良化法支持団体による図書隊司令と郁自身の拉致事件など、図書隊と郁に次々と危機が訪れます。これらの困難を乗り越える中で、郁は図書隊員としての自覚と誇りを深め、そして、ずっと探し求めていた「王子様」の意外な正体を知ることになるのです。
小説「図書館戦争」の長文感想(ネタバレあり)
有川浩さんの「図書館戦争」、本当に素晴らしい物語ですよね。最初にこのタイトルを聞いたとき、「図書館で戦争?」と、その突飛な設定に驚いたのを覚えています。でも、読み進めるうちに、その世界観にぐいぐい引き込まれていきました。
まず、この物語の根幹を成す設定が秀逸です。「メディア良化法」という、あらゆる表現を「公序良俗を乱す」という曖昧な基準で取り締まる法律。それに対抗するのが、「図書館の自由法」を盾に、時には武力も行使して本を守る「図書隊」。この対立構造が、物語全体に緊張感と、そして「表現の自由とは何か?」という深い問いを投げかけてきます。
現実の日本にも「青少年保護育成条例」のようなものは存在しますが、「メディア良化法」はそれをさらに推し進め、国家による大規模な検閲が日常化した世界を描いています。本が「狩られ」、図書館が武装し、防衛のために戦闘まで行う。そんなディストピア的な設定でありながら、登場人物たちの日常や感情はとてもリアルで、だからこそ、この「ありえないかもしれないけれど、もしかしたら…」と思わせる世界に強く引きつけられるのだと思います。
そして何より、登場人物たちが本当に魅力的!主人公の笠原郁は、まさに体当たりヒロイン。身長は高いけれど、中身は乙女で、考えるより先に体が動いてしまう猪突猛進タイプ。勉強は苦手だし、すぐにカッとなるけれど、誰よりも真っ直ぐで、強い信念を持っています。彼女が失敗したり、落ち込んだり、それでも立ち上がって前に進もうとする姿には、何度も勇気づけられました。読者が一番感情移入できるキャラクターではないでしょうか。彼女の成長物語としても、この作品は一級品です。
そんな郁を厳しく、しかし温かく見守るのが、堂上篤教官。郁からは「鬼教官」「チビ」と内心(時には口に出して)罵られながらも、彼女の才能を見抜き、特殊部隊へと引き上げます。口が悪く、手も早い(!)けれど、その厳しさの奥には、深い責任感と不器用な優しさが隠れています。郁がピンチの時には必ず駆けつけ、身を挺して守ろうとする姿は、まさに「王子様」…なのですが、郁自身はなかなか気づかない。この二人の関係性が、本当に絶妙なんです。
高校時代に郁を救った「王子様」が、実は目の前の鬼教官・堂上だった、という事実に郁が気づくシーンは、物語の大きな山場の一つ。郁の身長コンプレックスと、堂上の「チビ」呼ばわりが、実は過去の出来事に起因していた…という伏線回収も見事でした。普段は厳しい堂上が見せる、郁への特別な感情や、時折漏れる優しさに、読んでいるこちらもドキドキさせられます。身長差を含めた二人のやり取りは、時にコミカルで、時に切なくて、この物語の大きな推進力になっています。
脇を固めるキャラクターたちも、個性的で素晴らしいです。堂上の親友であり、常に冷静で優しい笑顔を絶やさない小牧幹久。彼は郁にとっても良き理解者であり、堂上との橋渡し役としても重要な存在です。彼が抱える、幼馴染・中澤毬江との関係も、また別の切ない物語として描かれていて、胸を打ちます。
郁の同期であり、当初は犬猿の仲だった手塚光。超エリートで真面目、それゆえに融通が利かない部分もありましたが、郁と関わる中で人間的に成長していきます。兄との確執や、情報屋の柴崎麻子との微妙な関係など、彼自身の物語も興味深いです。手塚が郁に「付き合ってくれ」と告白する場面は、意外性もあって印象的でした。
そして、郁の親友でありルームメイトの柴崎麻子。図書館業務部のエースで、驚異的な情報収集能力を持つクールビューティー。一見、感情を表に出さないタイプに見えますが、実は友情に厚く、郁のことを誰よりも心配しています。彼女の鋭いツッコミや、手塚との丁々発止のやり取りは、物語の良いアクセントになっています。
図書特殊部隊を率いる玄田竜助隊長の豪快さと頼もしさ、そして図書隊全体の理念を体現するような稲嶺和市司令の存在感も、物語に厚みを与えています。特に稲嶺司令が過去の「日野の悪夢」と呼ばれる事件で片足を失いながらも、なお「本を守る」という信念を貫く姿は、図書隊の精神的支柱そのものです。
アクションシーンも見逃せません。図書館という知的な空間で繰り広げられる、銃撃戦や格闘戦。有川さんはミリタリーにも造詣が深いようで、装備や戦術の描写にもリアリティがあり、手に汗握る展開が続きます。「図書館戦争」というタイトルに偽りなし、と言える迫力です。郁が持ち前の運動神経で活躍する場面もあれば、戦闘の恐怖に打ち震える場面もあり、その生々しさが戦争の厳しさを伝えてきます。
しかし、この物語は単なるアクションやラブコメではありません。その根底には、一貫して「表現の自由とは何か」「知る権利とは何か」という重いテーマが流れています。「正論は正しい、だが正論を武器にする奴は正しくない」という堂上の言葉は、非常に示唆に富んでいます。情報が溢れる現代社会において、何が「正しい」情報で、何が「有害」な情報なのか。誰がそれを判断するのか。そして、表現を規制することは、本当に社会を「良化」させるのか。作中では、検閲を推進する側の論理や、事なかれ主義に陥りがちな世間の空気、そして図書館内部での自主規制の問題なども描かれており、読者に様々な角度から考えることを促します。
特に印象的だったのは、「図書館の自主規制を考えるフォーラム」での中学生の研究発表のエピソードです。「どうして大人はただ本を面白がるということを子供に許してくれないのか。自分たちはただ面白がるためだけに本を読むくせに。」という言葉には、ハッとさせられました。読書の意義や価値はもちろん大切ですが、それ以前に、まず「面白いから読む」「楽しいから読む」という純粋な気持ちがあってこそ。その自由が、何よりも尊重されるべきだというメッセージが、強く心に残りました。
「表現の自由」は、普段私たちが当たり前のように享受しているものです。しかし、それは歴史の中で多くの人々が戦い、守り抜いてきたものであり、決して盤石なものではないのかもしれません。この物語を読むと、自由に本を読み、情報を得られることのありがたみを痛感します。それは、まるで私たちが普段意識せずに吸っている空気のようなもので、失われそうになって初めて、そのかけがえのなさに気づくのかもしれません。
郁と堂上の不器用ながらも進展していく恋愛模様、手に汗握るアクション、そして「表現の自由」という普遍的なテーマ。これらが絶妙なバランスで織り交ぜられ、読者を飽きさせません。郁が拉致され、絶体絶命のピンチに陥るクライマックスは、息をのむ展開でした。そして、ついに「王子様」の正体を知り、堂上への尊敬と特別な感情を自覚した郁が、彼に向かって「わたしはあんたを超えるんです。だから絶対辞めません」と宣言するラストシーンは、彼女の成長と決意が凝縮されていて、胸が熱くなりました。
読み終えた後には、爽やかな感動と共に、少しだけ社会について考えるきっかけを与えてくれる。そんな素晴らしい作品です。登場人物たちのその後や、図書隊の未来が気になって、すぐに続編を読みたくなること間違いなしです。まだ読んだことがない方には、ぜひ手に取ってみてほしい一冊です。
まとめ
有川浩さんの小説「図書館戦争」は、「本を読む自由」が脅かされる世界で、その自由を守るために戦う「図書隊」の活躍を描いた、感動と興奮の物語です。メディア良化法による検閲が横行する近未来の日本を舞台に、個性豊かな登場人物たちが織りなすドラマは、読む人を飽きさせません。
主人公・笠原郁の真っ直ぐな成長物語、鬼教官・堂上篤との不器用で甘酸っぱい恋愛模様、そして手に汗握るアクションシーン。これらのエンターテイメント性の高い要素に加え、「表現の自由とは何か?」という普遍的で重要なテーマが、物語に深みを与えています。
登場人物たちの魅力的な会話、心に響くセリフ、そして緻密に練られた世界観。すべてが一体となって、読者を「図書館戦争」の世界へと引き込みます。読み終わった後には、きっと爽やかな感動と、本が読めることへの感謝の気持ちが湧き上がってくるはずです。続編も刊行されており、シリーズ通して楽しめる、おすすめの作品です。