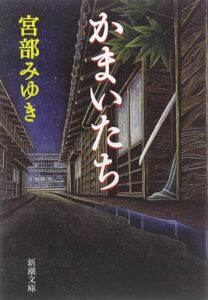 小説「かまいたち」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの作品は数多く読んでいますが、この『かまいたち』は、初期の作品集でありながら、その後の活躍を予感させる魅力にあふれていますね。江戸の町を舞台にした、ぞくりとするような事件と、そこに生きる人々の細やかな心情が描かれていて、ページをめくる手が止まりませんでした。
小説「かまいたち」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの作品は数多く読んでいますが、この『かまいたち』は、初期の作品集でありながら、その後の活躍を予感させる魅力にあふれていますね。江戸の町を舞台にした、ぞくりとするような事件と、そこに生きる人々の細やかな心情が描かれていて、ページをめくる手が止まりませんでした。
この本には表題作「かまいたち」を含む4つの短編が収められています。「師走の客」「迷い鳩」「騒ぐ刀」、どれも個性的で読み応えがありますよ。特に「迷い鳩」と「騒ぐ刀」は、後に人気シリーズとなる「霊験お初捕物控」の原型とも言える作品で、お初という不思議な力を持つ少女の活躍が描かれています。宮部さんの描く時代小説の世界観に、どっぷりと浸ることができる一冊だと思います。
この記事では、それぞれの物語がどんなお話なのか、そして物語の結末に触れつつ、私が読んで何を感じたのかを、詳しくお話ししていきたいと思います。まだ読んでいない方も、すでに読んだ方も、一緒に『かまいたち』の世界を楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは、さっそく物語の概要から見ていきましょう。
小説「かまいたち」の物語の概要
『かまいたち』は、宮部みゆきさんの初期の才能がきらめく時代小説中短編集です。表題作「かまいたち」をはじめ、趣の異なる四つの物語が収められています。どの作品も江戸の町の空気感や、そこに生きる人々の息づかいが感じられて、まるでタイムスリップしたかのような気分にさせてくれますよ。
まず表題作の「かまいたち」。江戸の夜道を恐怖に陥れる謎の辻斬り「かまいたち」。人を斬るものの金品は奪わないという不気味な犯行に、人々は怯えていました。そんな中、町医者の娘おようは、偶然辻斬りの現場を目撃してしまいます。しかも、その犯人らしき男が、自分の住む長屋の向かいに引っ越してきて…。おようの恐怖と疑念、そして事件の真相がサスペンスフルに描かれます。最後には、あっと驚くような事実が待っています。
次に「師走の客」。千住の旅籠「梅屋」を営む夫婦のもとに、毎年師走になると訪れる不思議な客がいました。その客は宿賃代わりに、金で作られたという干支の細工物を置いていきます。十二支揃えば大変な価値になると言われ、夫婦はすっかり信用し、毎年客が来るのを楽しみにしていました。しかし、その話には裏があり…。正直者の夫婦が巻き込まれる騒動と、その顛末が小気味よく描かれた一編です。人情噺のような温かさも感じられますね。
そして「迷い鳩」と「騒ぐ刀」。これらは、不思議な力を持つ少女お初が登場する連作です。日本橋の一膳飯屋「姉妹屋」で働くお初は、ある時期から人には見えないものが見えたり、聞こえない声が聞こえたりするようになります。岡っ引きの兄が関わる事件に、その力ゆえに巻き込まれていく「迷い鳩」。そして、質に入れた脇差が発端となり、次々と起こる凄惨な殺人事件の謎をお初たちが追う「騒ぐ刀」。こちらは後の「霊験お初捕物控」シリーズへと繋がっていく物語で、怪異と謎解きが融合した独特の世界観が楽しめます。人の心の闇や怨念といった、少し重いテーマも扱われています。
小説「かまいたち」の長文感想(物語の結末に触れています)
さて、ここからは各短編について、物語の核心に触れながら、私が読んで感じたことを詳しくお話ししていきたいと思います。まだ結末を知りたくない方は、ご注意くださいね。
「かまいたち」について
まず表題作の「かまいたち」。これは本当に、最後までハラハラさせられるミステリー仕立ての作品でした。主人公のおようの視点で物語が進むので、読者もおようと同じように「向かいに越してきた新吉が辻斬りなのでは?」と疑いながら読み進めることになります。
おようが辻斬りの現場を目撃してしまう場面。夜道で急に斬りつけられる恐怖、犯人の顔を見てしまったかもしれないという動揺、そして自分が斬られずに見逃されたことへの不可解さ。このあたりの描写がとても巧みで、一気にお話に引き込まれました。しかも、番屋に駆け込んでも死体が消えていて、誰も信じてくれない。おようの孤独感や焦りがひしひしと伝わってきます。
そんな中、向かいに越してきた飾り職人の新吉が、あの夜見た辻斬りの男と瓜二つだった。これはもう、疑うなという方が無理ですよね。おようが新吉を警戒し、証拠を掴もうと必死になる姿は、読んでいて胸が痛みました。特に、新吉に脅されたり、周囲から嘘つき呼ばわりされたりしながらも、自分の見たことを信じ、真実を突き止めようとする健気さには心を打たれます。駕籠かきの平太という味方が現れたときは、ほっとしましたね。
しかし、物語の終盤で明かされる真相には、本当に驚かされました。新吉は辻斬りではなく、実は南町奉行・大岡忠相の密命を受けて動いていた内密の同心だったのです。彼が斬っていたのは、実は乱心して夜な夜な辻斬りを行っていた旗本。そして、おようが目撃した夜、新吉が斬った相手もその旗本だったけれど、すぐさま別の仲間が死体を運び去ったために、現場からは消えていた、というわけです。
つまり、おようはずっと勘違いしていたんですね。しかも、思い詰めたおようは、新吉の腕を匕首で傷つけてしまう。真相を知ったときのおようの衝撃と、新吉への申し訳ない気持ちを思うと、こちらまで苦しくなりました。一番の被害者は、勘違いされて怪我までさせられた新吉かもしれません。それでも、最後は新吉がおようを責めることなく、むしろその勇気を称えるような形で終わるのが救いです。大岡忠相も登場し、事件が丸く収まる様子は、まるで時代劇のラストシーンのようで、読後感は意外なほどすっきりとしていました。「ちゃんちゃん♪」と音が聞こえてきそうな、と表現されている方もいましたが、まさにそんな感じでした。初期の作品ながら、構成の巧みさ、人物描写の確かさは流石だなと感じます。
「師走の客」について
次に「師走の客」。これは先の「かまいたち」とは打って変わって、江戸の小噺のような、軽妙で心温まるお話でした。
千住の旅籠「梅屋」の夫婦、竹蔵とお里。真面目にコツコツと商売を営む二人のもとに、毎年決まって師走にやってくる常二郎という客。この常二郎が、なかなか食えない男なんですね。伊達様の城下で小間物屋を営んでいると名乗り、宿賃の代わりに「将軍様や伊達様も集めている」という金製の干支の細工物を置いていく。十二支揃えば百両の値打ちがあると聞かされ、竹蔵夫婦はすっかり信用してしまいます。
毎年、次の干支の細工物を持ってくる常二郎を楽しみに待つ夫婦の姿は、微笑ましくもあり、少し危なっかしくもあります。最初のうちは目利きにも出していたのに、年々信用が増して、それすらしなくなる。常二郎が細工物を蔵にしまう時だけは、なぜか自分自身でやりたがる、という伏線もさりげなく張られています。
そして、ついに事件が起こります。蛇年の細工物を持ってきた常二郎が、「これは大きすぎて宿賃代わりでは損だ」と言い出し、足りない分の十両を払ってくれと言い出すのです。十二支揃わないと価値がなくなると信じ込んでいる竹蔵は、渋々十両を支払います。しかし、その後で細工物がすべて偽物だったことが判明!常二郎はまんまと十両を騙し取り、姿をくらましてしまったのです。蔵にしまう際に、本物と偽物をすり替えていたんですね。
「正直者が馬鹿を見る」のか…と、読んでいるこちらもがっかりしかけたのですが、ここからがこの話の面白いところ。なんと、常二郎が慌てていたのか、本物の蛇の置物だけはすり替え忘れて、梅屋に残していってしまったのです。偽物だと思っていた他の干支の置物も、実は常二郎が置いていった本物の一部が紛れ込んでいた可能性も示唆されつつ、結局、竹蔵夫婦は損をするどころか、思いがけず価値のあるものを手に入れることになります。騙されたけれど、結果オーライ、という結末がとても小気味いいですね。常二郎の慌てふためく姿を想像すると、思わず笑ってしまいます。人の好い夫婦が最後に報われる展開に、心が温かくなりました。
「迷い鳩」について
そして、「迷い鳩」。ここから、後の人気シリーズ「霊験お初捕物控」のヒロイン、お初が登場します。この作品が書かれたのはデビュー前とのことですが、すでにお初のキャラクターや、物語の独特な雰囲気が確立されていることに驚かされます。
日本橋通町の一膳飯屋「姉妹屋」で、兄嫁のおよしさんと一緒に働くお初。十六歳のお初は、初めての月のもの(初潮)を迎えた頃から、不思議な力が備わります。他の人には見えないものが見えたり、聞こえない声が聞こえたりするのです。作中では、その力が月のものや、兄嫁に育てられていることへの気兼ねといったストレスから開花したのではないかと推測されていますが、この設定が面白いですよね。
物語は、お初が偶然通りかかった商家のお内儀・お清の袖に、べっとりと血が付いているのを見てしまうところから始まります。しかし、その血はお初にしか見えず、周りの人には全く見えません。気になったお初は、岡っ引きである長兄の六蔵や、下っぴきのような仕事もする次兄の直次と共に、お清が女主人を務める「柏屋」を探り始めます。
柏屋では、主人の宇三郎が原因不明の病で寝たきりになっており、女中が次々と辞めていくという奇妙な出来事が続いていました。お初の不思議な力は、柏屋に隠された恐ろしい秘密を少しずつ明らかにしていきます。酒樽から血が滴る幻を見たり、「人殺し!」という声を聞いたり…。そして、行方不明になった女中のおつねが殺されていること、さらに、おつねと連絡を取り合っていた鳩使いの圭太も殺害されていたことを突き止めます。
事件の真相は、お清とその手代である誠太郎による、主殺しでした。お清は誠太郎にそそのかされ、仏壇のろうそくに砒素を仕込み、毎日のおつとめで宇三郎に少しずつ毒を吸わせていたのです。その事実に気づいたおつねと圭太を、誠太郎が口封じのために殺害したのでした。お清がおつとめの際にろうそくに火を灯さなかったのは、自分自身が毒にあたらないようにするためだった、というわけです。
お清が犯行に至った動機には、夫への不満や寂しさといった、女心の複雑さが描かれていて、同情の余地がないわけではありません。しかし、だからといって殺人が許されるはずもなく、その結末は悲しいものでした。お初の持つ力が事件解決の糸口となる展開は、後のシリーズにも通じる面白さがあります。ただ、お初自身はその力を持て余し、悩み苦しむ姿も描かれており、単なる超能力ヒロインではない、人間味あふれるキャラクター造形が印象的でした。
「騒ぐ刀」について
最後に「騒ぐ刀」。これも「迷い鳩」に続く、お初が登場する物語です。個人的には、この短編集の中で最も読み応えがあり、印象に残った作品でした。「かまいたち」がサスペンス、「師走の客」が人情噺、「迷い鳩」が怪異譚とすれば、この「騒ぐ刀」は、よりダークでホラー要素の強い物語と言えるかもしれません。
物語の発端は、南町奉行所の同心・内藤新之助が、生活苦から自分の脇差を質に入れてしまうところから始まります。ところが、質から受け戻した脇差は、自分のものとは違う、奇妙な刀でした。その刀は夜な夜なうめき声をあげ、関わった人間が次々と惨たらしい死を遂げていくのです。その殺され方は、とても人の仕業とは思えないほど凄惨で、読んでいるこちらも背筋が寒くなりました。
お初は、その刀から異様な気配を感じ取ります。兄たちと共に事件を追ううちに、刀にまつわる過去の因縁が明らかになっていきます。かつて、二人の刀鍛冶、国広と国信が、一人の女性を巡って争ったこと。そして、国広の強い怨念が、彼が打った鍔のない刀に宿り、「虎」と呼ばれる妖刀となって殺戮を繰り返していること。その妖刀を封じることができるのは、国信が「守り刀」として鍛えた刀だけであること…。内藤新之助が手にしたのは、まさにその「守り刀」だったのです。
事件の真相にたどり着くまで、なかなか核心が見えず、もどかしい気持ちで読み進めました。妖刀「虎」の正体、そしてそれを操る者の存在。謎が謎を呼び、ページをめくる手が止まりません。そして、ついに明らかになる怨念の深さと、それが引き起こす悲劇の恐ろしさ。人の恨みというものが、これほどまでに凄まじい力を持ちうるのかと、考えさせられました。
クライマックス、妖刀「虎」と「守り刀」が対峙する場面は、息を呑むような迫力がありました。「守り刀」に導かれるように現れた、不思議な犬・小太郎の存在も、物語に幻想的な彩りを添えています。最後、妖刀「虎」に本来の鍔が戻ると、刀はみるみるうちに錆びて赤い鉄粉となり、春の風に吹かれて消えていきます。まるで、長年にわたる国広の怨念が、ようやく浄化され、昇華していったかのようでした。それはまるで、固く凍り付いていた悲しみが、春の陽光に溶けていくような、切なくも美しい光景に感じられました。
事件は解決しますが、残されたのは重い読後感でした。人の心の闇、怨念の恐ろしさを突きつけられたような気がします。しかし、それと同時にお初の優しさや、兄たちとの絆、そして困難に立ち向かう人々の姿に、救いも感じられました。この作品で描かれたテーマや雰囲気は、「霊験お初捕物控」シリーズへと確かに受け継がれていくことになります。
四編を読み終えて
この『かまいたち』に収められた四編は、それぞれ異なる味わいを持ちながらも、宮部みゆきさんらしい読みやすい文章、巧みなストーリーテリング、そして人間ドラマの深さが共通して感じられました。デビュー初期の作品集とは思えない完成度の高さです。特に、江戸という時代の空気感、市井に生きる人々の喜びや悲しみ、そして時に起こる不可解な事件を、見事に描き出しています。
「かまいたち」でのハラハラするサスペンス、「師走の客」での心温まる人情噺、「迷い鳩」「騒ぐ刀」での怪異と謎解き。一冊で様々なタイプの時代小説を楽しめる、とてもお得な作品集だと言えるでしょう。特に「霊験お初」シリーズのファンにとっては、お初の原点を知る上で欠かせない一冊だと思います。宮部みゆきさんの時代小説入門としても、おすすめです。どの話から読んでも楽しめますが、やはり収録順に読んでいくと、お初が登場する後半への流れがより自然に感じられるかもしれませんね。
まとめ
宮部みゆきさんの時代小説短編集『かまいたち』、いかがでしたでしょうか。この記事では、収録されている四つの物語、「かまいたち」「師走の客」「迷い鳩」「騒ぐ刀」について、その概要と、結末にも触れながら詳しい感想をお話ししてきました。
江戸の町を舞台に繰り広げられる、ミステリーあり、人情噺あり、怪異譚ありのバラエティ豊かな物語は、どれも宮部さんならではの筆致で描かれ、読者を引き込みます。特に、町医者の娘おようが辻斬りの謎に迫る表題作や、後の人気シリーズの原型となった、不思議な力を持つ少女お初の活躍を描く「迷い鳩」「騒ぐ刀」は、読み応えがありました。
初期の作品でありながら、構成の巧みさ、人物描写の深さ、そして読後には温かい気持ちや、時にはぞくりとするような感覚を残す筆力は、さすが宮部みゆきさんだと改めて感じさせられます。時代小説がお好きな方はもちろん、ミステリーや少し不思議な物語がお好きな方にも、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。きっと、江戸の町の魅力と、そこに生きる人々の物語に夢中になることでしょう。































































