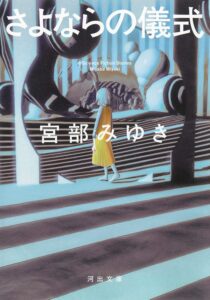 小説「さよならの儀式」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「さよならの儀式」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
宮部みゆきさんといえば、緻密なミステリーや心温まる時代小説のイメージが強いかもしれませんが、この「さよならの儀式」は、なんとSF短編集なんです。初めて知った時は「宮部さんがSF?」と少し驚きましたが、読んでみると、そこには紛れもなく宮部さんならではの深い人間描写と、社会への鋭い問いかけがありました。ミステリーファンも時代小説ファンも、そしてSFファンも、きっと引き込まれる魅力を持った一冊だと思います。
本書には8つの物語が収められています。近未来を舞台にした話、タイムスリップ、ロボットと人間の絆、異星人との遭遇、死者蘇生技術、そして仮想空間のような閉じた町の話まで、実に多彩なSF的テーマが扱われています。どれも「もしもこんな世界があったら?」と考えさせられる、刺激的な設定ばかりです。しかし、単なる空想物語ではなく、それぞれの物語の根底には、現代社会が抱える問題や、人間の普遍的な感情が描かれており、読後には深い余韻が残ります。
この記事では、まず各短編がどのような物語なのか、その導入部分や設定を中心にご紹介します。そして後半では、物語の核心や結末にも触れながら、私が感じたこと、考えたことを、たっぷりと語っていきたいと思います。少し長い語りになりますが、この魅力的な作品の世界を、少しでも深く味わっていただけたら嬉しいです。宮部みゆきさんの新たな一面に触れる、特別な読書体験になるかもしれませんよ。
小説「さよならの儀式」のあらすじ
「さよならの儀式」は、それぞれ独立した8つのSF短編から構成されています。ここでは、各物語がどのような世界を描いているのか、その入り口をご紹介しましょう。
まず『母の法律』。ここでは「マザー法」という法律が存在します。これは、虐待を受けた子供を、適正があると判断された「完璧な両親」の元で育てるという制度。主人公の二葉は、この法律によって養父母の元で姉の一美と共に育てられましたが、養母の死により、16歳で再び施設に戻ることになります。そんな彼女の元に、実母である死刑囚が面会を求めているという知らせが届くところから物語は動き出します。
次に『戦闘員』。80歳になる達三は、日課の散歩の途中で、防犯カメラを壊そうとしている少年を見かけます。少年は「あのカメラは異星人の監視装置だ」と主張します。最初は老人の日常に起こった奇妙な出来事かと思いきや、話は思わぬ方向へ。達三は、この少年の言葉を信じ、共に「戦闘員」として見えない敵に立ち向かうことになるのでしょうか。
『わたしとワタシ』は、タイムスリップを扱った物語。45歳の「わたし」が実家で出会ったのは、なんと30年前、高校生だった頃の「ワタシ」。未来の自分に対して、若き日のワタシは容赦のない言葉を投げかけます。過去の自分との対峙は、「わたし」に何をもたらすのでしょうか。未来の社会状況を示唆する描写も印象的です。
表題作でもある『さよならの儀式』は、人間とロボットの関係を描きます。老朽化したロボットを回収・処理する施設が舞台。そこでは、長年連れ添ったロボットとの別れを受け入れられない人々のために、精神的なケアも行われています。自分を育ててくれた旧式ロボットとの別れを惜しむ女性が施設を訪れ、担当者は規則を破り、最後の対面をさせようと試みます。人間とロボットの間に育まれた絆の形とは。
『星に願いを』では、高校生の秋乃が、最近様子のおかしい妹・春美を心配しています。学校でのいじめを疑いますが、春美が本当に怯えているのは別の存在のようです。そんな中、町で無差別殺人事件が発生。犯人は宇宙人に精神を乗っ取られているという噂も。姉妹の日常と、非日常的な事件が交錯します。
『聖痕』は、少しミステリーの色合いが濃い物語。子供に関する問題を扱うコンサルタントの元に、ある父親から調査依頼が舞い込みます。彼の息子・和己は、14歳の時に実母とその内縁の夫を殺害した過去を持ちますが、今は更生し社会生活を送っています。しかし、ネット上では「和己は死んで“黒き救世主”となり、虐待親に制裁を加えている」という噂が流布されているというのです。噂の真相と、和己が見たという「妙なもの」の正体を探ります。
『海神の裔(かいしんのすえ)』は、フランケンシュタインの技術を応用した「屍者(ししゃ)」、つまり死体から作られた存在が登場します。明治時代の日本の漁村を舞台に、青い目をした屍者「トム」が、村人たちのために力を尽くす姿が、発見された古い資料を通して語られます。異質な存在と村人たちの交流を描く、どこか不思議で温かい物語です。
最後の『保安官の明日』は、外界から隔絶された町「ザ・タウン」が舞台。保安官は、新しくやってきた助手のチコと共に、町で起こる様々な問題を解決しています。しかし、この町には大きな秘密が隠されていました。若い女性の拉致事件をきっかけに、町の成り立ちと、「リセット」の意味が明らかになっていきます。人間の歪んだ願望が作り出した世界の物語です。
小説「さよならの儀式」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは各短編について、物語の核心や結末にも触れながら、私が感じたことを詳しくお話ししていきたいと思います。ネタバレを含みますので、未読の方はご注意くださいね。
『母の法律』
この物語の核となる「マザー法」。虐待された子供を救うための法律、という大義名分はありますが、読み進めるうちに、その制度の持つ冷たさや歪さが浮かび上がってきます。二葉と一美は「完璧な」養父母の元で、物質的には恵まれた環境で育ちますが、そこには本当の意味での温かい家庭があったのか、疑問を感じずにはいられません。特に、養母が亡くなった途端、まるで用済みになったかのように施設へ戻される姉妹の姿は、制度の非情さを象徴しているように思えました。
そして、物語の後半、死刑囚である実母との面会。ここで姉の一美が抱えていた秘密と、二葉自身も知らなかった事実が明らかになります。実は、二葉が養父母に引き取られたのは、実母が「娘を手放す代わりに死刑を回避する」という裏取引に応じたからだった、と。さらに衝撃的なのは、その裏取引を持ちかけたのが、他ならぬ姉の一美だったということです。一美は、自分だけが実母から虐待を受けていたと感じ、復讐のために、そして自分だけが「まともな」環境で育つために、実母と妹を切り捨てた。このどす黒い事実は、読んでいるこちらも胸が苦しくなりました。
結局、二葉は実母とも、そして姉とも決別する道を選びます。「完璧な親」も「血の繋がった親」も、彼女にとっては安らぎの場ではなかった。マザー法というシステムが生み出した悲劇であり、人間のエゴや愛情の歪みが克明に描かれた、非常に重い読後感の残る一編でした。制度は人を救うために作られるはずなのに、運用の仕方や、関わる人間の思惑によって、いとも簡単に人を傷つける凶器にもなりうるのだと、改めて考えさせられました。
『戦闘員』
この話は、最初は少しユーモラスな雰囲気さえ漂います。頑固そうだけどどこか憎めないおじいさん・達三と、「防犯カメラは異星人の監視装置だ」と主張する不思議な少年・守。守の言うことは荒唐無稽に聞こえますが、達三は次第に彼の言葉を信じ始め、見えない「敵」と戦う「戦闘員」となっていきます。
守が壊そうとしていたカメラは、実は地域住民の健康状態を監視し、異常があれば通報するシステムの一部でした。しかし、そのシステムには欠陥があり、誤作動によってマイクロ波を放出し、住民(特に子供や老人など、抵抗力の弱い人々)の健康を蝕んでいたのです。守はそれに気づき、自分や他の子供たちを守るために、一人で戦っていたのでした。異星人の仕業というのは、子供らしい空想と、大人に信じてもらうための方便だったのかもしれません。
達三は、守の話を頭から否定せず、むしろ共感し、行動を共にします。最初は防犯カメラを物理的に壊そうとしますが、やがて、そのシステムの「目」をごまかす方法、つまり健康であるかのように偽装する方法を思いつきます。この展開が面白いですよね。物理的な破壊ではなく、情報的な撹乱で対抗しようとする。老人の知恵と、少年の純粋な危機感が結びついた瞬間です。
最後は、達三が健康診断で「異常なし」と偽装することに成功し、守と共に勝利を喜びます。しかし、根本的な解決には至っていません。システムは依然として存在し、危険を撒き散らしているかもしれない。それでも、ささやかな抵抗が成功したことに、一筋の光を感じます。日常に潜む見えない脅威と、それに立ち向かう普通の人々の勇気を描いた、心温まるようでいて、少し背筋が寒くなるような物語でした。守くんと達三じいさんのコンビ、なんだか応援したくなります。
『わたしとワタシ』
タイムスリップしてきた過去の自分との対話、というのはSFでは定番の設定ですが、宮部さんはそこに現代社会への皮肉を織り交ぜています。45歳の「わたし」の前に現れた15歳の「ワタシ」は、未来の自分に対して非常に辛辣です。「もっと輝いていると思った」「こんな風になるなんてがっかり」といった言葉を浴びせかけます。誰しも若い頃は、未来の自分に対して漠然とした期待や理想を抱いているものですが、現実の自分と向き合った時、そのギャップに戸惑うのかもしれません。
この物語で特に印象的だったのは、「わたし」が未来(つまり「わたし」の現在)の飲み物を「ワタシ」に勧める場面。ペットボトルのお茶を飲んだ「ワタシ」は、「薬みたいな味がする」と言います。そして「わたし」は内心で思うのです。「そうか、この頃はまだ、こんな味ではなかったんだ」と。これは、私たちの食生活や環境が、気づかないうちに少しずつ変化(あるいは悪化)していることへの警鐘のように感じられました。毎日飲んでいるものだから慣れてしまっているけれど、過去から来た人間にとっては異様に感じる。この描写は、じわじわと広がる未来への不安を感じさせます。
また、高校生の「ワタシ」が、大人になった「わたし」の服装や生活ぶりを見て幻滅する様子は、現代を生きる私たちの姿を映し出しているようにも思えました。忙しさにかまけて、自分自身を大切にすることを忘れがちになっていないか。過去の自分が今の自分を見たら、胸を張って「これが私だよ」と言えるだろうか。そんなことを考えさせられました。
結局、「ワタシ」は元の時代に帰っていきますが、「わたし」の心には、過去の自分から突きつけられた厳しい言葉と、未来への漠然とした不安が残ります。単なるタイムスリップものに留まらず、現代社会と個人の生き方について考えさせられる、ビターな味わいの作品でした。「わたし心外。」という一文には、思わず苦笑してしまいましたが、同時に我が身を振り返るきっかけにもなりました。
『さよならの儀式』
表題作でもあるこの短編は、人間とロボットの関係性という、SFの古典的テーマを真正面から描いています。近未来、家庭用ロボットは普及していますが、旧式化すれば廃棄される運命にあります。物語の舞台は、そんなロボットたちを回収し、所有者との「別れ」をサポートする施設。
依頼者の女性・志摩子は、幼い頃から自分を育ててくれた旧式ロボット「ハーマン」との別れをどうしても受け入れられずにいます。彼女にとってハーマンは、単なる機械ではなく、かけがえのない家族同然の存在なのです。施設の担当者である男性・香屋は、ロボットに対して複雑な感情を抱えています。彼自身、幼い頃にロボットに母親代わりをさせていた経験があり、そのロボットへの愛着と、人間としての母親への罪悪感、そしてロボットに対する嫉妬心のようなものが入り混じった感情を持っているのです。
香屋は、規則を破って、志摩子とハーマンの最後の対面をセッティングします。ハーマンは既に聴覚センサーが故障しており、言葉を理解できません。そこで志摩子は、かつてハーマンから教わった手話で、感謝の気持ちを伝えようとします。この場面は、本当に胸に迫るものがありました。言葉が通じなくても、心を通わせようとする人間の姿と、それに応えようとする(かのように見える)ロボットの仕草。ハーマンが、まるで自分の役割が終わったことを悟ったかのように、静かに機能停止していくラストは、涙なしには読めませんでした。
この物語は、テクノロジーが進化し、ロボットがより身近になった時、私たちは彼らとどう向き合うべきなのか、という問いを投げかけます。ロボットに愛情を感じることは自然なことなのか、それとも人間の傲慢なのか。香屋が抱える「人間の自分よりもロボットの方が愛され、豊かな人生を歩んでいる」という葛藤は、非常に現代的な悩みとも言えるかもしれません。便利さの中で人間が失っていくものは何か、という香屋のモノローグ、「人類は進歩しつつ、確実に不器用になりつつある」という言葉が、重く心に響きました。人間と非人間の境界線が曖昧になっていく未来で、私たちは「心」をどこに見出すのでしょうか。感動的でありながら、深い問いを残す名編だと思います。
『星に願いを』
この物語は、最初は思春期の少女の不安定な心を描いているように見えます。主人公の秋乃は、妹・春美の突然の不調の原因を探ろうとします。学校でのいじめ、家庭環境、様々な可能性を考えますが、春美が怯えているのは、もっと得体のしれない何か、彼女曰く「宇宙人」の存在でした。
この設定自体がSF的ですが、物語はさらに予想外の方向へ展開します。町で無差別殺傷事件が発生し、犯人が秋乃たちの家の近くまで迫ってくるのです。そして、犯人は「宇宙人に操られている」と叫びます。このあたりから、現実と妄想の境界線が曖昧になっていきます。春美が見ていた「宇宙人」は、彼女の精神的な不安定さが見せた幻覚なのか、それとも本当に存在する脅威なのか?
登場する大人たち(特に少し頼りない父親や、空気が読めない担任教師)の描写が、物語の不穏な雰囲気を一層際立たせています。子供たちが感じている恐怖や危機感を、大人たちはまともに取り合おうとしません。この断絶感が、姉妹をさらに孤立させていくように見えます。
結末は、はっきりとした答えが示されないまま終わります。秋乃が犯人と対峙し、春美を守ろうとしたところで、場面は唐突に終わる。これが現実の出来事だったのか、それとも秋乃の見た悪夢、あるいは春美の妄想が伝染した結果なのか、解釈は読者に委ねられます。個人的には、春美の感じていた「宇宙人」の恐怖と、現実の無差別殺人事件という暴力性が、どこかでシンクロしてしまったのではないかと感じました。現代社会の漠然とした不安や、コミュニケーション不全が生み出す歪みが、「宇宙人」という形で象徴されているのかもしれません。すっきりとした解決はありませんが、そのぶん、読後に様々な想像を掻き立てられる、不思議な魅力のある作品でした。
『聖痕』
この短編は、SFというよりは、オカルトミステリーやサイコスリラーに近い雰囲気を持っています。過去に母親とその愛人を殺害した少年・和己。彼は医療少年院を経て社会復帰しますが、ネット上では彼を神格化するような奇妙な噂が広がっていきます。「和己は死んで“黒き救世主”となり、虐待された子供たちのために、加害者の親に“聖痕(スティグマ)”を与えて罰している」というのです。
調査を依頼されたコンサルタントの女性・千川は、現実的な視点から、この噂の背後にあるものを探ろうとします。ネット上の扇動者「ユダ」の正体、和己自身の現在の心理状態などを調査していく過程は、宮部さんらしい丁寧なミステリーの筆致で描かれています。
しかし、物語が進むにつれて、単なるネット上の噂話では片付けられないような、超常的な現象が示唆され始めます。和己自身が「何か」を見たと語り、実際に虐待を行っていた親が奇妙な痣(聖痕)と共に変死する事件も起こる。そして、調査を進める千川自身にも、驚くべき過去と能力があることが明かされます。彼女もまた、かつて特殊な力を持っていた(あるいは、今も持っている)存在だったのです。この展開は、物語に更なる深みと複雑さを与えています。
ラストシーン、千川と和己の前に、明らかに人ならざる存在、噂されていた「黒き救世主」のような影が現れます。そして、その存在が消えた後、和己の手の甲には聖痕が残されていた。これは、彼らが体験したことが幻覚や妄想ではなく、現実だったことを示唆しています。和己は本当に「救世主」になってしまったのか、それとも何かに利用されているだけなのか。虐待という社会問題と、超常現象、ネット社会の闇が絡み合い、非常に濃密で不気味な余韻を残します。人間の心の闇が生み出したものなのか、それとも本当に人知を超えた存在がいるのか。答えは出ませんが、その曖昧さが逆に恐怖を煽る、秀逸な一編だと感じました。
『海神の裔』
この物語は、他の短編とは少し毛色が異なり、時代小説のような趣があります。舞台は明治時代の日本の漁村。そこに現れたのは、フランケンシュタインの物語に出てくるような、死体から作られた「屍者」のトム。彼は青い目を持ち、言葉は片言ですが、驚異的な力と知識で、寂れた漁村の復興に貢献します。
屍者という、本来なら人々から恐れられ、忌み嫌われるはずの存在が、村人たちに受け入れられ、尊敬されていく過程が、温かく描かれています。トムは、最新の漁業技術を教えたり、堤防を築いたり、村のために献身的に働きます。その姿は、怪物的というよりも、むしろ聖人のようにさえ見えます。村人たちも、最初は戸惑いながらも、トムの誠実な人柄(?)に触れ、次第に彼を仲間として受け入れていく。この交流の様子は、読んでいて心が洗われるようでした。
しかし、物語には哀しみも漂っています。トムはあくまで「作られた存在」であり、人間ではありません。彼がどれだけ村に尽くしても、本当の意味で人間社会に溶け込めるわけではない。また、彼を作り出した技術の背景には、生命倫理に関わるような暗い側面も示唆されています。
物語は、トムに関する記録を発見した現代の研究者の視点を交えながら進みます。発見された資料は、トムと村人たちの交流を感動的に語る一方で、その記録が誰によって、どのような意図で書かれたのか、という謎も提示します。もしかしたら、都合の良い部分だけが記録されたのかもしれない、という疑念も残る。
それでも、異質な存在を受け入れ、共に生きようとした人々の姿を描いたこの物語は、非常に印象的でした。外見や出自にとらわれず、相手の本質を見ようとすることの大切さを教えてくれるようです。宮部さんの描く人情味あふれる世界観が、SF的な設定と見事に融合した、美しくも切ない物語でした。まるで、打ち捨てられた貝殻の中に、思いがけず美しい真珠を見つけたような、そんな読後感でした。
『保安官の明日』
8編の中で、最もSF的な設定が色濃く、そして最も「歪んだ」世界を描いているのが、この『保安官の明日』かもしれません。舞台となる「ザ・タウン」は、一見するとアメリカの田舎町のような、のどかな場所です。しかし、この町は外界から完全に隔絶されており、住人たちは皆、ある目的のためにここに「置かれている」存在なのです。
物語は、ベテラン保安官と、新米助手のチコの視点を通して、この町の異常性を少しずつ明らかにしていきます。町で起こる事件は、どこか現実味がなく、登場人物たちの反応も不自然です。そして、物語の核心で明かされるのは、この町が、ある大富豪が自分の出来の悪い息子(ピーター)の人生をやり直させるために作り出した、巨大な仮想現実(あるいはそれに近い閉鎖環境)であるという事実です。
住人たちは、ピーターの人生の「リセット」に合わせて、記憶を操作され、同じような日常を何度も繰り返させられています。彼らは、大富豪に雇われた役者か、あるいはピーターの更生(?)のために利用されている、一種の生きた人形のような存在なのです。保安官もまた、このシステムの管理者であり、同時に囚われ人でもあります。彼は、この繰り返される茶番にうんざりしながらも、自分の役割を演じ続けるしかない。
若い女性の拉致事件が起こり、犯人が自殺するという結末も、結局はピーターの「失敗」をリセットするための一つのシナリオに過ぎなかったのかもしれません。保安官が「これでまたリセットされる」と呟く場面は、この町の不条理さと、そこに生きる人々の絶望を象徴しています。
人間のエゴや願望が、他者の人生を踏みにじってでも実現されようとする。その恐ろしさが、この閉鎖された町の設定を通して、強烈に描かれています。親が子のために良かれと思ってやったことが、結果的に歪んだ支配を生み出してしまう。このテーマは、現代の親子関係や教育問題にも通じるものがあるかもしれません。非常にダークで、後味の悪い物語ですが、それだけに強く印象に残り、人間の欲望の深淵を覗き込んだような感覚を覚えました。もし自分がこの町の住人だったら…と考えると、ぞっとしますね。
まとめ
宮部みゆきさんのSF短編集「さよならの儀式」、いかがでしたでしょうか。8つの物語は、それぞれ異なるSF的テーマを扱いながらも、通底しているのは宮部さんならではの深い人間洞察と、現代社会への問いかけです。近未来の法律、異星人の影、タイムスリップ、ロボットとの絆、超常現象、異種との共生、そして仮想空間。多彩な舞台設定の中で、人間の喜び、悲しみ、愛情、憎しみ、エゴ、希望といった普遍的な感情が、鮮やかに描き出されていました。
どの物語も、単純なハッピーエンドや、すっきりとした解決が用意されているわけではありません。むしろ、読後に重い問いを残したり、もやもとした気持ちになったりするものも少なくありませんでした。しかし、それこそが宮部作品の魅力なのかもしれません。簡単に答えの出ない問題だからこそ、私たちは考え続け、物語の世界に深く引き込まれていくのではないでしょうか。特に『母の法律』や『保安官の明日』で描かれた人間のエゴの深さや、『さよならの儀式』や『海神の裔』で描かれた人間と非人間の間に生まれる絆の形は、強く心に残りました。
SFというジャンルに馴染みがない方でも、心配はいりません。難解な科学理論が展開されるわけではなく、あくまでも「もしもこんな世界があったら、人々はどう生きるのか」という点に焦点が当てられています。宮部さんの確かな筆力によって、どの物語もリアリティをもって迫ってきます。ミステリーファンなら『聖痕』の展開に、時代小説ファンなら『海神の裔』の雰囲気に、きっと引き込まれるはずです。宮部みゆきさんの新たな魅力を発見できる、読み応えのある一冊。ぜひ手に取って、この不思議で、時に切なく、そして考えさせられる物語の世界に触れてみてください。































































