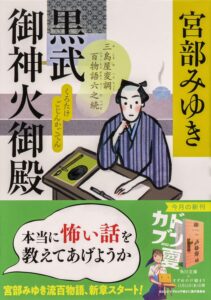 小説「黒武御神火御殿 三島屋変調百物語六之続」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんが紡ぎ出す「三島屋変調百物語」シリーズは、江戸の袋物屋・三島屋の奥座敷「黒白の間」で語られる怪異譚を集めた人気シリーズですね。本作はその第六弾となります。
小説「黒武御神火御殿 三島屋変調百物語六之続」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんが紡ぎ出す「三島屋変調百物語」シリーズは、江戸の袋物屋・三島屋の奥座敷「黒白の間」で語られる怪異譚を集めた人気シリーズですね。本作はその第六弾となります。
前作まで聞き手を務めていたおちかさんがお嫁に行かれ、本作からは三島屋の次男坊、富次郎さんが新たな聞き手となります。おちかさんの聡明で物静かな聞き手ぶりも素晴らしかったですが、若旦那である富次郎さんが、これからどんな風に語り手と向き合い、物語を受け止めていくのか。期待と少しの寂しさが入り混じる、そんな心持ちでページをめくり始めました。
本作には、富次郎さんが聞き手として初めて対峙する四つの物語が収められています。幼馴染が語る一家離散の真相、村の因習に隠された哀しい秘密、走り飛脚が出会った不思議な道連れ、そして表題作でもある、謎めいた屋敷での恐ろしくも奇妙な一夜。どの話も、人の心の闇や情念、そして思いがけない救いが描かれていて、ぐいぐいと引き込まれました。それでは、物語の詳しい内容と、私の感じたことをお話ししていきましょう。
小説「黒武御神火御殿 三島屋変調百物語六之続」のあらすじ
三島屋の次男・富次郎は、姉代わりであったおちかの後を継ぎ、百物語の聞き手という大役を務めることになりました。まだ二十二歳の若者であり、絵師を目指していた彼にとって、人の心の奥底に触れる怪異譚を聞くことは、大きな戸惑いと試練の連続です。それでも、訪れる語り手たちの「語りたい」という切実な思いに応えようと、富次郎は懸命に耳を傾けます。古参の女中・おしまや、守り役として側に控えるお勝の助けを借りながら、彼は自分なりの聞き手の在り方を模索し始めます。
最初の語り手は、富次郎の幼馴染でもある豆腐屋の八太郎でした。彼は、幼い頃に経験した一家離散の出来事を語ります。家族の中に静かに、しかし確実に亀裂を入れていったある「異変」。それは人の悪意なのか、それとも目に見えぬものの仕業なのか。恐ろしい真相が、富次郎の目の前で明かされていきます。
次に訪れたのは、富次郎の母・お民と同年代の女性、お花。彼女は故郷の村に伝わる奇妙な因習について語り始めます。桜の名所である美しい丘に、なぜか自分の家系の女だけは登ることを許されない。その理由には、過去の悲劇と、今なお残る強い念が関わっていました。禁を破った先に待ち受ける運命とは…。
三人目の語り手は、走り飛脚の亀一。彼は、妻子を亡くした失意の中で経験した不思議な出来事を打ち明けます。孤独な道中で彼についてくるようになった、顔のない存在。その正体と目的を探るうちに、亀一は自身の心の奥底にしまい込んでいた感情と向き合うことになります。「同行二人」という言葉が、切なくも温かい意味合いを帯びて響きます。
そして最後に語られるのが、表題作「黒武御神火御殿」。全身に傷跡を持つ男・甚三郎が語るのは、若い頃に迷い込んだという謎の屋敷での壮絶な体験です。神隠しのように集められた男女、次々と現れる異形の者たち、そして屋敷に渦巻く強大な怨念。甚三郎は、そこで繰り広げられた生き残りをかけた一夜を、富次郎に語り聞かせます。この長く、そして複雑な物語は、富次郎にとっても大きな試金石となるのでした。
小説「黒武御神火御殿 三島屋変調百物語六之続」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは「黒武御神火御殿 三島屋変調百物語六之続」を読んで私が感じたことを、物語の核心に触れながら、存分にお話ししたいと思います。ネタバレを含みますので、未読の方はご注意くださいね。
まず、本作全体を通して強く感じたのは、聞き手が富次郎さんに変わったことによる「変化」と「継承」です。おちかさんが背負っていた深い哀しみと、どこか達観したような静けさとは対照的に、富次郎さんは若者らしい実直さ、戸惑い、そして優しさをもって語り手に向き合います。彼の悩みや成長が、物語の縦糸としてしっかりと描かれているのが印象的でした。
最初の物語「泣きぼくろ」は、富次郎さんの聞き手としての門出にふさわしい、しかしながら実に業の深い話でしたね。語り手の八太郎が富次郎さんの幼馴染という設定も、周旋役の灯庵(蝦蟇仙人)の配慮なのでしょうが、語られる内容は凄まじいものでした。
八太郎の家族が崩壊していく過程は、本当にぞっとします。特に、母親が徐々に正気を失っていく様子、そしてその原因が、亡くなった姉の「泣きぼくろ」と同じ場所にできた痣(あざ)にあるのではないかと疑われるあたりは、怪談としての不気味さが際立っていました。結局、その痣が直接的な原因だったのか、それとも家族の中に元々あった歪みが別の形で噴出したのか、明確な答えは示されません。この「わからなさ」が、かえって現実的な恐怖を感じさせるんですよね。理由がはっきりしない災厄ほど、対処のしようがなく、恐ろしいものはありません。
家族という、本来なら最も安全であるはずの場所が、疑心暗鬼と憎悪によって地獄へと変わっていく。子供だった八太郎の視点から語られることで、その理不尽さと哀しみが一層胸に迫ります。富次郎さんが、この重い話をどのように受け止め、聞き手としての第一歩を踏み出したのか。彼の心中を思うと、こちらも固唾を飲んでしまいます。ただ聞くだけでなく、語り手の心を少しでも軽くするために、富次郎さんが言葉を探す姿には、彼の誠実さが表れていました。
二番目の「姑の墓」は、因習と怨念という、これまた怪談の王道ともいえるテーマを扱っています。桜が咲き誇る美しい丘。しかし、お花の家系の女だけはその絶景を見ることが許されない。その理由が、過去に起きた姑による嫁いびりと、その果ての悲劇にあると明かされるとき、やりきれない気持ちになりました。
お恵という娘が、理不尽な因習に反発し、禁を破って丘に登ろうとする気持ちは、痛いほどよく分かります。なぜ自分たちだけが、遠い過去の出来事のせいで、こんな不自由を強いられなければならないのか。しかし、その行動がさらなる悲劇を招いてしまう展開は、やるせないですね。「昔からの言い伝えには耳を傾けるべき」という教訓めいたものを感じさせつつも、同時に、その言い伝えを生んだ人間の業の深さ、怨念の恐ろしさを突きつけられます。
印象的だったのは、語り終えたお花に対して、富次郎さんがかけた言葉です。姑になることへの不安を口にするお花に、富次郎さんは、過去の怨念の連鎖を断ち切るように、未来へ目を向けることの大切さを語ります。それは、聞き手としてただ話を聞くだけでなく、語り手の心を少しでも救おうとする富次郎さんの優しさの表れでしょう。おちかさんとは違う、富次郎さんならではの関わり方が見えた場面でした。心の持ちよう一つで、過去の呪縛から解き放たれることもあるのかもしれない。そんな希望を感じさせてくれる結びでした。
三番目の「同行二人」は、個人的に最も心に残った、そして救いのある物語でした。妻子を失い、生きる意味を見失っていた走り飛脚の亀一。彼が道中で出会う「のっぺらぼう」は、最初は不気味な怪異として描かれますが、次第にその存在が、亀一自身の心の反映であり、そして彼と同じように喪失の痛みを抱えた魂であることがわかってきます。
飛脚問屋の支配人の言葉が、深く胸に響きました。「ここはおまえさんの人生の峠越えだよ」「たとえ相手が化け物であっても、この世のあっちからこっちまで駆け抜けるのが身上の飛脚が、袖ふり合った縁を無下にするな」。この言葉に励まされ、亀一はのっぺらぼう――寛吉という名の若者の霊――と向き合うことを決意します。
亀一が、寛吉の境遇を知り、彼の無念を受け止める中で、自分自身の心の傷とも向き合っていく過程が丁寧に描かれています。「俺は心を失くしてたんだ」という亀一の気づきは、読んでいて涙がこぼれそうになりました。失意の底にあった亀一が、寛吉との出会いを通して、再び「生きたい」という気持ちを取り戻していく。それは、怪異譚でありながら、見事な再生の物語でもありました。富次郎さんも、この話には深く心を動かされたのではないでしょうか。悲劇は悲劇として受け止めつつ、それでも人は前を向いて生きていけるのだという、温かいメッセージを感じました。三島屋の百物語には、こうした人の心の機微や救いを描いた物語が必ず含まれているのが、シリーズの大きな魅力の一つだと思います。
そして、いよいよ表題作「黒武御神火御殿」。これはもう、他の三編とは趣が異なり、スケールの大きな伝奇活劇といった趣でしたね。物語の半分近くを占めるだけあって、読み応えも十分でした。
語り手の甚三郎の風貌からして、いかにも訳ありな雰囲気が漂っています。彼が語る、黒武家の屋敷での一夜の出来事は、まさに悪夢そのものです。神隠しのように集められた男女、次々と襲い来る異形の怪物たち。屋敷全体が、強い怨念によって異界化しているような描写は、息を飲むような迫力がありました。特に、耶蘇教(キリスト教)の信仰が、歪んだ形で怨念の源となっているという設定は、宮部さんの作品では珍しく、興味深く読みました。
本作では、日本の八百万の神々の考え方と、西洋の一神教の考え方の対比が、物語の背景として描かれています。どちらが良い悪いという話ではなく、信仰が受け入れられなかった者の絶望が、いかに強大な負の力となり得るか、という点が恐ろしく感じられました。屋敷の主であった黒武家の当主や、彼に従った者たちの怨念が、物理的な形を伴って襲いかかってくる。その描写は凄まじく、ハラハラドキドキの連続でした。
この物語で特に印象的だったのは、登場人物たちの人間臭さです。語り手の甚三郎は、見た目こそ強面ですが、怖がったり、動揺したりする場面も多く、決して完璧なヒーローではありません。しかし、土壇場で見せる胆力や、生き延びようとする執念には、人間的な強さを感じます。そして、私が特に魅力を感じたのは、お秋という女性です。彼女の気風(きっぷ)の良さ、甚三郎を叱咤激励する姿は、読んでいて実に小気味よかった。彼女のような存在がいたからこそ、甚三郎も極限状況を乗り越えられた部分があるのではないでしょうか。彼女の存在は、暗く恐ろしい物語の中で、まるで一点の灯火のようでした。
また、この章では、嬉しいサプライズとしておちかさんが登場しますね。三島屋に持ち込まれた謎の印半纏(しるしばんてん)の調査で、富次郎さんが嫁ぎ先の瓢箪古堂を訪れる場面。そこで描かれるおちかさんの幸せそうな様子には、読んでいるこちらも本当に嬉しくなりました。富次郎さんが少し妬いてしまう描写も微笑ましく、二人の姉弟のような絆を感じさせます。おちかさんが物語の本筋に深く関わるわけではありませんが、彼女が元気でいることが確認できただけでも、シリーズのファンとしては満足でした。
そして、この長大な物語を聞き終えた富次郎さんの対応も見事でした。甚三郎が体験したことは、あまりにも壮絶で、常軌を逸しています。富次郎さんは、その話をただ受け止めるだけでなく、最後に絵を描かないという選択をします。語られた物語を絵に残すことは、富次郎さんにとって一つの表現方法ですが、この「黒武御神火御殿」の物語は、絵にすることで、かえってその恐ろしさや業の深さを矮小化してしまう、あるいは、再びその闇を呼び覚ましてしまう危険性を感じたのかもしれません。彼の判断は、聞き手としての誠実さと、物語に対する深い敬意の表れだと感じました。お勝さんが側にいてくれることも、富次郎さんにとって大きな支えになっているのでしょうね。
富次郎さんは、おちかさんのように自身が深い傷を負っているわけではありません。だからこそ、語り手の壮絶な体験に圧倒されそうになりながらも、持ち前の素直さや共感力で、懸命に寄り添おうとします。その姿は、読んでいて応援したくなりますし、彼がこれからどのように聞き手として成長していくのか、ますます楽しみになりました。
「黒武御神火御殿 三島屋変調百物語六之続」は、恐怖、哀しみ、不思議、そして再生と、様々な感情を呼び起こされる四つの物語が詰まった、実に味わい深い一冊でした。富次郎さんという新しい風が、三島屋の百物語にどのような変化をもたらしていくのか、次作への期待が膨らみます。
まとめ
宮部みゆきさんの「黒武御神火御殿 三島屋変調百物語六之続」、いかがでしたでしょうか。聞き手が富次郎さんにバトンタッチされ、新たな局面を迎えた三島屋シリーズ。若き聞き手の奮闘と成長ぶり、そして彼が受け止める四つの怪異譚は、どれも心に深く刻まれるものでした。
家族の崩壊を描く静かな恐怖、因習に秘められた哀しい過去、喪失から再生へと向かう道程での不思議な出会い、そして壮大なスケールで描かれる怨念と対峙する一夜。バラエティに富んだ物語は、私たち読者を江戸の闇と光の世界へと誘ってくれます。人の心の奥底に潜む恐ろしさだけでなく、そこから立ち上がろうとする人間の強さや温かさも描かれているのが、このシリーズの素晴らしいところですね。
富次郎さんが、これからどんな物語と出会い、聞き手としてどのように深みを増していくのか。そして、時折姿を見せてくれるであろう、おちかさんの幸せな様子も楽しみにしつつ、次なる百物語を心待ちにしたいと思います。まだ読まれていない方はもちろん、シリーズを追いかけている方にも、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。































































