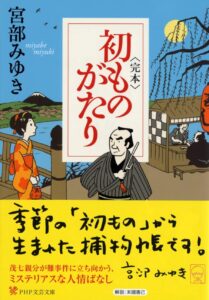 小説「初ものがたり」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんが描く江戸の町、深川本所を舞台にした、心温まり、時に胸が締め付けられるような物語の数々。岡っ引きの茂七親分と、謎多き稲荷寿司屋の親父を中心に、人々の喜びや悲しみ、そしてささやかな日常に起こる事件が描かれています。
小説「初ものがたり」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんが描く江戸の町、深川本所を舞台にした、心温まり、時に胸が締め付けられるような物語の数々。岡っ引きの茂七親分と、謎多き稲荷寿司屋の親父を中心に、人々の喜びや悲しみ、そしてささやかな日常に起こる事件が描かれています。
この作品は、六つの短編からなる連作集です。一つ一つの話は独立していますが、読み進めるうちに登場人物たちの関係性や、物語の背景にある大きな流れのようなものが少しずつ見えてくるのが魅力です。特に、茂七親分が事件に行き詰まったとき、ふらりと立ち寄る稲荷寿司屋の屋台での親父とのやり取りは、物語の重要なスパイスになっています。
この記事では、各話の物語の筋道に触れながら、その結末にも言及していきます。また、私がこの物語を読んで感じたこと、考えたことを、少し長くなりますが詳しくお伝えしたいと思います。江戸の風情や人情話が好きな方、そして少しだけミステリの要素も楽しみたい方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。
小説「初ものがたり」のあらすじ
物語の舞台は江戸、深川本所界隈。このあたり一帯を取り仕切る「回向院の旦那」こと岡っ引きの茂七が、さまざまな事件に関わっていきます。茂七は、どんな事件であっても自分の心の秤を頼りに、情理を尽くして解決へと導こうとする、頼りがいのある親分です。彼のもとには、下っ引きの糸吉や権三といった面々もいます。
そんな茂七が、考え事に行き詰まったり、少し息抜きをしたいときに立ち寄るのが、深川富岡橋のたもとにある稲荷寿司の屋台。この屋台を営む親父は、多くを語らず、どこか影のある人物ですが、その鋭い観察眼やぽつりともらす一言が、しばしば茂七に事件解決の糸口を与えることになります。この稲荷寿司屋の親父の素性は謎に包まれており、茂七だけでなく、読者の興味も引きつけます。
物語は連作短編の形式で進みます。醤油売りの女性が殺された「お勢殺し」、供え物の稲荷寿司に毒が仕込まれ子供たちが犠牲になった「白魚の目」、鰹を千両で売ってくれという奇妙な依頼から始まる「鰹千両」、いかさま霊感商売が絡む「太郎柿次郎柿」、盗まれた新巻鮭の裏にある人間関係を描く「凍る月」、そして霊能力者が襲われ、行方不明者捜しへと繋がっていく「遺恨の桜」。
これらの事件を通して、江戸に生きる人々のささやかな営み、喜び、悲しみ、そして時にやるせない人の業が描かれます。茂七親分の人情味あふれるお裁きと、稲荷寿司屋の親父の загадка な存在感が、物語全体に深みを与えています。読み終えた後には、登場人物たちの息遣いが聞こえてくるような、そんな余韻に浸れる作品です。
小説「初ものがたり」の長文感想(ネタバレあり)
宮部みゆきさんの「初ものがたり」を読み終えて、心の中にじんわりと温かいものが広がると同時に、いくつかの物語では、ずしりと重い感情も残りました。江戸の町を舞台にした人情噺でありながら、そこには現代にも通じるような人間の心の闇や、社会の不条理さも巧みに織り込まれているように感じます。
まず、この物語の大きな魅力は、やはり主人公である岡っ引きの茂七親分と、謎多き稲荷寿司屋の親父の関係性でしょう。茂七親分は、正義感が強く、弱い立場の人々に寄り添う優しさを持っています。事件の真相を追い求める厳しい一面もありますが、その根底には常に「人」への深い眼差しがあるように思います。彼が下すお裁きは、単に犯人を捕まえるだけでなく、関わった人々の今後の人生をも見据えたような、温かみのあるものです。
一方、稲荷寿司屋の親父。彼の存在が、この物語に独特の奥行きを与えています。深川富岡橋のたもとでひっそりと屋台を出し、多くを語らない。しかし、その佇まいや、時折見せる鋭い洞察力は、彼がただ者ではないことを匂わせます。茂七親分が捜査に行き詰まったとき、親父の屋台で稲荷寿司や季節の料理をつつきながら交わす会話は、まるで禅問答のようでもあり、茂七にとっては思考を整理し、新たな視点を得るための大切な時間となっています。親父がぽつりともらす言葉が、事件解決の鍵となることも少なくありません。彼の過去には何があったのか、なぜ岡っ引きの茂七に一目置かれているのか、そしてなぜやくざ者の梶屋の勝蔵までもが彼に頭が上がらないのか。物語が進むにつれて、その謎は深まるばかりで、読んでいるこちらも「親父さん、あなたはいったい何者なんだ?」と思わずにはいられません。作中で、彼がかつて「屋敷」に住んでいたことを匂わせる場面もあり、元は武士だったのではないか、あるいは何か特別な役職に就いていたのではないか、などと想像が膨らみます。この謎が、物語全体を貫く縦糸の一つとなっているのです。
六つの短編は、それぞれ独立した事件を扱っていますが、どれも印象深いものばかりでした。
最初の「お勢殺し」は、醤油の担ぎ売りであるお勢という女性が水死体で見つかる話です。容疑者として浮かび上がるのは、彼女と付き合いのあった野崎屋の音次郎。アリバイがあると主張する音次郎ですが、茂七親分は稲荷寿司屋の親父との会話からヒントを得て、そのアリバイを崩していきます。男女のもつれが原因と思われた事件ですが、そこにはお勢の一途な思いと、それを利用した男の身勝手さが描かれており、やりきれない気持ちになりました。茂七親分と稲荷寿司屋の親父の、少し緊張感をはらんだやり取りが、この話の読みどころの一つだと感じました。蕪汁をすすりながら事件の核心に迫っていく茂七親分の姿が目に浮かぶようです。
次に「白魚の目」。これは読んでいて本当に胸が苦しくなりました。冬木町の小さな稲荷神社で、身寄りのない子供たちが五人も毒殺されてしまうという、痛ましい事件です。毒が仕込まれていたのは、お供え物の稲荷寿司。この「稲荷寿司」という小道具が、稲荷寿司屋の親父と何か関係があるのかと思いきや、直接的な繋がりはなく、それがかえって事件のやるせなさを際立たせているようにも感じました。犯人は比較的早い段階で推測できるのですが、その動機や手口があまりにも非情で、怒りすら覚えます。しかし、茂七親分は直接的な罰を与えることが難しい状況の中で、機転を利かせ、子供たちの無念を少しでも晴らすような、そして未来に繋がるような形で事件を収めます。その裁きの見事さには感嘆しましたが、読後感としては最も重く、後味の悪さが残る一編でした。人の心の闇の深淵を覗き込んだような気持ちになりました。
重苦しい「白魚の目」の後で、少し心が和んだのが「鰹千両」です。棒手振りの魚屋、角次郎のもとに、「鰹一匹を千両で買いたい」という奇妙な話が舞い込みます。持ちかけたのは大店の呉服屋の主人。もちろん、話はそんな単純なものではありません。呉服屋の真の目的は、角次郎の美しい娘、おはるでした。金か、娘か。究極の選択を迫られる家族。茂七親分は、角次郎一家の心根を確かめ、彼らのために奔走します。角次郎の妻おせんが、茂七親分の問いかけに思わず手を上げてしまう場面は、娘を思う親の必死な気持ちが伝わってきて、胸が熱くなりました。そして、茂七親分の粋な計らいによって、事件は人情味あふれる結末を迎えます。これぞ時代劇の醍醐味、と感じさせてくれるような、読後感の良い話でした。茂七親分のカッコよさが際立つ一編です。
「太郎柿次郎柿」では、日道さまという、不思議な力を持つとされる拝み屋の少年が登場します。失せ物探しから人の寿命まで言い当てるという評判ですが、茂七親分はそのいかにも胡散臭いやり方が気に入りません。現代で言うところの霊感商法のようなもので、しかもそれを幼い子供に強いているのが親だという点が、やるせない気持ちにさせます。この話の筋は、兄が弟を殺してしまうという悲劇なのですが、それ以上に印象に残ったのは、稲荷寿司屋の親父が菓子作りを習いに行ってしまい、その間寂しい思いをした茂七親分のために、柿羊羹を振る舞う場面です。ここでの二人の会話の中に、親父の過去をうかがわせる「昔わたしが住んでいた屋敷」という言葉がこぼれ落ち、ミステリアスな親父の人物像にさらに興味をかき立てられます。
「凍る月」は、下酒問屋の主人、松太郎が、貰い物の新巻鮭を盗まれたと茂七親分のもとへやってくるところから始まります。しかし、松太郎が本当に気に病んでいたのは、鮭のことではなく、時を同じくしていなくなった女中のおさとのことでした。店の信用や世間体、そして秘めた想い。お店に生きる人々の複雑な人間関係や、ままならない思いが描かれており、切なさが漂う物語です。この話でも、茂七親分と稲荷寿司屋の親父のやり取りが光ります。茂七は、親父が気に入らない拝み屋の日道さまの元を訪ねているのを目撃してしまい、心中穏やかではありません。親父への信頼と、日道への不信感の間で揺れる茂七の気持ちが伝わってきます。鮭の切り身をつつきながらの、腹の探り合いのような二人の会話は、静かな緊張感に満ちていて引き込まれました。
そして最後が「遺恨の桜」。拝み屋の日道さまが何者かに襲われ、大怪我を負います。時を同じくして、お夏という女性が、いい仲だった清一が行方不明になり、殺されて埋められているのではないかと茂七のもとへ駆け込んできます。このお夏もまた、日道さまを頼っていた一人でした。二つの事件は繋がり、やがて真相が明らかになっていきます。この話では、日道さまの霊視のからくりが、稲荷寿司屋の親父によって解き明かされます。そのトリックは、わかってしまえば単純なことなのですが、人の心の隙につけ込む巧妙さがあります。そして、親父の正体についても、茂七の下っ引きである権三が「武士ではないか」と推測する場面があり、ますます謎が深まります。事件の落としどころも、茂七親分らしい、関係者の心情に配慮したもので、読後感は悪くありません。しかし、物語の最後で、稲荷寿司屋の親父の過去や正体は完全には明かされず、続編を匂わせるような形で終わります。作者のあとがきによれば、諸事情で続編は書かれていないとのことですが(あとがき執筆時点)、いつかこの親父の物語が読めたら、と願わずにはいられません。桜餅の関東風と関西風の違いなど、江戸の文化に触れる描写も興味深かったです。
全体を通して感じたのは、宮部みゆきさんの筆致の確かさです。江戸の町の空気感、人々の息遣いが、まるで目の前にあるかのように生き生きと描かれています。特に、食べ物の描写がとても美味しそうで、稲荷寿司はもちろん、蕪汁、白魚、鰹、柿羊羹、新巻鮭、鰆の塩焼きなど、読むとお腹が空いてきます。それらの食べ物が、単なる小道具ではなく、登場人物たちの心情や関係性を映し出す鏡のようにも機能しているのが見事です。
まるで複雑な織物のように、人々の縁と事件が絡み合っていくのです。 悲しい話、やるせない話も多いのですが、その中に必ず茂七親分の人情や、稲荷寿司屋の親父の静かな存在感があり、それが救いとなっています。人間の弱さや醜さも描きながら、それでも人の善意や温かさを信じさせてくれる。そんな深みのある物語だと思いました。派手な立ち回りや、奇抜なトリックがあるわけではありませんが、じっくりと腰を据えて、江戸の市井の人々のドラマに浸りたい方には、ぜひおすすめしたい作品です。読み終えた後、きっと美味しい稲荷寿司が食べたくなることでしょう。
まとめ
宮部みゆきさんの小説「初ものがたり」は、江戸の深川本所を舞台に、岡っ引きの茂七親分と謎多き稲荷寿司屋の親父を中心に描かれる、六つの連作短編集です。人情味あふれる物語の中に、ミステリの要素も散りばめられており、読み応えがあります。
各話では、殺人事件から子供たちの悲劇、奇妙な依頼、いかさま商売、盗難事件、そして失踪事件まで、様々な出来事が起こります。茂七親分は、持ち前の正義感と人情でこれらの事件に向き合い、時に稲荷寿司屋の親父の助言を得ながら、真相へと迫っていきます。その過程で描かれる江戸の人々の暮らしや心の機微は、読者の心を打ちます。
物語の魅力は、茂七親分の温かいお裁きと、最後まで загадка な存在である稲荷寿司屋の親父のキャラクター、そして二人の間に流れる静かな信頼関係にあります。後味の悪い話もありますが、全体としては江戸の風情と人情が心地よく感じられ、読後には温かい気持ちと、少しの切なさが残る作品です。時代小説や人情噺が好きな方、そして宮部みゆきさんのファンの方には、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。































































