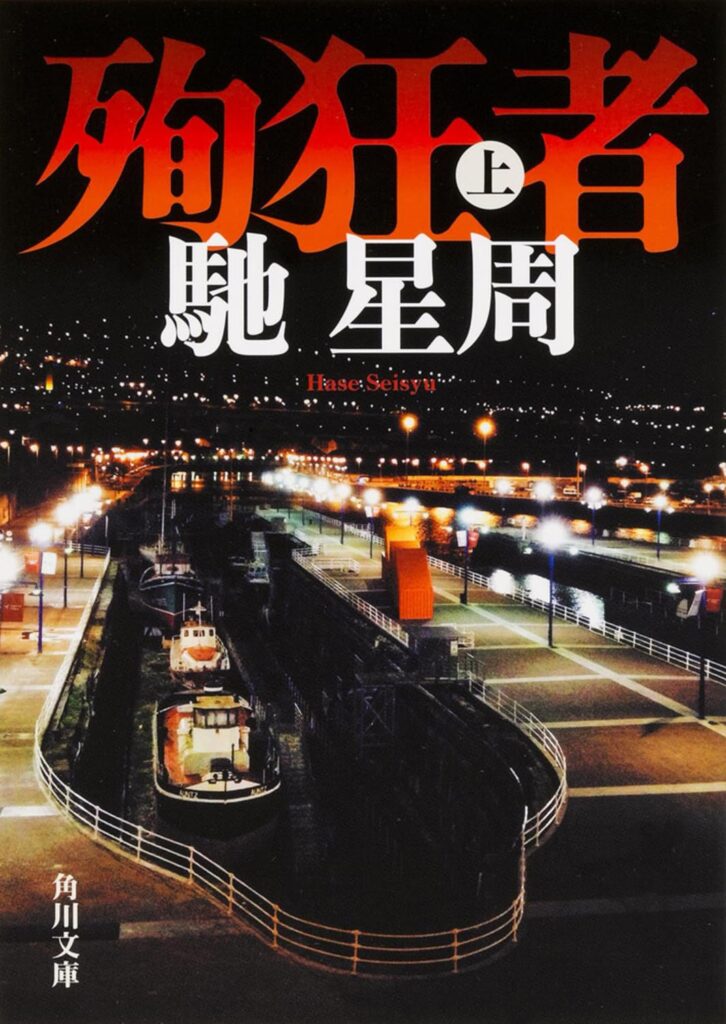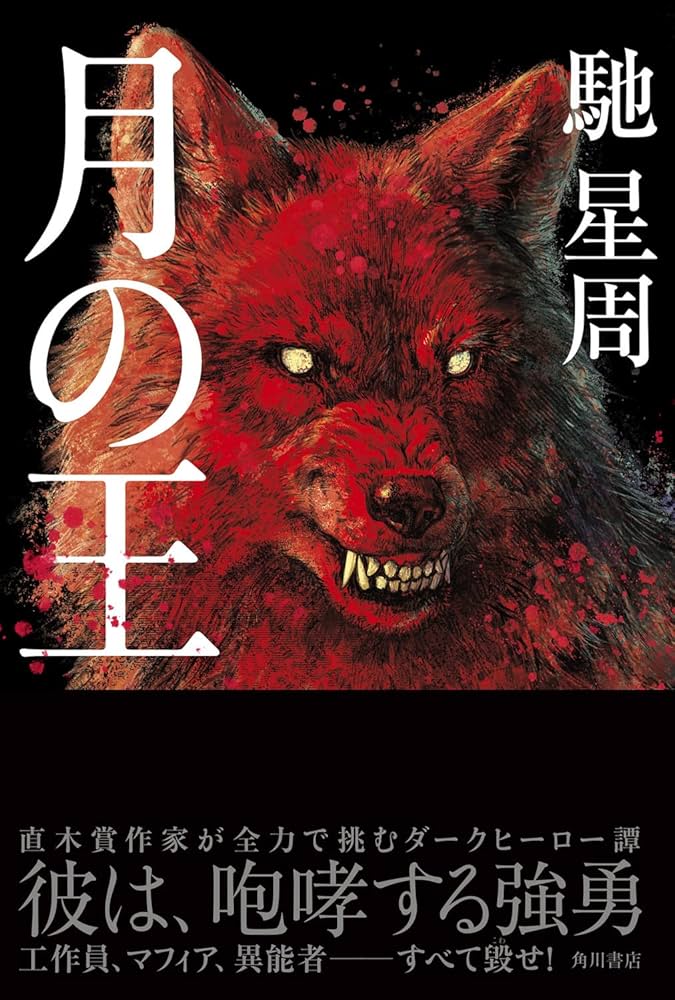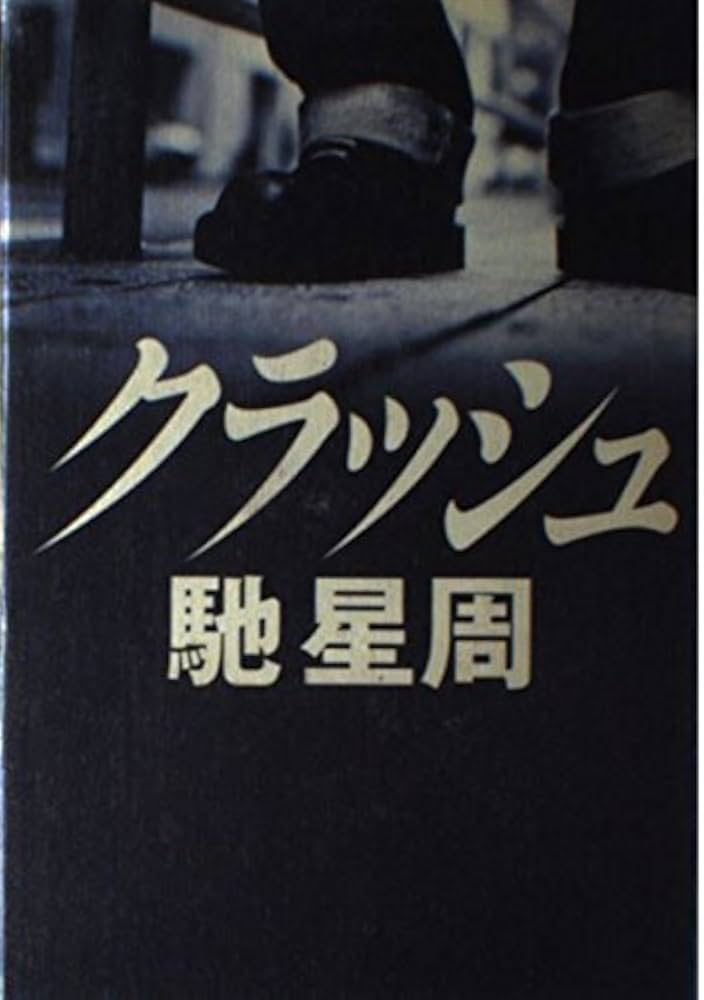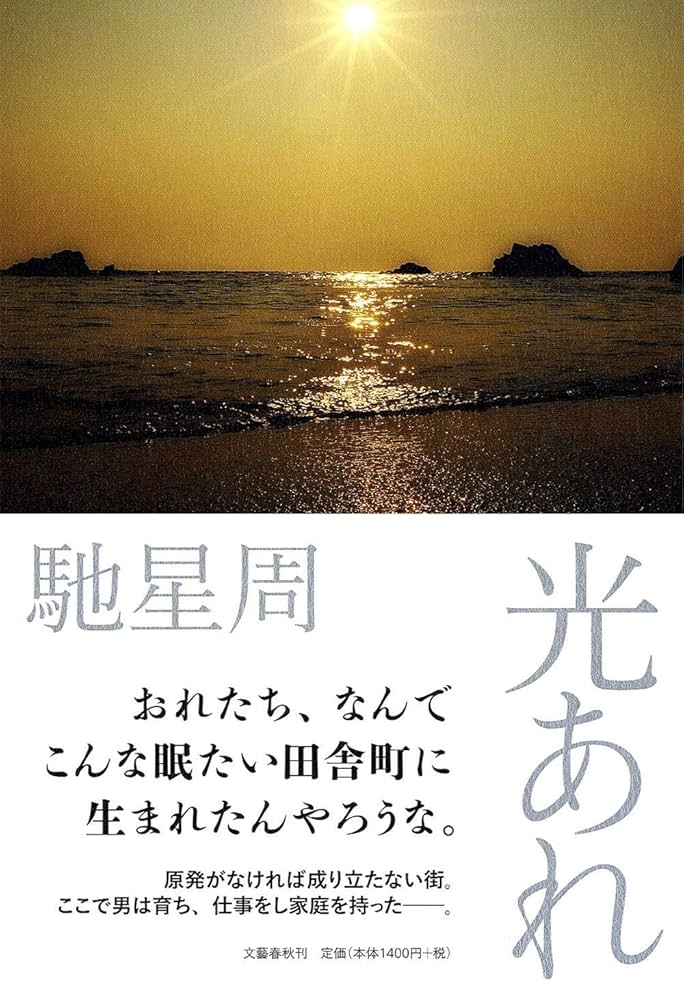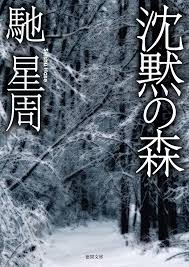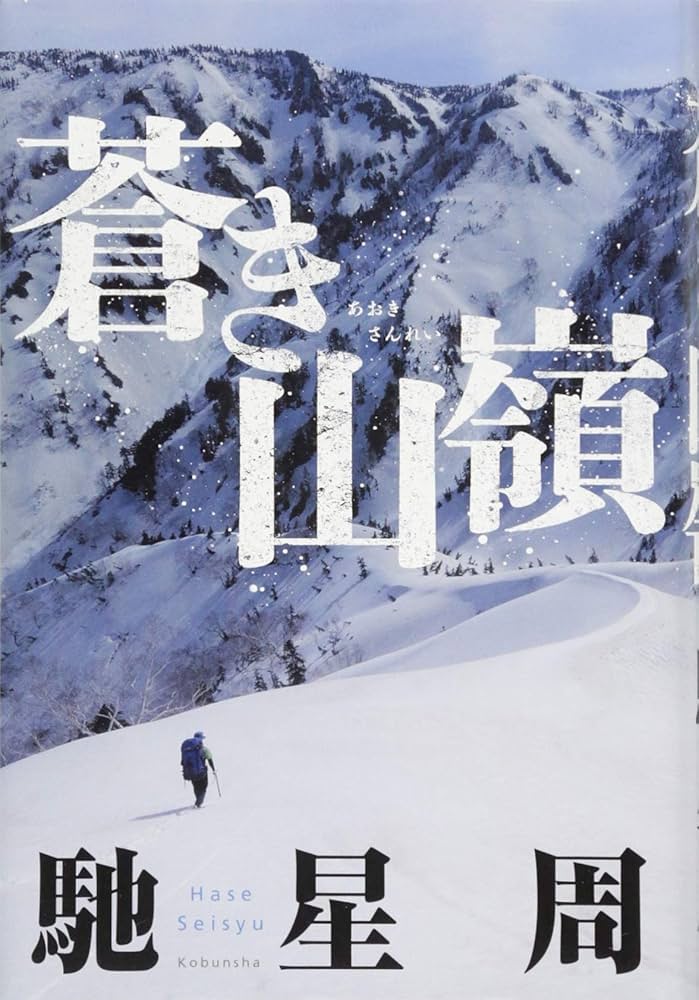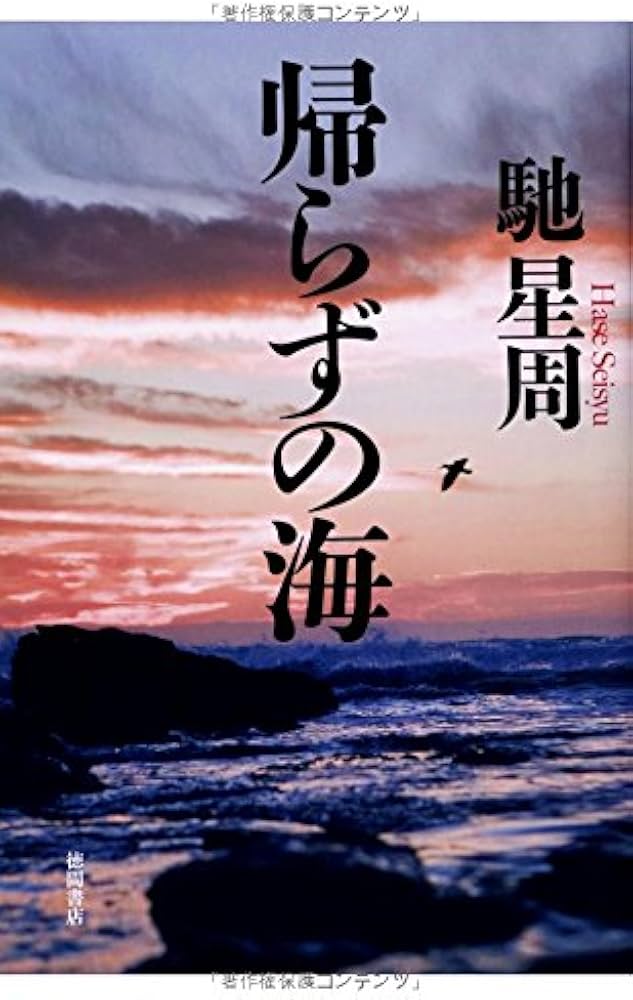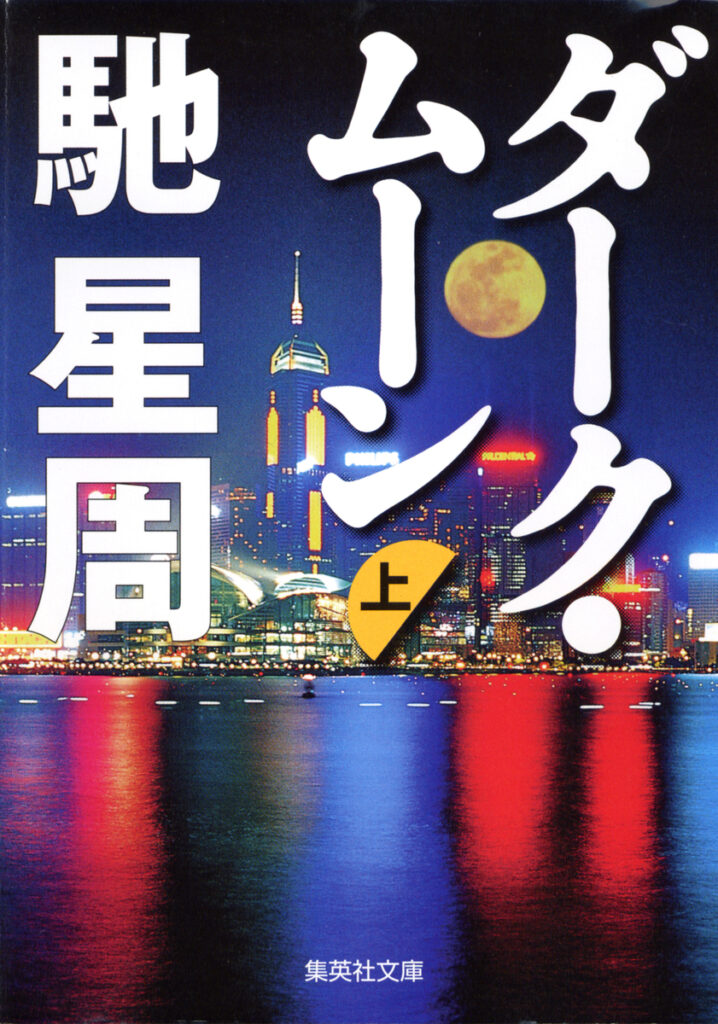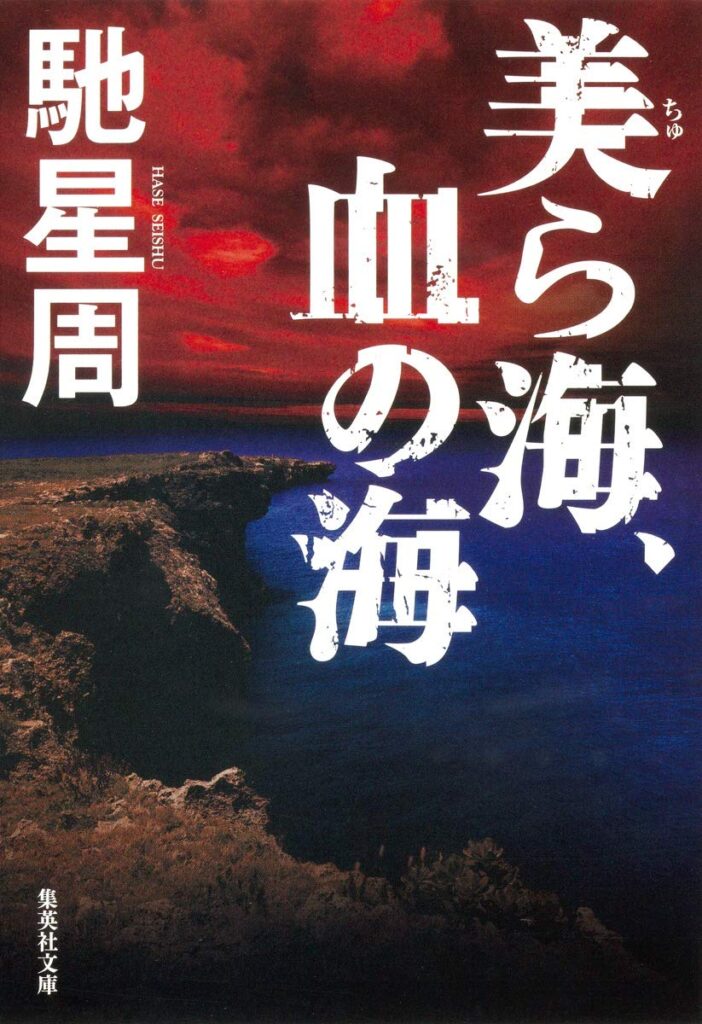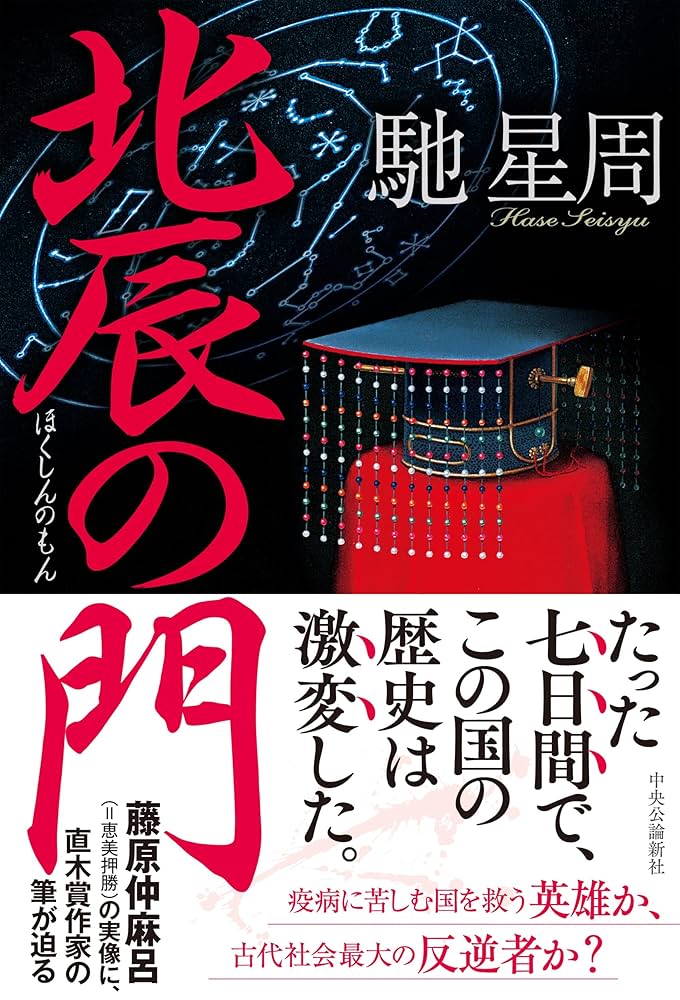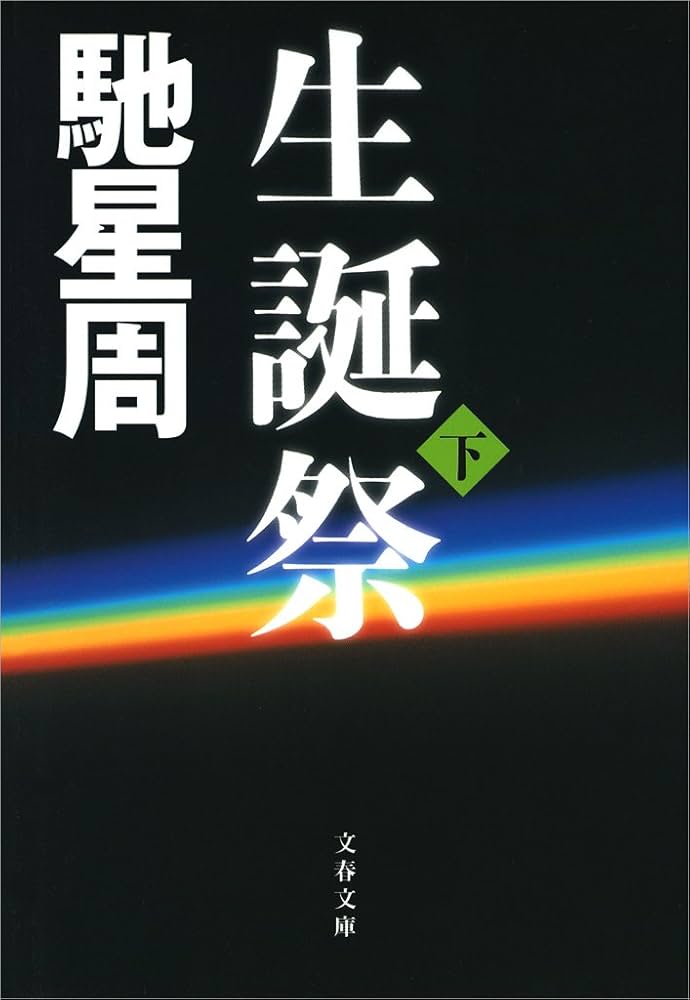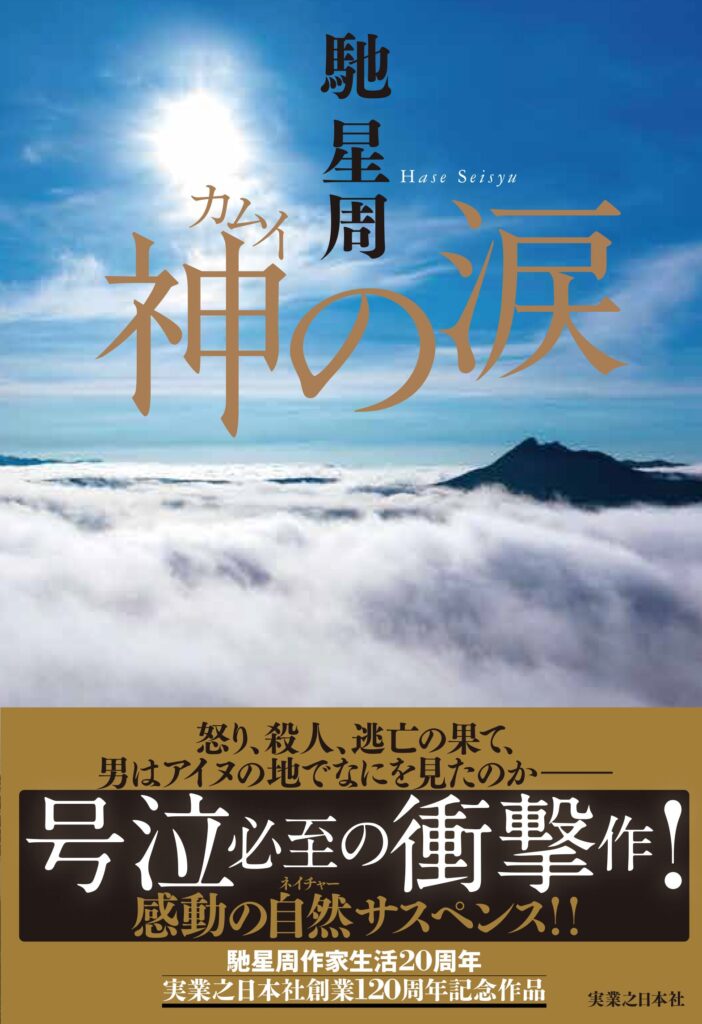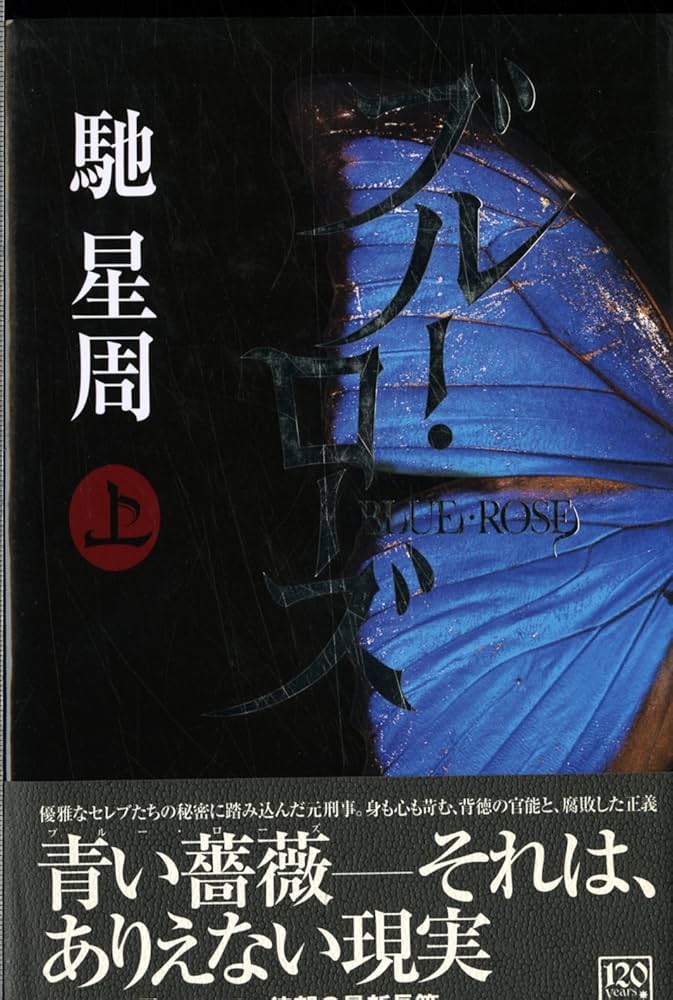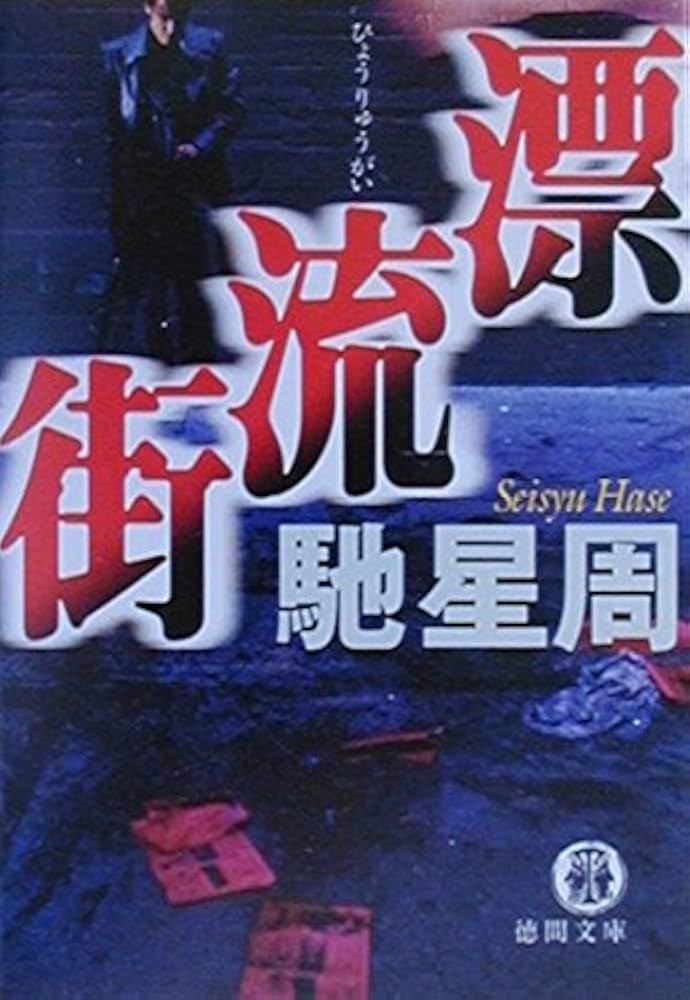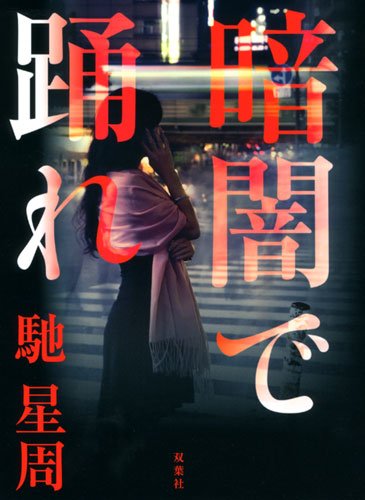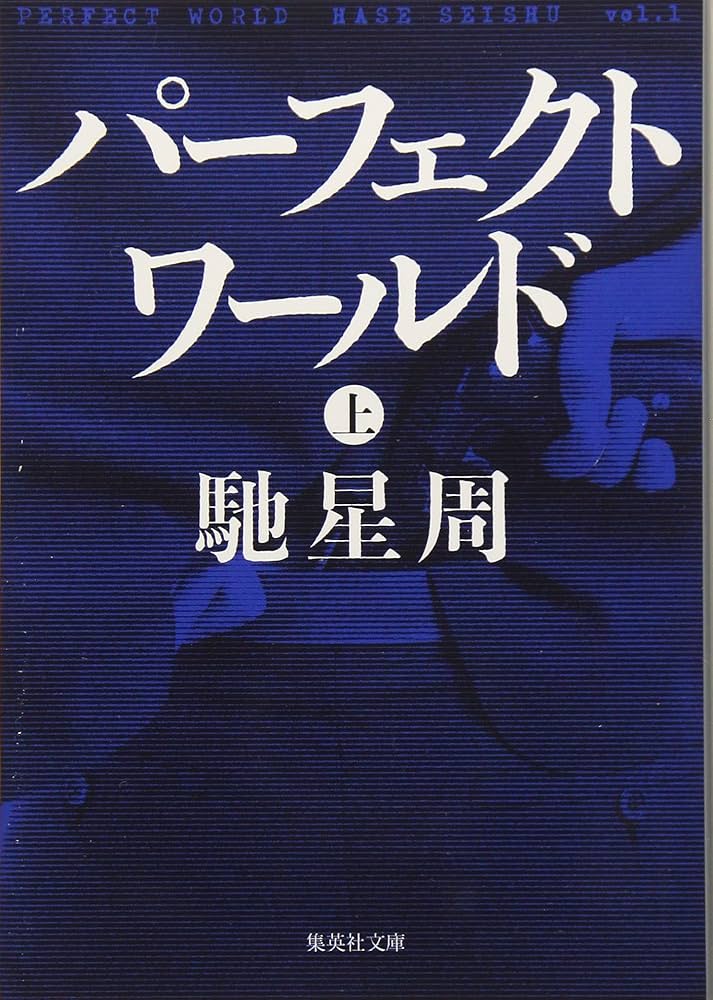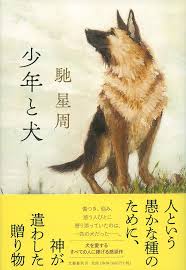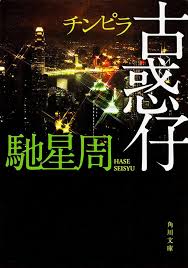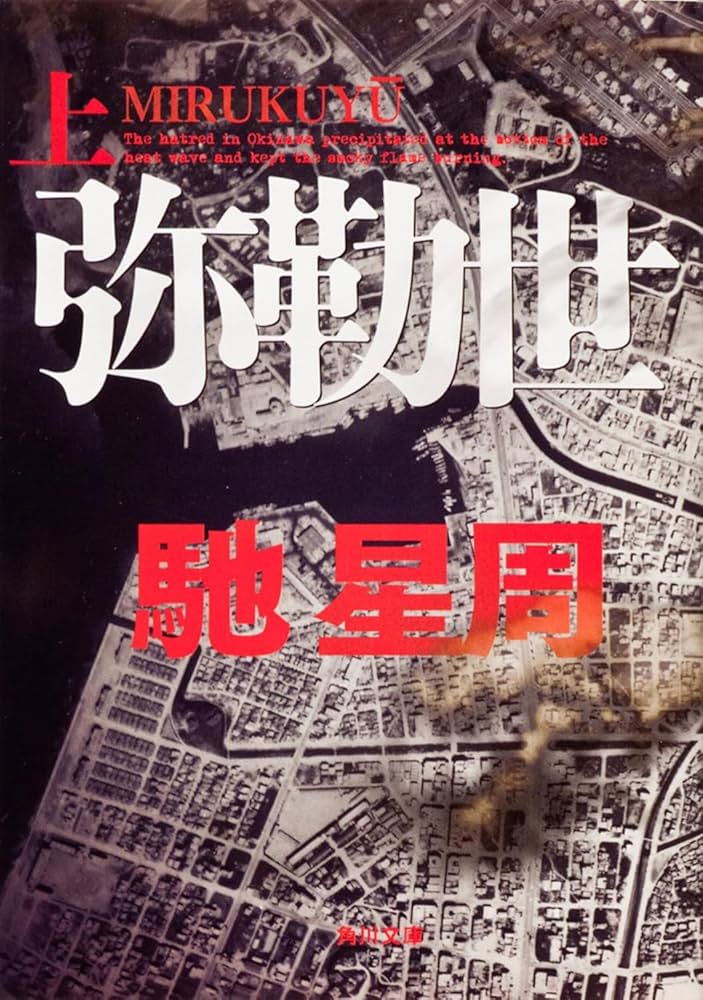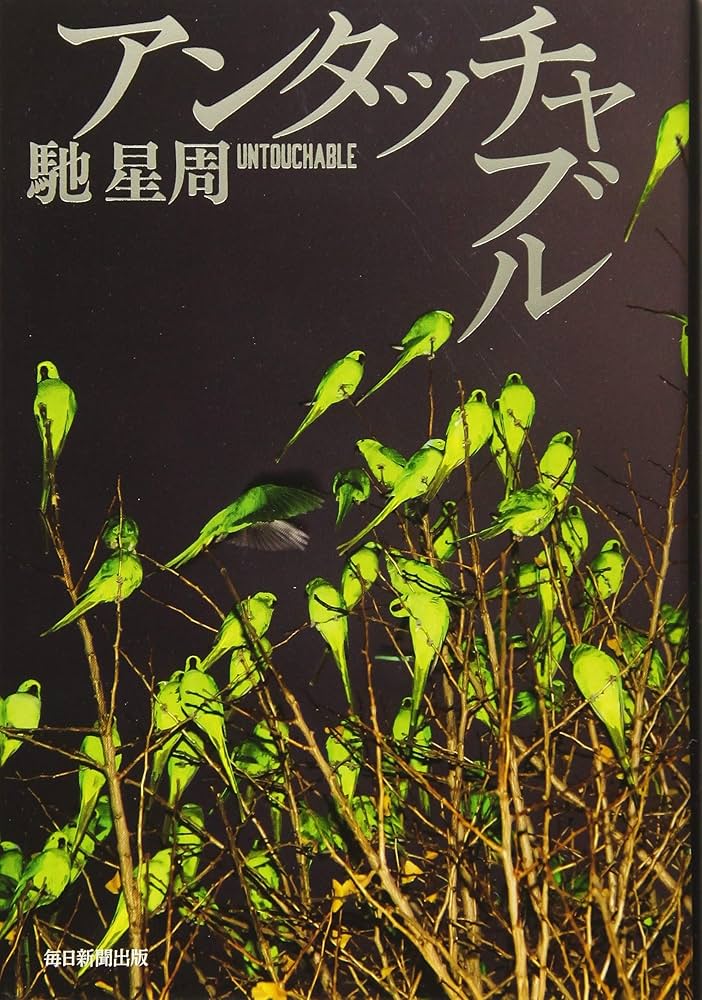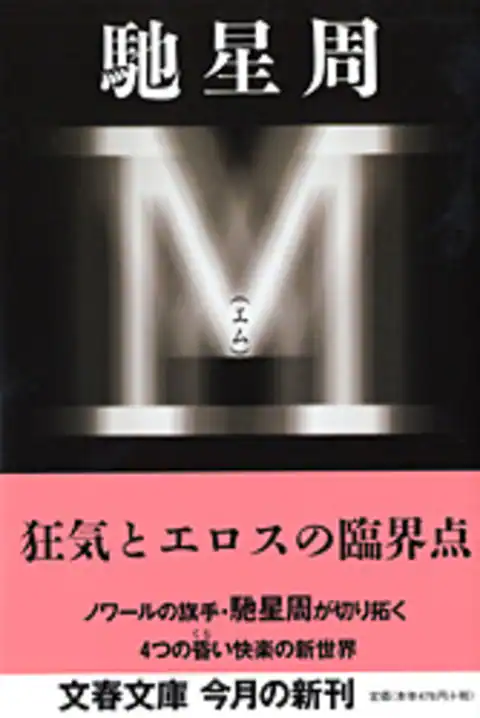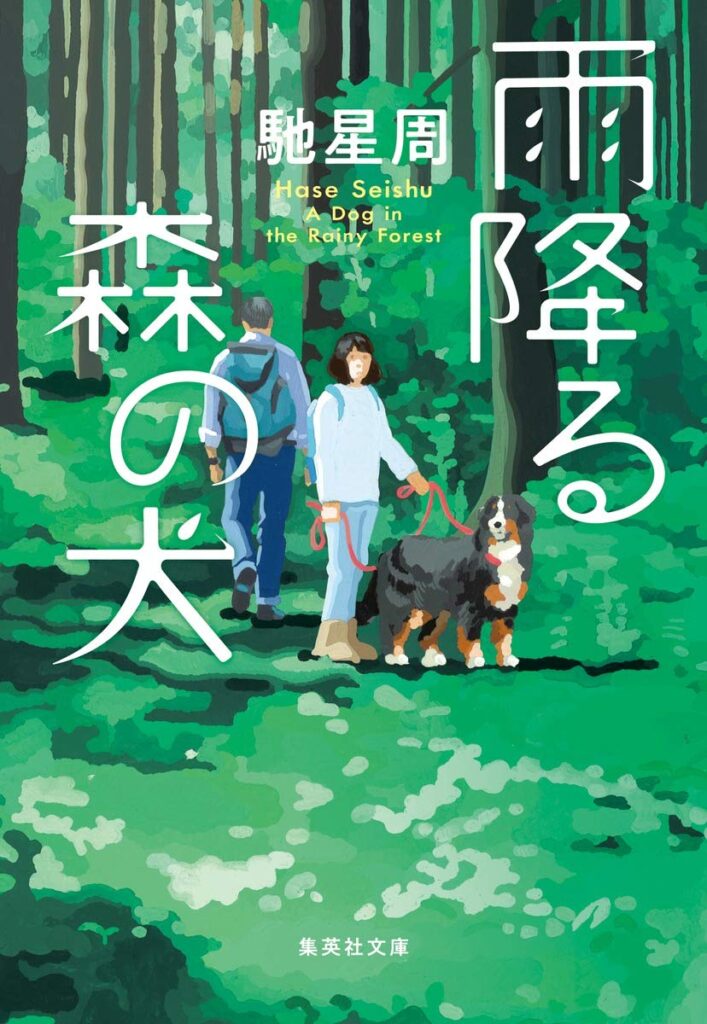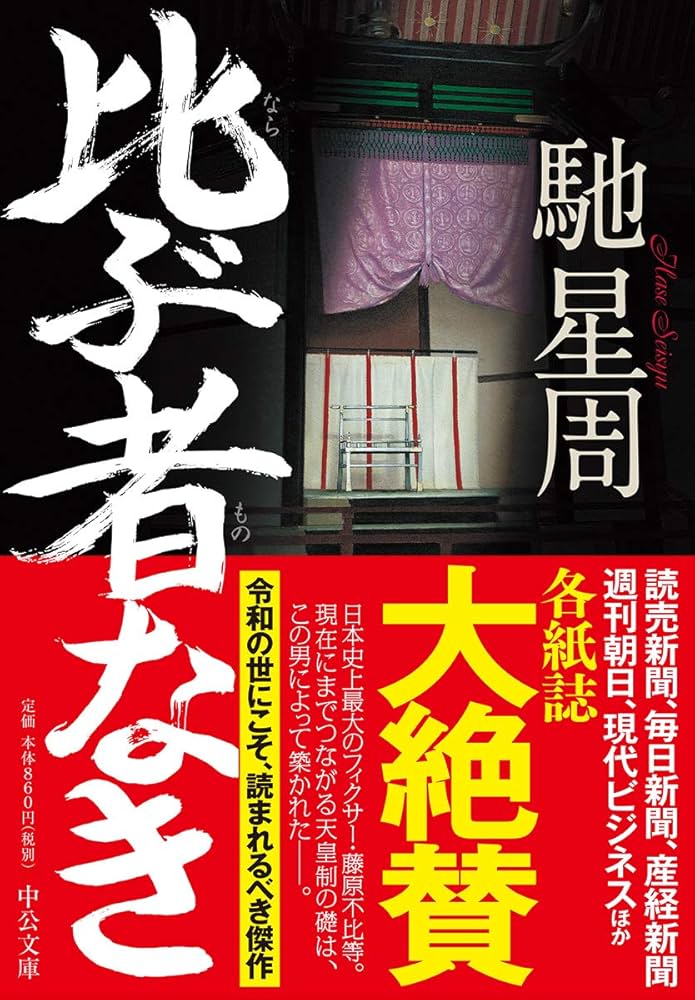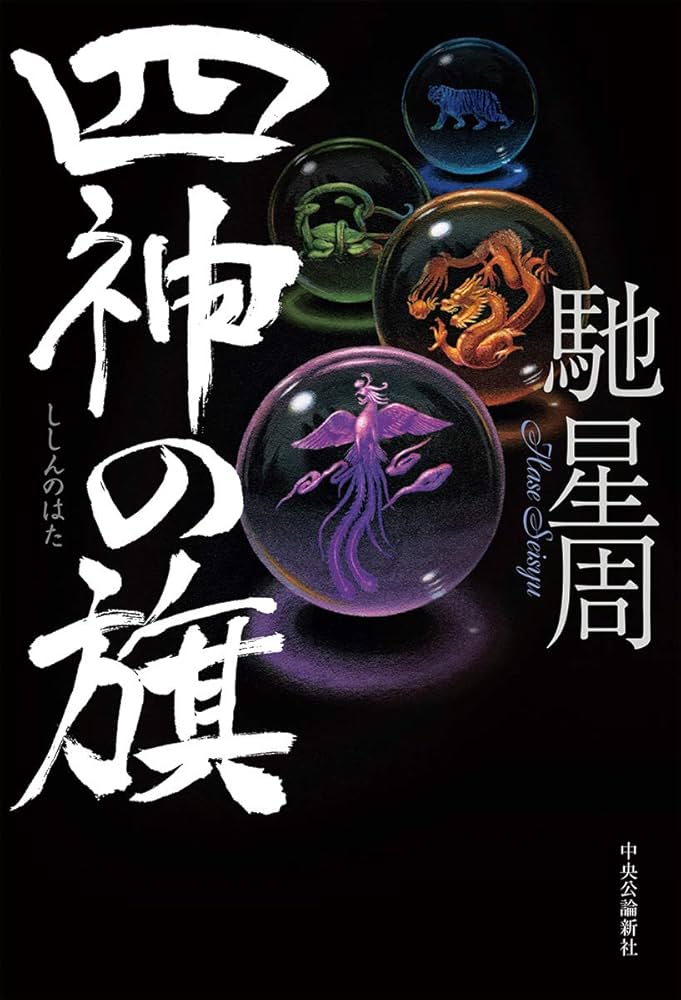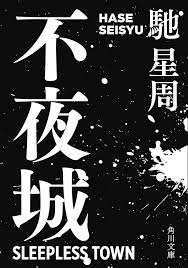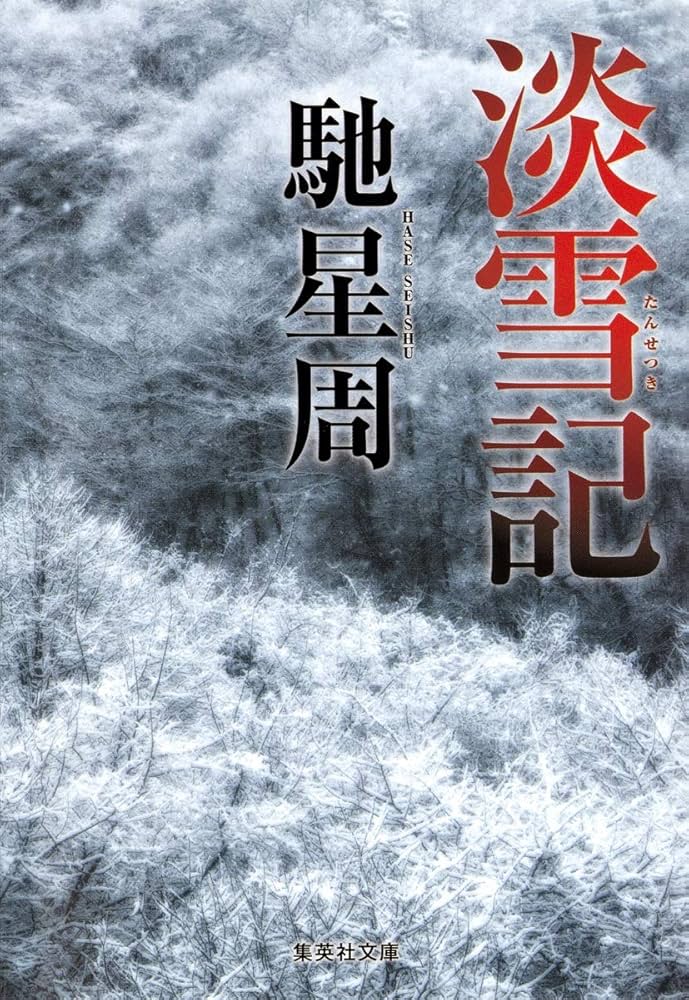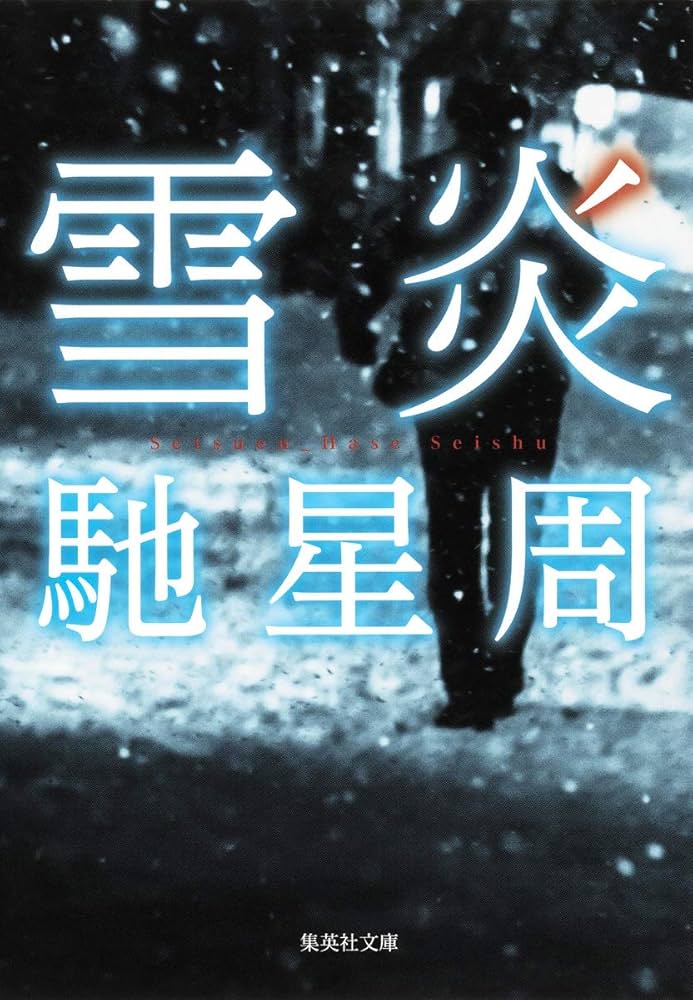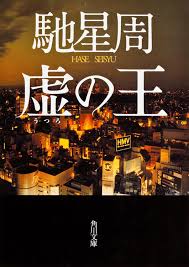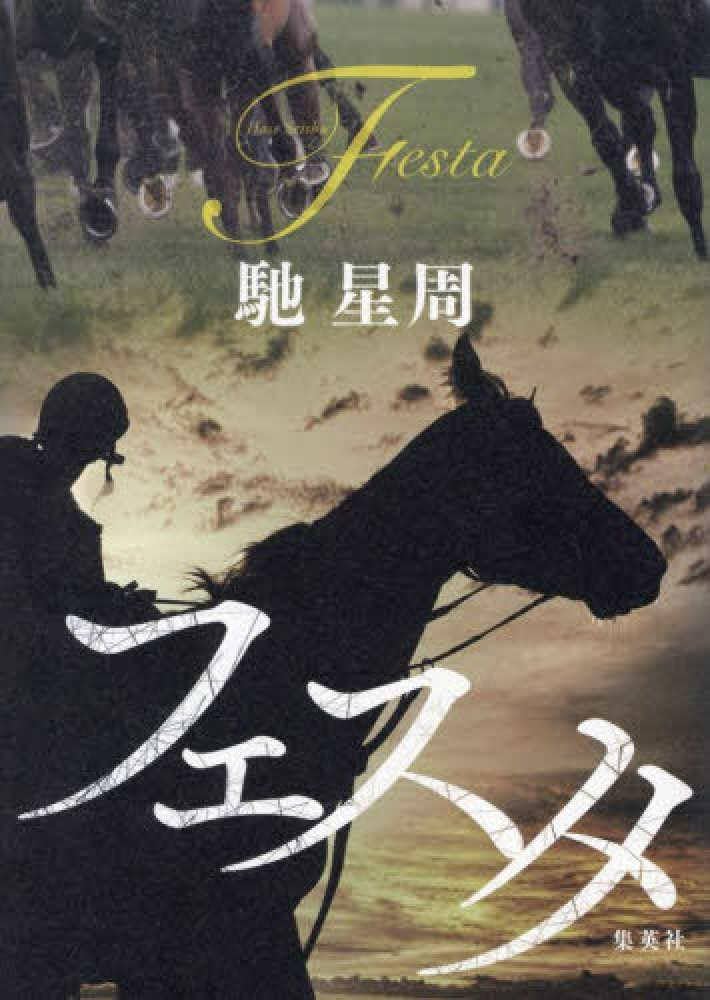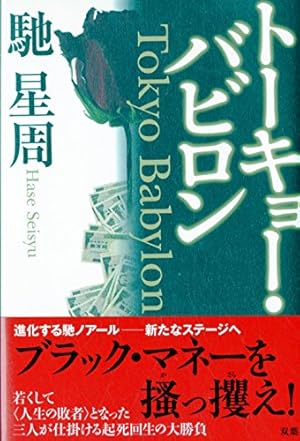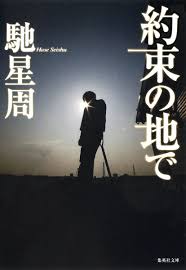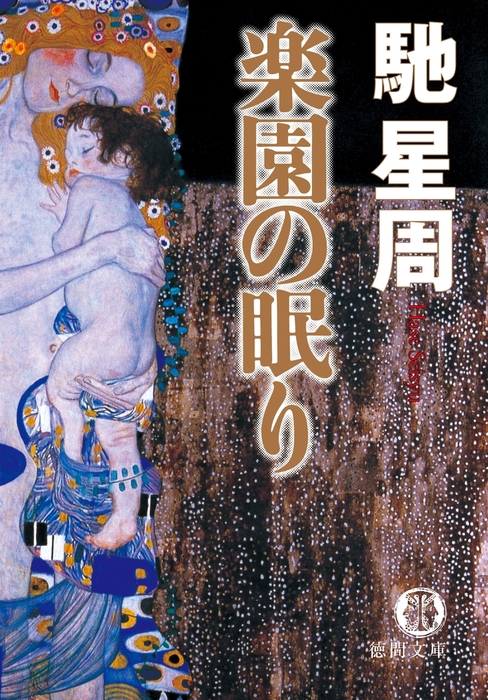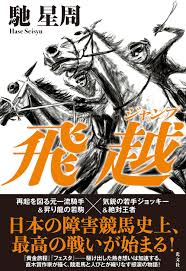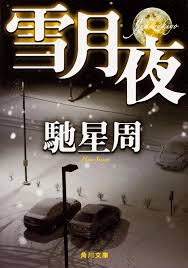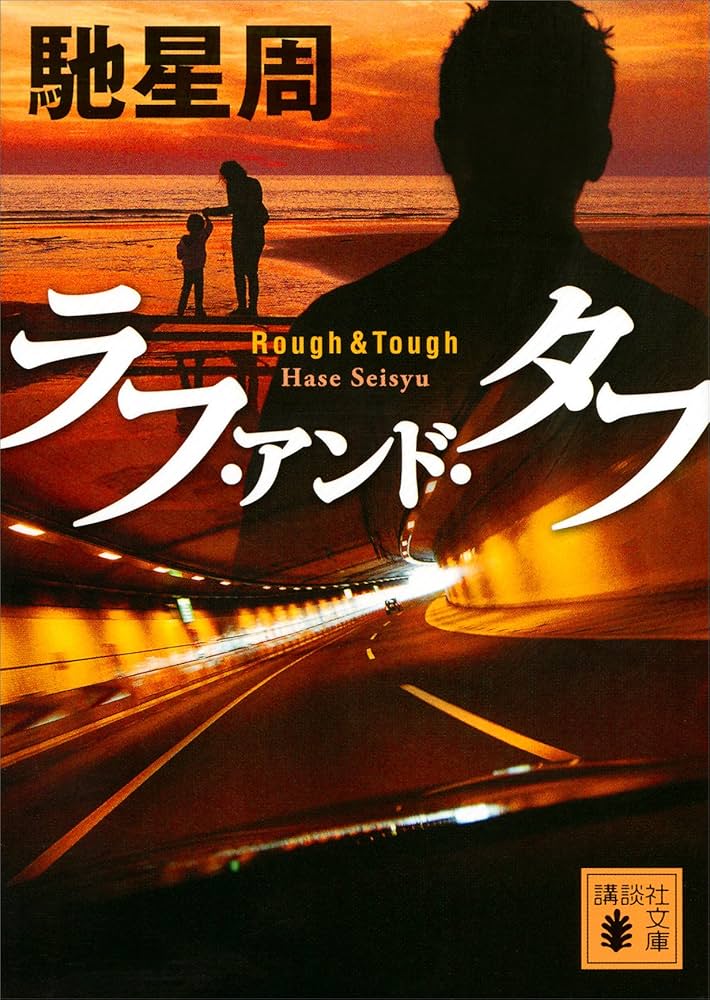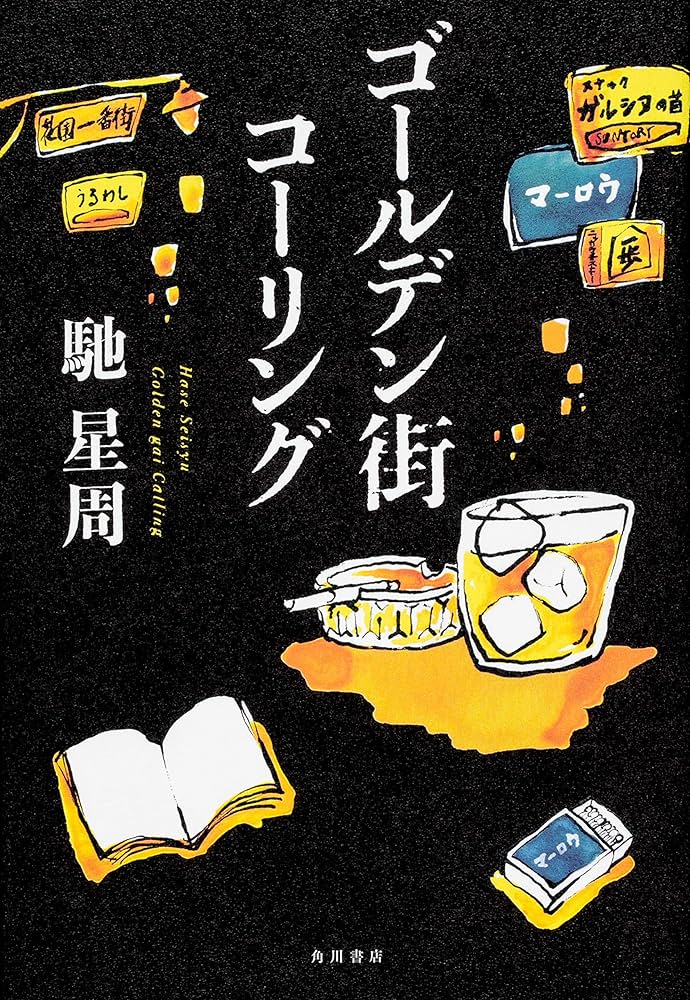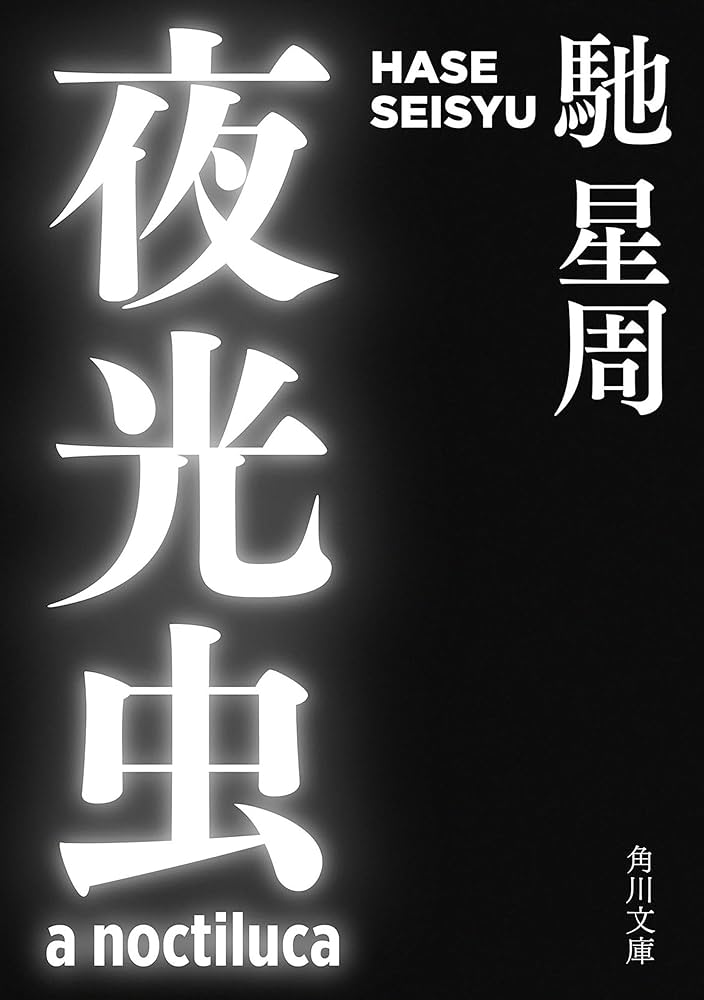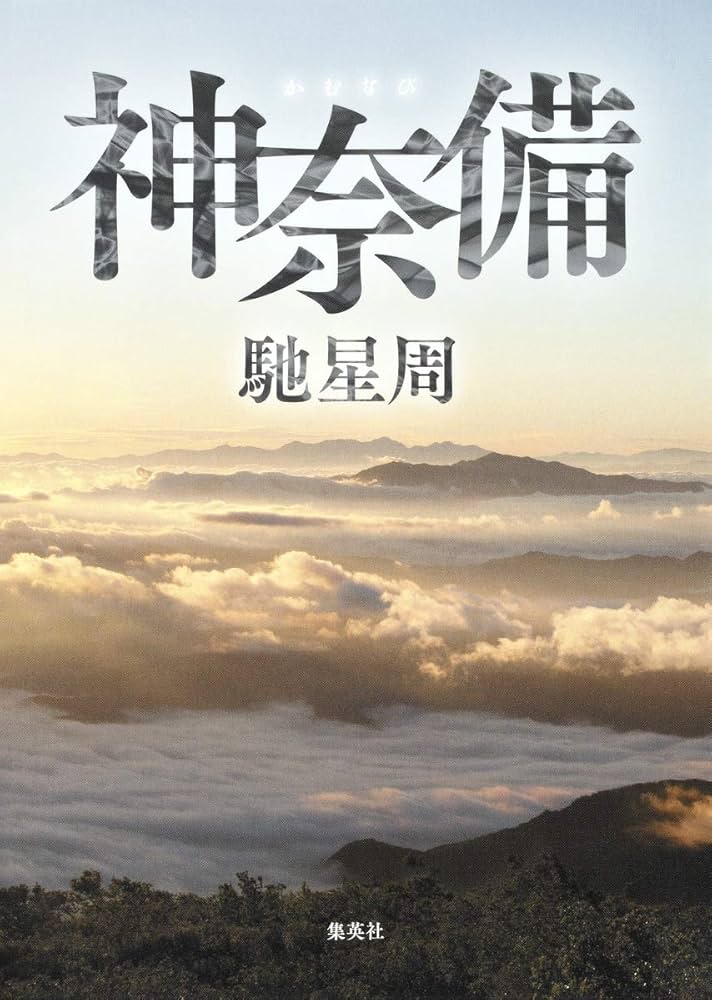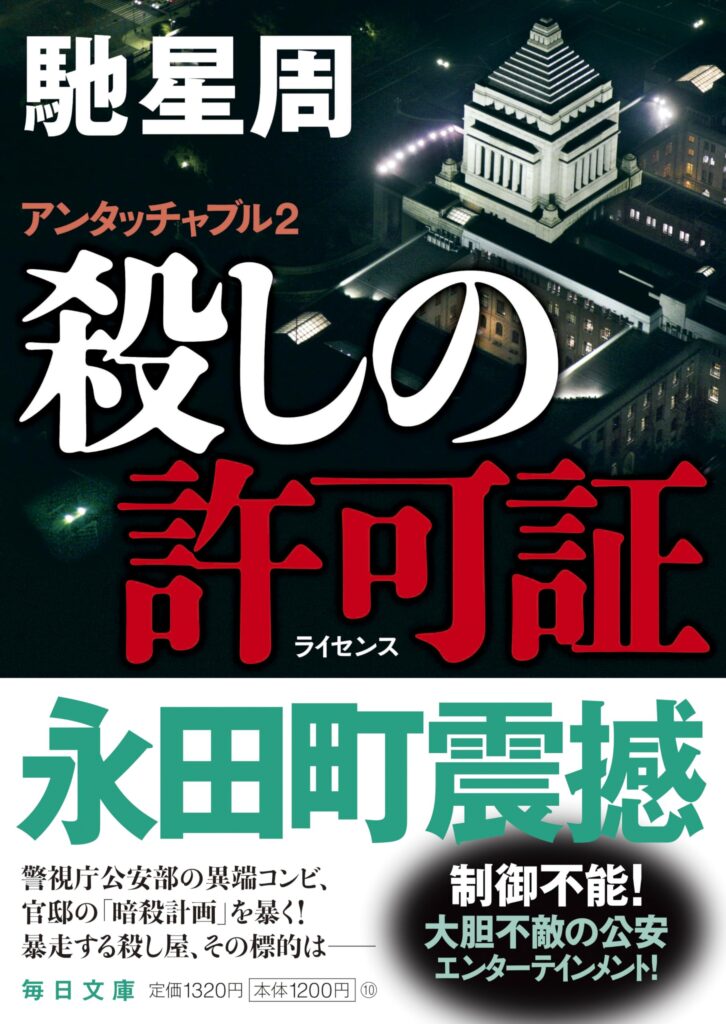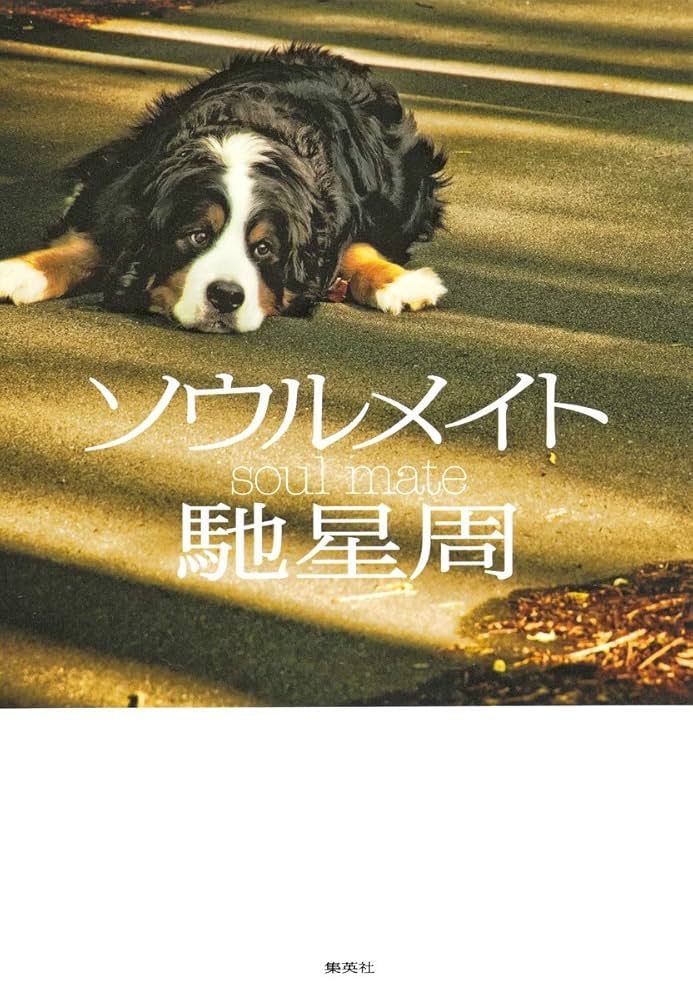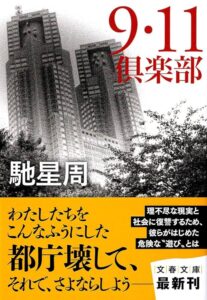 小説「9・11倶楽部」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「9・11倶楽部」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、単なる娯楽小説として片付けるには、あまりにも重く、鋭利な刃物のように読者の心に突き刺さります。テロによって家族を奪われた男が、社会から見捨てられた子供たちと出会い、やがて自らがテロリストへと変貌していく。その過程は、読む者の倫理観を激しく揺さぶり、正義とは何か、悪とは何かという根源的な問いを投げかけてきます。
馳星周さんという作家が描くノワール(暗黒小説)の世界は、常に救いがなく、登場人物たちは破滅へとひた走ります。しかし、その破滅の中に、奇妙な純粋さや切実な願いが見え隠れするからこそ、私たちは心を鷲掴みにされてしまうのかもしれません。この「9・11倶楽部」という作品も、その例外ではありません。
この記事では、物語の結末に触れる詳細な解説と、私の心を揺さぶった点についての長い語りを記しています。もし、あなたがこの物語の核心に触れる覚悟があるのなら、このまま読み進めていただけると嬉しいです。きっと、忘れられない読書体験の入り口になるはずですから。
「9・11倶楽部」のあらすじ
東京で救急救命士として働く織田は、かつて地下鉄サリン事件で最愛の妻と幼い息子を失った過去を持つ、心を閉ざした男です。彼の日常は、人の生死の境をさまよう現場と、空虚な私生活との往復でしかありませんでした。生きる意味を見失い、ただ職務だけをこなす日々。彼の心は、あの事件の日から時が止まったままだったのです。
そんなある日、織田は新宿の路上で倒れていた一人の少女、笑加(えみか)を救います。それが、彼の運命を大きく変える出会いとなりました。笑加を介して、織田はリーダー格の少年・明(あきら)をはじめとする、戸籍を持たず、親もなく、社会の片隅でひっそりと生きる子供たちの存在を知ることになります。
彼らは、行政の「浄化作戦」によって親たちを強制送還され、この国に取り残された子供たちでした。法からも社会からも見捨てられ、自分たちの力だけで生き抜いている彼らの姿に、織田は次第に心を動かされます。食料や医薬品を届け、彼らのささやかな暮らしを支えるうちに、織田は彼らの中に、失ったはずの「家族」の温もりを見出し始めるのでした。
しかし、その思いは純粋な庇護欲だけではありませんでした。子供たちを守りたいという切実な願いは、やがて社会そのものへの憎悪と結びつき、危険な狂気を帯びていきます。守るためには手段を選ばない。その歪んだ正義感が、織田と子供たちを、後戻りのできない破滅的な計画へと駆り立てていくことになるのです。
「9・11倶楽部」の長文感想(ネタバレあり)
この物語を読み終えた時、心にずっしりと重い塊が居座り、しばらく動くことができませんでした。それは不快な重さではなく、人間の悲しみや怒り、そして絶望の中から生まれる切実な愛の形に触れてしまったことによる、魂の震えのようなものだったと記憶しています。馳星周さんの作品は、いつも私たちに厳しい現実を突きつけますが、「9・11倶楽部」が突きつけてくるものは、その中でも特に鋭く、痛みを伴うものでした。
物語の主人公である織田は、テロの犠牲者です。地下鉄サリン事件という理不尽な暴力によって、彼は人生の全てであったはずの家族を奪われました。救急救命士という、命を救う仕事に就きながら、彼の心は救われることなく、巨大な喪失感を抱えたまま生きています。この設定が、まず物語全体に重苦しい影を落としています。彼の行動原理のすべては、この癒えることのない傷から始まっているのです。
そんな彼が、新宿の闇に生きる子供たちと出会います。彼らは、織田とは違う形の「暴力」の犠牲者でした。オウム真理教というカルト集団によるテロが「非合法な暴力」であるとするならば、子供たちの家族を奪ったのは、行政による「新宿浄化作戦」という「合法的な暴力」です。国家という巨大なシステムが、その正義の名の下に、いとも簡単に家族を引き裂き、子供たちを社会の枠外へと追いやった。この構図が、この物語の核心を突いています。
織田は、子供たちの境遇に自分のかつての絶望を重ね合わせます。テロによって孤児になった自分と、国家によって孤児にされた子供たち。彼は、両者を等価なものとして捉え始めるのです。この認識の変化こそが、彼を狂気へと駆り立てる最初の引き金でした。彼の中で、守るべき対象であったはずの「社会」や「国家」が、憎むべき「敵」へと姿を変えた瞬間です。
彼は子供たちに食料を与え、医薬品を届け、彼らのささやかなコミュニティを守ろうとします。一見すると、それは心優しい大人の善意に見えるかもしれません。しかし、彼の行動は次第に常軌を逸していきます。それはもはや「保護」ではなく、「支配」に近いものでした。彼は子供たちの中に、失った妻と息子の姿を幻視し、彼らを自分の所有物のように感じ始めます。この擬似家族は、彼の空っぽの心を埋めるための代替品でしかなかったのかもしれません。
この歪んだ愛情が、物語を破滅へと加速させます。子供たちがマフィアに絡まれた時、織田は法に訴えることをしません。彼にとって、警察もまた「国家」という敵の一部でしかないからです。彼は自らの手で、暴力をもって問題を解決しようとします。そして、ついに一線を越えてしまう。笑加の薬代を手に入れるため、間接的に人を殺めるという罪を犯すのです。この時、命を救うはずの救急救命士は、命を奪うことを厭わない復讐者へと完全に変貌を遂げました。
そして、物語は決定的な転換点を迎えます。織田の狂信的な思想と、ストリートで生き抜いてきた明の実践的な知恵が結びつき、反撃のための組織「9・11倶楽部」が結成されるのです。このネーミングセンスには、戦慄を覚えました。アメリカ同時多発テロ事件。それは、国家の権力や経済の象徴に対する未曾有の攻撃でした。彼らは、自分たちの個人的な復讐を、その世界史的なテロ行為に重ね合わせることで、国家に対する「戦争」なのだと宣言したのです。
彼らの標的は、自分たちを追い詰めた元凶、東京都庁。織田は救急救命士としての専門知識を駆使して建物の脆弱性を分析し、爆弾の材料を調達します。一方、明をはじめとする子供たちは、その「見えない存在」であることを武器に、都庁内部へと潜入していく。大人は子供に気づかず、子供は大人を意に介さない。都会の雑踏が生み出すその断絶を、彼らは最強のステルス機能として利用するのです。この計画の緻密さと、その裏にある子供じみた万能感の入り混じった描写は、息を飲むほどの迫力でした。
物語の終盤、計画が実行に移される場面では、登場人物たちの役割が完全に入れ替わります。感情の波に乗り、破滅的な高揚感に浸る織田は、まるで癇癪を起こした子供のようです。対照的に、リーダーの明はどこまでも冷静に状況を判断し、仲間たちの安全を確保しようと努めます。過酷な現実が、子供を大人にし、守られるべきだった大人が、最も制御不能な子供へと退行してしまった。この倒錯した関係性が、悲劇性を一層際立たせていました。
クライマックス、都庁で爆弾が炸裂します。彼らの「戦争」は、一つの結果を出しました。国家の象徴は傷つき、彼らの声なき声は、爆音となって東京中に響き渡ったのです。しかし、それは何かの始まりではありませんでした。それは、すべての終わりを意味していたのです。
織田は、逃げることを選びませんでした。彼は燃え盛る摩天楼を見上げながら、当局に捕らえられます。その表情には、絶望ではなく、ある種の達成感すら浮かんでいたように描かれています。彼は涙を流しますが、それは後悔の涙ではない。失った家族、そして守ろうとした新しい家族のために、自分はやるべきことをやったのだという、独善的で、しかしあまりにも純粋な満足感からの涙だったのではないでしょうか。彼は、自らの破滅と引き換えに、彼だけの「救済」を手に入れたのです。
一方、子供たちはどうなったのか。彼らは計画通り、混乱に乗じて都会の闇へと再び姿を消します。彼らは生き延びました。しかし、彼らの前には、無国籍の孤児という絶望的な現実が、依然として横たわっているだけです。彼らの復讐は、何も解決しませんでした。ただ、自分たちの存在を巨大な暴力として刻みつけただけ。その後に残るのは、瓦礫と、埋めようのない孤独だけです。この救いのない結末こそが、馳星周さんの描く世界の真骨頂なのでしょう。
この物語は、私たちに問いかけます。正義とは一体何なのか。法や社会が救いの手を差し伸べない時、人は何を頼りに生きればいいのか。そして、暴力の連鎖は、どこで断ち切ることができるのか。織田はテロの犠牲者でありながら、テロの加害者になりました。彼の動機は、歪んではいるものの、根底には「愛」がありました。では、彼の行為は断罪されるべき「悪」でしかないのでしょうか。
私は、この問いに簡単な答えを出すことができません。ただ、この物語が描いたのは、社会の光が当たらない場所で、声もなく死んでいく人々がいるという紛れもない事実です。そして、その声なき声が、怒りや憎しみと結びついた時、それは世界を揺るがすほどの破壊的な力を持つことがあるという、冷徹な現実です。「9・11倶楽部」は、その現実を、一切の感傷を排して描いた、痛切な警告の書なのだと感じます。
読後、心に残るのは、どうしようもない哀しみです。織田の狂気も、子供たちのしたたかさも、すべてが哀しい。彼らが求めたのは、おそらく大それたことではなかったはずです。ただ、人として当たり前に生きること。愛する家族と穏やかに暮らすこと。そのささやかな願いが踏みにじられた時、人は鬼にもなれてしまう。この物語は、その人間のどうしようもない業を、まざまざと見せつけてくれました。忘れがたい、魂を揺さぶる一冊です。
まとめ
小説「9・11倶楽部」は、テロによって家族を失った男が、社会に見捨てられた子供たちと出会い、国家への復讐を企てるという衝撃的な物語です。その根底にあるのは、暴力の連鎖という重いテーマと、歪んだ形でありながらも切実な「家族」への渇望でした。
主人公・織田の行動は、決して許されるものではありません。しかし、彼をそこまで追い詰めた社会の非情さや矛盾を目の当たりにすると、彼を単純な悪人として断罪することをためらってしまいます。この物語は、読者の倫理観を激しく揺さぶり、簡単な答えを与えてはくれません。
馳星周さんならではの、一切の救いがない冷徹な筆致で描かれる破滅への道筋は、読む者に深い哀しみと、どうしようもない現実の重さを突きつけます。エンターテインメントとして消費するにはあまりにも痛みを伴いますが、だからこそ、心に深く刻まれる作品だと言えるでしょう。
読了後に残るのは、爽快感ではなく、重い問いかけです。しかし、その問いと向き合うことこそが、この物語を読むということの本当の意味なのかもしれません。人間の心の深淵を覗き込むような、強烈な読書体験を求める方に、ぜひ手にとっていただきたい一冊です。