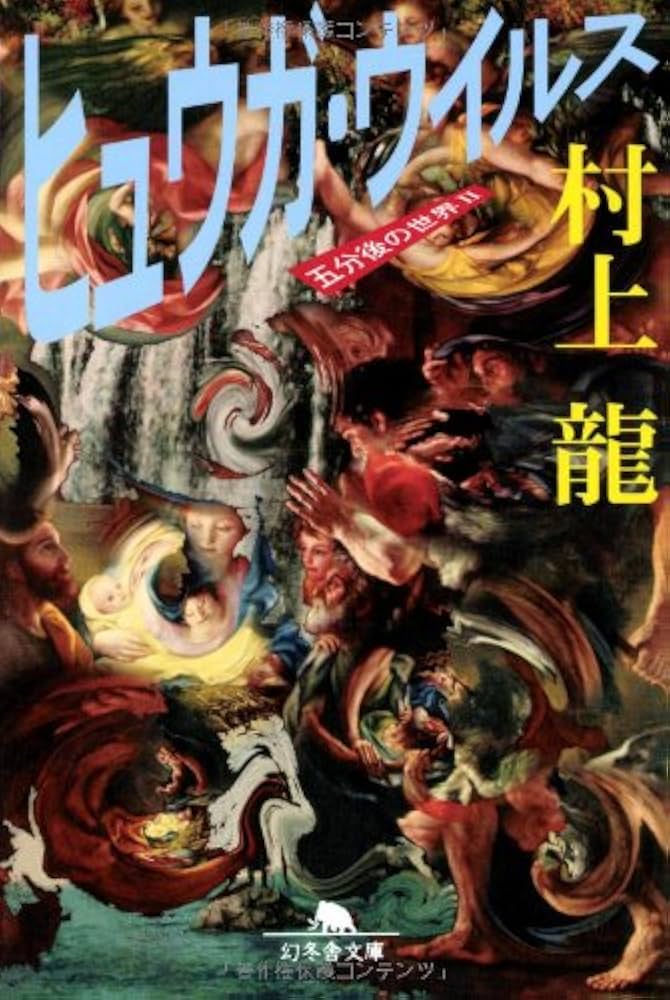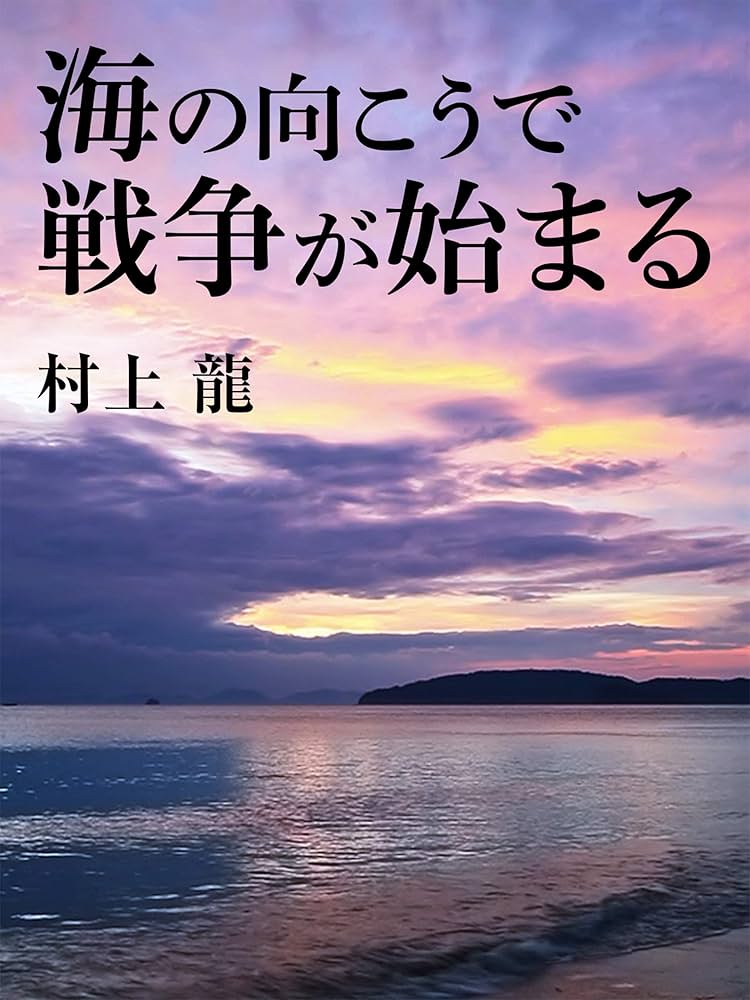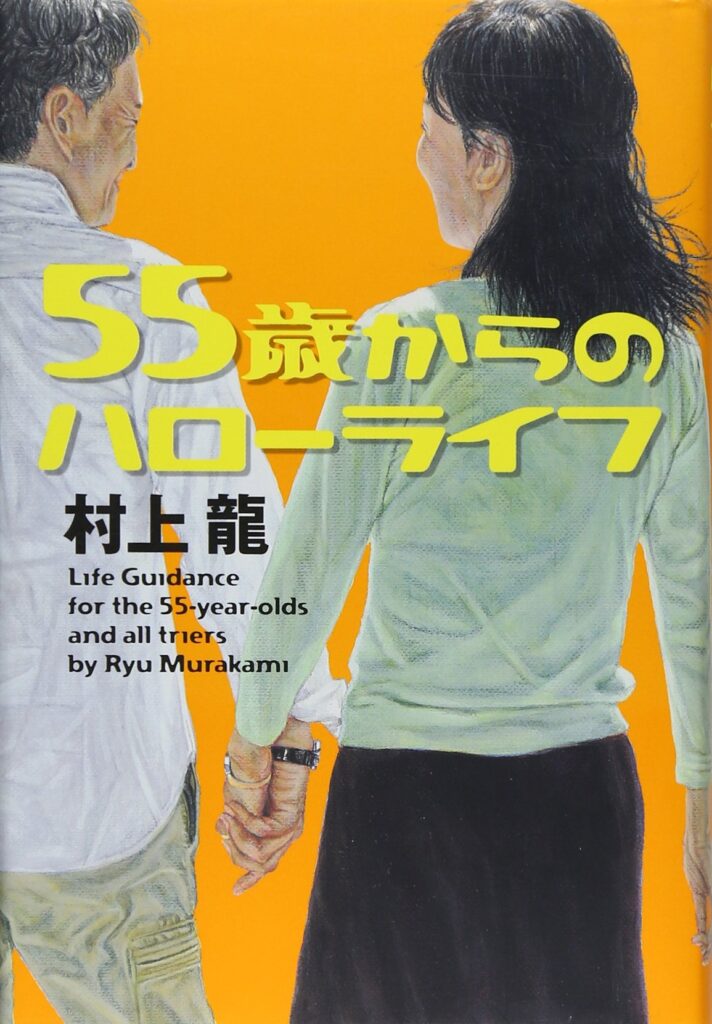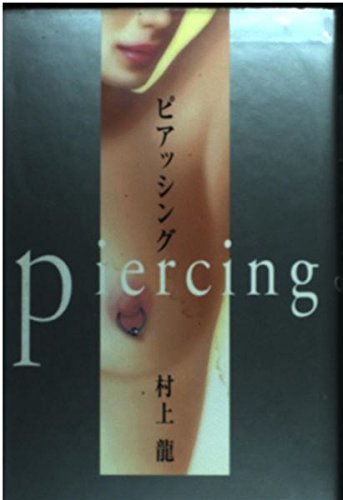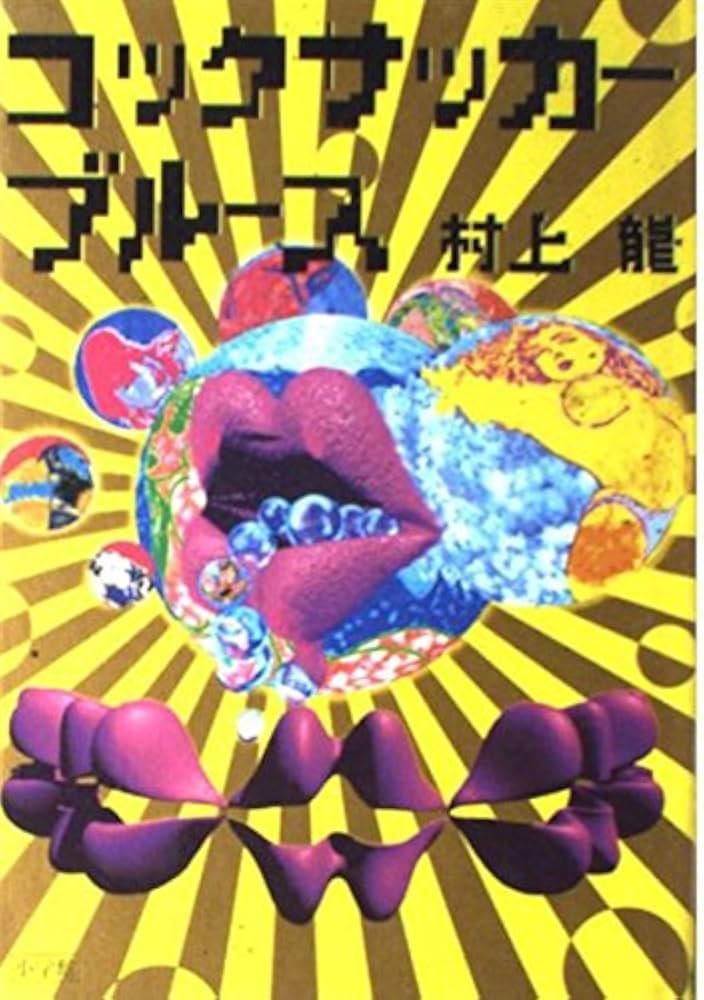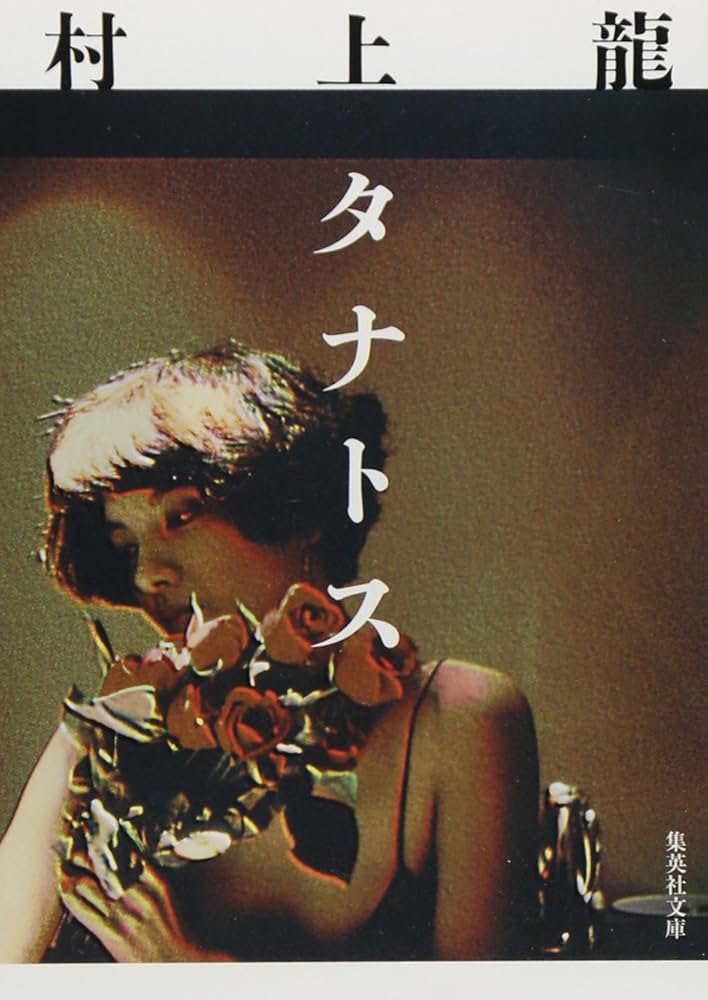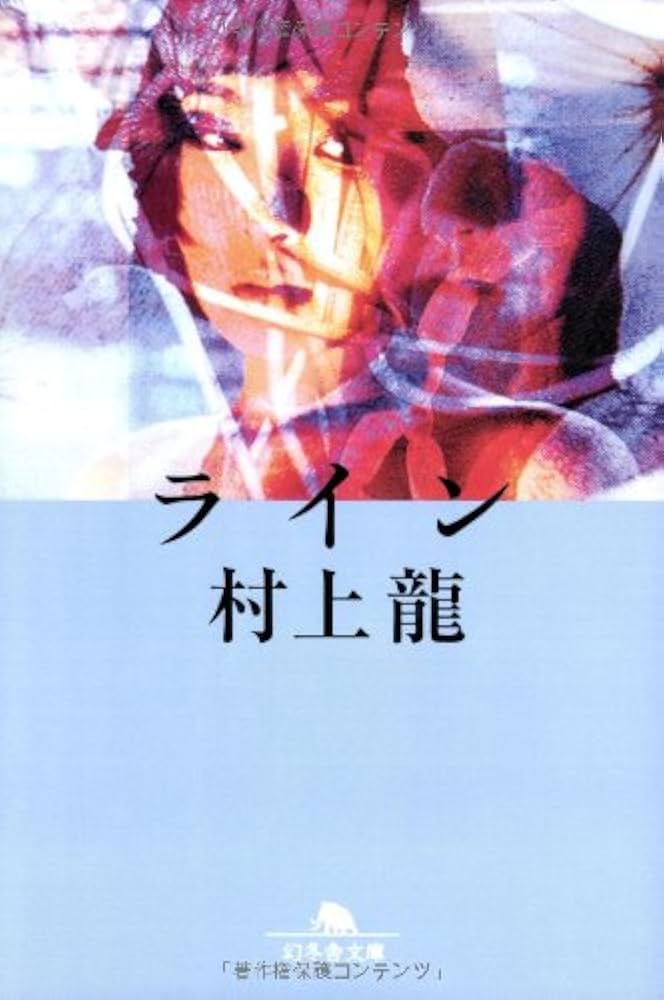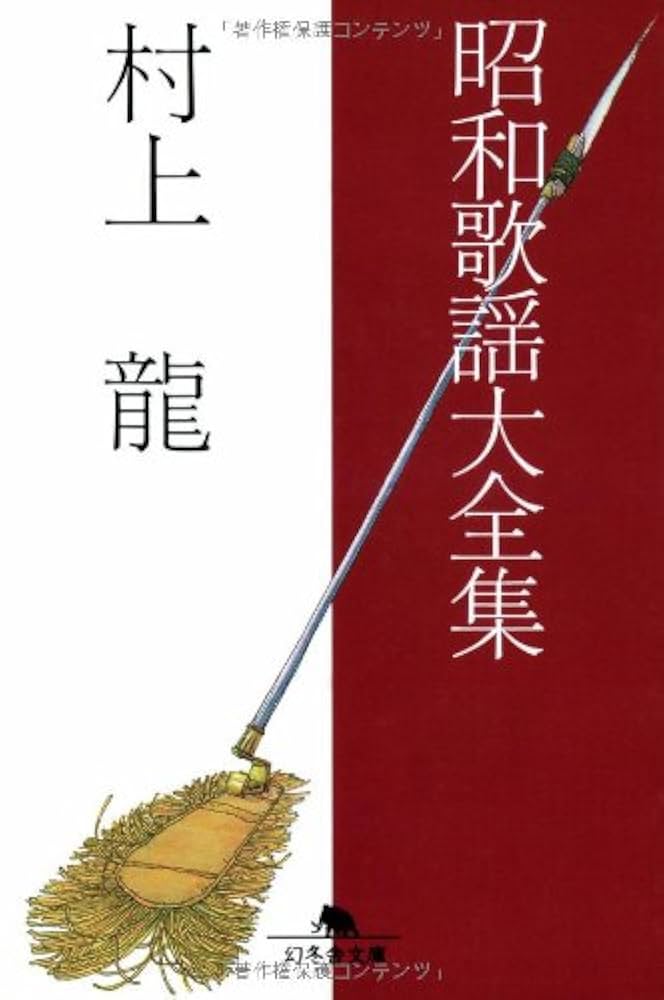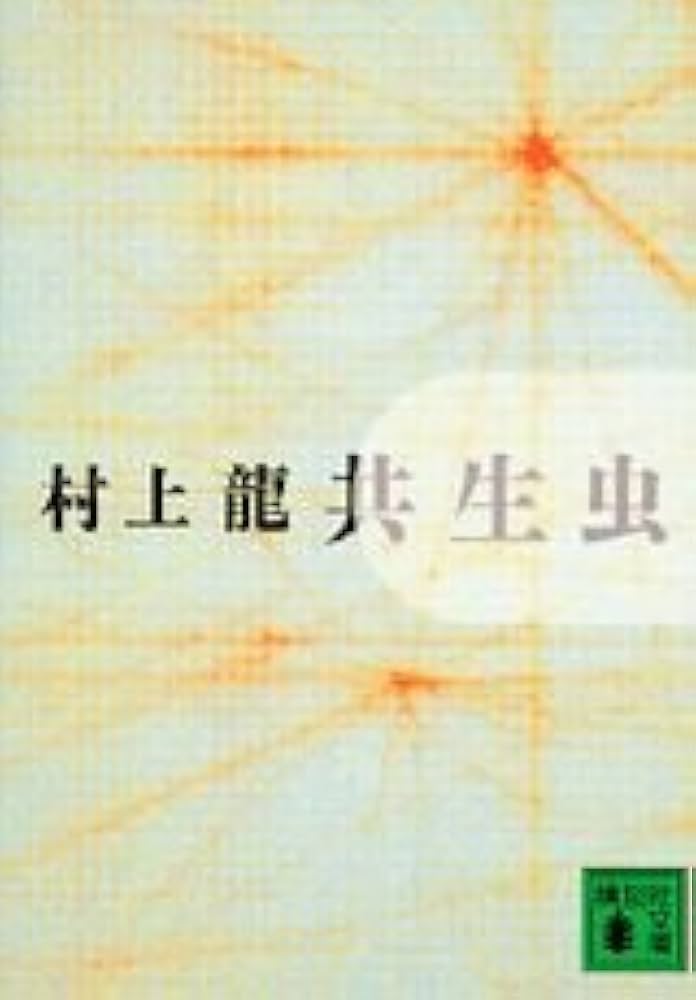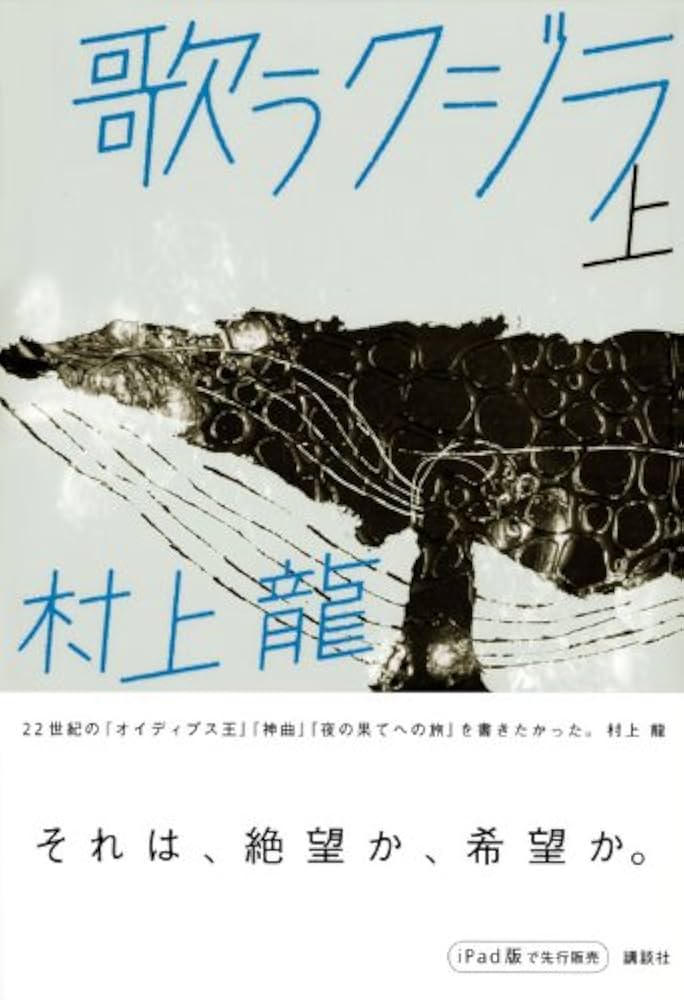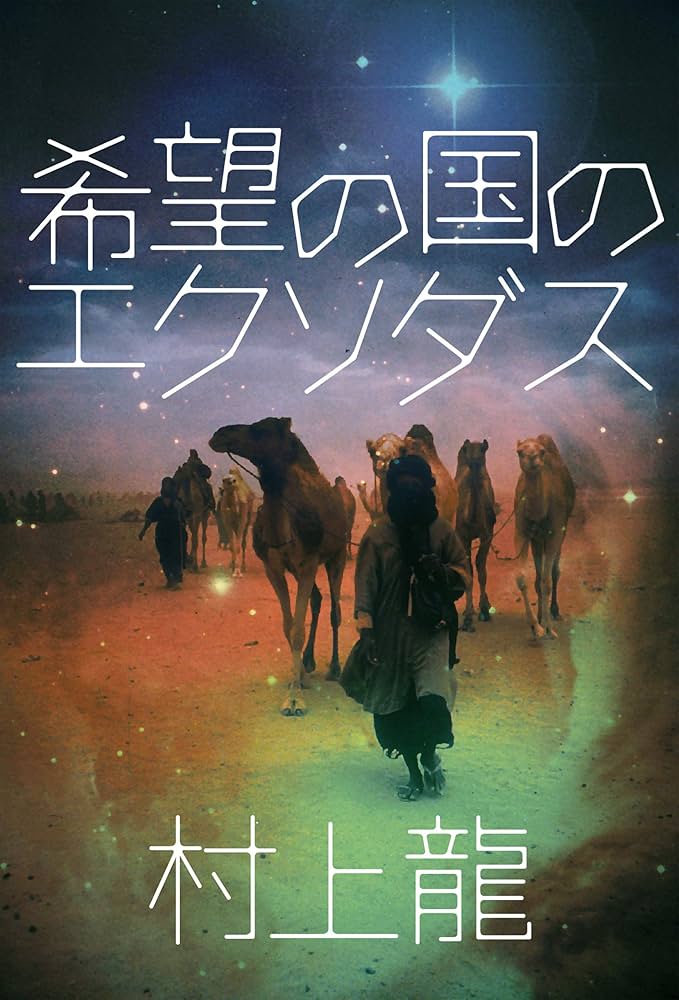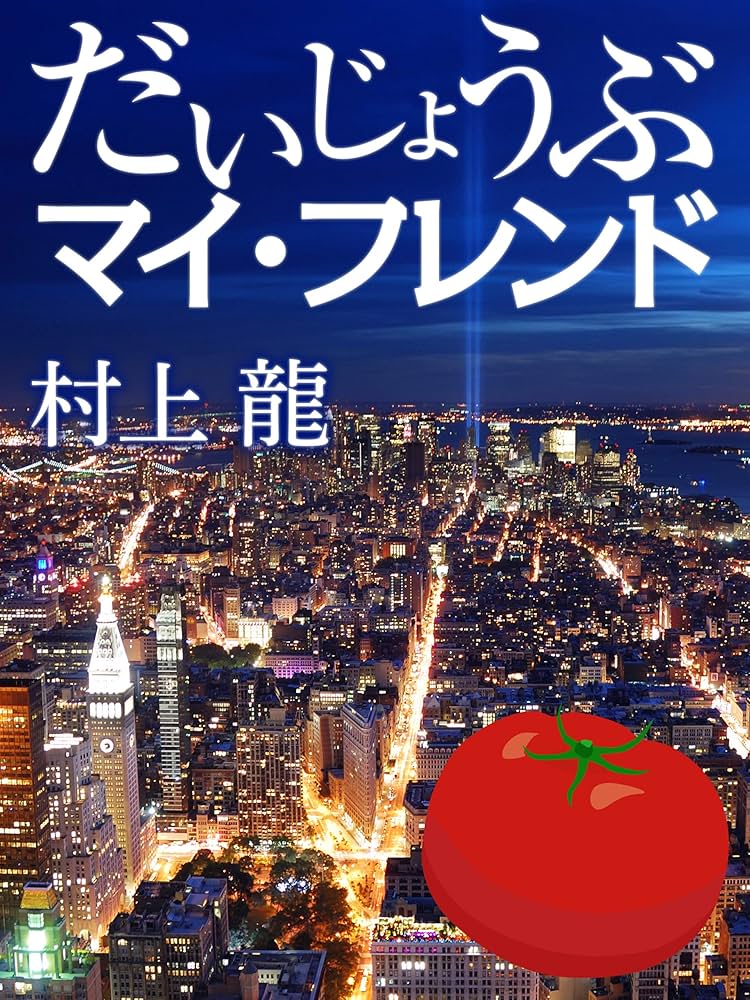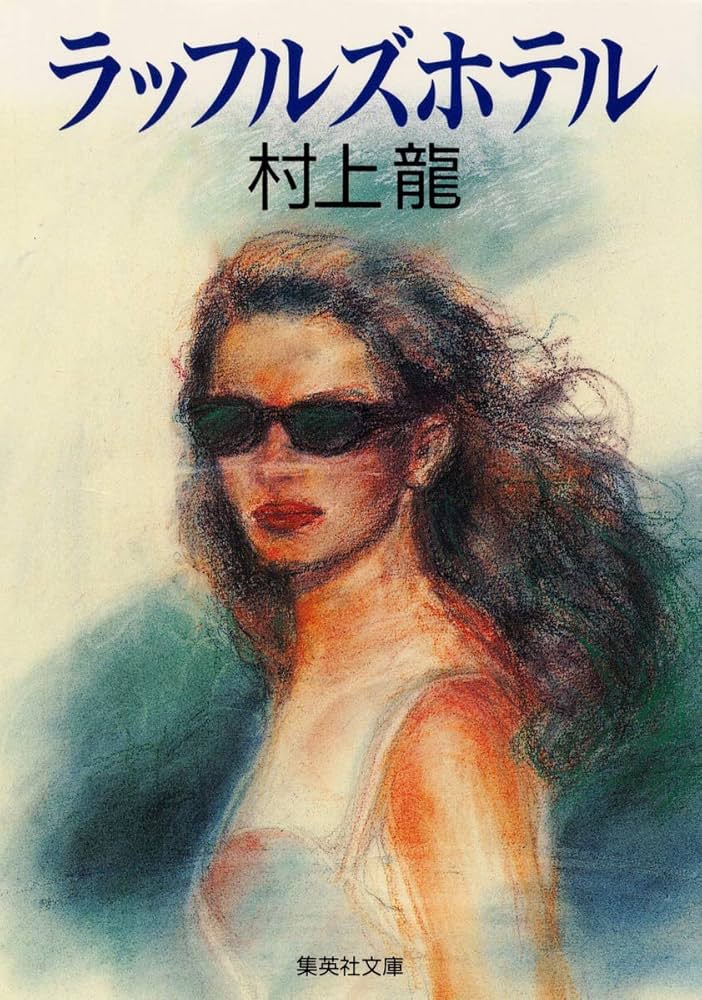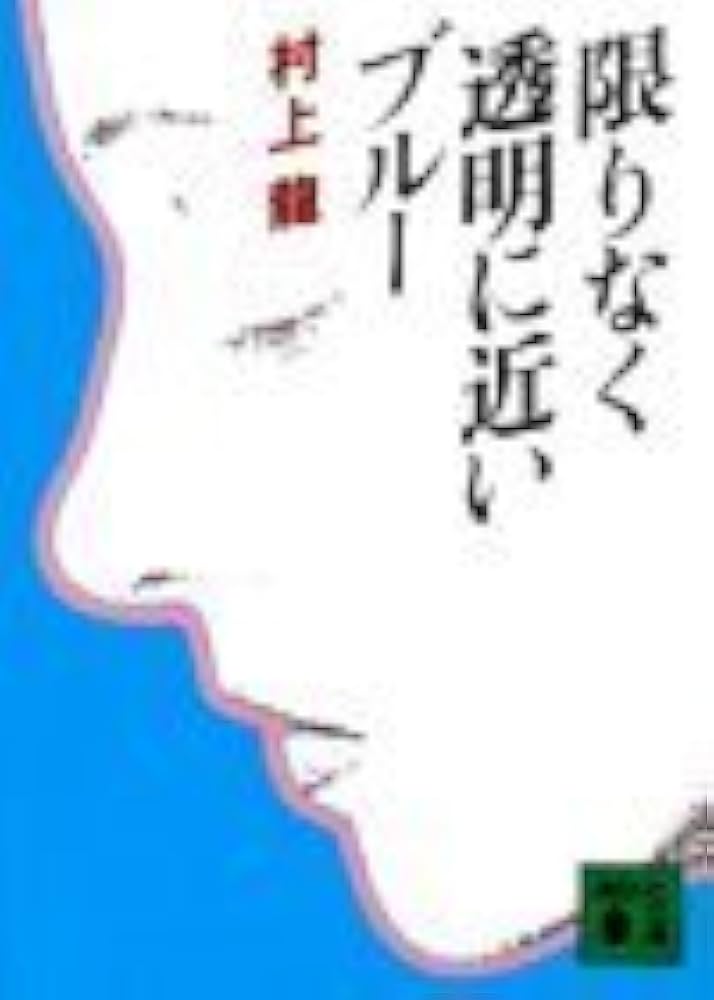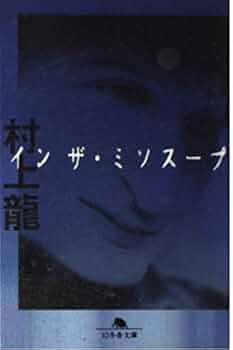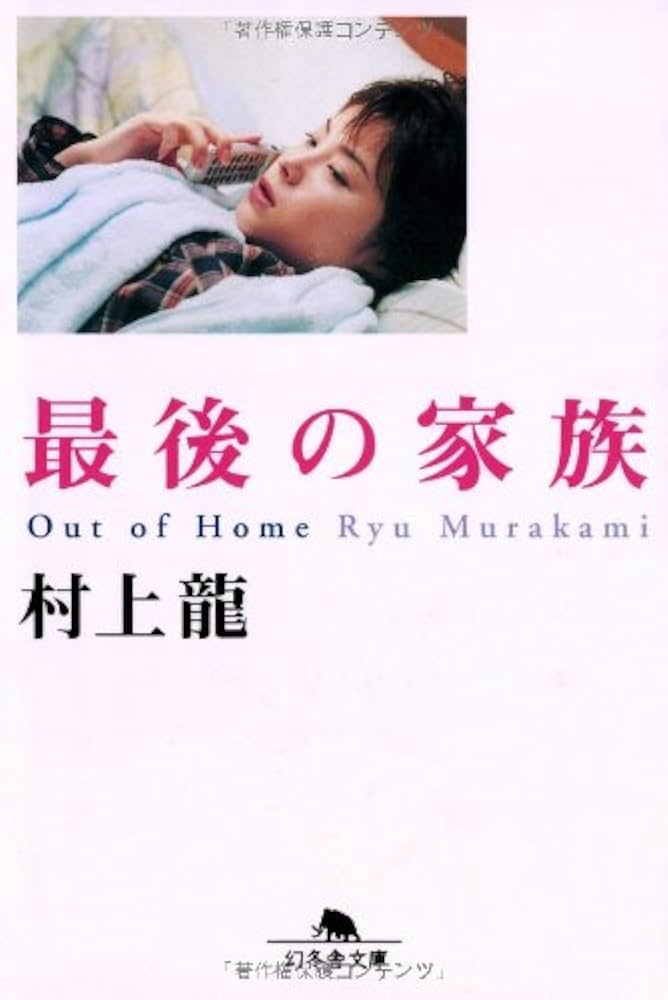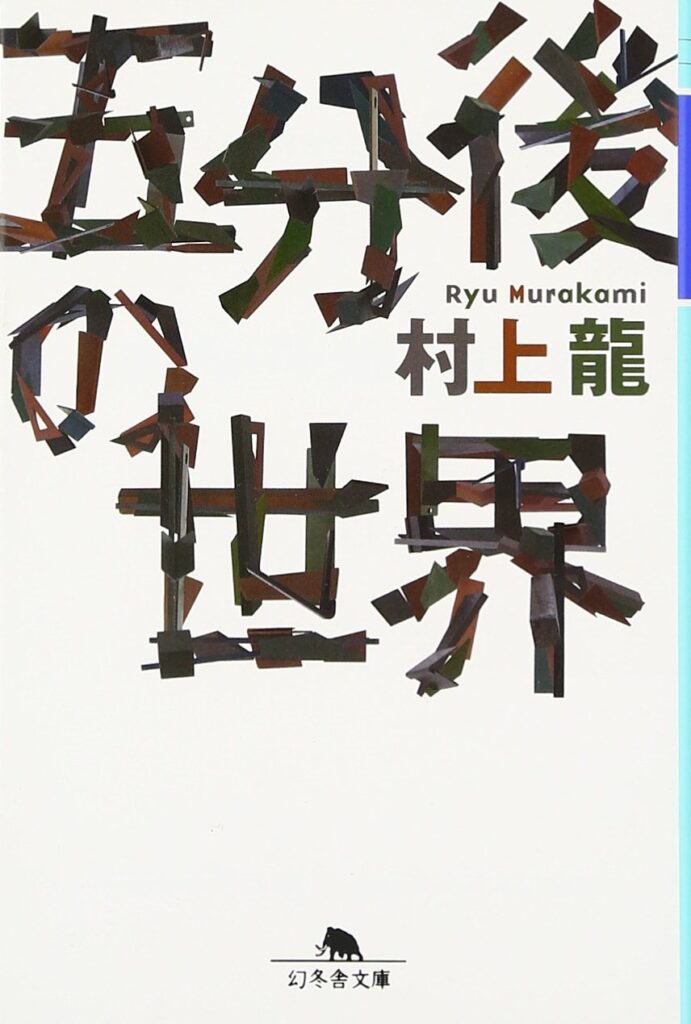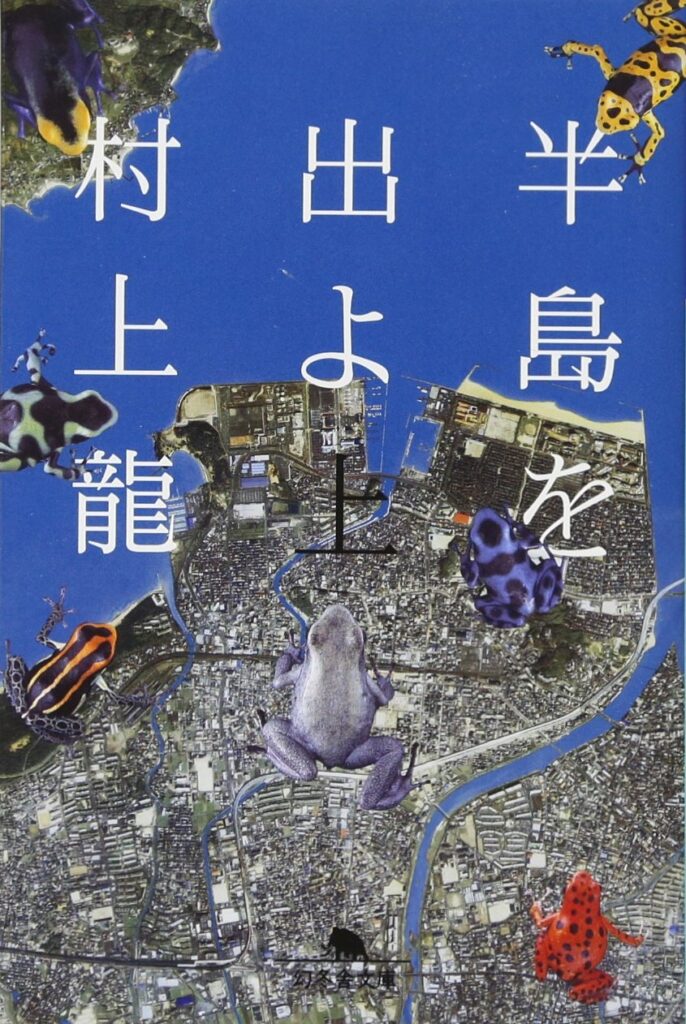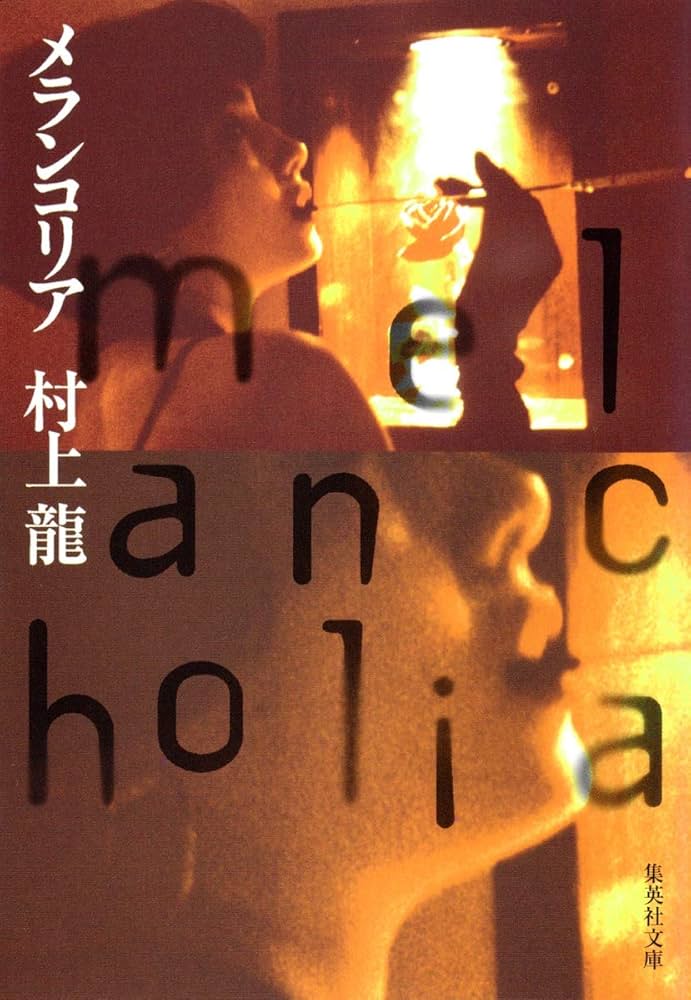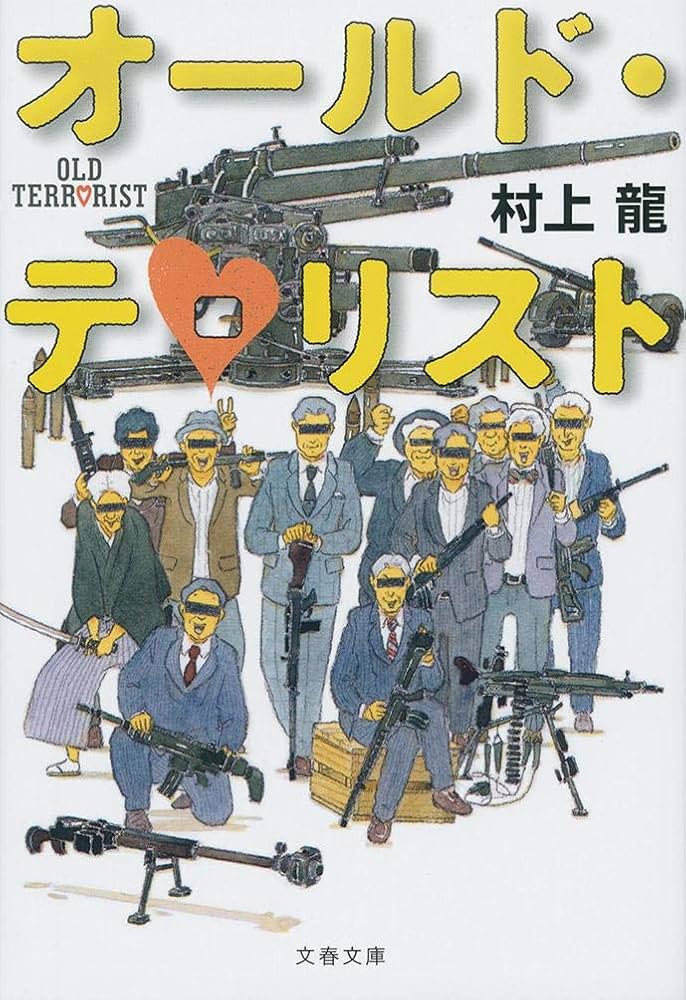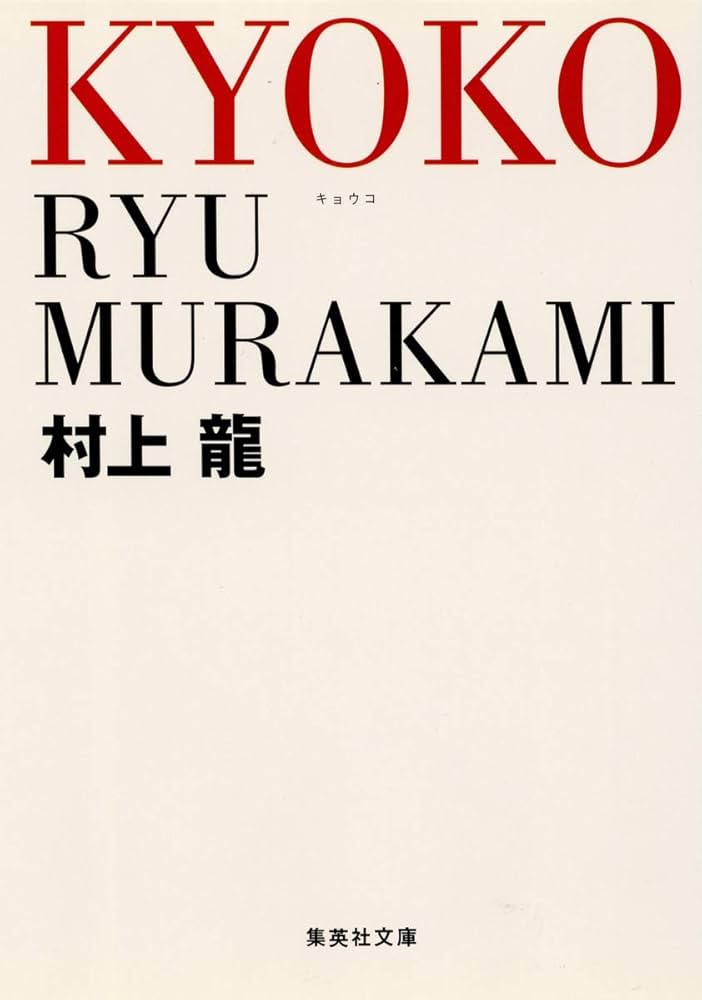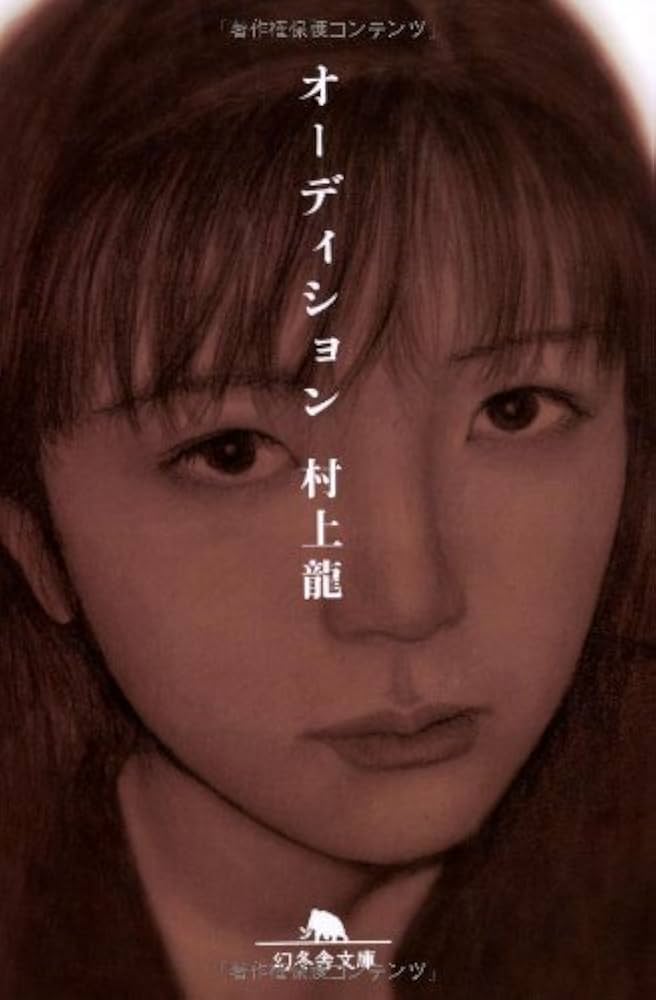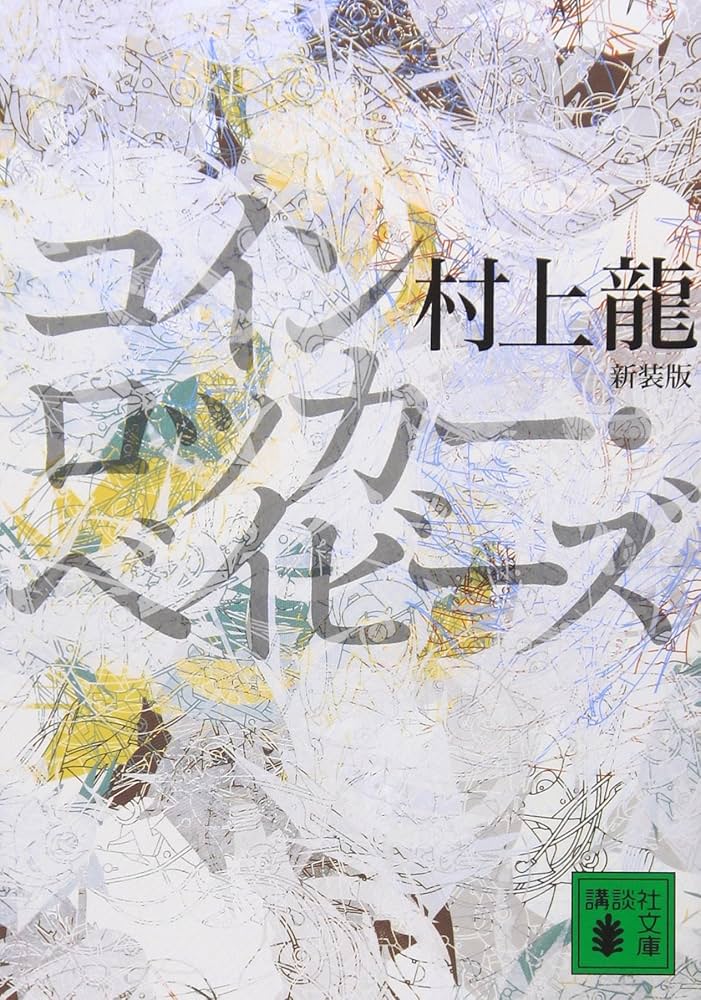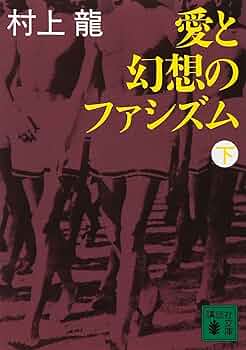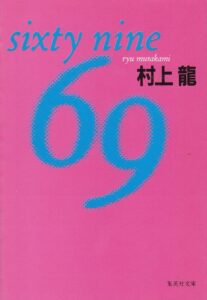 小説「69」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「69」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
1984年のケン、本名・矢崎剣介が、まだ17歳だった1969年を振り返るかたちで、この物語は進んでいきます。ただの懐かしい思い出話ではありません。大人の視点から、若かった自分の青臭さや、有り余るエネルギー、そして無謀な行動の意味を、愛情を込めて解き明かしていくのです。
舞台は1969年の長崎県佐世保市。ベトナム戦争が激化し、日本では学生運動が盛んだった時代です。しかし、この物語の面白いところは、佐世保という米軍基地のある街が舞台だということ。アメリカという巨大な存在を身近に感じながら、そこから流れ込んでくるロックや映画といった文化に、若者たちは熱狂していました。
彼らの反抗は、政治的な思想から生まれるものではありませんでした。むしろ、自分たちを縛り付ける学校や社会の「退屈」そのものに向けられていたのです。アメリカ文化のカッコいい部分だけを取り入れて、退屈な日常をぶっ壊そうとする。その根底には「楽しく生きなければ罪だ」という、シンプルで力強い哲学がありました。
「69」のあらすじ
物語を動かすのは、語り手である矢崎剣介、通称「ケン」。壮大な計画を立てては、周りを巻き込むお調子者です。彼の相棒が、ハンサムで物事を冷静に進める山田正、通称「アダマ」。この二人が中心となって、物語はとんでもない方向へ転がっていきます。すべての始まりは、ケンが憧れる美少女「レディ・ジェーン」の存在でした。
ある日、喫茶店でケンは、レディ・ジェーンが学生運動について「わかるごたる気もする」と呟くのを聞いてしまいます。これをケンは、「彼女は過激な活動をする男が好きだ」というサインだと、盛大に勘違いしてしまうのです。彼女の気を惹きたい一心で、ケンはとてつもない計画を思いつきます。それは、高校をバリケードで封鎖するというものでした。
ケンとアダマは、数少ない政治意識を持つ生徒たちをうまく乗せ、「造反有理」といったスローガンを校舎に描き、計画を実行に移します。もちろん、このバリケード封鎖は政治的な活動ではなく、あくまでケンの個人的な目的と、面白いことをやりたいという衝動から生まれたパフォーマンスでした。この無謀な計画が、どのような結末を迎えるのでしょうか。
このバリケード封鎖は、物語のほんの序盤に過ぎません。この行動によって手に入れた「無期謹慎」という名の自由な時間。それを手にしたケンたちが、退屈を打ち破るために次なる、そしてさらに壮大な計画へと突き進んでいくのです。このあらすじの先には、さらなる展開が待っていますが、それは物語の大きな魅力なので、ここでは秘密にしておきましょう。
「69」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、物語の核心に触れる部分、つまり結末までのネタバレを含んだ詳しい感想を書いていきたいと思います。まだ「69」を読んでいない方は、ご注意ください。この物語がなぜこれほどまでに多くの人を惹きつけるのか、その魅力を深く掘り下げていきます。
想像力が世界を創る
この物語の根底に流れているのは、「想像力が権力を奪う」という力強いメッセージです。主人公のケンは、学校や社会が押し付ける「退屈」という名の権力に、自らの想像力で立ち向かっていきます。彼の武器は、イデオロギーや暴力ではなく、ロックミュージックであり、映画であり、そして何よりも「面白いことをやってやろう」という純粋なエネルギーなのです。
個性的な登場人物たち
物語の魅力は、なんといっても登場人物たちの生き生きとした姿にあります。主人公のケンは、次から次へと思いつきで行動し、周りを振り回しますが、どこか憎めません。彼の途方もないアイデアを、現実的な計画に落とし込んでいくアダマの存在が、物語に安定感と推進力を与えています。この二人の友情と共闘関係が、読んでいて本当に心地よいのです。
そして、全ての始まりであるレディ・ジェーン。彼女はケンにとっての絶対的な女神であり、彼女の気を惹くためという動機が、物語全体を動かすエンジンとなります。この動機の不純さ、個人的な欲望こそが、この物語を普遍的な青春の物語として輝かせているのだと感じます。政治的な正しさではなく、一人の女の子を振り向かせたいという衝動。これほどパワフルなものはありません。
パフォーマンスとしての反逆
最初の大きな見せ場である高校のバリケード封鎖。このエピソードは、彼らの反抗が本質的に「パフォーマンス」であったことを象
徴しています。彼らは革命家を演じ、それっぽい言葉を並べますが、その心は行為自体の「カッコよさ」に酔っています。このネタバレをすると、彼らの行動が滑稽に見えるかもしれませんが、そうではありません。
彼らにとって、政治的な思想はアクセサリーのようなものでした。大切なのは、退屈な日常に風穴を開け、自分たちが物語の主人公になること。結果的に彼らは警察に捕まり、無期謹慎処分を受けます。しかし、ケンにとってそれは失敗ではなく、むしろ望んでいた「悪名」と「自由な時間」を手に入れた成功体験となるのです。ここが、この物語の面白い転換点です。
退屈との再会と新たな創造
手に入れた自由な時間も、やがて「退屈」に変わっていきます。刺激を求めて博多へ向かったケンは、そこでドラッグに溺れる少女と出会い、カウンターカルチャーの暗い側面を目の当たりにします。華やかなイメージとは違う現実に打ちのめされるこの経験は、ケンにとって重要な転機となりました。
彼は、既存のカルチャーに乗っかるのではなく、自分たちの手で、自分たちのための世界をゼロから創造することを決意します。この幻滅からの再生こそが、物語をさらに大きなステージへと押し上げるのです。ここから、物語はクライマックスであるフェスティバル計画へと向かっていきます。
「モーニング・エレクション・フェスティバル」という宇宙
ケンが次に考えたのは、音楽、演劇、映画を融合させた巨大な文化祭「モーニング・エレクション・フェスティバル」の開催でした。このネーミングからして、若者の有り余るエネルギーが感じられて、思わず笑みがこぼれます。このフェスティバル計画は、単なるイベント企画ではありません。
それは、自分たちの価値観に基づいた、まったく新しい世界、いわば「一時的な自律空間」を創造する試みでした。ケンのアイデアとアダマの実行力が見事に噛み合い、計画は着々と進んでいきます。この準備期間の描写が、本当にワクワクするのです。
映画、音楽、そして対立
フェスティバルの目玉として、彼らは自主制作映画『ジョーの詩』を撮り始めます。もちろん、主演はレディ・ジェーン。彼女を撮影に巻き込むという下心満載のこの計画は、素人ならではの情熱とドタバタに満ちていて、読んでいて最高の気分になります。
同時に、フェスティバルに出演してくれるバンドを探して、佐世保の街を駆け回ります。当時の音楽シーンの熱気が伝わってくるような描写は、音楽好きにはたまりません。彼らは、自分たちの手で、この佐世保にウッドストックのような伝説的な空間を創り出そうと奔走するのです。
しかし、物語は順風満帆には進みません。彼らの計画は、地元の工業高校を牛耳る番長の縄張りを侵してしまいます。ここから物語の敵は、学校の先生という権威から、生身の暴力を持つ不良グループへと変わります。停学処分では済まない、身体的な危険。この新たな緊張感が、物語をさらに加速させます。
祭りの日のカタルシス
そして迎えるフェスティバル当日。このクライマックスシーンの描写は、圧巻の一言です。アマチュアバンドが掻き鳴らす轟音、スクリーンに映し出される自分たちの映画、熱狂する観客。あらゆる困難を乗り越えて、ケンたちの想像力が現実になった瞬間です。
この場面は、混沌としたエネルギーと、それを成し遂げたという達成感に満ちています。あれほど大きな障害だった番長グループとの対立さえも、この祭りの熱狂の中に飲み込まれ、いつの間にか解消されてしまう。この大団円は、まさしくカタルシス。若者のエネルギーが全てを肯定し、洗い流していく、最高の瞬間です。この結末のネタバレを知っていても、読むたびに胸が熱くなります。
祭りの後とそれぞれの未来
物語は、フェスティバルの成功で終わりません。ケンとレディ・ジェーンの恋は、はっきりとした結末を迎えることなく、自然と終わりを迎えます。彼女を手に入れるという目的は達成されません。しかし、それでいいのです。この物語は、目的を達成するまでの「過程」こそが全てだったからです。
最終章では、映画『アメリカン・グラフィティ』のように、登場人物たちのその後の人生が淡々と語られていきます。作家になったケン、実業家になったアダマ、平凡な家庭を築いたレディ・ジェーン。1969年という特別な一年を共有した彼らが、それぞれの道を歩んでいく。このエピローグが、あの夏の輝きを、二度と戻らない特別なものとして、読者の心に刻みつけるのです。
「退屈」との終わりなき戦い
著者は「あとがき」で、この物語で戦っていた本当の敵は「退屈」そのものだったと語ります。そして、退屈に勝つ唯一の方法は、喜びとエネルギーをもって、能動的に生きること、つまり「戦い続ける」ことだと。この物語は、その長く続く戦いの中の、輝かしい勝利の記録なのです。
1969年という時代を舞台にしながらも、この物語が持つメッセージは、現代を生きる私たちにも強く響きます。抑圧や同調圧力に対して、自分だけの「面白いこと」で反逆する。人生を自分自身の手で創造していく。そのための情熱的で、愛すべき青写真が、この「69」という物語なのだと、私は思います。
まとめ
村上龍の小説「69」は、1969年の佐世保を舞台に、ケンとアダマという二人の高校生が、退屈な日常を打ち破るために壮大な計画を実行していく物語です。憧れの女の子の気を惹くという不純な動機から始まったバリケード封鎖は、やがて街中を巻き込む巨大なフェスティバルへと発展していきます。
この物語のあらすじを追うだけでも、その破天荒でエネルギッシュな展開にワクワクさせられます。しかし、本作の本当の魅力は、その根底にある「楽しく生きることは戦いだ」という力強い哲学にあります。ネタバレになりますが、彼らの計画は全てが成功するわけではありません。それでも、想像力を武器に退屈に立ち向かう姿は、読む者に勇気を与えてくれます。
ケンの軽快な一人称で語られる文章は、読者を一気に1969年の世界へと引き込みます。ロックや映画といったカウンターカルチャーの熱気と、若者たちの有り余るエネルギーが、ページから溢れ出てくるようです。単なる青春小説という枠には収まらない、普遍的な輝きを持つ一冊です。
まだ読んだことがない方はもちろん、かつて読んだという方も、ぜひ改めて手に取ってみてください。きっと、日々の退屈を吹き飛ばしてくれるだけのパワーをもらえるはずです。この感想が、そのきっかけになれば幸いです。