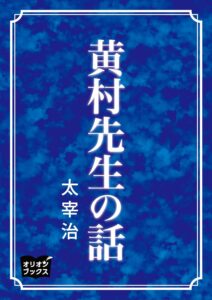 小説「黄村先生言行録」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治が描く、どこか憎めない人物、黄村先生。彼の起こす騒動は、私たち読者に微笑ましさと、ほんの少しの哀愁を感じさせるかもしれません。
小説「黄村先生言行録」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治が描く、どこか憎めない人物、黄村先生。彼の起こす騒動は、私たち読者に微笑ましさと、ほんの少しの哀愁を感じさせるかもしれません。
この物語は、黄村先生という、世間から少し離れて風流を気取る人物が、ある日突然、山椒魚に夢中になるところから始まります。その熱中ぶりは周りを巻き込み、思いがけない結末へと向かっていきます。一見すると他愛のない出来事のようですが、そこには人間の持つ純粋さや愚かさ、そして当時の社会状況に対する作者の眼差しが込められているように思えます。
この記事では、まず「黄村先生言行録」の物語の筋道を、結末まで含めて詳しくお伝えします。物語の展開を知りたい方、あるいは読んだけれど内容を再確認したいという方にお読みいただければと思います。どのような顛末を迎えるのか、黄村先生の行動とその結果に注目してみてください。
そして、物語の詳細をお伝えした後には、私がこの作品を読んで感じたこと、考えたことを、ネタバレを気にせずにたっぷりと語りたいと思います。黄村先生の魅力、作品の持つ意味、太宰治の描きたかったものなど、様々な角度から掘り下げていきますので、作品への理解を深める一助となれば幸いです。
小説「黄村先生言行録」のあらすじ
物語は、語り手である「私」が、敬愛する黄村先生について語るところから始まります。「はじめに、黄村先生が山椒魚に凝つて大損をした話をお知らせしませう」という一文で、これから語られる出来事が、先生にとってあまり芳しくない結果に終わることが示唆されます。黄村先生は、いわゆる風流人として描かれており、世俗的なことにはあまり関心がないように見えます。
ある早春の日、「私」は黄村先生と一緒に井の頭公園へ散歩に出かけます。公園内にある水族館を訪れた際、先生は水槽の中の山椒魚を見て、まるで子供のように興奮し、「やあ! 君、山椒魚だ! 山椒魚。たしかに山椒魚だ。生きてゐるぢやないか、君、おそるべきものだねえ」と大きな声を上げます。しかし、その生態については詳しくなく、動物学的な知識がないことを残念がるのでした。
それから約一ヶ月後、「私」が阿佐ヶ谷にある先生の自宅を訪ねると、驚いたことに先生はすっかり山椒魚の研究に没頭していました。関連する書籍を読み漁り、まるで動物学者のような口ぶりで山椒魚に関する知識を「私」に披露します。石川千代松博士や佐々木忠次郎といった学者の名前を挙げながら、その生態や日本の巨大山椒魚について熱弁をふるい、「神よ、私はただ、大きい山椒魚を見たいのです」と、その強い願望を吐露するのでした。
その後、「私」は仕事の都合で山梨県の湯村温泉へ行くことになります。滞在中、ちょうど厄除け地蔵のお祭りが開かれており、賑わいの中でふと見世物小屋が目に入ります。小屋の前では、「伯耆国は淀江村の百姓、太郎左衛門が、五十八年間手塩にかけて、身のたけ一丈、頭の幅は三尺」という巨大な山椒魚がいるという口上が述べられていました。「私」は、これが先生が熱望していた伯耆国淀江村の大山椒魚に違いないと直感します。
「私」は興奮のあまり、すぐに先生へ「ダイサンセウミツケタ」と電報を打ちます。その知らせを受けた先生は、その日の夜にはもう大金を持って湯村温泉に駆けつけました。先生は本気でその大山椒魚を買い取るつもりだったのです。早速、見世物小屋の主人を宿に呼び、購入の交渉を始めますが、主人は「商売道具である山椒魚を、隠居の道楽のために売ることはできない」と、きっぱりと断ります。
失意の黄村先生は、宿に戻る際、酔いと落胆からか階段を踏み外し、腰を強く打ってしまいます。結局、大山椒魚購入のために持ってきた大金は、その怪我の湯治代としてほとんど消えてしまいました。物語の最後で「私」は、黄村先生は自ら失敗を演じることで、それを私たちへの教訓として示してくださるような方なのだろう、と述懐するのでした。
小説「黄村先生言行録」の長文感想(ネタバレあり)
「黄村先生言行録」を読み終えて、まず心に残るのは、黄村先生という人物の、なんとも言えない愛嬌と、その行動が引き起こす一種の「滑稽さ」です。風流人を気取り、俗世間から距離を置いているように見える先生が、山椒魚という一つの対象に異常なまでの情熱を注ぎ、結果的に「大損」をしてしまう。この一連の出来事は、読んでいて思わず笑みがこぼれてしまいます。
先生の滑稽さは、本人が至って真面目である点に起因するように思います。井の頭公園で山椒魚を見つけた時の、あの子供のようなはしゃぎっぷり。そして、その後わずか一月で専門家気取りになるほどの猛勉強ぶり。その熱意は純粋そのもので、だからこそ、その後の展開がより一層おかしくも、そして少し切なくも感じられるのです。
彼は山椒魚について語る際、著名な学者の名前を挙げ、専門用語を交えながら滔々と述べ立てます。しかし、その知識は急ごしらえのものであり、語り手である「私」による括弧書きのツッコミが、その付け焼き刃ぶりを効果的に示しています。この「私」の視点が、読者と先生との間に程よい距離感を作り出し、先生の行動を客観的かつ微笑ましく眺めることを可能にしています。
先生が「神よ、私はただ、大きい山椒魚を見たいのです、人間、大きいものを見たいといふのはこれ天性にして、理窟も何もありやせん」と語る場面は、非常に印象的です。人間の根源的な欲求、理屈を超えた衝動のようなものを、先生は正直に口にします。この言葉には、彼の純粋さ、ある種の無邪気さが表れていると言えるでしょう。大きいもの、珍しいものへの憧れは、誰しもが持っている感情かもしれません。
そして物語は、先生のその願いが叶うかもしれない、という展開を迎えます。「私」が旅先の湯村温泉で見つけた見世物小屋の巨大山椒魚。これこそ先生が夢見た「伯耆国淀江村の大山椒魚」ではないか、と。ここでの「私」の行動も興味深い点です。先生の話を聞いていた時は、どこか小馬鹿にしていたような素振りも見せていた「私」が、いざ本物(かもしれないもの)を目の当たりにすると、先生以上に興奮し、電報まで打ってしまうのです。
この「私」の反応は、人間の心の奥底にある好奇心や、珍しいものに対する興奮をよく表しています。普段は冷静な人物でも、非日常的な出来事に遭遇すると、思わず感情が高ぶってしまう。先生の情熱が「私」にも伝染したかのようです。そして、この電報が、物語をクライマックスへと導きます。
知らせを受けて飛んできた先生の行動力には驚かされます。大金を携え、すぐさま現地に赴き、山椒魚を購入しようと試みる。その情熱と行動力は、普段の飄々とした姿からは想像もつかないほどです。しかし、見世物小屋の主人との交渉は、あっけなく失敗に終わります。現実の壁、商売という論理の前では、先生の純粋な熱意も通用しませんでした。
この交渉決裂の場面は、風流を気取る先生と、生活のために働く見世物小屋の主人との対比を際立たせます。先生にとっては趣味であり道楽であっても、主人にとっては生活の糧。その価値観のずれが、交渉不成立という結果を生んだのでしょう。いくら風流を気取って高尚な趣味に没頭しても、現実の生活者の論理の前では、それは単なる「暇人の道楽」と見なされてしまうのかもしれません。
そして、失意の先生を襲う、階段からの転落という更なる不運。大山椒魚の購入資金として持ってきた大金は、結局、自身の怪我の治療費に消えてしまうという、なんとも皮肉な結末を迎えます。まさに「大損」です。この結末は、先生の行動の滑稽さを決定的なものにすると同時に、どこか物悲しさも漂わせています。
物語の最後に「私」は、先生が自らの失敗を教訓として示すために、わざとこのような行動をとったのではないか、と解釈します。しかし、読者としては、先生はそんな深謀遠慮から行動したわけではなく、ただただ山椒魚に夢中になり、その純粋な欲求に従って行動した結果、失敗してしまっただけなのではないか、と感じられます。そこに計算や打算はなく、ただ純粋であるが故の失敗。だからこそ、先生の姿は憎めず、愛おしくさえ思えるのです。
この作品が書かれたのは、太平洋戦争の最中である1942年から1943年にかけてです。この時代背景を考慮すると、単なる滑稽譚として読むだけでは見過ごしてしまうかもしれない、深い意味合いが込められているようにも思えます。作中で引用されている『中庸』の「南方之強、北方之強」に関する一節は、そのヒントとなるかもしれません。
『中庸』では、寛容さや教え導く力を「南方の強さ」、武力や死をも恐れぬ勇猛さを「北方の強さ」とし、真の強さとは、和を保ちながらも流されず、公明正大であること、平時も有事も自分の責務を忘れず、節操を変えないことだと説かれています。この引用は、表面的には黄村先生の言動とは直接関係ないように見えますが、当時の社会状況、すなわち戦争へと突き進む世相に対する、太宰の隠されたメッセージと解釈することも可能です。
「衽金革、死而不厭、北方之強也(武器や武具を寝具とするかのごとく戦いに明け暮れ、死をも恐れぬことが北方の強さである)」という部分などは、当時の軍国主義的な風潮を暗に示しているとも考えられます。そして、それに対して「君子和而不流、強哉矯(指導者とは和を保ちながらも他人には流されない強さを持っているものである)」や「中立而不倚、強哉矯(公明正大であること。それこそが本当の強さなのだ)」といった言葉を置くことで、武力に偏重する社会への疑問や批判を投げかけているのではないでしょうか。
黄村先生の、ある意味で世間離れした純粋な行動と、その結果としての「滑稽な」失敗は、戦争という狂気じみた現実に対する、ささやかな抵抗のようにも見えます。誰もが「北方の強さ」を求められる時代にあって、山椒魚という、およそ生産的とは言えないものに情熱を傾ける先生の姿は、別の価値観、別の「強さ」のあり方を示唆しているのかもしれません。それは、権力や時流に流されず、自分の信じるもの(たとえそれが山椒魚であっても)に純粋に向き合う姿勢、と言えるかもしれません。
もちろん、これは深読みしすぎかもしれません。しかし、太宰治という作家が、単なる面白い話としてこの作品を書いたとは考えにくいのも事実です。彼の作品には、常に時代や社会に対する鋭い観察眼と、人間存在への深い洞察が込められています。「黄村先生言行録」もまた、軽妙な筆致の裏に、複雑な思いやメッセージが隠されているのではないでしょうか。黄村先生の「滑稽さ」は、笑いと共に、ある種の哀れみや、そしてもしかしたら、当時の社会そのものの「滑稽さ」への皮肉をも含んでいるのかもしれません。
まとめ
太宰治の「黄村先生言行録」は、黄村先生という風流人が山椒魚に魅せられ、大騒動を巻き起こす物語です。先生の純粋すぎる情熱と、その結果招かれる「大損」という結末は、読者に微笑ましさと共に、どこか物悲しい余韻を残します。
物語の筋書きを追うだけでも、黄村先生のキャラクターや、「私」との軽妙なやり取りを楽しむことができます。特に、先生が専門家気取りで山椒魚について語る場面や、見世物小屋の山椒魚を前にした先生と「私」の興奮ぶりは、印象的な場面と言えるでしょう。結末のあっけなさ、皮肉っぽさも、太宰治らしい味わいがあります。
しかし、この作品の魅力は、単なる面白い話に留まりません。先生の行動を通して描かれる人間の純粋さや愚かさ、そしてそれが現実の壁にぶつかる様は、普遍的なテーマを内包しています。さらに、執筆当時の時代背景を考えると、『中庸』の引用などを通して、当時の社会状況に対する作者の批評的な眼差しを読み取ることも可能です。
「黄村先生言行録」は、軽やかな筆致で描かれた、一見すると他愛のない物語のようでいて、読む人によって様々な解釈や感想を抱かせる、奥深い作品です。黄村先生のどこか憎めないキャラクターと、その言動が織りなす「滑稽」な世界に、ぜひ触れてみてください。読後には、きっと先生のことが忘れられなくなるはずです。




























































