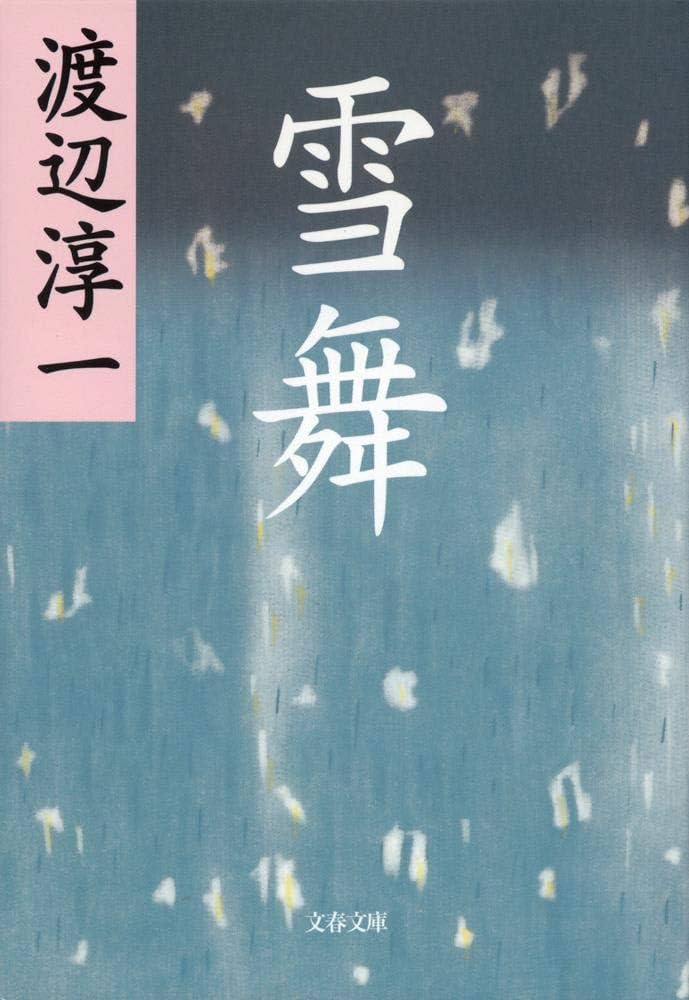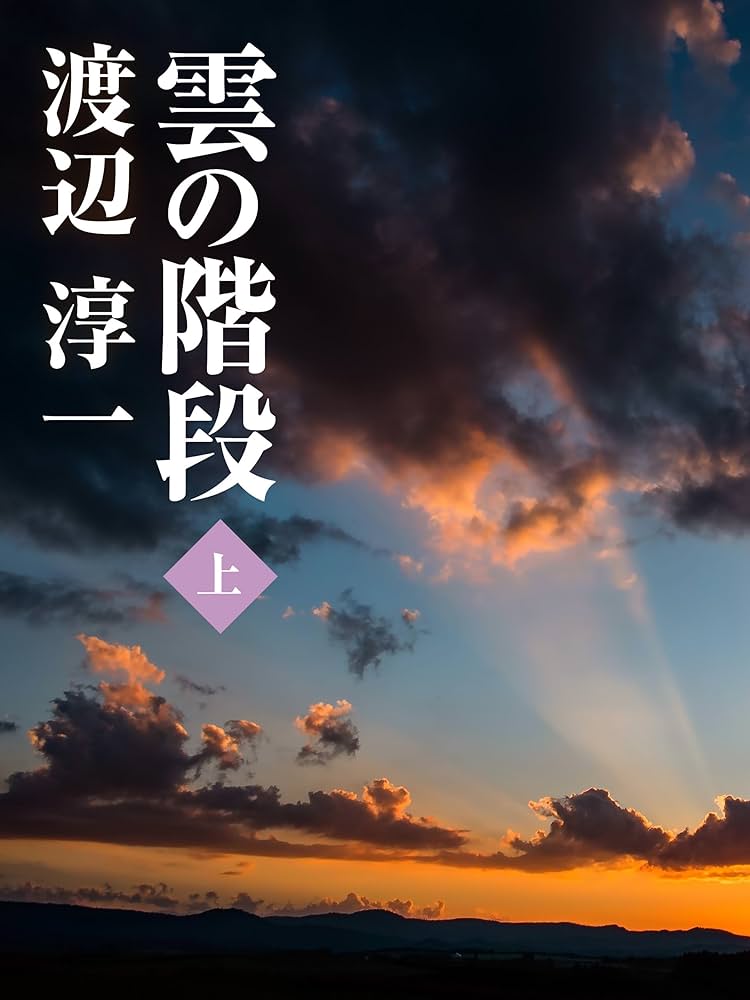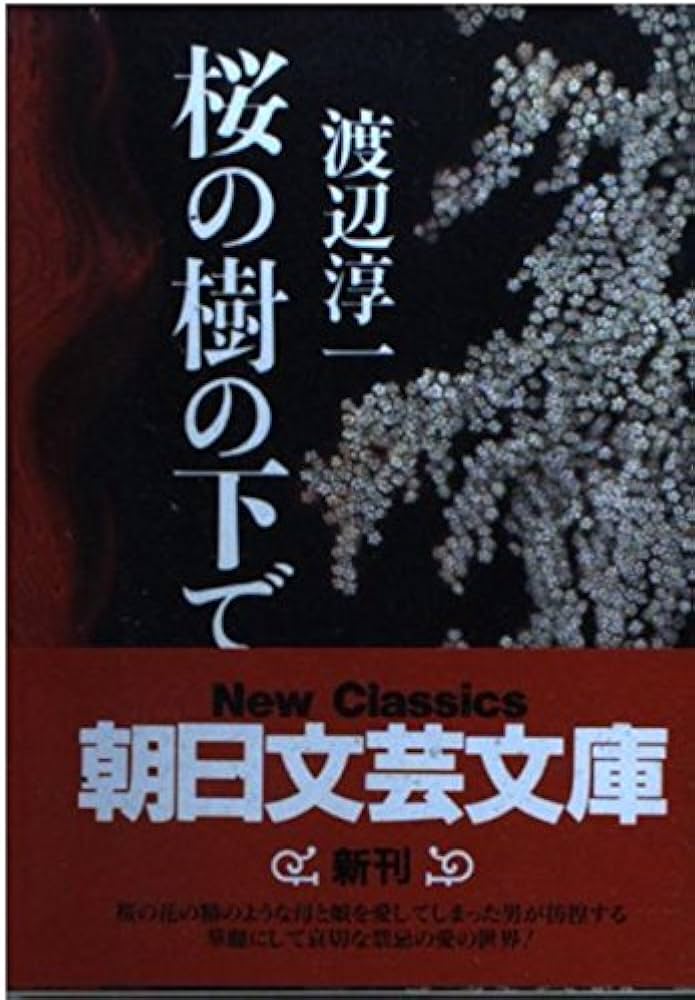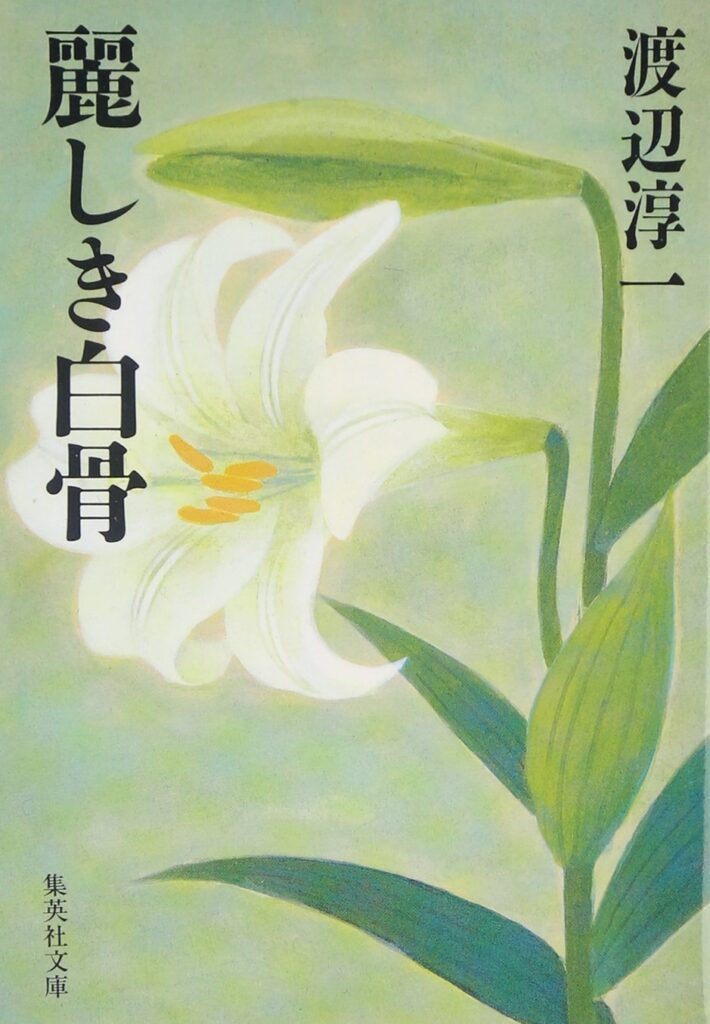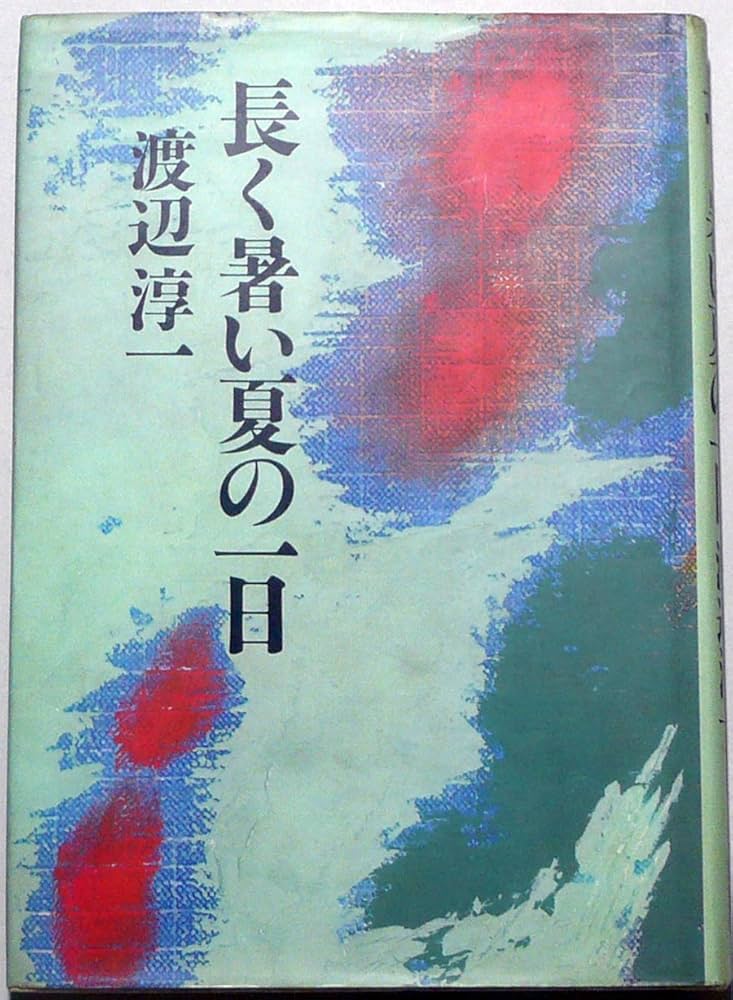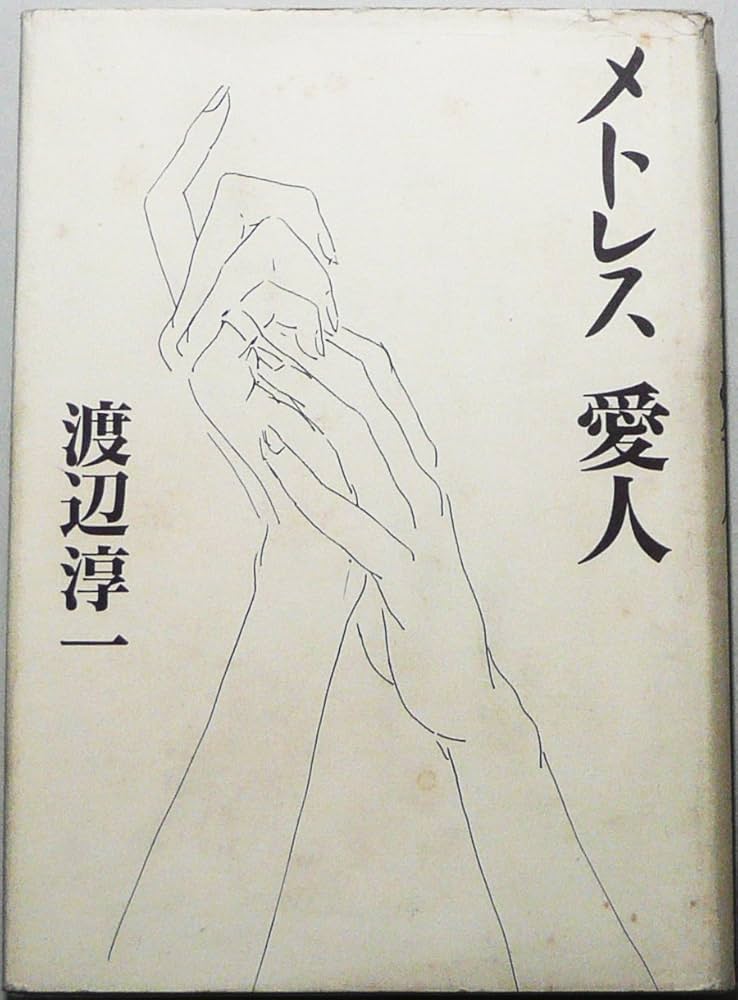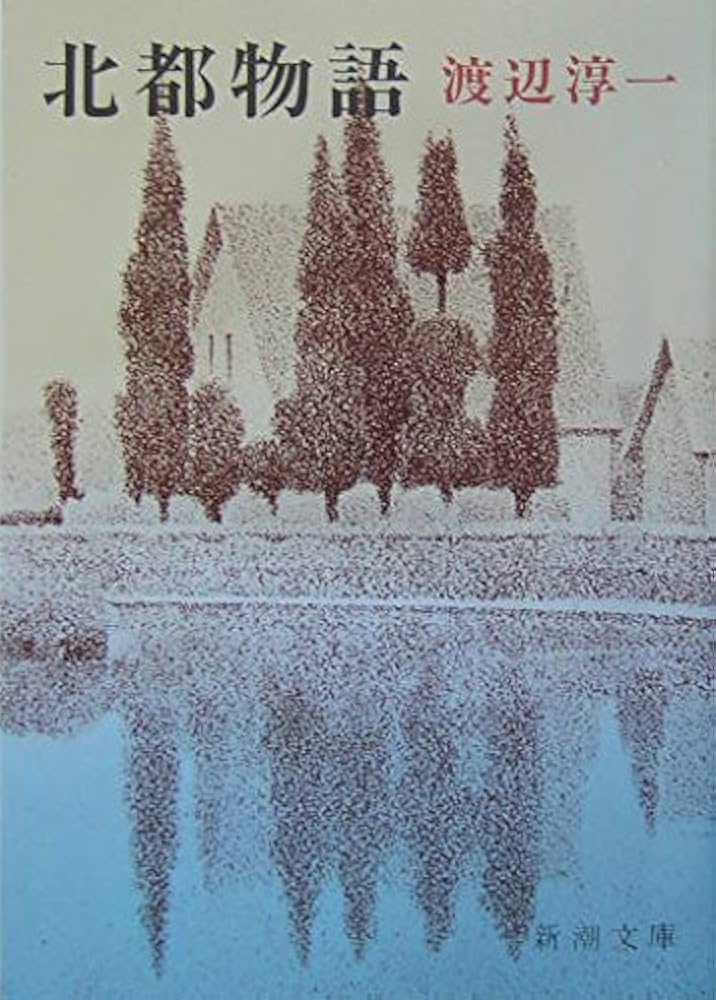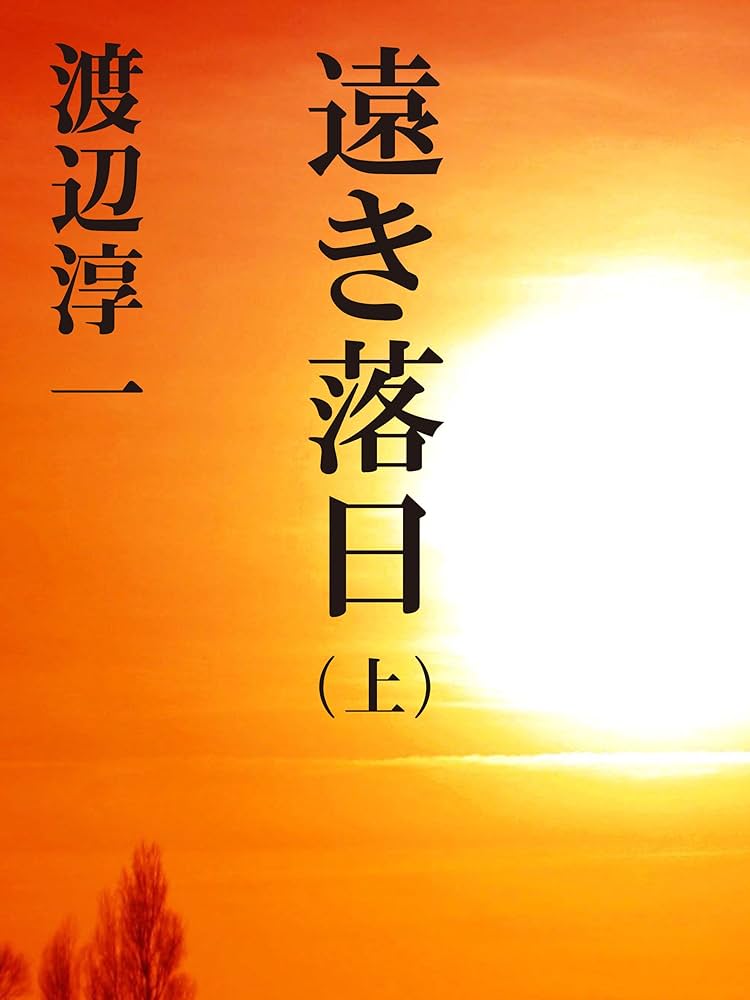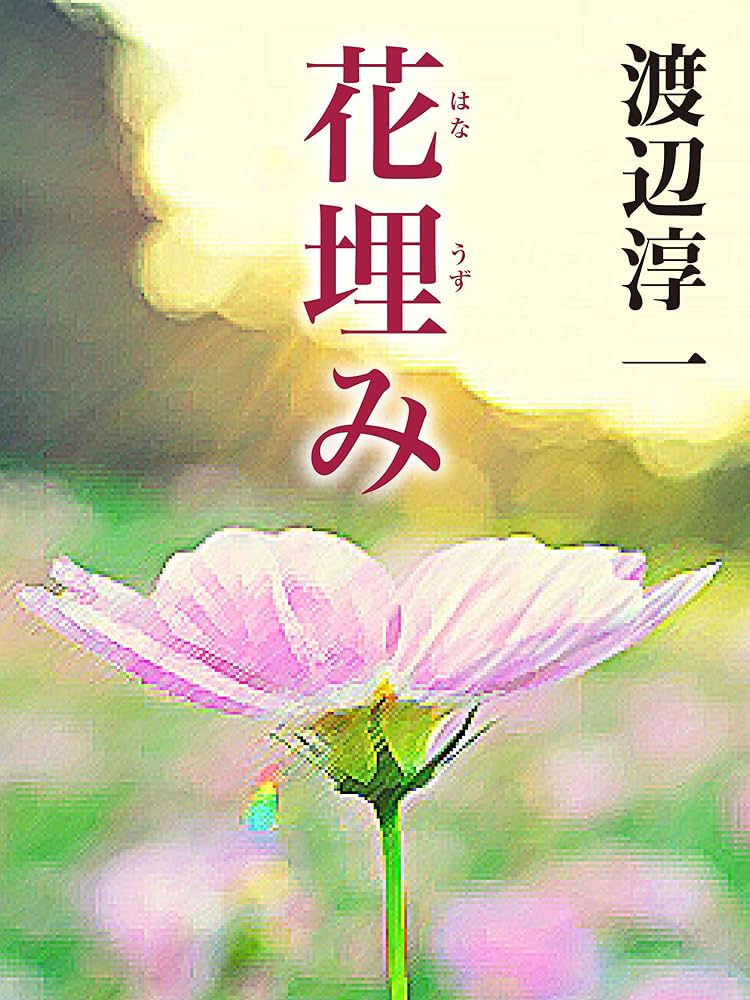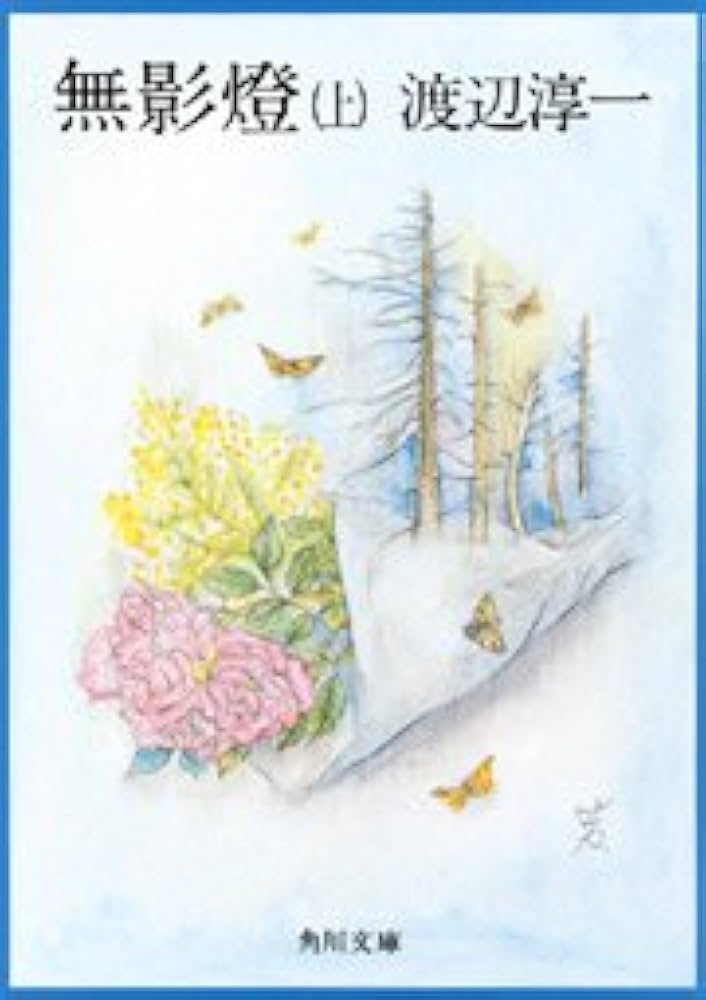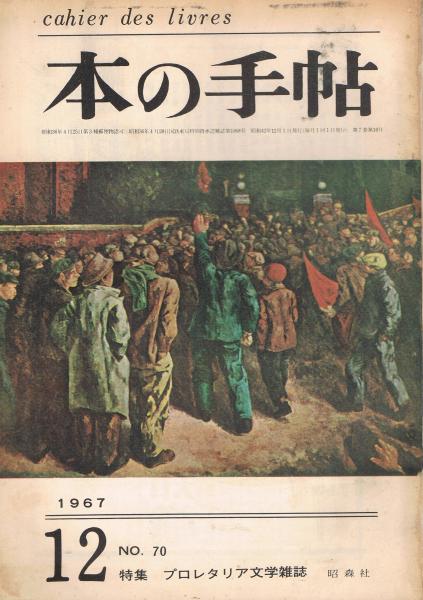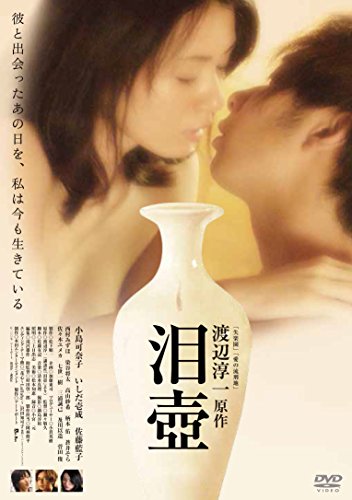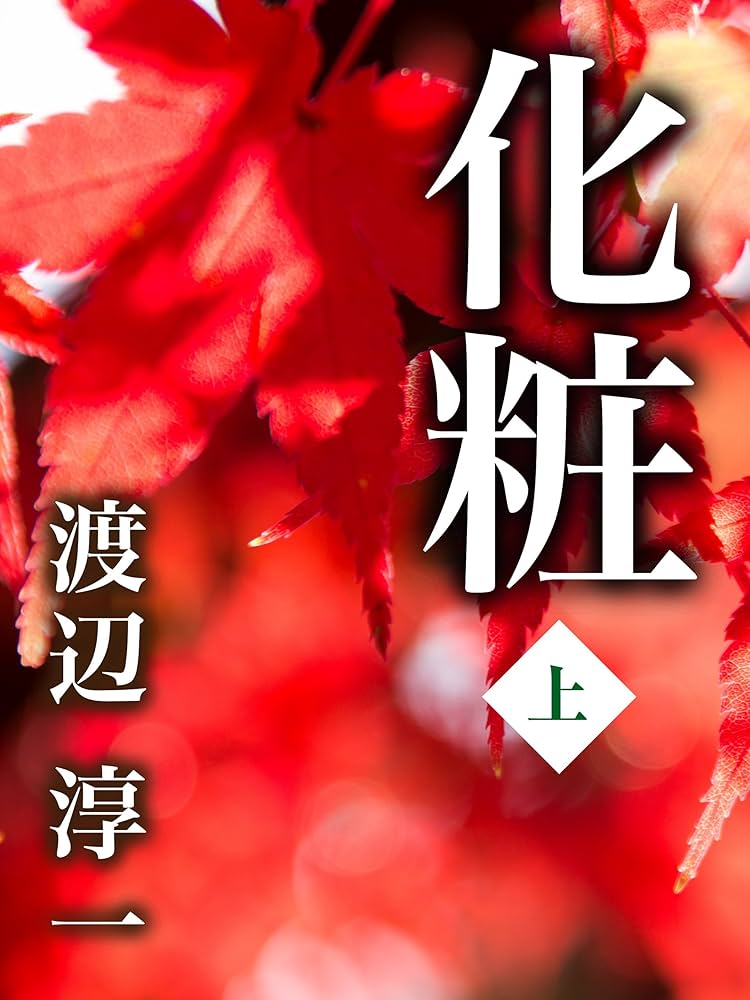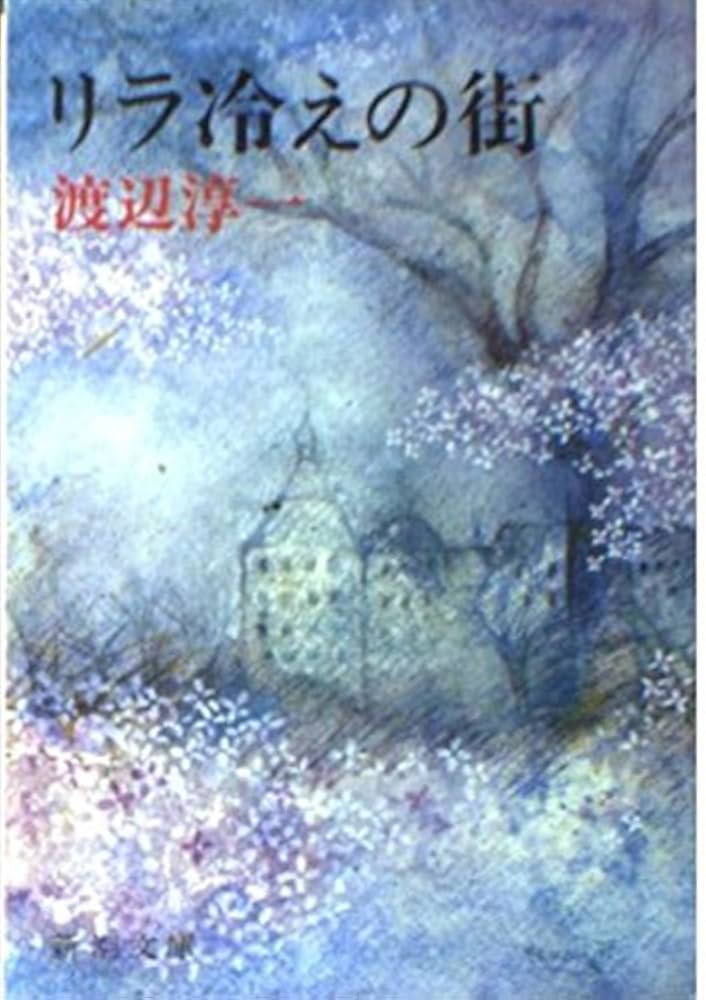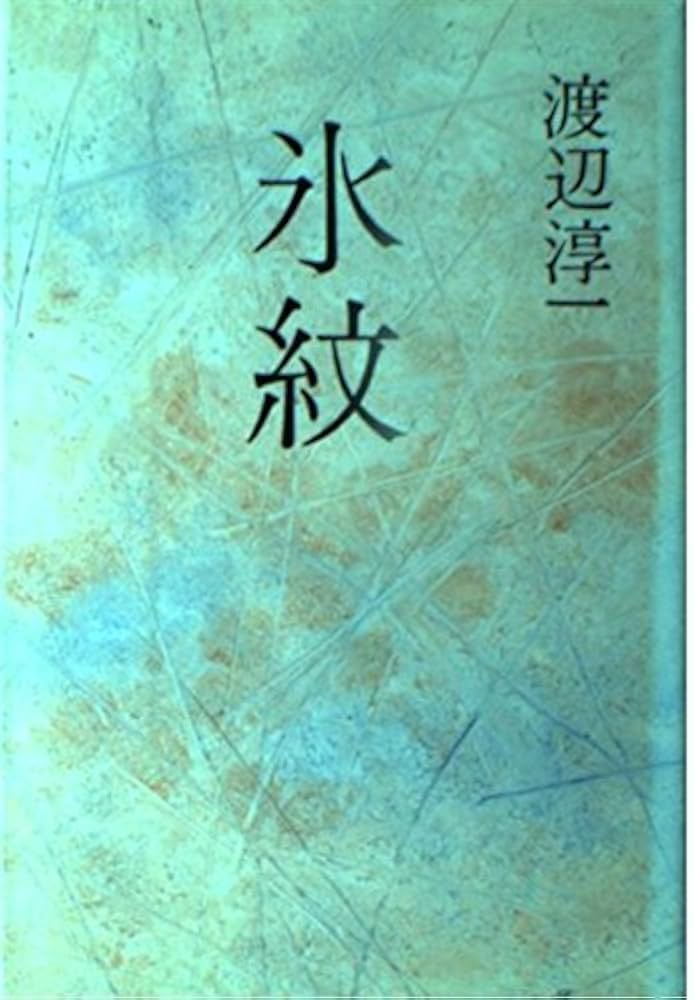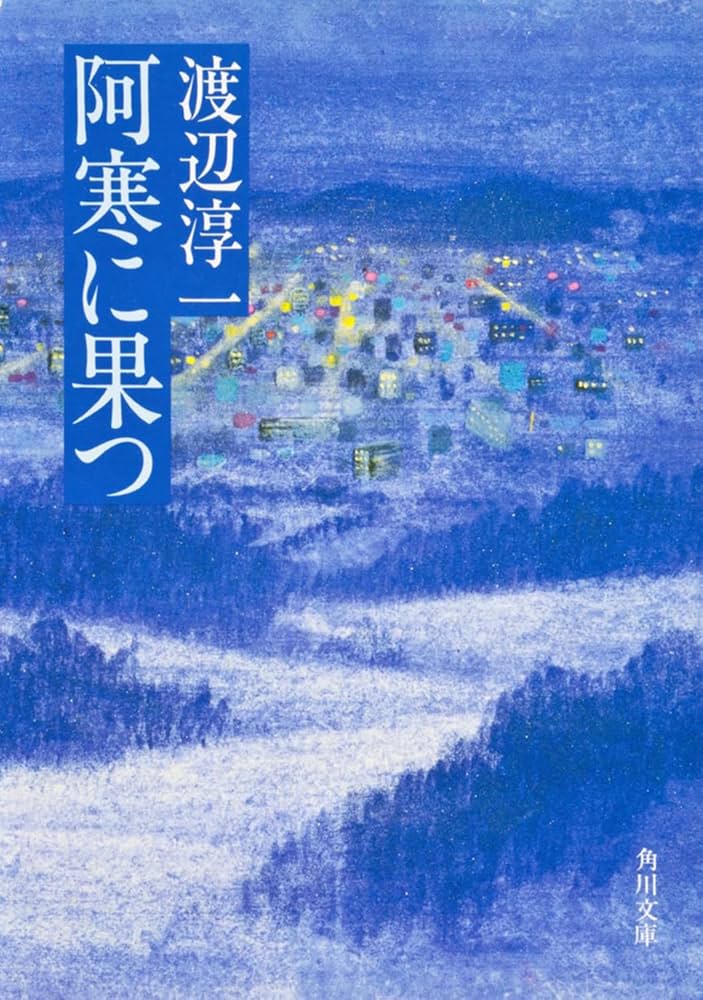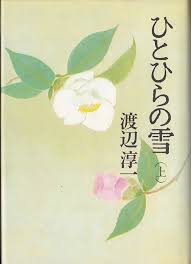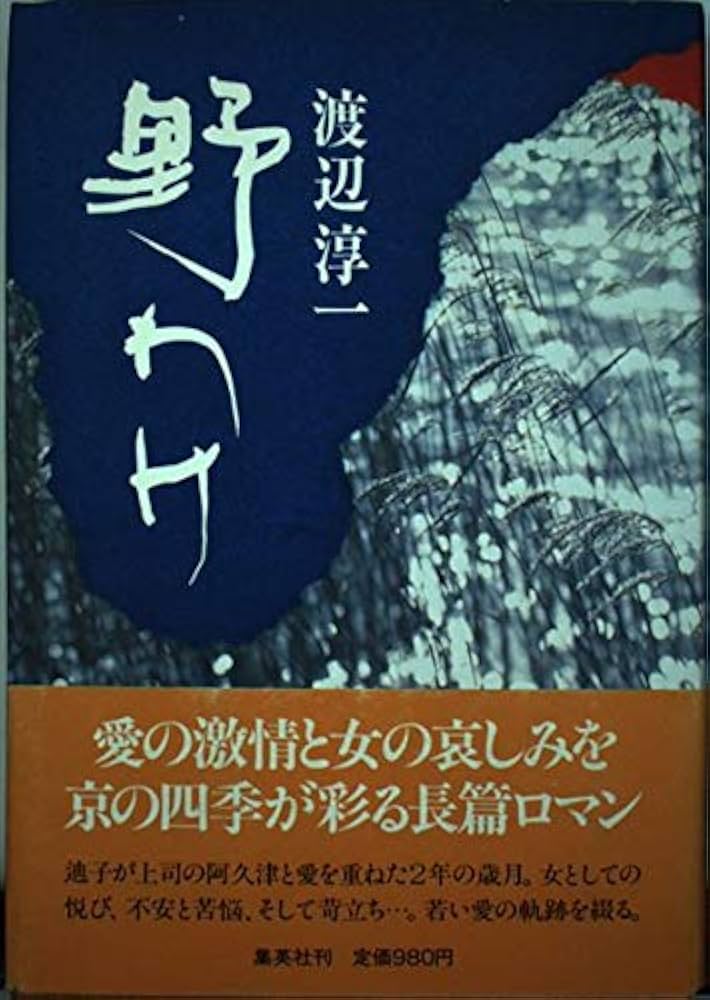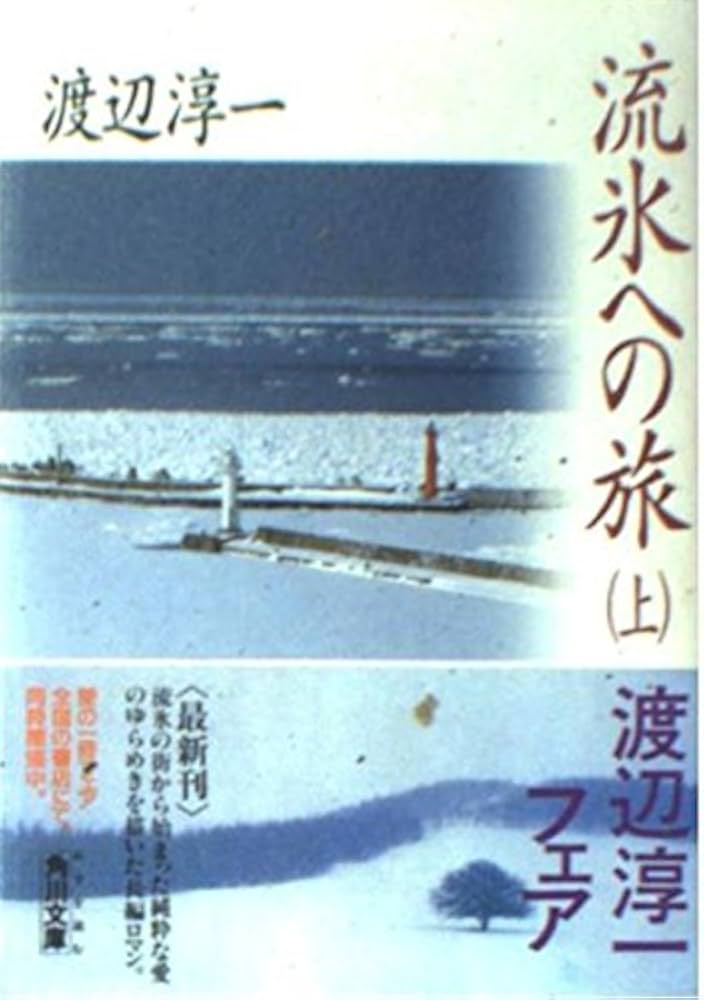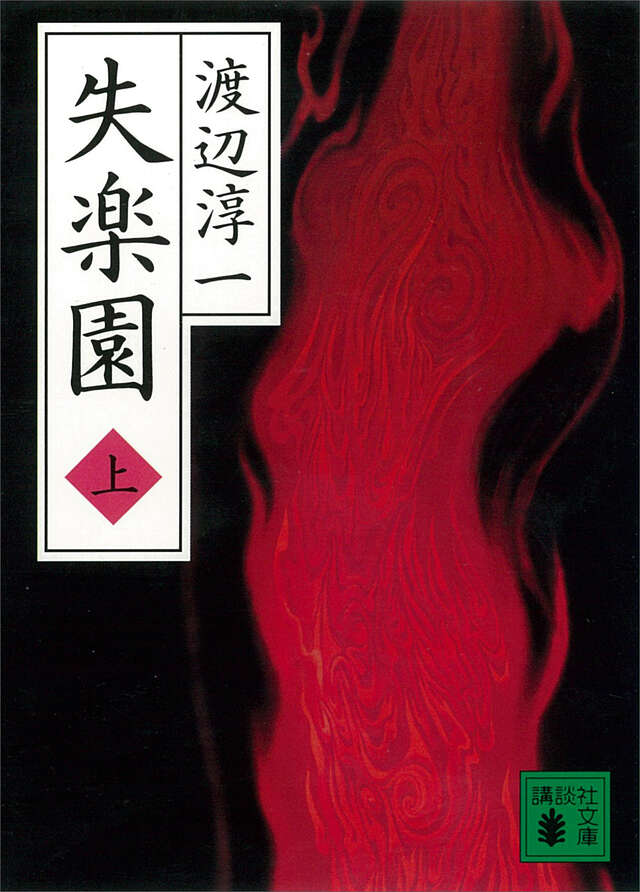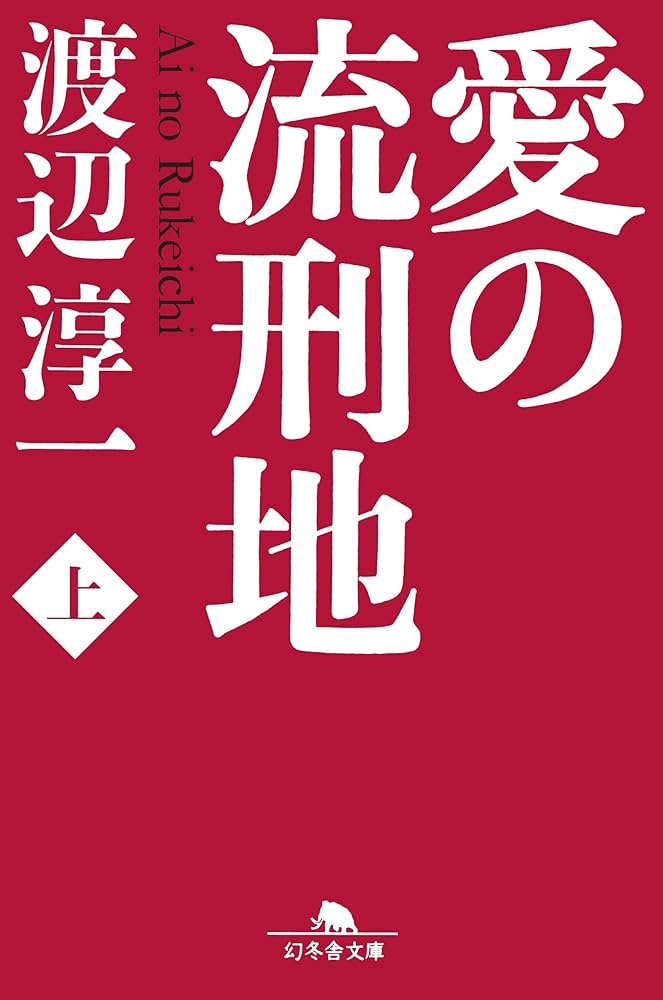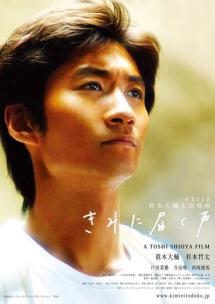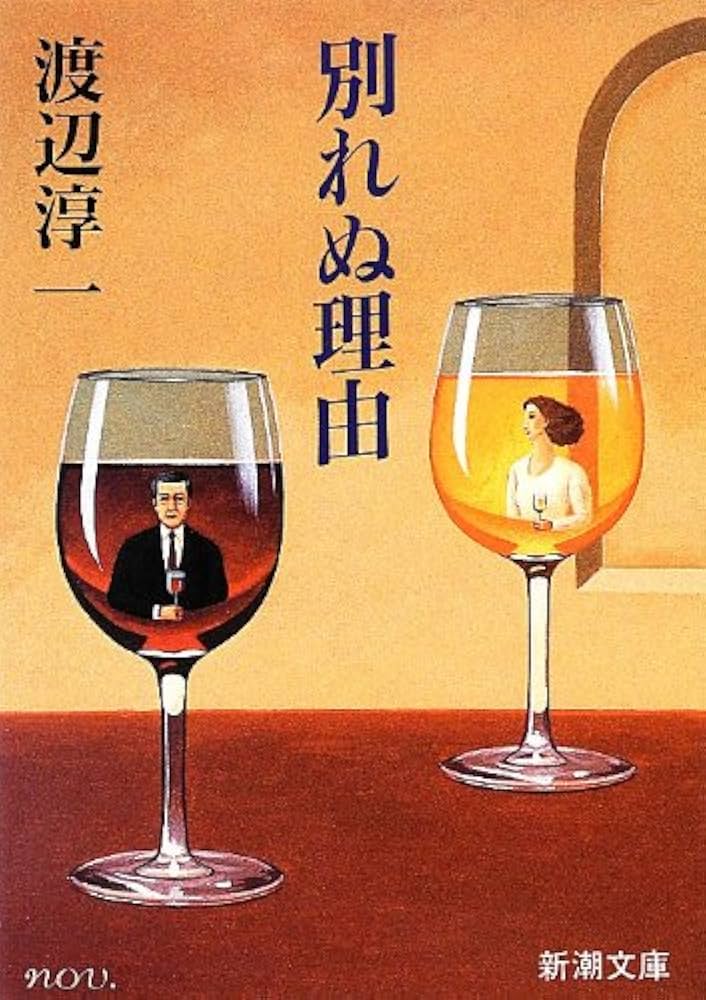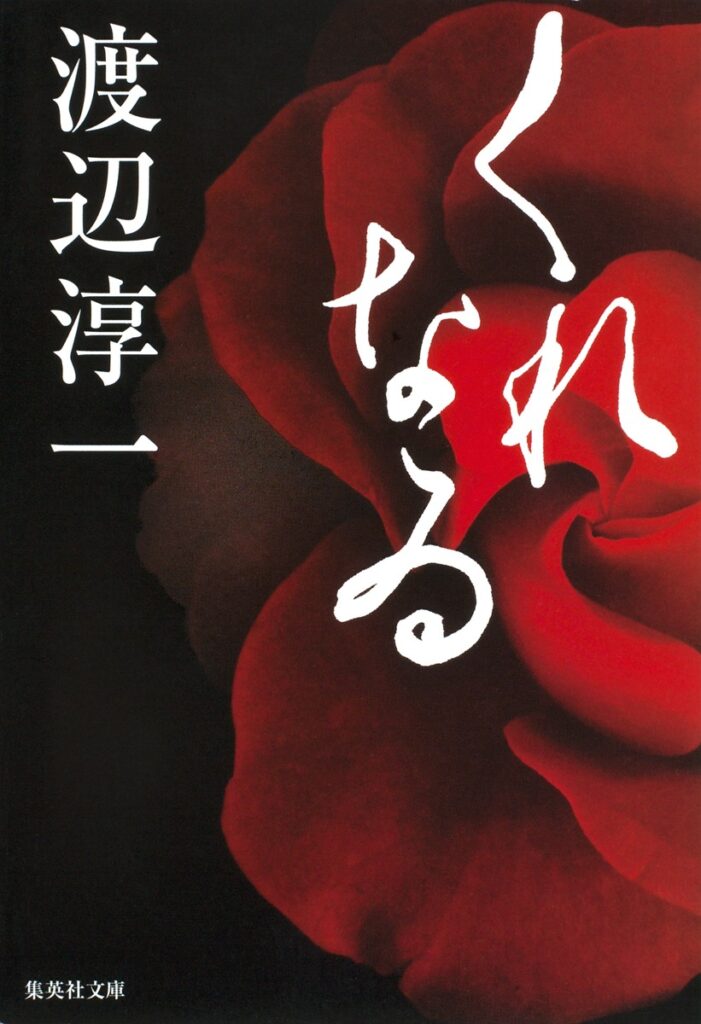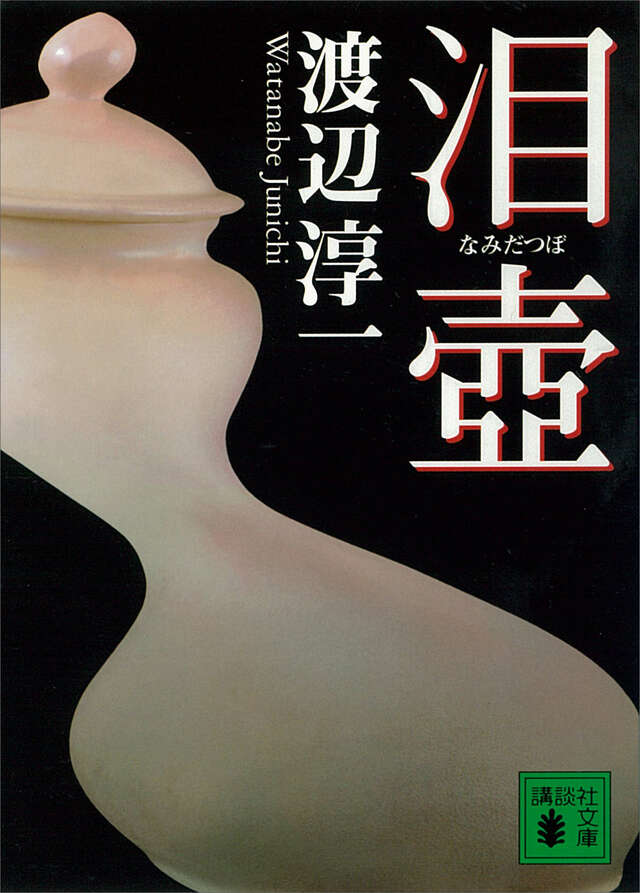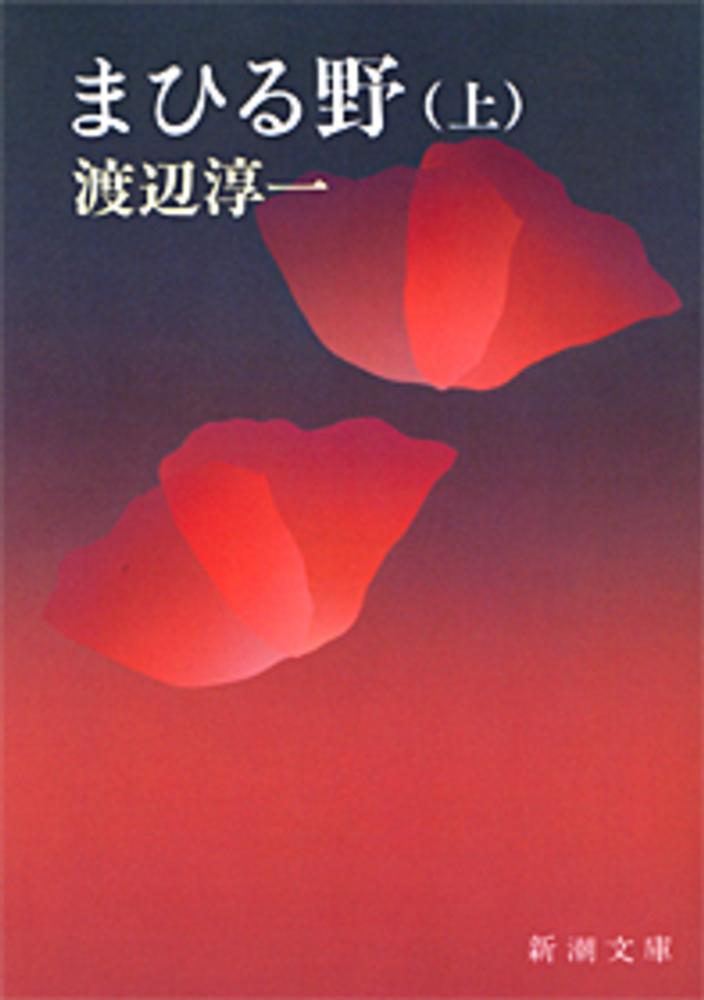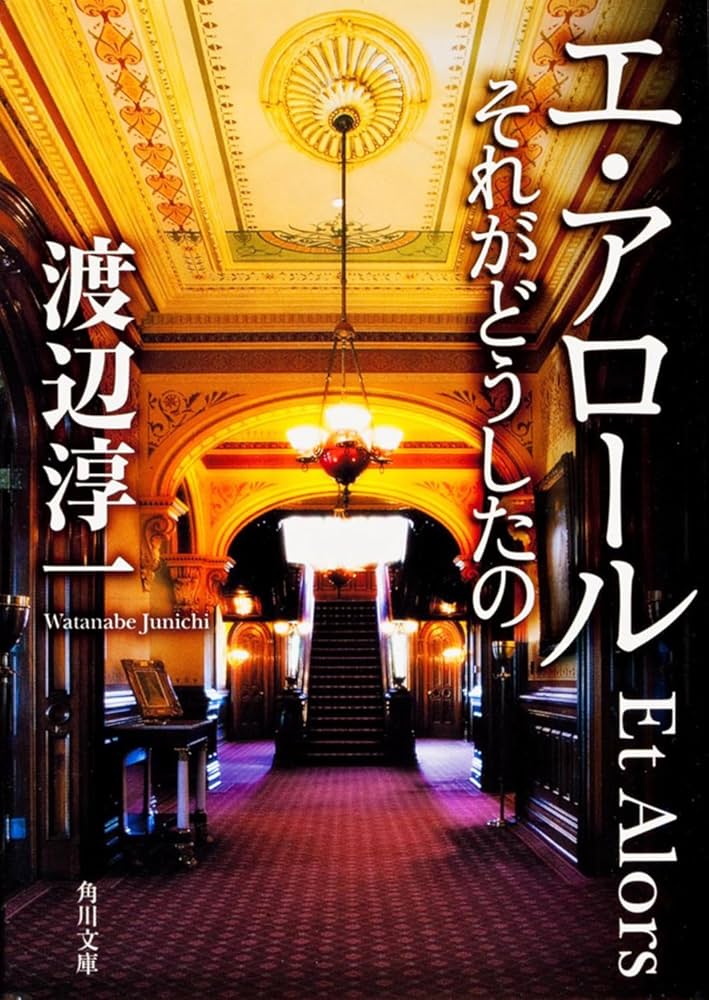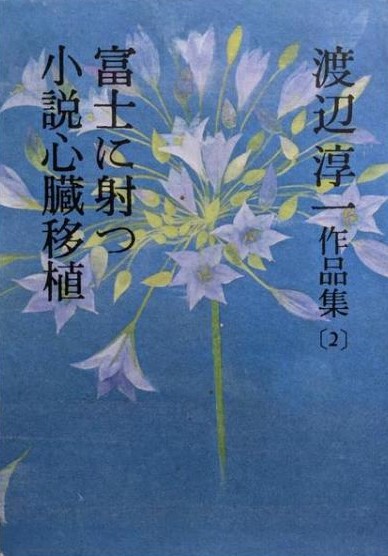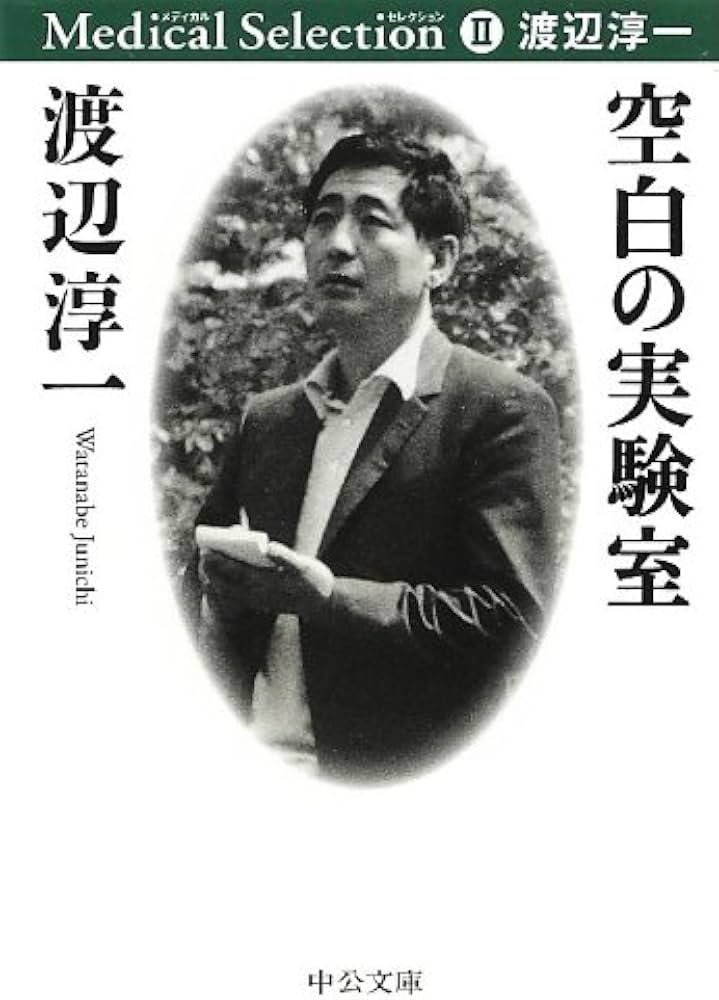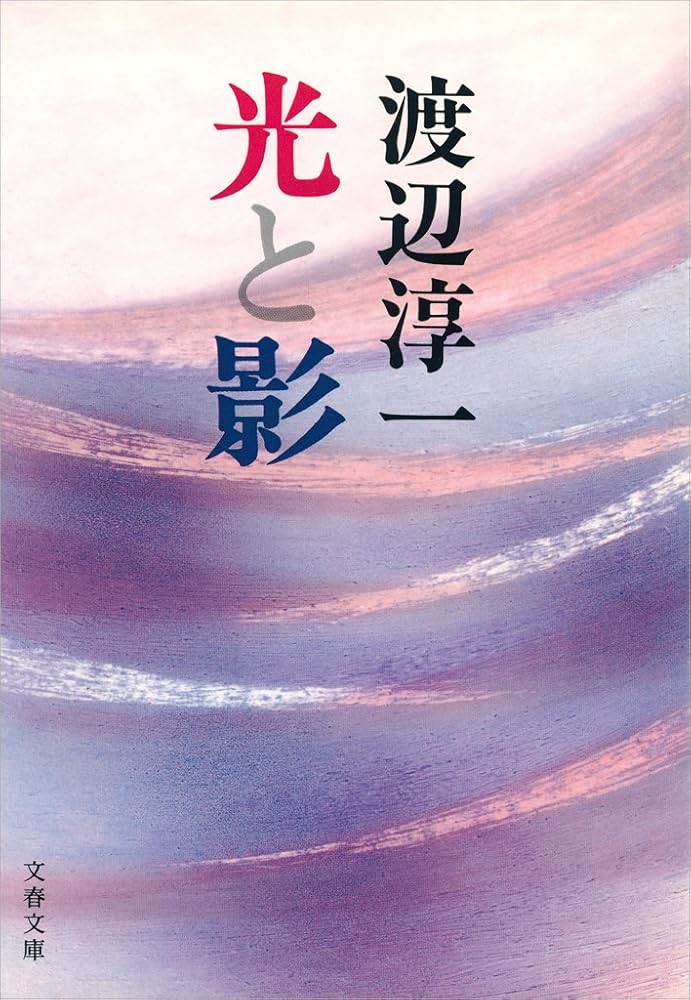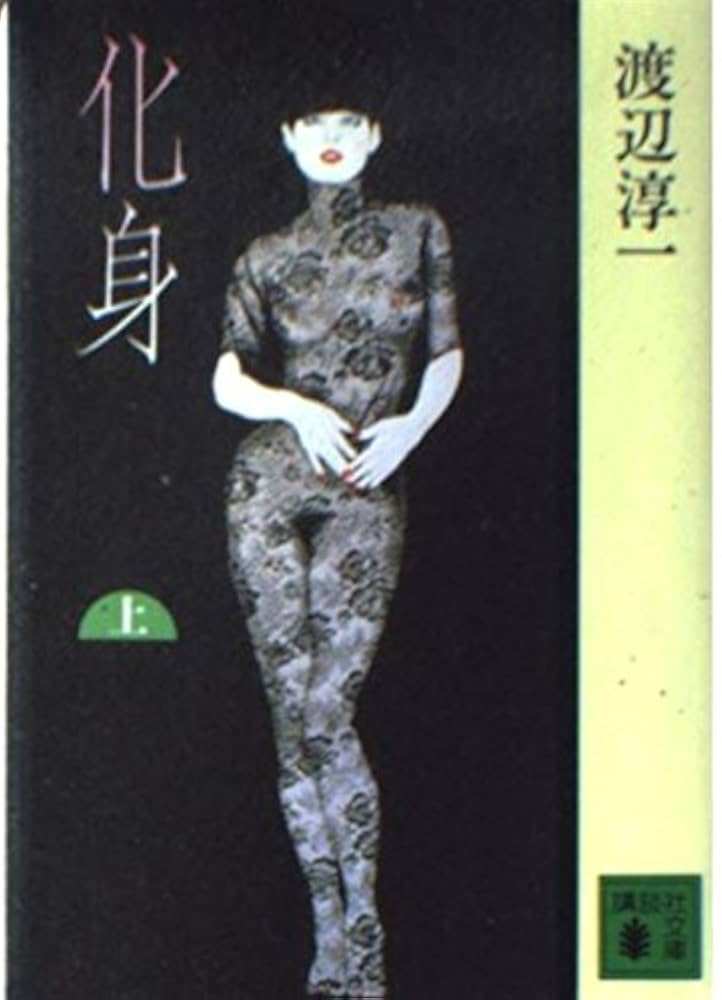小説「麻酔」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「麻酔」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
本作は、作家であり医師でもあった渡辺淳一さんだからこそ描けた、医療の現場が持つ緊張感と、そこに生きる人々の人間模様を深くえぐり出した物語です。ある日突然、平凡で幸せだったはずの家族を襲った悲劇。それは、誰にでも起こりうる、すぐ隣にある恐怖なのかもしれません。
物語は、一件のありふれた手術から始まります。しかし、その手術が引き金となり、一人の女性が意識の戻らない状態に陥ってしまいます。この出来事を境に、夫、子供たち、そして手術を担当した医師たちの運命は、複雑に絡み合いながら、大きく狂い始めていくのです。残された家族の苦悩、罪悪感に苛まれる夫、そして自らの過ちと向き合う医師。それぞれの視点から、この重い現実が描かれていきます。
この記事では、まず物語の骨格となる部分を、結末には触れずにご紹介します。そして後半では、物語の核心に触れながら、登場人物たちの心の動きや、この物語が私たちに問いかけるものは何なのかを、じっくりと考えていきたいと思います。ネタバレを含みますので、未読の方はご注意ください。
渡辺淳一さんが描く、人間の愛と罪、そして再生の物語。その重厚な世界に、一緒に浸ってみませんか。この物語は、単なる医療ドラマではなく、私たちの生き方そのものを問い直す、深い思索に満ちた一冊なのです。
「麻酔」のあらすじ
石鹸会社に勤める福士高伸は、仕事に没頭する一方で、会社の若い同僚である恵理と密かな関係を続けていました。家庭では、妻の邦子が家事一切をこなし、二人の子供、結婚を控えた容子と大学生の浩平も何不自由なく暮らし、福士家は絵に描いたような平穏な毎日を送っていました。高伸にとって、そんな日常は当たり前のもので、その大切さに気づくことはありませんでした。
そんなある日、妻の邦子に子宮筋腫が見つかります。担当医からは「ごく簡単な手術で、1時間ほどで終わります」と説明を受け、高伸も家族も、誰もがその言葉を疑いませんでした。手術当日、高伸は仕事の都合で病院には行かず、すべてが無事に終わるものと信じきっていました。この「簡単な手術」という言葉が、後に重く響いてくることになります。
しかし、手術が終わる時間を過ぎても、病院からの連絡はありません。不安に思った高伸が病院に駆けつけると、そこで告げられたのは信じられない事実でした。手術は無事に終わったものの、邦子は麻酔から一向に覚醒しないというのです。原因は、麻酔導入時のミスの可能性が高いとのこと。昨日まで当たり前にあった日常が、ガラガラと音を立てて崩れ落ちた瞬間でした。
なぜ、簡単なはずの手術でこんなことが起きたのか。医師の説明はどこか歯切れが悪く、高伸の不信感は募るばかりです。意識の戻らない妻を前に、家族は途方に暮れます。約束されていたはずの穏やかな未来は閉ざされ、先も見えない絶望的な現実と、これから長い闘いを強いられることになるのです。
「麻酔」の長文感想(ネタバレあり)
この物語「麻酔」に触れるとき、私の心にまず浮かぶのは、ありふれた日常に潜む「落とし穴」の恐ろしさです。主人公の福士高伸は、仕事もでき、家庭もあり、さらには若い愛人もいる。一見、彼は人生の成功者に見えるかもしれません。しかし、その足元は、彼自身が気づかぬうちに脆く崩れやすいものとなっていたのです。
妻の邦子にすべてを任せきりにした家庭。その外で別の女性と関係を持つ背徳感。物語の冒頭で描かれる彼の日常は、後に彼を苛む罪悪感の伏線として、実に巧みに配置されています。彼が妻の不在によって初めて知る「些細な日常の幸せ」は、失ってからでなければその価値に気づけない人間の愚かさを、痛いほどに突きつけてきます。
渡辺淳一さんは、医師としての経験から、「簡単な手術」という言葉が持つ幻想と危険性を、誰よりも深く理解していたのでしょう。作中で何度も繰り返されるこの言葉は、読者にも「大丈夫だろう」という安心感を与えます。だからこそ、邦子が目覚めないという事態が起こったときの衝撃は、計り知れないものがあります。医療に「絶対」はない。この冷徹な事実を、私たちは物語を通して突きつけられるのです。
悲劇の引き金となった麻酔科医・野中のミスは、「麻酔中に席を外した」という、あまりにも人間的な怠慢でした。これが予測不能なアレルギー反応や、極めて困難な状況下での判断ミスであったなら、物語の様相は違っていたかもしれません。しかし、原因が「防げたはずの不注意」であるからこそ、残された家族の怒りと無念は、より深く、やり場のないものとなるのです。
妻が植物状態に陥ったことで、高伸の人生は一変します。かつての愛人であった恵理との関係は、もはや耐え難い罪悪感の象徴でしかなくなり、彼は彼女との関係を断ち切ります。そして、意識のない妻への、常軌を逸したともいえる献身が始まるのです。彼の心の中は、後悔と贖罪の念で渦巻いていたことでしょう。
私がこの物語で最も心を揺さぶられた描写の一つが、高伸が夜の病室で、意識のない邦子の体を愛撫する場面です。これは単に性的な衝動として描かれているのではありません。言葉の通じない妻に対して、彼に残された唯一のコミュニケーション手段が、かつて夫婦であった頃の根源的な身体の言語だったのです。それは、失われた妻を取り戻したいという彼の絶望的な叫びであり、痛切な愛の表現に他なりません。
この悲劇は、子供たちの未来にも暗い影を落とします。結婚を目前に控えていた娘の容子は、母親の不幸を前にして、自分だけが幸せになることへの罪悪感に苛まれます。マリッジブルーに陥る彼女の姿は、家族という共同体が負った傷の深さを物語っています。
一方、息子の浩平は、怒りを剥き出しにします。彼は、父親である高伸の不倫を知り、激しく反発します。母親が吹き込んだ留守番電話のメッセージを、いつまでも消すことができない彼の行動は、この非情な現実を受け入れられない、彼の悲痛な心の叫びそのものでした。家族は、外からの悲劇によって、内側からも崩壊の危機に瀕していたのです。
物語には、高伸の苦悩を映し出す、もう一つの重要な出来事が挿入されます。彼が勤務先の会社で、シャンプーとリンスを取り違えるという、重大なミスを犯してしまうのです。これは、医療ミスを犯した野中医師と、それを糾弾する立場であった高伸の状況を反転させる、見事な仕掛けです。
この自らの失敗を通じて、高伸は初めて、人間は誰でも過ちを犯す可能性があるという、当たり前の、しかし厳しい現実に直面します。怒りに燃えていた彼の心に、わずかながらも、ミスを犯した野中医師の立場を想像する余地が生まれます。この出来事は、彼の人間的な成長において、決定的な転換点となったのではないでしょうか。
物語の視点は、やがて苦悩する医師・野中へと移ります。彼もまた、単純な悪人として描かれてはいません。自らが犯したミスの重さに苛まれ、組織の一員として病院を守らねばならないという圧力との間で引き裂かれます。彼の内面的な葛藤を描くことで、この物語は、個人の責任を追及するだけでなく、医療システム全体が抱える問題をも示唆しているのです。
病院側の初期対応は、責任回避としか言えないものでした。真実を知りたいと願う家族の問いかけは、曖昧な言葉ではぐらかされ、彼らは深い無力感に苛まれます。医療という専門性の高い密室で起きた出来事に対して、素人が真実を解き明かすことの困難さを、まざまざと見せつけられます。
最終的に病院側が提示した和解金は、8000万円でした。人の命、失われたかけがえのない時間を、お金に換算することの虚しさ。しかし、疲れ果てた家族にとって、それを受け入れる以外に道は残されていませんでした。これは、悲劇に対する社会的な「落としどころ」の限界を示しており、読者にやるせない気持ちを抱かせます。
物語は、クライマックスに向けて、一つの希望の光を灯します。それは、娘・容子の結婚式です。深い悲しみの中、それでも未来へ向かって人生を続けていこうとする家族の決断は、痛ましくも、力強い輝きを放っています。邦子の不在という大きな穴を抱えながらも、家族は一つの祝祭を執り行うのです。
そして、小説における最も感動的な場面が訪れます。結婚式を終えた高伸が、病床の妻にそのことを報告した、まさにその時、奇跡が起こります。娘の晴れ姿を心で聞いたかのように、邦子が大きく目を見開いたのです。それが医学的に意味のある反応だったのか、単なる筋肉の反射だったのか、答えはありません。
しかし、この一瞬の出来事が、絶望の淵にいた家族にとって、どれほど大きな救いとなったことか。それは、言葉にならないほどの感動と、最後の贈り物でした。この曖昧さこそが、この場面の持つ力を最大限に引き出しており、読者の涙を誘わずにはいられません。
この束の間の奇跡の後、家族は最も辛い決断を下します。邦子の生命維持を終えることに同意したことが、静かに示唆されます。娘の結婚という新たな始まりの直後に訪れる、母の死という終わり。この鮮やかな対比は、人生の光と影を強烈に描き出しています。
物語は、それぞれの登場人物が、この悲劇をどう乗り越え、その後を生きていくのかを描いて、静かに幕を閉じます。野中医師は、自らの意思で福士家を訪れ、心からの謝罪をします。浩平は、母の声を消去し、未来へ歩み出す決意を固めます。そして高伸は、失ったもののかけがえのなさを胸に刻み、変えられた人間として、残りの人生を生きていくのです。そこに描かれるのは幸福な結末ではありませんが、ある種の「清々しさ」に満ちています。
渡辺淳一さんがこの物語で一貫して伝えたかったのは、「科学や技術がどれほどすすんでも、それを扱うのは人間であり、人間が扱う以上、思いもしない事故が起きる可能性がないとはいいきれない」という事実でしょう。これは、医療現場に限らず、私たちの社会全体に対する、深い警句でもあるのです。
まとめ
渡辺淳一さんの小説「麻酔」は、医療ミスという一つの悲劇を軸に、人間の愛憎、罪と赦し、そして家族の再生を描ききった、重厚な人間ドラマでした。簡単な手術で妻が植物状態になるという衝撃的な出来事は、登場人物たちの人生を根底から揺るがします。
物語は、単純に医師の責任を追及するだけでは終わりません。過ちを犯してしまった医師の苦悩や、組織防衛に走る病院の姿、そして何より、残された家族が悲しみの中でいかにもがき、傷つけ合い、それでも絆を取り戻そうとする過程が、克明に描かれています。
特に、主人公である夫・高伸が、自らの不倫という過去の罪と向き合いながら、意識のない妻に献身を尽くす姿は、複雑で、深く、心を打ちます。そして、絶望の果てに訪れる、ほんの束の間の奇跡と、その後の家族の決断。悲劇の中にも、確かな救いと希望の光が示されています。
この物語を読み終えたとき、私たちは、日常のすぐ隣にある不条理さと、それでも生きていくことの重みを、改めて感じさせられるでしょう。人間の強さと弱さを見つめ続けた渡辺淳一さんだからこそ描けた、忘れがたい一作です。