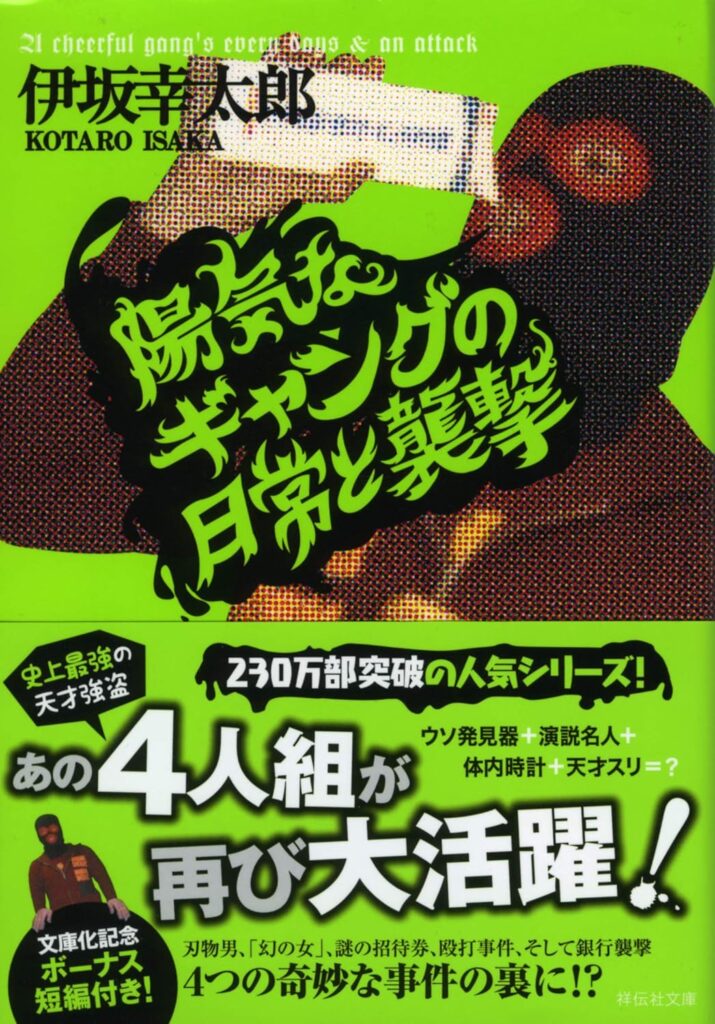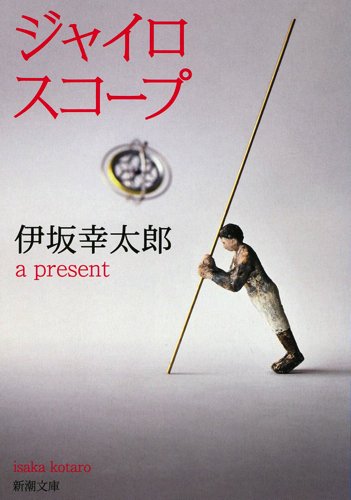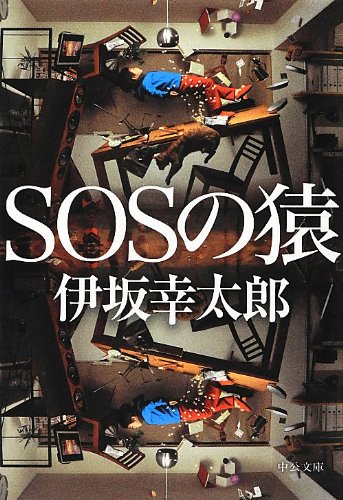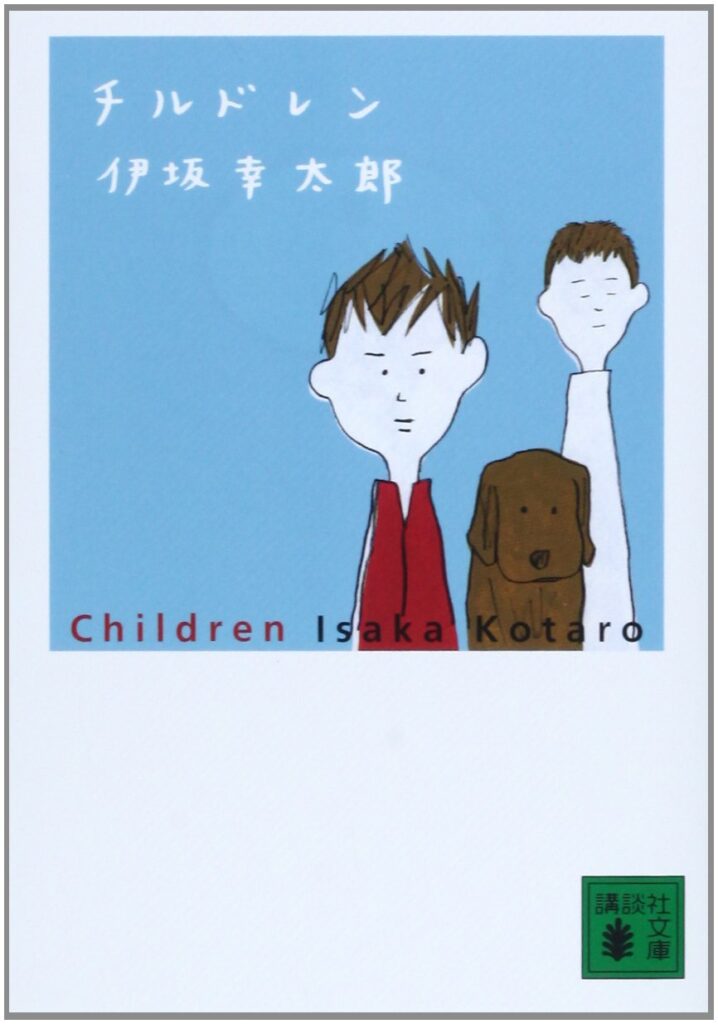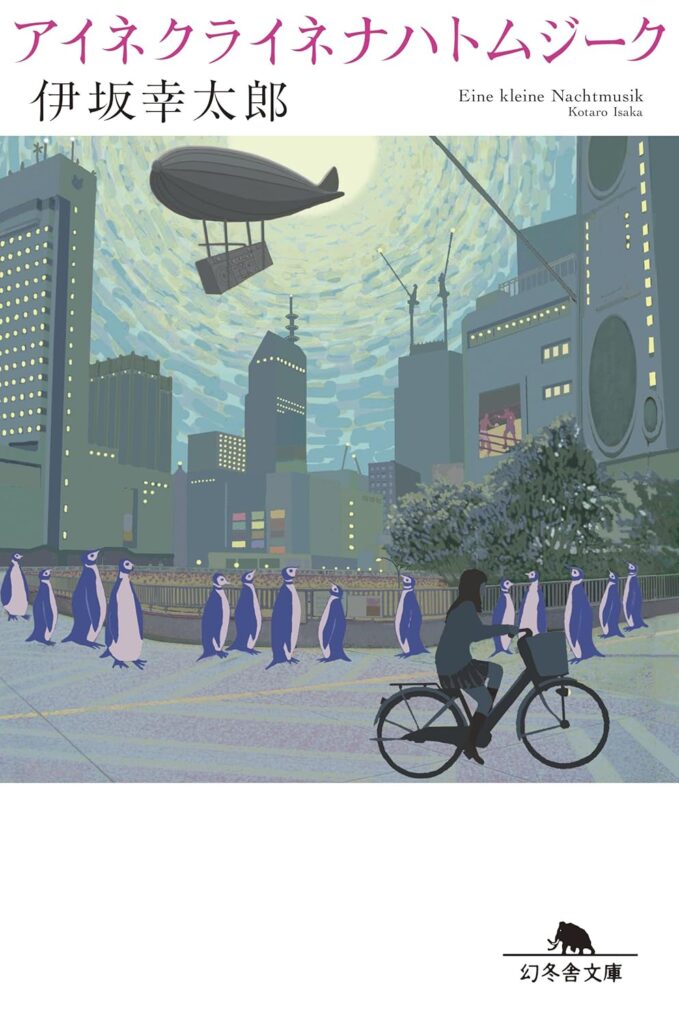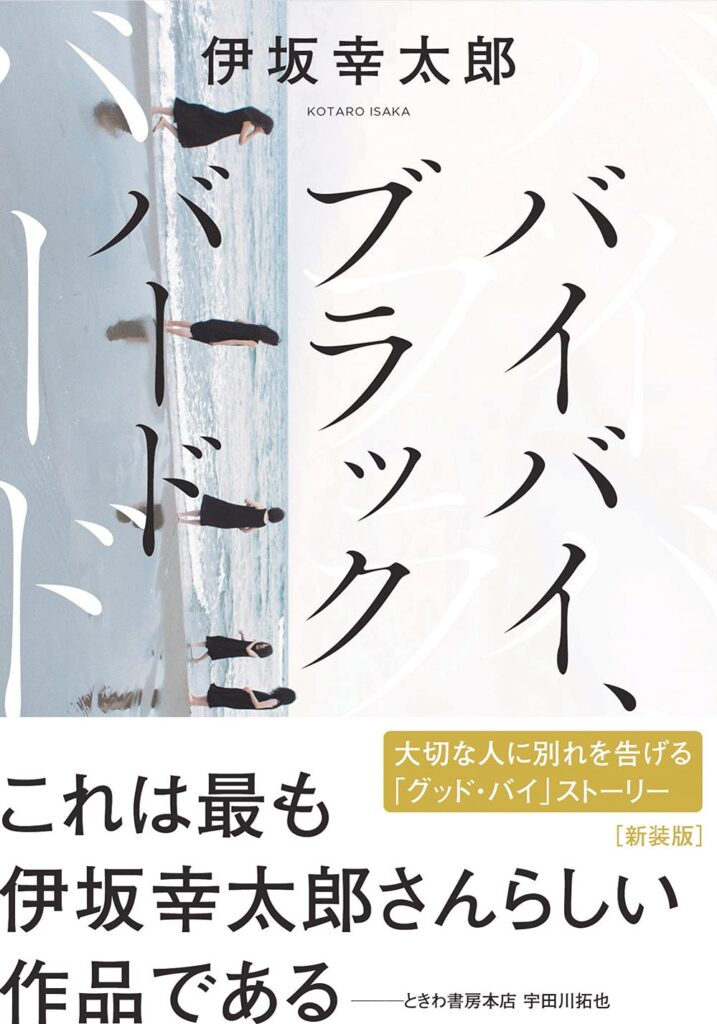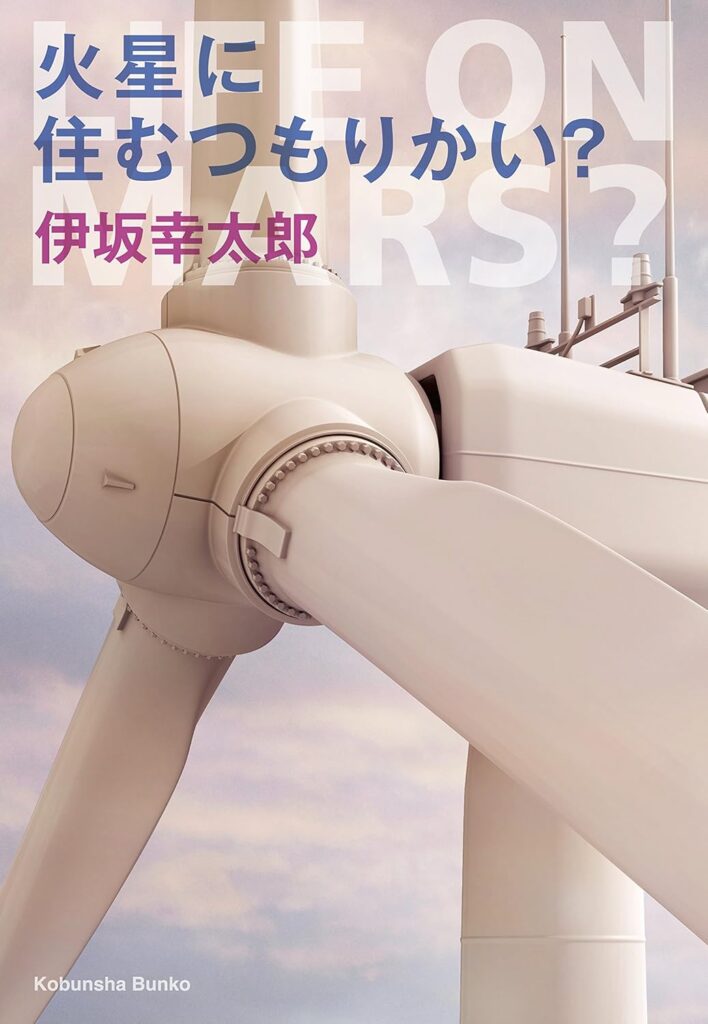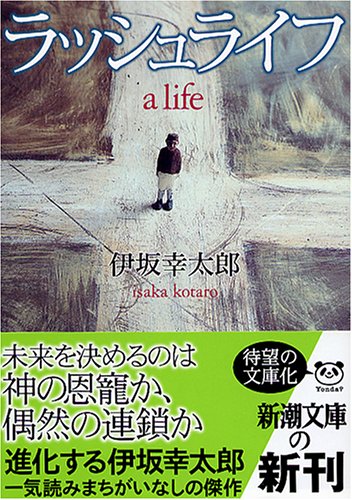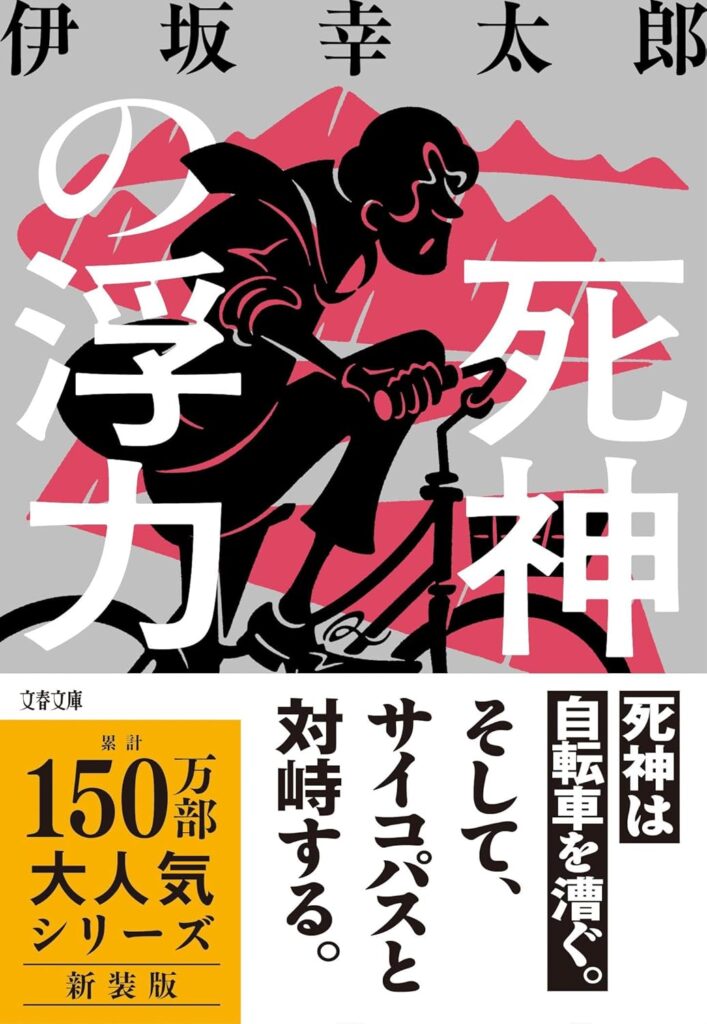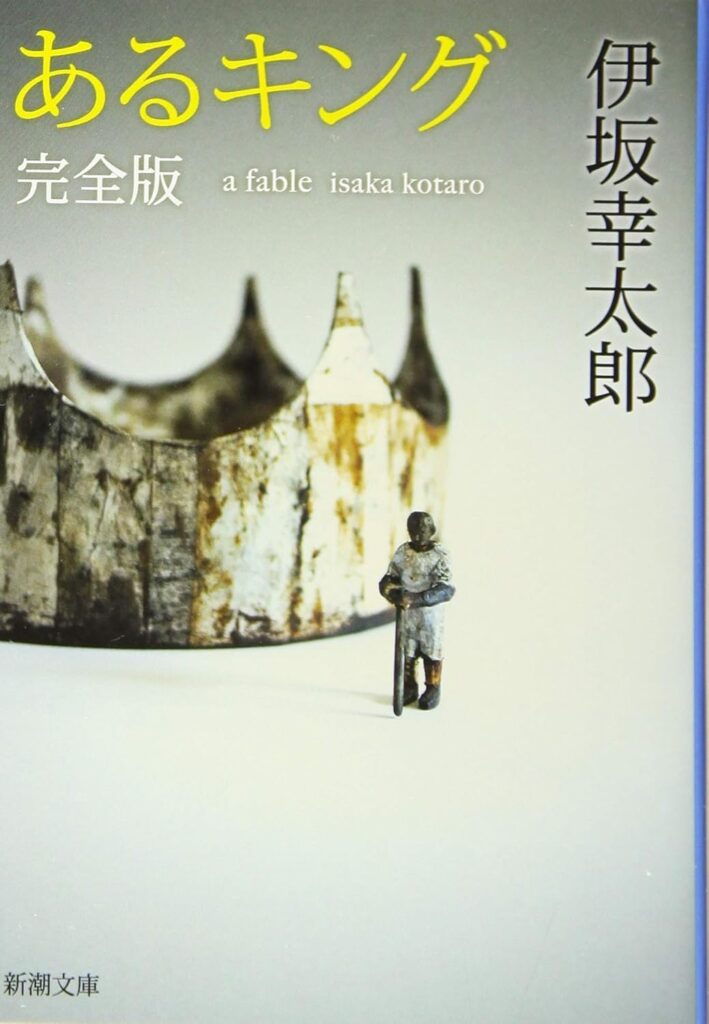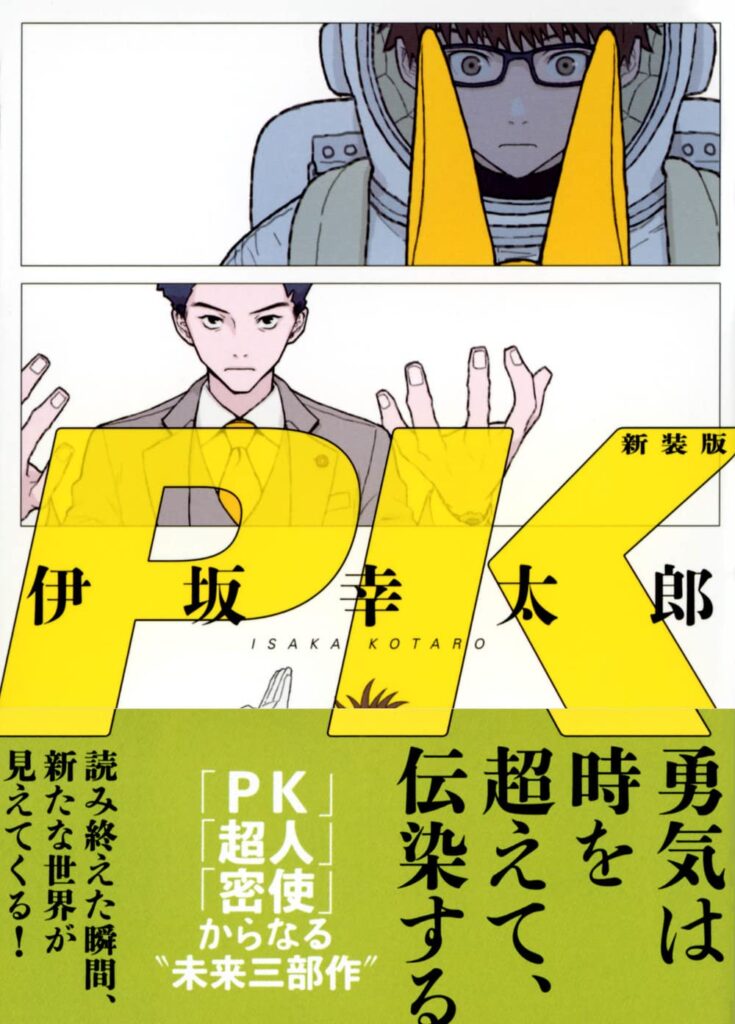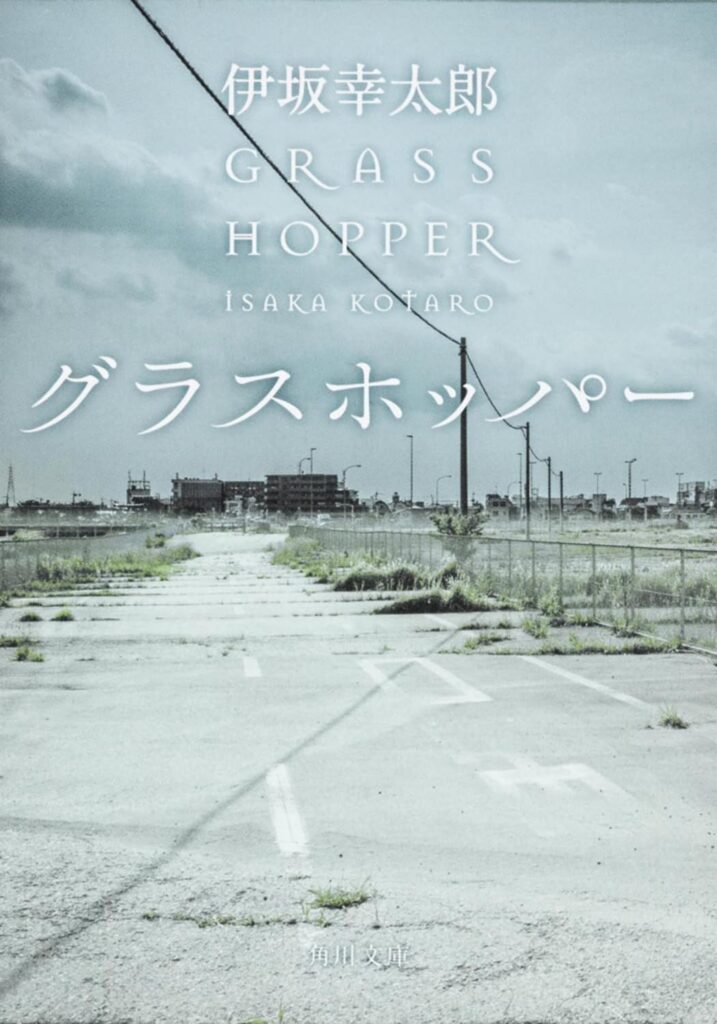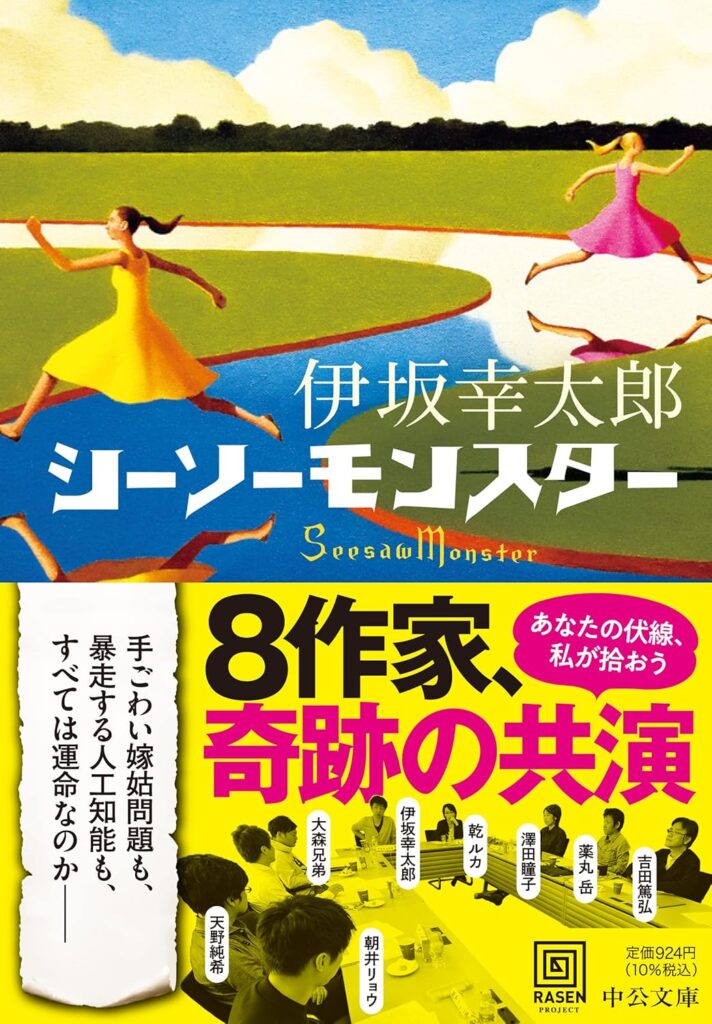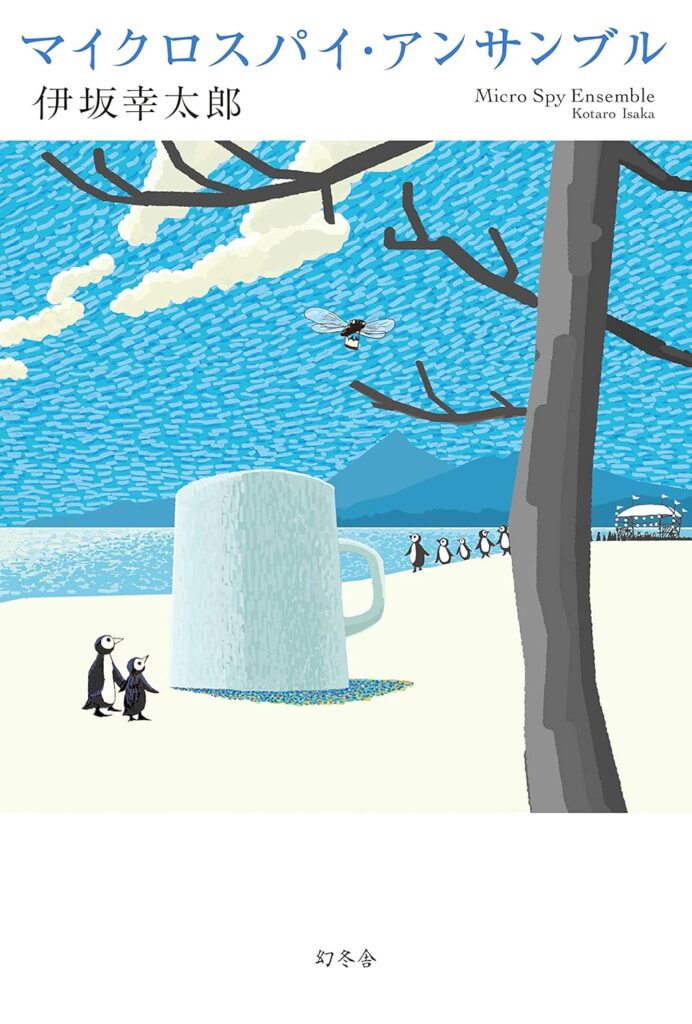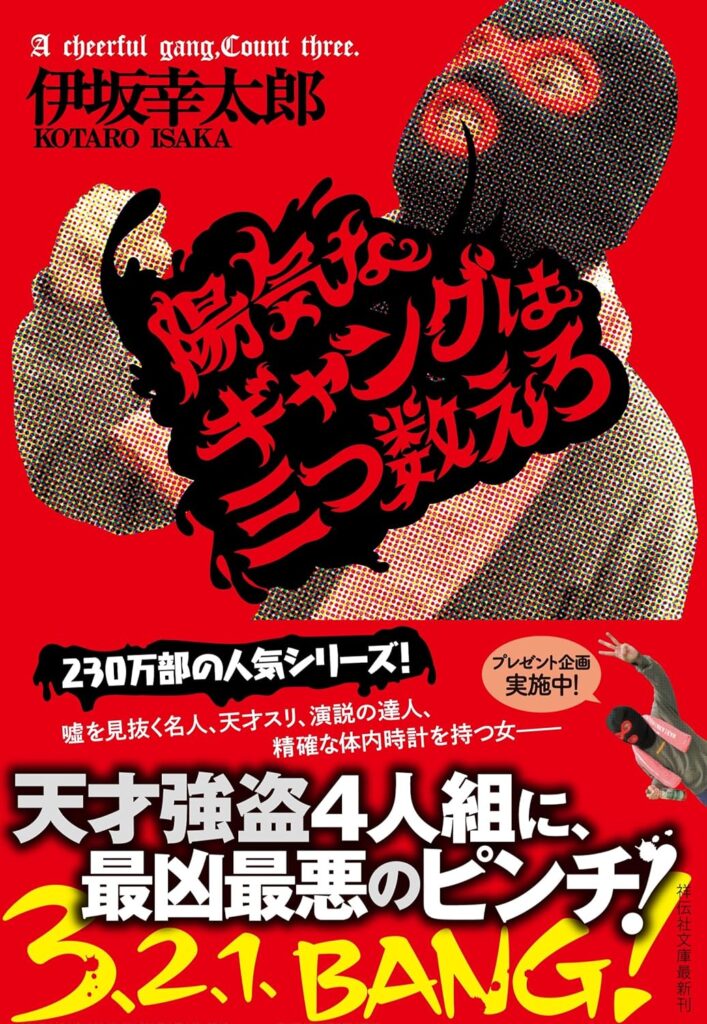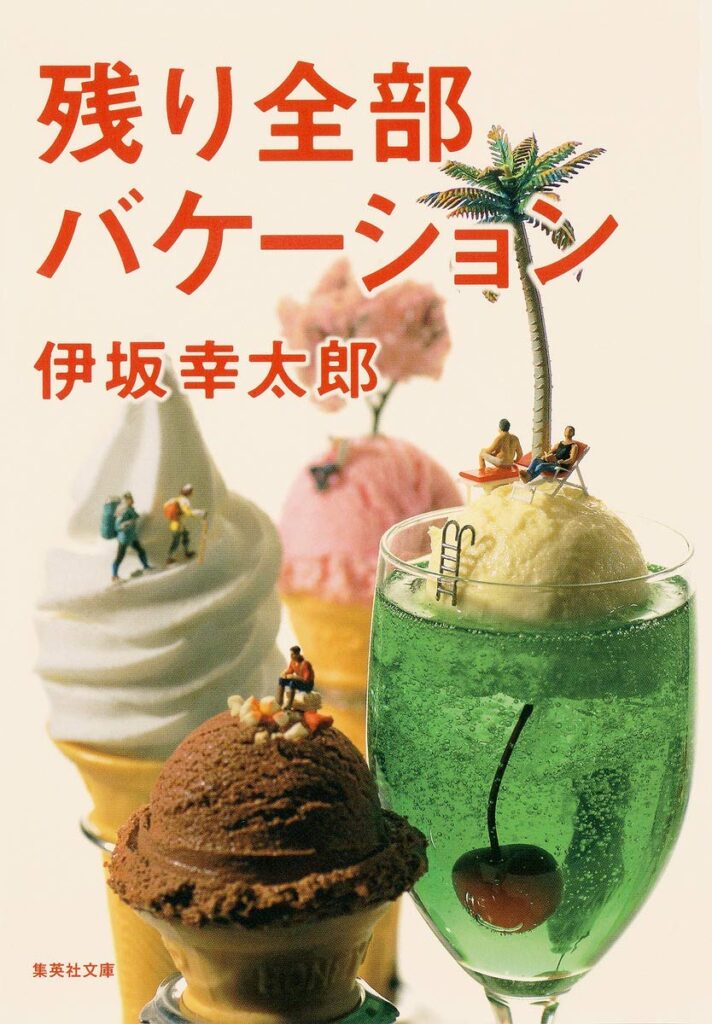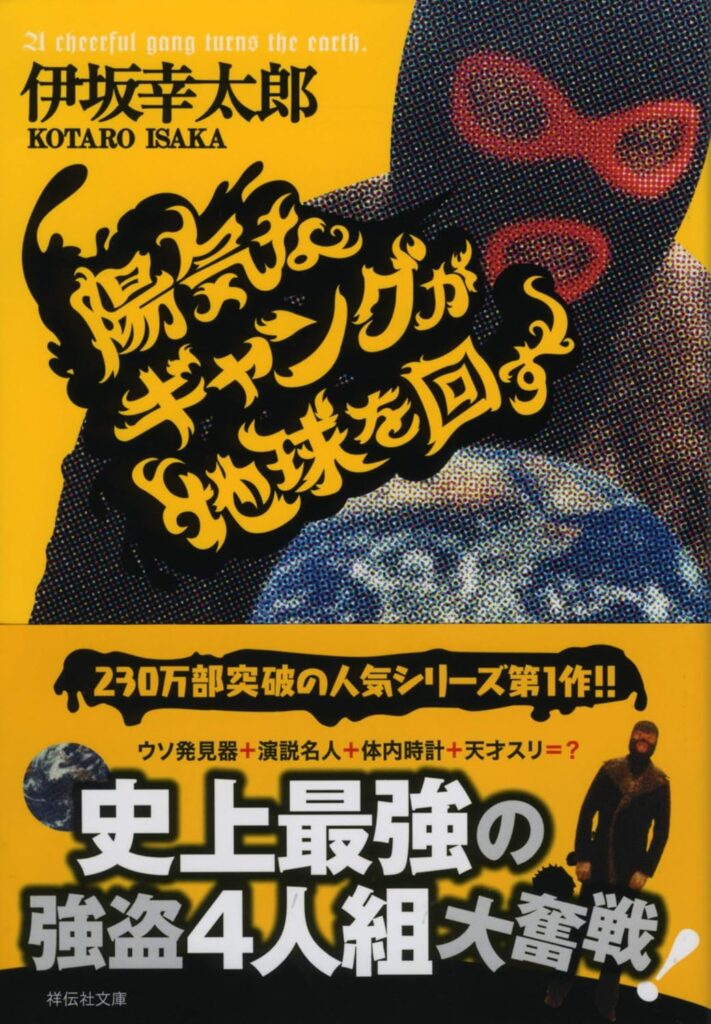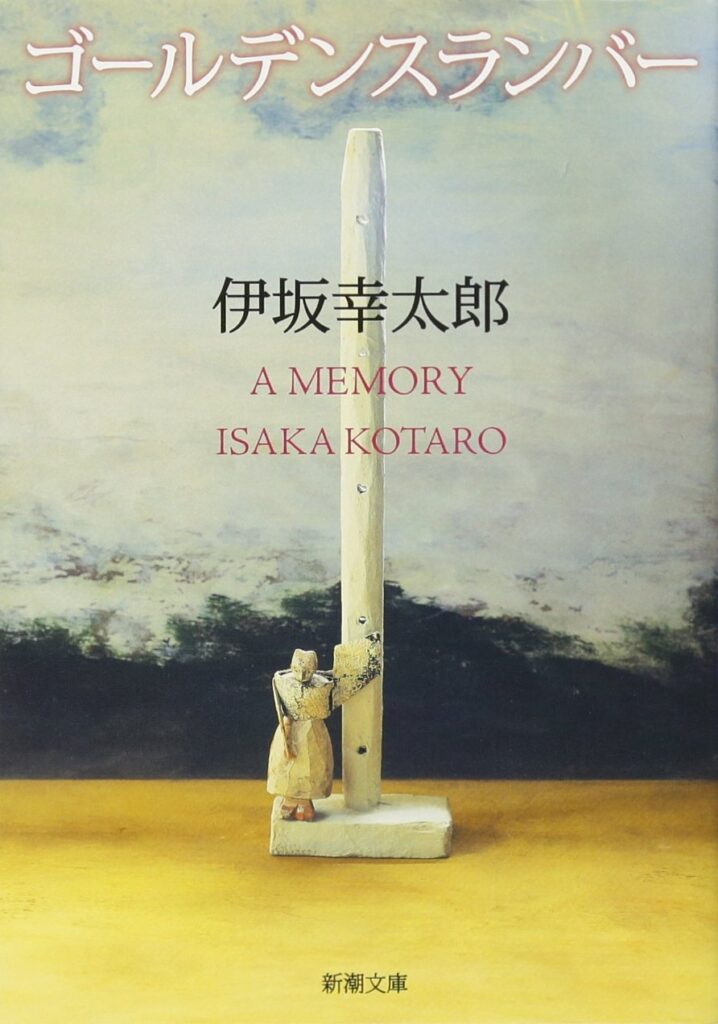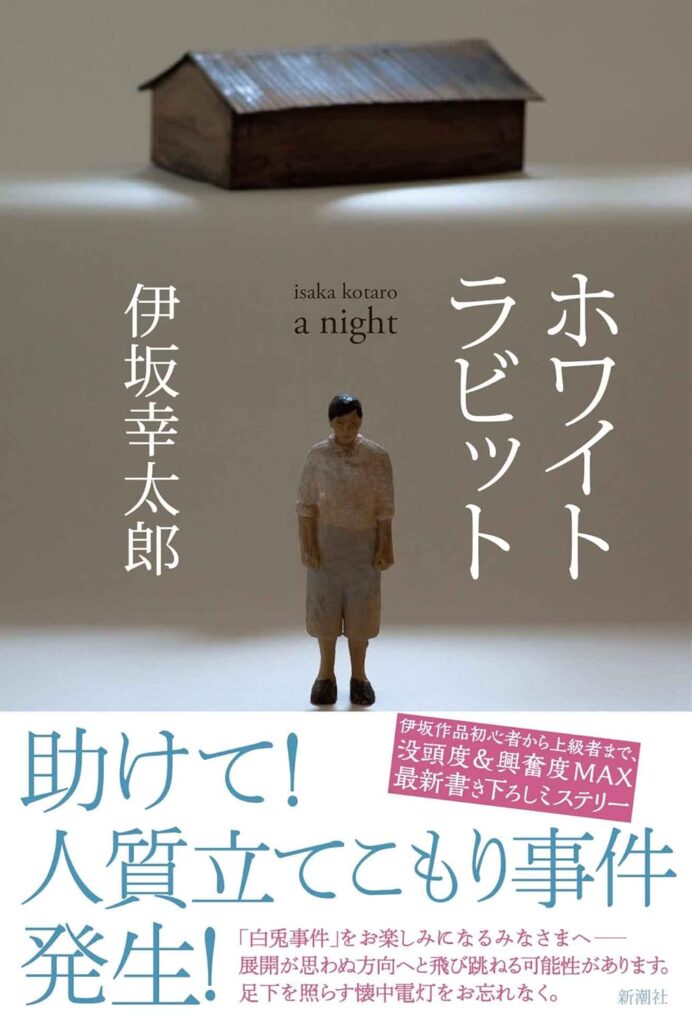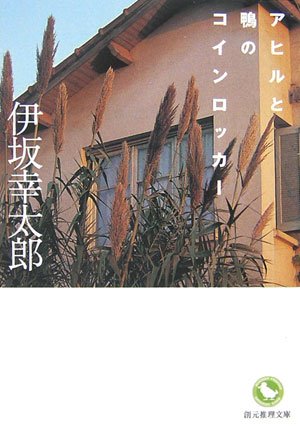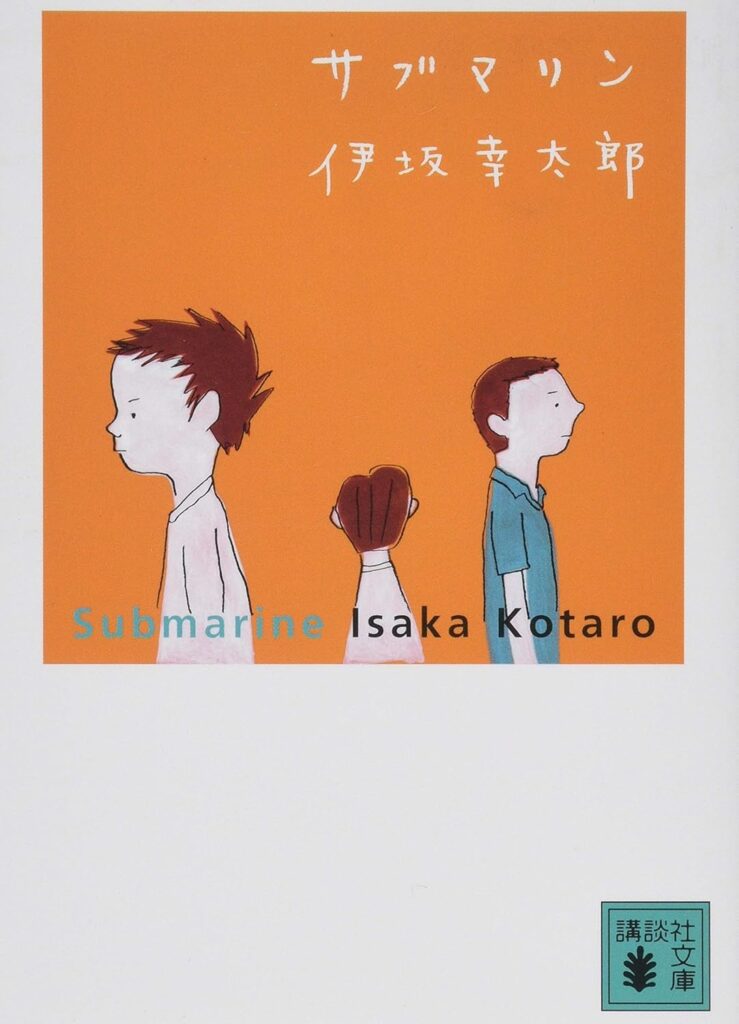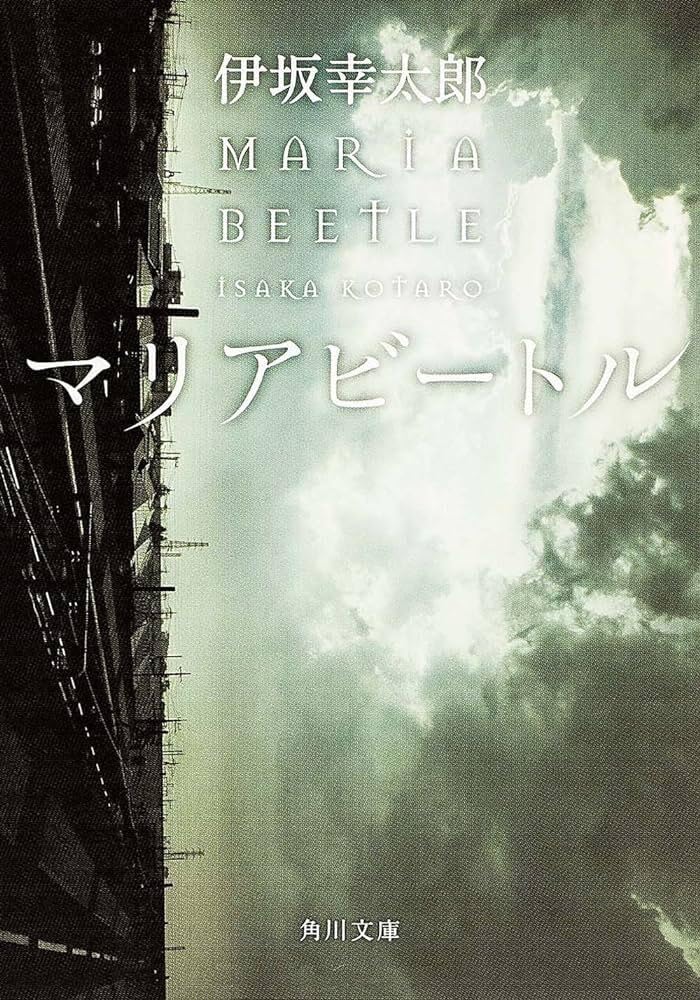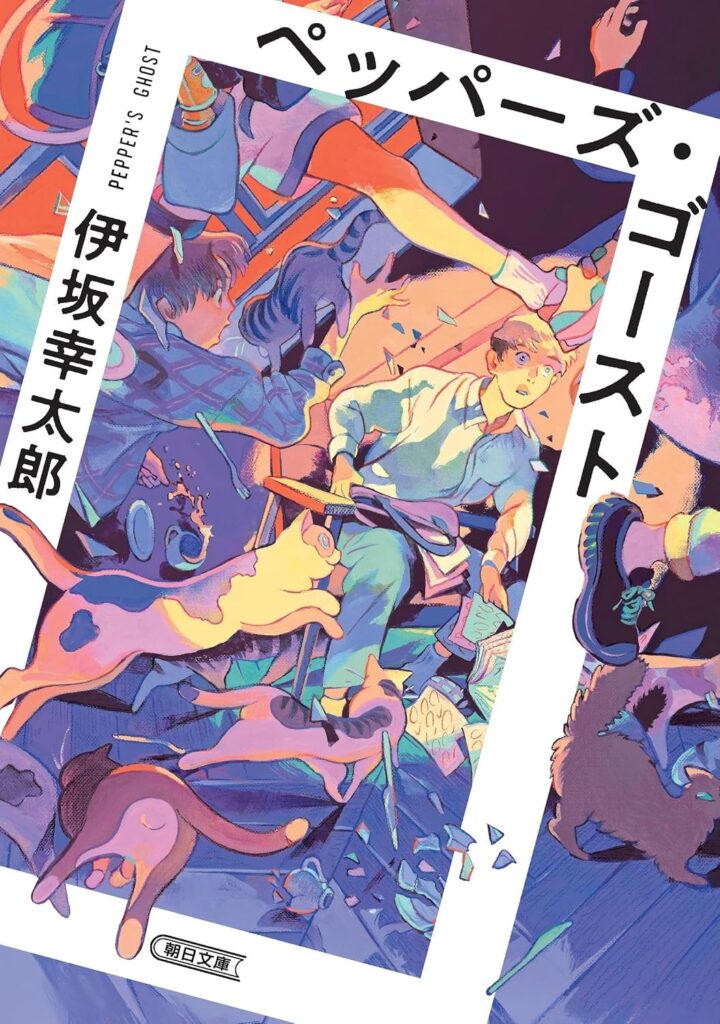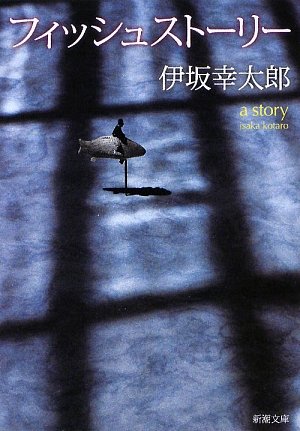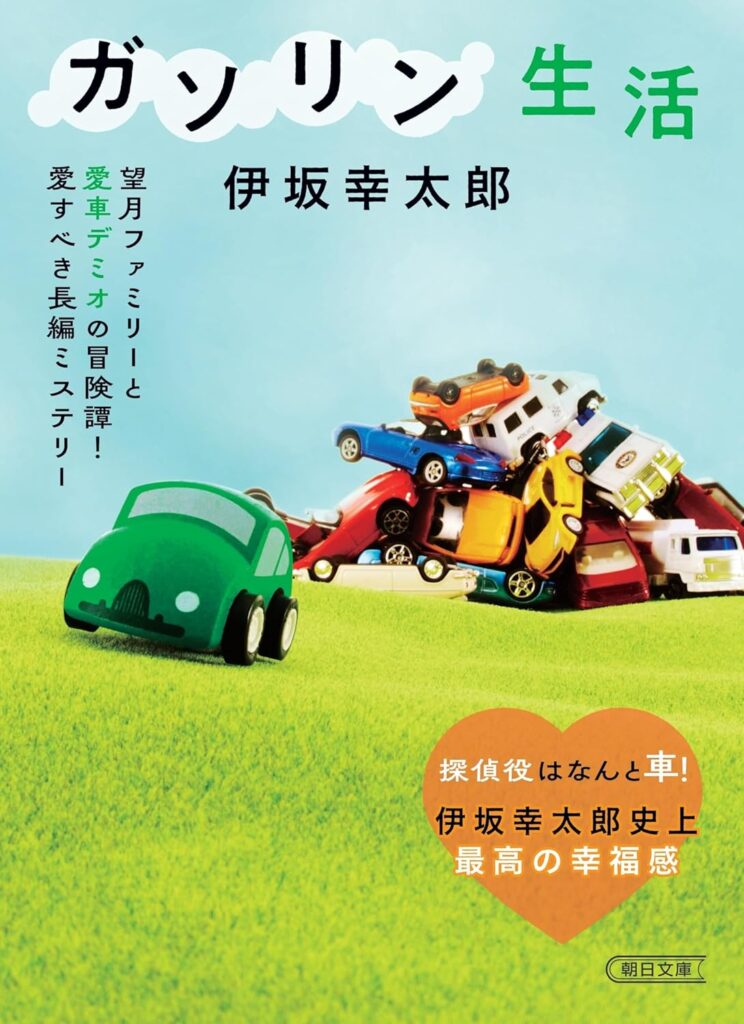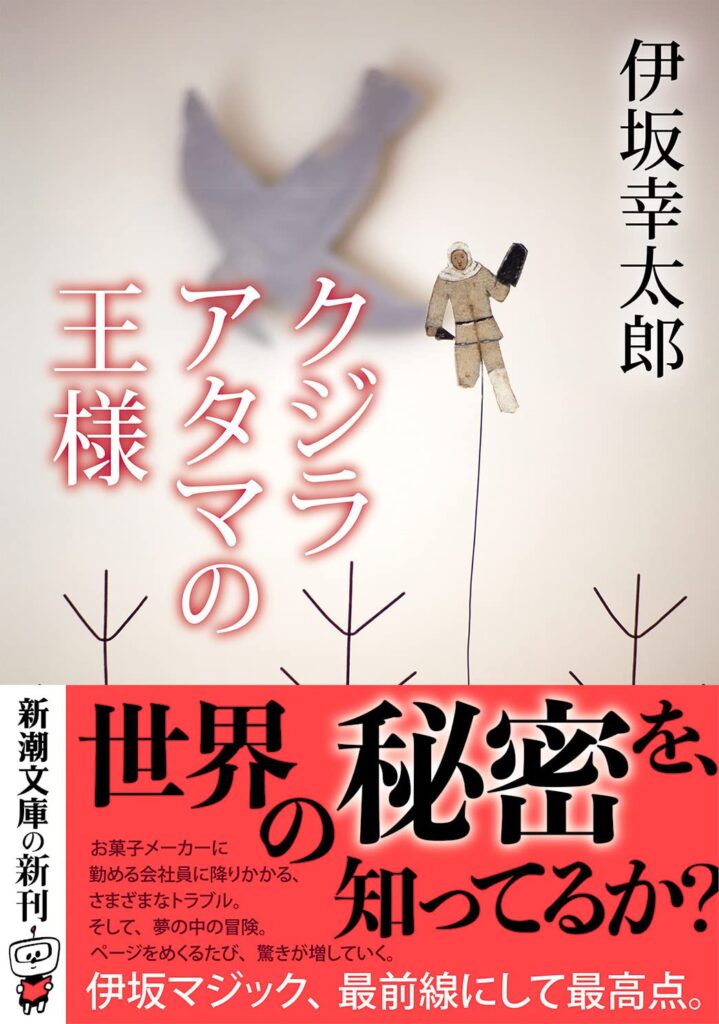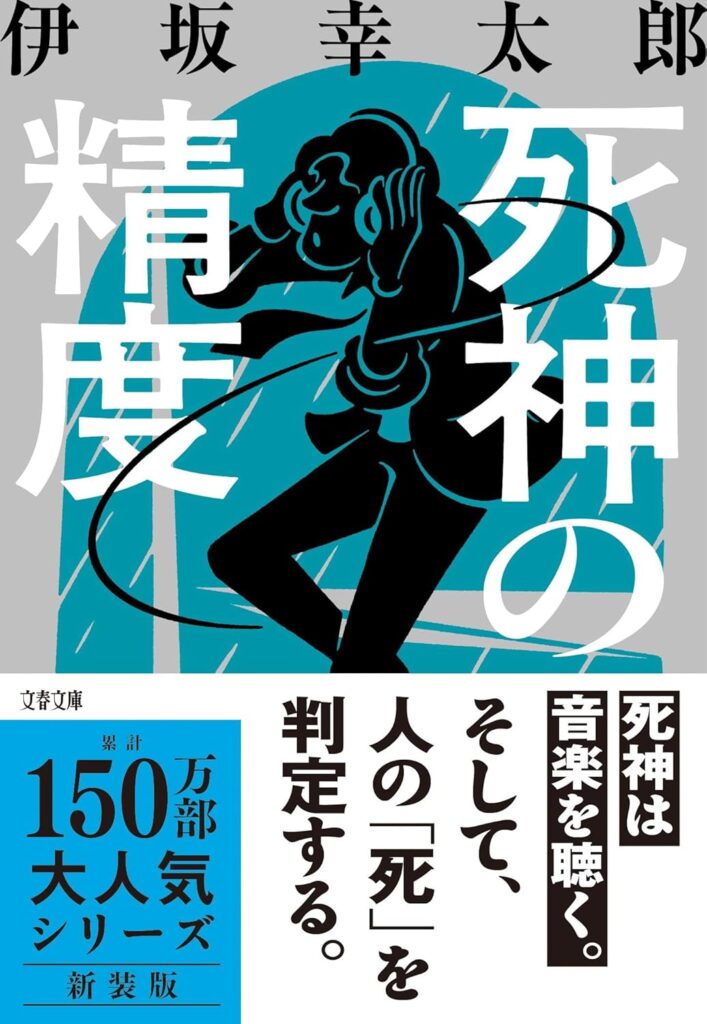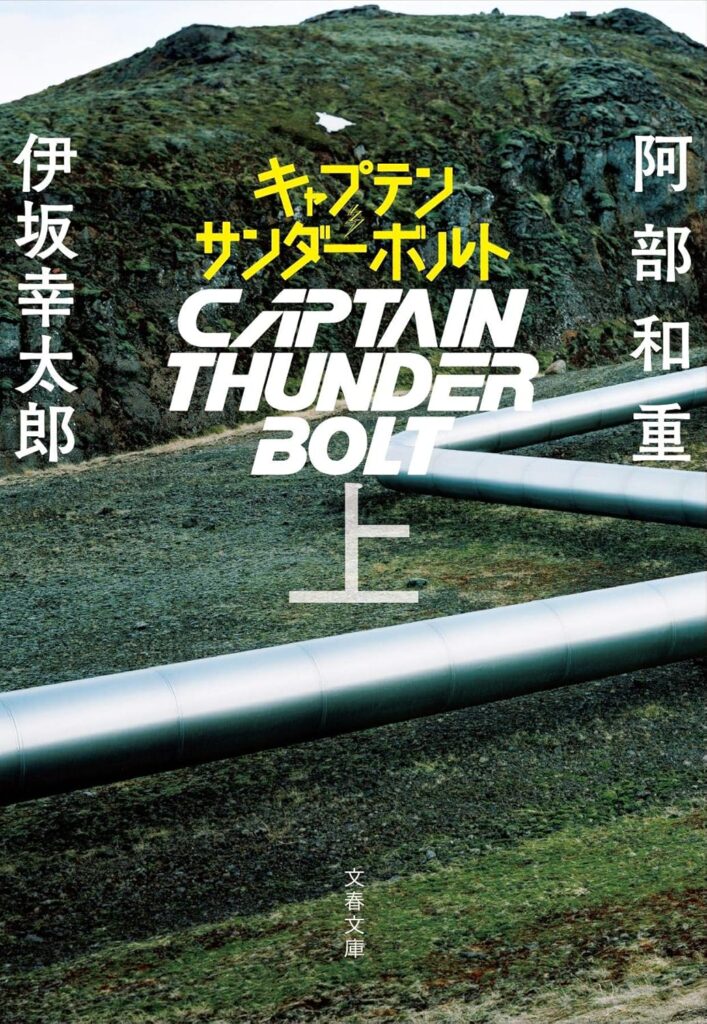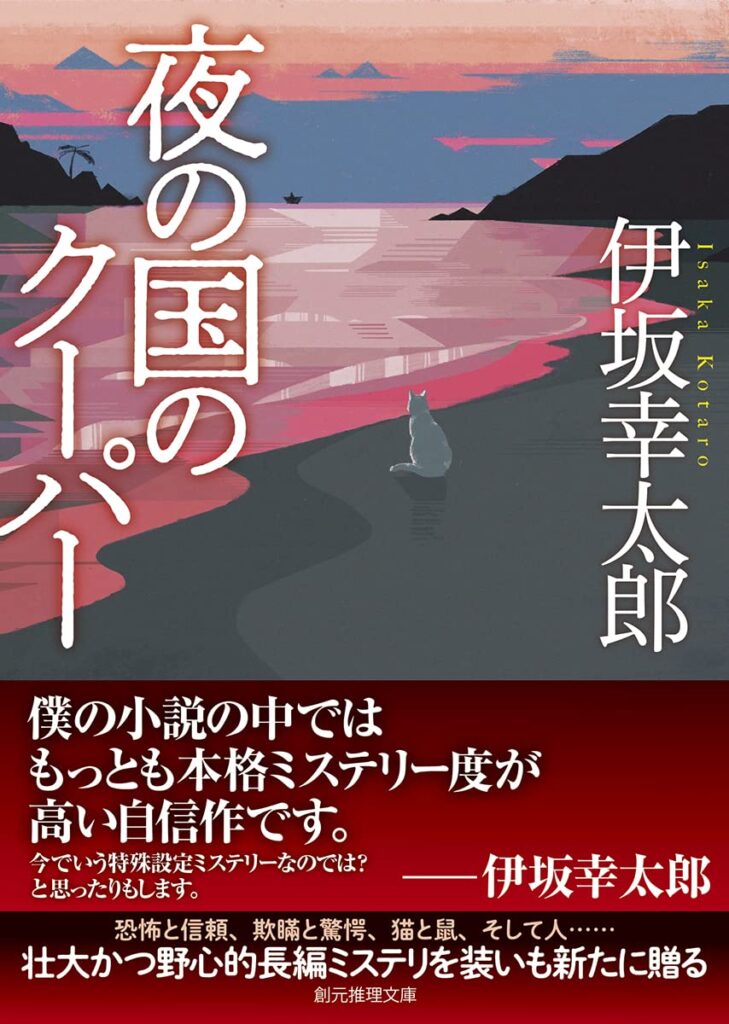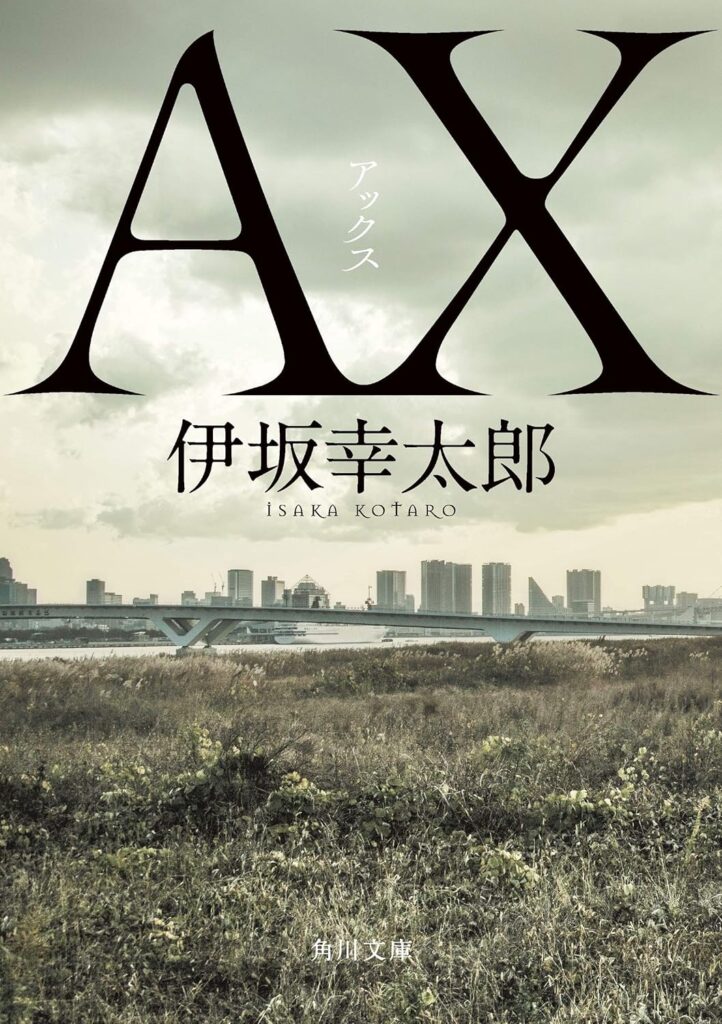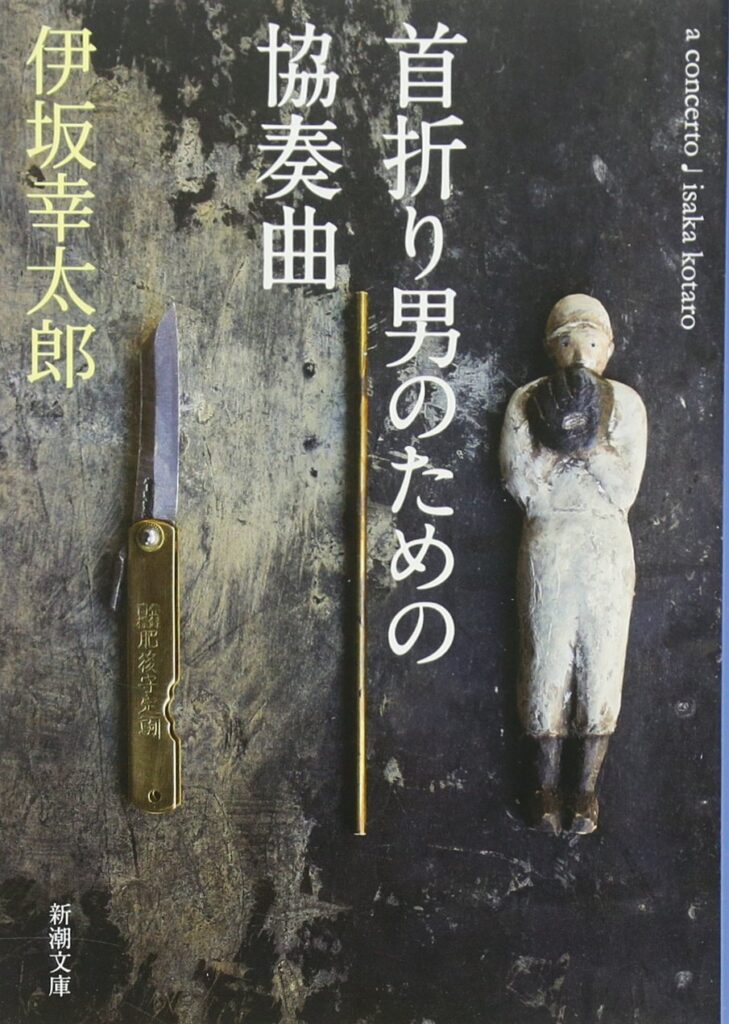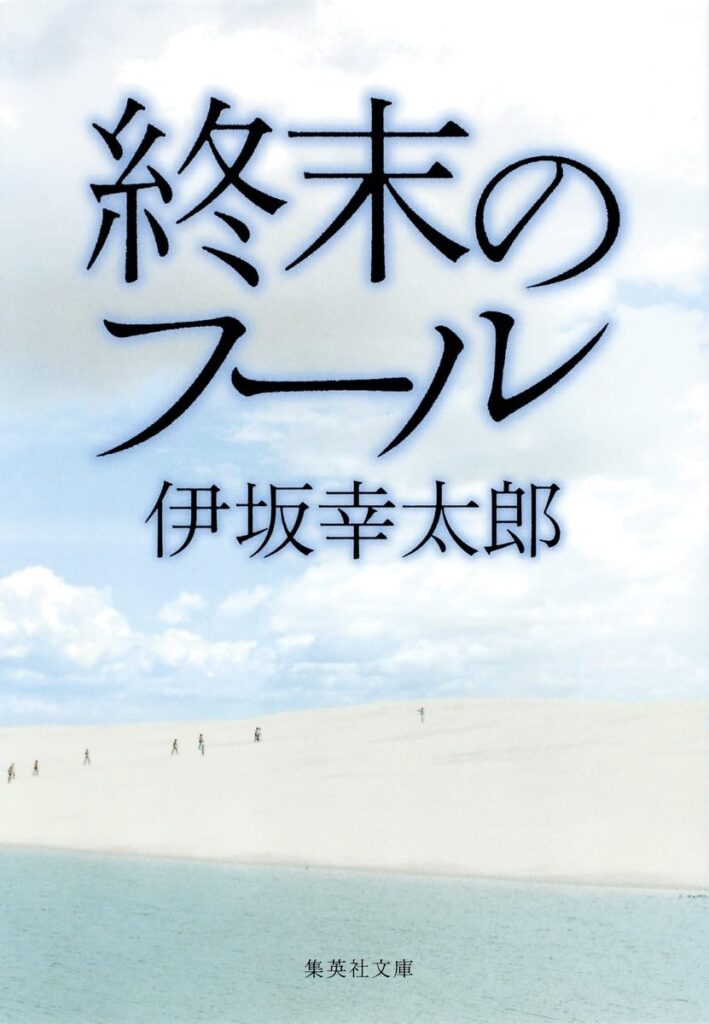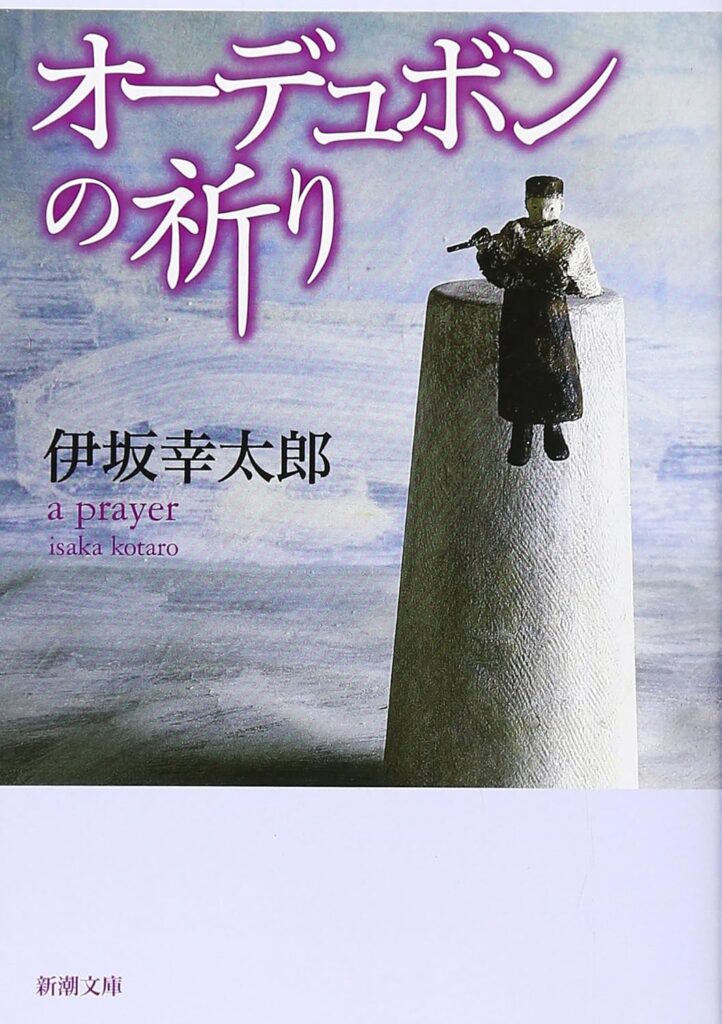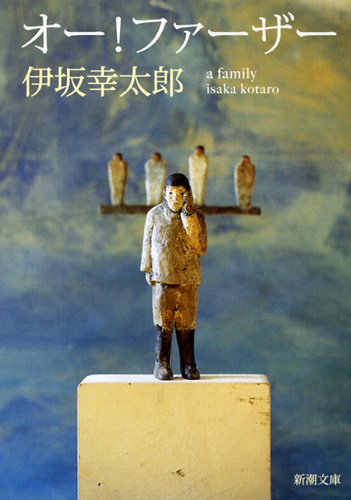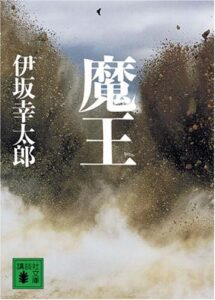 小説「魔王」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。伊坂幸太郎さんが描く、少し不思議な力を持った兄弟が、巨大な存在に立ち向かおうとする物語です。現代社会が抱える空気感や、流されやすい人々の心理に、静かに、しかし鋭く切り込んでいく作品と言えるでしょう。
小説「魔王」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。伊坂幸太郎さんが描く、少し不思議な力を持った兄弟が、巨大な存在に立ち向かおうとする物語です。現代社会が抱える空気感や、流されやすい人々の心理に、静かに、しかし鋭く切り込んでいく作品と言えるでしょう。
物語は、ごく普通の会社員である兄・安藤が、ある日突然、自分が念じた言葉を他人に言わせることができる「腹話術」という能力に目覚めるところから始まります。彼はその力を使って、世の中のちょっとした理不尽に立ち向かおうとしますが、やがて急速に支持を集める若い政治家・犬養の存在に言い知れぬ危機感を覚えます。人々を扇動し、大きな流れを作っていく犬養に対し、安藤はたった一人で、その流れを止めようと試みます。
この記事では、兄・安藤の物語「魔王」と、その五年後を描く弟・潤也の物語「呼吸」を合わせて、物語の詳しい流れを追いながら、そこに込められたメッセージや登場人物たちの心の動きを、ネタバレを交えつつ詳しく読み解いていきます。特に、作品を読んだ後に感じたことや考えたことを、たっぷりと書き記していますので、すでに読まれた方も、これから読もうと考えている方も、ぜひご覧ください。
小説「魔王」のあらすじ
物語は、会社員の安藤が通勤電車の中で体験した奇妙な出来事から幕を開けます。席を占領する若者に注意できない老人を見て、「もし自分が老人だったらこう言うのに」と考えた瞬間、その老人が安藤の考えた通りの言葉を若者にぶつけたのです。最初は偶然かと思いましたが、会社でも同様の現象が起こり、安藤は自分が「念じた言葉を相手に言わせる力」を持っていると確信します。彼はこの力を「腹話術」と名付け、その使い方や限界について考察を始めます。バー「ドゥーチェ」で実験を重ねるうち、相手を見ていないと力は発動しないことなどを突き止めます。
そんな中、安藤は未来党の党首である犬養舜二という政治家に注目します。テレビで見た犬養の言葉や振る舞いから、彼が首相になれば日本がファシズムのような危険な方向へ進むのではないかという強い不安を抱きます。犬養の人気は日増しに高まり、社会には排他的な空気が漂い始めます。安藤の弟・潤也とその恋人・詩織と遊園地に行った際には、乗るはずだったアトラクションの席が事故で大破するという出来事もあり、安藤は自分の命が狙われている可能性すら感じ始めます。アメリカ人の友人アンダーソンの家が放火される事件も起こり、安藤の危機感は頂点に達します。
犬養が街頭演説を行うと知った安藤は、「腹話術」を使って犬養に不適切な発言をさせ、彼の評判を落とそうと計画します。しかし、演説会場には安藤の力を妨害する能力を持つ人物、バー「ドゥーチェ」のマスターが待ち構えていました。安藤の計画は失敗し、彼は力の衝突による消耗で倒れてしまいます。安藤はこの出来事の後、命を落とすことになります。彼が恐れた通り、犬養はやがて日本の首相の座に就くのでした。
安藤の死から五年後、物語の視点は弟の潤也に移ります。潤也は詩織と結婚し、仙台で暮らしていました。兄の死後、潤也には不思議な能力が備わっていました。それは「じゃんけんで絶対に負けない」という「幸運」の力です。ある日、兄の友人だった島と再会した潤也は、彼が未来党員となり、犬養の側近として活動していることを知ります。また、ドゥーチェのマスターも犬養の周辺に関わっており、犬養の周りで起こる不審な出来事には超能力が関与しているのではないか、そして兄・安藤もその犠牲になったのではないかという疑念を深めます。潤也は、兄が立ち向かおうとしたものに、自分なりの方法で向き合うことを決意します。彼は「幸運」の力を使って競馬で莫大な資金を得て、来るべき時に備えるのでした。
小説「魔王」の長文感想(ネタバレあり)
伊坂幸太郎さんの『魔王』を読むと、いつも私たちの周りを取り巻く「空気」のようなものについて考えさせられます。それは目に見えないけれど、確かに存在していて、時に私たちを特定の方向へと強く押し流そうとする力です。この物語は、そんな抗いがたい流れの中で、個人がどう考え、どう行動するのかを問いかけてくる作品だと感じています。
物語は二部構成になっています。第一部「魔王」では兄の安藤が、第二部「呼吸」では弟の潤也が、それぞれの視点と能力で、巨大化していく政治家・犬養とその支持者たちが作り出す社会のうねりに向き合っていきます。
まず、兄の安藤についてです。彼はごく普通の会社員ですが、「考えろ、考えろ」と自分に言い聞かせながら物事を深く考察する癖があります。この「考える」という行為が、物語全体を貫く重要なテーマになっているように思います。彼が手に入れた「腹話術」という能力は、他人の言葉を操るという、ある意味で非常に強力な力です。しかし、安藤はこの力を私利私欲のために使うのではなく、むしろ社会の不条理や危険な兆候に対して使おうとします。
特に彼が危機感を抱くのが、政治家・犬養の存在です。犬養は巧みな言葉で人々を魅了し、強いリーダーシップを発揮しますが、安藤はその裏に潜む危うさ、全体主義的な匂いを敏感に感じ取ります。人々が熱狂し、思考停止に陥っていく様子を目の当たりにして、安藤は「このままではいけない」と強く思うわけです。彼の「考えろ」という口癖は、まさにこの思考停止への抵抗の表れなのでしょう。
安藤が「腹話術」を使って犬養の演説を妨害しようとする場面は、物語のクライマックスの一つです。しかし、結果は失敗に終わります。そこには、安藤と同じような、あるいはそれ以上の力を持つ存在(ドゥーチェのマスター)がいたからです。これは、個人の力が必ずしも巨大な流れを変えられるわけではない、という現実の厳しさを示しているのかもしれません。そして、安藤はその抵抗の果てに命を落としてしまいます。彼の行動は、結果だけを見れば無力だったのかもしれません。しかし、それでも彼は「考え」、そして行動した。その一点において、彼の生き様は決して無意味ではなかったと、私は感じます。彼は、大きな流れにただ身を任せるのではなく、立ち止まって考えることの尊さを、その身をもって示してくれたのではないでしょうか。
そして物語は、安藤の死から五年後の世界、「呼吸」へと移ります。主人公は弟の潤也です。彼は兄とはまた違ったタイプの人間です。兄ほど理詰めで考えるタイプではなく、どちらかというとのんびりとした雰囲気を持っています。しかし、彼にもまた特殊な能力が備わっていました。それは「幸運」、特に「じゃんけんに絶対に負けない」という力です。
一見すると、「腹話術」に比べて地味で、何に役立つのか分からないような能力です。しかし、この「幸運」が、物語の後半で重要な意味を持ってきます。潤也は、兄・安藤の死の真相を探る中で、犬養とその周辺に兄と同じような能力者が関わっていた可能性に気づきます。そして、兄が立ち向かおうとした巨大な存在に、今度は自分が向き合わなければならないと感じるようになります。
潤也がとった方法は、兄とは異なります。彼は直接的な対決を避け、「幸運」の力を使って競馬で莫大な資金を稼ぎます。このお金を何に使うのか、具体的な計画はまだ語られませんが、彼が「兄貴がやろうとしたこと」を引き継ごうとしているのは明らかです。「馬鹿でかい規模の洪水が起きた時、俺はそれでも、水に流されないで、立ち尽くす一本の木になりたいんだよ」という潤也の言葉は、彼の決意を表しています。兄・安藤が流れに抗おうとして押し流されたのに対し、潤也は流れの中でしっかりと根を張り、立ち続けようとしている。まるで、激流の中に打ち込まれた一本の杭のように、彼は自分なりの方法で抵抗しようとしているのです。
この潤也の物語は、詩織という彼の妻の視点から語られる部分が多いのも特徴的です。詩織は特殊な能力を持たない、ごく普通の女性です。だからこそ、彼女の目を通して描かれる潤也の行動や決意が、より際立って見えます。彼女は潤也の行動に不安を感じながらも、彼を信じ、支えようとします。この二人の関係性が、物語に温かみと希望を与えているように感じます。
『魔王』という作品全体を通して感じるのは、やはり「考えること」の重要性です。犬養のような存在は、現代社会にも形を変えて現れる可能性があります。人々を熱狂させ、特定の方向に導こうとする声は、インターネットなどを通じて、より簡単に私たちの耳に届くようになりました。そんな時代だからこそ、安藤のように立ち止まって「考えろ」と自問し、潤也のように流されずに「立ち尽くす」姿勢が必要なのではないでしょうか。
また、伊坂さんの他の作品との繋がりも見逃せません。『死神の精度』に登場する死神・千葉が、本作にも少しだけ顔を出しています。こうした遊び心も伊坂作品の魅力の一つですが、それだけでなく、『魔王』の五十年後を描いたとされる『モダンタイムス』という作品も存在します。これらを合わせて読むことで、より深く伊坂さんの描く世界観やテーマ性を理解できるかもしれません。
この作品は、派手なアクションや爽快な結末があるわけではありません。むしろ、読後には少し重たい問いかけが残るかもしれません。安藤の死は報われたのか、潤也の未来はどうなるのか、明確な答えは示されません。しかし、だからこそ、私たちは物語の登場人物たちと共に「考える」ことになるのだと思います。社会の大きな流れの中で、個人としてどう生きるべきか。簡単に答えの出る問いではありませんが、この物語は、その問いと向き合い続けること自体の尊さを教えてくれる、そんな作品だと感じています。エンターテインメント性は他の伊坂作品に比べてやや控えめかもしれませんが、現代を生きる私たちにとって、非常に示唆に富んだ、読む価値のある一冊であることは間違いありません。
まとめ
この記事では、伊坂幸太郎さんの小説『魔王』について、物語の詳しい流れと、そこから感じ取れるメッセージなどを、ネタバレを含みながら詳しくお話しさせていただきました。兄・安藤が手にした「腹話術」という力と、彼が対峙した政治家・犬養が象徴する社会の大きな流れ。そして、兄の遺志を継ぐ形で「幸運」という力に目覚めた弟・潤也の決意。二人の兄弟の物語を通して、作品が問いかけるテーマを掘り下げてみました。
物語の中心にあるのは、「考えること」の重要性です。周りの空気に流されず、自分の頭で判断し、行動すること。安藤の抵抗は結果的に命を落とす悲劇に繋がりますが、その姿勢自体に価値があったのではないでしょうか。そして、潤也は兄とは違うアプローチで、その「考える葦」であろうとします。彼の未来はまだ示されていませんが、詩織という存在と共に、希望を感じさせる終わり方だったと思います。
この『魔王』という作品は、読者に多くのことを考えさせる力を持っています。現代社会と照らし合わせながら読むと、さらに深い示唆を得られるはずです。もし、まだ読んだことがない方がいらっしゃれば、ぜひ手に取って、安藤や潤也と共に「考え」、そして何かを感じていただけたら嬉しいです。