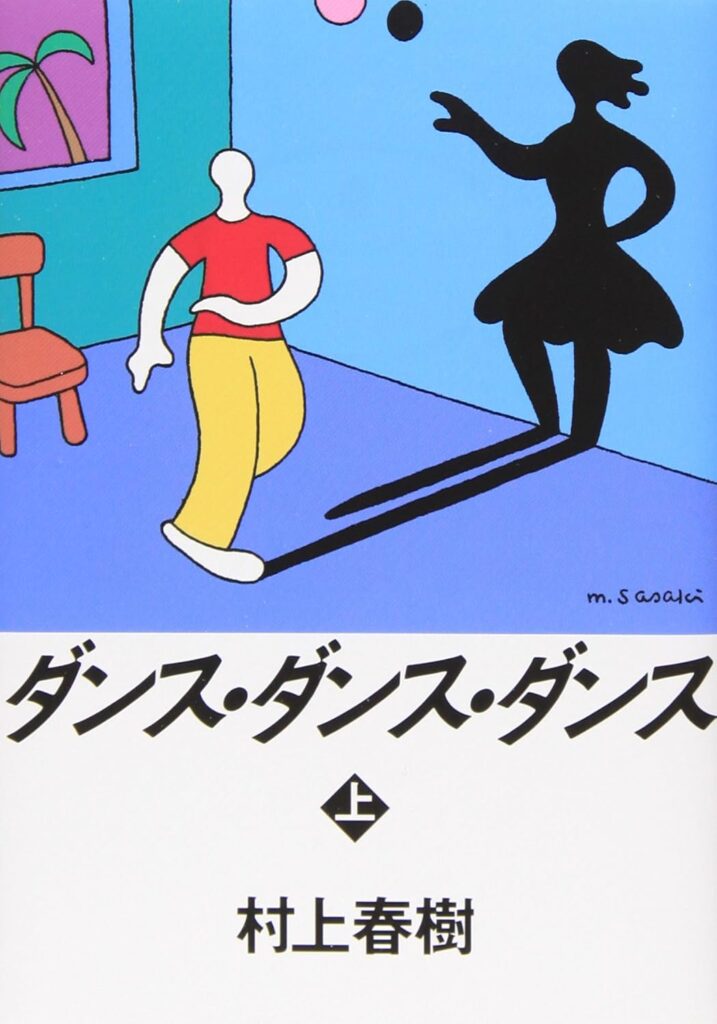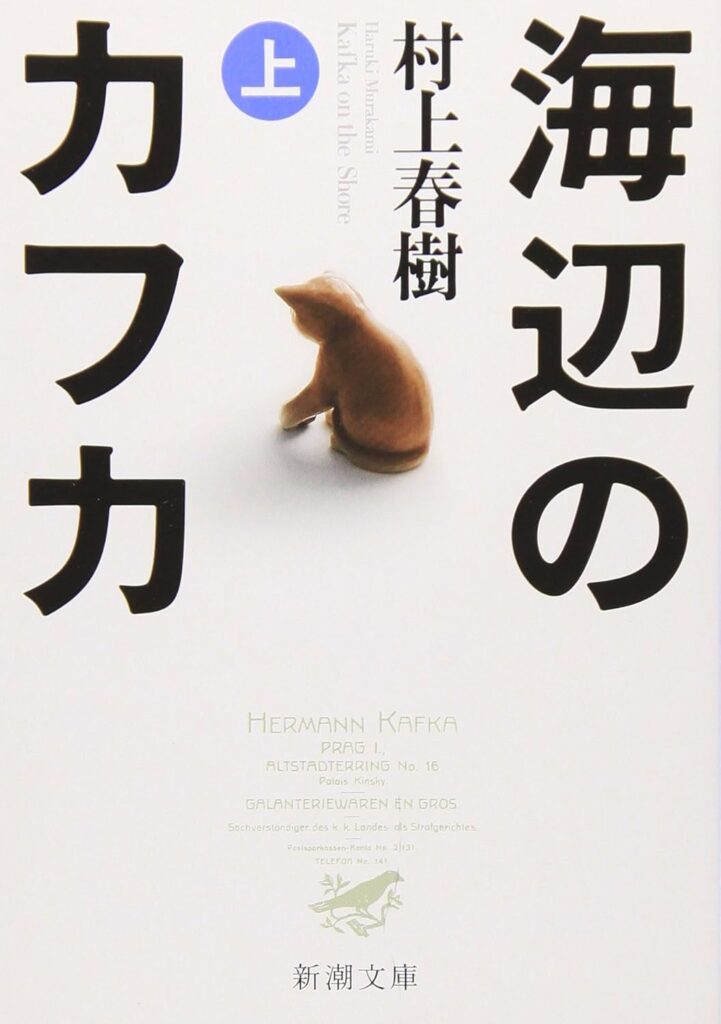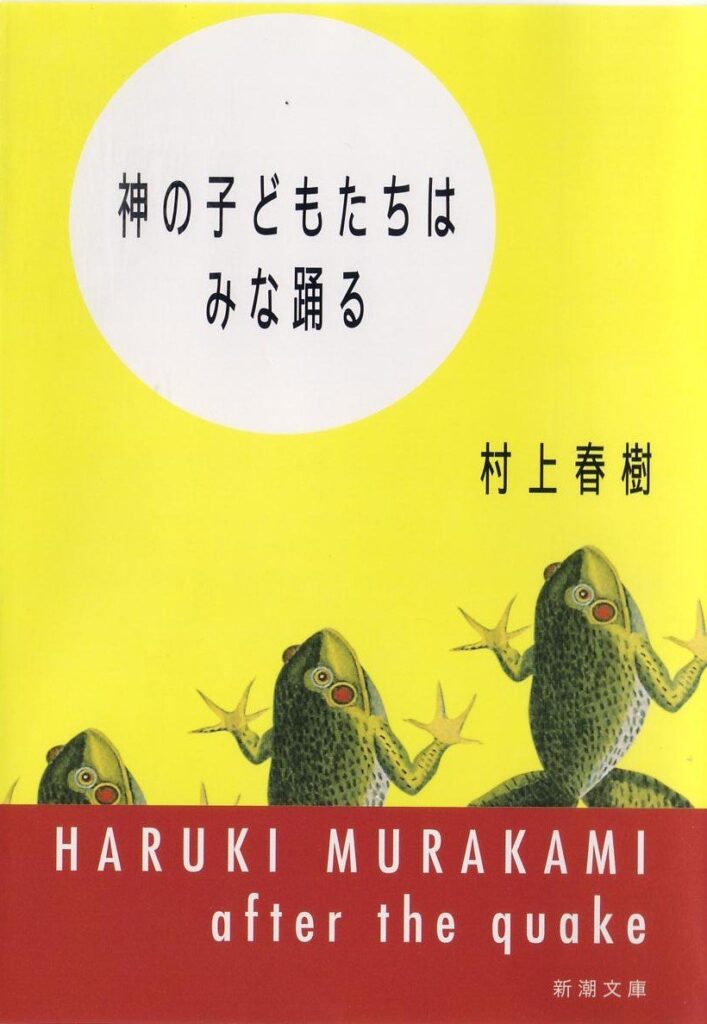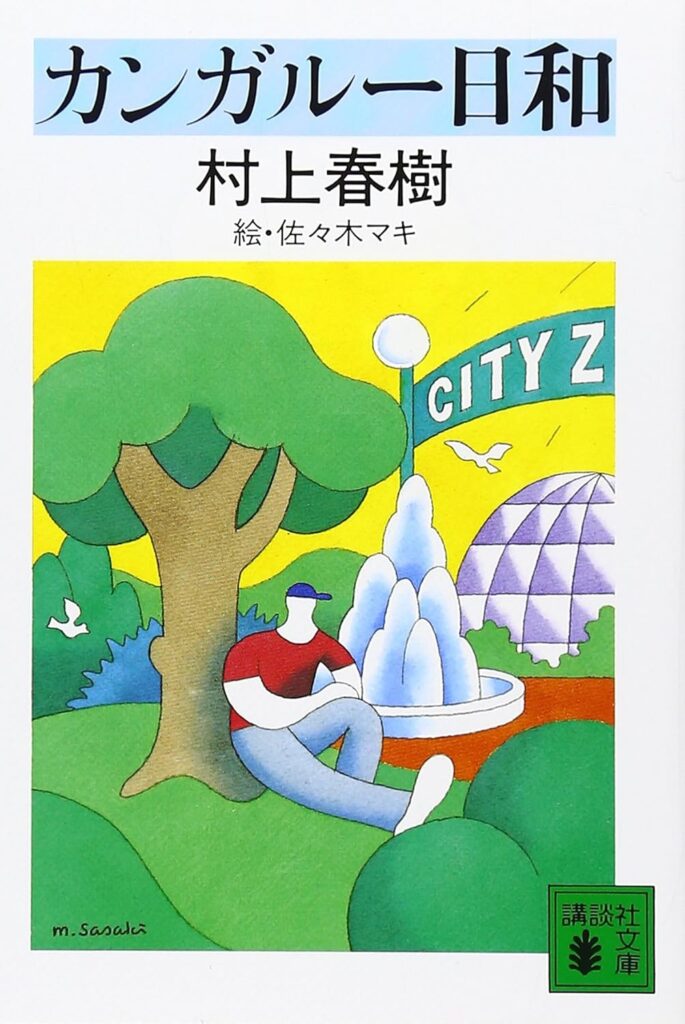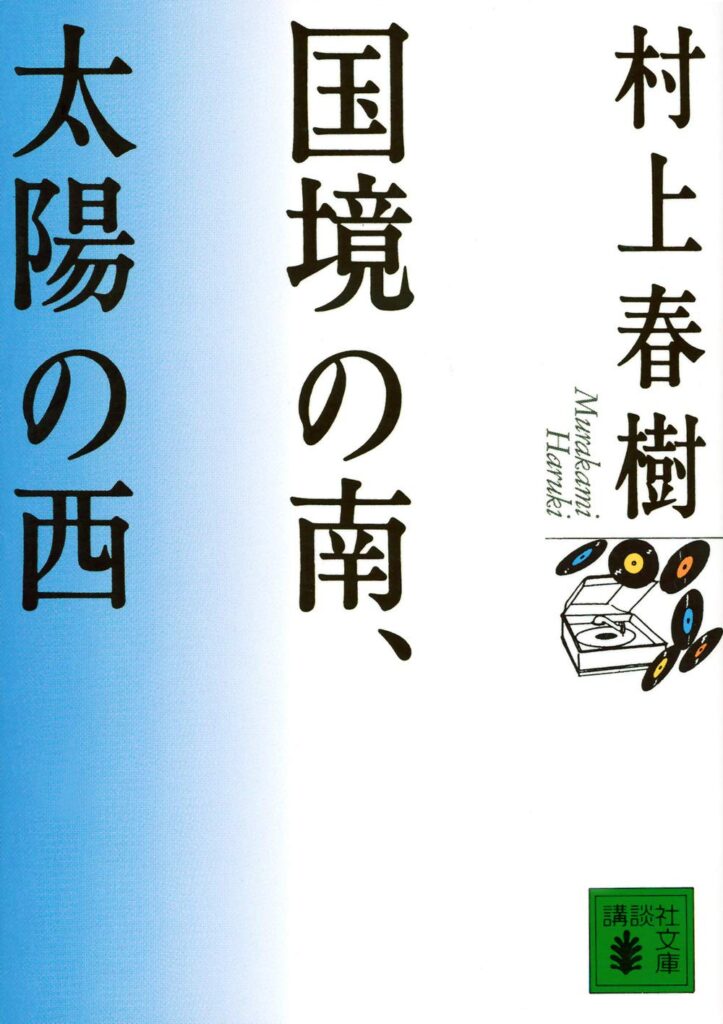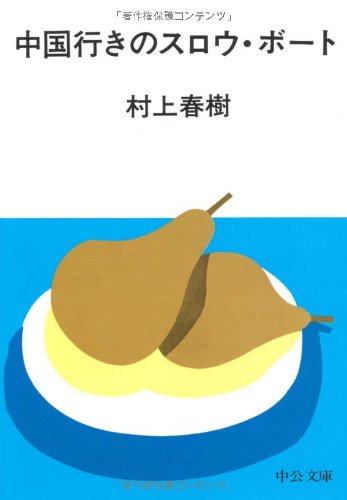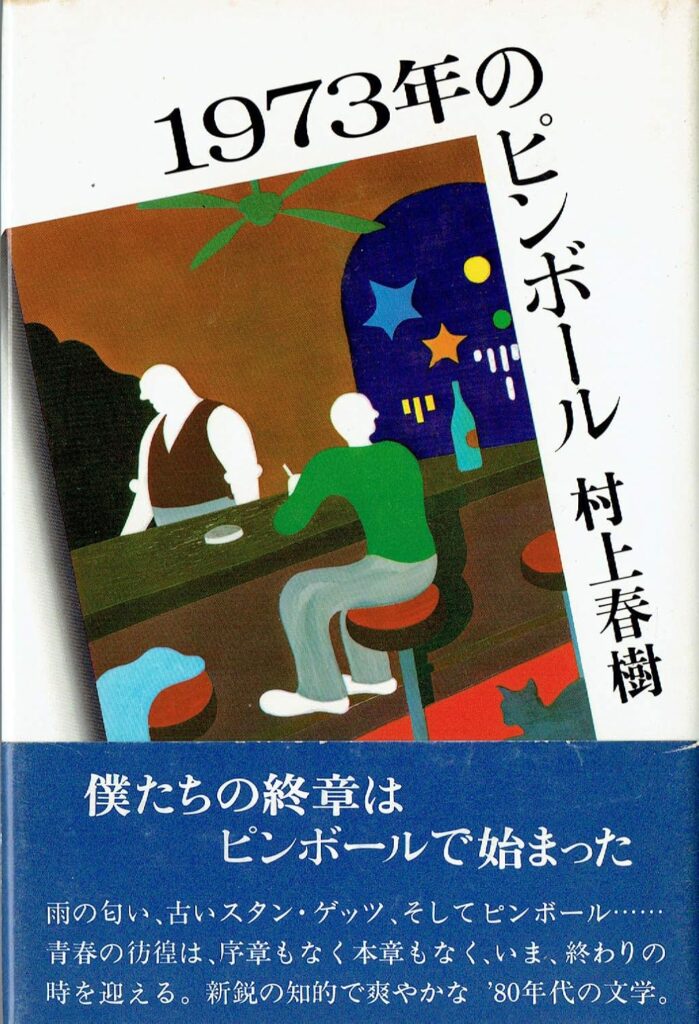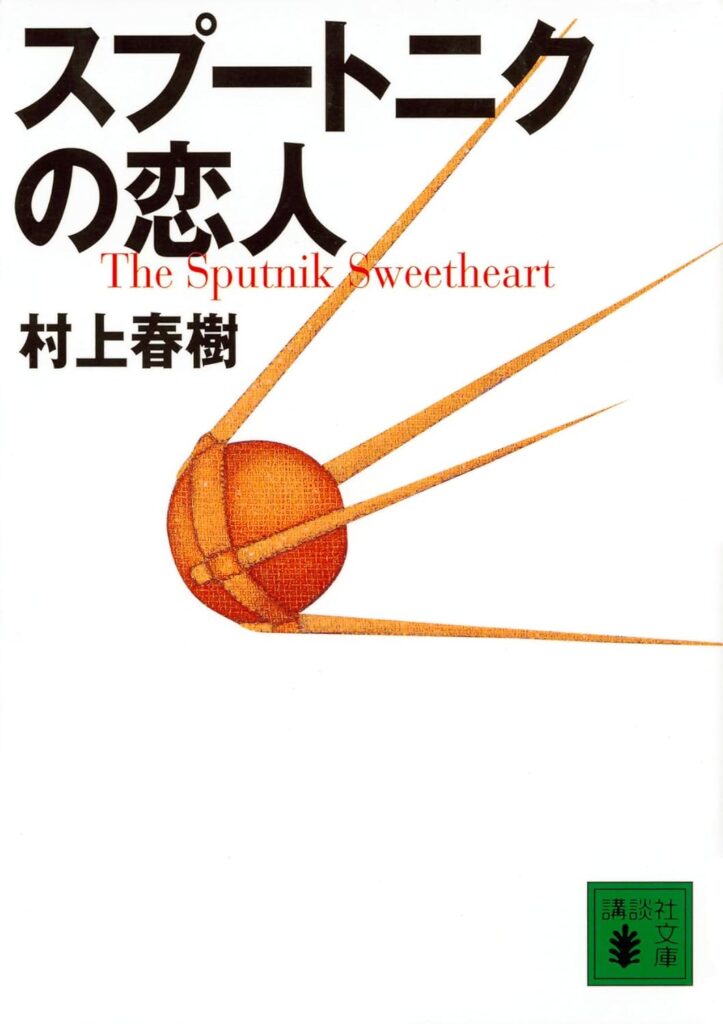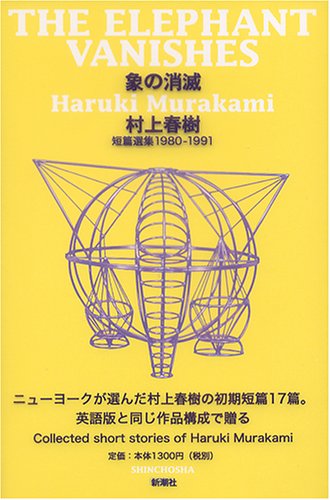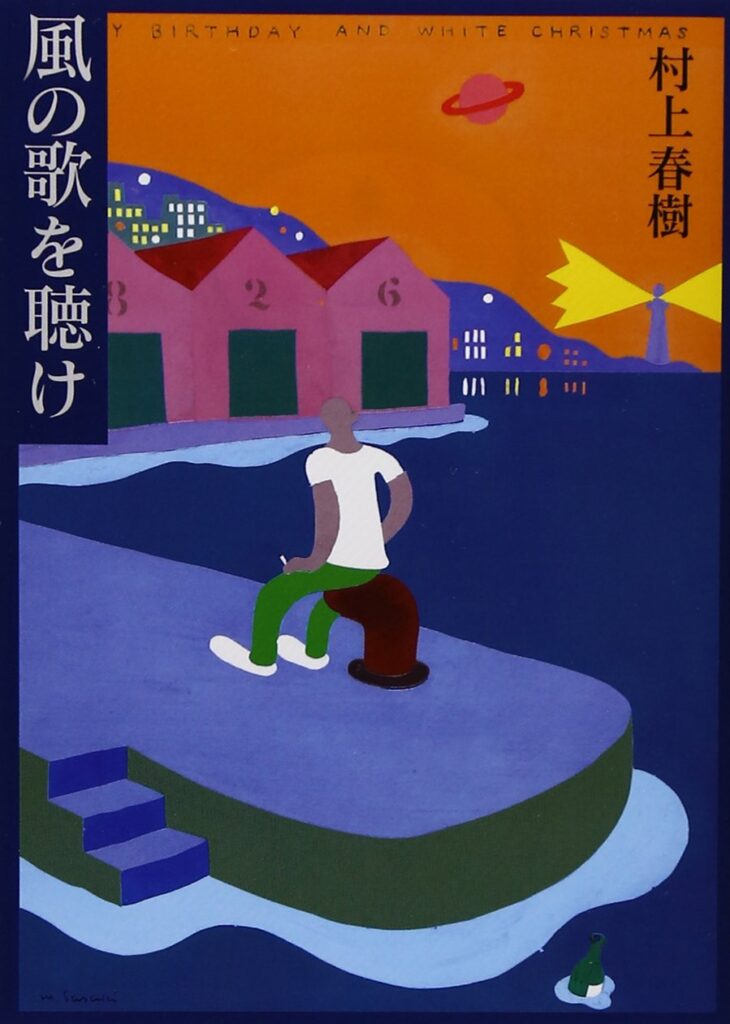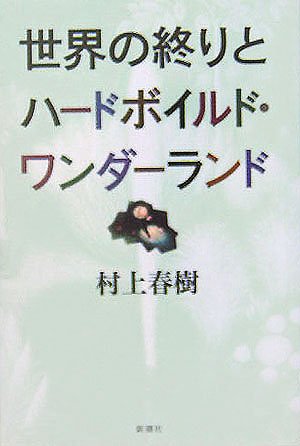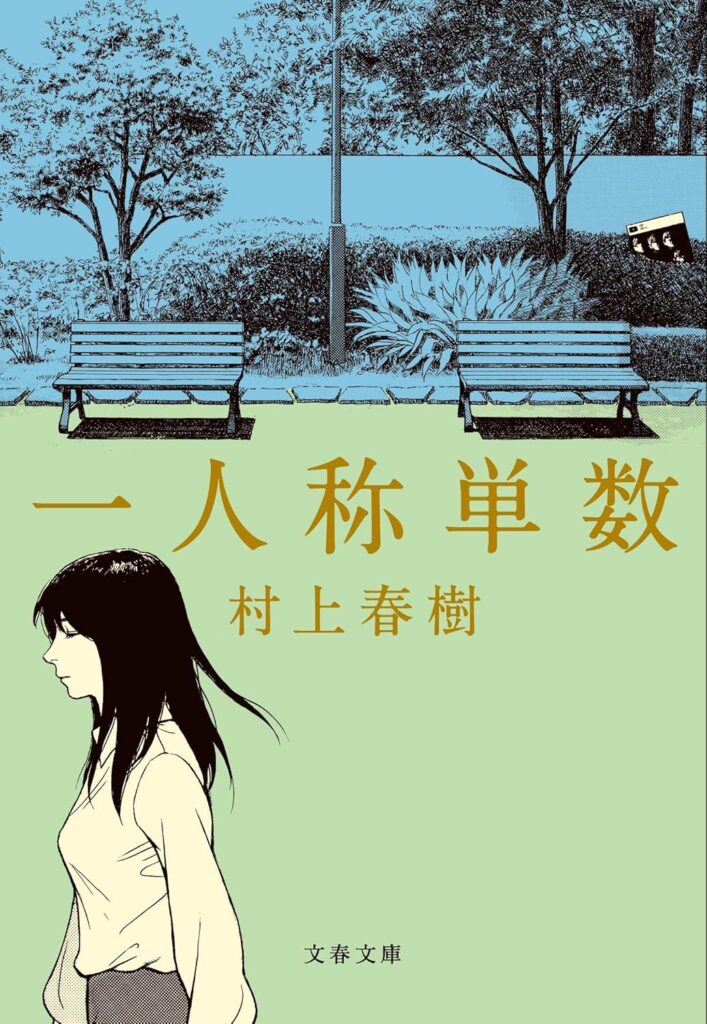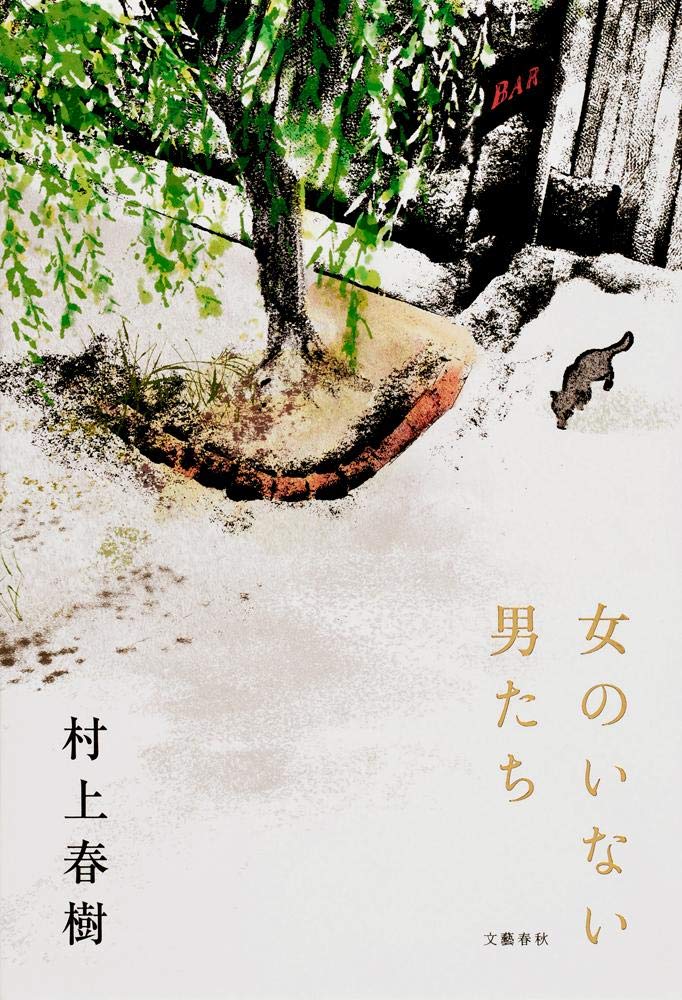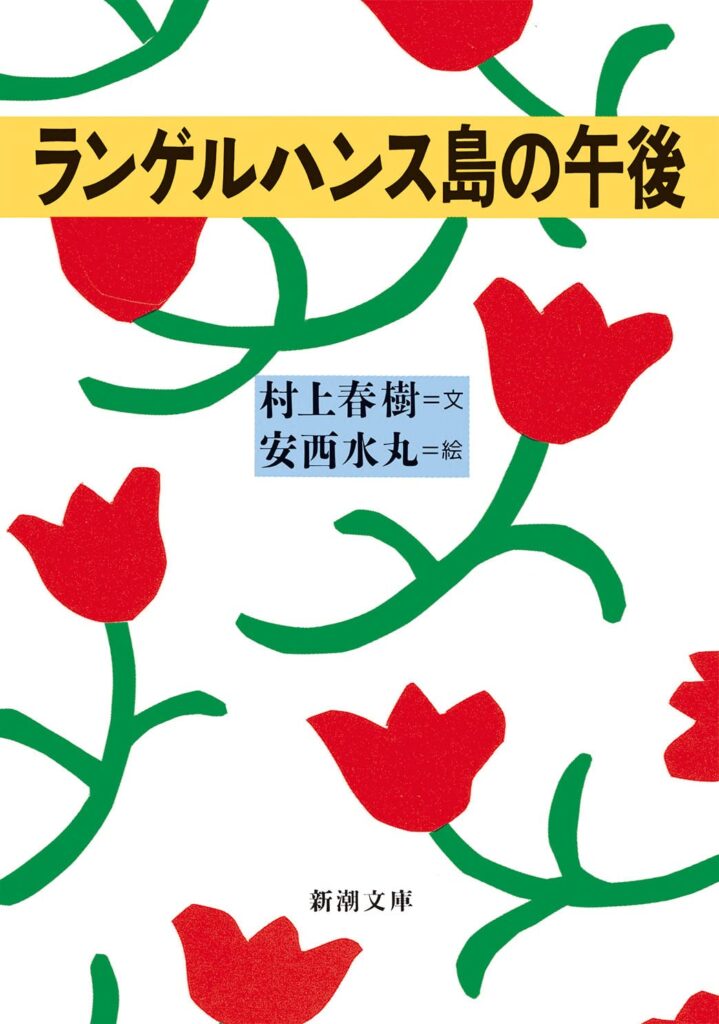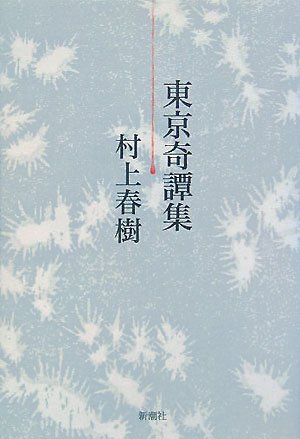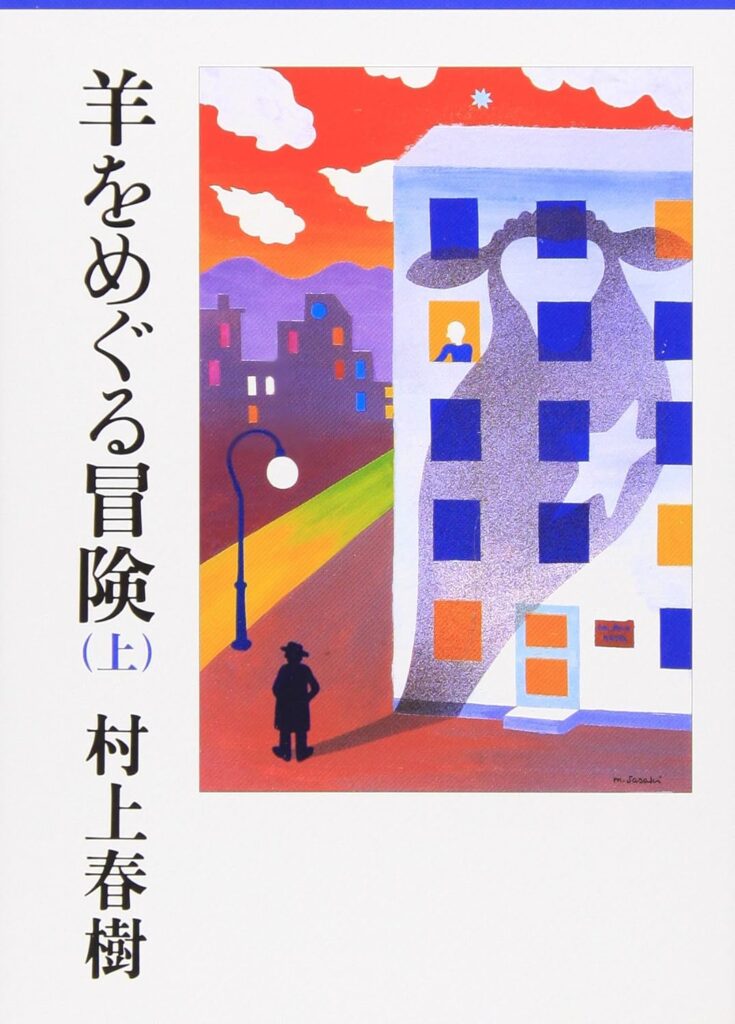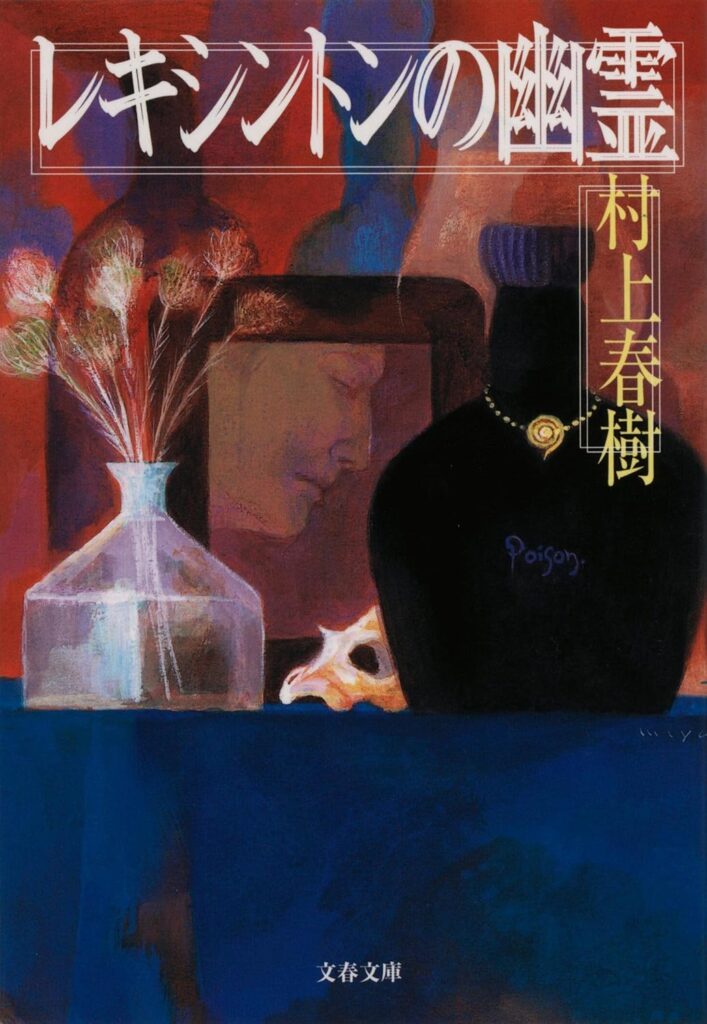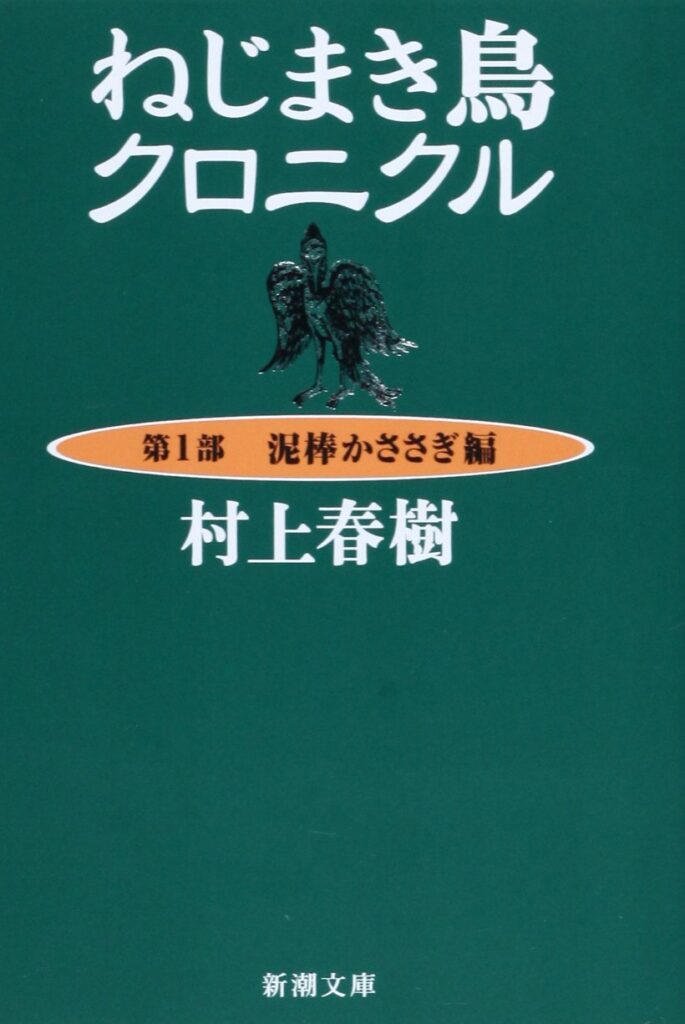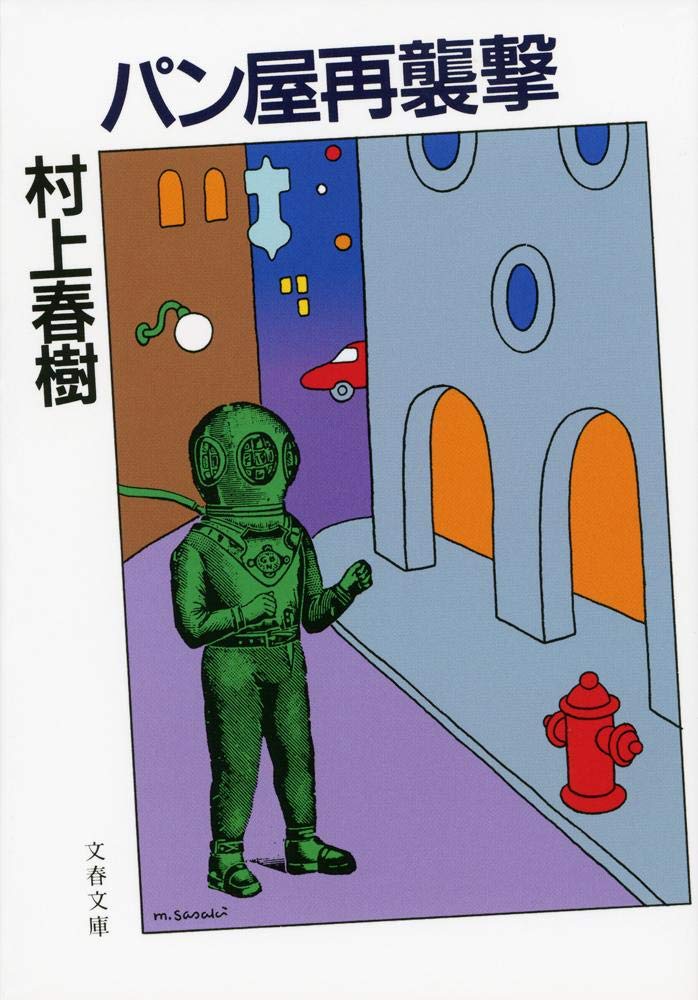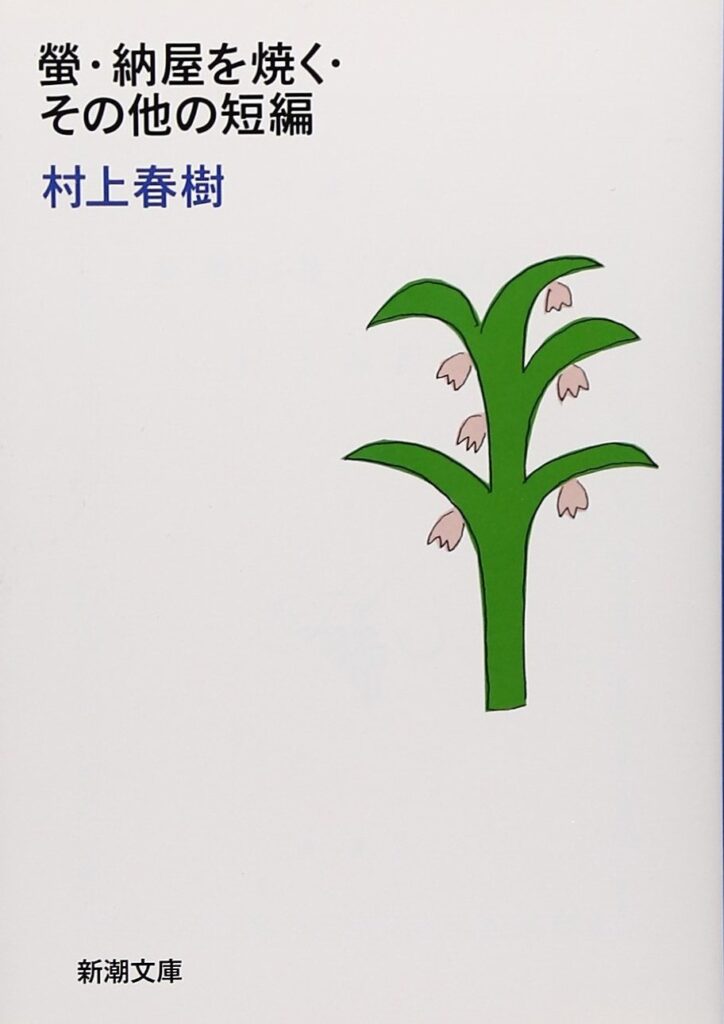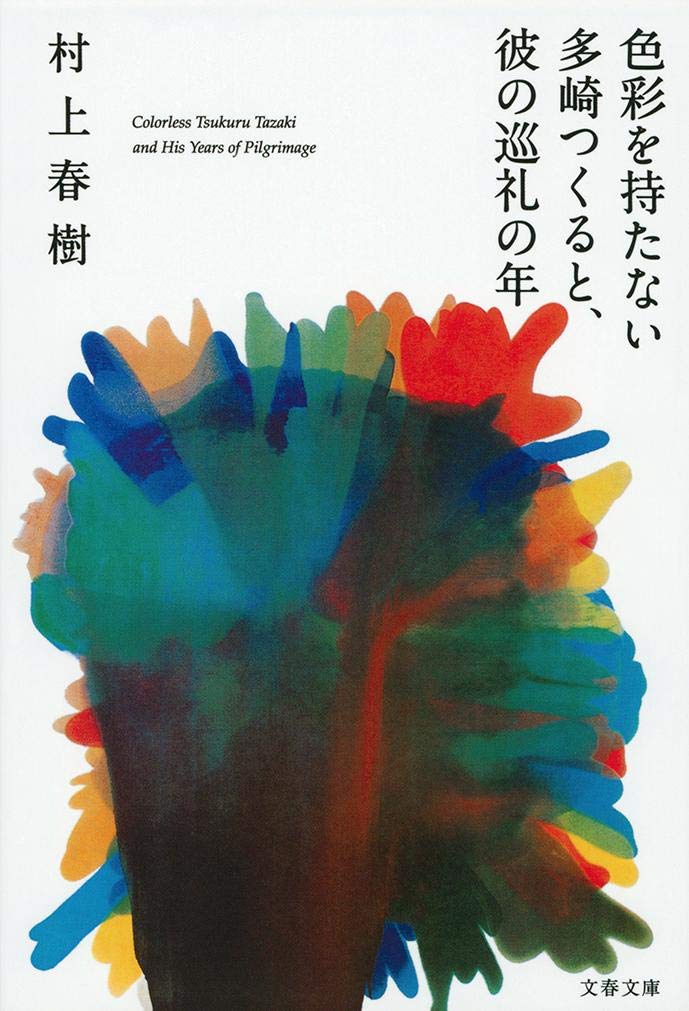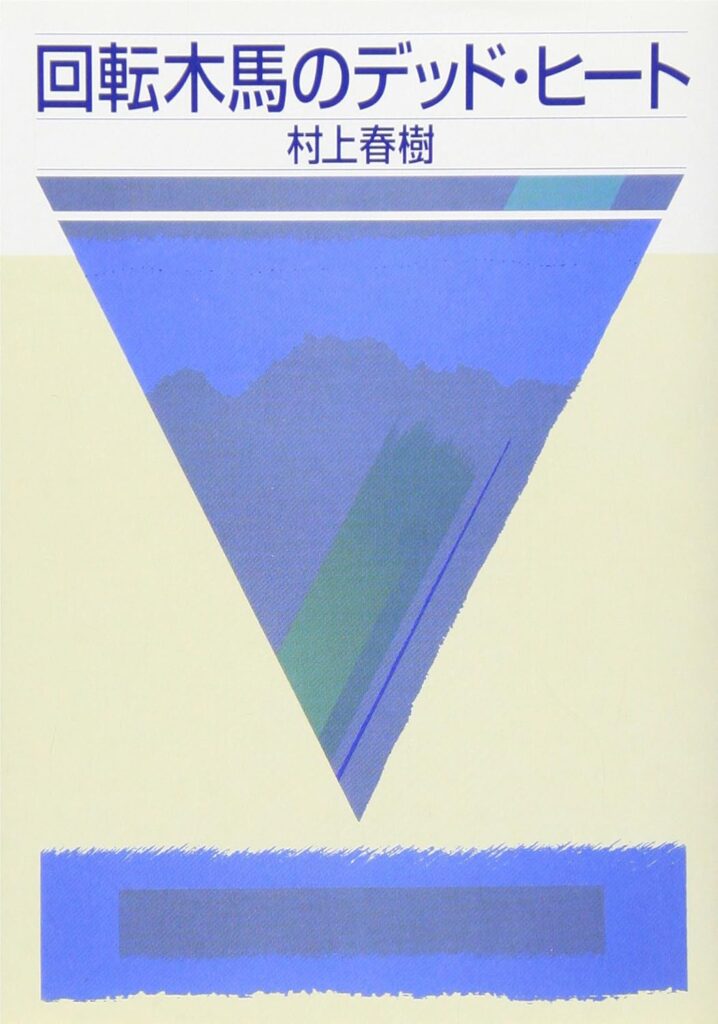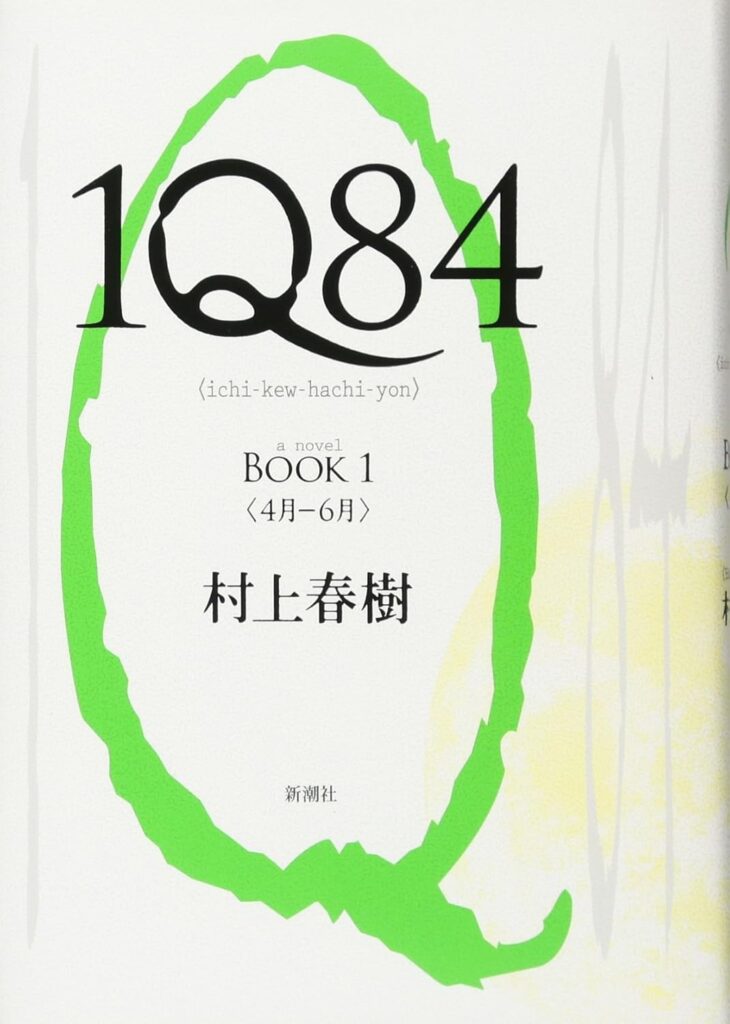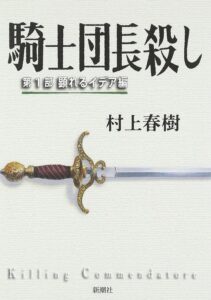 小説「騎士団長殺し」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。村上春樹さんの作品の中でも、特に長く、そして深い謎に満ちた物語として知られていますね。肖像画家である主人公が、妻との予期せぬ別れをきっかけに、これまでの日常から離れ、新たな場所で生活を始めることから物語は動き出します。
小説「騎士団長殺し」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。村上春樹さんの作品の中でも、特に長く、そして深い謎に満ちた物語として知られていますね。肖像画家である主人公が、妻との予期せぬ別れをきっかけに、これまでの日常から離れ、新たな場所で生活を始めることから物語は動き出します。
その新しい住処となったのは、小田原の山中にある、かつて著名な日本画家が使っていたアトリエでした。そこで彼は、屋根裏に隠されていた「騎士団長殺し」と題された奇妙な日本画を発見します。この絵との出会いが、主人公を現実と非現実が入り混じる、不思議な出来事へと誘っていくことになるのです。この記事では、物語の詳しい流れと、そこに込められた意味について、私なりの解釈を交えながらお話ししていきたいと思います。
物語には、謎めいた隣人や、突如姿を現す不思議な存在、そして「メタファー」と呼ばれる異世界が登場します。主人公がこれらの出来事にどのように関わり、何を見つけ、どのように変化していくのか。その過程を追いながら、この壮大な物語が持つ魅力や、読後に残る深い余韻について、じっくりと考えていきましょう。ネタバレを含みますので、未読の方はご注意くださいね。
小説「騎士団長殺し」のあらすじ
物語の始まりは、主人公である肖像画家の「私」が、妻の柚から突然別れを告げられる場面です。理由も告げられぬまま家を出た私は、あてもなく車で日本各地を彷徨う長い旅に出ます。しかし、旅の途中で車が故障し、立ち往生してしまいます。そんな時、大学時代の友人である雨田政彦から、彼の父で高名な日本画家・雨田具彦が使っていた小田原の山中にあるアトリエを借りないかと提案されます。父が認知症で施設に入って以来、空き家になっていたその家で、私は新たな生活を始めることにしました。
引っ越して落ち着いたある日、私は屋根裏で一枚の奇妙な日本画を発見します。それは「騎士団長殺し」と題され、モーツァルトのオペラ『ドン・ジョヴァンニ』の場面を、日本の飛鳥時代を舞台に描いたものでした。強い力を持つその絵に私は深く惹きつけられます。そんな折、アトリエの敷地内にある古い石積みの祠から、夜ごと微かな鈴の音が聞こえてくるようになります。好奇心に駆られた私は、友人の許可を得て、祠を塞いでいた重い石を業者に頼んで動かしてもらい、中の穴へと降りていきます。穴の底には古びた鈴が落ちていました。
その出来事をきっかけに、私の前に不思議な存在が現れます。身長60センチほどの、古い甲冑を身に着けた「騎士団長」です。彼は自らを、具体的な形を持たない「イデア」が具現化したものだと名乗り、その姿は屋根裏で見つけた絵の中の人物から借りていると説明します。騎士団長は、私が祠を開けたことによって出現したこと、そして祠の石を動かす際に手伝ってくれた、谷の向こうの豪邸に住む謎めいた紳士、免色渉に礼を言う必要があると語ります。
免色渉は私に自身の肖像画制作を依頼します。制作を進める中で、私は免色の複雑な過去や、彼がこの土地に移り住んできた理由を知ることになります。また、私は週に二回、近所の絵画教室で子供たちに絵を教えており、そこには秋川まりえという才能ある13歳の少女がいました。免色はどうやら、まりえが自分の娘かもしれないと考えているようでした。しかし、ある日、まりえが学校へ行かずに姿を消してしまいます。私は騎士団長の助けを借りながら、まりえを探すため、「メタファー」と呼ばれる危険な異世界へと足を踏み入れることになるのです。
小説「騎士団長殺し」の長文感想(ネタバレあり)
村上春樹さんの「騎士団長殺し」を読み終えたとき、まるで長い夢から覚めたような、不思議な感覚に包まれました。現実と非現実が複雑に絡み合い、深い森の奥へと迷い込んでいくような読書体験でしたね。この物語は、単なる不思議な出来事の連続ではなく、喪失感や心の傷を抱えた主人公が、自己の内面と向き合い、再生していく過程を描いた、非常に重層的な物語だと感じました。
まず、主人公の「私」についてですが、彼は肖像画家として、対象の本質を見抜く鋭い観察眼を持っています。しかし、物語の序盤では、妻からの突然の別れによって、自身の足元が崩れていくような不安定さを抱えています。目的のない放浪の旅は、彼の混乱と喪失感を象徴しているかのようです。小田原のアトリエでの新しい生活は、彼にとって外界から隔絶された、自己と向き合うための静かな時間を与えます。そこで発見される「騎士団長殺し」の絵は、彼の内なる世界への扉を開く鍵となります。絵と対峙する時間は、彼が再び創造的な活動へと向かうための重要なステップでした。
物語の核心にあるのは、やはり「騎士団長殺し」という絵画の存在でしょう。雨田具彦が第二次大戦下のウィーンで、日本の飛鳥時代を舞台に『ドン・ジョヴァンニ』の一場面を描いたという設定自体が、時代も文化も超えた普遍的なテーマ、例えば善と悪、愛と裏切り、生と死といったものを内包しているように思えます。絵に描かれた暴力的な場面は、具彦自身の過去のトラウマや、人間が持つ根源的な闇を象徴しているのかもしれません。この絵が屋根裏に秘匿されていたという事実も、隠された真実や抑圧された記憶といったモチーフを暗示しているように感じられます。主人公がこの絵に強く惹きつけられるのは、彼自身の内面にも、この絵が持つ力と共鳴するものがあったからではないでしょうか。
そして、物語を動かす重要な存在が「騎士団長」です。自らを「イデア」と称するこの小さな存在は、プラトンのイデア論を思い起こさせますね。つまり、現実世界の物事の「原型」や「本質」のようなもの。彼が絵の中から抜け出してきたかのように現れ、主人公に語りかける姿は、まさに非現実的です。しかし、彼の言葉や行動は、しばしば主人公が進むべき道を示唆し、内面の探求を促します。彼は主人公の無意識や、具彦の残留思念のようなものが形をとった存在なのかもしれません。騎士団長との対話を通じて、主人公は現実世界の裏側にある、目に見えない力や法則の存在を認識していくことになります。
免色渉という人物も、この物語において非常に重要な役割を担っています。白いジャガーを乗りこなし、洗練された物腰でありながら、どこか掴みどころのない謎めいた存在です。彼は潤沢な資産を持ち、目的のためなら手段を選ばない冷徹さも持ち合わせています。彼がこの土地に来た目的、すなわち自分の娘かもしれない秋川まりえを見守ること、そして可能ならば関わりを持つこと。その執念にも似た思いは、彼の過去の深い後悔や孤独感から来ているのでしょう。主人公は、免色の肖像画を描く過程で、彼の内面に隠された複雑な感情や、人間的な脆さに触れていきます。免色は、富や知性といった外面的なものだけでは測れない、人間の心の深淵を体現する存在として描かれているように感じました。主人公とは対照的な存在でありながら、二人の間には奇妙な共感や信頼関係が芽生えていくのも興味深い点です。
秋川まりえの存在は、物語に一筋の光をもたらす一方で、危うさも感じさせます。彼女の純粋さや鋭い感受性は、大人たちの複雑な世界とは対照的です。彼女が絵画教室で見せる才能は、主人公にとっても刺激となります。しかし、その純粋さゆえに、周囲の状況や人々の思惑に翻弄されやすい存在でもあります。彼女の突然の失踪は、物語に大きな転換点をもたらします。彼女を探すために、主人公は「メタファー」の世界へと足を踏み入れる決意をするのです。まりえの失踪と救出劇は、単なるサスペンス要素ではなく、主人公が自身の内なる世界(メタファー)の危険な領域を探求し、乗り越えるべき試練として描かれているのではないでしょうか。
そして、「メタファー」の世界。これは村上作品にしばしば登場する、現実とは法則の異なる異世界ですね。「騎士団長殺し」におけるメタファーの世界は、特に「ダブル・メタファー」という、より深く、危険な領域として描かれています。そこは、物事の本質や象徴性が剥き出しになったような場所であり、安易に踏み込めば抜け出せなくなる危険な場所です。主人公が騎士団長を(象徴的に)殺す儀式を経てこの世界に入る展開は、自己の内部にある何か(例えば古い自己やトラウマ)を一度破壊し、再生するための通過儀礼のようにも思えます。メタファーの世界での彷徨は、主人公にとって究極の自己探求であり、そこで彼は免色の助けを借りて現実世界へと帰還します。この経験は、彼の内面に大きな変化をもたらしたはずです。それはまるで、暗い洞窟を探検し、出口の光を見出したかのような、困難な道のりの末の達成感と、新たな視点の獲得だったのではないでしょうか。
物語全体を貫いているのは、「喪失」と「再生」のテーマだと思います。主人公は妻を失い、日常を失います。そして、物語の終盤では、住んでいたアトリエが火事で焼失し、「騎士団長殺し」の絵も失われてしまいます。多くのものを失いながらも、彼は最終的に妻の柚と和解し、新たな命(娘の室)を授かります。これは、失われたものへの哀悼と共に、未来への希望、新しい始まりを示唆しています。アトリエや絵画といった、過去の象徴が失われることで、主人公はしがらみから解放され、真に新しい人生を歩み始めることができるのかもしれません。
「騎士団長殺し」は、非常に長く、多くの謎を含んだ物語です。すべての謎が明確に解き明かされるわけではありません。騎士団長の正体、免色のその後、メタファーの世界の厳密な意味など、読者の解釈に委ねられている部分も多いです。しかし、それこそが村上作品の魅力であり、読み終えた後も長く心に残り、考え続けさせる力を持っているのだと思います。主人公が経験した不思議な出来事を通して、私たちは自分自身の内面にあるかもしれない「騎士団長」や「メタファー」の世界について、思いを巡らせることになるのです。喪失感を抱えながらも、希望を失わずに生きていくことの尊さを、静かに、しかし深く語りかけてくる作品でした。
まとめ
「騎士団長殺し」は、妻との別れを経験した肖像画家が、小田原の山中で不思議な出来事に次々と遭遇する物語です。屋根裏で見つけた謎めいた絵画「騎士団長殺し」、突如現れた「イデア」としての騎士団長、謎多き隣人・免色渉、そして「メタファー」と呼ばれる異世界への冒険。これらが複雑に絡み合いながら、壮大な物語が紡がれていきます。
この物語は、単なるファンタジーやミステリーではありません。主人公が経験する喪失と再生、自己の内面との対峙、現実と非現実の境界線といった、村上春樹さんならではの深遠なテーマが扱われています。登場人物たちの抱える孤独や秘密、そして彼らの間で育まれる奇妙な関係性も、物語に深みを与えています。
読み終えた後も、多くの謎や象徴的な出来事が心に残り、様々な解釈を巡らせたくなるでしょう。それは、この物語が私たち自身の心の奥底にある何か普遍的なものに触れているからかもしれません。「騎士団長殺し」は、じっくりと時間をかけて向き合い、その世界に深く浸ることで、より豊かな読書体験が得られる作品だと感じます。