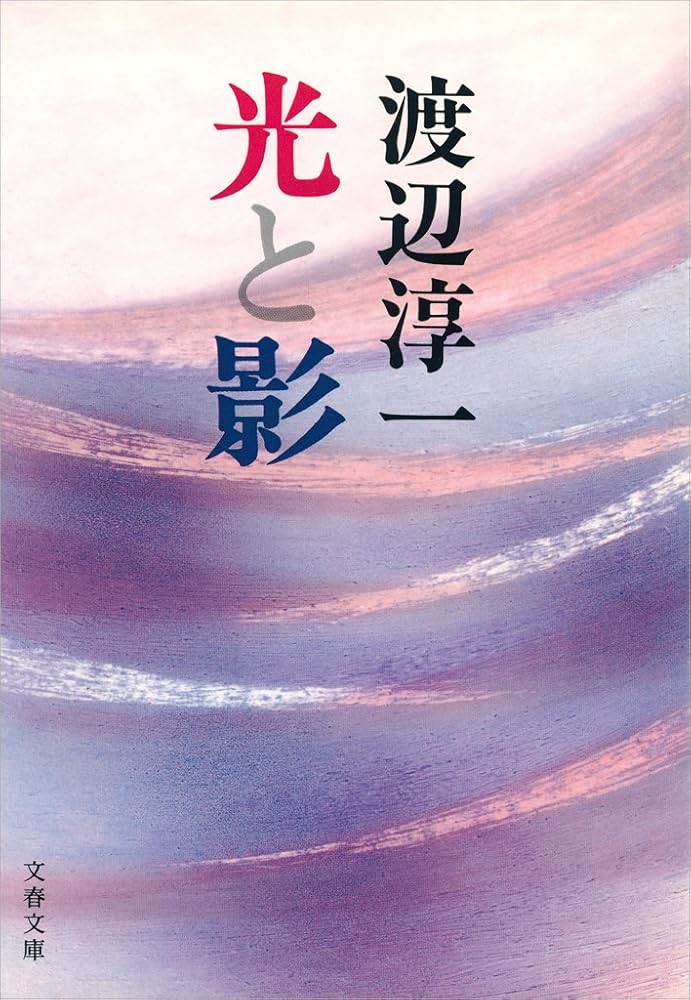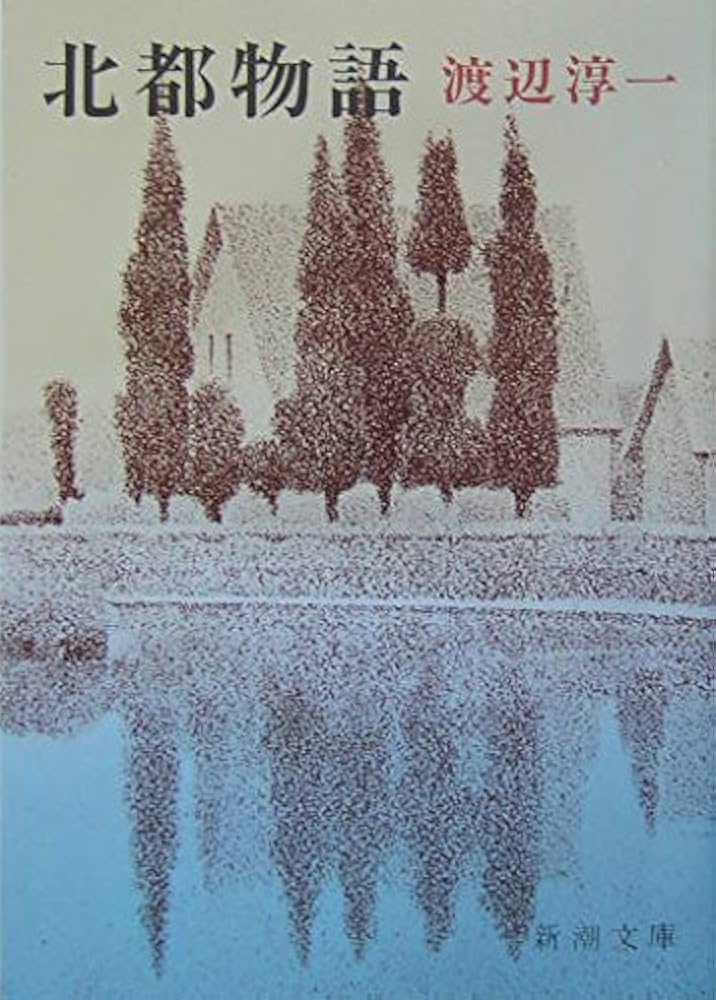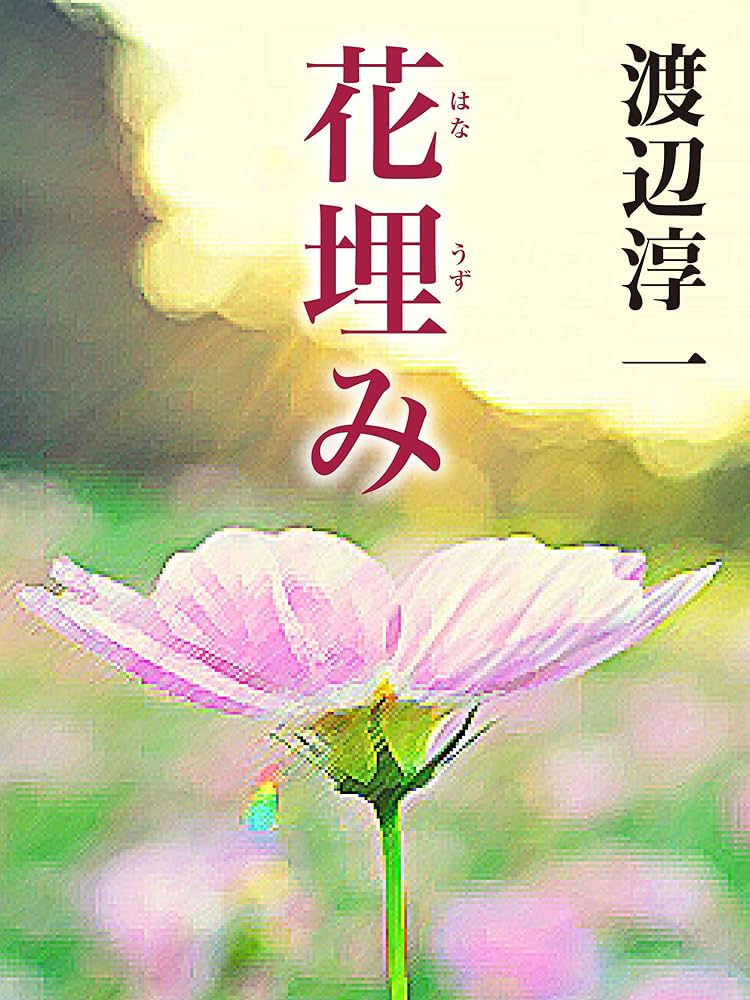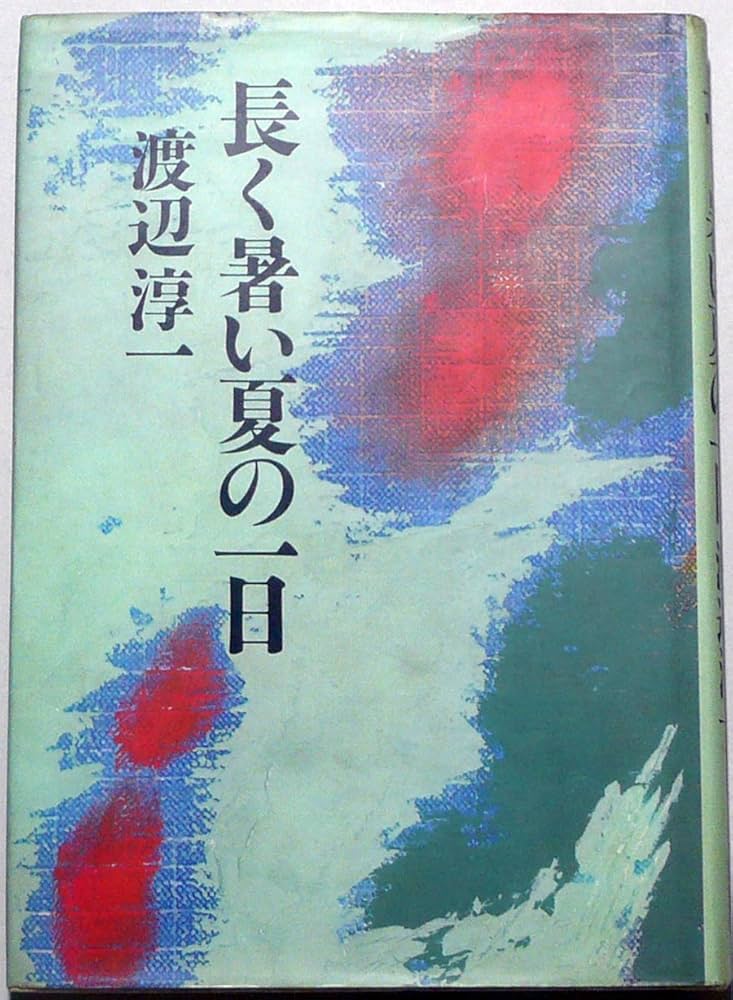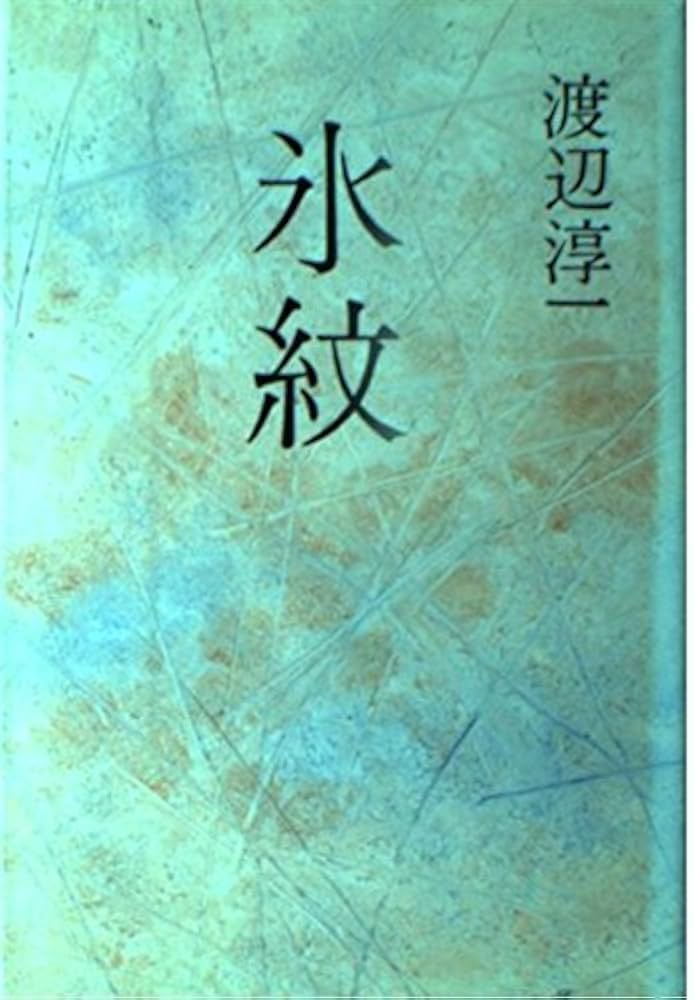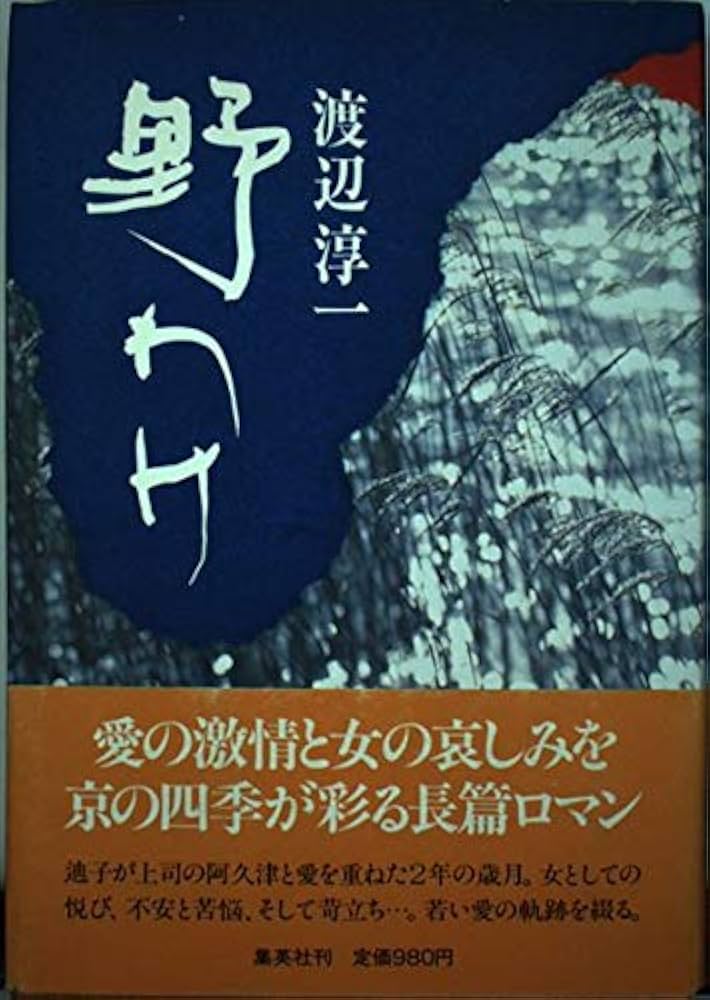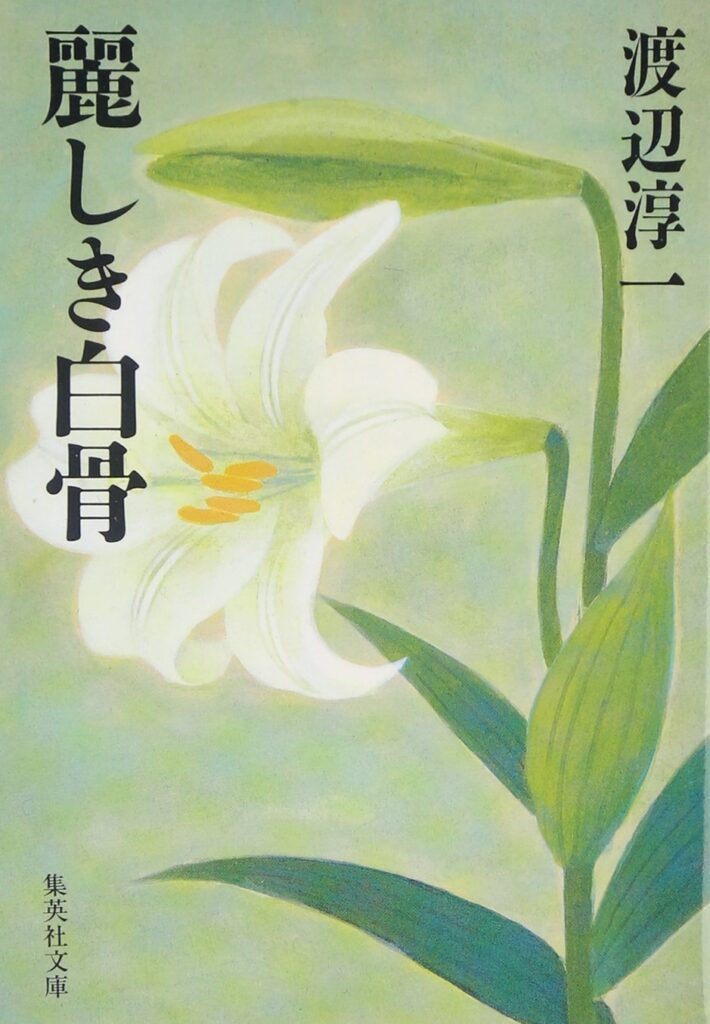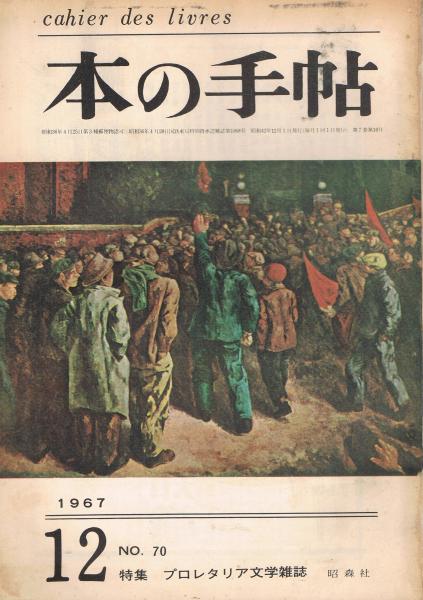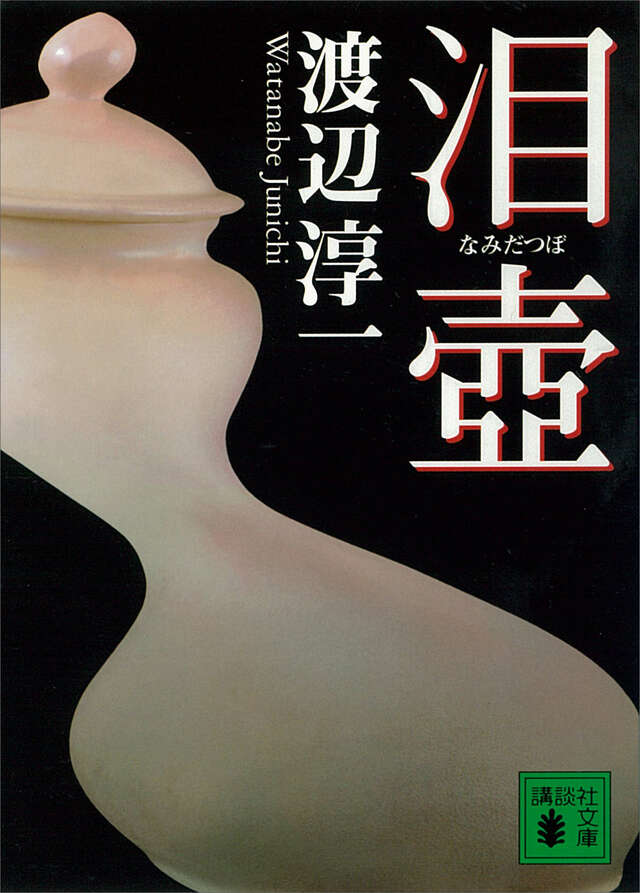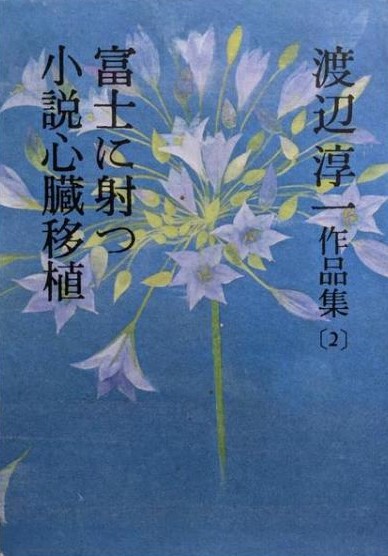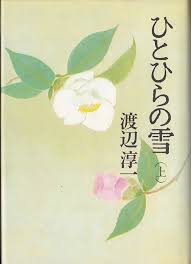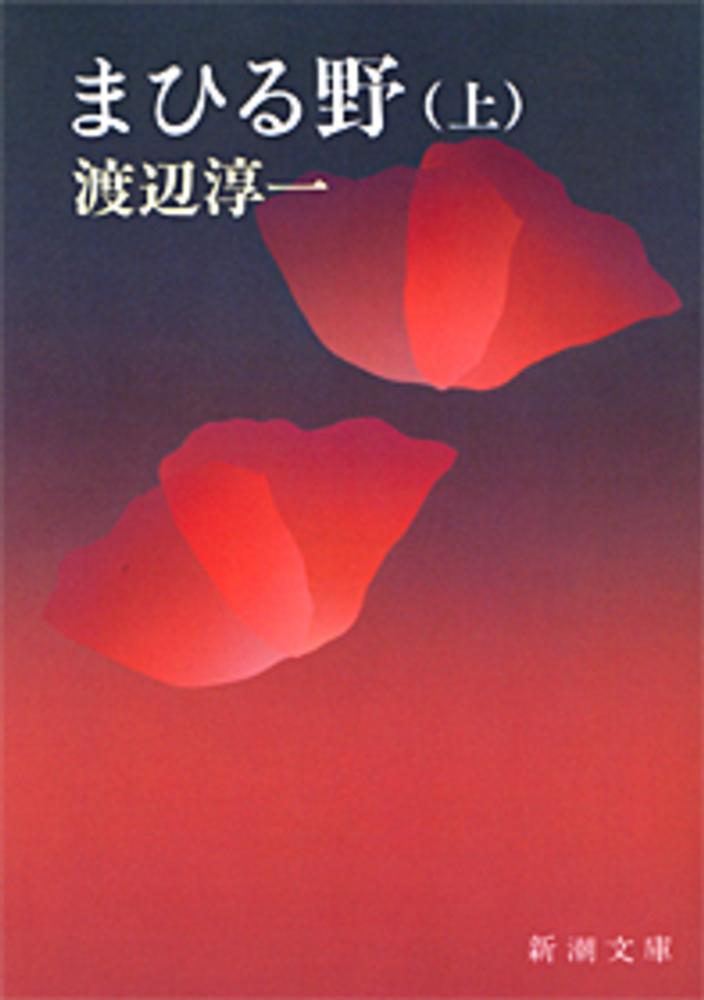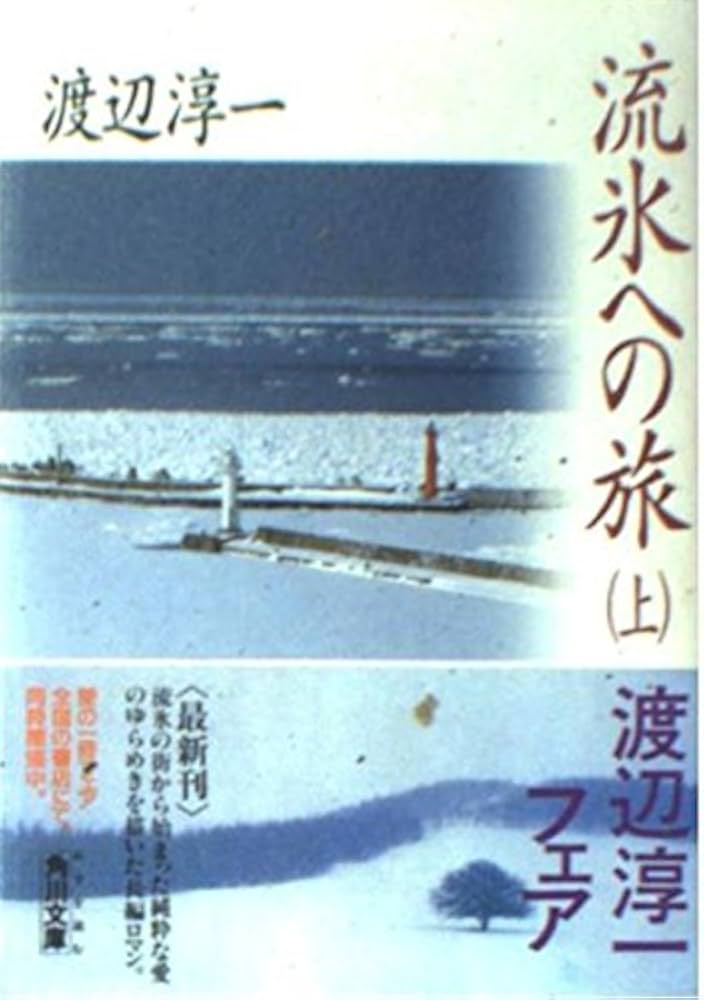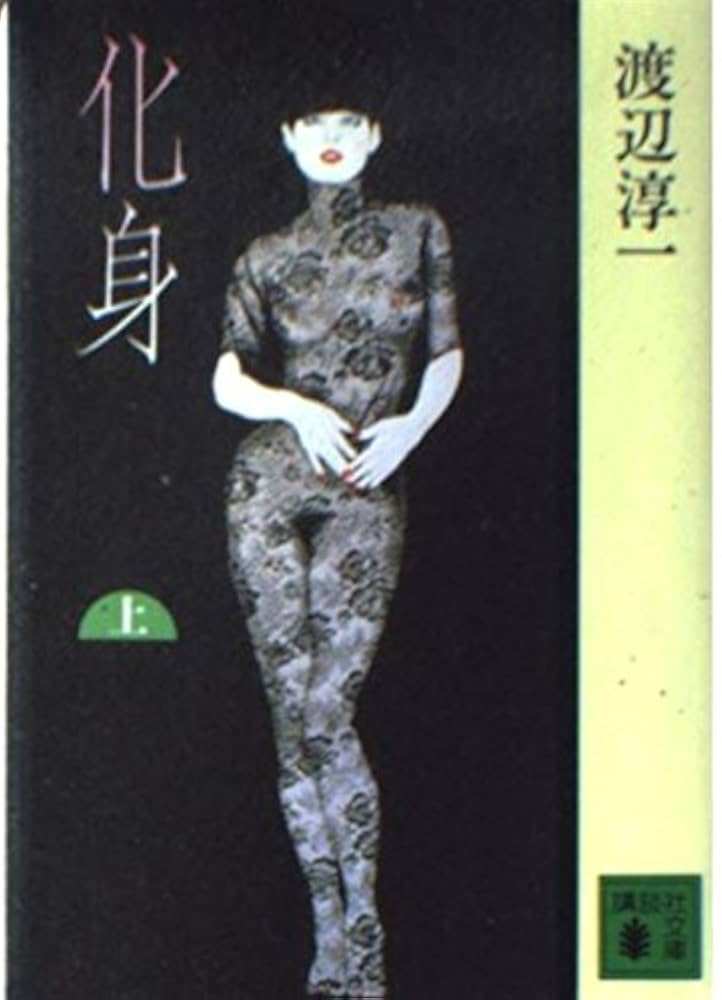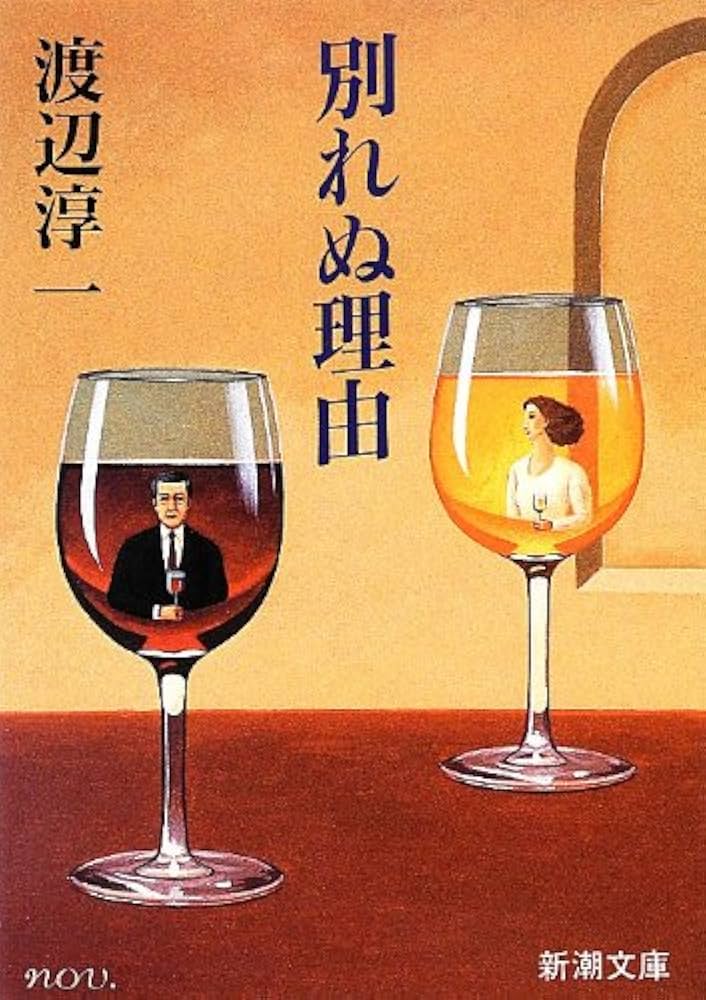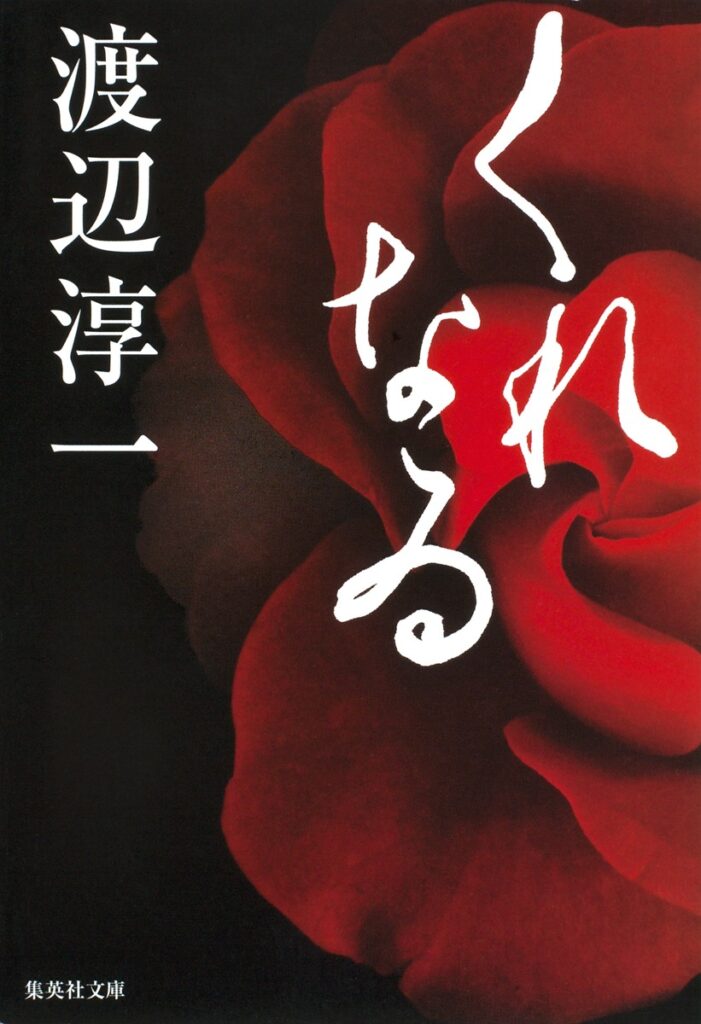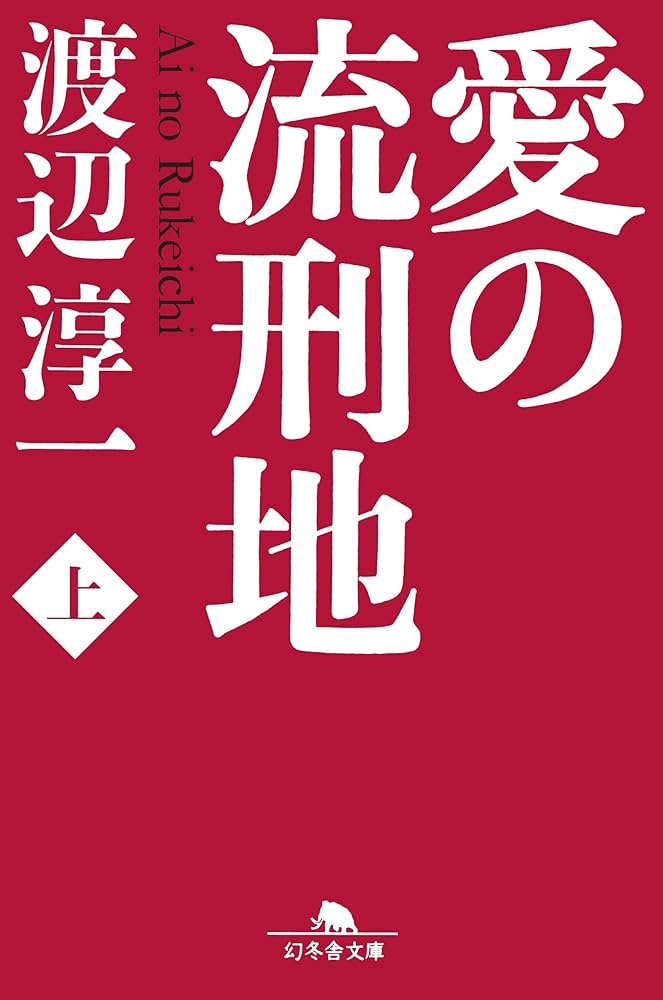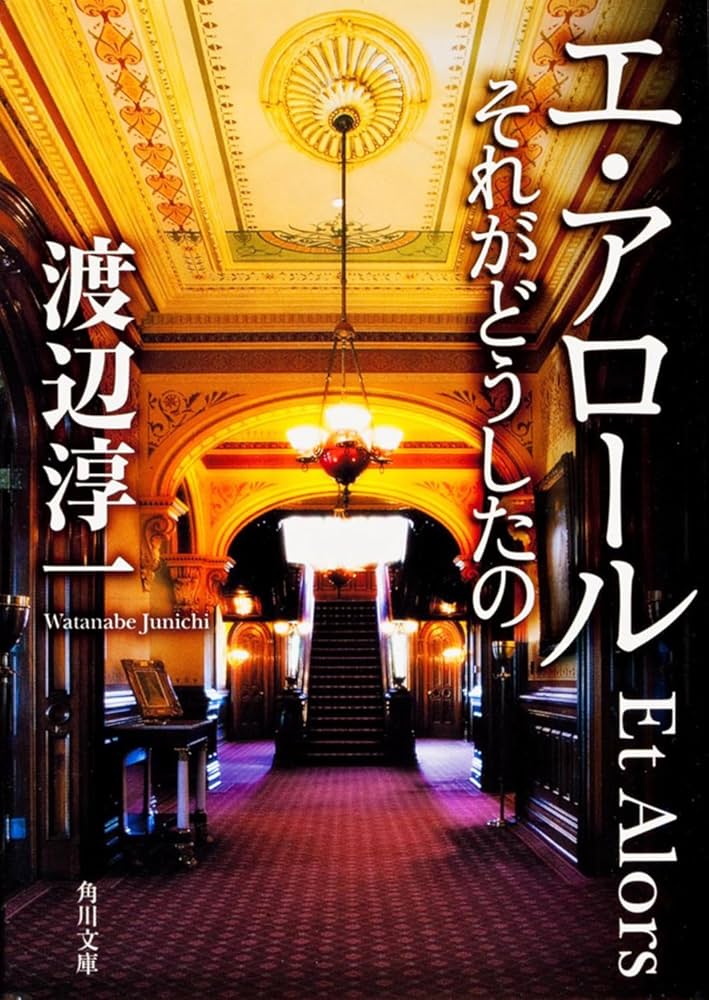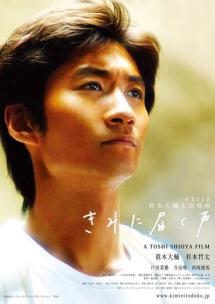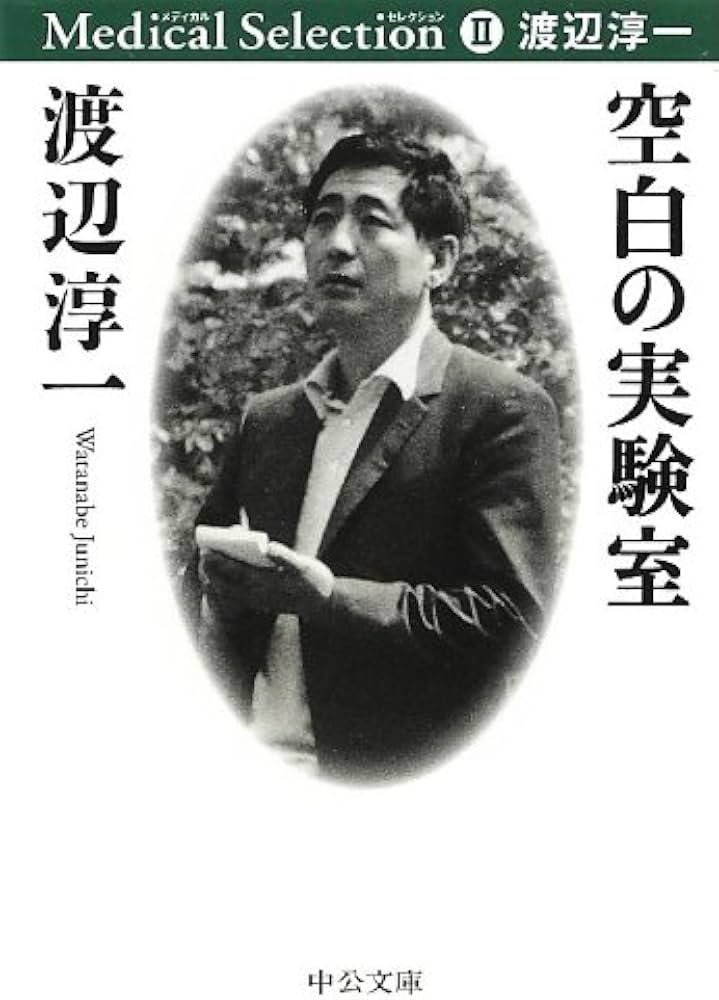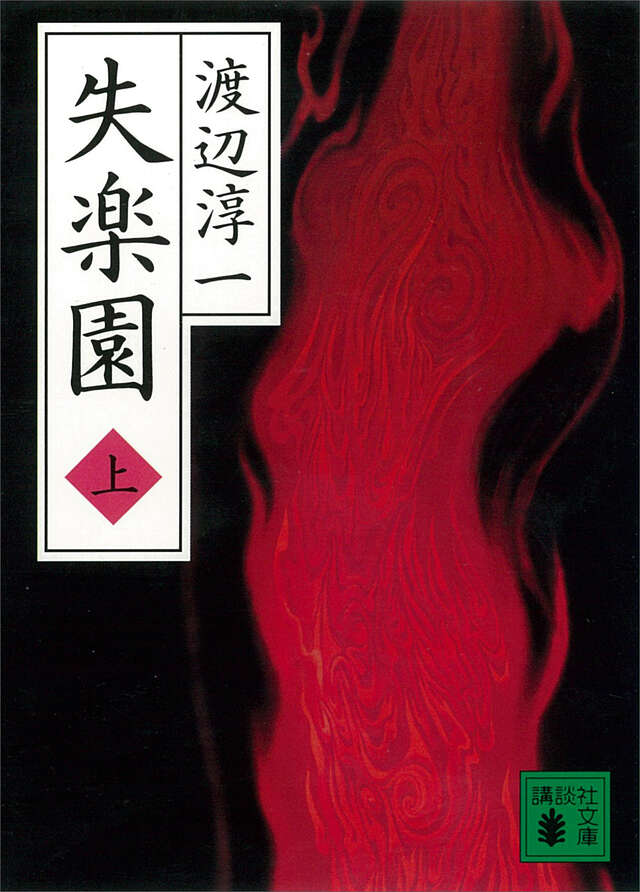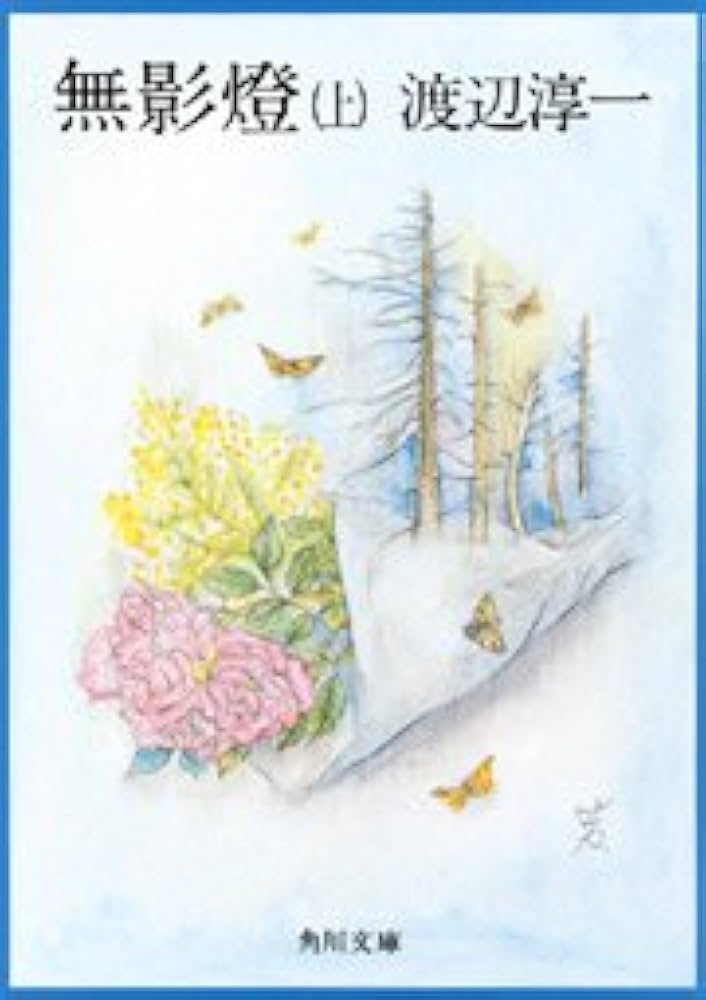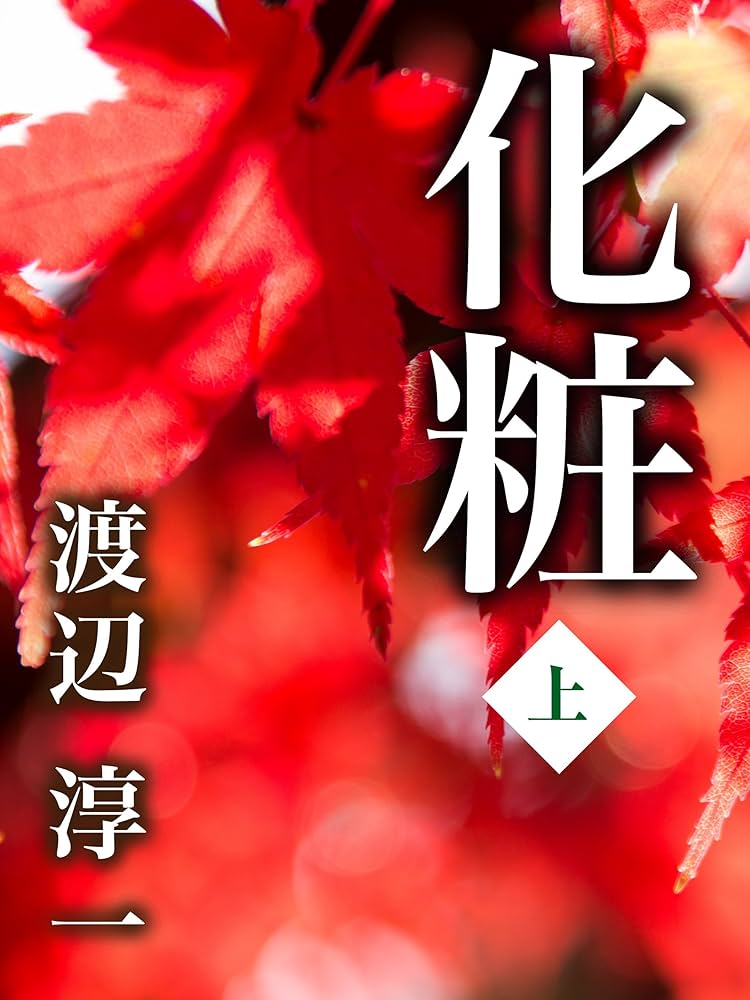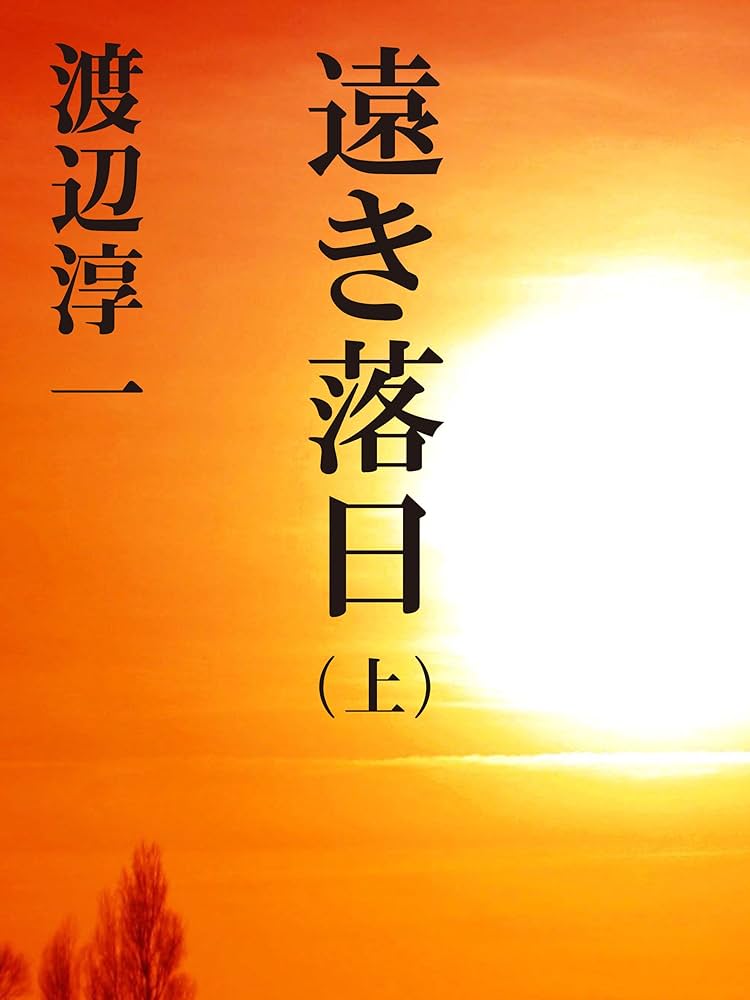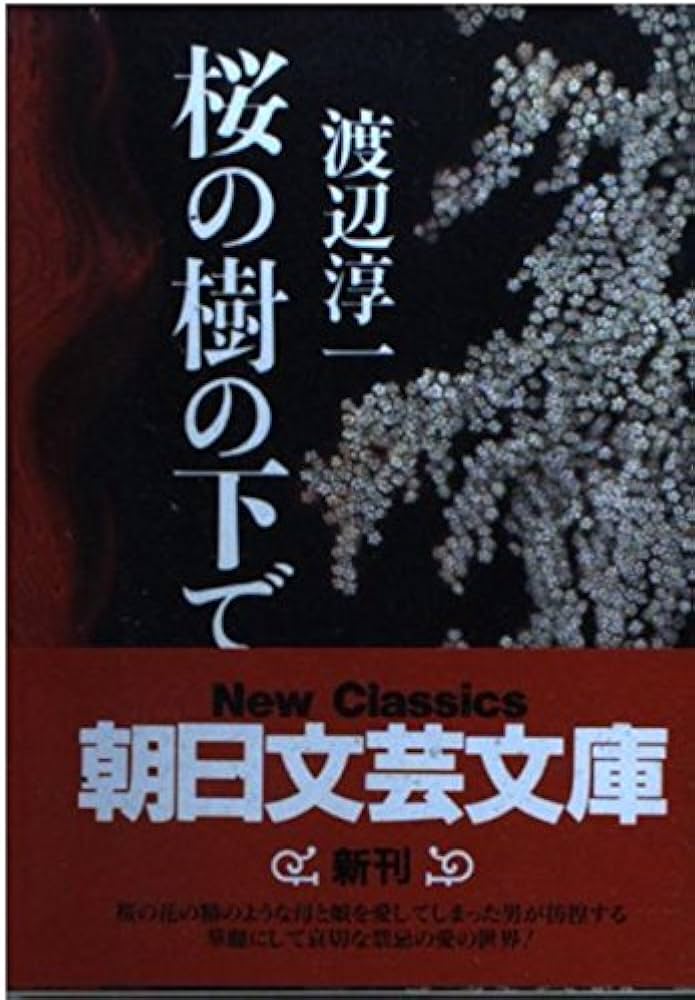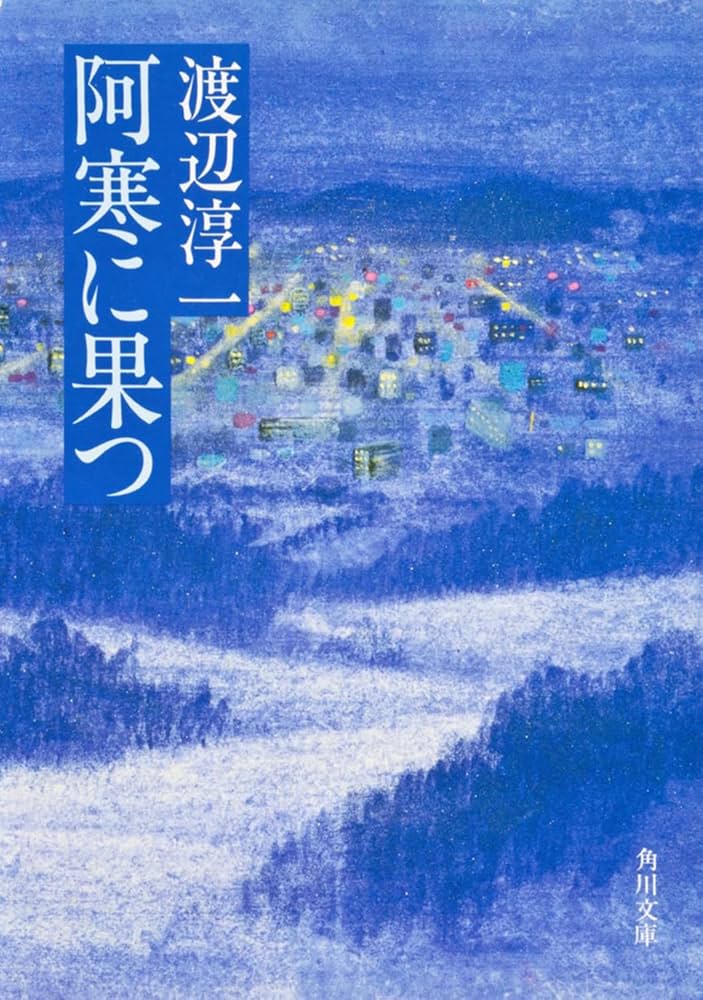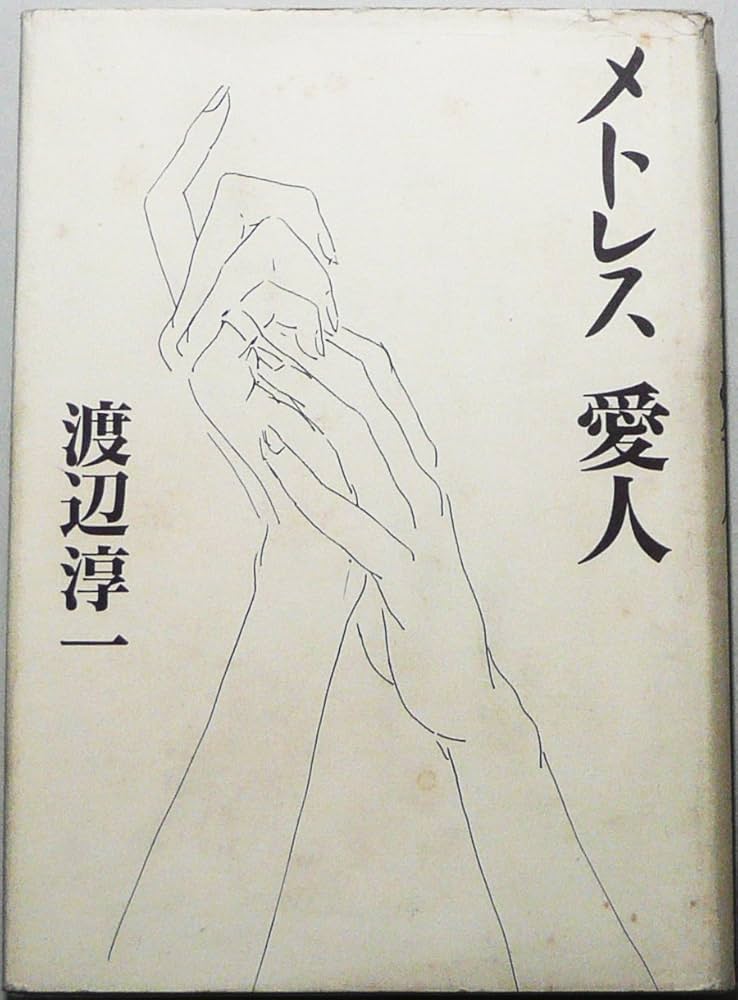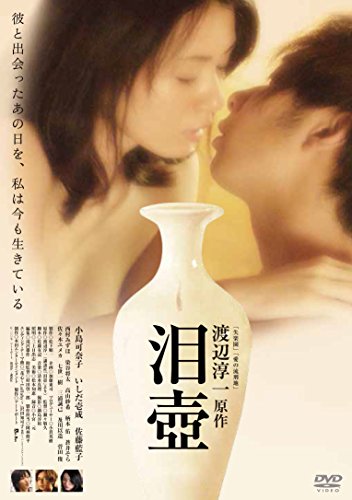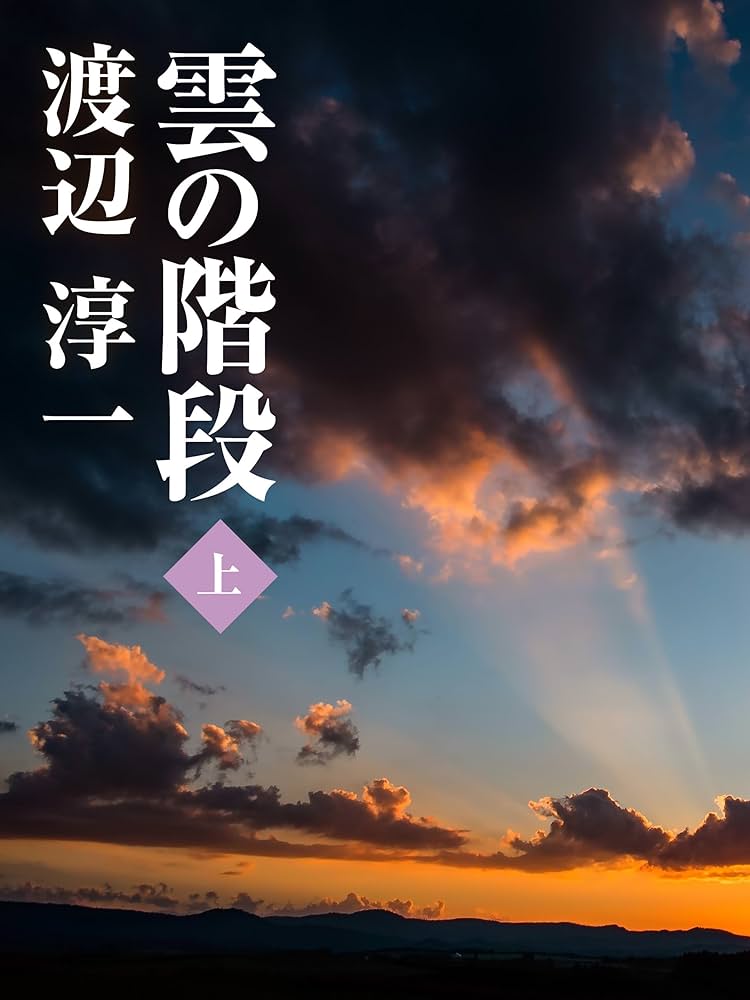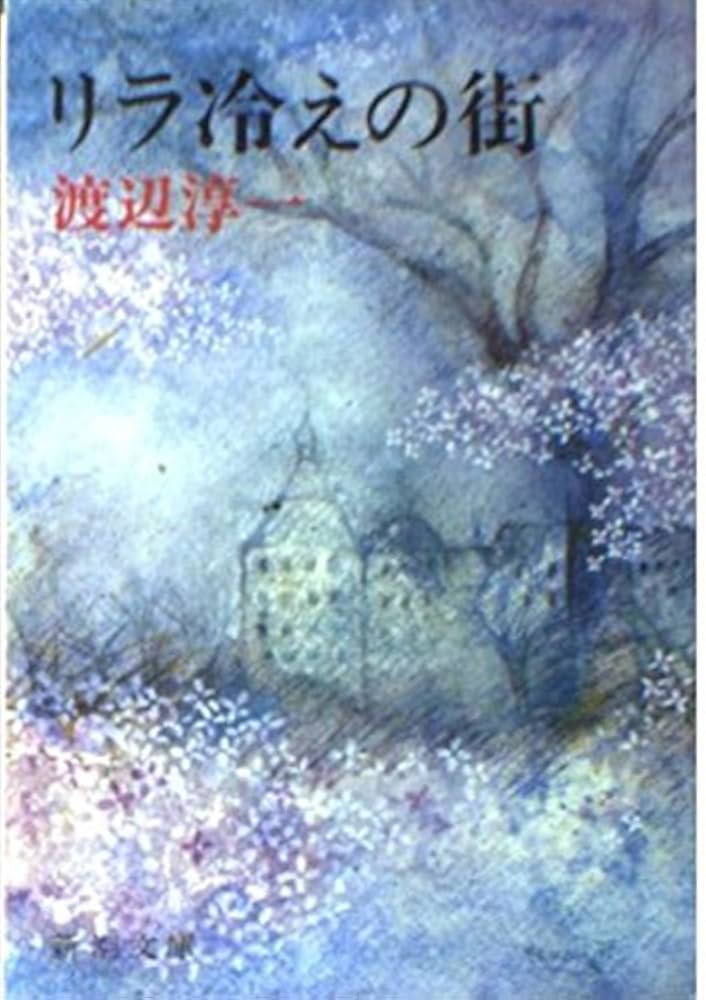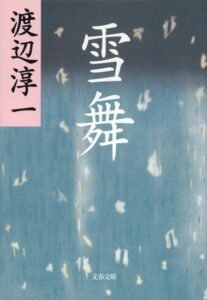 小説「雪舞」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「雪舞」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
渡辺淳一さんが描く医療小説の中でも、特に生命の重さと医師の倫理観を鋭く問う作品として、私の心に深く刻まれているのがこの『雪舞』です。物語の舞台は、雪深い札幌の大学病院。そこでは、一人の若き脳外科医が、救いがたい病を抱えた幼い命を前に、究極の選択を迫られます。
この物語は、単に医療の現場を描くだけではありません。医師としての使命感、立ちはだかる医学の限界、そして何よりも、患者の家族が抱える言葉にならない苦悩が、重厚な人間ドラマとして織りなされていきます。登場人物たちの正義と正義がぶつかり合う様は、読む者の心を激しく揺さぶります。
この記事では、物語の核心に触れながら、その結末までを追っていきます。そして、私がこの作品から何を感じ、何を考えさせられたのか、その思いの丈を綴りました。この物語が投げかける、重く、そして切実な問いに、一緒に向き合っていただければ幸いです。
「雪舞」のあらすじ
物語の舞台は、雪に閉ざされた札幌の大学病院。若くして将来を嘱望される脳外科医・野津修平のもとに、一人の赤ん坊が運び込まれます。患者は、著名な建築家である桐野倫一郎の長男・亮一。しかし、輝かしい家庭の裏で、夫妻の関係はすでに冷え切っていました。
精密検査の結果、亮一は重度の水頭症を患っており、たとえ手術をしても、植物状態で数年生きるのがやっとという、絶望的な診断が下されます。この事実は、ただでさえぎくしゃくしていた夫婦関係に決定的な亀裂を入れ、特に夫は、息子の障がいの責任を一方的に妻に押し付け、彼女を精神的に追い詰めていきました。
亮一の治療方針を巡る院内のカンファレンスで、野津はわずかな可能性に懸けて手術を行うべきだと強く主張します。しかし、彼の上司である脳外科医長・遠野は、無益な治療で患者を苦しめるべきではないと、その主張を退け、手術はしないという命令を下します。
遠野医長が学会で札幌を離れた、まさにその時。野津は、我が子の看病と夫からの精神的虐待に苦しむ母親の姿を前に、医師として、一人の人間として、重大な決断を迫られることになります。上司の命令に背いてでも、彼はメスを握るのか。その選択が、関わる人々の運命を大きく揺り動かしていくのです。
「雪舞」の長文感想(ネタバレあり)
この『雪舞』という物語を読み終えたとき、私の胸に去来したのは、感動という一言では表しきれない、ずしりとした重みと、深く静かな哀しみでした。ただ涙を誘うだけの悲劇ではなく、人間の倫理観そのものを根底から揺さぶるような、恐ろしくも真摯な問いがそこにはありました。
物語の舞台である雪深い札幌は、この作品の空気感を象徴しているように感じます。すべてを白く覆い隠す雪は、無菌の手術室の冷たさや、登場人物たちが抱える孤独、そしてどうしようもない運命の非情さを映し出しているかのようでした。この厳しい自然の中で、一つの命を巡る人間ドラマが繰り広げられます。
主人公は、若く優秀な脳外科医、野津修平。彼は、現代医学の限界に挑戦しようという情熱と理想に燃えています。彼の前に現れるのが、重い病を抱えた赤ん坊、亮一とその両親です。社会的成功者である建築家の父と、年の離れた若く美しい母。しかしその内実は、すでに崩壊していました。
そして、野津の理想と対峙するのが、上司である遠野医長です。彼は、長年の経験から医学の限界を知り尽くした現実主義者。この二人の医療哲学の衝突が、物語の大きな軸となっていきます。さらに、野津に想いを寄せる看護婦・祥子が、彼の苦悩を静かに見守る存在として描かれ、物語に奥行きを与えています。
物語は、亮一の絶望的な診断から大きく動き出します。重度の水頭症。たとえ生き永らえても、意思の疎通もできない植物状態のまま、数年の命。この宣告は、すでに冷え切っていた桐野夫妻の関係を、修復不可能なまでに破壊しました。特に夫が妻を「お前のせいだ」と責め立てる場面は、読んでいて胸が張り裂けそうでした。
亮一の病は、もともと存在した夫婦間の不和を、ただ表面化させたに過ぎません。夫の非情な言葉は、健常な跡継ぎを得られなかったことへの失望と、結婚生活そのものへの不満からくる、身勝手な責任転嫁に他ならないのです。母親は、我が子の看病と夫からの精神的暴力という、二重の地獄を生きることになります。
物語の核心は、亮一への手術を行うか否かを決めるカンファレンスの場面で訪れます。野津は、わずかでも可能性があるのなら手術をすべきだと強く主張します。亮一の脳の萎縮は1.4cm。手術適応外の基準である1.5cmまで、あとわずか0.1cm。この数字が、野津の挑戦心を掻き立てます。
しかし、遠野医長は「手術は見合わせ、経過を見守る」と、冷静に、そして厳格に命じます。彼の判断は、長年の臨床経験に裏打ちされた現実主義的なものであり、患者を無用な苦痛から守るという医師の原則に基づいています。そして彼は、その決定を下した直後、学会出張のために札幌を離れるのです。この権威の不在が、野津の心を大きく揺さぶります。
この対立は、単なる治療方針の違いではありません。それは、当時の医療現場を支配していた、二つの異なる「パターナリズム(父権主義)」の衝突でした。患者や家族の意思が尊重されるという考えがまだ希薄だった時代。医師が最善と信じる道を決定するのが当たり前でした。遠野の判断も、野津の主張も、その枠組みの中での正義なのです。
遠野が不在の間、野津は苦悩します。手術不能を告げたときの父親の落胆した顔、そして何より、地獄のような日々を送っていると伝え聞く母親の存在が、彼の心を蝕んでいきました。苦しんでいる人を前に、何もしないでいることが本当に正しいのか。彼の信念が、根底から揺らぎ始めます。
彼の決意は、単なる功名心や傲慢さから来たものではないと、私は感じました。それは、医師としての使命感、人道的な衝動、そして、母親の言葉にならない叫びを敏感に感じ取ってしまったが故の、ほとんど抗いがたい感情の奔流だったのではないでしょうか。彼は、母親の「この苦しみを終わらせてほしい」という暗黙の願いを、一身に背負ってしまったのです。
そして、野津は医長の命令に背き、禁断の手術を強行します。後輩の谷村医師だけを伴い、麻酔医の再三の警告も振り切ってメスを進める場面は、息が詰まるほどの緊張感に満ちていました。それは、病院の規律を破り、医学の定石に逆らう、許されざる越権行為でした。しかし、彼の心の中では、それは亮一を救うだけでなく、母親を地獄から解放するための、唯一の手段となっていたのです。
手術の結果は、あまりにも無情なものでした。手術そのものは終わったものの、亮一の小さな体はそれに耐えきれず、静かに息を引き取ります。野津の理想と挑戦は、最悪の形で幕を閉じました。
学会から戻った遠野医長が、すべてを知って野津を叱責する場面は、この物語の頂点です。「手術すべきと言うのは死なずに済む医者の理屈だ。君は殺される者の身になって考えたことがあるのか?」この言葉は、どんな理屈をも超えて、執刀医が背負う責任の重さを、読者に突きつけます。
一方、息子の死を知った父・桐野は、その怒りの矛先を野津と病院に向け、医師会に彼を告発します。しかし、驚くべきことに、あれほど厳格だった遠野が、野津を庇おうとするのです。「手術を決めたのは俺だと言うことにしろ!」と。しかし、野津はその庇護を拒絶し、「手術を決めたのは自分だ」と、すべての責任を一人で引き受けることを選びます。
最終的に、遠野の采配により、野津は札幌を追われ、道東の港町・根室の病院へ事実上の左遷となります。かつての野心は消え、厳しい自然の中で贖罪の日々を送る彼の姿は、痛々しくも静謐な空気をまとっていました。
物語の終わりは、一本の電話によってもたらされます。遠野から告げられたのは、桐野家との示談が成立したこと、そして、桐野夫人が新しい命を授かったということでした。「事件のことはもう忘れろ」。その言葉は、厳しい命令でありながら、野津に対する最大限の赦しのように響きます。
電話を切った後、窓の外に舞う雪を見ながら、野津は知らず知らずのうちに涙を流します。この「雪舞」の情景こそ、この物語が持つすべての哀しみと、ほんのわずかな救いを象徴しているように思えてなりませんでした。彼の流した涙は、罪悪感を洗い流す浄化の涙だったのかもしれません。そして舞い落ちる雪は、人の力ではどうすることもできない運命の大きな流れを、静かに示しているようでした。この結末は、決して単純なハッピーエンドではありません。桐野家の再生は、亮一と野津という二つの犠牲の上に成り立っているのですから。このやりきれない皮肉こそが、渡辺淳一作品の真骨頂なのかもしれません。
まとめ
渡辺淳一さんの小説『雪舞』は、一人の医師の決断を通して、生命の尊厳とは何か、救いとは何かという、重く、答えの出ない問いを私たちに投げかけます。物語全体を覆うのは、雪のように冷たく、そして静かな哀しみです。
主人公の野津医師が犯した過ちは、許されるものではないかもしれません。しかし、彼の行動の根底にあった、苦しむ人を救いたいという純粋な思いや、母親の絶望に共感してしまった人間的な弱さを思うと、一方的に彼を断罪することはできないのです。
この物語は、明確な答えを与えてはくれません。ただ、登場人物たちが直面した出口のない問いの前に、私たち読者を立たせるだけです。何が正しく、何が間違っていたのか。読み終えた後も、その問いが心に深く残り、考え続けずにはいられなくなります。
最後の場面で舞う雪は、この物語のすべてを象徴しているかのようです。それは、罪を洗い流す浄化のようでもあり、どうしようもない運命の非情さのようでもあります。深く心に刻まれる、忘れがたい読書体験でした。